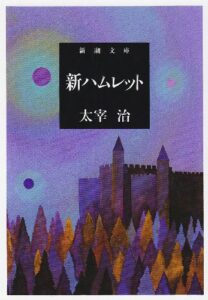
小説『新ハムレット』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治がシェイクスピアの古典的名作をどのように読み解き、新たな物語として再構築したのか、その魅力に迫ってみたいと思います。原作の『ハムレット』をご存知の方も、そうでない方も、きっと楽しめるはずです。
この作品は、戯曲形式で書かれており、登場人物たちの会話を通して物語が進行します。デンマーク王国を舞台に、ハムレット王子とその周囲の人々の複雑な人間関係や心理的な葛藤が描かれています。原作とは異なる設定や展開が多く、太宰治ならではの解釈が光る一作と言えるでしょう。
この記事では、まず物語の筋道を追いながら、その結末にも触れていきます。その後、私自身がこの作品を読んで感じたこと、考えたことを、少し長くなりますが詳しく述べていきたいと思います。原作との比較や、太宰作品としての特徴など、様々な角度から『新ハムレット』の世界を味わっていただければ幸いです。
それでは、太宰治が描くもう一つのハムレットの物語を、一緒に紐解いていきましょう。登場人物たちの心の揺れ動きや、彼らが紡ぎ出す言葉の数々に、ぜひ注目してみてください。
小説「新ハムレット」のあらすじ
デンマーク王国では、先王が亡くなって二ヶ月。先王の弟であるクローヂヤスが新たに王位に就き、先王の妃であったガーツルードを妻に迎えました。王位継承の謁見式で、クローヂヤスはノルウェーとの戦争の危機が迫る国の安定のため、自分が王となりガーツルードと結婚したと説明します。
先王の息子ハムレットは、父の死から立ち直れず、喪服で謁見式に出席していました。彼はフランスへの遊学を望んでいましたが、クローヂヤスは将来王位を継ぐ彼に国内で政治を学ぶことを望みます。二人きりの話し合いで、クローヂヤスはハムレットに、臣下の前では「父」と呼んでほしいと頼み、相談役としてハムレットの旧友ホレーショーを呼んだことを伝えます。
一方、宰相ポローニヤスの息子レヤチーズは、フランスへ戻る許しを得ます。旅立つ前、彼は妹のオフィリヤに、ニヒリストで道楽者と見られているハムレットへの恋を諦めるよう忠告します。ポローニヤスも娘に対し、評判の落ちたハムレットとの結婚は難しいだろうと、隠れて逢瀬を重ねていたことを責め立てるのでした。
そんな中、ホレーショーはハムレットに、先王の幽霊が現れ、クローヂヤスに毒殺されたと訴えているという噂を伝えます。ハムレットはその噂が真実だと打ち明け、父のため、そして根拠のない噂に苦しむ叔父と母のためにも真相を突き止めると誓います。さらにハムレットは、オフィリヤを妊娠させてしまったという秘密を抱えていました。
王妃ガートルードは、ハムレットの不安定さを心配しホレーショーに相談しますが、彼がハムレットをかばっているのではないかと疑念を抱きます。そこへクローヂヤスが現れ、オフィリヤの妊娠とポローニヤスの辞表提出を告げます。クローヂヤスはオフィリヤを田舎へ行かせ、ハムレットと別れさせようと考えます。ハムレットは父ポローニヤスに結婚を誓いますが、ポローニヤスはクローヂヤスへの疑念から、ある計画をハムレットとホレーショーに持ちかけます。
ポローニヤスの計画は、先王殺害を匂わせる内容の劇を上演することでした。劇を見たガートルードは気分を害し退席。クローヂヤスは表向きは演技を褒めつつ、後にポローニヤスを呼び出し、裏切りだと詰問します。ポローニヤスが先王の死の真相について迫ると、クローヂヤスは逆上し、彼を刺殺してしまいます。ガートルードはその場に隠れており、一部始終を目撃し逃げ出します。そして、彼女は庭園の小川に身を投げて命を絶ってしまうのでした。すべてを知ったハムレットは、父を裏切った者たちへの怒りと絶望から、短剣で自身の頬を切り裂くのでした。クローヂヤスは自分の罪を認めつつも生き延びることを誓い、ハムレットとの間の疑念は残されたまま物語は幕を閉じます。
小説「新ハムレット」の長文感想(ネタバレあり)
太宰治の『新ハムレット』を読み終えて、まず感じたのは、原作であるシェイクスピアの『ハムレット』とは全く異なる、それでいて深く心を揺さぶられる物語だということでした。もちろん、登場人物の名前や基本的な関係性は踏襲されています。デンマークの王子ハムレット、叔父であり継父となった国王クローヂヤス、母である王妃ガーツルード、宰相ポローニヤスとその娘オフィリヤ、息子レヤチーズ、ハムレットの友人ホレーショー。これらの名前を聞けば、多くの人があの有名な悲劇を思い浮かべることでしょう。しかし、太宰治はこの馴染み深い設定を借りながら、登場人物たちの性格や動機、そして物語の結末に至るまで、大胆なアレンジを加えています。それは単なる翻案やパロディという言葉では片付けられない、太宰治自身の思索と苦悩が色濃く反映された、独立した作品として成り立っていると感じました。
原作のハムレットが、父王暗殺の復讐という明確な動機を持ち、狂気を装いながらも知略を巡らせ、孤独な戦いに身を投じていく英雄的な(あるいは悲劇的な)存在であるのに対し、太宰版ハムレットは、もっとずっと人間臭く、弱さを抱えた青年として描かれています。彼は父の死や母の再婚に深く傷つき、憂鬱に沈んでいます。しかし、その苦悩は復讐心よりも、むしろ周囲の人々との関係性、特に「愛」をめぐる不信感や渇望に向けられているように見えます。「愛は言葉だ。言葉が無くなれや、同時にこの世の中に、愛情も無くなるんだ。」という彼の台詞は、この作品の核心を突くものかもしれません。彼は母ガーツルードや恋人オフィリヤからの明確な「愛の言葉」を求めますが、それが得られないことに苛立ち、絶望していくのです。オフィリヤを妊娠させてしまったことへの責任感と、彼女や生まれてくる子への愛情も感じさせますが、それ以上に自身の内面的な混乱や、周囲への不信感が彼の行動を支配しているように感じられます。原作のような復讐のための策略ではなく、彼の行動はしばしば衝動的で、自己破壊的ですらあります。ポローニヤスを殴ってしまう場面や、最終的に自身の頬を切り裂く行為は、彼の内面の激しい葛藤と、それをうまく表現できない不器用さの表れではないでしょうか。
クローヂヤスもまた、原作の冷酷な簒奪者とは異なる貌を見せます。もちろん、彼が先王の死に関わっている(あるいは少なくとも殺意を抱いていた)ことは示唆されますし、保身のために嘘をつき、最終的にはポローニヤスを殺害するという罪を犯します。しかし、太宰版クローヂヤスは、常に不安や罪悪感に苛まれているような、ある種の繊細さ、弱さを持った人物として描かれています。彼はハムレットに対して、臣下の前だけでも父と呼んでほしいと頼んだり、王としての重圧や孤独を吐露したりします。ポローニヤス殺害の後、ハムレットに自身の罪を認めつつも、「汚辱の中にいながら、耐え忍んで生き、恋も虚栄も忘れて宿命をまっとうする」と誓う姿は、悪役というよりも、罪を背負いながらも生き続けようとする、痛々しい人間の姿を映し出しているように思えました。原作ではハムレットの復讐の対象として断罪されるべき存在ですが、『新ハムレット』では、彼に対しても同情や憐憫の情を禁じ得ませんでした。
王妃ガーツルードの描かれ方も印象的です。原作では、やや受動的で、息子の苦悩や夫の策略に翻弄される存在として描かれることが多いように思いますが、太宰版ガーツルードは、より能動的に苦悩し、自身の感情と向き合おうとしているように見えます。彼女はハムレットの不安定さを心から心配し、ホレーショーに相談を持ちかけます。また、オフィリヤに対しては、母親のような優しさを見せ、彼女の告白に涙し、自身の「汚い、いやらしい」過去への後悔を口にします。先王の臨終の場であった腰掛けに座り、「自分は間違ったことをした」と嘆く姿は、単なる弱い女性ではなく、自らの罪と向き合い、苦しむ一人の人間としての深みを感じさせます。最終的に彼女が選んだ自死は、原作の事故死とは異なり、彼女自身の絶望と贖罪の意識の表れとして、より重く響きました。
オフィリヤの造形も、原作とは大きく異なります。原作のオフィリヤは、父と恋人ハムレットとの間で引き裂かれ、狂気に陥り、悲劇的な最期を迎える薄幸の乙女という印象が強いですが、『新ハムレット』のオフィリヤは、ハムレットの子を身ごもりながらも、精神的な強さや純粋さを失いません。彼女は父や兄の心配をよそに、ハムレットへの愛を貫こうとし、ガーツルードの優しさに触れて慰められます。そして、愛を言葉で確認しようとするハムレットに対し、「神は言葉に表すこともないまま、皆を愛している」と反論する場面は、彼女の持つ信仰心や、ハムレットとは異なる愛の捉え方を示しており、非常に印象的でした。原作のような狂気や死ではなく、彼女が生き延び、ガーツルードの愛を信じるようにハムレットを諭す姿は、この作品に一条の光を与えているように感じます。
宰相ポローニヤスも、原作の道化役的な側面は薄れ、より策謀家として、また娘を思う父親としての側面が強調されています。彼がクローヂヤスへの疑念から劇の上演を計画する展開は、原作のハムレットの役割を彼が担うという面白い改変です。しかし、その計画が裏目に出てクローヂヤスに殺害されてしまう結末は、彼の人間的な限界と悲劇性を示しています。彼の息子レヤチーズは、原作のようにハムレットとの決闘で死ぬのではなく、ノルウェーとの戦争で命を落とすという設定に変更されており、物語における役割は相対的に小さくなっていますが、ハムレットにとっては同年代のライバルとして意識される存在でした。ハムレットの友人ホレーショーは、原作同様、ハムレットの理解者であり、狂言回し的な役割も担いますが、彼自身も王家の複雑な問題に巻き込まれ、苦悩する姿が描かれています。
『新ハムレット』全体を貫いているのは、太宰治特有の人間観察と、登場人物たちの内面に対する深い洞察です。特に、「愛」や「言葉」、「真実」と「嘘」といったテーマが繰り返し問い直されます。ハムレットは愛を言葉で確認しようとしますが、オフィリヤは言葉にならない愛の存在を説きます。クローヂヤスやポローニヤスは嘘や策略を巡らせますが、その根底にはそれぞれの弱さや保身、あるいは歪んだ正義感があります。登場人物たちは、互いに疑心暗鬼になりながら、本心を探り合い、あるいは隠し合います。その心理的な駆け引きは、読んでいて息苦しくなるほどですが、同時に人間の持つ普遍的な弱さや愚かさ、そして愛おしさを映し出しているようにも感じられました。
太宰治自身の人生や苦悩が、この作品に色濃く投影されていると感じる読者も多いのではないでしょうか。特にハムレットの抱える憂鬱や自己否定感、愛への渇望と不信、そして自己破壊的な衝動には、太宰自身の姿が重なって見えるかもしれません。また、登場人物たちが繰り広げる道化的な言動や、シニカルでありながらもどこか滑稽さを伴うやり取りには、太宰作品にしばしば見られる「道化」の精神が息づいているようにも思えます。自分自身を客観視し、時には嘲笑するかのような筆致は、この作品に独特の奥行きを与えています。
戯曲形式で書かれていることも、この作品の特徴の一つです。台詞が中心となって物語が進行するため、読者は登場人物たちの言葉一つひとつに集中し、その裏にある感情や意図を読み解くことになります。舞台設定や状況説明は最小限に留められており、それがかえって登場人物たちの心理描写を際立たせているように感じました。太宰治の巧みな言葉遣いと、リズミカルでありながらも緊張感のある台詞の応酬は、読者を強く引き込みます。
物語の結末は、原作の『ハムレット』が多くの主要人物の死によって幕を閉じる壮絶な悲劇であるのに対し、『新ハムレット』は異なる様相を呈します。死ぬのはポローニヤスとガーツルードのみ。ハムレットは自らの頬を傷つけ、クローヂヤスは罪を抱えながらも生き続けることを選びます。オフィリヤやホレーショーも生き残ります。この結末は、ある意味で原作よりも救いがない、あるいはより現実的な苦悩が続くことを示唆しているのかもしれません。ハムレットとクローヂヤスの間の疑念やわだかまりは解消されず、「この疑惑は自分が死ぬまで持ち続けるだろう」というハムレットの言葉は重く響きます。派手な破滅ではなく、日常の中に潜む苦悩や葛藤を抱えながら生きていかざるを得ない人間の姿を描いている点で、より太宰治らしい結末と言えるのかもしれません。
『人間失格』や『斜陽』といった作品で知られる太宰治は、しばしば暗い、退廃的といったイメージを持たれがちですが、『新ハムレット』を読むと、彼の文学の持つ多面性を改めて感じさせられます。西洋古典への深い造詣と、それを独自の世界観で再構築する知的な遊び心。人間の弱さや醜さを鋭く描き出しながらも、その奥底にある純粋さや切実な願いをも見つめようとする視線。そして、絶望の中にも、かすかな希望や生き続けることへの意志のようなものを感じさせる筆致。この作品は、太宰文学の豊かさを知る上で、非常に重要な一作だと思います。
この作品が書かれたのが1941年、太平洋戦争へと突き進む不穏な時代であったことを考えると、また違った感慨も湧いてきます。国家や大義名分といったものが声高に叫ばれる時代にあって、個人の内面的な苦悩や、家族という小さな共同体の中での愛憎、欺瞞といったテーマを描いたことには、太宰なりの抵抗やメッセージが込められていたのかもしれません。英雄的な行為や死ではなく、凡庸な日常の中で悩み、傷つきながらも生きていくことの重さ。それこそが、太宰が描きたかった人間の真実の姿だったのではないでしょうか。
現代に生きる私たちが『新ハムレット』を読む意味はどこにあるのでしょうか。原作の『ハムレット』が持つ普遍的なテーマ、例えば「生きるべきか死ぬべきか」といった問いや、復讐の是非、権力闘争といった要素は、形を変えながらも現代社会にも通じるものがあります。しかし、太宰版『新ハムレット』は、より個人的な、内面的な問題に焦点を当てているように感じます。愛するとはどういうことか、信じるとはどういうことか。言葉はどこまで真実を伝えられるのか。私たちは、他者との関係の中で、あるいは自分自身の内面で、ハムレットやクローヂヤス、ガーツルードが抱えたような葛藤や矛盾に、日々直面しているのではないでしょうか。
この作品を再読して、改めてその言葉の力に引き込まれました。特にハムレットの台詞には、ハッとさせられるような鋭い洞察や、胸を締め付けられるような切実さが満ちています。彼の苦悩は、決して他人事とは思えません。同時に、彼を取り巻く人々、それぞれの立場や思いにも共感できる部分があり、単純な善悪では割り切れない人間の複雑さを感じさせられます。読み返すたびに新しい発見があり、登場人物たちの誰かに心を寄せたり、あるいは反発を覚えたりする、そんな奥深い作品だと思います。もし、あなたがまだ太宰治の『新ハムレット』を読んだことがないのであれば、ぜひ一度手に取ってみることをお勧めします。きっと、あなたの心に何かを残してくれるはずです。
まとめ
この記事では、太宰治の小説『新ハムレット』について、物語の展開を追いながら結末に触れ、そして私なりの深い思いや考えを述べてきました。シェイクスピアの有名な悲劇を下敷きにしながらも、登場人物の性格設定や物語の展開、そして結末に至るまで、太宰治独自の大胆な解釈と創造性が光る、まったく新しい物語として読むことができる作品です。
原作の英雄的なハムレット像とは異なり、太宰版ハムレットは愛と言葉をめぐって苦悩する、より人間臭い青年として描かれています。クローヂヤスやガーツルードといった他の登場人物たちも、単純な悪役や悲劇のヒロインではなく、弱さや罪悪感を抱えながら生きる複雑な人間として造形されています。特にオフィリヤの描かれ方は原作と大きく異なり、物語に独自の光を与えています。
この作品は、「愛」「言葉」「真実」「嘘」といった普遍的なテーマを、登場人物たちの心理的な駆け引きを通して深く掘り下げています。太宰治自身の苦悩や人生観が色濃く反映されているとも言え、彼の文学の多面性や奥深さを知る上で欠かせない一作です。戯曲形式というスタイルも、登場人物たちの言葉とその裏にある感情を際立たせ、読者を引き込みます。
原作とは異なり、多くの登場人物が生き残る結末は、派手な悲劇ではなく、苦悩や葛藤を抱えながらも生きていかざるを得ない、という現実の厳しさや重さを示唆しているのかもしれません。太宰治が描いたもう一つの『ハムレット』の世界、ぜひあなた自身の目で確かめてみてください。きっと、心に残る読書体験となることでしょう。




























































