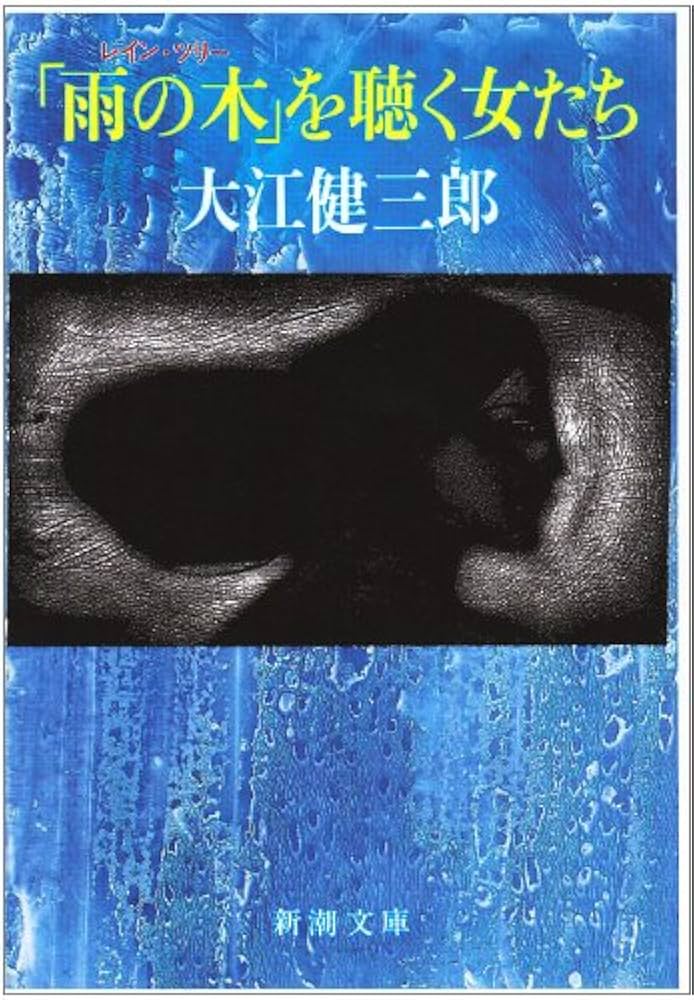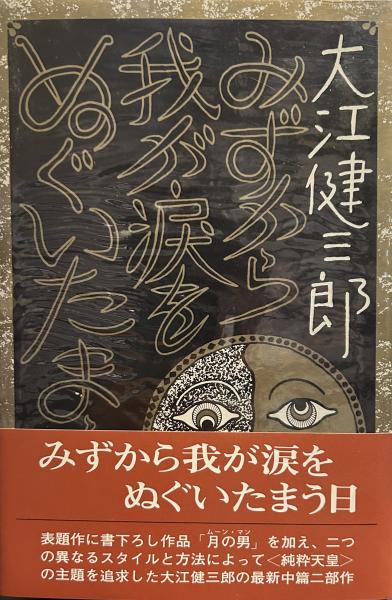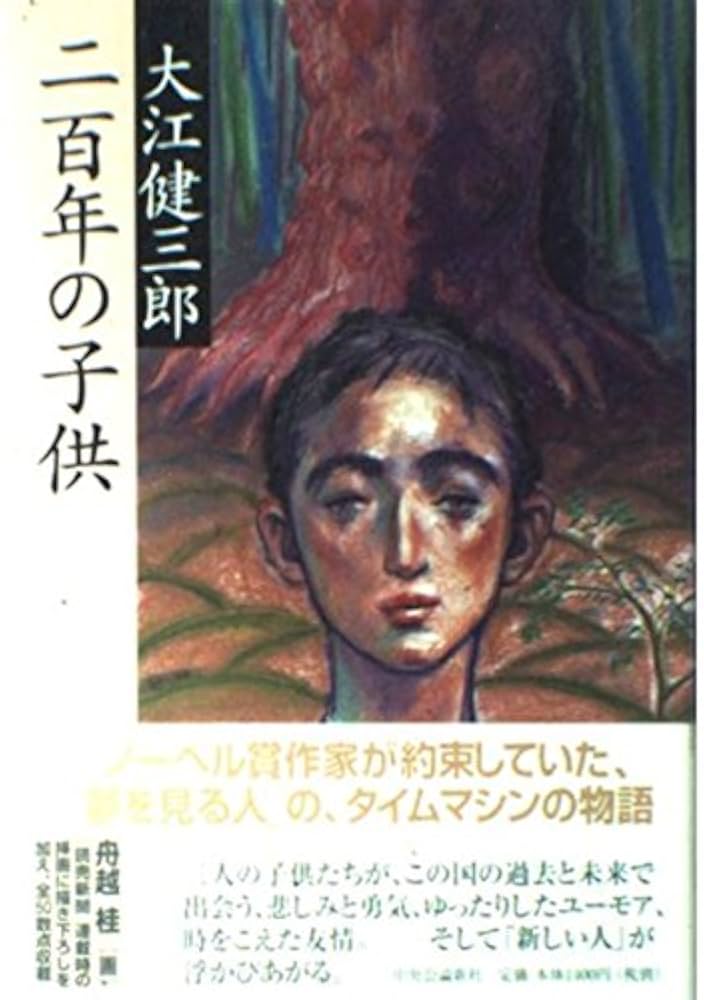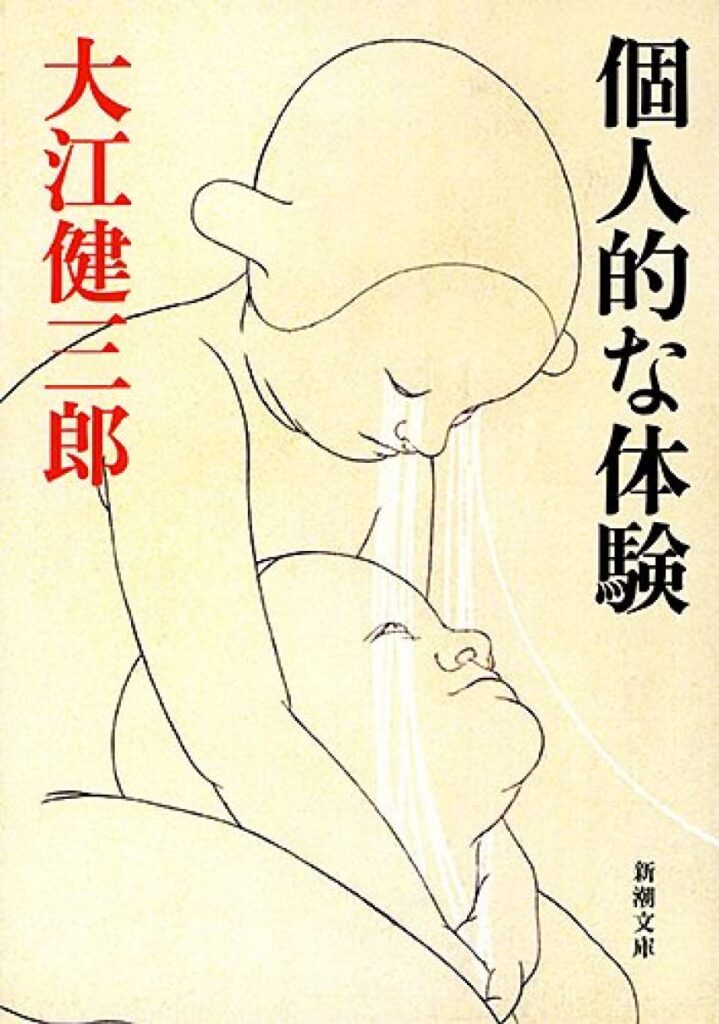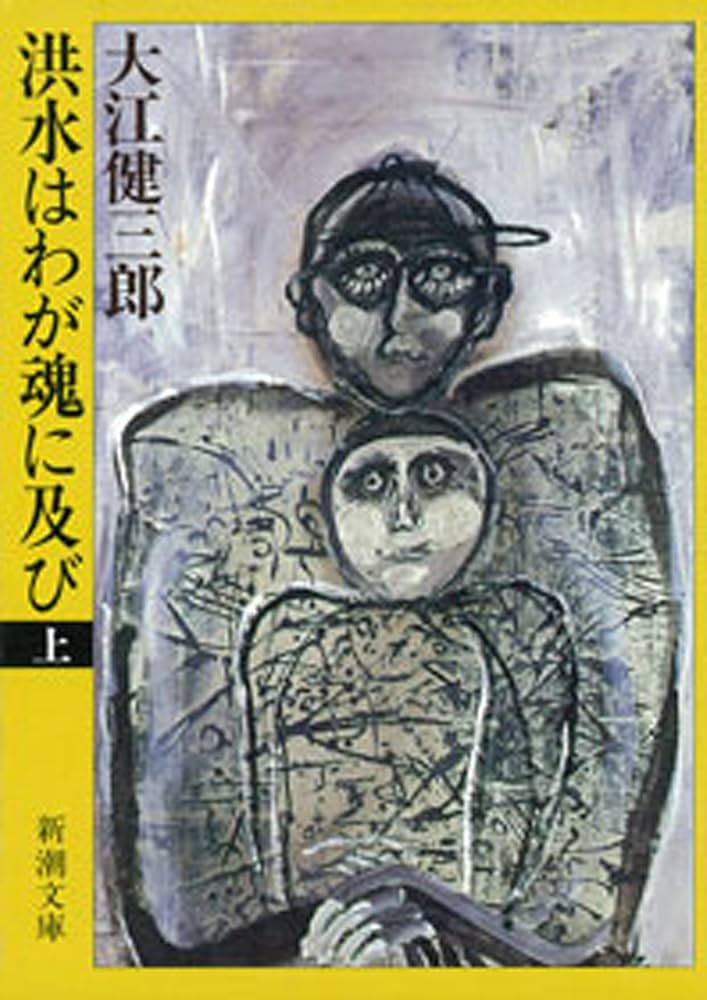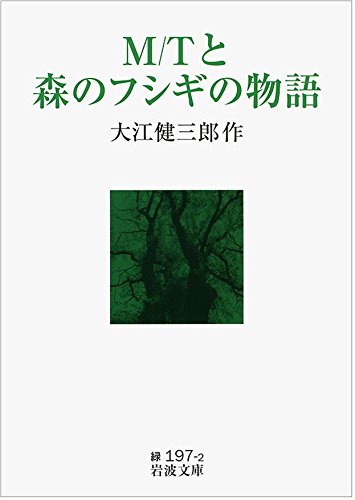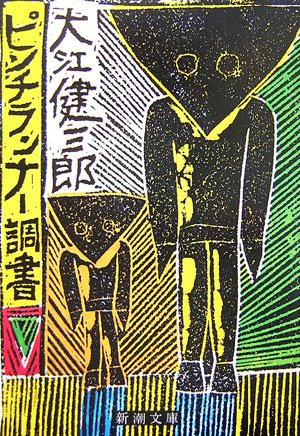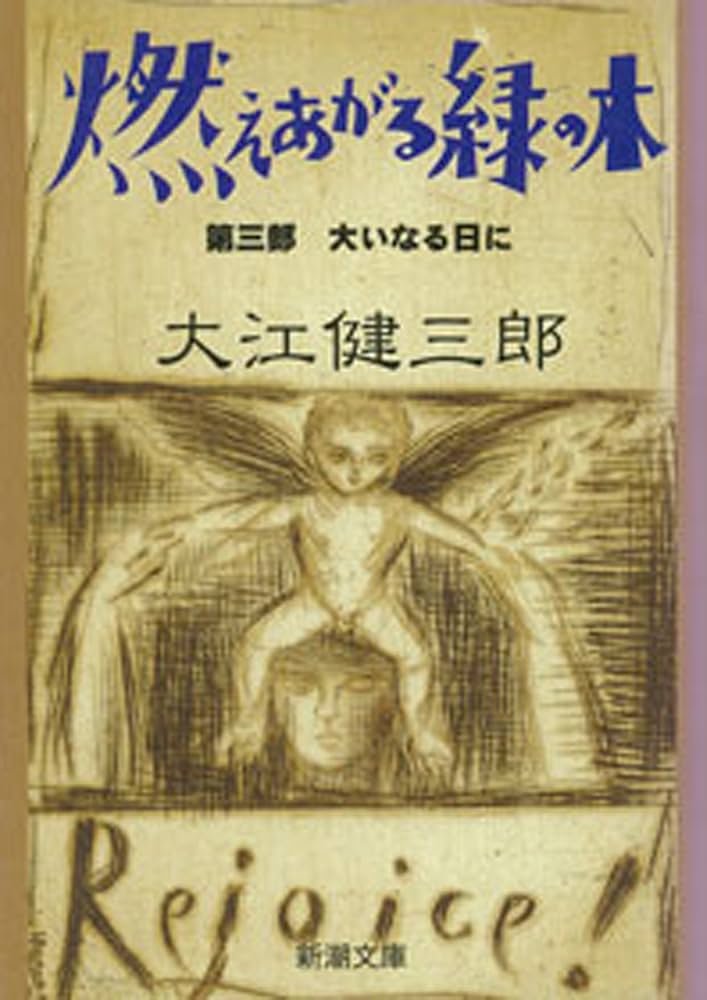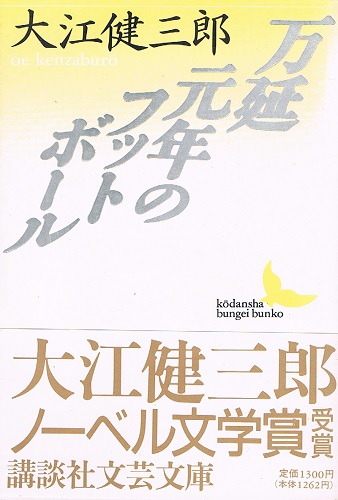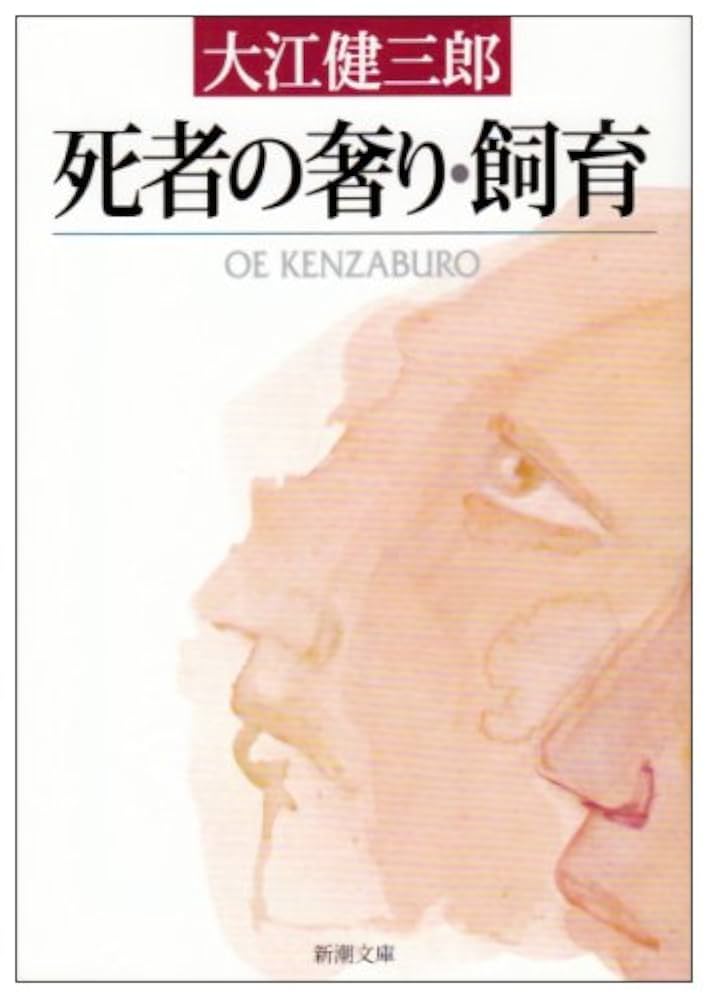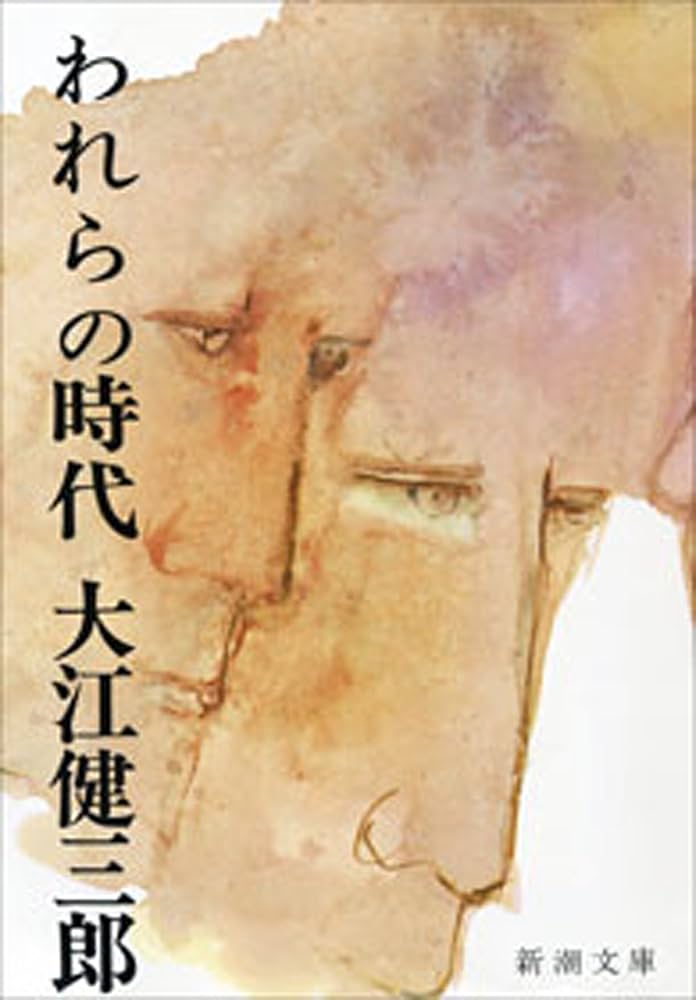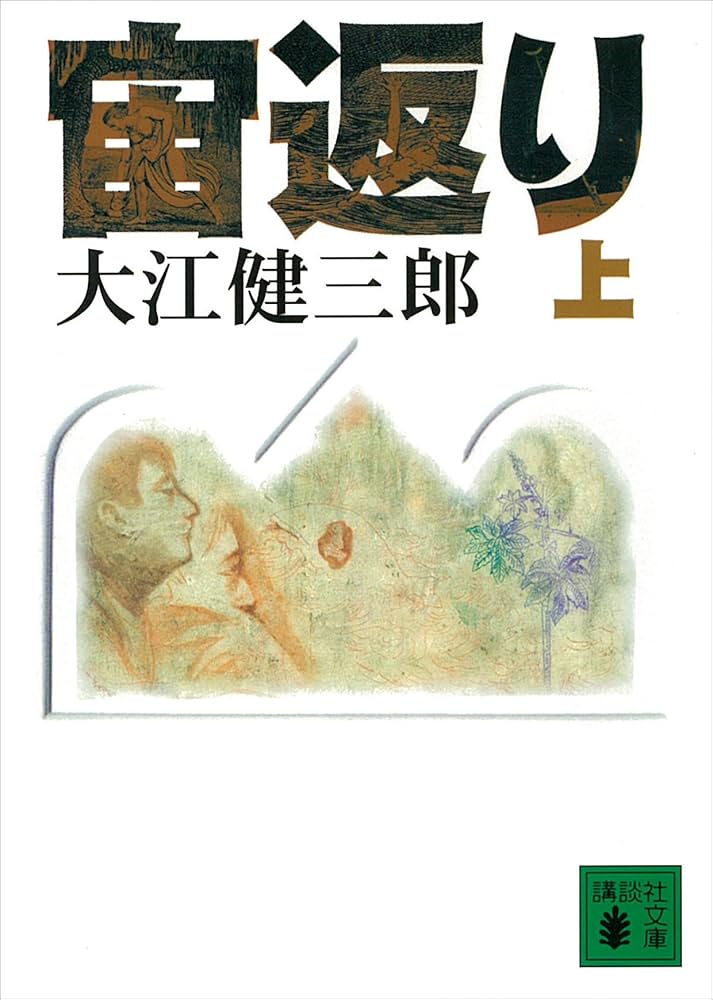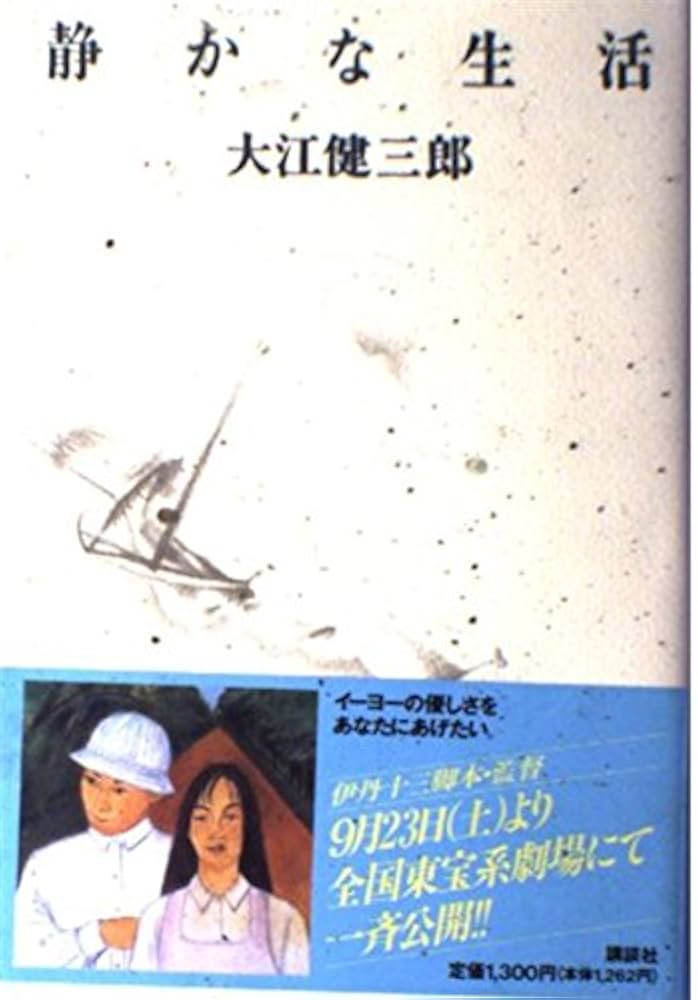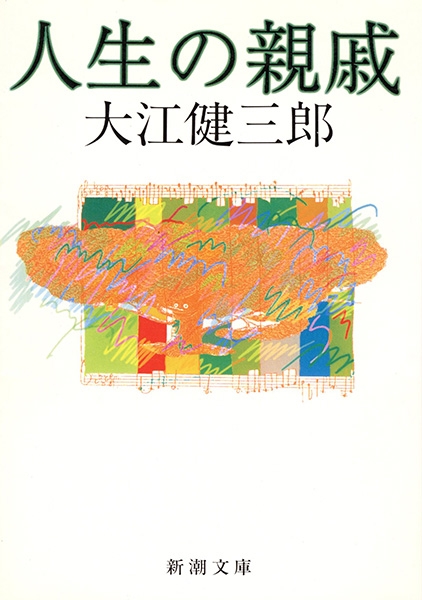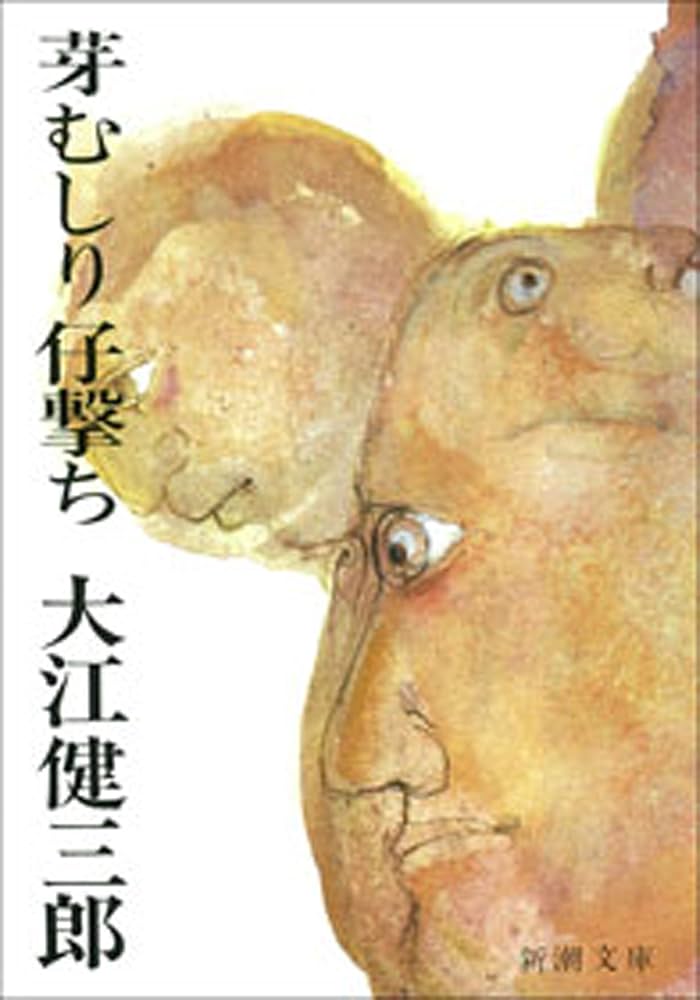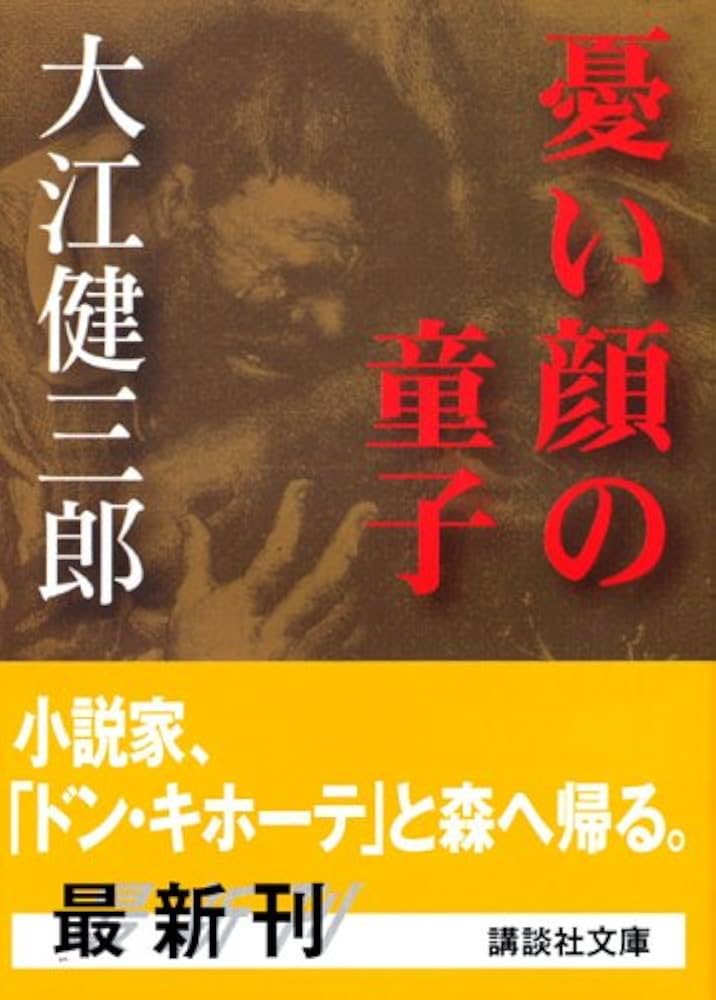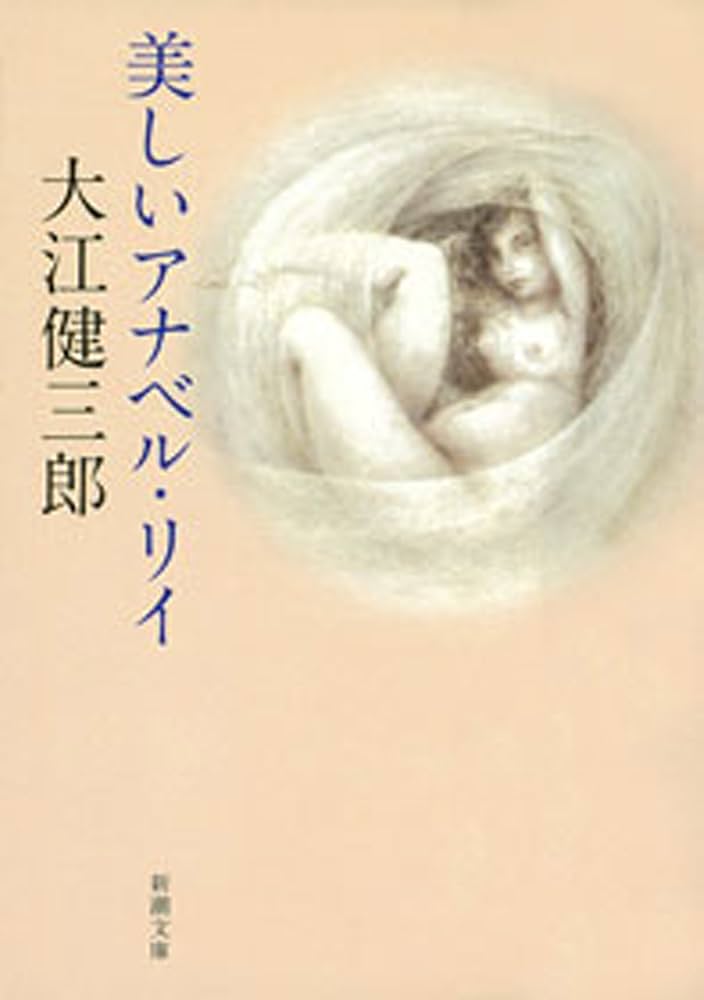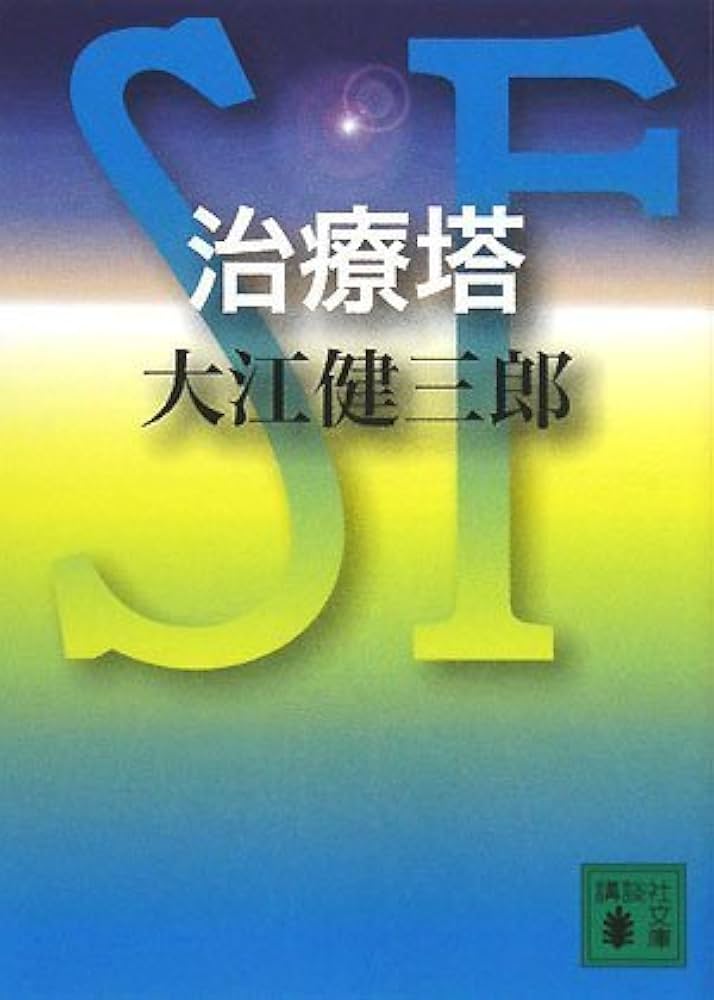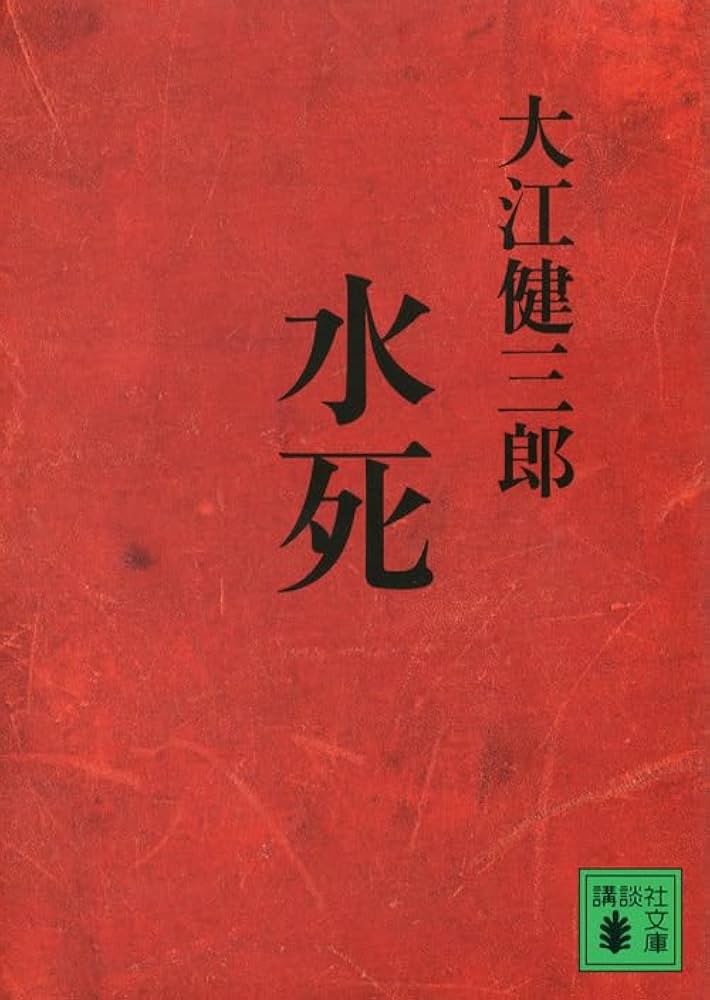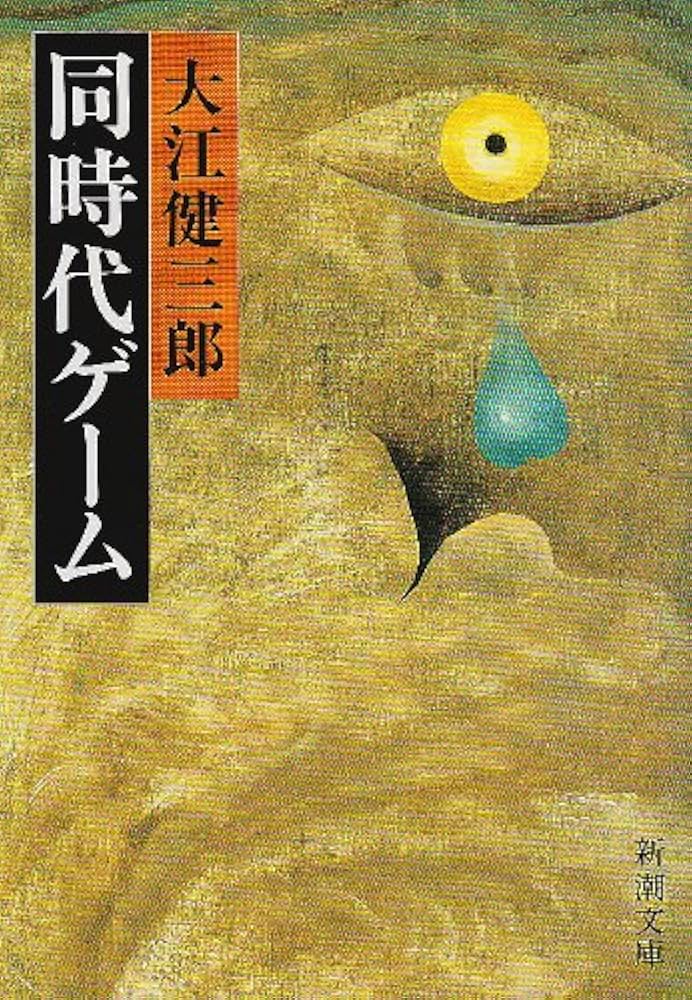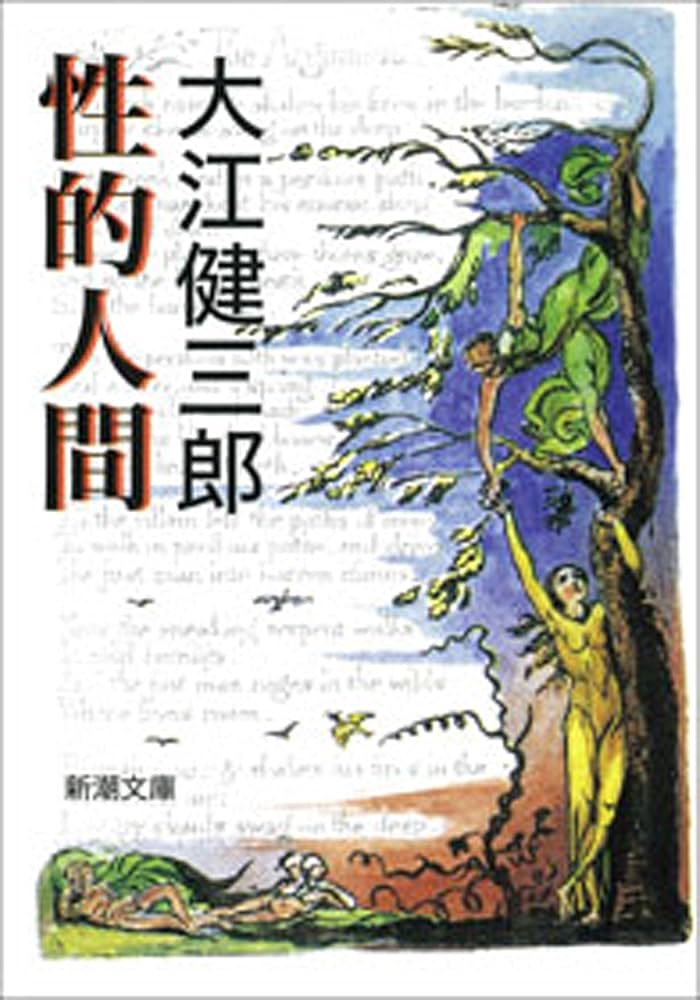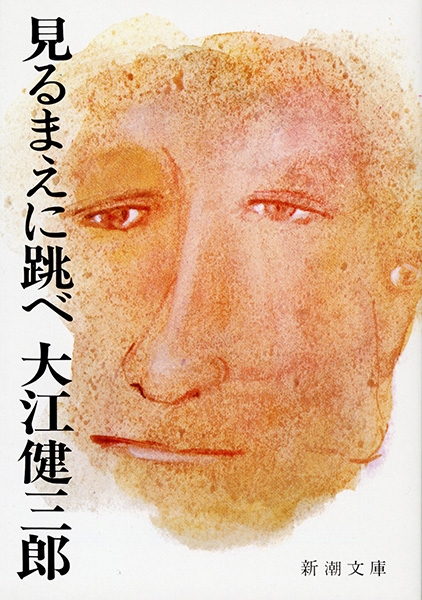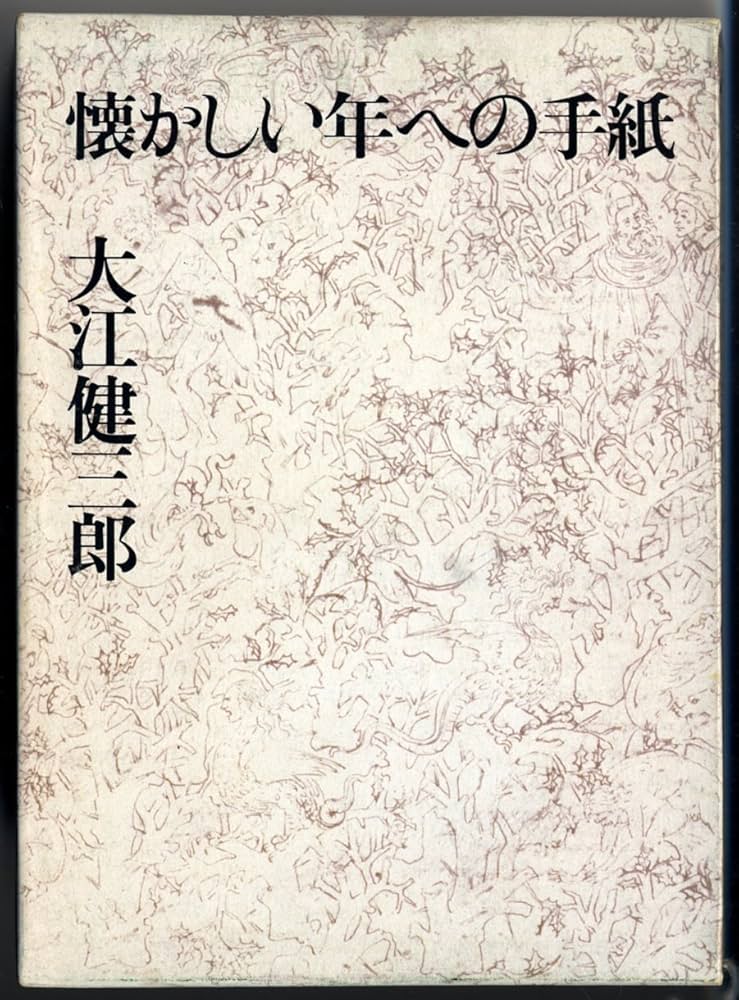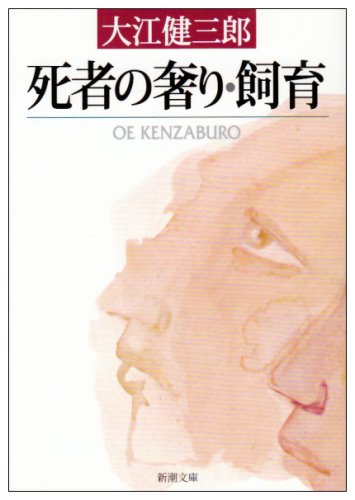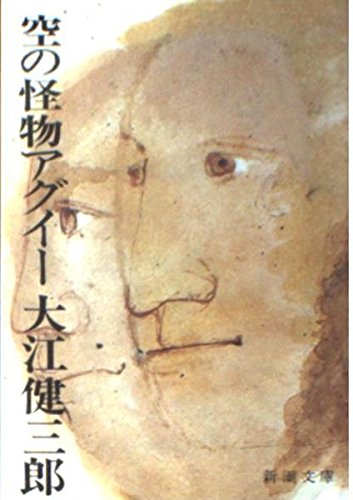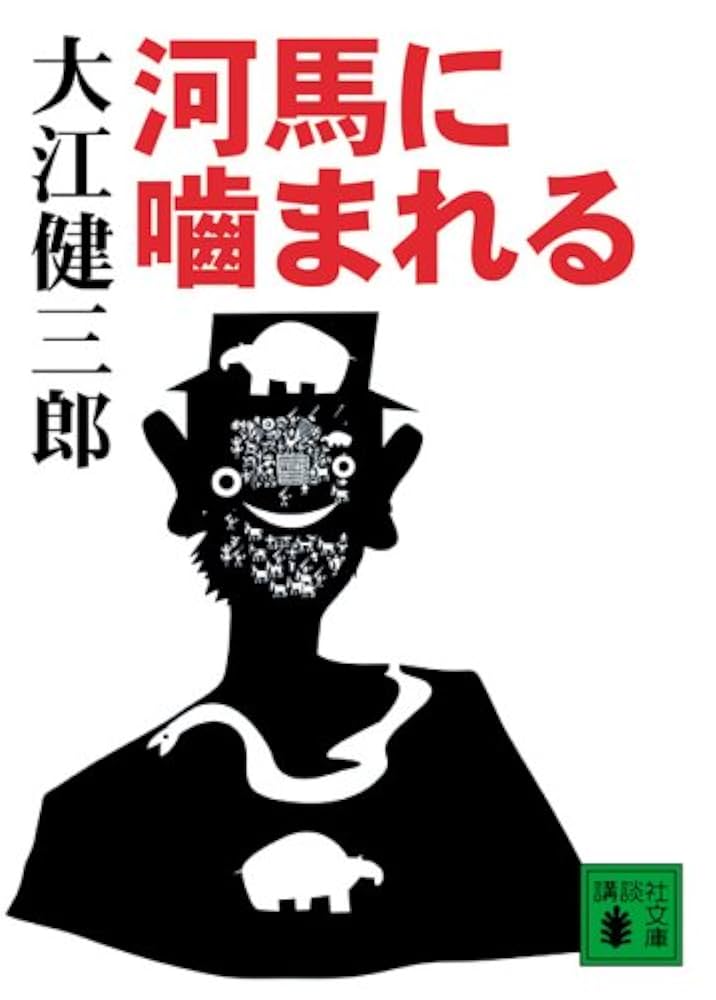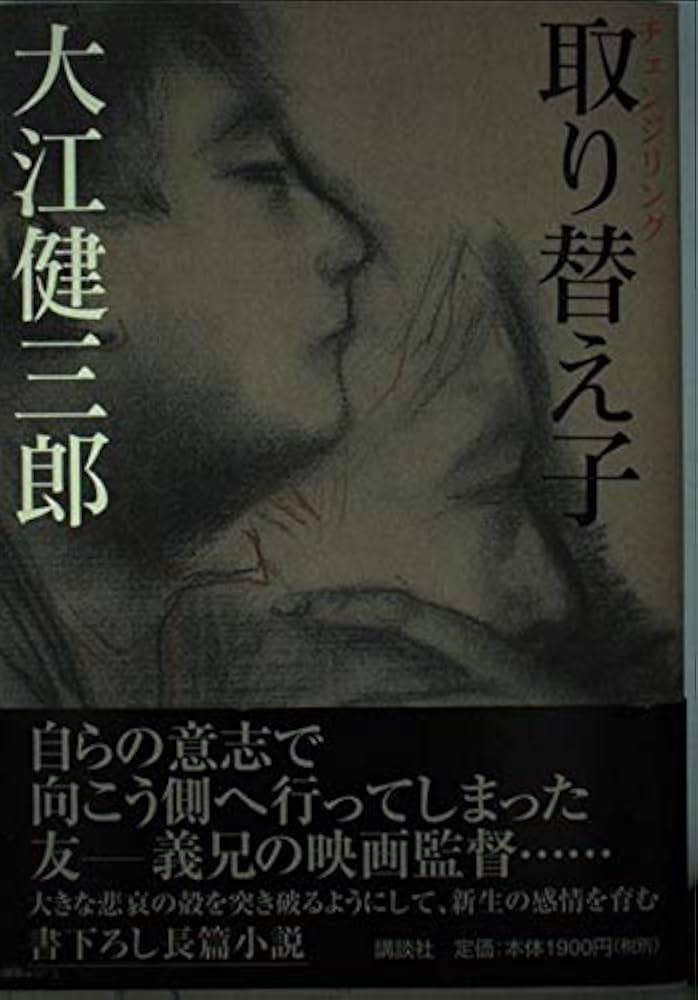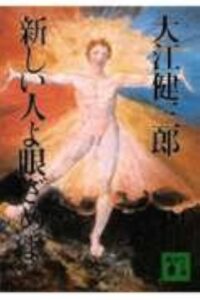 小説『新しい人よ眼ざめよ』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。大江健三郎が描く、知的障害を持つ息子との日々を綴ったこの連作短編集は、読む者の魂を揺さぶらずにはおきません。
小説『新しい人よ眼ざめよ』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。大江健三郎が描く、知的障害を持つ息子との日々を綴ったこの連作短編集は、読む者の魂を揺さぶらずにはおきません。
これから詳しくお話ししていきますが、『新しい人よ眼ざめよ』は単なる私小説の枠には収まらない、人間の再生と救済をテーマにした壮大な物語です。父親である「僕」と息子「イーヨー」の関係性が、ウィリアム・ブレイクの詩を通して深まっていく過程は、本当に感動的ですよ。
この記事では、まず作品の概要をお伝えし、その後に物語の核心に触れるネタバレありの感想をたっぷりと語らせていただきます。『新しい人よ眼ざめよ』が持つ多層的な魅力を、余すところなくお伝えできればと思います。
これから『新しい人よ眼ざめよ』を読む予定の方は、あらすじの部分までを参考にしてくださいね。すでに読まれた方は、深い感想部分で一緒に作品世界に浸りましょう。それでは、始めていきますよ。
『新しい人よ眼ざめよ』のあらすじ
物語の語り手は、著名な作家である「僕」です。彼には知的障害を持つ息子「イーヨー」がいます。本作は、思春期から青年期へと向かうイーヨーと、彼に向き合う家族、特に父親である「僕」の心の軌跡を描いた連作集となっています。各章にはウィリアム・ブレイクの詩や絵画のタイトルが冠され、現実の出来事とブレイクの幻想的な世界が交錯しながら物語は進んでいきます。
ヨーロッパでの仕事から帰国した「僕」は、成長に伴い精神的に不安定になったイーヨーの姿に直面します。家族も手を焼くほどの荒れた状態を見せるイーヨーでしたが、ふとした瞬間に深い悲しみを湛えた表情を見せるのです。そんな息子の姿に、「僕」はブレイクの詩集『無垢の歌、経験の歌』を重ね合わせ、自らの内面や過去とも向き合い始めます。
日々の生活の中で、イーヨーは様々な経験を重ねていきます。てんかんの発作という命の危機、社会の中で障害者が直面する冷たい視線や緊張感、そうした困難の中で、「僕」は息子の「死」を意識し、苦悩します。しかし、イーヨーは時折、父親の想像を超える精神的な強さや、物事の本質を突くような言葉を発し、「僕」に驚きと新たな気づきをもたらすのです。
やがてイーヨーは、野鳥の声を聞き分ける繊細な聴覚や、独特の言葉遊びの才能を見せ始めます。さらに音楽への適性が開花し、作曲の才能さえ発揮するようになります。息子の成長と変化を目の当たりにしながら、「僕」は彼のために世界の事象を言葉にする「定義集」を作ろうと試みます。父と子は、互いに影響を与え合いながら、少しずつ、しかし確実に新しい関係性を築いていくのです。
『新しい人よ眼ざめよ』の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、いよいよ核心に触れていきますね。ネタバレを含みますので、ご注意ください。この作品を読み終えたとき、私が感じたのは、圧倒的な「浄化」の感覚でした。大江健三郎という作家が、自身の最も個人的で痛切な体験を、ウィリアム・ブレイクというフィルターを通すことで、普遍的な魂の救済の物語へと昇華させている。その筆力と覚悟に、ただただ打ちのめされました。『新しい人よ眼ざめよ』は、読むたびに新しい発見と感動を与えてくれる、真の名作だと思います。
まず、この作品の骨格を成している「僕」とイーヨーの関係性について深く考えてみましょう。モデルとなった大江自身と息子・光さんの関係が色濃く反映されていることは周知の事実ですが、小説として読むとき、そこには「父と子」という普遍的なドラマが浮かび上がります。知的障害を持つ息子を受け入れ、共に生きるということ。そこにはきれいごとだけではない、日々の苦闘や絶望、そして「僕」自身の身勝手さや弱さも包み隠さず描かれています。だからこそ、彼らが到達する境地が輝きを放つのでしょう。
物語の序盤、思春期を迎えて荒れるイーヨーの姿は、読んでいて胸が締め付けられるものがあります。言葉でうまく感情を伝えられないもどかしさ、肉体の成長に精神が追いつかないアンバランスさ。「僕」はそんな息子を前に当惑し、時には逃げ出したいという感情さえ抱きます。このあたりのリアリティは、同じように困難を抱える家族を持つ人々にとって、痛いほどの共感を呼ぶのではないでしょうか。しかし、「僕」は逃げません。ブレイクの詩を羅針盤として、息子の内面世界へ分け入ろうとするのです。
ここでウィリアム・ブレイクの存在が非常に重要になってきます。『新しい人よ眼ざめよ』において、ブレイクは単なる引用元ではありません。「僕」とイーヨーをつなぐ共通言語であり、世界を解釈するための聖典のような役割を果たしています。「無垢」と「経験」の間で揺れ動く魂のありようを、ブレイクの詩句が鮮烈に照らし出すのです。難解とされるブレイクの詩が、イーヨーという無垢な魂を通して具体化され、逆にイーヨーの不可解な言動が、ブレイクの詩によって意味を与えられる。この相互作用が見事としか言いようがありません。
特に印象的なのは、イーヨーのてんかん発作のエピソードです。息子の命が脅かされる事態に直面し、「僕」は「死」の恐怖と向き合います。それは、障害を持って生まれた息子に対し、心のどこかで抱き続けてきた罪悪感や不安が噴出する瞬間でもあったでしょう。しかし、この壮絶な体験を通して、「僕」はブレイクが描く「死と再生」のテーマを、観念としてではなく、肌感覚として理解していくのです。死の淵から戻ってきたイーヨーは、何か一つ脱ぎ捨てたかのように、精神的な深みを増していきます。
また、山荘での嵐の夜の出来事も忘れられません。悪夢にうなされる「僕」に対し、イーヨーが「大丈夫です! それはただの夢ですから!」と声をかける場面。これは、私にとって本作の中でも一、二を争う感動的なシーンです。知的障害を持ち、現実と非現実の境界が曖昧だと思われていたイーヨーが、「夢」という抽象概念を理解し、しかも父親を慰め、現実へと引き戻す役割を果たしたのです。この逆転現象に、「僕」は、そして読者は、イーヨーの魂の成熟を見せつけられます。
イーヨーの成長は、音楽の才能の開花という形でも現れます。野鳥の声を聞き分け、言葉遊びを楽しみ、やがて作曲へと至るプロセスは、彼の内面に豊かな世界が広がっていることの証明です。障害によって閉ざされているように見えても、魂は独自の表現方法を模索し、外の世界とつながろうとしている。その生命力の強さに、心を打たれます。音楽は彼らにとって、言葉を超えたコミュニケーションの手段となり、絆をより強固なものにしていくのです。
「僕」が試みる「定義集」の作成も、非常に興味深い試みです。息子に世界の成り立ちや事象を教えるために、言葉を吟味し、定義していく作業。それは、父親として息子を導こうとする行為であると同時に、「僕」自身が世界を再定義し、息子を受け入れるための準備作業でもあったように思います。言葉によって世界に秩序を与え、その秩序の中に息子の居場所を見つけようとする、切実な祈りのような行為だと感じました。
物語は、イーヨーの青年期への移行とともに、新たな局面を迎えます。養護学校の寄宿舎生活という、親元を離れての挑戦。これは、イーヨーにとっても家族にとっても大きな試練です。「僕」は不安を募らせますが、イーヨーは予想外の適応力を見せます。ここにも、親が思う以上に子供は成長し、自立の力を秘めているという真実が描かれています。過保護になりがちな「僕」が、息子を信じて送り出す過程は、父親としての「僕」の成長物語でもあります。
そして、多くの読者が胸を熱くしたであろう結末、最終章「新しい人よ眼ざめよ」での出来事について語らなければなりません。ここには重大なネタバレが含まれます。寄宿舎から戻ったイーヨーが、いつもの愛称で呼ばれることを拒否し、本名である「光」として応答する場面です。「イーヨーはもう居ないのですから」という彼の言葉は、子供時代の終わりと、一人の独立した人格としての「眼ざめ」を力強く宣言しています。
この瞬間、『新しい人よ眼ざめよ』というタイトルの真の意味が明らかになります。「新しい人」とは、子供時代という「無垢」と、様々な困難という「経験」を経て、より高次の段階へと再生したイーヨーのことでしょう。そして同時に、そんな息子を通して絶望を乗り越え、希望を見出した父親、「僕」自身もまた「新しい人」へと眼ざめたのだと言えます。二つの魂が共鳴し、再生を果たした瞬間です。
この結末がもたらすカタルシスは計り知れません。障害を持つ子との生は、これからも困難の連続かもしれません。しかし、彼らはもう以前の彼らではありません。互いを一人の人間として尊重し、支え合う確かな基盤ができたのです。ブレイクの詩が予言したように、闇を経て光へと至る道筋が、彼らの人生の中に示されたのです。
大江健三郎は、個人的な苦悩を出発点としながら、それを芸術的な高みへと引き上げ、私たち読者に普遍的な希望を提示してくれました。人間はどんなに傷つき、絶望の淵に立たされたとしても、他者との関わりの中で、あるいは芸術や魂の深いレベルでの交流を通して、再び立ち上がり、新しく生まれ変わることができる。そんな力強いメッセージが、この作品全体から伝わってきます。
『新しい人よ眼ざめよ』を読むことは、自分自身の内面を見つめ直す旅でもあります。私たちは皆、心のどこかに傷や弱さを抱えて生きています。「僕」の苦悩は私たちの苦悩であり、イーヨーの純粋さは私たちが失ってしまった、あるいは心の奥底に眠らせている何かを呼び覚ましてくれます。この作品は、読む者の魂に直接語りかけ、静かな、しかし確かな変革を促す力を持っています。
長く語ってきましたが、この作品の魅力は尽きることがありません。一文一文が重みを持ち、読むたびに異なる響きを伝えてきます。もしあなたが今、人生の困難に直面しているなら、あるいは人間存在の深淵に触れたいと願うなら、ぜひこの本を手に取ってみてください。きっと、あなたの中の「新しい人」を呼び覚ますきっかけになるはずです。
最後に、この作品が持つ社会的意義についても触れておきたいと思います。障害を持つ人々とその家族の生を、感傷や同情ではなく、尊厳を持って描いたこと。彼らの内面の豊かさと可能性を提示したこと。これは、発表当時から現在に至るまで、社会の意識を変える上で大きな役割を果たしてきたと言えるでしょう。文学が持つ力を改めて感じさせてくれる、真の傑作です。
ここまでネタバレを含んで感想を綴ってきましたが、作品の真価は、実際にその文章に触れ、物語の世界に身を浸すことでしか分かりません。私のこの拙い文章が、あなたが『新しい人よ眼ざめよ』という素晴らしい作品と出会う、あるいは再会する一助となれば幸いです。魂の再生の物語を、ぜひあなた自身の目で確かめてみてください。
まとめ:『新しい人よ眼ざめよ』のあらすじ・ネタバレ・長文感想
今回は、大江健三郎の傑作『新しい人よ眼ざめよ』について、あらすじからネタバレを含む深い感想まで、じっくりとお話ししてきました。
この作品は、知的障害を持つ息子イーヨーと、作家である父「僕」の魂の交流を描いた連作短編集です。ウィリアム・ブレイクの詩的世界と現実の過酷な日常が重なり合い、その中で父子が葛藤し、成長し、やがて「新しい人」としての再生を果たすまでの道のりが感動的に綴られています。
特に、イーヨーが子供時代の愛称を捨て、自立した個人としての自覚を示す結末は、読む者に深い衝撃と希望を与えてくれます。それは、困難な状況にあっても人間は精神的に高められ、再生することができるという力強いメッセージです。
『新しい人よ眼ざめよ』は、単なる家族の記録を超え、普遍的な人間愛と魂の救済を描いた文学の金字塔です。この記事を読んで興味を持たれた方は、ぜひ原作を手に取り、その深く豊かな世界に触れてみてください。あなたの心にも、きっと静かな眼ざめが訪れることでしょう。