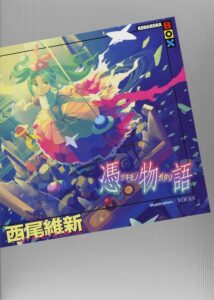 小説「憑物語」の物語の筋道を物語の結末まで含めてお伝えします。読み応えのある所感も書き記していますので、どうぞお付き合いください。この作品は、〈物語〉シリーズのファイナルシーズンの一作として刊行され、主人公である阿良々木暦の身に起こる重大な変化と、それに伴う彼の葛藤が描かれています。
小説「憑物語」の物語の筋道を物語の結末まで含めてお伝えします。読み応えのある所感も書き記していますので、どうぞお付き合いください。この作品は、〈物語〉シリーズのファイナルシーズンの一作として刊行され、主人公である阿良々木暦の身に起こる重大な変化と、それに伴う彼の葛藤が描かれています。
「憑物語」は、これまでのシリーズで積み重ねてきた暦の行動の結果が、彼自身に跳ね返ってくるという、非常にシリアスな局面を迎える物語です。彼がこれまで助けてきたヒロインたちとは異なり、今回は暦自身が大きな問題を抱え、その解決のために奔走することになります。
物語の核心に触れる部分も多く含んでおりますので、まだ作品をお読みでない方はご注意ください。しかし、この作品の持つ深いテーマ性や、キャラクターたちの魅力、そして西尾維新さんならではの展開の妙を、少しでもお伝えできればと考えております。
それでは、まずは「憑物語」がどのような物語なのか、その概要からご紹介いたしましょう。この物語が持つ独特の雰囲気や、引き込まれる世界観の一端を感じ取っていただければ幸いです。
小説「憑物語」のあらすじ
大学受験を目前に控えた二月。阿良々木暦は、妹の月火と風呂場で戯れている最中、ふと洗面所の鏡に自分の姿が映らなくなっていることに気づきます。この異常事態は、暦がこれまで幾度となく吸血鬼の力を行使してきたことによる、吸血鬼化の進行を意味していました。もはや、単なる吸血鬼の眷属ではなく、「生まれついて」の吸血鬼へと変質しつつあったのです。
この事態を重く見た暦は、吸血鬼の専門家である影縫余弦と、その式神である斧乃木余接に助けを求めます。余弦は、暦の吸血鬼性が危険なレベルにまで高まっていること、そしてこれ以上吸血鬼の力を使えば、専門家として彼を排除しなければならなくなると警告します。暦は、今後一切吸血鬼の力を使わないと固く誓います。
しかし、そんな暦の決意を嘲笑うかのように、彼の妹である火憐と月火が何者かによって誘拐されてしまいます。妹たちを救い出すためには、吸血鬼の力を使わざるを得ないかもしれない。そんな葛藤を抱えながら、暦は犯人が指定した場所へと向かうことになります。
神原駿河の家で妹たちがさらわれたことを知った暦は、現場に残された手紙に従い、北白蛇神社へ。そこには、以前から暦の前に現れては不穏な言葉を残していく謎の存在、忍野扇が待ち構えていました。扇は暦を挑発しますが、暦は妹たちを救う決意を胸に、神社の階段を上り始めます。
道中、余接は自らの成り立ちについて語り始めます。彼女は、かつて人形師であった手折正弦によって死体から作られた付喪神であること、そしてその所有権を巡って、正弦と余弦が争った過去があることを明かします。もし余弦が間に合わず、暦が正弦に太刀打ちできないようなら、自分自身を差し出すようにと余接は暦に告げます。
神社の境内で暦たちを待っていたのは、妹たちを誘拐したと思われる手折正弦でした。しかし、正弦の口から語られたのは意外な言葉でした。彼は自分がなぜここにいるのか、なぜ暦を殺そうとしているのかさえ理解しておらず、何者かに操られている可能性を示唆します。そして、「忍野メメを探せ」という言葉を残し、突如現れた余弦の式神である余接の「アンリミテッド・ルールブック」によって粉砕されてしまうのでした。正弦を操り、暦と余接の関係を悪化させることが黒幕の狙いだったのではないかと余接は推測し、暦の力になることを改めて約束するのでした。
小説「憑物語」の長文感想(ネタバレあり)
「憑物語」は、阿良々木暦という存在の根幹に関わる変化が描かれる、非常に重要な一作だと感じています。彼が吸血鬼の力を使い続けた結果、人間としての境界線が曖昧になっていく様は、読んでいて胸が締め付けられる思いでした。
物語の冒頭、暦が鏡に映らない自分を発見する場面は衝撃的です。日常の中に潜む非日常、そのコントラストが鮮やかで、一気に物語の世界に引き込まれました。妹の月火との何気ない会話ややり取りが、その後のシリアスな展開をより一層際立たせているように思います。
吸血鬼化が進行し、「治す手段はない」と宣告される暦の絶望は計り知れません。これまで彼は、他者を救うためにその力を行使してきましたが、その代償が自分自身に降りかかってきたのです。この「代償」というテーマは、〈物語〉シリーズ全体を貫く重要な要素の一つであり、「憑物語」ではそれが暦自身に向けられる形で、より深刻な問題として提示されています。
そんな絶望的な状況の中で、斧乃木余接の存在が際立ってきます。感情が希薄なはずの彼女が、暦に対して見せる気遣いや優しさは、どこか人間的であり、読んでいて心が温かくなりました。彼女の過去や、影縫余弦、手折正弦との関係性も明らかになり、キャラクターとしての深みが増したように感じます。特に、暦に対して「僕のようになったらダメだからね」と語る場面は、彼女の複雑な心情が垣間見え、印象的でした。
専門家である影縫余弦の厳しさも、物語に緊張感を与えています。彼女は暦に対して非情な宣告をしますが、それは専門家としての立場を貫いているからであり、決して暦を憎んでいるわけではないことが伝わってきます。彼女の存在が、暦に「人間であり続けること」への強い意志を促しているのかもしれません。
「これ以上吸血鬼の力を使わない」という暦の決意は、妹たちの誘拐という事件によって、早々に試されることになります。この展開は非常に巧みで、読者の心を揺さぶります。力を使えば妹を助けられるかもしれないが、使えば人間ではなくなってしまう。その究極の選択を迫られる暦の葛藤は、読んでいて息苦しさを感じるほどでした。
忍野扇の暗躍も、物語に不穏な影を落としています。彼女(彼?)の目的は一体何なのか、なぜ暦の前に現れるのか。その謎は深まるばかりで、今後の展開への興味をかき立てられます。扇の言葉は常に多義的で、暦だけでなく読者をも惑わし、物語のミステリアスな雰囲気を高めています。
手折正弦との対峙は、意外な結末を迎えます。彼自身も何者かに操られていたという事実は、事件の背後にさらなる黒幕がいることを示唆しています。そして、彼が残した「忍野メメを探せ」という言葉。シリーズ初期から登場し、暦にとって大きな影響を与えた忍野メメの不在が、ここにきて再びクローズアップされるのは興味深い展開です。
この作品では、暦の人間性が試されると同時に、彼を取り巻く人々との絆も試されているように感じました。火憐や月火といった妹たちの存在は、暦にとって守るべきものであり、彼の行動原理の大きな部分を占めています。彼女たちが危険に晒されることで、暦は自身の限界や無力さを痛感させられます。
また、影縫余弦や斧乃木余接といった、ある意味では「人間ではない」存在たちが、暦に対して人間的な情を示したり、あるいは人間としてのあり方を問うたりする構図も面白いと感じました。彼女たちとの関わりを通して、暦は自分自身を見つめ直し、人間としてどう生きるべきかを模索していくことになります。
西尾維新さん特有の言葉遊びや、哲学的な問答も健在です。シリアスな状況の中にも、思わずクスリとさせられるような掛け合いが挟まれることで、物語に独特のリズムが生まれています。特に暦と余接の会話は、どこか噛み合っているようで噛み合っていない、不思議な魅力があります。
「憑物語」を読むことで、私たちは「人間であるとはどういうことか」「何かを得るためには何かを失わなければならないのか」といった、普遍的な問いを投げかけられているような気がします。暦が直面する問題は極端なものですが、その根底にある葛藤や苦悩は、私たち自身の日常にも通じる部分があるのではないでしょうか。
物語の結末では、手折正弦を操っていた黒幕の正体は明かされず、暦の吸血鬼化の問題も根本的な解決には至っていません。しかし、暦は余接という新たな協力者を得て、前に進む決意を固めます。この終わり方は、〈物語〉シリーズのファイナルシーズンがまだ始まったばかりであることを示唆しており、今後の展開への期待感を高めてくれます。
この作品を通じて、阿良々木暦というキャラクターの魅力が、より一層深まったように感じます。彼は決して完璧なヒーローではなく、過ちを犯し、悩み、苦しみながらも、それでも誰かのために立ち上がろうとする。そんな彼の人間臭さが、多くの読者を惹きつけるのではないでしょうか。
「憑物語」は、〈物語〉シリーズのファンであれば必読の一作であることはもちろん、まだシリーズに触れたことのない方にとっても、西尾維新さんの作り出す世界の奥深さや、キャラクターたちの生き生きとした姿を感じ取ることができる作品だと思います。読み終えた後には、きっと阿良々木暦という青年の未来を見届けたくなるはずです。
まとめ
小説「憑物語」は、主人公・阿良々木暦が自身の存在意義を問われる、重厚なテーマを内包した物語です。鏡に映らないという衝撃的な事態から始まり、吸血鬼化の進行という逃れられない現実に直面する暦の苦悩が、痛いほど伝わってきます。
これまでの彼の行いが、巡り巡って自身に返ってくるという展開は、シリーズを通じた一つの大きな転換点と言えるでしょう。妹たちの誘拐という事件は、そんな暦にさらなる試練を与え、彼の決意を揺るがします。
斧乃木余接をはじめとする周囲のキャラクターたちとの関係性も、物語に深みを与えています。特に余接の存在は、絶望的な状況に置かれた暦にとって、一条の光となるのかもしれません。彼女の過去や、専門家たちとの因縁も絡み合い、物語は複雑な様相を呈していきます。
「憑物語」は、シリアスな展開の中にも西尾維新さんらしい言葉遊びや軽妙な会話が織り交ぜられ、読者を飽きさせません。物語の結末は多くの謎を残しつつも、暦の未来への一歩を感じさせるものでした。この作品を読むことで、〈物語〉シリーズの持つ奥深さを再認識し、続く物語への期待が一層高まることでしょう。


.jpg)


赤き征裁vs橙なる種-728x1024.jpg)






曳かれ者の小唄-721x1024.jpg)





























青色サヴァンと戯言遣い-722x1024.jpg)







兎吊木垓輔の戯言殺し-724x1024.jpg)











































.jpg)




十三階段.jpg)