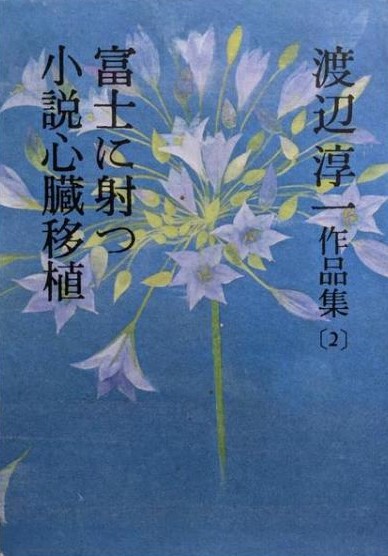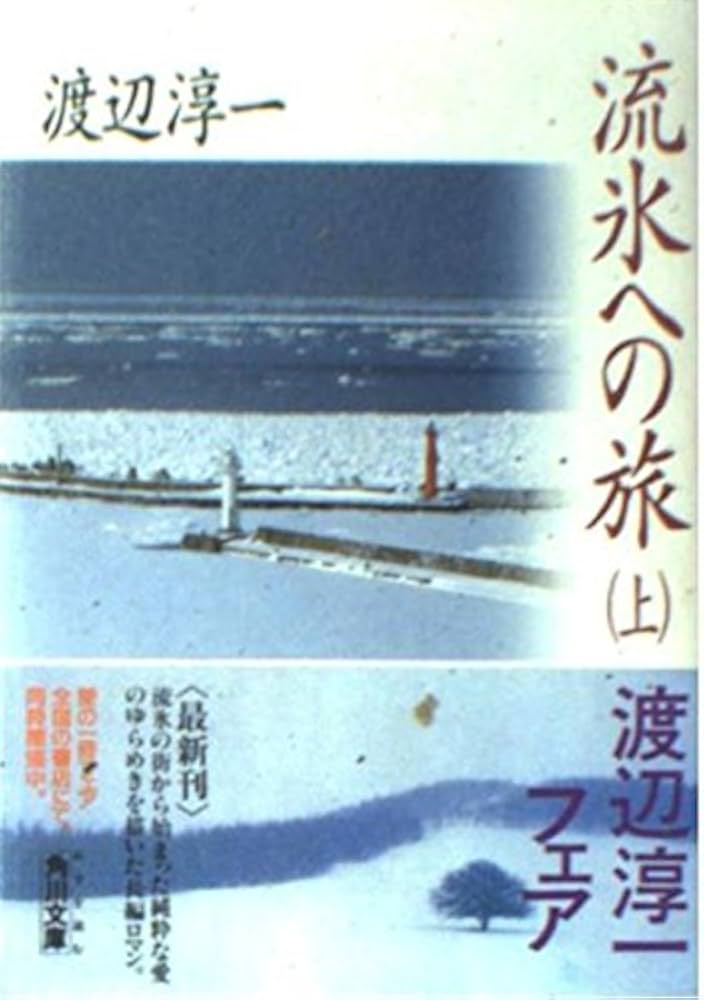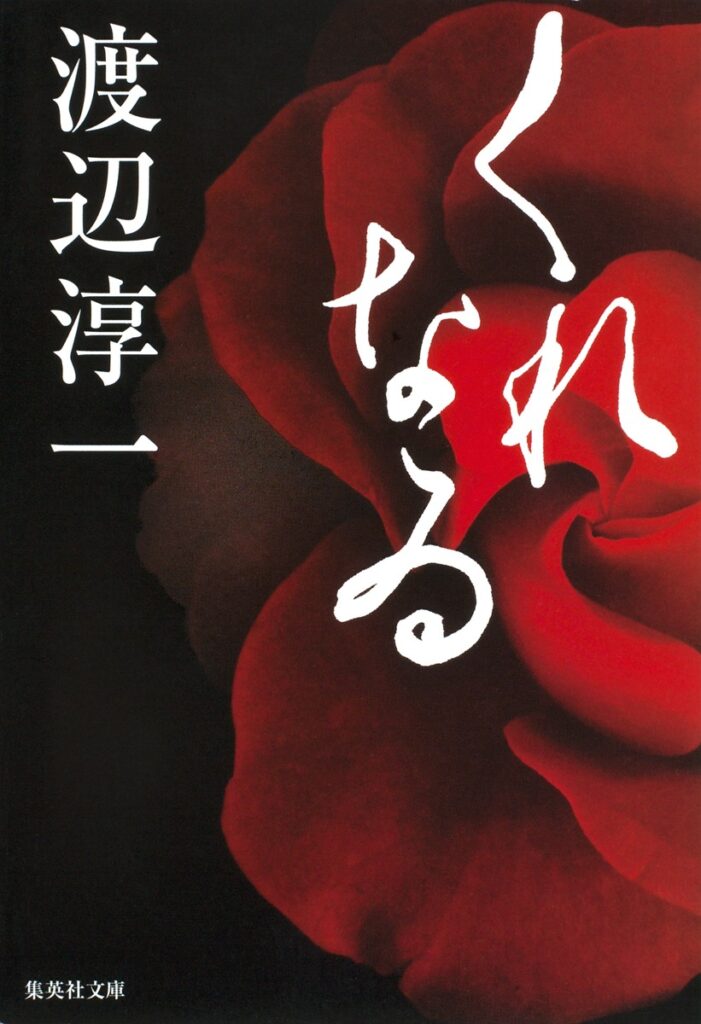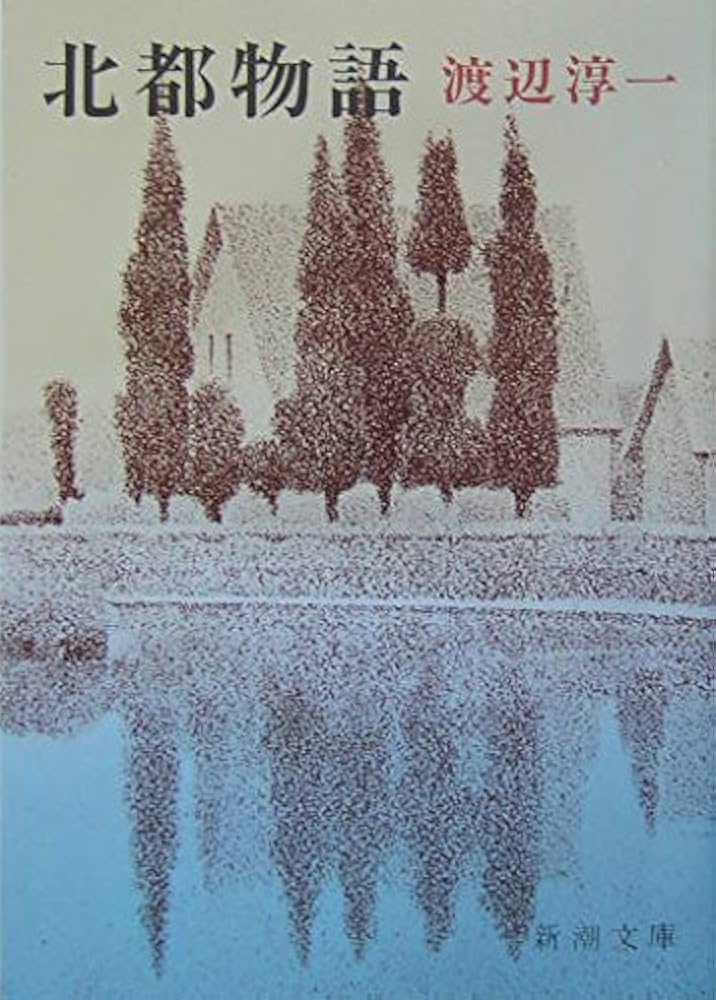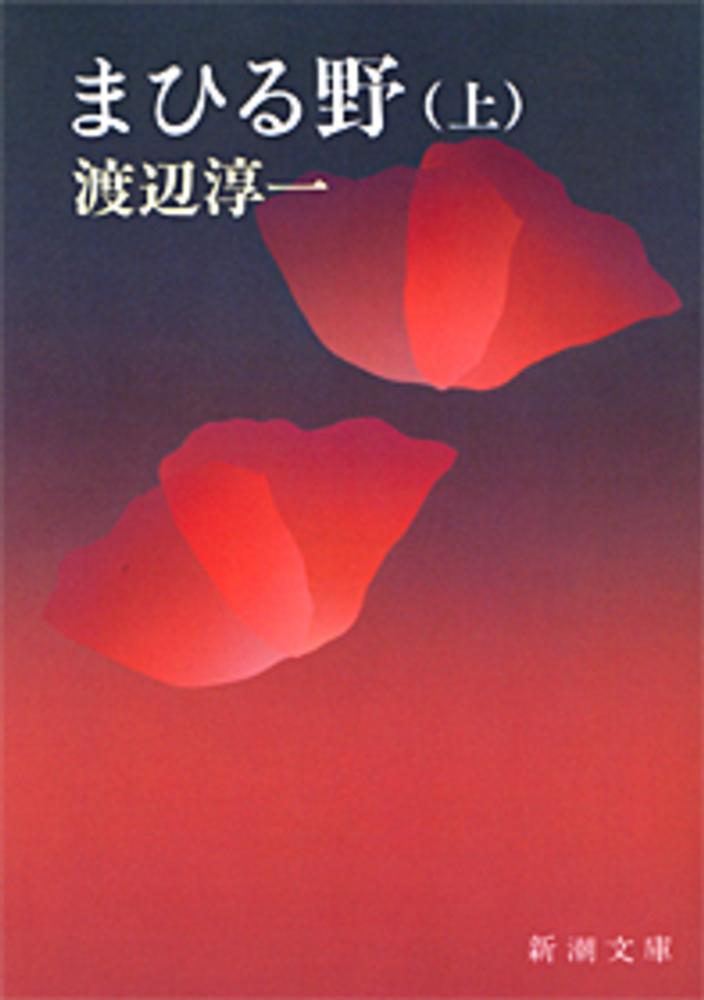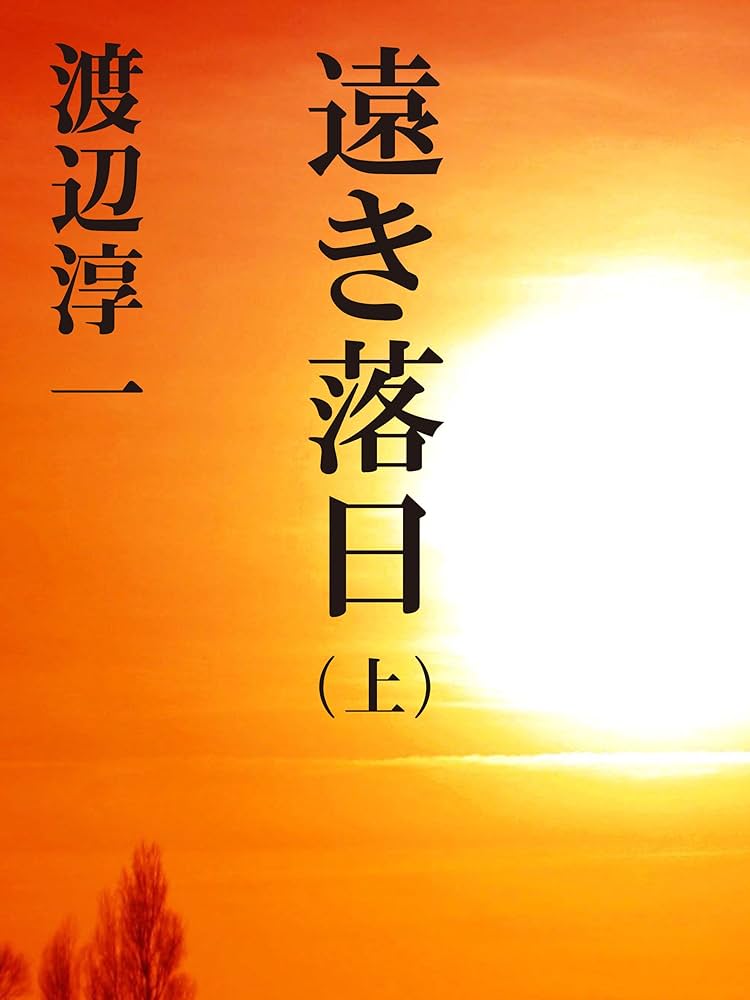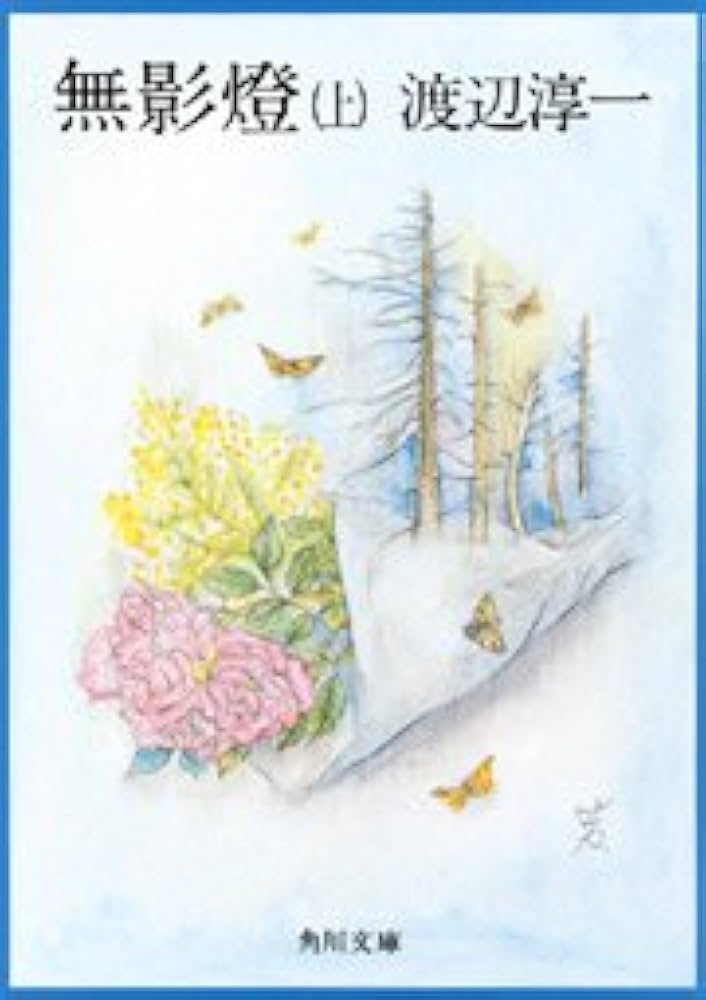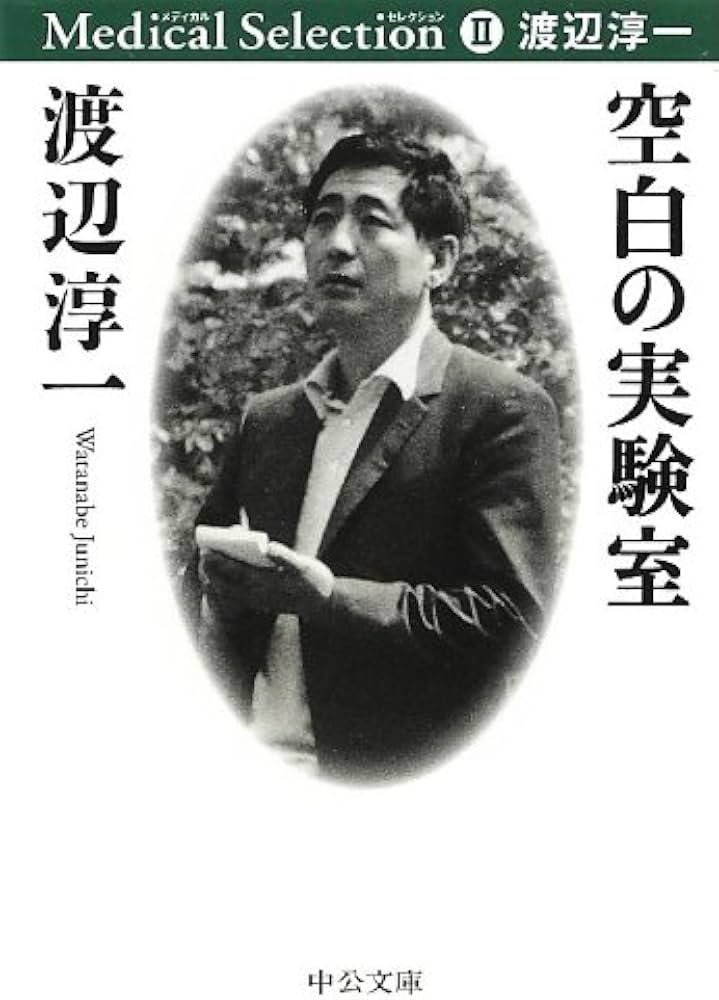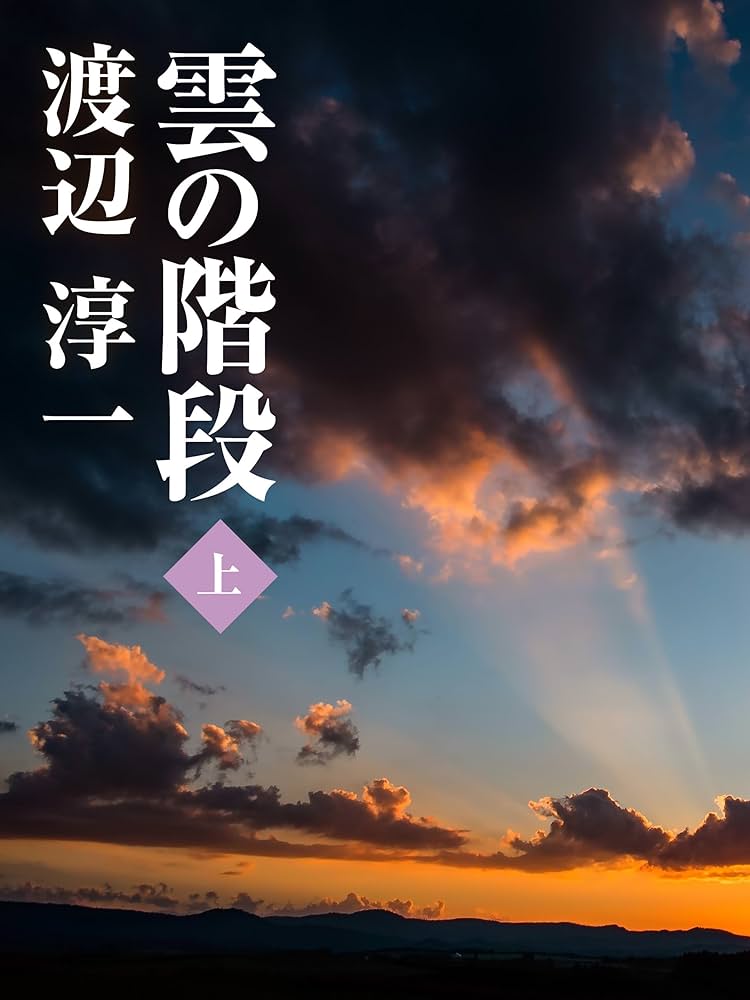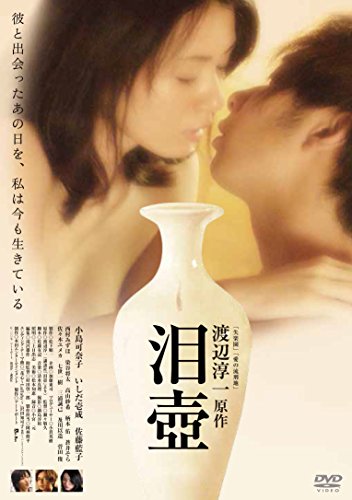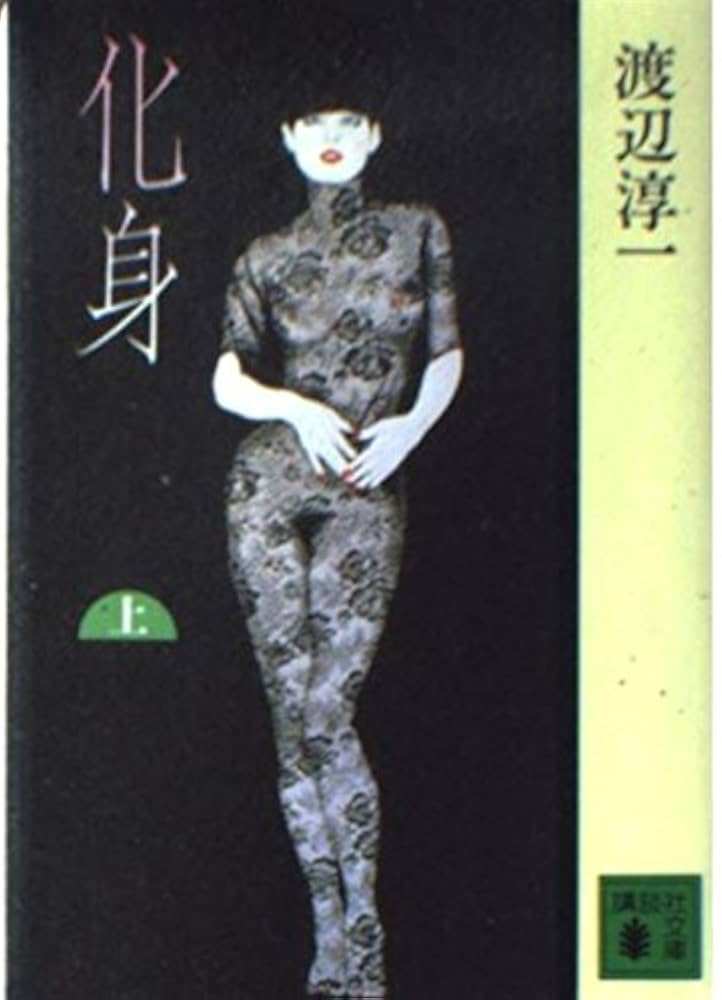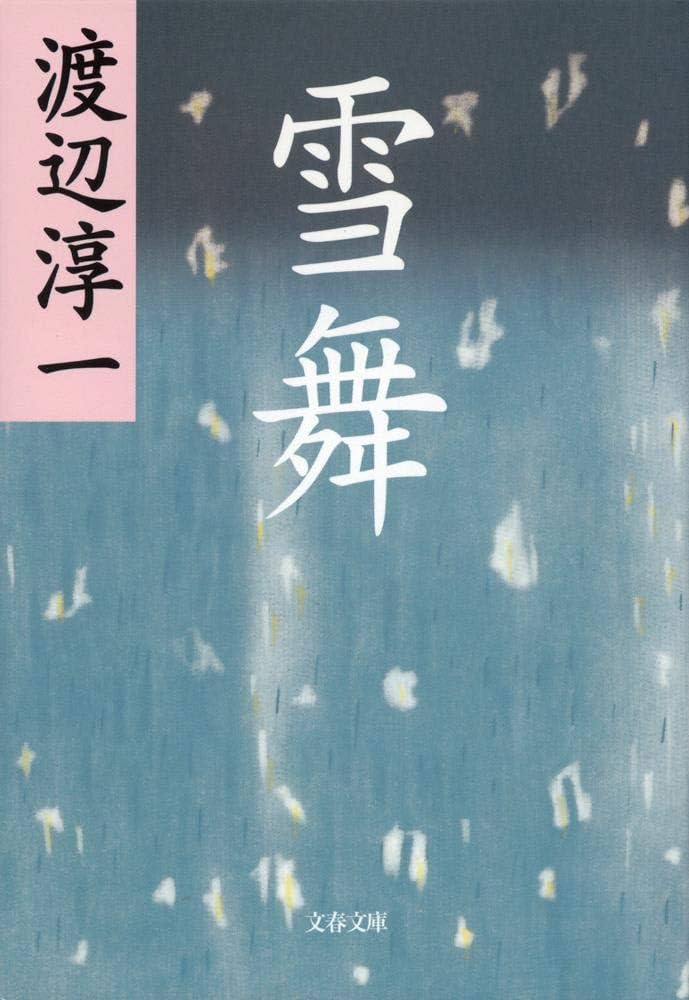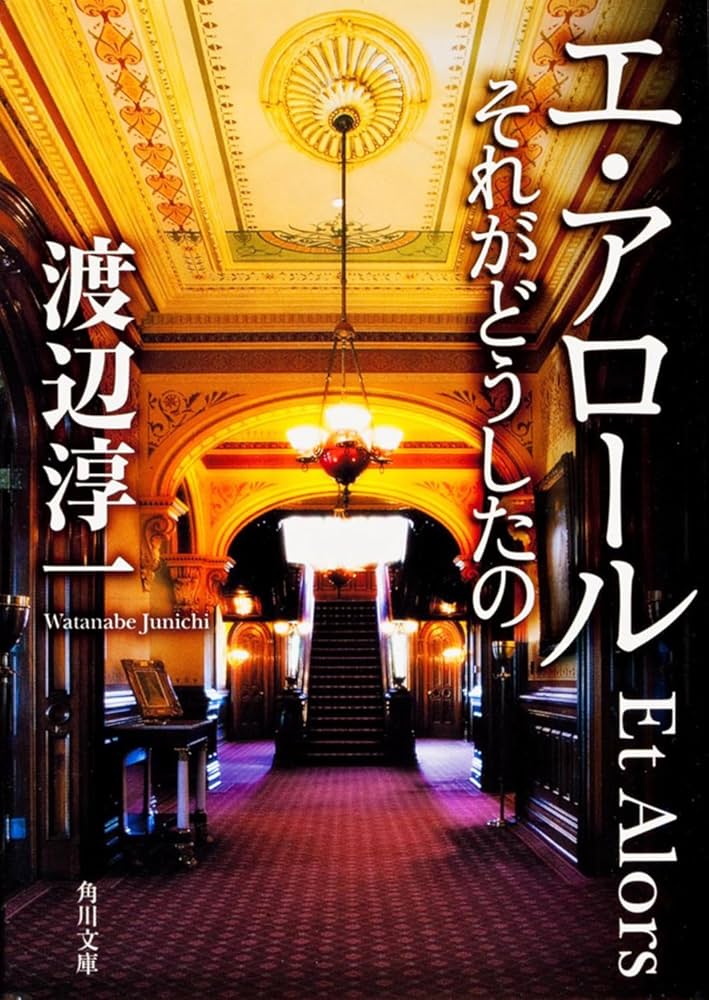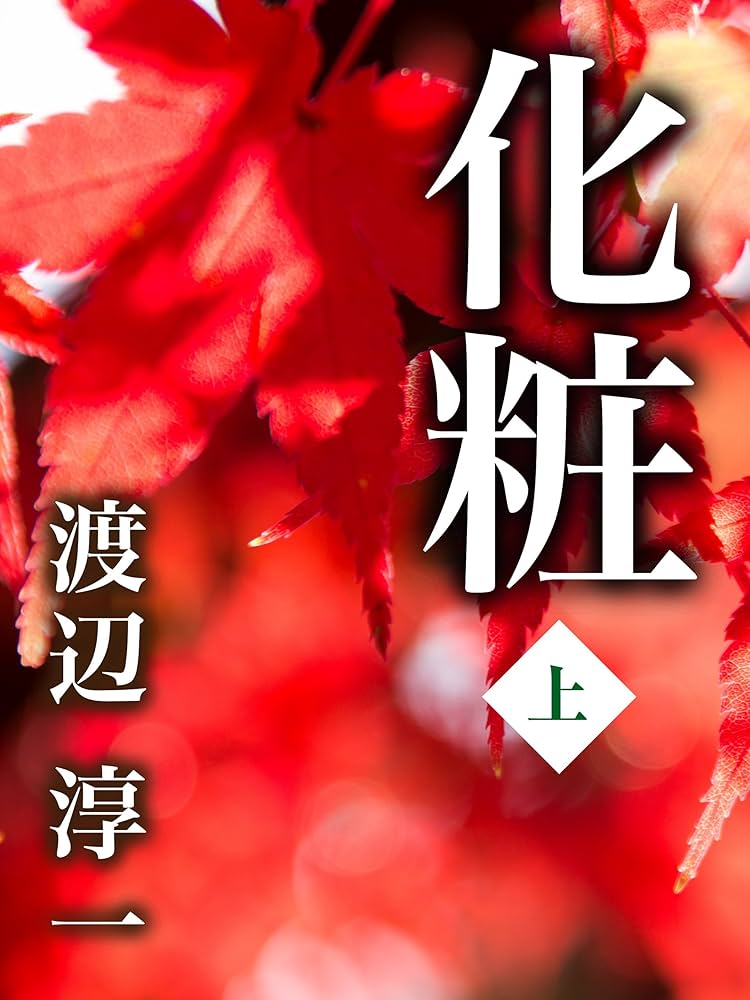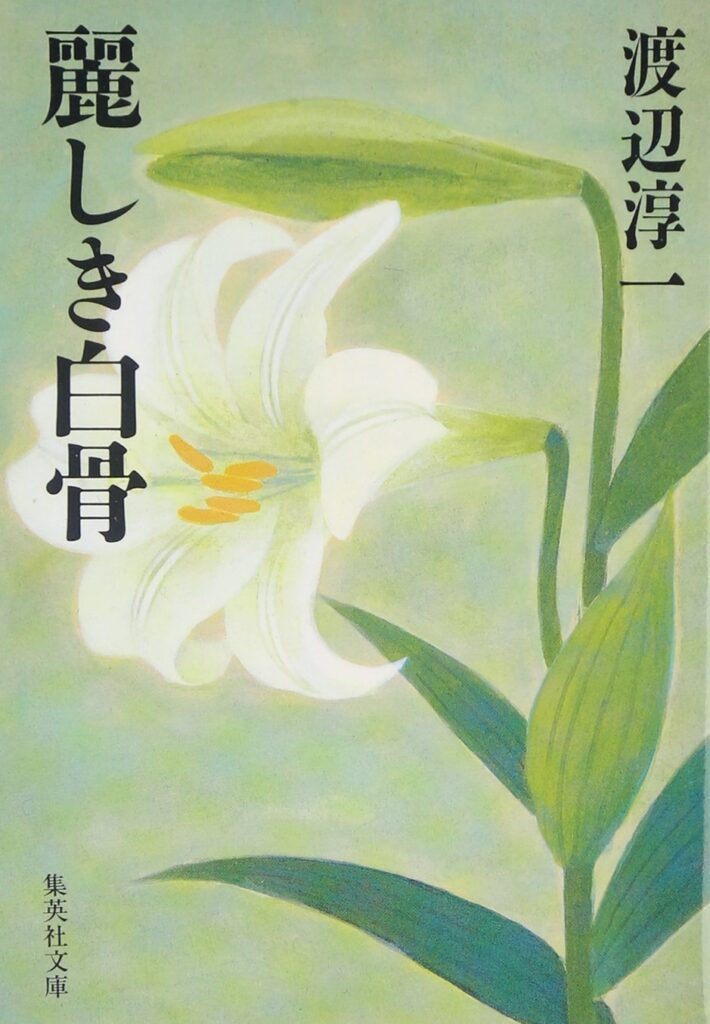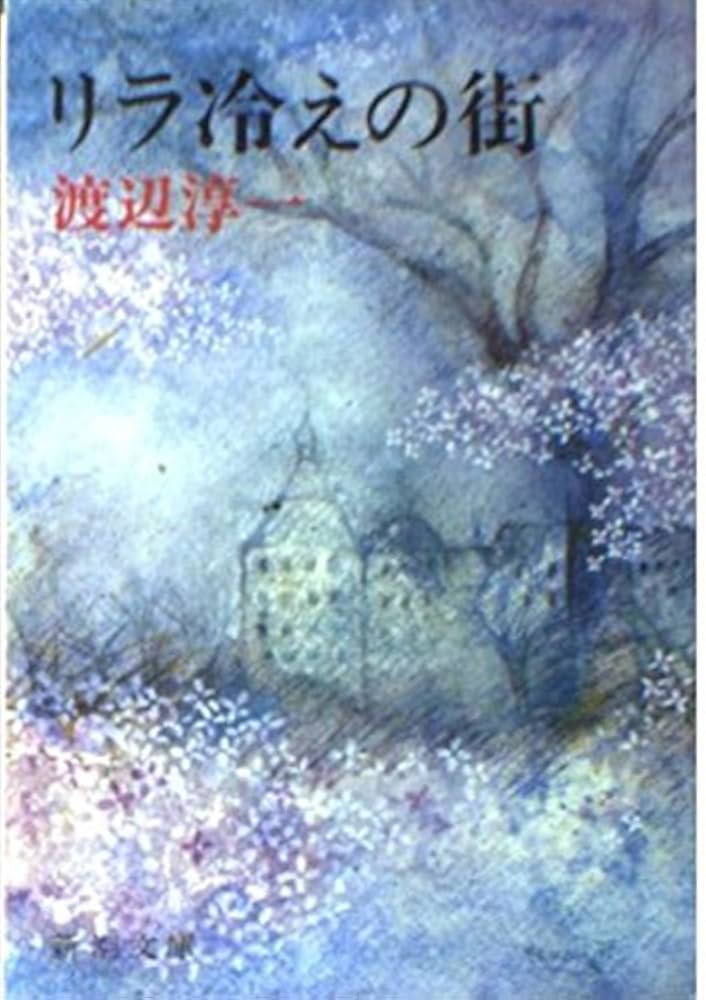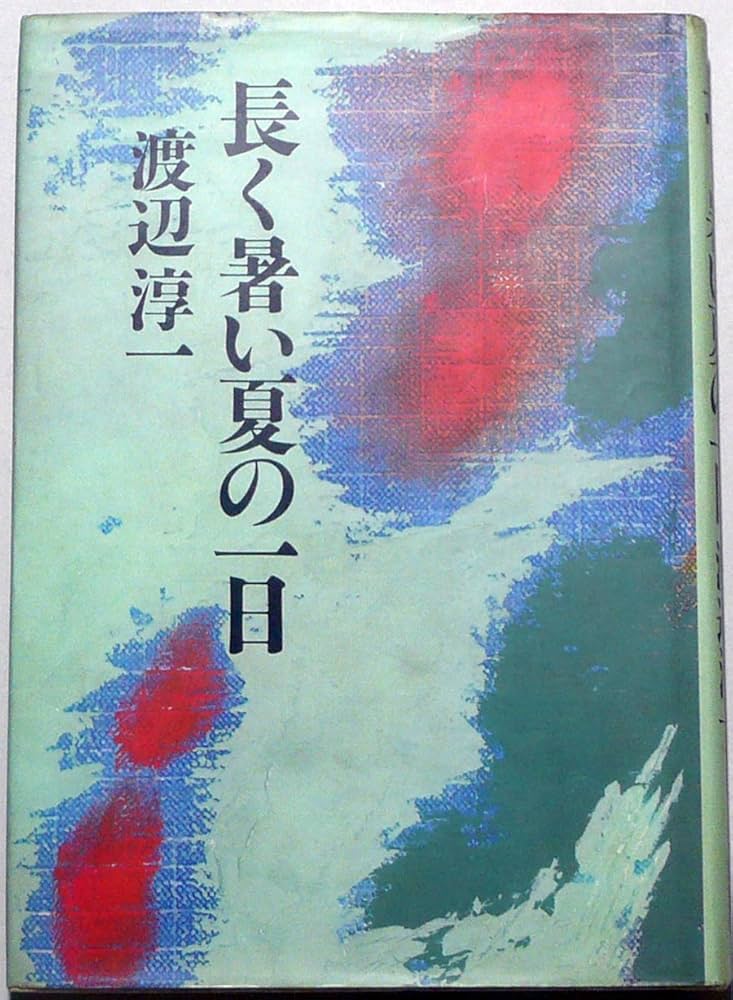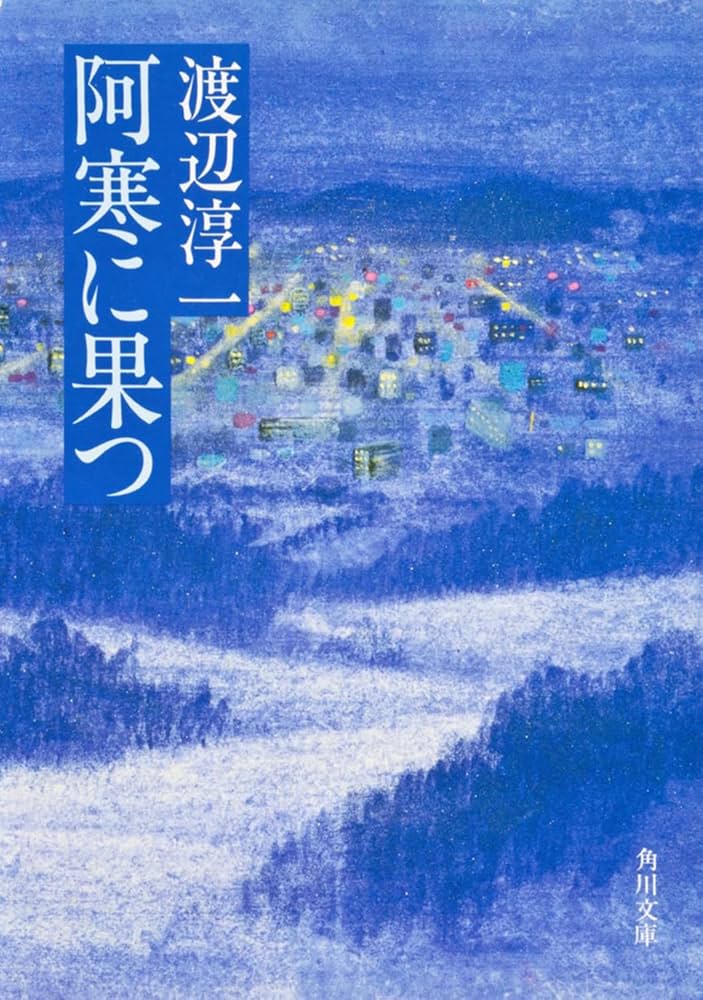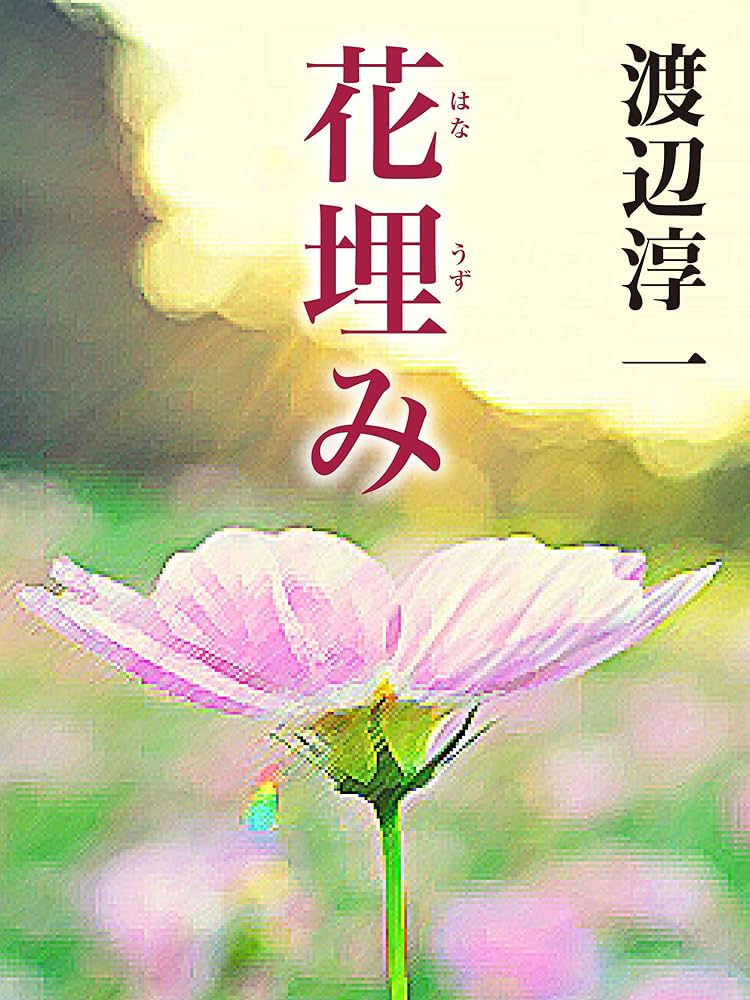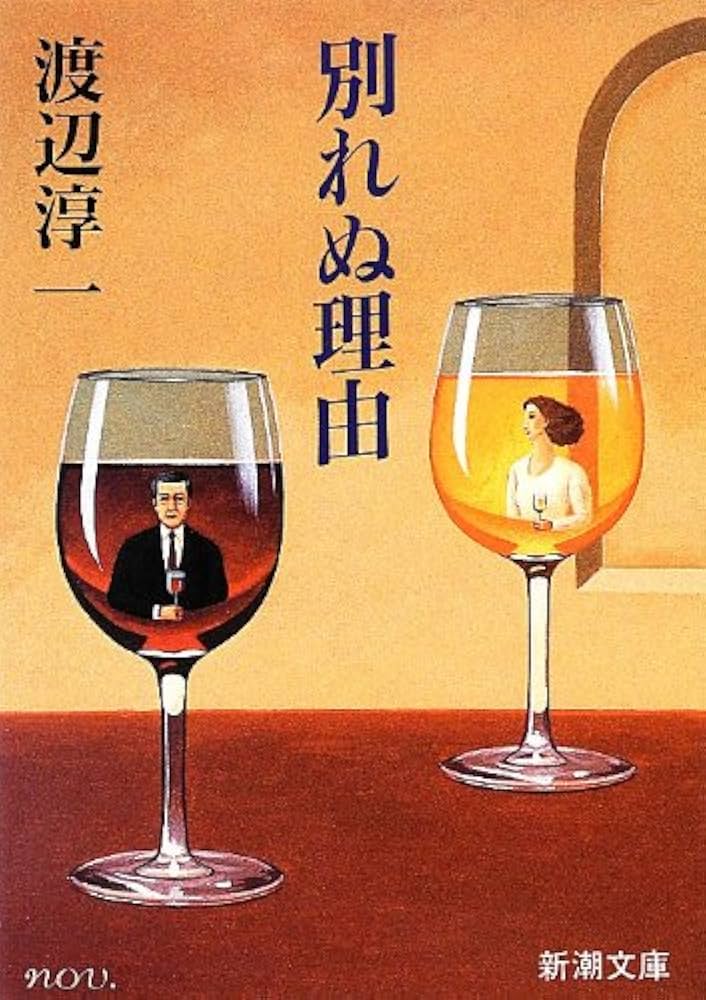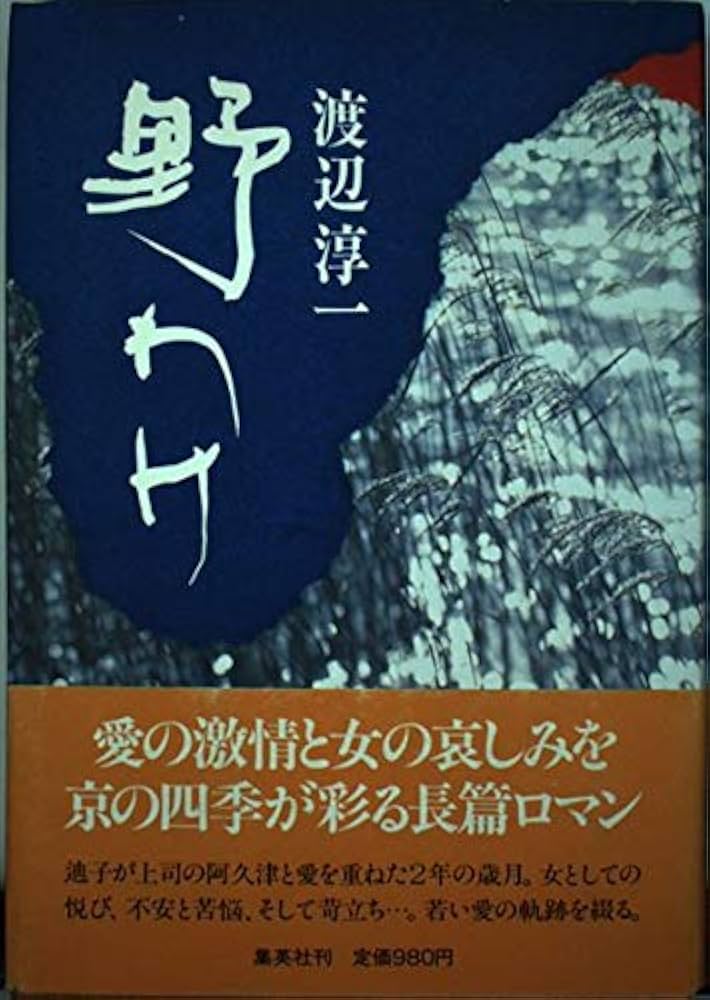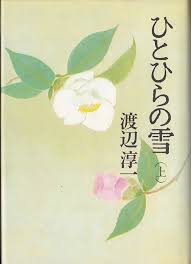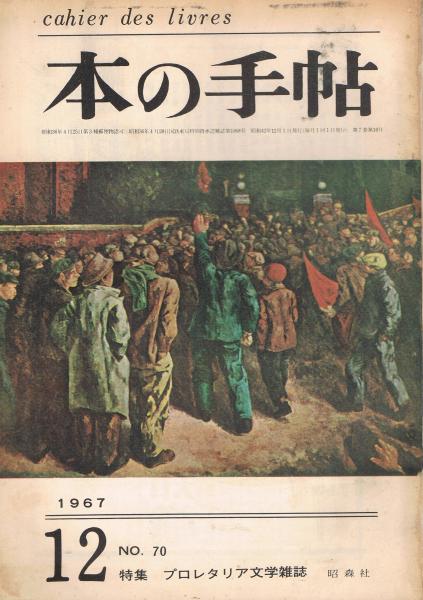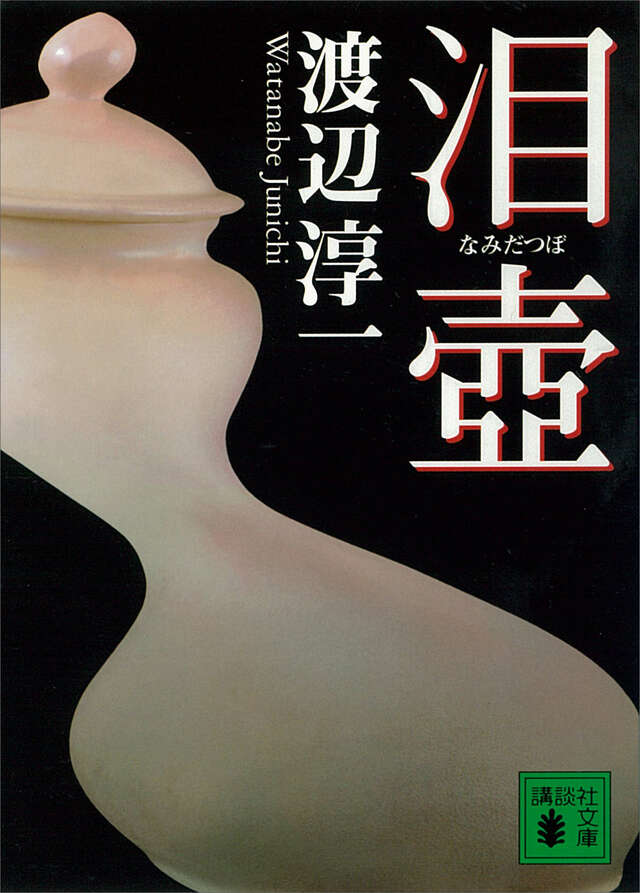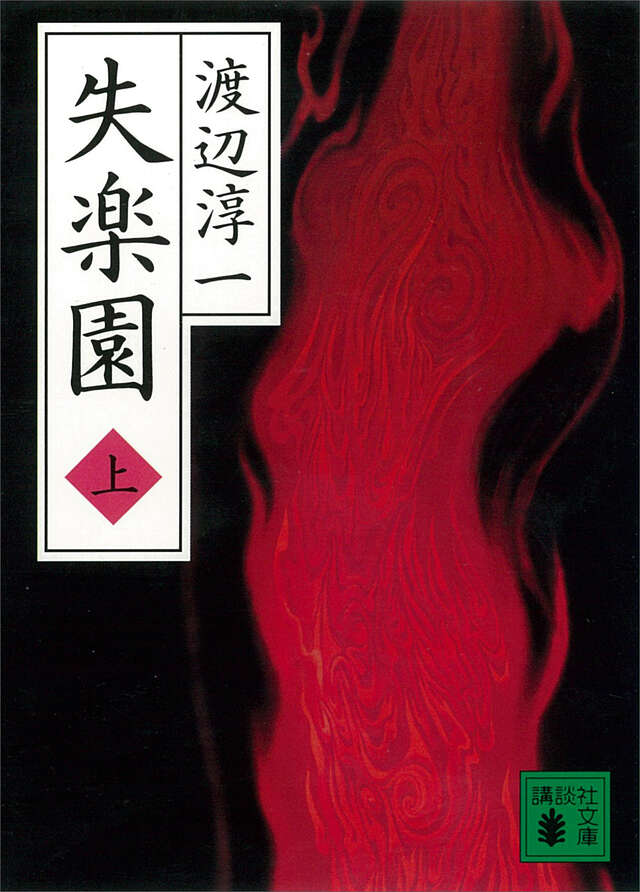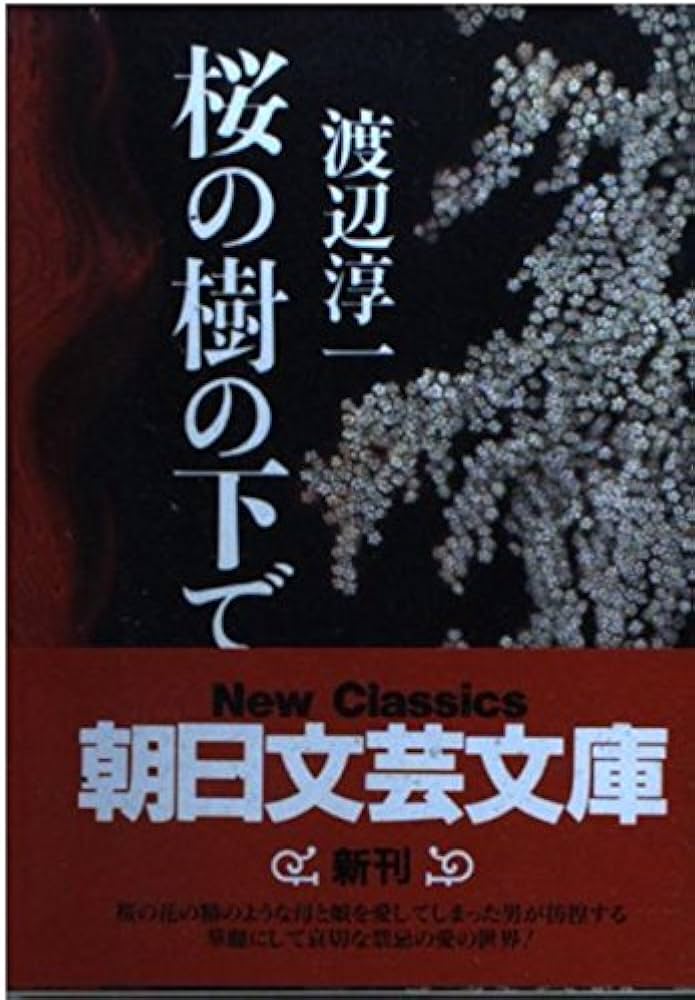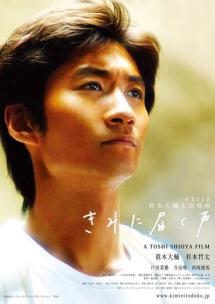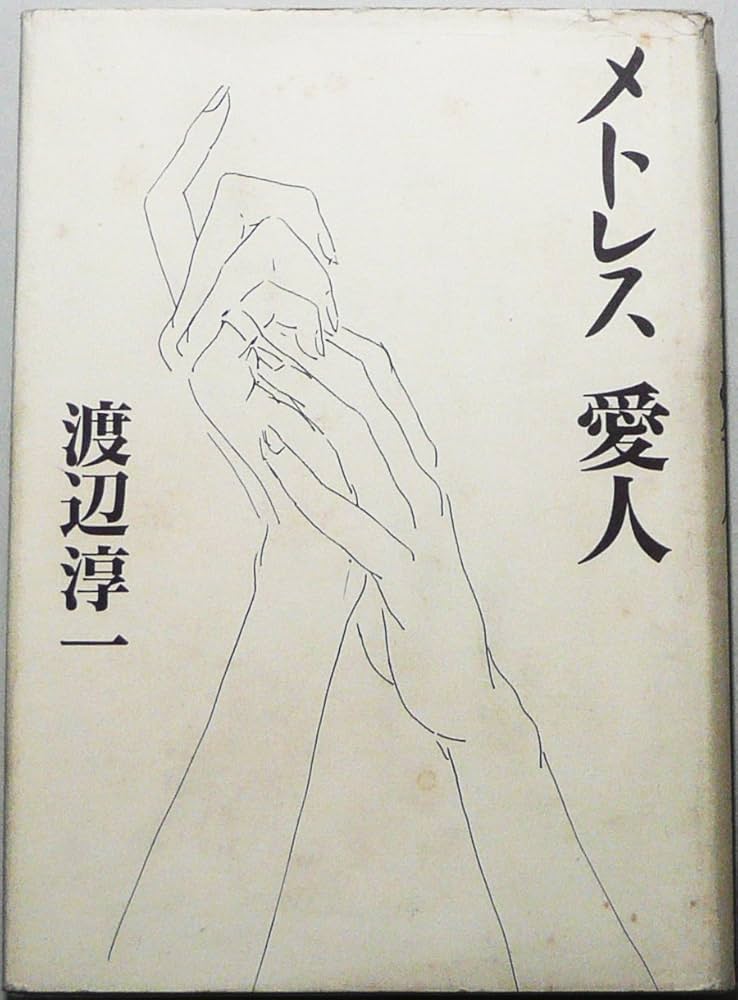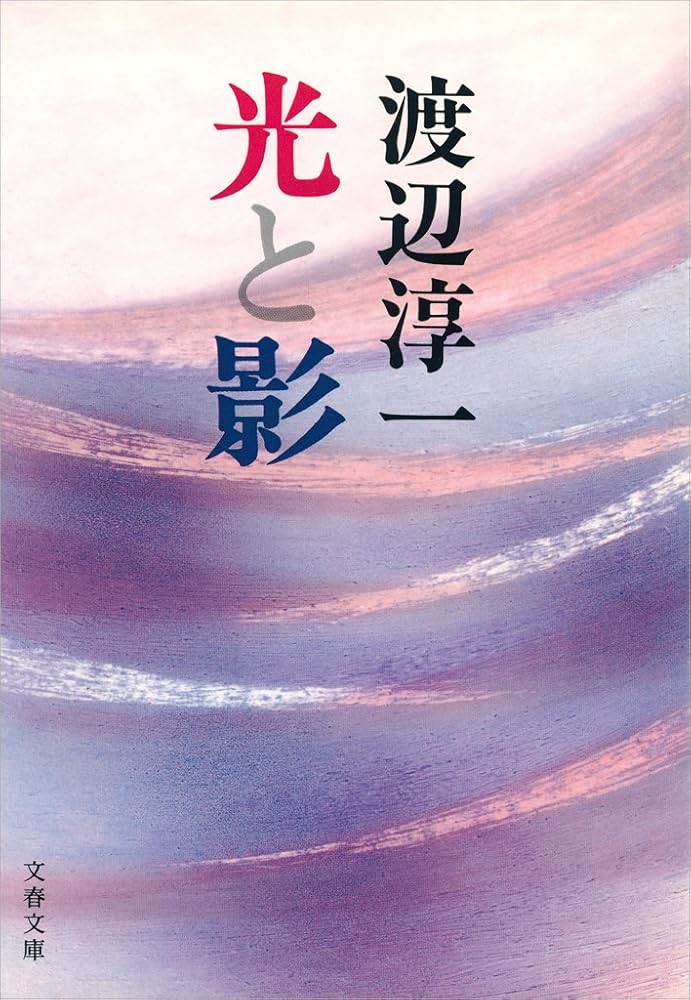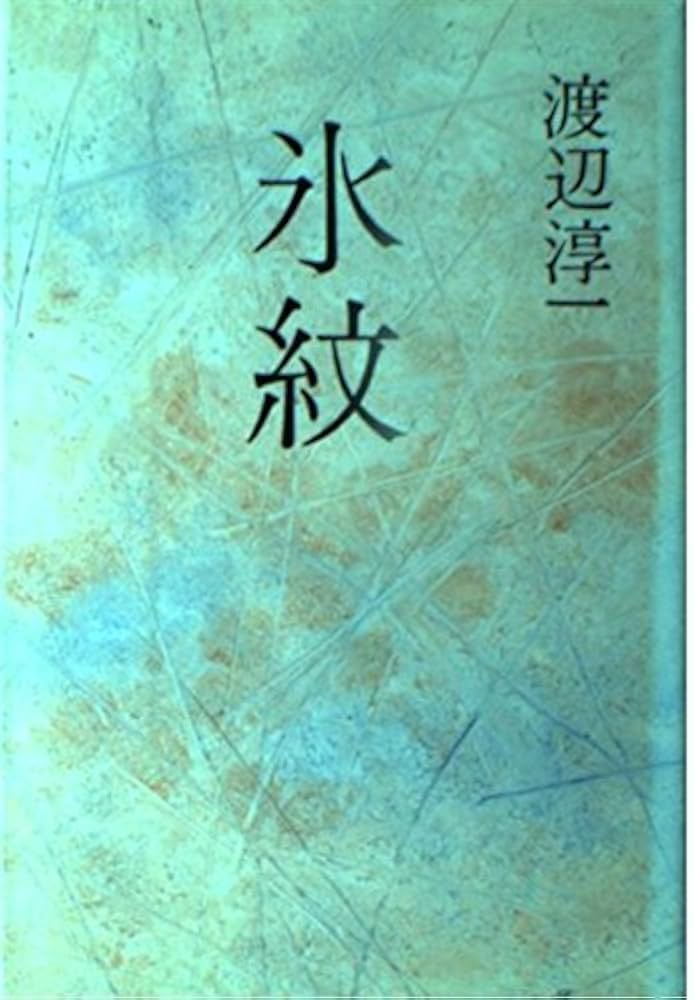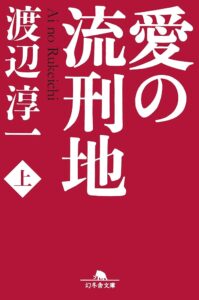 小説「愛の流刑地」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「愛の流刑地」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、男女の愛が迎える一つの究極的な形を、息をのむような筆致で描ききった渡辺淳一氏の代表作の一つです。発表当時、その衝撃的な内容から社会に大きな議論を巻き起こしたことを記憶されている方も多いのではないでしょうか。
物語は、一人の男が「愛しているから、殺しました」と告白するところから始まります。常識では到底理解しがたいその一言を、しかし読み進めるうちに、読者はただの猟奇的な事件として片付けられなくなっていきます。なぜ男は愛する女をその手にかけなければならなかったのか。そして女は、なぜそれを望んだのか。二人の愛の軌跡をたどることで、私たちは愛という感情の持つ底知れない深さと、時に社会の倫理観とは相容れない純粋さについて、深く考えさせられることになるのです。
この記事では、まず物語の骨格を追い、その後で核心に触れる踏み込んだ考察を記しています。二人がたどり着いた愛の終着点、そして「愛の流刑地」という題名に込められた真の意味まで、私自身の解釈を交えながら、じっくりと語っていきたいと考えています。この物語が問いかけるものに、一緒に向き合っていただければ幸いです。
これから「愛の流刑地」の世界に触れる方にも、かつて読んだけれどもう一度その深淵を覗いてみたいという方にも、この記事が何かしらの道しるべとなれば嬉しいです。それでは、愛と死が溶け合った、あまりにも濃密な物語の扉を開けていくことにしましょう。
「愛の流刑地」のあらすじ
かつて恋愛小説で一世を風靡したものの、現在は落ち目の作家である村尾菊治。50代半ばを迎え、創作への情熱も枯れ果てたかのように感じていた彼の前に、一人の女性が現れます。彼女の名前は入江冬香。30代後半の人妻であり、菊治のデビュー作からの熱心な読者でした。古風で慎ましい佇まいの中に、満たされない何かを隠しているかのような冬香に、菊治は強く惹かれていきます。
二人の出会いは、やがて抑えきれない恋情へと発展し、秘密の逢瀬を重ねるようになります。菊治との関係を通じて、冬香はそれまで知らなかった女としての喜びに目覚めていきました。夫や子供との安定した家庭生活がありながらも、彼女の心と体は菊治を求め、その愛はどんどん純度と激しさを増していきます。それは、菊治にとってもまた、失いかけていた創作意欲と男としての自信を蘇らせる、鮮烈な体験でした。
しかし、二人の愛が深まれば深まるほど、その関係は危ういものとなっていきます。情事の快楽が頂点に達したとき、冬香の口から「いっそ、このまま殺して」という言葉が漏れるようになります。はじめは戸惑う菊治でしたが、その言葉は次第に二人の愛の儀式のような響きを帯びていきました。愛の極限で死を願う女と、その願いを受け止めようとする男。
そして、運命の夜が訪れます。燃え上がるような情事の果てに、冬香は再び菊治に懇願します。「お願い、殺して…」。彼女の言葉に導かれるように、菊治の手は彼女の首にかかり、そして……。物語は、この衝撃的な行為の真相と、その愛の結末を、法廷という社会的な舞台の上で問い直していくことになります。
「愛の流行地」の長文感想(ネタバレあり)
この物語は、読者をいきなり当事者に仕立て上げるところから始まります。冒頭、主人公の村尾菊治が警察に出頭し、「愛する女を殺した」と自供するのです。動機は「愛しているから」。この矛盾をはらんだ一言が、私たち読者に投げかけられた最初の、そして最大の問いとなります。これは、これから語られるすべてが、単純な善悪や常識の物差しでは測れない領域に属するものであるという、作者からの宣言のように感じられました。
私たちは、事件の結末を知った上で、菊治の回想という形で二人の愛の軌跡を遡っていくことになります。この構成が非常に巧みで、私たちは菊治の視点を通して、彼がどうしてその結論に至ったのかを追体験させられるのです。単なる犯罪ノンフィクションではなく、愛という感情がいかにして人を常軌を逸した場所へと導くのか、その心理の深淵を覗き込む旅が、ここから始まるのです。
物語の主人公である村尾菊治は、55歳の作家です。若い頃に書いた小説で成功を収めたものの、その後は鳴かず飛ばずで、創作への情熱も人生への手応えも失いかけている男性です。彼の内面は、過去の栄光への執着と、現在の枯渇感という、一種の虚無に覆われています。彼が送る日常は、輝きを失った灰色の世界だったと言えるでしょう。
そんな彼の前に現れたのが、入江冬香でした。彼女は単なる美しい不倫相手という存在ではありません。菊治にとって冬香は、失われた情熱の炎を再び灯してくれる女神(ミューズ)であり、作家として、そして男としての存在価値を再確認させてくれる、まさに希望の光そのものでした。彼が冬香に惹かれたのは、彼女自身の魅力もさることながら、彼自身の内なる渇望が、彼女という存在を強く求めた結果だったのだと感じます。
ヒロインの入江冬香は、36歳の貞淑な主婦として登場します。エリートの夫と三人の子供に恵まれ、傍目には何不自由ない満たされた生活を送っているように見えます。しかし、彼女の魂は深く乾いていました。夫との間には情緒的な交流も、性的な充足もなく、その心は「愛」というものに飢えていたのです。彼女の物静かな態度の裏には、燃え上がるような情熱を秘めた火山が眠っていました。
菊治との出会いは、その火山の噴火のきっかけとなります。彼との性愛を通じて、冬香は眠っていた自己を解放し、凄まじいほどの変貌を遂げます。それは単に快楽を知ったというレベルの話ではありません。彼女は自らの存在のすべてを懸けて、愛の頂きを極めようとする求道者のようになります。そして、この物語の悲劇性を真に牽引していくのは、実は菊治ではなく、この冬香の純粋で絶対的な意志なのです。
二人の関係が、どこにでもあるような不倫の恋と一線を画すのは、そのあまりにも純粋な精神性の追求にあります。逢瀬を重ねる中で、二人は互いの中に失っていたものを見出し、魂の深い部分で結びついていきます。渡辺淳一氏の作品に特徴的な濃密な性愛の描写は、ここでは単に官能的な場面としてではなく、二人の精神的な結合が肉体を通して表現される、重要なプロセスとして描かれています。
冬香が経験するエクスタシーは、彼女を日常から完全に切り離していきます。妻として、母としての役割は色褪せ、菊治との逢瀬だけが彼女の生きる世界のすべてとなります。その変貌は、菊治自身にさえ畏怖の念を抱かせるほどでした。彼女の求める愛は、もはやこの現実世界に留まることを許さない、超越的な領域へと向かっていたのです。
そして、その超越への渇望が、あの運命的な言葉を生み出します。「このまま、殺して…」。快楽の絶頂で冬香が発するこの言葉は、物語の核心を貫くキーワードとなります。これは、最高の幸福の瞬間を永遠にしたい、という彼女の魂の叫びでした。愛が爛熟し、これ以上の高みが望めないと感じたとき、彼女はその完璧な状態のまま時間を止め、凍結させることを望んだのです。
菊治は最初、その言葉に狼狽します。しかし、彼女の真剣な願いに応えるうちに、それは二人の愛を確かめ合う神聖な儀式へと変わっていきました。この「殺して」という願いは、彼らの愛が、生(エロス)と死(タナトス)が不可分に結びついた、危険で甘美な領域に踏み込んだことを示していました。そして、菊治は、その願いを叶えることができる唯一の存在として、自らの役割を意識し始めます。
運命の夜、菊治はついにその一線を越えます。それは衝動的な殺人ではありませんでした。彼らの愛の論理からすれば、それは必然的な帰結であり、むしろ究極の愛の成就だったのです。冬香の願いを叶えること、それこそが彼女への最大の愛の証であると、彼はその瞬間に信じたのでしょう。行為の後の彼の茫然自失とした描写は、愛の理想と、人の死という生々しい現実との残酷な乖離を浮き彫りにしています。
物語の後半は、法廷劇の様相を呈します。菊治の行為は社会の法によって裁かれることになります。彼は一貫して「彼女の願いに応えた、愛の行為だった」と主張しますが、法の世界ではその主張は「言い逃れ」としてしか扱われません。ここには、個人の内面にある主観的な真実と、社会が共有する客観的なルールとの、埋めがたい溝が横たわっています。
二人の間で交わされた濃密な愛の記憶や、魂の交歓は、法廷という場で「動機」「嘱託の有無」「殺意」といった無味乾燥な言葉に解体されていきます。彼らにとって神聖であったはずのものが、第三者によって分析され、裁断されていく過程は、読んでいて非常に空しい気持ちになりました。二人の世界がいかに特殊で、社会の物差しでは到底測れないものであったかを、この法廷の場面は逆説的に示しているのです。
この裁判において、読者の視点を代弁するような役割を担うのが、女性検事の織部です。彼女は当初、菊治の主張を冷笑的に見ていますが、事件を深く知るにつれて、次第に冬香という女性の心理に奇妙な共感を覚え、困惑していきます。社会の正義を代表する検事でさえも揺さぶられる様子は、この物語が持つ抗いがたい説得力を象徴しているように思えます。
私たちは織部検事と共に、常識と、二人が生きた異質な愛の論理との間で引き裂かれるような感覚を味わいます。法は菊治を「殺人者」として断罪しようとしますが、物語を読んできた私たちは、その単純なレッテル貼りをためらわざるを得ません。この葛藤こそが、作者が私たち読者に突きつけたかったものなのかもしれません。
そして、物語は衝撃的な結末を迎えます。刑務所で服役する菊治のもとに、冬香が生前にしたためた手紙が届くのです。そこには、満たされない日常への絶望と、菊治との愛が頂点に達した瞬間に死にたいという彼女の明確な意志、そしてその願いを叶えてくれた菊治への感謝の言葉が綴られていました。
この手紙は、すべてを覆します。冬香は単なる被害者ではなく、この愛の悲劇の脚本家であり、演出家だったのです。彼女は自らの死を計画し、菊治にその実行を託しました。菊治の行為は、彼女の意志を完遂するための、神聖な義務の遂行だったということになります。彼は殺人者ではなく、愛する人の願いを叶えた、ただ一人の理解者だったのです。
この瞬間に、菊治は自らが置かれた状況の真の意味を悟ります。彼が服役しているこの刑務所こそが、冬香が二人きりの愛を守るために用意した「流刑地」だったのです。社会から隔絶されたこの場所でなら、二人の愛は誰にも汚されることなく、純粋な形で永遠に存在し続けることができる。罰として与えられたはずの刑期が、聖なる愛の聖域へとその意味を変えるのです。
この物語は、渡辺淳一氏が生涯をかけて追求した「エロス(生・愛)」と「タナトス(死)」というテーマの、一つの到達点と言えるでしょう。愛がその純度を高めていけばいくほど、それは生の領域を超え、死の匂いを帯び始める。究極の快楽は、究極の終焉への憧れと紙一重であるという、渡辺文学の核心がここにあります。
最後に、この物語は私たちに重い問いを残します。子供を捨て、恋人に自分を殺させた冬香の行為は、究極の愛だったのでしょうか。それとも、究極の自己中心的な行為だったのでしょうか。彼女の願いを叶えた菊治は、献身的な愛の殉教者なのでしょうか。それとも、自らの行為を愛という言葉で美化した、自己欺瞞に満ちた男なのでしょうか。答えは、簡単には出ません。この答えの出ない問いを抱え、考え続けることこそが、「愛の流刑地」という作品を体験するということなのだと、私は思います。
まとめ
渡辺淳一氏の「愛の流刑地」は、男女の愛が到達しうる一つの極限を描ききった、強烈な印象を残す物語です。物語の核心にあるのは、「愛しているから殺した」という一人の男の告白と、その裏に隠された、愛する女の驚くべき真意でした。
二人の愛は社会の常識や倫理観から逸脱し、法によって裁かれます。しかし、物語の最後に明かされる真実によって、その裁きさえもが無意味に感じられるほどの、二人だけの絶対的な愛の形が浮かび上がります。菊治が服役する刑務所は、罰の場所ではなく、二人の愛を永遠に封じ込めるための聖域、「愛の流刑地」へと姿を変えるのです。
この作品を読むことは、私たち自身が持つ愛や死、そして社会の規範といったものに対する考えを、根底から揺さぶられるような体験となるでしょう。読み終えた後も、登場人物たちの選択が正しかったのか、間違っていたのか、その問いが長く心に残り続けます。
それは、この物語が安易な答えを提示するのではなく、人間の感情の複雑さと、法では裁ききれない魂の領域を描いているからに他なりません。愛とは何かを深く問いかける、忘れがたい一作です。