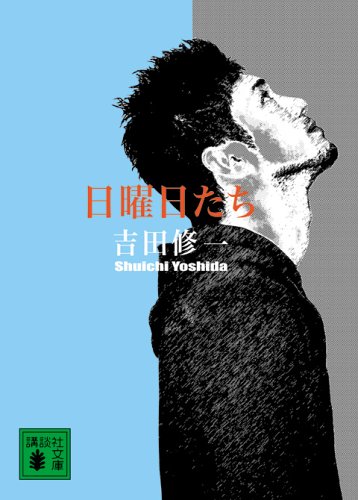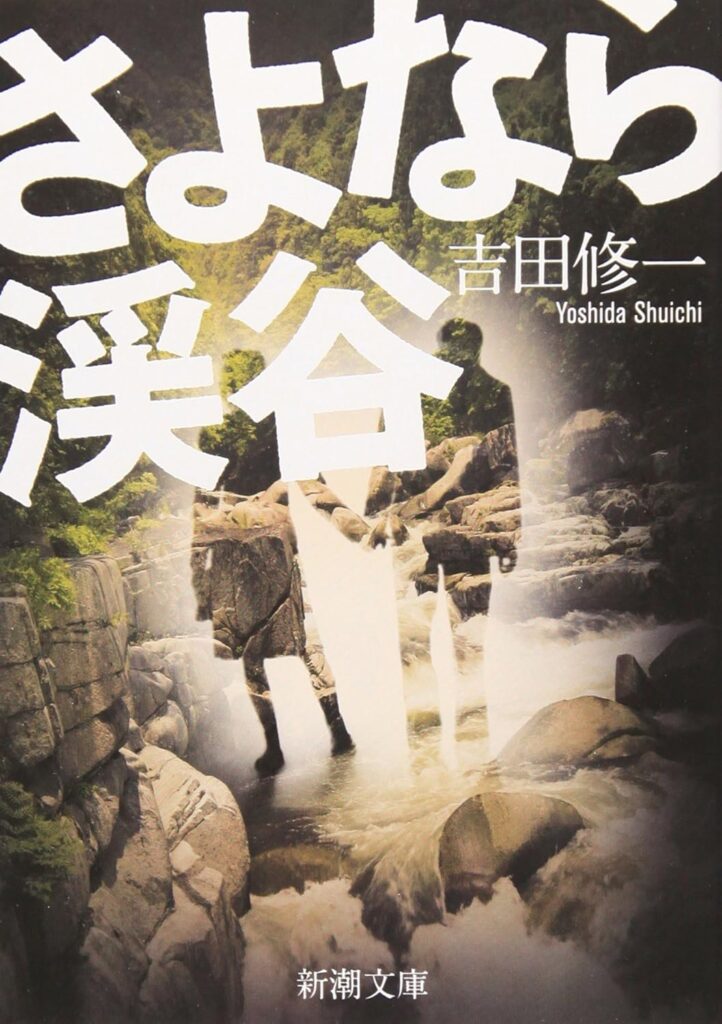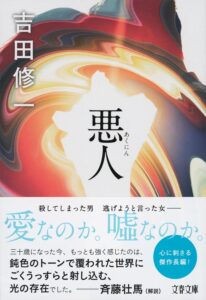 小説「悪人」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。吉田修一さんの手によるこの物語は、読む者の心に深く問いを投げかける作品です。一人の女性が殺害された事件を軸に、加害者、被害者、そしてその周囲の人々の人間模様が、繊細かつ鋭い筆致で描かれていきます。
小説「悪人」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。吉田修一さんの手によるこの物語は、読む者の心に深く問いを投げかける作品です。一人の女性が殺害された事件を軸に、加害者、被害者、そしてその周囲の人々の人間模様が、繊細かつ鋭い筆致で描かれていきます。
物語を読み進めるうちに、「本当の悪人とは誰なのか?」という問いが、まるで自分自身に向けられているかのように感じられるかもしれません。登場人物たちの抱える孤独や痛み、そして一瞬の希望が交錯する中で、私たちは善と悪の境界線が曖昧になっていくのを目撃します。それぞれの立場や背景を知るにつれ、単純には割り切れない感情が湧き上がってくることでしょう。
この記事では、まず「悪人」の物語の核心に触れるあらすじを、重要な展開や結末にも言及しながらお伝えします。そして、その後に続く長文の感想では、各登場人物の心理や行動、そして作品全体が持つテーマ性について、ネタバレを気にせずに深く掘り下げていきます。
この作品に触れたことがある方も、これから手に取ろうと考えている方も、この記事を通じて「悪人」という物語が持つ多層的な魅力や、読後に残る問いについて、改めて考えるきっかけとなれば幸いです。どうぞ最後までお付き合いください。
小説「悪人」のあらすじ
福岡県の寂れた漁港で、保険外交員の女性・石橋佳乃が遺体で発見されるところから、物語は静かに動き出します。彼女の首には絞められた痕があり、事件は殺人として捜査が開始されます。佳乃は出会い系サイトを利用しており、事件当夜もサイトで知り合った男と会う約束をしていました。当初、捜査線上に浮かんだのは、裕福な大学生である増尾圭吾でした。彼は事件当日、佳乃と会っていたものの、途中で彼女を置き去りにしたと供述します。
しかし、捜査が進むにつれて、新たな容疑者が浮上します。それは、長崎県の田舎町で暮らす土木作業員の清水祐一でした。祐一もまた、佳乃と出会い系サイトを通じて連絡を取り合っており、事件当夜、佳乃と会っていたことが判明します。増尾の証言や周辺の聞き込みから、警察は次第に祐一に疑いの目を強めていきます。祐一は、幼い頃に母親に捨てられた過去を持ち、祖父母と静かに暮らしていましたが、どこか満たされない思いを抱えていました。
そんな中、祐一は出会い系サイトで佐賀県に住む馬込光代という女性と知り合います。光代もまた、妹夫婦の家で肩身の狭い思いをしながら、紳士服店で働く孤独な日々を送っていました。二人はメールでのやり取りを通じて、互いの孤独に引かれ合うように心を通わせていきます。そして、祐一が佳乃を殺害した容疑で追われる身であることを知りながらも、光代は彼と共に逃避行に出ることを決意します。
祐一と光代の逃避行は、決して許されるものではありませんでした。しかし、二人にとっては、生まれて初めて互いを必要とし、受け入れ合える相手との時間でした。祐一は光代に対して、これまで誰にも見せることのなかった優しさや純粋な一面を垣間見せます。光代もまた、祐一の犯した罪を知りながらも、彼を信じ、献身的に支えようとします。二人の逃避行は、刹那的な安らぎと、常に追われる恐怖が隣り合わせの日々でした。
彼らが逃避行の末に辿り着いたのは、かつて祐一が祖父と訪れたことのある、海を見下ろす灯台でした。そこで束の間の穏やかな時間を過ごす二人でしたが、警察の捜査の手は確実に迫っていました。祐一は、自分が犯した罪の重さと、光代の未来を思い、ある決断を下します。そして、灯台での最後の夜、祐一は光代を気絶させ、わざと彼女に暴行したかのように装い、一人で逮捕される道を選びます。それは、光代が自分と関わったことで共犯者として扱われないようにするための、祐一なりの最後の優しさであり、歪んだ愛の形でした。
事件は解決し、祐一は逮捕されます。しかし、物語は単純な犯人探しのミステリーとして終わるわけではありません。本当に「悪人」だったのは誰なのか。祐一なのか、彼を追い詰めた社会なのか、あるいは被害者や他の登場人物たちの中に潜むエゴイズムなのか。読者一人ひとりに重い問いを投げかけ、深く考えさせる結末となっています。
小説「悪人」の長文感想(ネタバレあり)
吉田修一さんの小説「悪人」を読み終えたとき、ずっしりとした重い塊が胸の中に残りました。それは決して不快なものではなく、人間という存在の複雑さ、そして「悪」とは何かという根源的な問いに触れたことによる、ある種の感慨のようなものだったと思います。この物語は、私たちに単純な善悪のレッテルを貼ることの危うさを教えてくれます。
まず、主人公の一人である清水祐一について考えてみたいと思います。彼は間違いなく人を殺めた加害者です。しかし、物語を読み進めるうちに、彼を単なる「悪人」として断罪することに躊躇いを覚えてしまうのです。幼い頃に母親に捨てられたトラウマ、誰にも理解されない孤独感、そして社会の底辺で生きる閉塞感。これらが彼の人格形成に大きな影響を与えたことは想像に難くありません。彼の金髪が徐々に明るくなっていく描写は、彼の内なる攻撃性や、どこか刹那的な生き方を象徴しているようにも感じられました。
祐一が石橋佳乃を殺害してしまった直接的な引き金は、佳乃の挑発的な言動と、祐一が感じた侮辱、そして誰も自分を信じてくれないだろうという絶望感でした。もちろん、それらが殺人を正当化するものでは決してありません。しかし、あの極限状況で、彼の心の中で何が起きていたのかを想像すると、一方的に彼を断罪するだけでは、この物語の本質を見誤ってしまうような気がします。彼が内に秘めていた純粋さや、不器用な優しさは、馬込光代との関係性の中で、より鮮明に浮かび上がってきます。
そして、もう一人の主人公である馬込光代。彼女もまた、深い孤独を抱えて生きてきた女性です。妹夫婦の家での居心地の悪さ、平凡な仕事、そして満たされない日常。そんな彼女にとって、祐一との出会いは、暗闇の中に差し込んだ一筋の光のように感じられたのかもしれません。祐一が殺人犯であると知りながらも、彼と共に逃げることを選んだ彼女の行動は、常識的に考えれば理解しがたいものです。しかし、彼女の「生まれて初めて、良い方に選り分けられた」という言葉には、これまで誰にも必要とされず、常に「悪いほうへ入れられてしまう」と感じてきた彼女の切実な想いが凝縮されているように思えます。
光代が祐一との逃避行を「バスジャックのバスに乗らなかった」自分、つまり日常から逸脱し、特別な存在になれた自分と重ね合わせる場面は非常に印象的です。しかし、客観的に見れば、彼女はむしろ危険な「バスジャックのバスに乗りたがっている」ようにも見え、その矛盾が彼女の心の複雑さを物語っています。彼女は祐一を救いたかったのか、それとも祐一と共にいることで自分自身が救われたかったのか。おそらく、その両方だったのでしょう。灯台での二人の生活は、破滅へと向かうことが分かりきっている、あまりにも儚く、しかし強烈な輝きを放つ時間でした。
増尾圭吾という存在も、この物語における「悪」を考える上で非常に重要です。彼は直接的に手を下したわけではありませんが、その軽薄さ、自己中心的な振る舞い、そして無自覚な傲慢さは、石橋佳乃を間接的に死へと追いやった一因と言えるでしょう。彼は佳乃を見下し、弄び、そして危険な状況に置き去りにしました。しかし、彼自身にその罪の意識は薄く、むしろ自分も被害者であるかのような態度すら見せます。佳乃の父親が増尾に対して抱いた無力感や怒りは、読者の感情を代弁しているかのようです。増尾のような「取るに足らない悪意」が、時として取り返しのつかない悲劇を引き起こすという現実は、私たちの日常にも潜んでいるのかもしれません。
被害者である石橋佳乃もまた、単純な「善人」として描かれてはいません。彼女は虚栄心から出会い系サイトを利用し、より条件の良い男を求め、時には相手を挑発するような言動も取ります。もちろん、彼女が殺されて良い理由には全くなりませんが、彼女の内面にもまた、現代社会に生きる人間の弱さや歪みが反映されているように感じられます。彼女が生前に抱えていたであろう焦燥感や孤独感を思うと、一概に彼女を責めることもできません。この物語では、被害者と加害者という単純な二項対立では捉えきれない、人間の多面性が描かれています。
祐一の祖母・房枝さんの「馬鹿にされてたまるか」という言葉も心に残ります。悪質な訪問販売の男たちに対して、最初は何もできなかった彼女が、勇気を振り絞って立ち向かう姿は、人間の尊厳とは何かを考えさせます。しかし、その一方で、私たちは誰かを「罰したい」という感情を抱いてしまうことがあります。自分が不当な扱いを受けたとき、相手に相応の報いがあってほしいと願うのは自然な感情かもしれません。しかし、その感情がエスカレートしたとき、私たちは無意識のうちに誰かを「悪人」と断罪し、石を投げる側に回ってしまう危険性を孕んでいるのではないでしょうか。
この小説のタイトルである「悪人」とは、一体誰を指すのでしょうか。もちろん、法を犯した祐一は「悪人」です。しかし、物語を読み終えたとき、その言葉は祐一だけを指しているのではないように思えてきます。増尾の無自覚な悪意、佳乃の虚栄心、光代の現実逃避的な選択、そして事件を取り巻く人々の好奇の目や無責任な噂話。さらには、私たち読者の中に潜む、誰かを裁きたいという欲求。それら全てが、この物語における「悪」の要素を構成しているのかもしれません。
現代社会は、情報が瞬時に拡散し、匿名性の陰で誰もが簡単に他者を批判し、攻撃できる時代です。SNSなどでは、誰かが「悪人」として認定されると、集団で徹底的に叩きのめすような光景も珍しくありません。しかし、その「悪人」とされた人物の背景や、そこに至るまでの経緯を深く知ろうとする人は少ないのではないでしょうか。この物語は、そうした現代社会の風潮に対しても警鐘を鳴らしているように感じます。
祐一と光代が最後に辿り着いた灯台は、二人にとって唯一の安息の場所であり、同時に逃れられない現実を象徴する場所でもありました。暗い海を照らす灯台の光は、二人の刹那的な幸福と、その先にある絶望の両方を映し出していたのかもしれません。祐一が光代を突き放す形で選んだ結末は、歪んではいるものの、彼なりの愛情表現であり、贖罪の形だったのではないでしょうか。光代が祐一を「私を愛してくれる人がいる。そんな場所を見つけた」と感じた瞬間は、彼女にとって紛れもない真実だったはずです。
この物語は、私たちに明確な答えを与えてはくれません。読み終えた後も、登場人物たちの誰に感情移入し、誰の行動をどう解釈するかは、読者一人ひとりに委ねられています。そして、それこそがこの作品の持つ大きな魅力なのでしょう。私たちは、彼らの姿を通して、自分自身の内面と向き合い、「悪とは何か」「正しさとは何か」という問いを考え続けることになるのです。
私は、清水祐一を完全な悪人だとは思えませんでした。彼の犯した罪は許されるものではありませんが、彼の中にも確かに人間らしい感情や、誰かを想う心があったことを感じ取れたからです。そして、彼をそこまで追い詰めたものは何だったのかを考えると、社会の構造や、人間関係の歪みといった、より大きな問題にも思い至ります。
馬込光代の選択もまた、一概に否定することはできません。彼女が祐一との逃避行に見た希望は、たとえそれが幻想であったとしても、彼女にとっては生きる意味そのものだったのかもしれません。彼女の孤独の深さを思うと、その選択を誰が責められるでしょうか。
「悪人」を読んで、私は「悪」というものが、固定された絶対的なものではなく、状況や立場、そして個人の内面によって揺れ動く相対的なものであるということを改めて感じました。そして、誰もが状況次第では「悪人」になり得る可能性を秘めているのかもしれない、という恐ろしさも同時に感じたのです。この物語は、私たちに人間存在の深淵を覗かせ、そして静かに問いかけ続けます。「あなたは、誰を『悪人』だと思いますか?」と。
まとめ
吉田修一さんの小説「悪人」は、読後に深い余韻と、重くも大切な問いを残してくれる作品です。殺人事件という悲劇を軸にしながらも、単なる犯人探しの物語に留まらず、人間の心の奥底に潜む孤独や弱さ、そして「悪」の本質に鋭く迫っています。
登場人物たちは、決して単純な善悪の型にはめられるような人々ではありません。加害者である清水祐一が見せる純粋さ、被害者である石橋佳乃が抱える虚栄心、そして二人を繋ぐ馬込光代の切実なまでの孤独感。それぞれの行動や心理は、読む者の心を揺さぶり、誰が本当の「悪人」なのかという問いを突きつけてきます。
この物語を通じて、私たちは日常の中に潜む些細な悪意や、社会の歪みが、時に取り返しのつかない悲劇を生み出す可能性について考えさせられます。そして、他者を容易に「悪人」と断罪することの危うさ、表面的な情報だけでは見えてこない人間の多面性についても、改めて気づかされるでしょう。
小説「悪人」は、読むたびに新たな発見や解釈が生まれる、奥深い作品です。この記事が、これから作品を手に取る方、あるいは再読する方にとって、物語をより深く味わい、そこに込められたメッセージを考えるための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

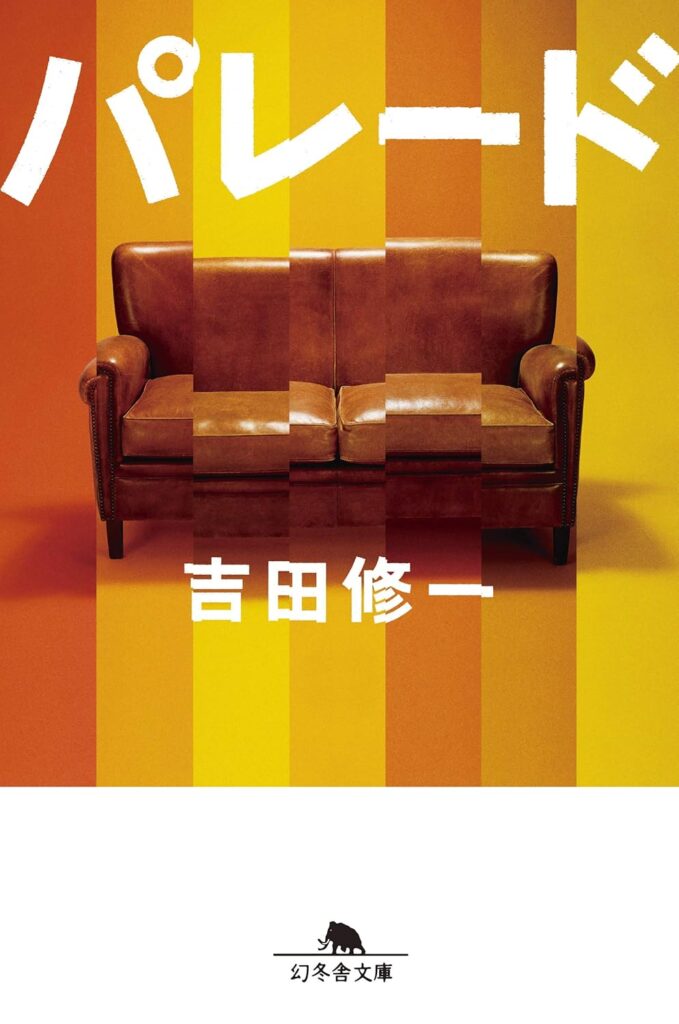
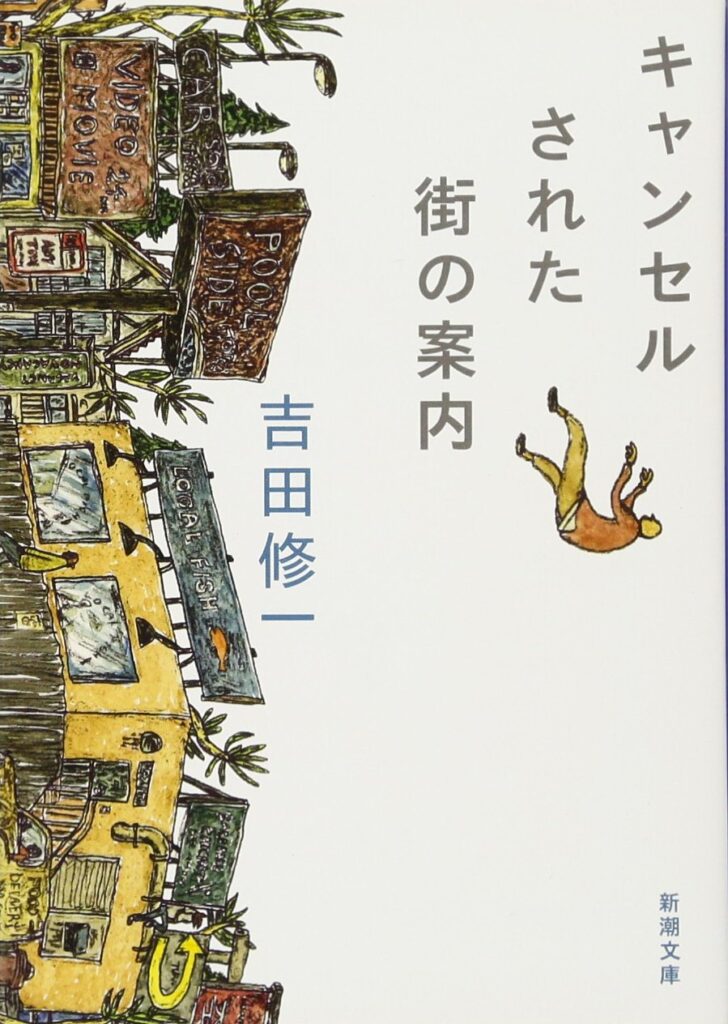
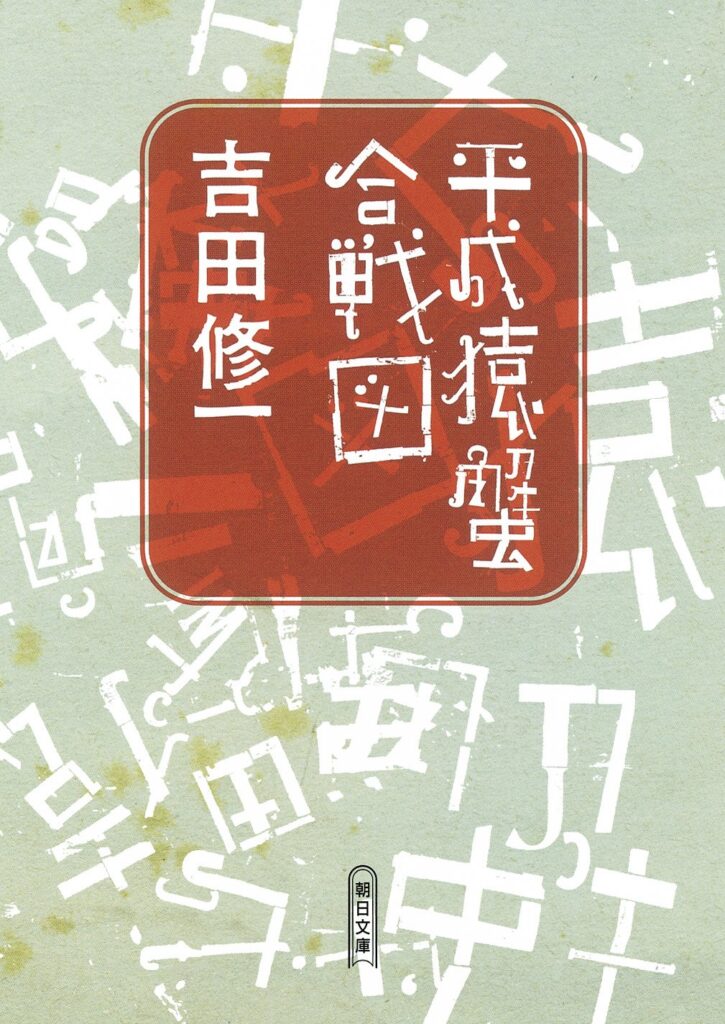
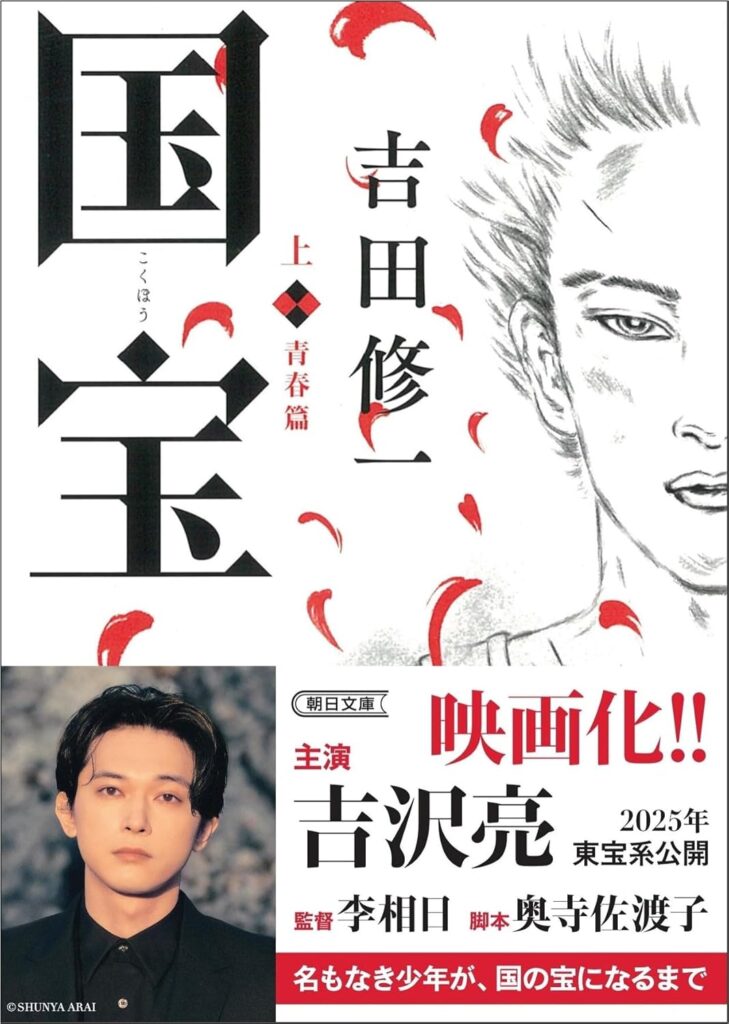
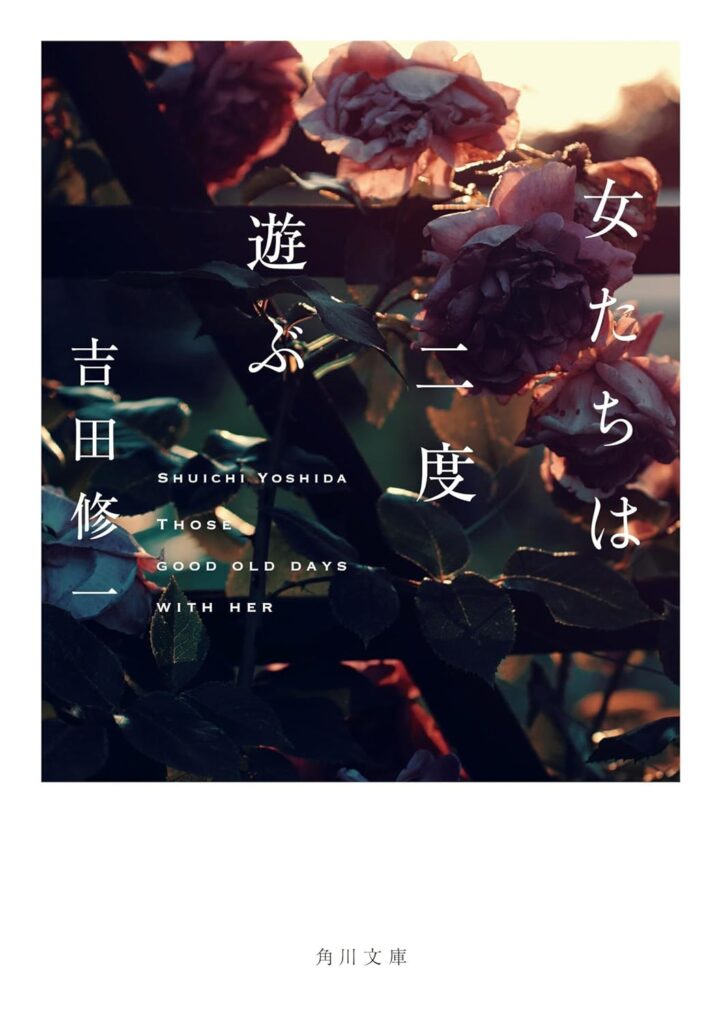
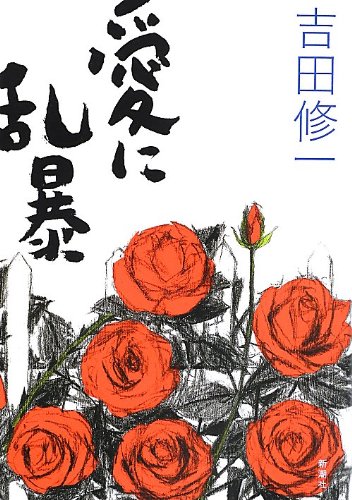
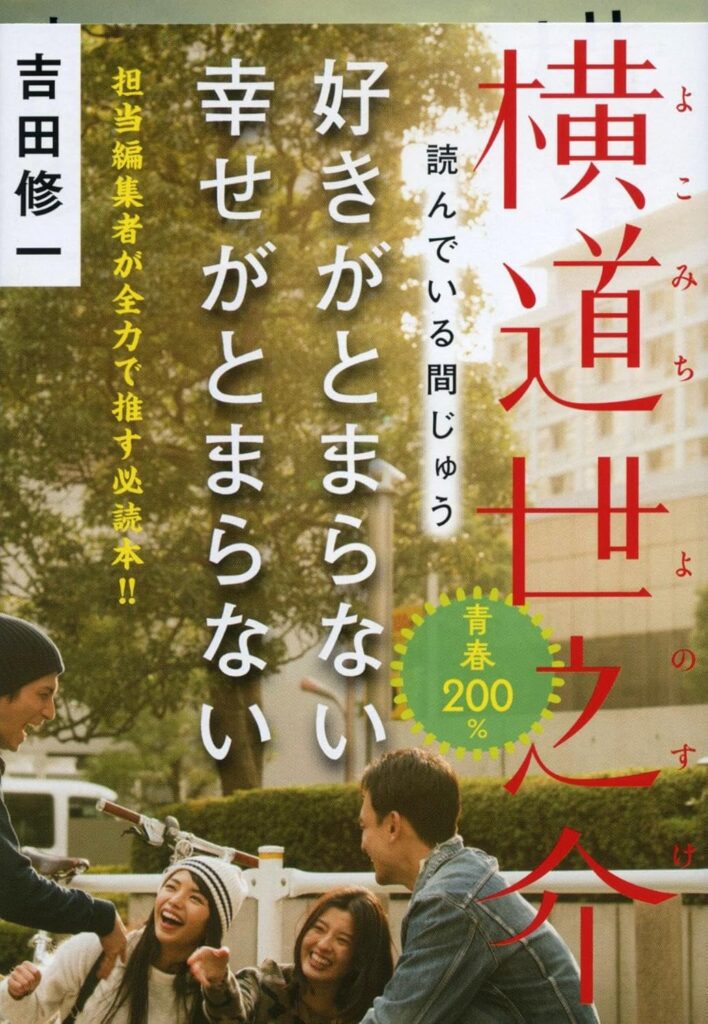
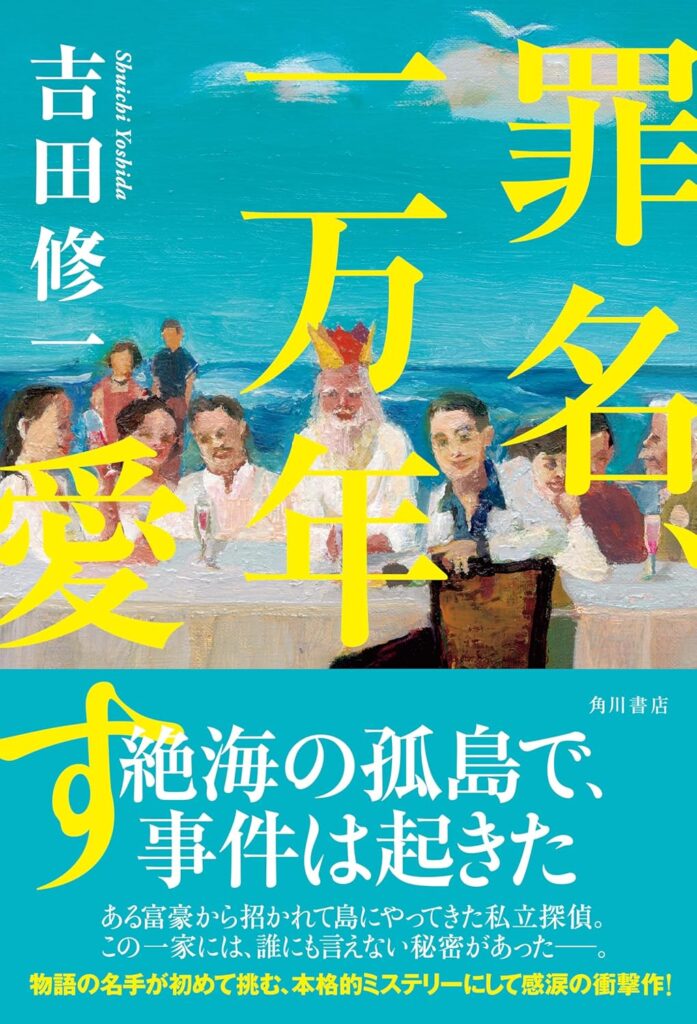
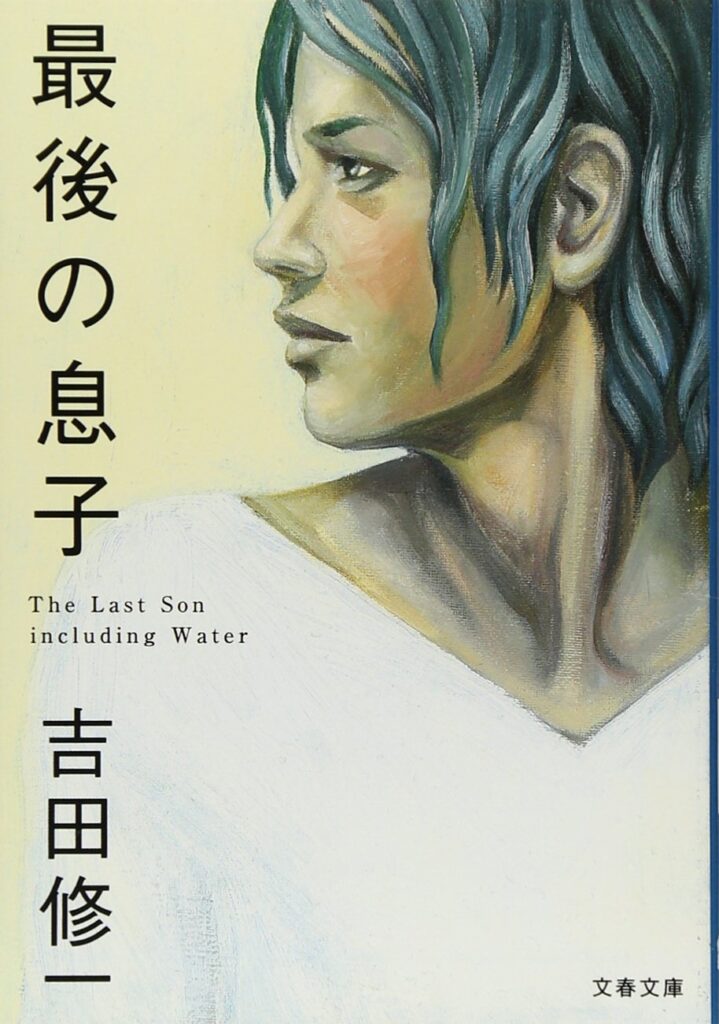
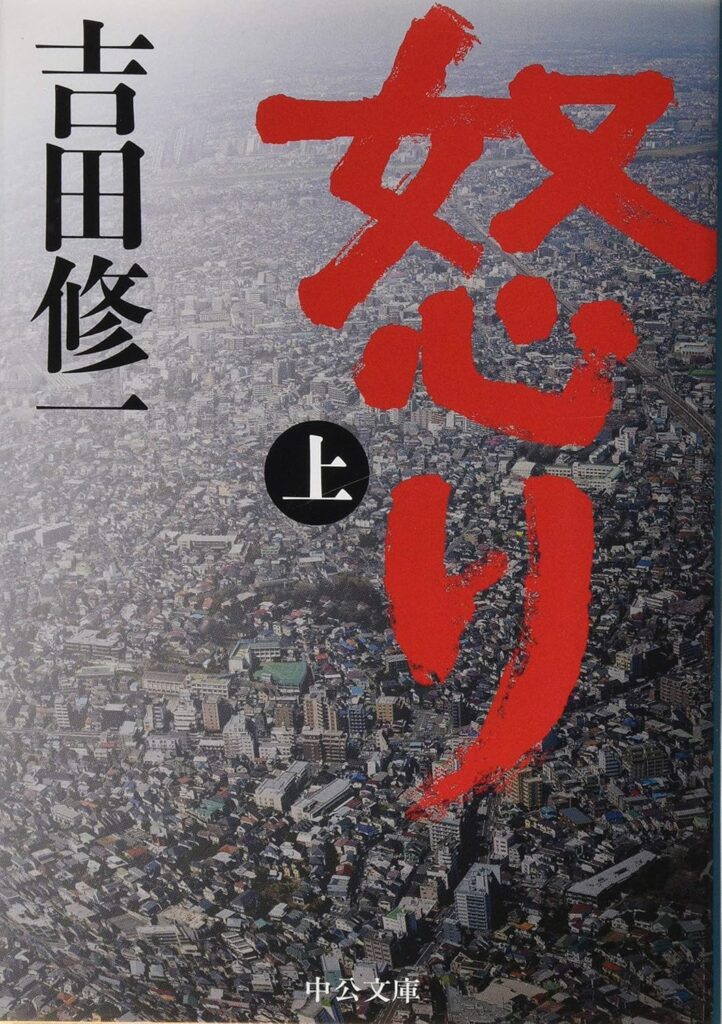
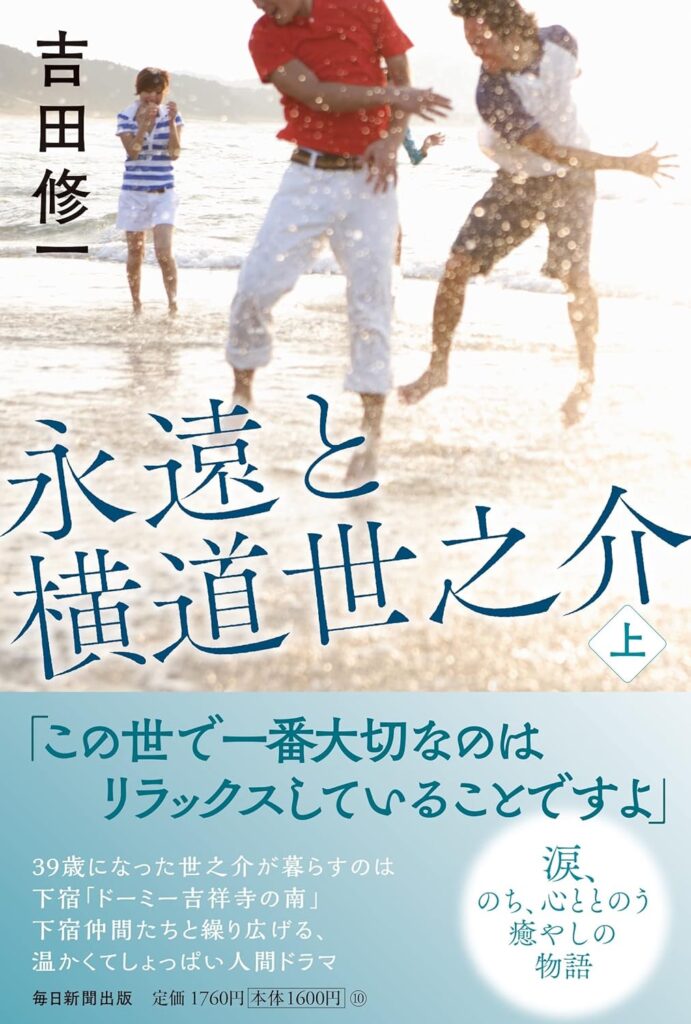
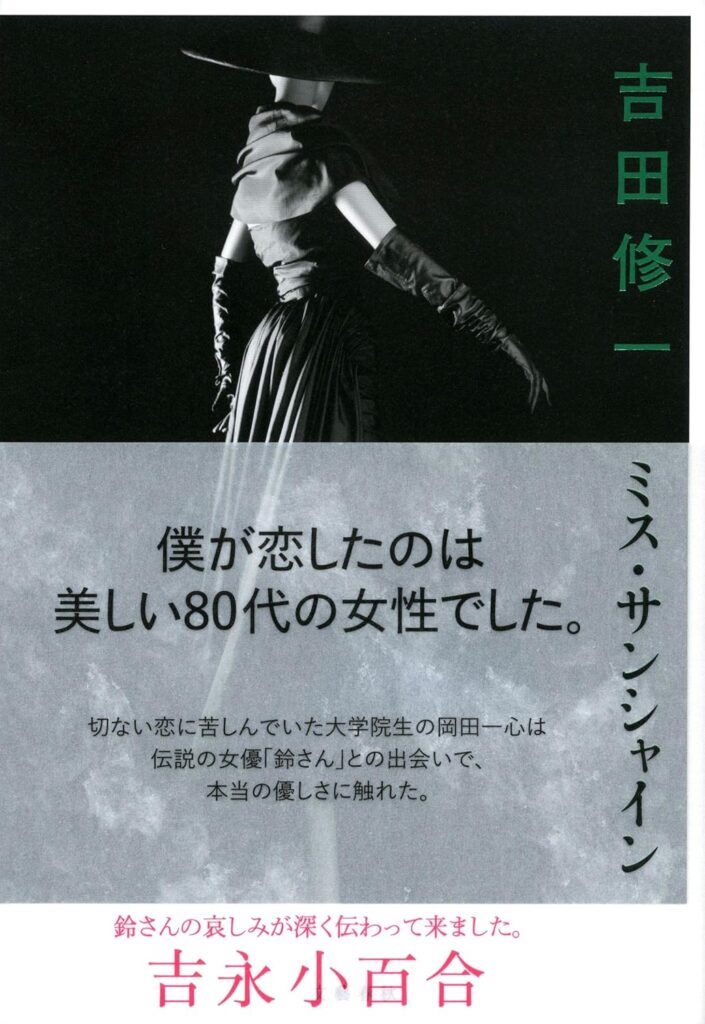
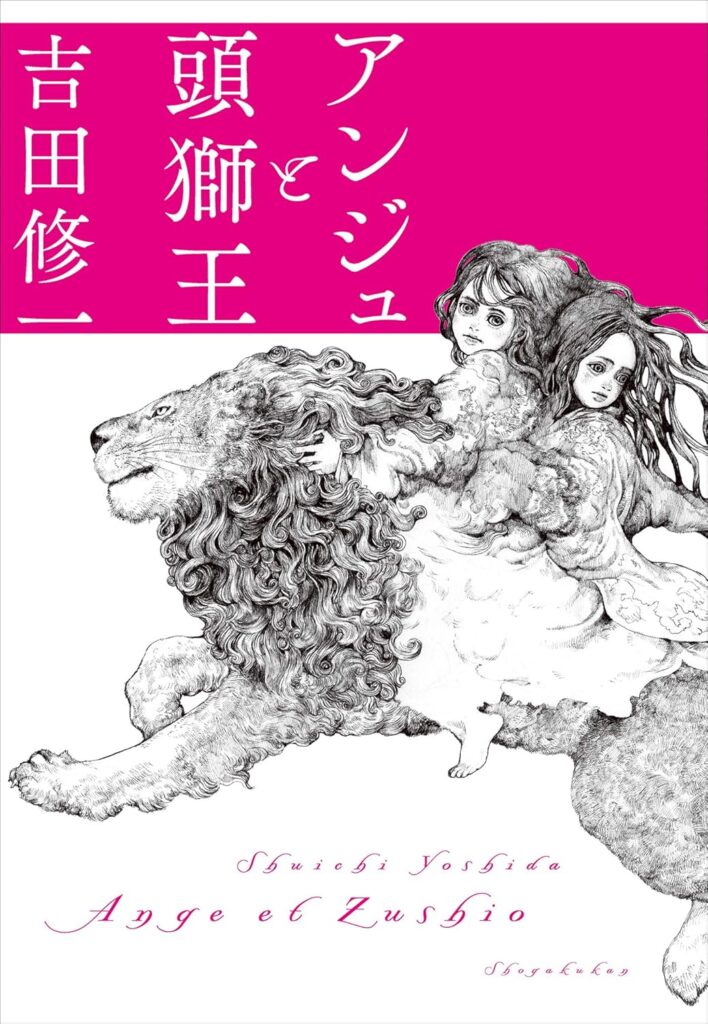
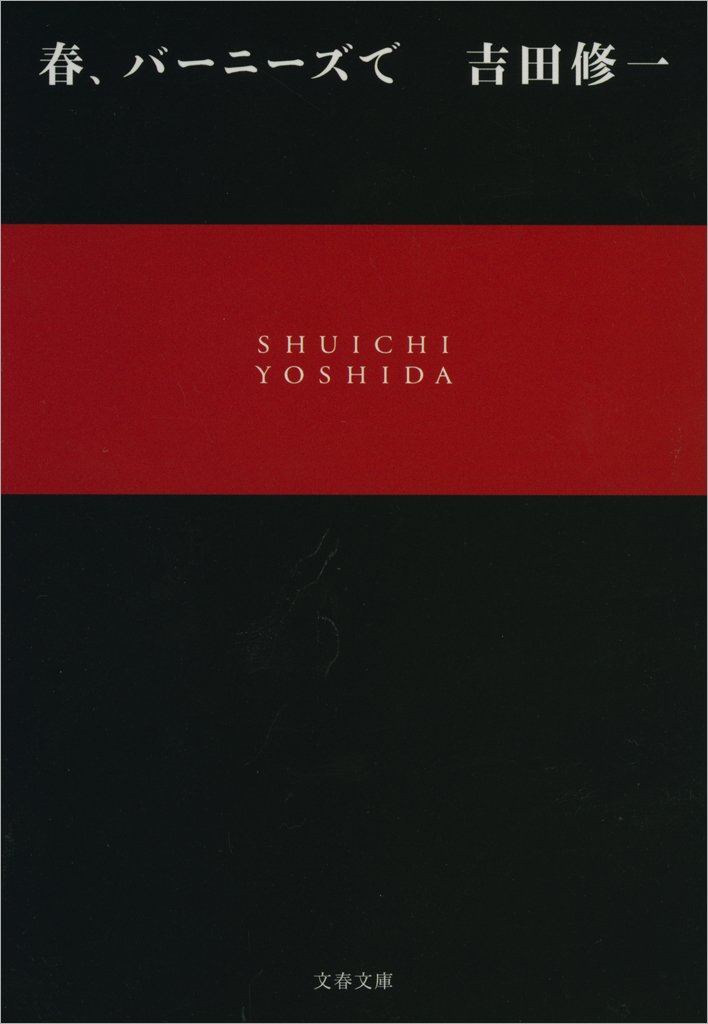
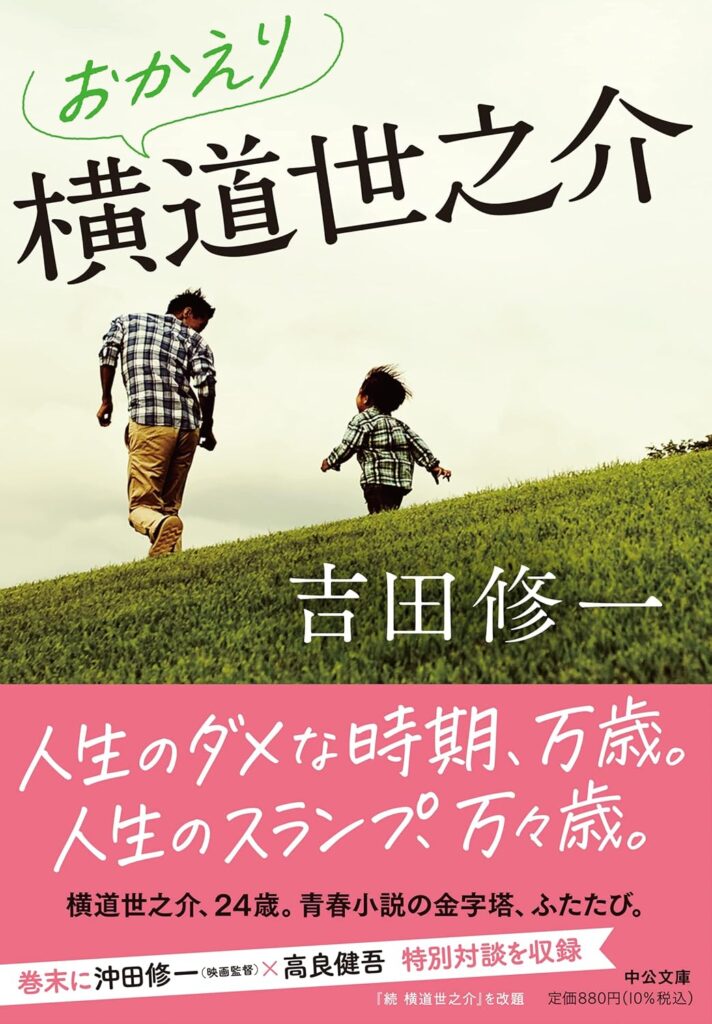
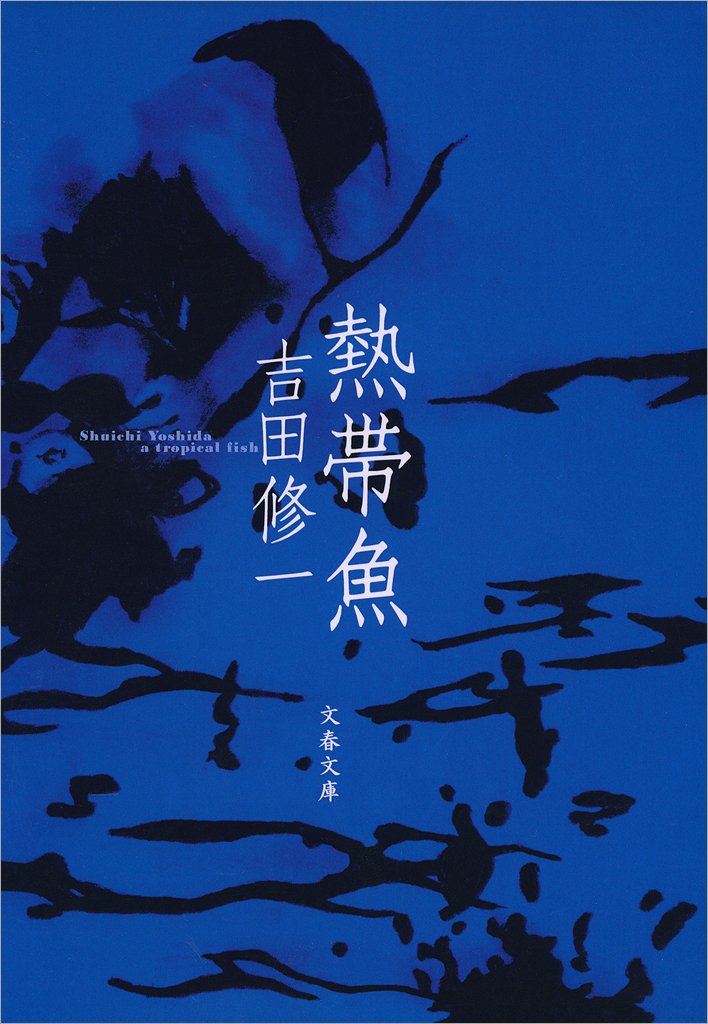
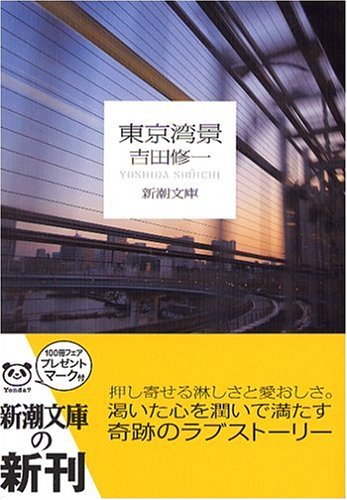
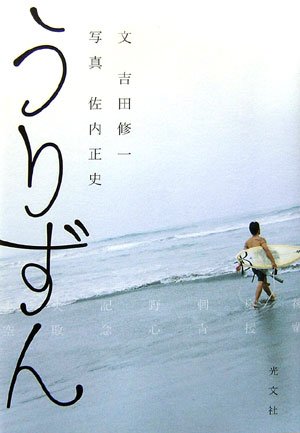
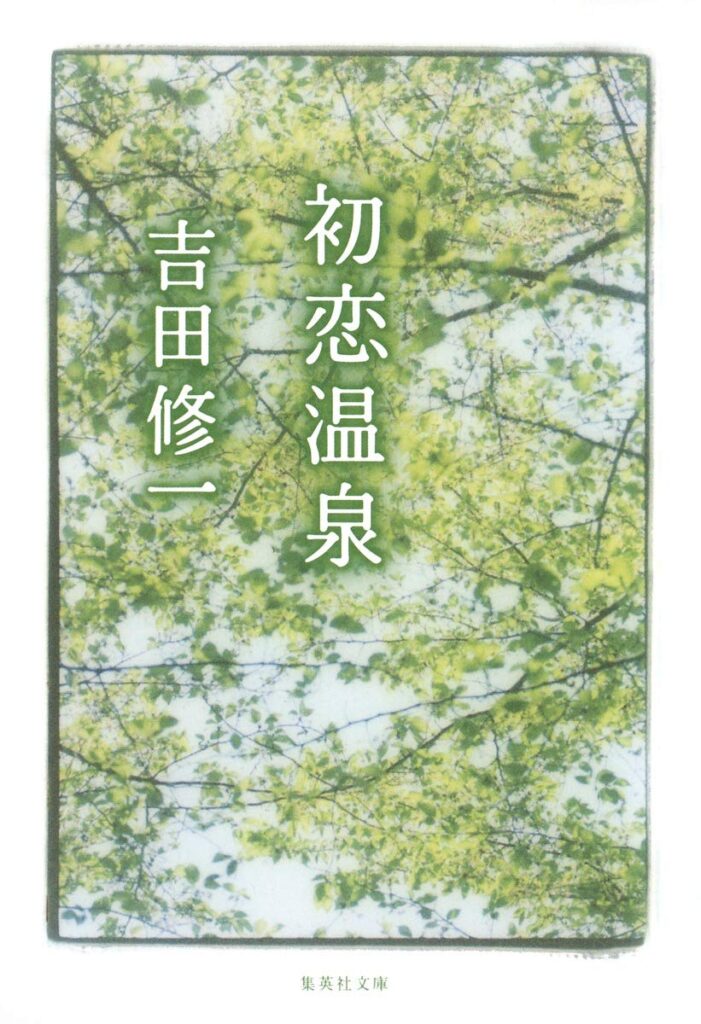
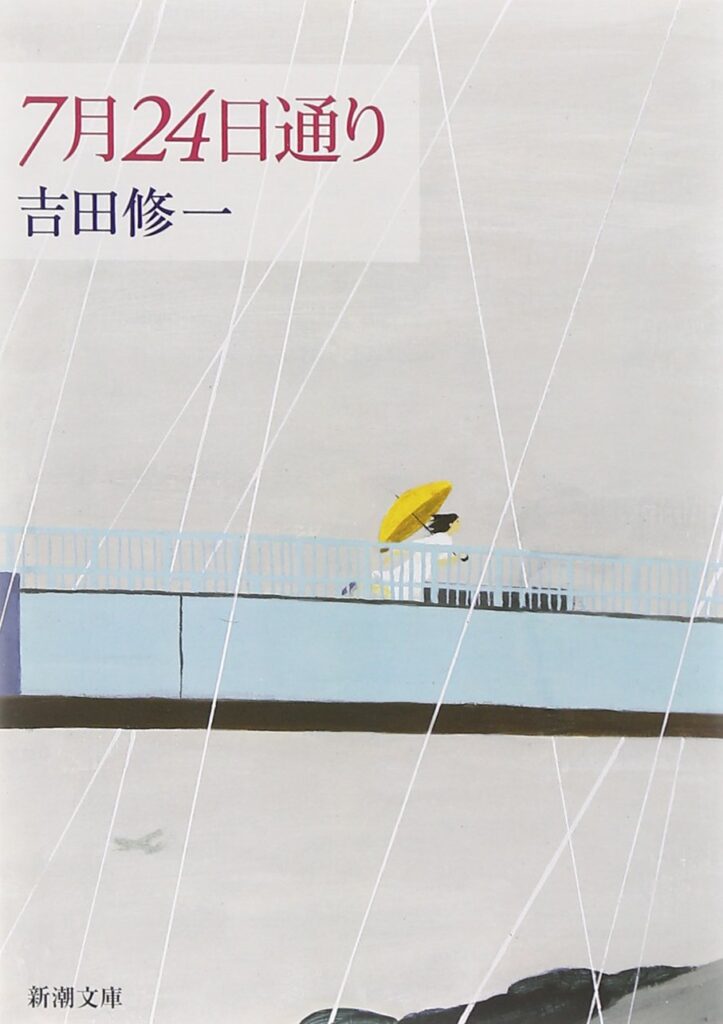
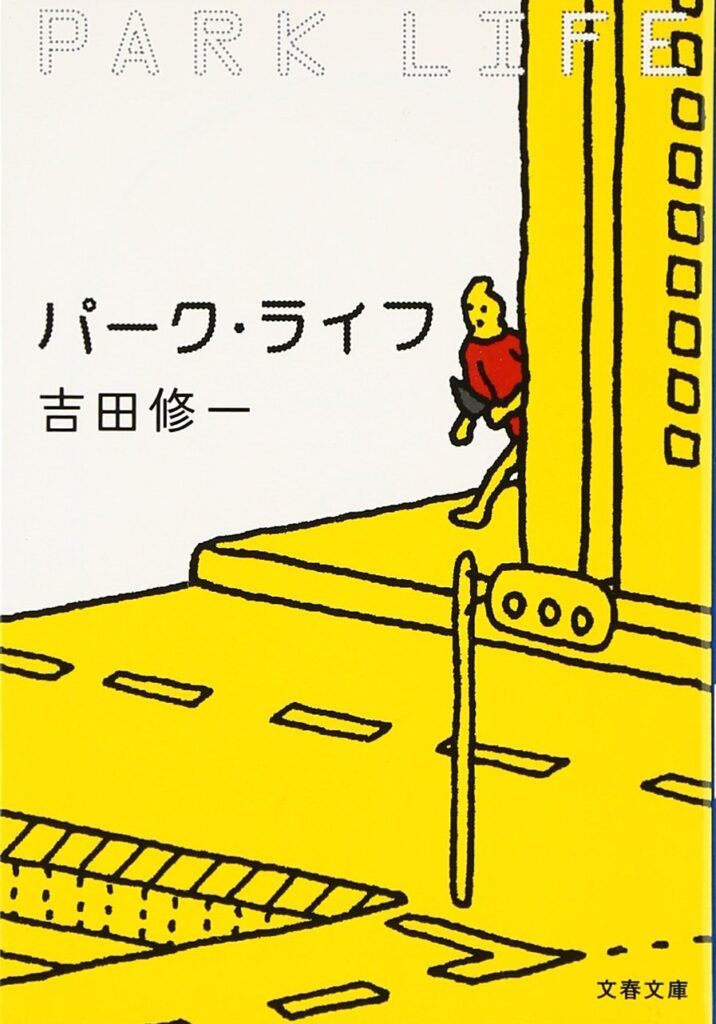
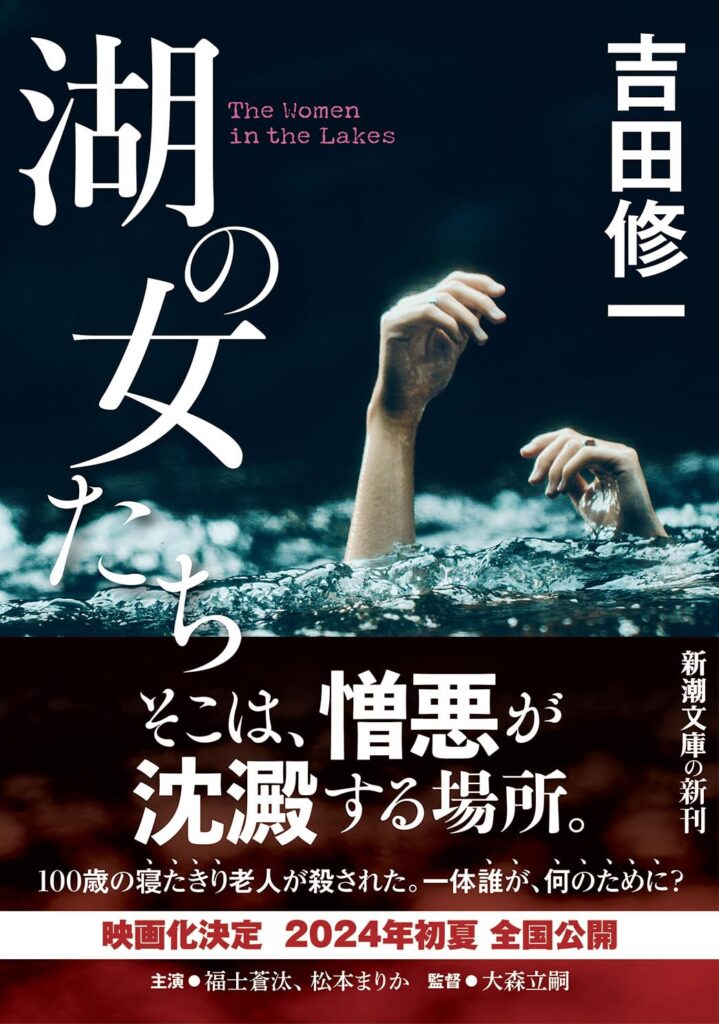
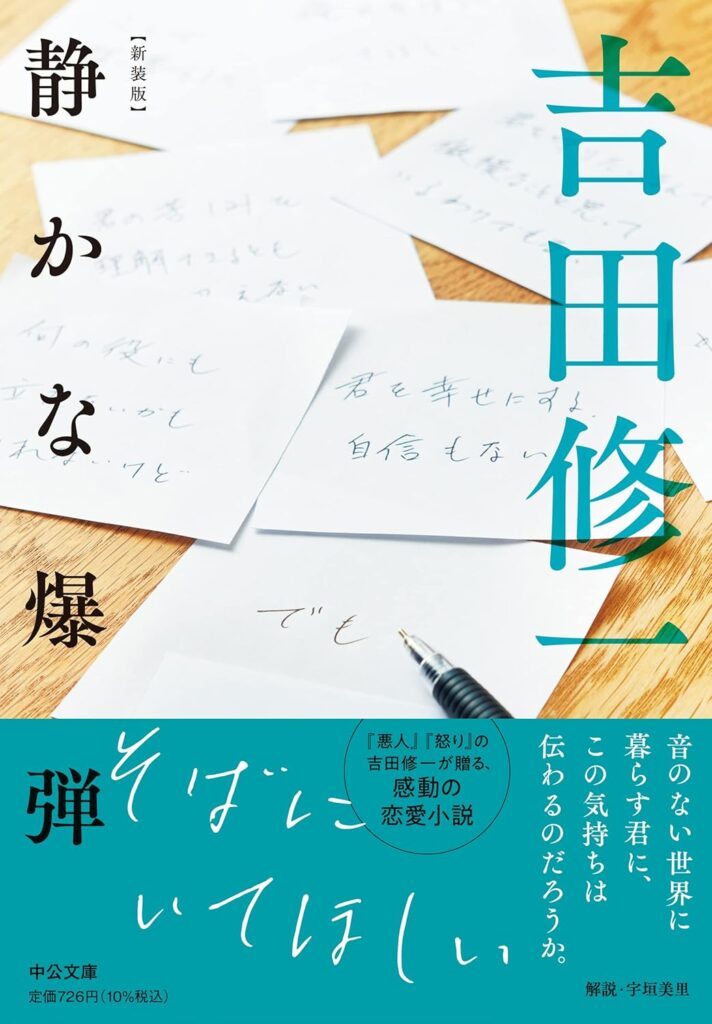
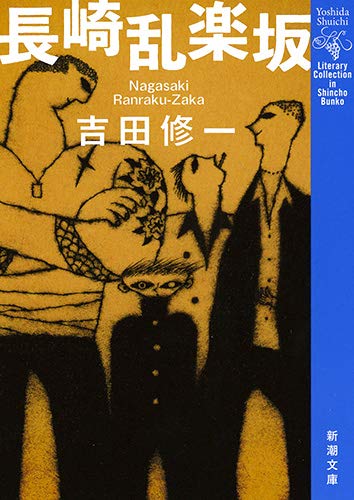

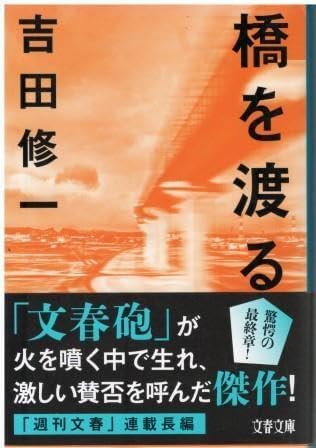
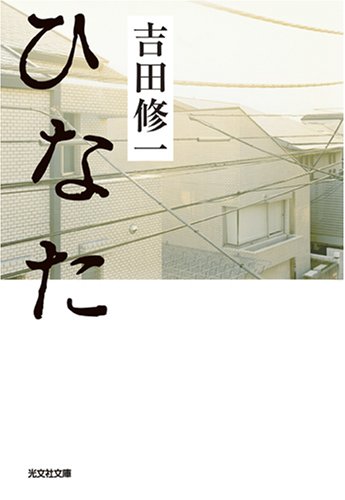
-728x1024.jpg)