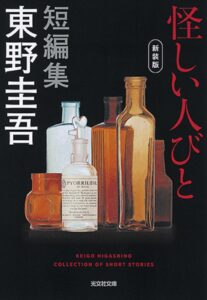 小説「怪しい人びと」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が描く、日常に潜む人間の不可解さ、とでも申しましょうか。一見、どこにでもいそうな人々が、ふとしたきっかけで奇妙な、あるいは不穏な側面を覗かせる。そんな短編が七つ、収められています。
小説「怪しい人びと」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が描く、日常に潜む人間の不可解さ、とでも申しましょうか。一見、どこにでもいそうな人々が、ふとしたきっかけで奇妙な、あるいは不穏な側面を覗かせる。そんな短編が七つ、収められています。
本作は、1994年に光文社から単行本として世に出され、時を経て2020年に文庫化されました。初期の作品ながら、氏の持ち味である、人間の心理の襞を描き出す手腕はすでに確立されているように見受けられます。殺人事件だけでなく、強盗や詐欺まがいの出来事、人間関係のもつれなど、題材は多岐にわたりますが、その根底に流れるのは、やはり「人」そのものの怪しさ、なのかもしれません。
この記事では、各短編の物語の筋立てに触れつつ、結末まで踏み込んだ私なりの評価を詳しく述べていきます。少々長くなりますが、お付き合いいただければ幸いです。あなたの隣人も、もしかしたら……などと考えながら読むのも、一興かと存じますよ。
小説「怪しい人びと」のあらすじ
『怪しい人びと』は、日常に潜む人間の不可解な一面を描いた七つの物語から構成される短編集です。それぞれの物語で、平凡な人々が奇妙な状況に巻き込まれたり、あるいは自ら怪しい行動に走ったりする様が描かれます。
「寝ていた女」では、親切心から同僚に部屋を貸した主人公が、ある日見知らぬ女が自室で寝ているのを発見します。同僚たちも知らないというその女の正体と、部屋が使われた真の目的が明らかになっていく、少々皮肉な物語です。「もう一度コールしてくれ」は、過去の野球の試合での判定に恨みを持つ男が、その審判への復讐心を抱きながら強盗を企てるものの、詰めが甘く失敗する顛末を描きます。人間の執念と、自身の弱点から目を背ける心理が描かれています。
「死んだら働けない」では、仕事一筋だった真面目な係長が会社の休憩室で亡くなっているのが見つかります。一見過労死かと思われたその死には、仕事への情熱が生んだ、あまりにも人間的な、そして悲劇的な真相が隠されていました。「甘いはずなのに」は、愛娘を事故で失った男が、再婚相手の妻に娘殺害の疑いを抱きながら新婚旅行に出かける物語です。疑念と愛情の間で揺れ動く心理と、意外な真実が心を打ちます。
「灯台にて」は、常に自分を見下す幼馴染との関係に悩む主人公が、一人旅で訪れた灯台で体験する出来事を描きます。ある出会いがきっかけとなり、長年の関係性が逆転する瞬間が訪れます。「結婚報告」では、友人から届いた結婚報告に添えられた写真の女性が見知らぬ別人だったことから、主人公が友人の身を案じ調査に乗り出す、少しコミカルながらも事件性を帯びた物語です。「コスタリカの雨は冷たい」は、海外赴任を終え、最後に妻と訪れたコスタリカで強盗被害に遭う夫婦の物語。助けてくれた人物にも裏があり、人間不信に陥りそうになりながらも、ささやかな人の温かさに救われる結末が待っています。
小説「怪しい人びと」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは各短編について、物語の核心、つまり結末部分にも遠慮なく触れながら、私なりの評価を述べさせていただきましょう。未読の方はご注意ください。この『怪しい人びと』という作品集、タイトルが示す通り、登場人物たちの「怪しさ」が様々な形で描かれています。それは、犯罪行為であったり、人間関係における歪みであったり、あるいは単なる奇行であったり。しかし、その根底にあるのは、極めて人間的な感情、弱さ、あるいは狡さなのです。それを東野圭吾氏が、時にコミカルに、時にシニカルに、そして時には切なく描き出しています。
まず「寝ていた女」。これは、主人公カワシマの人の好さ、というよりは、やや脇の甘さが招いた騒動、とでも言いましょうか。同僚に頼まれ、デート場所として自室を提供する。まあ、ありがちな話かもしれませんが、それが次々と連鎖していくあたり、彼の人の良さがうかがえます。しかし、その善意が悪用される。部屋に寝ていた女の正体は、同僚・片岡の恋人である広江の共犯者。広江は会社から盗んだ溶剤を隠し、転売するためにカワシマの部屋を利用していた。片岡が広江に見栄を張って「自分の契約している空き部屋だ」と嘘をついたことが、この勘違いを生んだわけです。結末で、真相を知って苦笑するカワシマと、何も知らずに「俺って女を見る目があるだろ」と自慢する片岡の対比は、なかなかに皮肉が効いています。人間の愚かさ、特に見栄や思い込みが引き起こす滑稽さを描いた小品ですが、ミステリとしての驚きは正直なところ、さほどありません。怪しいのは女だけでなく、部屋を借りた同僚たち全員、そして嘘をついた片岡自身も含まれる、という構造は面白いのですが、やや肩透かし感は否めませんね。
次に「もう一度コールしてくれ」。これは、過去の出来事に囚われた男の執念と、結局は自分自身の弱さから逃れられない現実を描いた物語です。主人公・芹沢豊は、高校時代の野球の試合でのアウト判定が、自分の人生を狂わせたと信じ込んでいる。その恨みを審判の南波に向け、強盗の逃走中に南波宅へ向かうという行動に出ます。この執念深さ、責任転嫁の心理は、理解できなくもありません。誰しも、人生の失敗を何かのせいにしたくなるものですから。しかし、南波から告げられた真相は、豊にとって残酷なものでした。彼は確かに一度ベースに触れたが、直後に手を放してしまった。つまり、アウトは正当な判定だった。彼の弱点は、常に「詰めが甘い」こと。それは野球のプレーだけでなく、今回の強盗からの逃走失敗にも表れている。南波の「人生はやり直しがきく」という言葉も、豊には届かない。結局、彼は自分の弱さと向き合うことから逃げ続けた結果、現在の境遇に至ったわけです。このやるせなさ、自業自得という結末は、なかなかに苦い味わいです。過去の判定という一点に固執する心理描写は見事ですが、強盗という犯罪と結びつける展開は、少々飛躍があるようにも感じられます。ただ、人間の「思い込み」の恐ろしさを描いている点では、興味深い一編と言えるでしょう。
「死んだら働けない」。これは、現代社会における働き方、あるいは生き方について考えさせられる物語です。仕事人間の林田係長が、会社の休憩室で死んでいる。過労死か、あるいは最新鋭のロボットの誤作動か? しかし、真相はもっと俗っぽく、そして悲しいものでした。林田を殺害したのは、取引先のメーカーの山岡。休日にもかかわらず林田に呼び出され、些細な不調のために修理を強要された山岡は、疲労と苛立ちが募っていました。そして、楽しみにしていたドラマの最終回を休憩室で見ようとした際、仕事の話を続け、鼻をすする音で視聴を邪魔する林田に、ついに堪忍袋の緒が切れてしまう。この動機、あまりにも人間的ではありませんか。もちろん殺人は許されることではありませんが、山岡の心情に、一抹の同情を禁じ得ない読者もいるのではないでしょうか。さらに皮肉なのは、殺害された林田が、息を吹き返した後に取った行動です。彼は自分が殺されたのではなく、新型ロボットの暴走が原因だと勘違いし、会社に迷惑をかけまいと、その事実を隠蔽しようとして休憩室に戻り、力尽きるのです。死の間際まで「仕事」のことを考えていた彼の生き様は、哀れであり、また滑稽でもあります。最後の、主人公・川島が本社へ異動するのを工場の人々が見送るシーン。「兵士を戦場に送り出す行為に似ていた」という描写は、企業社会への痛烈な皮肉として響きます。仕事に全てを捧げることが美徳とされがちな風潮に、一石を投じる作品と言えるでしょう。
「甘いはずなのに」。これは、収録作の中でも特に感情に訴えかける物語かもしれません。妻・尚美とハワイへ新婚旅行に来た主人公・伸彦。しかし、彼は前妻との娘・宏子の事故死に、尚美が関与しているのではないかと疑っています。新婚旅行という、本来なら幸福感に満ちているはずの状況で、伸彦は疑念と苦悩に苛まれる。一方の尚美は、なぜか伸彦の疑いをはっきりと否定しない。このすれ違いが、物語に緊張感を与えます。伸彦が怒りのあまり尚美に手を上げそうになる場面は、彼の苦しみの深さを物語っています。この膠着状態を打破するきっかけとなるのが、ハワイで出会った老夫婦の言葉です。「夫婦は互いを想い合うもの」「誰にでも思い違いはある」。この言葉に、伸彦は衝撃的な真相に気づかされます。宏子の事故死の原因は、実は伸彦自身にあった。そして尚美は、伸彦を苦しませまいとして、自ら悪役を演じ、疑いを引き受けていたのです。伸彦に憎まれることを覚悟の上で。この尚美の深い愛情、自己犠牲の精神には、胸を打たれます。タイトル「甘いはずなのに」が、伸彦の心情と、隠された真実の両方を暗示しており、実に秀逸です。人間の愛と、それが故に生じてしまう悲しい誤解を描いた、切なくも美しい物語と言えるでしょう。疑心暗鬼が、まるで砂漠の蜃気楼のように、ありもしない罪の形を見せていたのかもしれません。
「灯台にて」。これは、長年の歪んだ人間関係が、ある出来事をきっかけに劇的に逆転する様を描いた、少々ブラックな味わいの一編です。主人公の「僕」は、幼馴染の佑介に常に従属的な立場を強いられてきました。佑介は僕を見下すことで、自分の優位性を保とうとする。これは、現実の人間関係でも見られる、実に不快な力学ですね。僕がこの関係から脱却しようと決意し、一人旅に出る。しかし、そこにも佑介は絡んできます。僕が旅先で訪れた灯台。そこで出会った灯台守は、なんと同性愛者で、僕に迫ってきます。危機一髪で難を逃れた僕は、この出来事を佑介への復讐に利用することを思いつく。事情を隠して佑介に灯台へ泊まるよう勧め、案の定、佑介は灯台守に襲われ、そしてカッとなって殺害してしまうのです。僕は、その夜灯台で何が起こったかを正確に察知し、佑介の弱みを握ることに成功します。結果、二人の関係は完全に逆転する。この結末は、ある種の爽快感を感じさせると同時に、人間の狡猾さ、執念深さをも感じさせます。僕が掴んだ「切り札」は、佑介を永遠に支配下に置く力となりました。道徳的には問題のある結末ですが、長年虐げられてきた者の逆襲譚として読むならば、収録作中、最もカタルシスを得られる作品かもしれません。しかし、見方を変えれば、僕もまた佑介と同じように、相手の弱みを利用して関係性をコントロールしようとしているわけで、結局は同類の人間なのかもしれない、という皮肉な解釈も成り立ちます。
「結婚報告」。これは、一見深刻そうな導入から、ややコミカルなドタバタ劇へと展開する物語です。友人・典子から届いた結婚報告。しかし、同封された写真の女性は典子ではない。心配した主人公・智美が典子の元を訪ねると、そこには奇妙な人間模様と、小さな事件が待っていました。写真の女性は、典子の夫・昌章の元恋人・秋代。彼女は、自分が昌章の妻であるべきだと主張し、典子たちの新生活をかき乱そうとしていたのです。しかし、物語はさらに捻りを加え、この秋代が、昌章の蝶のコレクションを狙った隣人・桜井によって殺害されてしまう。動機は蝶の窃盗であり、秋代はその場に居合わせたために殺された、という偶然の悲劇。秋代自身も、ようやく典子を認め、気持ちの整理をつけようとしていた矢先だったというのも、皮肉な巡り合わせです。智美の心配は杞憂に終わり、事件も解決。典子夫妻との再会を約束して帰路につく智美、という結末は、後味の悪さを残しません。ミステリとしての深みはあまりありませんが、勘違いや偶然が重なって起こる騒動を軽妙に描いた、読みやすい一編と言えるでしょう。登場人物たちのキャラクターも、どこか憎めないおかしみがあります。
最後に「コスタリカの雨は冷たい」。これは、異国の地での不運な出来事と、それでも失われない人の温かさを描いた物語です。トロントでの駐在生活を終え、妻・ユキコと共に最後の旅行でコスタリカを訪れた「僕」。しかし、そこで強盗に遭うという災難に見舞われます。助けてくれた親切な警察官。これで一件落着かと思いきや、僕はあるきっかけ(カメラの電池カバー)から、その警察官が強盗グループと繋がっていたことに気づきます。旅行者を狙って犯行を計画し、自らは救助役を演じて事件を穏便に済ませる、という悪質な手口。異国の地で、頼りになるはずの警察官にまで裏切られたとなれば、人間不信に陥るのも無理はありません。旅行は散々な結果に終わり、失意のうちに帰国する夫婦。しかし、彼らを待っていたのは、隣家のタニヤ婆さんからの温かい「Welcome」のメッセージでした。このささやかな、しかし心からの歓迎の言葉が、夫婦の傷ついた心を優しく癒します。コスタリカでの出来事が「冷たい雨」だったとすれば、この隣人の親切は、さしずめ「乾いた心に染み渡る温かい飲み物」といったところでしょうか。人間の悪意に触れた後だからこそ、日常にある小さな善意がより一層輝いて見える。そんな対比が印象的な、心温まる結末です。
全体を通して見ると、『怪しい人びと』に収められた物語は、人間の持つ「怪しさ」を様々な角度から切り取っています。それは、犯罪に繋がるような悪意や狡猾さだけではありません。見栄、執着、思い込み、愛情ゆえのすれ違い、仕事への情熱、人間関係における力学、そういった日常的な感情や状況の中に、ふとした拍子に顔を出す「歪み」や「不可解さ」こそが、本作のテーマなのかもしれません。東野圭吾氏の初期の作品でありながら、その後の作品にも通じる、人間の心理に対する深い洞察が感じられます。派手なトリックや大掛かりな事件があるわけではありませんが、読後、自分の周りにいる人々、あるいは自分自身の心の内に潜む「怪しさ」について、ふと考えさせられる。そんな味わいを持つ短編集と言えるでしょう。
まとめ
東野圭吾氏の短編集『怪しい人びと』について、物語の筋立てから結末の核心部分、そして私なりの評価まで、詳しく述べてまいりました。いかがでしたでしょうか。本作は、日常に潜む人間の不可解さ、奇妙さ、そして時に見せる悪意や弱さを、七つの異なる物語を通して描き出しています。
殺人、強盗、詐欺まがいの行為、あるいは単なる人間関係のもつれ。描かれる出来事は様々ですが、その根底にあるのは、誰もが持ちうる普遍的な感情の揺らぎです。見栄を張る心、過去への執着、仕事への情熱、愛情ゆえの誤解、支配欲、そして異郷での不安。そうした感情が、登場人物たちを「怪しい」行動へと駆り立てるのです。
東野氏らしい、人間の心理の機微を捉えた描写は、初期の作品ながら見事と言わざるを得ません。派手さはありませんが、じわりと心に染みる皮肉や、やるせない現実、そして時にはささやかな救いが描かれています。あなたの隣人、あるいはあなた自身の心の中にも、ここに描かれた「怪しい人びと」の影が潜んでいるのかもしれませんね。そう考えると、日常が少し違って見えてくるのではないでしょうか。
































































































