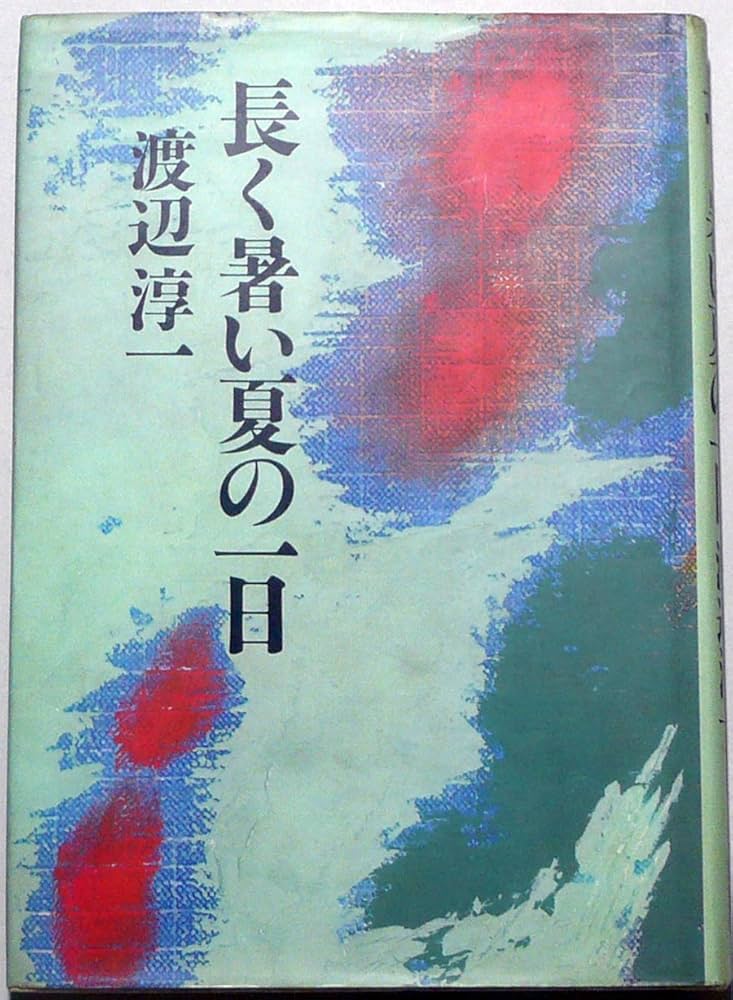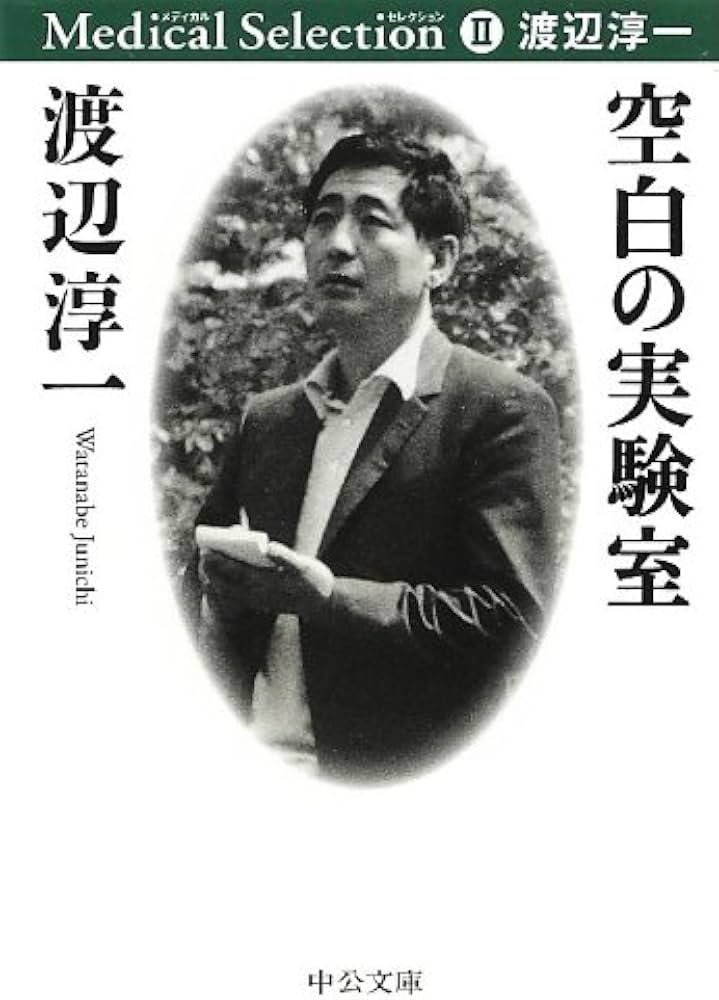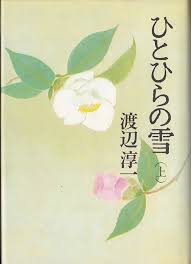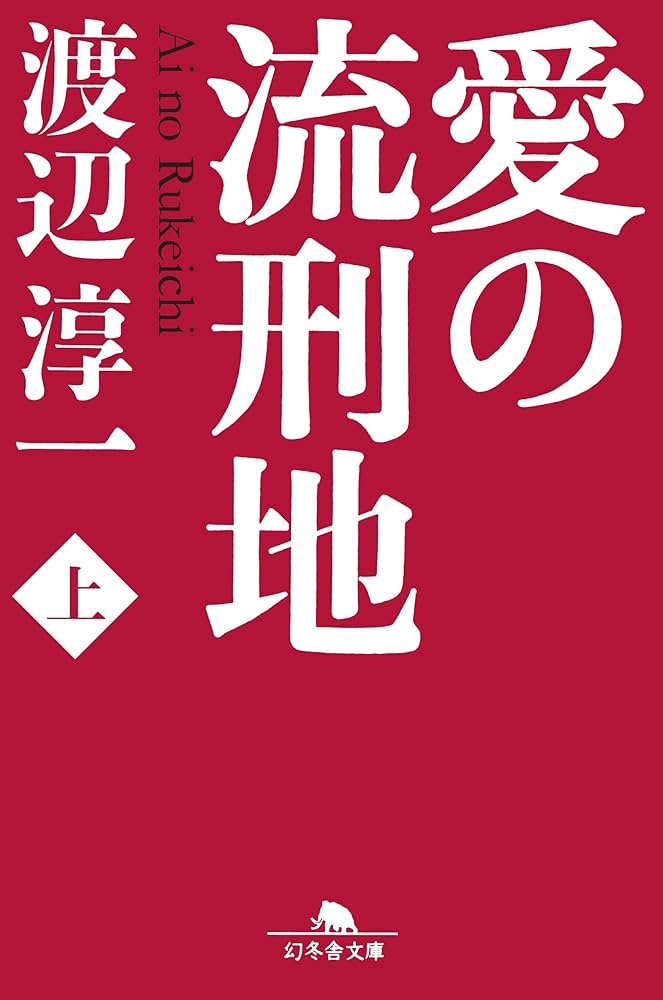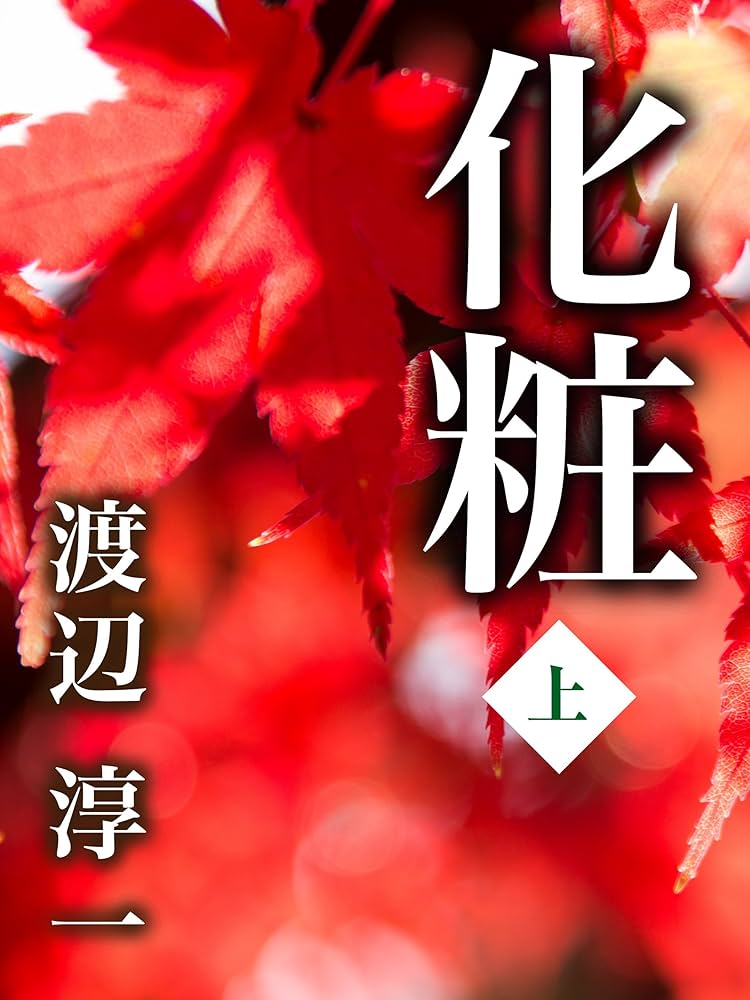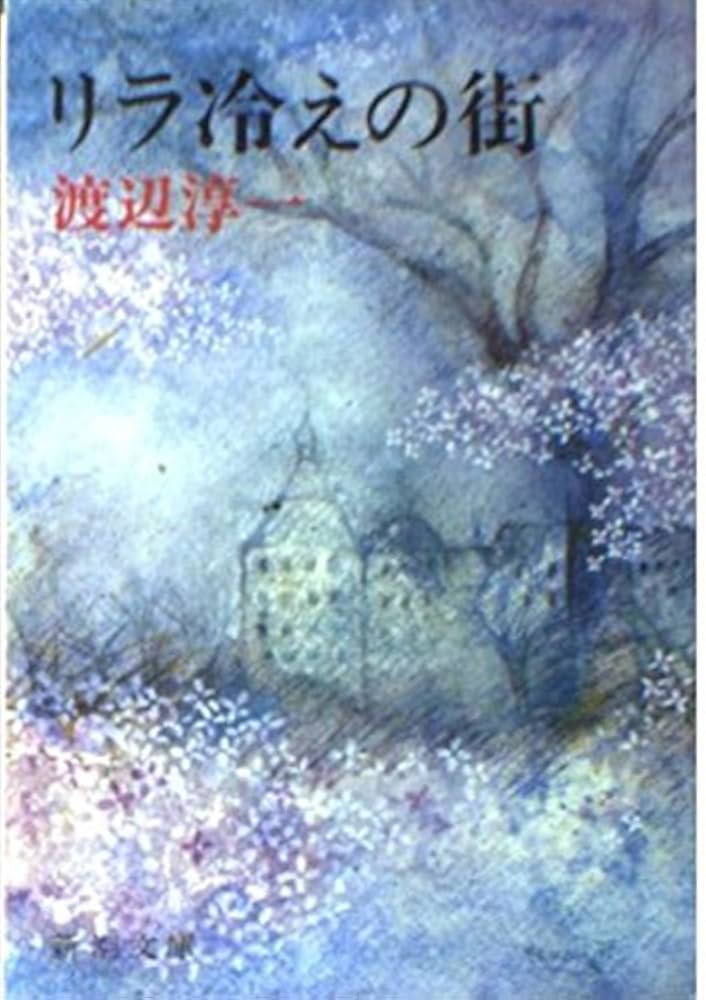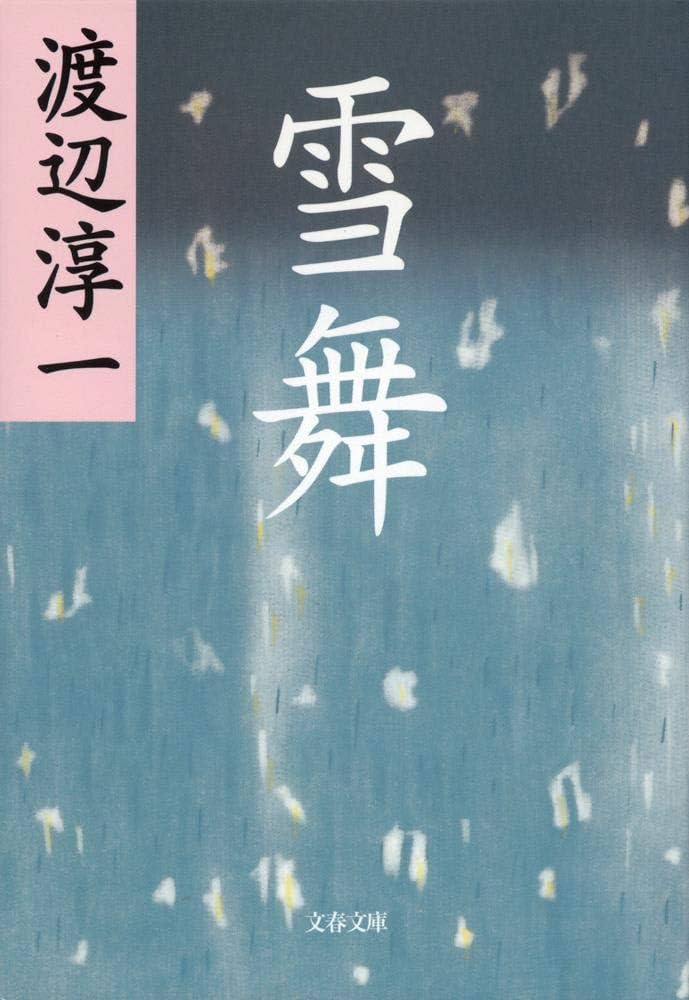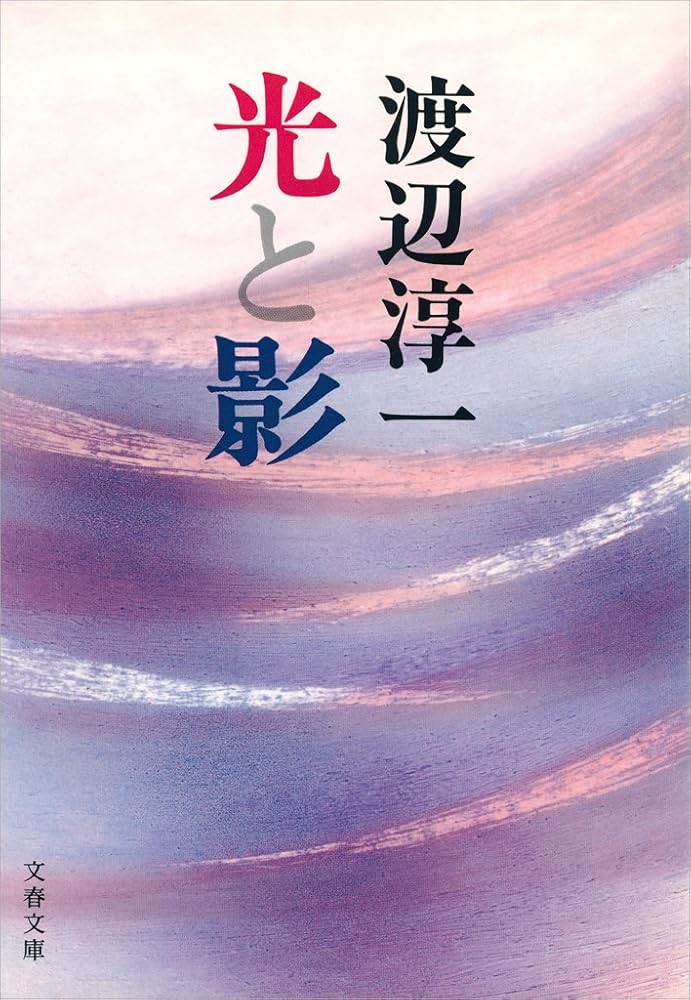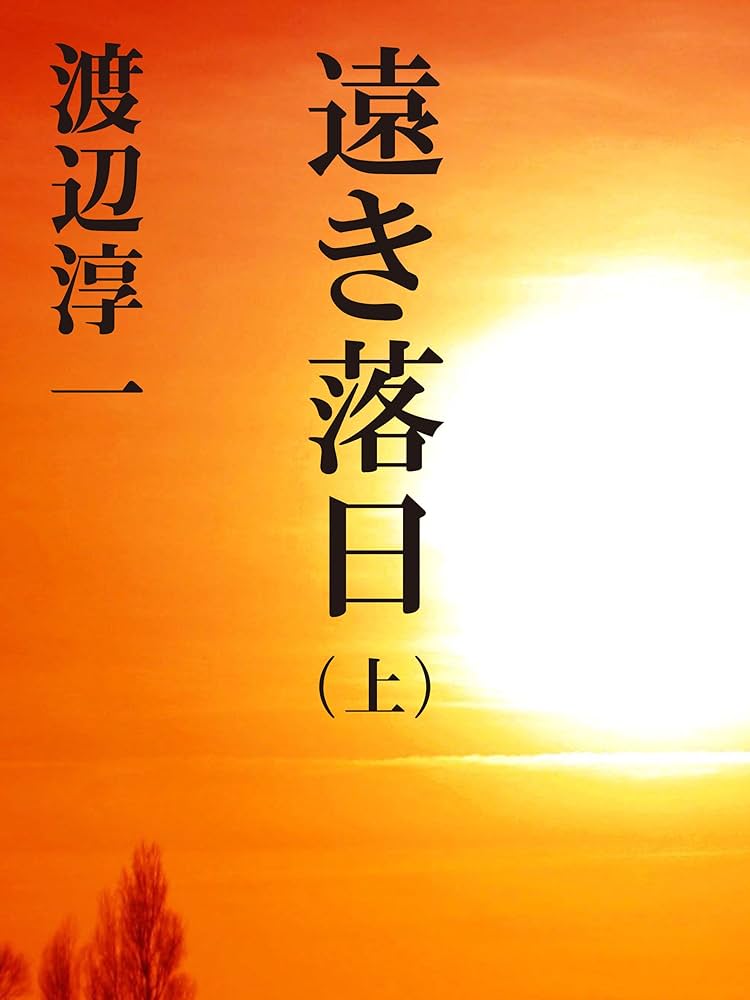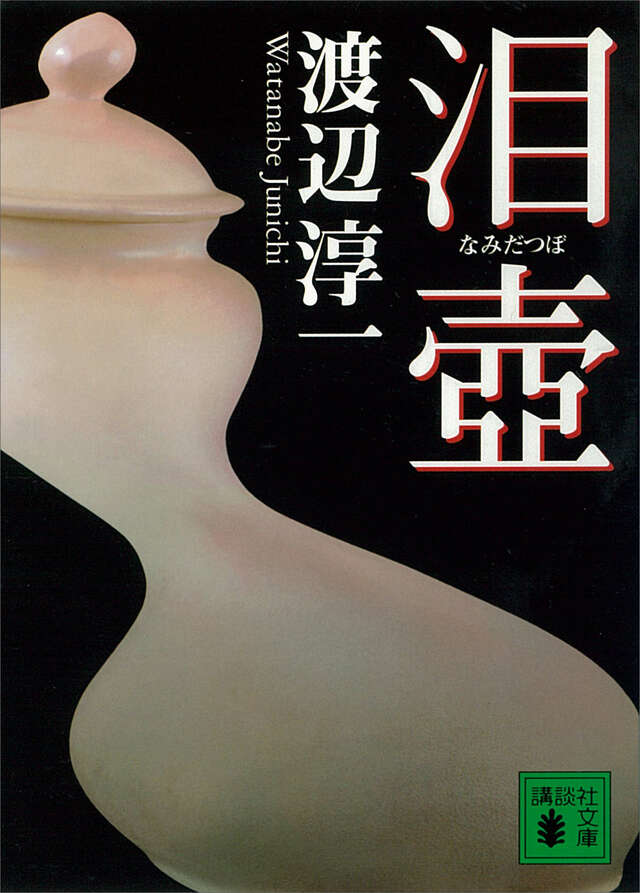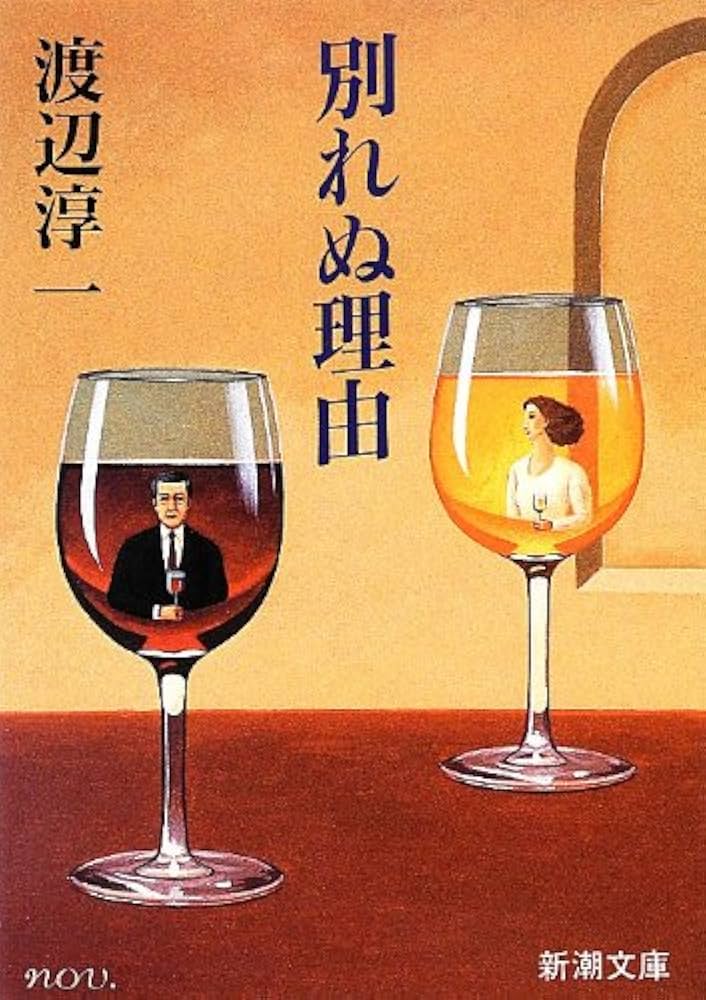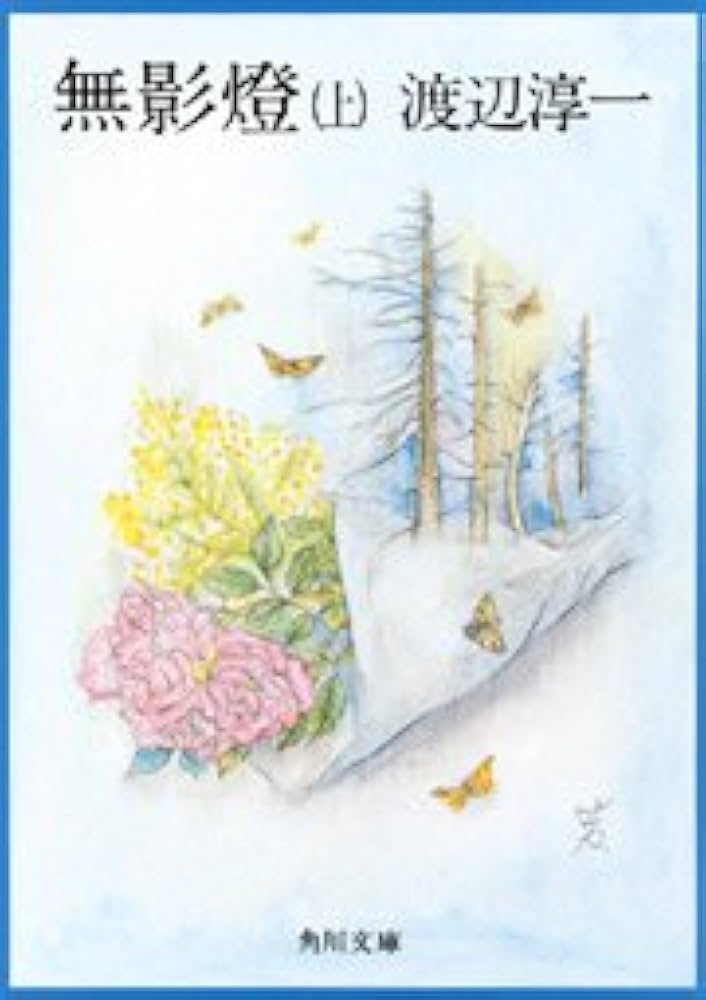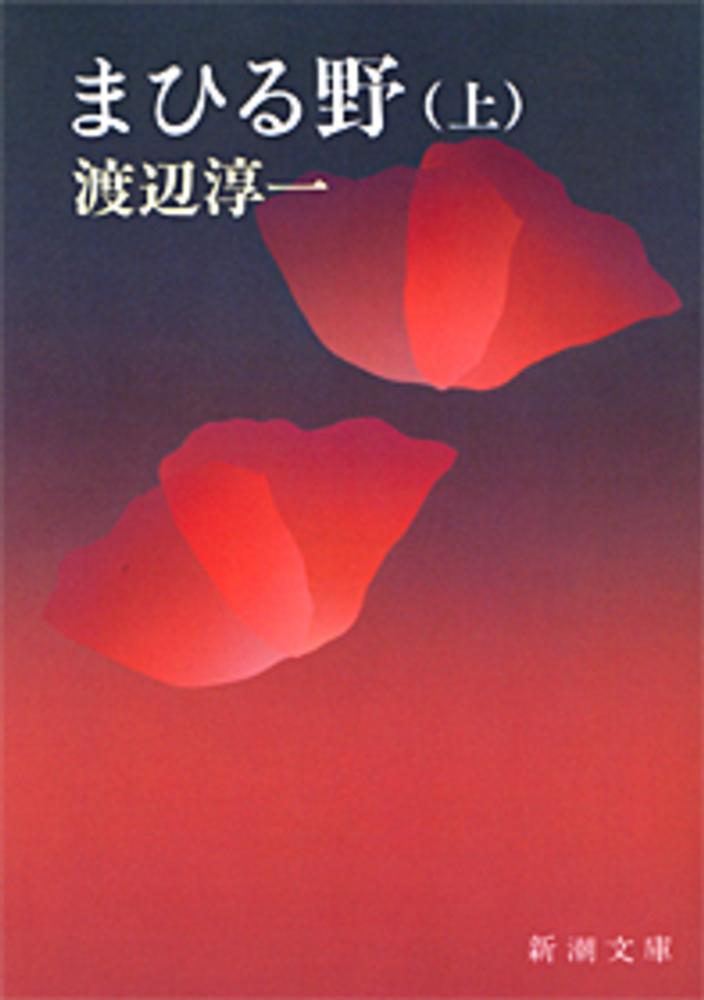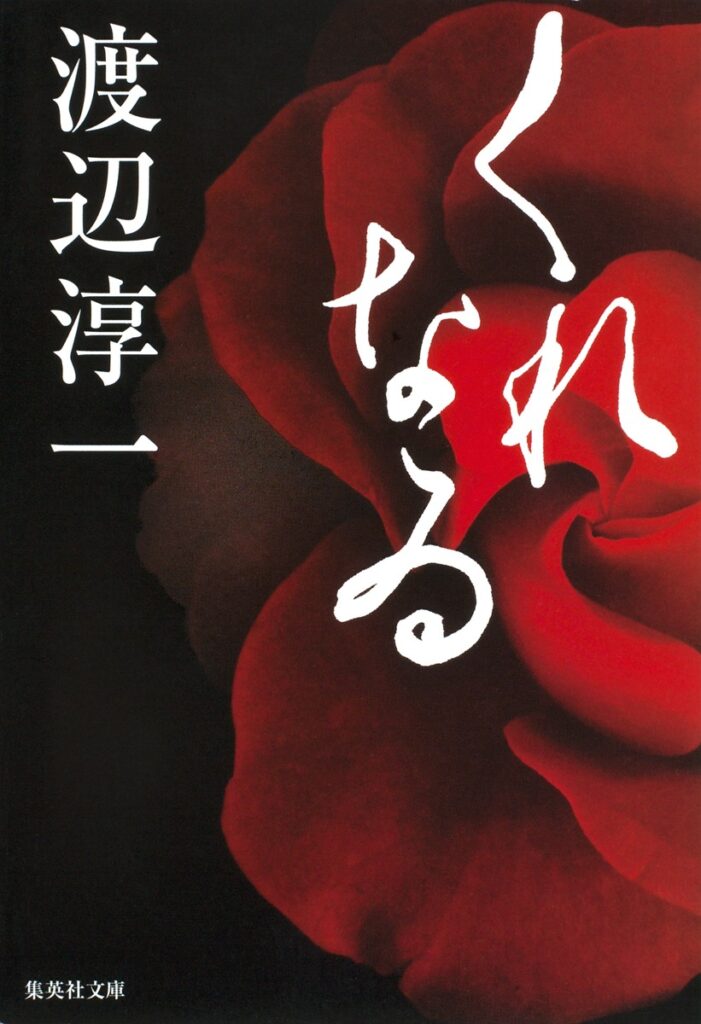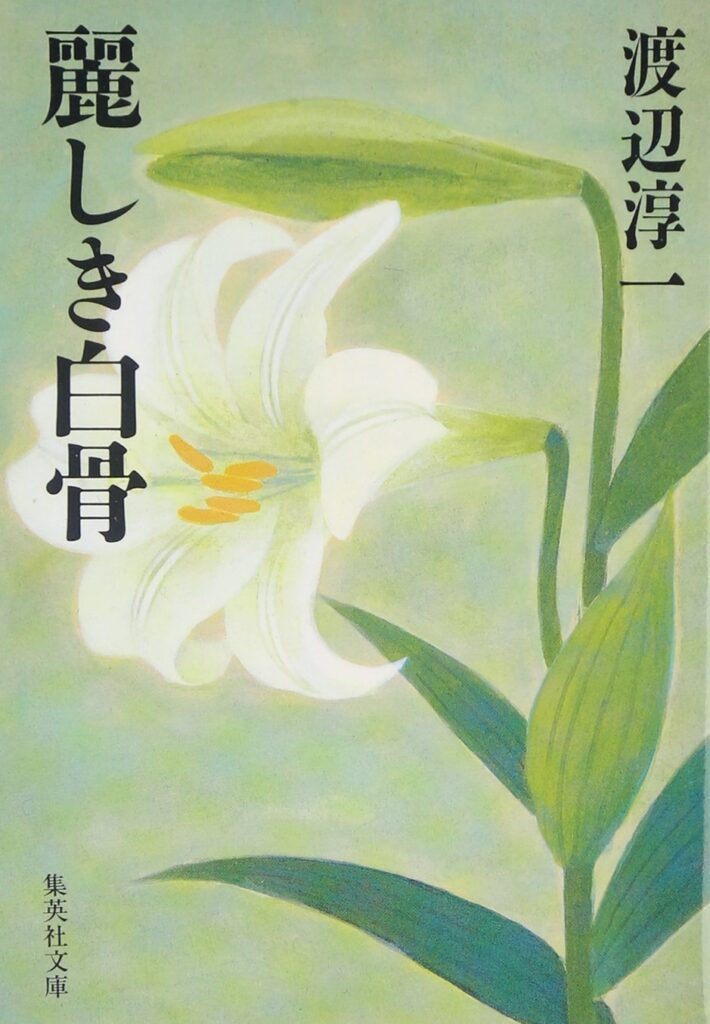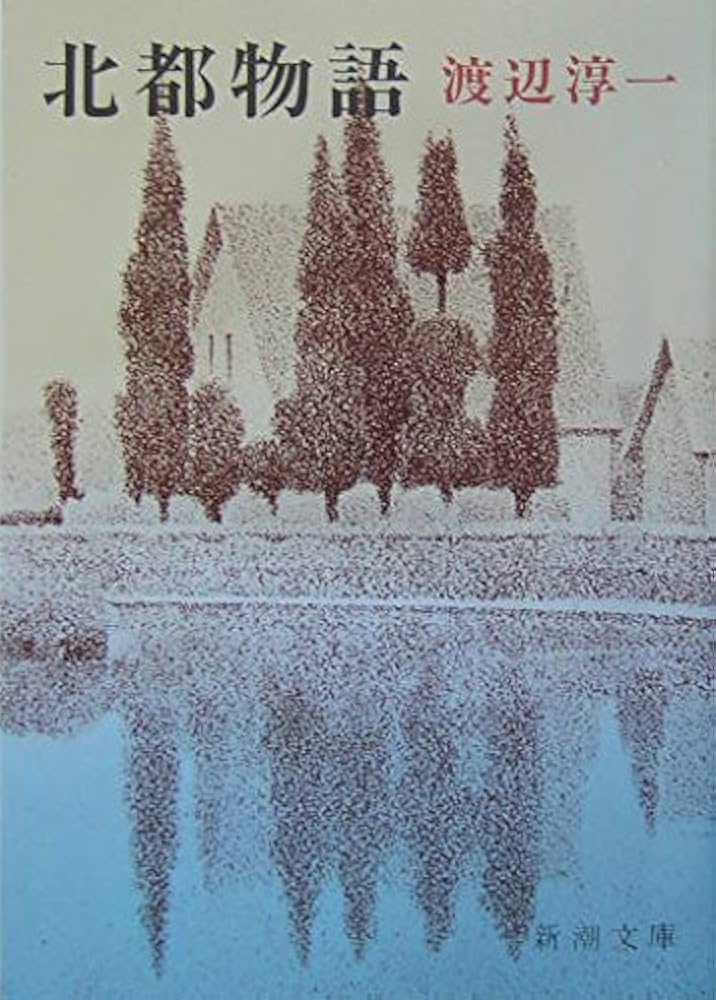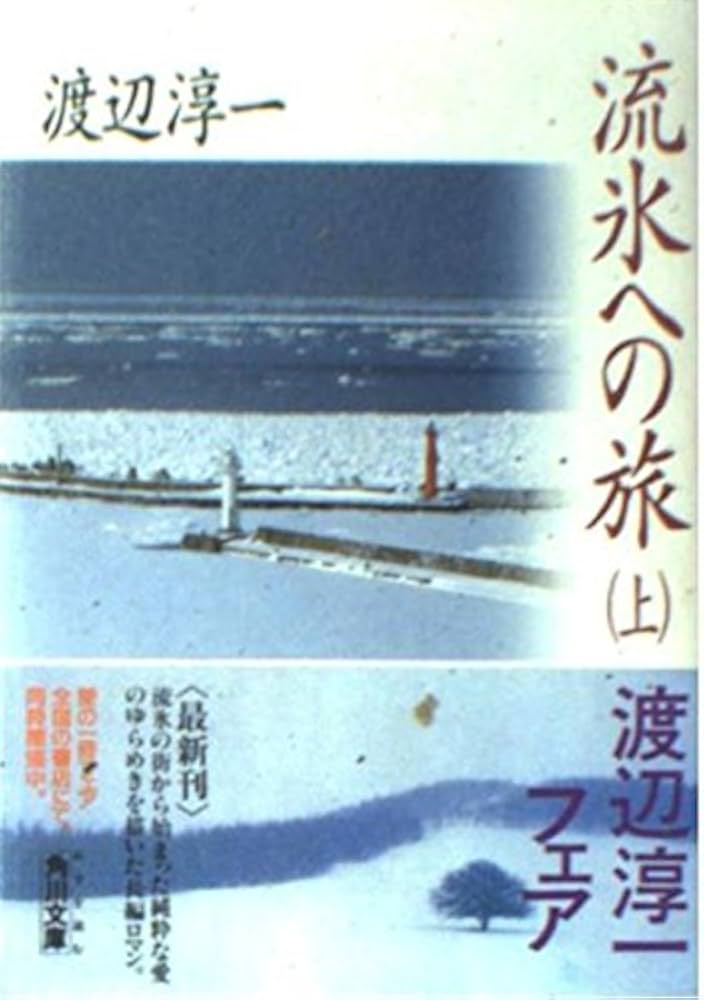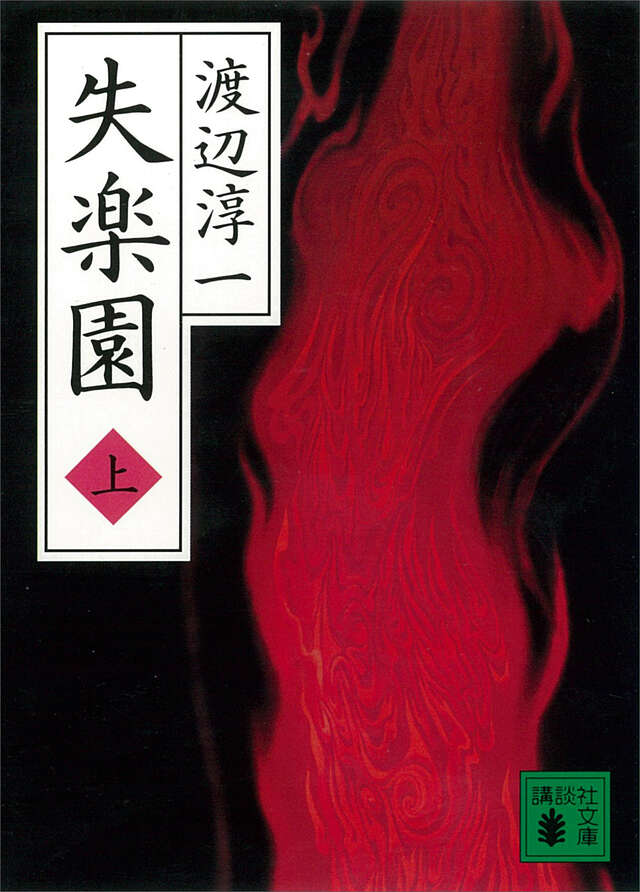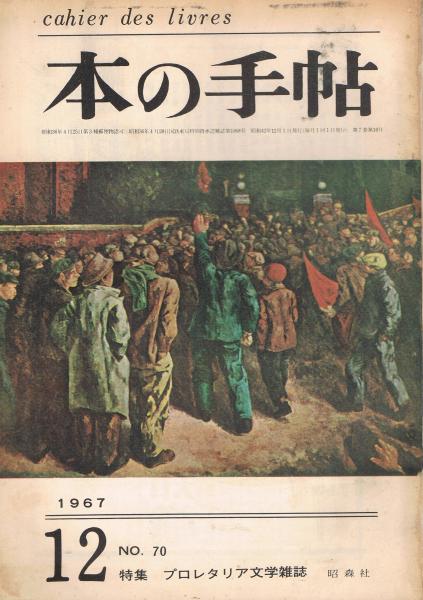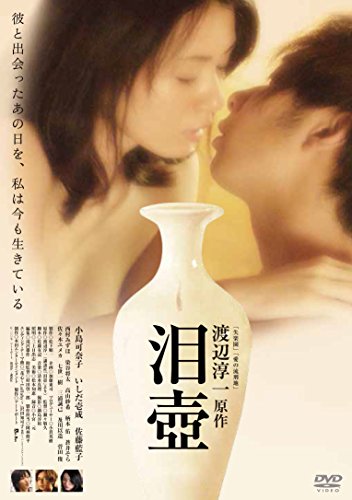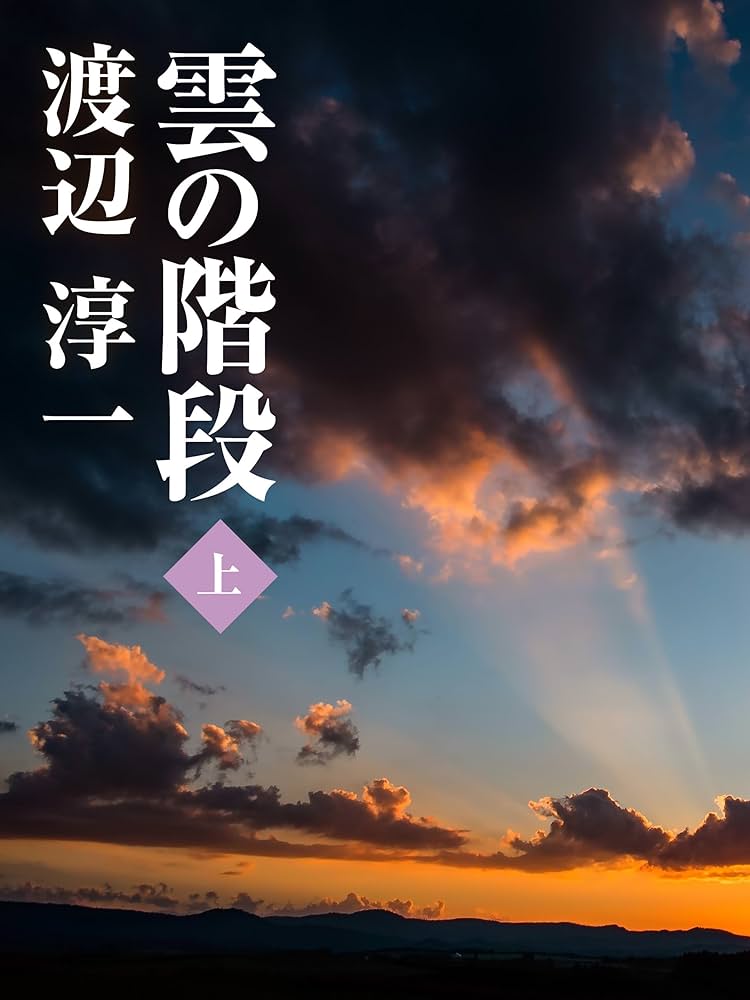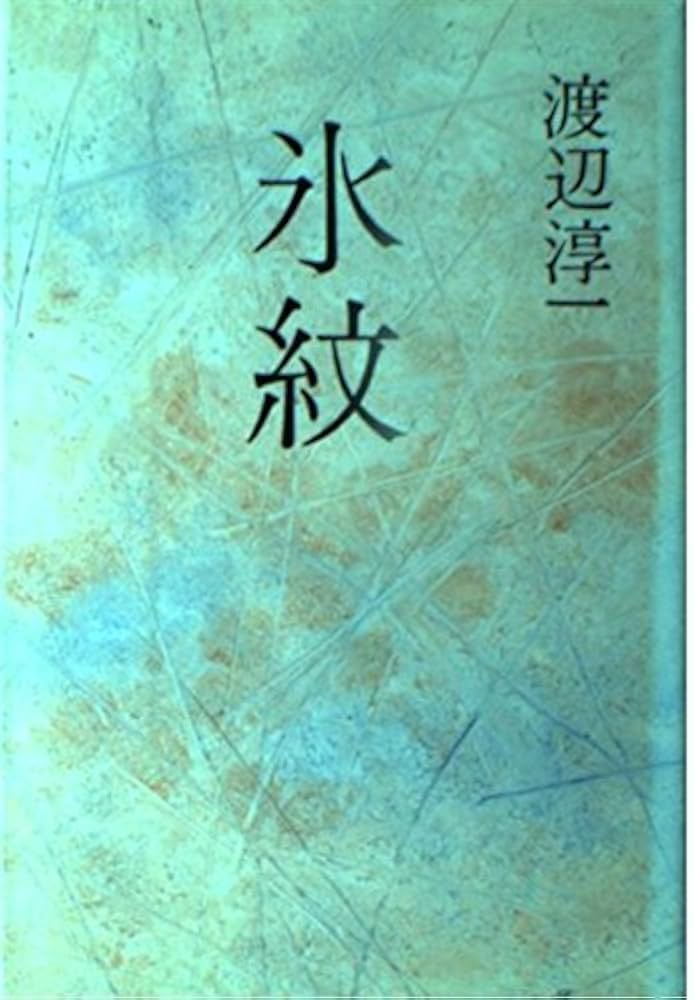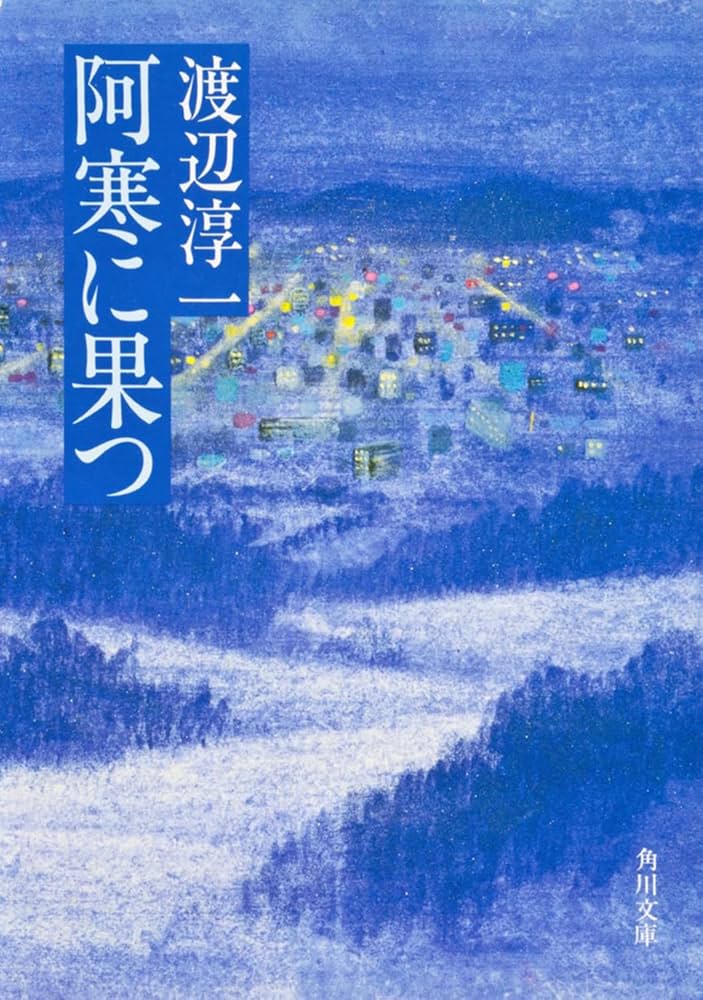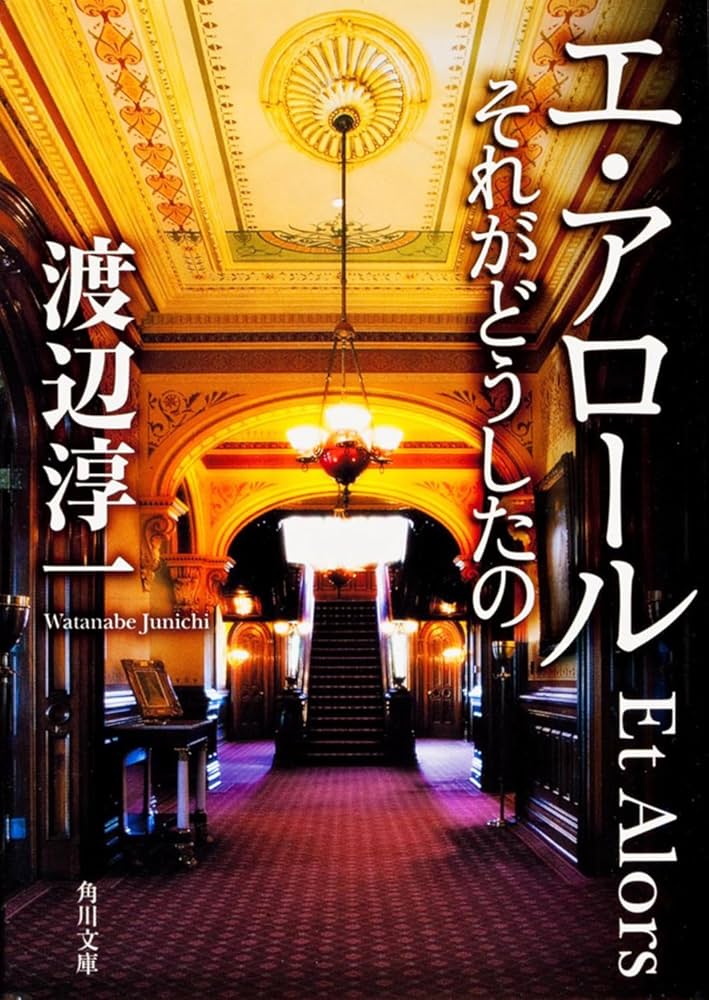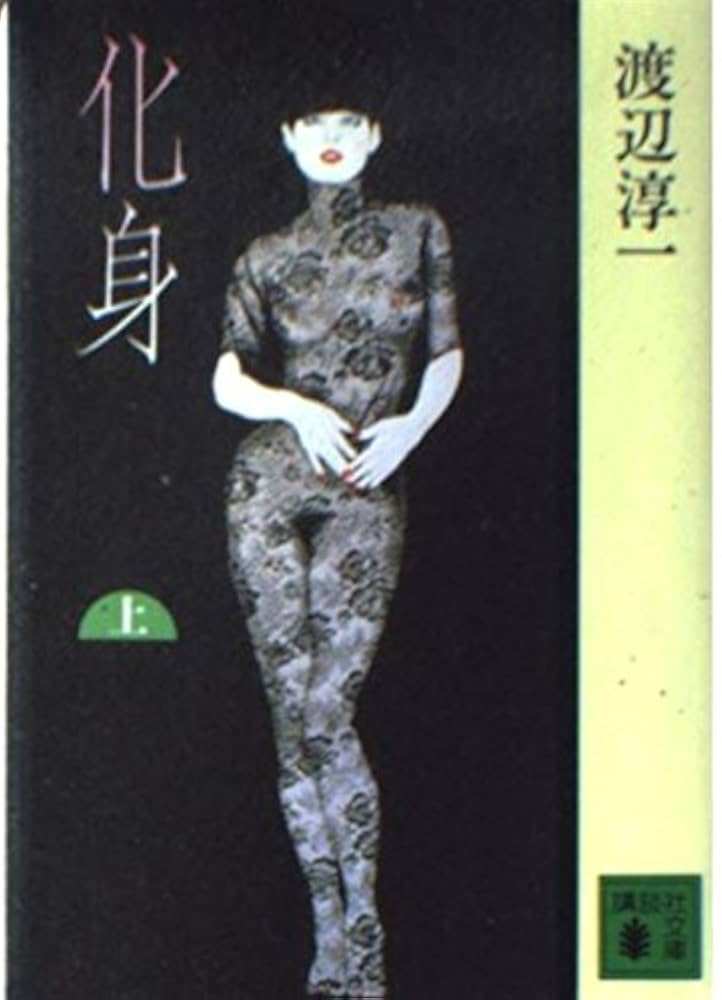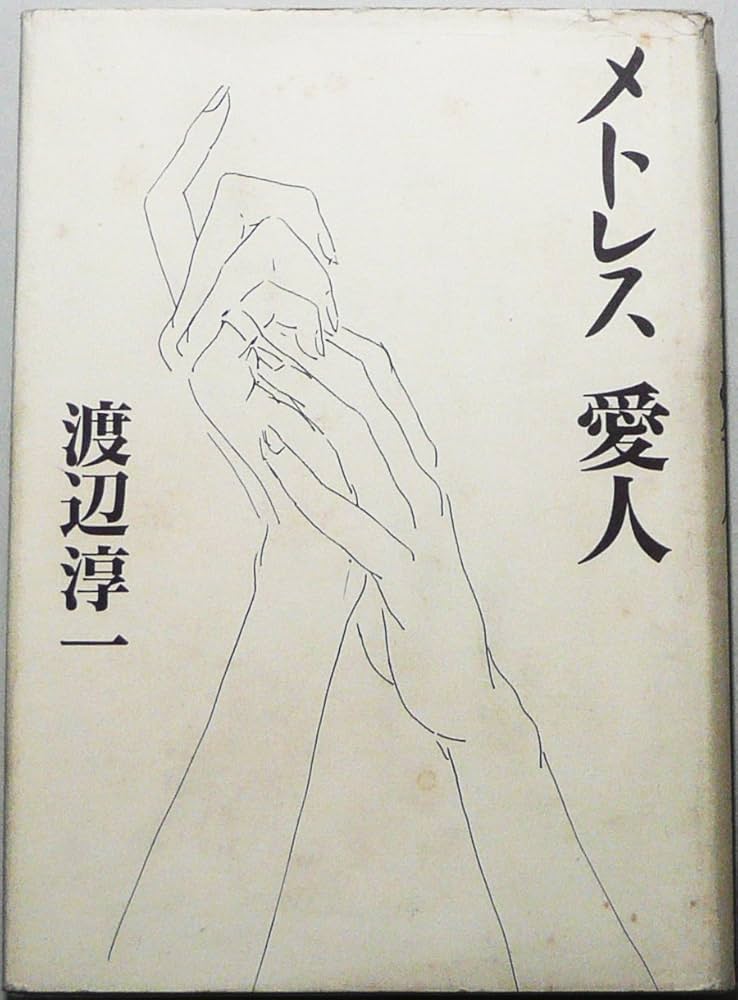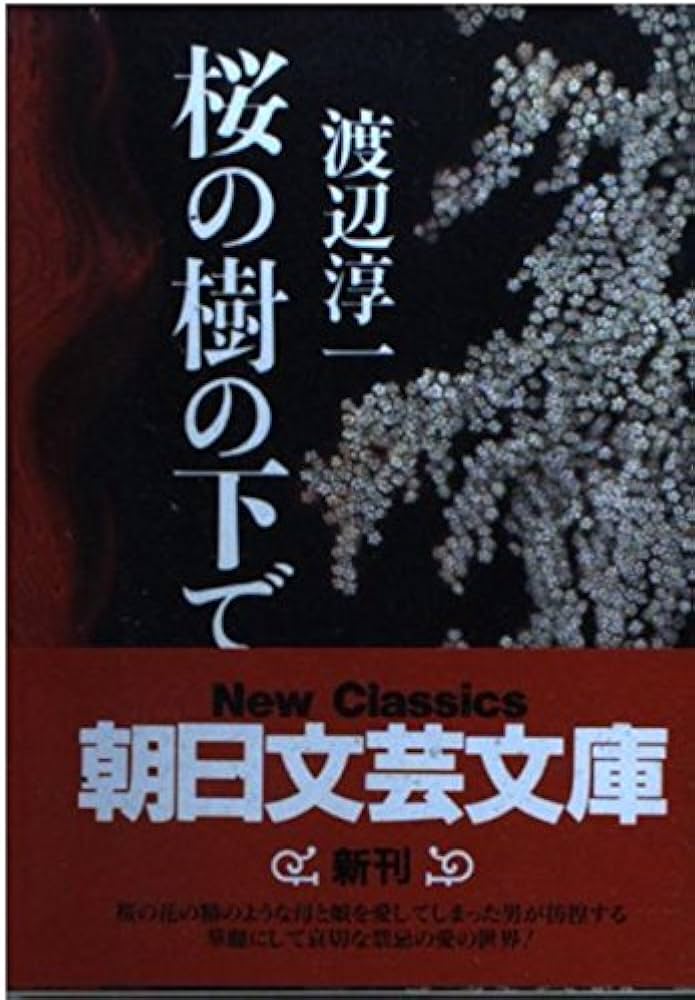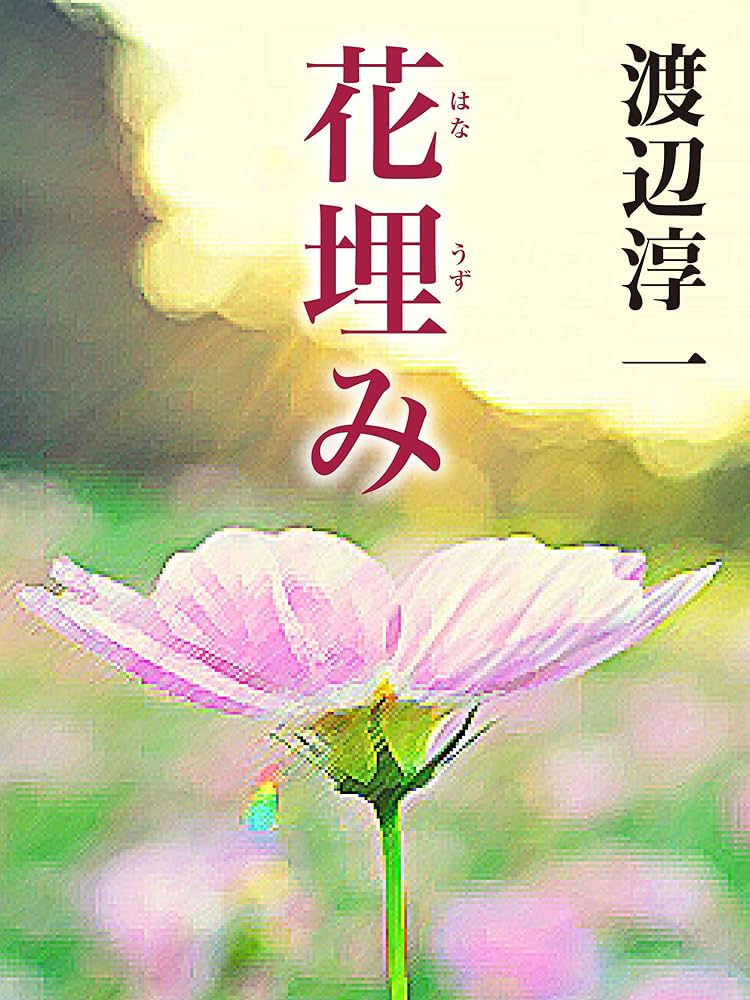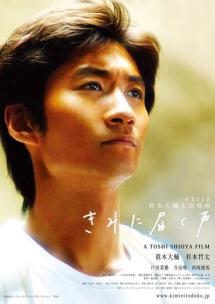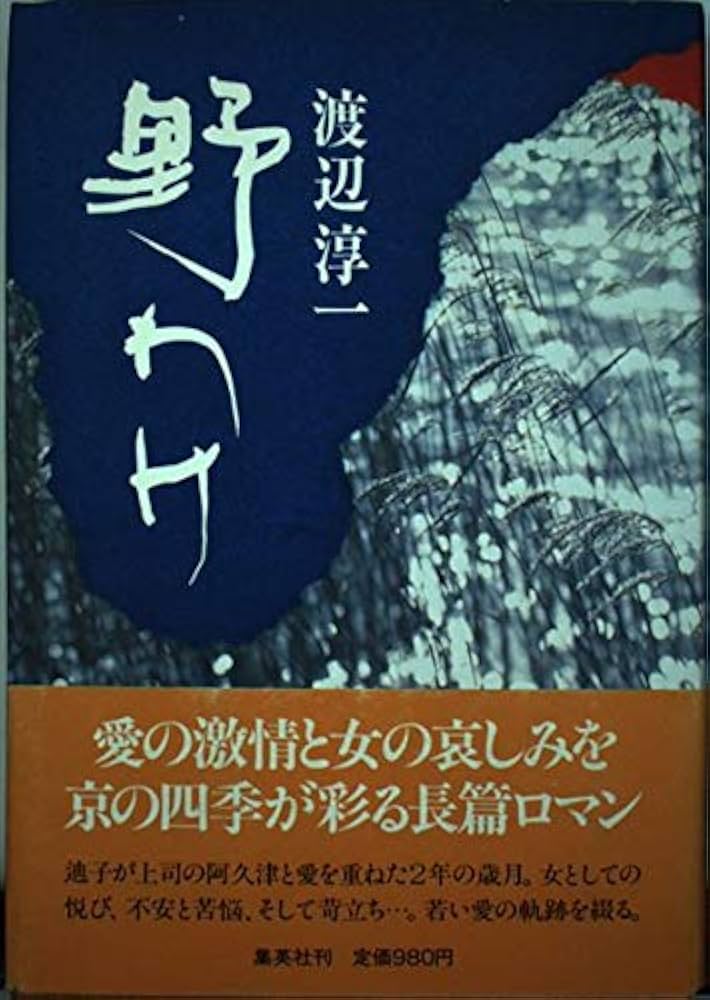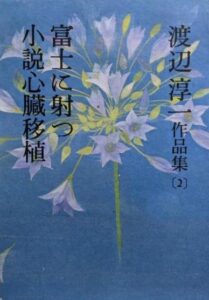 小説「心臓移植」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「心臓移植」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この作品は、単に医療の現場を描いた物語という枠には到底収まりきらない、私たちの社会と倫理に鋭いメスを入れるような一冊です。1968年に日本で初めて行われた心臓移植手術、いわゆる「和田心臓移植事件」を題材にしており、その発表は手術からわずか数ヶ月後という衝撃的なものでした。
この迅速な作品化が、『心臓移植』にフィクションを超えた、まるでドキュメンタリーのような生々しい緊迫感を与えています。さらに特筆すべきは、作者である渡辺淳一氏が、事件の舞台となった札幌医科大学に籍を置く現役の医師だったという事実です。内部の人間だからこそ知り得たであろう、大学病院という閉鎖された組織の空気感や権力構造が、物語の隅々にまで色濃く反映されています。
この物語は、一個人の創作活動というよりも、自らの立場を賭した「告発」に近い性格を帯びていました。実際に、この作品がきっかけで渡辺氏は大学を去り、作家の道へ進むことになります。その覚悟が、物語に並々ならぬ熱量と切実さを与えているのです。
この記事では、そんな『心臓移植』の物語の核心部分に触れながら、なぜこの作品が今なお多くの人の心を揺さぶり続けるのか、その理由を深く掘り下げていきたいと思います。生命の尊厳、科学の進歩がもたらす光と影、そして組織の中でかき消されていく個人の良心。物語を通じて、現代に生きる私たちにも通じる普遍的なテーマを一緒に考えていきましょう。
「心臓移植」のあらすじ
物語の舞台は、日本の北に位置する大学病院。そこには、「日本初」となる心臓移植手術の成功という栄光に執念を燃やす、天才的な外科医・天木有作教授がいました。彼は卓越した技術と人を惹きつけるカリスマ性を持ちながらも、その野心は時に倫理観さえも凌駕する危うさを秘めています。彼の周りには、その野望を後押しする妻や忠実な部下たちがおり、彼の行動を誰も止められない状況が形作られていきます。
その野心の対象となるのが、重い心臓病を患う一人の青年です。彼の病状は深刻ですが、物語は一貫して「心臓移植だけが本当に唯一の道だったのか」という疑問を投げかけます。天木の動機が、純粋な救命精神からなのか、それとも歴史に名を刻みたいという功名心からなのか。その境界線は、非常に曖昧に描かれています。
時を同じくして、平凡な大学生活を送っていた健康な青年・江口克彦の日常が、突如として暗転します。彼は友人との旅行中、不慮の溺水事故に遭い、意識不明のまま天木のいる大学病院へ運び込まれます。この偶然の悲劇が、彼の身体を、天木の壮大な野望を実現するための「提供者(ドナー)」という役割へと変えてしまうのです。
この緊迫した状況の中、天木教授のチームに所属する若手医師の大鈴は、性急で疑わしい医療行為の数々に深い良心の呵責を覚えます。また、病院の公式発表の裏に何かを感じ取った新聞記者の富塚は、真相を求めて粘り強く取材を試みます。しかし、大学病院という巨大な組織の壁が、彼らの前に立ちはだかるのでした。
「心臓移植」の長文感想(ネタバレあり)
この『心臓移植』という作品を読んだ時の衝撃は、今でも忘れられません。これは単なる医療ドラマではない。むしろ、社会派のノンフィクションを読んでいるかのような、肌が粟立つほどのリアリティと緊迫感に満ちています。物語の根底に流れるのは、実際の事件を告発しようとする作者の執念にも似た強い意志でした。
作者である渡辺淳一氏が、事件の渦中にあった大学の内部者であったという事実が、この物語に他にはない深みと重みを与えています。これは、外から見た正義ではなく、内側から見た矛盾と葛藤の物語です。彼がこの作品を発表するために、医師としてのキャリアを捨てる覚悟をしたという背景を知ると、一文一文の重みがまるで違って感じられます。
物語の冒頭から、私たちは天木有作という教授の強烈な野心に引き込まれます。彼の存在は、まさしく「光と影」そのもの。神業的な手術の腕を持ちながら、その心は「日本初」という名誉欲に支配されています。その野心に、周囲の人々の運命が否応なく巻き込まれていく様は、読んでいて息苦しくなるほどでした。
この物語で最もおぞましいと感じたのは、ドナーとされた青年・江口克彦の「死」が、いかに曖昧に、そして意図的に作り上げられていくかの描写です。病院に運び込まれた彼に対し、最大限の蘇生努力が払われるどころか、まるで「移植に適した状態」を維持するかのような処置が施されていきます。
筋弛緩剤や麻酔薬の投与。それは、まだ生きているかもしれない人間を「モノ」として扱う行為に他なりません。「脳死」の判定も、客観的なデータに基づく厳密なものではなく、移植を強行するための儀式のように進められていきます。科学の名の下で、一人の人間の命がこれほど軽く扱われる現実に、深い怒りと無力感を覚えました。
私が特に心を掴まれたのは、作者が加えた「ダブルハート方式」という創作です。実際の事件では心臓を丸ごと入れ替える方式でしたが、渡辺氏はあえて、患者自身の心臓を残したままドナーの心臓を補助的に植え付けるという設定を選びました。これは、単なる医学的な改変ではありません。
この設定こそが、この物語を文学の高みへと昇華させていると私は思います。一つの身体に二つの心臓が存在するという異様な状況は、この物語が内包するあらゆる二元性を象徴しているかのようです。生きようとする本来の自己と、他者から与えられた生命力とのせめぎ合い。自然な生と、人工的に延命された生との対立。そして、一つの命を救う行為が、別の命の犠牲の上に成り立つという、移植医療そのものが抱える根源的な矛盾を見事に描き出しています。
手術室の場面は、「白い宴」という言葉がこれ以上なくしっくりくる、神聖さと冒涜性が入り混じった異様な空間として描かれています。神のように振る舞う天木教授と、その権威の前では無力な他の医師たち。若手医師の大鈴が抱く倫理的な葛藤の声は、巨大な組織の論理によっていともたやすくかき消されてしまいます。
私自身、もし大鈴の立場だったらどうしただろうか、と考えずにはいられませんでした。目の前で行われる非人道的な行為に声を上げる勇気があっただろうか。それとも、組織の圧力と自らの将来を天秤にかけ、沈黙してしまっただろうか。彼の苦悩は、組織に属する全ての人間にとって他人事ではない、普遍的な問いを投げかけてきます。
そして、手術は「成功」したと発表されます。華々しい記者会見が開かれ、メディアはこれを無批判に「快挙」として報じます。しかし、その裏側では、移植を受けたレシピエントの身体が静かに、しかし着実に蝕まれていくのです。
病院が発信する楽観的な経過報告とは裏腹に、彼は深刻な拒絶反応と感染症に苦しみます。この、外部に向けた「成功のプロパガンダ」と、内部で進行する「身体の崩壊」という現実の対比が、天木教授と病院組織の冷酷な欺瞞を容赦なく暴き出します。彼らの関心は、もはや患者の命を救うことではなく、自分たちが作り上げた「神話」をいかに維持するかにすり替わっていました。
その欺瞞の壁に挑むのが、新聞記者の富塚です。彼はわずかな情報から病院の闇を嗅ぎつけ、真相を追及しようと奔走します。しかし、彼の前には「沈黙の掟」によって固く閉ざされた組織の壁が立ちはだかります。彼の孤独な戦いは、強大な権力の前でジャーナリズムがいかに無力になりうるかをも示していました。
物語の終盤、レシピエントの死期が迫るにつれ、組織的な隠蔽工作はさらに露骨になります。天木のチームの目的は、完全に「ダメージコントロール」へと移行します。個人の命よりも、大学病院という組織の権威と体面を守ることが絶対的な使命となるのです。この描写は、現実の事件で指摘された数々の疑惑と不気味なほどに重なります。
そして、物語は救いのない結末を迎えます。レシピエントは術後83日目に亡くなりますが、その死因は移植の失敗ではなく、「不運な事故」として発表されます。これもまた、現実の事件で行われた説明と全く同じであり、最後まで真実を捻じ曲げようとする組織の醜悪さを見せつけられました。
物語の最後に、登場人物たちが迎えるそれぞれの末路には、一切のカタルシスがありません。天木教授は誰からも責任を問われることなく、その地位に留まります。良心の呵責に苦しんだ大鈴は、医学そのものに絶望します。正義を求めた富塚記者は、真実を暴けぬまま敗北します。この救いのなさが、かえって読者に強烈な印象を残すのです。
結局のところ、この悲劇は天木有作という一人の野心的な医師だけが生み出したものではありません。彼の暴走を止められなかった大学病院のシステム。自浄作用を発揮せず、権威を守るために団結した医学界。そして、当初は批判精神を忘れ、快挙として称賛してしまったメディア。社会の根幹をなす様々な組織が、連鎖的に機能不全に陥った結果でした。
この小説が告発した問題は、決して過去のものではありません。iPS細胞、ゲノム編集と、科学技術は日進月歩で進化し、かつては神の領域とされた生命のあり方さえも問い直そうとしています。そんな現代だからこそ、「科学の進歩と人間の精神的な進歩のギャップ」という、渡辺淳一氏がこの作品に込めたテーマが、より一層重く響いてくるのです。
『心臓移植』は、読む者に深い問いを投げかけ、考え込ませる力を持った作品です。それは時に苦しく、目を背けたくなるような現実を突きつけます。しかし、だからこそ、私たちはこの物語から目を逸らしてはならない。科学と、生命と、そして人間そのものについて考える上で、避けては通れない一冊だと、私は強く感じています。
まとめ
渡辺淳一氏の『心臓移植』は、単なる小説の枠を超え、日本の社会と医療倫理に大きな一石を投じた「事件」とも呼べる作品でした。実際の心臓移植事件をモデルに、その直後に発表されたこの物語は、フィクションでありながら、生々しい告発の書としての側面を持っています。
本文では、物語の詳しい筋道を紹介しつつ、その核心に迫る部分まで踏み込んで考察しました。「日本初」の栄光に憑りつかれた天才外科医、彼の野望の犠牲となるドナーとレシピエント、そして組織の中で葛藤する良心。彼らが織りなすドラマは、読む者の心を強く揺さぶります。
特に、作者の創作である「ダブルハート方式」の意味や、隠蔽されていく真実、そして救いのない結末が問いかけるものは非常に重いものがあります。これは一人の医師の問題ではなく、大学病院、医学界、そしてメディアといった、社会システム全体の機能不全が引き起こした悲劇でした。
科学技術が進化し続ける現代において、生命の尊厳とは何か、私たちは技術とどう向き合うべきか、この物語が突きつける問いは色褪せることがありません。重厚で、時に読むのが辛くなるかもしれませんが、それ以上に得るものが多い、必読の傑作です。