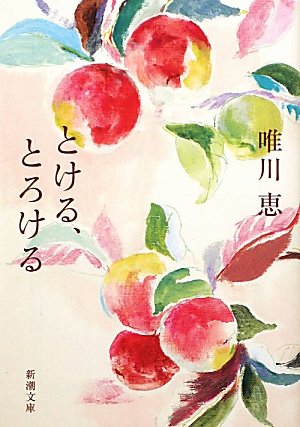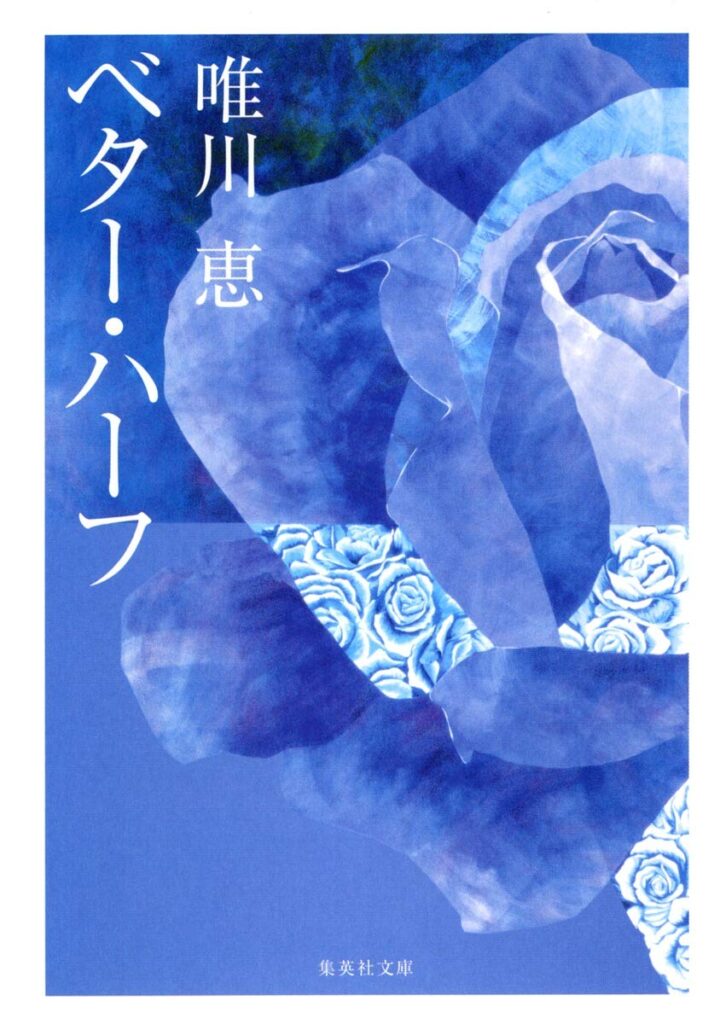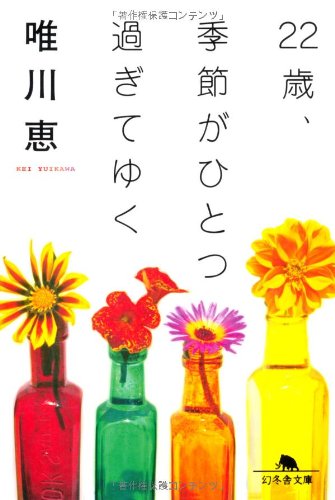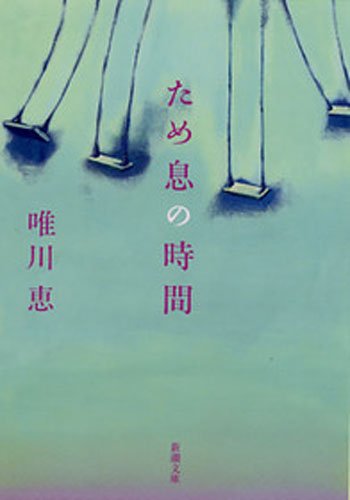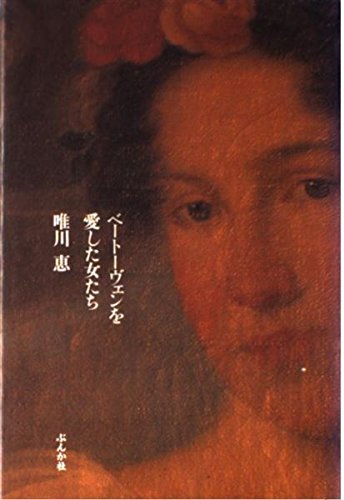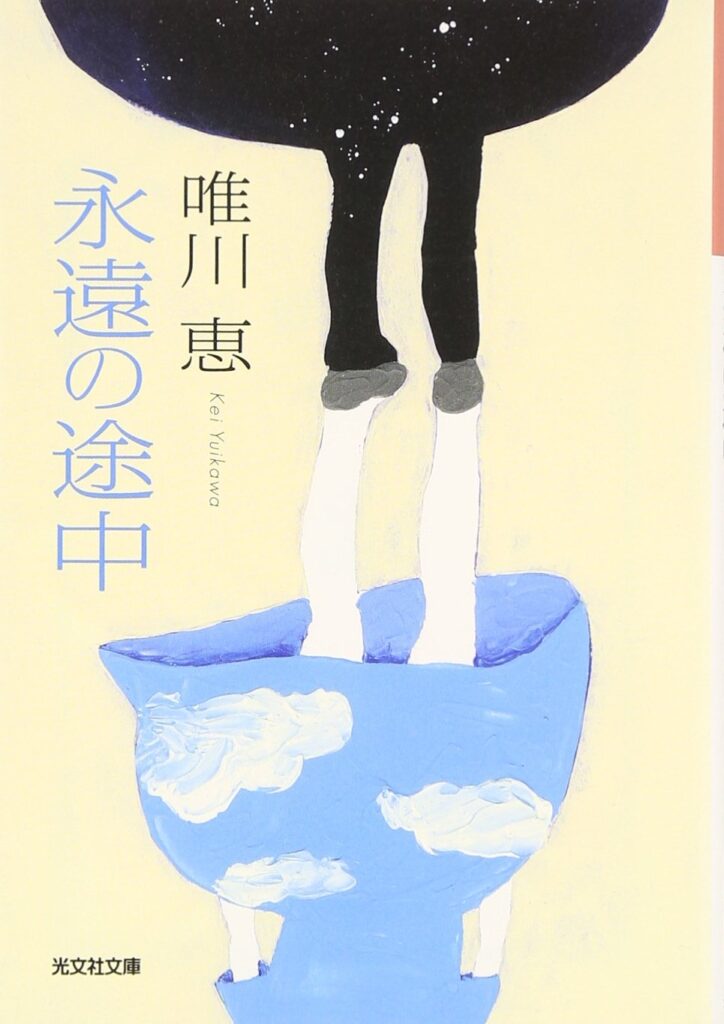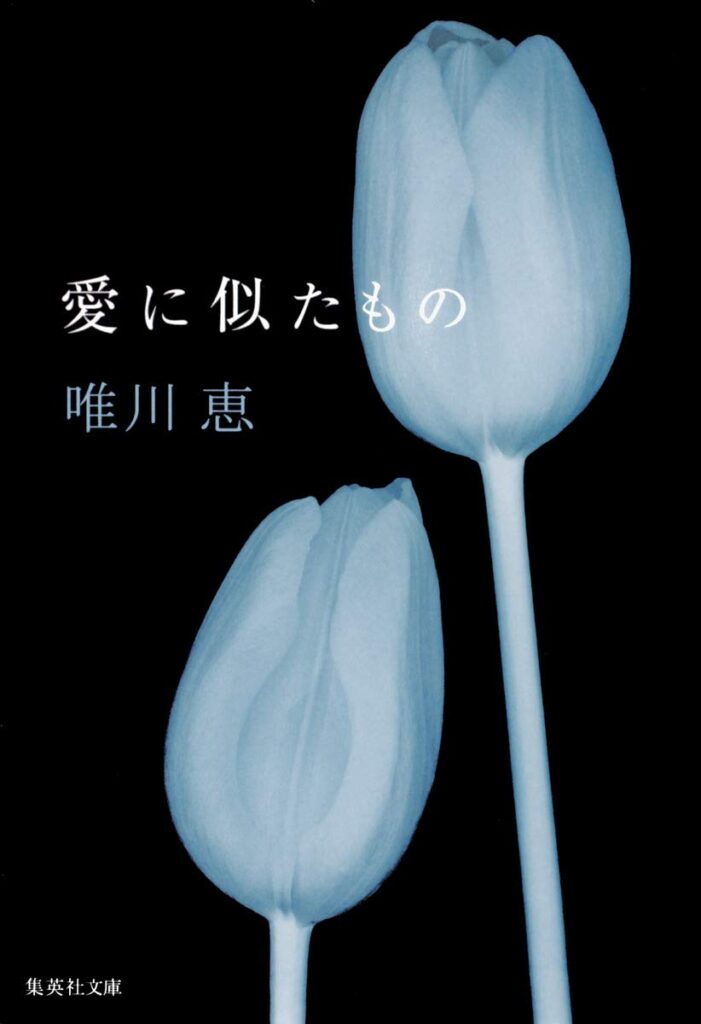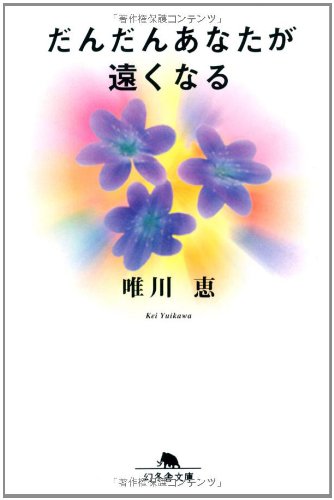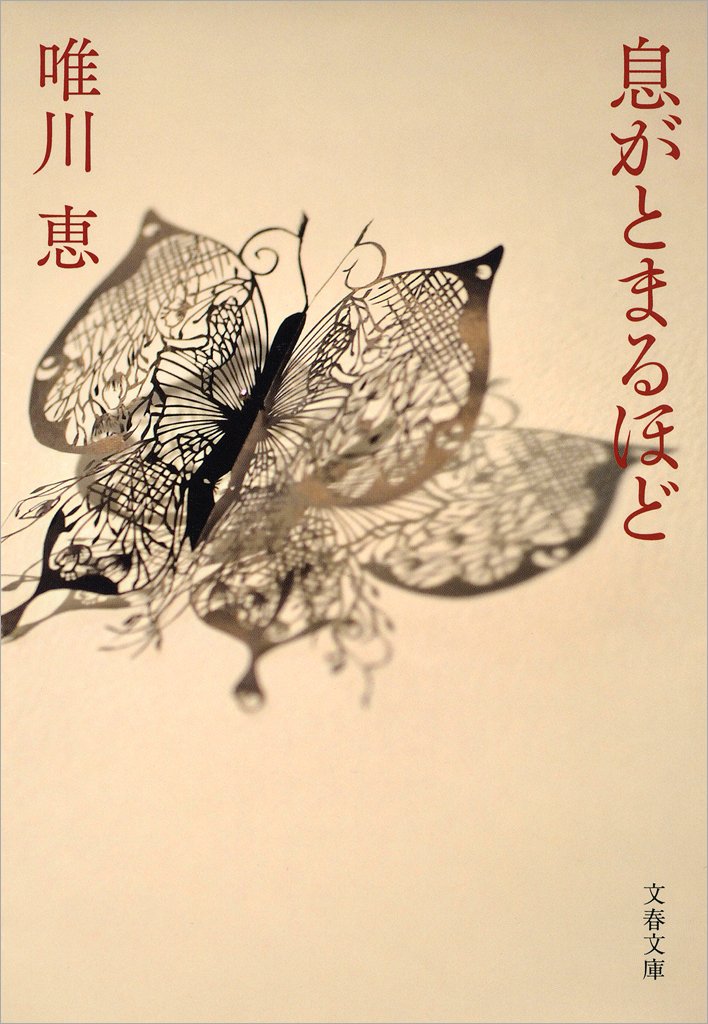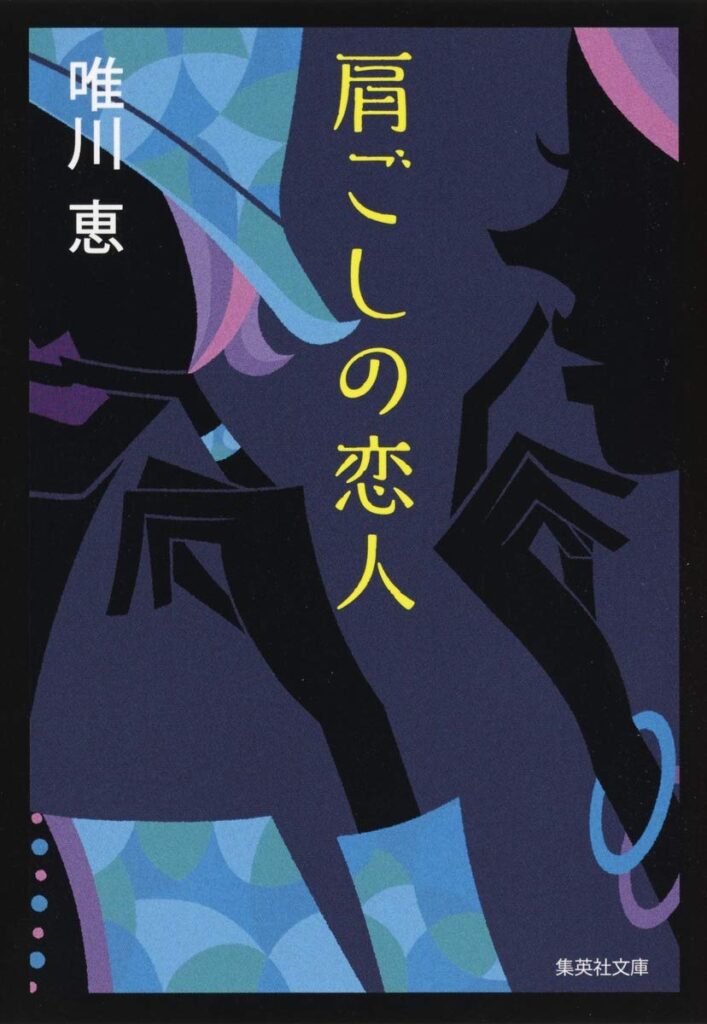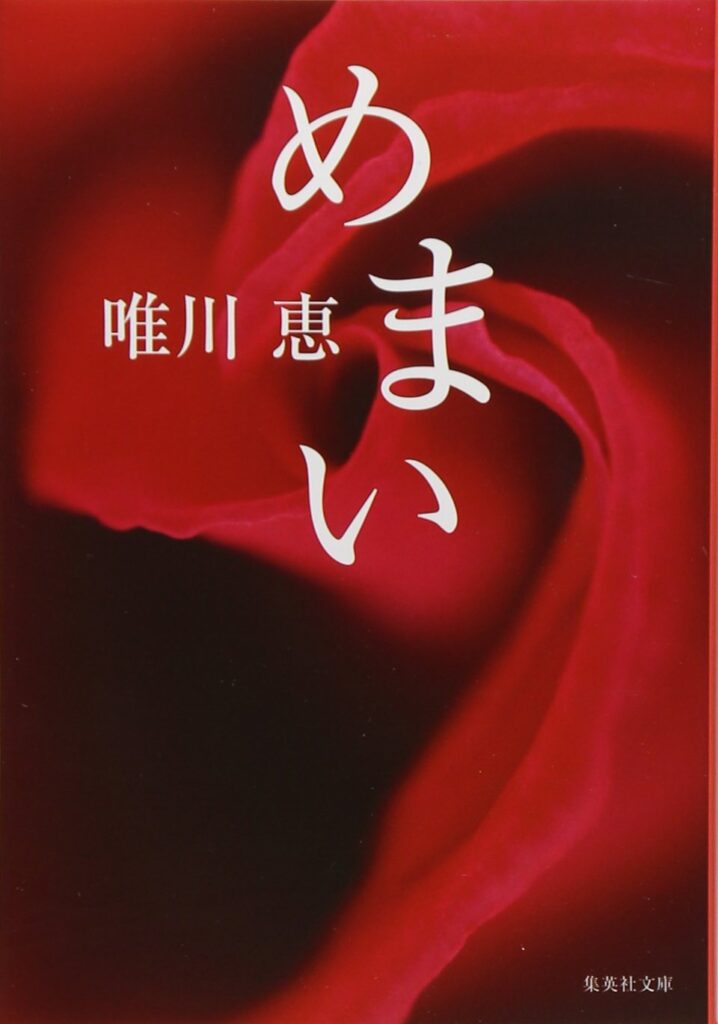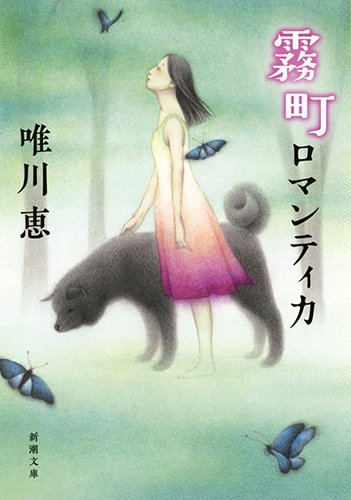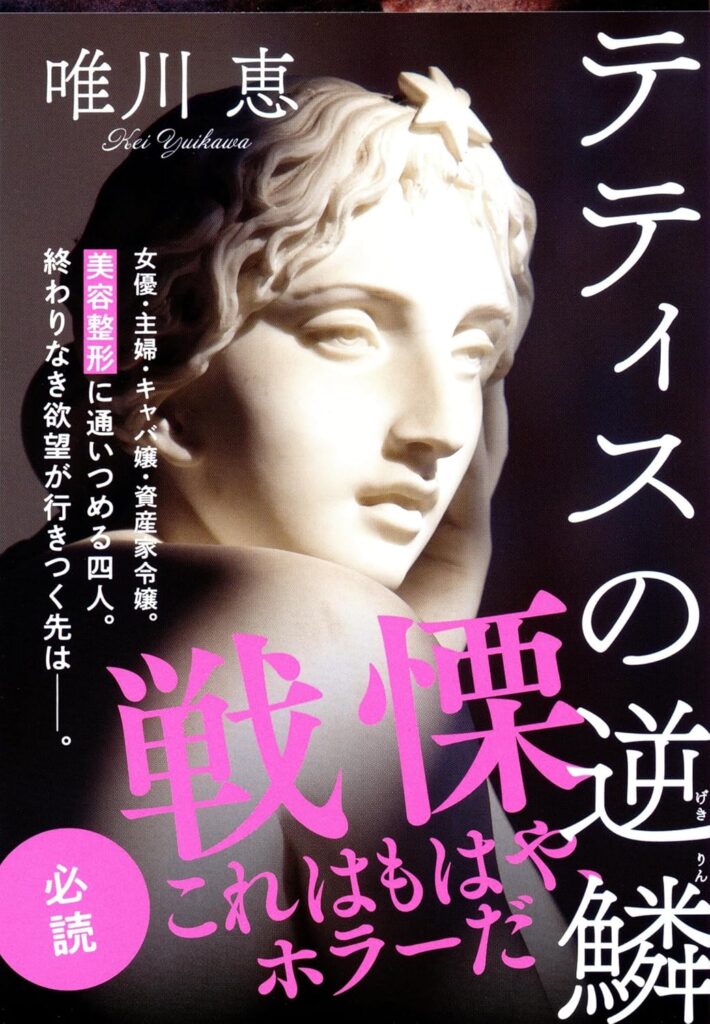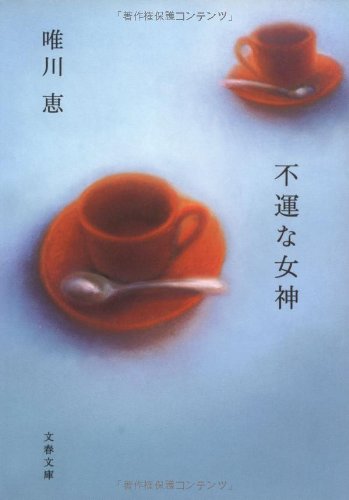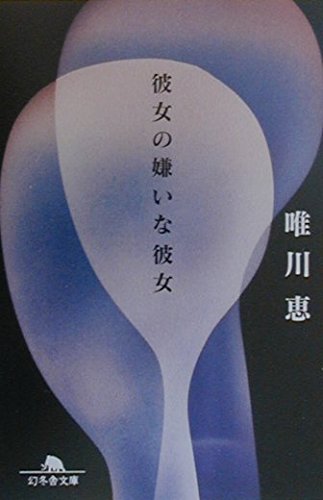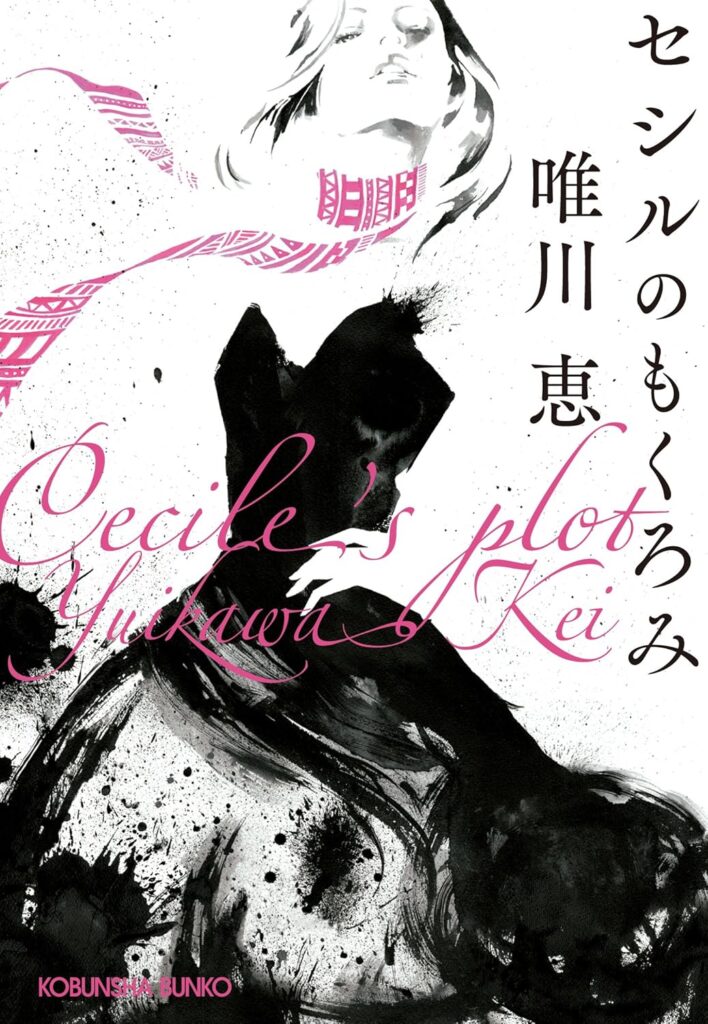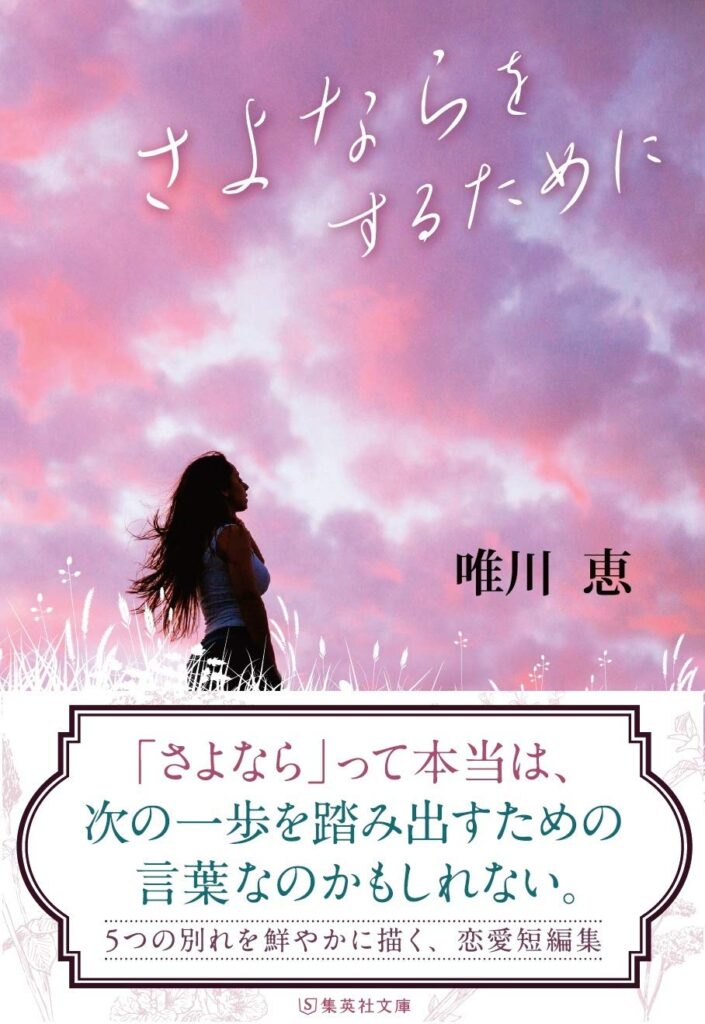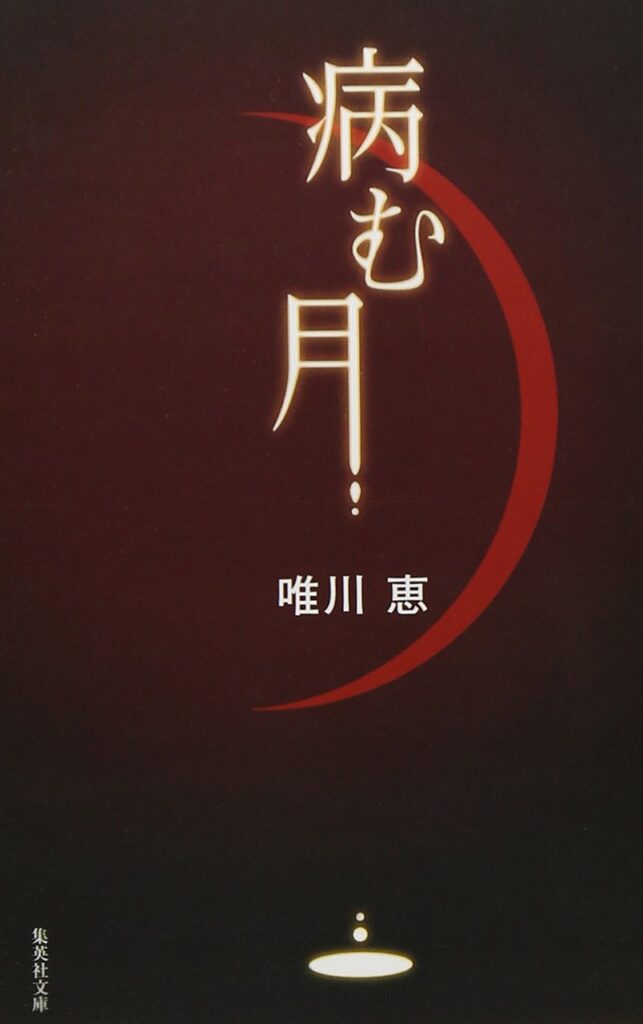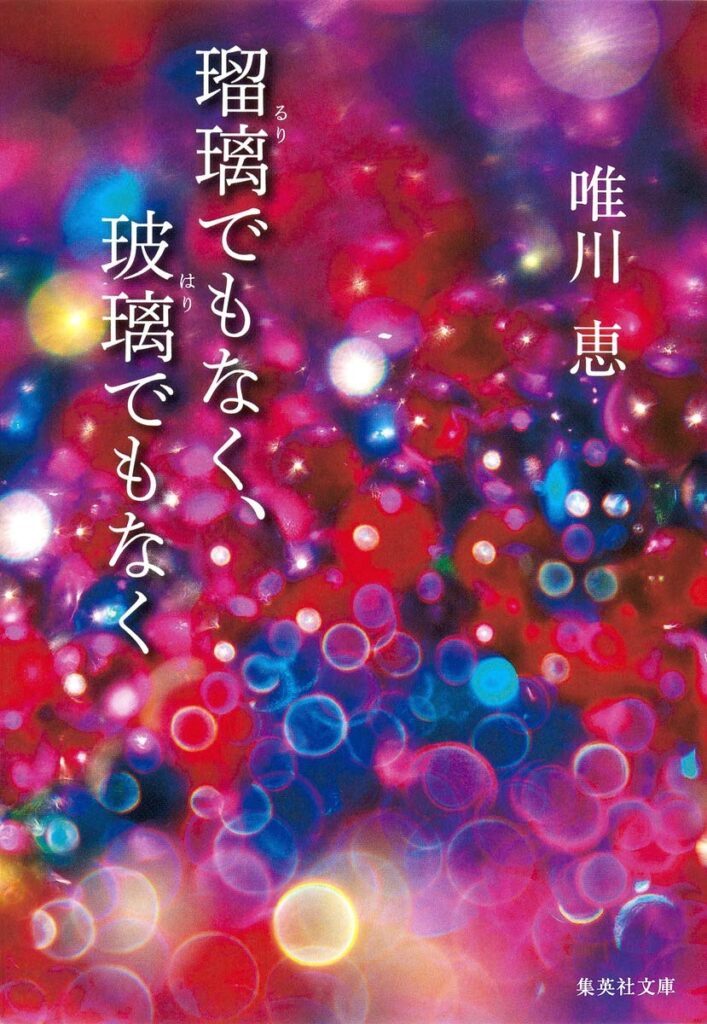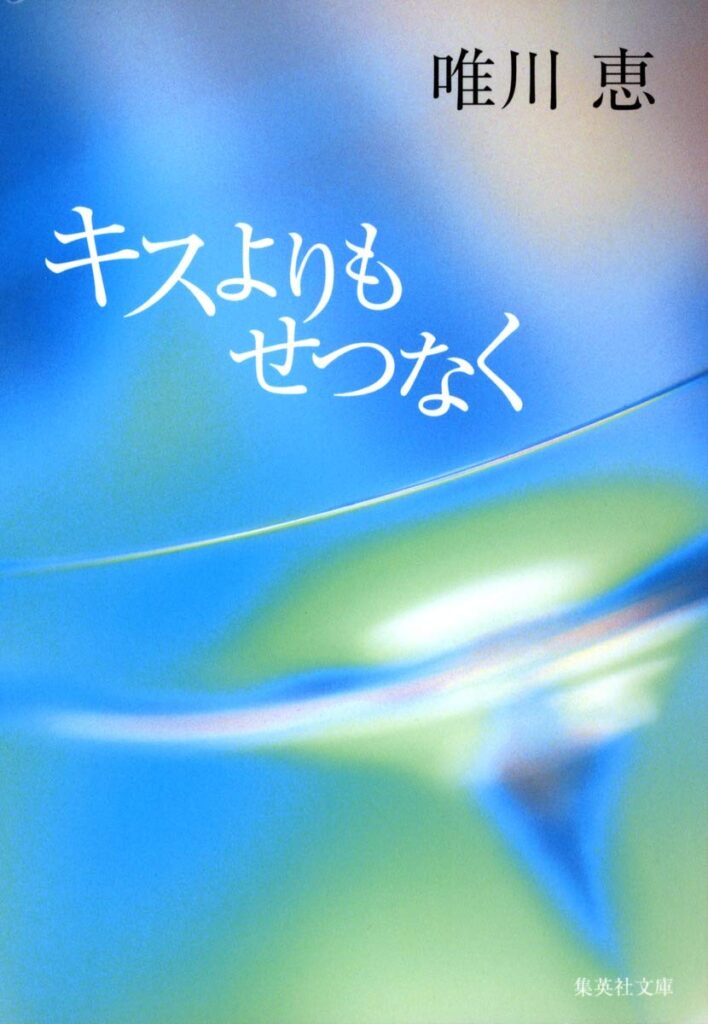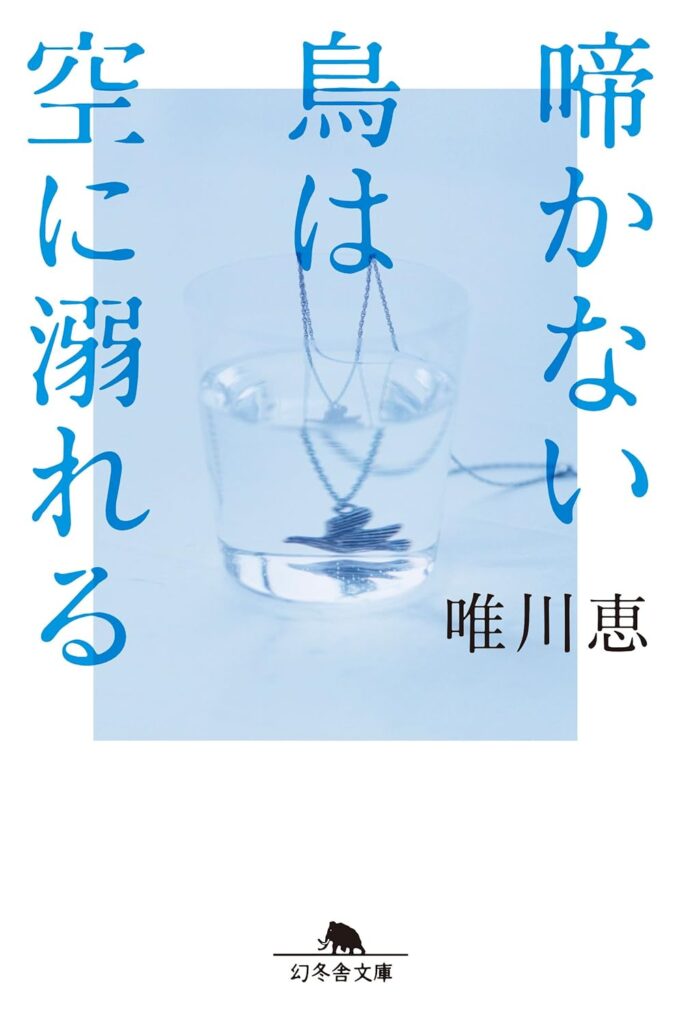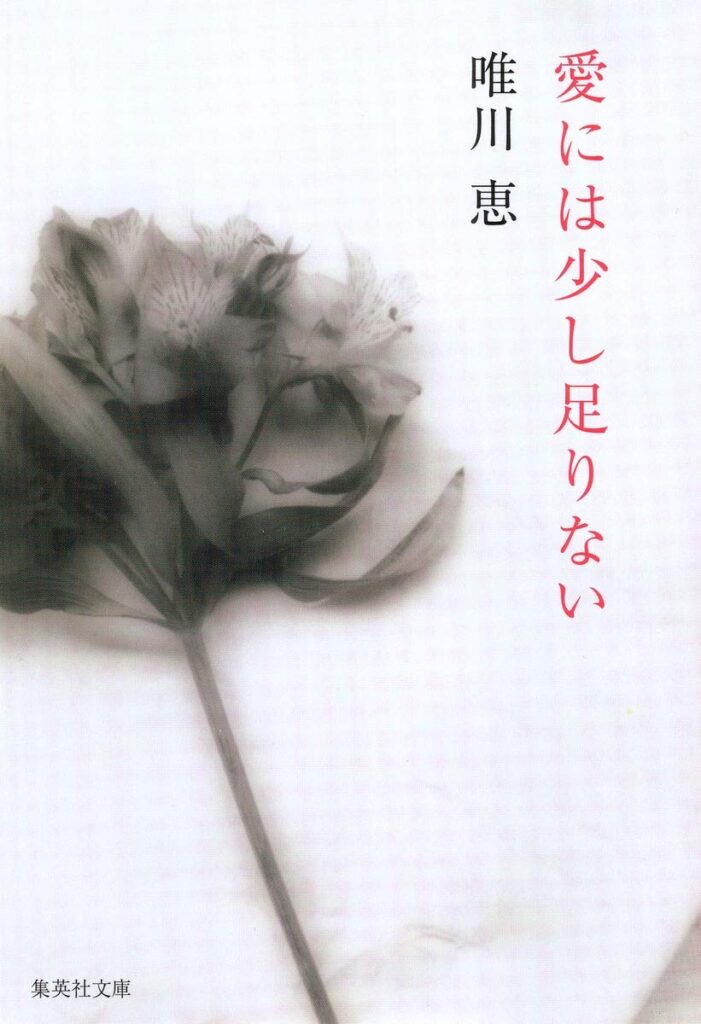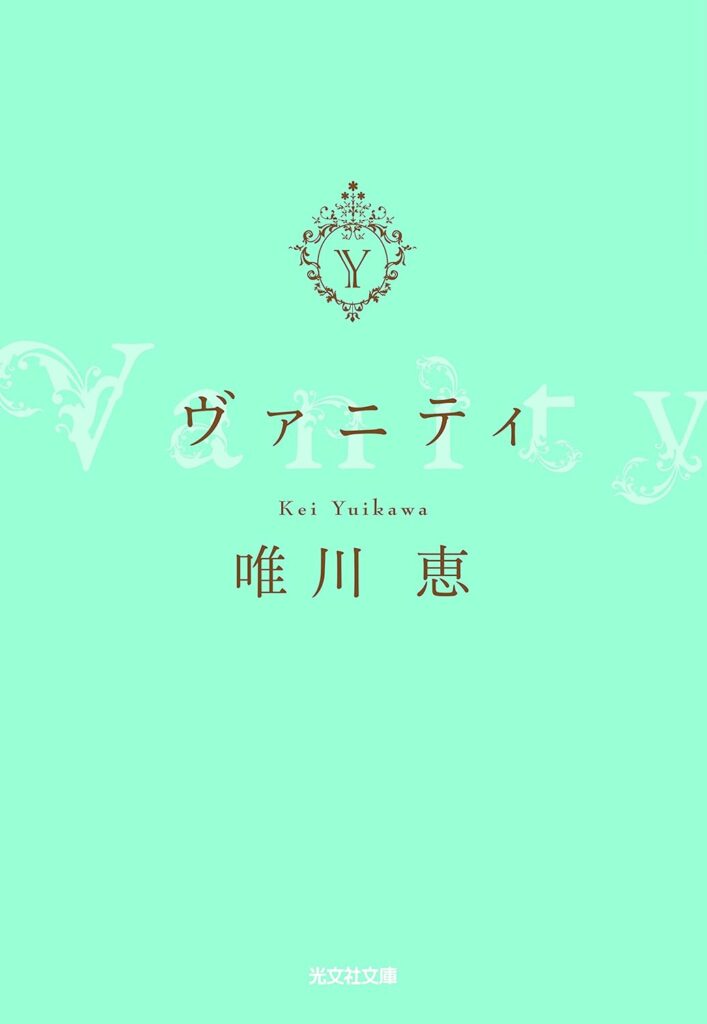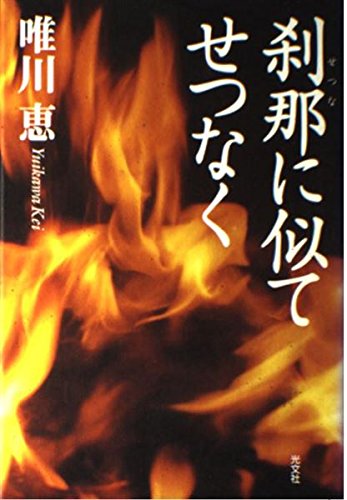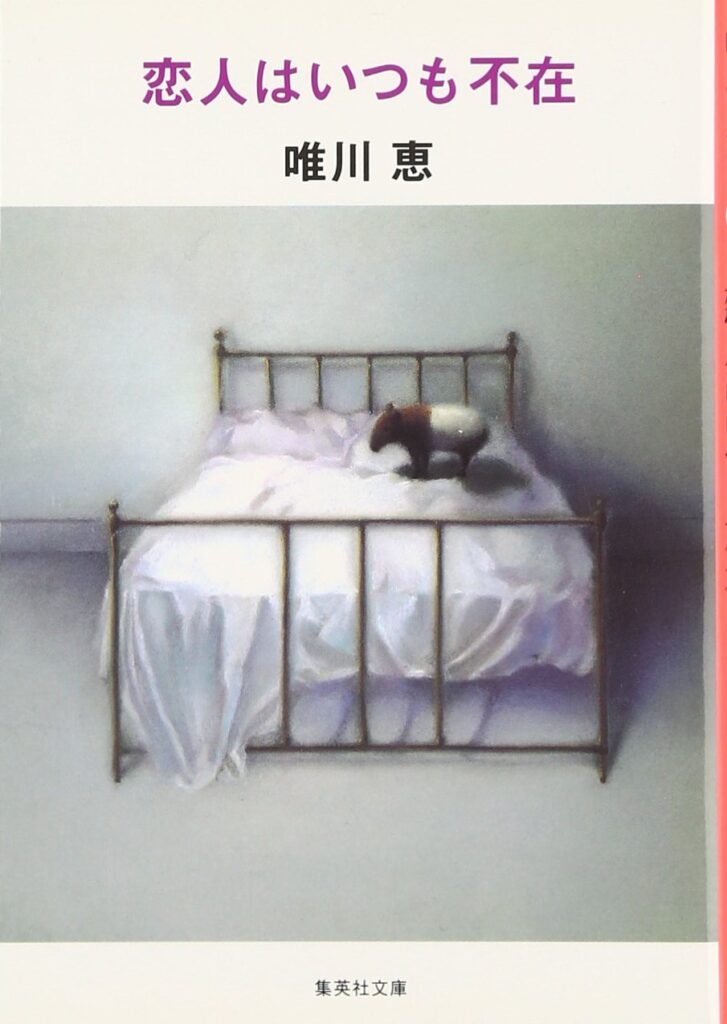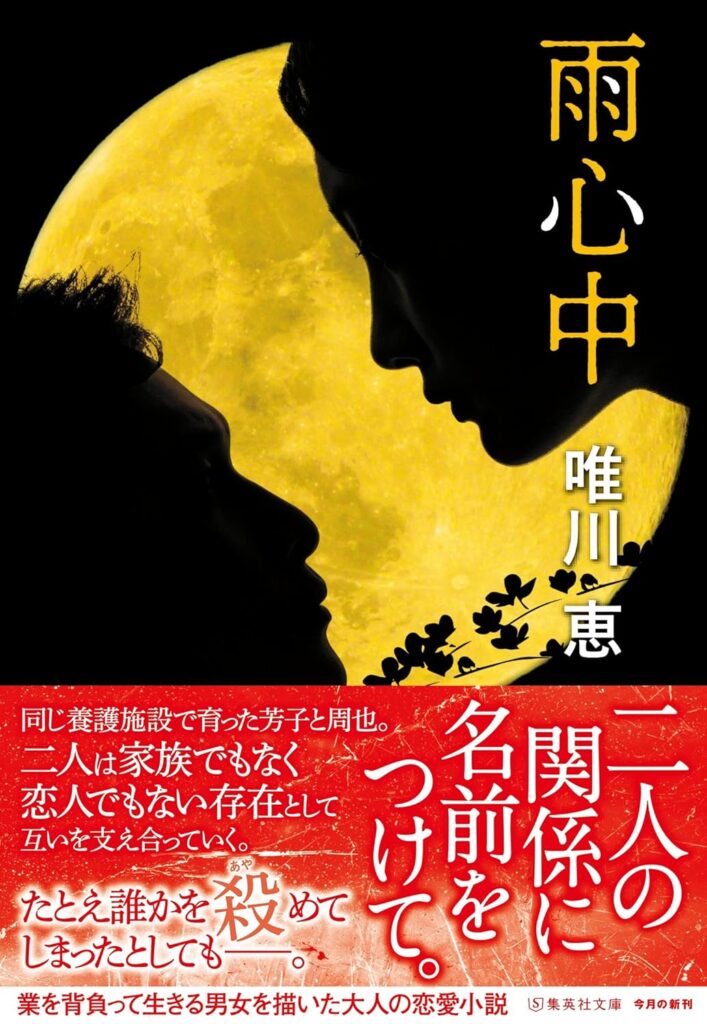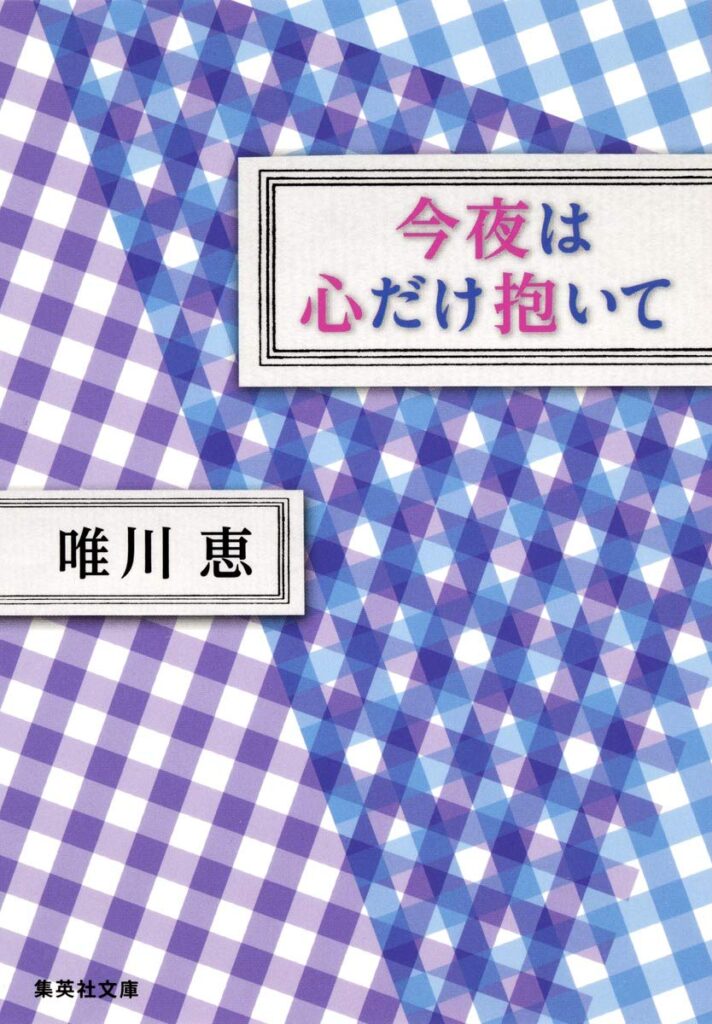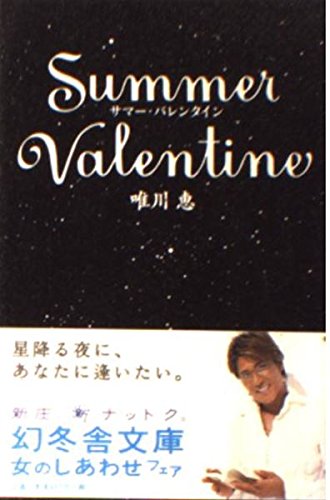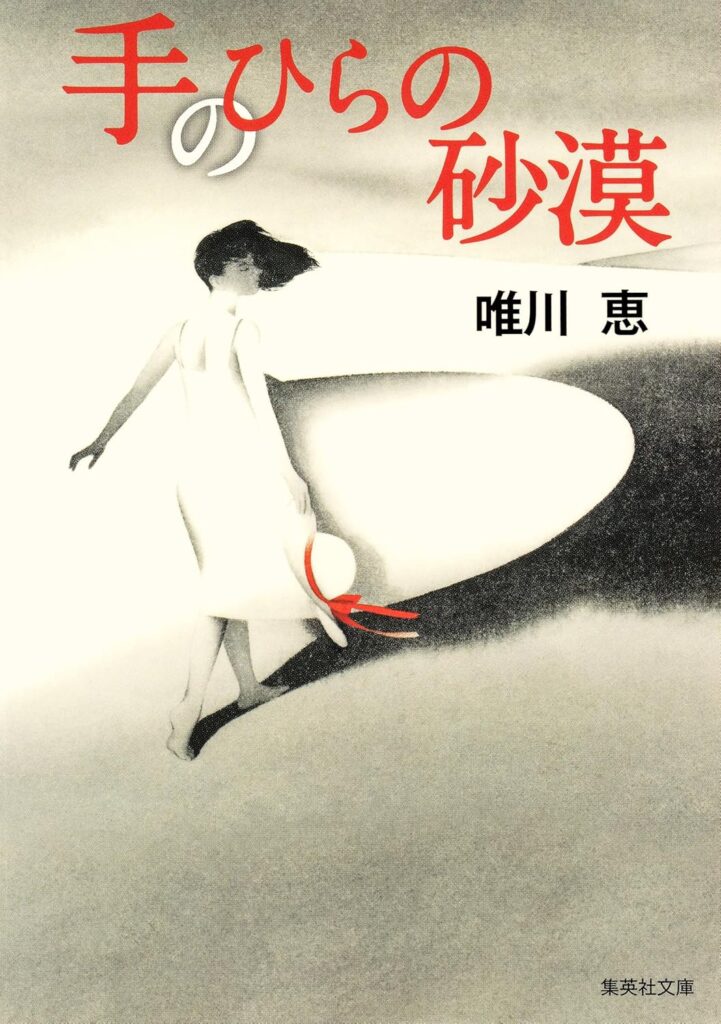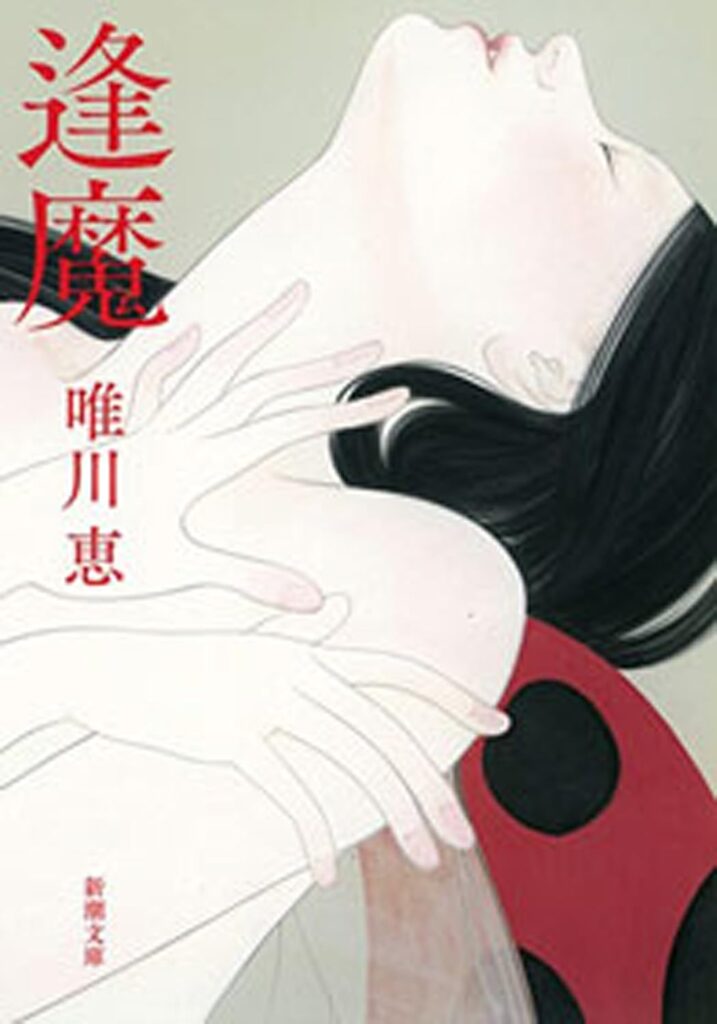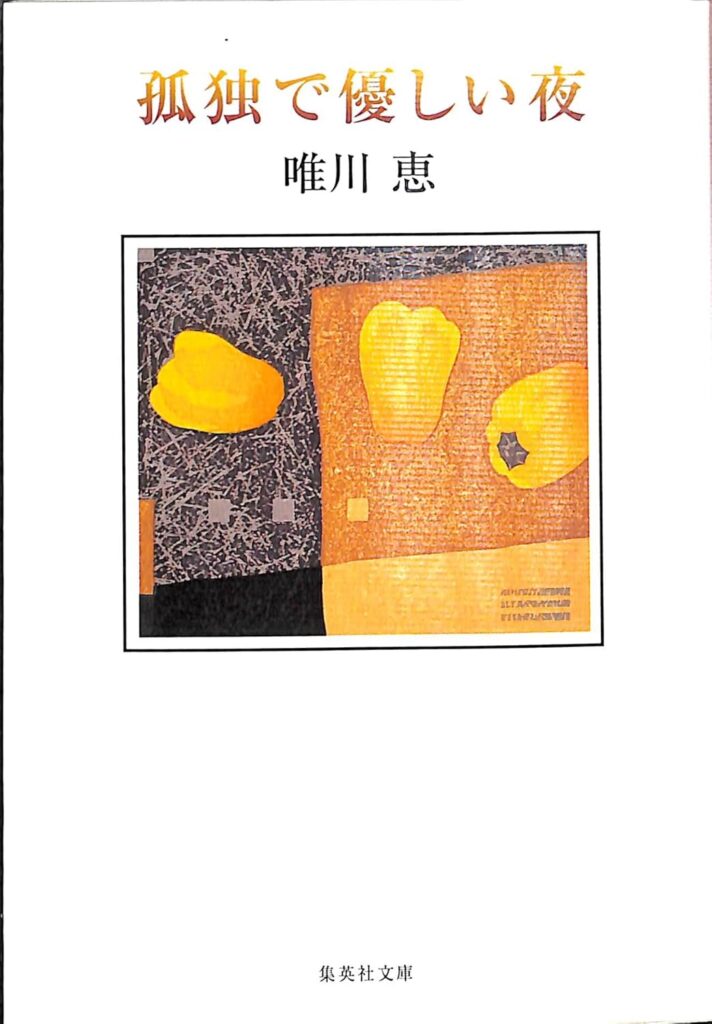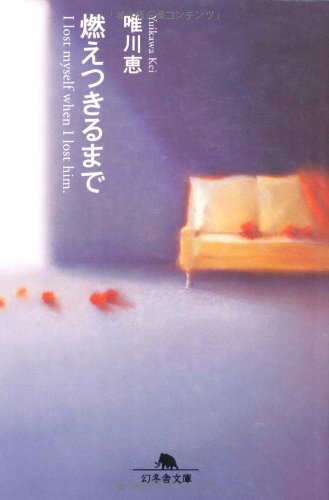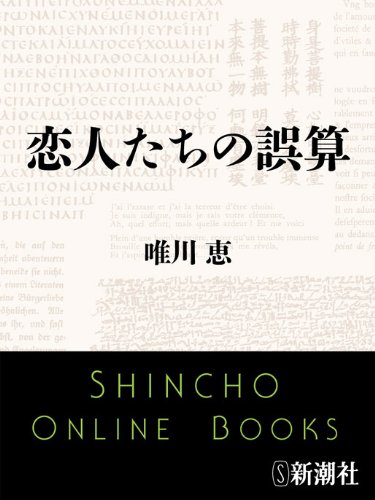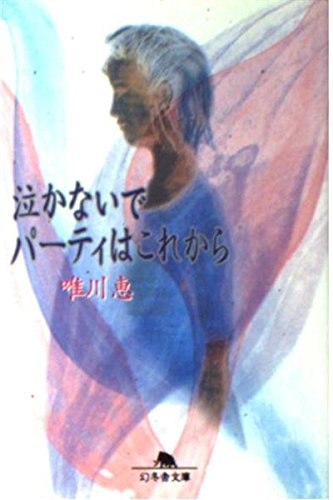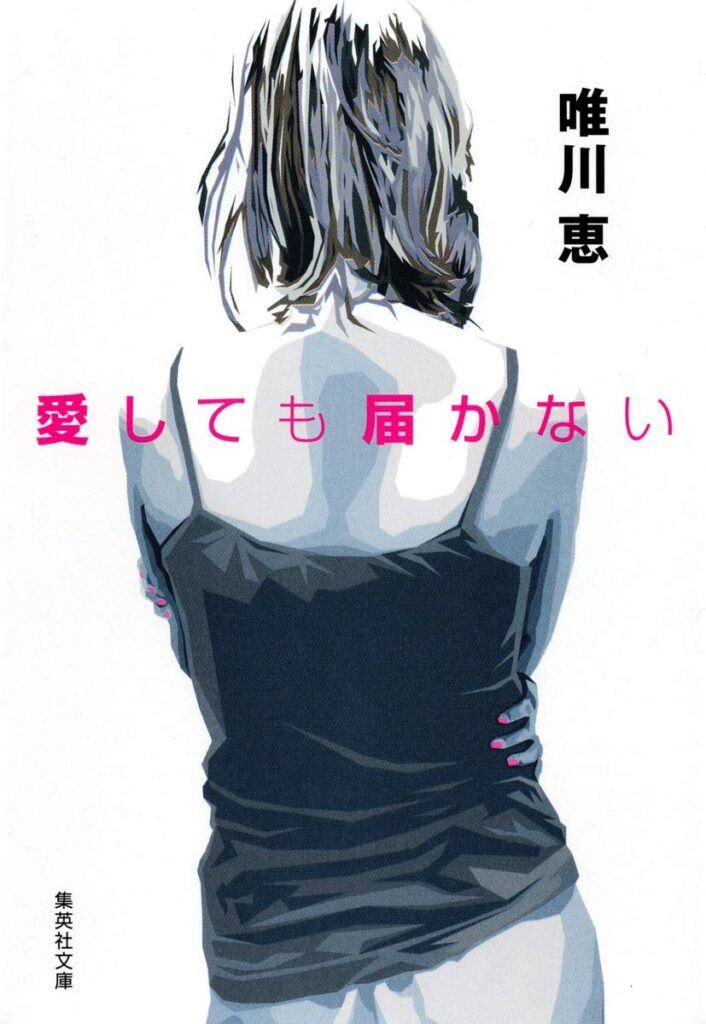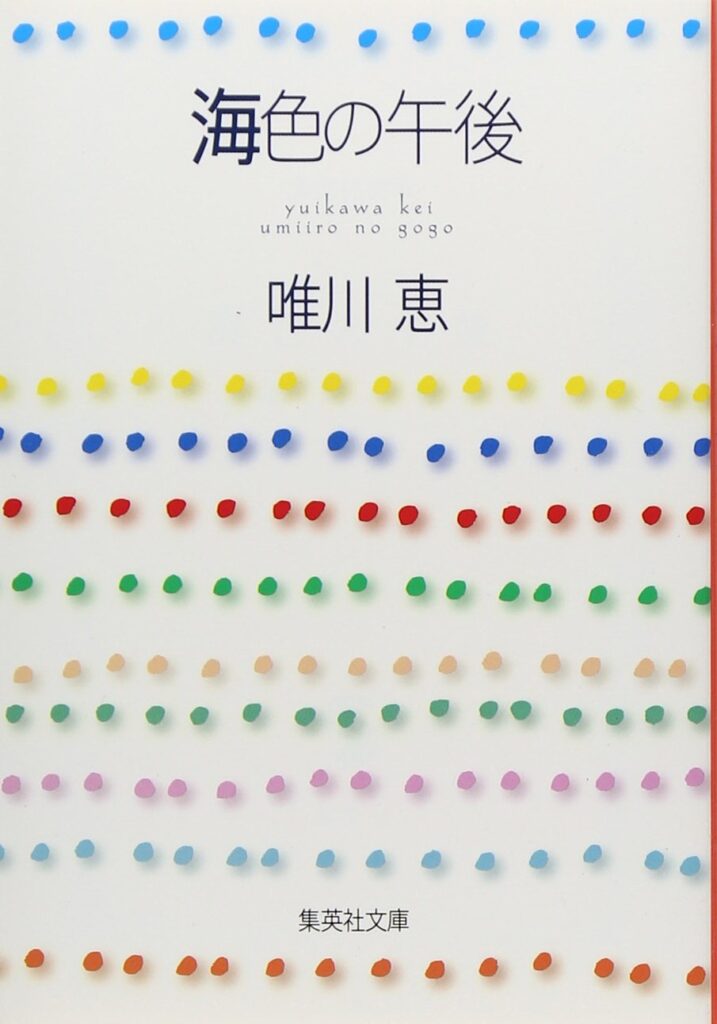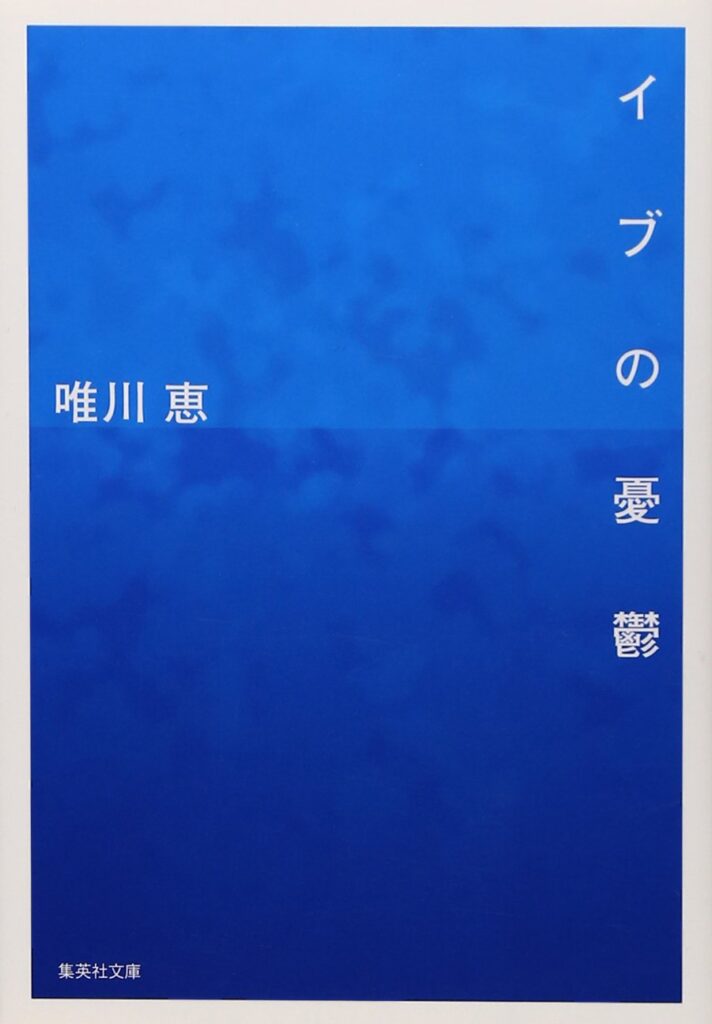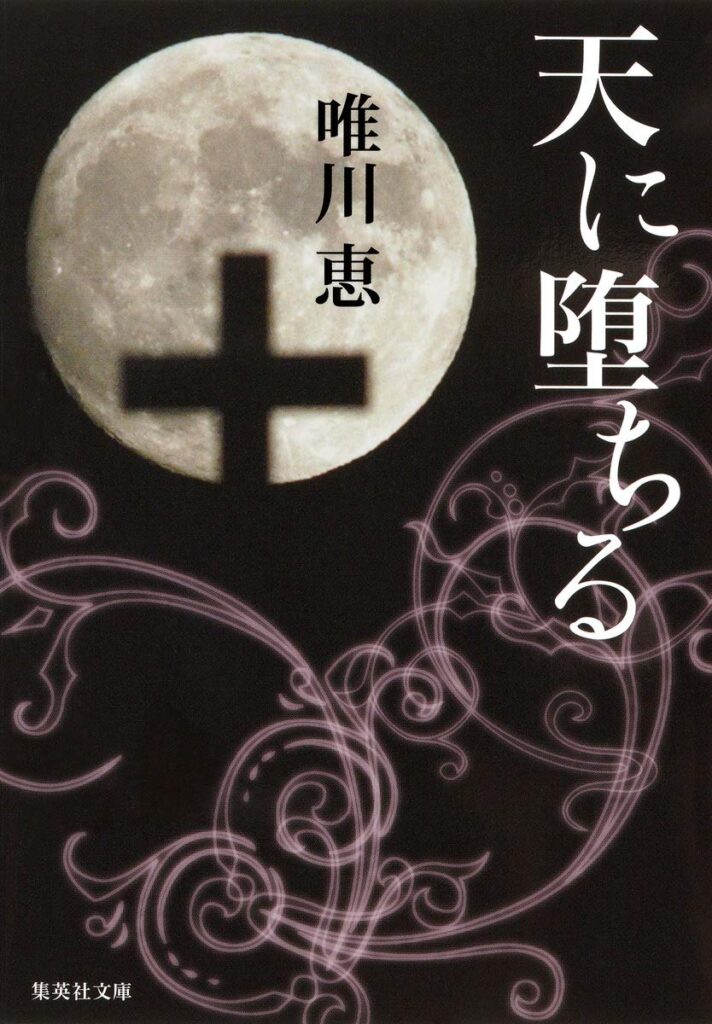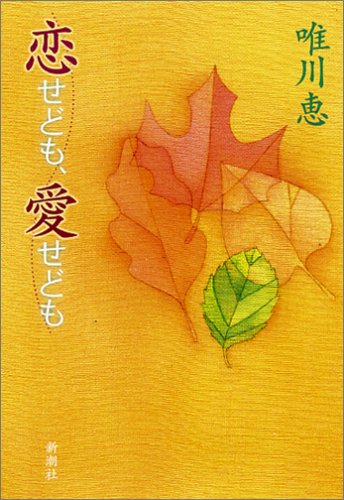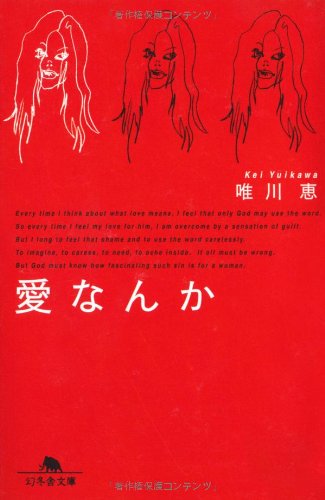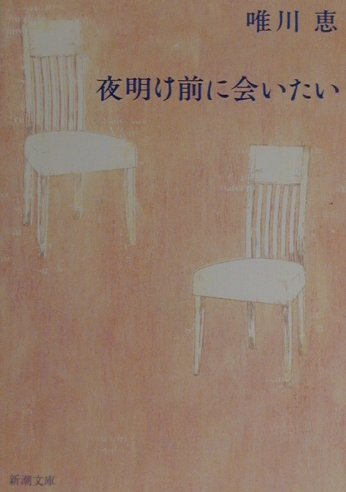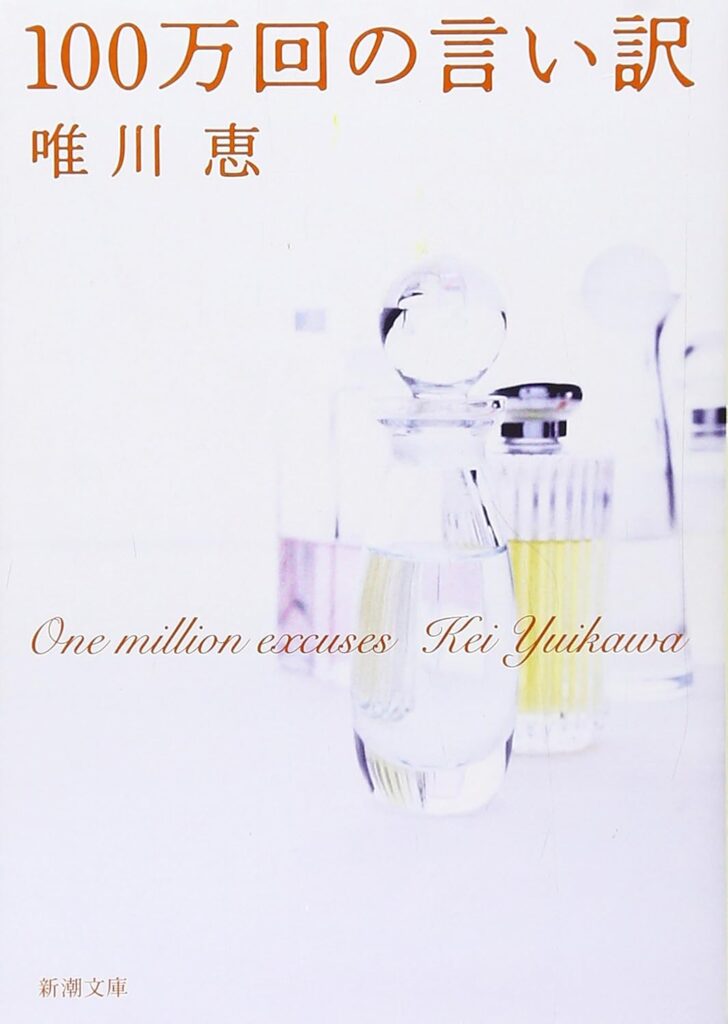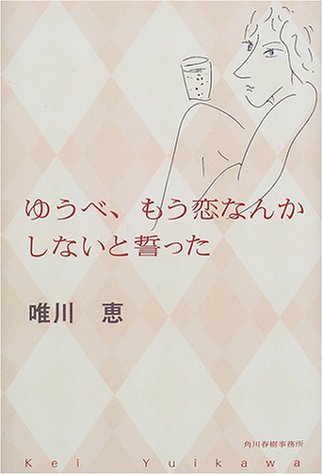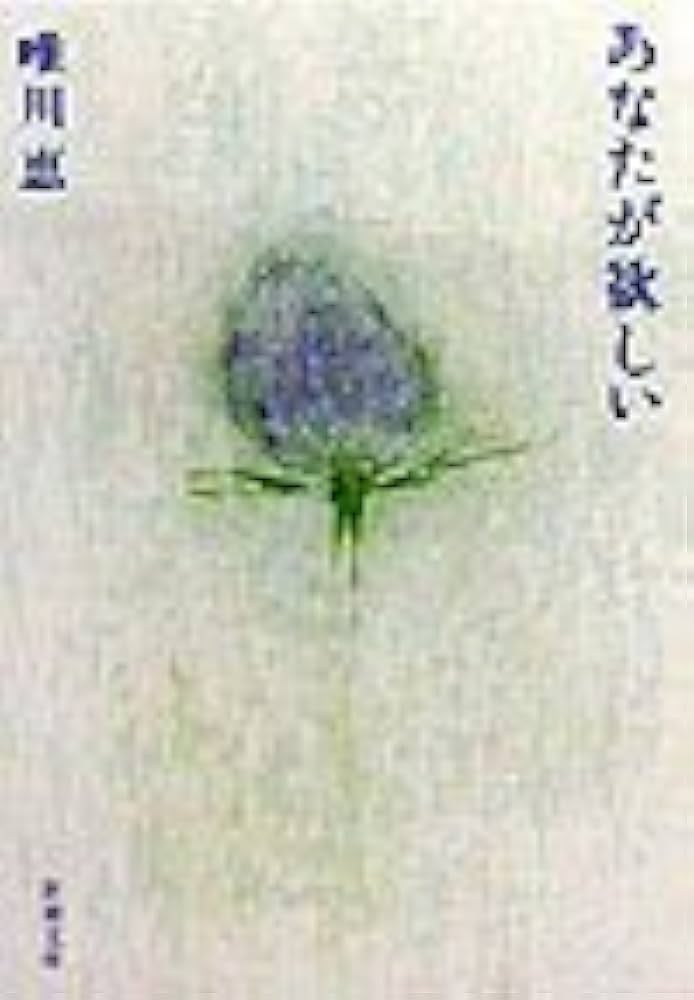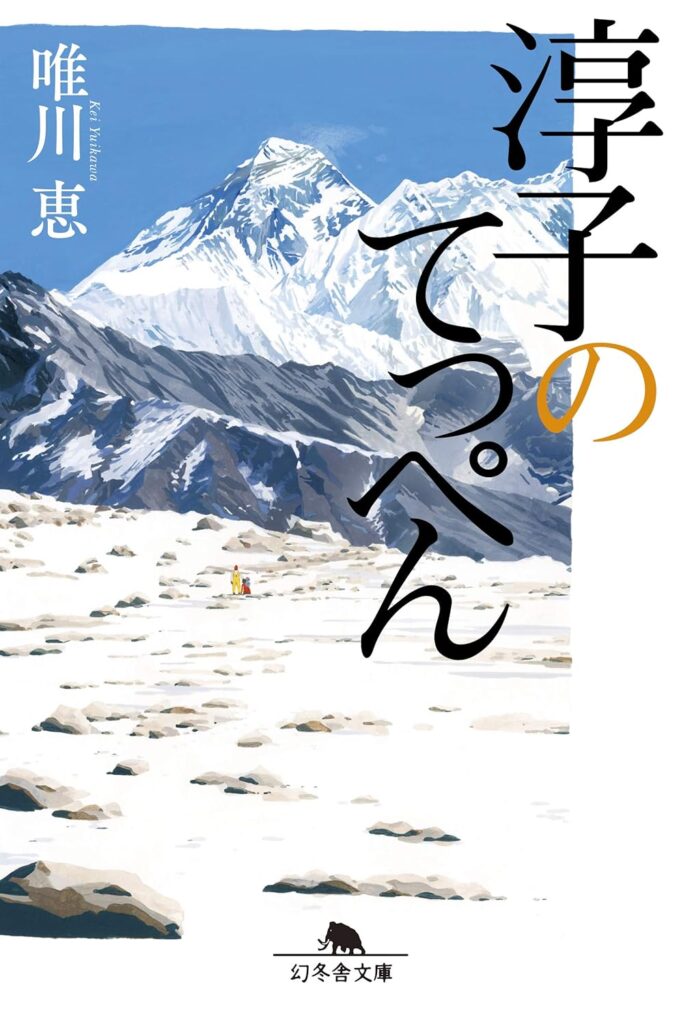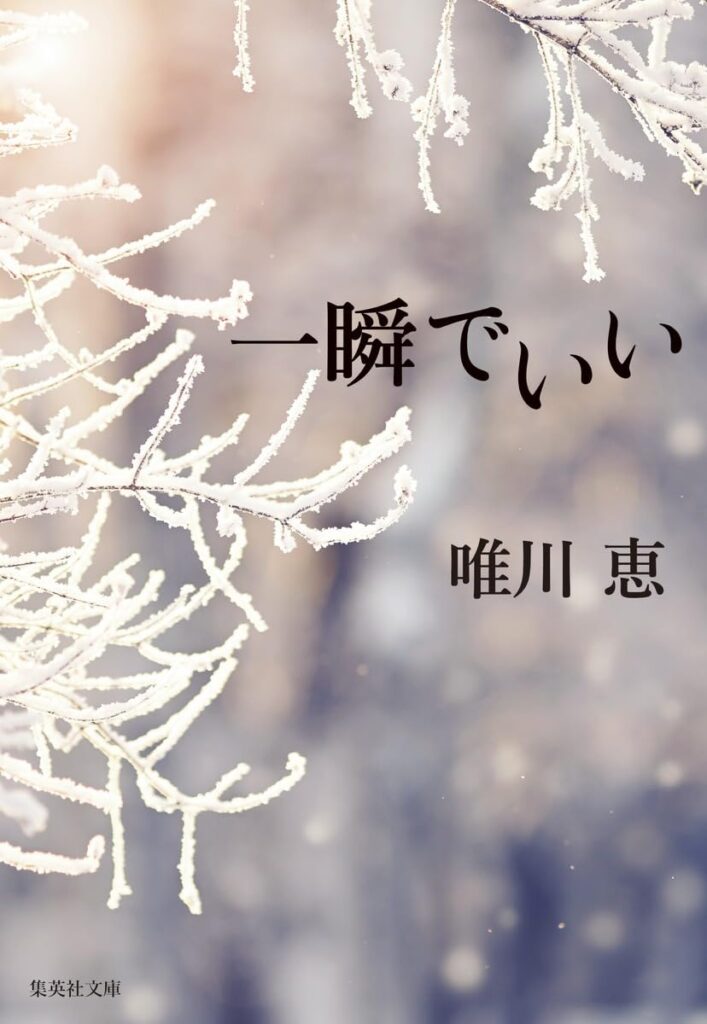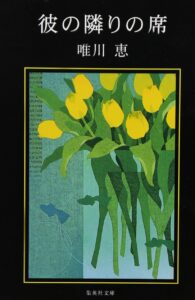 小説『彼の隣りの席』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説『彼の隣りの席』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
唯川恵さんの『彼の隣りの席』は、学生時代の友人との再会をきっかけに展開する恋愛小説です。平凡なOLである主人公が、かつて憧れていた男性と大人になってから再び巡り会う物語で、日常に潜むドラマが静かに描かれます。
本作は、一見するとよくある恋愛のパターンを辿りながらも、その裏に繊細な心理描写と人間関係の機微が光ります。昔からの仲間内で起こる恋の波紋に、読者は懐かしさとハラハラする気持ちを覚えるでしょう。
読み進めるうちに、登場人物たちの揺れ動く感情に引き込まれていきます。もどかしさや切なさを感じつつも、自分自身の青春時代や過去の恋愛を重ねてしまい、物語に引き込まれることでしょう。
小説『彼の隣りの席』のあらすじ
主人公の芽以子(めいこ)は平凡なOLで、25歳になった今も特に波風のない日常を過ごしています。ある日、親友の佳苗(かなえ)の婚約パーティーに出席した芽以子は、学生時代から憧れていた同級生の彰生(あきお)と再会します。彰生は佳苗の元恋人でもあり、小説家を志していた才能ある男性です。久しぶりに目の前に現れた彼は相変わらず自信に満ちた雰囲気で、芽以子に笑顔で話しかけてきました。
パーティー後、彰生は芽以子に連絡をくれて、二人は食事に出かける仲になります。遠い存在だった憧れの彼が自分に興味を持ってくれたことに戸惑いながらも、芽以子の心はときめきを抑えられません。彰生はわがままで子供っぽい言動もしますが、ふと見せる優しさや夢を語る真剣な横顔に、芽以子はますます惹かれていきます。
しかし、彰生の存在は芽以子の心だけでなく周囲の人間関係にも影響を及ぼし始めます。婚約者のいる佳苗は、親友である芽以子と元恋人の彰生が親しくなることに複雑な思いを抱きます。佳苗は表向きは芽以子を応援しつつも、内心では動揺を隠せません。かつての恋人を巡って、大切な友人同士の間に微妙な緊張が生まれてしまうのです。
やがて物語は後半に入り、登場人物たちの想いがぶつかり合う展開へと突き進みます。ある出来事をきっかけに佳苗と彰生が言い争う場面があり、佳苗の婚約者までも巻き込んだ騒動に発展します。
一方で芽以子も、彰生の気まぐれな振る舞いに何度も振り回され傷ついていきます。それでも彼を嫌いになれない自分に戸惑い、芽以子は悩み苦しみます。
最終的に、芽以子は苦渋の末にある決断を下します。自分自身と周囲の幸せを見つめ直した彼女は、彰生との関係にけじめをつける道を選びました。平凡だけれど確かな安心感のある日常へと歩み出すことで、芽以子はもう一度自分の人生を取り戻していきます。物語の結末は静かに描かれ、読後には切なさとともに温かな余韻が残るでしょう。
小説『彼の隣りの席』の長文感想(ネタバレあり)
『彼の隣りの席』を読み始めてまず感じたのは、物語の入り口がとても身近で現実味があるということです。親友の婚約パーティーで昔の仲間たちと再会するというシチュエーションは、ありそうでいて特別な高揚感があります。学生時代に憧れていた男性と大人になって再会する芽以子の姿に、自分だったらどうだろうと想像が膨らみ、読み手として一気に引き込まれました。本作は1990年代に発表された作品ですが、当時はまだ携帯電話が普及しておらず、芽以子が家の電話にかかってきた彰生からの連絡に胸を高鳴らせる描写には時代を感じつつも、その分彼からの電話を待つドキドキ感が伝わってきて、かえって新鮮でした。
再会の場面では、佳苗の婚約パーティーというおめでたい席にも関わらず、どこか張りつめた空気を感じました。佳苗が元恋人の彰生と対面したときの微妙な表情や、芽以子が憧れの人を前に胸を高鳴らせながらも遠慮がちに会話する様子が目に浮かぶようでした。佳苗の婚約者は二人の過去の関係を知らないのかもしれませんが、読者としてはその場に流れる気まずさをはっきりと感じ取ることができます。冒頭から、人間関係の機微によって祝宴の場に影が差す描写に引き込まれ、これから何かが起こる予感にドキドキしました。
物語が進むにつれ、芽以子と彰生の距離が急速に縮まっていく展開に胸が高鳴りました。ずっと憧れていた相手から連絡が来て二人きりで食事に行く――そんな夢のような展開に、読んでいるこちらまで一緒に舞い上がるような気持ちになりました。芽以子が「まさか彼が私に…」と戸惑いつつも心を躍らせる心情描写は丁寧で、共感しやすかったです。平凡なOLである自分に自信家の彰生が興味を示してくれるなんて信じられない、という芽以子の喜びと戸惑いが痛いほど伝わってきました。例えば、初めて彰生から下の名前で呼ばれたときや、別れ際に不意に手を握られたときなど、芽以子の心臓が飛び出しそうなほど高鳴っているのがこちらにも伝わってきます。思わず頬が紅潮するような甘い瞬間の連続で、芽以子と一緒に恋の浮かれた空気を味わいました。
一方で、彰生の人物像には序盤から不穏な影も見えていました。彼は才能があり魅力的ですが、同時に自己中心的で子供っぽいところがあります。デートの約束をしても突然自分の都合で予定を変えたり、芽以子の相談事を「そんな暗い話は聞きたくない」と軽くあしらったりする場面もありました。私はその描写に、思わず眉をひそめつつも「こういう勝手な男性、現実にもいるな」と感じてしまいました。嫌なことは話して共有したい女性と、嫌なことは聞きたくないという男性のすれ違いがリアルで、著者の描写力に唸らされます。それでも芽以子は彰生と一緒にいられる嬉しさの方が勝ってしまい、小さな不満には目をつぶってしまうのです。このあたりの心理描写は生々しいほど現実的で、読みながら胸が痛くなりました。
彰生にも実は脆い一面があります。小説家を目指す彼は、自分の才能に絶対の自信を持っているように振る舞っていますが、内心では焦りや不安も抱えているように感じました。思うように作品が評価されない苛立ちをぽろりと漏らす場面では、普段の強気な彼が一瞬弱気になり、その表情はまるで自信をなくした少年のようでした。そんな彰生の姿を見てしまえば、芽以子が「私が支えなきゃ」と思ってしまうのも無理はありません。彼の弱さを知るからこそ、芽以子はますます彼に惹かれていったのだと思います。読者である私も、勝手だと分かっていながら時折見せる彰生の寂しげな横顔にはどこか憐れみを感じてしまい、完全には嫌いになれませんでした。
芽以子自身も、佳苗に対して少なからず後ろめたさを抱えています。それでも、一度燃え上がった恋心は自分ではどうすることもできない──そんな葛藤が彼女の胸には渦巻いていました。親友を傷つけたくない気持ちと、憧れの人への想いとの板挟みになり、芽以子が一人で思い悩む場面も印象に残っています。彼女は佳苗に「大丈夫」と笑顔を見せつつ、その陰で不安と罪悪感に揺れているのです。読者としては、「こんな恋はやめておいた方がいい」と忠告したくなる半面、そのどうしようもない気持ちにも共感してしまい、もどかしい気持ちでページをめくりました。
芽以子は次第に彰生との時間を最優先し、週末のほとんどを彼の部屋で過ごすようになりました。まるで新婚夫婦のような甘い同棲生活に、彼女は浸っていきます。二人で料理をしたりテレビを観たりといった何気ない共同生活に、芽以子は小さな幸せを感じます。しかし、佳苗は親友として表面上は芽以子の恋を応援しようとしますが、やはり心中は穏やかではいられませんでした。本当は佳苗自身、彰生への未練を少なからず残していたのかもしれませんが、彼女はそれを認めまいと自分に言い聞かせているようにも見えました。かつて自分が深く愛した男性が親友に優しく微笑むのを目にして、複雑な思いを抱える佳苗の気持ちは想像に難くありません。物語の中でも、佳苗が芽以子に「本当に大丈夫?」「彼に振り回されてない?」とそれとなく釘を刺すような場面が描かれていました。芽以子は「心配しすぎだよ」と笑ってみせるものの、佳苗の言葉にはどこか棘があり、会話の端々から二人の間に微妙な溝ができていくのを感じます。長年の友情にヒビが入っていく過程がとても切なく、読んでいて胸が痛みました。
さらに印象的だったのは、中盤以降で描かれる女性同士の友情の亀裂と緊張感です。恋に夢中な芽以子の変化は職場にも表れていました。芽以子の職場では、彼女が男性社員と親しげに話しているのを見た別の女性社員が嫉妬し、冷たく当たるようになるという小さなトラブルも起こります。そのエピソードは佳苗との関係に重なるように感じられ、人間関係の難しさを際立たせていました。会社での場面でも、女性の同僚同士が男性社員を巡って噂話をしたり牽制し合ったりする描写があり、「やはり人間関係にヒビが入る原因は男絡みなんだな」と考えさせられました。作者は職場での何気ない人間関係の軋みを通して、恋愛が女性同士の友情に与える影響を巧みに描いていたように思います。元OLでもある唯川恵さんならではのリアリティが随所に光っていました。また、芽以子の周囲には、不倫の恋に踏み込んでしまった女性や、将来が見えない同棲生活に不安を抱える女性も登場し、それぞれが不安定な愛に揺れていました。そうした脇役たちのエピソードも物語に厚みを加え、様々な形の愛の難しさを浮き彫りにしていたように思います。
物語の後半、ついに佳苗・彰生・芽以子の三人がぶつかるクライマックスが訪れます。特に忘れられないのは、佳苗が感情を爆発させるシーンです。ある集まりの席で、佳苗が抑えていた思いをついに彰生にぶつけ、「いい加減にして!」「芽以子をこれ以上振り回さないで」と声を震わせながら訴える場面にはハラハラしました。その場に居合わせた佳苗の婚約者も、彼女の激しい剣幕に戸惑い、場が一瞬で凍り付くような緊張感が生まれます。彰生は最初こそ余裕ぶった態度でしたが、佳苗の本気の怒りに気圧されたのか言葉に詰まり、しまいにはその場から逃げるように立ち去ってしまいました。このとき彰生が真っ先に逃げ出した姿には、彼の弱さと身勝手さが象徴されているようで印象的です。この修羅場的な場面は非常にドラマチックで、読みながら思わず手に汗を握りました。
佳苗の涙ながらの訴えによって、芽以子もようやく現実を突きつけられます。親友がそこまで感情を露わにするほど、自分は危うい恋にのめり込んでいたのだと悟ったのでしょう。私はこのシーンで、佳苗がかわいそうにも思えましたし、芽以子に対しても「早く目を覚まして!」と言いたい気持ちになりました。長年の友情を壊してまで手に入れたい恋とは何なのか、芽以子は深く考え始めます。ここで初めて芽以子は、見て見ぬふりをしていた問題から目を背けられなくなり、彼女の中で何かが音を立てて崩れ始めたように感じました。その夜、芽以子が自分の部屋で一人涙をこぼしながら「私、何をやっているんだろう…」と呟くシーンには胸が締め付けられました。
クライマックスの後、物語はゆっくりと静かな余韻へと移行していきます。修羅場の後始末をするように、芽以子と佳苗は本音をぶつけ合い、お互いに涙を流しながらわだかまりを解いていきました。この和解のシーンは胸が熱くなりました。誤解や嫉妬で絡まった糸を解きほぐすように二人が心を通わせ直す場面では、読者としてホッとすると同時に、友情の尊さに思わず涙がこぼれそうになりました。佳苗は「私たち、元に戻れるよね?」と不安げに尋ね、芽以子が「うん、もちろん」と泣き笑いで応える描写には、私ももらい泣きしそうになりました。人間関係は壊れるのは一瞬ですが、修復するには勇気と誠意が要るのだと改めて感じさせられます。
そして迎える結末は、激しいドラマの後とは思えないほど穏やかでした。彰生という嵐のような存在が去ったあとの芽以子の日常が静かに描かれ、かえってその静けさが心に沁みました。私は最初、芽以子が最後にどちらかというと消極的な選択をしたように感じてしまいました。しかし、読み返してみると、それこそが彼女にとっての前向きな決断だったのだと分かります。平凡で安らかな日々こそが、芽以子が本当に求めていた幸せだったのでしょう。大きな恋の熱が冷めた後に残るのは、自分を大切に思ってくれる人や当たり前の優しさなのかもしれません。そのことに気づいた芽以子の表情は、ラストシーンで晴れやかだったように私には思えました。静かながら希望を感じるエンディングに、私も深く安堵しました。
エンディング付近に登場する芽以子の会社の先輩・大槻さんの存在も、とても印象に残りました。大槻さんは物語を通して芽以子のことを静かに気遣い、彼女が落ち込んでいる時にはさりげなく「大丈夫か」と声をかけてくれる優しい男性です。恋に浮かれる芽以子は彼の好意に気づかないふりをしていましたが、私は読んでいて何度も「大槻さんのほうが絶対いい人なのに!」と思ってしまいました。例えば、疲れている芽以子にそっと温かい飲み物を差し出すような場面では、そのさりげない優しさに心がほっとしました。大槻さんのように穏やかで包容力のある男性こそ、芽以子に安定した幸せをもたらしてくれる存在だったはずです。結局、芽以子は大槻さんとは友人以上の関係にはなりませんが、だからこそ彼の誠実さが際立ち、報われない優しさが胸に沁みました。読後には「もし芽以子が最初から大槻さんを選んでいたら…」と考えずにはいられませんでした。とはいえ、恋の相手は理屈で選べるものではないという現実も、本作は痛感させてくれます。安定をもたらす男性と心をかき乱す男性、どちらを選ぶのかという難しさが本作では象徴的に描かれていたとも言えるでしょう。芽以子が後者を選んでしまったことに歯がゆさを感じつつも、現実の恋愛でも往々にして起こり得ることだと感じました。
『彼の隣りの席』というタイトルについても、読み終えたあと深く考えさせられました。芽以子はまさに“彼の隣の席”に座ることを願い、その席を手に入れましたが、そこは決して居心地の良い場所ではありませんでした。憧れの彼の隣に寄り添う高揚感と同時に、常に振り回される不安定なポジションは、タイトルが象徴するように危うさをはらんでいたように思います。最終的に芽以子は自らその席を立つ決断をしますが、その選択には大きな勇気が必要だったでしょう。隣の席が空いたことで、彼女はようやく自分自身の居場所を取り戻し、地に足の着いた人生を歩み始めることができたのです。タイトルにはそんな皮肉と示唆が込められているように感じました。
読み終えて振り返ると、序盤では胸がときめき、中盤では苛立ちや不安を募らせ、終盤では涙とともに安堵するなど、物語に合わせて私の感情も大きく揺さぶられました。全編を通じて、人間関係のもつれや女性の心理描写が実に丁寧でリアルでした。唯川恵さんの筆致は、決して大袈裟な表現をせず日常の延長線上にあるドラマを描くのが特徴です。文章も平易で読みやすく、情景や心情の移り変わりがすっと胸に染み込むようでした。本作でも、派手な演出はないのに心情の機微がひしひしと伝わってきて、何度も胸が締め付けられました。恋愛模様だけでなく、女友達同士の関係性の移ろいも丁寧に描かれていて、友情の物語としても心に残るものがありました。特に女性読者であれば、芽以子の恋に一喜一憂する気持ちや、友人との微妙な距離感の変化に強く共感できるのではないでしょうか。男性の読者にとっても、女性の繊細な心理や人間関係の機微を知る上で示唆に富む物語だと思います。携帯のない時代設定も手伝って、恋人を待つ時間のもどかしさや友人とのすれ違いに、より切実な重みが感じられました。
本作を通じて、「普通の幸せ」とは何だろうかと改めて考えさせられました。芽以子にとって当たり前の毎日や平凡な幸せは、一度は退屈に思えたものだったかもしれません。それがどれほど貴重で温かなものかは、激しい恋に傷ついた末にようやく気づけるものだったのでしょう。華やかな恋のときめきよりも、何気ない日常に寄り添ってくれる優しさや安定こそが、人生においてかけがえのない宝物なのかもしれません。私自身、物語を読み終えてから、自分にとって「当たり前」だと思っていた日々の中にある幸せを、もう一度噛みしめたくなりました。芽以子もこの経験を糧に、今度こそ自分にとって本当に大切な幸せを掴んでくれるだろうと信じています。
私は、本作をかつて苦い恋を経験したことがある人や、じっくりと人間ドラマを味わいたい人にぜひ勧めたいです。恋愛で悩んだとき、自分の幸せとは何かを考えるきっかけを与えてくれる、心に残る一冊だと思います。
まとめ
『彼の隣りの席』は、再会の恋から始まる物語を通じて、人間関係の繊細さと「普通の幸せ」の尊さを静かに教えてくれる作品でした。読み終えたあと、私は芽以子の選択に切なさと温かさが入り交じった不思議な余韻を感じました。
全体を通して大きな盛り上がりがあるわけではありませんが、その分リアルな心理描写に共感し、登場人物の気持ちに寄り添って読むことができました。等身大の女性たちが直面する恋愛と友情の問題は、誰にでも起こり得るものとして心に響きます。
本作を読み終えたとき、題名の意味をかみしめながら、普通の日常が持つ幸せについて改めて考えさせられました。ドラマチックではないかもしれませんが、そこに描かれた感情の動きはとても丁寧で、読後には静かな感動が残ります。
刺激的な恋愛だけでなく、地に足の着いた幸せの大切さを感じたい方におすすめしたい一冊です。恋愛における現実と理想の狭間で揺れ動く気持ちを味わいたい人や、共感できる恋愛小説を探している人には、ぜひ『彼の隣りの席』を手に取ってみてほしいと思います。