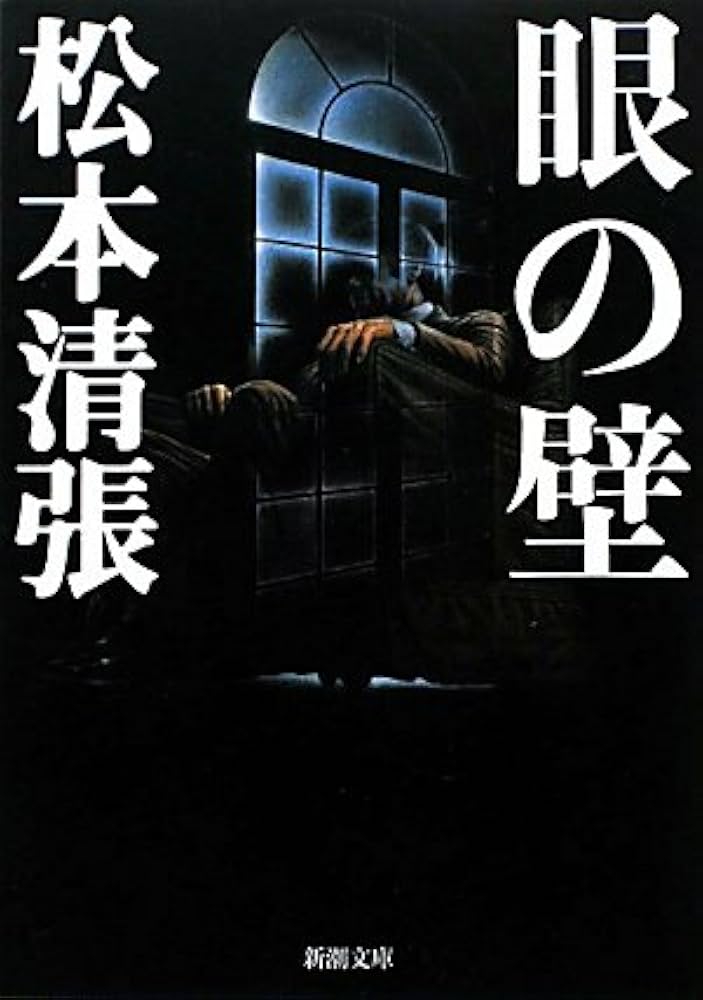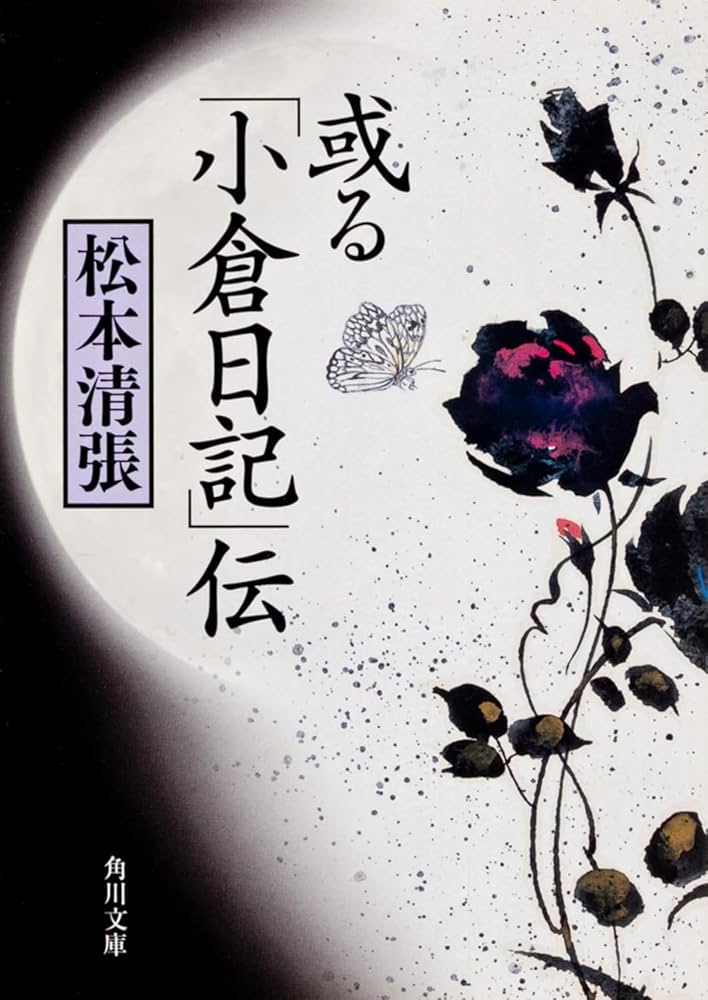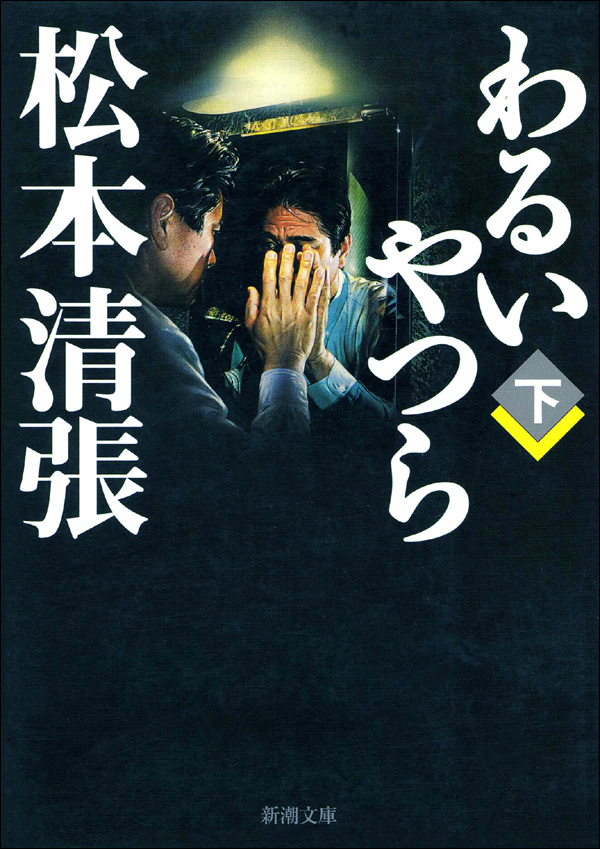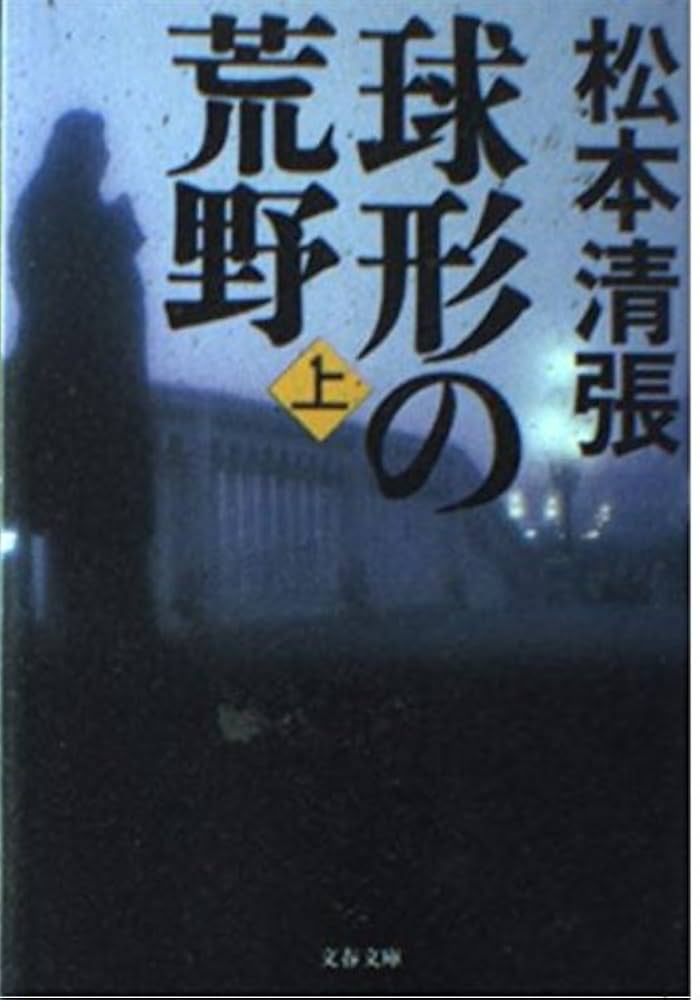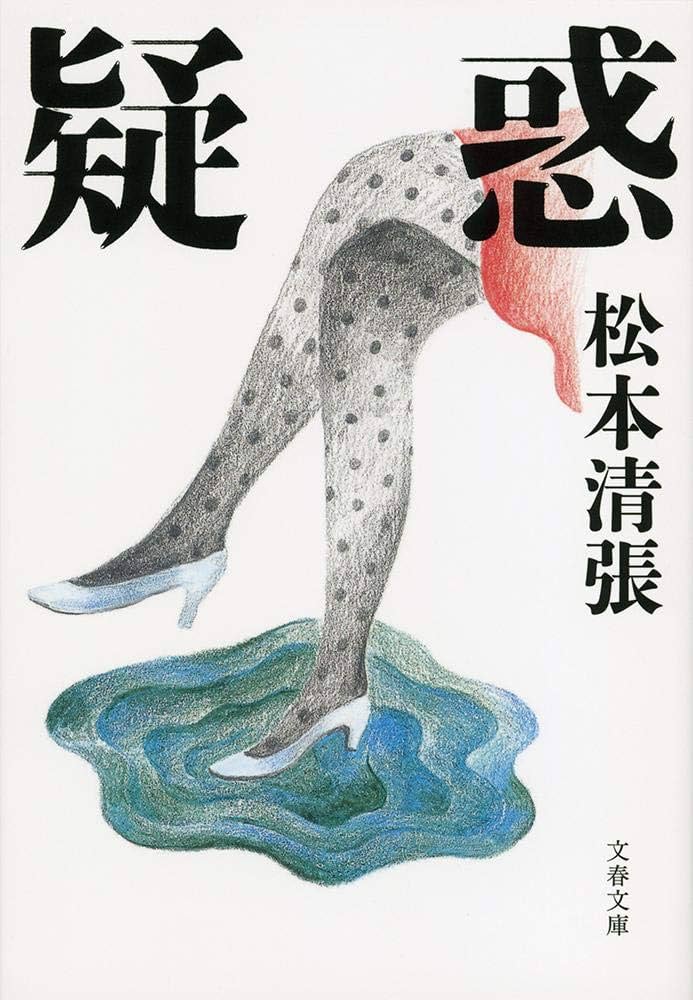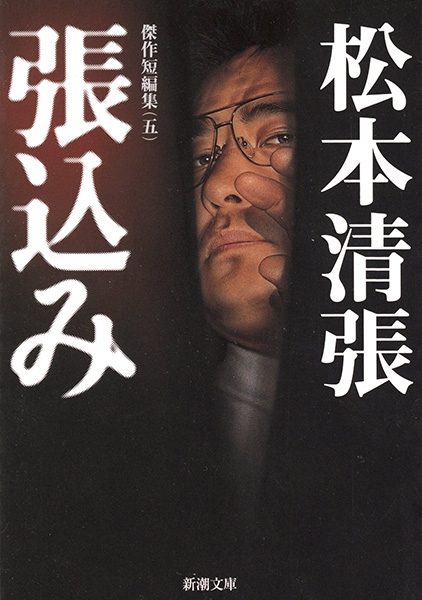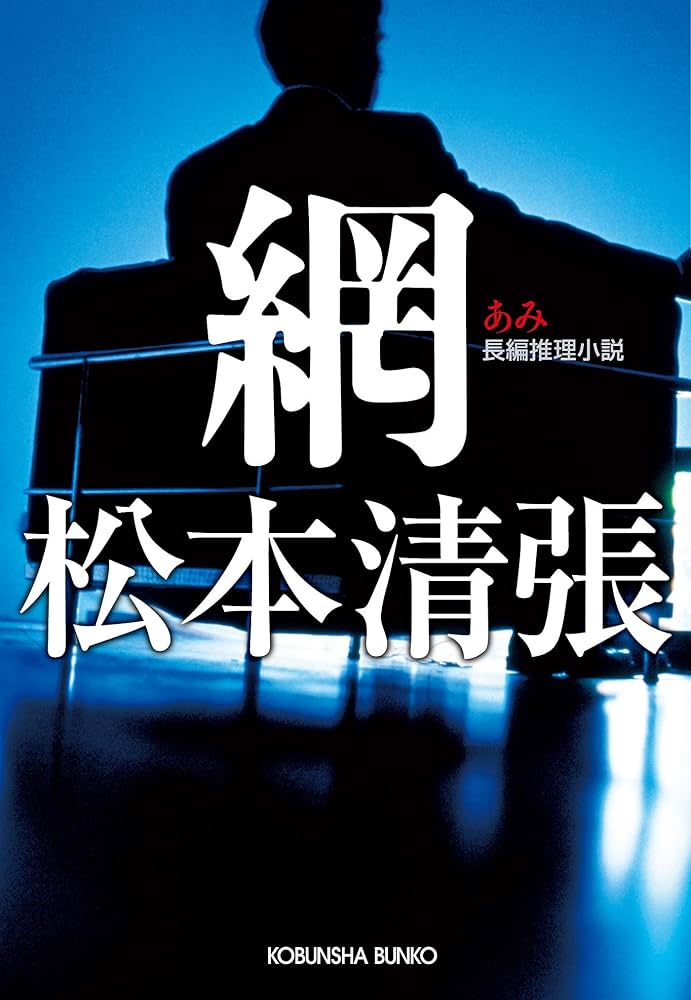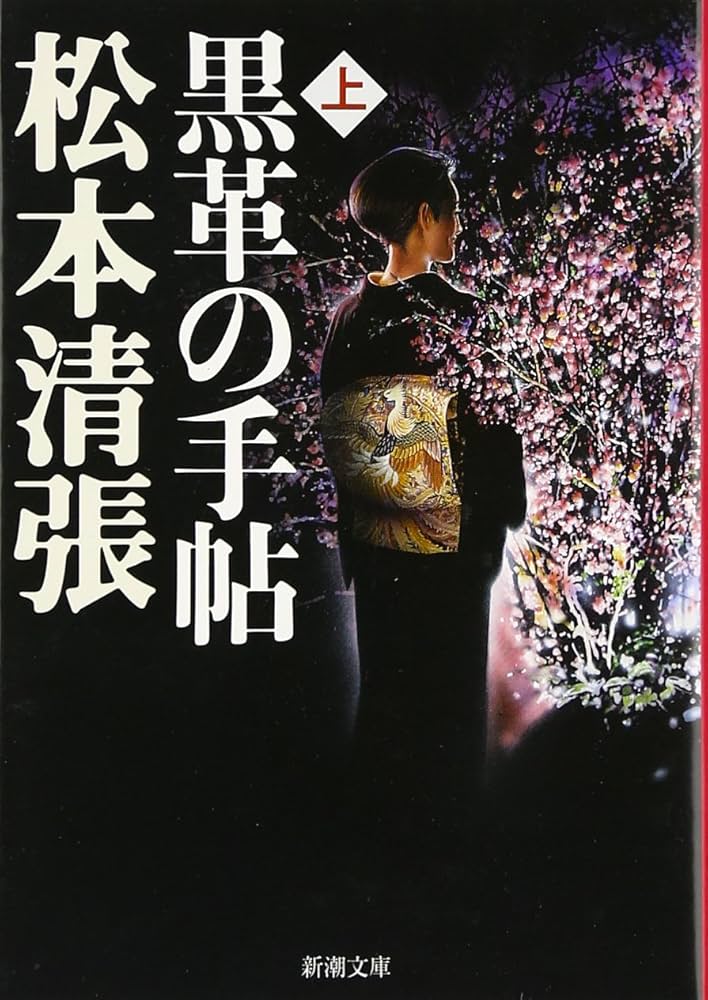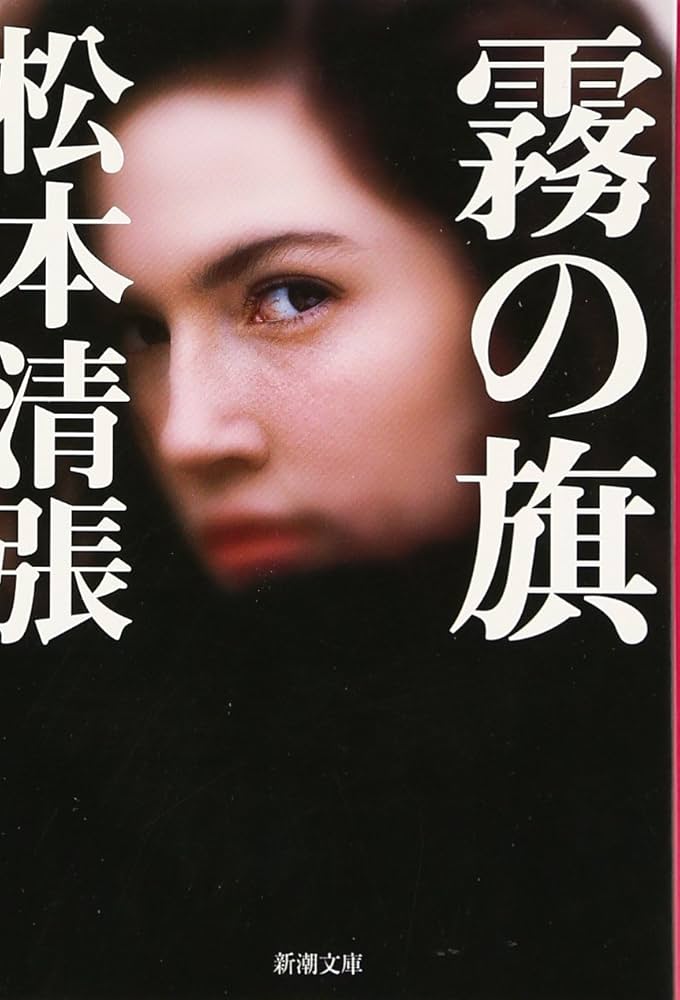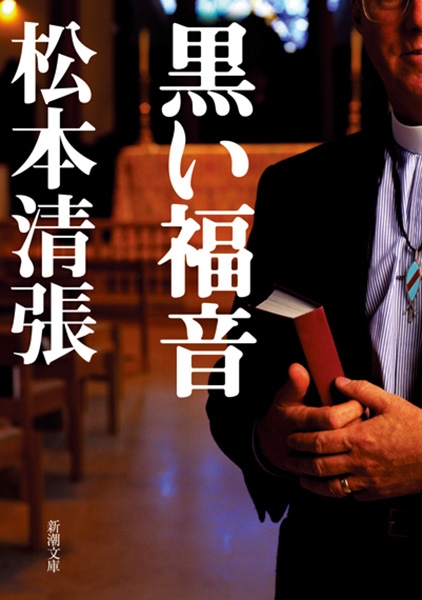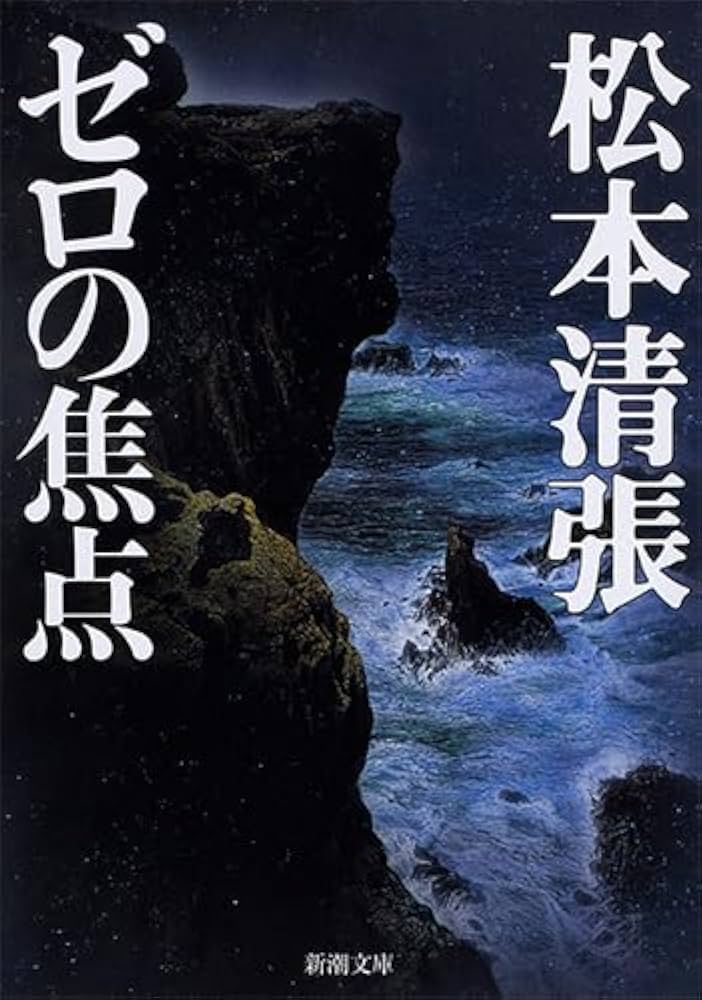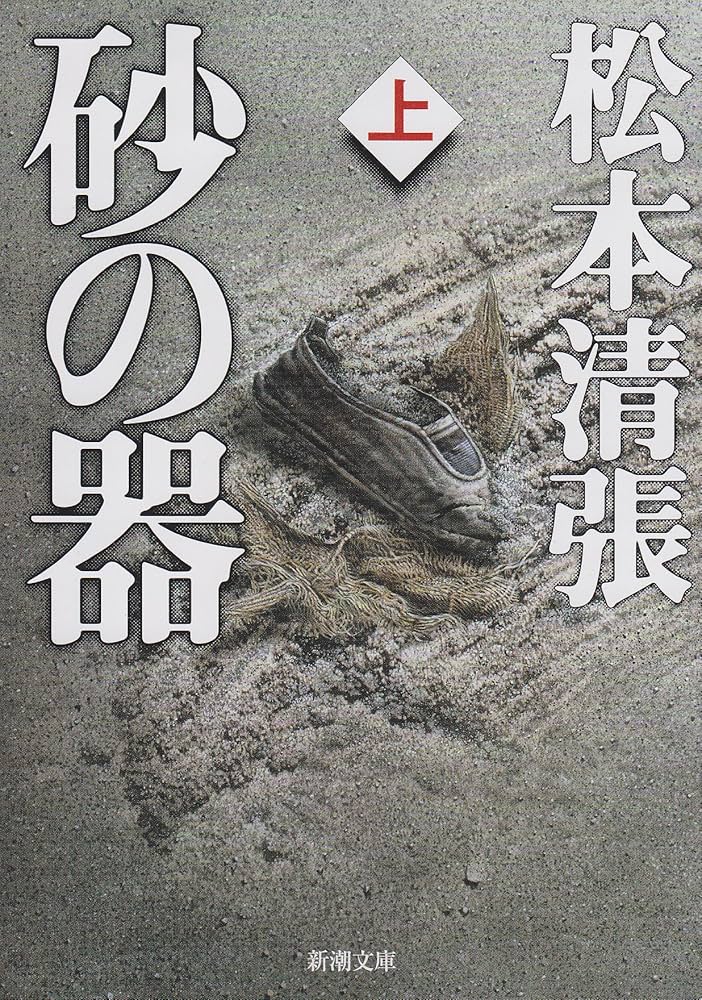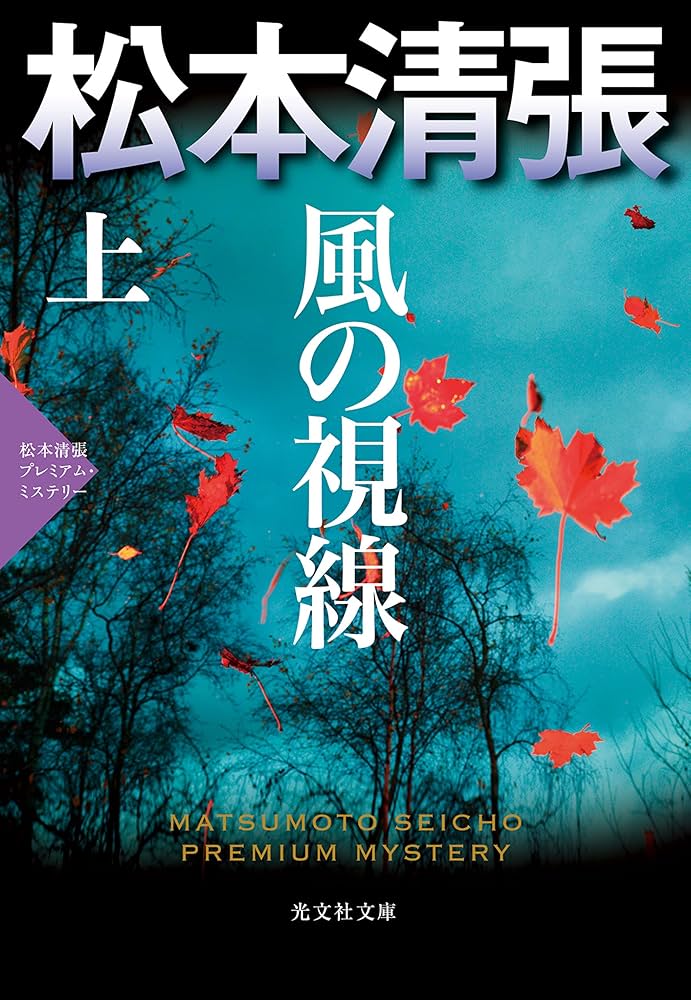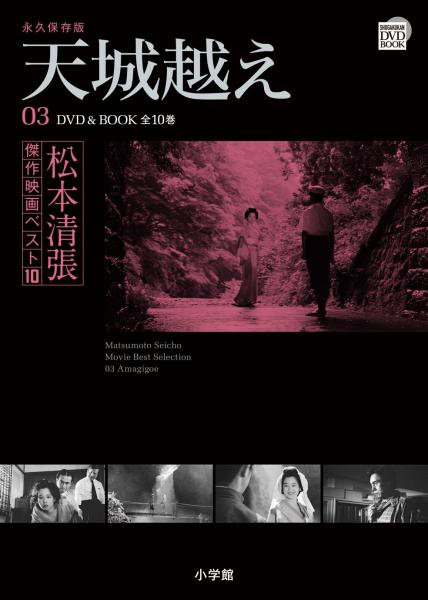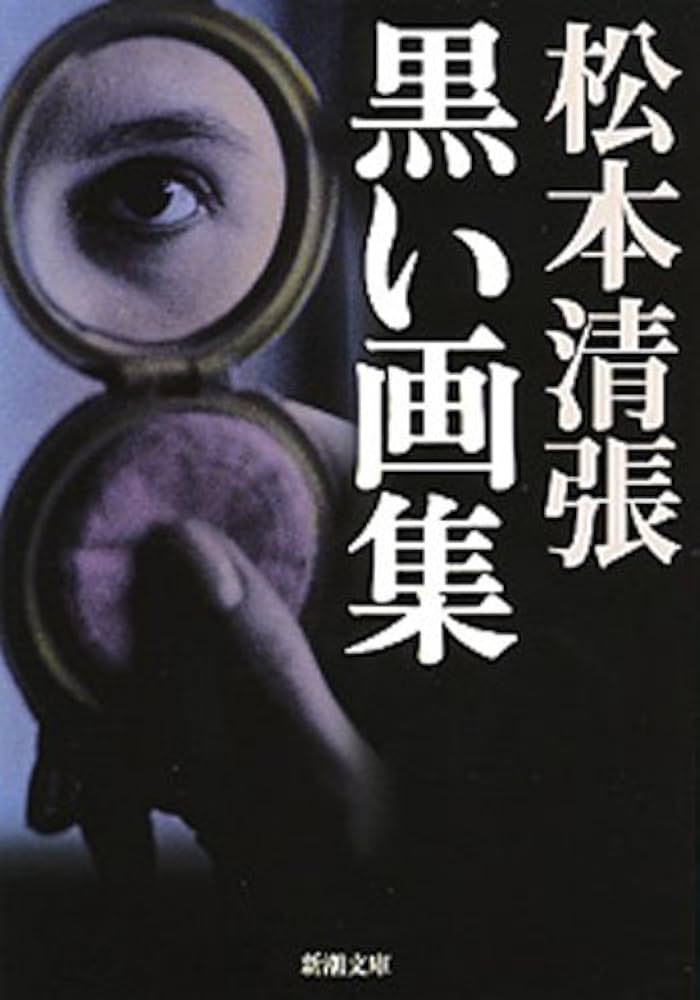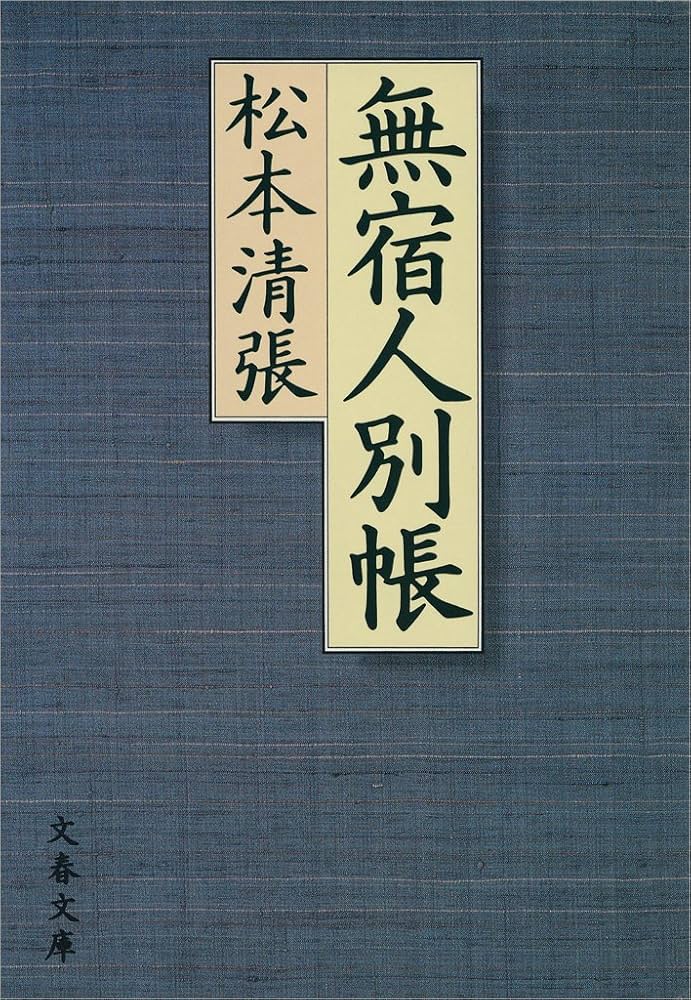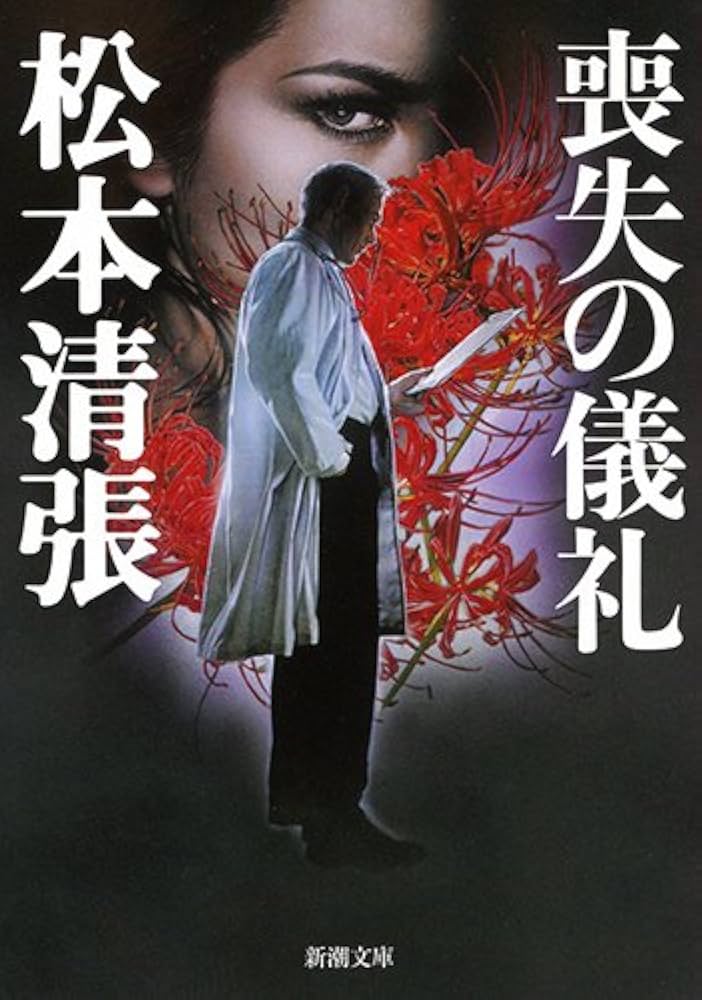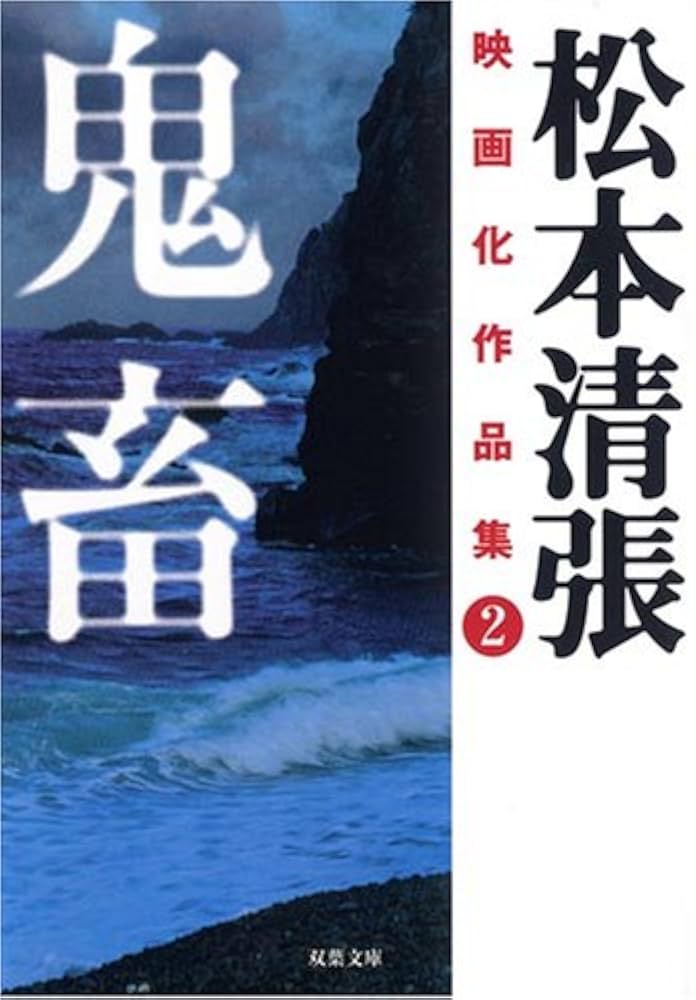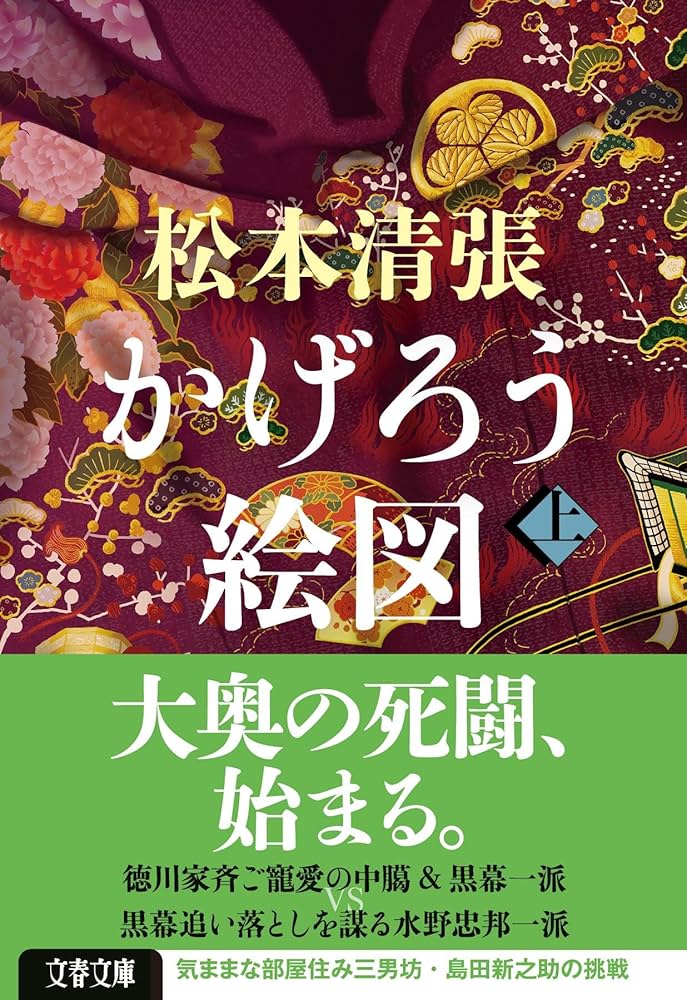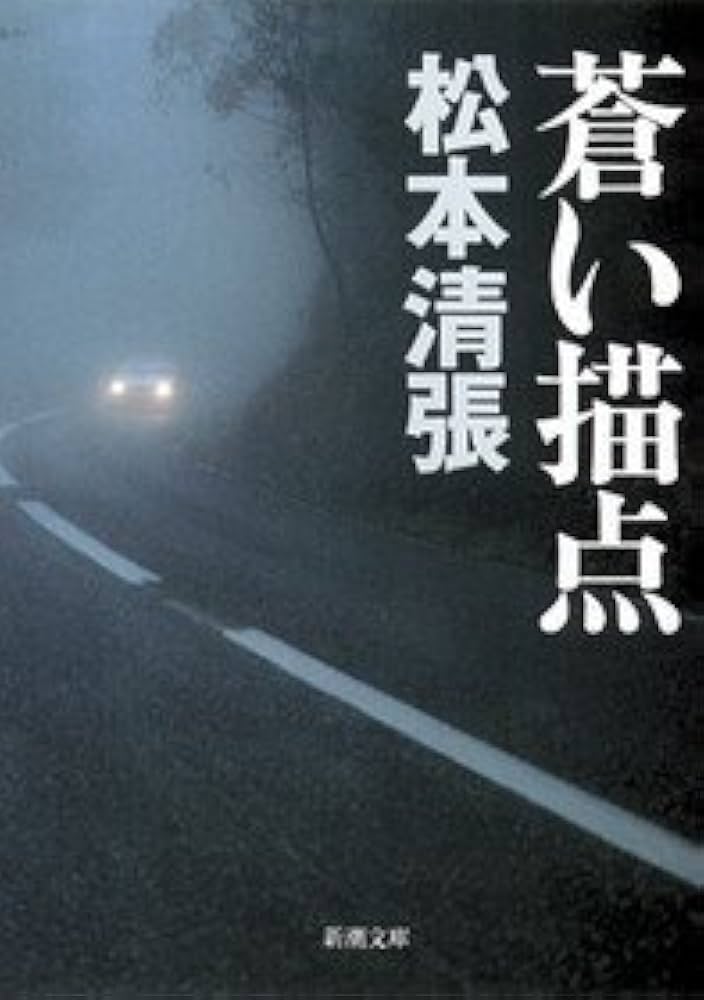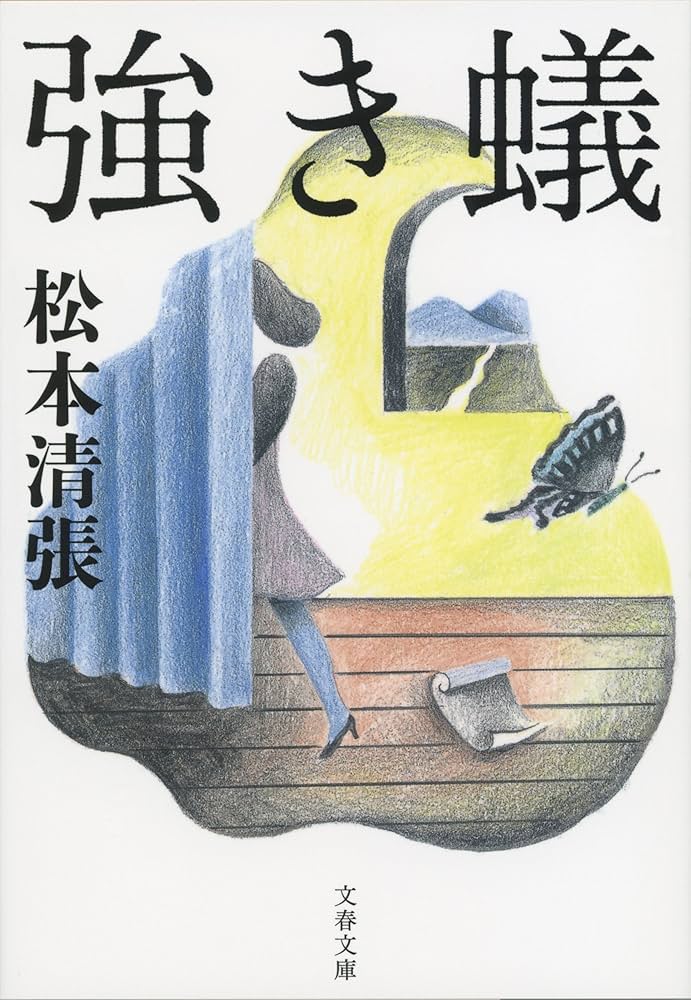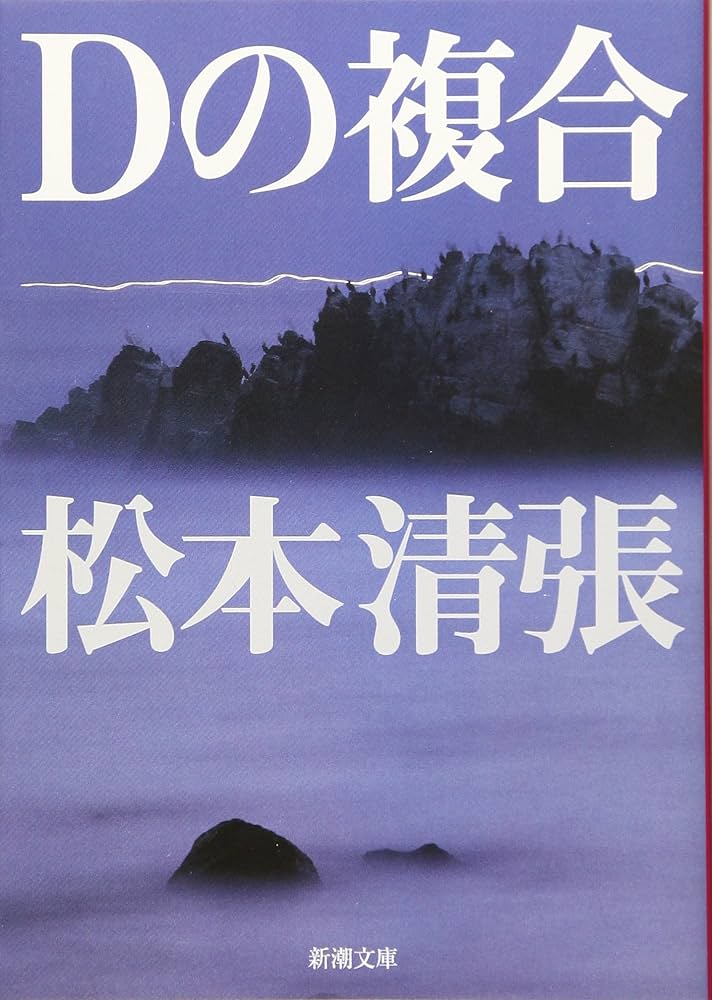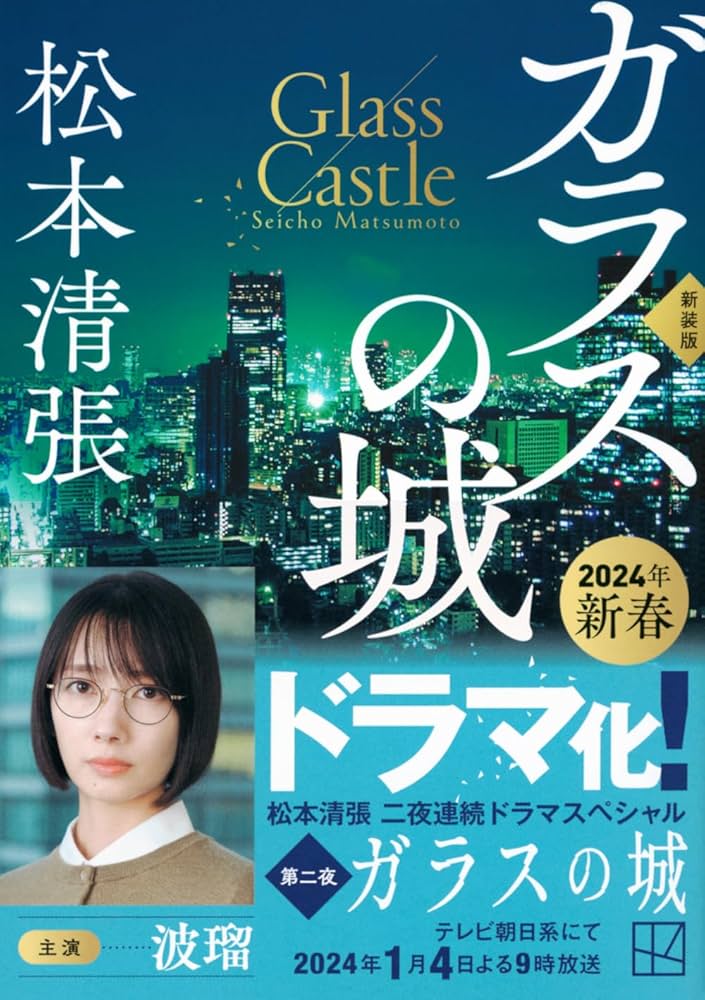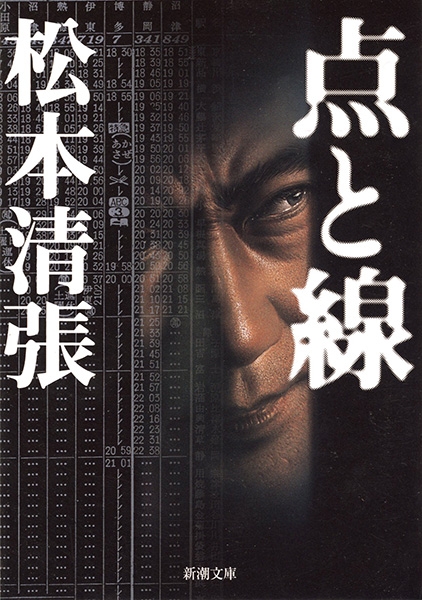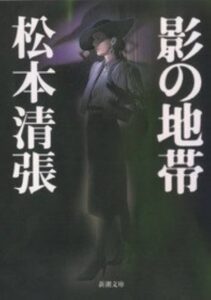 小説「影の地帯」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「影の地帯」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
本作は、松本清張作品の中でも特に社会の闇と人間の深層心理を鋭く描いた傑作として知られています。一人の平凡なカメラマンが、ほんの些細な偶然から、政財界を揺るがす巨大な陰謀に巻き込まれていく様は、まさに圧巻の一言です。
物語の魅力は、なんといってもその緻密なプロットと、リアリティあふれる描写にあります。単なるミステリーに留まらず、当時の日本の社会が抱えていた問題を浮き彫りにし、読者に強烈な問いを投げかけます。なぜ事件は起きたのか、そして「影の地帯」とは一体何を指すのか。その答えに近づくにつれて、私たちは言いようのない恐怖と戦慄を覚えることになるでしょう。
この記事では、まず物語の導入部分であるあらすじを、核心には触れない範囲でご紹介します。その後、物語の真相に迫る重大なネタバレを含む、詳細な感想を綴っていきます。この作品が放つ独特の雰囲気や、登場人物たちの葛藤、そして社会の深淵に潜む悪の正体について、深く掘り下げていきたいと思います。
これから「影の地帯」を読もうと考えている方、あるいは既に読了し、他の人の解釈や感想に触れたいと思っている方、どちらにも楽しんでいただける内容を目指しました。この物語が持つ重層的な魅力を、少しでもお伝えできれば幸いです。それでは、松本清張が描き出した、光の当たらない世界の探訪へと参りましょう。
「影の地帯」のあらすじ
物語の始まりは、主人公であるフリーカメラマンの田代利介が、取材先の九州から東京へ戻る飛行機の中での出来事でした。富士山の写真を撮りたいという一心で、窓際の席を譲ってもらったことが、彼の運命を大きく狂わせる引き金となります。席を代わってくれたのは、謎めいた美女と、彼女とは不釣り合いな雰囲気を持つ赤ら顔の男。この偶然の出会いが、後に彼を底知れぬ闇へと誘うとは、知る由もありませんでした。
東京に戻った田代は、行きつけの銀座のバーで、飛行機で出会った男と再会します。その直後から、バーのマダムの様子がおかしくなり、ついには忽然と姿を消してしまいます。時を同じくして、政界の大物である山川亮平の失踪が報じられ、世間は騒然となります。一見、無関係に見える二つの事件。しかし、田代だけが、その両方にあの男の影がちらついていることに気づいていました。
事件の真相を追ううちに、田代は信州の地で再びあの男に遭遇します。男が受け取っていた大きな木箱、そして夜の湖から聞こえる不気味な水音。探求心は次第に恐怖へと変わり、ついには何者かに命を狙われる事態にまで発展します。彼は、自分が足を踏み入れたのが、単なる失踪事件の謎ではなく、命がけの危険な領域であることを悟るのでした。
警察の捜査も難航し、事件は完全に行き詰まったかのように見えました。田代は、身の危険を感じながらも、自らの手で真相を突き止めようと決意します。一体、マダムと大物政治家はどこへ消えたのか。そして、田代を執拗に追う男たちの目的とは何なのか。物語は、誰も想像し得なかった驚愕の結末へと突き進んでいきます。
「影の地帯」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の核心に触れるネタバレを含んだ感想になります。未読の方はご注意ください。この物語の最も恐ろしい部分は、その犯罪のメカニズムにあります。単なる殺人事件ではなく、人間という存在そのものを「消滅」させるという、冷徹で計画的な手口は、読者に強烈な衝撃を与えます。
犯人たちが用いたのは、パラフィンを使った死体の完全処理でした。殺害した人間の体を工業用のパラフィンに漬け込み、固化させた後、電動カンナでまるごと削り取ってしまうのです。そうして出来上がった、人体の組織とパラフィンが混ざったおが屑を、工業廃棄物として湖の底に遺棄する。この方法であれば、死体は文字通り跡形もなく消え去り、物証は何も残りません。
この手口は、著者の徹底した取材から生まれたものであり、そのリアリティが恐怖を増幅させます。人間を「モノ」として扱い、工場のライン作業のように処理していく過程は、非人間的であると同時に、工業化社会の歪みを象徴しているようにも感じられます。個人の尊厳やアイデンティティは完全に破壊され、匿名の「削りカス」へと変えられてしまうのです。
この冷酷な犯行計画を立案し、実行していた組織こそが、物語のタイトルである「影の地帯」の正体です。それは、政界の腐敗と深く結びついた、社会の隅々にまで根を張る巨大な犯罪ネットワークでした。彼らは、自らの汚職や不正を知る者を、この世から痕跡すら残さずに消し去っていたのです。
銀座のバーのマダムは、客の会話から組織の秘密を知ってしまったために消されました。政界の大物・山川は、組織にとって邪魔な存在となったために排除されました。田代が出会った赤ら顔の男などは、その組織の末端で動く駒に過ぎなかったのです。
そして、物語は最大の衝撃を迎えます。この巨大な陰謀を裏で操っていた黒幕が、田代が信頼していた写真仲間、久野正一であったことが明らかになるのです。彼は、田代の調査を手伝うふりをしながら、その行動を監視し、組織に情報を流していました。味方だと思っていた人間が、実は最も恐ろしい敵だったという展開は、まさに悪夢です。
この「裏切り」という要素が、物語に深みを与えています。社会の巨大な悪というだけでなく、ごく身近な人間の内面に潜む闇をも描き出しているからです。友情や信頼といった人間的な感情さえも、金と権力の前ではいとも簡単に踏みにじられてしまう。その現実を、まざまざと見せつけられた気がしました。
久野もまた、田代と同じ写真家でした。真実を写し出すべき人間が、その魂を悪に売り渡し、真実を隠蔽するためにその知恵を使う。この対比は非常に皮肉であり、悲しいものです。彼は、光の当たる場所ではなく、影の中で生きることを選んでしまったのです。
物語の冒頭で登場した謎の美女の役割も、最後には明らかになります。彼女は、組織が利用する「ハニートラップ」役であり、犯行に日常性を偽装するための小道具に過ぎませんでした。彼女自身もまた、組織にとっては使い捨ての駒の一人に過ぎなかったのです。醜悪な陰謀の真相が暴かれるにつれて、彼女の存在感は希薄になっていきます。
事件は解決し、久野をはじめとする犯人たちは逮捕されます。しかし、物語は決して爽快なハッピーエンドでは終わりません。彼らを裏で操っていた大物政治家たちは、権力という見えない壁に守られ、罪を問われることはありませんでした。この結末に、私は松本清張の社会に対する冷徹な視線を感じずにはいられませんでした。
直接の実行犯を捕らえても、彼らを生み出した社会の構造そのものが変わらなければ、また新たな「影の地帯」が生まれるだけ。真の悪は、決して法の裁きを受けることなく、のうのうと生き続ける。このやるせない現実こそが、この作品が突きつける最も重いテーマなのかもしれません。
主人公の田代は、事件を乗り越え生き延びましたが、彼が失ったものもまた大きかったでしょう。彼は、この世界の光だけでなく、その下に広がる深い闇を知ってしまいました。美しい風景を見ても、人の笑顔に触れても、その裏に潜むかもしれない悪意を意識せずにはいられなくなったのではないでしょうか。
この物語が読後に残すのは、一種の虚無感と、社会に対する不信感です。しかし、それと同時に、たとえ無力であっても、真実を追い求めようとする人間の意志の尊さも教えてくれます。田代は特別な人間ではありません。ごく普通の市民が、勇気と執念で巨大な悪に立ち向かっていく姿に、私たちは希望を見出すこともできるのです。
「影の地帯」とは、特定の場所を指す言葉ではないのだと思います。それは、私たちの社会、そして私たち自身の心の中に存在する、光の当たらない領域そのものなのでしょう。私たちは皆、知らず知らずのうちに、その領域と隣り合わせで生きているのかもしれません。
この作品は、単なるエンターテインメントとして消費されるべきものではないと感じます。社会の仕組みや、人間の本質について、深く考えさせられる力を持っています。なぜ人は道を誤るのか。正義とは何か。そして、本当の恐怖とは何か。次々と問いが浮かんできます。
松本清張作品の魅力は、その徹底したリアリズムにありますが、本作はその中でも特に際立っています。死体処理の具体的な描写から、政財界の癒着構造まで、まるでノンフィクションを読んでいるかのような錯覚に陥るほどです。
この物語を読んで、私たちは何を学ぶべきなのでしょうか。それは、物事の表面だけを見て判断することの危うさであり、見えない部分にこそ真実が隠されているという教訓かもしれません。そして、どんなに巨大な悪であっても、その始まりはほんの些細な綻びであるということ。田代の何気ない行動が、結果的に巨大な犯罪組織を崩壊させるきっかけとなったように。
まとめ
松本清張の「影の地帯」は、単なるミステリーの枠を超えた、社会派エンターテインメントの金字塔と言える作品でした。一人のカメラマンが偶然から巨大な陰謀に巻き込まれていく過程は、スリルとサスペンスに満ちています。読者は主人公と共に、息をのみながら事件の真相へと迫っていくことになります。
この物語の核心にあるのは、人間という存在を「消滅」させるという恐るべき犯行手口と、その背後にある政財界の深い闇です。ネタバレになりますが、味方だと思っていた人物の裏切りや、決して裁かれることのない真の黒幕の存在は、読後に重い余韻を残します。勧善懲悪では終わらない、社会の不条理を見事に描き切っています。
あらすじを追うだけでも十分に楽しめますが、この作品の本当の魅力は、その深層に流れるテーマ性にあります。人間の尊厳とは何か、社会における正義とは何かを、私たちに鋭く問いかけてくるのです。感想は人それぞれだと思いますが、多くの人が社会の構造的な問題について考えさせられるのではないでしょうか。
まだこの傑作に触れたことのない方は、ぜひ一度手に取ってみることをお勧めします。光と影が織りなす、緻密で重厚な物語の世界に、きっと引き込まれるはずです。そして、読了後には、あなたの見る世界が少しだけ変わっているかもしれません。