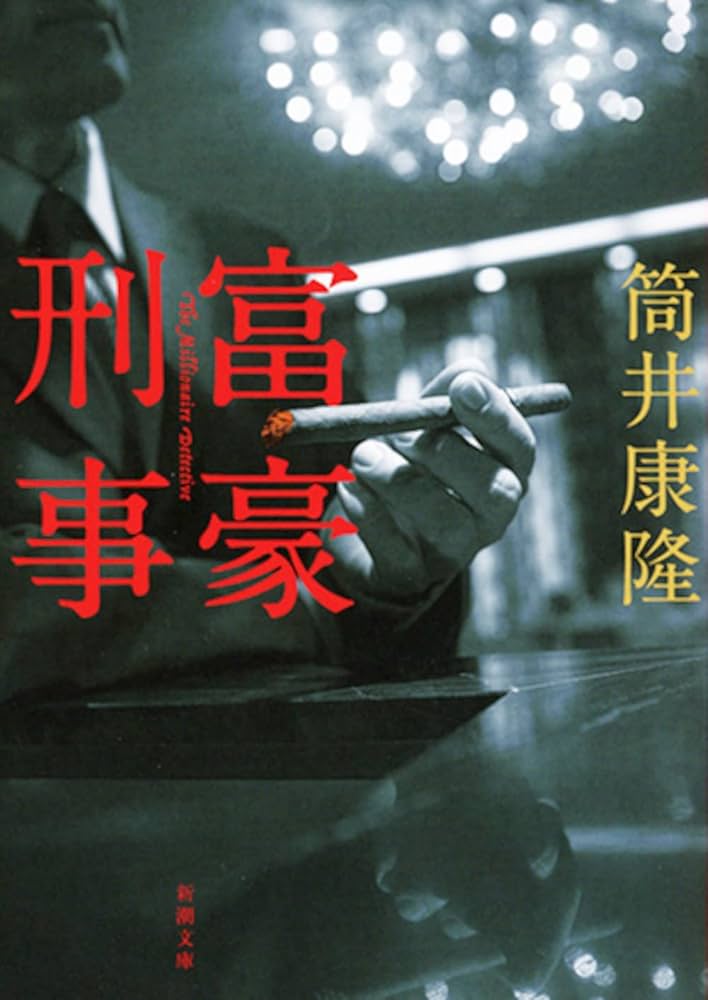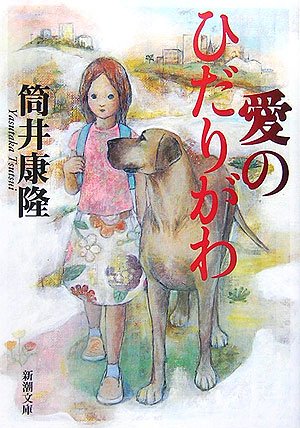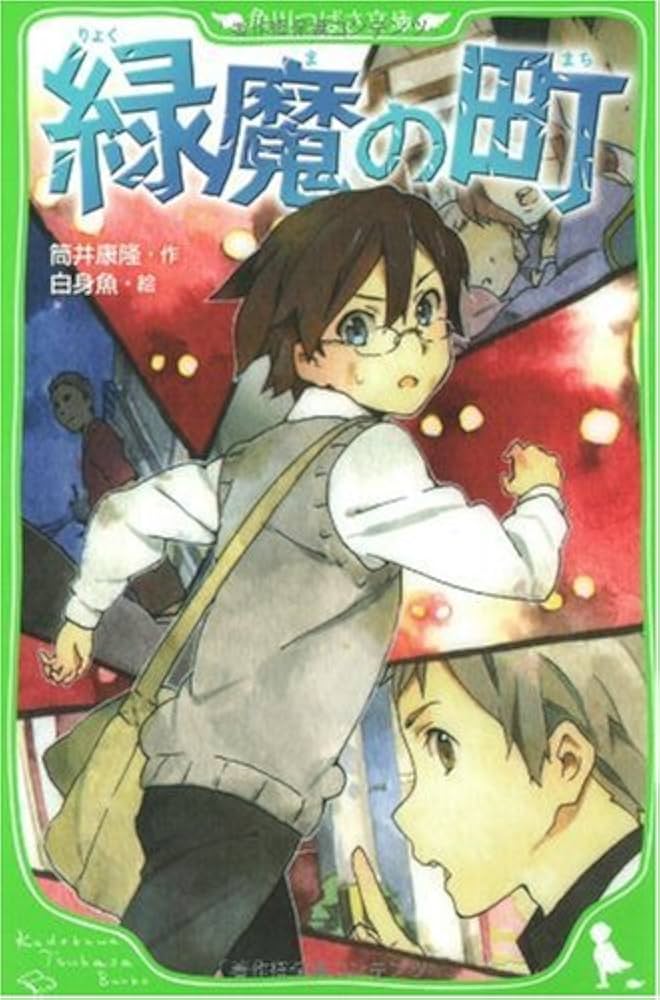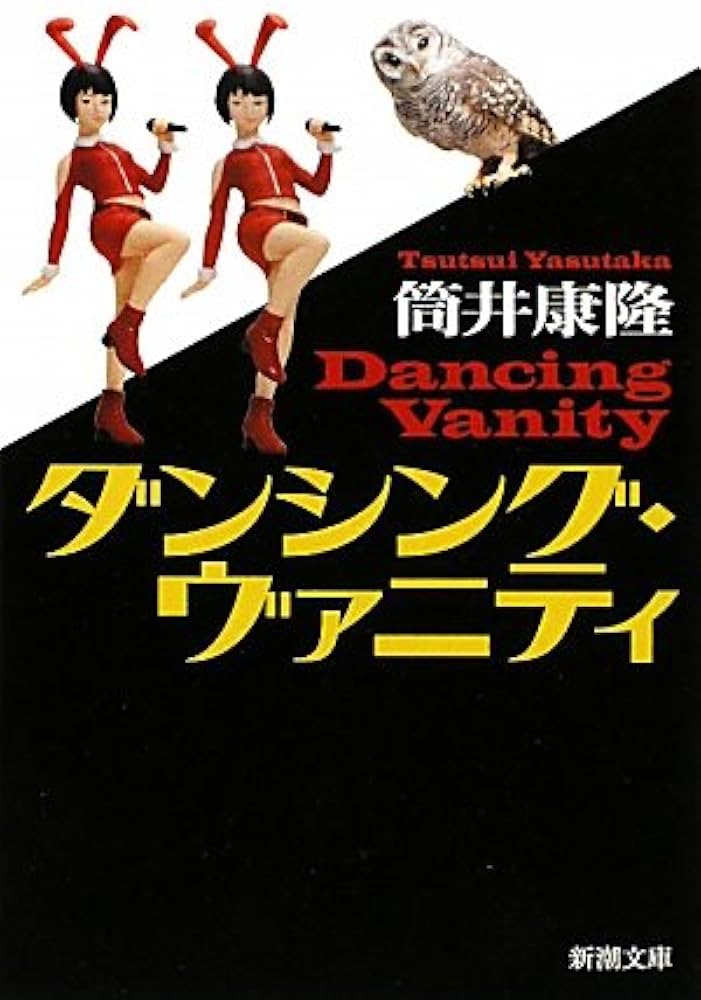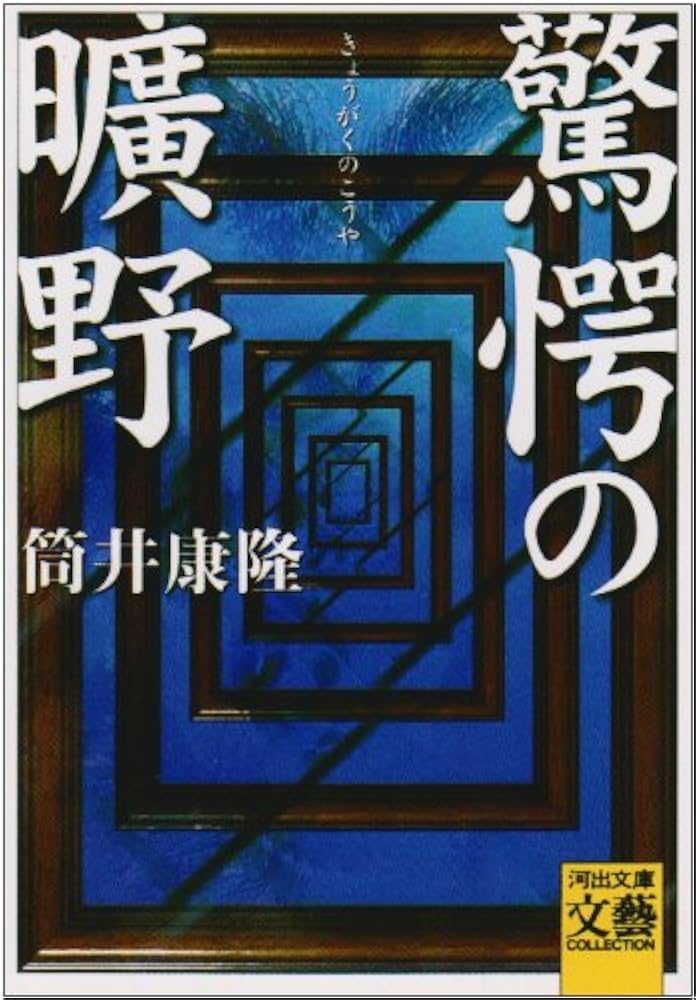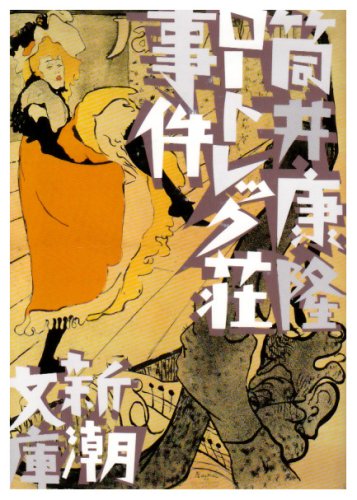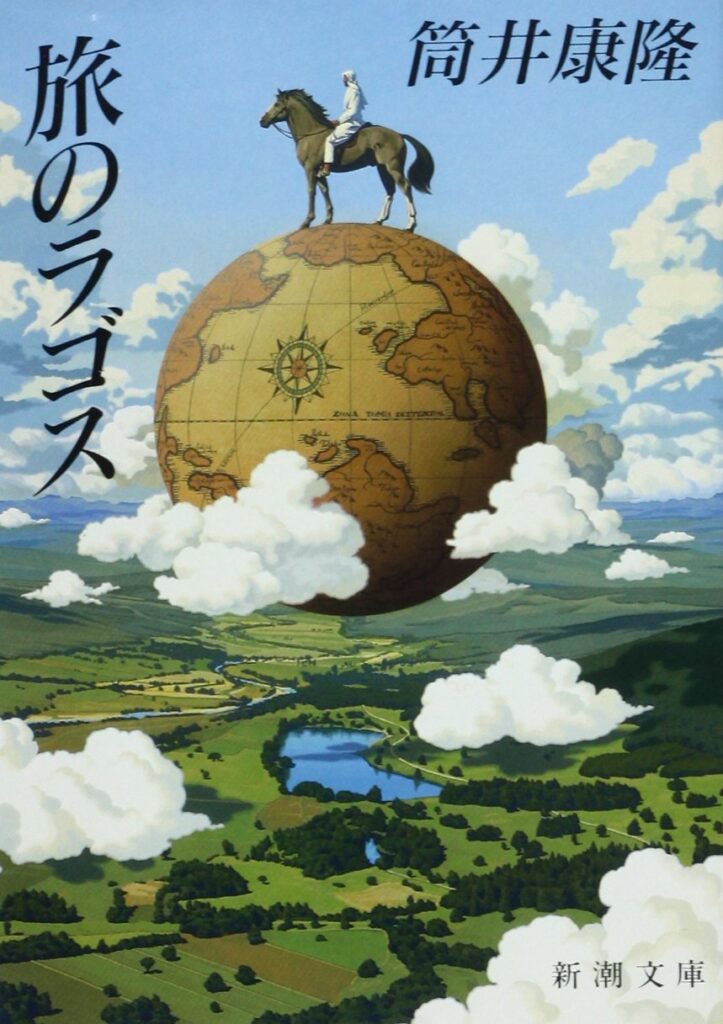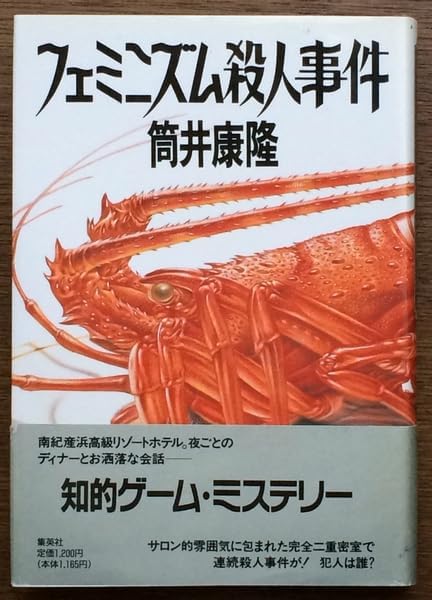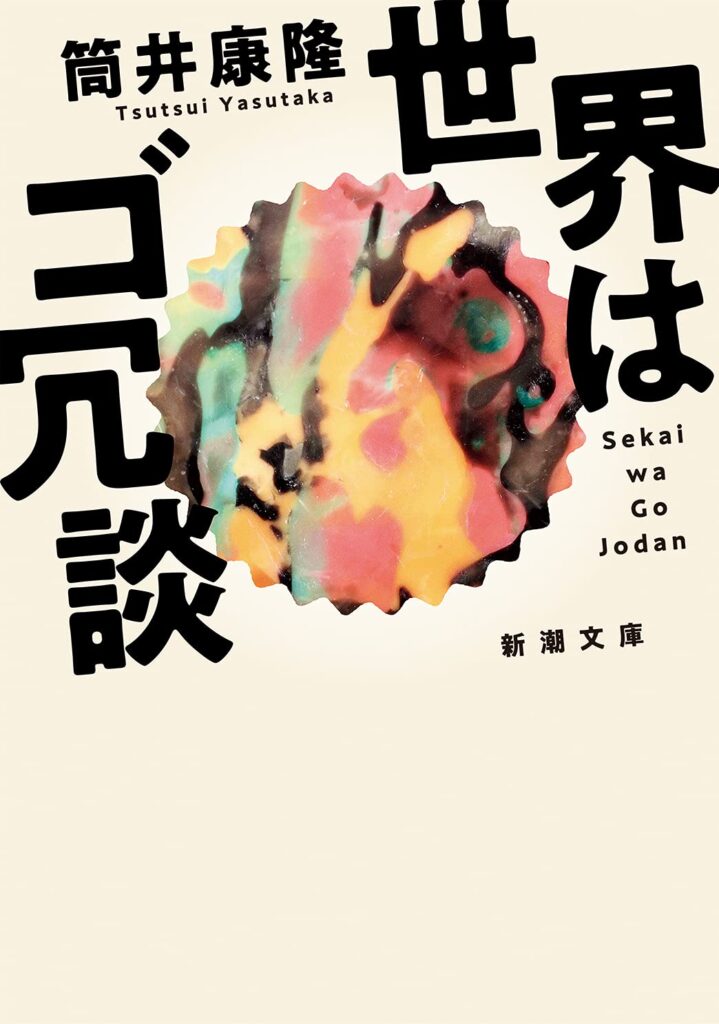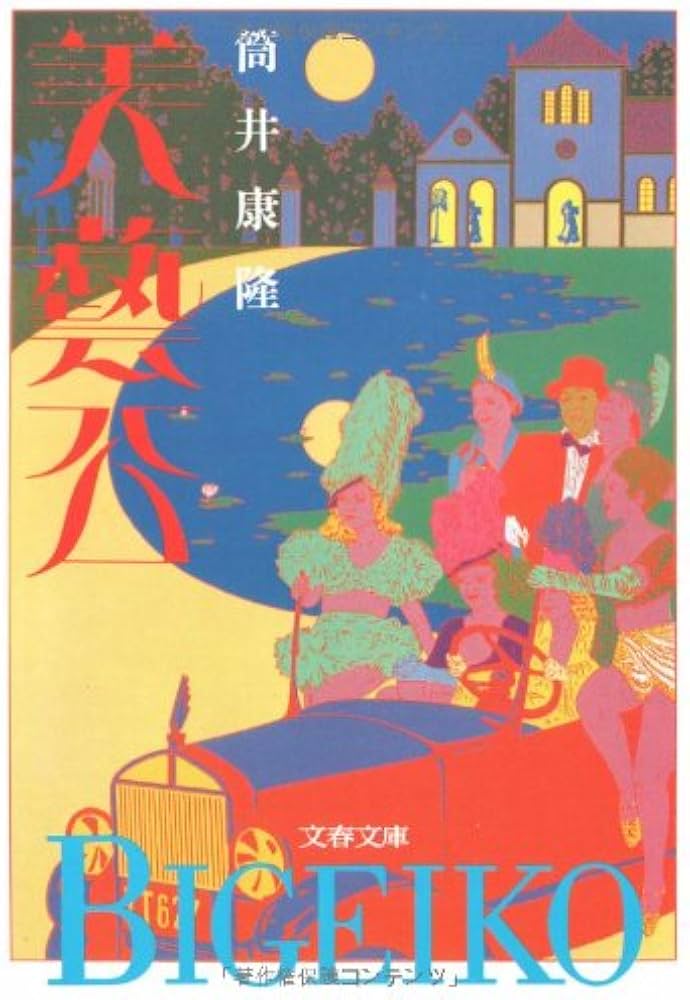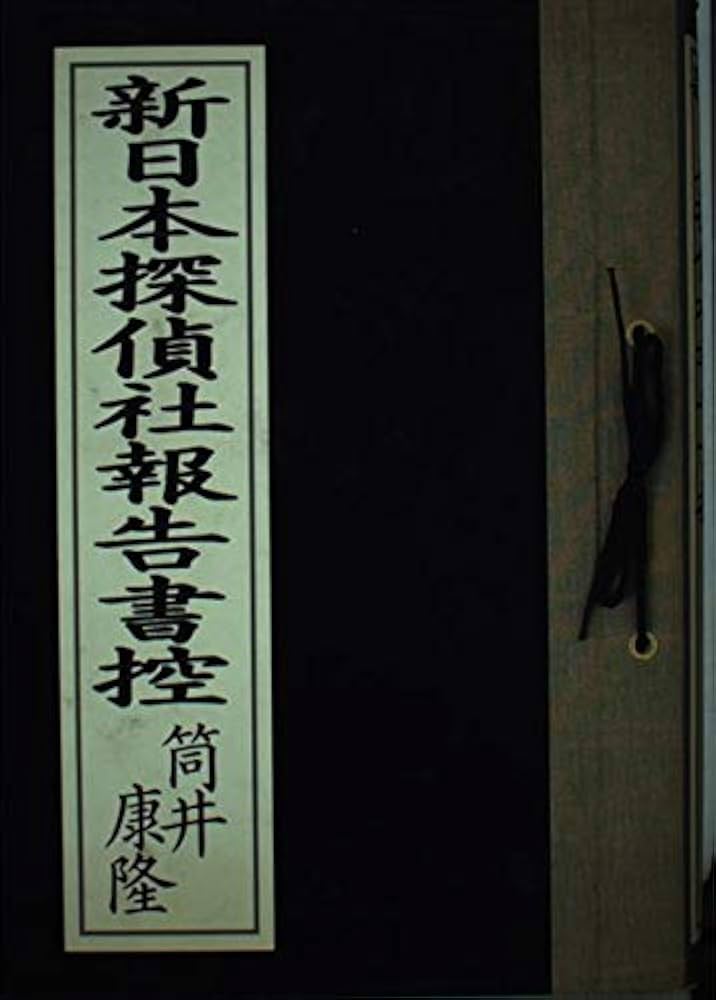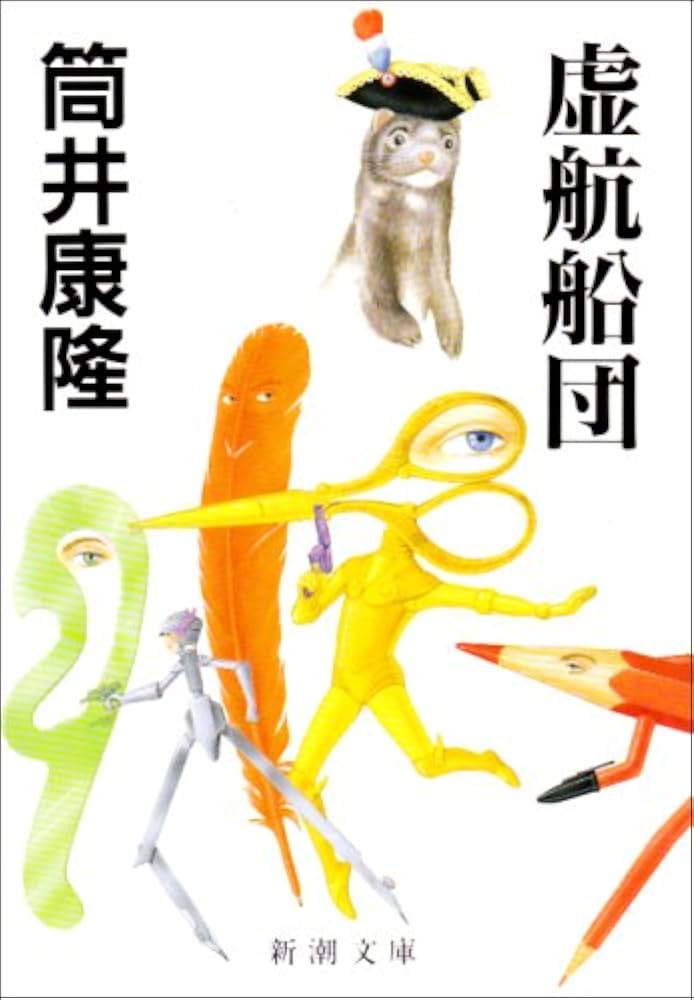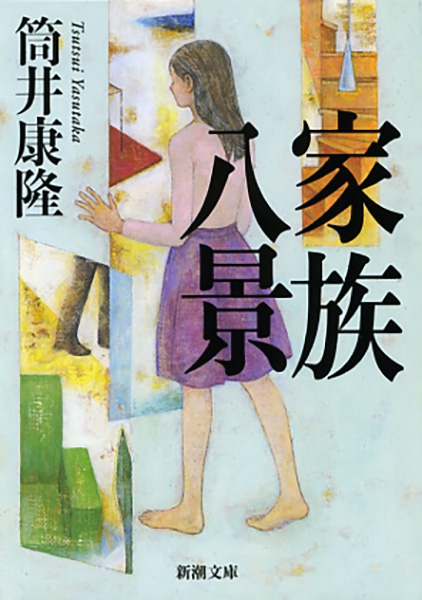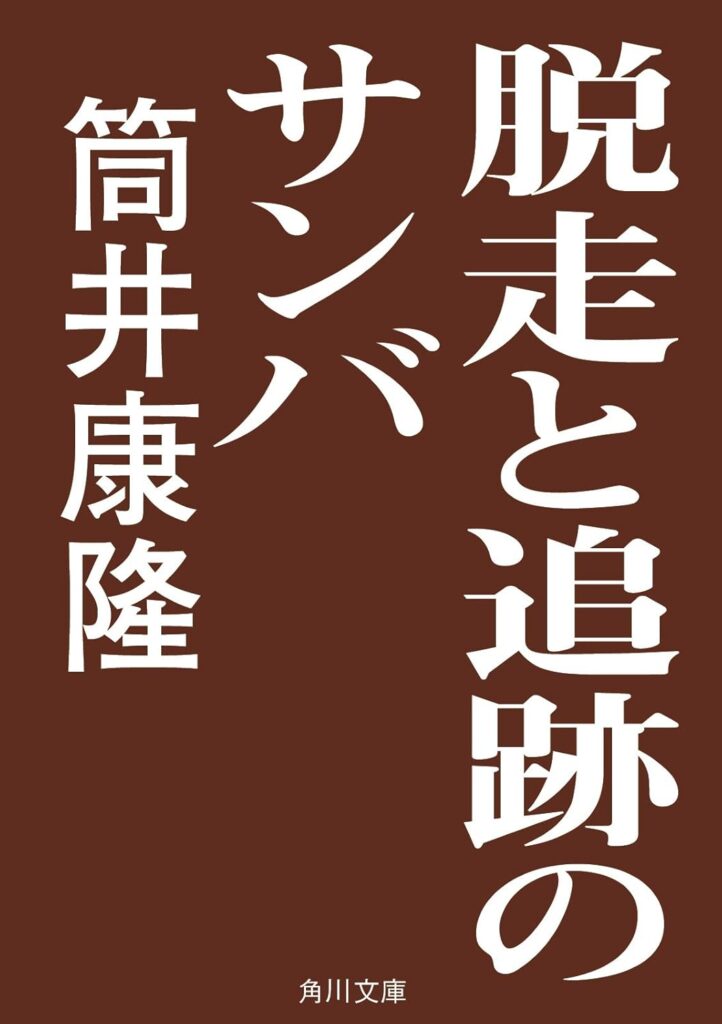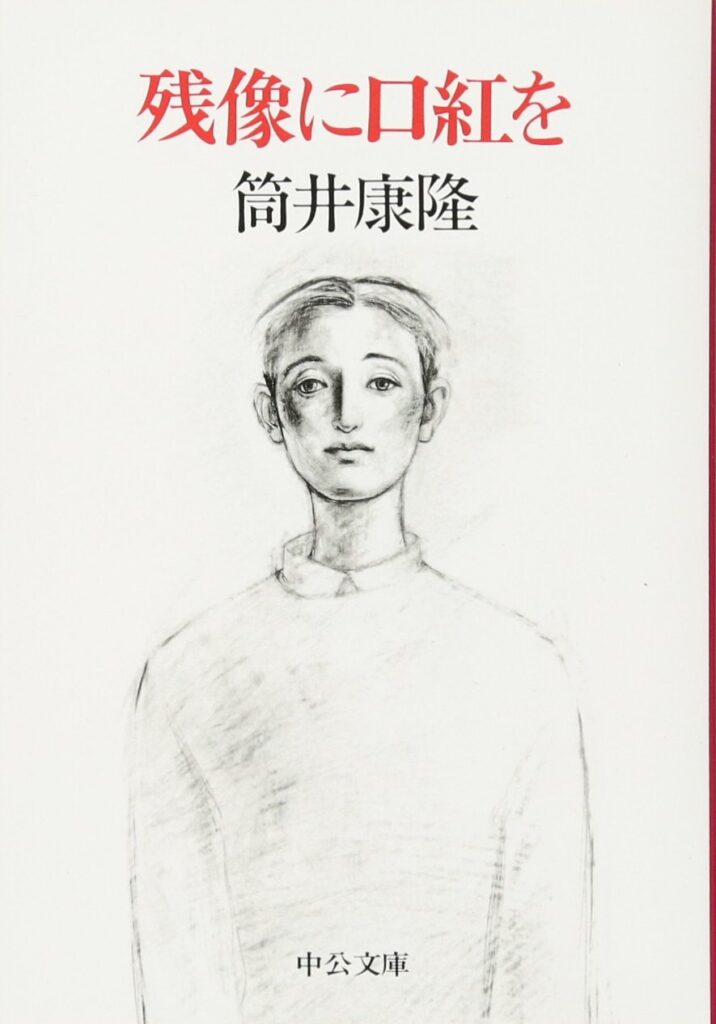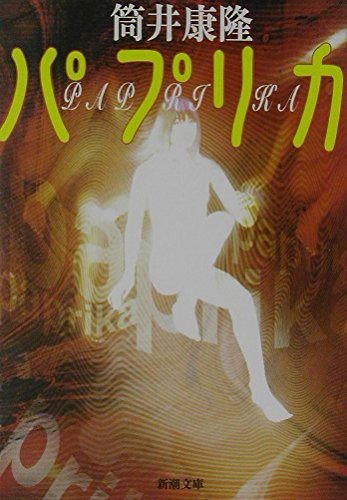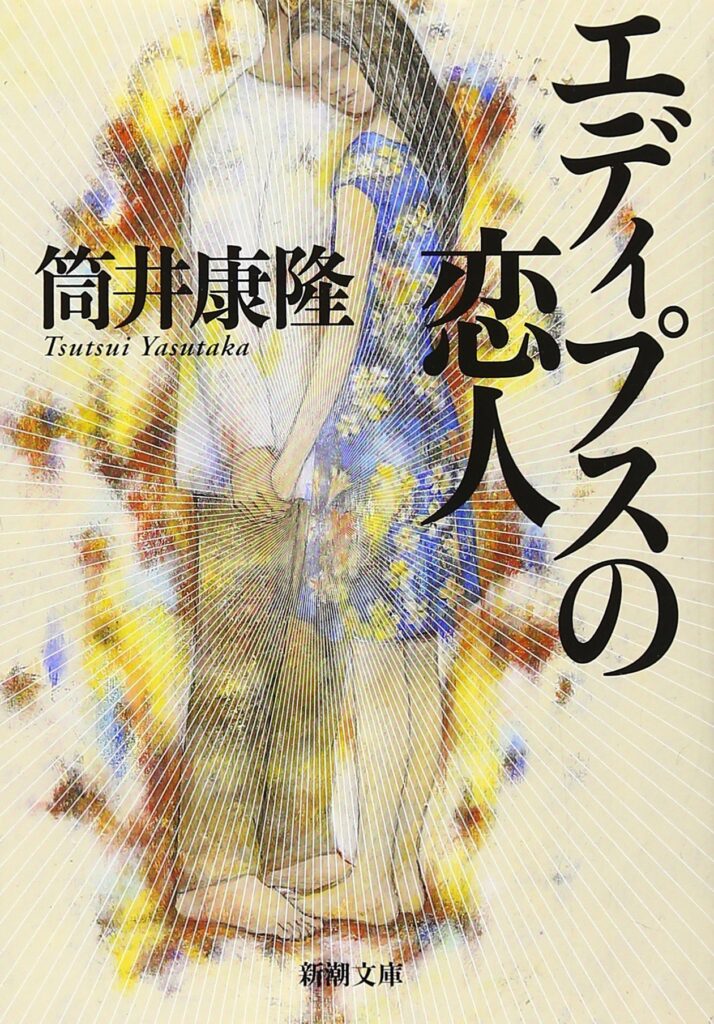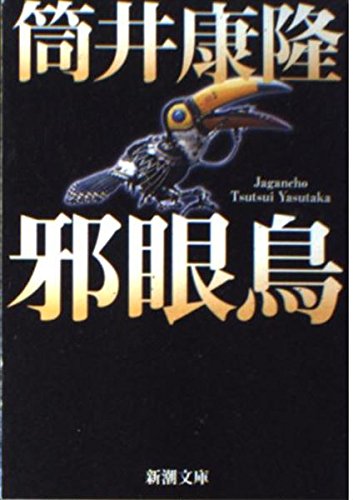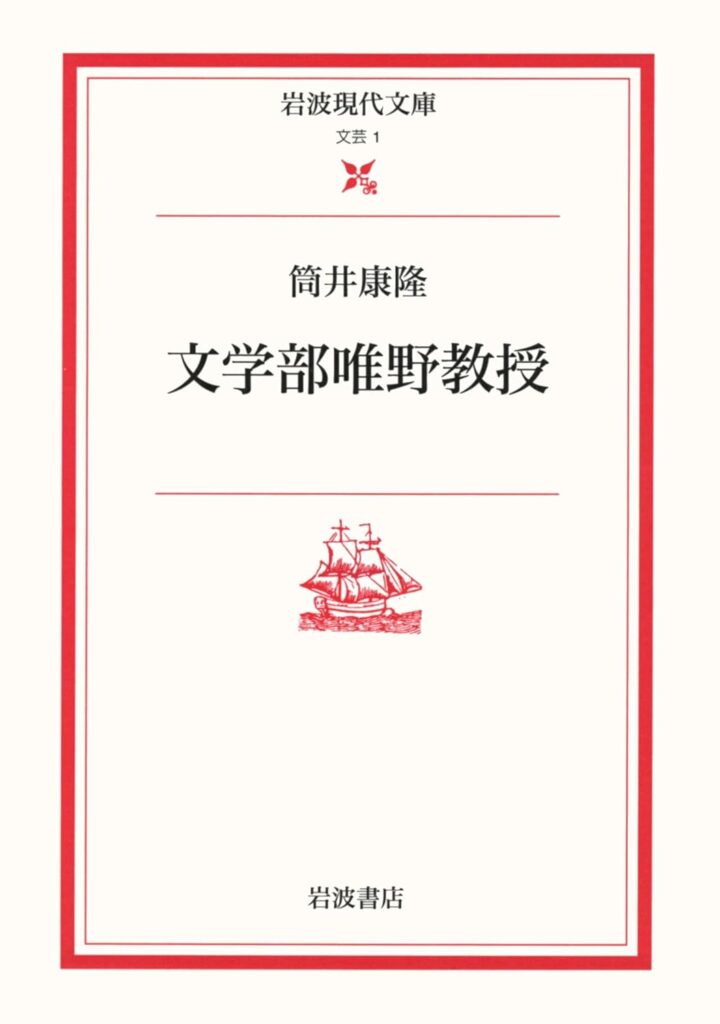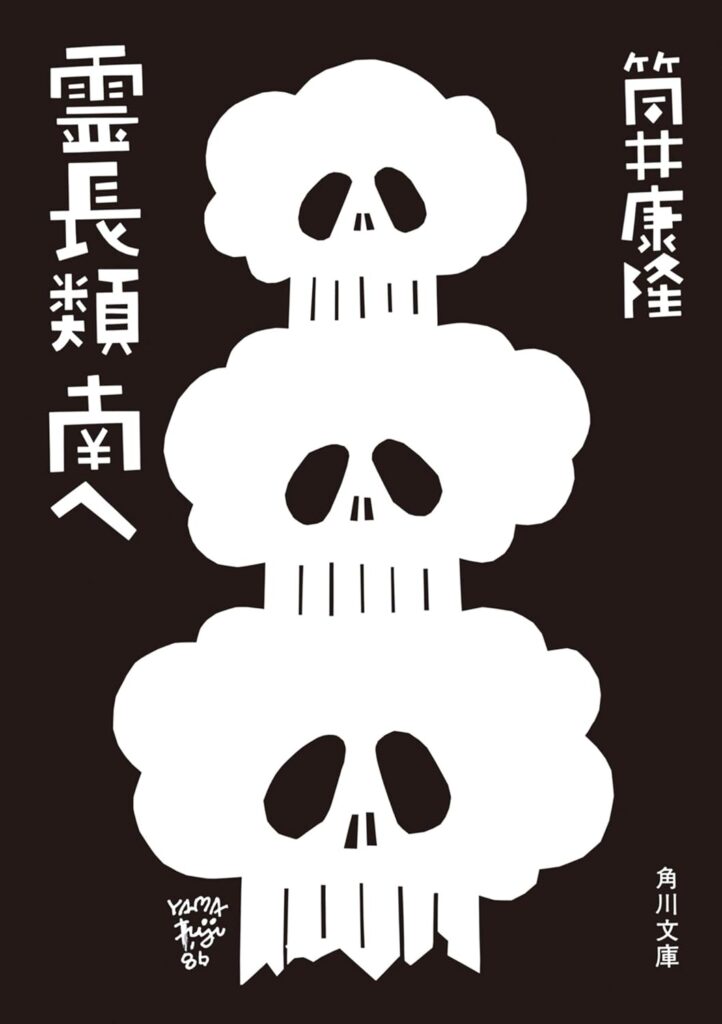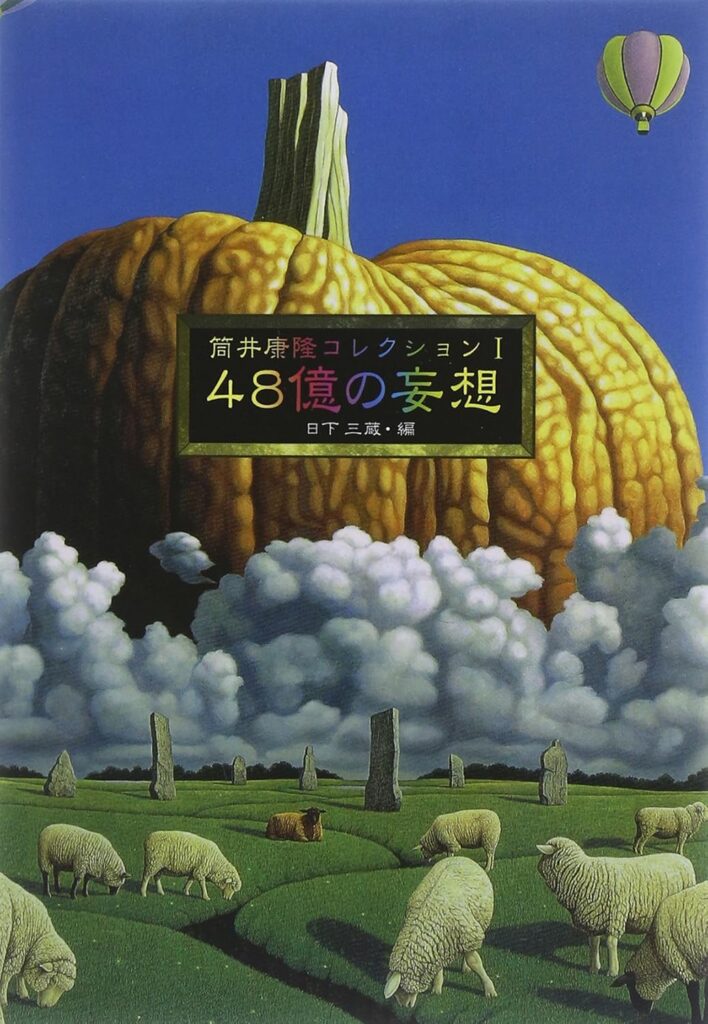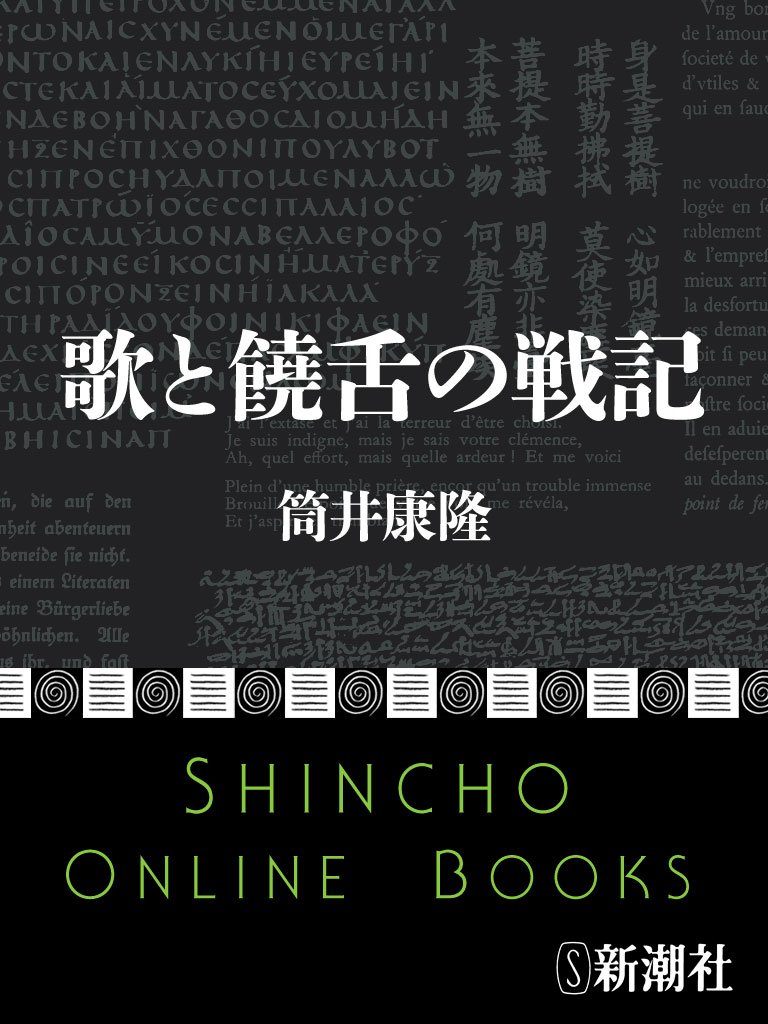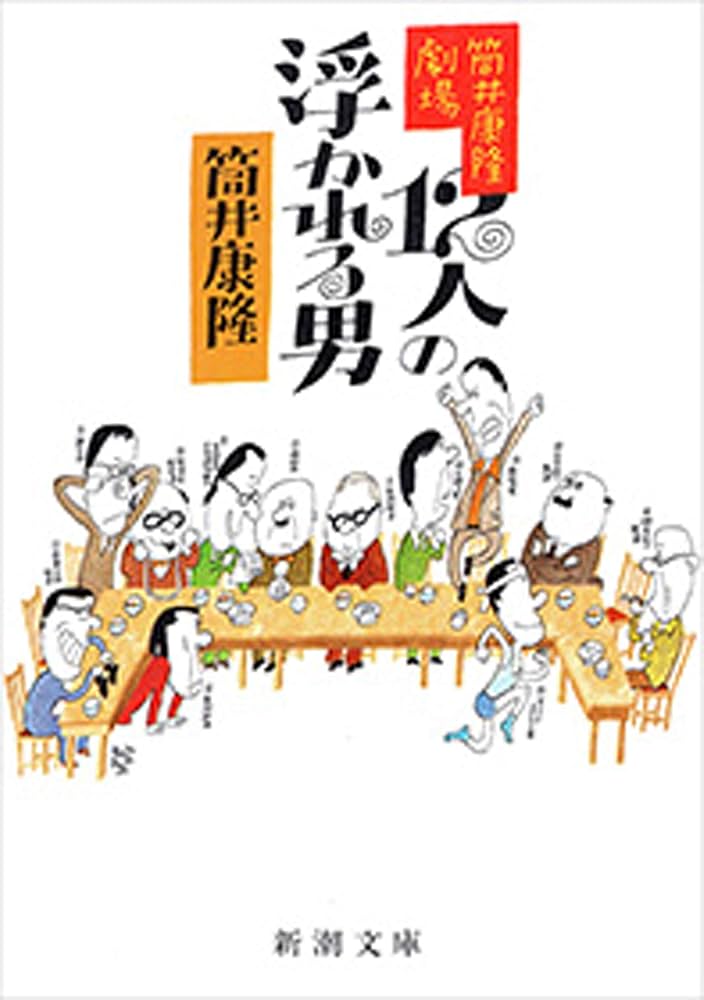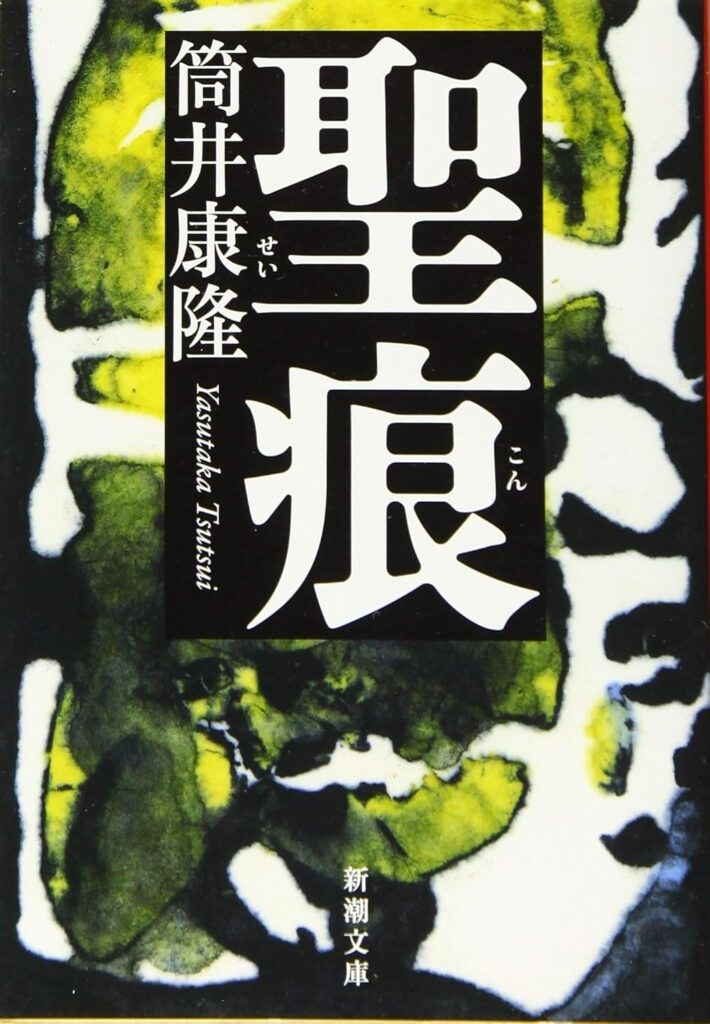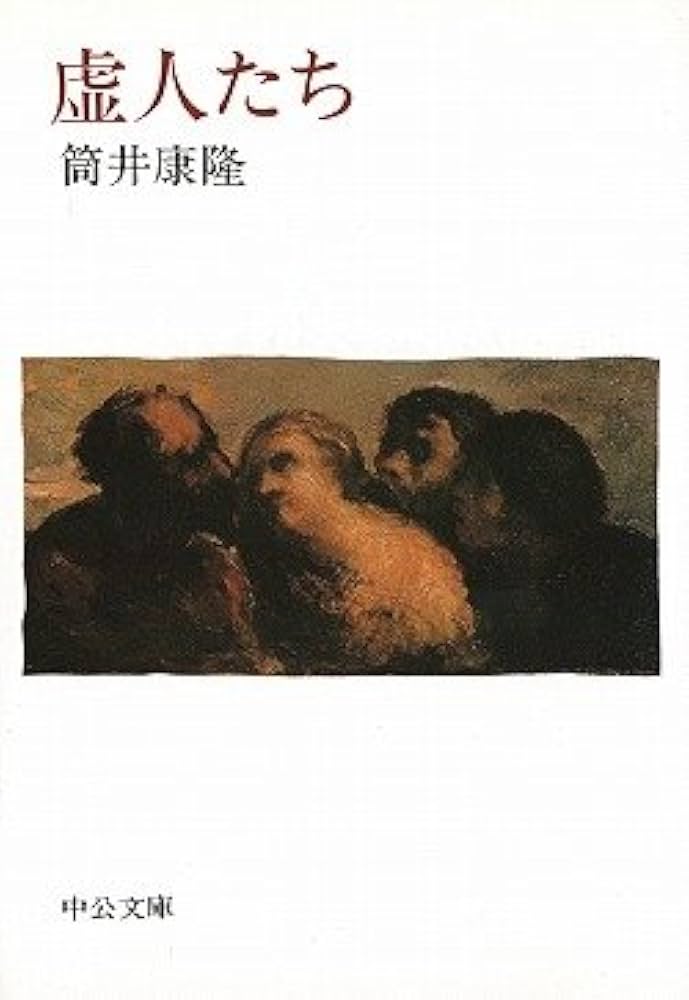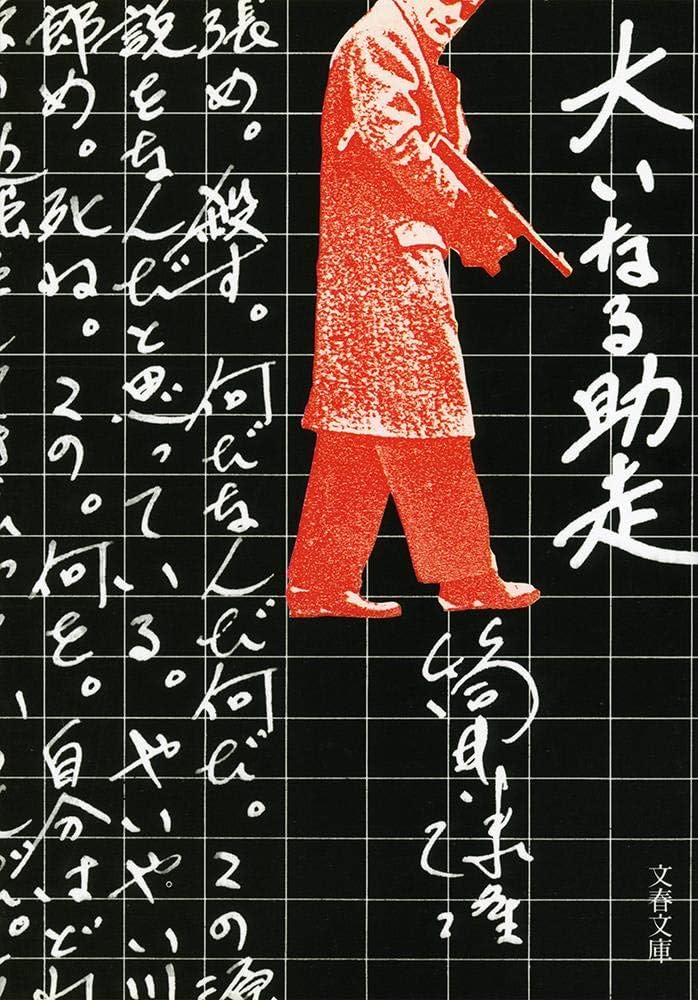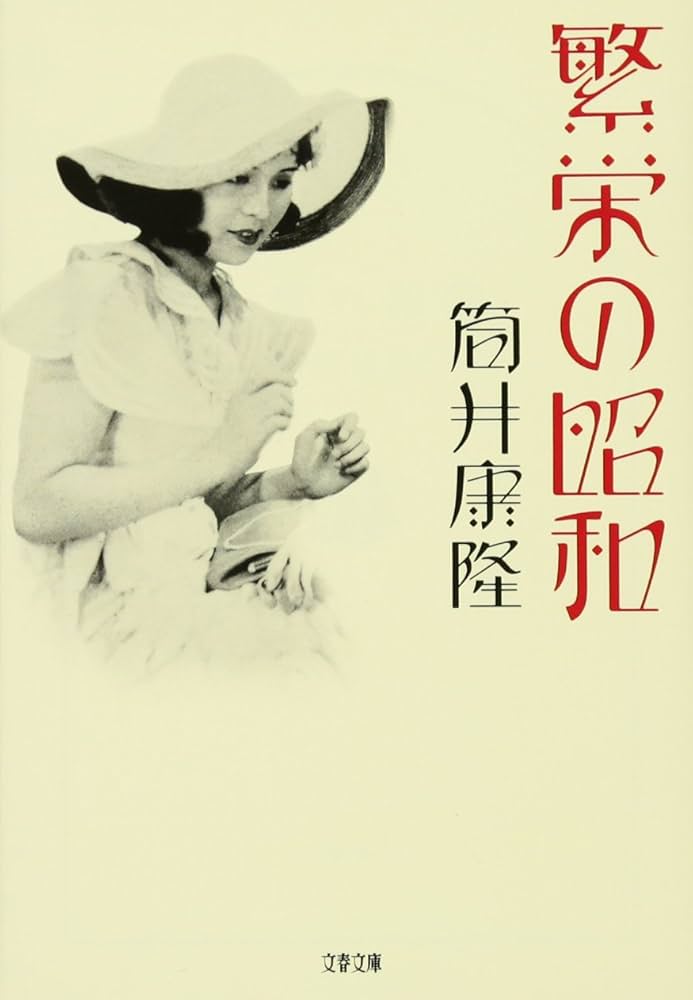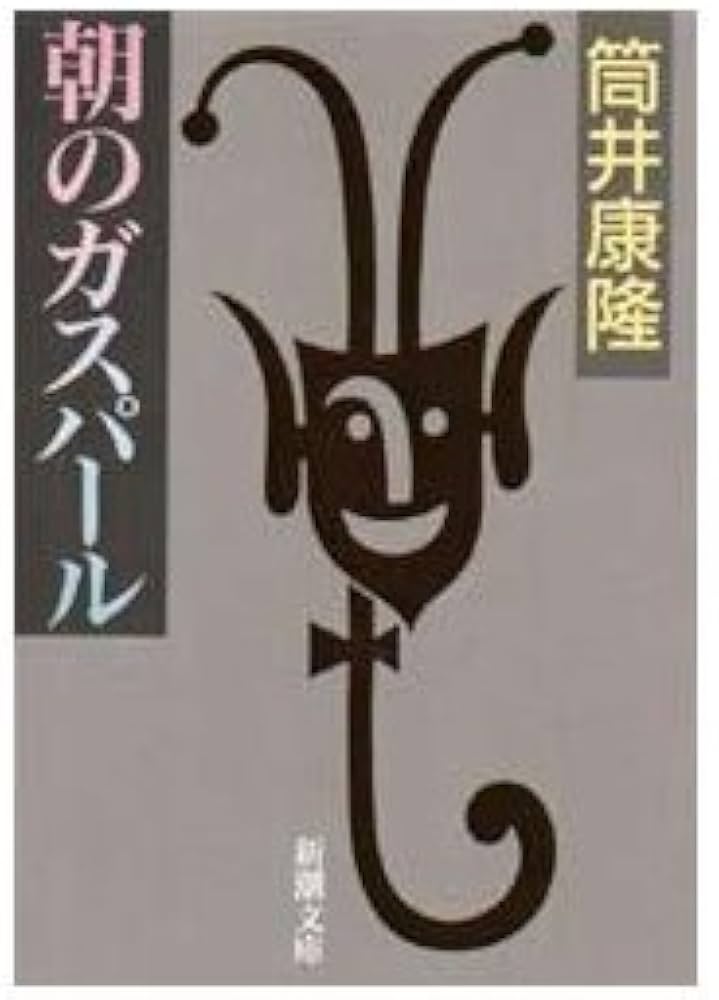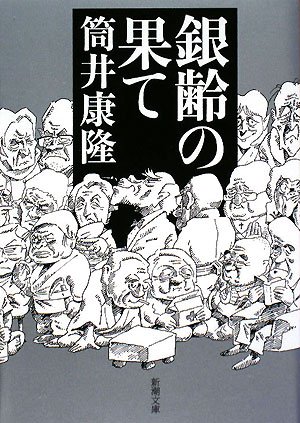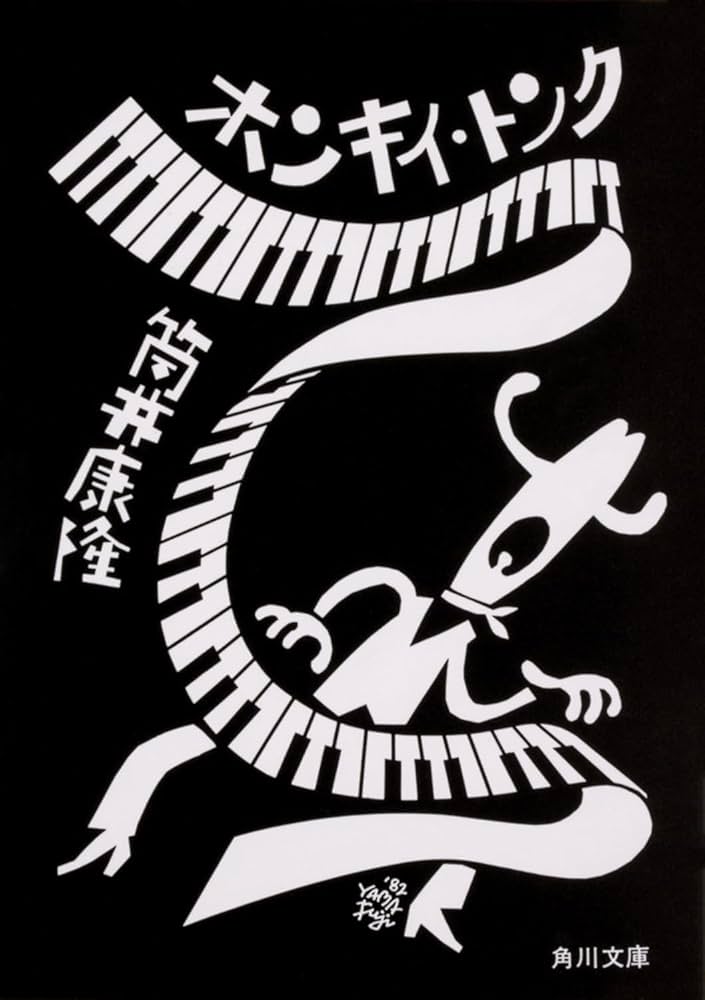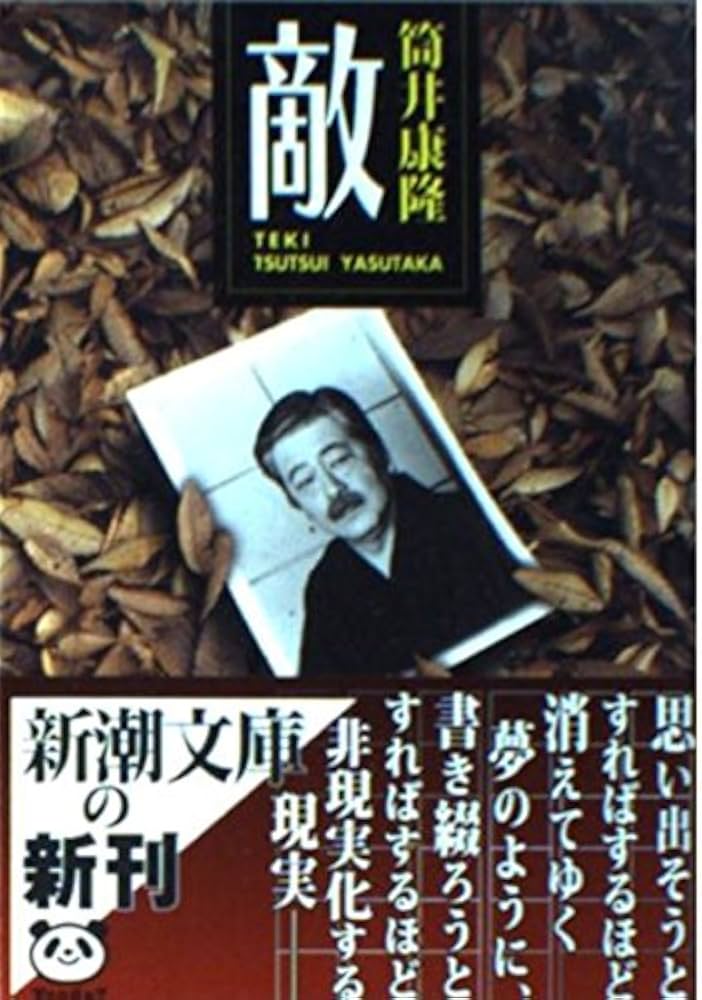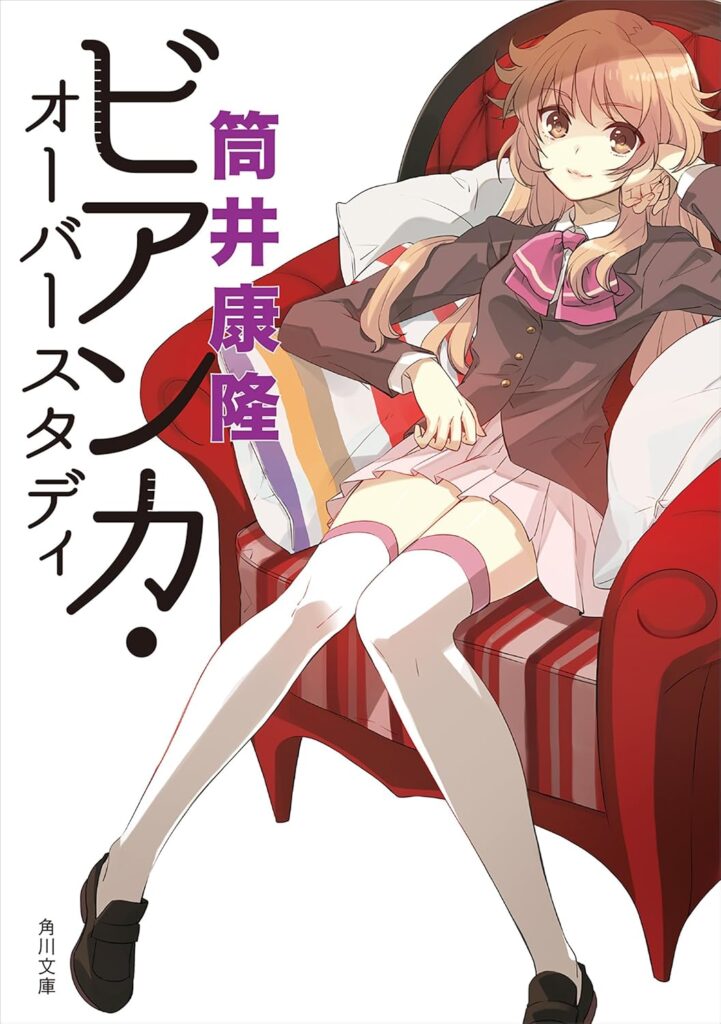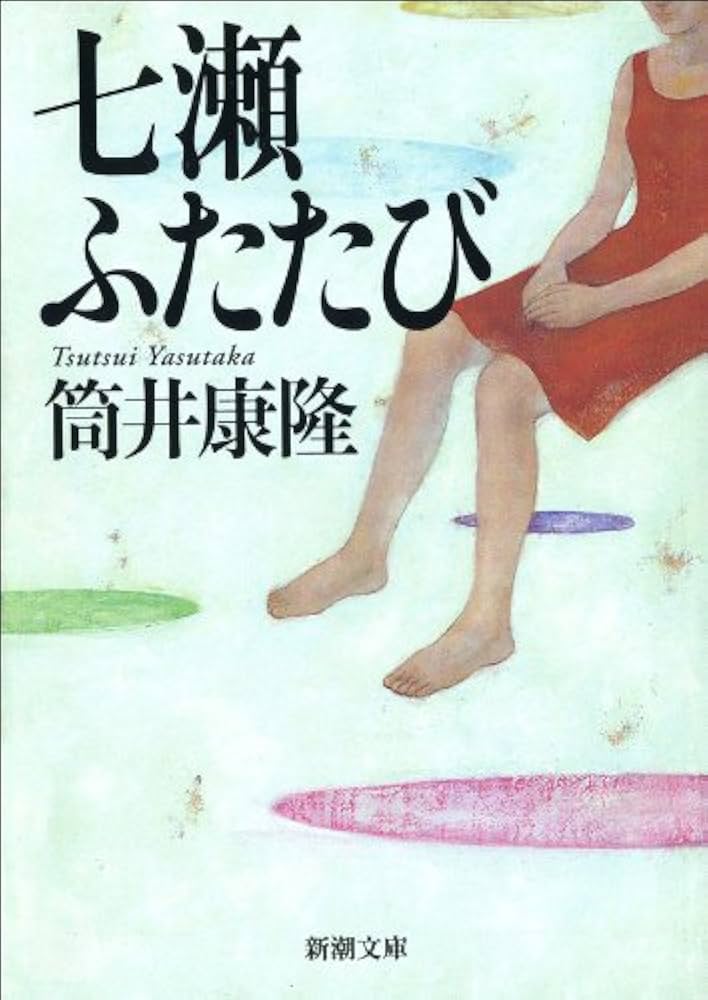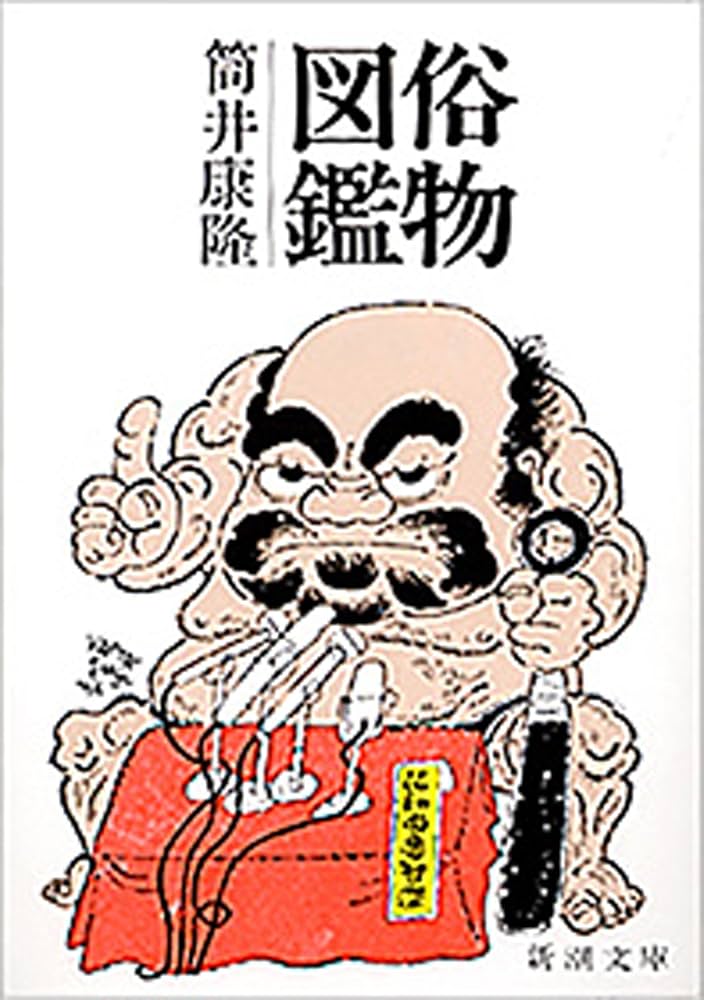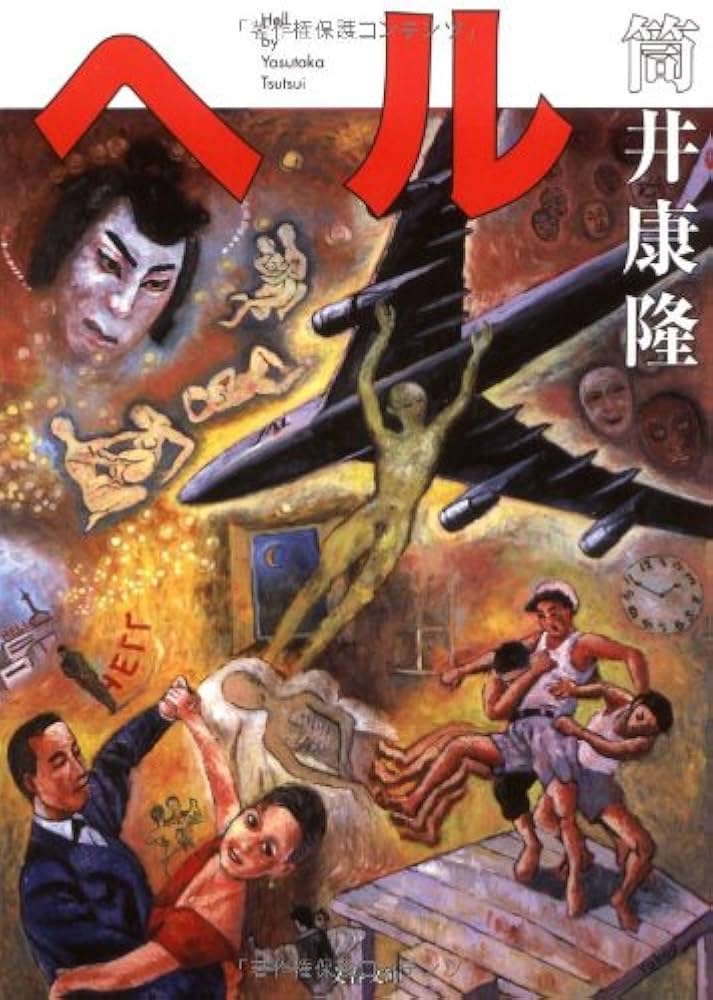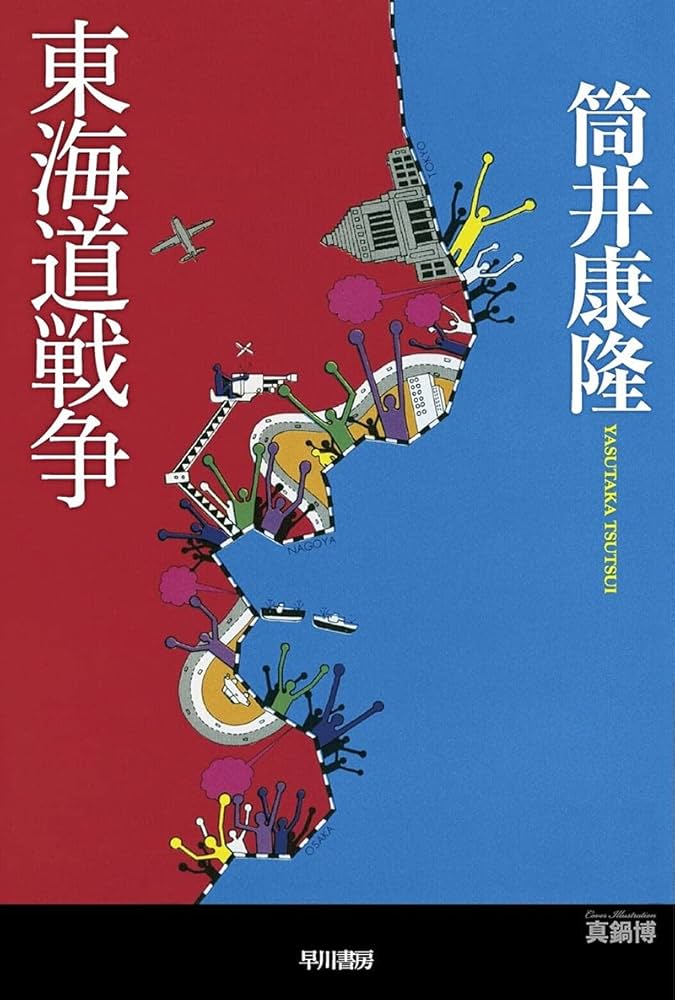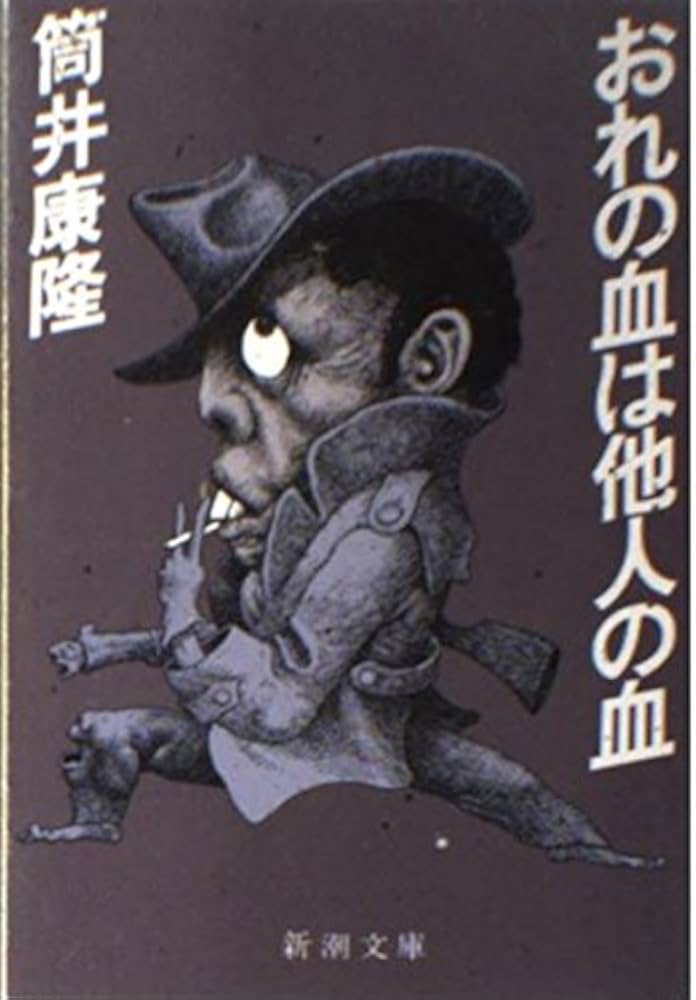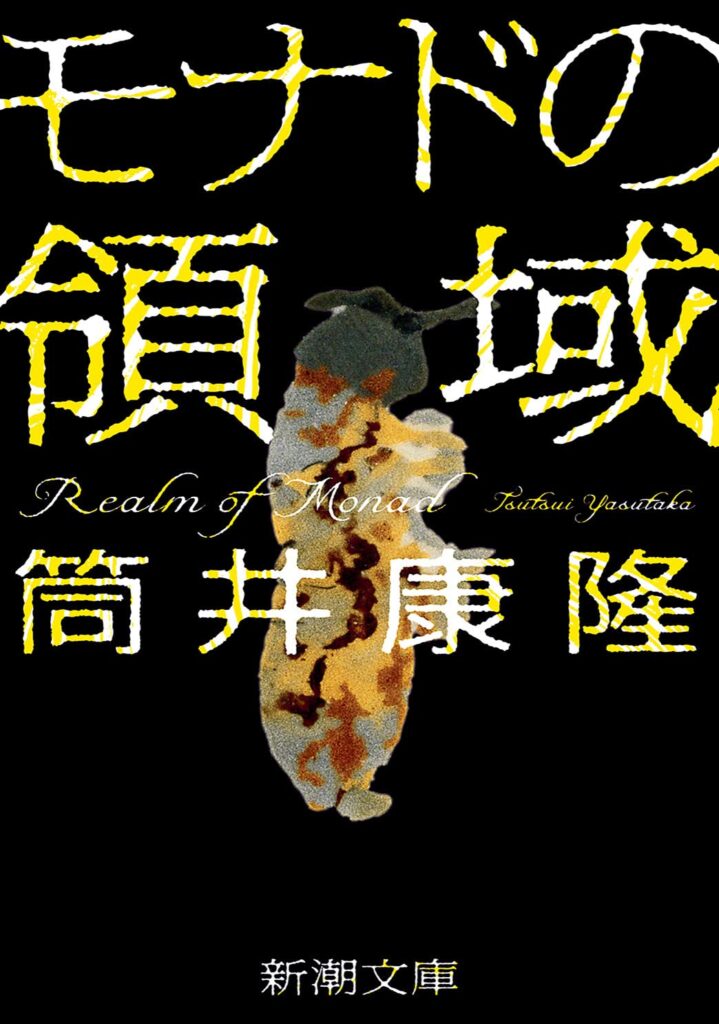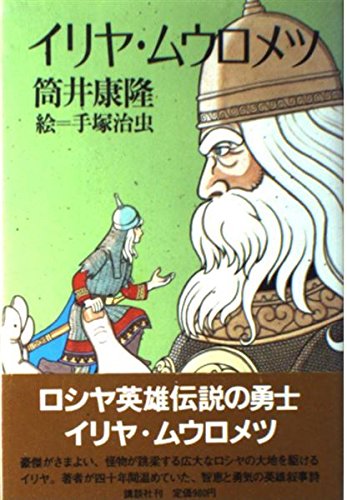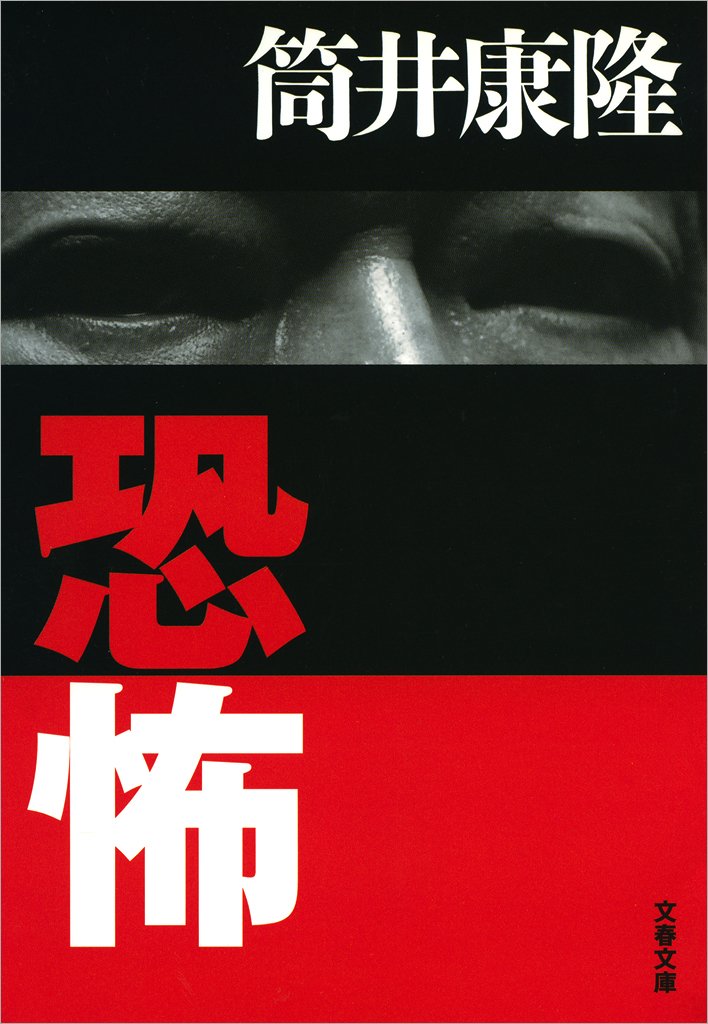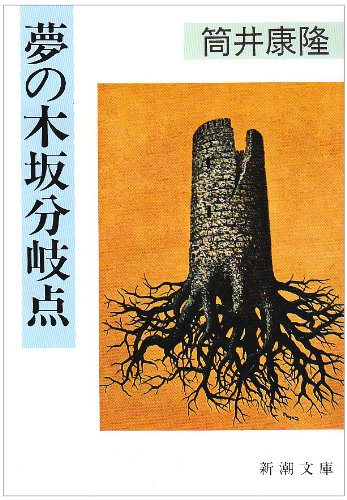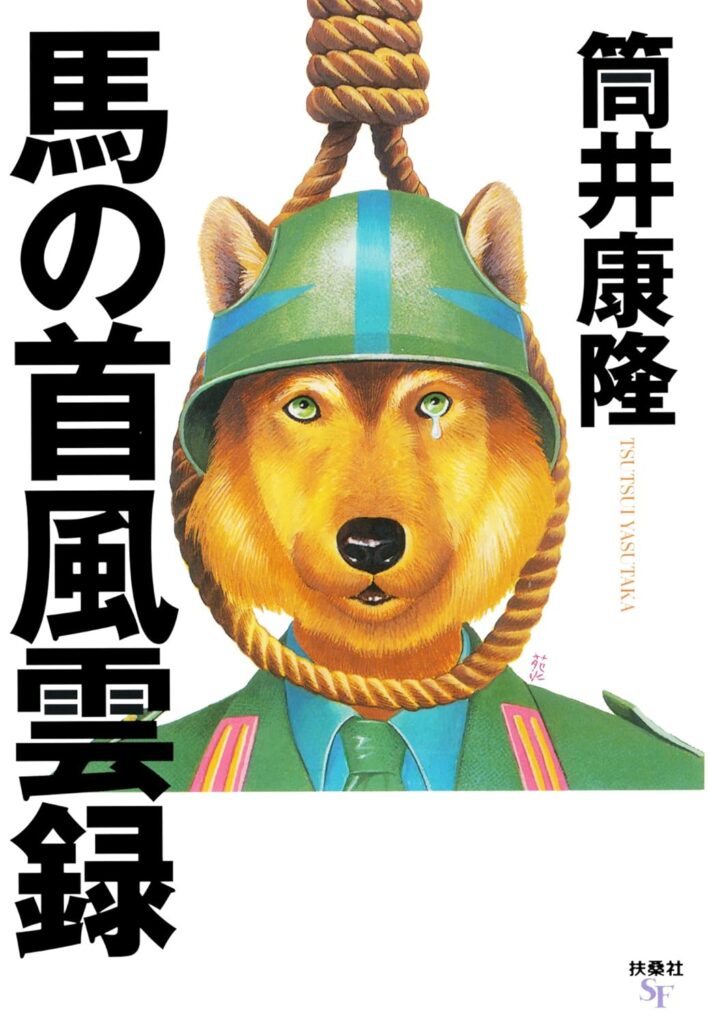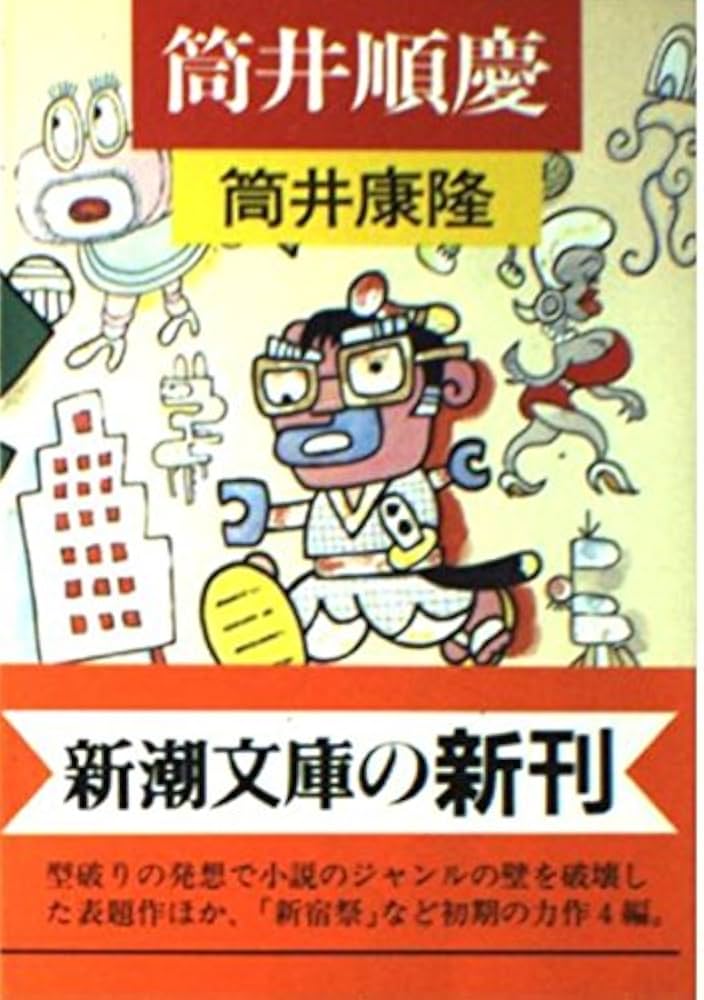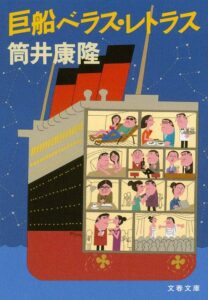 小説『巨船ベラス・レトラス』のあらすじを核心に触れつつ紹介します。長文で深く掘り下げた考察もしていますので、どうぞお付き合いください。
小説『巨船ベラス・レトラス』のあらすじを核心に触れつつ紹介します。長文で深く掘り下げた考察もしていますので、どうぞお付き合いください。
筒井康隆氏のこの作品は、文学界に鋭い問いかけを投げかける意欲作です。一見すると奇妙な出来事が連続する物語ですが、その根底には現代の文学が抱える問題や、作者自身の文学に対する情熱が描かれています。読者は、文学の価値とは何か、そして文学はどこへ向かうべきなのかという問いに、否応なく向き合うことになるでしょう。
文学の世界を舞台に、常識を超えた展開が繰り広げられる本作は、まさに筒井文学の真骨頂と言えます。予測不能なストーリーの先に、一体何が待ち受けているのか。その全てを、これから紐解いていきます。
この作品は、単なるフィクションとして読むだけでなく、文学そのものへの批評としても読み解くことができる奥深い一冊です。ぜひ最後まで読み進めて、その魅力の一端に触れてみてください。
小説『巨船ベラス・レトラス』のあらすじ
物語は、文学界に衝撃が走る事件から幕を開けます。イタリアン・カフェで開催されていた「パンクロックと文学の会」で、爆弾騒ぎが発生し、観客が死傷するのです。この事件で逮捕されたのは、富山県の鉄工所に勤める29歳の同人誌作家、鮪勝矢。彼は、大御所作家や大手出版社を逆恨みした末の凶行に及んだとされ、文壇に大きな波紋を広げます。
文学新人賞のパーティー会場では、この鮪の事件が専らの話題となっていました。その会場でひときわ注目を集めるのは、わずか20歳にして新進気鋭の小説家として頭角を現す村田澄子です。彼女は2年前まで名門高校に通う女子高校生でしたが、文芸部に嫌気が差し退学。現在は、盲目の詩人である七尾霊兆に師事しています。
七尾は、サングラスをかけずに象牙のステッキを手に、村田に付き添われてパーティーに現れます。彼は前衛詩人であり、数多くの文学賞の選考委員を兼ね、現在は文芸雑誌『ベラス・レトラス』を舞台に新作を発表しています。『ベラス・レトラス』は、パソコンソフト会社で莫大な財産を築いた社長、狭山銀次が創刊した文芸誌です。この雑誌には、詩人だけでなく革新的な作風の推理作家やミステリー作家も寄稿しており、原稿料は1枚5万円という破格の値段でした。
七尾は来場者との歓談の最中に次回作の構想を思いつき、頭の中で練り上げていくうちにすっかり夢中になってしまいます。詩作に没頭するあまり、自分がどこにいるのか分からなくなるのは、彼にとって初めてのことではありませんでした。周囲のざわめき、話し声、ナイフやフォークが皿にぶつかる音、高級な料理の匂い、そして揺れる足元。これらの要素から、彼は自分が巨大な客船のレストランにいることを察します。
ラウンジには多くの文壇関係者が集まっていましたが、誰もこの船がどこに向かっているのか知りません。上甲板の揺り椅子で、船内で知り合った乗客と会話を楽しんでいると、聞き覚えのある澄子の声が聞こえてきます。七尾は、自分と同じくこの船のオーナーである狭山社長に招かれた愛弟子と共に、ディナー会場へ向かうのでした。
驚くべきことに、船のボイラー室には、あの事件で死刑判決を受け拘置所にいるはずの鮪勝矢までが、火夫の格好をして石炭や売れ残りの新刊書を釜の中に投げ入れていました。高級なワインと豪華なステーキに舌鼓を打つ七尾たちの前で、主催者の狭山は文学の海を突き進んでいくことを宣言します。食事の後、船内を散策していた澄子が偶然デッキチェアで出会ったのは、とある出版社による著作権侵害行為を告発するために現れた、この作品の作者、筒井康隆氏その人でした。船内の広々とした劇場には乗船客から乗組員までほぼ全員が集まり、侃々褞々の文学論争が巻き起こります。いつの間にかいなくなってしまった澄子は、船の舳先で女神像になっているのでした。
小説『巨船ベラス・レトラス』の長文感想(ネタバレあり)
筒井康隆氏の『巨船ベラス・レトラス』は、文学というものが現代においてどのような位置づけにあるのか、そしてその未来はどこへ向かうべきなのかという、深遠な問いを投げかける作品です。この物語は、単なる奇想天外な展開に留まらず、文学界が抱える閉塞感、商業主義への傾倒、そして真の創造性とは何かについて、私たち読者に再考を促します。
まず、冒頭で描かれる鮪勝矢による爆弾テロ事件は、文学に対する絶望と、その絶望が暴走した結果として現れる破壊衝動の象徴です。彼は、純粋な文学への情熱を抱きながらも、大手出版社や既存の文壇に認められない不満を募らせ、最終的には凶行に及びます。この事件は、現代文学が抱える「売れる」ことへの圧力と、その中で埋もれていく才能、そして文学本来の価値を見失いつつある現状を、痛烈に批判しているかのようです。文学が社会に影響を与える力が弱まり、エンターテイメントの一種として消費される傾向が強まる中で、鮪の行動は、文学の存在意義を暴力的なまでに問い直す行為と言えるでしょう。
村田澄子と七尾霊兆の登場は、文学の異なる側面を示しています。村田は若き新進作家であり、その才能は文壇の注目を集めています。彼女は、既存の枠組みにとらわれず、新しい文学を創造しようとする意欲の象徴かもしれません。一方、盲目の詩人である七尾は、視覚に頼らず言葉の本質を捉えようとする、純粋な文学の探求者です。彼が『ベラス・レトラス』という雑誌に作品を発表していることは、その雑誌が既存の文壇とは一線を画し、真に革新的な文学を求める場であることを示唆しています。彼らの存在は、商業主義に染まりつつある文学界に一石を投じる、希望の光のようにも見えます。
そして、この物語の中心となる存在が、実業家である狭山銀次が創刊した文芸雑誌『ベラス・レトラス』と、彼が所有する「巨船」です。狭山は、文学とは無縁に思えるIT業界で成功を収めた人物でありながら、文学に対して並々ならぬ情熱を抱いています。彼が莫大な私財を投じて『ベラス・レトラス』を創刊し、破格の原稿料を支払うのは、文学の価値を「金銭」という形で示し、文学者たちを経済的な制約から解放しようとする試みと解釈できます。しかし、その一方で、文学の価値を金銭で測ることへの疑問も生じさせます。文学は、金銭的な価値を超えた、より精神的な豊かさをもたらすものではないのか、と。
「巨船」という設定は、非常に象徴的です。文学者たちが、どこに向かっているのかも知らぬまま、広大な大海原へと旅立つという状況は、現代文学が「漂流」している状態を表しているかのようです。既存の価値観や規範が揺らぎ、文学の方向性が見失われつつある中で、彼らは新しい文学の可能性を探し求めて、あてのない旅に出るのです。船内での豪華な食事や生活は、文学者が享受するべき「特権」のように描かれながらも、その実態は、外界から隔絶された空間で、文学が孤立しつつある状況を暗示しているのかもしれません。文学は、大衆から離れ、閉鎖的な世界に閉じこもっているのではないか、という問いを投げかけているのです。
ボイラー室で石炭と共に売れ残りの新刊書を燃やす鮪勝矢の姿は、現代文学の現状を痛烈に風刺しています。彼の行為は、文学作品が商品として消費され、売れ残れば捨てられるという、商業主義の残酷さを露呈させています。文学が本来持つべき価値、すなわち思想や感情を伝え、人々の心を揺さぶる力は、売上という数字に埋もれてしまっているのです。鮪の存在は、文学が単なる商品として扱われることへの怒りと、それに抗う姿勢を示しているように見えます。
物語のクライマックスで、作者である筒井康隆氏自身が登場する場面は、この作品の最も挑発的な部分の一つです。彼が、出版社による著作権侵害を告発するために現れるという設定は、文学者が自身の作品を守ることの困難さ、そして文学が直面する倫理的な問題を示唆しています。作者自身の登場は、この物語が単なる虚構ではなく、文学を巡る現実の闘いを描いていることを強く印象付けます。そして、船内の劇場で巻き起こる侃々褞々の文学論争は、文学者たちが文学の未来について真剣に議論する姿を描いていますが、その結論は見出されません。文学がどこへ向かうべきなのか、その答えはまだ見つかっていないのです。
最後に、村田澄子が船の舳先で女神像になっているという結末は、非常に示唆に富んでいます。彼女は、新しい文学の担い手として期待されながらも、最終的には「女神」として祀り上げられてしまいます。これは、文学が崇高なものとして敬われながらも、現実の社会から乖離し、手の届かない存在になってしまうことへの警鐘かもしれません。文学が、大衆から離れて孤立し、一部の専門家や愛好家だけのものになってしまうことへの危機感が込められているように感じられます。
『巨船ベラス・レトラス』は、文学が置かれている現状を、時に残酷なまでに、時に滑稽なまでに描き出しています。商業主義に翻弄される文学、既存の価値観に縛られる文学、そしてその中で新しい可能性を模索する文学者たち。筒井康隆氏は、これらの要素を巧みに組み合わせることで、文学そのものへの愛憎と、その未来への深い考察を提示しています。この作品は、文学を愛する者にとって、あるいは文学に関心を持つ者にとって、避けては通れない一冊と言えるでしょう。
筒井氏の作品は、常に既存の概念や常識を打ち破ろうとする試みに満ちています。この『巨船ベラス・レトラス』も例外ではありません。彼は、文学の「聖域」に土足で踏み込み、その内側にある矛盾や問題を容赦なくえぐり出します。しかし、それは決して文学への批判だけではありません。むしろ、文学への深い愛情と、その再生への願いが込められていると私は感じています。文学が、読者の心を揺さぶり、社会に影響を与える力を取り戻すためには、既存の枠組みを打ち破り、新たな地平を切り開く必要があるという、筒井氏からのメッセージが込められているのではないでしょうか。
この物語は、私たちに問いかけます。文学は、どこへ向かうのか?そして、私たちは文学に何を求めるのか?その答えは、一人ひとりの読者の心の中にこそ存在するのかもしれません。
まとめ
筒井康隆氏の『巨船ベラス・レトラス』は、文学界の現状と未来に対する鋭い洞察に満ちた作品です。鮪勝矢のテロ行為に始まり、文学者たちが乗る謎めいた「巨船」での旅、そして作者自身の登場に至るまで、予測不能な展開が続きます。
この物語は、文学の商業化、才能の埋没、そして文学が社会に与える影響力の低下といった、現代文学が抱える様々な問題点を浮き彫りにしています。しかし、単なる批判に終わらず、新しい文学の可能性を探求しようとする希望も感じさせる作品です。
『ベラス・レトラス』という雑誌、そしてそれを創刊した狭山銀次の存在は、文学の新たな道を模索する試みとして描かれています。しかし、その試みが必ずしも成功しているとは言えず、文学が直面する困難さを物語っています。
最終的に、この作品は読者に対し、文学とは何か、そして文学はどこへ向かうべきなのかという問いを投げかけます。文学を愛する全ての人にとって、深く考えさせられる一冊であることは間違いありません。