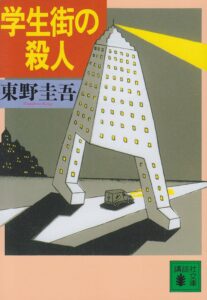 小説「学生街の殺人」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏の初期作品群に数えられる本作、ある意味で荒削りとも言えるかもしれませんが、後の片鱗を感じさせる部分も散見される一作です。舞台は、時代の移ろいとともに活気を失った旧学生街。そこで起こる連続殺人事件を軸に、若者の将来への不安や、人間関係の希薄さが描かれます。
小説「学生街の殺人」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏の初期作品群に数えられる本作、ある意味で荒削りとも言えるかもしれませんが、後の片鱗を感じさせる部分も散見される一作です。舞台は、時代の移ろいとともに活気を失った旧学生街。そこで起こる連続殺人事件を軸に、若者の将来への不安や、人間関係の希薄さが描かれます。
物語の中心人物は、大学卒業後も目的を見出せず、ビリヤード場でアルバイトをして日々を過ごす津村光平。彼の周囲で起こる不可解な事件、そして恋人の死。彼は否応なく事件の渦中へと巻き込まれていきます。本稿では、その事件の顛末と、そこに隠された人間模様について、少々辛口な視点も交えつつ、詳しく語っていきましょう。
この記事には、事件の真相や犯人に関する記述が含まれています。まだ本作を読んでいない方、あるいは新鮮な気持ちで謎解きを楽しみたい方は、この先を読むのをお控えください。まあ、それでも構わないという奇特な方だけ、私の語りにお付き合いいただければ幸いです。
小説「学生街の殺人」のあらすじ
物語の舞台は、大学の移転によりかつての賑わいを失った寂れた旧学生街。主人公の津村光平は、大学は卒業したものの、明確な目標もなく、親には大学院に進学したと嘘をついて仕送りを受けながら、ビリヤード場「青木」でアルバイトとして働いています。彼の日常は、特に代わり映えのしない、ある種の停滞感の中にありました。
そんなある日、光平の同僚である松木が、自室で何者かに殺害されているのが発見されます。松木は脱サラしてこの街に来た男でしたが、自身の過去を多く語らず、光平にとっても謎の多い人物でした。彼が死の直前に光平に残した「俺はこの街が嫌いなんだ」という言葉が、不気味に響きます。警察の捜査が始まりますが、犯人に繋がる手がかりはなかなか見つかりません。
第一の事件から間もなく、第二の悲劇が起こります。光平の恋人である広美が、彼女の働いていたバーの控室で殺害されてしまうのです。しかも、その現場は密室状態でした。広美もまた、光平にとっては知らない部分が多い女性でした。特に、毎週火曜日に彼に内緒である施設に通っていたこと、それが障害を持つ子供たちのための施設だったことを、光平は彼女の死後初めて知るのでした。
立て続けに起きた二つの殺人事件。関連はあるのか、それともないのか。光平は、広美の妹である悦子と共に、広美が通っていた施設を探り始めます。なぜ彼女はそこへ通っていたのか、それが事件とどう結びつくのか。しかし、調査を進める中で、今度はその施設の園長までもが殺害されるという第三の事件が発生。複雑に絡み合う事件の糸をたどりながら、光平は思いもよらない真実へと近づいていくことになります。
小説「学生街の殺人」の長文感想(ネタバレあり)
さて、東野圭吾氏の「学生街の殺人」について、少々踏み込んだ話をさせていただきましょうか。この作品、世間的な評価は必ずしも高いとは言えないようです。まあ、それも致し方ない面はあるかもしれません。後の氏の作品群に見られるような、読者の心を鷲掴みにするような強烈なギミックや、社会問題を鋭くえぐるような深みは、まだこの段階では完成されていない、そう言えるでしょう。しかし、だからといって凡作と切り捨てるのは早計というものです。この作品には、この作品なりの味わい、そして後の成功を予感させる確かな萌芽が見て取れます。
まず、舞台設定が秀逸です。大学の移転によって寂れてしまった旧学生街。かつての活気は失われ、どことなく物悲しい雰囲気が漂う。この閉塞感のある空間が、物語全体に独特の陰影を与えています。時代の変化に取り残されたような街並みは、まさに主人公・津村光平の心象風景そのものと言えるかもしれません。大学を卒業しても将来の展望を描けず、モラトリアム期間を引き延ばすかのようにアルバイト生活を続ける彼。その姿は、発表当時の1990年代初頭の若者像を反映しているとも言えますが、不思議と現代にも通じる普遍的な悩みとして響いてきます。自分の進むべき道が見えない不安、社会に対する漠然とした不満。そういった若者の心理描写は、なかなかに的を射ているのではないでしょうか。
しかし、その主人公・光平の人物造形については、少々物足りなさを感じざるを得ません。彼は事件の第一発見者となり、恋人を失い、自ら真相を探ろうとするのですが、どうにも主体性に欠ける印象が拭えないのです。状況に流され、周囲の人間の言葉に影響されやすい。もちろん、平凡な若者が突然事件に巻き込まれた際のリアルな反応、と言われればそうなのかもしれませんが、ミステリの探偵役としては、やや魅力に乏しいと言わざるを得ません。彼がもっと強い意志や、独自の洞察力を見せてくれれば、物語はさらに引き締まったことでしょう。
事件の謎解き、いわゆるフーダニット(誰が犯人か)とハウダニット(どうやってやったか)の部分を見てみましょう。連続殺人、密室トリックと、ミステリの王道を行く要素が盛り込まれています。特に、第二の殺人における密室トリックは、古典的ながらも一定の工夫が見られます。ただ、全体を通して見ると、伏線の張り方や回収の仕方に、若干の粗削りさが感じられるのも事実です。犯人の意外性という点では、ある程度は成功していると言えるかもしれませんが、その動機や背景描写には、もう少し深みが欲しかったところ。特に、広美が隠していた秘密、障害者施設との関わりなどが、事件の核心に繋がっていく展開は悪くないのですが、その繋がり方がやや強引に感じられる部分もあります。
私がこの作品で特に興味深く感じたのは、人間関係の希薄さ、他者への無関心さというテーマです。光平は恋人である広美のことを、実はほとんど何も知らなかった。彼女が何を考え、何に悩み、どこへ通っていたのか。それは、二人の関係性が「お互い干渉しない」という暗黙のルールの上に成り立っていたからですが、その結果、彼は彼女の死の真相を探る上で、大きな壁にぶつかることになります。松木にしても、光平にとっては職場の同僚という以上の存在ではなく、彼の素性や悩みを知ろうともしなかった。この「知らなさ」が、事件をより複雑にし、光平を苦しめることになるのです。
現代社会においても、身近な人間のことをどれだけ理解しているかと問われれば、自信を持って答えられる人は少ないのではないでしょうか。表面的には繋がっていても、心の奥底では孤独を抱えている。そんな現代人の姿が、この学生街という閉鎖的な空間の中で、より際立って描かれているように感じます。広美が抱えていた秘密や、彼女がボランティアに通っていた理由。それは、彼女なりの過去との向き合い方であり、他者との繋がりを求める心の表れだったのかもしれません。しかし、最も身近なはずの光平は、そのサインを受け取ることができなかった。この断絶こそが、本作が内包する悲劇性の本質ではないでしょうか。
また、物語の終盤で明かされる、一連の事件の裏に隠されたもう一つの真実。これは、なかなか巧みな構成だと評価できます。犯人が判明した後も、どこか腑に落ちない感覚が残るのですが、最後の最後でその謎が解き明かされる。この二段構えの構造によって、読後感は単なる犯人当てミステリに留まらないものになっています。この辺りの構成力は、さすが東野圭吾氏と言えるでしょう。まるで迷宮に迷い込んだ鼠のように、光平は右往左往するばかりですが、最後に示される全体像は、ある種のやるせなさを伴いつつも、カタルシスを感じさせます。
全体として見れば、確かに粗削りな部分や、登場人物の魅力不足といった点は否めません。しかし、寂れた学生街という舞台設定の妙、若者の抱える普遍的な悩み、人間関係の希薄さというテーマ性、そして練られたプロット。これらが組み合わさることで、単なる暇つぶしのミステリ以上の読み応えを与えてくれる作品となっているのです。派手さはないかもしれませんが、じっくりと物語の世界に浸り、登場人物たちの心の機微に思いを馳せる。そんな読書体験を求める方には、 durchaus(ドゥルヒアウス:ドイツ語で「まったく」「完全に」)楽しめる一冊と言えるのではないでしょうか。光平が、一連の事件を経て、過去のしがらみを断ち切り、新たな一歩を踏み出すラストシーンは、ほろ苦いながらも、かすかな希望を感じさせます。まあ、彼がその後どうなったかは、知る由もありませんがね。
まとめ
さて、東野圭吾氏の「学生街の殺人」について語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。本作は、氏の初期作品ということもあり、後の洗練された作品群と比較すると、いささか見劣りする点があることは認めざるを得ません。しかし、寂れた学生街という舞台設定、若者の抱える普遍的な葛藤、そして巧みに構成されたミステリ要素は、決して侮れない魅力を持っています。
特に、登場人物たちの間の微妙な距離感、互いを知らないことから生じる悲劇は、現代社会にも通じるテーマであり、深く考えさせられるものがあります。主人公・光平の頼りなさには、もどかしさを感じるかもしれませんが、それもまた、等身大の若者の姿なのかもしれません。事件の真相、そして隠されたもう一つの真実が明かされた時、あなたはきっと、ある種の感慨を覚えることでしょう。
派手な展開や強烈な感動を求める読者には、少々物足りないかもしれません。しかし、じっくりと物語を味わい、人間心理の綾に触れたいと考えるならば、手に取る価値は十分にあると言えます。まあ、結局のところ、本を読むという行為は個人の趣味嗜好に左右されるものです。私のこの語りが、あなたの選択の一助となれば幸いですが、そうでなくとも、それはそれで仕方のないことでしょう。
































































































