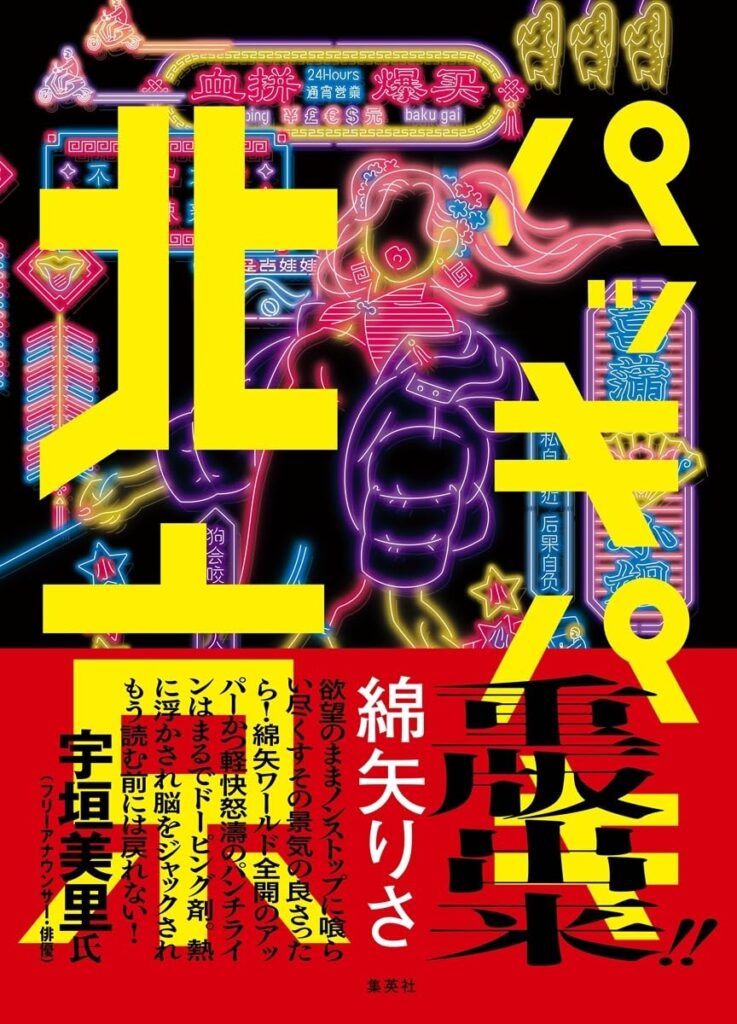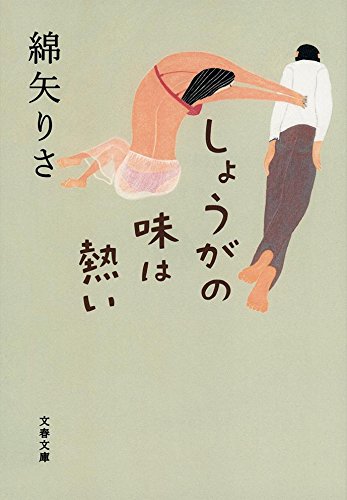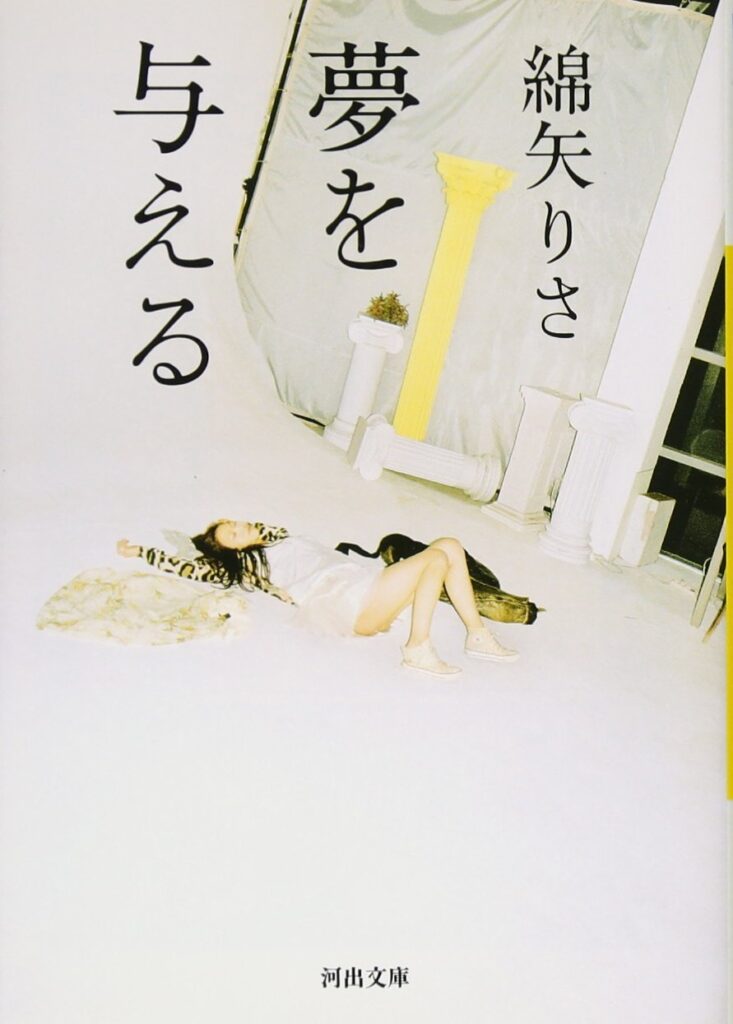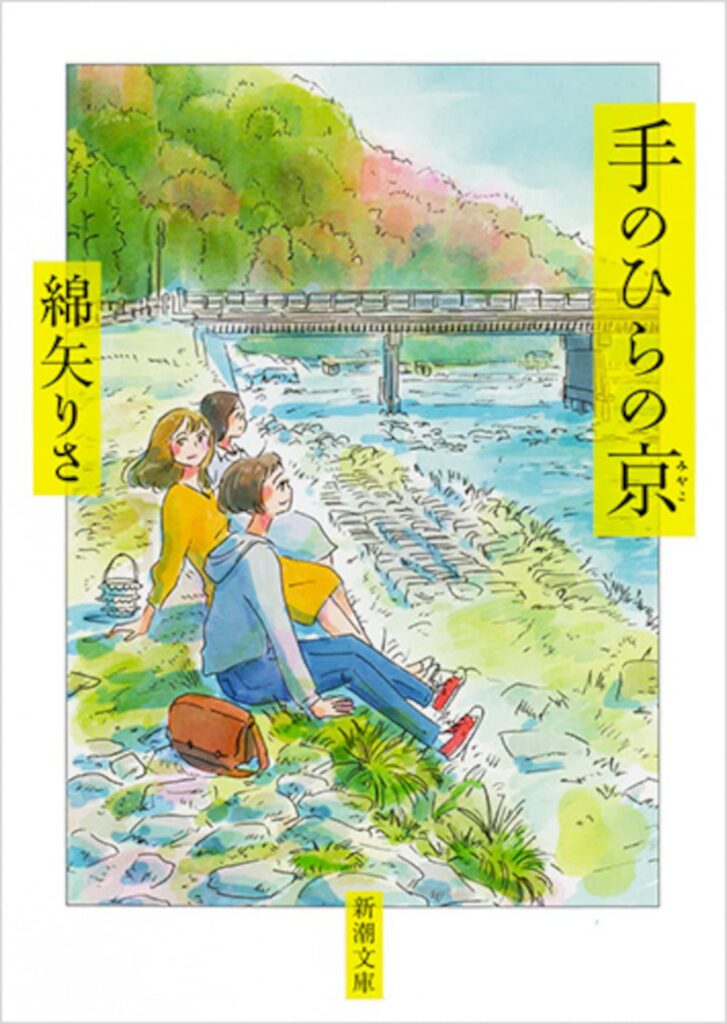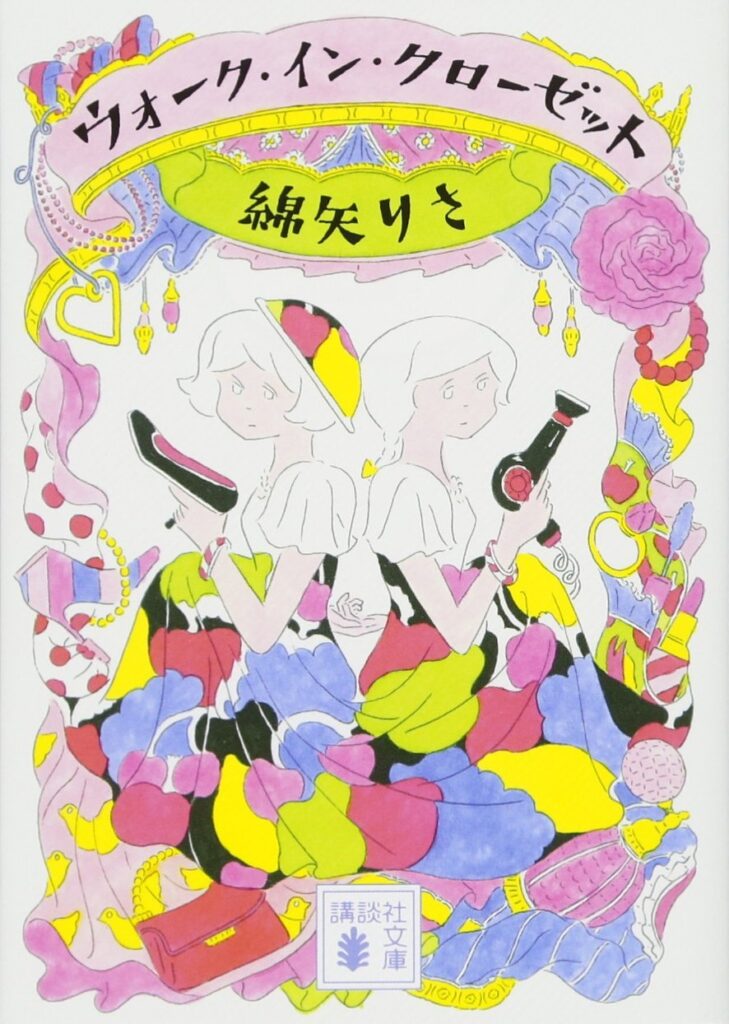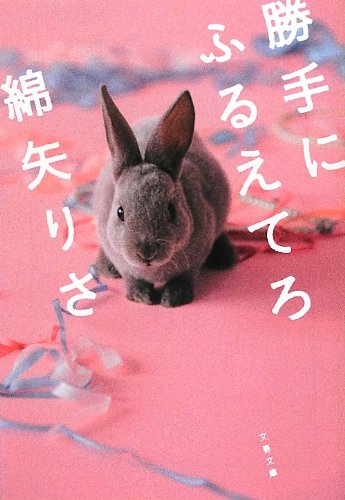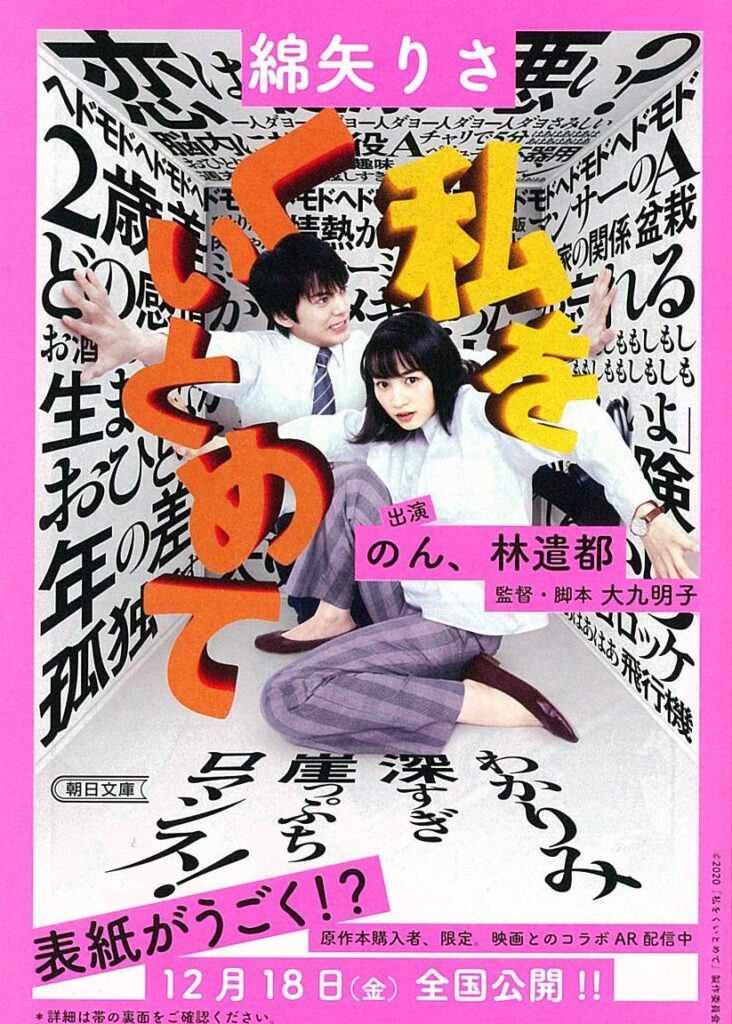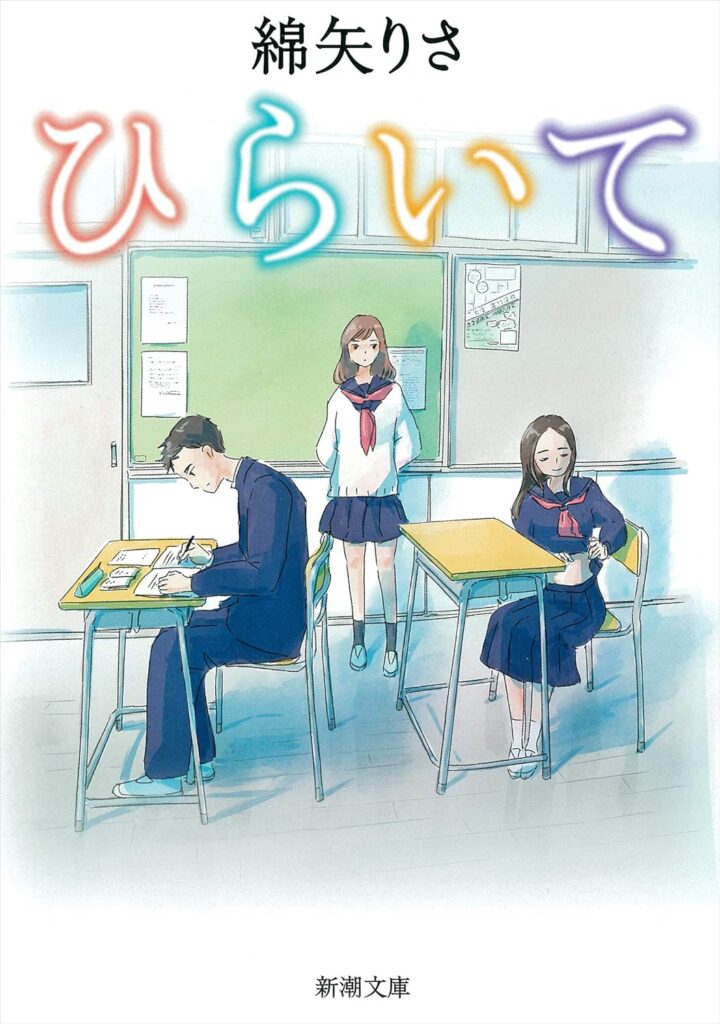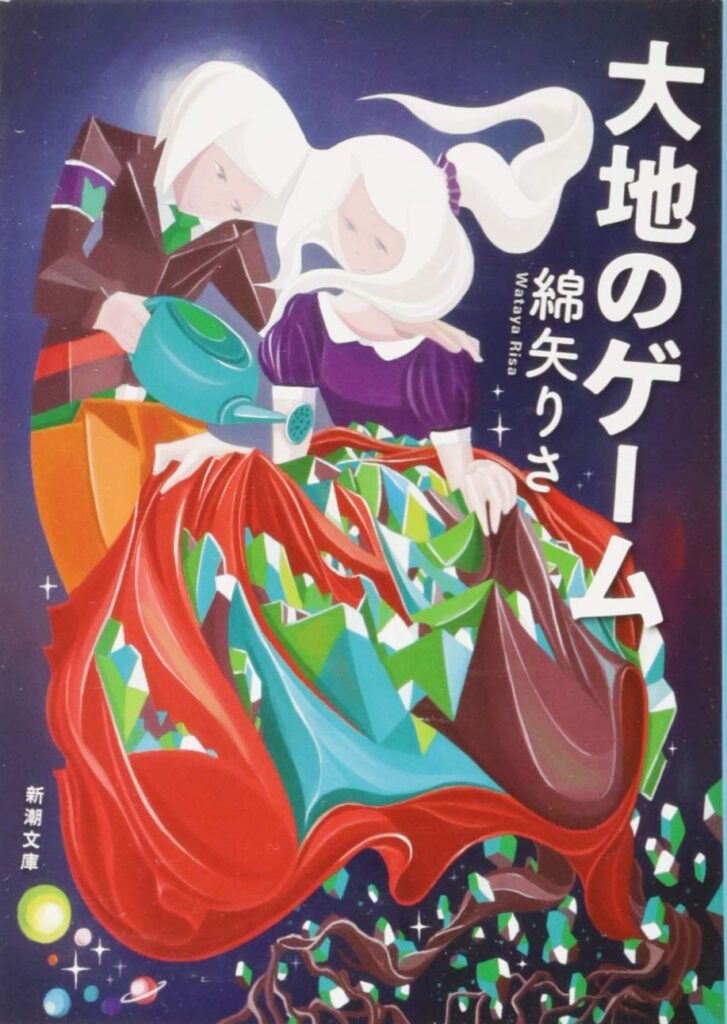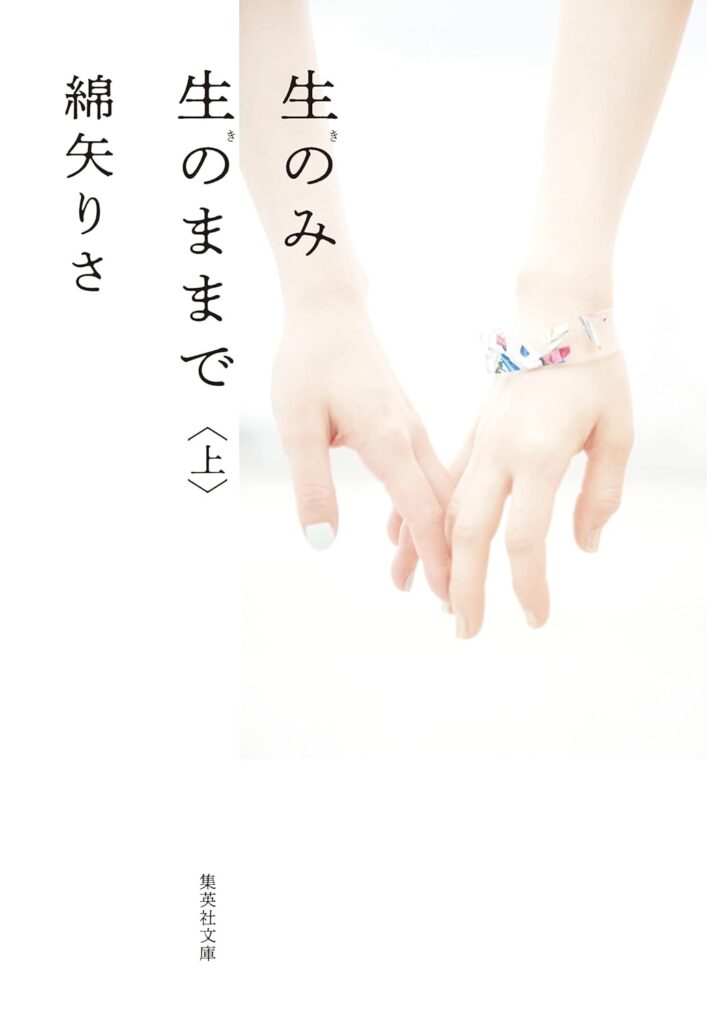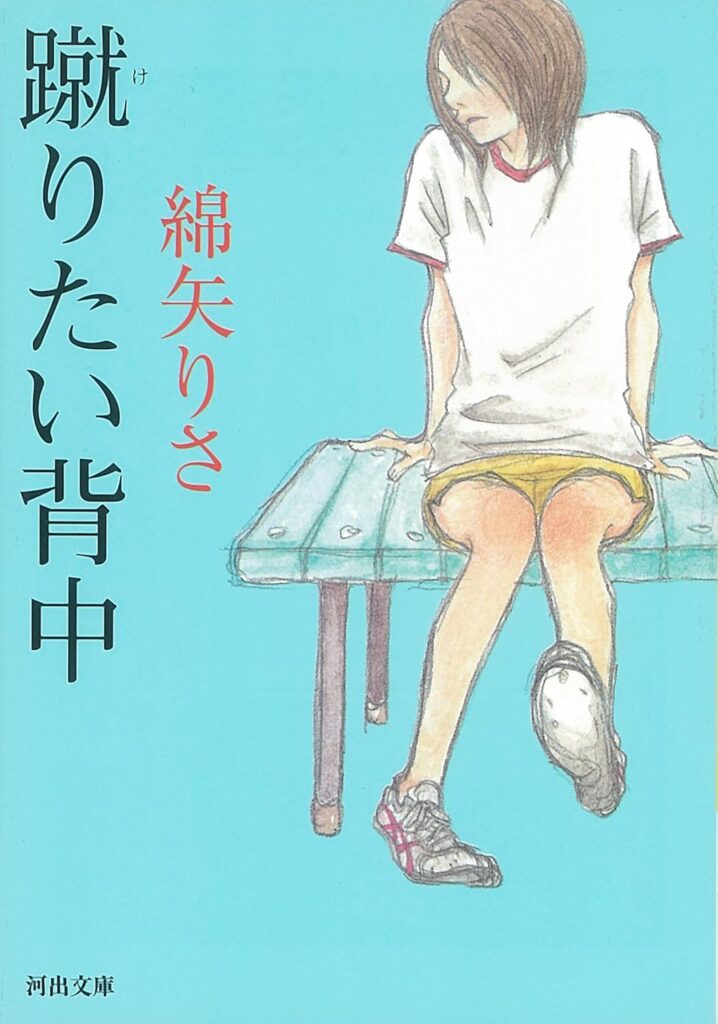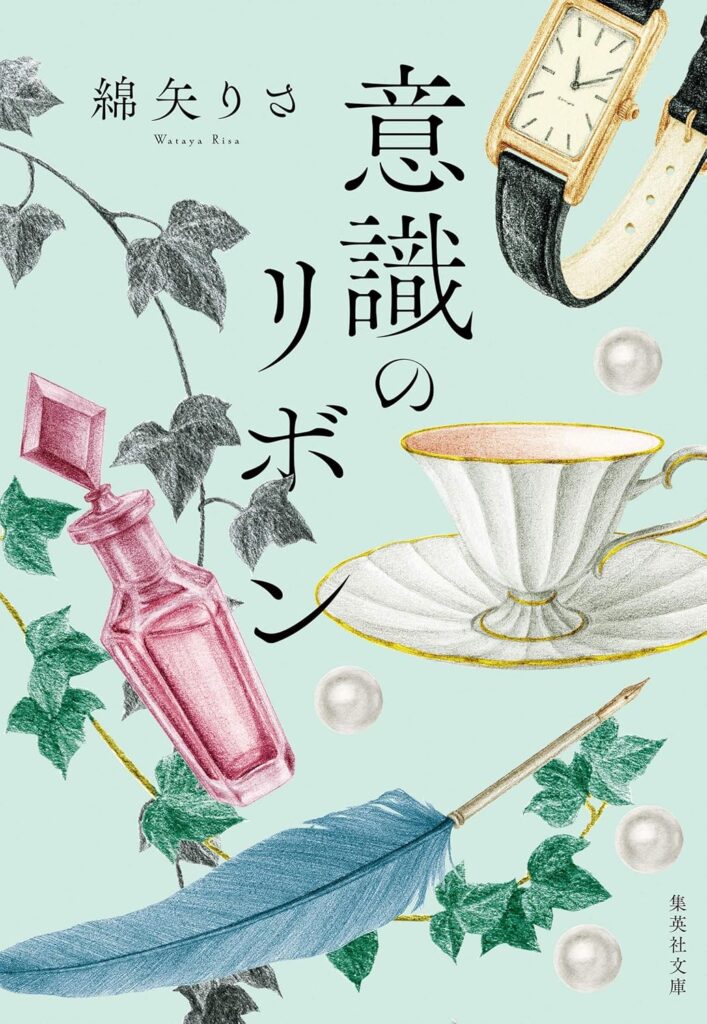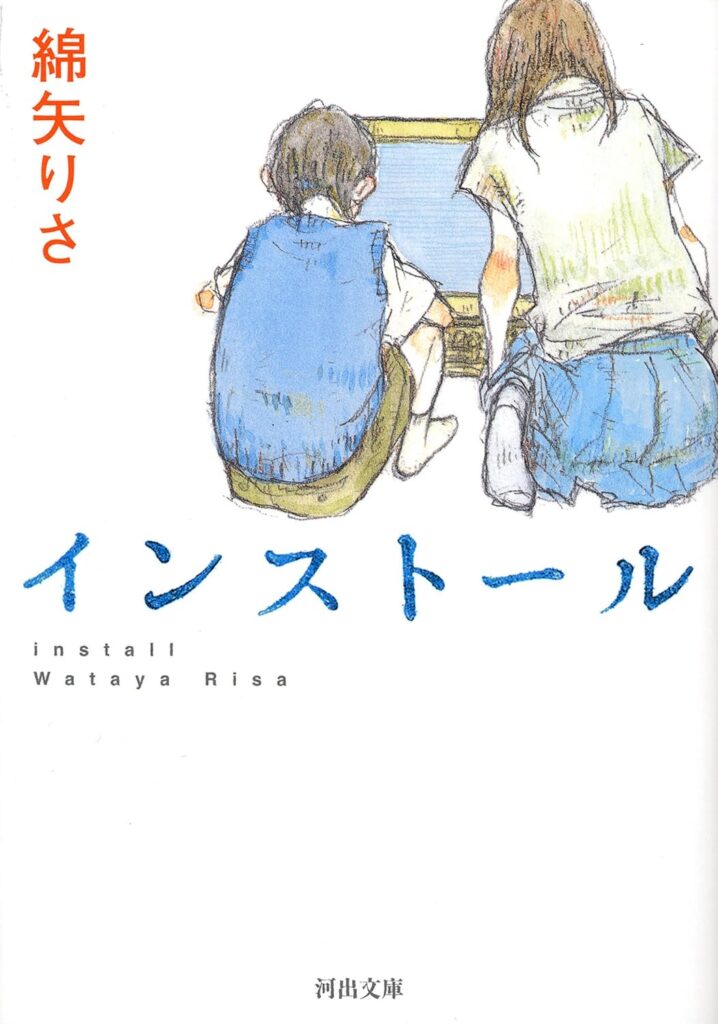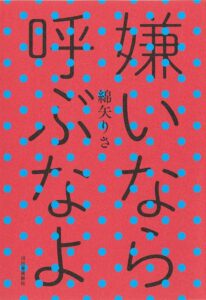
小説「嫌いなら呼ぶなよ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。芥川賞作家である綿矢りささんの、ちょっとドキッとするような、それでいて私たちの日常にも潜んでいるかもしれない人間の心理を描いた作品集です。収録されている四つの物語は、それぞれ異なる主人公たちの、一見普通に見えて、実はかなり危うい、そんな一面を切り取っています。
現代社会ならではの承認欲求やSNSとの関わり方、人間関係の複雑さ、そして世代間のギャップなど、身近なテーマが扱われているので、読みながら「あ、これわかるかも」「うわ、これは怖いな」と感じる部分がたくさんあるかもしれません。登場人物たちの行動は時に突拍子もなく、読んでいてハラハラさせられることも。
この記事では、まず各短編がどのようなお話なのか、その概要をお伝えします。そして、物語の核心部分にも触れながら、私がこの「嫌いなら呼ぶなよ」という作品集を読んで何を感じ、どう考えたのか、詳しい思いを綴っていきます。
これから「嫌いなら呼ぶなよ」を読もうと思っている方、すでに読んでもっと深く知りたいと感じている方、どちらの方にも楽しんでいただけるように、物語の魅力や登場人物たちの心の動き、そして作品全体が持つメッセージについて、私なりの視点で語っていきたいと思います。少し長くなりますが、お付き合いいただけると嬉しいです。
小説「嫌いなら呼ぶなよ」のあらすじ
「嫌いなら呼ぶなよ」は、四つの独立した短編から構成される作品集です。それぞれが現代社会の空気感をまといながら、人間の少し歪んだ、でもどこか共感してしまうような側面を描き出しています。
一つ目の「眼帯のミニーマウス」では、見た目への強いこだわりを持つ主人公りなが登場します。幼い頃の体験から承認欲求がねじれてしまった彼女は、美容整形への関心を深めていきます。職場で整形をカミングアウトしたことをきっかけに、同僚たちとの間で奇妙なコミュニケーションが生まれていく様子が描かれます。彼女の行動はエスカレートし、周囲を驚かせるような事態へと発展していきます。
二つ目の「神田タ」は、人気YouTuberに熱中する女性、ぽやんちゃんが主人公です。彼女は熱心なファンでありながら、時に過激なコメントを送るアンチのような側面も持っています。ある日、憧れのYouTuber本人と予期せず接近する機会を得ますが、そこで知った事実に彼女の感情は激しく揺さぶられます。SNS時代のファン心理と、それが暴走した時の危うさを感じさせる物語です。
三つ目の表題作「嫌いなら呼ぶなよ」は、ある夫婦が妻の親友の新築祝いに招かれる場面から始まります。しかし、そのパーティーは和やかなものではなく、夫の不倫を糾弾するための「裁判」のような場でした。招かれた側の夫の視点から、逃げ場のない状況での心理的な駆け引きや、人間関係における欺瞞、そして「嫌いなのに、なぜ呼ぶのか」という疑問が描かれます。
最後となる「老は害で若も輩」は、作家、ライター、そして出版社の若い編集者という三者の間で交わされるメールのやり取りだけで構成された物語です。インタビュー記事の内容を巡る作家とライターの対立は、やがて世代間の認識の違いやプライドのぶつかり合いへと発展し、思わぬ方向へと転がっていきます。それぞれの立場からの主張が、皮肉たっぷりに描かれています。
小説「嫌いなら呼ぶなよ」の長文感想(ネタバレあり)
綿矢りささんの「嫌いなら呼ぶなよ」、読み終えた後、なんとも言えないざわざわした気持ちと、妙な納得感が入り混じった感覚に包まれました。収録されている四つの物語は、どれも現代を生きる私たちのすぐ隣にあるような、でも少し(いや、かなり?)歪んだ人間関係や個人の内面を、容赦なく、それでいてどこか軽やかに描き出しています。ここからは、物語の核心に触れながら、私が感じたことを詳しくお話ししたいと思います。まだ読んでいない方はご注意くださいね。
まず「眼帯のミニーマウス」。主人公のりなは、承認欲求モンスターとでも言うべき存在ですよね。幼い頃のミニーマウスの服から始まり、ゴスロリ、そして美容整形へと、彼女の関心は常に「他者からどう見られるか」という点に集中しています。二重整形をした後、それを隠すどころか、大げさな眼帯をして、さらに注目を集めようとする姿には、正直「そこまでする!?」と驚かされました。でも、彼女の「誰よりも目立ちつつ、誰よりも正体不明でいられたあの安らぎ」という感覚、少しわかる気もするんです。SNSで匿名のアカウントを使って大胆な発言をする心理と、どこか通じるものがあるのかもしれません。
職場の同僚たちの反応も、またリアルで。「くっくるー」とか「yummy係長」とか、あだ名も面白いんですが、彼女たちのりなに対する遠慮のないツッコミは、女子特有の(と言ってしまうと語弊があるかもしれませんが)マウンティングや、集団の中でのパワーバランスを巧みに描いているように感じました。「毒をもって毒を制す」という表現がありましたが、まさにそんな感じ。りなが整形をしていないのに包帯ぐるぐる巻きで出社するという奇策に出たのは、同僚たちへのある種の反撃であり、自己防衛だったのでしょう。彼女なりのプライドの守り方なのかもしれませんが、その痛々しさに胸が締め付けられるような思いもしました。結局、好きな上司に「面白い」と思われたことで、彼女の行動は(一時的にせよ)肯定されてしまう。この結末も、なんとも皮肉が効いていますよね。
次に「神田タ」。YouTuberとその熱狂的なファンの関係性を描いたこの話は、現代的で非常に考えさせられました。主人公のぽやんちゃんは、一見すると「ぽやん」とした癒し系の女性。でも、その内面には、応援しているはずのYouTuber・神田に対する複雑な感情、愛憎入り混じったような執着心を抱えています。コメント欄での熱烈な応援と、辛辣なダメ出し。この二面性が、まず怖い。彼女は神田に認められたい、特別な存在として認識されたいという強い願望を持っているわけですが、その根底には、もはや恋愛感情に近いような、危ういレベルの思い込みがあったのではないでしょうか。
衝撃的だったのは、神田本人ではなくスタッフが「いいね」をしていたこと、そして神田自身はコメントを読んでいなかったという事実を知った後の、ぽやんちゃんの行動です。怒りに任せて神田のカバンに火をつけるなんて、常軌を逸しています。未遂に終わったとはいえ、一歩間違えれば犯罪です。彼女をそこまで駆り立てたのは、裏切られたという思いと、自分が「ウゾウムゾウ」の一人として扱われたことへの屈辱感だったのでしょう。芥川龍之介の「蜘蛛の糸」のカンダタになぞらえたタイトルが、ここで効いてきますよね。「後ろ振り向いて、”お前らは来るな!”って言ったとたんに…切れちゃうんだよ」という神田(もしくはスタッフ)の言葉は、ファンを見下しているようにも聞こえますが、同時に人気商売の難しさや孤独感も表しているのかもしれません。ラスト、彼のおしっこの色で熱が冷めた、というのも、なんとも言えない生々しさがあって…。結局、彼女の熱狂は、どこか現実離れした偶像崇拝だったのかもしれない、と思わされました。
そして表題作「嫌いなら呼ぶなよ」。これはもう、設定からして恐ろしいですよね。親友の新築祝いだと思ってウキウキついて行ったら、待っていたのは夫の不倫を糾弾する公開裁判。逃げ場のない空間で、妻とその友人たちから次々と浴びせられる詰問の言葉。読んでいて息が詰まるようでした。主人公である不倫夫・霜月一誠の視点で物語が進むので、彼の焦りや戸惑い、そして開き直りにも似た心情がダイレクトに伝わってきます。
「口先だけでごまかして…あなたには人の心がないの?」と問い詰められても、どこか他人事のように状況を分析しようとする一誠。彼のモノローグで語られる不倫に対する持論(「不倫はスポーツ競技の一種目」とか「アイデンティテイ、生業、業の深い、明日を生きるエネルギー」とか)は、不謹慎極まりないけれど、妙に理路整然としていて、彼の自己中心的な性格を際立たせています。「サイテー男」なのは間違いないのですが、ここまで徹底していると、一周回って清々しさすら感じてしまう…というのは言い過ぎでしょうか。いや、やっぱり擁護はできませんね。
タイトルになっている「嫌いなら呼ぶなよ」という一誠の心の叫び。確かに、糾弾するためにわざわざ家に招くというのは、陰湿なやり方かもしれません。でも、それは彼が招いた事態でもあるわけです。楓や友人たちにとっては、これが彼に対する最大限の「おもてなし」だったのかもしれない。子どもの頃は嫌いな子を家に呼ばなかったけれど、大人になると、もっと複雑で、屈折したやり方で相手と対峙することがある。そんな大人の世界の、暗くて粘着質な部分を見せつけられたような気がしました。「焦点が涅槃」なんて表現も、綿矢さんらしい切れ味だなと感じました。
最後の「老は害で若も輩」は、形式が面白かったですね。作家の「綿矢りさ」(本人!?と思わせる)と、40代のライター、そして20代の出版社の男性編集者・内田。この三者のメールの応酬だけで物語が構成されています。最初は作家とライターの間の、記事の内容を巡るプロ意識(という言葉は使えませんが、仕事上のこだわり)のぶつかり合い。お互いに自分の正当性を主張し、一歩も譲らない様子は、読んでいてヒリヒリしました。「繊細ヤクザ」なんて言葉も出てきましたが、傷つきやすさを盾に相手を攻撃するような、そういうコミュニケーションって、確かにあるなと。
面白かったのは、途中からその対立の矛先が、中立を装って事態を静観していた若い編集者の内田に向かっていくところです。「俺はモメごとが嫌いなんだ、全てをナァナァで済ませて…それがそんなにダメなことなのか?」という内田の本音。これも、すごくよくわかる。面倒なことには関わりたくない、波風立てずに仕事を終わらせたい。そういう気持ち、誰にでもあるのではないでしょうか。でも、その「ナァナァ」な態度が、当事者たちから見れば無責任で、火に油を注ぐ結果になってしまう。
そして、クライマックスの内田の豹変ぶりには笑ってしまいました。寝落ちから目覚めて、無意識のうちに(?)書き殴っていたメールの下書き。「ご教授いただき、自らの青二才ぶりにたただただ恥じ入るばかりでございます」なんて殊勝な書き出しから一転、「おどしたり説教したり芸術ヤクザこのボケ」「誌面に載せられるものを渡せ。」そして極めつけの「ババア死ね」。普段抑圧しているものが一気に噴出した、その破壊力たるや。タイトル通り、「老」も「若」も、それぞれの立場で「害」であり「輩」である、という痛烈なメッセージを感じました。世代間の断絶や、それぞれの立場の言い分。それを、こんな形で突き付けてくるとは。綿矢さん自身の名前を作中で使っているあたりも、覚悟というか、何か挑戦的なものを感じさせます。
この四つの物語を通して感じるのは、綿矢りささんの人間観察の鋭さと、それを言葉にする力です。登場人物たちは皆、どこか「普通じゃない」。でも、その「普通じゃなさ」は、私たちの心の中にも、もしかしたら少しだけ、潜んでいるのかもしれない。承認欲求、嫉妬、見栄、自己中心性、攻撃性…。そういった、普段は蓋をしている感情が、何かのきっかけで暴走してしまう。そんな人間の危うさを、綿矢さんは、時にブラックに、時に滑稽に、そして常にするどく描き出しているように思います。
読んでいて決して心地よい気持ちになる話ばかりではありません。むしろ、嫌悪感を抱いたり、気分が悪くなったりする人もいるかもしれません。登場人物たちの行動に「ありえない!」と腹を立てることもあるでしょう。でも、なぜか目が離せない。それは、彼らが抱える問題が、形は違えど、現代社会を生きる私たち自身の問題と地続きであるように感じられるからではないでしょうか。SNSでの炎上、ルッキズム、不倫、世代間の対立…ニュースや日常で見聞きする出来事が、物語の中で生々しく再現されているかのようです。
そして、それらを決して説教臭くなく、むしろ突き放したような視点で、軽快な文体で描いているのが、綿矢さんならではの持ち味なのだと感じます。「嫌いなら呼ぶなよ」というタイトル自体が、この作品集全体を象徴しているようにも思えます。嫌いなもの、見たくないものから目を背けるのではなく、あえてそれを呼び込み、観察し、描写する。その姿勢が、読者である私たちにも、自分自身や周りの世界を、少し違う角度から見つめ直すきっかけを与えてくれるのかもしれません。読後、心に残るざわざわ感は、きっとその証なのでしょう。
まとめ
綿矢りささんの「嫌いなら呼ぶなよ」は、現代社会に潜む人間の心の闇や、少し歪んだ人間関係を、四つの短編を通して鋭く描き出した作品集でした。どの物語も、登場人物たちの行動や心理描写が非常に印象的で、読みながら何度もハッとさせられたり、時には苦笑いを浮かべてしまったり。
「眼帯のミニーマウス」では過剰な承認欲求とルッキズム、「神田タ」ではSNS時代のファン心理の暴走、「嫌いなら呼ぶなよ」では不倫をめぐる人間関係の泥沼、そして「老は害で若も輩」では世代間の衝突や仕事上のプライドのぶつかり合いが、それぞれ独特の切り口で描かれています。
登場人物たちは、決して模範的な人々ではありません。むしろ、共感しがたい、危うさを感じさせる人物が多いかもしれません。しかし、彼らが抱える悩みや葛藤、そして時に見せる攻撃性や自己中心的な部分は、もしかしたら私たち自身の心の中にも存在するのかもしれない、と考えさせられます。
決して読後感が爽やかとは言えないかもしれませんが、人間の本質や現代社会のリアルな一面に触れたい、少し刺激的な読書体験をしたい、という方にはぜひ手に取ってみてほしい一冊です。綿矢りささんならではの観察眼と、独特の言葉選びが光る、忘れられない読書体験になると思います。