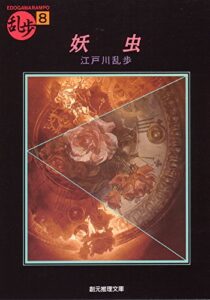 小説「妖虫」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。江戸川乱歩が生み出した数々の探偵小説の中でも、本作は異彩を放つ一作と言えるでしょう。名探偵・明智小五郎が登場しない物語でありながら、乱歩特有の猟奇的で怪奇な雰囲気は健在です。
小説「妖虫」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。江戸川乱歩が生み出した数々の探偵小説の中でも、本作は異彩を放つ一作と言えるでしょう。名探偵・明智小五郎が登場しない物語でありながら、乱歩特有の猟奇的で怪奇な雰囲気は健在です。
物語は、あるレストランでの不穏な会話から幕を開けます。読唇術という特殊な能力を持つ家庭教師・殿村京子が、怪しい男たちの殺人計画を読み取ったことで、主人公たちは底知れぬ事件へと巻き込まれていくのです。次々と起こる残酷な殺人、姿を見せない犯人、そして不気味なサソリの影。
この記事では、まず「妖虫」の物語の筋道を詳しく追いかけます。どのような事件が起こり、どのように解決へと向かうのか、結末まで含めてお伝えします。物語の核心に触れる内容となりますので、未読の方はご注意ください。
そして後半では、この「妖虫」という作品を読んで私が抱いた思いや考察を、詳しく述べていきたいと思います。トリックの妙や欠点、登場人物たちの魅力や謎、そして作品全体が持つ独特な読後感について、ネタバレを気にせずに語り尽くします。乱歩作品がお好きな方、本作に興味を持たれた方にとって、何かしらの参考になれば幸いです。
小説「妖虫」のあらすじ
大学生の相川守は、妹の珠子、そして珠子の家庭教師である殿村京子と共にレストランで食事をしていました。その時、殿村は離れた席に座る二人の男たちの会話を読唇術で読み取り、恐ろしい殺人計画が立てられていることに気づきます。犯行場所と時間を知った守は、好奇心と正義感から、単身で「化物屋敷」と呼ばれる廃屋へ乗り込むことを決意します。
深夜、化物屋敷に忍び込んだ守は、明かりの灯る部屋を覗き見ます。そこには、レストランで見かけた青眼鏡の男、そして椅子に縛り付けられた女性の姿がありました。さらに、部屋に置かれた大きな木箱の中から、姿は見えない何者かの声が響いています。捕らえられていたのは、数日前から行方不明になっていた人気女優の春川月子でした。守が息をのんで見守る中、月子は無残にも刃物で刺されてしまいます。守は慌てて警察を呼びに戻りますが、現場に戻ると月子も犯人たちの姿も消え失せていました。その後、警察による捜索の結果、屋敷内から月子のバラバラにされた遺体が発見されるのでした。
警察での事情聴取を終えた帰り道、守は偶然にも、見世物小屋から出てくる青眼鏡の男を目撃します。後を追いますが、尾行は感づかれてしまい、男は「次の標的は妹の珠子だ」と不気味な予告を残して姿を消します。身の危険を感じた守と父の操一は、名高い私立探偵・三笠竜介に事件の解決を依頼することにしました。
守は依頼のため三笠の屋敷を訪れますが、そこにいたのは偽者の三笠でした。守は屋敷に仕掛けられた巧妙な罠にかかり、落とし穴から地下室へと突き落とされ、閉じ込められてしまいます。驚いたことに、その地下室には本物の三笠竜介もまた監禁されていたのです。本物の三笠は、携帯している「探偵の七つ道具」を駆使し、地下室からの脱出を試みます。
一方、偽者の三笠は守からの依頼と偽って相川家を訪れ、珠子の身の安全のため、別の場所へ避難させることを提案します。操一と珠子を言葉巧みに自動車に乗せ、親戚の家へと向かうふりをしますが、道中で操一は睡眠薬で眠らされ、珠子は仲間と共に化物屋敷へと連れ去られてしまいます。化物屋敷では青眼鏡の男が待ち構えており、珠子を十字架に磔にして殺害しようとしていました。しかし、その危機一髪の状況で、偽三笠の部下だと思われていた二人が、実は変装した本物の三笠と守であったことが判明します。形勢は逆転し、三笠が青眼鏡の男に拳銃を突きつけます。守が警察を呼びに行き、犯人逮捕かと思われた瞬間、近くにあった張りぼての岩の中から何者かの手が伸び、三笠は刃物で刺されてしまいます。混乱の中、青眼鏡の男は屋敷に火を放ち、珠子を連れて逃走します。翌日、銀座のデパートのショーウィンドウに、マネキン人形のように飾られた珠子の惨殺死体が発見されるという、おぞましい結末を迎えます。
珠子の死後、家庭教師の殿村は、珠子の先輩であり守の恋人でもある桜井品子の家庭教師となります。しかし、今度は品子が犯人の新たな標的となってしまいます。守は、刺された傷で入院中の三笠探偵を見舞います。三笠は、犯人から贈られた見舞いの品に毒が仕込まれていたことを見抜き、毒に苦しむふりをして油断させていました。三笠は守に、今度こそ品子を守り抜くと固く約束します。ある夜、品子は自室の窓の外に巨大なサソリの影を見ます。翌晩、庭に潜んで様子を窺っていた守は、サソリの姿をした何者かが品子の寝室に近づこうとしているのを発見。格闘の末、そのサソリ姿の人物が非常に小柄であることに気づきます。守は相手を取り押さえますが、別の仲間に麻酔薬で眠らされ、連れ去られてしまいます。翌朝、守は丸の内のオフィス街に置かれた巨大なサソリの張りぼての中から、眠らされた状態で発見されました。
時を同じくして、桜井家には巨大なサソリの被り物と、「品子を誘拐する」という予告状が届けられます。品子の父は警察に通報し、警官たちが桜井家にやってきて事情聴取を行い、証拠品としてサソリの被り物を持ち帰ります。しかし、その後、品子の部屋で女中が殴り倒され、殿村が縛られているのが発見され、品子の姿は消えていました。先ほどの警官たちは偽者で、サソリの被り物の中に品子を隠して連れ去ったのでした。品子誘拐の報を受け、守、操一、そして本物の警察が桜井家に駆けつけますが、捜査は難航します。
人々が桜井家で対策を練っていると、そこへ一人の老人と、大きな荷物を担いだ男が現れます。老人は変装した三笠探偵であり、男は彼の助手でした。三笠は屋敷を調査した後、集まった人々に「犯人はこの中にいる」と宣言します。三笠は、化物屋敷の張りぼての岩や木箱の中に潜んでいた人物、そして守と格闘したサソリ姿の小柄な人物が、青眼鏡の男が出てきた見世物小屋にいた「一寸法師の娘」と呼ばれる身体の小さな女性であると推理します。三笠は既にその女性を捕らえており、助手が運んできた荷物の中に隠していました。
姿を現した小さな女性は、殿村京子を見るなり「お母さん」と呼び、彼女に抱きつきます。一連の事件の真犯人、青眼鏡の男の正体は、家庭教師の殿村京子だったのです。すべてのトリックを三笠に見破られた殿村は犯行を認めますが、「品子はまもなく死ぬ」と勝ち誇ったように告げます。殿村は桜井家の屋根裏に品子を隠し、時限式の殺害装置を仕掛けていたのです。しかし、三笠はそれをも見抜き、既に装置を解除して品子を救出していました。万策尽きた殿村は、娘に毒を飲ませて道連れにし、自らも毒をあおって命を絶つのでした。
小説「妖虫」の長文感想(ネタバレあり)
江戸川乱歩の「妖虫」を読み終えて、まず感じたのは、やはり乱歩作品ならではの、あの独特な薄暗く、じっとりとした空気感でした。名探偵・明智小五郎が登場しない物語ということで、少し毛色が違うのかと最初は思いましたが、読み進めるうちに、奇怪な事件、猟奇的な描写、そして読者の意表を突こうとする仕掛けは、まさしく乱歩の世界そのものでしたね。タイトルにもなっている「妖虫」、すなわちサソリが、物語全体に不気味な影を落としています。
物語の幕開け、レストランでの読唇術の場面は、非常に印象的です。家庭教師の殿村京子が、偶然にも隣の席の怪しい男たちの殺人計画を読み取ってしまう。この導入は、これから始まる事件への期待感を高めると同時に、ある種の「出来すぎた偶然」を感じさせずにはいられませんでした。なぜ犯人一味(と後にわかる)が、標的となる相川家の兄妹がいるかもしれない場所で、そんな重要な計画を話していたのか。そして、なぜ殿村が都合よくそれを読み取れたのか。この時点から、殿村京子という人物に対する疑念が、私の中で芽生え始めていました。乱歩自身も、後年、この導入部分について触れていますが、読唇術という小道具自体は面白いものの、その状況設定には、やはり少し無理があったのかもしれません。
事件の最初の舞台となる「化物屋敷」の描写も、乱歩らしさが満載です。打ち捨てられた古い屋敷、怪しげな明かり、そして姿の見えない声の主。こうしたゴシック的な雰囲気作りは、読者の恐怖心と好奇心を巧みに掻き立てます。ここで繰り広げられる女優・春川月子の殺害シーンは、なかなかに衝撃的でした。そして、その後のバラバラ死体の発見。乱歩作品においては、こうした猟奇的な描写は珍しくありませんが、「妖虫」におけるそれは、物語の序盤で読者に強烈なインパクトを与える役割を果たしています。ただ死体が発見されるだけでなく、その異常な状況が、事件の異様さを際立たせているのです。
そして登場するのが、本作の探偵役、三笠竜介です。白髭に丸眼鏡、「サルに洋服を着せたような」と形容される風貌は、スマートな明智小五郎とは対照的で、どこか胡散臭ささえ漂わせています。彼が颯爽と事件を解決していくのかと思いきや、序盤では犯人の罠にかかって地下室に閉じ込められたり、油断して背後から刺されたりと、なかなかに頼りない姿を見せます。この「頼りなさ」が、もしかしたら乱歩の狙いだったのかもしれません。読者に「この探偵、大丈夫か?」と思わせることで、犯人の優位性を際立たせ、物語のサスペンスを高める効果があったのではないでしょうか。あるいは、参考資料にあるように、当初は三笠を探偵役ではなく、ミスリードを誘う怪しい人物として描く構想もあったのかもしれません。明智小五郎という絶対的なヒーローではなく、どこか人間臭く、失敗もする老人探偵という設定は、ある意味で新鮮でした。
しかし、物語が進むにつれて、この三笠探偵、意外と(?)活躍を見せ始めます。特に、終盤の謎解きシーンは見事です。犯人である殿村京子のトリックを次々と暴き、追い詰めていく様は、さすが名探偵といったところ。変装して現れたり、助手の存在があったりと、探偵としてのギミックも用意されています。彼が携帯する「探偵の七つ道具」が具体的にどのようなものだったのか、もう少し描写があれば、さらにキャラクターが立ったかもしれませんが、それでも、最後の最後で事件を解決に導く姿は、読者に安堵感を与えてくれます。
本作の犯人である殿村京子。その正体には、正直なところ、比較的早い段階で気づいてしまいました。前述したレストランの場面の不自然さに加え、物語の進行の中で、彼女があまりにも都合よく事件に関わり、情報を得ているように見えたからです。特に、サソリのおもちゃを使ったトリックなどは、少し見え透いていた感は否めません。乱歩自身は、この犯人とその動機について「ちょっと珍しい着想であった」と自負していたようですが、読唇術を使う人物が犯人、というアイデア自体は面白いものの、その見せ方にもう一工夫あれば、もっと驚きがあったかもしれません。横溝正史が後に同じような読唇術のトリックを用いた短編「鏡の中の女」を書いているという事実は非常に興味深いですね。乱歩へのオマージュなのか、あるいは乱歩が活かしきれなかったアイデアをより洗練させた形で見せたかったのか、想像が膨らみます。
殿村京子の動機は、単なる快楽殺人や金銭目的とは一線を画す、複雑なものでした。見世物小屋で「一寸法師の娘」として虐げられていた実の娘への歪んだ母性愛、そして自分たち母娘をそのような境遇に追いやった社会全体への深い憎悪。この二つが絡み合い、彼女を冷酷な連続殺人鬼へと変貌させたのです。家庭教師という、子供に寄り添い、信頼される立場を利用して犯行を重ねるという倒錯性も、彼女の狂気を際立たせています。娘に毒を飲ませて心中するという結末は、悲劇的であると同時に、彼女の異常なまでの執念と母性の歪みを象徴しているように思えました。この複雑な動機設定は、「妖虫」を単なる通俗的な猟奇スリラー以上のものにしている重要な要素だと感じます。
「妖虫」というタイトル、そして作中に繰り返し登場するサソリのモチーフも、この作品の不気味さを高めるのに一役買っています。サソリは毒を持ち、暗闇で活動し、その姿は異形です。これらのイメージは、犯人・殿村京子の隠された毒性、社会の影で蠢く悪意、そして彼女の娘の身体的な特徴とも重なります。特に、巨大なサソリの着ぐるみが登場する場面は、視覚的にも強烈な印象を残します。子供向けの翻案「鉄塔の怪人」では、サソリがカブトムシに変えられたそうですが、それでは恐怖感が薄れてしまうでしょうね。やはり、この物語にはサソリの毒々しさが不可欠なのです。旧題が「妖蟲」であったというのも、昆虫に限らない節足動物全般を含む「蟲」という漢字の方が、サソリのイメージにはより合っていたのかもしれません。
トリックに目を向けると、読唇術の導入、サソリの扮装、死体をマネキン人形のようにショーウィンドウに飾るという大胆な犯行、偽警官による誘拐など、多彩なアイデアが盛り込まれています。特に、ショーウィンドウの死体という発想は、乱歩らしい悪趣味さとグロテスクさが際立っており、読者に鮮烈な印象を与えます。一方で、個々のトリックの実現性や、犯行計画の細部には、やや粗さが見られる部分も否定できません。例えば、偽三笠が本物の三笠を地下室に閉じ込めておく必要性や、サソリの着ぐるみを使った誘拐計画の現実味など、冷静に考えると疑問符が付く点もあります。しかし、それらの細かな点を補って余りあるのが、物語全体の勢いと、次々と読者を飽きさせない展開の妙なのでしょう。連載小説として、読者の興味を引きつけ続けるためのサービス精神が感じられます。
主人公である相川守の存在も、この物語に欠かせません。彼は探偵ではありませんが、正義感と好奇心から積極的に事件に関わっていきます。時には犯人に翻弄され、危険な目に遭いながらも、妹や恋人を守ろうと奮闘する姿は、読者の共感を呼びます。彼が探偵ではないからこそ、読者は彼と同じ視点で事件の謎や恐怖を体験することができます。彼の存在が、超人的な名探偵ではなく、一般人の視点を物語に持ち込んでいると言えるでしょう。
「妖虫」は、江戸川乱歩が休筆期間を経て、再び精力的に執筆活動を再開した時期の作品です。失敗に終わったとされる『悪霊』の後に書かれた本作には、通俗的な面白さを追求しつつも、新しい探偵小説の可能性を模索しようとした乱歩の意欲が感じられます。犯人の動機設定に見られる深みや、三笠竜介という新たな探偵像の試みなどは、その表れかもしれません。結果として、いつもの乱歩らしい猟奇スリラーに着地した感はありますが、その中にも、単なるマンネリズムではない、作家としての試行錯誤が垣間見えるように思います。
現代の視点から「妖虫」を読むと、もちろん時代を感じさせる部分はあります。特に、身体的な特徴を持つ人物を見世物にする描写などは、現代の倫理観からすれば問題視されるかもしれません。しかし、そうした時代性を差し引いても、人間の心の闇、歪んだ愛情、社会への反発といったテーマは、現代にも通じる普遍性を持っているのではないでしょうか。そして何より、江戸川乱歩が生み出す、あの妖しく蠱惑的な物語世界は、今読んでも色褪せることのない魅力に満ちています。
トリックの粗さや、犯人の意外性の点で物足りなさを感じる部分はあるものの、それを補って余りある雰囲気と魅力に満ちた作品でした。特に、殿村京子という犯人の造形と、その根底にある歪んだ母性の描写は、強く印象に残りました。明智小五郎シリーズとはまた違った、乱歩の暗黒面が色濃く反映された一作として、記憶に刻まれることでしょう。
まとめ
江戸川乱歩の「妖虫」は、名探偵・明智小五郎が登場しない異色作でありながら、乱歩特有の怪奇と猟奇に満ちた世界観を存分に味わえる長編探偵小説です。物語は、家庭教師・殿村京子の読唇術によって殺人計画が露見するところから始まり、主人公の相川守とその周辺の人々が、次々と恐ろしい事件に巻き込まれていきます。
物語の筋道を追っていくと、化物屋敷での惨劇、バラバラ殺人、不気味なサソリの出現、そして新たな探偵役・三笠竜介の登場と、息もつかせぬ展開が続きます。犯人の正体やトリックについては、やや早い段階で予想がつく部分もありますが、それを補うだけの猟奇的な描写や、サスペンスフルな雰囲気作りはさすが乱歩と言えるでしょう。特に、ショーウィンドウに飾られた死体や、サソリの扮装といった要素は、読者に強烈な印象を与えます。
この作品の核心にあるのは、犯人・殿村京子の複雑な動機です。見世物にされる娘への歪んだ母性愛と、社会への深い憎悪が、彼女を残酷な犯行へと駆り立てます。この動機の深さが、「妖虫」を単なるエンターテイメントに留まらない、人間の心の闇を描いた物語として印象深いものにしています。結末のネタバレになりますが、母娘の悲劇的な最期は、物語に重い余韻を残します。
「妖虫」は、トリックの完成度や犯人の意外性という点では他の乱歩作品に譲る部分があるかもしれませんが、独特の雰囲気、猟奇性、そして犯人の動機の深さにおいて、読む価値のある一作です。この記事を通して、「妖虫」のあらすじや、ネタバレを含む深い感想に触れていただき、作品への興味を深めていただけたなら幸いです。






































































