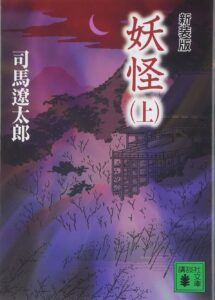 小説「妖怪」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。司馬遼太郎さんの作品の中でも、一風変わった雰囲気を持つこの物語は、多くの読者を惹きつけ、また同時に戸惑わせるかもしれません。歴史の大きな流れの中に、幻術という不可思議な要素が絡み合い、独特の世界観を織りなしています。
小説「妖怪」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。司馬遼太郎さんの作品の中でも、一風変わった雰囲気を持つこの物語は、多くの読者を惹きつけ、また同時に戸惑わせるかもしれません。歴史の大きな流れの中に、幻術という不可思議な要素が絡み合い、独特の世界観を織りなしています。
舞台は室町時代後期、応仁の乱前夜の混沌とした京の都です。政治は乱れ、人々の心もまた、先の見えない不安と迷信に満ちていました。そんな時代だからこそ、「妖怪」のような存在が、あるいは信じられ、あるいは利用されたのかもしれません。本作は、そんな時代の空気感を色濃く映し出しています。
この記事では、まず物語の筋道を、結末の核心に触れながら追っていきます。主人公である源四郎が、いかにして時代の波に呑まれ、不可思議な出来事に巻き込まれていくのか。そして、その先に待ち受ける運命とは何なのか。詳細にお伝えできればと思います。
さらに、読み終えた後に抱いた、個人的な思いや考察も詳しく記しました。なぜこの物語は「妖怪」と名付けられたのか、登場人物たちの行動に隠された意味は何か、そして司馬さんがこの作品を通して伝えたかったことは何なのか。読み応えのある内容を目指しましたので、ぜひ最後までお付き合いくださいませ。
小説「妖怪」のあらすじ
物語は、熊野の山中で育った青年、源四郎が自らを室町幕府六代将軍・足利義教のご落胤であると信じ、将軍となる野望を胸に京へ上るところから始まります。当時の京は、八代将軍・足利義政のもとで権力争いが激化しており、特に将軍正室の日野富子と、長年寵愛を受けてきた側室・今参局(お今)の対立は熾烈を極めていました。
京にたどり着いた源四郎は、その素性の怪しさと若さゆえか、日野富子の兄である日野勝光に目をつけられ、食客として日野家に迎え入れられます。富子たちは、この出自不明の青年を、政敵であるお今を排除するための駒として利用しようと考えます。そして源四郎は、お今の拉致という危険な任務を命じられることになります。
しかし、この計画は失敗に終わります。お今には唐天子(とうてんじ)と名乗る強力な幻術師が「憑いて」おり、源四郎は唐天子の不可思議な術の前に翻弄され、任務を遂行できませんでした。この一件で日野家での居場所を失った源四郎は、幻術に対抗しうる力を求め、剣術の修行に打ち込んだり、あるいは生活のために盗賊団の頭領となったりと、流転の日々を送ることになります。
その間も、源四郎の運命は富子とお今の争い、そして唐天子の幻術と深く関わり続けます。彼は幾度となく唐天子の術にかかり、意図せぬ方向へと導かれていきます。例えば、京のならず者集団である「印地」の大将になったりするのも、唐天子の影響があったのかもしれません。源四郎自身の意志とは裏腹に、彼の人生は時代の大きなうねりと怪異な力によって翻弄され続けるのです。
やがて、日野富子は義政の子を流産するという悲劇に見舞われます。しかし、富子はこの不幸を逆手に取り、お今が唐天子に命じて呪詛を行わせたせいだ、という根も葉もない噂を流布させます。この策略は見事に功を奏し、お今は失脚。ついには配流先で、富子の息のかかった者(あるいは唐天子の幻術に操られた源四郎自身)によって殺害されてしまいます。
最大のライバルを排除した富子ですが、これで政情が安定するわけではありませんでした。皮肉なことに、富子はその後男子(後の九代将軍・義尚)を産みますが、すでに義政は弟の義視を後継者として指名していました。これが新たな火種となり、富子と義視の対立、そして彼らを担ぐ守護大名たちの争いは、ついに応仁の乱という、日本史上でも類を見ない大乱へと発展していくのです。物語は、この大乱の始まりとともに、唐突に幕を閉じます。
小説「妖怪」の長文感想(ネタバレあり)
司馬遼太郎さんの作品といえば、緻密な歴史考証に基づいた重厚な歴史小説、特に幕末や明治維新、戦国時代を舞台にした英雄たちの物語を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。「竜馬がゆく」「坂の上の雲」「国盗り物語」など、枚挙にいとまがありません。しかし、この「妖怪」は、そうした代表作とは少し趣が異なります。歴史小説という枠組みの中にありながら、幻術という超常的な要素が色濃く、むしろ伝奇小説と呼ぶ方がしっくりくるかもしれません。
この作品が発表されたのは昭和43年。『坂の上の雲』という国民的長編の連載開始直前という時期にあたります。司馬さんが最も脂の乗っていた時期と言えるかもしれませんが、同時に、新しい表現を模索していた時期だったのかもしれません。幼少期に『聊斎志異』を愛読したという司馬さんは、他にも『大盗禅師』や『果心居士の幻術』、『梟の城』といった、幻術や忍術を扱った作品をいくつか残しています。「妖怪」もその系譜に連なる一作と言えるでしょう。
物語の主人公は源四郎。将軍の落胤を自称し、熊野から京へ出てきます。しかし、この主人公、司馬作品の他の主人公たち、例えば坂本龍馬や秋山兄弟、斎藤道三などと比べると、どうにも影が薄いというか、主体性に欠ける印象を受けます。将軍になるという大望を抱いてはいるものの、そのための具体的な計画があるわけでもなく、京に着いて早々、日野家の権力争いに駒として利用され、謎の幻術師・唐天子に良いように翻弄されるばかりです。
精神的にも不安定で、唐天子の幻術にかかりやすい。自分の意志で道を切り開いていくというよりは、流されるままに動いているように見えます。架空の人物を主人公に据えた司馬作品には、時折こうしたタイプの主人公が登場する気がします。『風の武士』などもそうだったかもしれません。もちろん、『梟の城』の葛籠重蔵のように、架空でありながら強烈な個性と主体性を持つ主人公もいますが、源四郎はどちらかというと前者です。そのため、読者としてはなかなか感情移入しづらい部分があるかもしれません。
この物語のもう一人の主役、あるいは真の主役かもしれないのが、幻術師・唐天子です。彼はどこから来て、何を目的としているのか、一切が謎に包まれています。今参局に「憑いて」いるとされながら、彼女を守るというよりは、むしろ混乱を煽っているようにも見えます。源四郎の前に幾度となく現れては不可思議な幻術で惑わせ、彼の運命を左右しますが、その行動原理は最後まで明かされません。
唐天子の繰り出す幻術の描写そのものは、非常に興味深く、読ませる力があります。人が忽然と消えたり、ありえない光景を見せたり。荒廃し、迷信がはびこる室町後期の京という舞台設定と相まって、不気味で妖しい雰囲気を醸し出しています。人々が「妖怪」の仕業と信じてもおかしくないような出来事が次々と起こる様は、伝奇小説としての面白さを確かに持っています。
しかし、この唐天子の存在が、物語全体としてうまく機能しているかというと、疑問が残ります。彼の幻術は個々の場面では印象的ですが、物語の大きな流れ、つまり応仁の乱へと至る歴史の必然性に、どれほど寄与しているのかが判然としないのです。源四郎がお今を殺害する(あるいはその手助けをする)場面も、唐天子の幻術の影響が示唆されますが、それが歴史を決定的に変えた、というほどのインパクトはありません。結局のところ、唐天子がいなくても、富子とお今の対立や、その後の応仁の乱は起こったのではないか、と思えてしまうのです。
物語の結末も、非常に唐突な印象を受けます。応仁の乱が始まり、源四郎もその戦乱の中に巻き込まれていく…というところで、ぷつりと終わってしまう。あれほど物語を引っ掻き回した唐天子がその後どうなったのか、源四郎自身の最終的な運命はどうなるのか、そうした点は一切語られません。伏線が回収されないまま放り出されたような、消化不良感を覚える読者は少なくないでしょう。
こうした点から、本作は司馬作品の中では「失敗作」あるいは「問題作」と評されることもあるようです。実際に、梅原猛氏は本作を批判的に見ています。一方で、海音寺潮五郎氏は新聞の書評で好意的に取り上げ、執筆に悩んでいた司馬さんを励ましたというエピソードもあります。評価が分かれる作品であることは間違いなさそうです。
では、司馬さんはこの作品で何を描こうとしたのでしょうか。明確な答えを見つけるのは難しいかもしれません。ただ、考えられることとしては、まず、応仁の乱前夜という、理由も大義名分も曖昧なまま、人々がただただ争いに巻き込まれていく時代の「わけのわからなさ」「不条理さ」を描こうとしたのではないでしょうか。唐天子という存在は、その混沌とした時代の象徴であり、人々の心の迷いや不安が生み出した「妖怪」そのものだったのかもしれません。
源四郎という主体性のない主人公も、そうした時代の不条理さに翻弄される、名もなき民衆の代表として描かれたのかもしれません。彼自身の野心や行動が歴史を動かすのではなく、ただ時代の大きな流れと、人知を超えた(かのように見える)力によって運命が左右されていく。そこに、歴史の非情さや、個人の無力さのようなものを読み取ることもできるでしょう。
また、日野富子や今参局といった歴史上の人物の描き方も興味深い点です。特に日野富子は、悪女として語られることが多いですが、本作では権力欲を持ちながらも、どこか人間的な弱さや気まぐれさも感じさせる人物として描かれています。近年の研究では、彼女が幕府財政を支えた有能な人物であったという側面も指摘されており、単純な悪女像ではない、多面的な人物像を提示しようとしたのかもしれません。
幻術という要素についても、単なる伝奇的な面白さだけでなく、当時の人々が実際に妖怪や呪術の存在を信じていたという時代背景を反映していると考えられます。科学的な合理性だけでは割り切れない、人間の心の闇や、時代の持つ不可思議な力のようなものを表現するための装置だったのかもしれません。
個人的な感想を正直に申し上げるなら、やはり物語としての完成度には疑問符がつきます。主人公に感情移入しにくく、物語の核となるべき幻術師の目的が不明瞭で、結末も唐突すぎる。司馬さんの他の傑作群と比べると、物足りなさを感じるのは否めません。しかし、それでもなお、この作品には独特の魅力があるとも感じます。
それは、応仁の乱前夜の、あの得体の知れない混沌とした時代の空気を、見事に描き出している点です。政治的な対立だけでなく、人々の心に巣食う不安や迷信、そして幻術という非日常的な要素が渾然一体となって、読む者を異様な世界へと引き込みます。個々のエピソード、特に唐天子の幻術にまつわる場面は、やはり司馬さんならではの筆力で、鮮やかに描かれています。
「妖怪」は、司馬遼太郎という作家の、ある種の実験的な試みだったのかもしれません。歴史の大きな流れを描くだけでなく、その時代に生きた人々の内面や、時代の持つ不可思議な側面にも光を当てようとした意欲作、と捉えることもできるでしょう。賛否両論あるのは承知の上で、司馬作品の多様性を知る上では、読んでみる価値のある一冊ではないかと思います。少なくとも、他の作品とは全く違う読後感を味わえることは間違いありません。
まとめ
この記事では、司馬遼太郎さんの小説「妖怪」について、物語の筋道を結末まで含めてご紹介し、さらに読み終えた後の個人的な思いを詳しく述べさせていただきました。将軍の落胤を名乗る源四郎が、応仁の乱前夜の京で、日野富子と今参局の権力争いや、謎の幻術師・唐天子に翻弄される様を描いた物語です。
本作は、司馬作品の中では異色とされ、評価も分かれるところです。幻術という伝奇的な要素が強く、主人公の人物像や物語の結末に、やや消化不良感を覚える方もいらっしゃるかもしれません。唐天子の目的や源四郎の主体性の欠如、唐突な終わり方など、疑問点が残ることも確かでしょう。
しかしながら、混沌とした室町時代後期の雰囲気や、人々の心に潜む闇、そして「妖怪」が跋扈するような時代の不可思議さを描いた筆致には、やはり引き込まれるものがあります。歴史の表舞台だけでなく、その裏側にある怪異や人々の迷いといった側面を描こうとした、司馬さんの意欲を感じさせる作品とも言えます。
「竜馬がゆく」や「坂の上の雲」のような、明快な英雄譚とは異なる、一筋縄ではいかない魅力を持つのが「妖怪」です。もし、まだ読んだことがないようでしたら、賛否両論あることを踏まえた上で、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。司馬文学の奥深さ、その多様性の一端に触れることができるかもしれません。この記事が、皆様の読書の一助となれば幸いです。






































