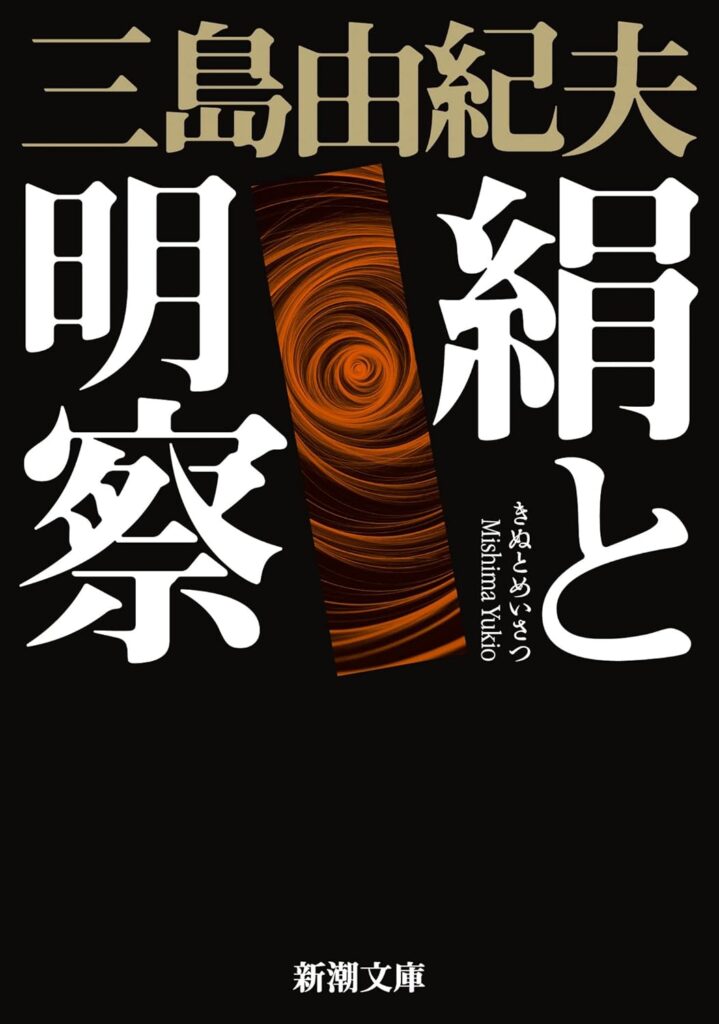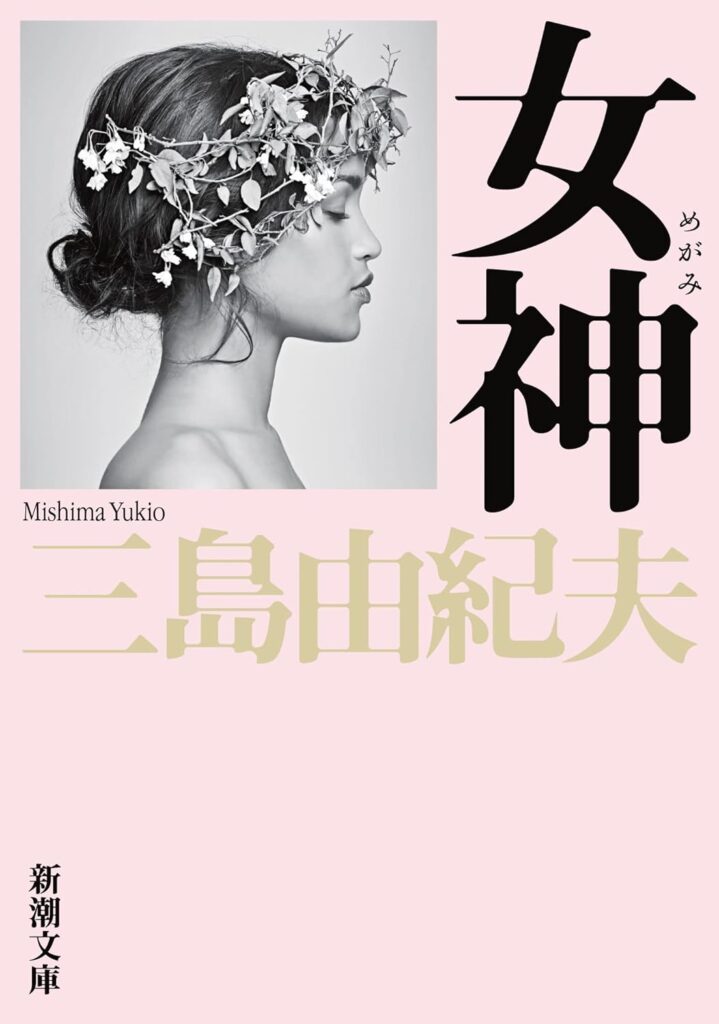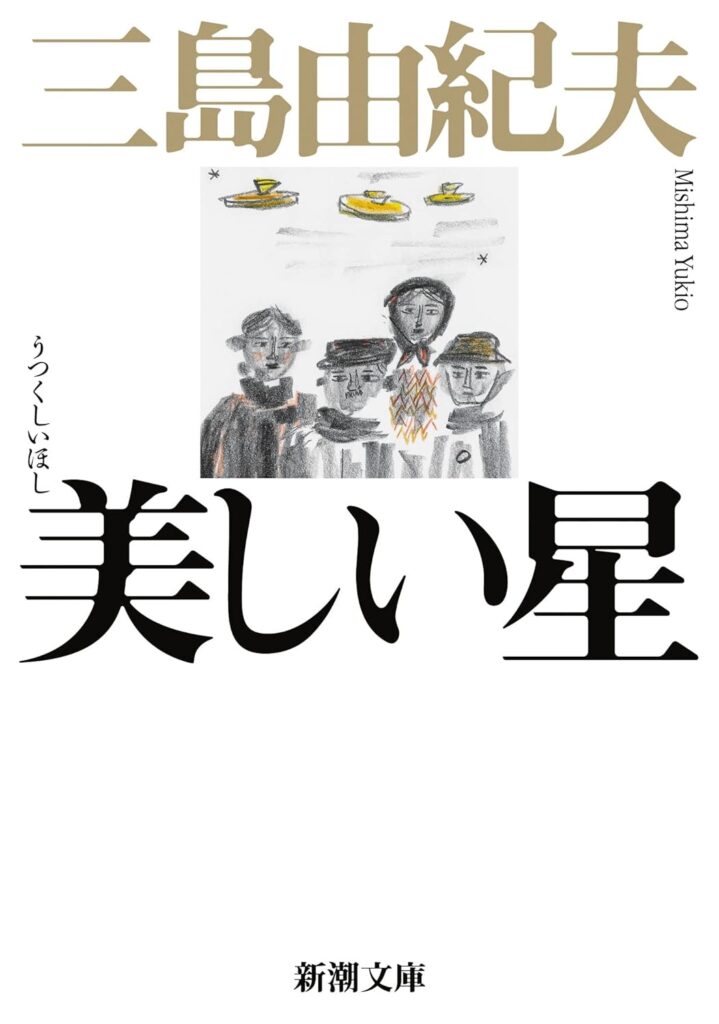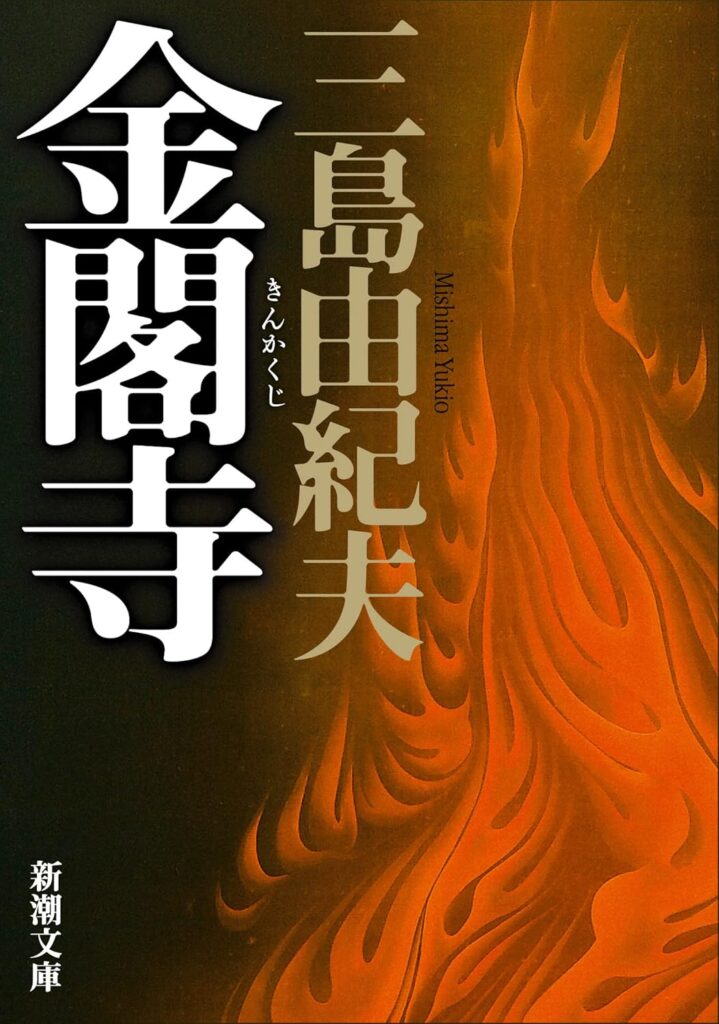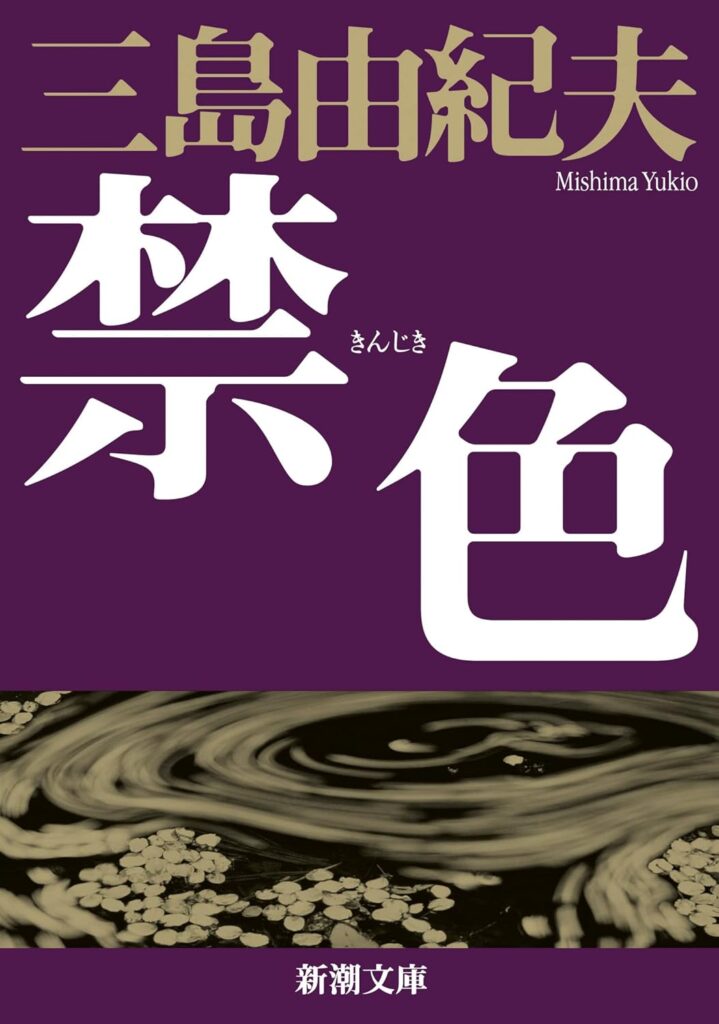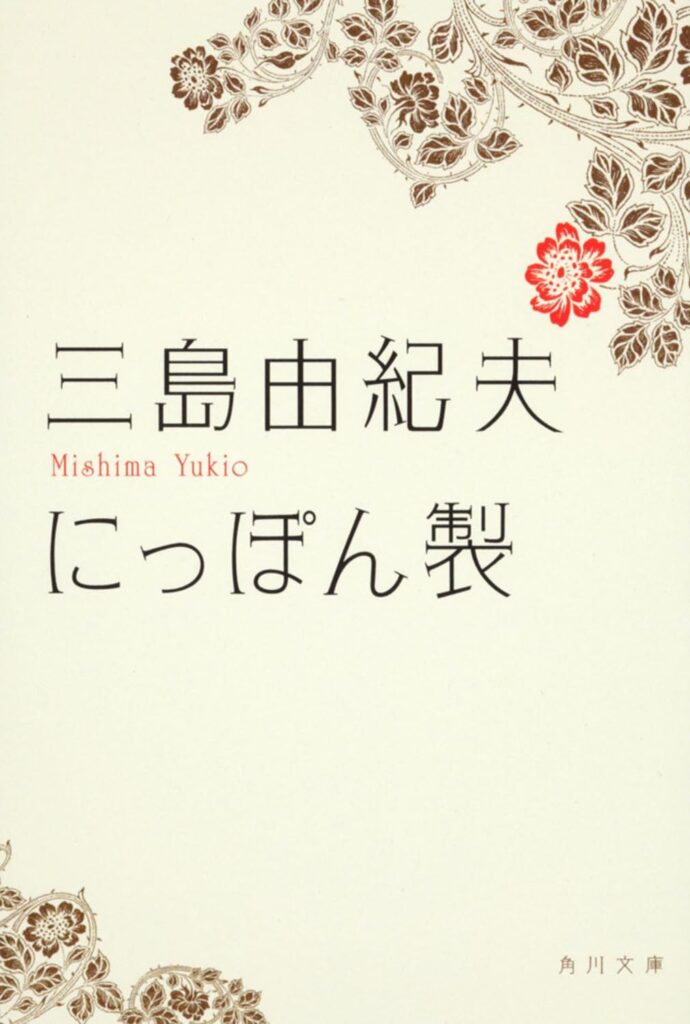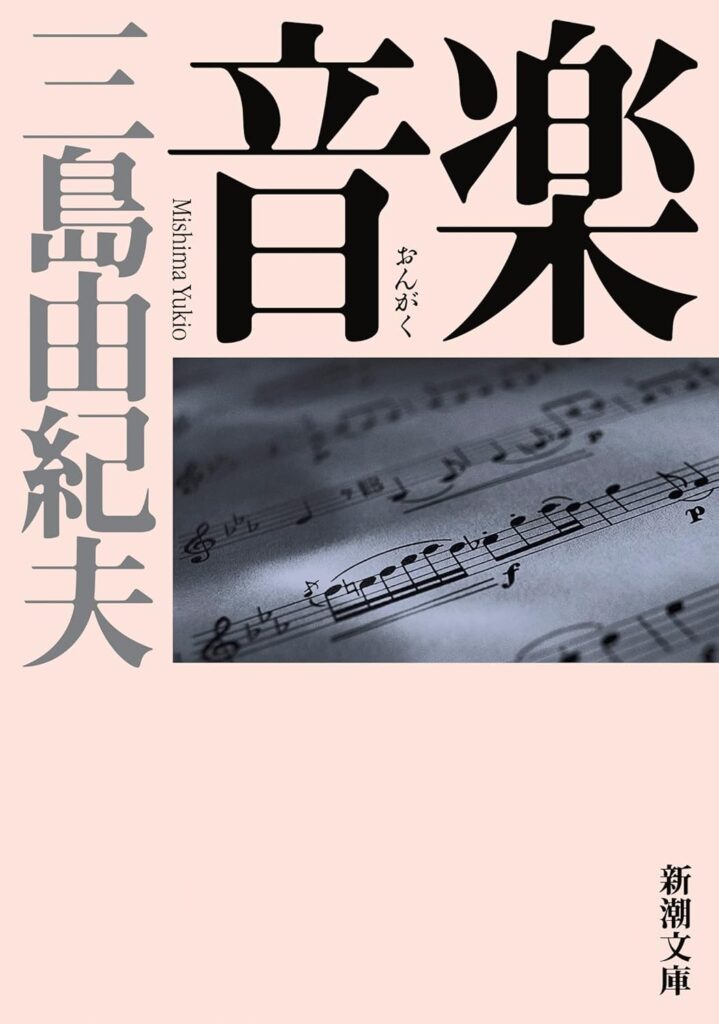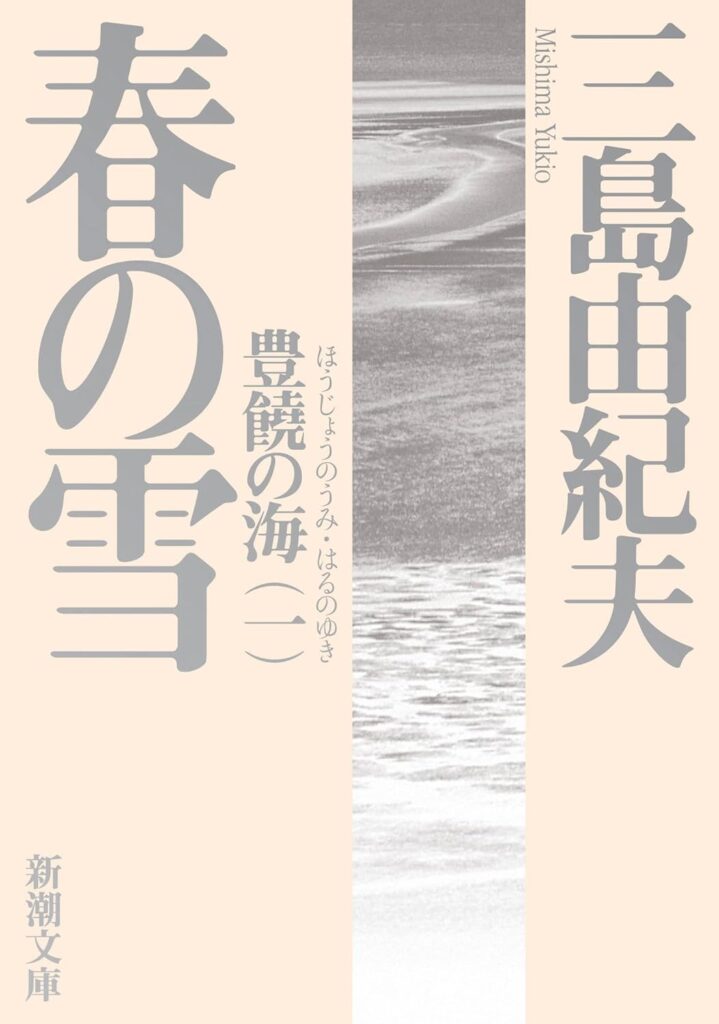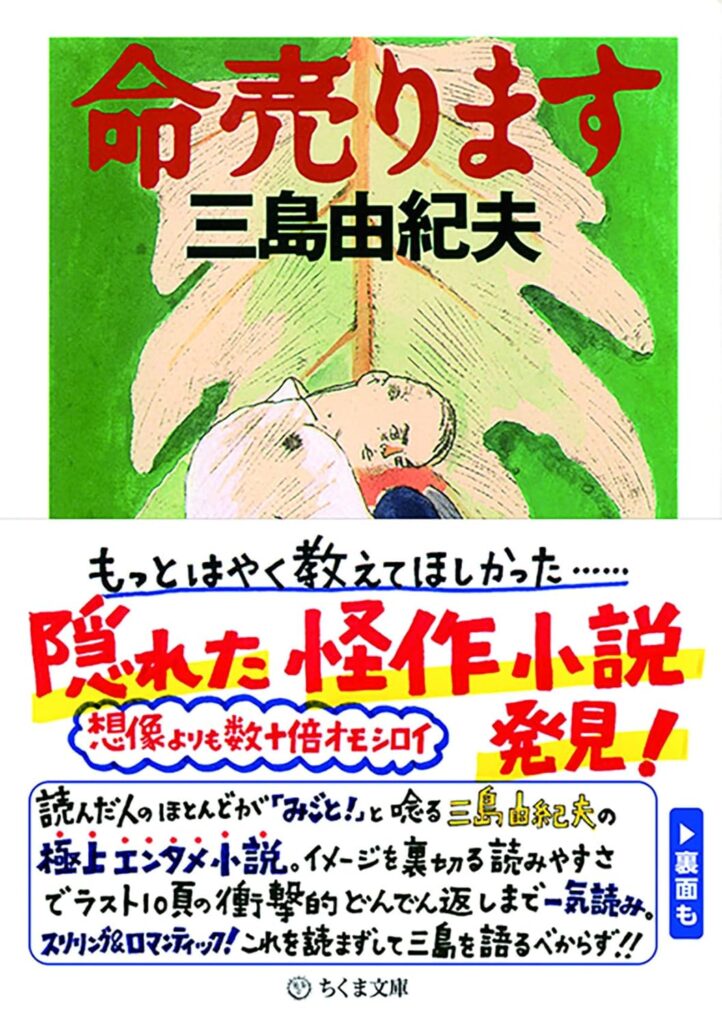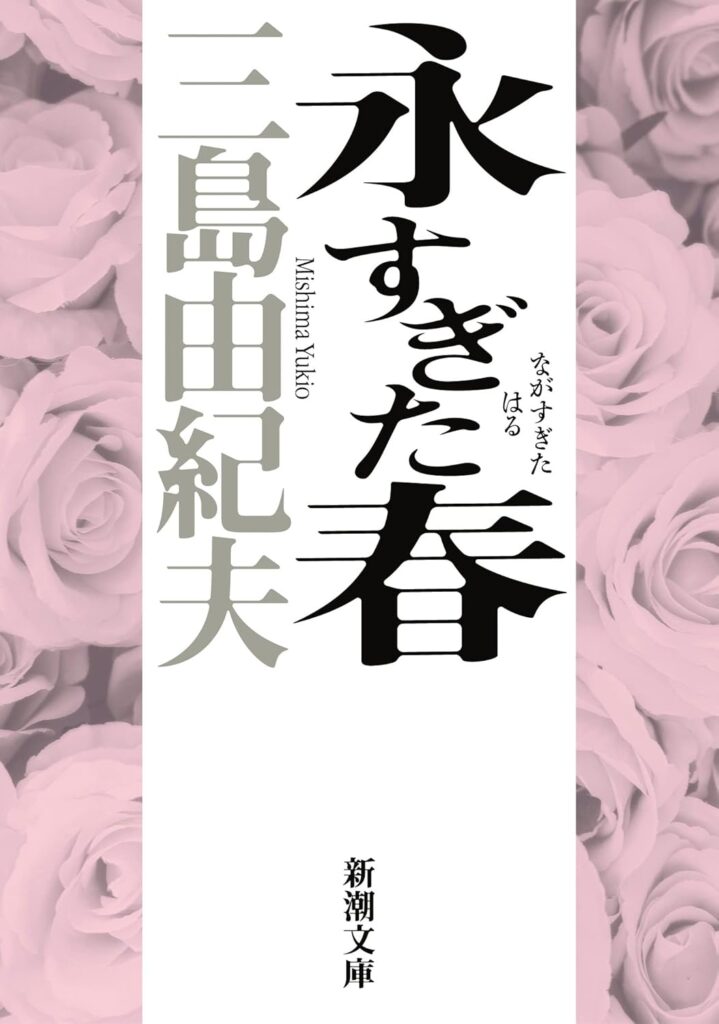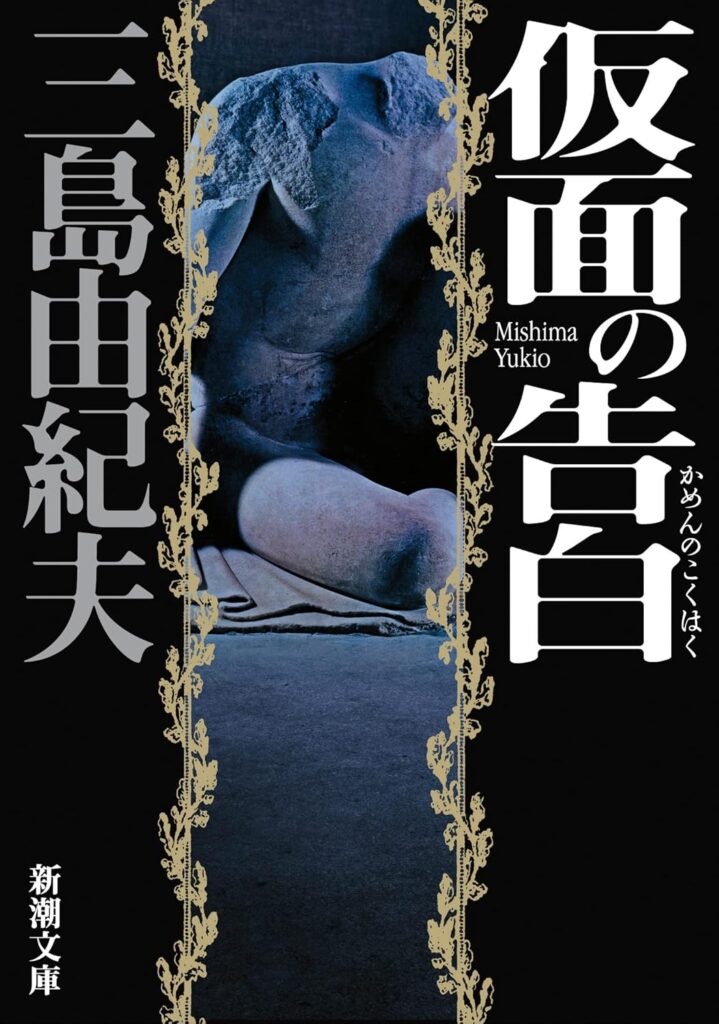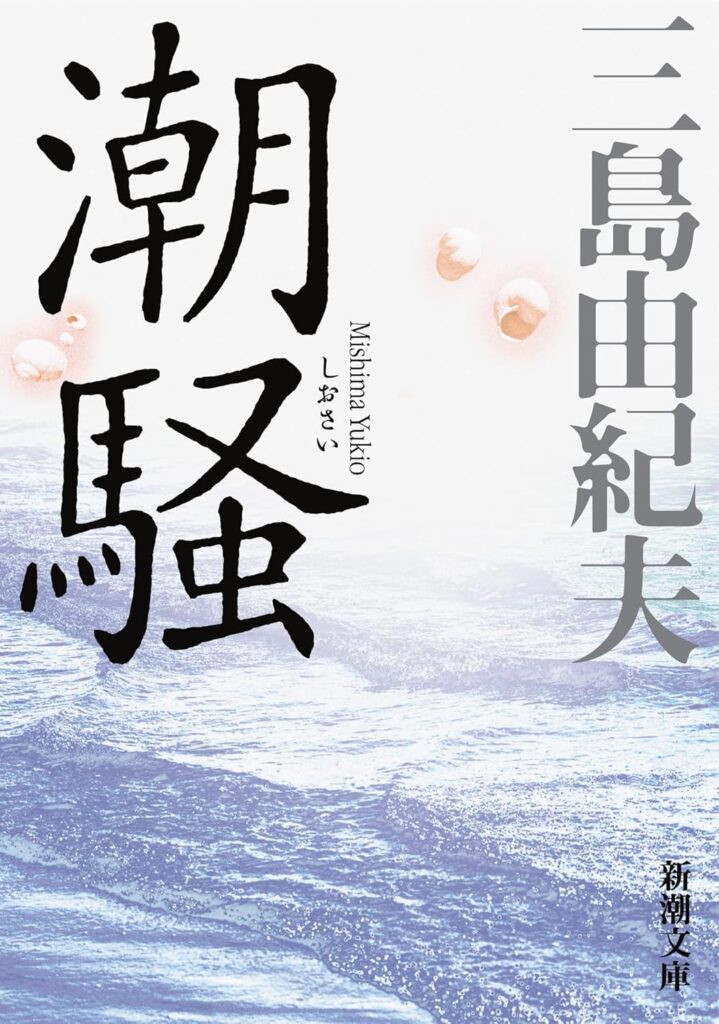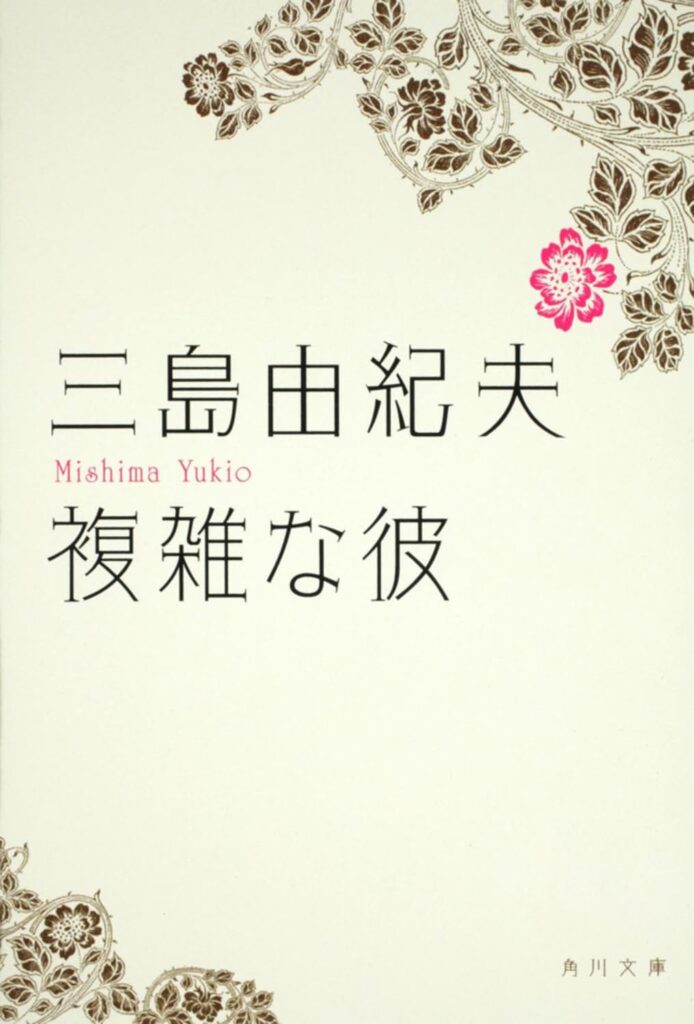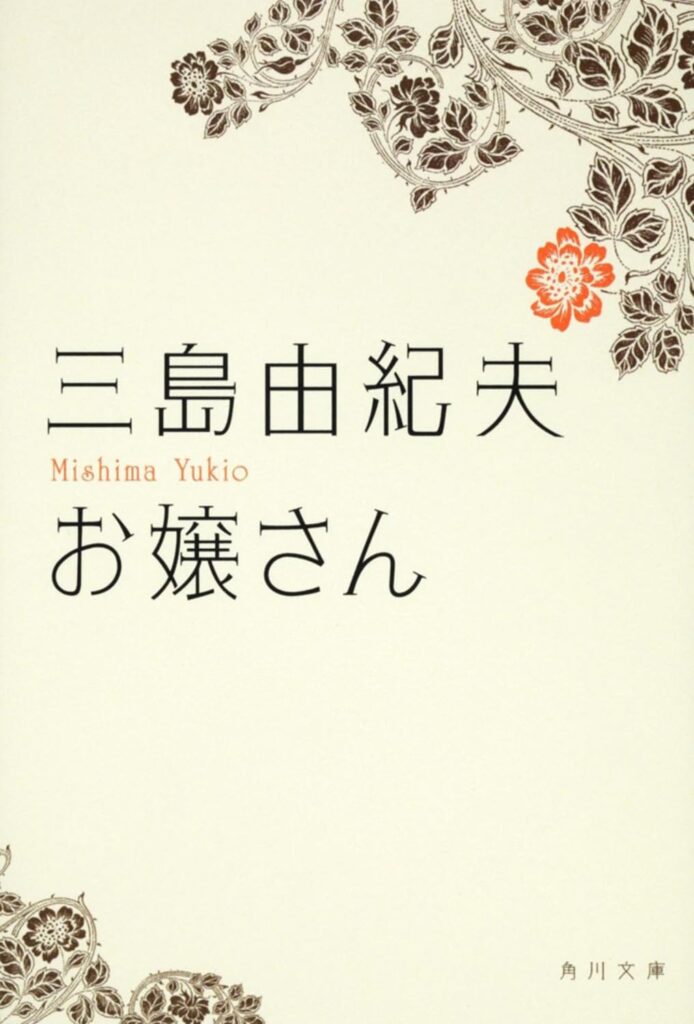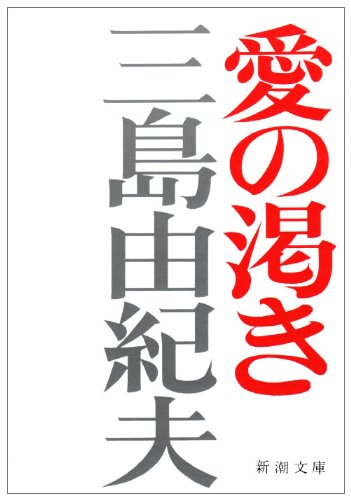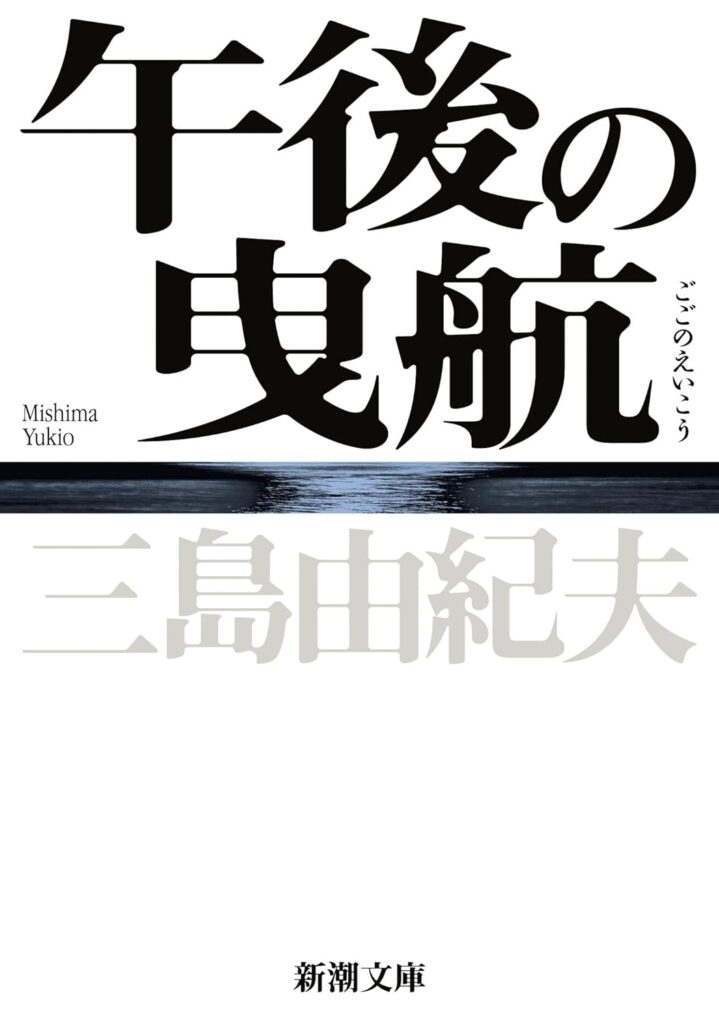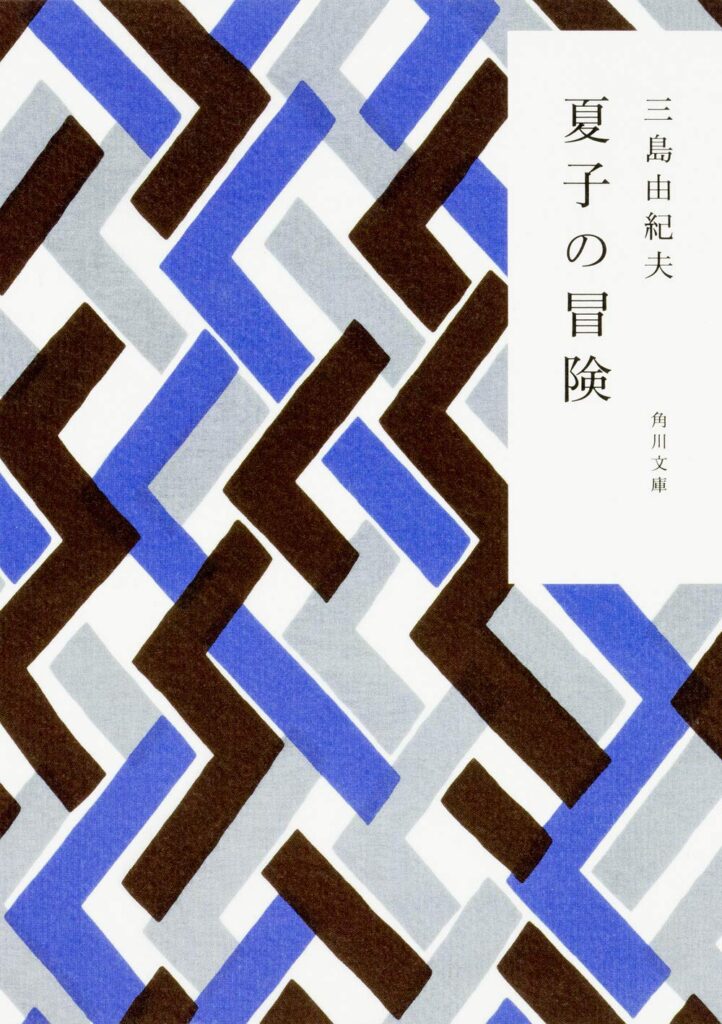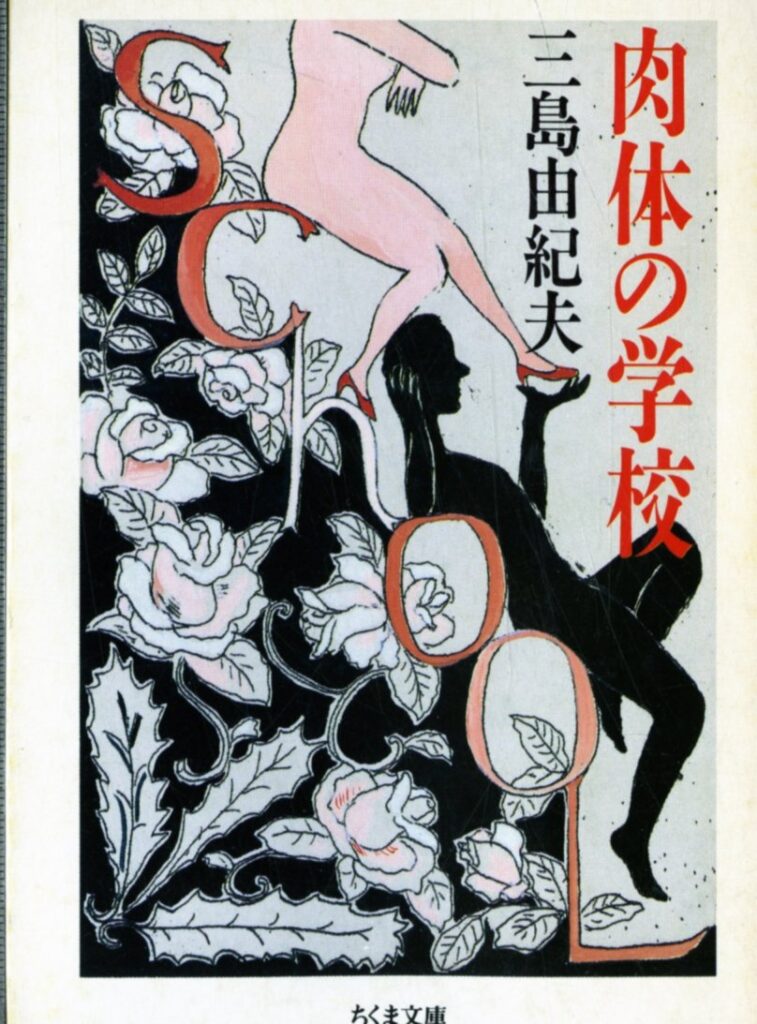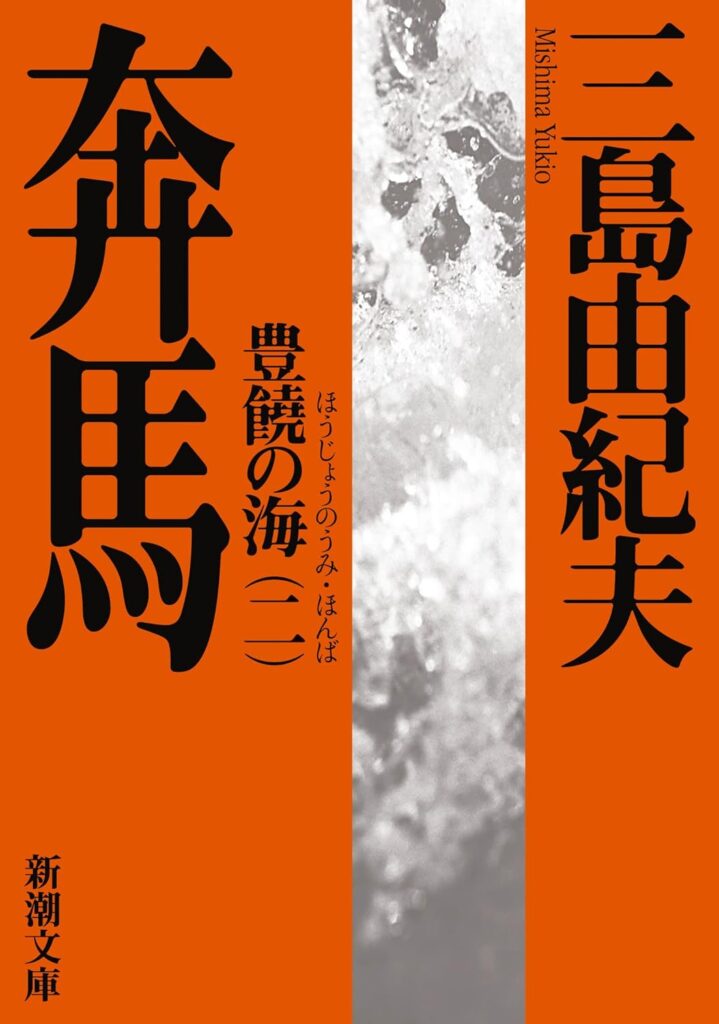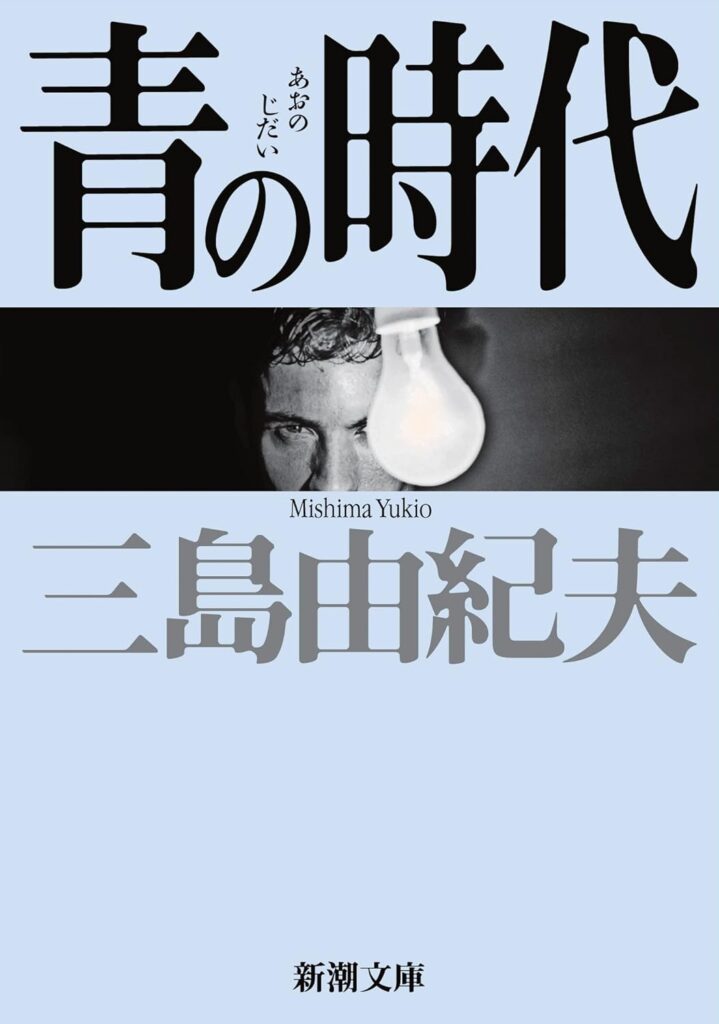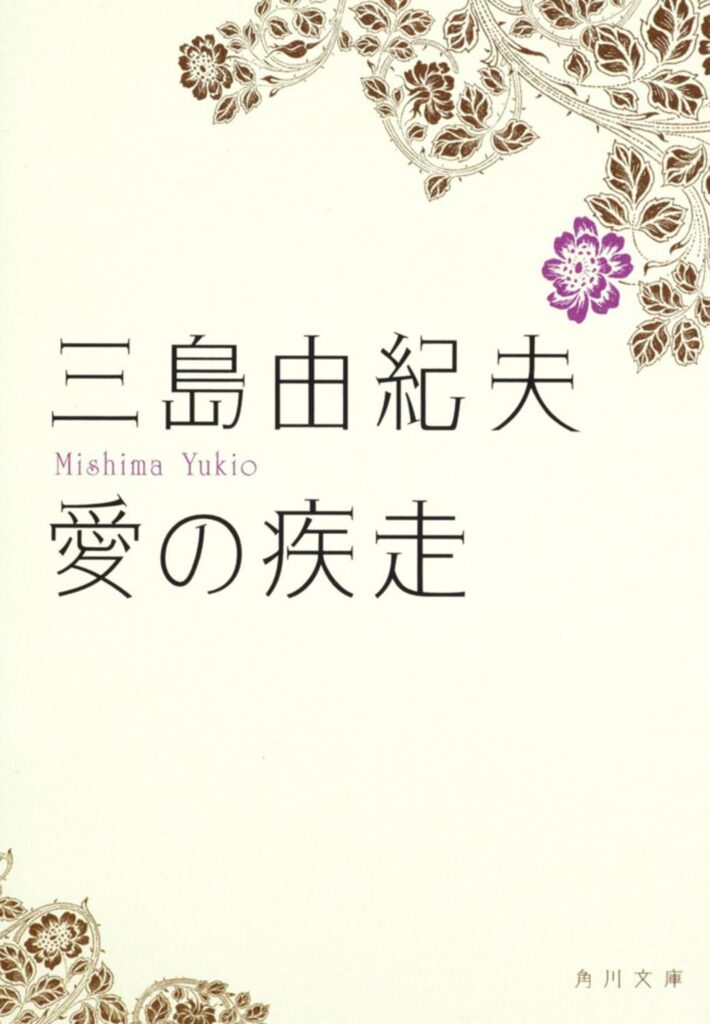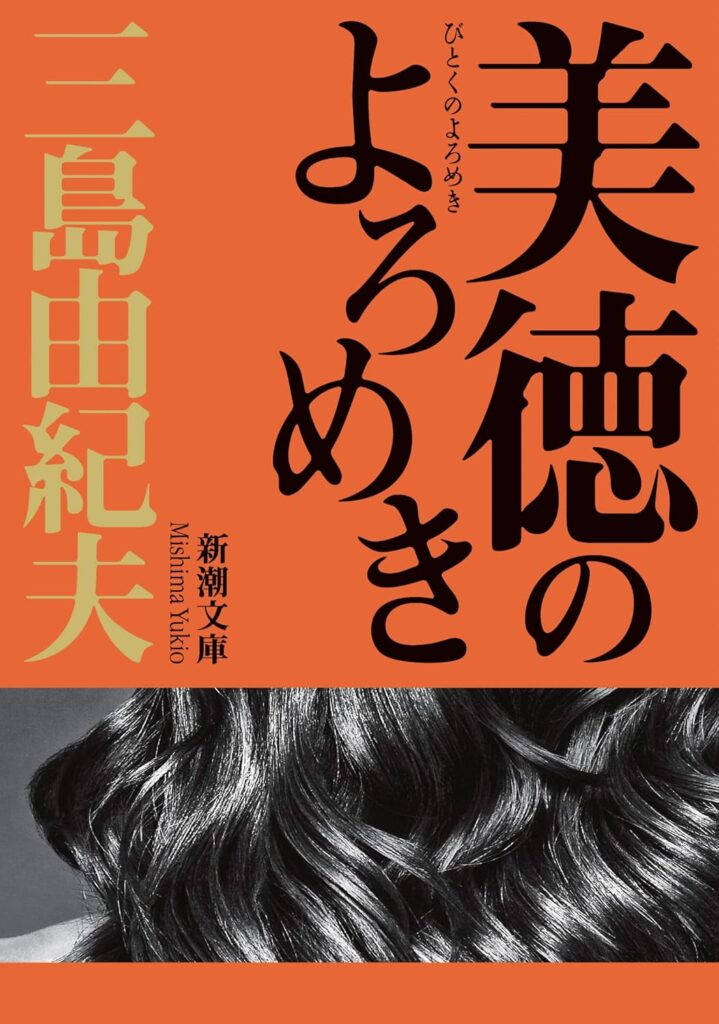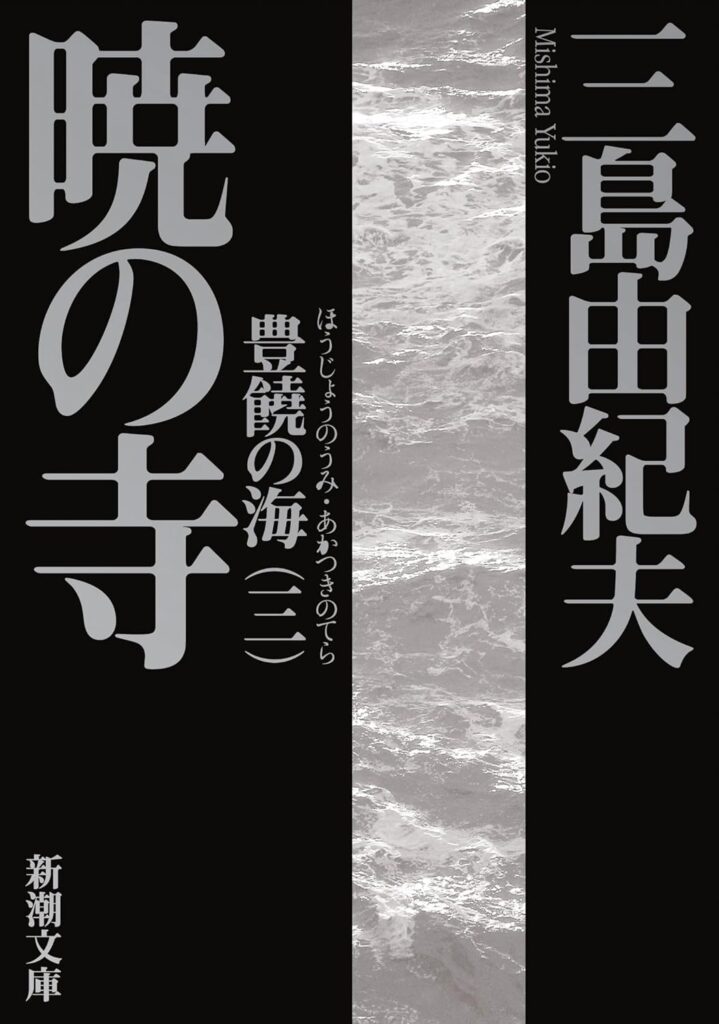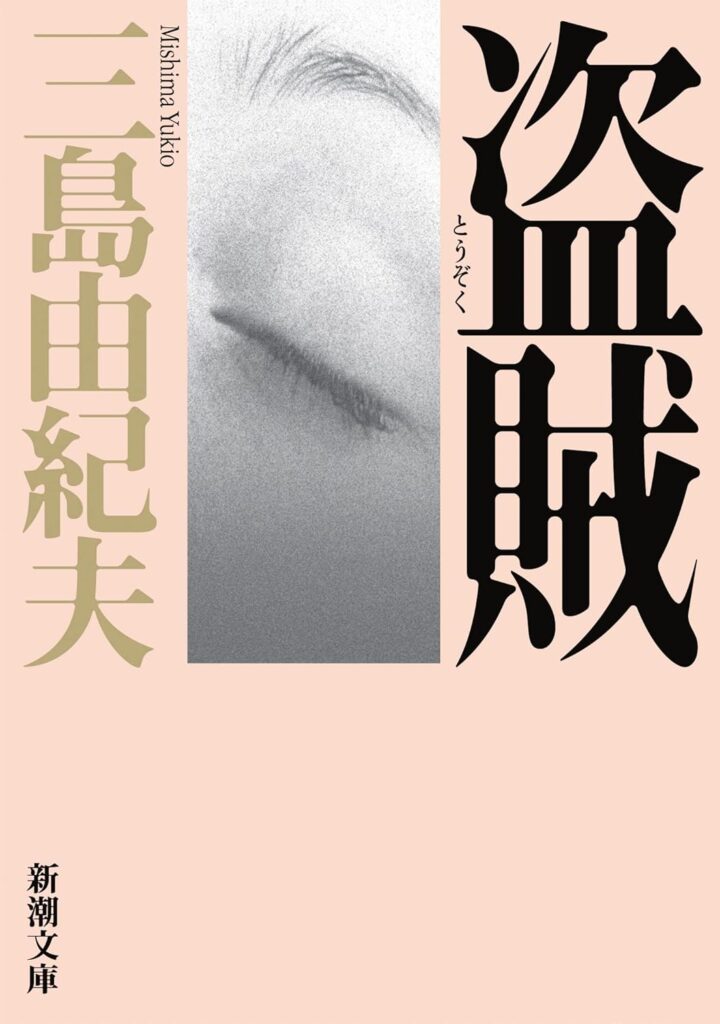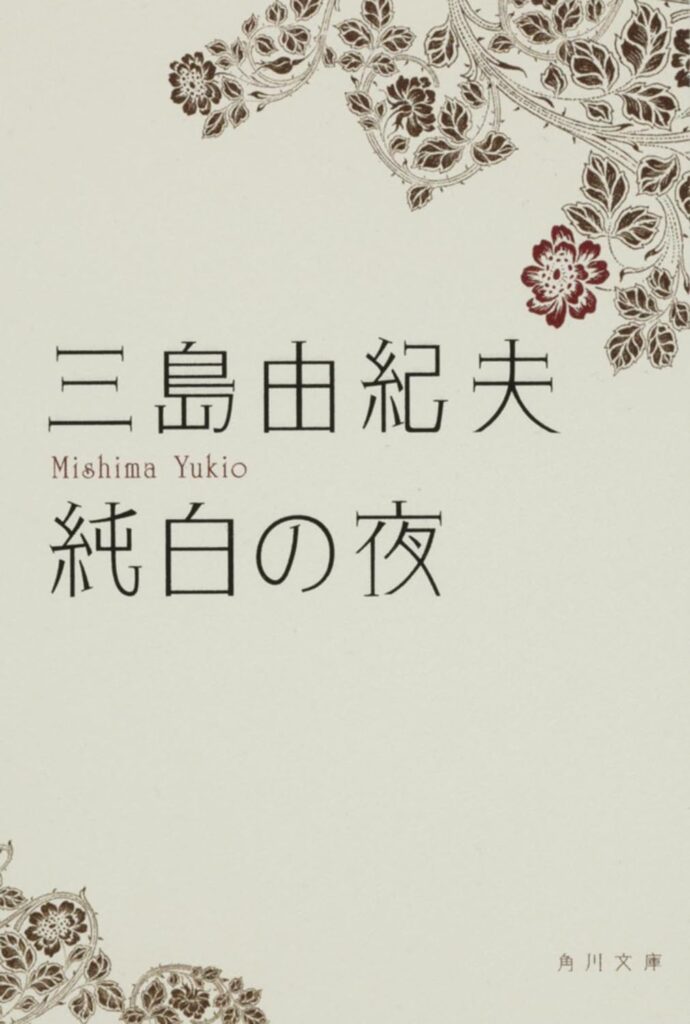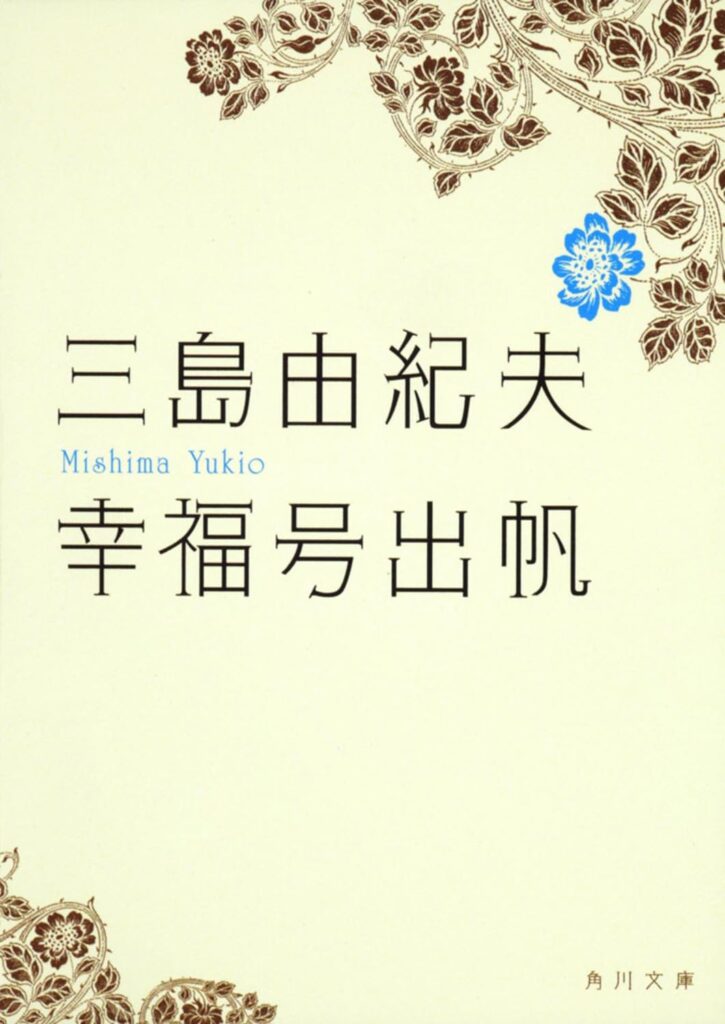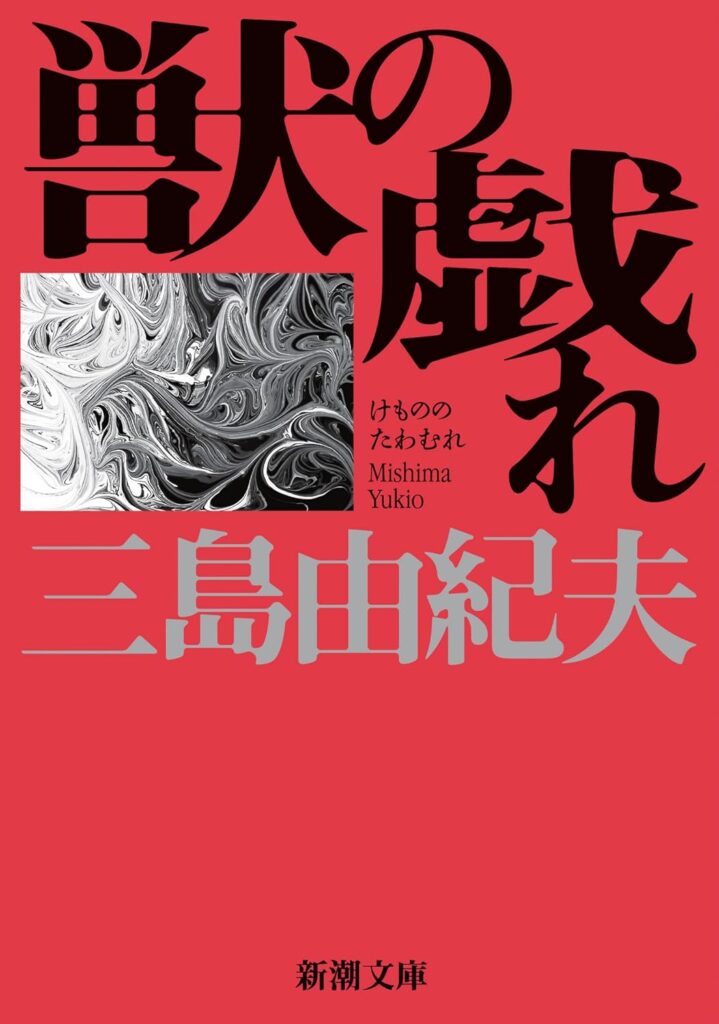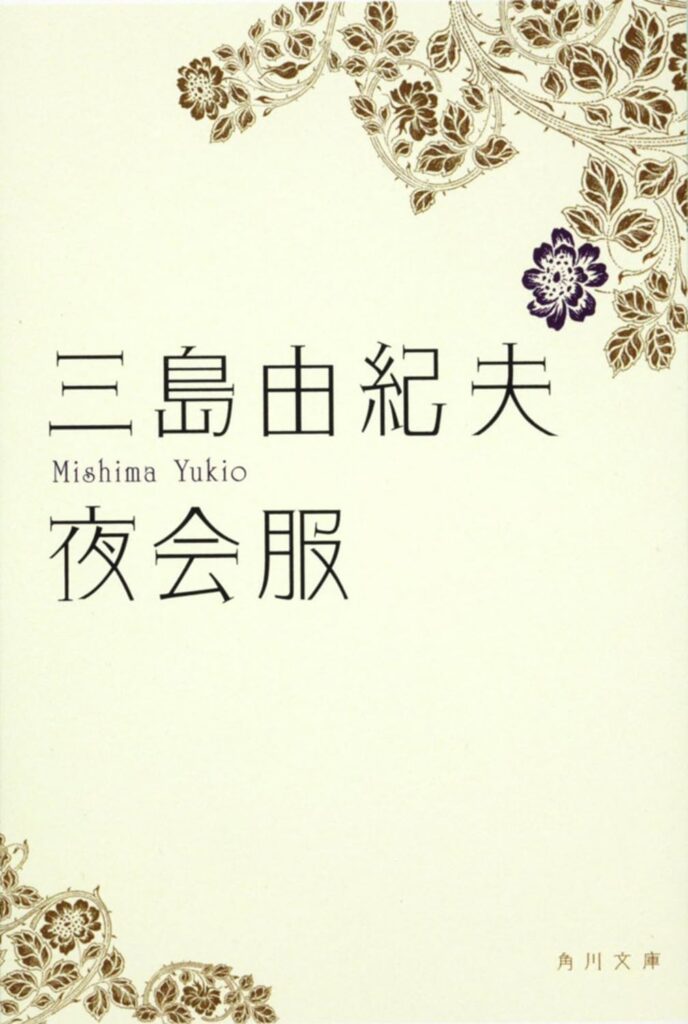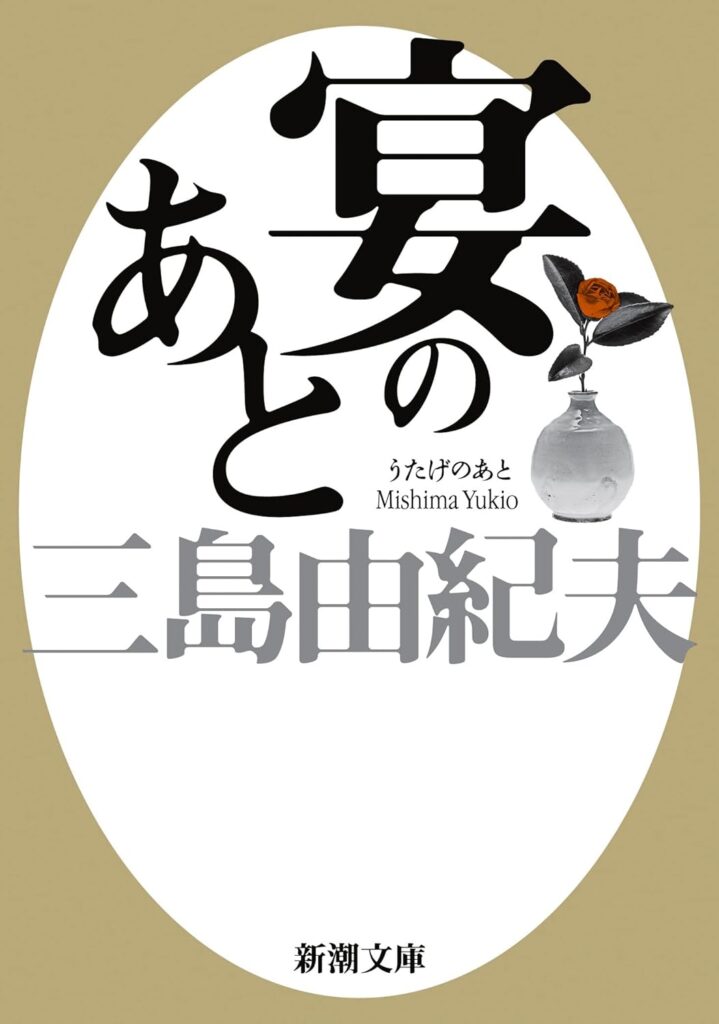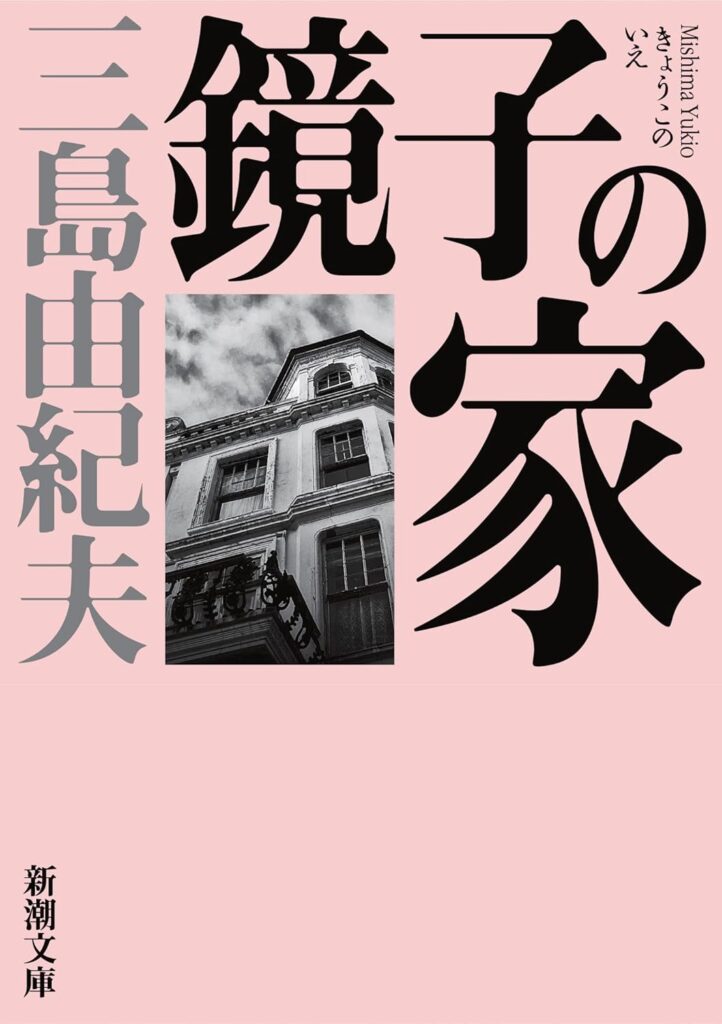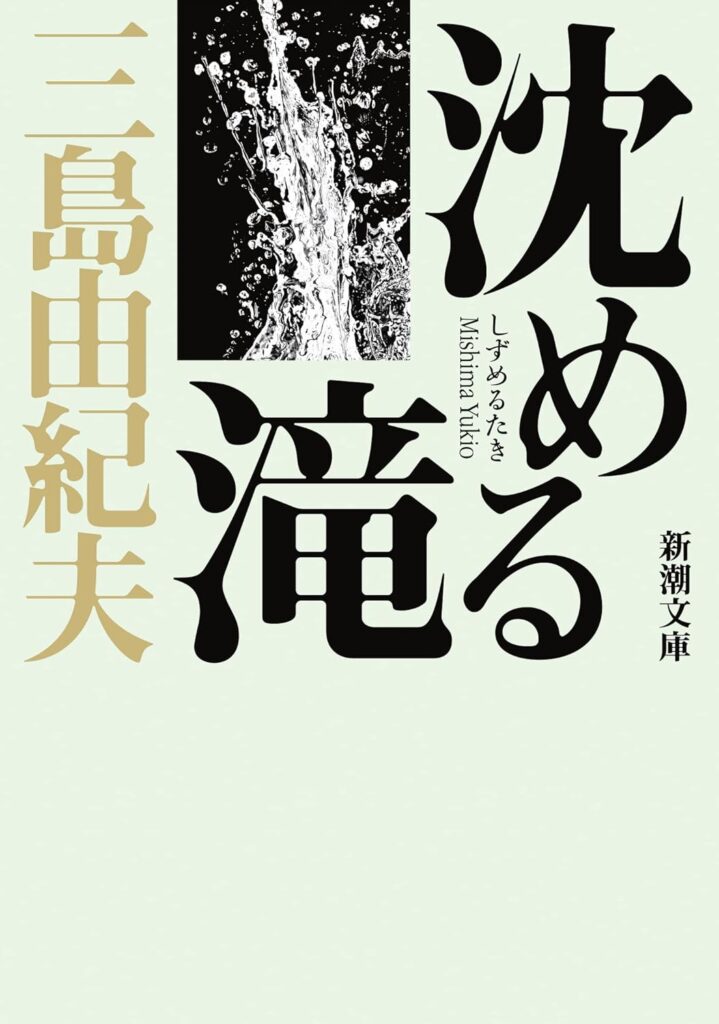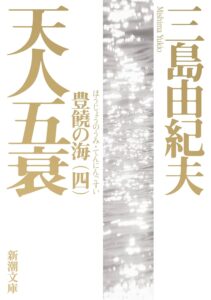 小説「天人五衰」のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文の感想も書いていますので、どうぞ。
小説「天人五衰」のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文の感想も書いていますので、どうぞ。
三島由紀夫がその文学的遺産として世に残した「豊饒の海」四部作は、彼の創作活動の頂点に位置する壮大な物語です。『春の雪』、『奔馬』、『暁の寺』、そして最終巻であるこの『天人五衰』から構成されています。この作品群は、主人公である本多繁邦が、左脇腹に三つの黒子を持つ若者たちが、彼の親友であった松枝清顕の生まれ変わりであると信じ、その転生を生涯にわたって追い続けるという「輪廻転生」の主題を中心に展開されていくのです。各巻の主要人物、すなわち清顕、飯沼勲、ジン・ジャンは、いずれも若くして夭折するという共通の運命を辿ります。
三島は、この四部作を通じて意図的に文体を変化させています。これは単なる物語の展開に合わせたものではなく、各巻のテーマや登場人物の「認識」の質を表現する文学的試みです。例えば、『春の雪』の装飾的で擬古文的な文体は、清顕の感性を通して見た貴族的な「夢」の世界を構築する役割を担っています。これに対し、『天人五衰』の比較的プレーンで硬質な文体は、最終的に到達する「無」の境地や、本多の認識の崩壊、透の冷酷な「見る」行為といった、より現実的で剥き出しの真実を描写するために選ばれたものと考えられます。このように、文体の変化は、各巻における「見る者」と「見られる者」の関係性、そして「認識」のあり方を文学的に表現する三島の高度な技巧であり、単なる物語の進行以上の深い意味合いを持っているのです。
『天人五衰』は、三島由紀夫が割腹自殺を遂げた1970年11月25日に書き上げられた、まさに彼の「遺作」です。この作品の完成と作者の自決が同時であったという事実は、本作が三島の思想と行動の集大成であることを強く示唆しています。この最終巻では、物語を長きにわたり牽引してきた本多繁邦が老境に差し掛かり、新たな転生候補である安永透との出会いを通じて、彼の人生における「輪廻転生」への確信が最終的に崩壊する過程が描かれています。
小説「天人五衰」のあらすじ
物語は1960年代末から70年代初頭を背景に始まります。76歳になった本多繁邦は、友人の久永慶子と共に静岡県の景勝地、三保の松原を訪れます。そこで、帝国信号通信所で働く16歳の孤児、安永透と偶然出会うのです。本多は透の左脇腹に、松枝清顕、飯沼勲、ジン・ジャンといった過去の転生者たちと同じ「三つの黒子」を発見し、透が清顕らの生まれ変わりであると確信します。
本多は透の中に「純粋な悪」と、自分自身と全く同じ「自意識の機構」を見出し、強い印象を受けます。妻の利枝を亡くし、跡継ぎのいない本多は、透を養子に迎えることを決意するのです。物語冒頭の三保の松原、特に「枯死寸前」の羽衣の松の描写は、本多の「あるべき美」への執着と、現実の「俗化」に対する幻滅を象徴しており、彼の「見る」行為がもはや真実を捉えきれない限界を示唆しています。三保の松原は謡曲「羽衣」の舞台であり、天人の美しく衰亡する姿が連想される場所です。
本多は透に洋食の作法からそつのない受け答えに至るまで、徹底した英才教育を施します。聡明な透は一見従順にそれらを習得しますが、内心では自分の中にある「悪」を使う機会を密かに狙っていました。透は次第に「悪魔的な行動」を取るようになり、婚約者を婚約破棄に陥れます。東京大学に入学してからは、養父である本多を虐待するようになるのです。その心労により、本多は公園で久々に「覗き見」をしてしまい、警察に捕まるという醜聞が報道されます。
この事件を機に、透は本多家の実質的な支配者となり、財産を狙って本多家を乗っ取ろうと画策し始めます。透は自分を美女と思い込んでいる精神的に不安定な女性、絹江を別荘に住まわせます。透の「悪」の本性の露呈と本多への虐待は、単なる養子と養父の関係の悪化に留まりません。それは本多自身の内なる「悪」や「傲慢さ」が透を通して具現化されたものであり、本多の「天人五衰」の相を加速させるのです。
久永慶子は、透に本多が彼を養子にした本当の理由、すなわち「三つの黒子」と「輪廻転生」の物語を打ち明けます。慶子は透に対し、「あなたは贋者であり、陰気な相続人になるだけだ」と怒りを込めて告げます。彼女は、清顕が恋情に、勲が使命に、ジン・ジャンが肉に「つかまれて」いたのに対し、透は「自分は人とはちがうという、何の根拠もない認識だけ」につかまれていたと指摘するのです。慶子の言葉に自尊心を深く傷つけられた透は、清顕の「夢日記」を読み、それを焼却した後、服毒自殺を図ります。
しかし、透は死にきれず、結果として双生児の「贋物」であることの証明となり、さらに「失明」してしまうのです。この事件により、透の性格は完全に変貌し、大学を辞め、点字を学び、穏やかな生活を送るようになります。彼は精神的に不安定な絹江という女性と結婚し、彼女のなすがままにされるようになるのです。絹江は透の頭に花を飾り、その様子は「天人五衰」のようだったと描写されます。やがて絹江は妊娠します。
透が21歳で絹江と結婚し妊娠させ、本多が期待した「20歳での夭折」が訪れなかったことで、本多の輪廻転生への確信は揺らぎます。自身の死期が近いことを感じた本多は、人生の締めくくりとして、60年ぶりに月修寺を訪れ、かつての恋人であった綾倉聡子(現・門跡)に面会を求めます。本多は聡子に清顕の思い出を語り、輪廻転生の物語が肯定されることを期待するのです。しかし、聡子は清顕のことを全く知らないと発言し、「松枝清顕さんという方は、お名をきいたこともありません。そんなお方は、もともとあらしやらなかつたのと違ひますか」と問いかけます。
この聡子の発言により、これまで本多が信じてきた輪廻転生の物語は一挙に崩れ去り、清顕、勲、ジン・ジャンの存在、ひいては本多自身の存在理由さえも「無」に帰そうかという衝撃を受けるのです。本多は「この庭には何もない。記憶もなければ何もないところへ、自分は来てしまつた」と感じ、物語は「空無」の中で締めくくられます。
小説「天人五衰」の長文感想(ネタバレあり)
三島由紀夫の文学的遺産において、「豊饒の海」は彼の創作活動の頂点に位置する四部作の長編作品です。この壮大な物語は、『春の雪』、『奔馬』、『暁の寺』、そして最終巻である『天人五衰』から構成されています。本作品群は、主人公である本多繁邦が、左脇腹に三つの黒子を持つ若者たちが、彼の親友であった松枝清顕の生まれ変わりであると信じ、その転生を生涯にわたって追跡し続けるという「輪廻転生」の主題を中心に展開されます。各巻の主要人物、すなわち清顕、飯沼勲、ジン・ジャンは、いずれも若くして夭折するという共通の運命を辿るのです。
第一巻『春の雪』では、若く高貴な松枝清顕と綾倉聡子の悲劇的な恋愛が、絢爛たる文体で描かれ、その「美」が際立っています。続く第二巻『奔馬』では、清顕の転生とされる飯沼勲が登場し、右翼思想と行動の美学が探求されるのです。第三巻『暁の寺』では、シャムの王女月光姫(ジン・ジャン)が転生者として現れ、唯識論をはじめとする仏教思想が深く考察されます。
三島は、この四部作を通じて意図的に文体を変化させています。これは単なる物語の展開に合わせたものではなく、各巻のテーマや登場人物の「認識」の質を表現する文学的試みです。例えば、『春の雪』の装飾的で擬古文的な文体は、清顕の感性を通して見た貴族的な「夢」の世界を構築する役割を担います。これに対し、『天人五衰』の比較的プレーンで硬質な文体は、最終的に到達する「無」の境地や、本多の認識の崩壊、透の冷酷な「見る」行為といった、より現実的で剥き出しの真実を描写するために選ばれたものと考えられます。このように、文体の変化は、各巻における「見る者」と「見られる者」の関係性、そして「認識」のあり方を文学的に表現する三島の高度な技巧であり、単なる物語の進行以上の深い意味合いを持っています。
『天人五衰』は、三島由紀夫が割腹自殺を遂げた1970年11月25日に書き上げられた、まさに彼の「遺作」です。この作品の完成と作者の自決が同時であったという事実は、本作が三島の思想と行動の集大成であることを強く示唆しています。この最終巻では、物語を長きにわたり牽引してきた本多繁邦が老境に差し掛かり、新たな転生候補である安永透との出会いを通じて、彼の人生における「輪廻転生」への確信が最終的に崩壊する過程が描かれています。作品の結末は「空無」へと帰結し、この「虚無」は三島が戦後日本に感じたものと一致すると解釈されています。
『天人五衰』の結末における「虚無」への到達は、単なる物語の終焉ではありません。それは三島自身の「文武両道」の思想、特に「鍛え上げられた肉体の破壊」としての自決と深く結びついた、自己否定の循環を内包する哲学的な帰結です。三島は「創作ノート」において、この四部作の結びとして「愛と死、政治と運命の大対立」を求めていたと記されており、そこには「行動者と記述者、存在と行為、肉体と精神等の人間の最重要の対立」があるべきだと考えていました。本多が最終的に「何もない」世界に到達する物語の結末は、三島が「虚無」を認識し、それを文学で表現する過程そのものであると捉えられます。そして、その文学的表現が究極の「自己否定」に至ることで、三島は自身の肉体という「存在」を破壊する「行動」を選んだのです。これは、彼の思想における「大対立」の最終的な解決であり、文学が信仰では救えない問題を扱う領域であるという彼の信念を体現しています。したがって、『天人五衰』は、三島の人生の最終章であり、文学と実存、哲学と行動が一体となった、極めて個人的かつ普遍的な「虚無」の探求の記録であると言えるでしょう。
主要登場人物の紹介:本多繁邦:永遠の「観察者」としての老いと変化
本多繁邦は、「豊饒の海」四部作を通して登場する唯一の人物であり、物語全体の「観察者」としての役割を担います。『天人五衰』では76歳から81歳という老境にあり、その肉体的・精神的な衰えが詳細に描かれています。彼は生涯を通じて「眺めること」を使命とし、情念に深く触れることなく、整然とした秩序を内外に保つことに専念してきた「見る者」です。しかし、その「見る」行為は、第三巻『暁の寺』において「覗き魔」へと転落し、彼の醜悪な側面が露呈します。最終的に、本多は自身の「過度の明晰」を慰めるために他人の「狂気」を必要とし、転生への執着から透を「穢そうとする」倒錯した側面も持つようになります。
本多の老いは、単なる加齢の描写に留まりません。それは仏教における「天人五衰」の相、特に「本座に安住することを楽しまない」という状態と深く共鳴しており、彼自身の内なる「腐敗」を象徴しています。天人五衰は、天人が死に至る際に現れる五つの兆候であり、肉体的な衰弱だけでなく、精神的な「本位を楽しまない」という状態も含まれます。本多は、長年転生を観察し、他者の人生に干渉することで自身の生を「本位を楽しまず」に生きてきたのです。終盤、81歳の本多は体の不調を通して「自らがすべて統制し支配できるという傲慢さ」を失いますが、これは肉体の苦痛が与える「解放」であると同時に、彼が「見る者」としての限界と、自己の「腐敗」を認識する過程と解釈できます。三島自身が自身の「腐敗」を自決の動機としたことと重ね合わせると、本多の老いは単なる肉体的な衰えではなく、三島が感じた戦後日本の「腐臭」や、自己の存在論的な「無」への接近を象徴しているのです。したがって、本多の老いと「天人五衰」の相は、彼の人生の終焉における肉体と精神の「腐敗」を多層的に表現しており、作品のタイトルが本多自身の内面的な状態をも指し示していると言えるでしょう。
主要登場人物の紹介:安永透:最後の転生候補としての登場と本性
安永透は、本多が人生の最後に「見出した」少年であり、清顕らの生まれ変わりであると看過されます。彼は16歳の孤児で、無線通信士として港に出入りする船を見張る仕事をしていました。透は「凍ったように青白い美しい顔」を持ち、「心は冷たく、愛もなく、涙もなかった」と描写されますが、「眺めることの幸福」を知り、自身の「見る」能力を天賦の才と信じ、あらゆる他人を軽蔑する強い自尊心を持つ存在です。本多は透の中に「純粋な悪」と、自身の「自意識の雛形」とも言える「磨き上げられた荒涼とした無人の工場」を発見するのです。
透の「見る」行為は、単なる視覚的な認識を超え、究極の明晰さの果てに「何も現れないことの確実な領域」に至るものです。透の「見る」は「何も創り出さないで、ただじっと眺め」るものであり、「見えざる水平線は、見える水平線よりもはるか彼方にあった」と表現されます。この究極の「見る」では、「美さえも、引きずり朽され使い古された裳裾のように、ぼろぼろになってしまう」とされ、「物象も認識もともどもに、酢酸に涵された酸化鉛のように溶解して」しまう「何も現れないことの確実な領域」が描かれます。これは、彼にとって「自己放棄」ひいては「死ぬこと」を意味するのです。透の「見る」は、対象と主体が単に映し合う通常の認識(主客の構造)を超越した状態を目指しています。認識が極限まで透徹した結果、認識対象も認識主体も溶解し、究極の「無」に至ることを示唆しているのです。この「無」への到達は、彼自身の存在の希薄化、すなわち「自己放棄」であり、ある意味で「死」に等しいでしょう。本多もまた「真に見たいものを見るためには、自分が死なねばならないと考えた」とされており、透はこの本多の深層にある「見る」ことの究極的な願望を、より純粋な形で体現しています。透の失明は、この「見る」ことの終焉であり、彼が「見る者」としての役割を終え、ある種の「死」を経験したことを象徴しています。したがって、透の「見る」行為は、単なる視覚能力ではなく、認識の限界を超えた「無」への探求であり、その過程で自己を放棄し、ある種の死を迎えるという、本多の精神的遍歴の極致を体現する存在です。
主要登場人物の紹介:久永慶子:物語の転換点となる役割
久永慶子は、本多の友人であり、物語の重要な転換点において透に真実を突きつける役割を果たします。彼女は透を「贋者」と断じ、彼の自尊心を打ち砕くことで、物語の輪廻転生という主題を揺るがす存在となるのです。慶子は、本多や透が追い求める「幻影」としての輪廻転生や「美」に対し、俗化された現実をも肯定的に捉える「現実主義者」として描かれており、彼女の存在が物語の「夢・幻」の境界を曖昧にする役割を果たします。慶子は透に「あなたには必然性もなければ、誰の目にも喪ったら惜しいと思わせるようなものが、何一つないんですもの」「あなたは贋者」と告げます。
また、荒れ果てた羽衣の松を見ても「これはこれで結構だわ」「いくら汚れていたって、いくら死にかけていたって、この松もこの場所も、幻影に捧げられていることは確かなんですもの」と肯定的に捉えているのです。本多が理想的な「美」や「転生」の幻影を追い、現実の俗化に幻滅するのに対し、慶子は「幻影に捧げられている」という本質を見抜きつつ、現実の「汚れた」「死にかけている」状態をも「日本的で、さりげなくて、自然」と肯定します。この姿勢は、本多の「あるべき『美』を前提にした知識人の限界」を対比的に浮き彫りにするのです。慶子の「贋者」という言葉は、透の自己認識だけでなく、本多が構築してきた「輪廻転生」という物語全体が「幻影」であった可能性を強く示唆します。彼女は、物語の「目に見えていたものと夢・幻の境界」を曖昧にし、読者に「何が現実か」という問いを投げかけるのです。したがって、慶子は単なる情報提供者ではなく、本多の幻想的な世界観と対峙する「現実」の象徴であり、物語の核心である「幻」の性質をより複雑に提示する役割を担っています。
主要登場人物の紹介:綾倉聡子:月修寺門跡としての存在と結末への影響
綾倉聡子は、第一巻『春の雪』のヒロインであり、松枝清顕の恋人であった女性です。清顕との悲劇的な恋の末に出家し、月修寺の門跡となっています。物語の最終盤、本多が60年ぶりに月修寺を訪れた際、彼が語る清顕の存在を全く知らないと発言し、物語の輪廻転生を根底から覆す決定的な役割を果たすのです。彼女は「忘却という羽衣が業の深い人間を静穏にしてくれる」存在として描かれ、老いても「清潔」で「凛とした美」を保ち、「浄化」された姿を見せます。
聡子の清顕に対する「忘却」は、単なる記憶の喪失ではありません。それは輪廻転生という物語の「時間」そのものを否定し、「空無」へと帰結させる決定的な要素です。彼女の「音楽性」は、この循環する時間の本質を体現し、本多の認識を揺るがします。本多が60年間追い求めてきた「輪廻転生」という物語は、彼の「認識」によって構築されたものに過ぎません。聡子の「清顕など知らない」という言葉は、その認識の根幹を否定し、本多の人生そのものを「夢」や「幻」へと帰結させるのです。聡子の「忘却」は、過去の「業」からの解放であり、彼女が「時間内存在」として「音楽性」を体現することで、循環する時間の本質を捉えています。これは、過去に執着し「時間外存在」として「見る」ことに固執した本多とは対照的です。聡子の「浄化された老い」は、最終的な「空無」の境地を象徴しています。したがって、聡子は単なる登場人物ではなく、三島が探求した「時間」と「認識」の最終的な真理、すなわち「空無」を体現する存在であり、彼女の言葉が物語全体の「豊饒の海」を「何もない」庭へと変容させるのです。
「天人五衰」の象徴性と主要テーマの考察:天人五衰の相と老い、腐敗の描写
「天人五衰」は仏教思想に由来し、欲界・色界の天人が寿命が尽きる際に現れる五つの異相を指します。三島は仏教大辞典からこれらの相を詳細に引用し、自身の「遺書」としてこの作品を残したことを示唆しています。本多の老いは、肉体の衰えとしてだけでなく、自身の「傲慢さ」や「支配欲」を失う過程として描かれ、ある種の「解放」をもたらします。彼は「人間に生まれてきたということの罠に一旦落ちながら、ゆくてにそれ以上の罠が待ち設けていてよい筈がない」と悟り、すべてを愚かしく受け入れる姿勢を見せるのです。
三島は「人間の美しさ、肉体的にも精神的にも、およそ美に属するものは、無知と迷蒙からしか生まれない」と述べ、知識を得ることで美を失うという独自の美学を提示しています。特に「肉体美」を「人間にとって本筋の美しさ」とし、精神的な美は二次的であると主張しています。透の「天人五衰」の相と本多の老いによる「腐敗」の描写は、三島が追求した「美」が、知性や知識の蓄積によって「醜さ」へと変質し、最終的に「無」へと帰結する過程を象徴的に示しています。透の頭に花が飾られ「天人五衰」のようだったと描写されるのは、彼が「贋者」として生きながらも、その存在が「天人」のような美しさから「腐敗」へと向かう過程を象徴しています。これは、本多が透の中に自身の「自意識の雛形」を見たことと結びつき、本多自身の「腐敗」と重なります。三島が「美は無知と迷蒙から生まれる」と主張し、知識の蓄積が美を失わせると考えるならば、本多の「過度の明晰」や「知性」は、彼を「覗き魔」へと転落させ、最終的な「何もない」境地へと導く「醜さ」の根源となるのです。この「天人五衰」は、単なる肉体的な衰えだけでなく、知性や認識が美を損ない、最終的に「無」へと帰する過程を多層的に表現しています。したがって、『天人五衰』の相は、透と本多の「美」が「腐敗」へと変質していく過程を象徴し、三島が提示する「知性」と「美」の逆説的な関係性を深く示しています。
「天人五衰」の象徴性と主要テーマの考察:輪廻転生の破綻と唯識論
本多は清顕の脇腹の三つの黒子を転生の証とし、その後の勲、ジン・ジャン、透にも同様の黒子を見出すことで、輪廻転生を確信してきました。しかし、『天人五衰』に至り、透が20歳で夭折しなかったこと、そして慶子によって「贋者」と断じられたことで、輪廻転生の物語は「途切れる」のです。最終的に、月修寺で聡子が清顕の存在自体を否定したことで、本多が60年間追い求めてきた輪廻転生の物語は「一挙に崩れ去る」のです。
「豊饒の海」は唯識思想という大乗仏教の思想を元に組み立てられています。唯識思想は「世界の全ては認識の過誤によるものである」とします。三島は、仏教が救済できない問題を文学が扱う可能性を信じていました。本多の「見る」行為は、唯識論的な「認識の相対性」へと帰結し、彼の人生が「虚無」へと流れ込んでいきます。輪廻転生の「破綻」は、単に物語の結末に留まらず、三島が唯識思想を批判的に受容し、仏教が提供できない「救済」を文学の領域に見出そうとした、彼の思想的到達点を示すものです。本多が信じてきた輪廻転生は、彼自身の「認識」によって作り上げられた幻想であり、聡子の言葉はその幻想の根底を覆します。これは、唯識思想が説く「世界の全ては認識の過誤」という概念を、物語の結末で具現化したものです。しかし、三島は単に仏教的虚無を提示するのではなく、仏教では救われない問題(例えば、人間の情念、行動、美、死)を文学が探求する可能性を示しました。『豊饒の海』が「白昼の下の空虚の海」を意味し、文学の固有性が信仰に収まりきれない問題にこそ存するという三島の考えは、この輪廻転生の破綻によって明確に示されるのです。したがって、輪廻転生の破綻は、三島が仏教の限界を認識し、文学こそが人間の存在と虚無の深淵を捉えることができる媒体であるという、彼の思想的信念の表明なのです。
「天人五衰」の象徴性と主要テーマの考察:「見る者」と「見られる者」の対立
本多繁邦は、物語全体を通して「眺める者」あるいは「見る者」として描写されます。彼は情念に触れず、客観的な視点から世界を観察し、法と知の存在として生きてきました。彼の「見る」行為は、対象と距離をとり、その性質を理解しようとすることであり、同時に、対象によって引き起こされる情念の火を自ら消してしまう性質を持つものです。しかし、第三巻『暁の寺』では、この「見る」行為が「覗き魔」へと転落し、その醜悪な側面が露呈します。本多は、覗き見を「客観性の病気」と呼び、なぜ「眺めること」が法に則り、なぜ「覗くこと」が法に背くのかを自問します。これは、「見る」こと、理解すること、認識することが、「覗き」という背徳的な態度に転落する危険性を常に孕んでいることを示唆しているのです。
一方、安永透もまた「純粋な認識者、ただ『見る者』」として描かれ、本多と同じ精神構造を持ちます。透の「見る」は、対象を冷酷に処理する「愛の欠如、酷薄」という性質を持つものです。本多は透の中に自身の「自意識の雛形」とも言える「磨き上げられた荒涼とした無人の工場」を発見するのです。本多と透の「見る」行為の共通性と差異は、物語の核心に迫ります。本多は情念を原動力とした「行動」ができない「見る者」であり、その認識は「虚無」へと帰結します。彼の記憶は、清顕、勲、ジン・ジャンといった「見られる者」の存在によって形成されてきたため、聡子の言葉は彼の「記憶」の根底を揺るがし、自己の同一性まで否定するのです。これは、本多が「行為」=「行動」の欠落した認識者であったため、他者から別の認識を突きつけられると、頭の中で作り上げられた世界が崩壊することを示しています。透の失明は、彼が「見る者」としての役割を終え、本多が「見られる」ことがなくなることを意味します。これは、本多が物語全体を通して最後まで「見る者」であり続け、「見られる者」として「行動」に踏み切ることなく、「言葉と折り合い」の世界に生き続けたことを示唆しているのです。したがって、「見る者」と「見られる者」の対立は、本多の「行動」の欠如と、その認識が最終的に「虚無」へと帰結する物語の構造を深く示していると言えるでしょう。
「天人五衰」の象徴性と主要テーマの考察:日本社会への警鐘と三島由紀夫の自決
「豊饒の海」の根底には、軍事を含む政治と経済の関係性という三島らしい主題が存在します。主人公の本多は法律家から弁護士になり、経済界の巨頭を暗殺させ、自身も大金持ちになります。しかし、これは政治(法律、軍事)を軽視し、経済のみに特化してきた人間の末路として描かれているのです。本多が膨大な財産を抱えながら養子の安永透に反逆され、いじめられる姿は、戦後日本が軍事力の強化を忘れ、経済成長に邁進した結果、長期停滞を招いたことへの三島なりの警鐘として描かれています。三島は、国家権力の正体はフィジカルなパワー、すなわち軍事力であり、それを強化せずに経済だけを強化することは無理であると指摘しているのです。
『天人五衰』は、三島由紀夫が自決した1970年11月25日に書き上げられた遺作であり、作品の完成と自決が同時であったことから、作品が彼の思想と行動の集大成であると強く示唆されています。三島は『天人五衰』の中で仏教大辞典の「天人五衰」の項を詳細に引用し、自身の「本位を楽しまなくなった」という腐敗の予感と死への必然性を結びつけているのです。これは、この作品が彼の「遺書」であり、最後の「切札」であったと解釈されています。彼は「五衰」のカードを示し、その後、自決という行動に出たのです。
三島の自決は、世間からは「愚挙」「犬死に」と評されましたが、「葉隠」の「武士道とは死ぬことと見つけたり」という言葉を引用し、三島が「一片の打算なき」武士道を実践したと解釈する見方もあります。彼の行動は、日本国憲法と民主主義に対する抗議であり、アメリカの傭兵となることへの危機感から来る「自主的国防」の必要性を訴えるものであったのです。三島の死は、当時の高度成長期の政治的腐臭や、現代の防衛論議の中核を指し示している可能性があり、彼の自決を「アメリカの傭兵になるな」という「決死の遺書」と捉える見解も存在します。したがって、『天人五衰』は、三島が戦後日本社会の経済偏重と精神的荒廃に感じた危機感を文学的に表現し、自身の行動によってその警鐘を究極の形で鳴らした作品であると言えるでしょう。
まとめ
三島由紀夫の『天人五衰』は、「豊饒の海」四部作の終章として、輪廻転生という長年のテーマを「無」へと帰結させる、衝撃的な結末を迎えます。物語は、本多繁邦が安永透という最後の転生候補を見出すところから始まりますが、透の「贋物」としての本性、そして本多自身の老いと精神的腐敗が描かれる中で、輪廻転生という概念そのものが「認識の過誤」であったと露呈するのです。最終的に、月修寺で聡子から清顕の存在を否定された本多は、「何もない」庭に立ち尽くし、彼の人生、そして彼が観察し続けてきた世界が、すべて「夢」や「幻」であったことを悟ります。
この「空無」の境地は、三島が戦後日本に感じた「虚無」と深く共鳴しています。彼は、経済的豊饒の中で失われた精神性や、軍事力を軽視した日本の現状に警鐘を鳴らし、その思想を文学作品として結晶させました。特に「天人五衰」の相の描写は、単なる仏教的知識の羅列ではなく、本多自身の肉体的・精神的衰弱、そして三島自身の「本位を楽しまない」という感覚と自決の必然性を象徴的に示しているのです。
三島は唯識思想を深く探求しながらも、仏教が提供できない救済を文学の可能性に見出しました。彼の作品は、人間の情念、行動、美、そして死といった、信仰では解決し得ない根源的な問いを追求する場であったのです。そして、その文学的探求の究極の到達点である「虚無」は、彼自身の肉体の破壊という行動と均衡します。このように、『天人五衰』は、三島由紀夫の文学、哲学、そして行動が一体となった、極めて個人的かつ普遍的な「虚無」の探求の記録であり、その意義は現代においても深く考察されるべきでしょう。