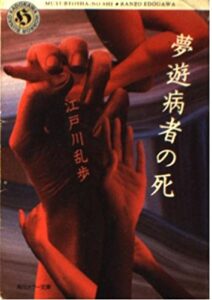 小説「夢遊病者の死」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「夢遊病者の死」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
江戸川乱歩の初期短編である本作は、ミステリーとしての面白さはもちろん、親子関係の葛藤や、病気を抱える者の苦悩といった、人間の深い部分を描き出している作品です。
発表されたのは大正時代ですが、現代にも通じるテーマ性が含まれており、読む者の心に強く響くものがあります。特に、うまくいかない親子関係や、社会との関わりに悩む人にとっては、共感できる部分が多いかもしれません。
この記事では、物語の結末に触れながら、その詳細なあらすじと、私が感じたこと、考えさせられたことを、少し長くなりますが、じっくりと語っていきたいと思います。ネタバレを避けたい方はご注意くださいませ。
小説「夢遊病者の死」のあらすじ
主人公の彦太郎は、夢遊病という持病のために、長年勤めていた木綿問屋を解雇されてしまいます。彼は、旧藩主であったM伯爵家で小使いとして働く父親のもとへ身を寄せますが、解雇の本当の理由である夢遊病のことは、恥ずかしさもあって父親に打ち明けられずにいました。
父親は、息子が店の金を使い込むなどの不祥事を起こして解雇されたのだろうと誤解し、彦太郎の自堕落な生活態度を厳しく叱責します。彦太郎もまた、病気の苦しみを理解してもらえないもどかしさや反発心から、父親に対して心を閉ざしてしまい、二人の関係は日を追うごとに険悪になっていきました。
ある雨の夜、いつものように激しい口論となり、取っ組み合いの喧嘩にまで発展します。彦太郎は部屋の隅でふさぎ込み、父親は気まずさからか銭湯へ出かけていきます。しばらくして雨が上がり、銭湯から戻った父親は、庭で月でも見ないかと息子を誘いますが、彦太郎は応じません。
翌朝、彦太郎が目を覚ますと、父親の姿が見えません。まだ出勤には早い時間です。嫌な予感を覚えた彦太郎が庭へ出てみると、縁側に置かれた籐椅子に座ったまま、父親が息絶えているのを発見します。後頭部を鈍器のようなもので強打された痕跡がありました。
彦太郎は慌てて伯爵家に知らせ、警察が呼ばれます。捜査の結果、現場には犯人の遺留品らしいものは見当たらず、ただ一束のダリヤの花が落ちているだけでした。唯一の手がかりは、雨上がりの庭に残された足跡。それは彦太郎の家の下駄によるものでした。関係者の足跡を除くと、その下駄の足跡だけが不審なものとして残ったのです。
その下駄は、彦太郎が普段履かない桐の地下穿きのものでした。自分が夢遊病者であることを思い出した彦太郎は、昨夜、無意識のうちに自分が父親を殺害してしまったのではないかと恐怖に駆られます。彼は警察の目を盗んで自転車で逃走しますが、真夏の炎天下を必死に逃げるうちに力尽き、路上で息絶えてしまうのでした。
小説「夢遊病者の死」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは小説「夢遊病者の死」を読んだ私の個人的な思いや考えを、結末の内容にも触れながら、詳しくお話しさせていただきたいと思います。この作品は、単なる謎解きミステリーという枠を超えて、人間の心の奥底にある闇や、社会との関わりの中で生じる苦悩を描いた、非常に考えさせられる物語だと感じています。
まず、主人公である彦太郎の置かれた状況に、私は深く同情しました。夢遊病という、本人にはどうすることもできない病気によって職を失い、将来への不安を抱えている。その上、唯一の肉親である父親には病気のことを理解してもらえず、怠け者だと決めつけられ、責め立てられる日々。彼の内面に渦巻く焦りや苛立ち、そして孤独感は、読んでいて胸が締め付けられるようでした。現代社会においても、病気や障害によって思うように働けず、周囲の無理解に苦しむ人々がいることを思うと、彦太郎の苦悩は決して他人事ではないと感じられます。
一方、父親の立場や心情も、全く理解できないわけではありません。息子が突然職を失い、ぶらぶらしている。その原因が分からず、将来を案じるあまり、つい厳しい言葉を投げつけてしまう。特に、当時は家長としての責任や世間体を重んじる風潮が強かったでしょうから、息子の状況に対する焦りや苛立ちは相当なものだったはずです。「人様が勧めて下さる所へハイハイと云って行けばいいのだ」という言葉には、息子の将来を思う親心と同時に、世間の常識から外れることへの恐れのようなものも感じられます。しかし、その思いやりの表現が、結果的に彦太郎を追い詰めてしまうことになるのが、この親子の悲劇性を際立たせています。
この物語の中心にあるのは、彦太郎と父親の間のコミュニケーション不全と、それによって引き起こされる「肉親憎悪」とも言うべき感情のねじれです。彦太郎は、夢遊病という自身の弱みを父親に打ち明けられない。父親は、息子の苦悩に気づかず、一方的に自分の価値観を押し付けてしまう。お互いに、ほんの少し歩み寄り、正直な気持ちを伝え合うことができれば、結末は違っていたかもしれないのに、それができない。親子という最も近いはずの関係性が、最も遠いものになってしまう。このもどかしさ、やるせなさは、多くの人が多かれ少なかれ経験したことのある感情ではないでしょうか。特に、思春期や青年期における親子関係の難しさを思い出させるものがあります。
「死んじまえ、死んじまえ、死んじまえ……」と彦太郎が心の中で繰り返す場面は、非常に印象的です。これは、直接的な殺意というよりも、どうしようもない閉塞感や、自分を理解してくれない存在への絶望感からくる、やり場のない感情の叫びのように聞こえます。現代で言うところの「ひきこもり」や「ニート」と呼ばれる若者が抱える問題にも通じる部分があるように感じました。社会との接点を失い、家族との関係も悪化し、孤独の中で負の感情を募らせていく。乱歩がこの作品を書いた大正時代と現代とでは、社会状況は大きく異なりますが、人間の抱える根源的な悩みや苦しみには、時代を超えた普遍性があるのだと改めて感じさせられます。
ミステリーとしての側面を見ると、この作品のトリックは非常に独創的です。凶器が「氷の花瓶」であり、犯行後には溶けて証拠が完全に消滅してしまうというアイデアは、発表当時としてはかなり斬新だったのではないでしょうか。偶然にも伯爵家の書生が落とした氷の花瓶が、庭で月を眺めていた父親の頭部を直撃し、死に至らしめる。そして、現場に残されたのは、花瓶に入れられていたダリヤの花だけ。この一連の出来事が、完全な事故でありながら、あたかも計画的な殺人事件のように見えてしまう構成は見事です。
しかし、このトリックの解明よりも、むしろ読者の心に残るのは、悲劇的な偶然の連鎖と、それによって引き起こされる彦太郎の運命です。庭に残された足跡が、実は被害者である父親自身のものであったこと。そして、その足跡が、彦太郎が普段履かない桐の地下穿きのものであったこと。これらの偶然が重なり、夢遊病者である彦太郎は、「自分が無意識のうちに父親を殺してしまった」という絶望的な結論に至ってしまいます。真実を知ることなく、罪の意識と恐怖に苛まれながら逃亡し、力尽きて死んでしまう彦太郎の姿は、あまりにも哀れで、救いがありません。
この物語の結末は、非常にやるせないものです。真犯人である書生は自首し、事件の真相は明らかになりますが、彦太郎の死は誰にも理解されないままです。「なぜ彦太郎は逃亡を試みたのか――その謎だけは残された」という最後の文章は、読者に重い問いを投げかけます。真実を知っていれば、彦太郎は死なずに済んだかもしれない。しかし、彼を死に追いやったのは、直接的な犯行ではなく、夢遊病という病気への恐怖、父親との断絶した関係、そして社会からの疎外感が生み出した、彼自身の絶望感だったのではないでしょうか。
この作品が書かれた大正時代は、近代化が進む一方で、古い価値観や社会的な制約も根強く残っていた時代です。夢遊病のような精神的な病に対する理解は乏しく、偏見も強かったことでしょう。彦太郎が自分の病気を隠そうとしたのも、そうした社会的な背景があったからかもしれません。また、家制度や世間体といったものが、親子のコミュニケーションを阻害する要因にもなっていたと考えられます。乱歩は、ミステリーという形式を借りながら、当時の社会が抱える息苦しさや、その中で生きる個人の苦悩を描き出そうとしたのかもしれません。
そして、驚くべきことに、この物語が提起している問題は、現代社会においても色褪せていません。コミュニケーションのあり方、家族関係の希薄化、精神的な問題を抱える人々への理解、社会的な孤立など、私たちが今まさに直面している課題と重なる部分が多くあります。特に、インターネットの普及などにより、人と人との直接的な関わりが変化している現代において、彦太郎と父親のようなすれ違いや誤解は、形を変えて存在し続けているのではないでしょうか。この作品を読むことは、現代社会における人間関係やコミュニケーションのあり方について、改めて考えさせられるきっかけを与えてくれます。
江戸川乱歩の初期作品には、本作のように、人間の異常心理や倒錯した感情、社会の暗部などを、怪奇的、幻想的な雰囲気の中に描いたものが多いと言われています。本作も、夢遊病という設定や、氷の凶器といった要素に乱歩らしい独創性が表れていますが、それ以上に、登場人物たちの内面描写、特に彦太郎の心理描写の巧みさが光っています。彼の焦燥感、絶望感、父親への愛憎入り混じった複雑な感情などが、短い物語の中に凝縮されて描かれており、読者は彼の苦悩に深く共感させられます。
読後、私の心には、何とも言えない重苦しさと、登場人物たちへの深い哀れみの感情が残りました。特に印象に残っているのは、彦太郎が父親に月見に誘われたにも関わらず、背を向けたまま応じなかった場面です。もしあの時、彦太郎が少しでも心を開いていれば、あるいは父親がもう少し息子の心情を察することができていれば、あの悲劇的な結末は避けられたかもしれない。そう思うと、人と人との間に存在する、見えない壁のようなものの存在を強く意識させられます。コミュニケーションのほんの少しの齟齬が、取り返しのつかない結果を招いてしまうことがあるのだということを、この物語は教えてくれます。
他の江戸川乱歩作品と比較してみると、例えば「人間椅子」や「芋虫」のような、より猟奇的、怪奇的な色彩の強い作品とは異なり、「夢遊病者の死」は、より現実的な人間関係のドラマに重きが置かれているように感じます。もちろん、ミステリーとしての仕掛けや、夢遊病という異常心理の要素はありますが、物語の核となっているのは、普遍的な親子の葛藤であり、社会の中で生きる個人の苦悩です。その意味で、乱歩の作品の中でも、特に共感を呼びやすい、心に深く響く作品の一つと言えるかもしれません。
「夢遊病者の死」というタイトルも、非常に示唆的です。彦太郎は文字通り夢遊病者であり、そして最終的に死を迎えますが、彼の死は、単なる病気によるものでも、事故によるものでもありませんでした。それは、社会やまわりの人々、そして自分自身からも理解されず、孤立し、絶望した末の死であったと言えます。夢遊病という状態は、現実と非現実の狭間をさまよう状態とも言えますが、彦太郎の生もまた、社会の中で自分の居場所を見つけられず、現実から遊離したような状態にあったのかもしれません。彼の死は、そうした生きづらさを抱えた魂の、悲痛な叫びのようにも聞こえます。
この作品が私たちに投げかけるメッセージは、一つではないでしょう。親子のコミュニケーションの大切さ、病気や弱さを抱える人への理解と思いやり、社会的な孤立の問題、そして、ほんの少しの偶然や誤解が人生を大きく狂わせてしまうことの恐ろしさ。様々な角度から、人間の存在や社会のあり方について深く考えさせられます。悲劇的な結末ではありますが、だからこそ、私たちはこの物語から多くのことを学び、自身の生き方や他者との関わり方を見つめ直すことができるのではないでしょうか。
江戸川乱歩の「夢遊病者の死」は、単なる古い時代のミステリー小説として片付けるにはあまりにも惜しい、深く、重いテーマを内包した作品です。ミステリーとしての面白さはもちろんのこと、人間の心理描写の巧みさ、時代を超えて共感を呼ぶテーマ性など、多くの魅力を持っています。読後には、登場人物たちの運命に思いを馳せ、自身の周りの人間関係や社会について、改めて考えさせられることでしょう。未読の方には、ぜひ一度手に取っていただきたい、心に残る一作です。
まとめ
江戸川乱歩の短編小説「夢遊病者の死」について、物語の結末に触れつつ、そのあらすじと、私が感じたことなどを詳しくお話しさせていただきました。この作品は、夢遊病という病を抱える主人公・彦太郎と、彼を理解できない父親との間の、痛ましい関係を描いています。
物語は、些細な誤解とコミュニケーション不足から生じる親子の確執、そして、偶然が重なって起こる悲劇的な事件へと展開していきます。特に、彦太郎が自身の夢遊病を恐れ、父親殺しの犯人は自分ではないかと疑心暗鬼に陥り、絶望の末に死んでしまう結末は、非常に胸に迫るものがあります。真実が明らかになった時には、もう手遅れなのです。
ミステリーとしてのトリック(溶ける凶器)も興味深いですが、それ以上に、この作品が強く訴えかけてくるのは、人間関係の難しさや、社会の中で孤立してしまう個人の苦悩といった、普遍的なテーマです。大正時代に書かれた物語でありながら、現代社会にも通じる問題点を鋭くえぐり出しており、読後に深い思索を促されます。
親子関係、病気への偏見、コミュニケーションの重要性など、様々なことを考えさせられる、読後感の重い作品ではありますが、それだけに心に深く刻まれる物語だと思います。江戸川乱歩の作品の中でも、人間ドラマとしての側面が強く、多くの人に読んでいただきたい一編です。






































































