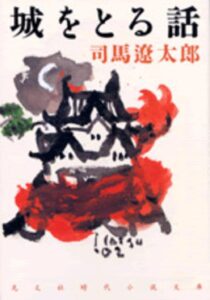 小説「城をとる話」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。司馬遼太郎さんが描く、戦国末期の奥州を舞台にした、一風変わった城盗りの物語は、読む者の心を掴んで離しません。
小説「城をとる話」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。司馬遼太郎さんが描く、戦国末期の奥州を舞台にした、一風変わった城盗りの物語は、読む者の心を掴んで離しません。
物語の中心となるのは、元佐竹家家臣の車藤左という、なんとも不思議な魅力を持つ男です。無骨でありながら、なぜか人を惹きつける。彼が、上杉家の家臣である中条佐内と共に、伊達家が築城中の帝釈城を乗っ取ろうと企てる、その大胆不敵な計画が物語の軸となります。
道中では、一癖も二癖もある人物たちが仲間に加わります。山賊同然の猟師、土地の巫女、そして花火師でもある商人。彼らとの出会いが、計画にどのような影響を与えていくのか。手に汗握る展開と、個性的な登場人物たちの活躍が見どころです。
この記事では、物語の結末にも触れながら、その詳しい流れと、私がこの作品から受けた深い感動や考察を、たっぷりとお伝えしていきたいと思います。痛快な冒険活劇の側面と、時代に翻弄される人々のドラマを、ぜひ味わってください。
小説「城をとる話」のあらすじ
物語は1600年、関ヶ原の戦いが近づく不穏な空気の中、会津若松の上杉家城下町から始まります。上杉景勝の家臣である中条佐内の元を、一人の男が訪ねてきます。その男は車藤左と名乗り、元は常陸の佐竹義宣に仕えていたといいます。飄々とした態度で、家を出た理由を「女房に嫌気がさしたからだ」などと嘯く藤左に、佐内は警戒心を抱きます。
しかし藤左は、上杉家の重臣しか知らないはずの、伊達領との国境・桔梗ヶ原での築城計画、すなわち帝釈城建設の情報を口にします。間もなく、佐内は家老の直江兼続(山城守)から呼び出され、桔梗ヶ原への潜入と偵察を命じられます。これを知った藤左は、当然のように同行を申し出、「たった一人で城を奪ってみせる」と豪語するのです。
佐内が趣味で集めていた古銭を勝手に持ち出し、それを活動資金として二人は伊達領へ向かいます。道中、山賊まがいの猟師・蜻蛉六(かげろうろく)、帝釈城のある黒橋村の巫女・おうう、火薬の扱いに長けた行商人・輪違屋満次郎といった、特殊な技能を持つ者たちと出会い、藤左は彼らを仲間に引き入れようとします。
黒橋村に潜入した一行ですが、警戒は厳しく、藤左は「侍二人で城を乗っ取りに来た」という噂をわざと流し、警戒心を油断へと変えようとします。おううの家に匿われた藤左は、村人を味方につける工作を進めます。一方、城の普請奉行である赤座刑部は、藤左たちの動きを怪しみ、村への圧力を強めていきます。
ある夜、村の若者・与吉が逃亡を図り撃たれる事件が起こり、藤左は彼を助けようとして捕らえられてしまいます。しかし翌朝、藤左は牢から忽然と姿を消し、何者かによって助け出されたことが判明します。これを機に、藤左は村人の信頼を完全に勝ち取り、城を内部から切り崩す計画を練り上げます。
藤左は、殺された与吉の兄・彦蔵ら村人と連携し、決行の夜を定めます。計画は、まず村の女子供を上杉領へ逃がし、その後、普請小屋の城方を襲撃して二ノ丸を占拠。同時に、別働隊の中条佐内と満次郎が、立ち退きを命じられていた赤土村の村人を率いて三ノ丸で蜂起し、本丸を孤立させるというものでした。対岸には上杉の援軍も待機させ、退路も確保するという、大胆かつ緻密な作戦でした。いよいよ、前代未聞の「城とり」が始まろうとしていました。
小説「城をとる話」の長文感想(ネタバレあり)
司馬遼太郎さんの「城をとる話」を読み終えたときの、胸のすくような爽快感と、登場人物たちの人間臭さに対する深い共感を、今でも鮮明に覚えています。戦国の動乱期を背景にしながらも、決して重苦しくはなく、どこか軽やかで、それでいて確かな手応えを感じさせてくれる、そんな作品でした。
物語の中心人物である車藤左の造形が、まず素晴らしいですね。「山から掘りおこしたばかりの山の芋のように無愛想」と描写されながら、出会う人々を不思議と魅了してしまう。この掴みどころのない、しかし底知れない魅力を持つ人物像は、本作が石原裕次郎さん主演の映画原作として企画されたという背景を知ると、なるほどと頷けます。司馬さんが裕次郎さんに感じていたであろう、スター特有の輝きや人を惹きつける力を、藤左というキャラクターに投影したのかもしれません。
対照的に、上杉家家臣の中条佐内は、実直で思慮深い人物として描かれています。藤左の破天荒な行動に振り回されながらも、彼を支え、計画の実現に不可欠な役割を果たします。佐内の堅実さが、藤左の奇抜さを際立たせると同時に、物語に安定感を与えています。彼の貨幣収集という一見地味な趣味が、計画の資金源となるあたりも、司馬さんらしい細やかな設定だと感じ入りました。
物語の舞台は関ヶ原合戦前夜の奥州。徳川家康による上杉討伐の動きが噂される中、伊達政宗もまた虎視眈々と領土拡大を狙っている、そんな一触即発の状況です。この緊迫した時代背景が、一介の牢人(藤左)と一地方武士(佐内)による「城とり」という、本来なら無謀としか思えない計画に、リアリティとスリルを与えています。歴史の大きなうねりの中で、個人の知恵と勇気がどのように事態を動かしていくのか、そのダイナミズムに引き込まれました。
帝釈城という、まだ完成途上の城を「とる」という目標設定が、物語をシンプルかつ力強く前進させています。難攻不落の巨大な城ではなく、建設中の、いわば「隙」のある城だからこそ、少人数での奪取計画に現実味が帯びてくる。この設定の妙が、読者を物語の世界にスムーズにいざなってくれます。
道中で藤左が出会う仲間たち、蜻蛉六、おうう、輪違屋満次郎の存在も、物語に深みと彩りを加えています。山での生きる術を知る猟師、土地の事情に通じ、人々の心の拠り所でもある巫女、そして火薬の知識を持つ商人。彼らは決して単なる「駒」ではなく、それぞれの背景や思惑を持ち、藤左の計画に主体的に関わっていきます。特に、満次郎の花火(煙)の技術が、後に重要な役割を果たすあたりは、伏線の巧みさを感じさせます。
巫女のおううは、本作におけるヒロイン的な存在と言えるでしょう。厳しい状況の中で気丈に振る舞い、藤左たちを助ける彼女の姿は印象的です。彼女を通じて、戦国の世に生きた女性の逞しさや、土地に根差した人々の暮らしぶりが垣間見えます。藤左との間に芽生えるほのかな感情も、物語に人間的な温かみを添えています。
藤左が取る戦略の面白さも特筆すべき点です。「侍二人で城をとりに来た」という、普通なら隠すべき情報を、あえて噂として流す。これにより、城方は油断し、村人たちの間には奇妙な期待感や連帯感が生まれていく。情報戦や心理戦を巧みに操る藤左の知略は、読んでいて実に痛快でした。
潜入後の展開は、サスペンスに満ちています。おううの家に身を潜める藤左たち、彼らの存在を嗅ぎつけようとする赤座刑部配下の探索、村人たちの動揺。いつ見つかるか分からない緊張感が続きます。特に、赤座刑部という、執拗で冷徹な敵役の存在が、物語の緊迫感を高めています。
藤左が一度捕らえられる場面は、物語の大きな転換点です。絶体絶命のピンチかと思いきや、翌朝には何者かの手引きで牢から脱出している。このミステリアスな展開は、読者の意表を突くと同時に、藤左が単なる知恵者や腕自慢ではなく、何か目に見えない力にも守られているような、不思議な「運」を持つ男であることを示唆しているように感じました。
そして、この事件をきっかけに、藤左は村人たちの心を完全に掴みます。築城のために立ち退きを迫られたり、重い賦役に苦しんだりしていた村人たちは、理不尽な支配に対する反感を抱えています。藤左は、その鬱積したエネルギーを巧みに利用し、彼らを「城とり」の協力者へと変えていくのです。単なる武力や策略だけでなく、人心を掌握することの重要性を描いている点は、司馬作品ならではの深みと言えるでしょう。
クライマックスに向けて練り上げられる城奪取の計画は、大胆かつ緻密です。女子供の避難、二ノ丸での籠城、三ノ丸での蜂起、そして上杉勢との連携。それぞれの役割分担やタイミングが計算され尽くされており、まるで盤上の駒を動かすような鮮やかさです。彦蔵をはじめとする村人たちが、自らの意志で危険な計画に参加していく姿には、胸が熱くなりました。
いよいよ作戦決行の夜。暗闇の中、それぞれの持ち場で計画が実行に移されていく描写は、息をのむような緊迫感に満ちています。火の手が上がり、鬨の声が響き、刀がぶつかり合う。その混乱の中で、藤左や佐内、そして仲間たちが、それぞれの役割を果たそうと奮闘する姿が目に浮かぶようでした。まさに、物語の最高潮です。
本作が、石原裕次郎さんのために書かれたという事実は、作品を読み解く上で興味深い視点を与えてくれます。映画『城取り』は、原作とは異なる部分も多いようですが、藤左のキャラクター造形には、やはり裕次郎さんのイメージが色濃く反映されていると感じます。もし裕次郎さんが藤左を演じていたら、きっと無骨さと甘さ、そして圧倒的な存在感を併せ持った、魅力的な主人公になったことでしょう。原作小説が新聞連載という形で結実したことは、私たち読者にとっては幸運だったのかもしれません。
「城をとる話」は、戦国時代の厳しい現実を描きながらも、冒険活劇としての楽しさ、人間ドラマとしての温かさ、そして歴史のダイナミズムを感じさせてくれる、実に読後感の良い作品です。司馬さんの筆致は、複雑な状況や登場人物たちの心理を、明快かつテンポ良く描き出し、読者を飽きさせません。歴史小説でありながら、エンターテイメントとしても一級品。司馬遼太郎作品の中でも、特に親しみやすく、何度でも読み返したくなる魅力を持った一冊だと、私は思います。
まとめ
司馬遼太郎さんの「城をとる話」は、関ヶ原前夜の奥州を舞台に、型破りな男・車藤左が、完成間近の帝釈城を奪取しようとする痛快な物語です。無骨ながらも人を惹きつける藤左と、実直な上杉家臣・中条佐内、そして道中で出会う個性豊かな仲間たちが織りなすドラマは、読者を飽きさせません。
物語の魅力は、その巧みなプロットにあります。「侍二人で城をとる」という大胆な噂を流し、敵の油断を誘い、虐げられた村人たちを味方につけていく藤左の知略。潜入、捕縛、脱出といったサスペンスフルな展開、そしてクライマックスの城攻防戦は、手に汗握る面白さです。
石原裕次郎さん主演の映画原作として企画されたという背景も、作品に興味深い彩りを添えています。藤左のキャラクターには、スター俳優の持つ輝きや魅力が投影されているのかもしれません。歴史の大きな流れの中で、個人の知恵と勇気が状況を切り開いていく様を描き出す、司馬さんならではの筆致も健在です。
単なる冒険活劇に留まらず、戦国の世に生きる人々の葛藤や逞しさ、人間関係の機微をも描き出した「城をとる話」。歴史小説ファンはもちろん、エンターテイメント作品としても、多くの方におすすめしたい、爽快で心に残る一冊です。






































