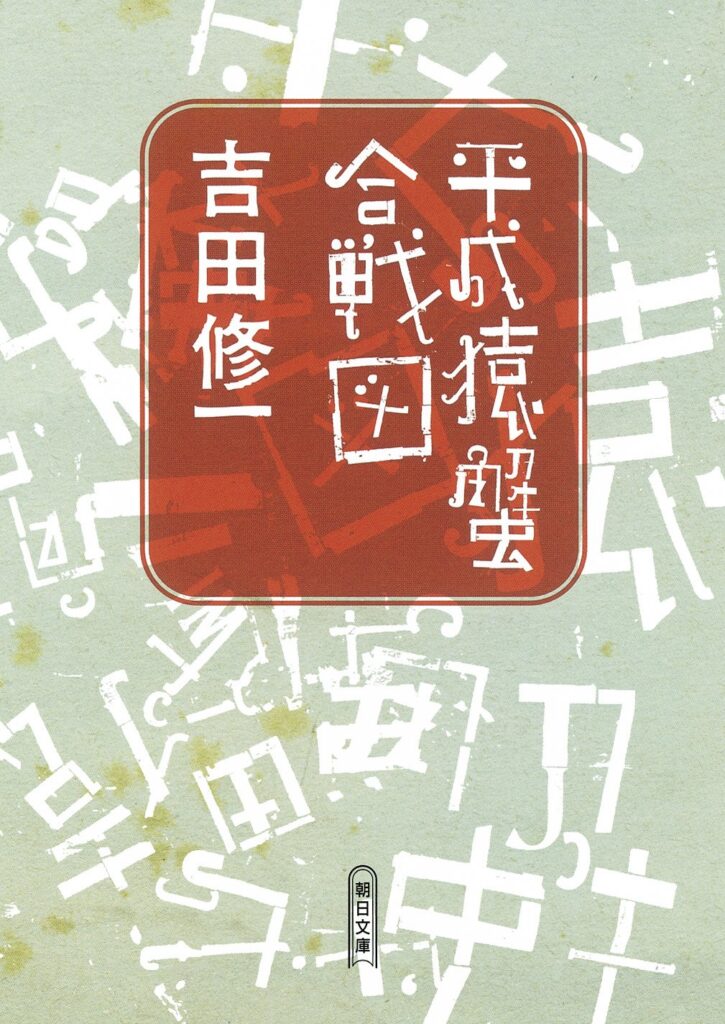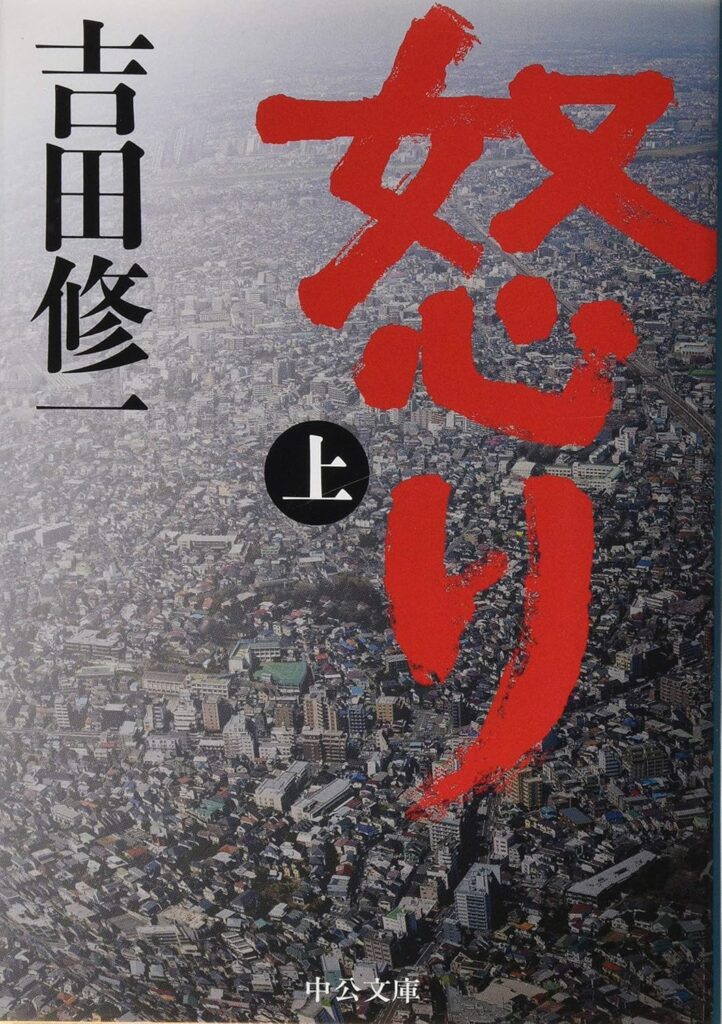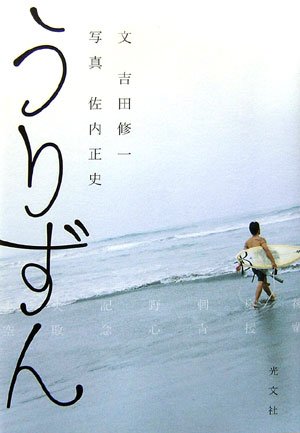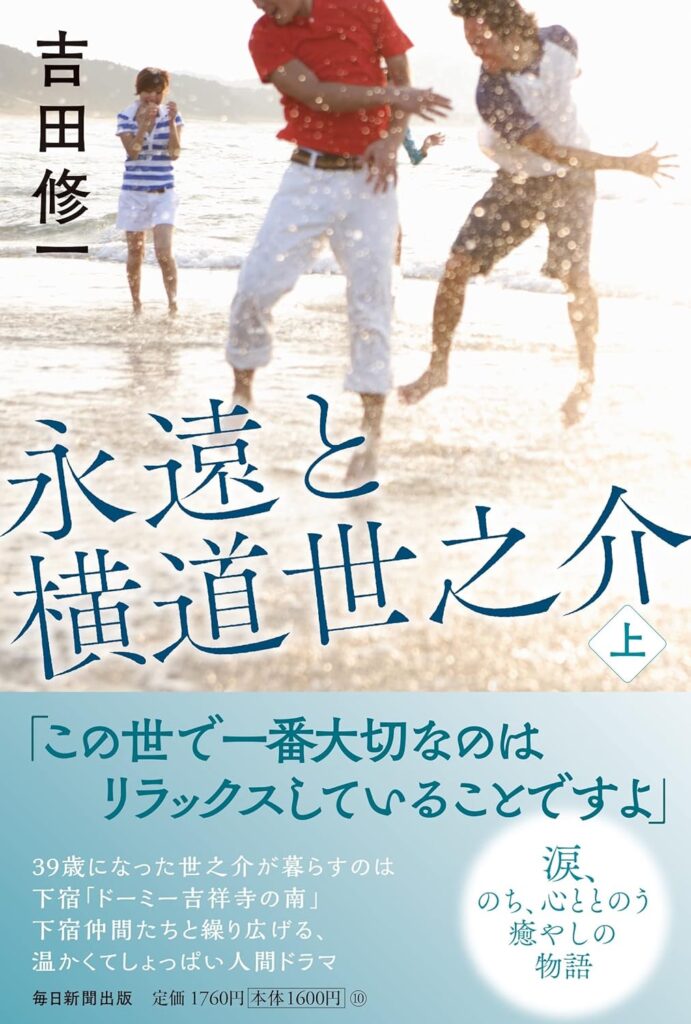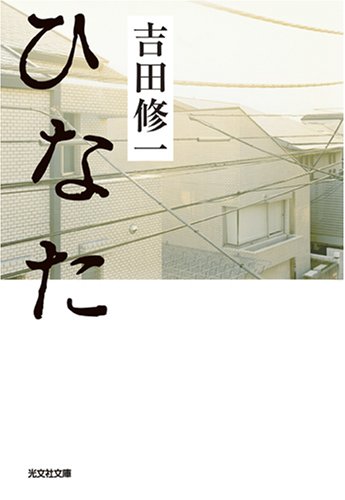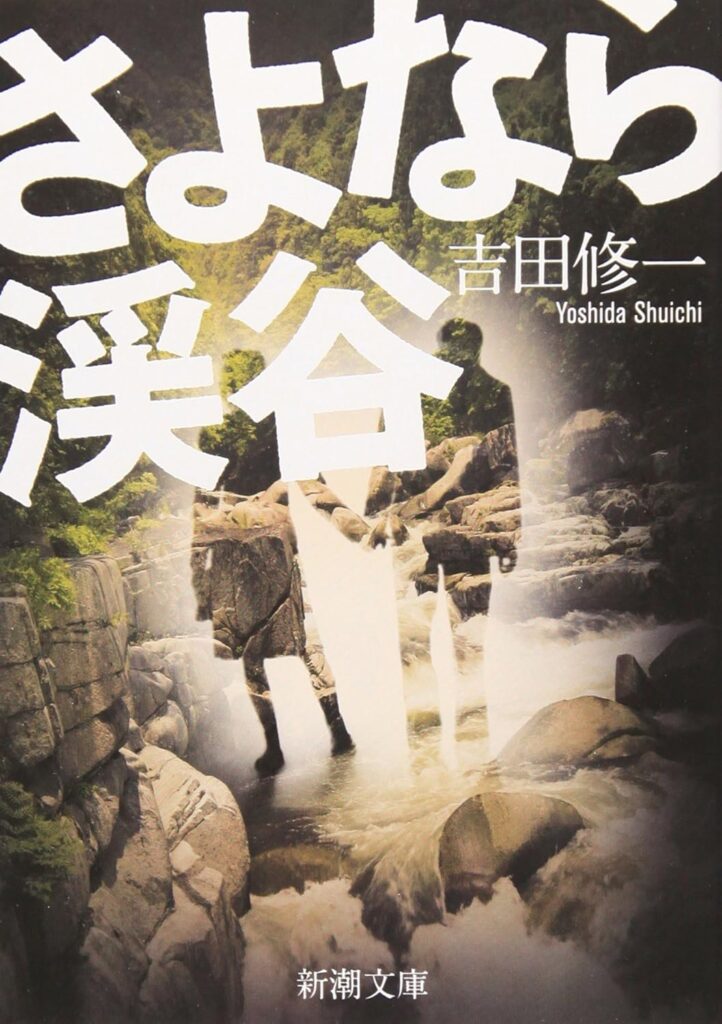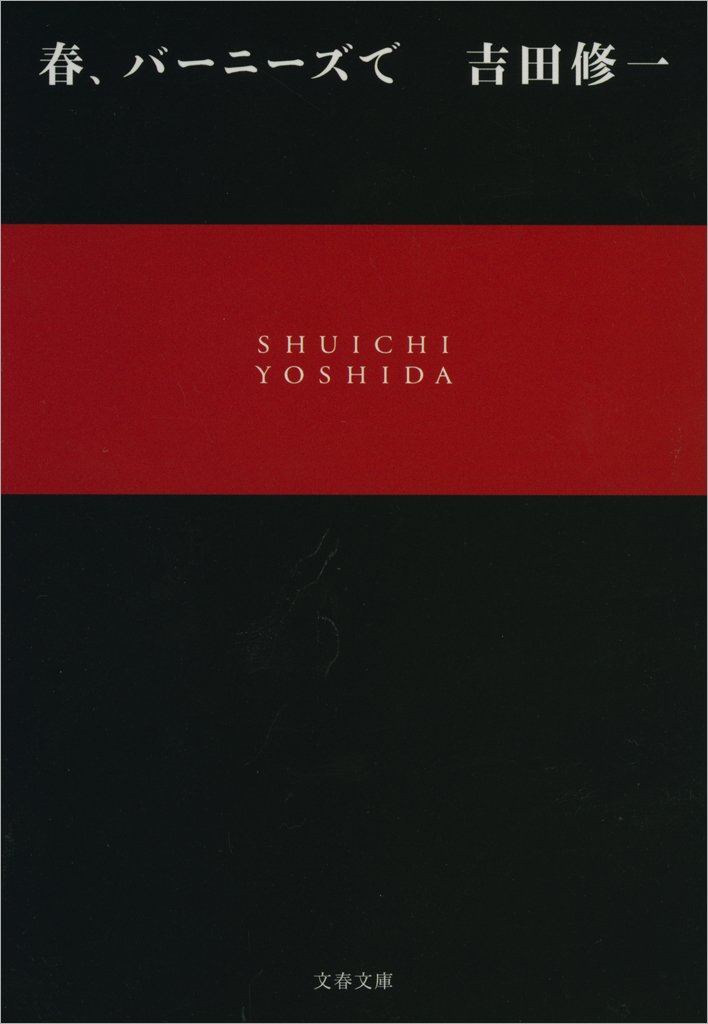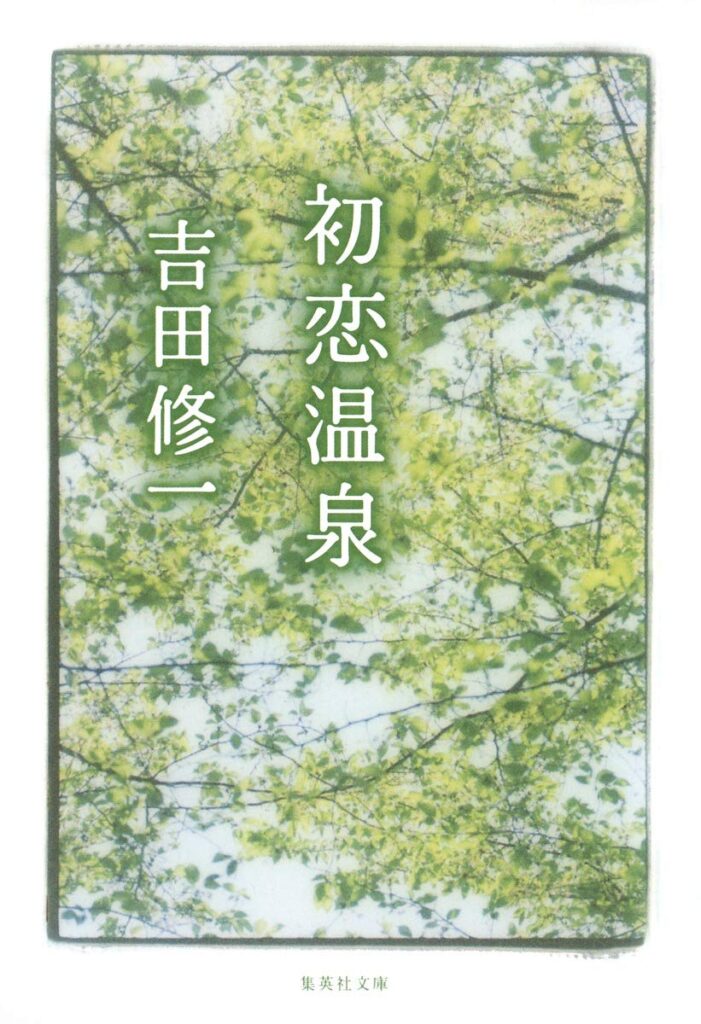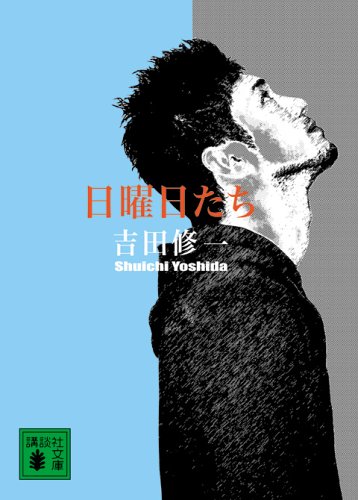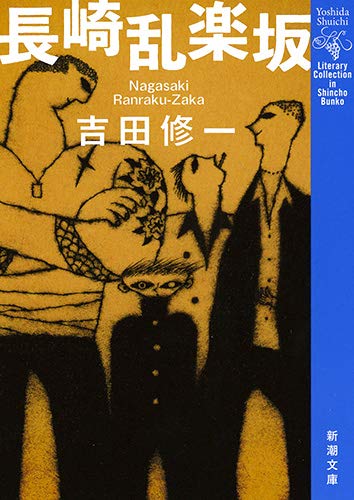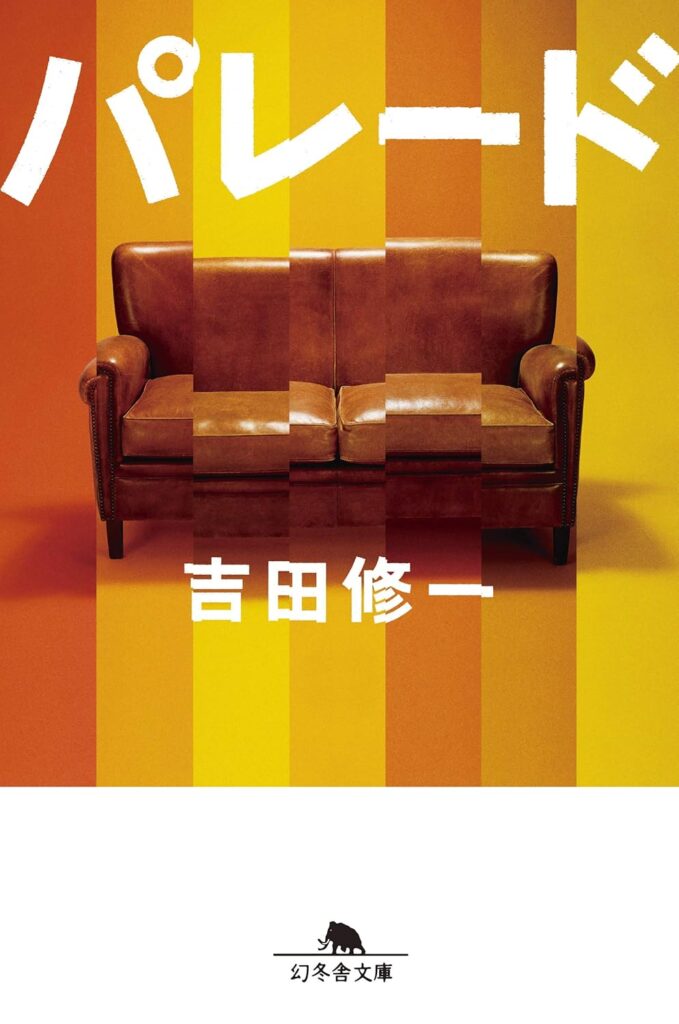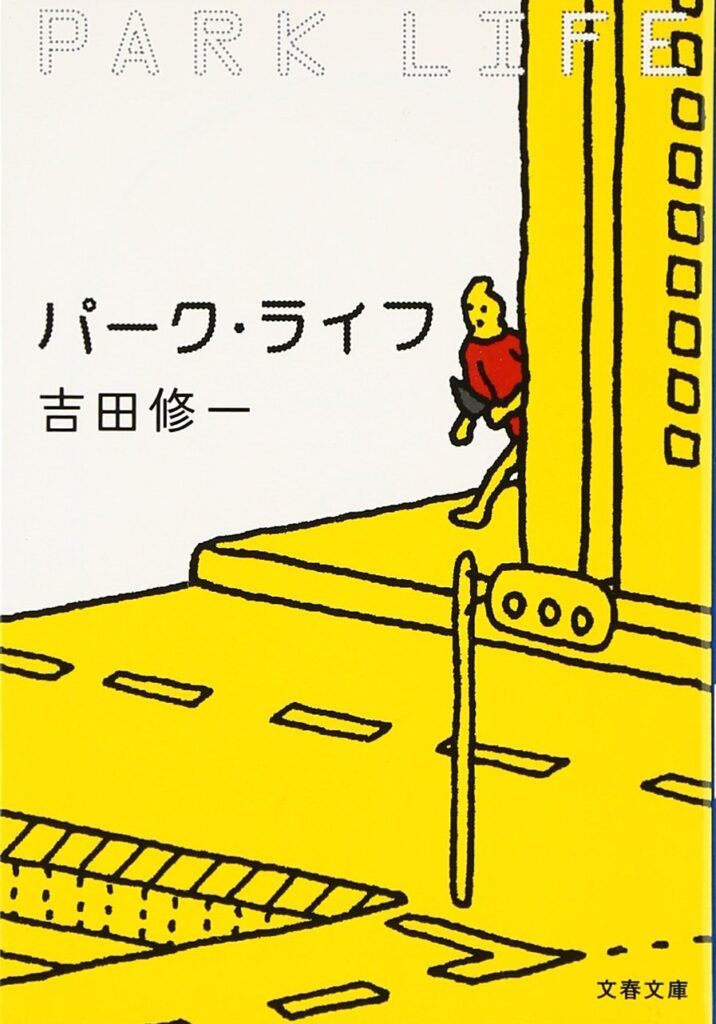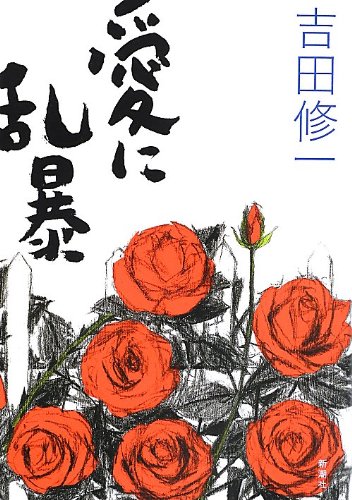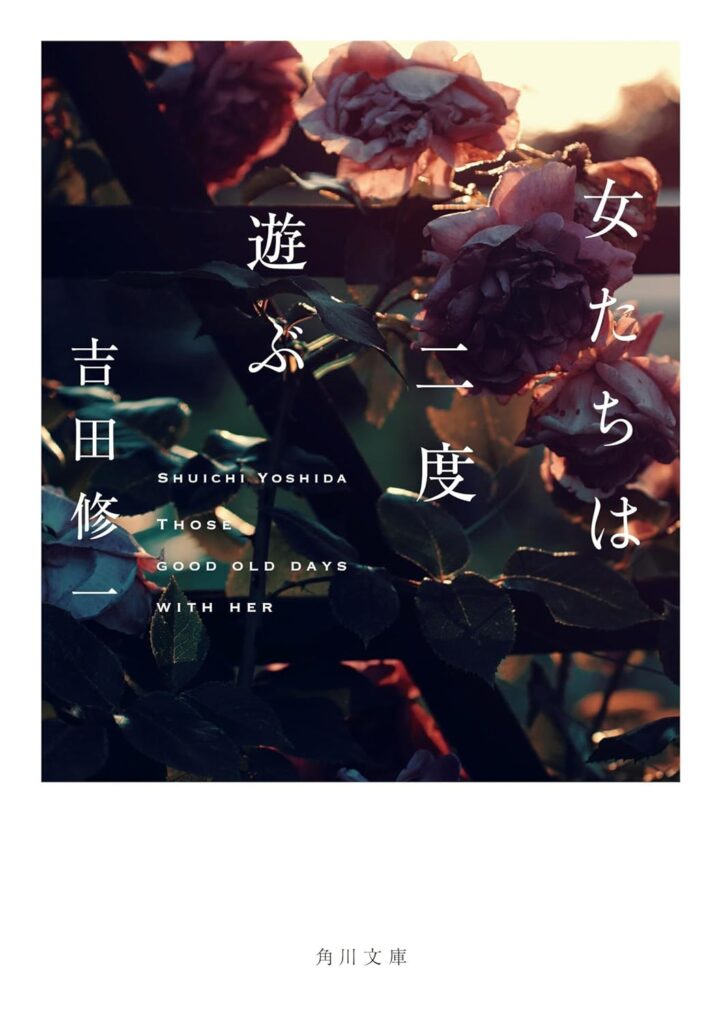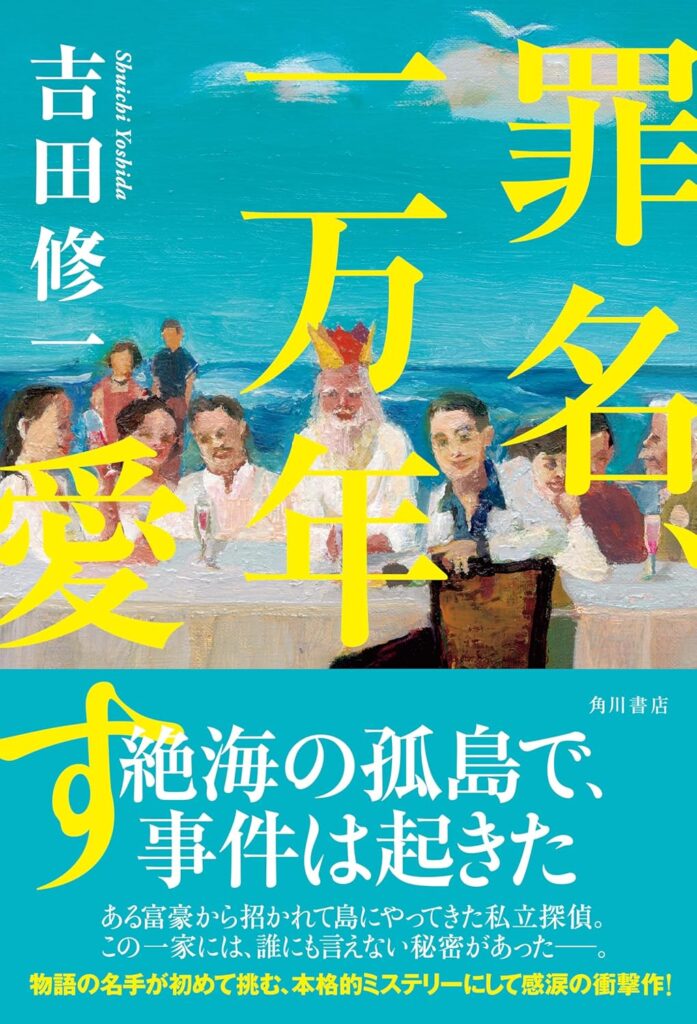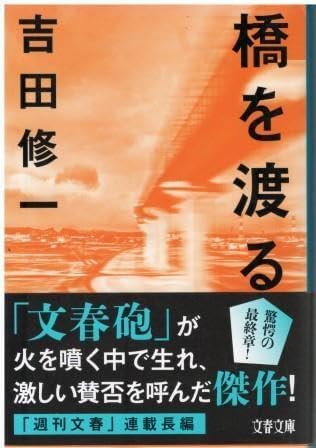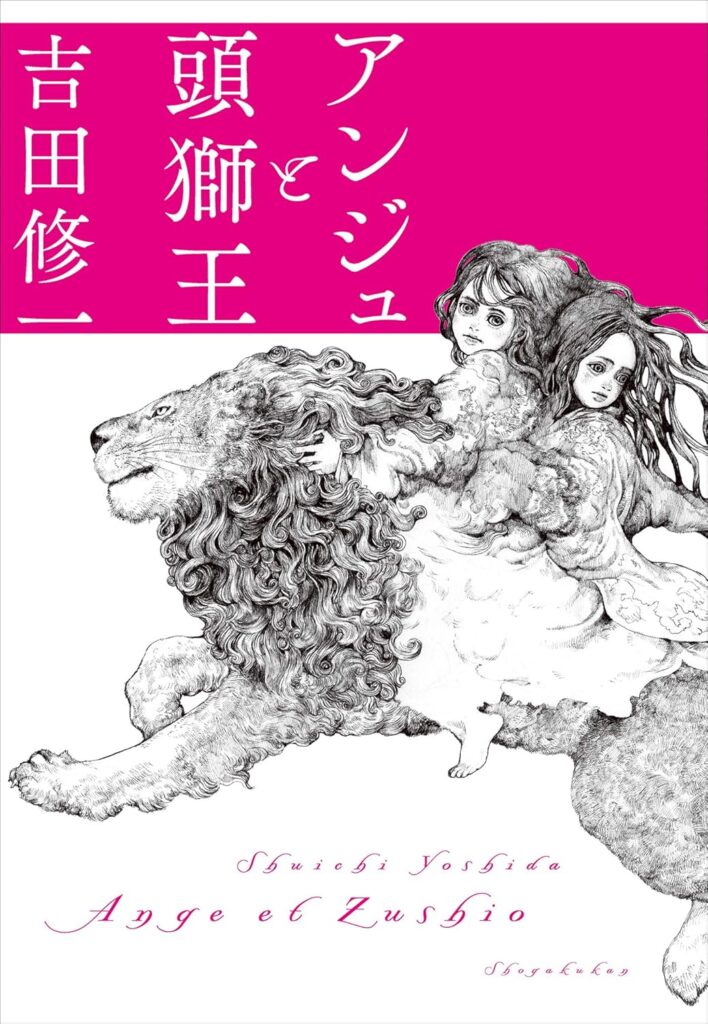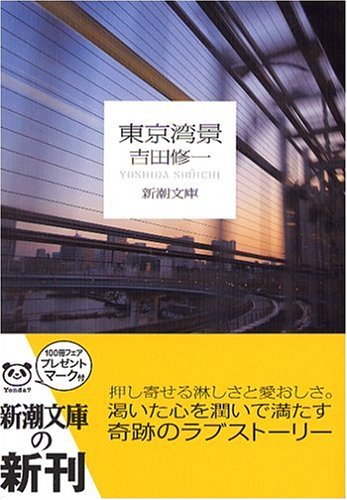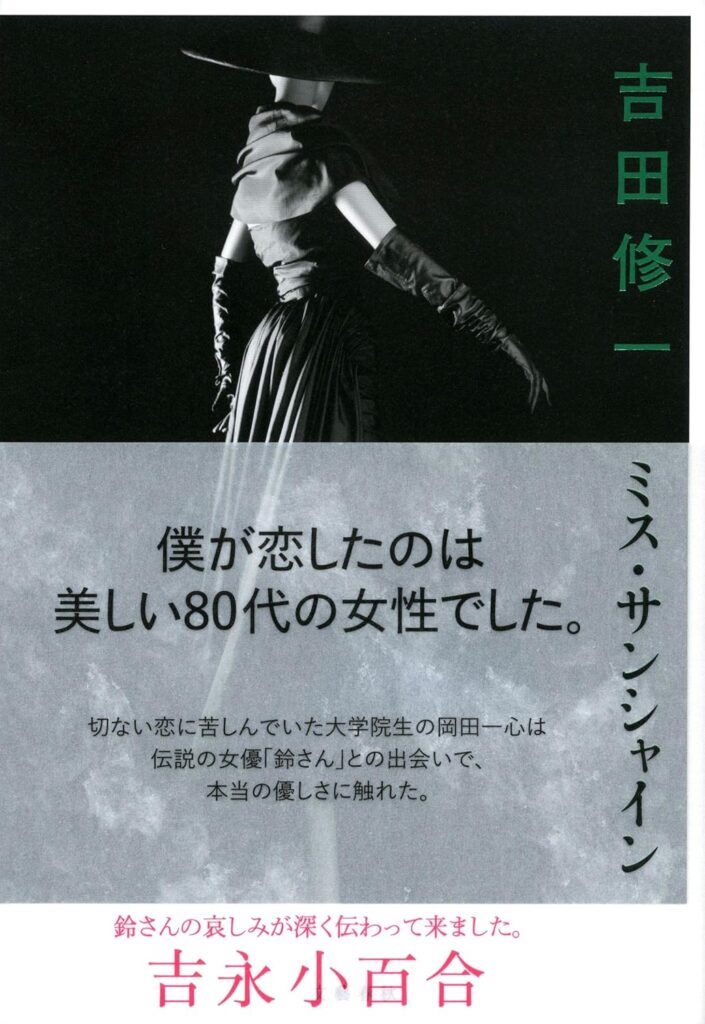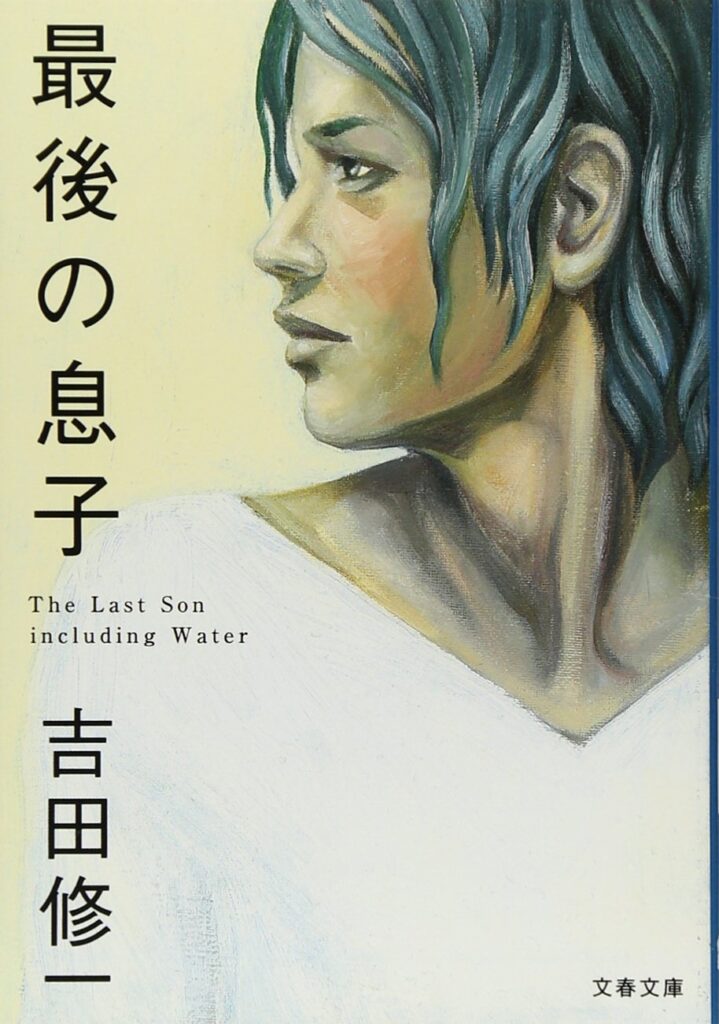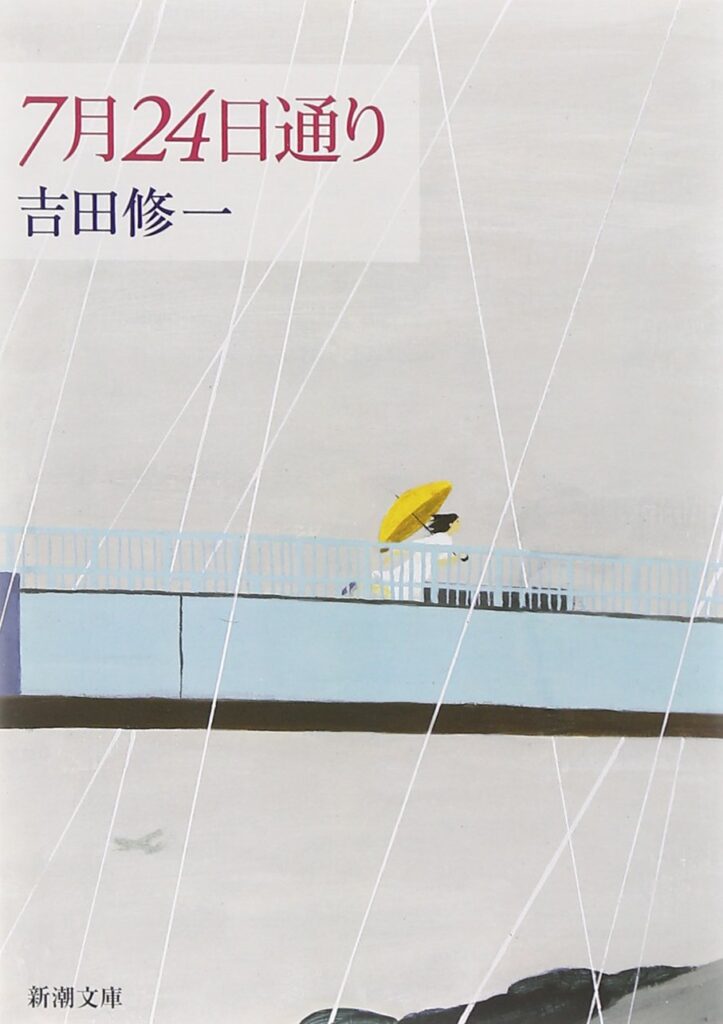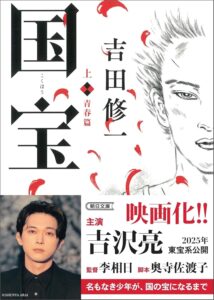 小説「国宝」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、読む者の心を鷲掴みにし、芸の道に生きる人間の凄まじいまでの情熱と、その裏に潜む孤独や犠牲を鮮烈に描き出しています。一度読み始めれば、主人公・立花喜久雄の数奇な運命から目が離せなくなることでしょう。
小説「国宝」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、読む者の心を鷲掴みにし、芸の道に生きる人間の凄まじいまでの情熱と、その裏に潜む孤独や犠牲を鮮烈に描き出しています。一度読み始めれば、主人公・立花喜久雄の数奇な運命から目が離せなくなることでしょう。
吉田修一さんの手によって紡がれたこの物語は、まるで壮大な絵巻物を見るかのようです。任侠の世界に生まれながら、類まれなる美貌と才能に導かれるように歌舞伎の世界へと足を踏み入れた喜久雄。彼が歩む道は、決して平坦なものではありません。血と汗と涙、そして愛憎が渦巻く中で、彼はただひたすらに芸の高みを目指し続けます。
本記事では、まず「国宝」がどのような物語であるのか、その核心に触れる部分も含めてお伝えします。そして、物語を深く味わったからこそ込み上げてくる、さまざまな感情や考察を、熱量を持ってお届けしたいと考えています。喜久雄の生き様、彼を取り巻く人々の想い、そして「芸」とは何かという問いに、皆様と共に迫っていければ幸いです。
歌舞伎という日本の伝統芸能を舞台にしていますが、そこで描かれる人間の葛藤や情熱は、私たちの日常にも通じる普遍的なもの。この記事が、まだ「国宝」を手に取られていない方にはその魅力を伝え、既に読まれた方には新たな発見や共感をもたらすことができれば、これほど嬉しいことはありません。どうぞ最後までお付き合いください。
小説「国宝」のあらすじ
物語は1964年、長崎の任侠・立花組組長の息子として生まれた立花喜久雄が主人公です。この世のものとは思えぬほどの美貌を持って生まれた彼は、父の死をきっかけに、その場に居合わせた上方歌舞伎の重鎮、二代目花井半二郎に引き取られ、大阪で歌舞伎役者としての道を歩み始めます。喜久雄の背中には、父との絆を示す刺青が彫られていました。
半二郎の息子であり、同い年の大垣俊介とは、親友でありながら生涯のライバルとなります。梨園の御曹司である俊介と、血縁のない新参者である喜久雄。二人は共に女形として厳しい稽古に励み、やがて喜久雄は花井東一郎という芸名で頭角を現し、「東一郎ブーム」を巻き起こすほどの人気を博します。
師である半二郎が事故で舞台に立てなくなった際、近松門左衛門の名作「曽根崎心中」のお初役に、実子の俊介ではなく喜久雄が抜擢されます。これが大きな転機となり、喜久雄の名声は不動のものとなりますが、俊介は苦悩し、喜久雄のかつての恋人・春江を伴い出奔。その後、半二郎は喜久雄を養子に迎え、三代目花井半二郎を襲名させますが、その襲名披露の舞台で師は倒れ、莫大な借金を遺してこの世を去ります。
東京へ拠点を移した喜久雄は、伝説的な女形・小野川万菊との出会いや、映画出演などを経験しながら、苦難の道を歩みます。一方、俊介も10年の時を経て歌舞伎界に復帰。メディアによって二人の対立構造が煽られ、喜久雄はスキャンダルにも見舞われます。それでも二人は時に反発し、時に認め合いながら芸を磨き合っていきます。娘・綾乃との関係は複雑化し、喜久雄は孤立を深めていきます。
やがて俊介は重い病に侵され、両足を失いながらも壮絶な執念で舞台に立ち続けますが、若くして亡くなります。生涯のライバルを失った喜久雄は、その悲しみを芸に昇華させ、その芸は人間業を超えた域に達していきます。「人間国宝」への推挙の話も持ち上がりますが、彼の心は舞台の上でしか見ることのできない「きれいな景色」を求め続けていました。
そして物語は、喜久雄が屈指の難役とされる「壇浦兜軍記」の阿古屋に挑む場面でクライマックスを迎えます。重要無形文化財保持者に認定された彼は、阿古屋を演じきる中で、役と一体化し、現実と舞台の境界を超越したかのような境地に至ります。幕が下りた後、阿古屋の姿のまま歌舞伎座を後にし、雑踏の中へ消えていくのでした。
小説「国宝」の長文感想(ネタバレあり)
吉田修一さんの「国宝」を読み終えた今、私の心には言葉にし難いほどの深い感動と、ある種の畏怖の念が渦巻いています。これは単なる芸道小説の枠を超え、人間の業、才能の残酷さ、そして一つのことに全てを捧げた人間の生き様そのものを描いた、壮大な叙事詩と言えるでしょう。主人公・立花喜久雄の人生は、まさに波瀾万丈。しかし、その激しさの中にこそ、人間という存在の持つ輝きと闇が凝縮されているように感じました。
喜久雄の物語は、彼の出自そのものが強烈な磁力を放っています。任侠の家に生まれ、その美貌ゆえに周囲を翻弄し、そして歌舞伎という芸の世界へ。この導入部からして、読者は彼の運命に引き込まれずにはいられません。彼が背負うことになる「血」の宿命と「芸」の宿命は、時に彼を助け、時に彼を苛みます。特に、父の仇でありながら、結果的に彼を芸の道へと導くことになる辻村という存在は、人間の複雑な因果を感じさせずにはおれませんでした。
大阪での修業時代、二代目花井半二郎の息子・俊介との出会いは、物語の大きな推進力となります。梨園の御曹司として生まれながらも、喜久雄の圧倒的な才能の前に屈折した感情を抱く俊介。そして、出自にコンプレックスを抱えながらも、ただひたすらに芸の高みを目指す喜久雄。二人は親友でありながら、最も熾烈なライバルとして互いを意識し続けます。この二人の関係性は、時に痛ましく、しかしそれ以上に切実で、彼らの芸を磨き上げる砥石のような役割を果たしていたのではないでしょうか。
「曽根崎心中」のお初役に喜久雄が抜擢される場面は、物語前半の大きなクライマックスです。師である半二郎の、血縁よりも才能を重んじる非情ともいえる決断。それは喜久雄の運命を決定づけると共に、俊介の心を深く傷つけ、彼の出奔へと繋がります。この出来事を通して、歌舞伎という伝統と格式、そして才能がせめぎ合う世界の厳しさが容赦なく描かれています。喜久雄の成功の陰には、常に誰かの犠牲や孤独があったという事実は、読んでいて胸が締め付けられる思いでした。
三代目花井半二郎を襲名し、これからという時に訪れる師の死と莫大な借金。喜久雄の人生は、一筋縄ではいきません。栄光と挫折は常に隣り合わせであり、彼が手にするものの代償はあまりにも大きいのです。東京へ拠点を移してからの苦闘、伝説の女形・小野川万菊との出会い、そして映画界への挑戦。これらのエピソードは、喜久雄が歌舞伎役者としてだけでなく、一人の表現者としていかにもがき、自己を模索し続けたかを示しています。万菊の存在は、喜久雄にとって目標であり、同時に計り知れないプレッシャーでもあったことでしょう。
十年ぶりに再会した俊介との関係も、物語に更なる深みを与えています。テレビプロデューサー竹野によってメディア戦略に利用され、スキャンダルに巻き込まれる喜久雄。彼の出自である任侠の世界との繋がりが、再び彼を苦しめます。しかし、こうした逆境の中でさえ、喜久雄と俊介は互いの芸を認め合い、時には共演し、芸術の高みを目指していくのです。彼らの間には、単純な友情やライバル心では語り尽くせない、複雑で強固な絆があったのだと感じます。
娘・綾乃との関係は、喜久雄の人間的な側面、特に父親としての未熟さや不器用さを浮き彫りにします。芸に全てを捧げるあまり、家庭を顧みることができなかった喜久雄。綾乃の非行や、その後の彼女からの拒絶は、彼が芸の道で得たものの大きさと、そのために失ったものの重さを象徴しているかのようです。「皆の幸せを奪っていく父親」という綾乃の言葉は、喜久雄の胸に深く突き刺さったことでしょうし、読者の心にも重くのしかかります。
俊介の病と、その最期は、この物語の中でも特に涙を誘う場面でした。両足を失いながらも、なお舞台に立ち続けようとする俊介の執念。それは、喜久雄とはまた異なる形の、芸への壮絶な愛の姿です。彼の死は、喜久雄にとって計り知れない喪失感をもたらしますが、同時に、喜久雄の芸をさらなる高みへと昇華させる触媒となったのかもしれません。ライバルの死を乗り越え、喜久雄はますます芸の道に没入していきます。
「人間国宝」への道が開かれようとする一方で、喜久雄の内面は常人には理解しがたい領域へと踏み込んでいきます。プロデューサーの竹野が彼を評した「ガラス玉のような目」、そして「舞台に生きる精霊」という言葉は、もはや人間的な感情を超越したかのような喜久雄の姿を見事に捉えています。「日本一の歌舞伎役者にして下さい。その代わり、他のもんはなんもいりませんから」という彼の「悪魔との取引」にも似た願いは、芸のためなら全てを犠牲にするという彼の覚悟を示しています。
そして、クライマックスである「阿古屋」の舞台。この場面の描写は圧巻の一言です。琴、三味線、胡弓を完璧に弾きこなし、阿古屋という役になりきる喜久雄。それはもはや演技ではなく、役が喜久雄に憑依したかのようであり、彼自身が歌舞伎そのものと化した瞬間だったのではないでしょうか。彼が長年求め続けてきた「幕の下りない舞台」が、この時、彼の内面で実現したのかもしれません。
最後の場面、阿古屋の姿のまま歌舞伎座を後にし、雑踏へと消えていく喜久雄。その顔に浮かんだ安堵のような微笑みを、娘の綾乃だけが見届けます。この結末は、多くの解釈を許すでしょう。それは芸術的超越の瞬間なのか、あるいは現実からの完全な離脱なのか。私には、彼が長年背負ってきた重圧から解放され、芸という名の「国宝」そのものとして永遠に生き続けることを選んだようにも思えました。
この物語を通して強く感じたのは、芸術というものの持つ魔力と、それに魅入られた人間の宿命です。喜久雄の人生は、幸福だったと言えるのかどうか、私には分かりません。しかし、彼がその生涯を賭して追い求めた「きれいな景色」は、間違いなく存在し、多くの人々を魅了し続けたのです。彼の生き様は、私たちに「何のために生きるのか」という根源的な問いを投げかけてきます。
登場人物たちもまた、それぞれに強烈な個性を放っていました。喜久雄を生涯にわたって支え続けた徳次。彼の無償の愛と献身は、喜久雄の孤独な魂にとって唯一の救いであったのかもしれません。そして、喜久雄の師であり義父である二代目花井半二郎。彼の厳格さと公正さ、そして喜久雄の才能を見抜く眼力は、物語の重要な転換点を作り出しました。
「国宝」は、歌舞伎という特殊な世界を描きながらも、そこに生きる人々の情念や葛藤は、私たち誰もが抱えるものと地続きであると感じさせてくれます。伝統と革新、血筋と才能、栄光と孤独、愛と憎しみ。これらの普遍的なテーマが、重厚な物語の中で複雑に絡み合い、読む者の心を揺さぶります。
吉田修一さんの筆致は、時に淡々と、時に激情的に、登場人物たちの内面を深く掘り下げていきます。その描写力によって、私たちはまるで喜久雄と共に舞台に立ち、彼と同じ景色を見ているかのような錯覚に陥るのです。読み終えた後も、しばらくはその世界から抜け出せないほどの強い印象を残す作品でした。この物語に出会えたことに、心から感謝したいと思います。
まとめ
吉田修一氏の長編大作「国宝」は、一人の歌舞伎役者・立花喜久雄の壮絶な人生を通じて、芸の道の厳しさ、人間の情念、そして孤高の頂点を描いた物語です。任侠の家に生まれながら、類まれな美貌と才能によって歌舞伎の世界に身を投じた喜久雄が、数々の試練や葛藤を乗り越え、芸の高みを追い求める姿には圧倒されます。
物語は、喜久雄の誕生から始まり、彼の成長、ライバルとの出会いと確執、師との絆、そして家族との複雑な関係を丁寧に描き出しています。その中で、彼がいかにして「国宝」と呼ばれるほどの芸を築き上げていったのか、その過程には息をのむほどの迫力があります。成功の裏にある犠牲や孤独も容赦なく描かれており、読者は芸術家の栄光と苦悩を深く感じ取ることでしょう。
特に、生涯のライバルであり友でもあった大垣俊介との関係や、最後の舞台となる「阿古屋」の場面は、この物語の大きな見どころです。喜久雄が芸の極致に達し、現実と舞台の境界を超越していくかのような描写は、読む者に強烈な印象を残します。芸に全てを捧げた人間の生き様とは何かを問いかけてくる、まさに魂を揺さぶる作品です。
この物語は、歌舞伎に馴染みのない方でも、一人の人間の生き様を描いたドラマとして十分に楽しむことができます。人間の持つ可能性と、一つのことに打ち込むことの尊さ、そしてそのために払われる代償について深く考えさせられるでしょう。「国宝」は、現代日本文学が誇るべき傑作の一つとして、長く読み継がれていくに違いありません。

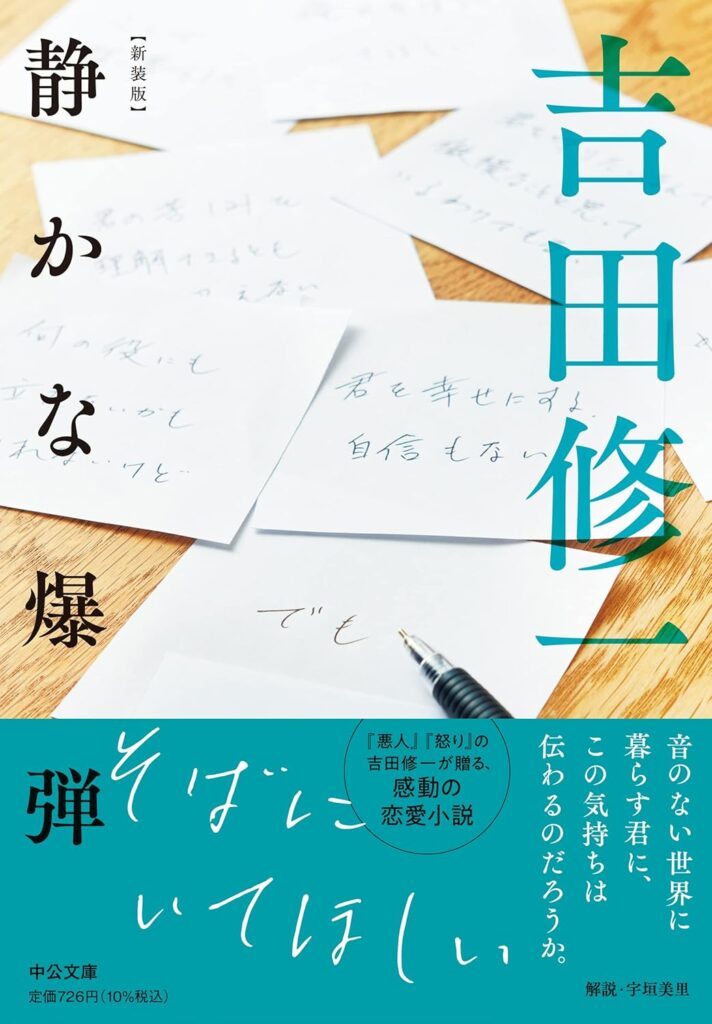
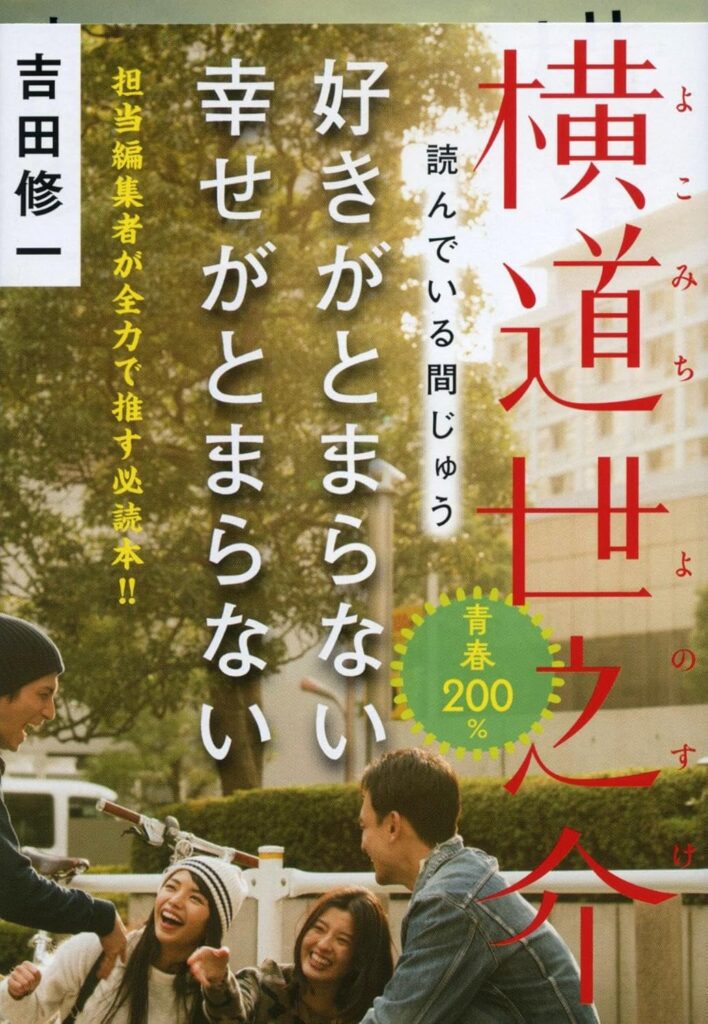


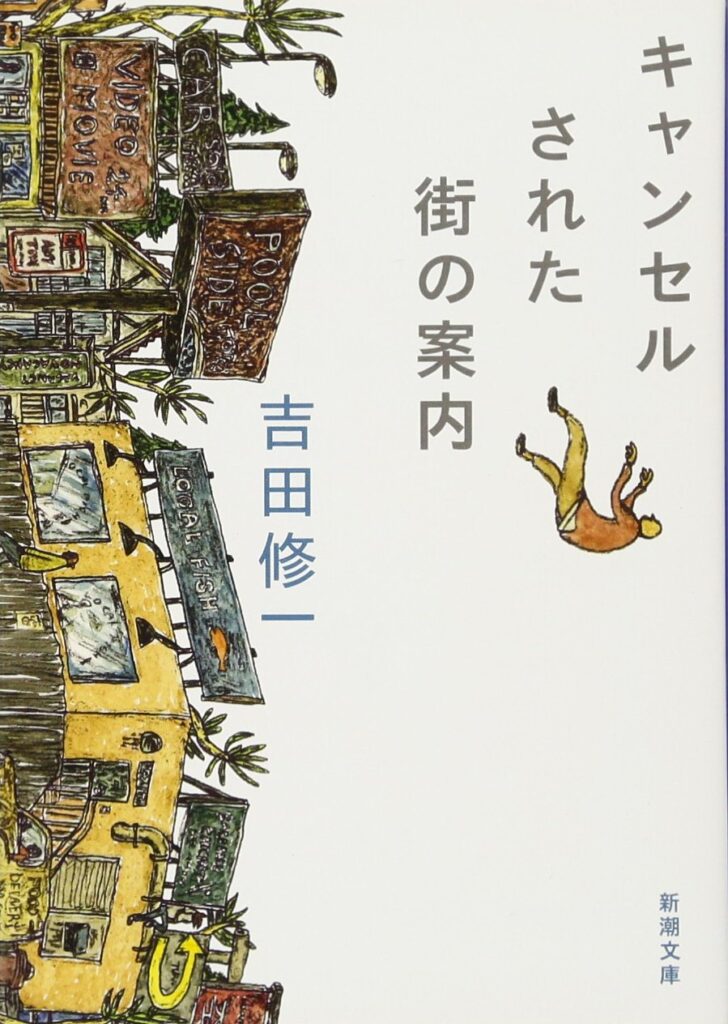
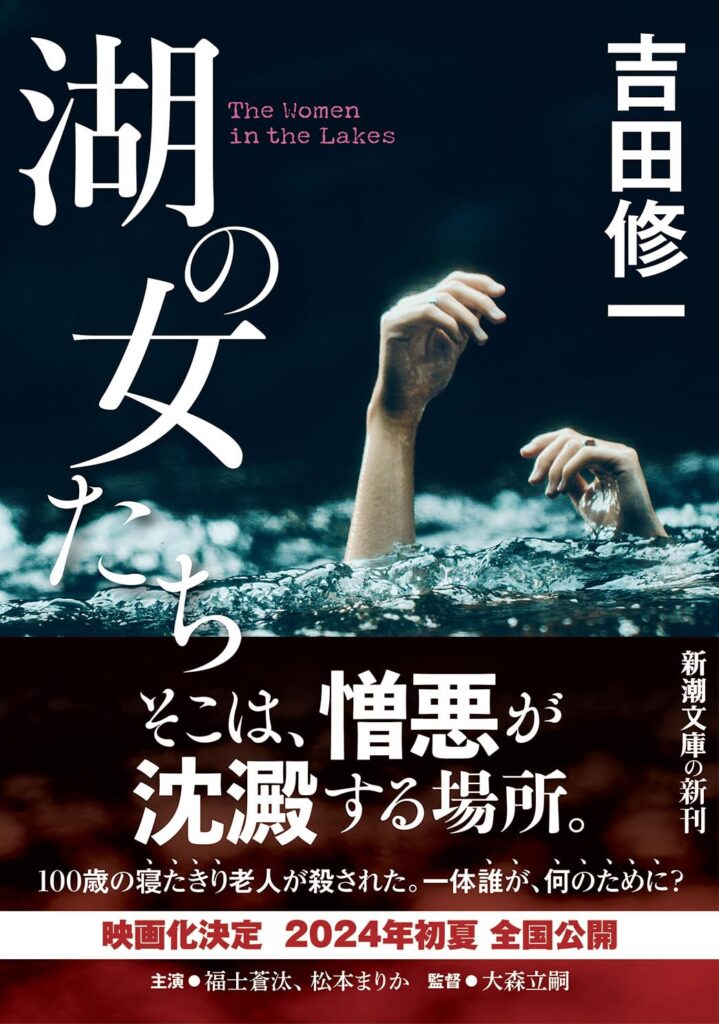
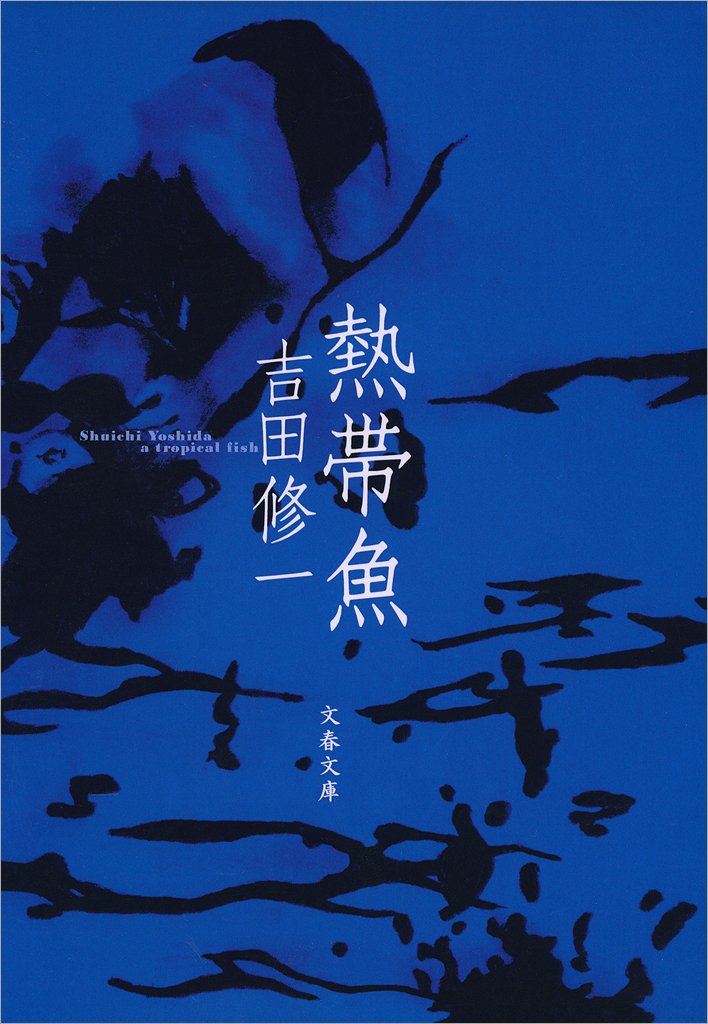
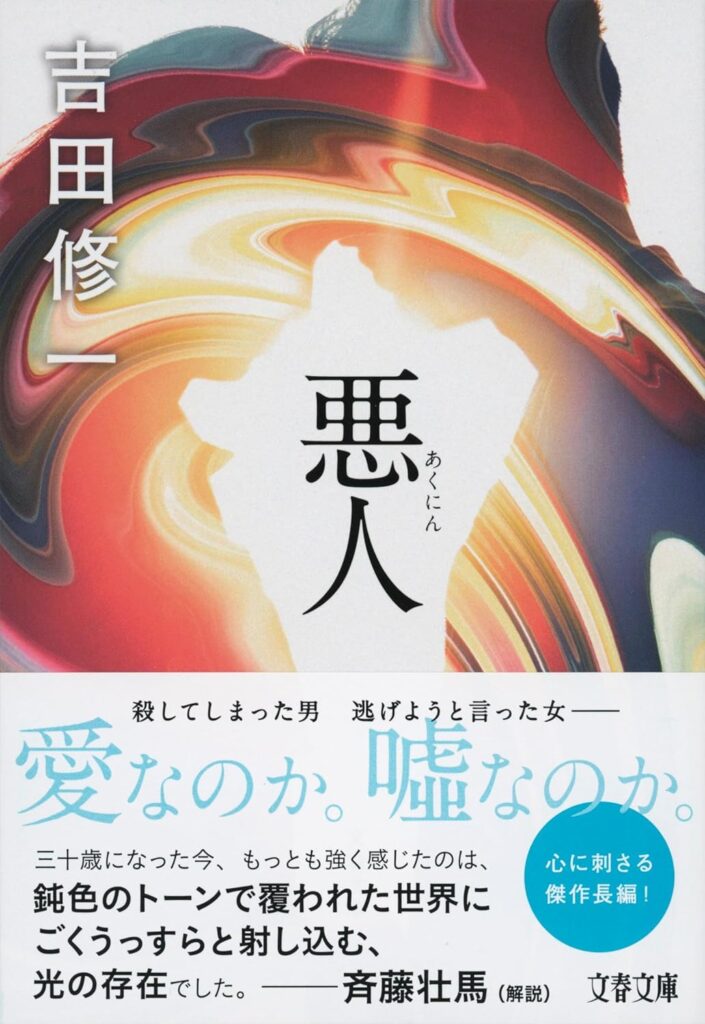
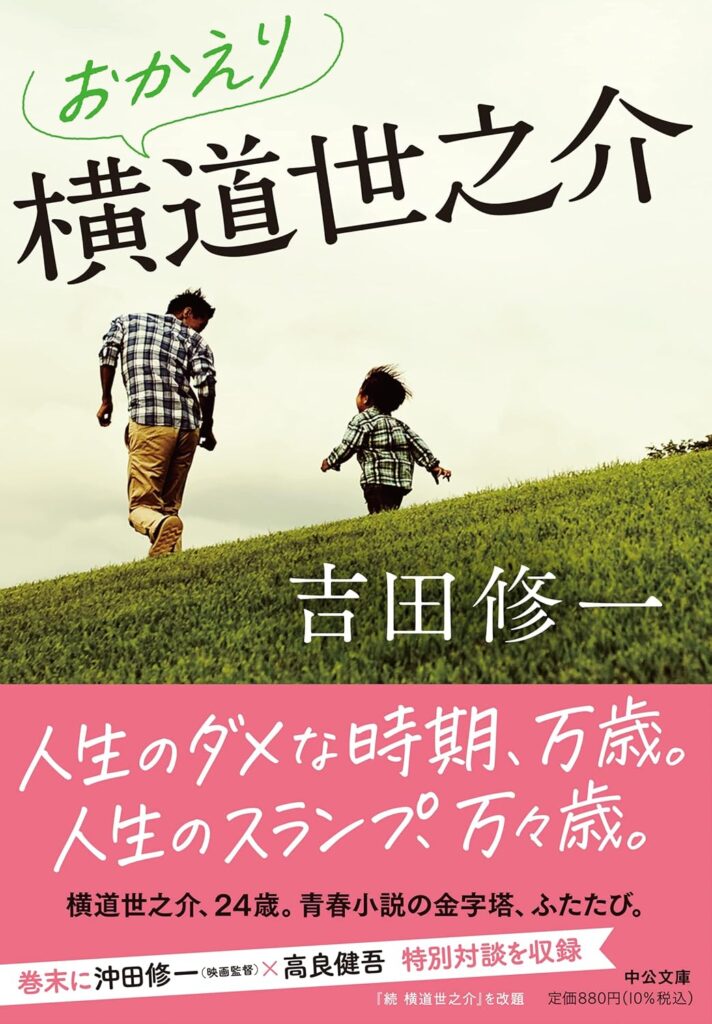
-728x1024.jpg)