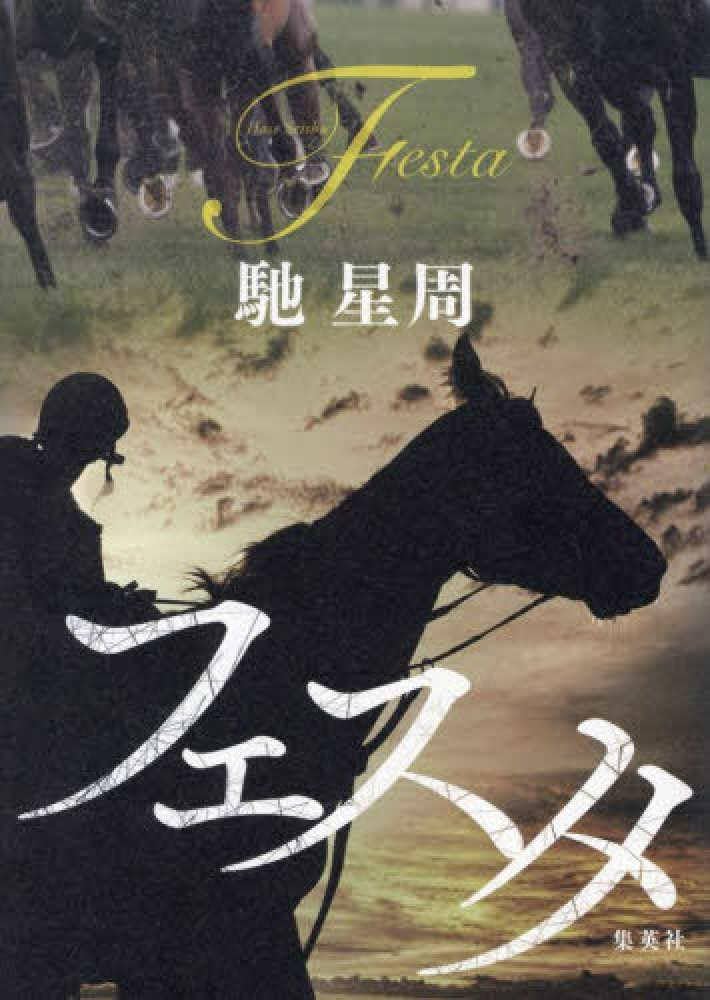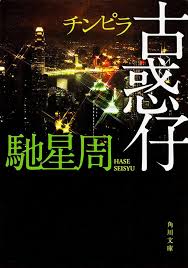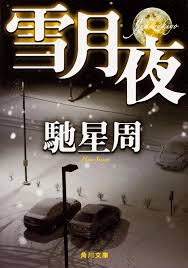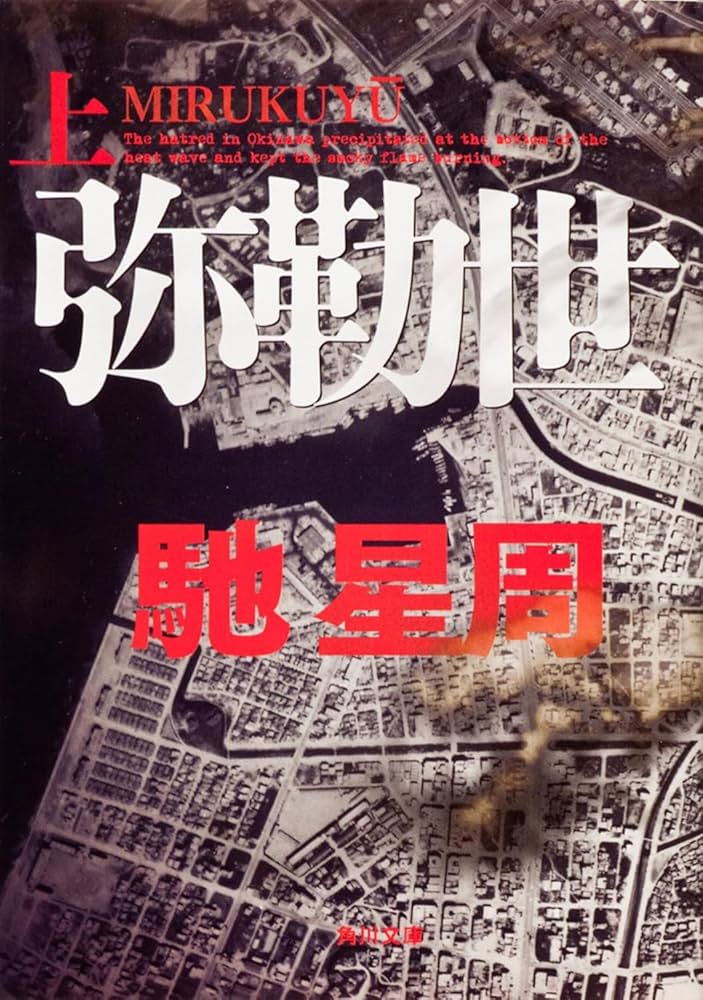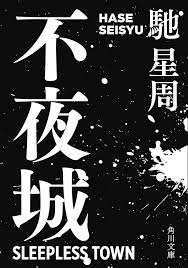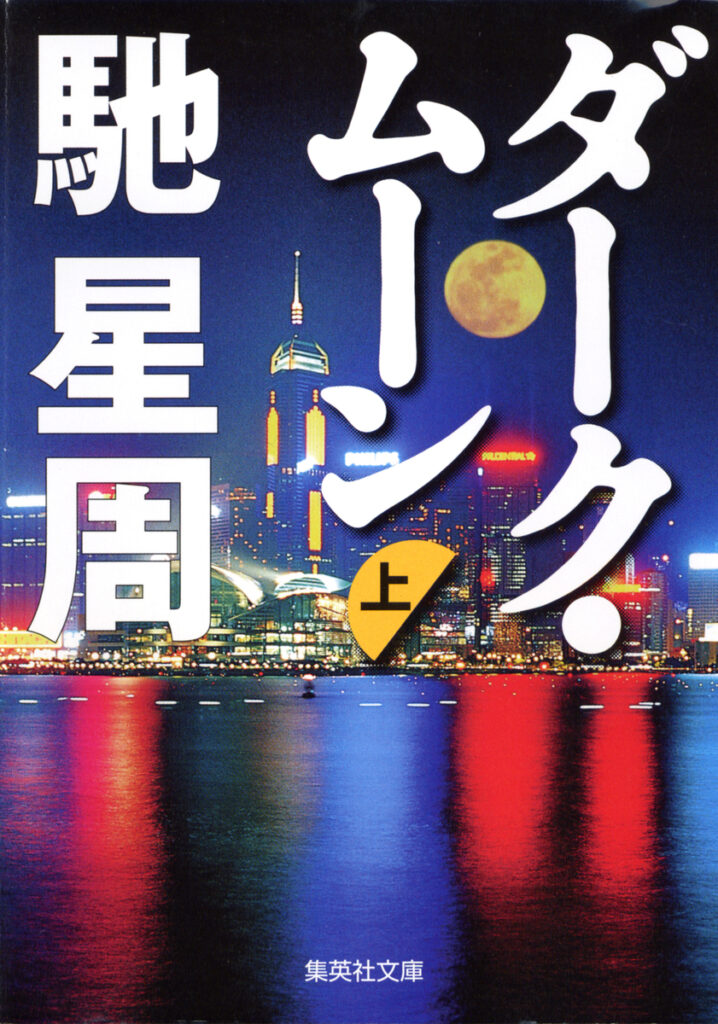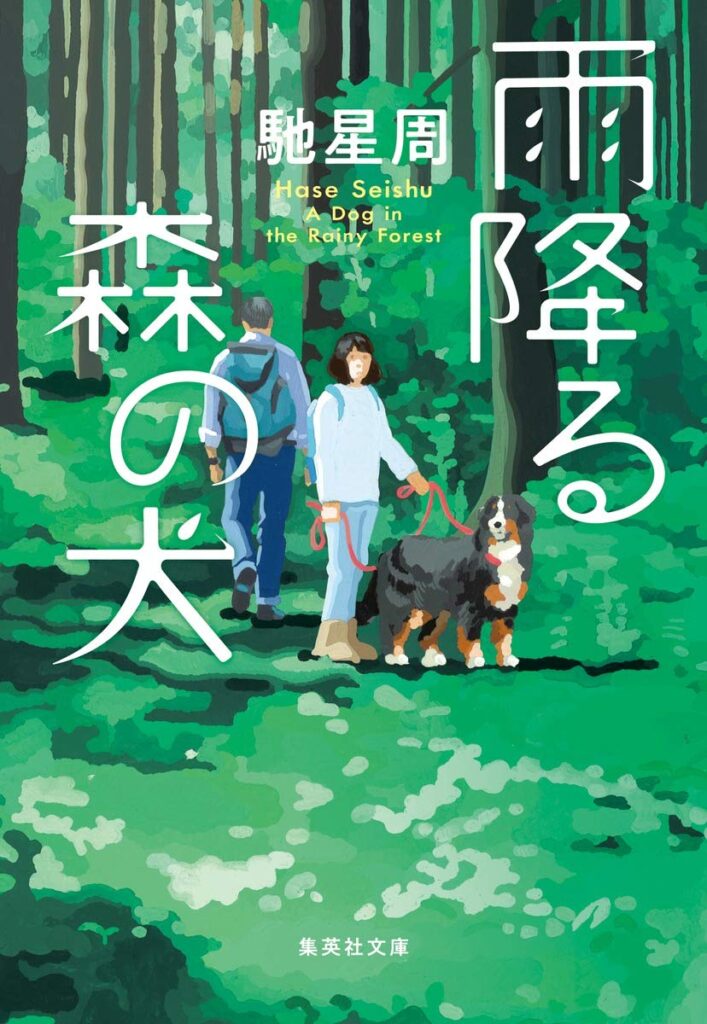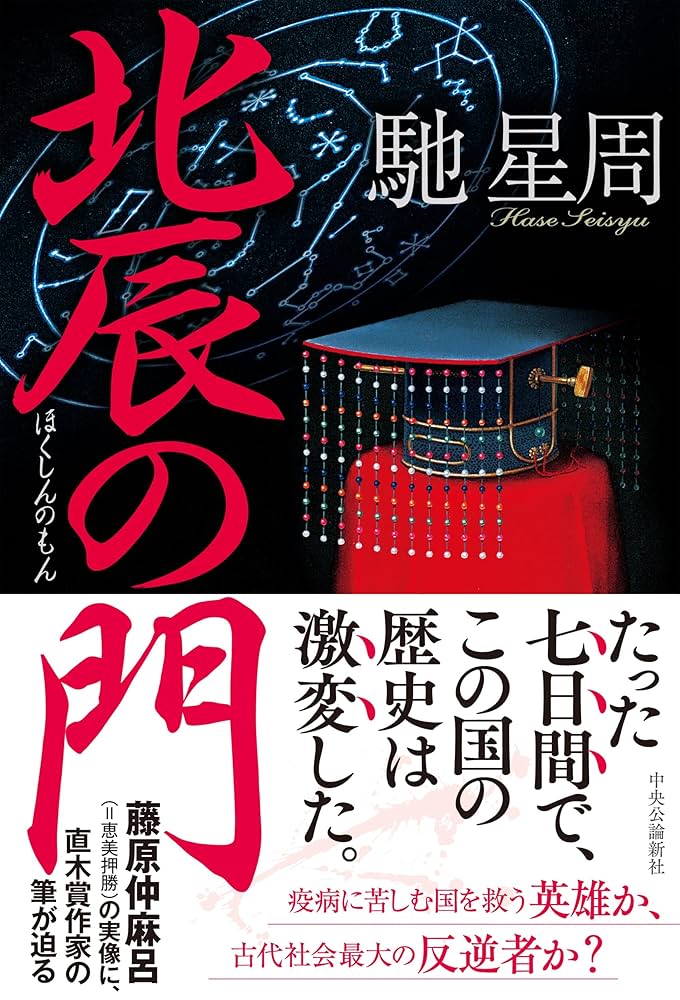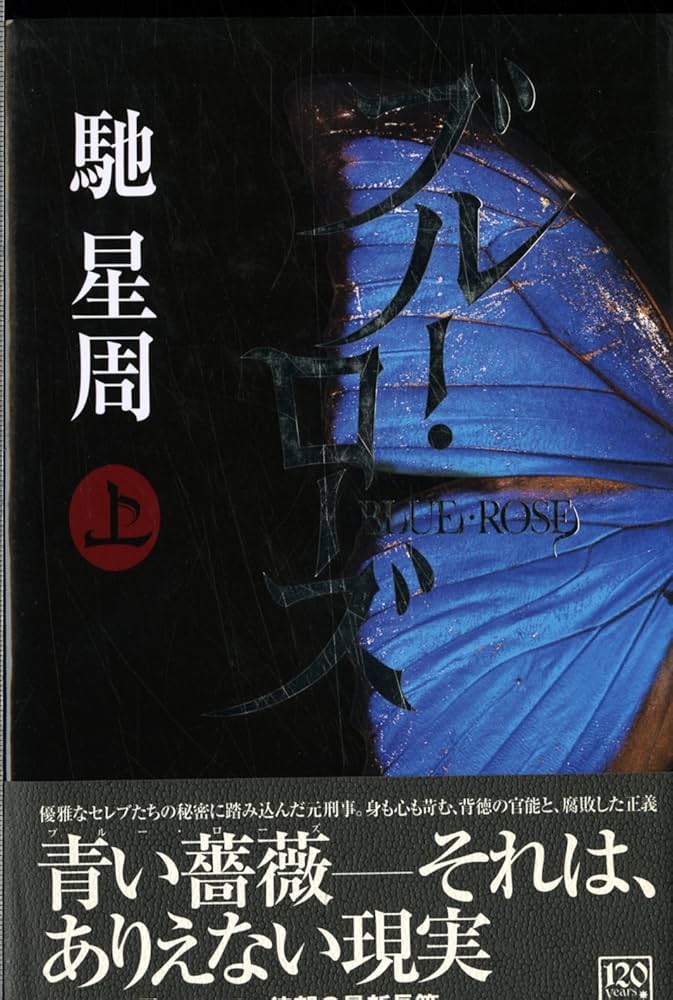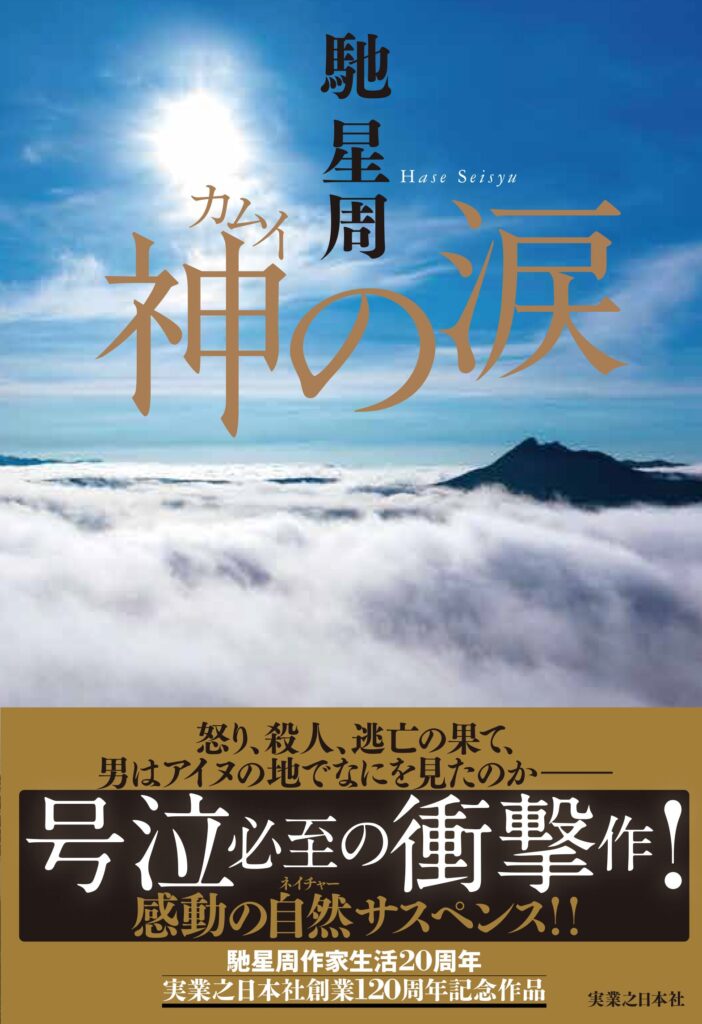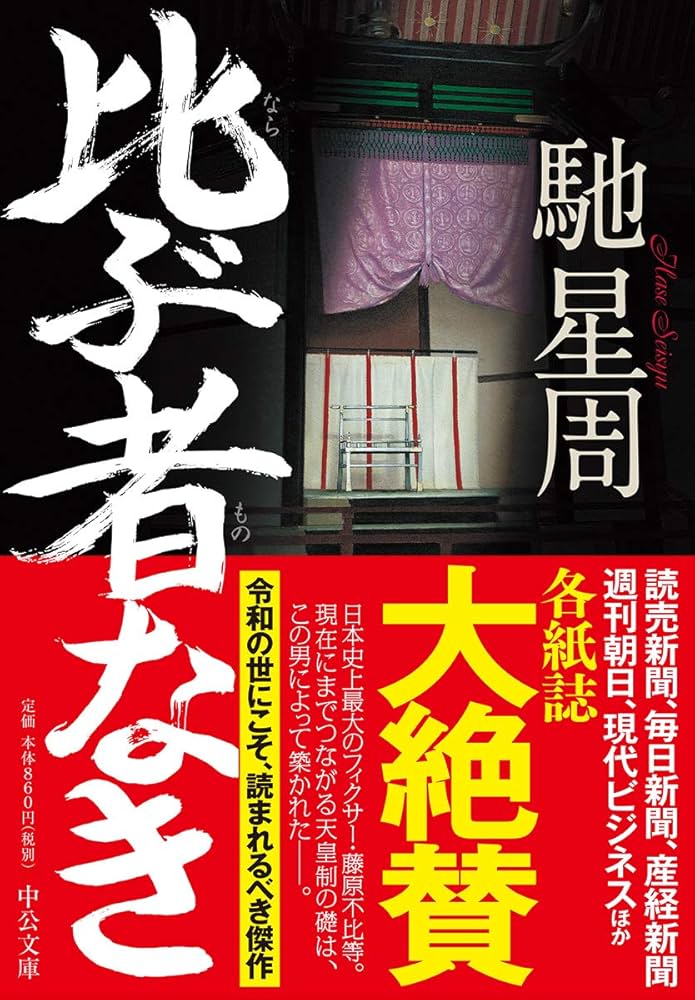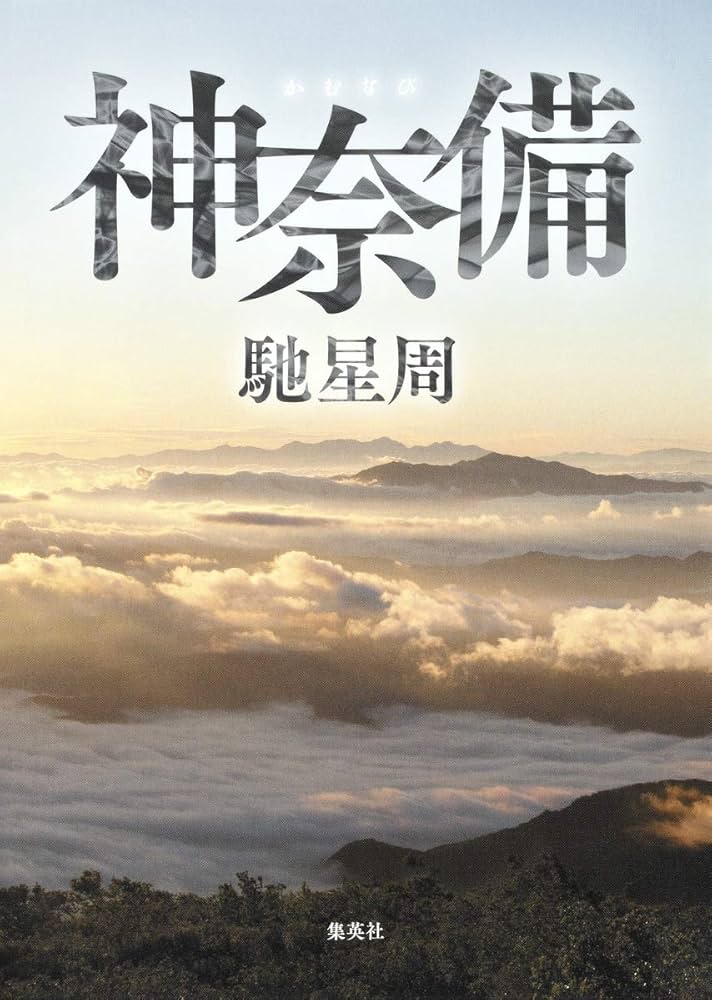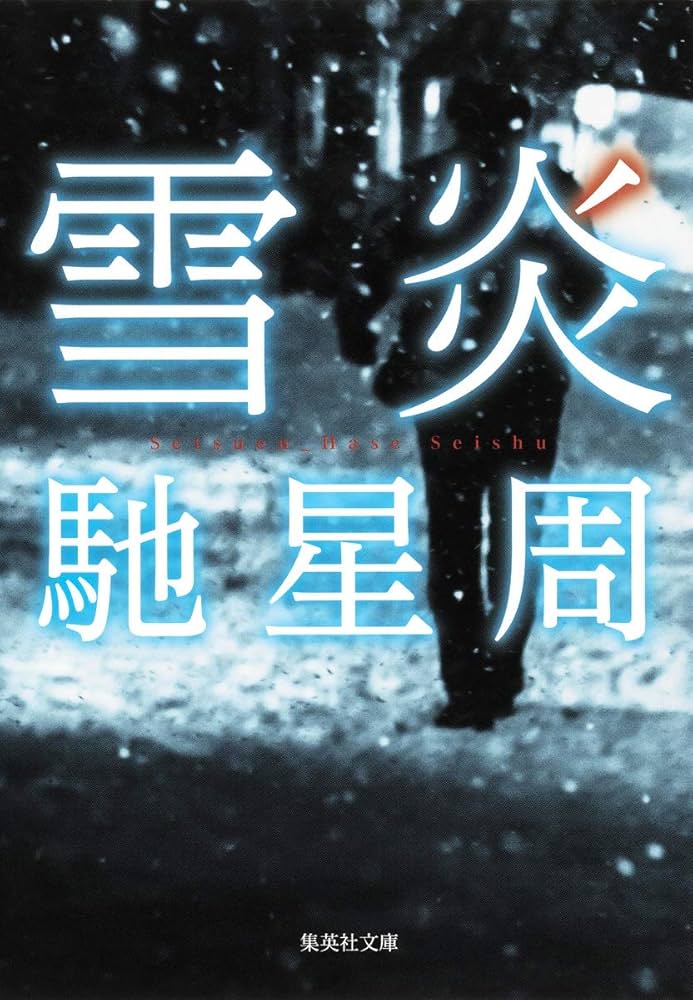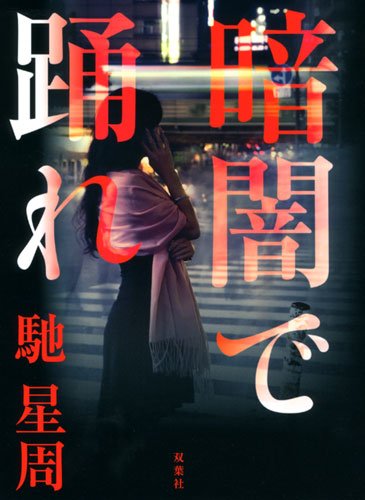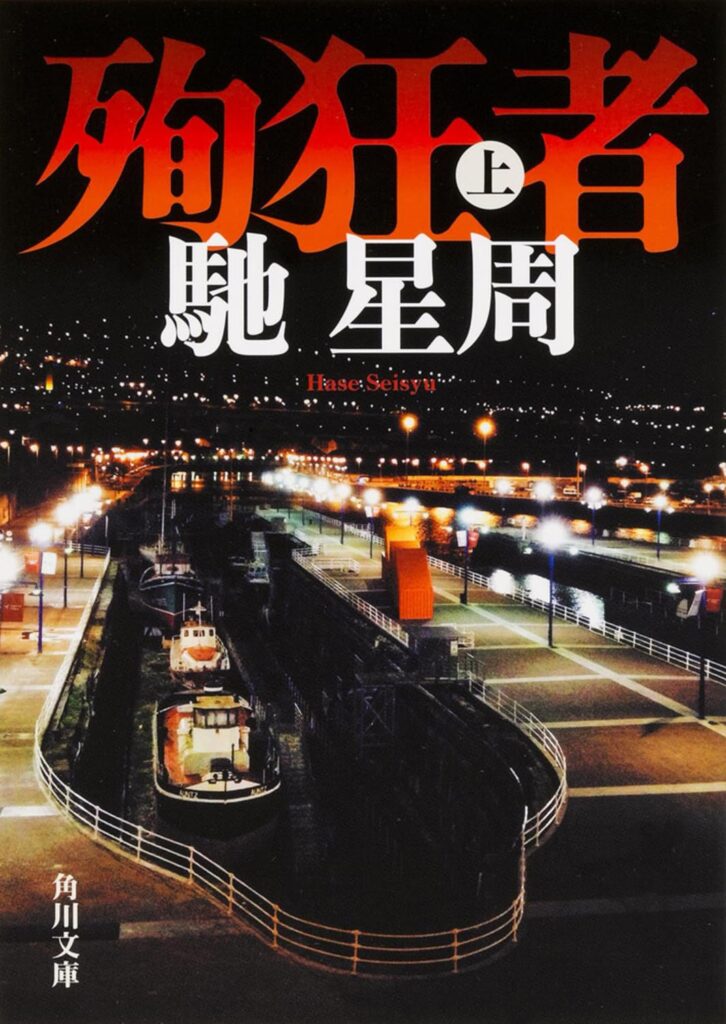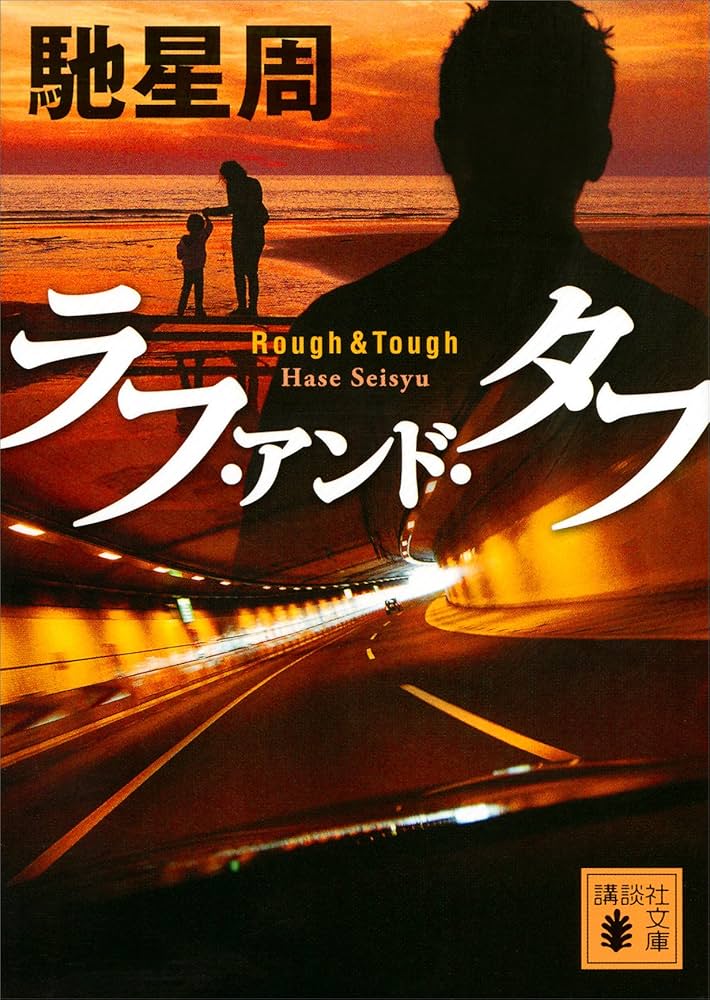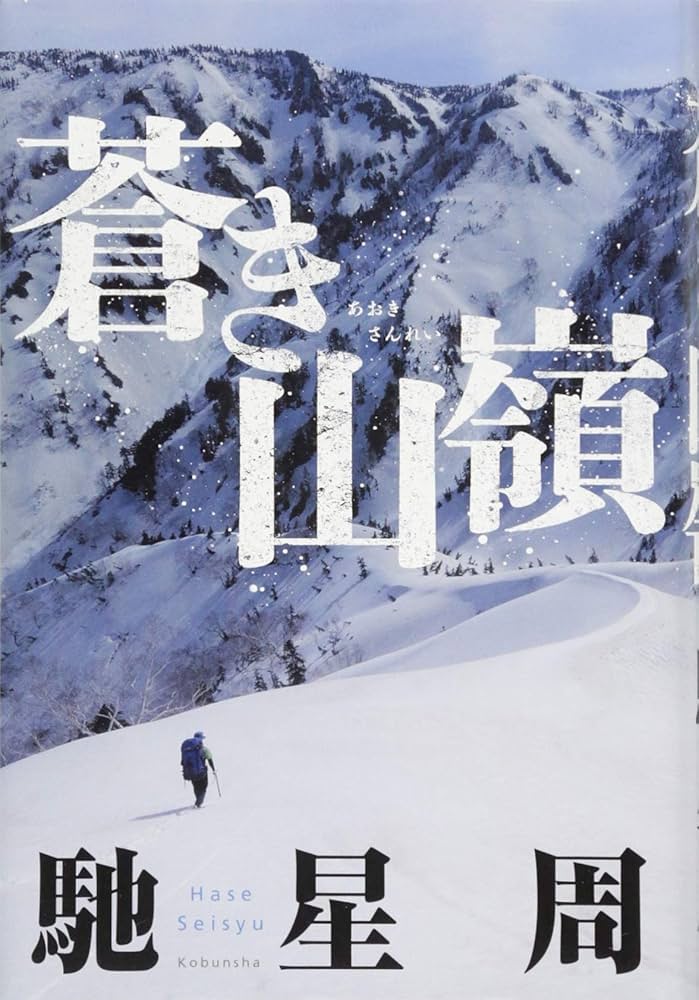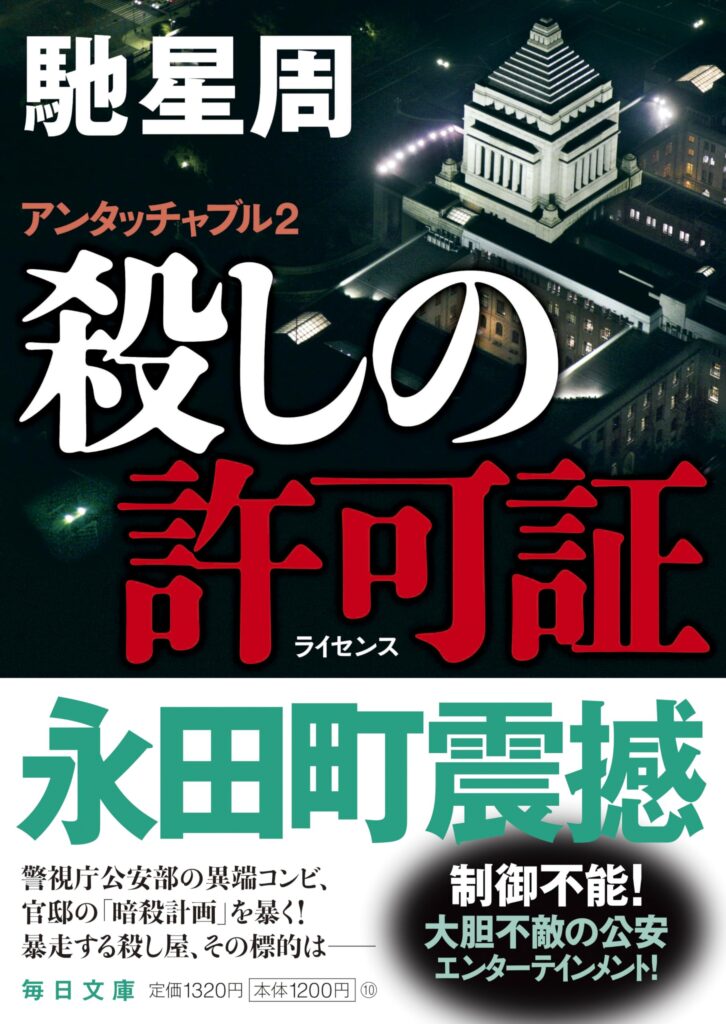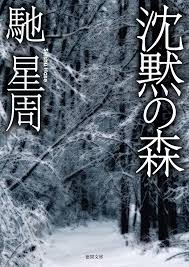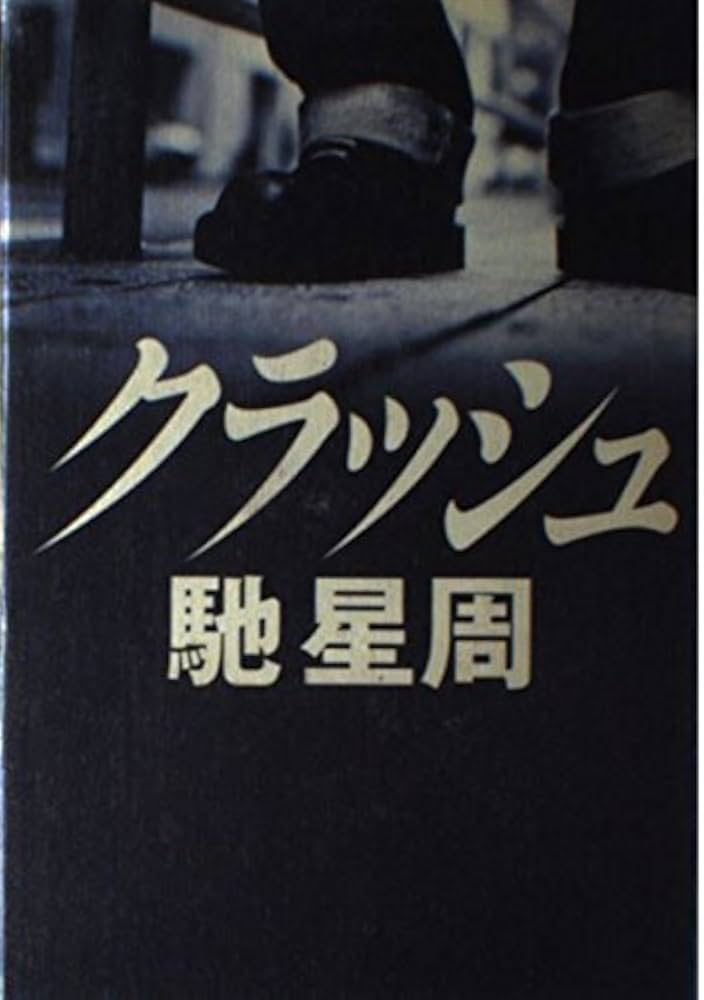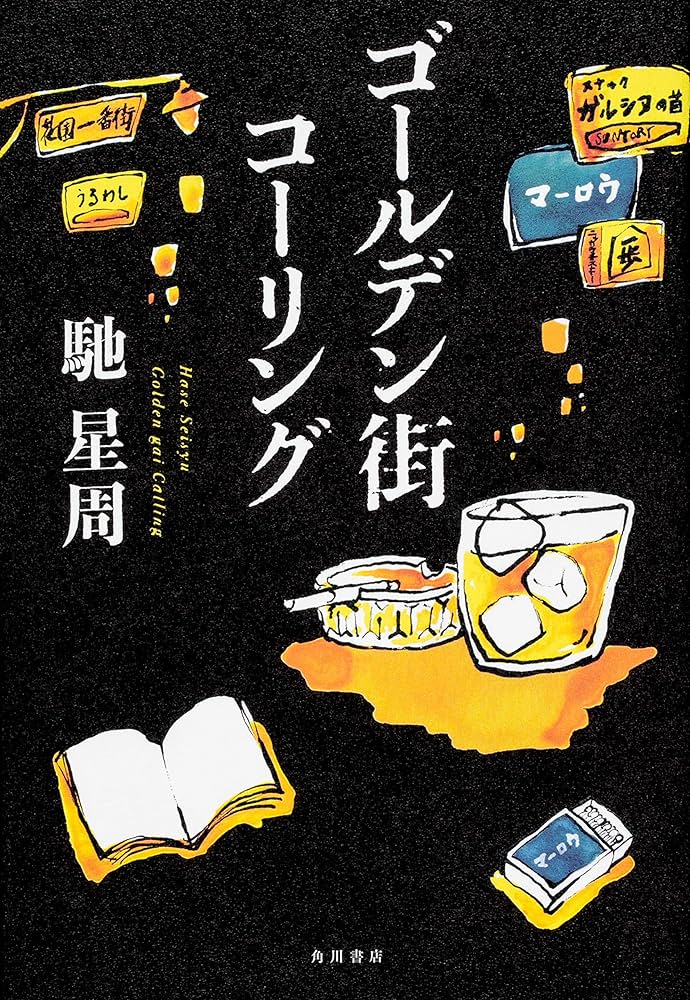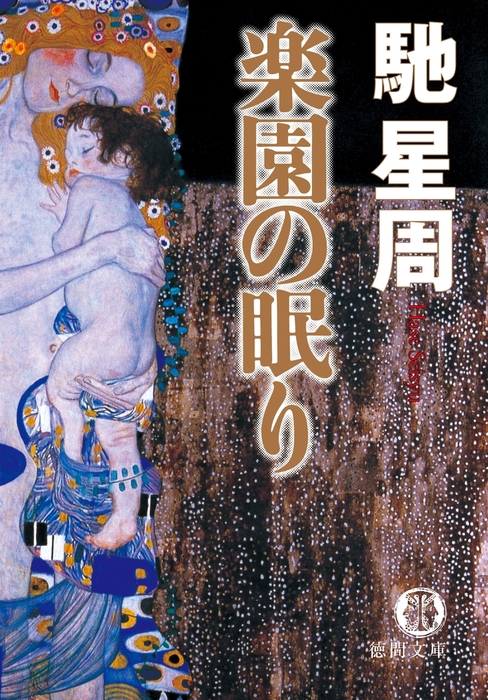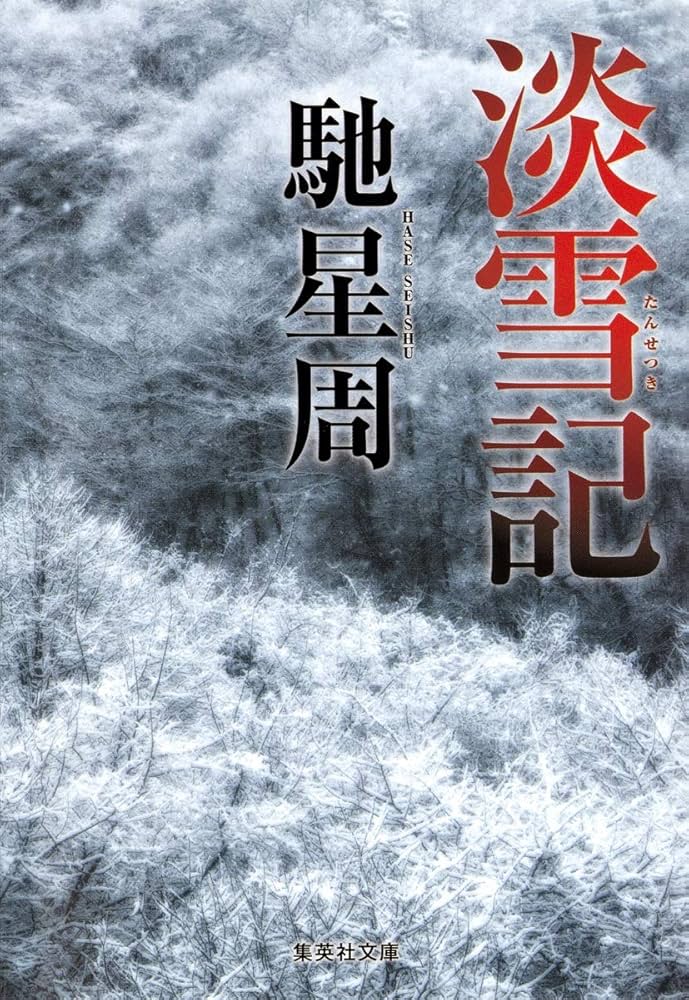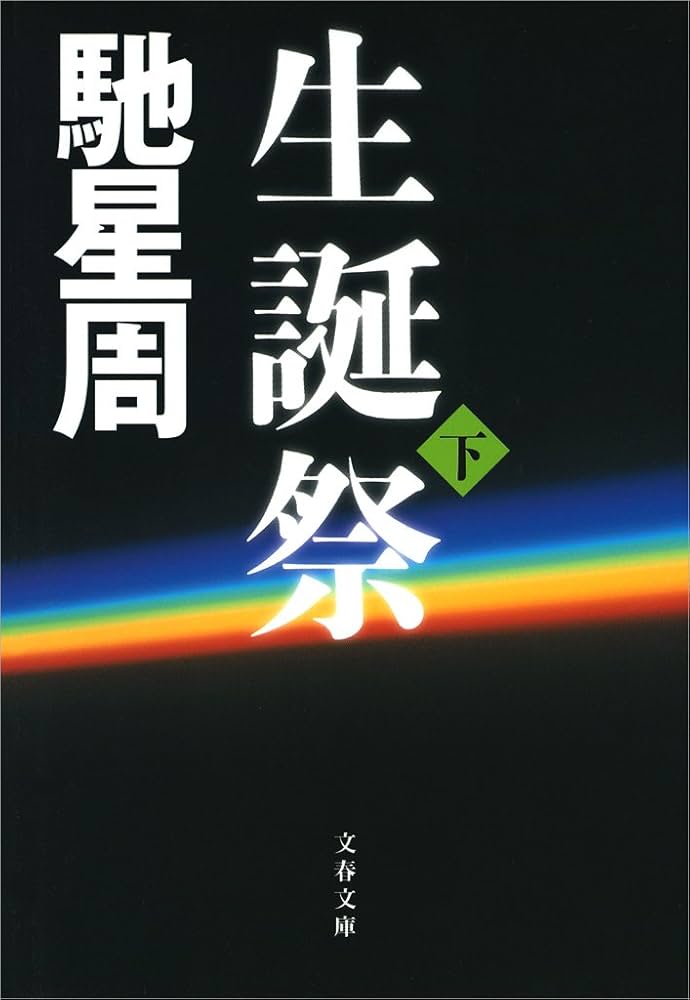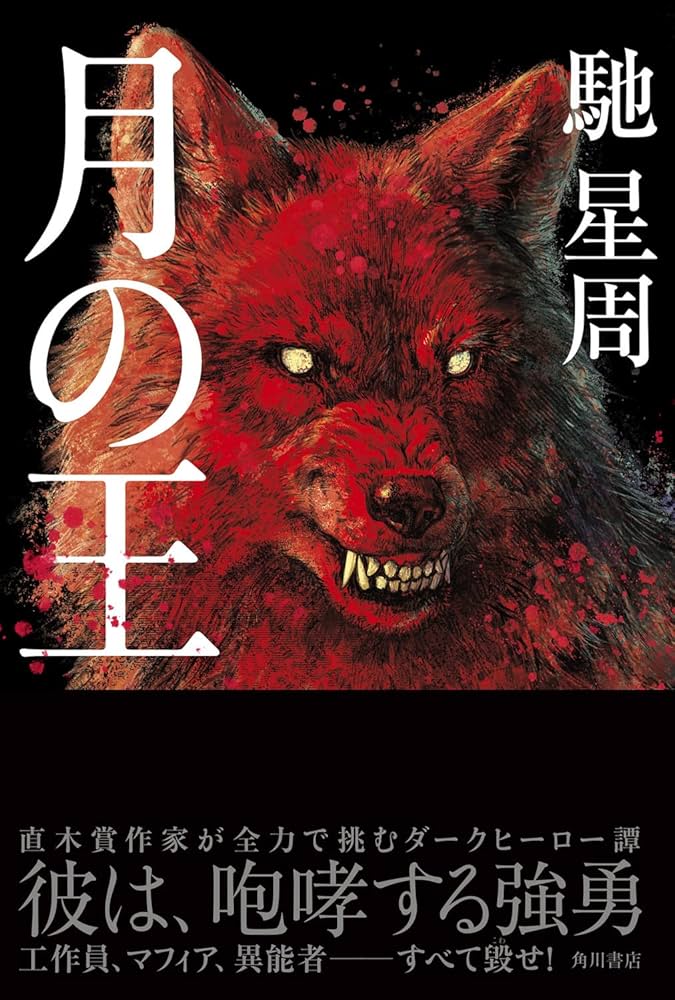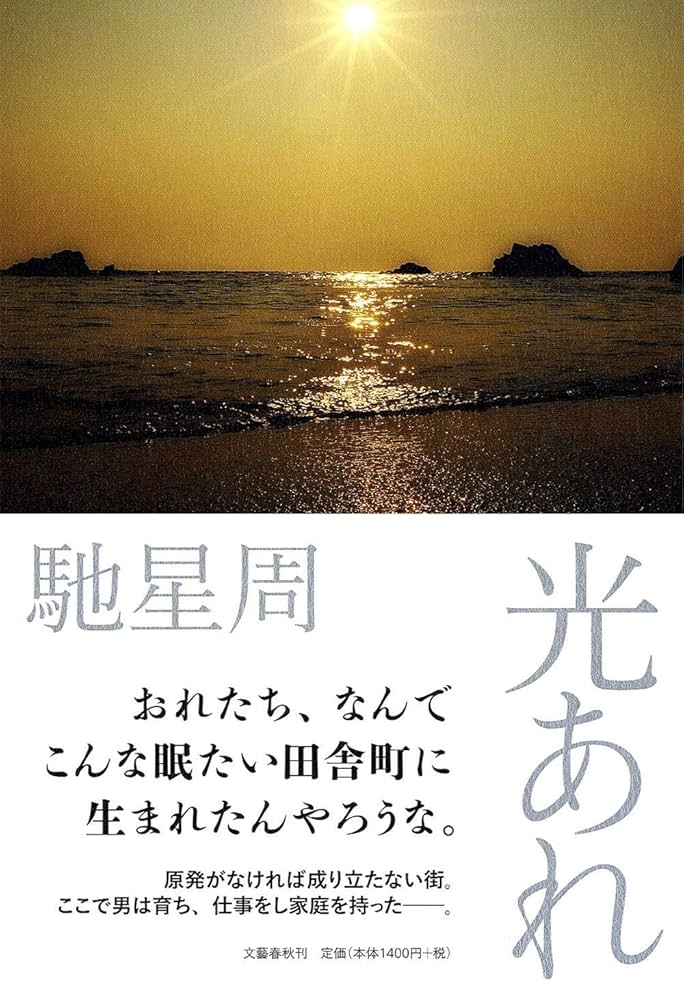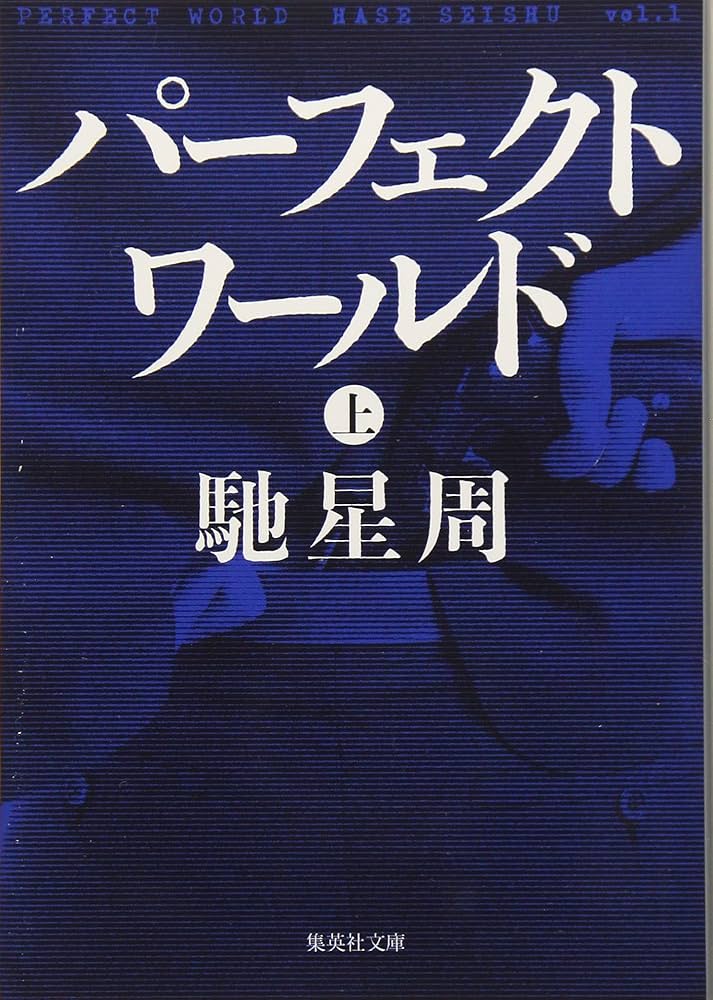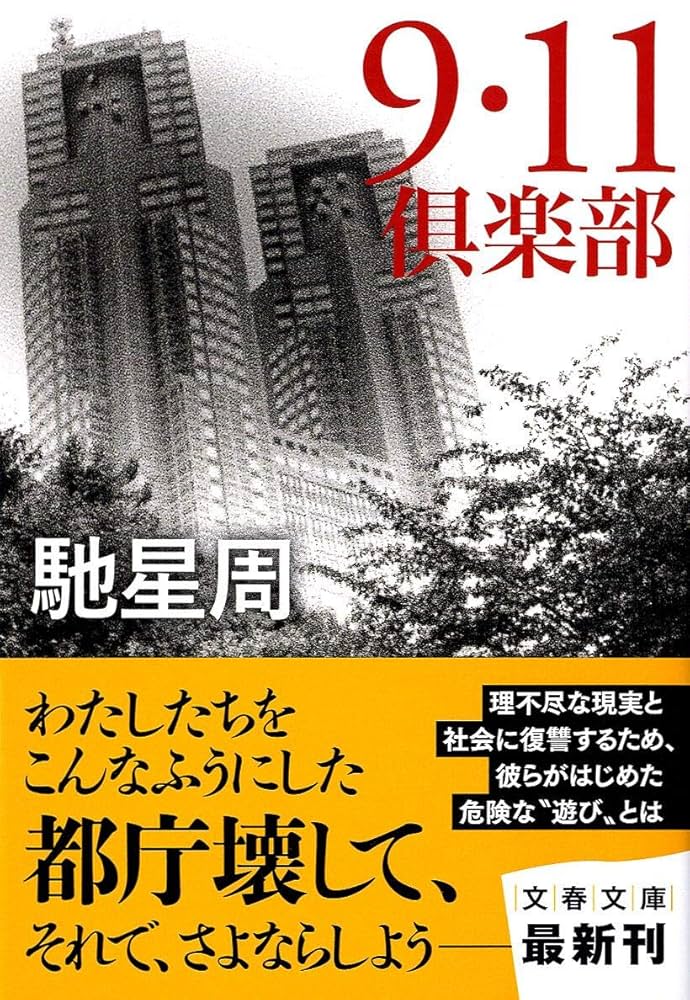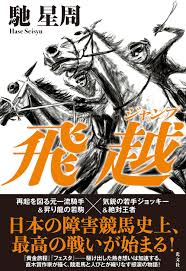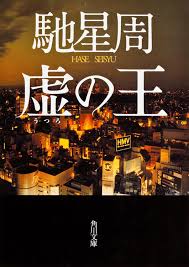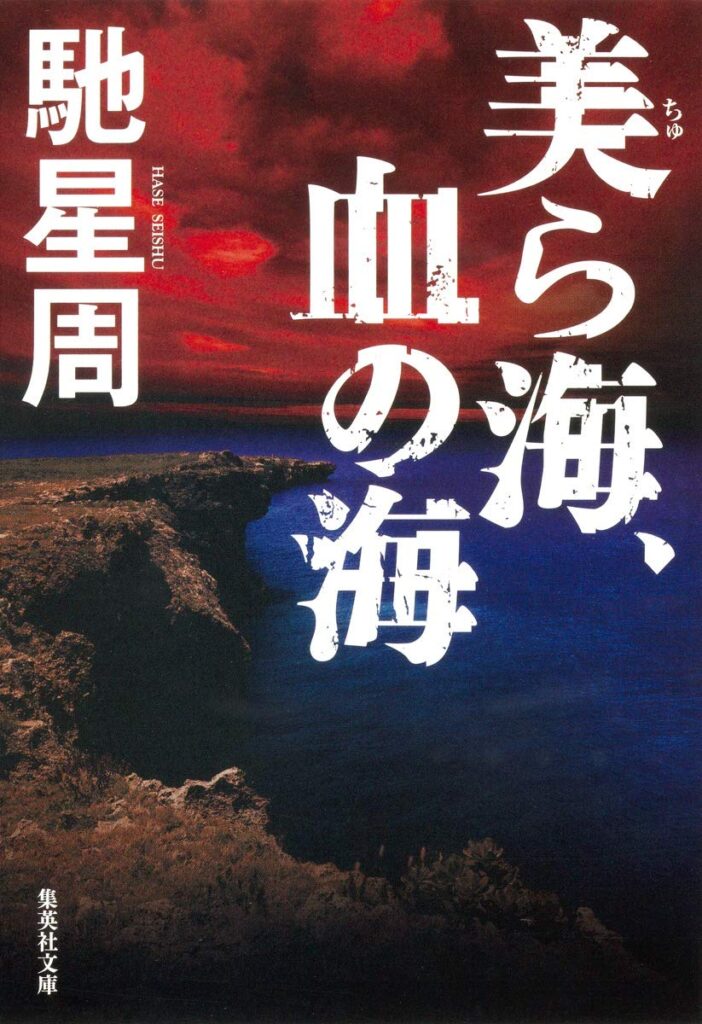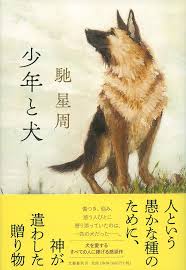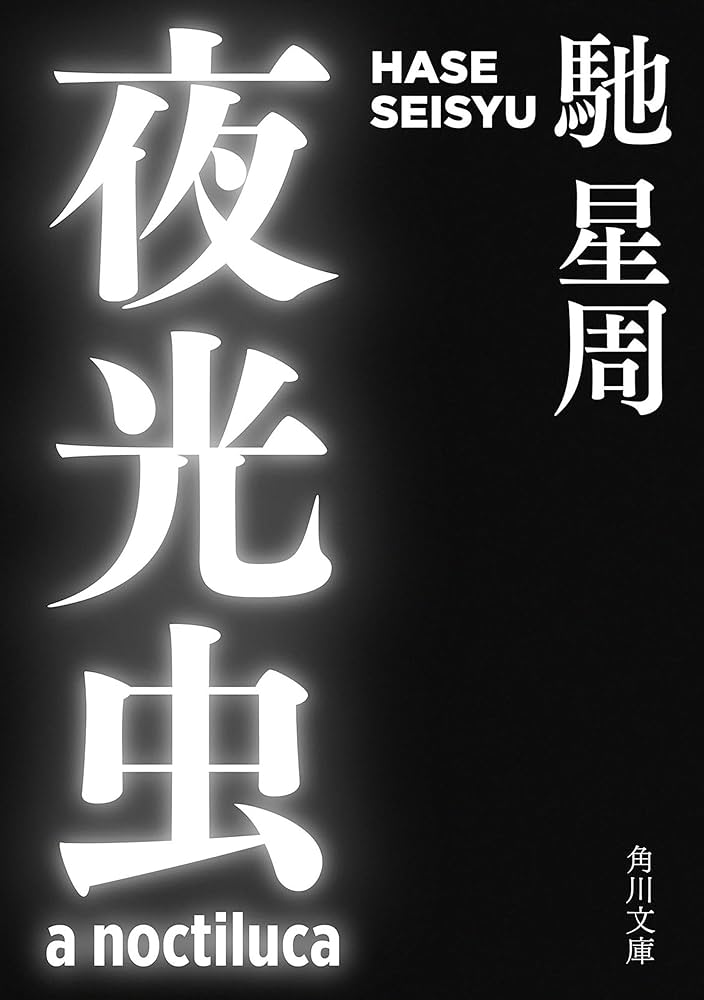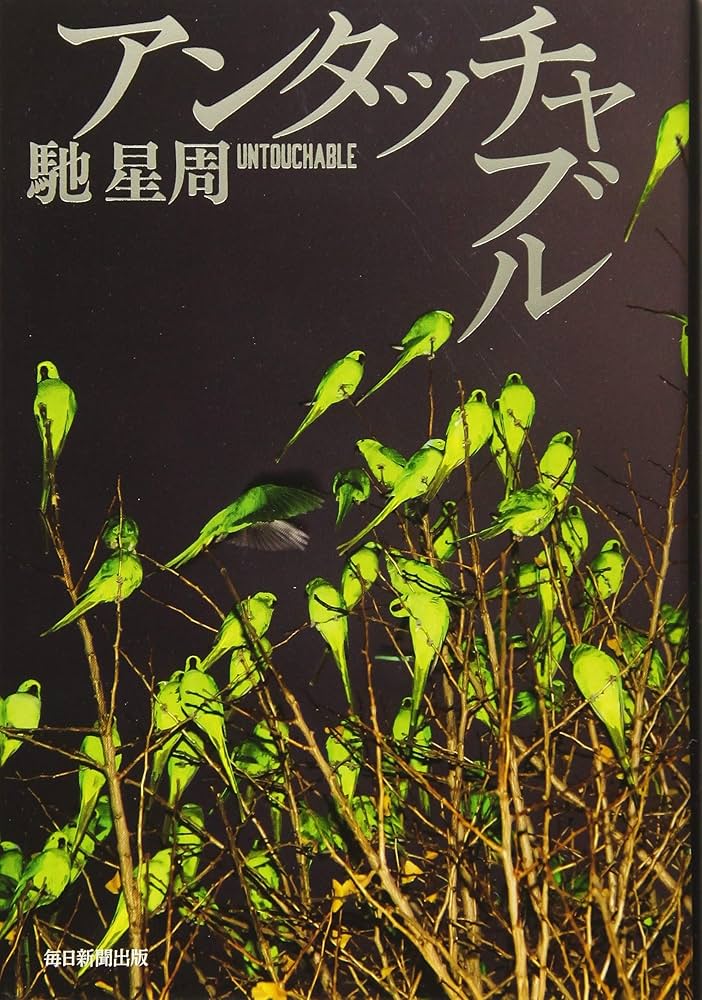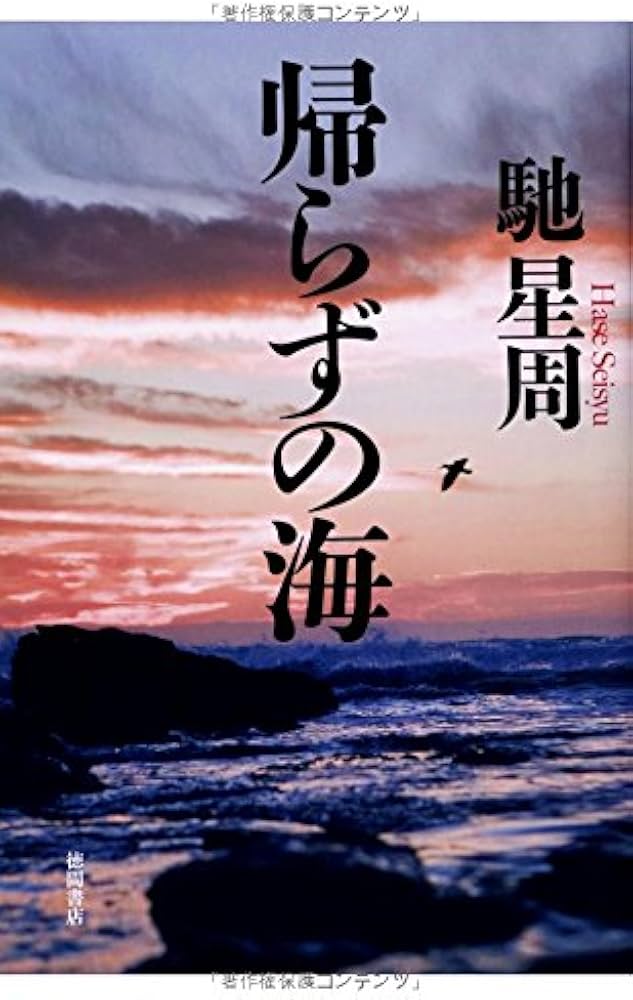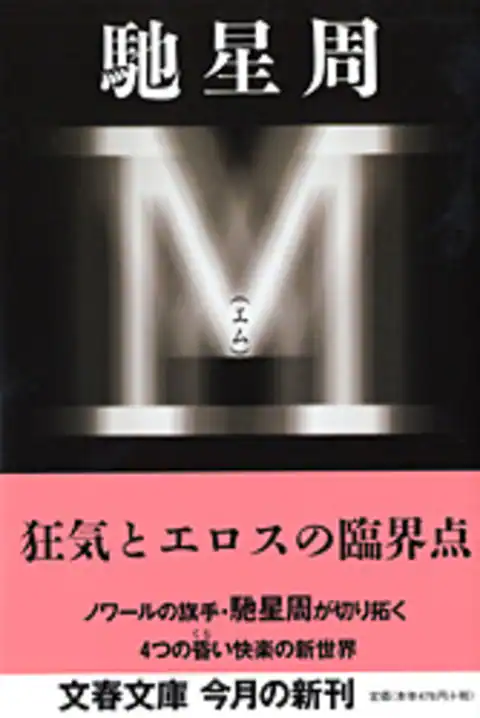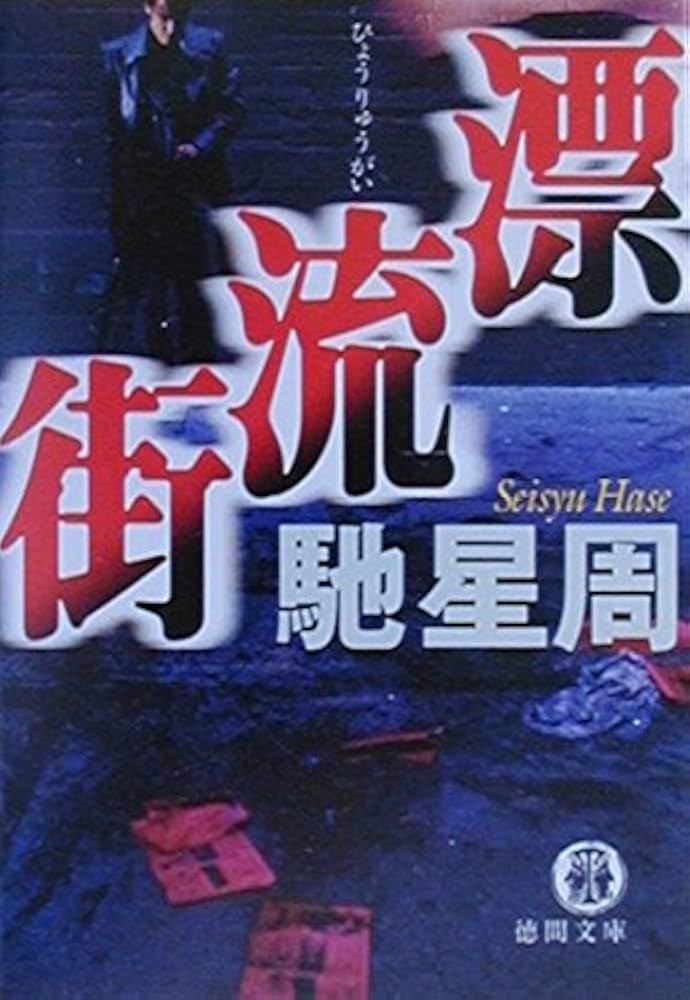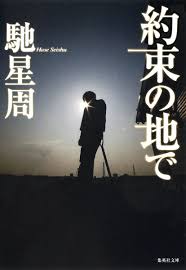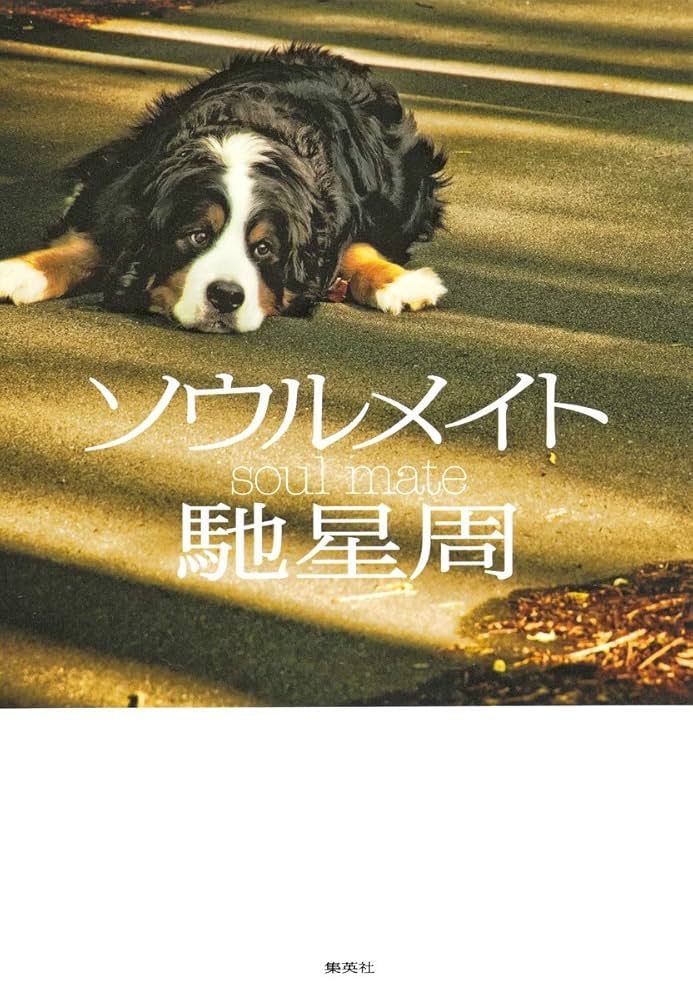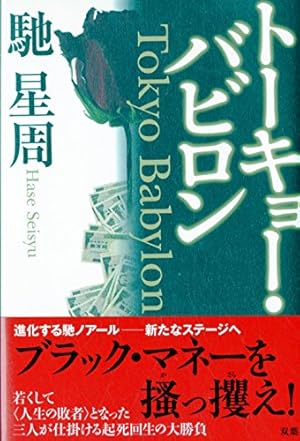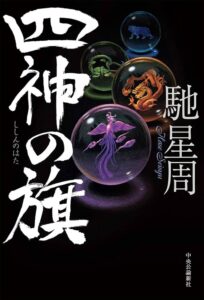 小説「四神の旗」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「四神の旗」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
奈良時代の幕開け、強大な権力で朝廷を支配した藤原不比等。しかし、その巨星が墜ちた時、歴史は新たな激動の時代へと突入します。本作は、不比等の死によって生じた巨大な権力の空白を埋めるべく、彼の遺志を継いだ四人の息子たちが、いかにして時代と対峙し、そして自らの運命に翻弄されていくかを描いた、壮大な歴史叙事詩です。
父が唯一恐れた男、皇親の筆頭である長屋王という巨大な壁。父の野望を継承するという重責。兄弟それぞれの思惑が絡み合い、奈良の都を舞台に繰り広げられるのは、血で血を洗う権謀術数の世界。馳星周さんならではの「歴史ノワール」とでも言うべき作風が、英雄譚ではない、人間の業や権力の魔性を生々しく描き出しています。
この記事では、まず物語の骨子を追い、その後で、なぜ彼らは破滅の道を突き進まなければならなかったのか、その悲劇の本質に迫る詳細な考察をお届けします。歴史の大きなうねりの中で、もがき、輝き、そして散っていった者たちの物語に、最後までお付き合いいただければ幸いです。
「四神の旗」のあらすじ
絶対的な権力者であった父、藤原不比等の死。その枕元に呼ばれた四人の息子たち――武智麻呂、房前、宇合、麻呂。彼らに遺されたのは、「そなたらはこの国の四神となれ」という、あまりにも重い遺言でした。それは父の果たせなかった野望の継承であり、彼らのその後の人生を決定づける呪いにも似た言葉となります。
しかし、父の遺志を継ぐべき四兄弟は、決して一枚岩ではありませんでした。父の冷徹さを最も色濃く受け継いだ長兄・武智麻呂。一族への忠誠と自らの道徳心との間で苦悩する次男・房前。武人として現実的な道を模索する三男・宇合。そして、風流人の仮面の下に野心を隠す末弟・麻呂。それぞれの思惑が交錯し、藤原氏の結束には早くも不協和音が響き始めます。
彼らの前に立ちはだかるのは、天武天皇の孫にして、時の左大臣、長屋王。皇統の守護者として、また類い稀な才覚を持つ為政者として、彼は藤原氏の台頭を断固として許しません。聖武天皇の生母(藤原氏出身)への称号を巡る「辛巳事件」を皮切りに、両者の対立は激化。法と伝統を重んじる長屋王の正論は、藤原四兄弟を苛立たせ、追い詰めていきます。
藤原氏が切り札としたのは、妹であり聖武天皇の妃である安宿媛を、前例のない「皇后」の座に就けることでした。これが実現すれば、藤原氏は天皇の外戚として盤石の地位を築くことができます。しかし、皇統の尊厳を揺るがすこの計画に、長屋王が賛同するはずもありません。対立がもはや回避不可能となった時、四兄弟は父の遺言を完遂するため、そして一族の未来のため、恐るべき陰謀へと手を染めていくのでした。
「四神の旗」の長文感想(ネタバレあり)
馳星周さんが描く歴史、それは常に血の匂いがします。本作「四神の旗」も例外ではなく、光り輝く平城京の甍(いらか)の下でうごめく、人間の欲望と業、そして権力闘争の凄まじさを、まさに「ノワール」という言葉がふさわしい筆致で描き切っています。これは単なる歴史物語ではありません。過去の亡霊に憑りつかれた男たちの、悲劇の記録なのです。
物語は、偉大すぎた父、藤原不比等の死から始まります。彼の存在そのものが、奈良時代の秩序でした。その死は、息子たちにとって父という庇護者を失うと同時に、巨大な遺産の継承者となることを意味しました。「四神となれ」という遺言は、彼らを鼓舞する祝福であると同時に、決して逃れることのできない呪いとして、四兄弟の肩に重くのしかかります。
この物語の巧みさは、まず四兄弟の描き分けにあります。彼らは「藤原氏」という一枚岩の集団ではありません。長兄の武智麻呂は、父の冷酷な野心、権力への渇望を最も純粋に受け継いだ人物です。彼にとって、長屋王の排除は一族の繁栄のための「必要悪」ですらなく、当然の権利であり、目的遂行のための冷徹な計算があるのみです。彼の存在が、藤原氏の暴走を牽引するエンジンとなります。
対照的に描かれるのが、次男の房前です。彼は一族の野望と、亡き元明天皇から受けた恩義、そして彼自身の良心との間で激しく引き裂かれます。この葛藤こそが、本作に人間的な深みを与えていると言えるでしょう。彼は決して聖人君子ではありません。自己中心的な面も描かれますが、それでもなお、一線を越えることへのためらいを持ち続けます。この房前の苦悩が、物語の結末の大きな伏線となっているのです。
三男の宇合は、現実主義の武人です。遣唐使としての経験から、よりプラグマティックな視点を持ち、兄たちの陰謀においては実行部隊として動きます。彼にとって重要なのは、観念的な思想よりも、目の前の現実をいかに動かすかという点にあります。彼の行動力がなければ、藤原氏の計画は絵に描いた餅で終わったかもしれません。
そして末弟の麻呂。芸術を愛する風流人という表の顔とは裏腹に、彼もまた兄たちと同じく、静かな野心を胸に秘めています。彼の存在は、文化や雅(みやび)といったものが、いかに政治的な権力と隣接しているかを示唆しているように感じられます。優雅な仮面の下で、彼もまた陰謀の重要な担い手となっていくのです。
彼ら四兄弟の前に、巨大な山として立ちはだかるのが長屋王です。本作における彼の造形は、単なる「主人公たちの敵役」にとどまりません。彼は天武天皇の血を引く皇親としての誇りと、律令国家の守護者としての強い自負心を持った、極めて有能な政治家として描かれます。彼の正しさは、一点の曇りもありません。
藤原氏が自分たちの一族の都合で国家のルールを捻じ曲げようとする時、長屋王は常に「法」と「伝統」を盾に、敢然と立ちはだかります。聖武天皇が母・宮子に「大夫人」という異例の称号を贈ろうとした際に、長屋王が「律令に定めなし」と一蹴する場面は、彼の原則主義を象徴する名場面です。この行動は、藤原氏にとって、そして天皇にとってさえ、公衆の面前で受けた屈辱でした。
しかし、このノワール的な世界では、その「正しさ」こそが命取りとなります。長屋王は、法というシステムを信じすぎていました。彼は、藤原兄弟がそのシステムの埒外で、非合法な手段に訴えてくる危険性を過小評価していたのかもしれません。彼の高潔さは、敵の行動を予測しにくくさせ、同時に自身の行動を予測可能なものにしてしまいました。結果として、彼は自らの正しさゆえに、陰謀の格好の標的となってしまうのです。
藤原四兄弟の野望の核心、そして長屋王との対立の頂点に位置するのが、彼らの妹・安宿媛(のちの光明皇后)の立后問題でした。皇族以外の女性が皇后になることは、それまでの常識を覆す、まさに国家的な一大事です。これが成し遂げられれば、藤原氏は未来永劫、天皇家の外戚として権力をほしいままにできる。父・不比等が夢見た究極の目標でした。
物語の中で、女性たちもまた重要な役割を担います。安宿媛は、兄たちの野望の象徴であり、最も重要な駒です。彼女がただ利用されただけの哀れな女性だったのか、それとも自らも権力を望み、兄たちの計画に積極的に加担したのか。その解釈は分かれるかもしれませんが、彼女が権力闘争の渦中でその純粋さを失っていく様は、悲劇的ですらあります。
また、彼女の母であり、不比等の後妻であった橘三千代の存在感も圧倒的です。宮中の力学を知り尽くした彼女は、それ自体が一個の勢力であり、その立ち居振る舞い一つが政治を動かします。彼女なくして、藤原氏の野望は成し遂げられなかったでしょう。この老獪な女性の姿は、本作屈指の印象を残します。
藤原氏の計画は、安宿媛が聖武天皇との間に皇子・基王を授かったことで、完成したかに見えました。しかし、その希望の光は、基王の夭折という形で無情にも断ち切られます。この喪失感と絶望が、藤原兄弟を後戻りできない道へと駆り立てるのです。自分たちの世継ぎを失い、一方で長屋王には息子たちがいる。この現実は、彼らにとって座視できない脅威となり、長屋王の排除を絶対的なものへと変えていきました。
そして、ついに「長屋王の変」の火蓋が切られます。漆部君足と中臣宮処東人という下級役人による密告。その内容は「長屋王が左道(あやしげな術)をもって国家を傾けようとしている」という、極めて曖昧で、だからこそ反証が困難なものでした。これは、法を重んじる長屋王を、法の土俵に上げることなく断罪するための、周到に仕組まれた罠でした。
この陰謀の実行に際して、兄弟間の亀裂は決定的となります。首謀者である武智麻呂、実行部隊を率いる宇合、そしてこれに同意する麻呂。しかし、次男の房前だけは、この非道な計画に加わることを拒みます。この房前の決断が、藤原氏全体の運命を後々まで左右することになるとは、この時誰も予想していませんでした。
長屋王邸を軍勢が包囲し、問答無用の糾弾が始まる。もはや逃れられないことを悟った長屋王は、見せしめの裁判という屈辱を拒み、妻の吉備内親王と息子たちと共に自害する道を選びます。その最期は壮絶であり、読む者の胸に深く突き刺さります。こうして、藤原氏の最大の政敵は、血塗られた形で歴史の舞台から姿を消しました。政治的には、これは「完全犯罪」の成功に見えました。
しかし、ノワールという物語の定石通り、完璧な犯罪など存在しません。法による裁きは免れても、因果応報の摂理からは誰も逃れられないのです。長屋王の死後、藤原四兄弟は権力の絶頂を極めます。妹は光明皇后となり、朝廷の要職は彼らが独占。父の遺言は、ついに達成されたかに見えました。だが、その栄華はあまりにも短命でした。
天平7年、大陸から持ち込まれた天然痘が、日本全土を襲います。疫病は首都・平城京で猛威をふるい、人々はこれを単なる病ではなく、非業の死を遂げた長屋王の「祟り」だと恐れおののきました。そして、その「呪い」は、ついに標的を捉えます。天平9年、わずか数ヶ月の間に、武智麻呂、房前、宇合、麻呂の四兄弟は、全員が病に倒れ、この世を去るのです。
「四神」となるはずだった者たちが、自らが生み出した亡霊の怨念と信じられた力によって滅びていく。この皮肉に満ちた結末は、圧巻の一言です。しかし、物語はここで終わりません。長屋王の祟りを恐れた聖武天皇が、その鎮魂のために東大寺と大仏の建立へと向かっていくことが示唆されます。一つの政治的暗殺が、日本史上最大級の国家仏教プロジェクトの引き金となった。この歴史のダイナミズムこそ、本作の醍醐味でしょう。
そして、物語は最後の、そして最大の皮肉を用意しています。四兄弟は死に、彼らの血筋である南家、式家、京家はやがて歴史の中で衰退していきます。最終的に藤原氏の栄華を担ったのは、陰謀への直接的な加担を拒んだ房前の血筋、北家でした。何世紀にもわたり宮廷を支配する摂関家は、この房前から始まるのです。父の野望は、最も父に似ていなかった息子の血筋によって、皮肉な形で成就されたのでした。馳星周さんは、この歴史の複雑怪奇な綾を、見事に描き切ってくれたのです。
まとめ
馳星周さんの「四神の旗」は、奈良時代前期を舞台に、藤原不比等の死後、その後継者である四兄弟が、最大の政敵・長屋王と繰り広げる壮絶な権力闘争を描いた傑作でした。歴史の教科書では数行で語られる「長屋王の変」の裏側で、いかに人間的な欲望や葛藤、そして陰謀が渦巻いていたのかを、生々しく体感させてくれます。
単に史実をなぞるのではなく、馳星周さんならではのノワール的な解釈が加わることで、登場人物一人ひとりの業の深さが際立ちます。父の呪縛に囚われた四兄弟、正しさゆえに滅びる長屋王、そして権力に翻弄される女性たち。彼らの生き様は、現代を生きる私たちの心にも、強く響くものがあります。
権力を手にした者が、その成功の果てに破滅していく皮肉な運命。そして、陰謀に加担しなかった者の血筋が最終的に繁栄するという、歴史の大きな皮肉。本作は、人間の野望の儚さと、思い通りにはいかない歴史の非情さを見事に描き出しています。
重厚な人間ドラマが好きな方、そして歴史の「もしも」の裏側を覗いてみたい方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。読後、奈良時代の風景が、以前とはまったく違って見えることになるでしょう。