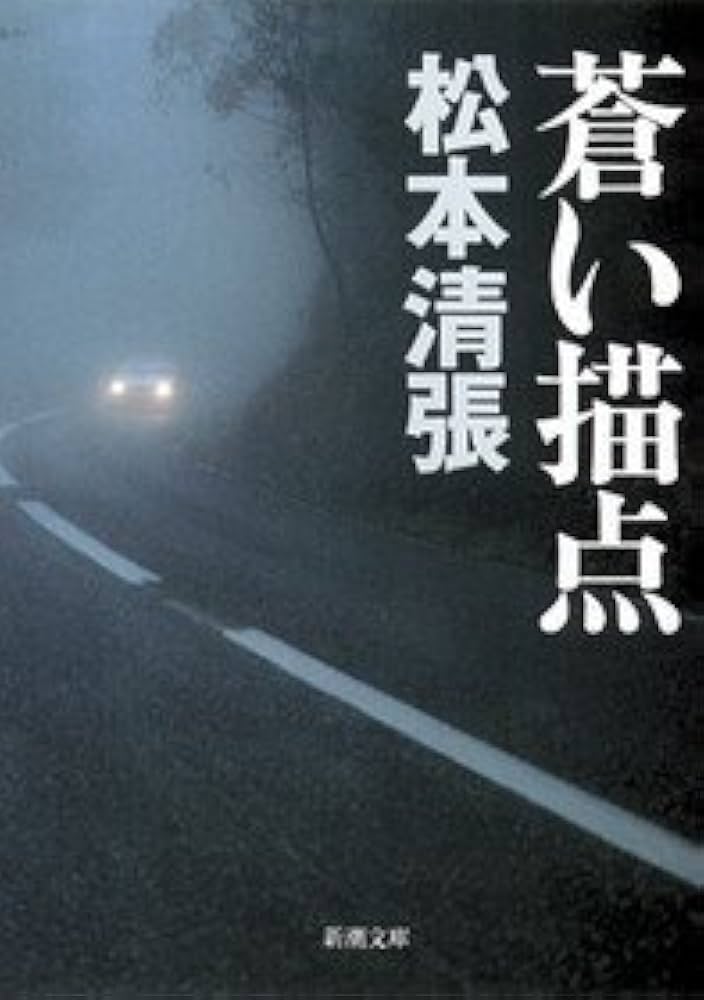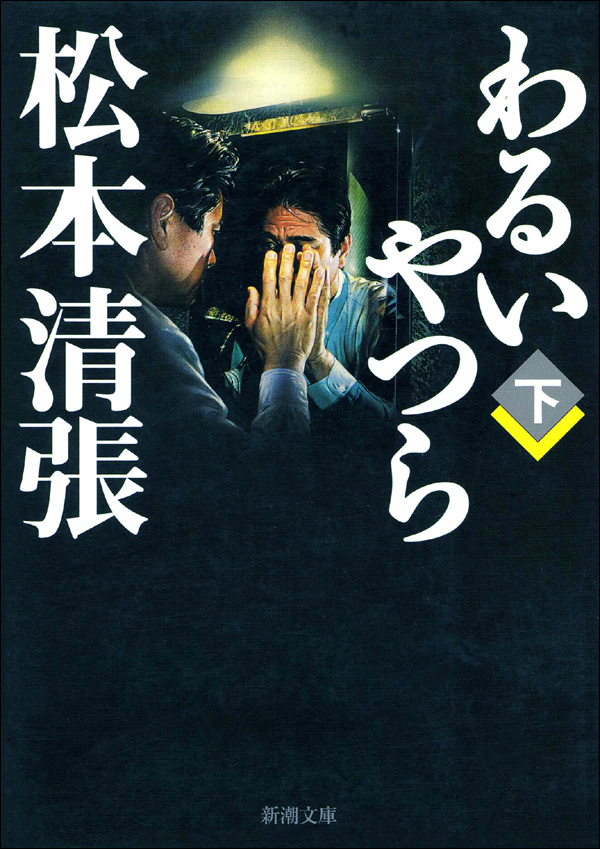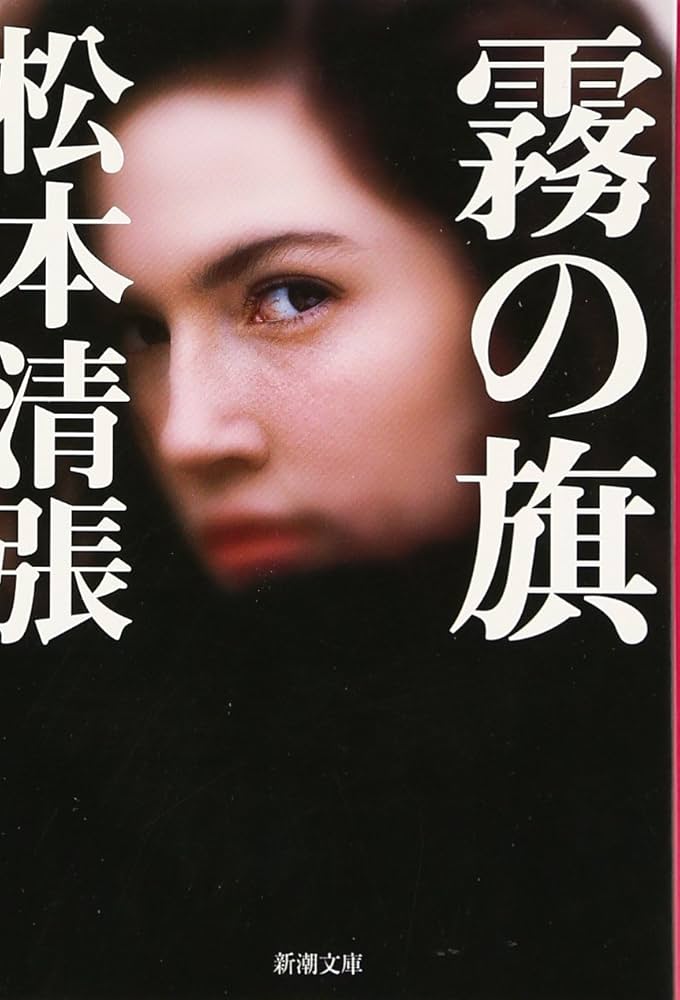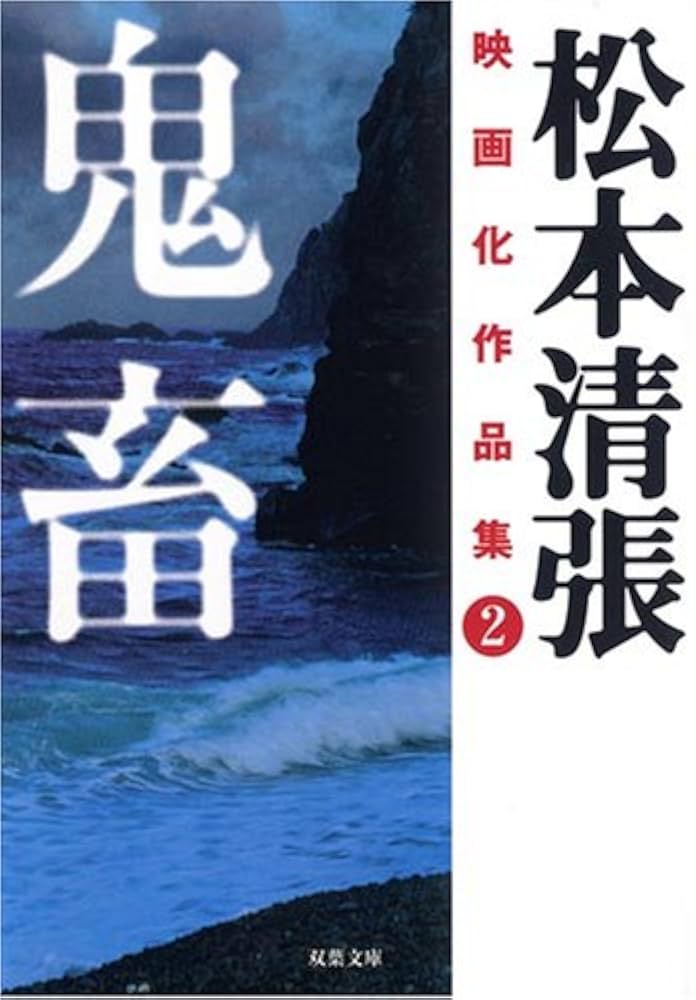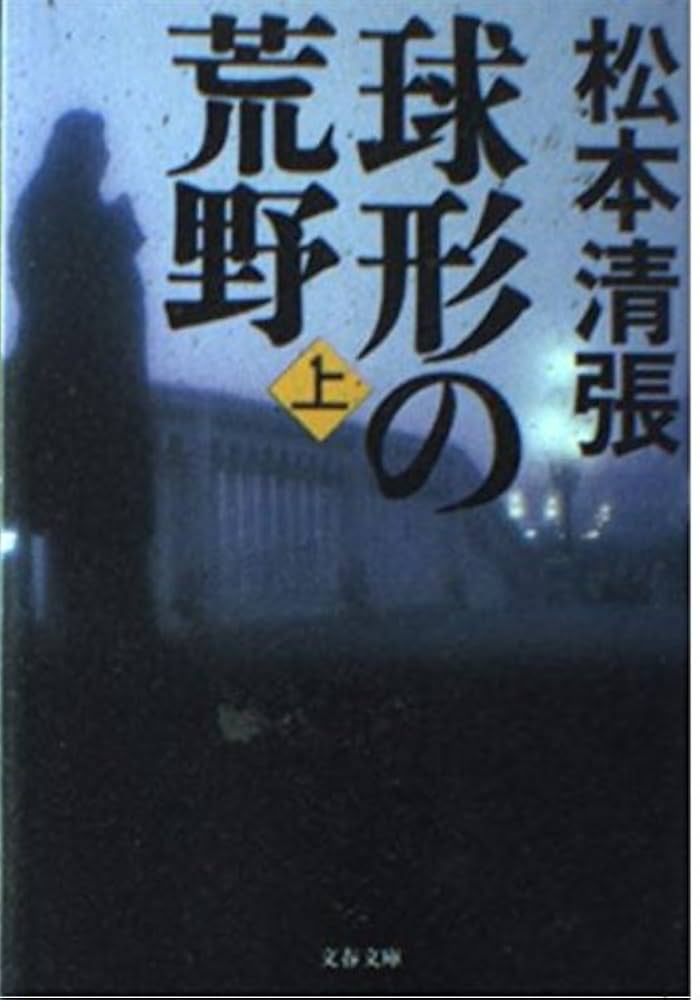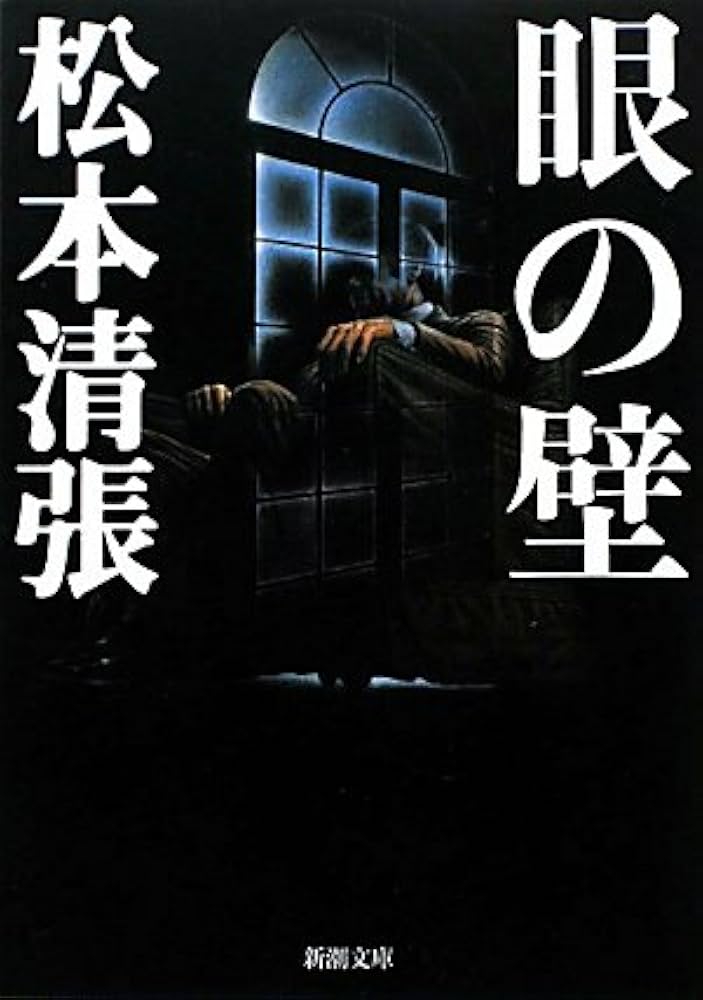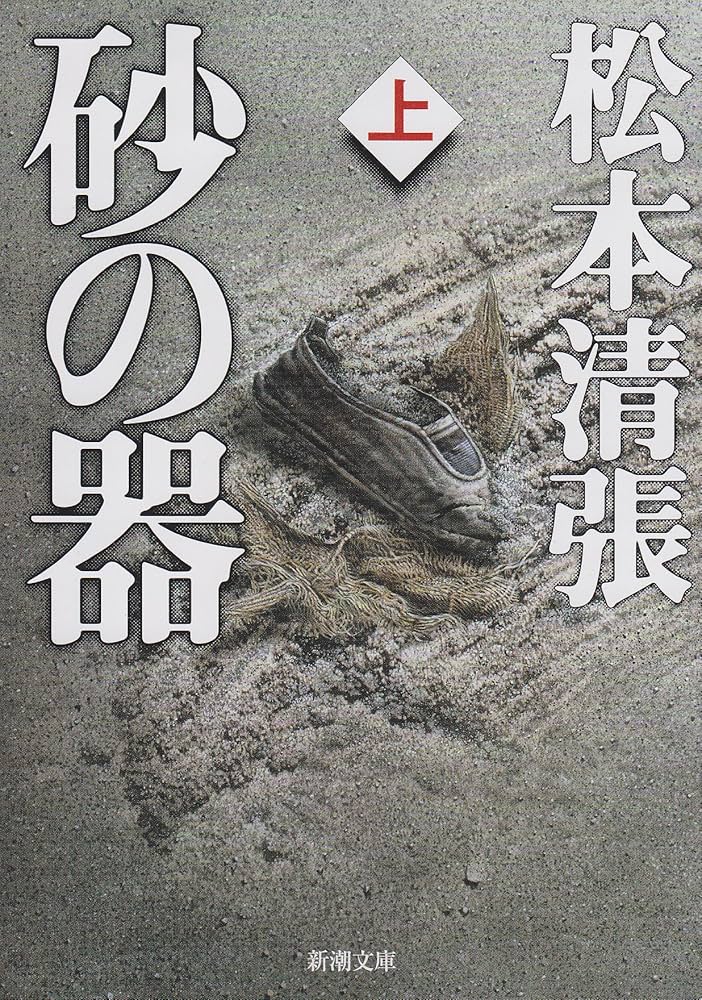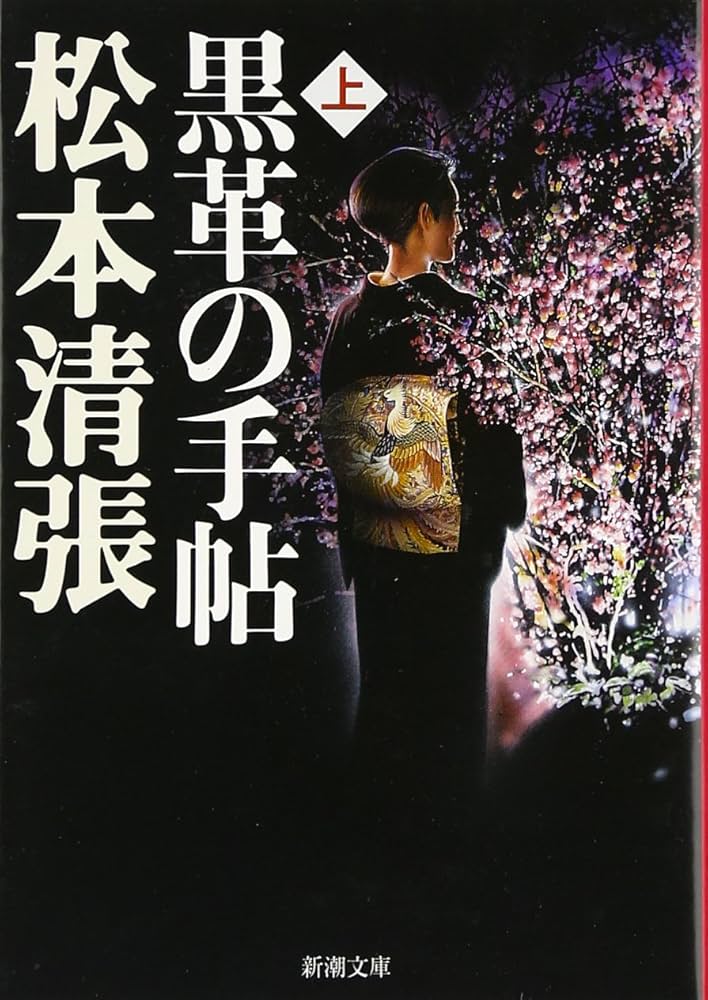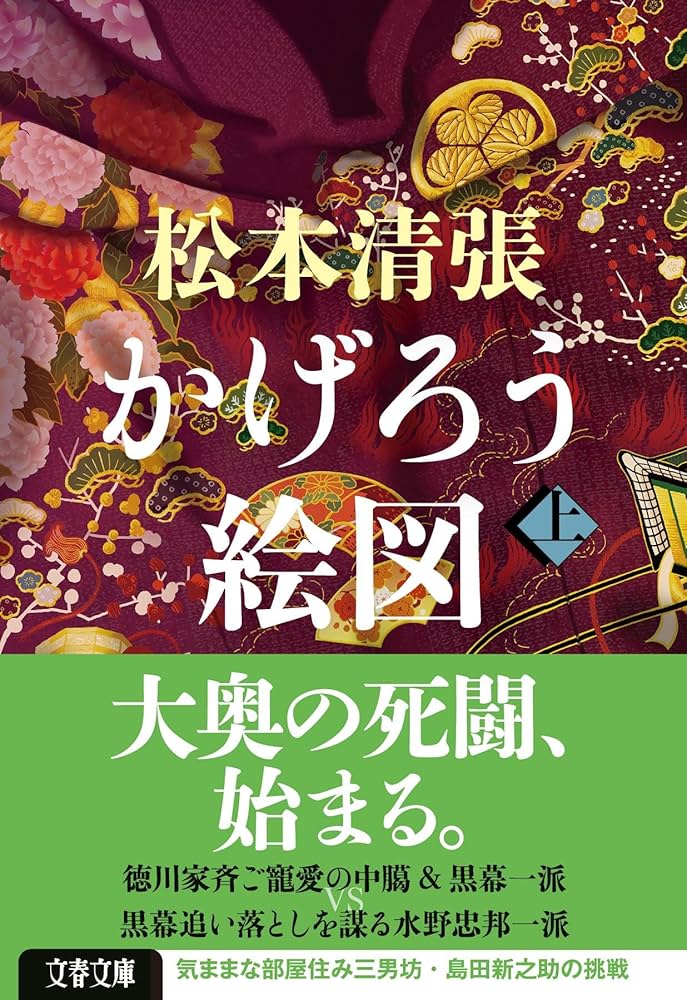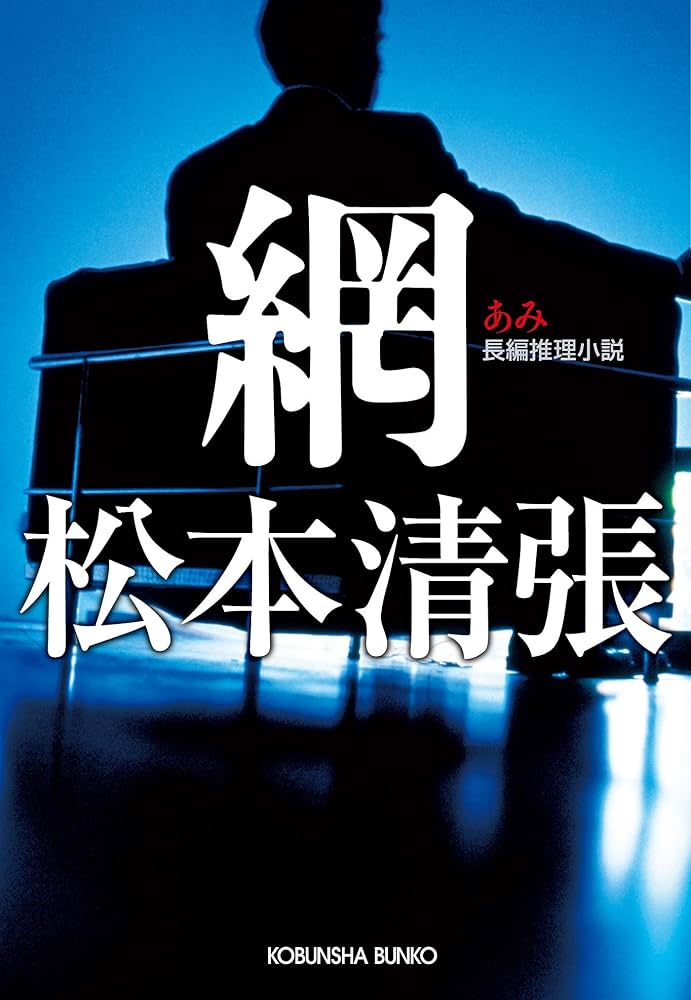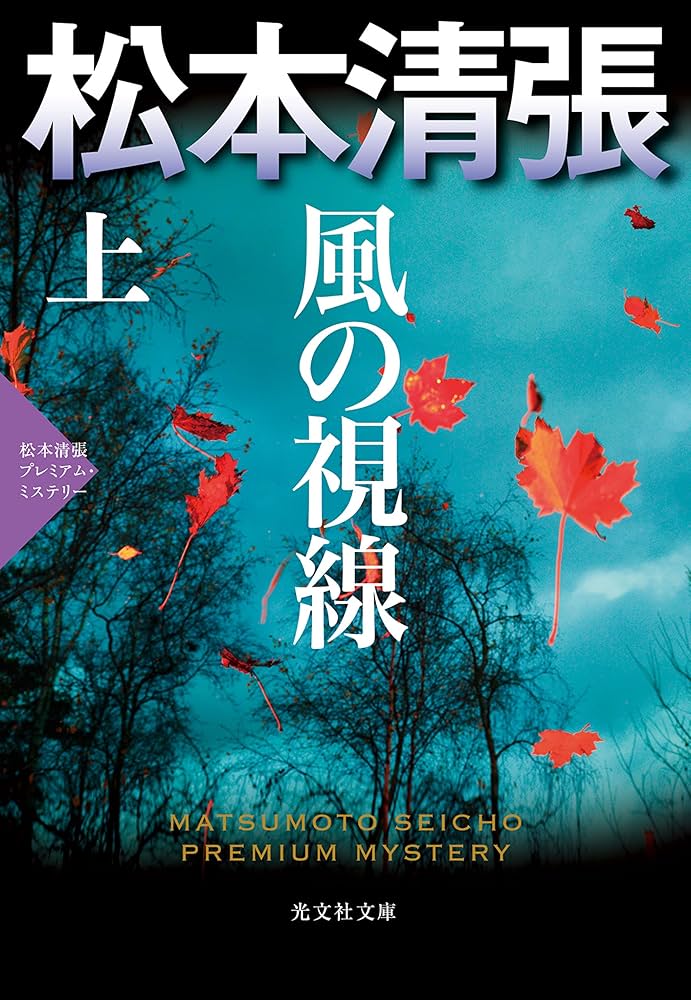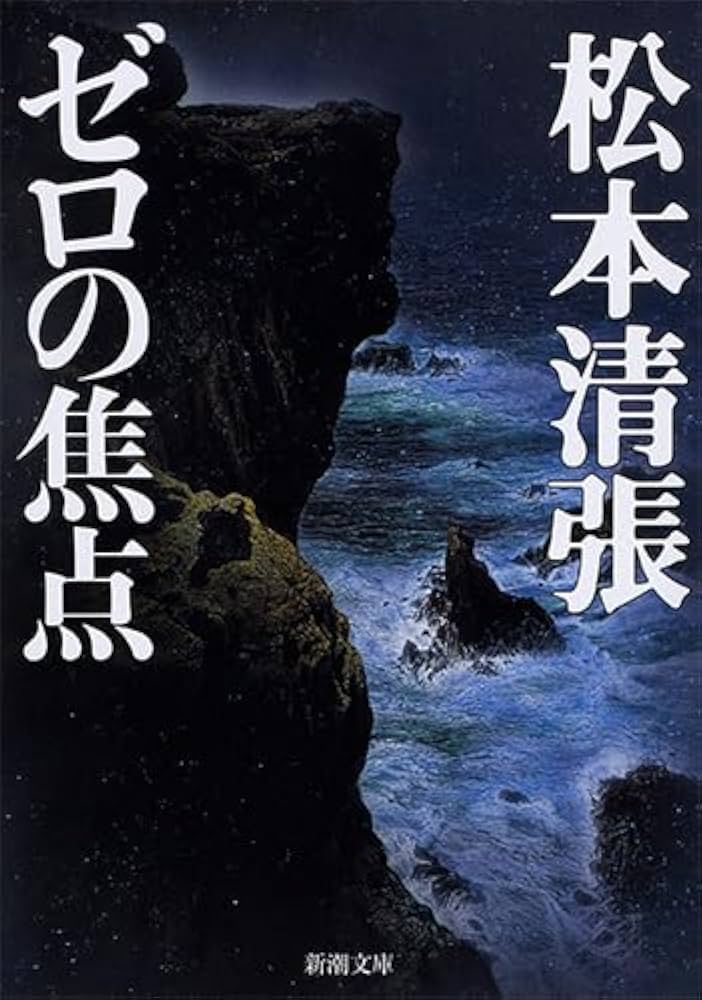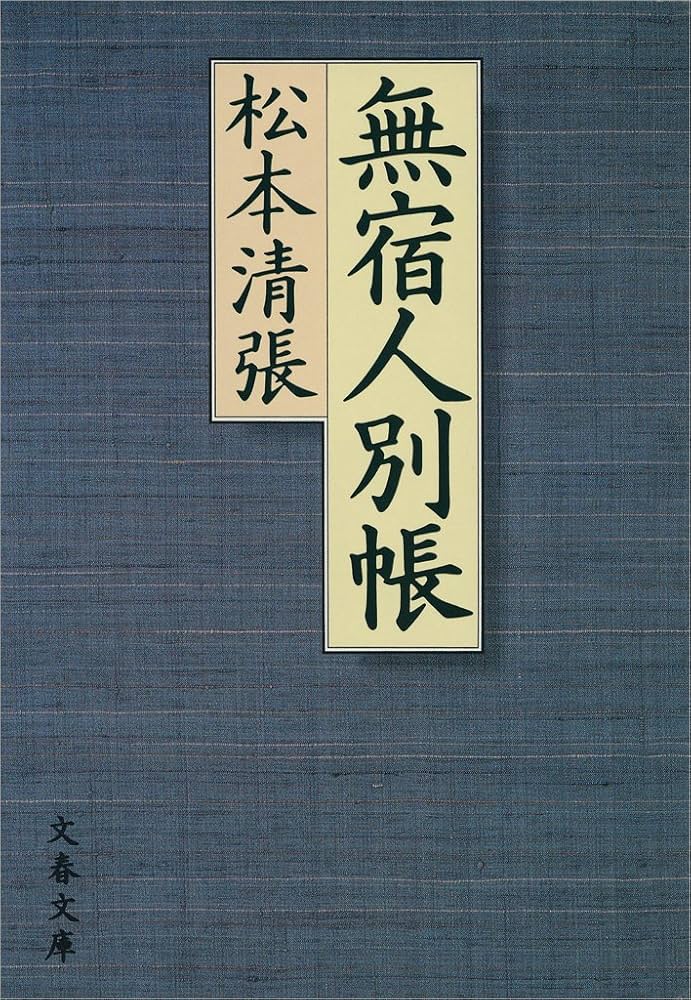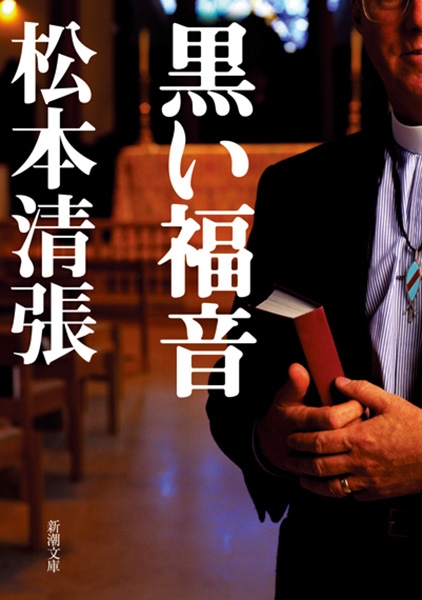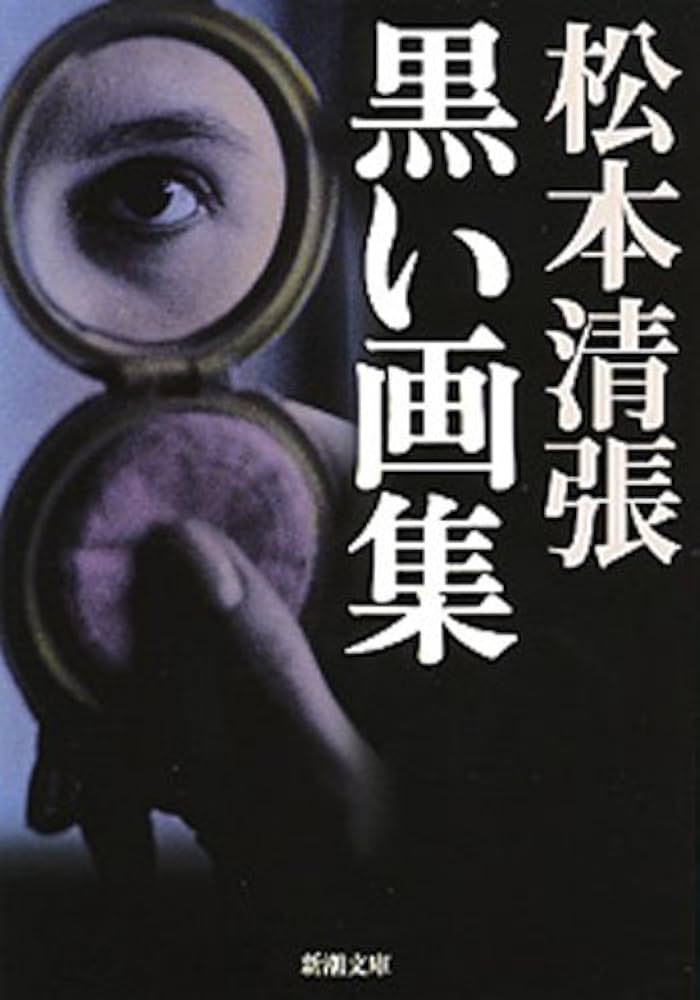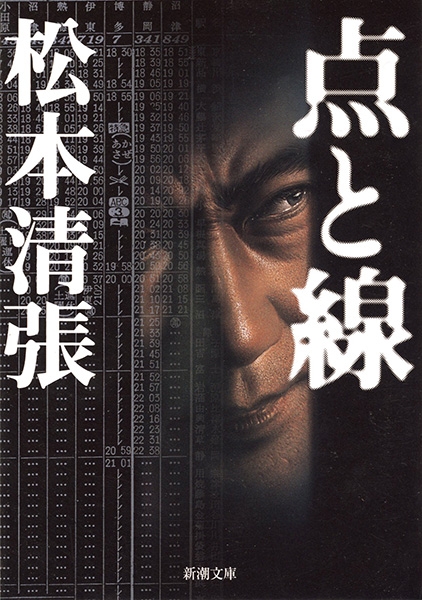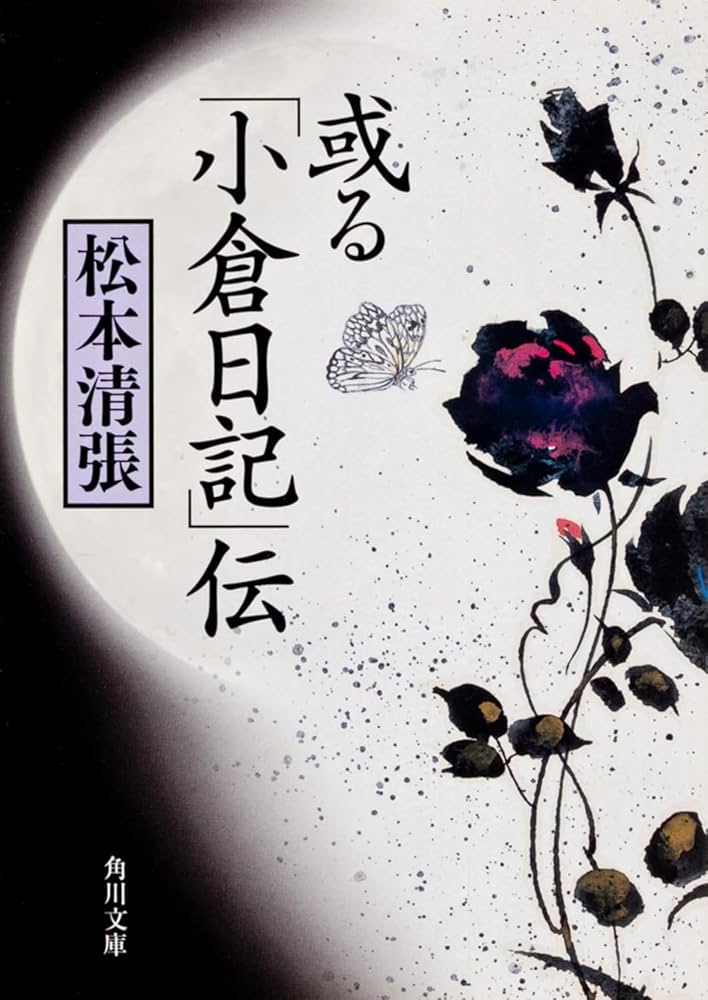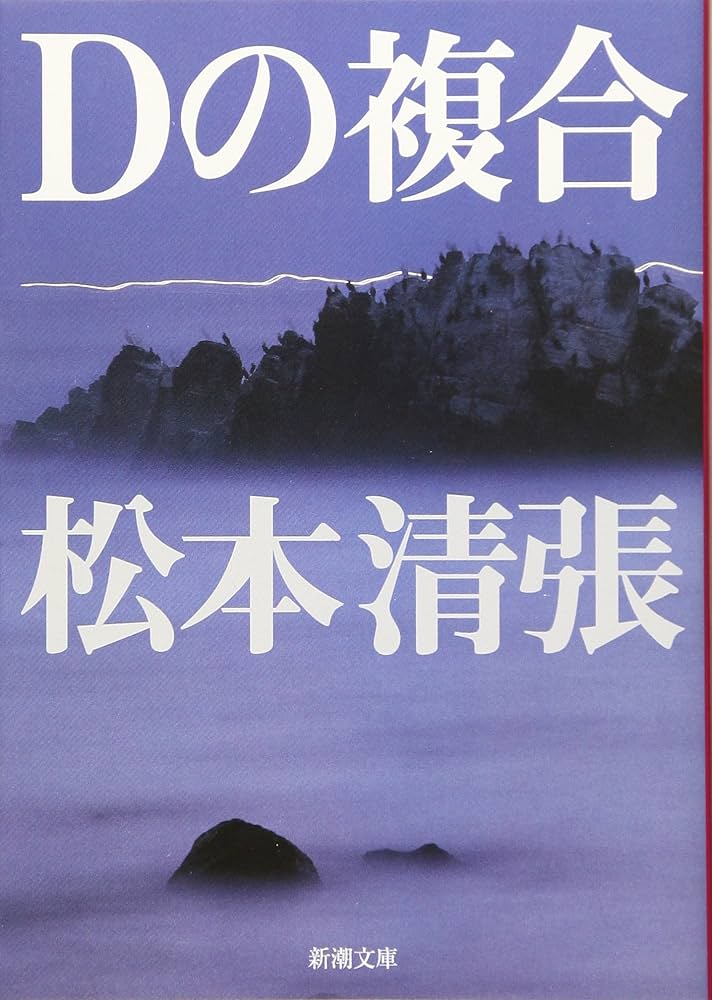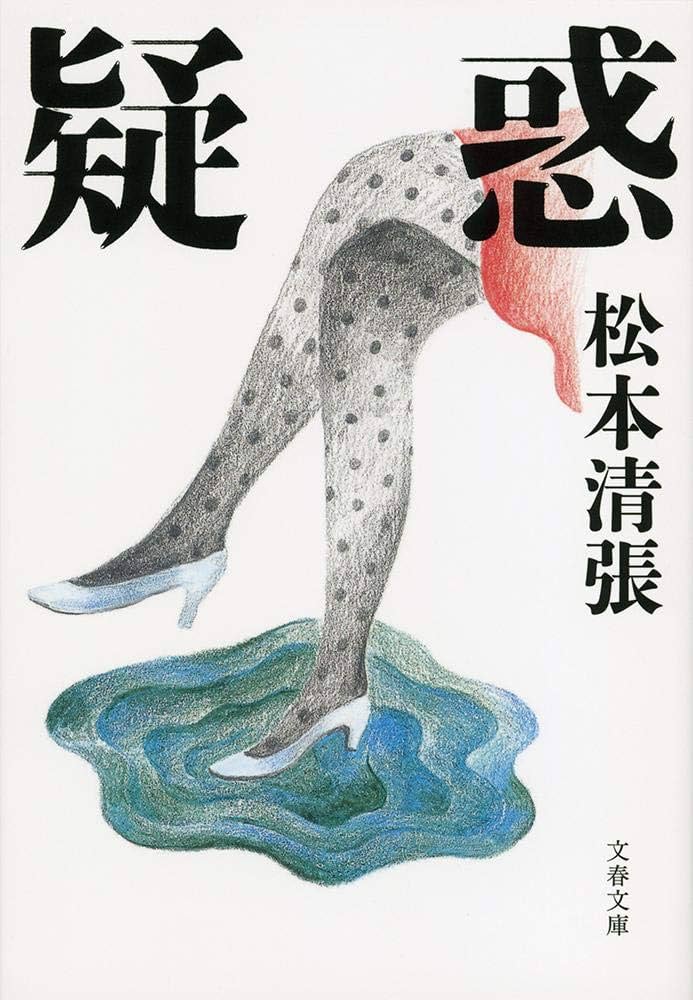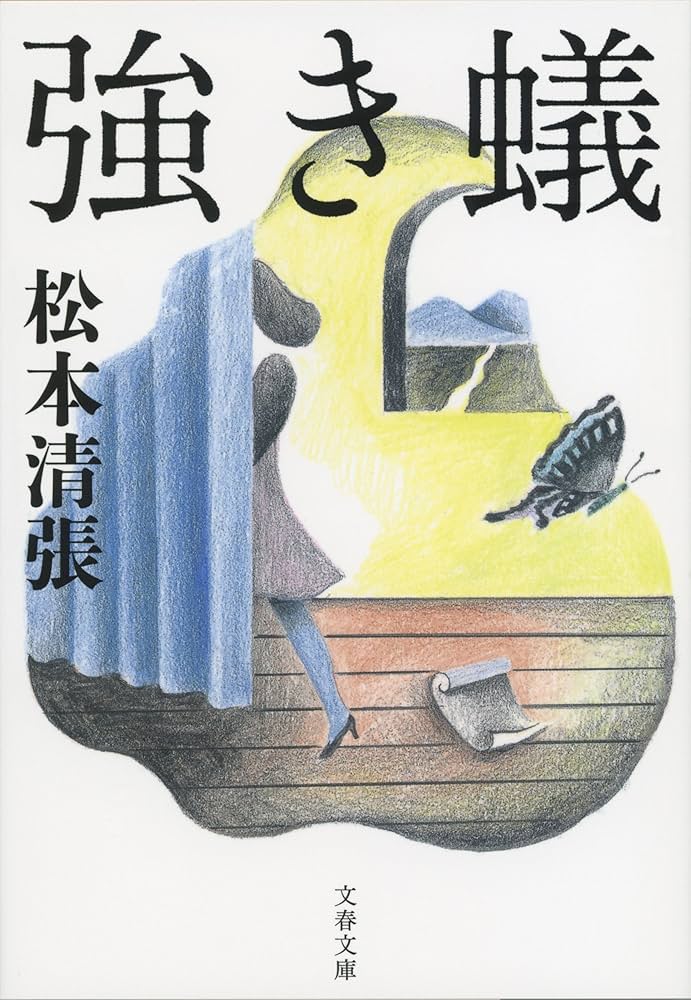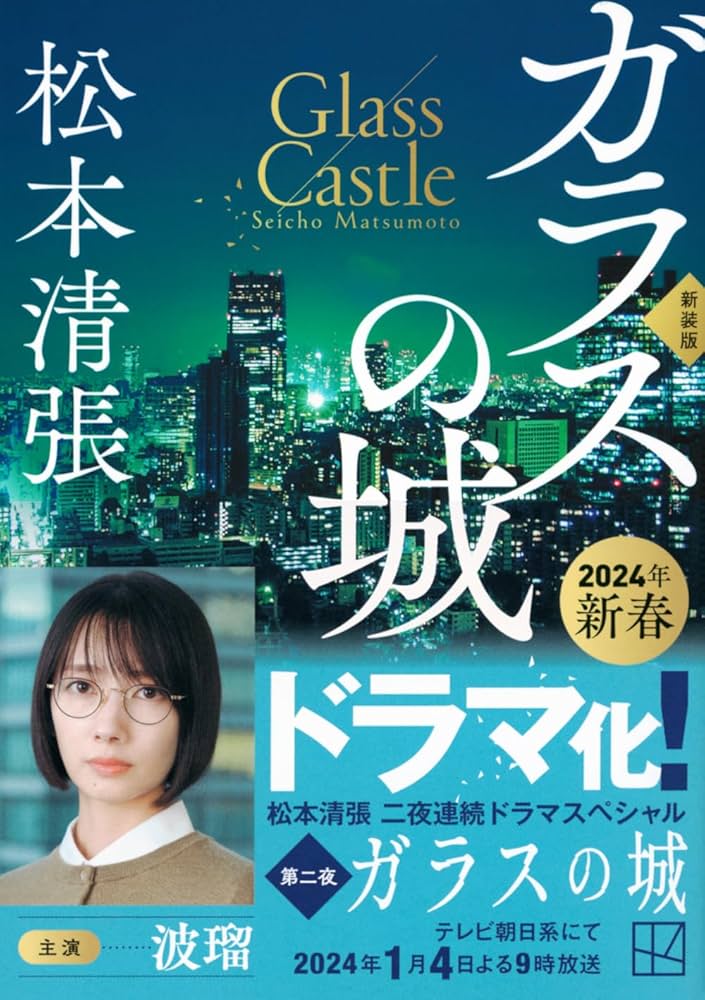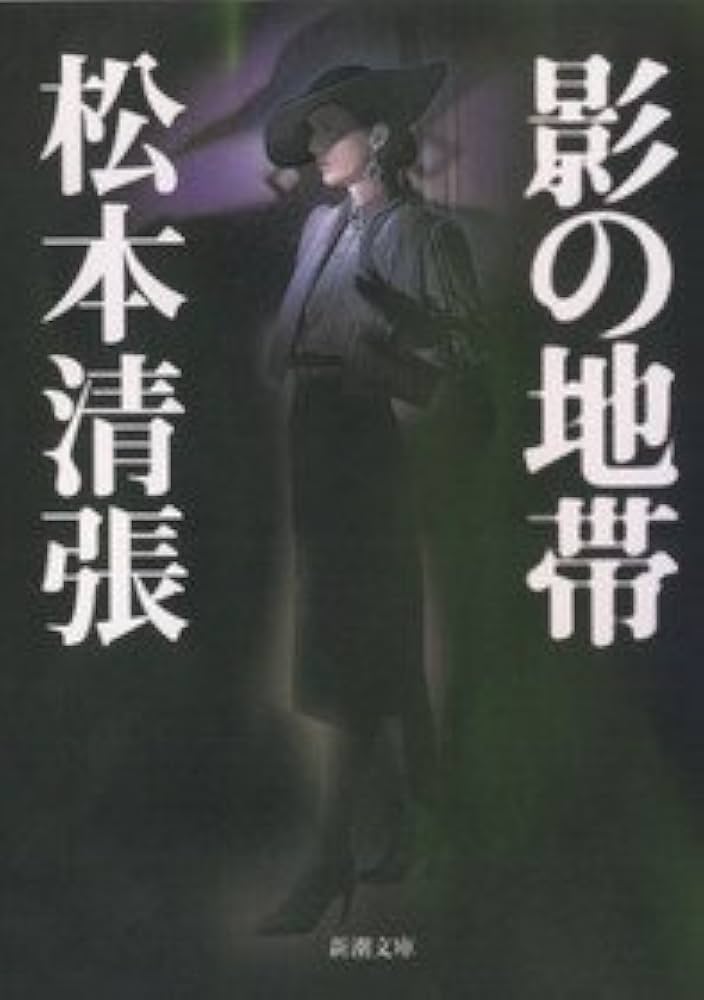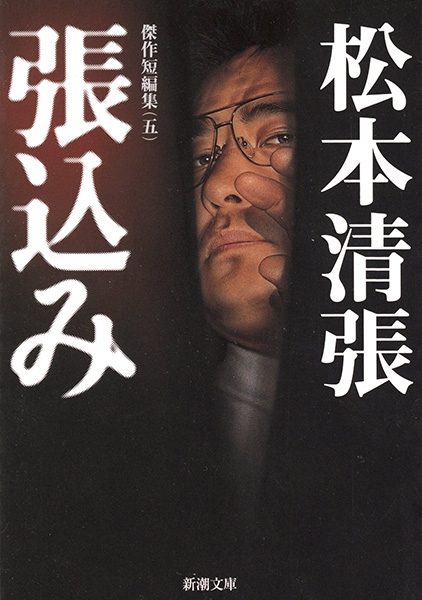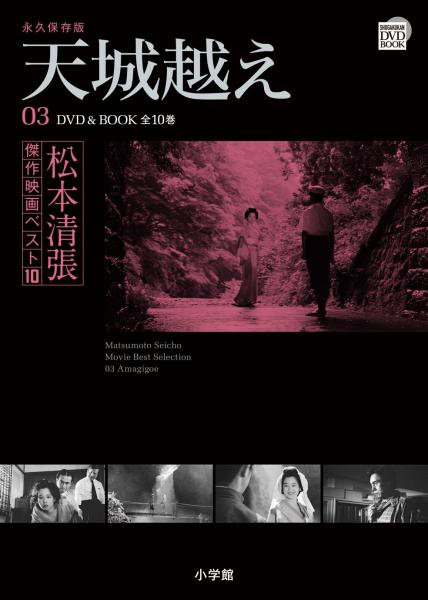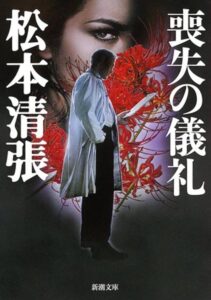 小説「喪失の儀礼」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「喪失の儀礼」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
松本清張作品の中でも、その特異な犯行手口と、胸を抉るような動機で知られる本作。物語は、ある医師の奇妙な死から始まります。それは単なる殺人ではなく、明確な意図を持った「儀式」でした。この異常な事件を皮切りに、物語は警察組織の壁、人間の思い込み、そして家族という名の閉ざされた空間の愛憎を描き出していきます。
この記事では、まず物語の導入部分となるあらすじを、核心のネタバレを避けつつご紹介します。事件の不気味な幕開けと、捜査が迷宮入りしていく様を追体験してみてください。なぜ犯人は、これほどまでに残酷で手の込んだ方法を選んだのか。その謎が、読者を物語の奥深くへと引きずり込んでいくのです。
そして後半では、物語の結末を含む完全なネタバレとともに、長文の感想を綴っています。全ての謎が解け明かされた時に現れる、犯人たちの悲痛な叫びとは何だったのか。「喪失の儀礼」というタイトルの本当の意味を、私なりの視点で深く掘り下げていきます。社会派ミステリーの巨匠が投げかける、重い問いを一緒に受け止めていただけたら幸いです。
「喪失の儀礼」のあらすじ
名古屋のホテルで、東京の大学病院に勤める医師・住田友吉の他殺体が発見されます。第一発見者は、前日にひょんなことから住田と接触していた名古屋中署のベテラン刑事、大塚でした。遺体はバスタブで手首の動脈を精密に切られ、意識のあるまま全身の血液を抜かれるという、極めて残忍で医学的知識を要する手口で殺害されていました。これは、犯人による強い憎悪と、何らかの儀式的な意味合いを感じさせるものでした。
捜査線上に浮かんだのは、製薬会社の営業係長・小池為吉。医師たちへの接待を行っており、医療業界の癒着が背景にあるのではと疑われます。しかし、小池には鉄壁のアリバイがありました。一方、被害者の住田は、業者から接待を受ける傍らで、業界の腐敗を告発する記事を匿名で寄稿していた二面性も判明します。住田の怨恨関係は複雑で、捜査は難航を極めていきました。
そんな中、事件から二ヶ月後、今度は東京の深大寺近くで、開業医・香原順治郎が全く同じ手口で殺害される第二の事件が発生します。二人の被害者の接点は、共に名古屋の医学会に出席していたことだけ。広域連続殺人事件となり、名古屋県警と警視庁の合同捜査が始まりますが、管轄の違いが捜査の壁となります。
捜査が進むうち、二人の被害者と俳句の会で繋がりがあった萩原和枝という老婦人と、その家族に捜査の光が当たります。しかし、彼らにもまた、犯行は不可能と思える完璧なアリバイが存在していました。犯人は一体誰なのか、そしてこの陰惨な「儀礼」に込められた目的とは何なのでしょうか。謎は深まるばかりです。
「喪失の儀礼」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の核心に触れるネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。この物語が突きつける真実の重みを、共に感じていきたいと思います。
まず、この物語を貫くのは、その異常なまでの犯行方法です。被害者を温かい湯に浸からせ、意識をはっきりと保たせたまま、自らの血がすべて失われていくのを長時間認識させる。これは単なる殺意の表明ではありません。犯人が被害者に与えたかったのは、死そのものではなく、「死に至るまでの時間」だったのです。この時間に、犯人は被害者に何かを思い出してほしかった。何かを悔い、苦しんでほしかった。この執念深い「儀礼」こそが、物語全体の根幹をなすテーマであり、読者に強烈な印象を与えます。
この儀式的な殺人を捜査する大塚刑事の視点は、私たち読者の視点と重なります。彼はベテラン刑事として数々の事件を経験していますが、これほどまでに冷酷で計画的な犯行には戦慄を覚えます。偶然にも事件直前に被害者と接触していたという事実が、彼をこの事件に個人的に引き込んでいくのです。彼の粘り強い捜査があったからこそ、事件の深層に光が当たることになります。
松本清張作品の魅力の一つに、社会の構造的な問題を鋭く描く点があります。本作でも序盤、製薬会社と医師の癒着という、おなじみのテーマが描かれます。営業係長の小池は、まさにその象徴的な存在です。読者は当初、この医療界の闇が事件の動機ではないかと推測します。しかし、清張はそれを巧みなミスディレクションとして配置しているのです。
社会の大きな不正義もさることながら、もっと個人的で、もっと根源的な人間の情念こそが、この物語を動かす原動力なのだと、物語は少しずつ明らかにしていきます。住田医師が持っていた告発者としての一面もまた、捜査を攪乱する要素として機能します。彼が単純な悪人ではないことが、動機の特定をより困難にしているのです。
第二の殺人が発生し、事件が連続殺人へと発展する展開は、物語のスケールを一層大きなものにします。名古屋と東京、二つの場所で全く同じ手口が繰り返されることで、犯人の揺るぎない決意が示されます。この二ヶ月という犯行間隔が、また不気味です。衝動的な犯行ではなく、警察の捜査が手詰まりになるのを冷静に待ち、計画を遂行する知能犯であることを物語っています。
そしてここでも、松本清張作品の真骨頂である「組織の壁」が立ちはだかります。名古屋県警と警視庁、管轄の違う警察同士の連携はスムーズに進みません。縄張り意識や情報共有の遅れが、神出鬼没の犯人に対して捜査を後手に回らせるのです。この社会システムの欠陥が、結果的に犯人に有利に働いてしまう皮肉な構造が、リアリティをもって描かれています。
捜査が混迷を極める中で登場する「赤い髪の女」の目撃情報。これは、読者の注意を惹きつける非常に巧みな幻影です。派手でミステリアスな存在は、いかにも怪しく見えます。しかし、これこそが犯人たちの仕掛けた罠でした。人は、異常なもの、目立つものに気を取られ、すぐそばにある平凡な日常に潜む恐怖を見過ごしてしまう。その心理を巧みに突いたトリックは見事というほかありません。
そして、物語の焦点は萩原家へと絞られていきます。家長の和枝、車椅子の息子・雄一、そしてその介護をする嫁の美奈子。一見、どこにでもあるような家族の風景。しかし、この家族の内部には、常人には計り知れない秘密が渦巻いていました。特に、和枝と美奈子の「嫁姑の不仲」は、周囲の誰もが知る事実でした。
この「不仲」こそが、本作で最も恐ろしいアリバイトリックの核心でした。仲の悪い者同士が互いのアリバイを証言する。普通なら、それは信憑性が低いと判断されるでしょう。しかし、彼女たちの憎しみ合いがあまりに有名だったために、かえって「あの二人が庇い合うはずがない」という強力な思い込みを捜査官に植え付けたのです。人間の先入観や固定観念を逆手に取った、まさに悪魔的な知略と言えるでしょう。
やがて大塚刑事の執念の捜査が、一つの綻びを見つけ出します。雄一が使う車椅子が、癒着の象徴であった小池の勤務する製薬会社のものだったことです。これまで無関係に見えた点と点が、ここで初めて線として繋がります。この瞬間から、事件は一気に真相へ向かって動き出すのです。この小さな物証から巨大な謎を解き明かしていく過程は、ミステリーの醍醐味に満ちています。
そして、全てのパズルのピースがはまる瞬間が訪れます。二年前、萩原家のもう一人の息子・修二が、バイク事故で瀕死の重傷を負いました。最初に運び込まれた病院の院長・香原は、愛人との情事に耽り、診療を拒否。次に回された大学病院では、住田医師の怠慢によって、修二は命を落としたのです。これが、あの残忍な儀式の動機でした。医療従事者による無責任な「人殺し」への、遺族による復讐。
動機が明らかになった時、読者は戦慄すると同時に、犯人たちに言いようのない感情を抱くことになります。彼らはただ嘆き悲しむだけではありませんでした。香原の不倫相手だった看護師に接触するなど、自らの手で息子の死の真相を突き止めていたのです。その執念は、法や社会が与えてくれなかった正義を、自らの手で執行するという決意へと繋がっていきました。
さらに、物語はもう一つの衝撃的な事実を明かします。現在の嫁である美奈子は、かつて修二の恋人であり、彼の子を宿していました。診療を拒否されたあの日、香原に突き飛ばされた衝撃で流産していたのです。彼女が雄一と結婚したのは、愛ではなく、復讐という共通の目的を遂行するため。萩原家という城塞に、共犯者として入り込むための偽装結婚でした。この事実が、萩原家の悲劇をより一層深く、救いのないものにしています。
クライマックス、萩原家の秘密に気づき、美奈子を脅迫しようとした小池が殺害されます。ここで車椅子の雄一が直接手を下したことが明らかになり、彼もまた計画の完全な当事者であったことが示されます。そして、全てを冷徹に操っていた首謀者が、母親の和枝であったことが確定するのです。彼女は子供たちを逃がし、一人で刑事たちと対峙します。
大塚刑事は、法の名の下に自首を勧め、罪を償うよう説得します。しかし、和枝から返ってきたのは、法や倫理を超越した魂の慟哭でした。「なぜ、わたしたちが反省しなければならないのですか」。彼女は叫びます。殺した二人の医師は、自分たちが死に追いやった萩原修二という青年のことを、完全に「忘れていた」からだと。
この「忘却」こそが、萩原家にとっては耐えられない侮辱であり、第二の殺人でした。自分たちの犯した罪を、日常の些細な出来事として記憶にすら留めていなかった加害者たち。その無神経さ、死者への礼節を欠いた態度こそが、彼ら自身の血塗られた「儀礼」を必要とさせたのです。忘れられた息子の苦しみを、加害者の肉体に、そして記憶に永遠に刻み込む。それこそが「喪失の儀礼」の真の意味でした。
物語は犯人を特定しながらも、決して単純な解決では終わりません。萩原家の行為は紛れもない凶悪犯罪です。しかし、その根底にある悲痛な叫びは、医療制度、法制度、そして社会そのものに見捨てられた者の最後の訴えでした。松本清張は、社会の無関心やシステムの不備が、いかにして人間を怪物に変えてしまうのかという、救いのない真実を読者に突きつけます。この結末は、法による秩序の回復というカタルシスではなく、道徳的な意味での「迷宮入り」という、重く、忘れがたい余韻を残すのです。
まとめ
松本清張の「喪失の儀礼」は、単なる復讐譚に留まらない、人間の尊厳を問う物語です。残酷な儀式殺人の裏には、加害者によって「忘れられた」被害者の無念がありました。その忘却こそが、遺族にとっては何よりも耐え難い苦痛だったのです。
この記事では、事件のあらましから始まり、物語の結末に至るまでのネタバレを含む詳細な感想を綴ってきました。犯人たちが作り上げた巧妙なアリバイトリック、そしてその根底にあった深い悲しみと怒り。それらがどのように絡み合い、悲劇的な結末へと向かっていったのかを追いました。
社会のシステムからこぼれ落ち、法による救済も得られなかった家族が、自らの手で歪んだ正義を執行するに至る過程は、読む者の心を強く揺さぶります。勧善懲悪では決して割り切れない、人間の業の深さを描いた傑作と言えるでしょう。
あなたはこの物語の結末を、どう受け止めましたか。「喪失の儀礼」というタイトルが持つ本当の意味を、ぜひ本を手に取って感じてみてください。きっと、忘れられない読書体験になるはずです。