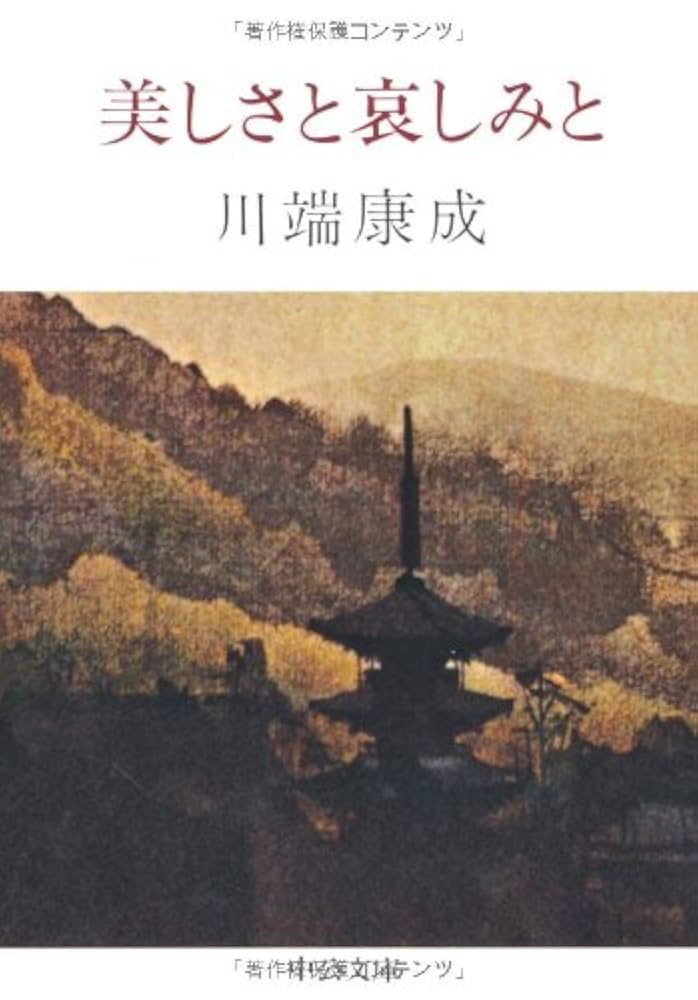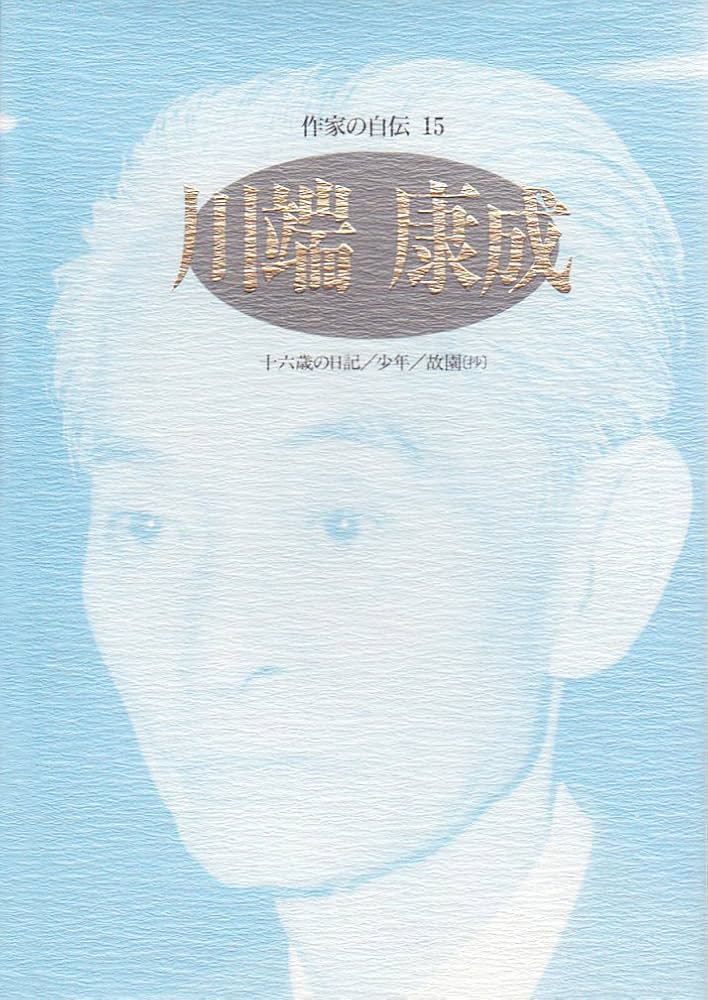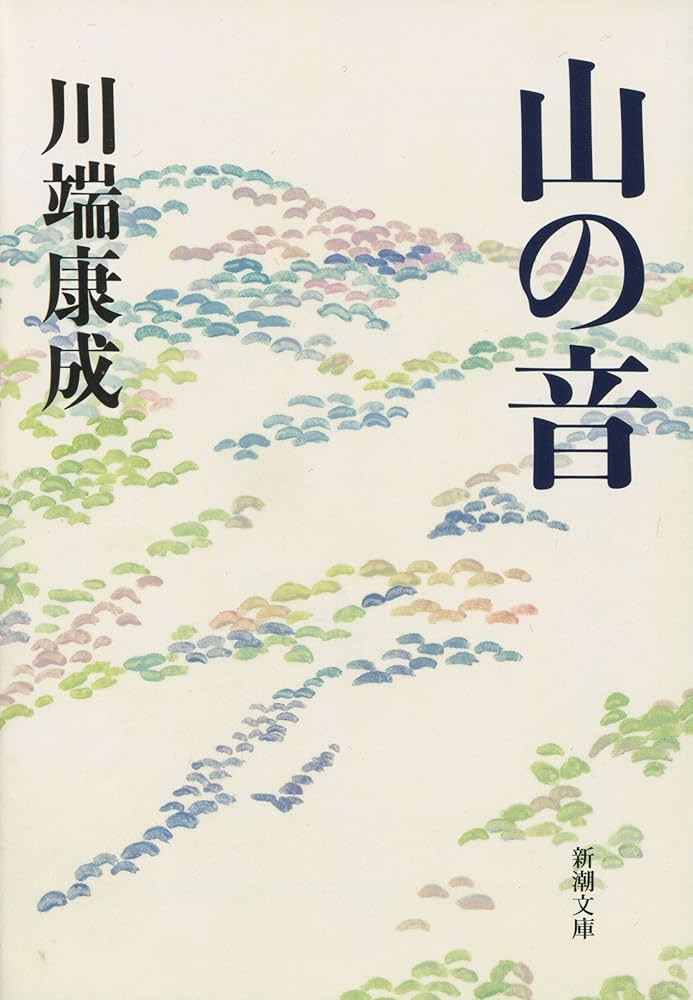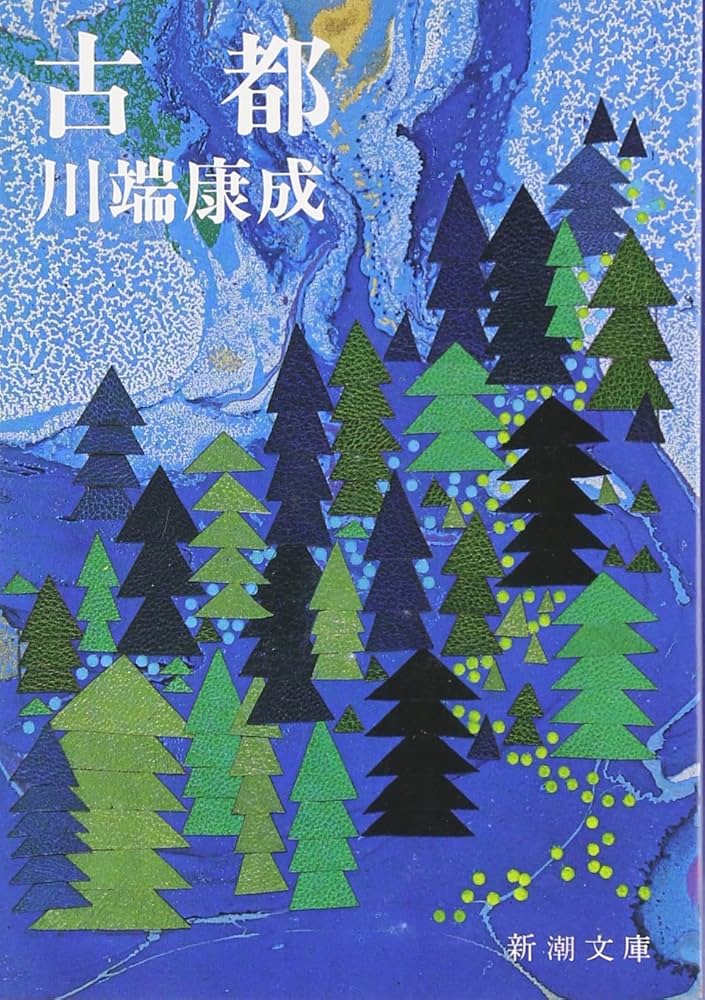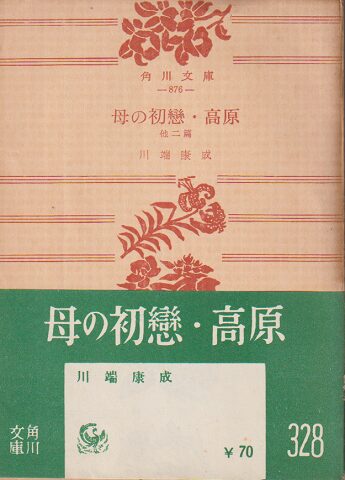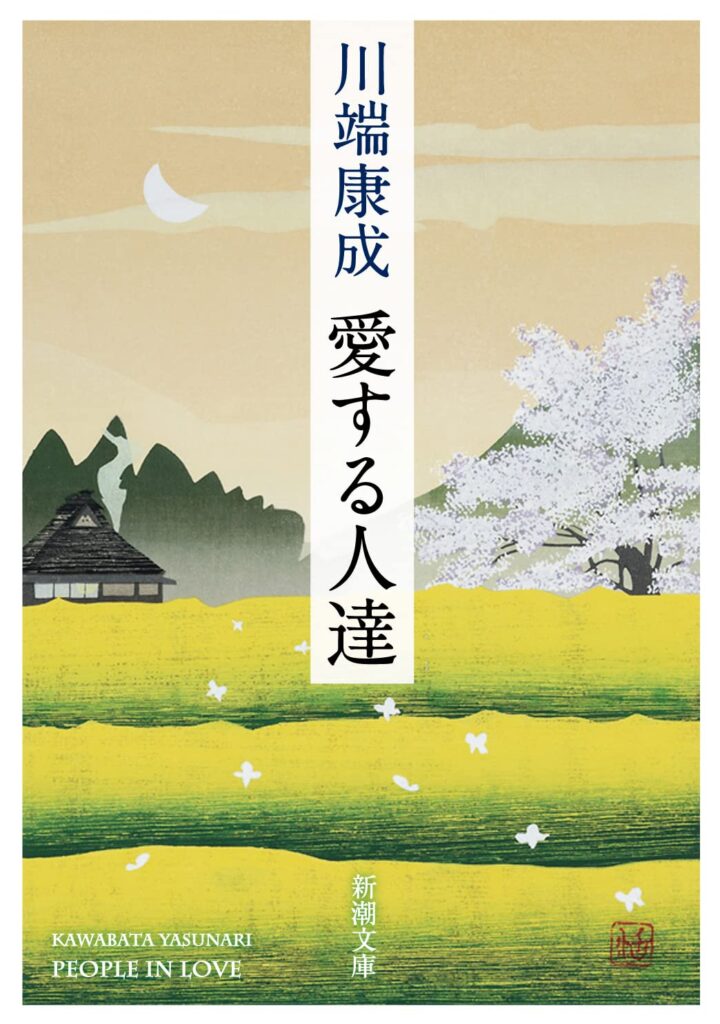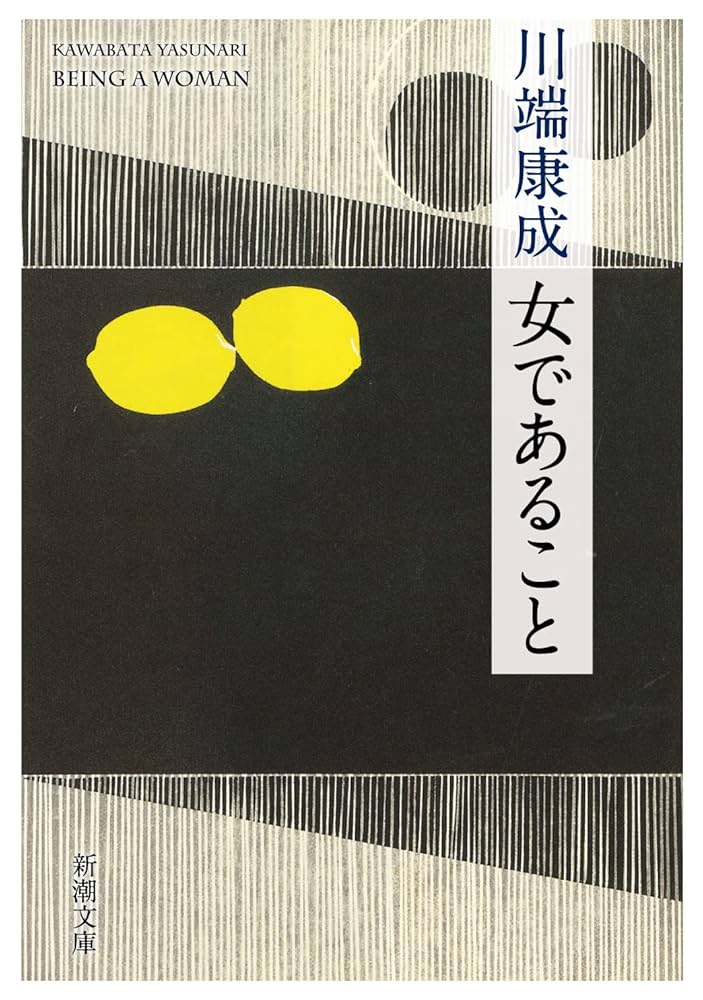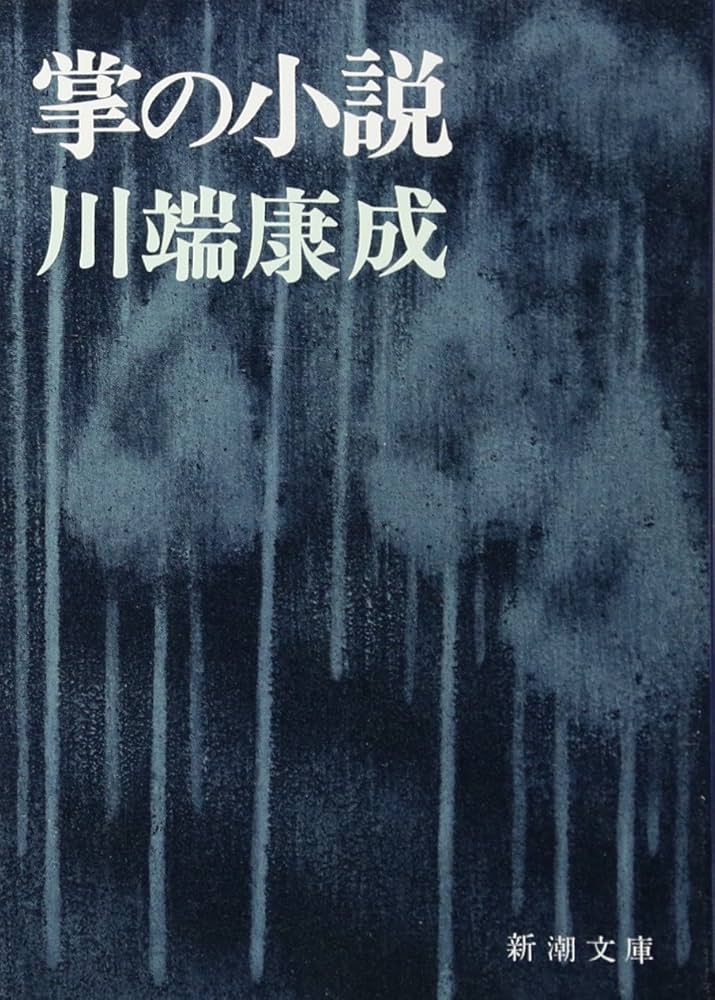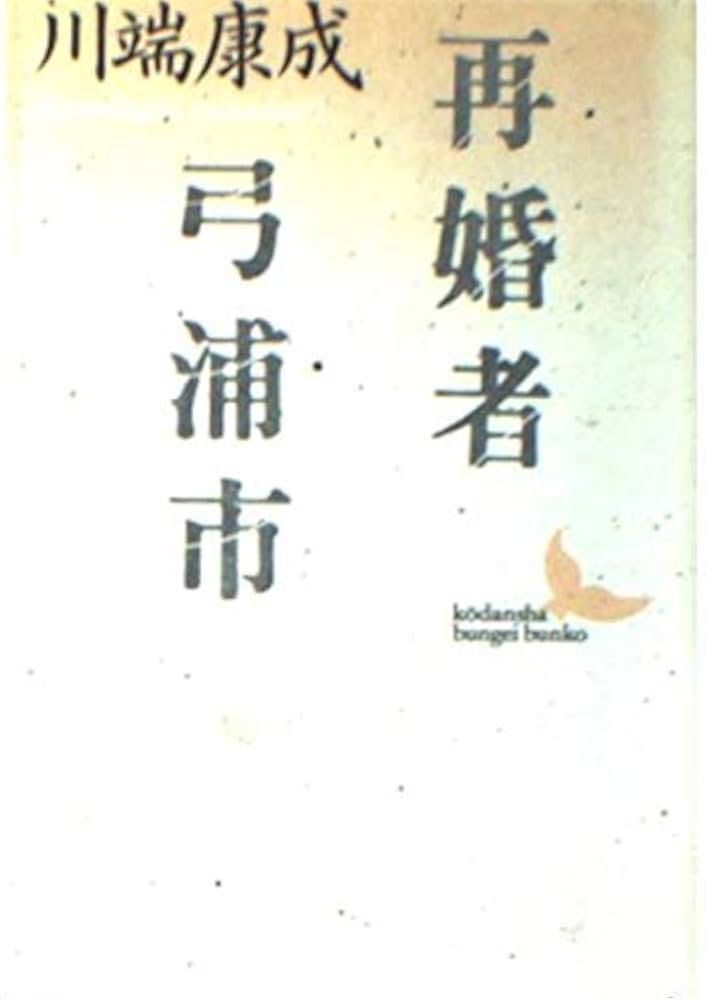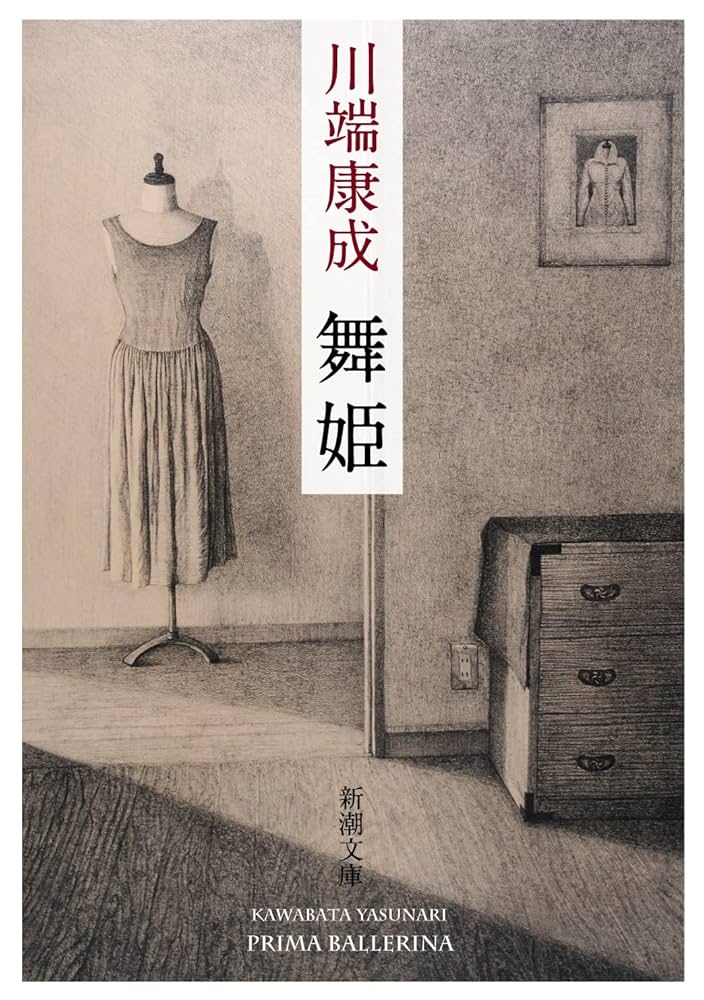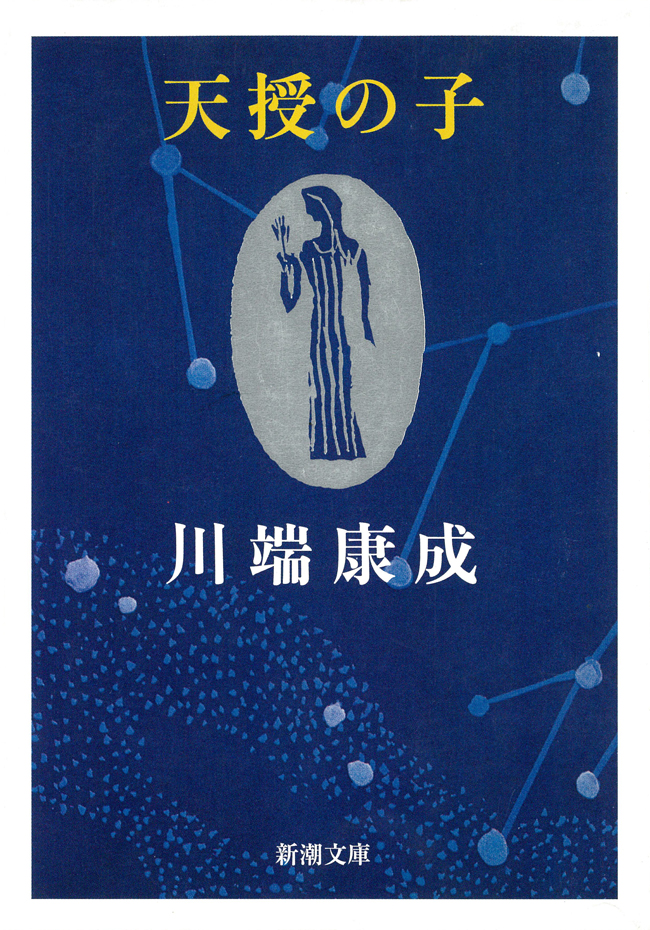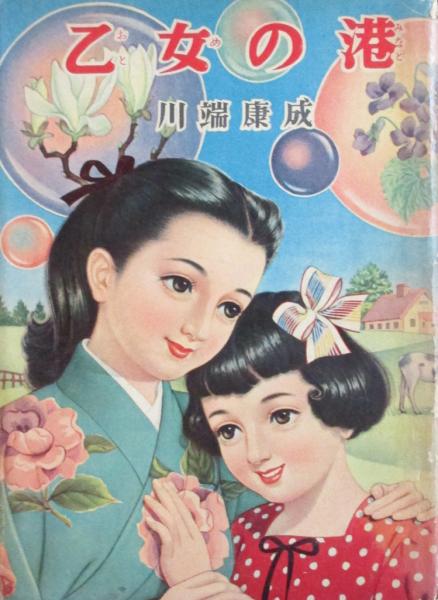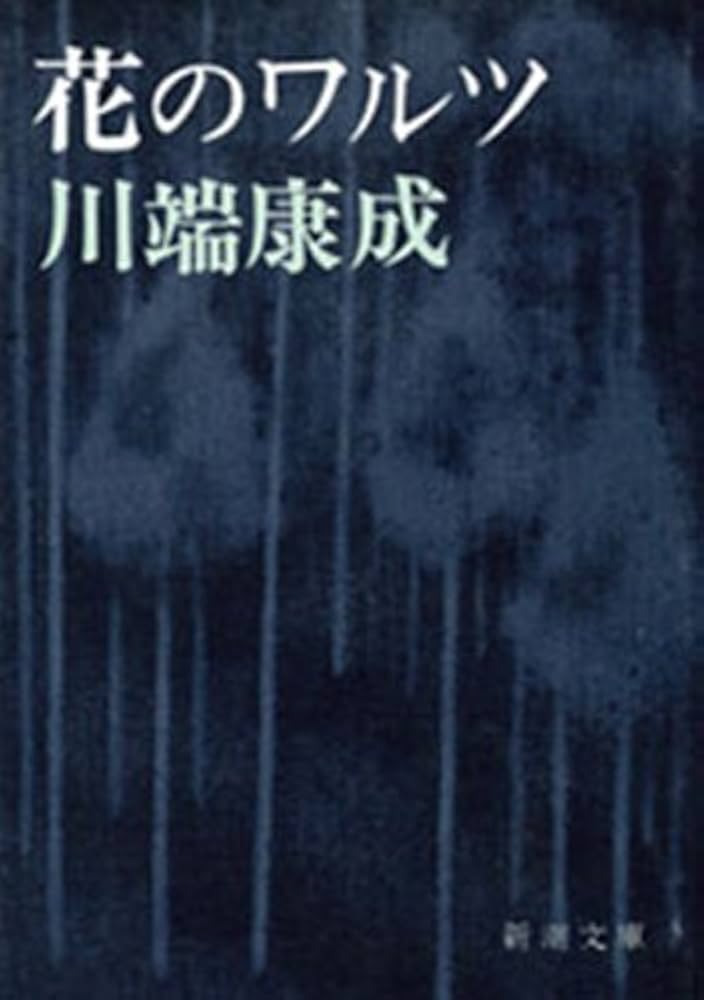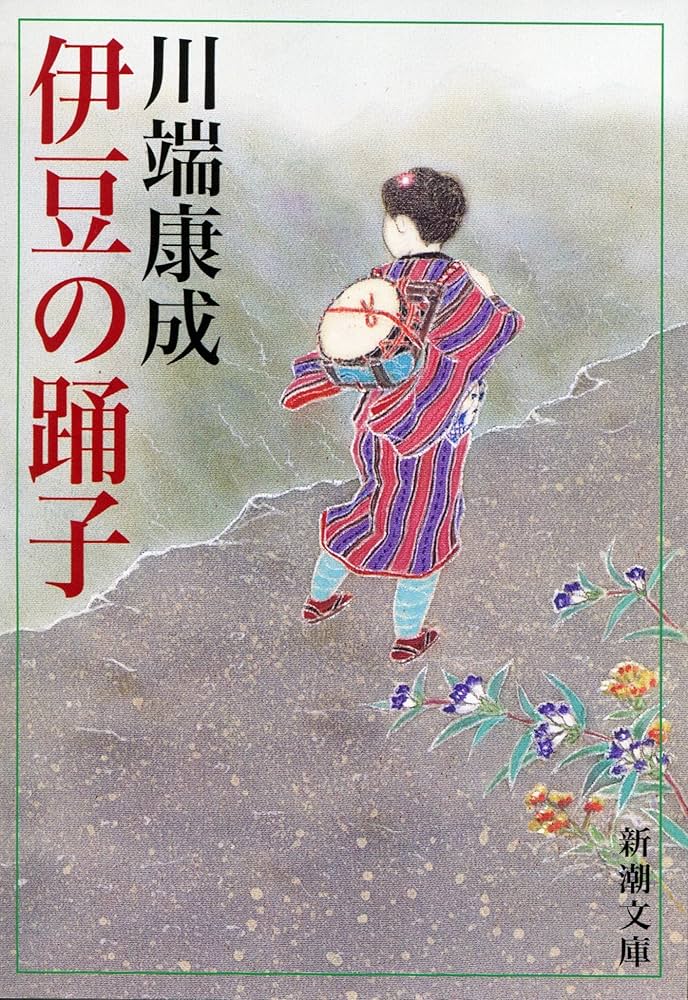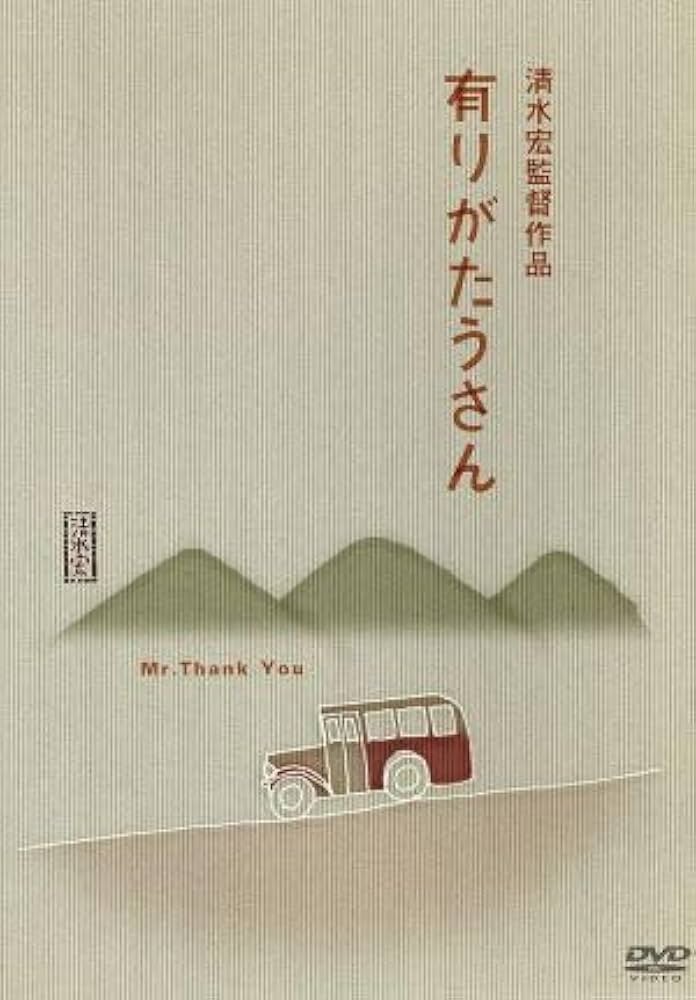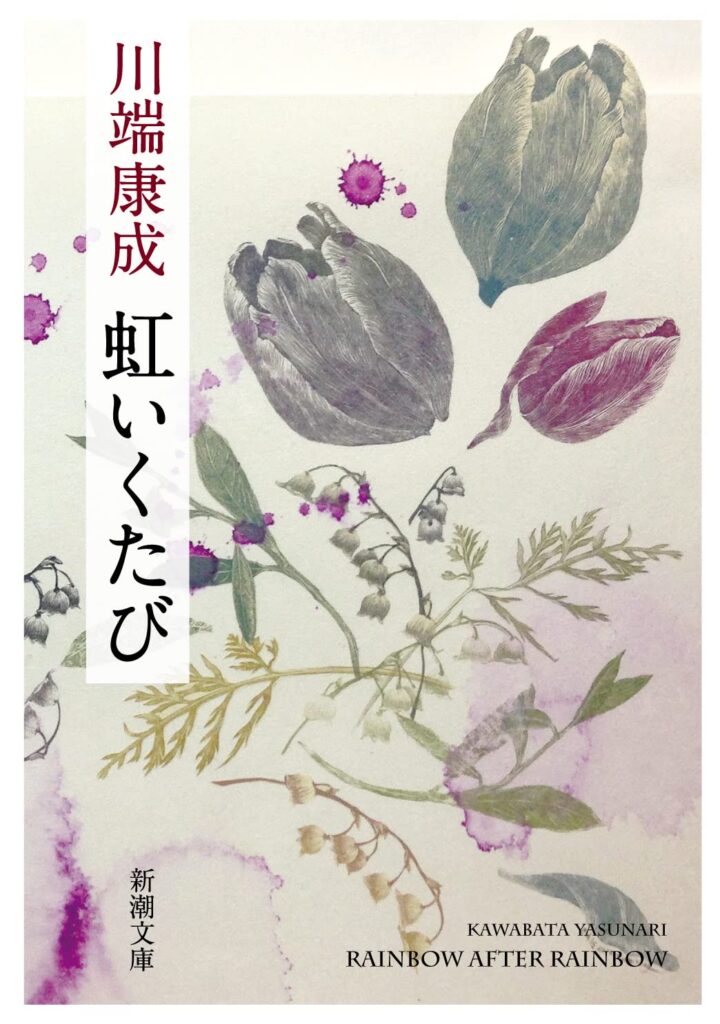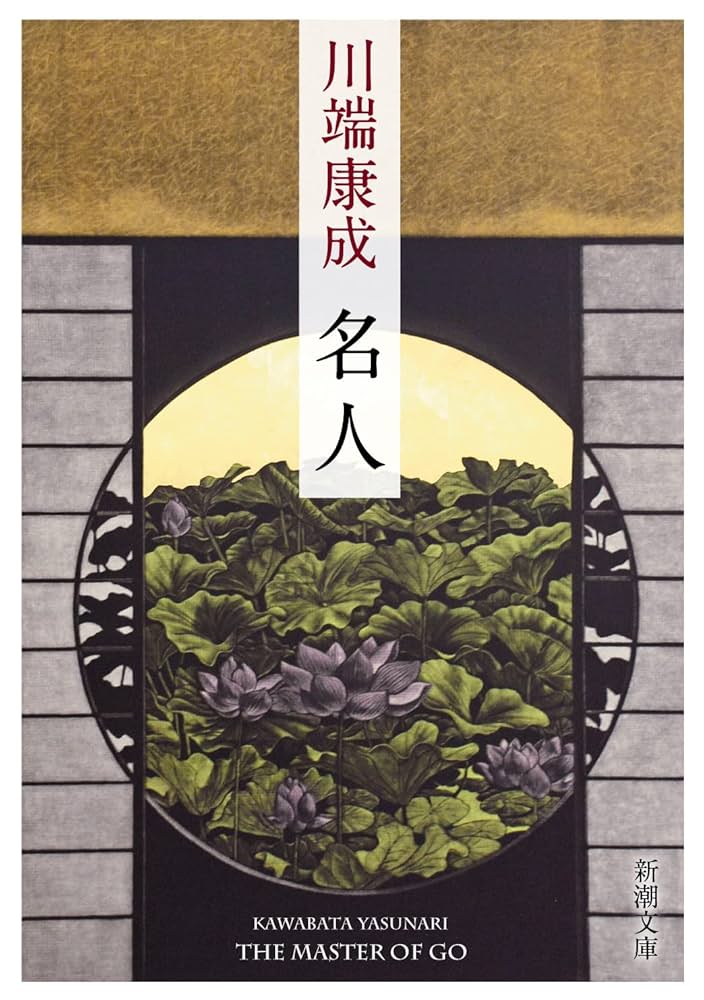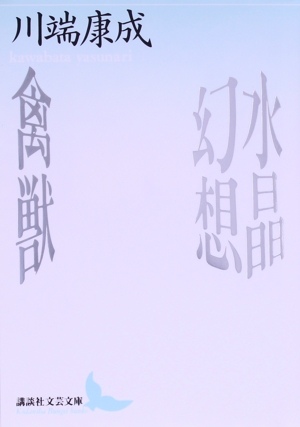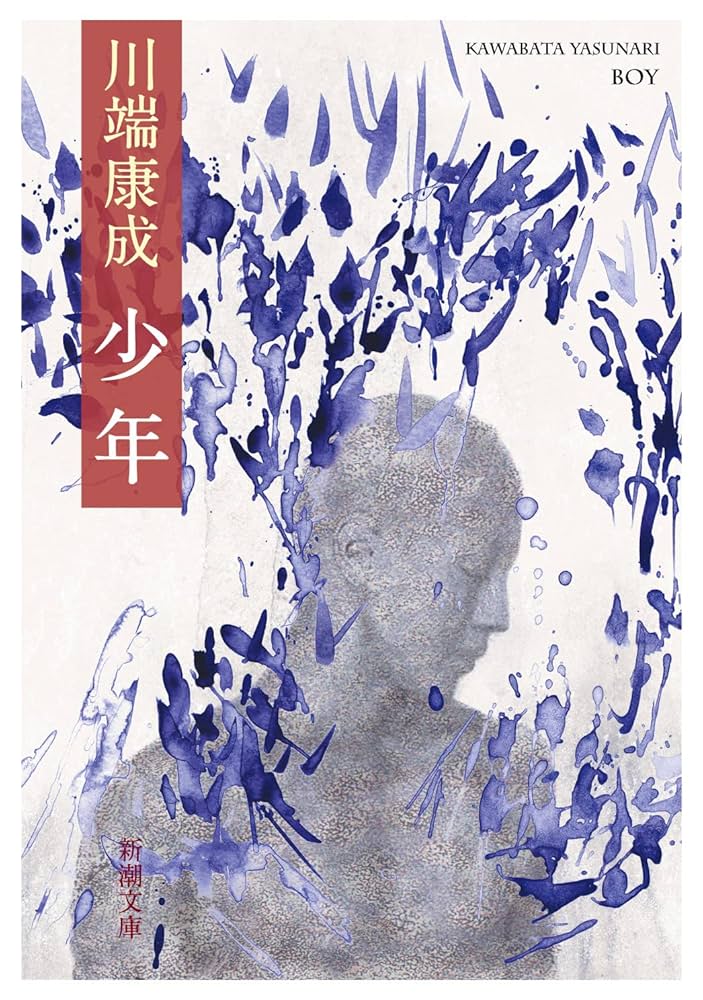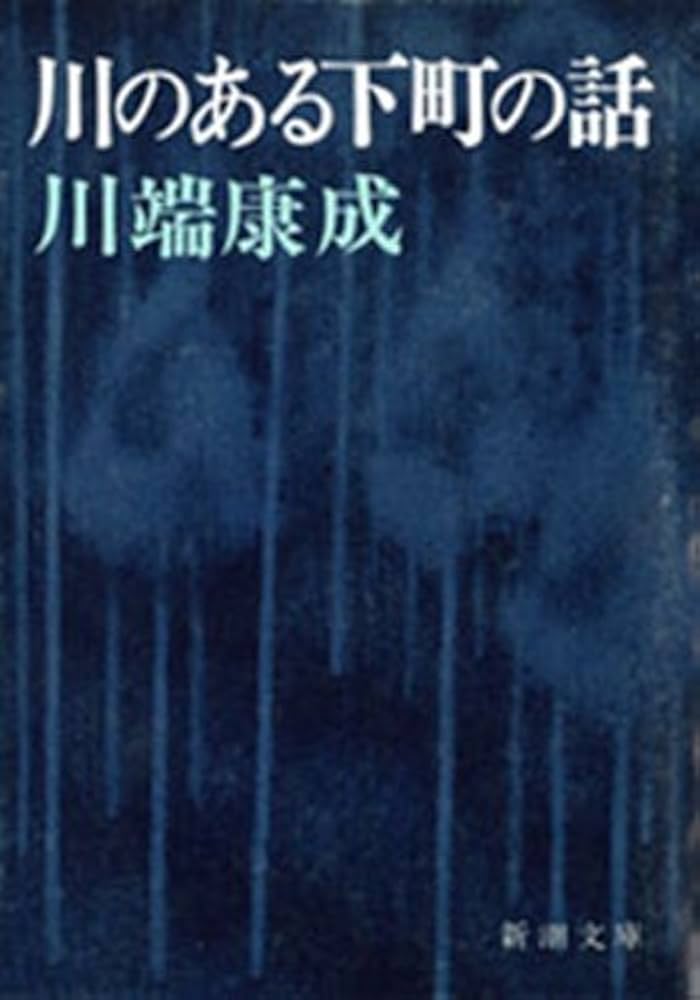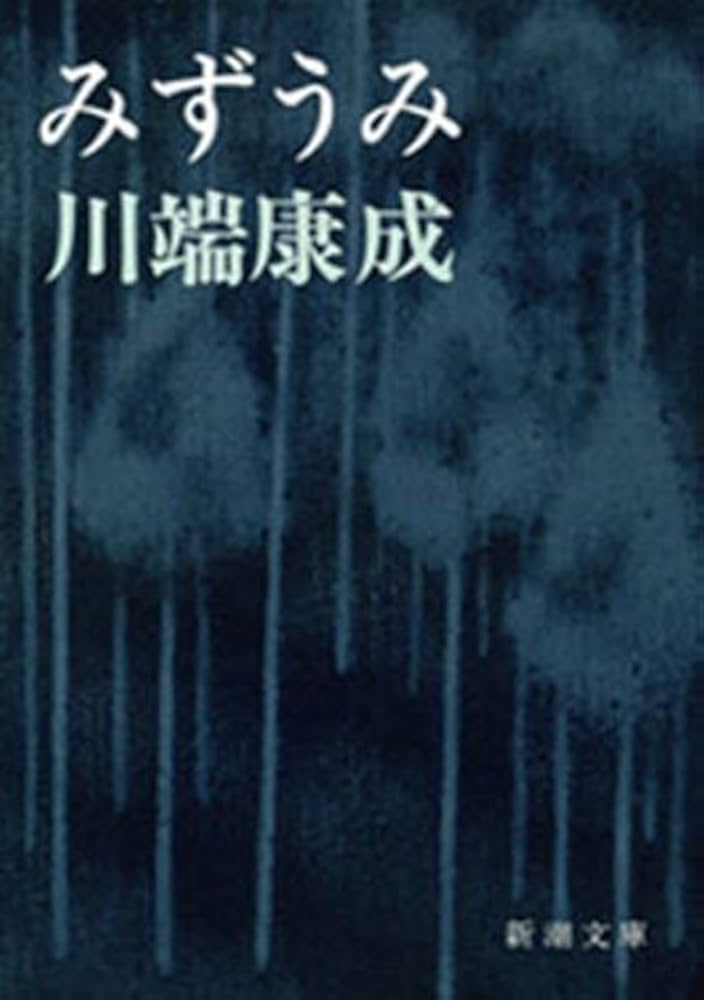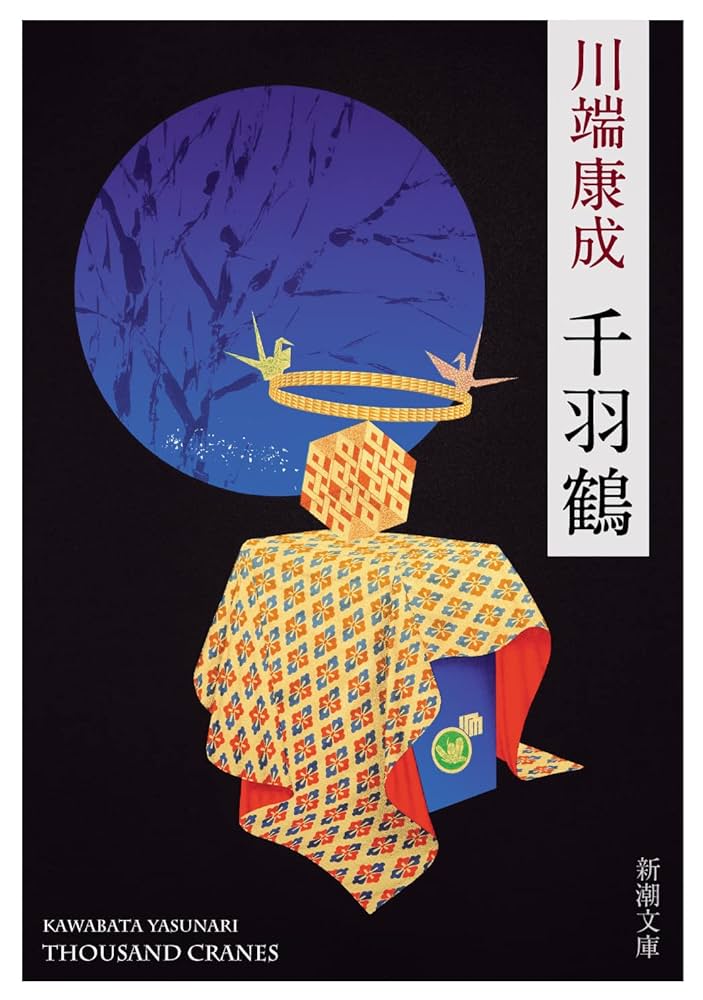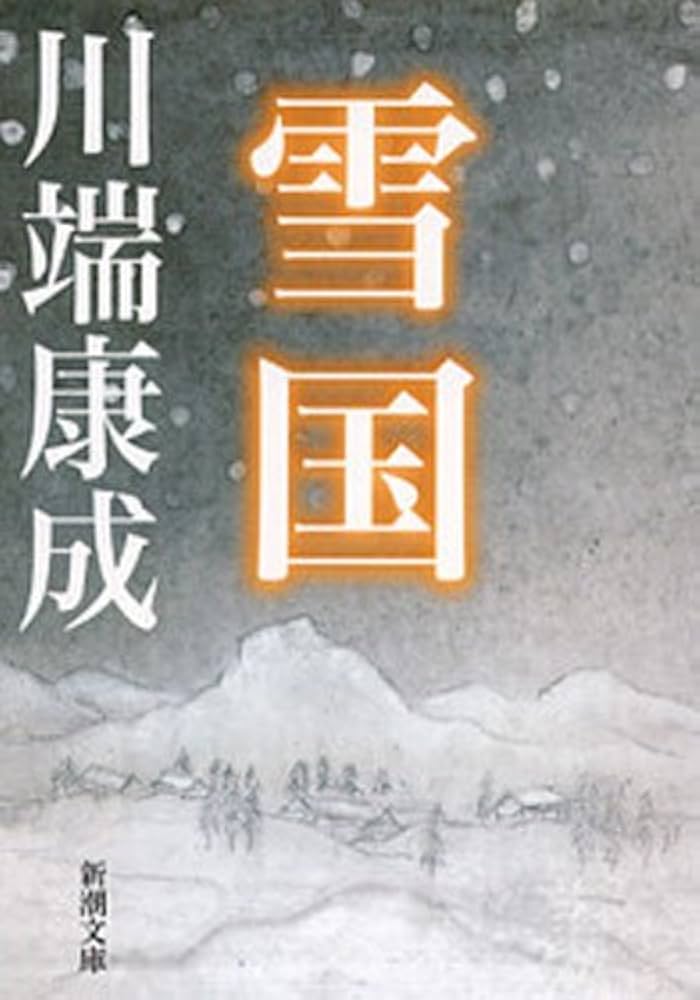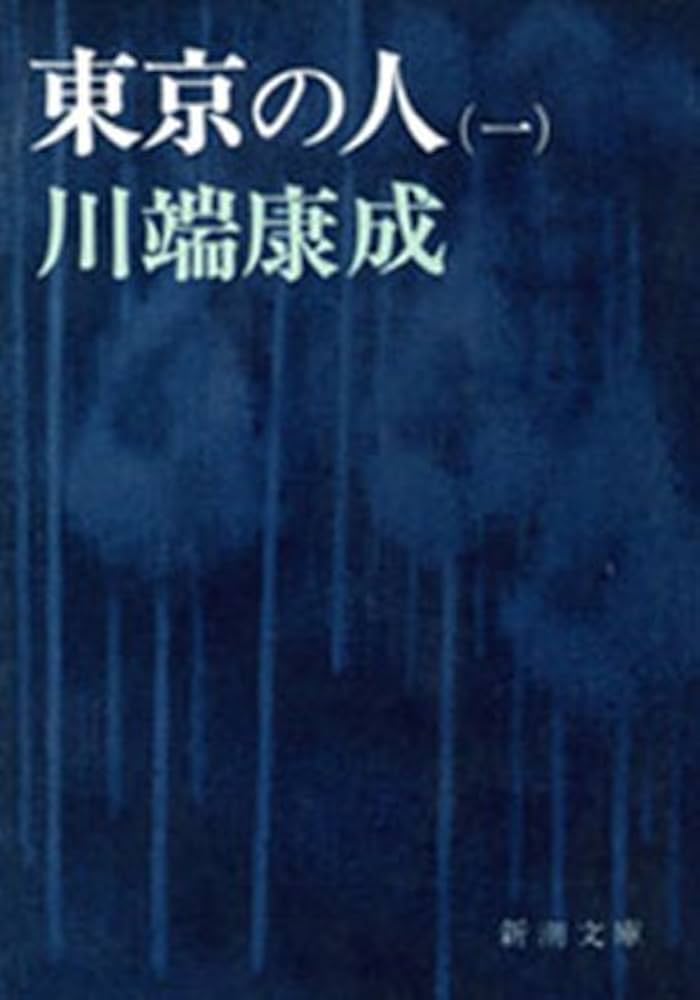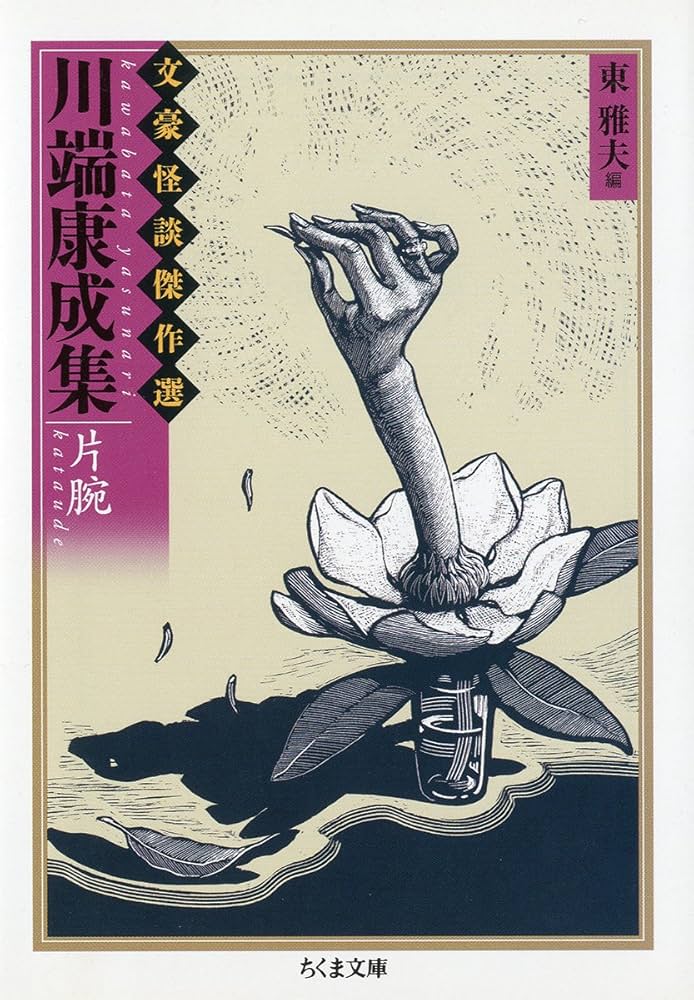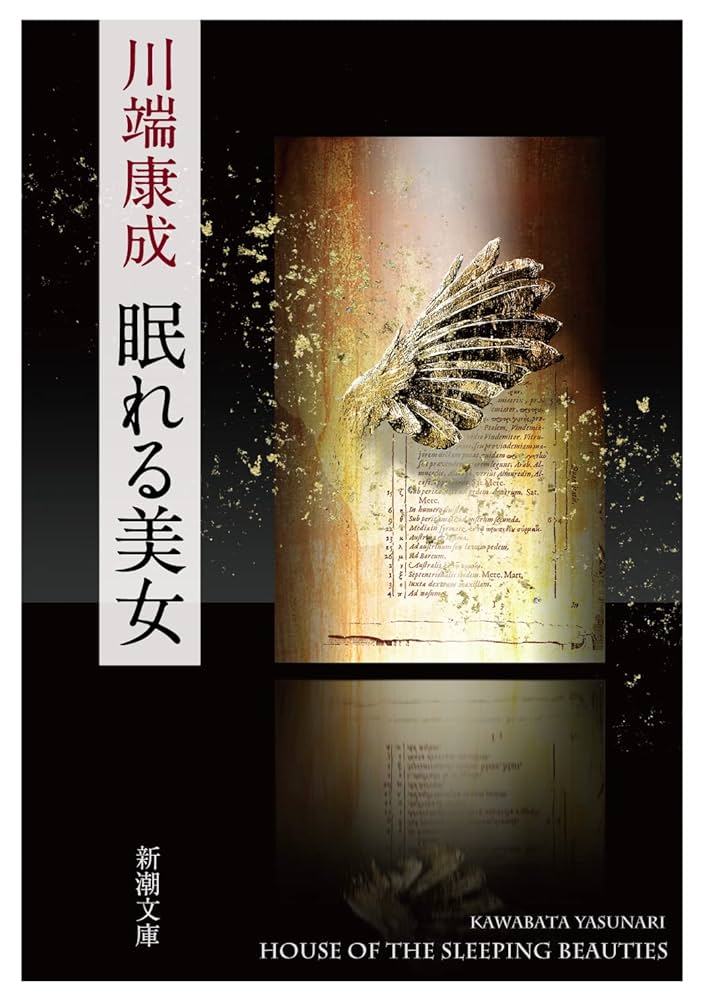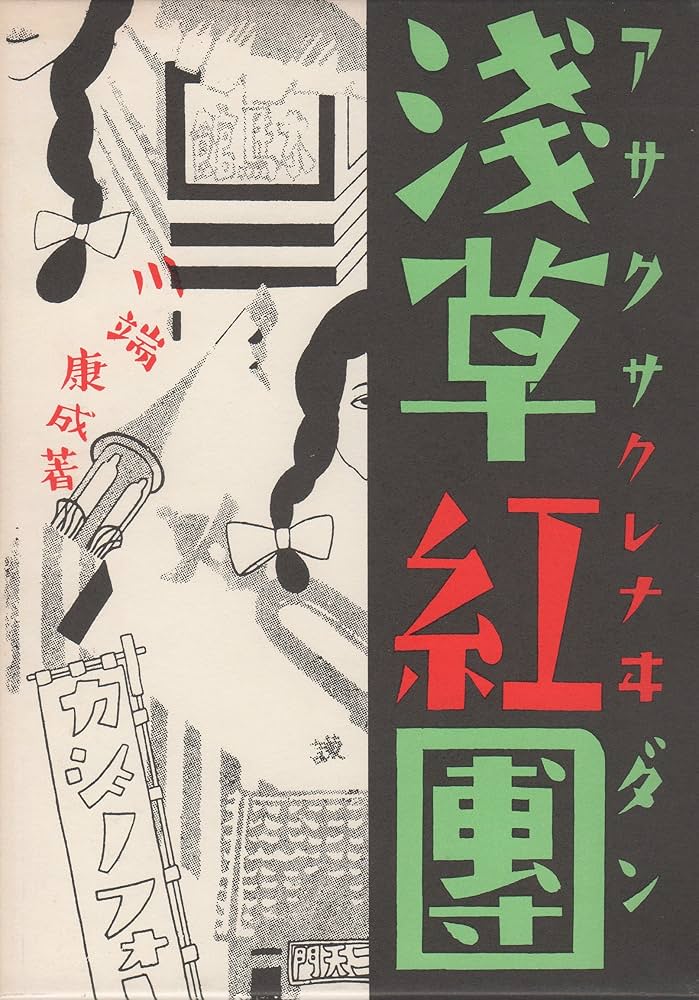小説「哀愁」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「哀愁」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
川端康成が描く世界は、美しくもどこか物悲しい、独特の空気に満ちていますよね。この「哀愁」という物語は、まさにその真骨頂。戦後の日本を舞台に、崩壊へと向かう一つの家族の姿を、静かで詩的な筆致で描き出しています。はっきりとした事件が次々と起こるわけではないのですが、登場人物たちの心の機微や、日常に潜む小さな変化が、深く胸に迫ってくるんです。
この記事では、まず物語の概要、つまりどんなお話なのかを知りたい方のために、物語の核心に触れすぎない範囲であらすじをまとめました。どのような人々が登場し、どんな状況に置かれているのか、その入り口をご案内します。これを読むだけでも、作品の持つ物悲しい雰囲気を感じていただけるはずです。
そして後半では、物語の結末にも触れるネタバレを含む、かなり踏み込んだ長文の感想を書いています。作中の象徴的な場面や、登場人物たちの行動の裏にある心理を、私なりにじっくりと読み解いてみました。一度この物語を読んだことがある方なら、きっと「ああ、なるほど」と思っていただけるポイントがあると思います。
「哀愁」のあらすじ
物語の舞台は、戦後の鎌倉に居を構える一つの家族、尾形家です。主人公は、会社重役を務める初老の男性、尾形信吾。彼は自身の肉体的な衰えや、忍び寄る死の気配を日々感じています。ある夜、裏山から不気味な地鳴りのような「山の音」を耳にした信吾は、それを自らの死の予兆ではないかと直感し、言い知れぬ不安に駆られます。
信吾の家庭は、平穏そうに見えて、実は静かな不協和音に満ちています。息子の修一は、若く美しい妻・菊子がいながら、戦争未亡人と公然と浮気を続けており、家庭を顧みません。その態度は無神経で冷たく、父である信吾との間には深い溝ができています。信吾は、そんな息子夫婦の関係に心を痛めながらも、可憐で心優しい嫁の菊子に、安らぎと清らかな愛情を見出していくのです。
信吾の菊子への思いは、単なる舅の嫁への情愛にとどまりません。彼は若き日に憧れ、早くに亡くなった妻の姉の面影を、菊子に重ね合わせていました。その思いは、息苦しい家庭生活の中での唯一の救いであると同時に、どこか危うい香りを漂わせています。
そんな中、家庭内の緊張をさらに高める出来事が起こります。夫との不和から、二人の子供を連れて娘の房子が出戻ってくるのです。彼女の存在は、尾形家に渦巻く鬱屈した空気をさらに重くします。信吾が感じる老いへの恐怖、家族の崩壊への予感、そして菊子への禁断にも似た思慕。物語は、この解決の見えない問題の行方を、静かに見つめていきます。
「哀愁」の長文感想(ネタバレあり)
この「哀愁」という物語を読み解くことは、川端康成という作家が抱いていた「滅びの美学」そのものに触れることだと感じています。これは単なる家族の物語ではなく、戦後の日本で失われゆくものの姿と、そこに宿る悲しい美しさを描いた、壮大な詩のような作品ではないでしょうか。
川端自身が「敗戦後の私は日本古来の悲しみのなかに帰つてゆくばかりである」と語ったように、彼は戦後の目まぐるしい変化や新しい価値観を信じず、もっと根源的で普遍的な日本人の情念に目を向けようとしました。この物語に流れる「哀愁」とは、まさにその「古来の悲しみ」が、一つの家族の肖像を通して結晶化したものなのだと思います。
物語の中心にいる主人公、尾形信吾は、まさに川端の分身のような存在です。彼は60歳を過ぎ、自身の老いを日々痛感しています。物忘れがひどくなり、亡くなった友人たちが夢に現れる。彼の内面は、静かに死へと向かうことへの諦めと恐怖に満ちています。
この信吾の個人的な感覚は、彼が「滅んで行く一族の最後の人が自分なんだ」と感じていた、川端自身の血統への意識と重なります。長く続いた伝統や文化が崩壊していく戦後日本と、老いによって衰えていく自らの肉体。この二重の「滅び」の感覚が、信吾の感じる寄る辺のない寂しさの正体であり、物語全体の基調をなしているのです。
そして、この物語のもう一人の主役が、信吾の嫁である菊子です。彼女は、夫・修一に裏切られ、不幸な結婚生活を送る、はかなく美しい女性として描かれます。信吾にとって、彼女は息苦しい家庭における唯一の光であり、救いです。
信吾の菊子への愛情は非常に複雑です。彼は、若くして亡くなった妻の姉、つまり彼の初恋の人ともいえる理想の女性の面影を、菊子に見ています。これは、現実の妻・保子との間にはない、失われた美への憧れです。このネタバレになりますが、彼の感情は単なるいたわりを超え、美への思慕という、ほとんど禁忌に近い領域にまで踏み込んでいきます。
対照的に描かれるのが、息子・修一の存在。彼は戦後の道徳的混乱を体現したような人物です。妻を傷つけることに何の罪悪感も抱かず、愛人との関係を隠そうともしない。父である信吾が大切にする倫理観や繊細な感受性を、冷笑的に踏みにじります。この父と子の断絶は、物語が進むにつれて決定的になっていくのです。
この家族の歪んだ三角関係こそが、物語の核心部分です。老いた父が抱く、清らかで禁忌の香りを帯びた美への憧れ。そして、若き息子が持つ、近代的で破壊的な欲望。その間で、菊子は、荒廃した世界で踏みにじられようとする、はかなく美しい伝統的価値の象徴として存在しているように私には思えました。
物語の最も痛切な転換点であり、最大のネタバレとなるのが、菊子の堕胎です。夫の裏切りの中で妊娠した彼女は、一人で子供を産み育てる未来を描けず、その命を諦める決意をします。信吾はその事実を知り、深い悲しみと無力感に打ちのめされながらも、彼女に付き添うのです。
この秘密の共有は、信吾と菊子の絆を悲劇的な形で深めます。しかしそれは、希望を分かち合うのではなく、巨大な喪失感を分かち合う絆でした。この堕胎は、尾形家の未来が文字通り絶たれてしまったことを象徴する、あまりにも重く、暗い出来事です。
本作で最も有名で、象徴的な場面が、信吾が菊子に能面をあてがうシーンでしょう。彼は「慈童」という、永遠の若者を表す能面を手に入れます。そしてある夜、その面を菊子の顔にかぶせてみる。すると、彼女の苦悩や個性は仮面の下に消え、そこには時を超えた抽象的な美だけが立ち現れます。
この行為は、信吾の倒錯した願望の表れです。彼は、苦しむ生身の人間である菊子を、傷つくことのない永遠の芸術品へと変えてしまいたいと願っているのです。それは美を愛するがゆえの行為でありながら、一人の女性の人間性を奪い、自らの鑑賞の対象にしようとする、根源的なエゴイズムと精神的な暴力をはらんでいます。
この物語には、もう一つの重要な象徴があります。それは、菊子の額にある、生まれた時についたかすかな傷跡です。信吾は、この傷跡を欠点ではなく、彼女がこの世に生を受けた証として、かけがえのないものだと感じています。完璧ではないからこそ愛おしい。この傷跡は、不完全さの中にこそ宿る真の美しさ、つまり「哀愁」の美学を体現しているのではないでしょうか。
物語を覆う「山の音」もまた、死の予感や、人間を超えた大いなる自然の力を象徴しています。信吾が聞くこの音は、虚無からの呼び声のようであり、彼を静かに死へと誘います。この抗いがたい自然の摂理と、家族の崩壊という人間社会の現実が交錯し、物語に深い奥行きを与えています。
この作品は、結局のところ、何一つ問題が解決しないまま幕を閉じます。修一の不倫は続き、菊子の悲しみは癒されず、信吾は老いと死の影の中を生き続ける。この「解決のなさ」こそが、この物語のすごみだと思います。
川端にとって「哀愁」とは、乗り越えるべき課題ではなく、ただそこにある人生のありさまそのものなのです。美しさと崩壊が、常に隣り合わせに存在する世界。その中で生きていくことの根源的な悲しみを、彼は描こうとしたのではないでしょうか。
この物語は、川端の他の作品、例えば『住吉』で語られる母親への「よこしまな嫉妬」や「悪心」といったテーマとも繋がっています。『山の音』の信吾が抱く菊子への感情は、その「悪心」が、美しくも無力な悲しみへと昇華された形だと言えるかもしれません。
読み終えた後に残るのは、カタルシスではなく、静かで長い余韻です。それはまるで、信吾が聞いた「山の音」の残響のように、いつまでも心の中に響き続けます。美しく、物悲しく、そして忘れがたいその響きこそ、川端康成が「哀愁」という作品を通して私たちに伝えたかった、この世界の本当の音色なのかもしれません。
まとめ
この記事では、川端康成の小説「哀愁」について、物語の導入となるあらすじから、結末に触れるネタバレありの深い感想まで、じっくりとご紹介しました。一つの家族の崩壊を通して、滅びゆくものの悲しい美しさを描いた、非常に印象的な物語です。
物語の概要では、主人公・信吾が抱える老いへの恐怖や、息子夫婦の不和、そして彼が嫁の菊子に見出す複雑な愛情といった、物語の基本的な設定に触れました。これだけでも、作品全体を覆う、静かで張り詰めた空気を感じていただけたかと思います。
そして感想の部分では、ネタバレを交えながら、なぜこの物語がこれほどまでに人の心を打つのかを、私なりに分析しました。「山の音」や「能面」といった象徴的なモチーフの意味や、登場人物たちの行動の裏にある心理を深掘りしています。
この物語は、明確な結末が示されないからこそ、読者の心に強い余韻を残します。もしこの記事を読んで興味を持たれたなら、ぜひ一度、この美しくも物悲しい世界に触れてみてください。読後、あなたの心にもきっと、あの静かな「山の音」が響くはずです。