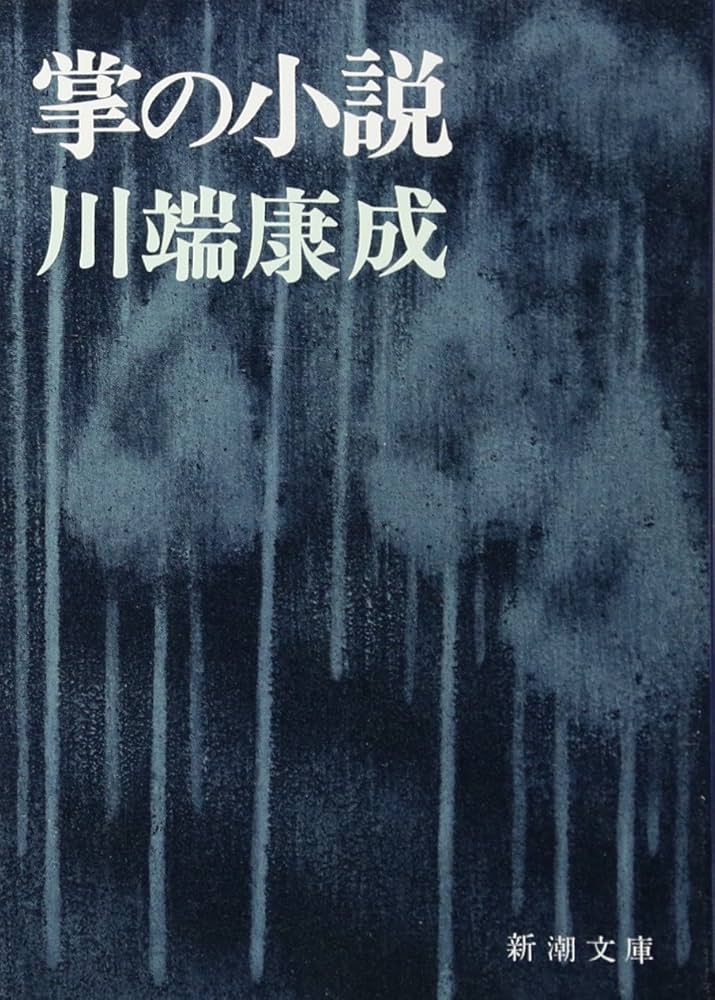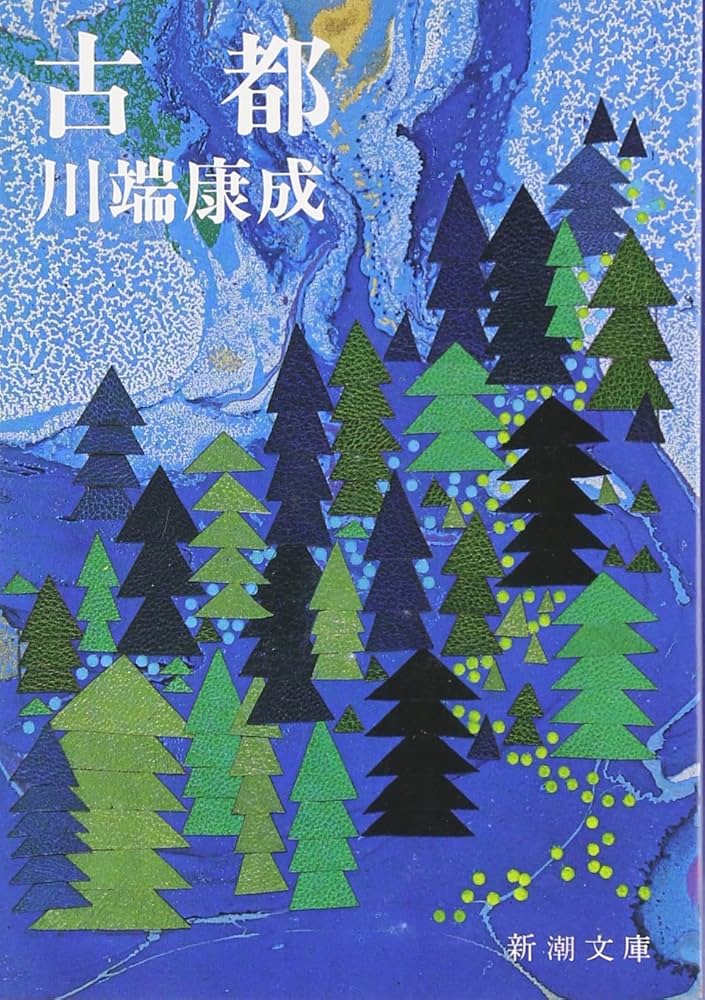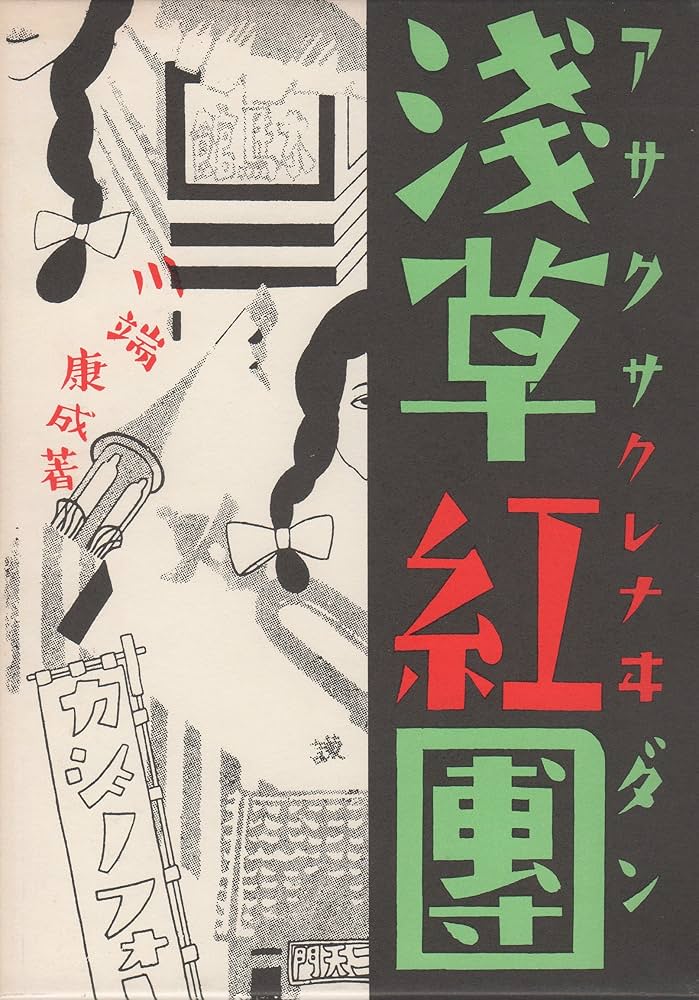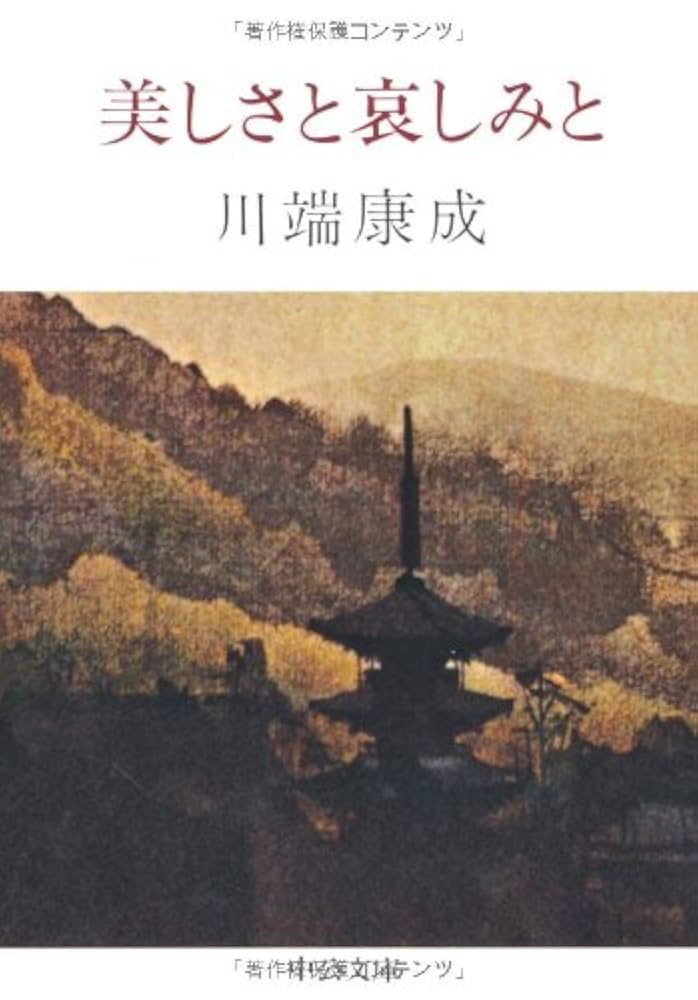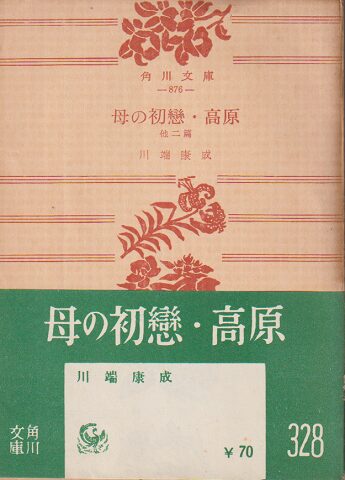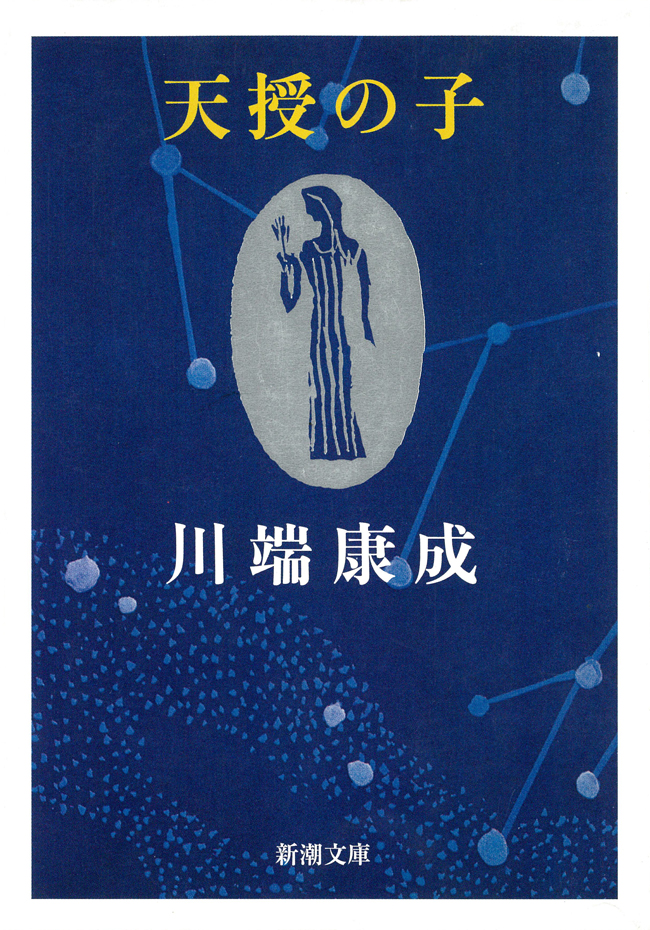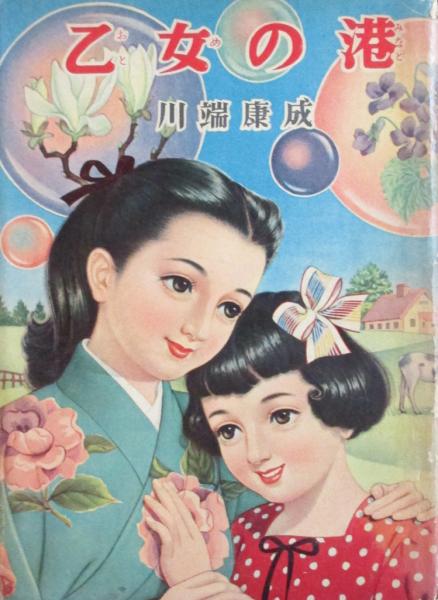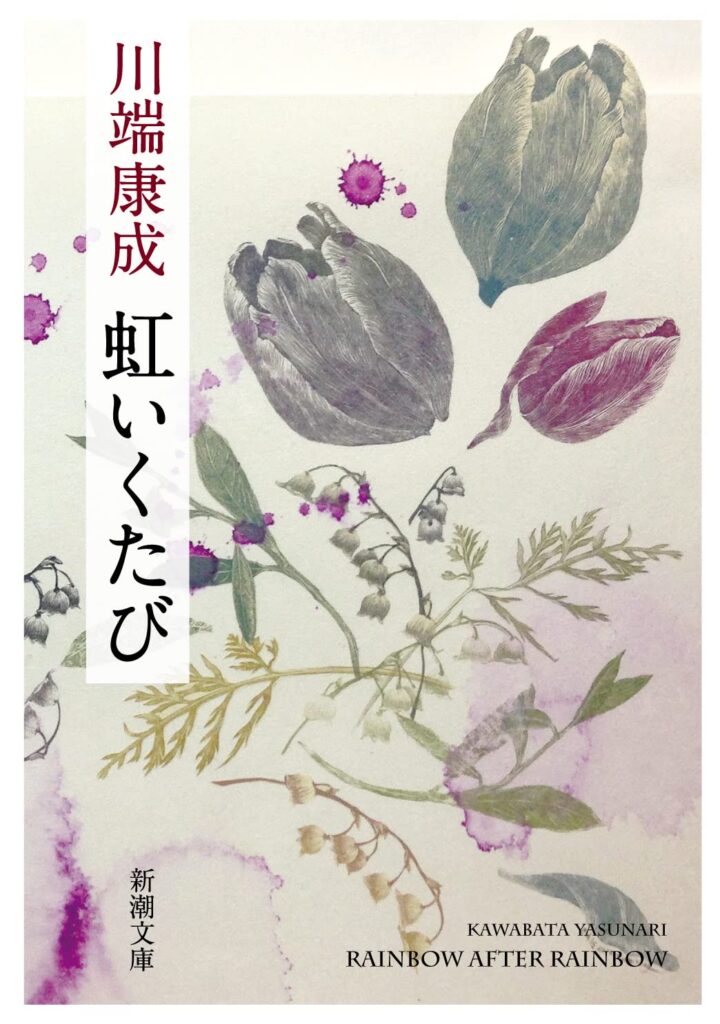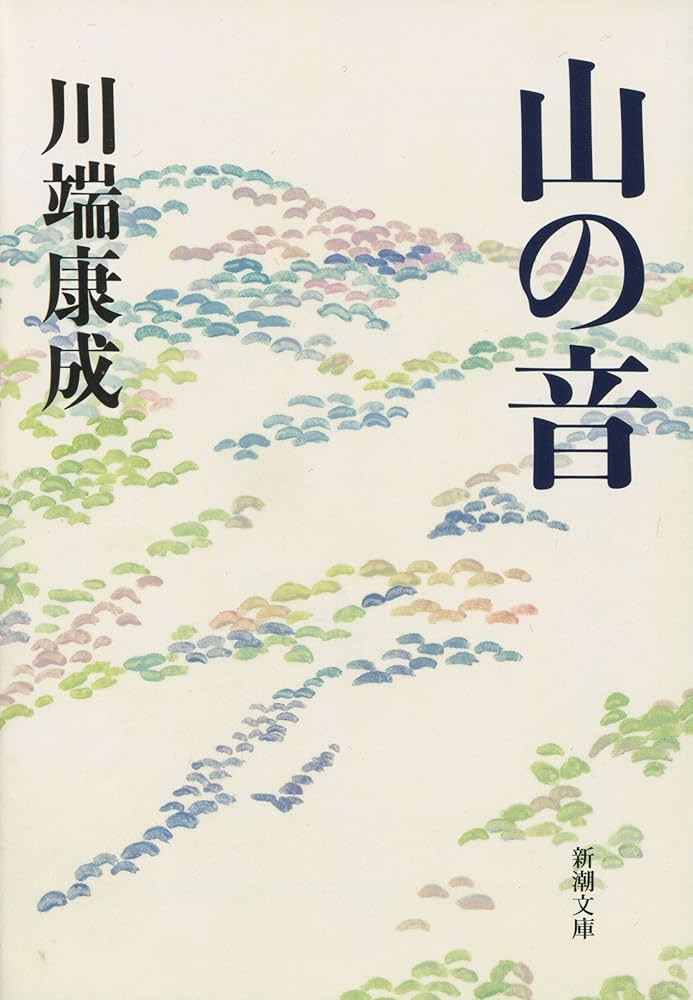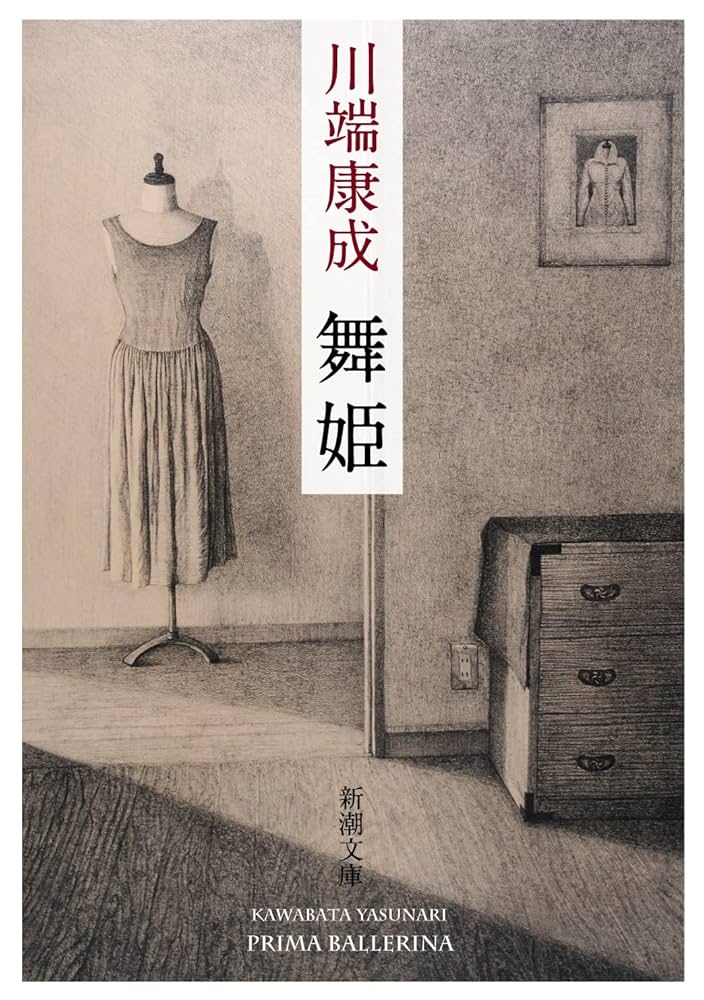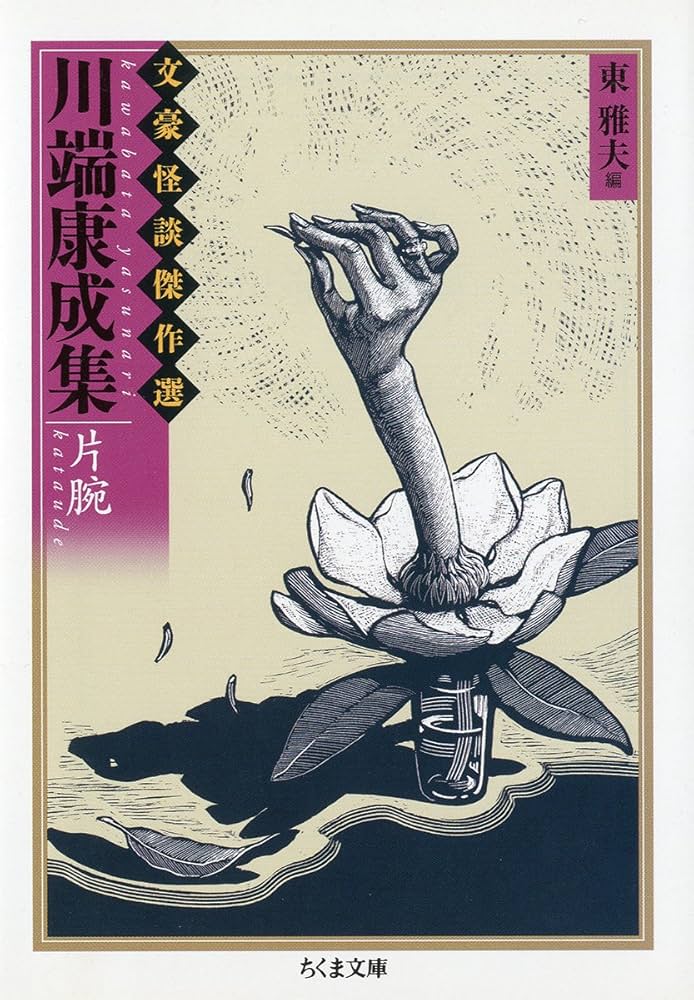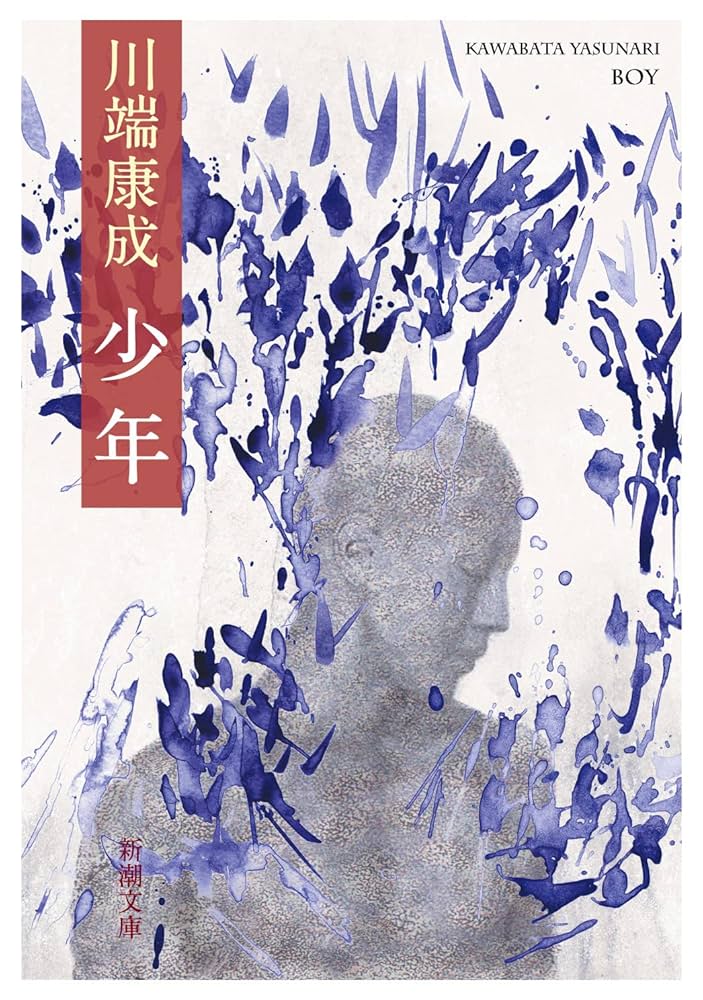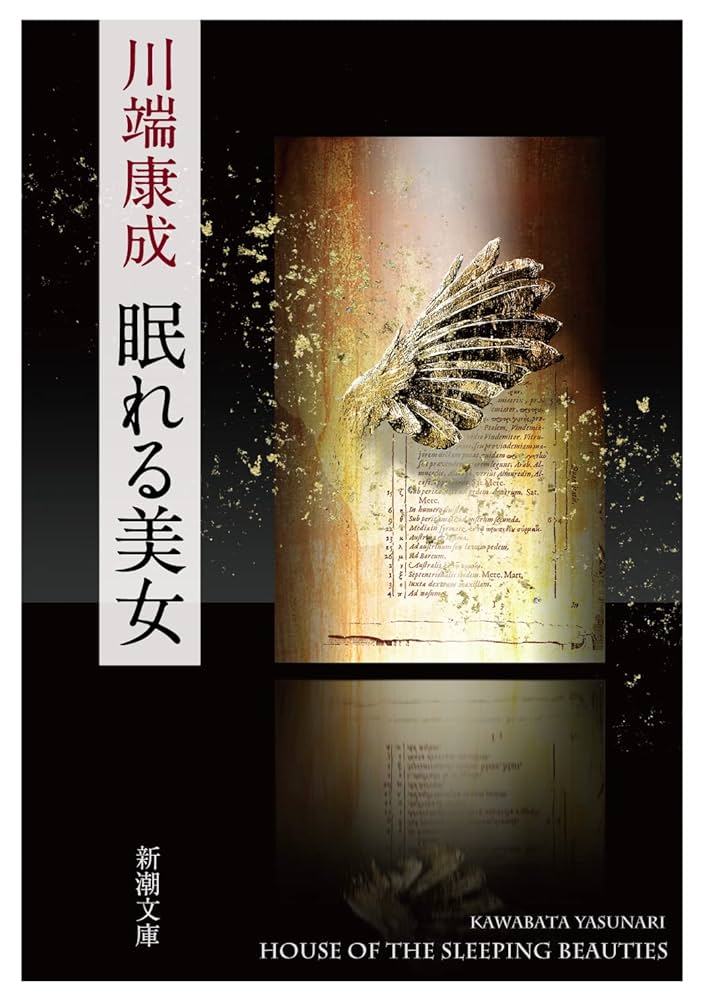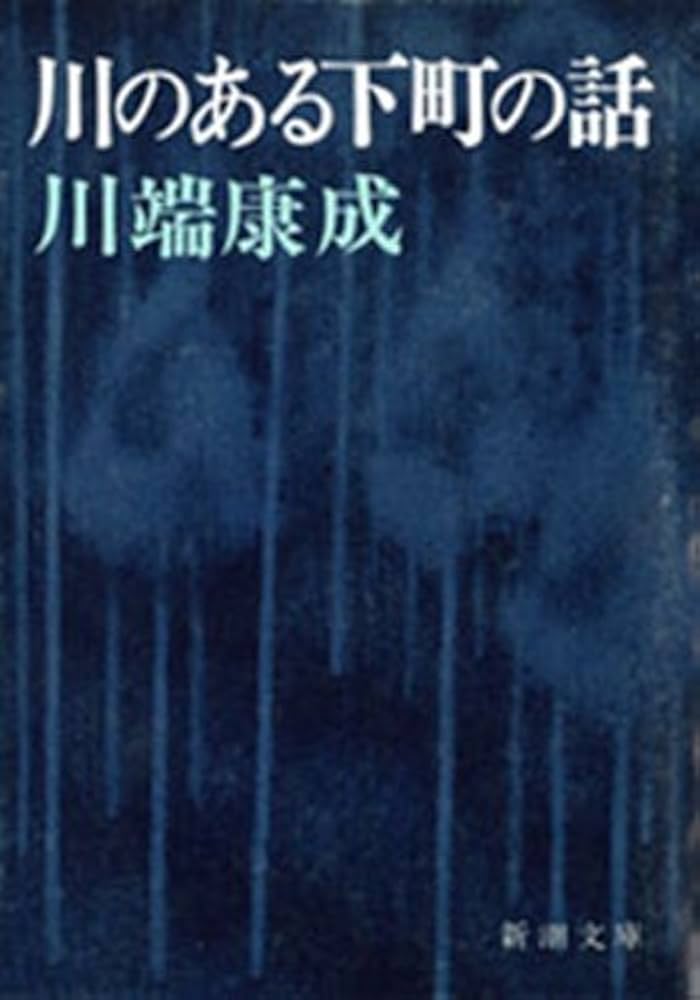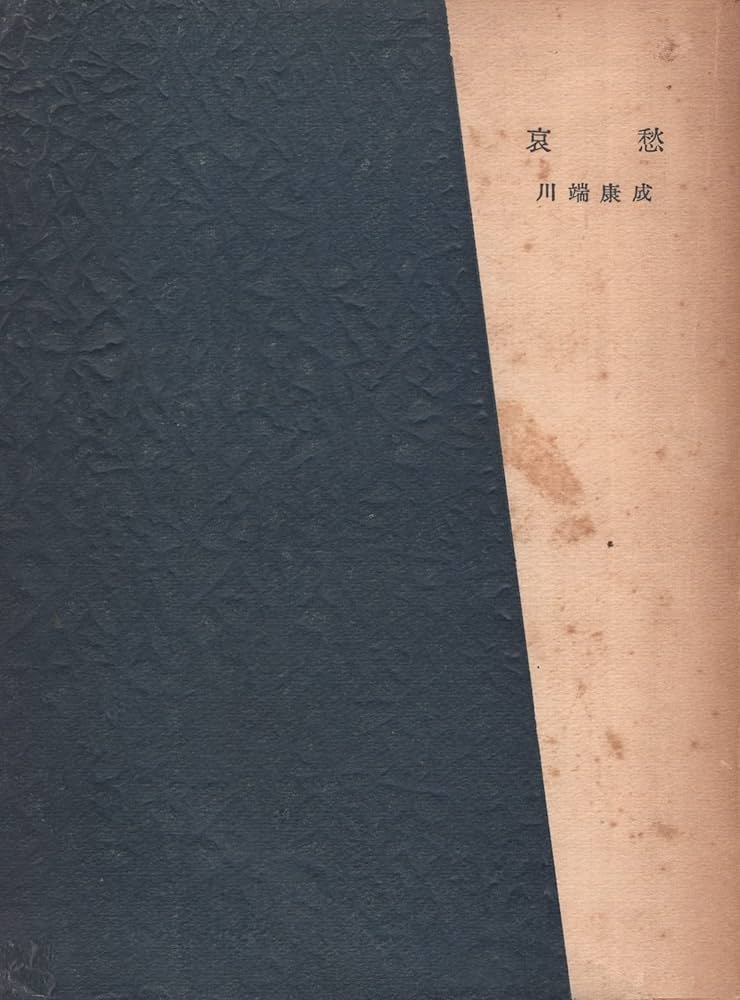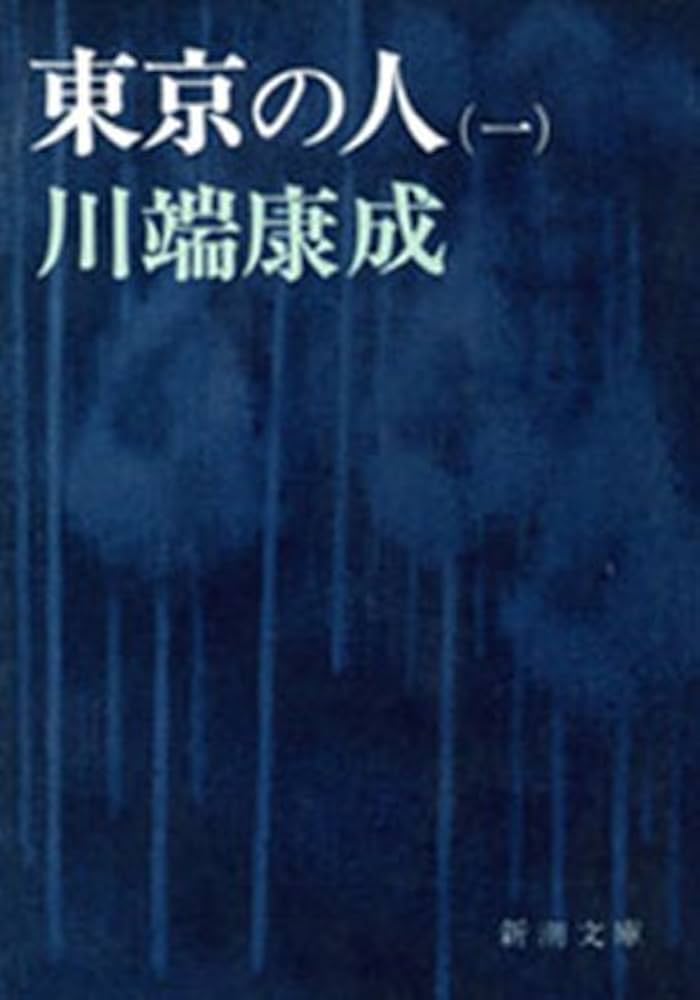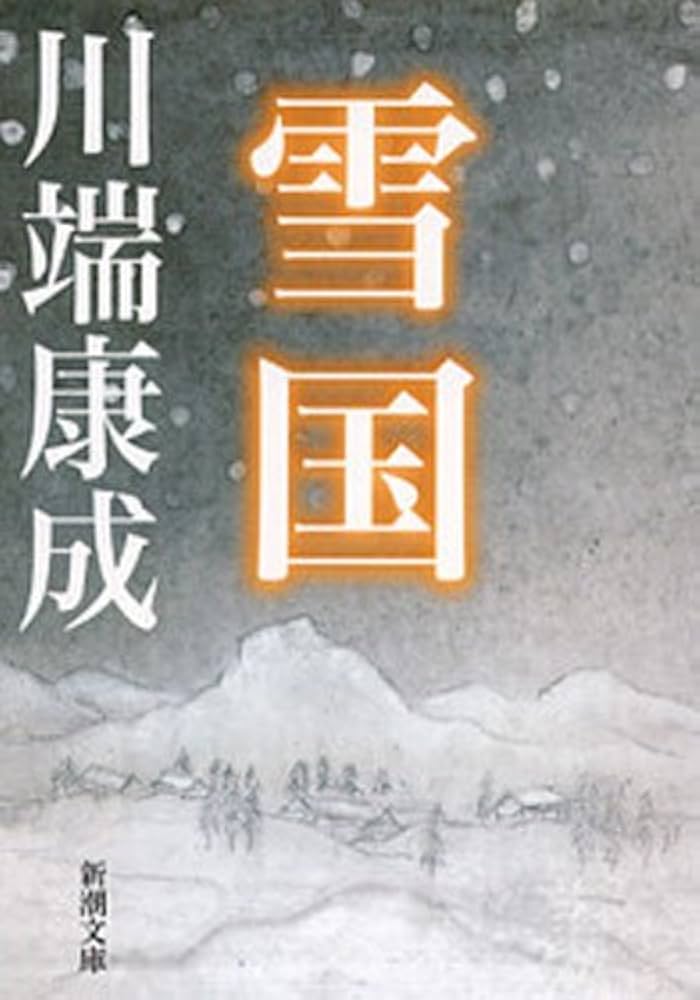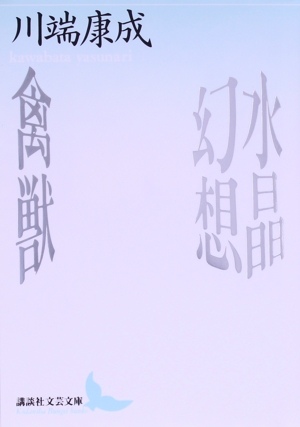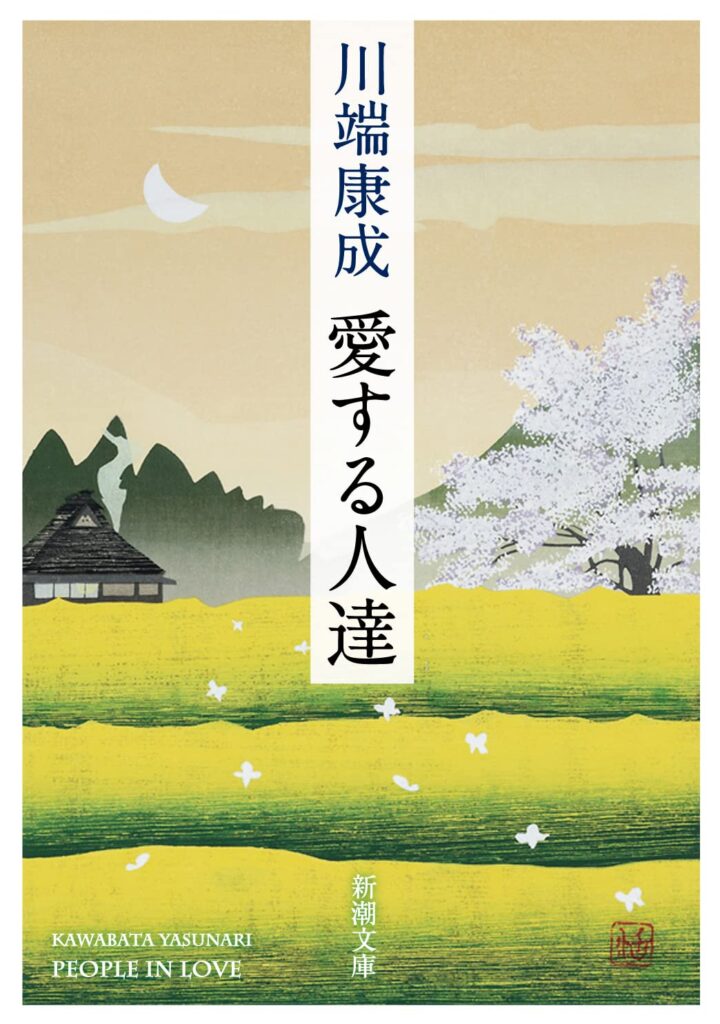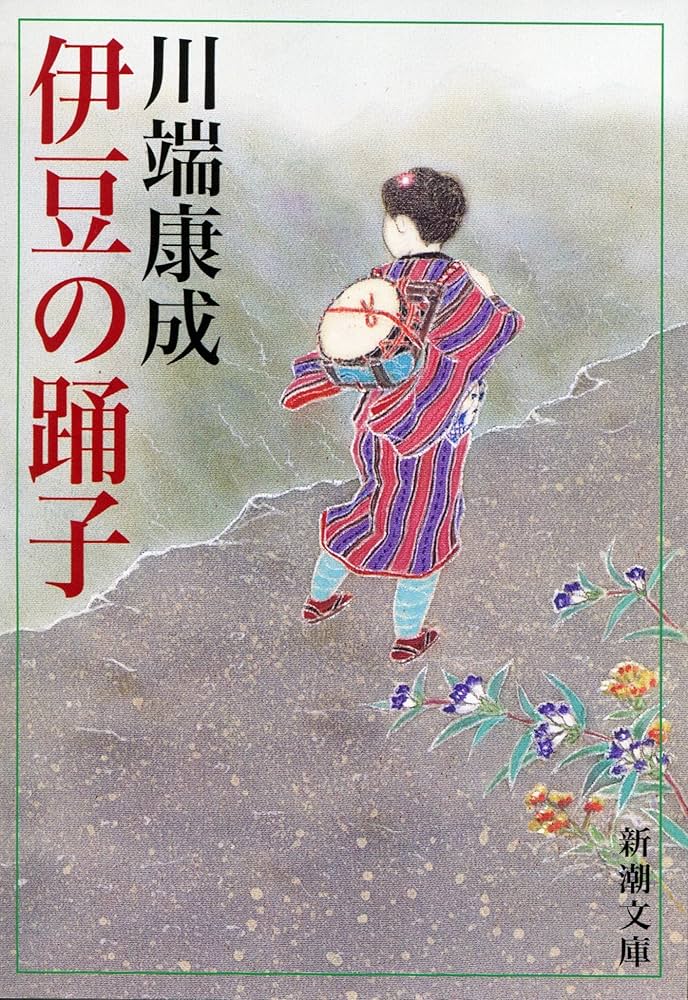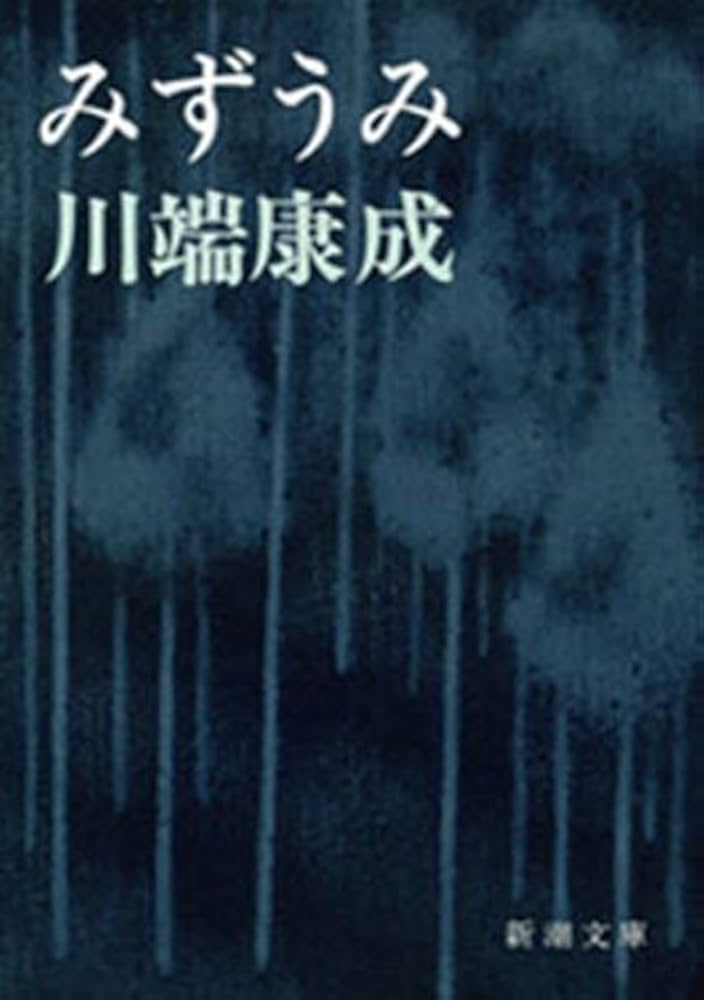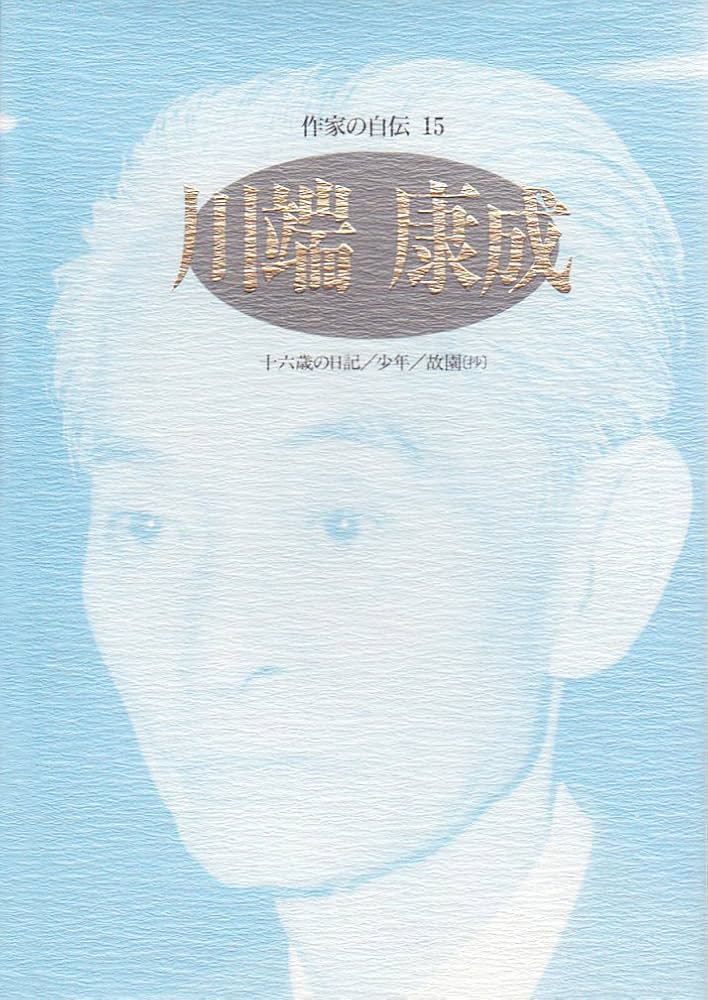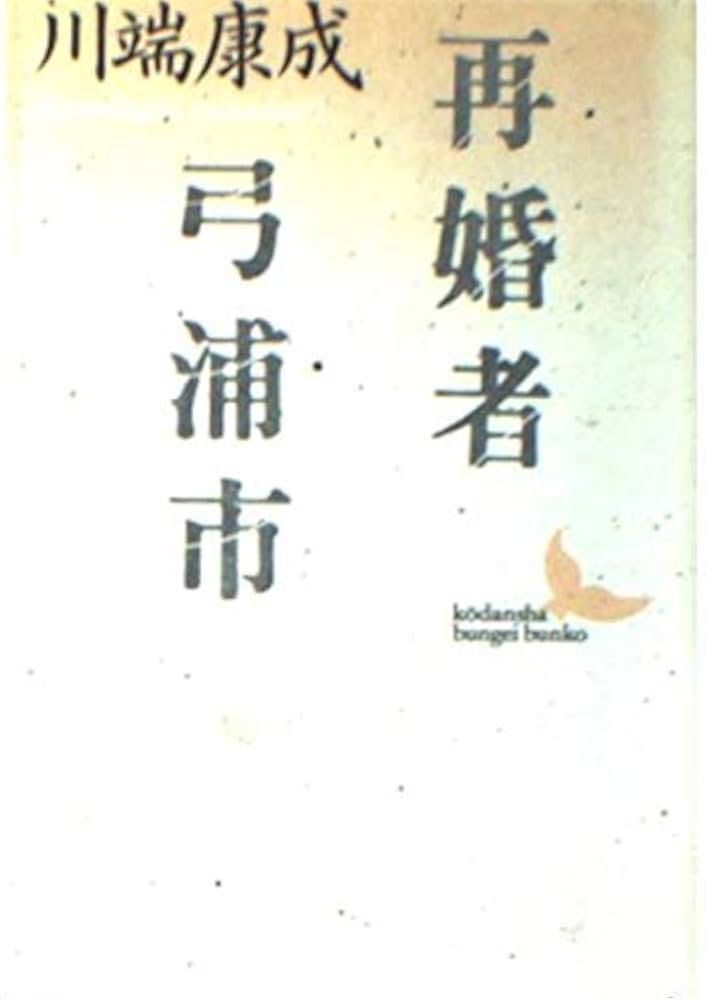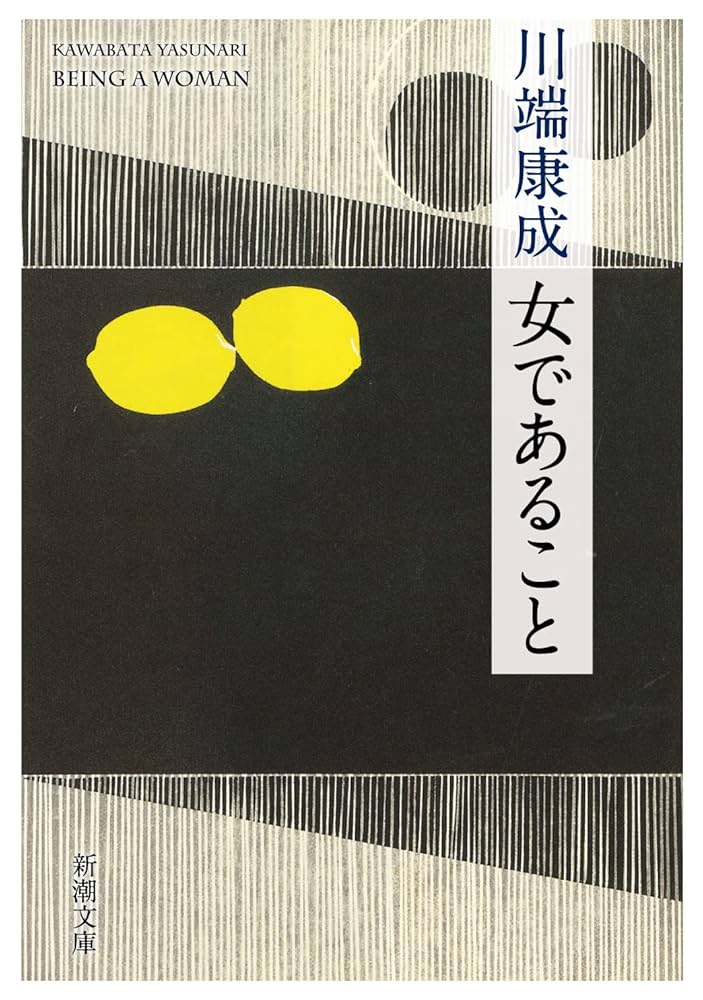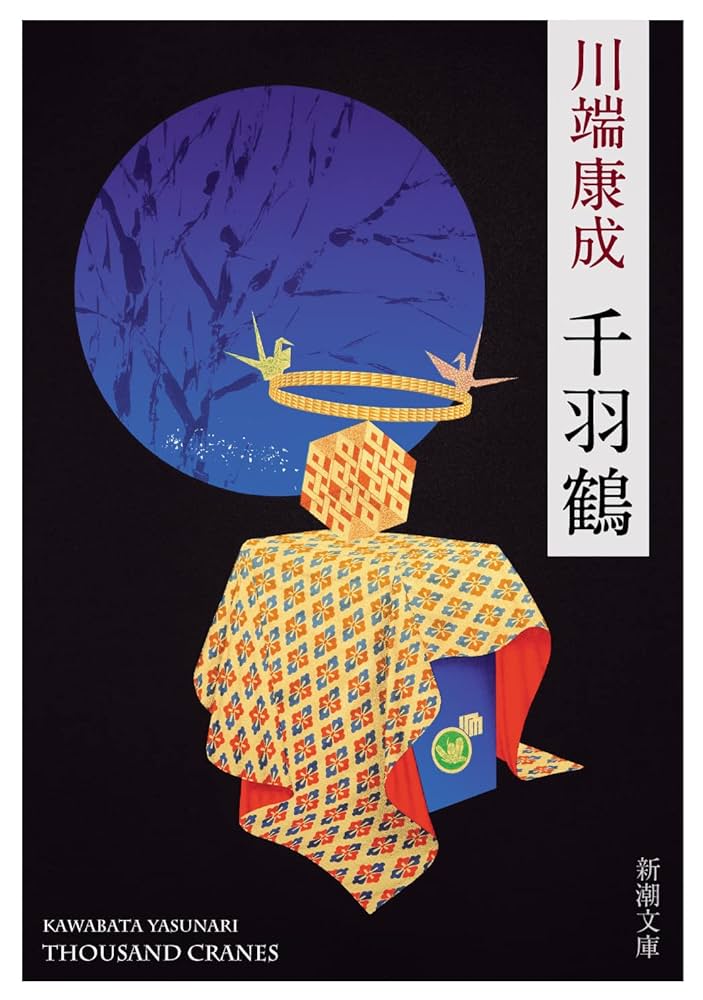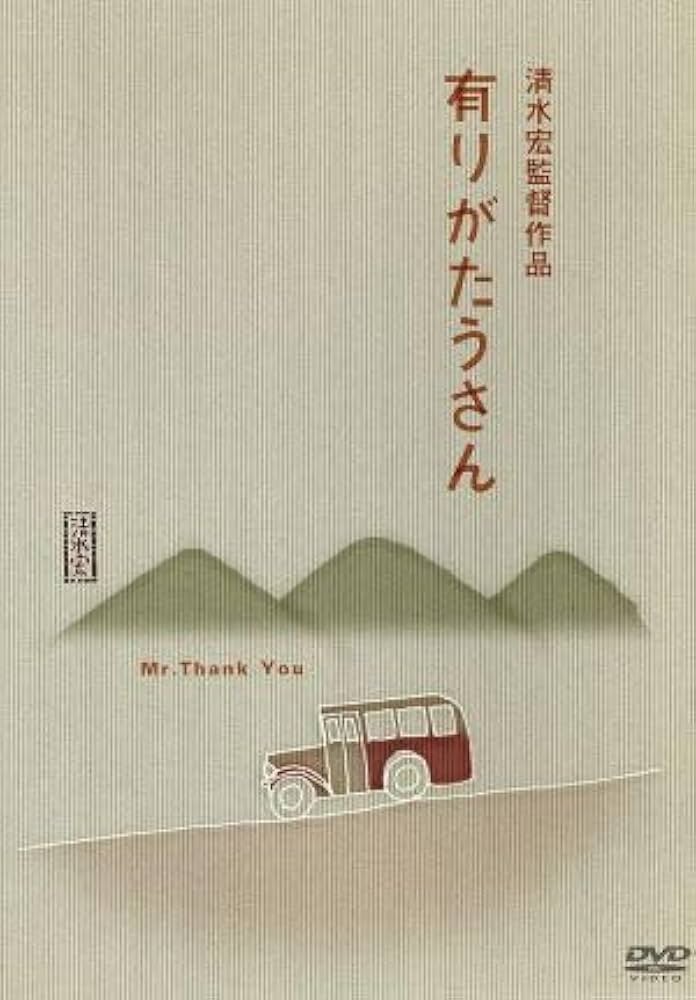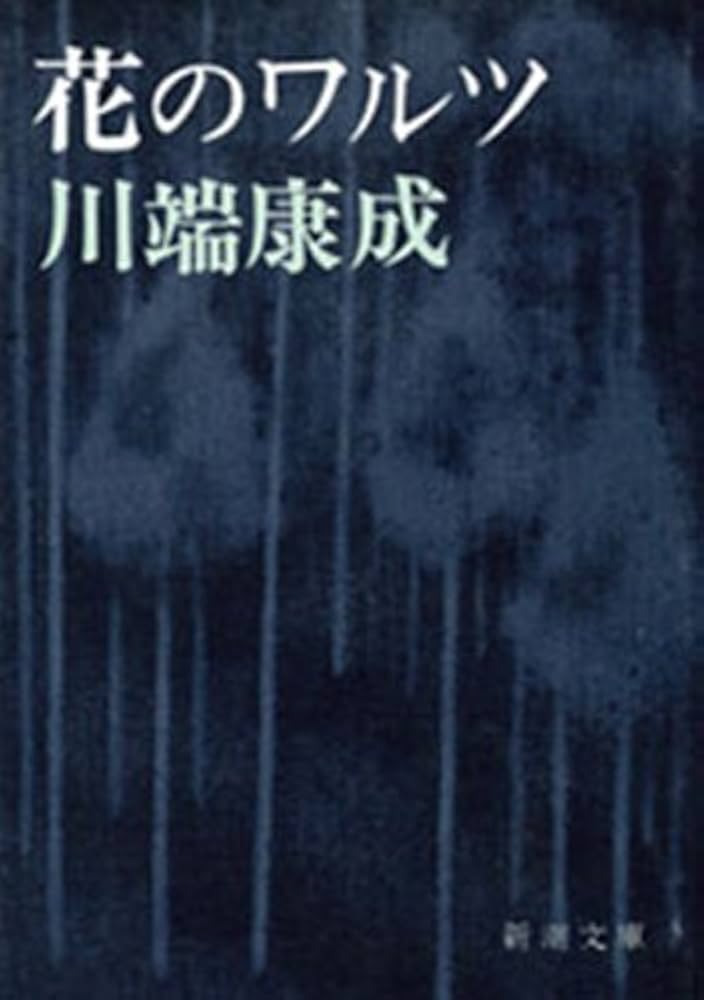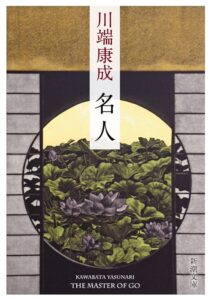 小説「名人」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「名人」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、単に囲碁の勝負を描いたものではありません。盤上の一手一手には、古い時代が終わりを告げ、新しい時代が生まれようとする瞬間の、激しいぶつかり合いが刻まれています。そこには、伝統と格式を背負い、その生涯を「芸道」に捧げた老名人の崇高な魂と、合理性と実力で未来を切り開こうとする若き挑戦者の情熱が描かれているのです。
観戦記者である「私」の目を通して語られるこの物語は、勝敗の記録を超えて、人間の尊厳とは何か、失われゆくものの美しさとは何かを、静かに、しかし深く問いかけてきます。なぜ名人は敗れなければならなかったのか。その敗北が、なぜ私たちの心をこれほどまでに揺さぶるのか。この記事では、その核心に迫っていきます。
これから、物語の詳しい流れを追いながら、その結末に隠された意味、そしてこの作品が放つ不朽の魅力について、私の解釈を交えながらじっくりと語っていきたいと思います。この静かなる死闘の物語に、しばしお付き合いいただければ幸いです。
「名人」のあらすじ
物語の幕は、引退を表明した第二十一世本因坊秀哉、終身名人の最後の対局、「引退碁」から上がります。彼は、囲碁を勝負事ではなく、精神性を極める「芸道」として捉える、まさに生ける伝説のような存在。その名人の前に、一年半にもわたる厳しいリーグ戦を勝ち抜き、挑戦者として現れたのが、若き天才棋士、大竹七段です。
この歴史的な一戦は、これまでの慣例とは異なる、極めて近代的な規則のもとで行われることになりました。持ち時間は各四十時間という長大なもの。そして、対局が中断される際には、次の手をあらかじめ紙に記して封をする「封じ手」という制度が、初めて導入されたのです。これは、絶対的な公平性を期すためのものでしたが、同時に、棋士同士の信頼よりも規則を優先する、新しい時代の到来を象徴していました。
対局は、東京、箱根、伊東と場所を移しながら、半年にわたって続きます。観戦記者である「私」は、盤上の攻防だけでなく、二人の棋士が放つ息遣いや緊張感、そして老いた名人の心身が静かにすり減っていく様を、間近で見つめ続けます。それはまるで、一つの時代の灯火が、ゆっくりと消えていくのを見守るかのようでした。
尋常ならざる緊張感の中、対局は進んでいきますが、ある局面で投じられた挑戦者の一手が、名人の心を激しく揺さぶります。その一手は、果たして勝負を左右するほどのものだったのでしょうか。そして、半年にわたる死闘の果てに、二人の棋士がたどり着いた結末とは、一体どのようなものだったのでしょうか。
「名人」の長文感想(ネタバレあり)
この物語の核心に触れるためには、まず、この引退碁が単なる一個人の最後の勝負ではなかったという事実を理解しなくてはなりません。これは、一つの時代の終わりを告げる儀式であり、二つの異なる価値観が、碁盤という宇宙で激突した壮大な記録なのです。
物語の中心にいる本因坊秀哉名人は、最後の世襲制本因坊でした。彼の存在そのものが、江戸時代から続く伝統と権威の象徴だったのです。彼は囲碁を「芸道」として捉え、礼節や品格を重んじました。その姿勢は、勝敗を超えた美しさと精神性を追求する、古き日本の求道者の姿そのものでした。
彼の引退は、単に一人の棋士が舞台を去るという意味に留まりません。彼は「本因坊」という家元制の名跡を日本棋院に譲渡し、実力によって王者を決める現代的なタイトル戦へと移行させることを決めていました。つまり、この引退碁は、名人自身の最後の戦いであると同時に、数百年の歴史を持つ伝統的な制度の、最後の幕引きでもあったのです。
この老いた名人に対峙するのが、若き挑戦者、大竹七段です。彼は、のちに囲碁界に革命を起こす木谷實をモデルとしています。大竹は、新しい時代の合理主義を体現する存在として描かれます。彼にとって囲碁は、精神的な道である以前に、論理と分析を尽くして勝利を目指す競技でした。
大竹は、古典的な定石に異を唱える「新布石」の創始者の一人であり、その棋風は力強く、革新的でした。彼が挑戦者として名人の前に立ったとき、それは単なる新旧世代の対決ではなく、囲碁を「芸道」と見る世界観と、「競技」と見る世界観の、宿命的な衝突の始まりを意味していました。
この歴史的な対局には、これまでにない厳格なルールが適用されました。特に重要だったのが「封じ手」です。対局の中断時に、次の手を書いて封筒に入れるこの制度は、公平性を担保するために導入されました。しかし、川端康成の目、そして名人の目には、この制度そのものが、神聖な芸道の世界への冒涜と映りました。
なぜなら、「封じ手」という規則の背後には、「相手が不正をするかもしれない」という不信の念が横たわっているからです。棋士の名誉や品格を信じるのではなく、規則で縛るという発想そのものが、近代的なものでした。名人が守ろうとした伝統の世界では、棋士の魂の気高さこそが、勝負の純粋性を担保する最後の砦だったのです。このルールが導入された時点で、名人の戦いは、大竹七段という一人の人間だけでなく、近代という巨大なシステムそのものに向けられていたと言えるでしょう。
物語の劇的な転換点であり、この小説のテーマを象徴するのが、「百二十一の封じ手」をめぐる事件です。挑戦者の大竹が封じたその一手は、盤面全体から見れば、ささいな探りの一手でした。しかし、この一手が開封された瞬間、名人は激しい怒りを露わにします。
名人の目には、この手が、対局の流れの中から自然に生まれたものではなく、ルールを戦術的に利用した「卑劣」なものと映りました。封じ手によって中断される二日間の時間を使い、自分だけがその後の複雑な変化を研究する時間を稼ぎ、相手には限られた対応しか考えさせない。名人は、その手を、芸道への冒涜であり、対局の調和を乱す行為だと感じ取ったのです。
これは、二つの価値観の衝突が決定的になった瞬間でした。名人の視点から見れば、それは道徳的な裏切りでした。しかし、大竹の視点からすれば、ルールの中で認められた、勝利のために最善を尽くす合理的な一手であり、何ら非難されるべきものではありませんでした。彼は規則を破ったわけではないのです。悲劇的なのは、名人が憤慨したその行為が、新しい時代の論理においては完全に正当なものだった、という点にあります。
この精神的な衝撃は、ただでさえ弱っていた名人の心身を深く蝕みました。封じ手事件の直後、名人は心臓の病で倒れ、対局は三ヶ月にもわたって中断されることになります。この中断期間が、物語にさらなる深みを与えています。語り手である「私」は、同じく病で療養していたもう一人の天才棋士、呉清源を見舞います。
呉清源もまた、大竹(木谷實)と共に新しい囲碁の時代を切り開いた革命家でした。彼もまた、かつて名人との対局で、打ち掛けをめぐる苦い経験をしています。ここで川端康成は、古い世代の象徴である名人と、新しい世代の象徴である呉清源が、同じように病に倒れている姿を描きます。これは、世代間の対立という単純な構図を超え、囲碁という芸道に命を捧げる求道者たちが、その献身ゆえに心身をすり減らしていくという、普遍的な犠牲の姿を浮かび上がらせているのです。
長い中断を経て、対局は伊東で再開されます。しかし、封じ手事件が残した心の傷は癒えていませんでした。精神的に動揺し、肉体的にも衰弱した名人は、ついに決定的な敗着となる一手(白百三十手目)を打ってしまいます。それは、普段の冷静な名人であれば、決して打つことのなかったであろう一手でした。
この一失は、封じ手事件が引き起こした精神的な動揺と、決して無関係ではありませんでした。芸道への冒涜に対する怒りが、神の領域にまで達していたはずの彼の判断力を曇らせ、集中力を奪ったのです。盤上ではすでに勝敗が決しているにもかかわらず、対局は二百三十七手まで続けられ、1938年12月4日、ついに半年に及ぶ死闘は幕を閉じます。結果は、大竹の五目勝ち。「不敗の名人」は、その最後の対局で、静かに敗れたのです。
名人の敗北は、個人の敗北ではありませんでした。それは、精神性と美意識を重んじた「芸道」という伝統的な世界観が、効率と合理性を追求する近代の競争社会の前に、静かに消え去っていく姿の象徴でした。名人の負けは、避けられない運命だったのかもしれません。なぜなら、勝負のルールだけでなく、「何が優れているか」という価値の基準そのものが、変わってしまったからです。
この物語は、観戦記者である「私」、すなわち川端康成自身の、美と死に対する哲学を色濃く反映しています。彼は、名人の敗北そのものの中に、悲劇的で崇高な美しさを見出しています。時代の流れに抗い、自らの信じる「芸」に殉じたその姿、そして敗北を静かに受け入れるその威厳にこそ、名人の真の価値が立ち現れると、川端は描いているのです。
この作品は、もともと新聞に連載された観戦記でした。しかし、川端は十数年という長い歳月をかけて、事実の記録を、深遠な文学作品へと昇華させました。彼の文章は、棋士たちの息遣い、石を打つ指の感触、息詰まるほどの静寂といった、目に見えないものを読者に伝えます。彼は勝敗の行方だけでなく、その死闘が放つ「気魄」や「呼吸」を描こうとしたのです。
この過酷な引退碁が、名人の命を縮めたと言われています。彼は、この対局から一年余り後に、この世を去りました。川端康成は、名人が亡くなるその場に偶然居合わせ、その死顔を写真に収めるという、運命的な最後の目撃者となります。象徴的な死である引退碁での敗北を記録し、そして肉体的な死をも見届けたこの経験が、この不朽の物語を完成させる最後の動機となったのです。
こうして生まれた『名人』は、単なる囲碁の物語ではなく、芸術とは何か、人生とは何か、そして、避けられない終焉が持つ哀しい美しさとは何かを問いかける、普遍的な瞑想録となりました。勝者がいれば、必ず敗者が生まれる。しかし、敗れることの中にこそ、人間の真の尊厳や美しさが宿ることもある。この物語は、その静かな真実を、私たちに教えてくれているように思います。
まとめ
小説「名人」は、囲碁の引退対局を舞台に、一つの時代の終焉と、そこに生きた人間の魂の気高さを描いた、類まれな作品です。伝統と格式を重んじる老名人と、合理主義を掲げる若き挑戦者。二人の対立は、単なる勝負を超え、古き日本と新しい日本の価値観の衝突そのものでした。
この記事では、物語の詳しい展開と結末、つまりネタバレに触れながら、その背景にある深い意味を考察してきました。特に、対局の運命を決定づけた「封じ手」事件は、二つの世界の断絶を象徴する、重要な出来事として描かれています。名人の敗北は、避けられない時代の流れへの、悲しくも美しい降伏だったのです。
この物語は、観戦記者であった作者、川端康成の美学が見事に結晶した作品でもあります。彼は、勝者の栄光ではなく、敗者の姿にこそ、失われゆくものの儚い美しさ、そして人間の尊厳を見出しました。その静かな眼差しが、単なる対局記録を、時代を超える文学へと昇華させているのです。
もしあなたが、単なる勝ち負けの物語ではない、人間の生き様や時代の移り変わりを感じさせる深い物語を求めているのなら、この『名人』は、きっと心に残る一冊となるでしょう。静寂の中に響く石の音に、耳を澄ませてみてはいかがでしょうか。