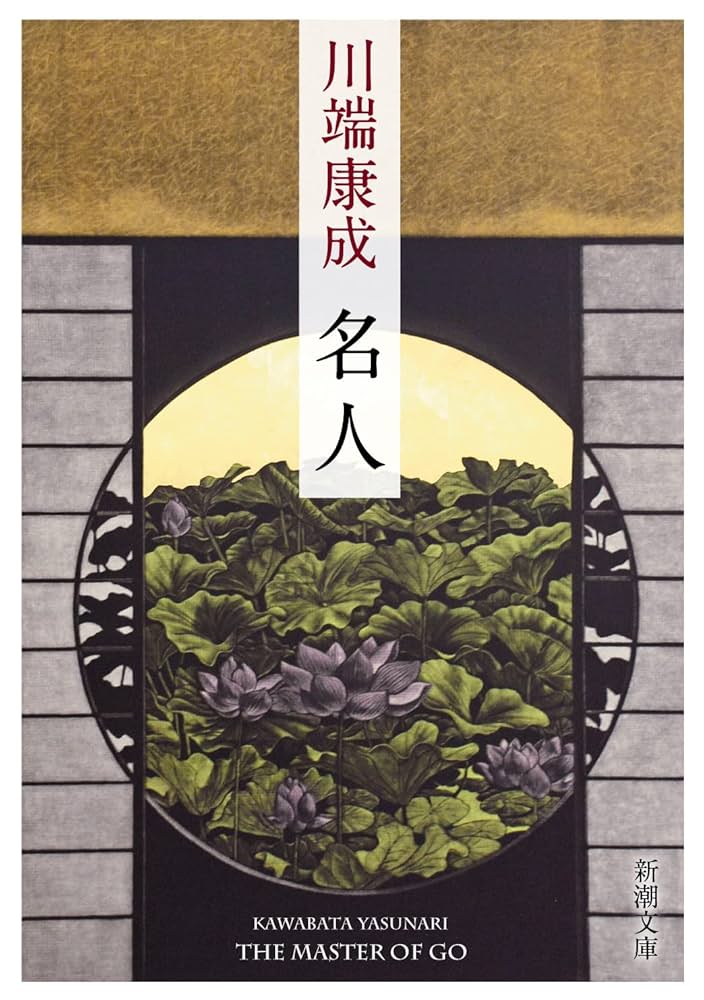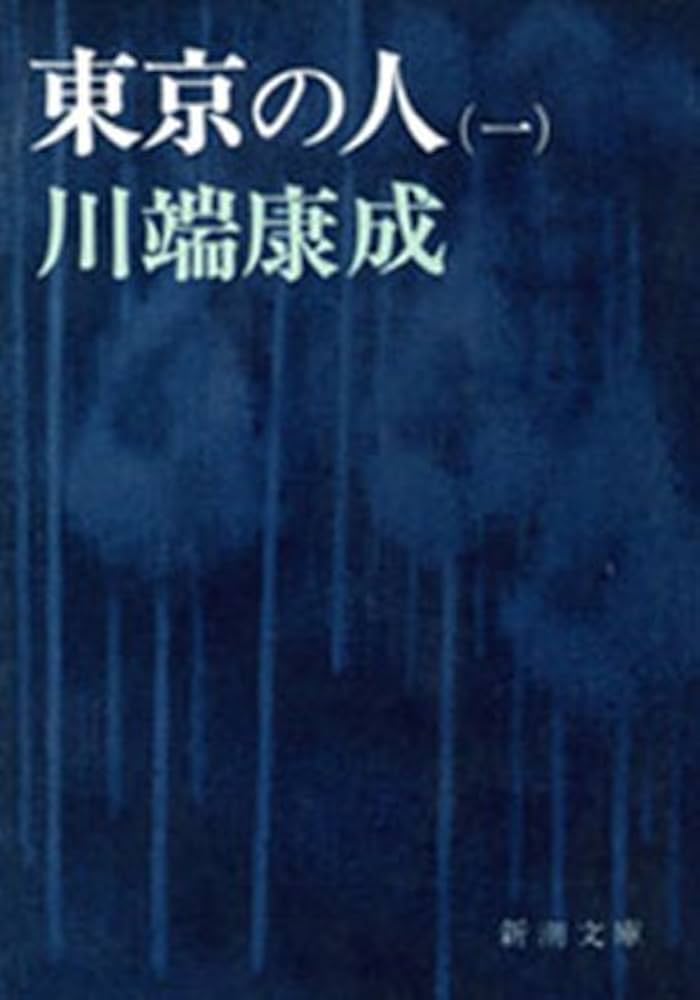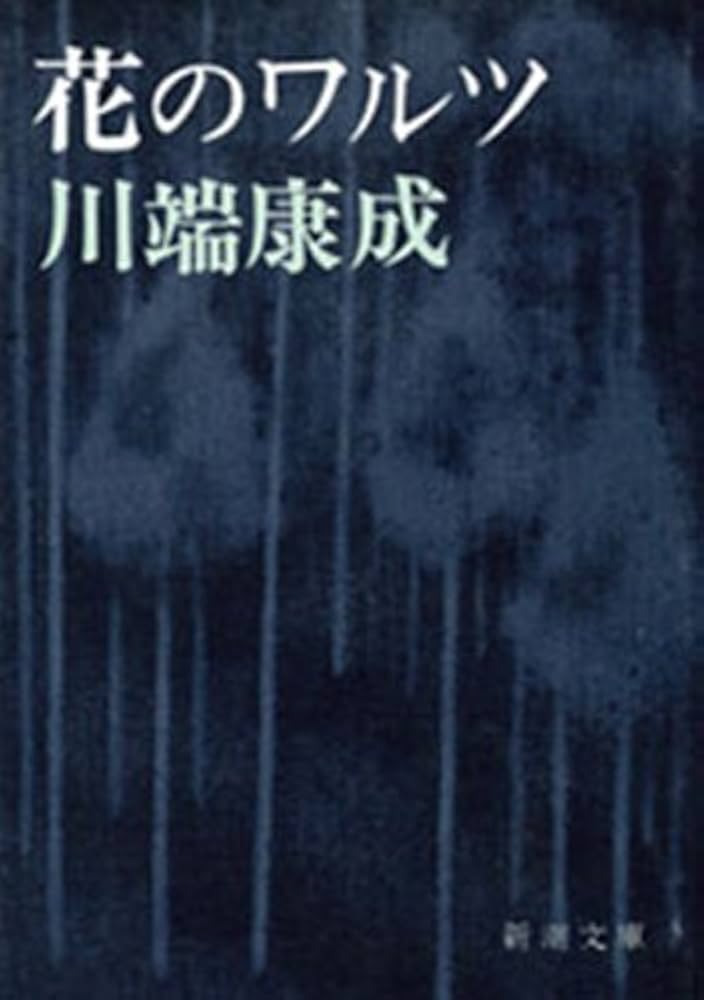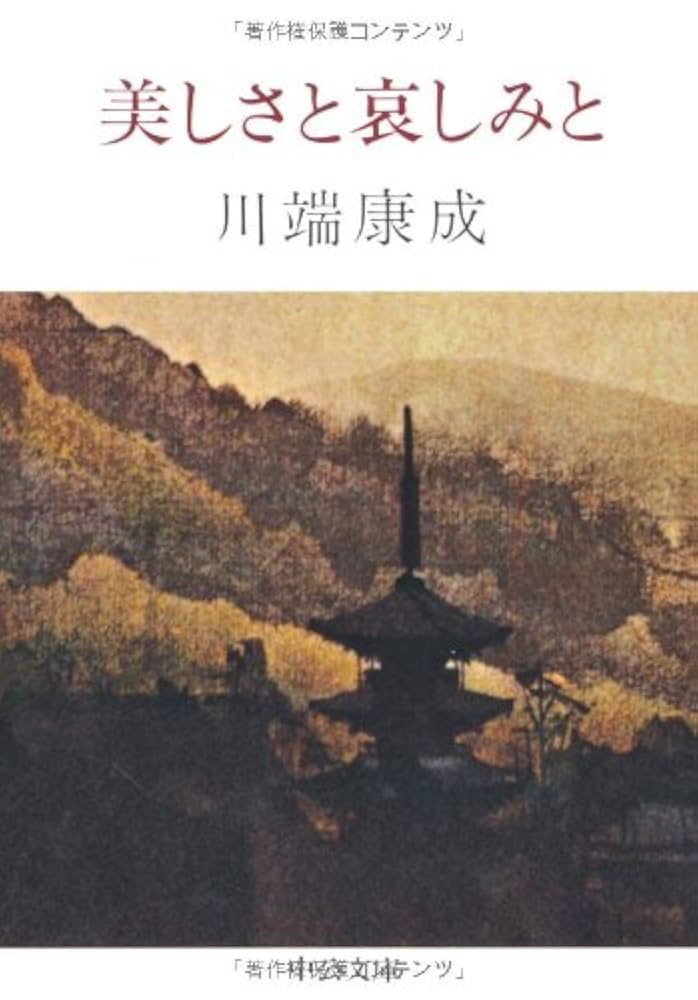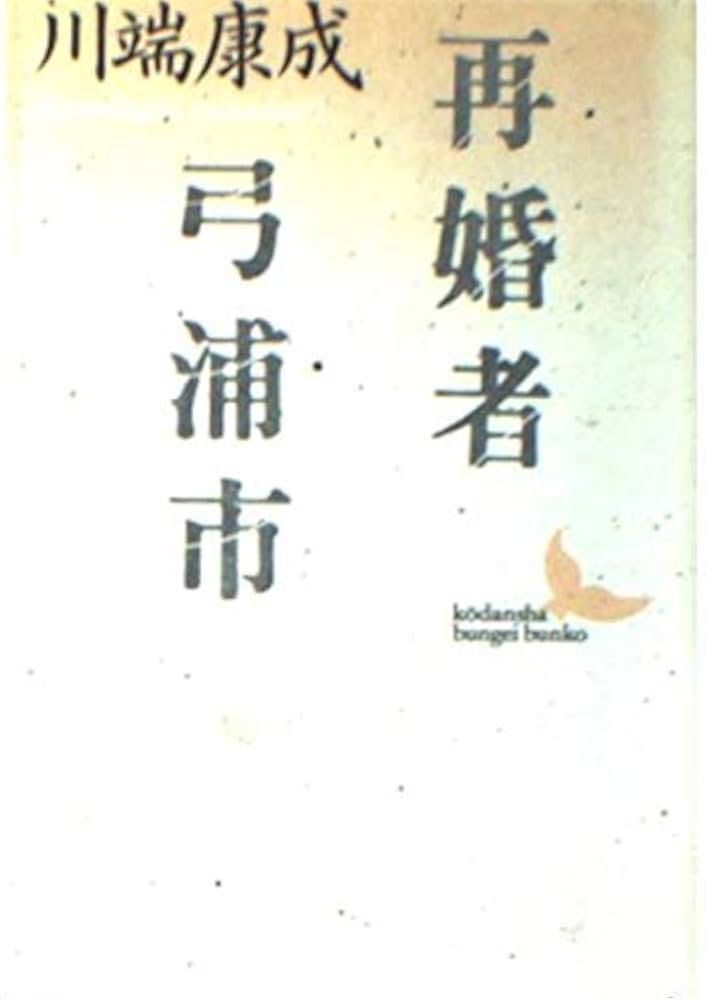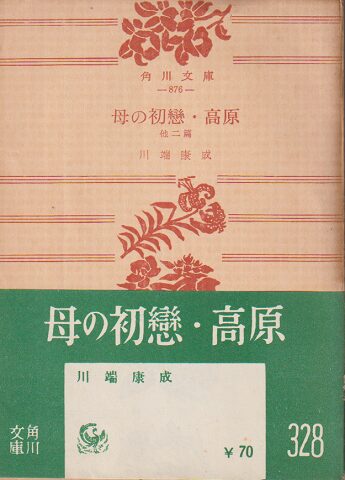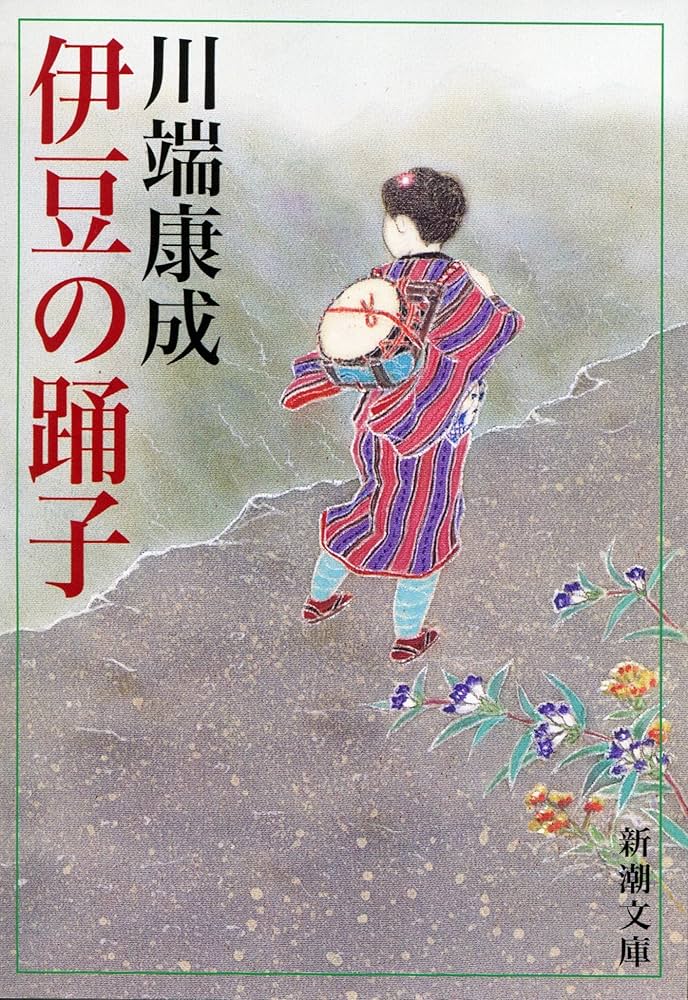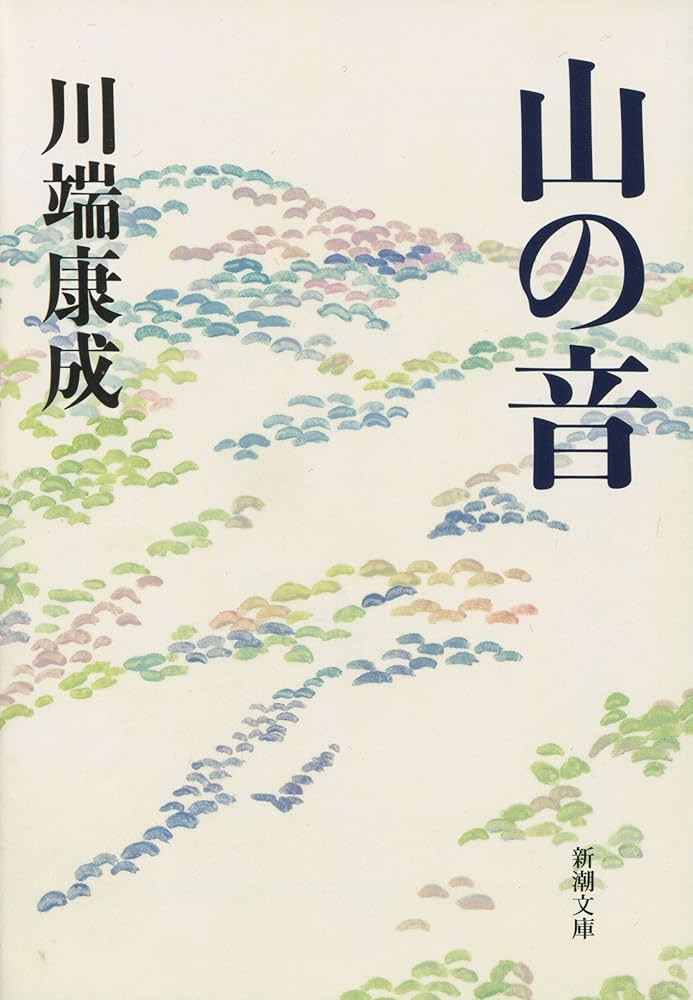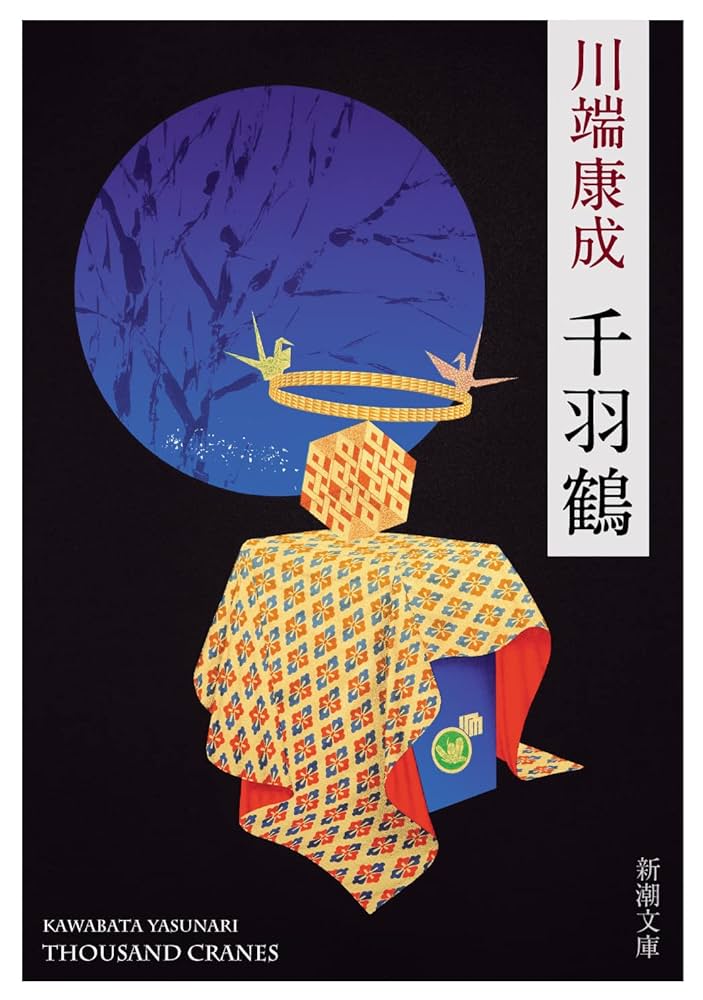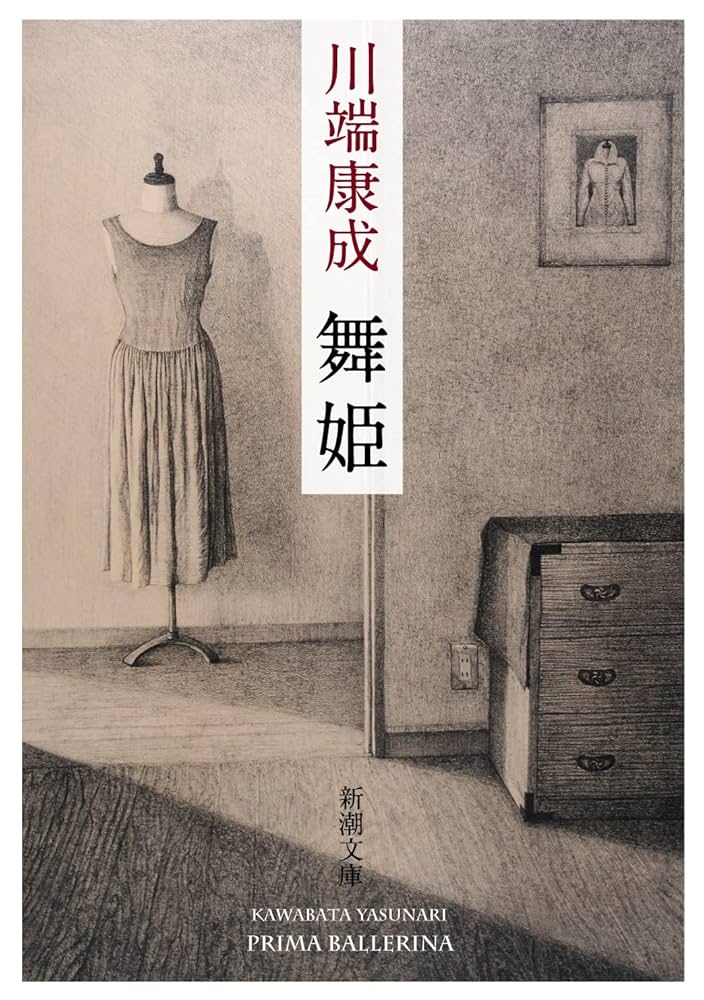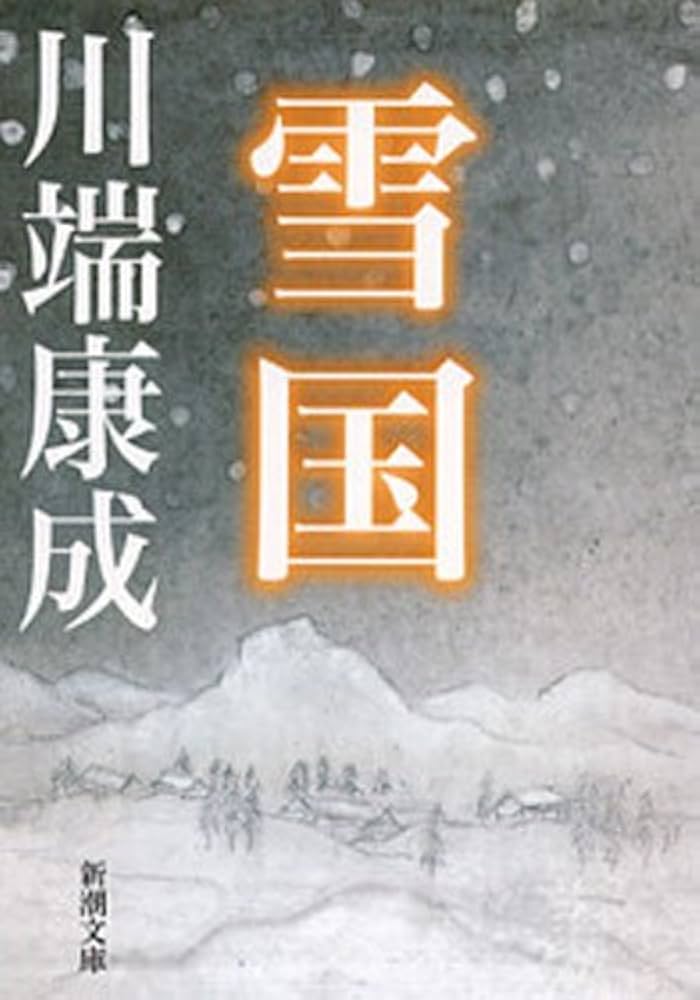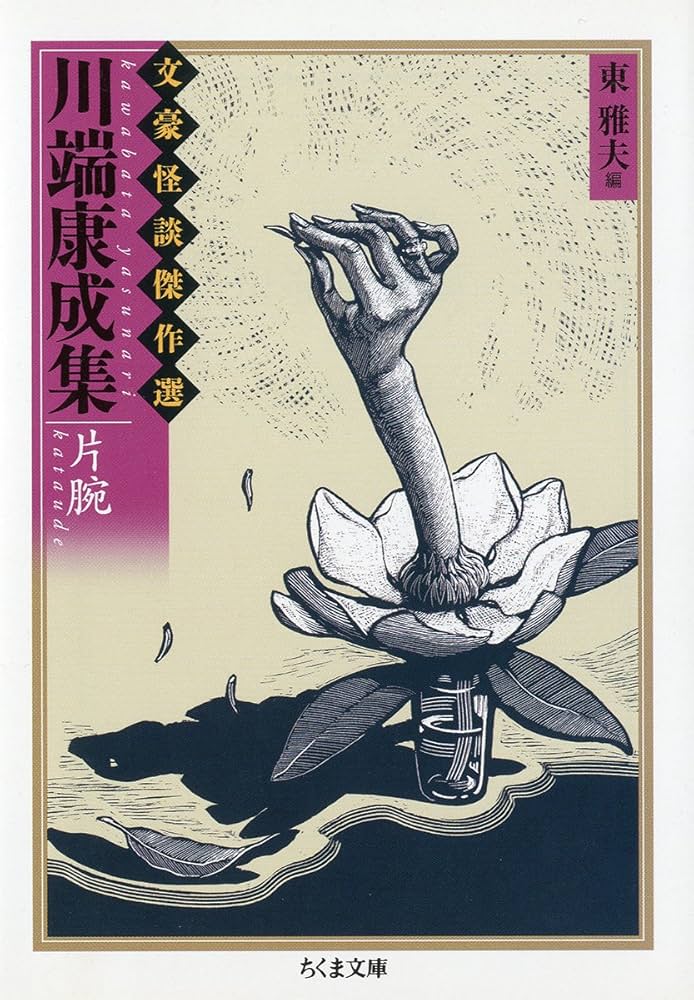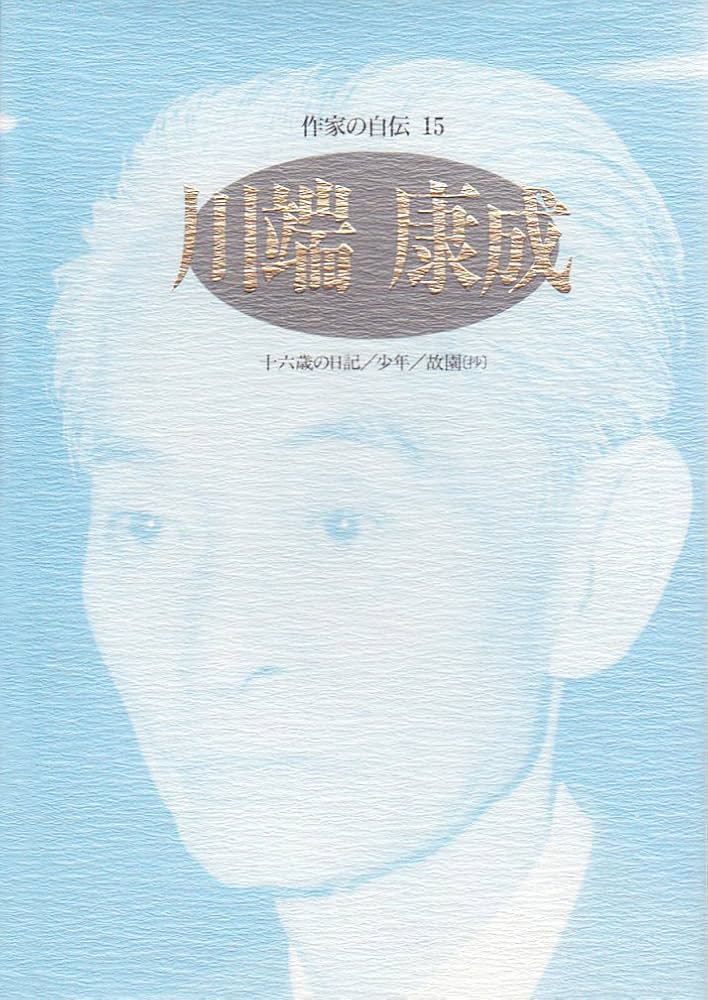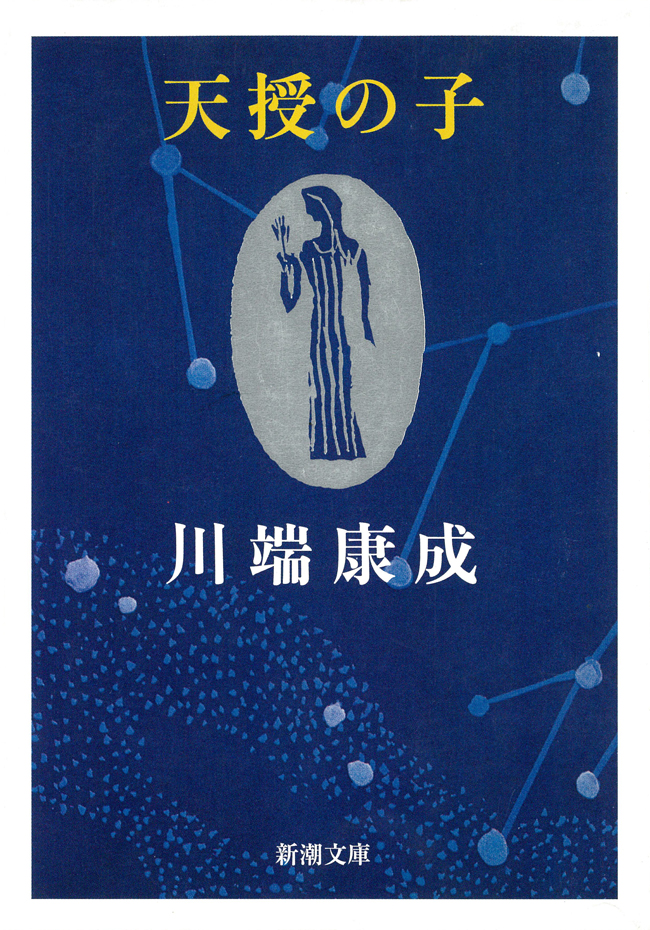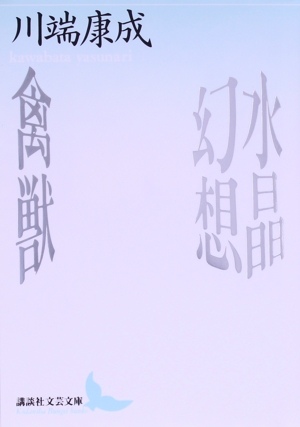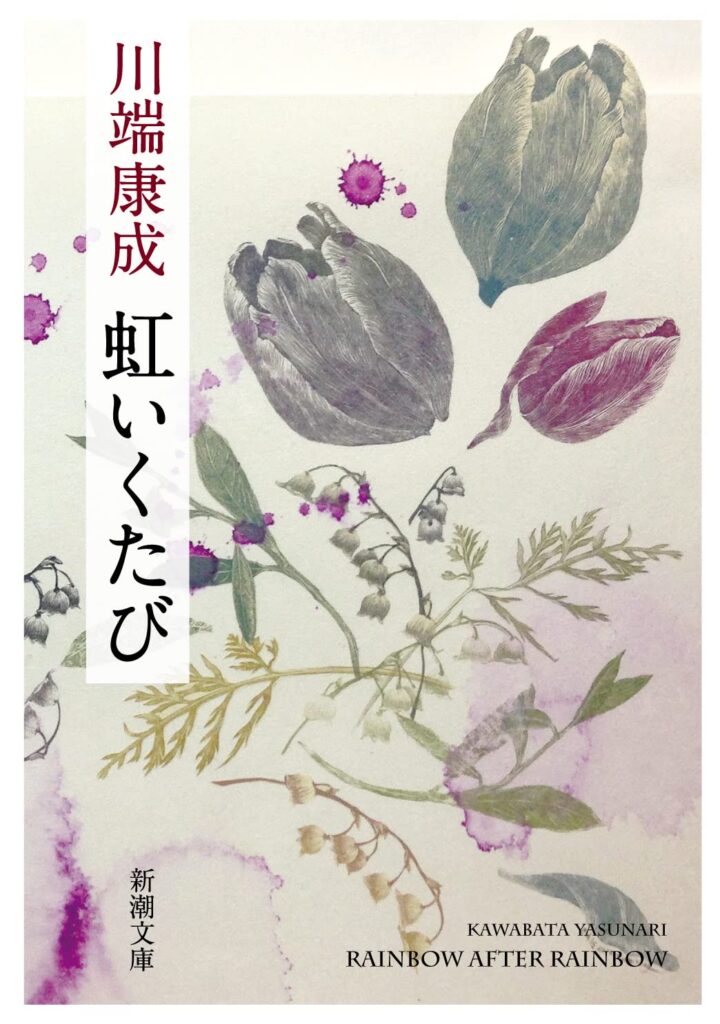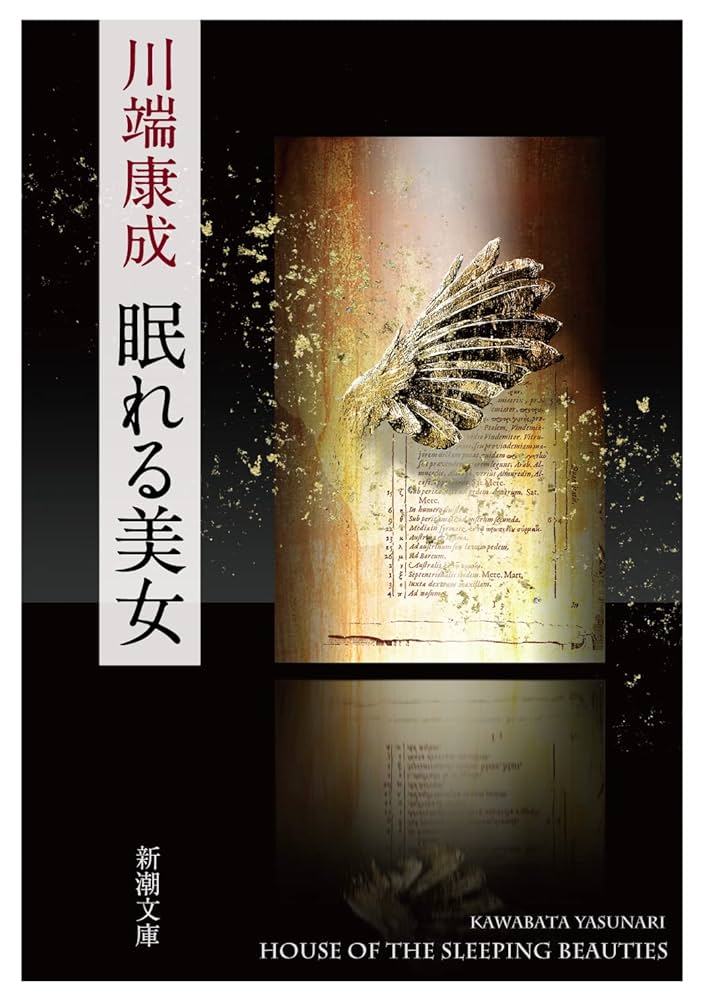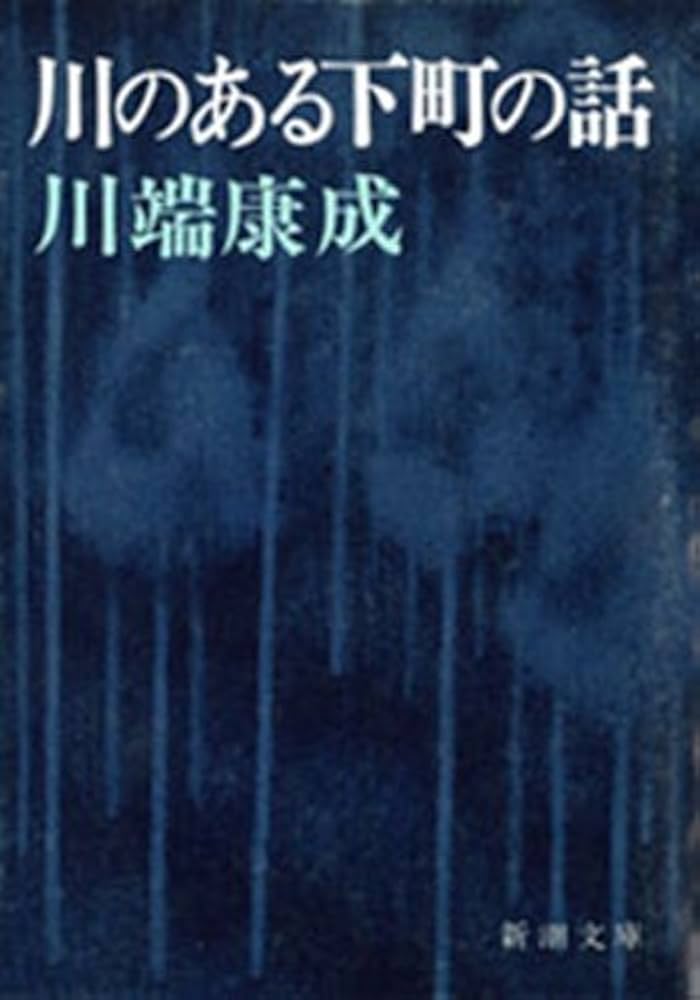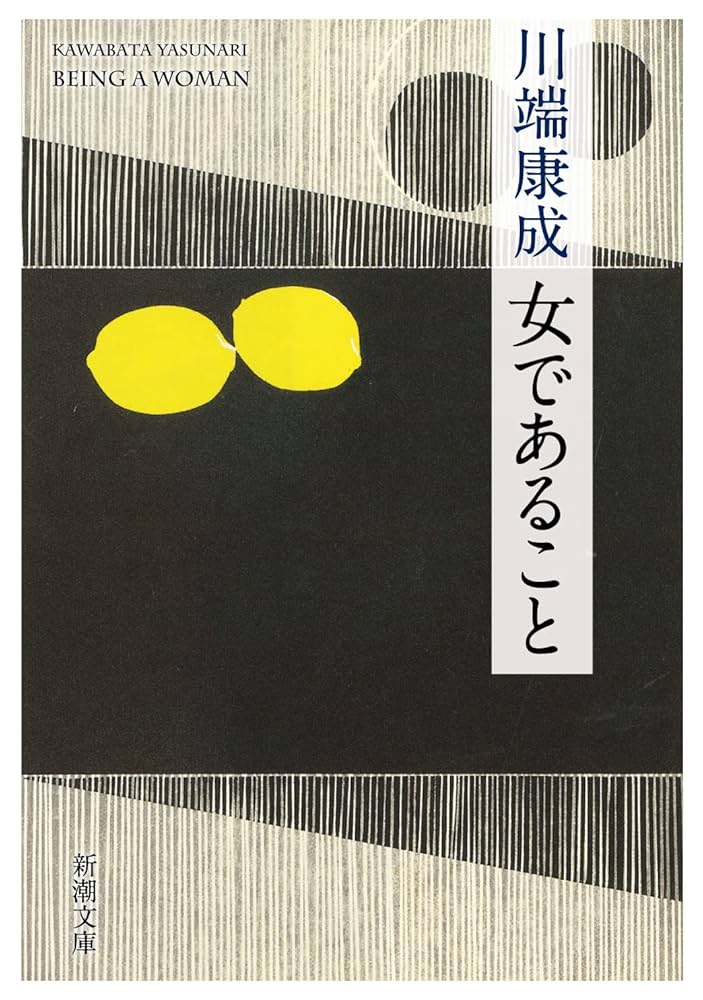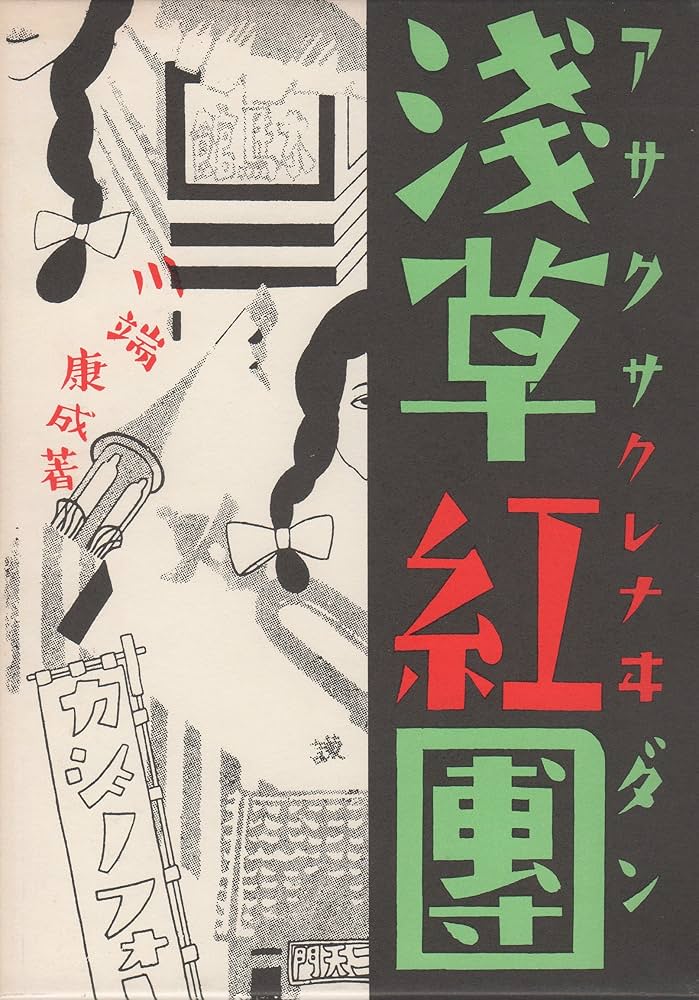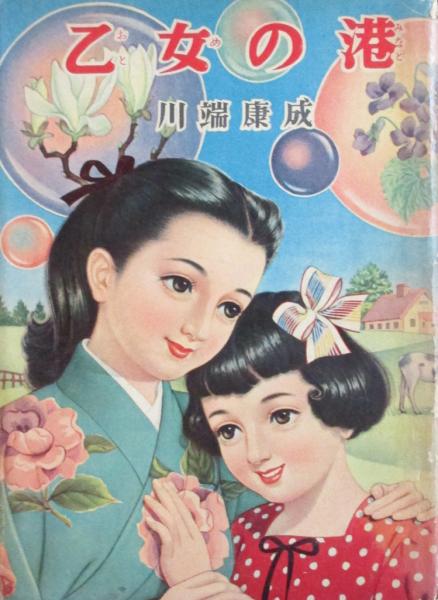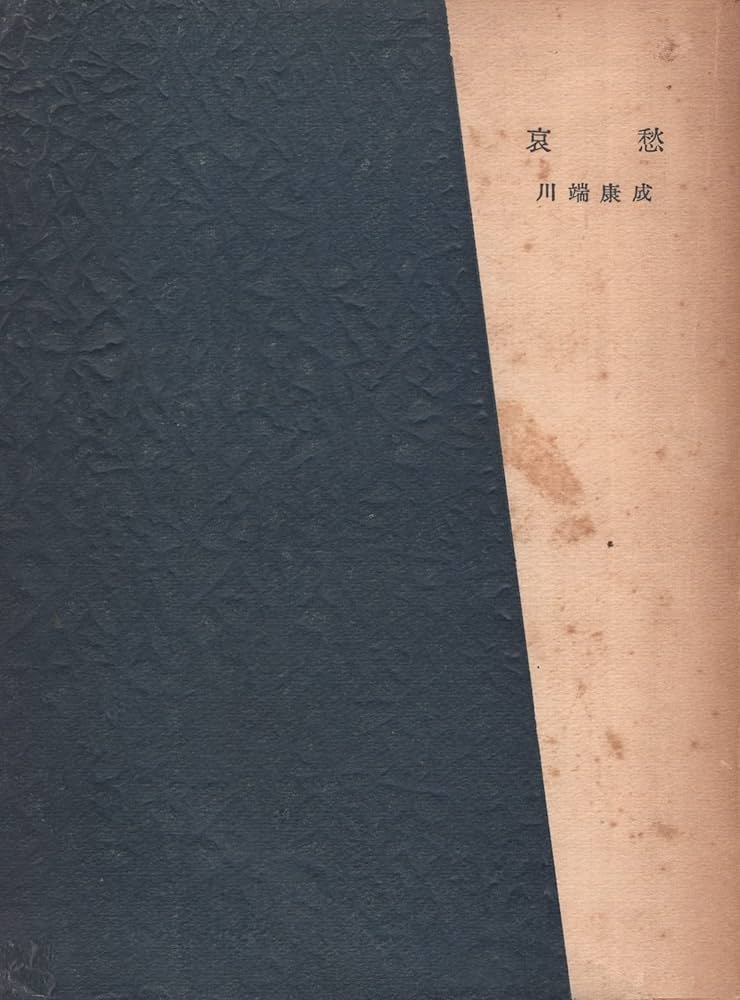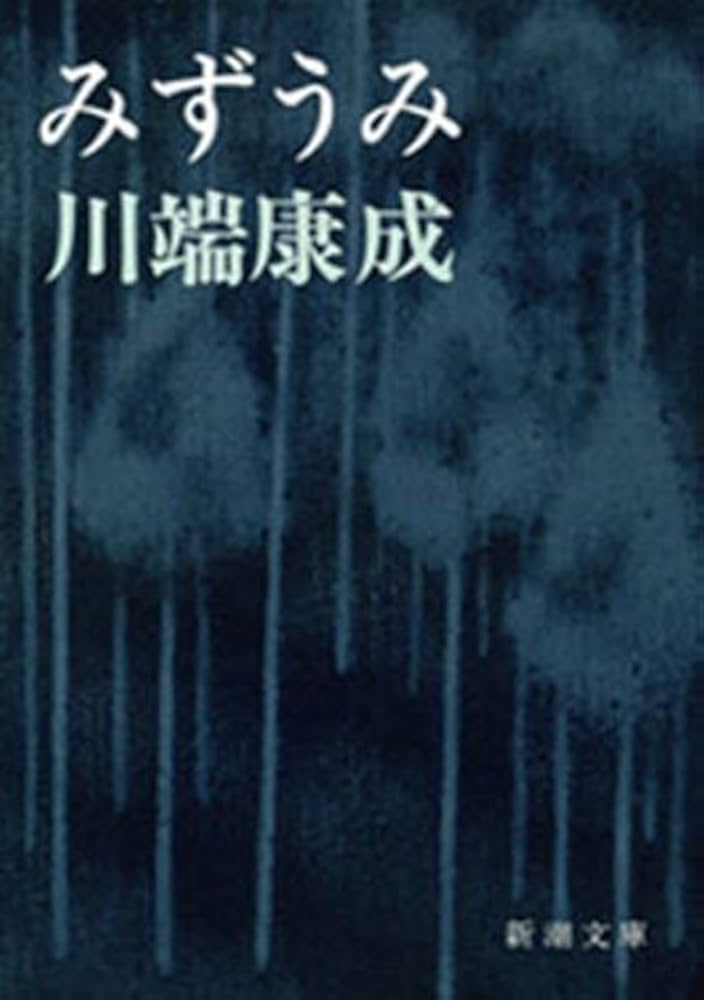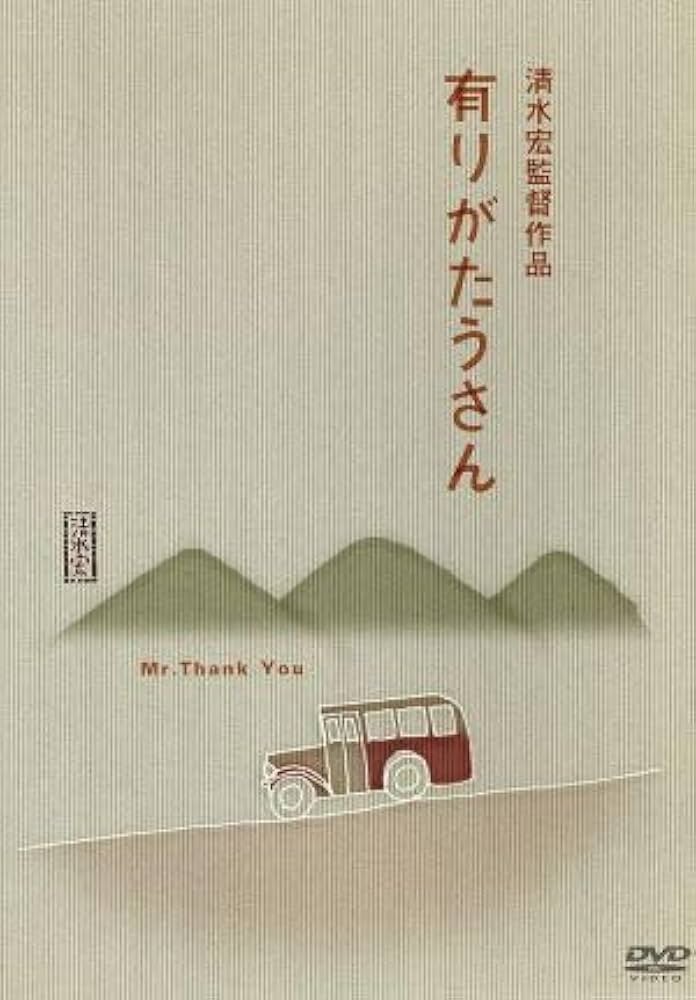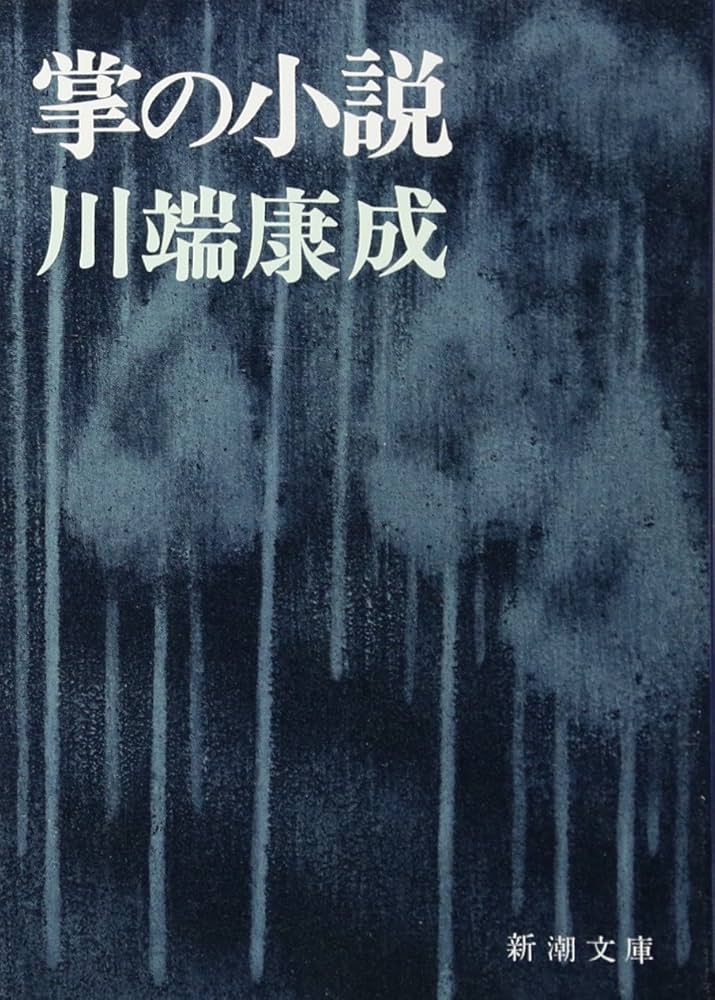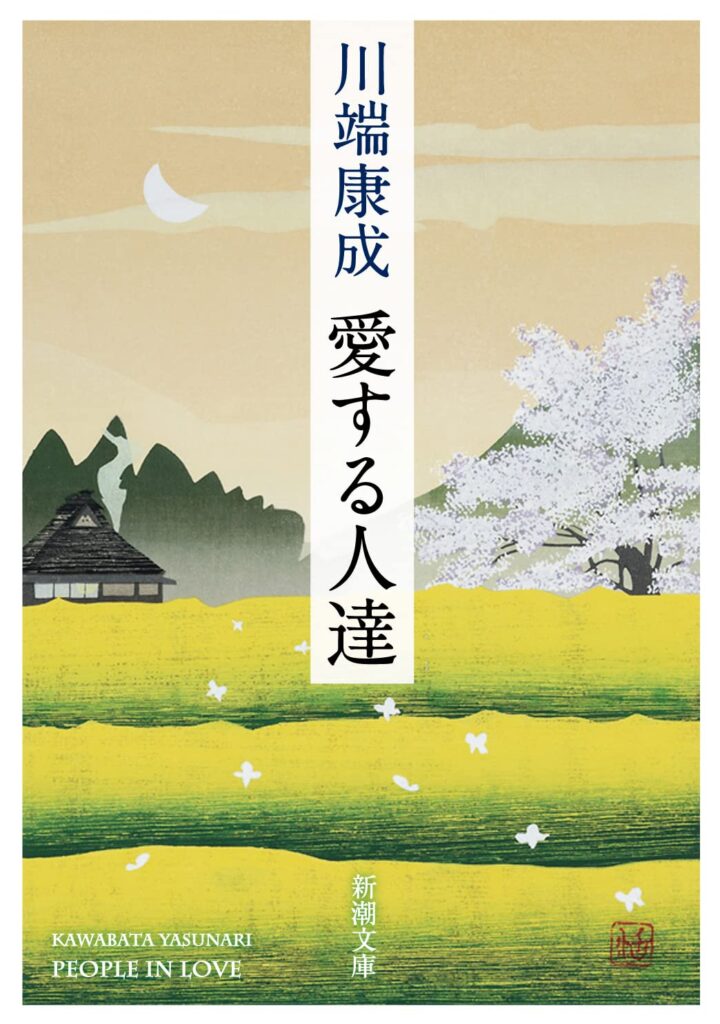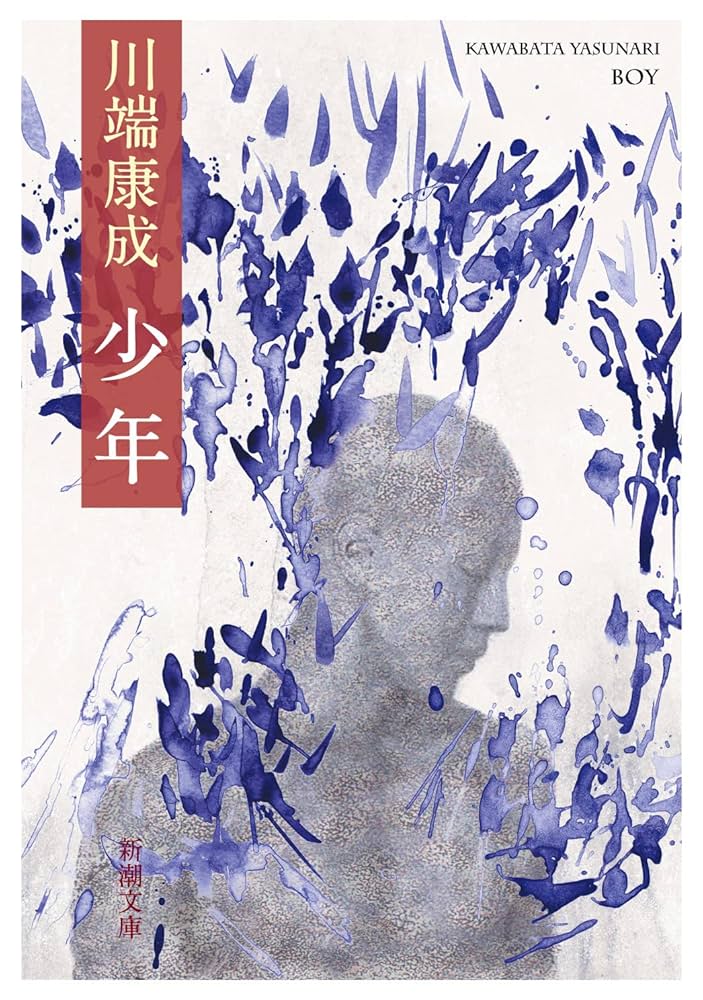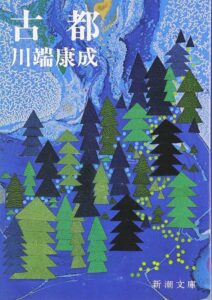 小説「古都」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「古都」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
本作は、ノーベル文学賞作家である川端康成の代表作の一つで、古都・京都を舞台に、運命に導かれるように出会った双子の姉妹の物語を描いています。美しくもはかない姉妹の絆を通して、日本の伝統的な美意識や、変わりゆく時代の中での人の心の機微が、繊細な筆致でつづられています。
物語の中心にいるのは、京都の老舗呉服問屋の一人娘として、何不自由なく育った佐田千重子です。しかし彼女は、自分が「捨て子」であったという事実を胸に秘め、どこか漠然とした孤独感を抱えて生きています。この秘められた出自が、物語全体の切ない色合いを決定づけているのです。
この記事では、まず物語のあらましをご紹介し、その後で物語の核心に触れるネタバレを含んだ深い感想を詳しく語っていきます。川端康成が描いた美しくも哀しい世界を、一緒に旅していただければ幸いです。
「古都」のあらすじ
物語の舞台は、歴史と伝統が息づく京都。中京の室町で呉服問屋を営む佐田家に、千重子という美しい娘がいました。両親の深い愛情のもとで育った彼女ですが、実は二十年前の祇園祭の夜に、神社の桜の下に捨てられていた子でした。その事実は、千重子の心に静かな影を落としています。
ある春の日、千重子は友人と北山杉の里を訪れます。そこで彼女は、自分と瓜二つの顔立ちをした村娘とすれ違います。言葉を交わすことはありませんでしたが、その幻のような出会いは千重子の心に強く焼き付き、言いようのないざわめきをもたらしました。自分の出自と何か関係があるのではないか、という予感が彼女の胸をよぎります。
そして、夏の祇園祭の宵山。祭りの喧騒の中、千重子は八坂神社の御旅所で、熱心に祈りを捧げる一人の娘を見つけます。それは、北山杉の里で出会った、あの自分そっくりの娘でした。娘の名前は苗子。二人は運命に引き寄せられるように、言葉を交わします。
この劇的な再会によって、二人が生き別れの双子の姉妹であったことが明らかになります。しかし、喜びも束の間、呉服問屋の令嬢と、山で働く労働者の娘という、あまりにも違う互いの境遇が、二人の間に見えない壁を作っていくのでした。二人の運命は、ここから大きく動き始めます。
「古都」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の結末にも触れる詳しい感想になります。ネタバレを避けたい方はご注意ください。この物語が持つ深い魅力と、心に残る情景について、存分に語っていきたいと思います。
物語の冒頭、千重子の家の庭にある楓の古木が描かれます。その幹には二つのくぼみがあり、それぞれにすみれが根付き、春になると可憐な花を咲かせます。千重子はこのすみれを見ながら、「上のすみれと下のすみれは、会うことがあるのかしら」と、ふと思うのです。この何気ない独白こそ、物語全体の運命を暗示しているように私には感じられました。まだ見ぬ双子の片割れへの、無意識の思慕が表れているのではないでしょうか。楓の古木は姉妹の生命の源、つまり母を象徴し、少し離れた二つのくぼみは、二人が育った異なる環境を物語っているようです。この冒頭の情景だけで、運命的な別離と、根源的な孤独、そして再会への渇望というテーマが、静かに提示されているのです。
物語の中で、京都という街は単なる背景ではありません。父・太吉郎は、京都で育つ楠を「大きい盆栽みたいな感じ」と表現し、千重子はそれを受けて「それが、京都やおへんの?」と応じます。ここで示されるのは、京都の美が人の手によって丹念に磨き上げられた「栽培された美」であるという認識です。この考え方は、物語全体を貫く重要な対比軸となっています。
その対極にあるのが、苗子の暮らす北山杉の里の自然です。天に向かって真っ直ぐに伸びる北山杉は、人の手が加えられてはいますが、その姿は素朴で力強い生命力に満ちています。これは、後に明らかになる苗子の人格そのものを象徴しているように思えます。磨き上げられた千重子の美しさと、野に咲く花のような苗子のたくましい美しさ。二人の姉妹は、それぞれが異なる美のあり方を体現しているのです。この対比が、物語に深い奥行きを与えています。
姉妹が劇的な再会を果たすのが、祇園祭の夜です。祇園囃子が響き、提灯の灯りが揺れる非日常的な空間で、二人はついに出会います。苗子は、生き別れの姉に会いたい一心で「七度まいり」を行っていました。彼女の切なる祈りが、この奇跡的な再会を引き寄せたのです。この場面の描写は本当に見事で、読んでいるこちらも祭りの熱気と喧騒の中にいるような気持ちになります。
「あんた、姉さんや」。苗子の純粋な叫びで、二人の血の繋がりが確かめられます。しかし、その直後、苗子は千重子に対して「お嬢さん」と、敬称を使い始めます。この一瞬の言葉の変化に、二人の間に横たわる社会的・経済的な隔たりの残酷さが凝縮されていると感じました。血という神聖な絆が確認された瞬間に、社会という現実が冷酷に二人を引き離そうとする。この出会いの場面は、二人の喜びと、これから待ち受ける悲劇の両方をはらんだ、本作屈指の名場面だと思います。
姉妹の再会は、彼女たちを取り巻く人々の心にも影響を及ぼします。特に重要なのが、西陣の帯職人・秀男の存在です。彼は当初、千重子の気品ある美しさに憧れていました。しかし、祇園祭の夜に苗子を千重子と見間違えたことから、三人の関係は複雑に絡み合っていきます。秀男は、苗子の素朴な純粋さに惹かれながらも、その面影に常に千重子の姿を重ねてしまうのです。
この揺れ動く恋心は、秀男が織る帯に象徴されます。彼は、帯を織る時「千重子と苗子とが、一つになってしまう」と語ります。この帯は、一人の姉を想いながら、もう一人の姉に捧げられるという、混乱した愛情の結晶なのです。千重子の幼馴染である真一と、その兄・竜助からの縁談も絡み合い、姉妹の恋模様は切なく展開していきます。ここでのネタバレになりますが、結局どの恋も成就しない結末が、また物悲しさを誘います。
夏に千重子が苗子を訪ねて北山の村へ行く場面は、二人の性質の違いを鮮やかに描き出しています。夕立に見舞われた際、たくましい苗子が華奢な千重子を自分の体でかばう姿は、一般的な姉妹の役割が逆転しており、非常に印象的です。労働の中で培われた苗子の強さと、大切に育てられた千重子の繊細さが、この行動一つで明確に示されます。
また、ここでの二人の会話は、価値観の根本的な違いを浮き彫りにします。人の手で育てられた北山杉を「切り花」のようだと評し、原生林を好む苗子。彼女の自然への深い畏敬の念と、人間が作り出す文明への静かな懐疑は、千重子を驚かせます。育った環境が、これほどまでに人の内面を形作るのかと、改めて考えさせられる場面でした。
物語が進むと、千重子への想いを断ち切れない秀男が、その面影を宿す苗子に結婚を申し込みます。妹の幸せを願う千重子はこの縁談に賛成しますが、苗子の心は揺れます。彼女は、秀男が愛しているのは自分ではなく、自分を通して見ている姉の「幻」であることを、痛いほど理解しているからです。
このネタバレは物語の核心の一つですが、最終的に苗子はこの結婚を断ります。それは、姉への愛情から身を引いたという面もありますが、それ以上に、「身代わり」になることを拒絶する、強い自己の尊厳の表れだと私は解釈しています。秀男が織った美しい帯は、混同された愛情の象徴でした。それを受け入れない苗子の決断は、他者の投影ではない、自分自身の独立した人格を守ろうとする、悲しくも力強い意志の表明なのです。
物語のクライマックスは、冬に訪れます。千重子の両親の温かい申し出により、苗子は一夜だけ佐田家で過ごすことになります。生まれて初めて同じ床で眠る姉妹。静かな冬の夜、二人が分かち合う時間は、奪われていた時間を取り戻すかのような、完璧で、そしてあまりにもはかない幸福の瞬間です。川端康成の抑制の効いた筆致が、この場面の情愛の深さを際立たせています。
千重子は「ずっと一緒にいてほしい」と願いますが、苗子の決意はすでに固まっていました。この夜、千重子の心は再び庭のすみれへと向かいます。「二株のすみれは会うこともなさそうに見えていたが、今夜、会ったのだろうか」。物理的な隔たりを超えて、二人の魂がようやく一つに巡り会えたことを、この内なる問いは示唆しているように感じました。この一夜の描写は、本作の中でも特に胸を打つ美しい場面です。
苗子は、秀男からの求婚も、佐田家からの養子の申し出も、すべてを断ります。この決断の背景には、二重の意味が込められていると私は考えます。一つは、姉への深い愛情からくる自己犠牲です。自分の存在が、千重子の築き上げてきた生活や幸せを乱してはならない、という強い思いがあったことでしょう。これは、彼女の優しさと献身の表れです。
しかし、もう一つの、そしてより深い層にあるのは、自己の尊厳を守るという強い意志です。北山の自然を愛する苗子にとって、洗練された京の町家で「栽培」されるように生きることは、本来の自分を殺すことと同義だったのかもしれません。彼女の選択は、姉のための犠牲であると同時に、自分自身の魂のあり方を守るための、気高い自己肯定の行為でもあったのです。
そして、物語はあまりにも有名な、あの結末を迎えます。ここが最大のネタバレとなります。淡い雪が降る早朝、苗子は旅立ちます。家を出る前、彼女は「これがあたしの一生のしあわせどしたやろ」と千重子に告げます。姉と再会し、一夜を共に過ごしたこと。それ自体が、彼女にとって満ち足りた幸福のすべてだったのです。この一言に、彼女の人生が集約されています。
千重子の涙の引き留めにも、苗子は静かに首を振るだけです。そして、雪の降り積もる通りへと歩み出し、決して一度も振り返りません。この「振り返らない」という行為が、別れを絶対的なものにし、物語を感傷的な悲劇から、神話的な愛と離別の領域へと昇華させているように感じます。物語は、ここで静かに幕を閉じます。
この物語は、何も解決しません。千重子の恋の行方も、佐田家の未来も描かれないまま終わります。しかし、この未解決の結末こそが、日本の伝統的な美意識である「物の哀れ」――万物は移ろいゆくという、優しくも哀しい感受性――を完璧に体現しています。
姉妹の絆の美しさは、それが束の間のものであったからこそ、より一層私たちの心に深く刻まれるのではないでしょうか。物語を読み終えた後も、雪の中を一人去っていく苗子の後ろ姿や、それを見送る千重子の姿が、深い余韻となって心に残り続けます。解決されないからこそ、読者は永遠に彼女たちの運命に思いを馳せることができるのです。これこそが、川端文学の真髄なのだと感じます。
まとめ
川端康成の「古都」は、単なる双子の姉妹の物語にとどまりません。それは、京都という土地が持つ歴史と伝統、人の手によって磨き上げられた美と、ありのままの自然の美との対比を見事に描き出した作品です。物語のあらすじを追うだけでも、その魅力の一端に触れることができるでしょう。
しかし、この物語の本当の価値は、結末のネタバレを知った上で、姉妹の心の機微や、作中に散りばめられた象徴を深く味わうことにあるのかもしれません。特に、苗子が下した決断と、雪の中に消えていく最後の場面が残す余韻は、読む人の心に長く、深く残り続けます。
千重子と苗子、二人の運命ははかなくも哀しいものでした。しかし、彼女たちが出会い、心を通わせた時間の輝きは、永遠のものです。失われゆく日本の伝統的な美への挽歌とも読めるこの物語は、私たちに「美しさ」とは何か、「幸福」とは何かを静かに問いかけてくるようです。
この記事を読んで、少しでも「古都」の世界に興味を持っていただけたなら、これ以上の喜びはありません。ぜひ一度手に取って、川端康成が描いた美しくも切ない世界を、ご自身の心で感じてみてください。