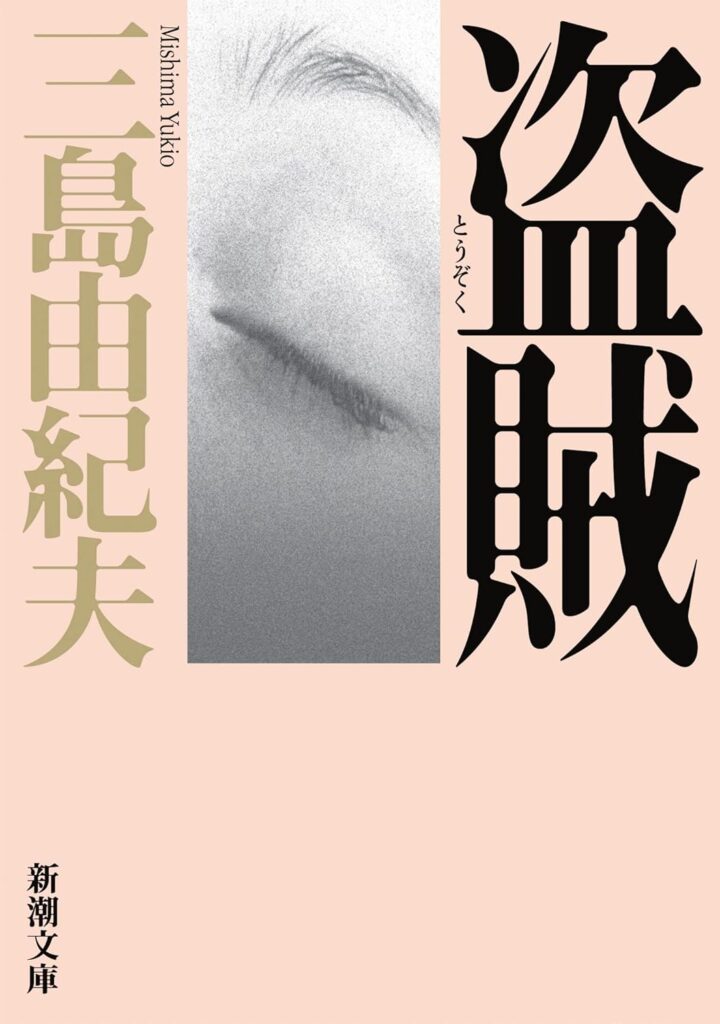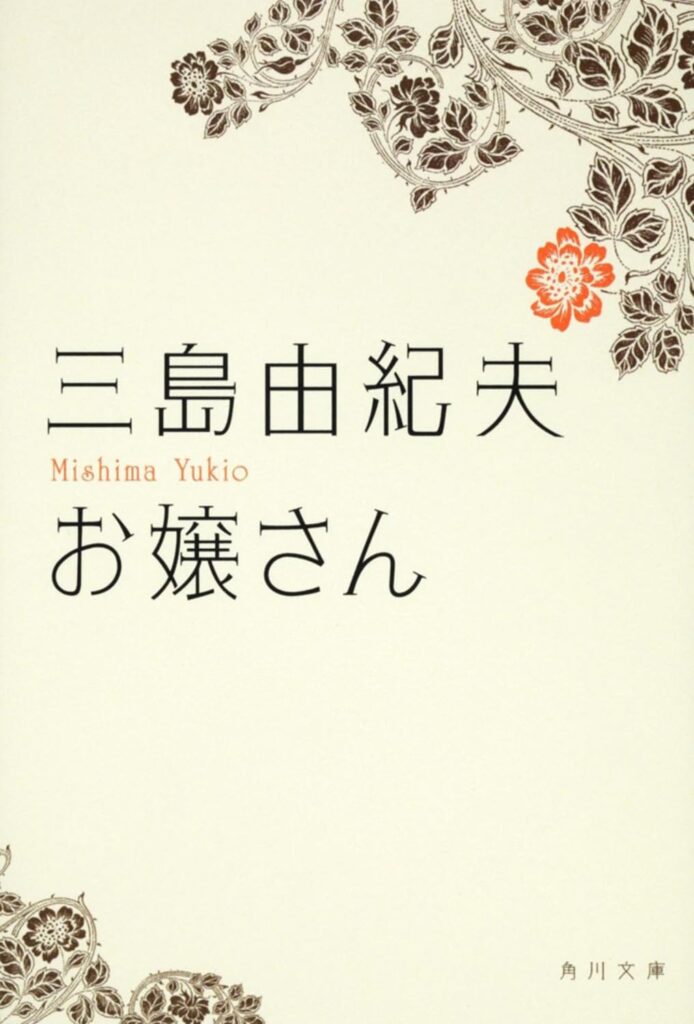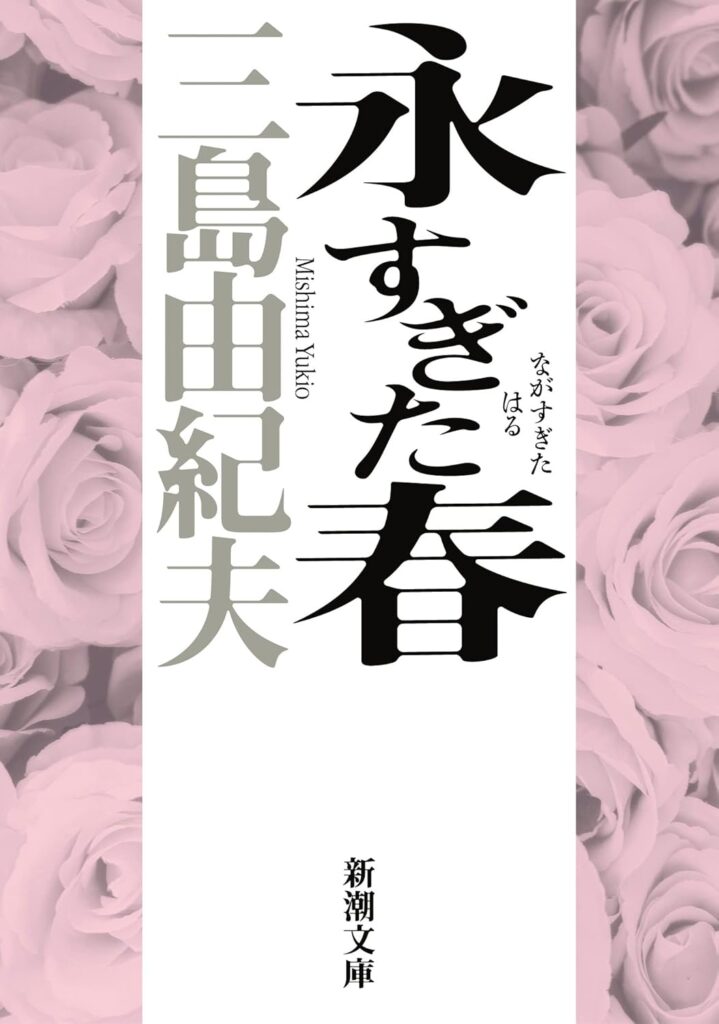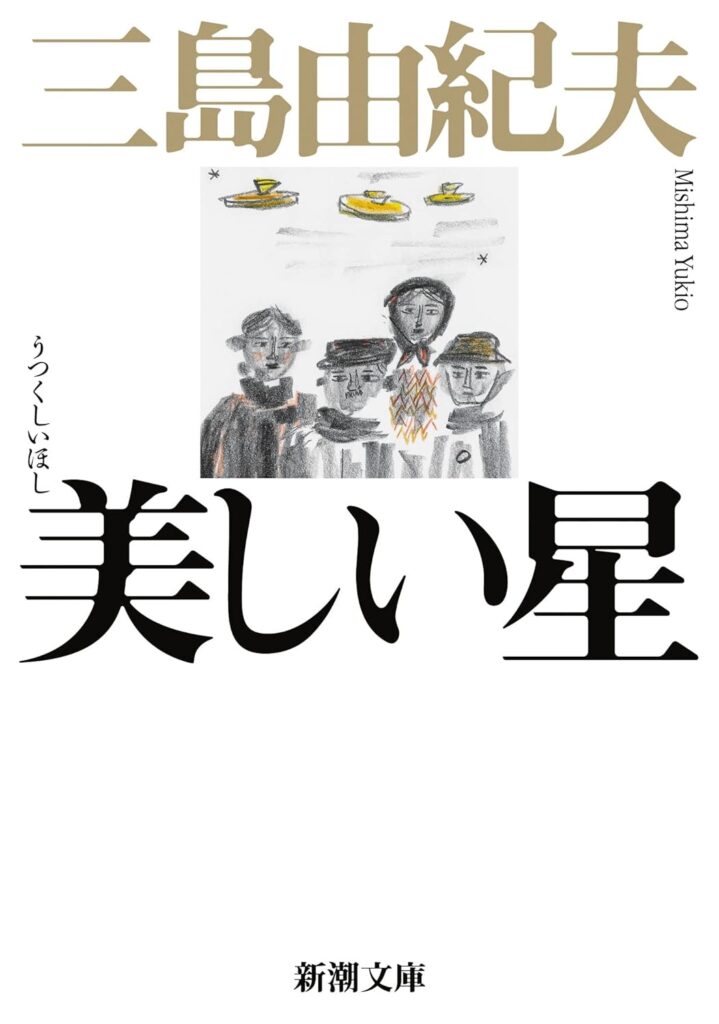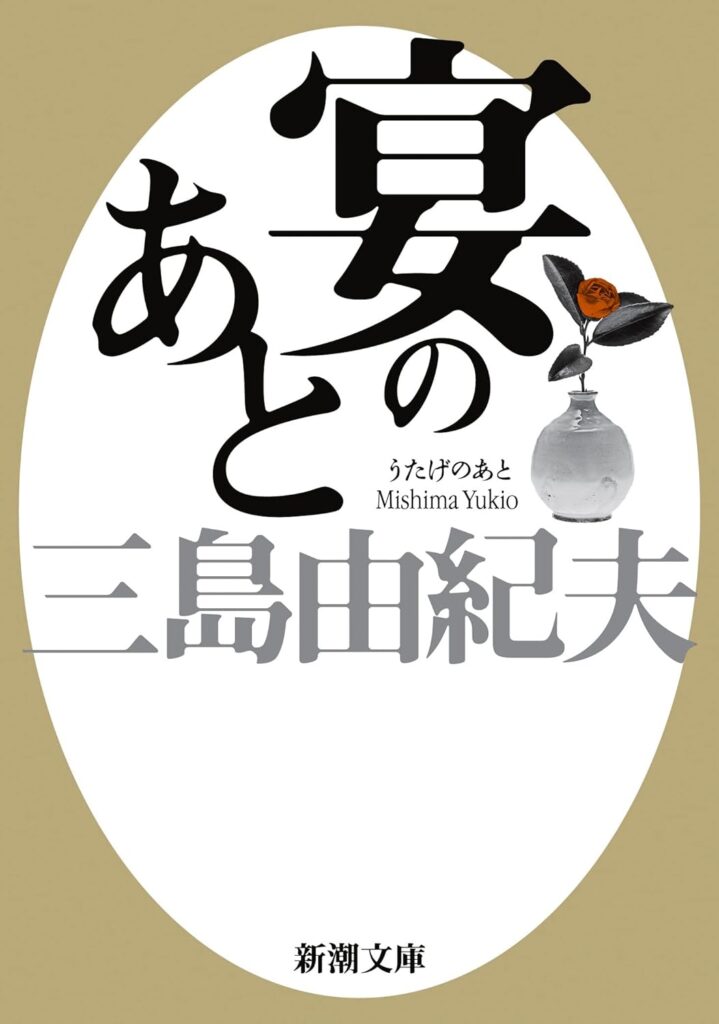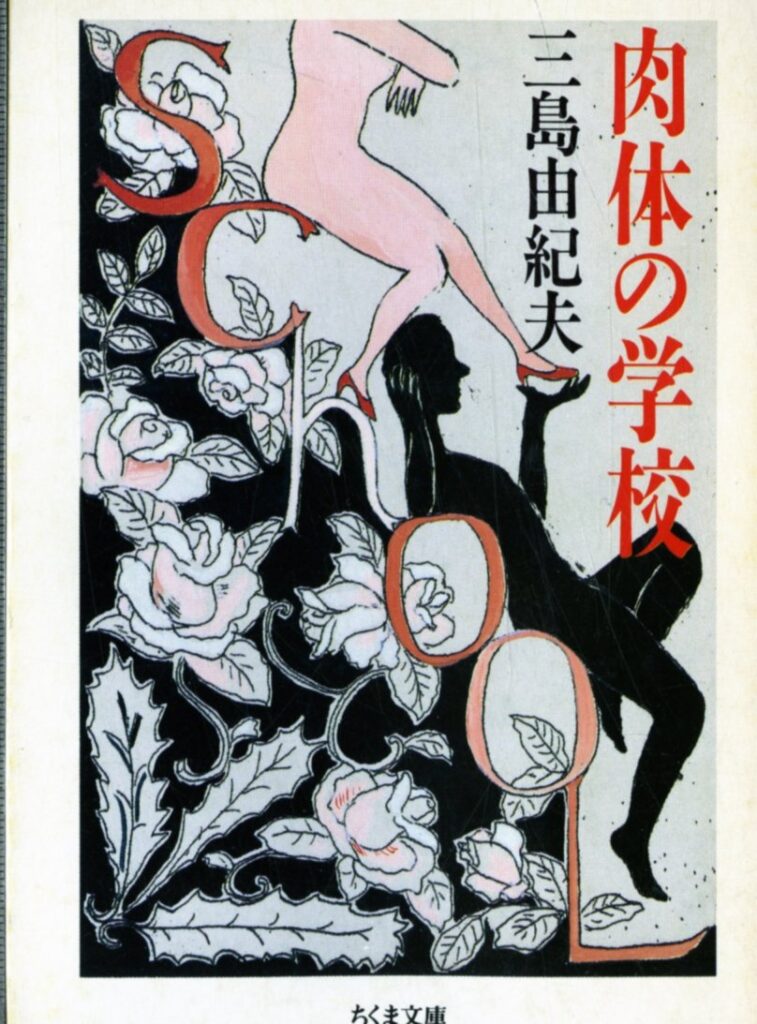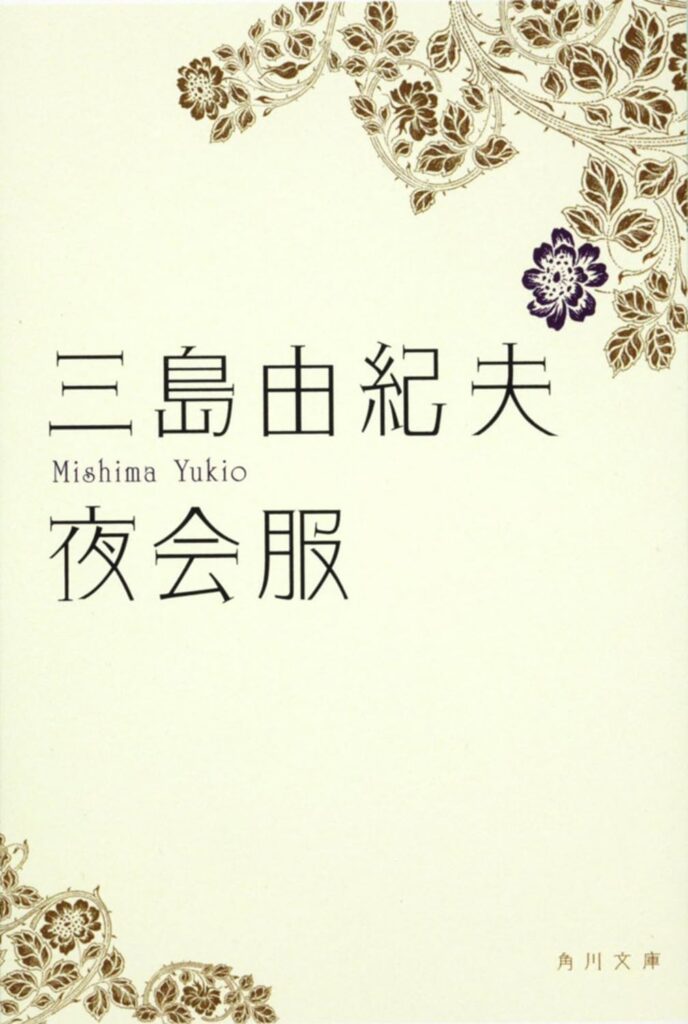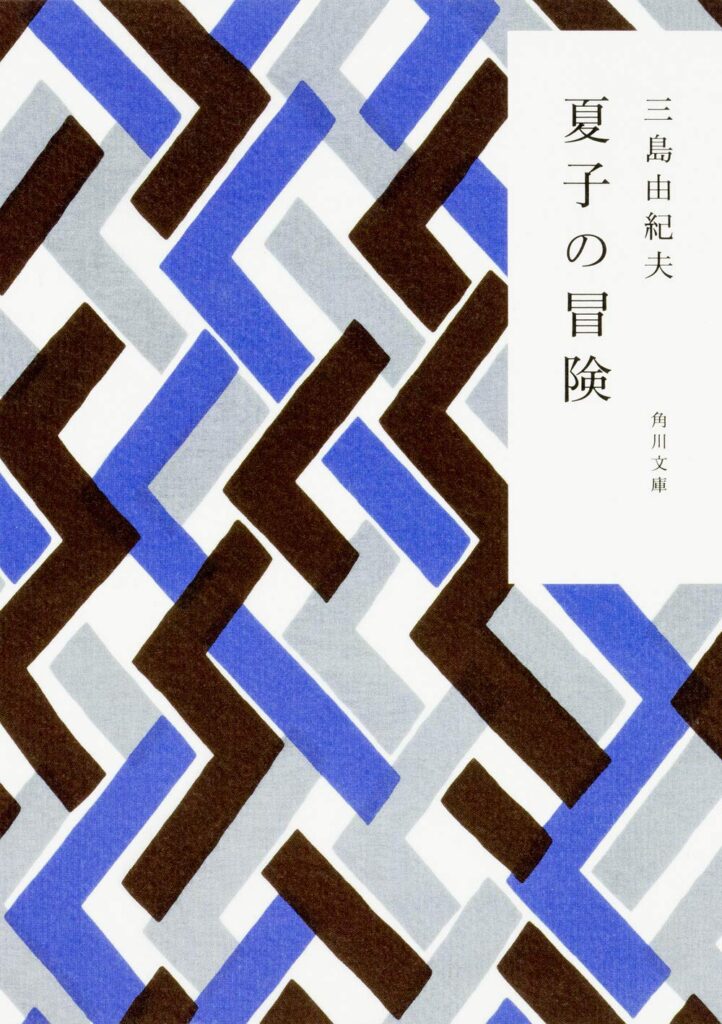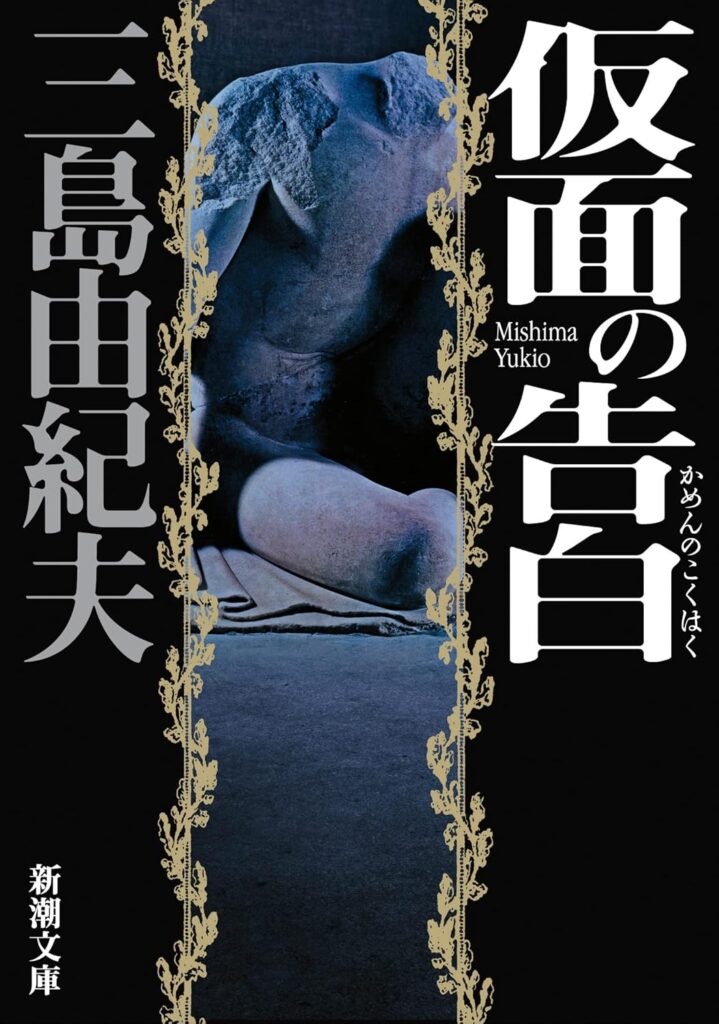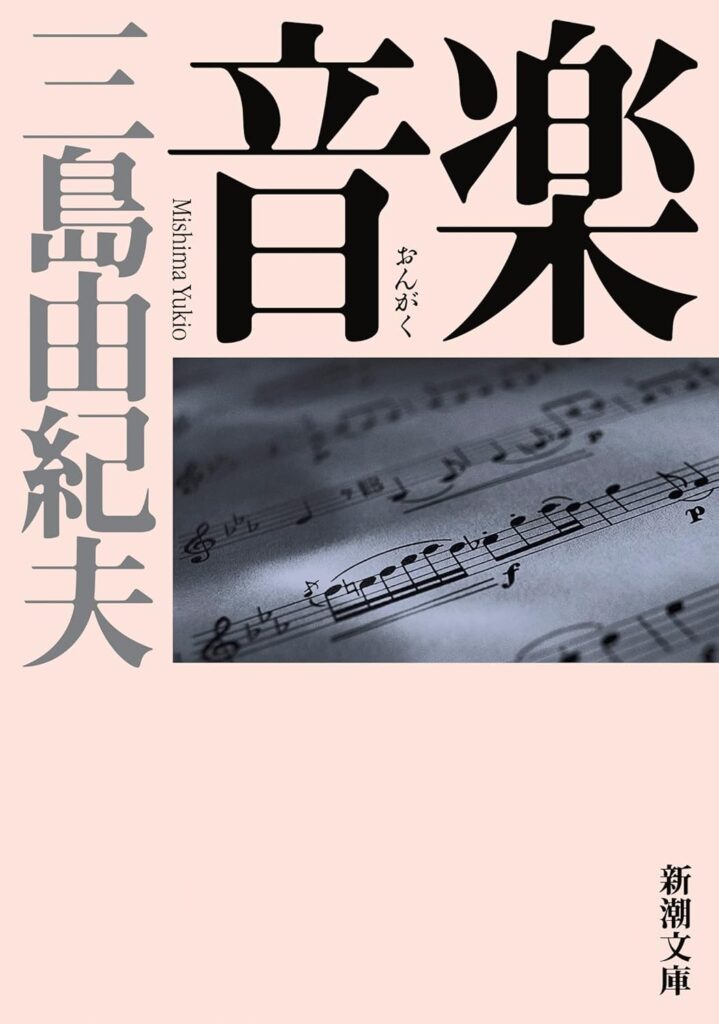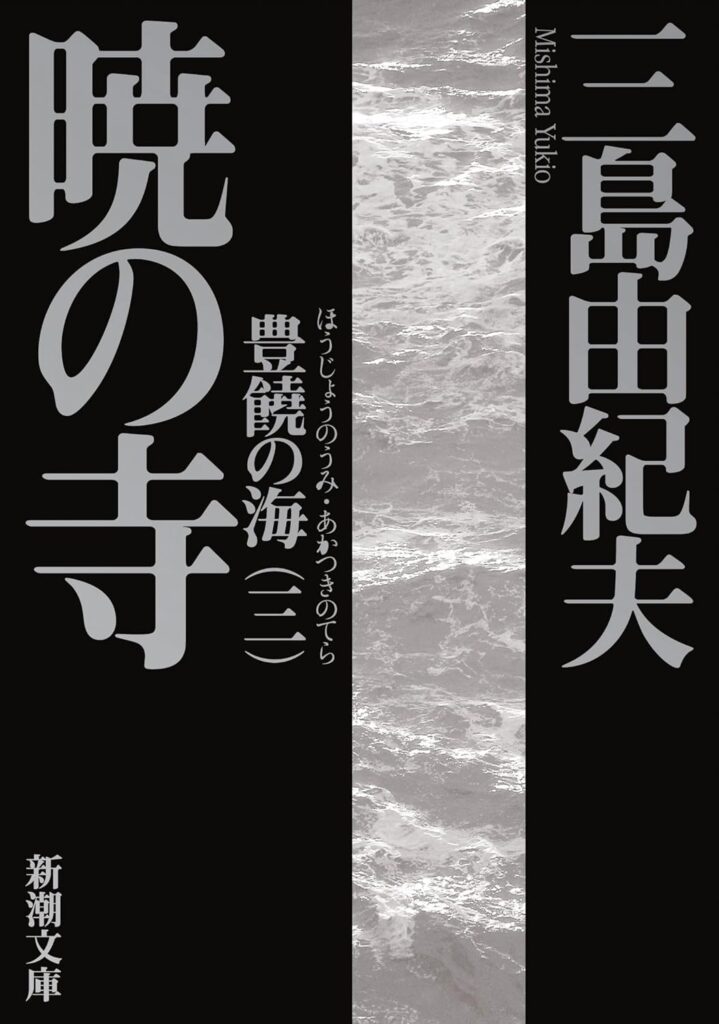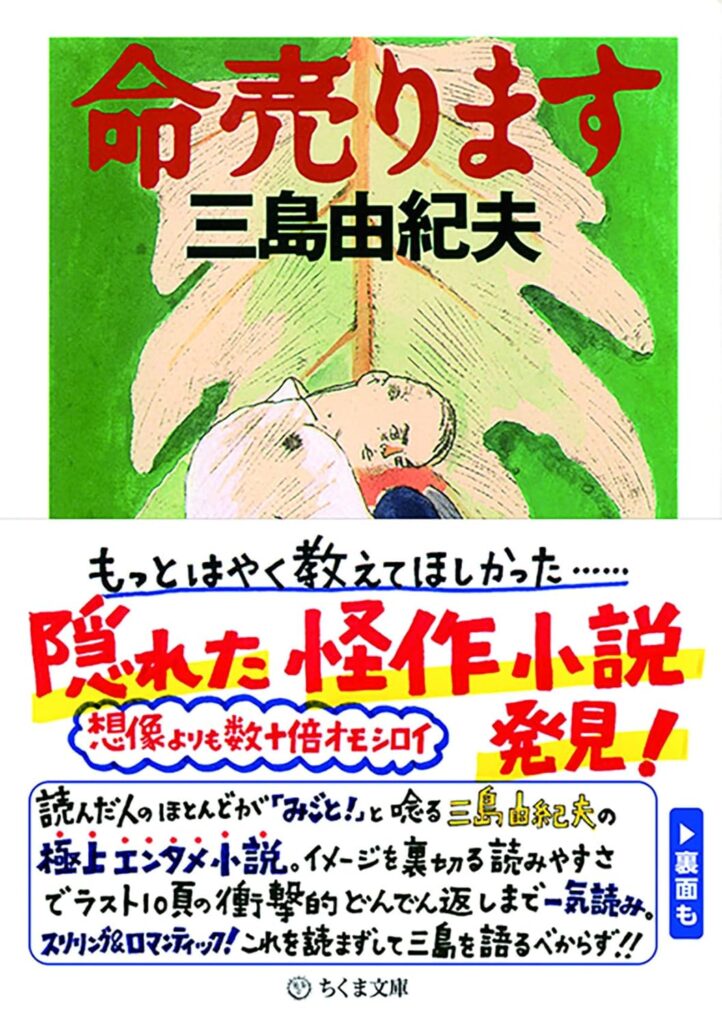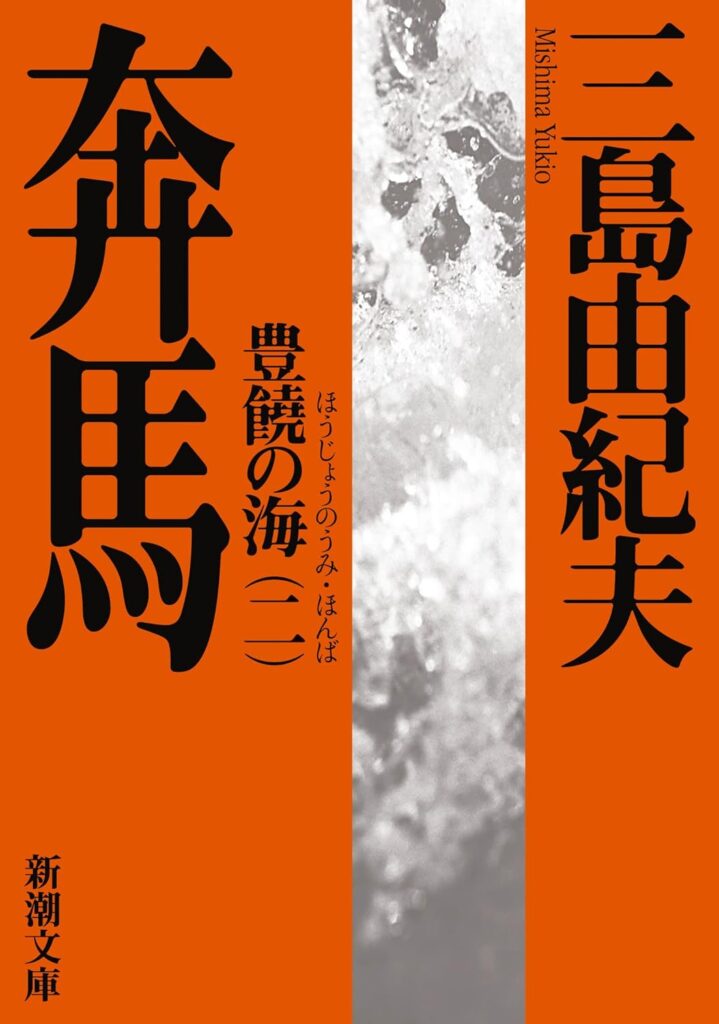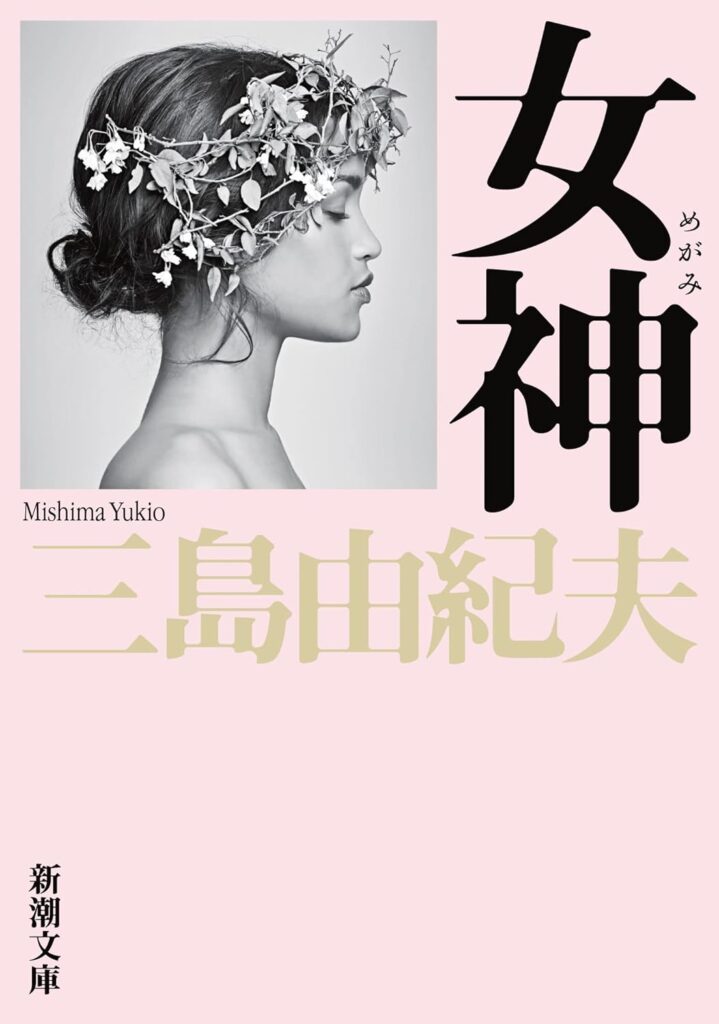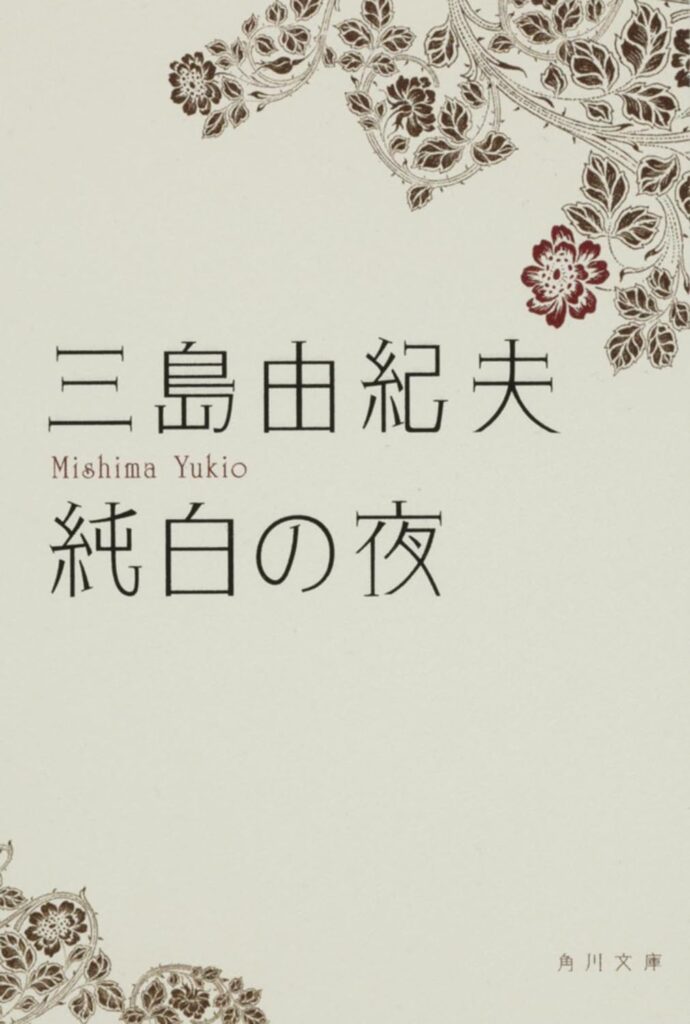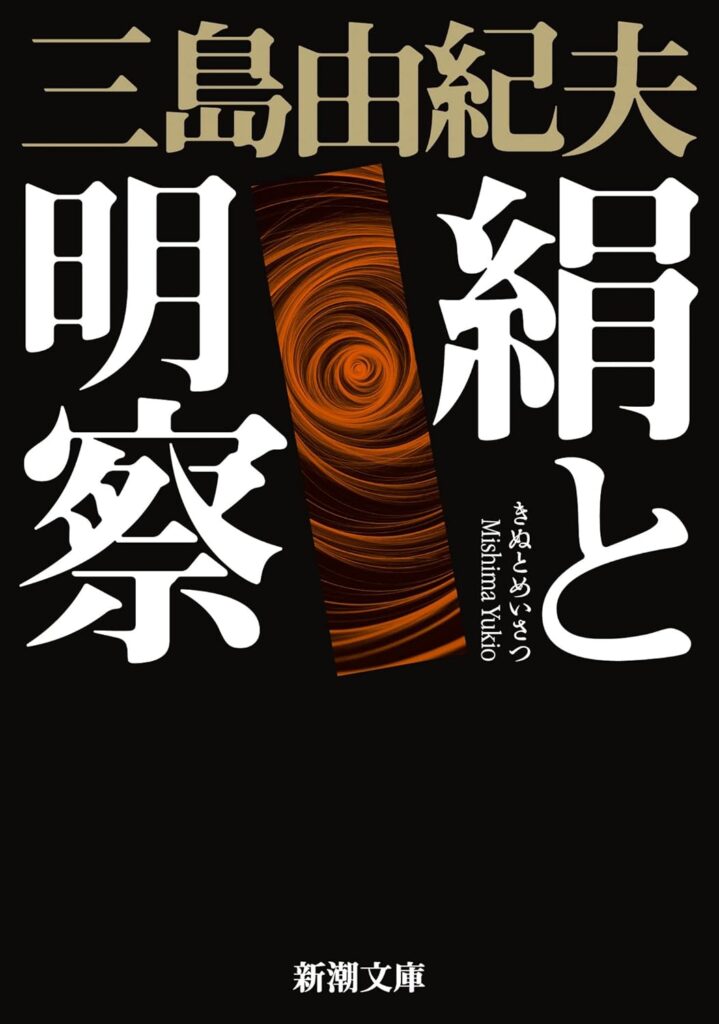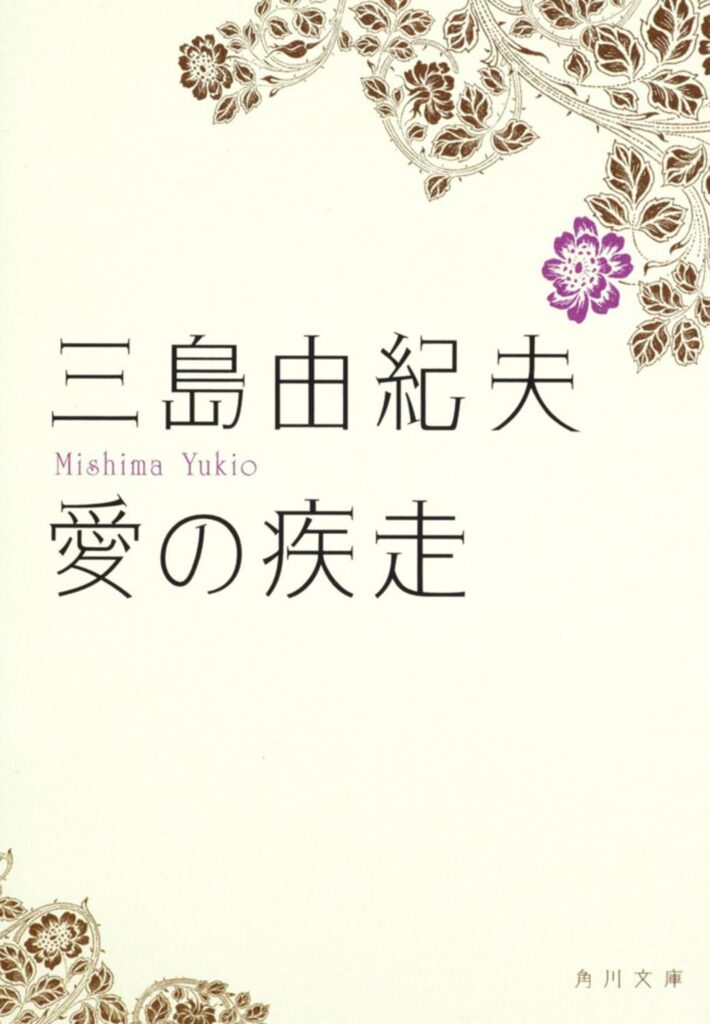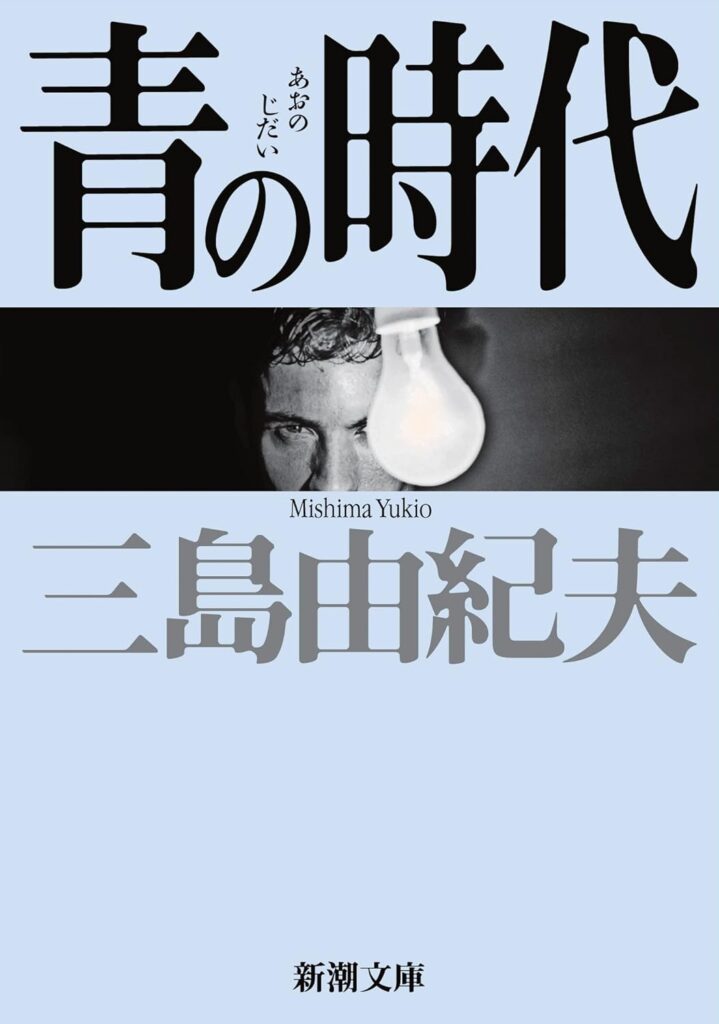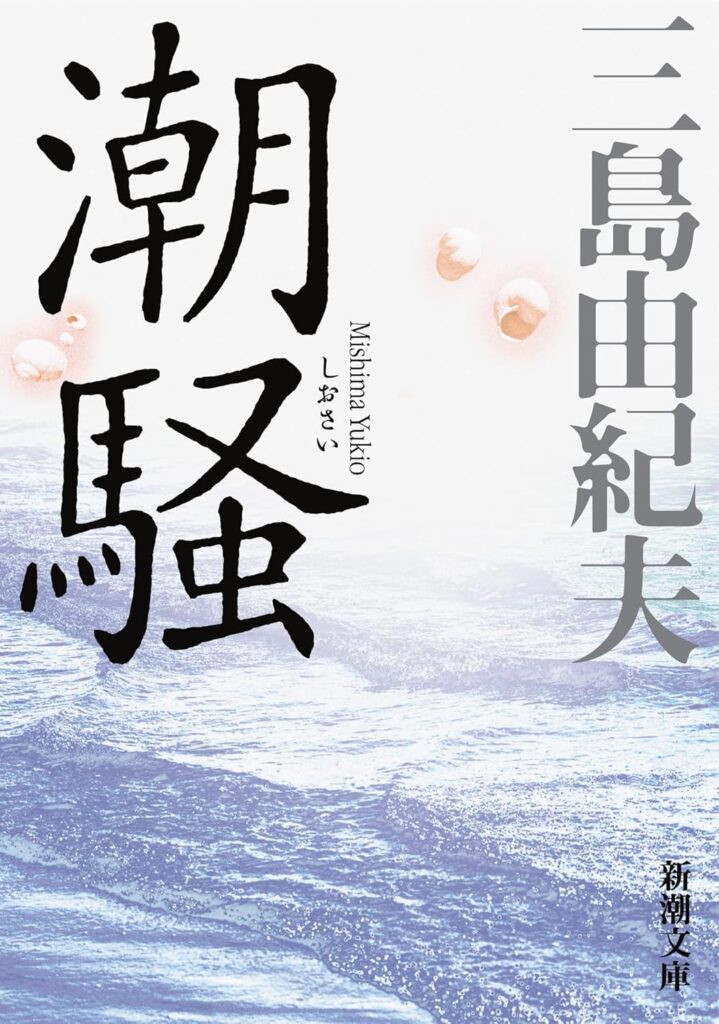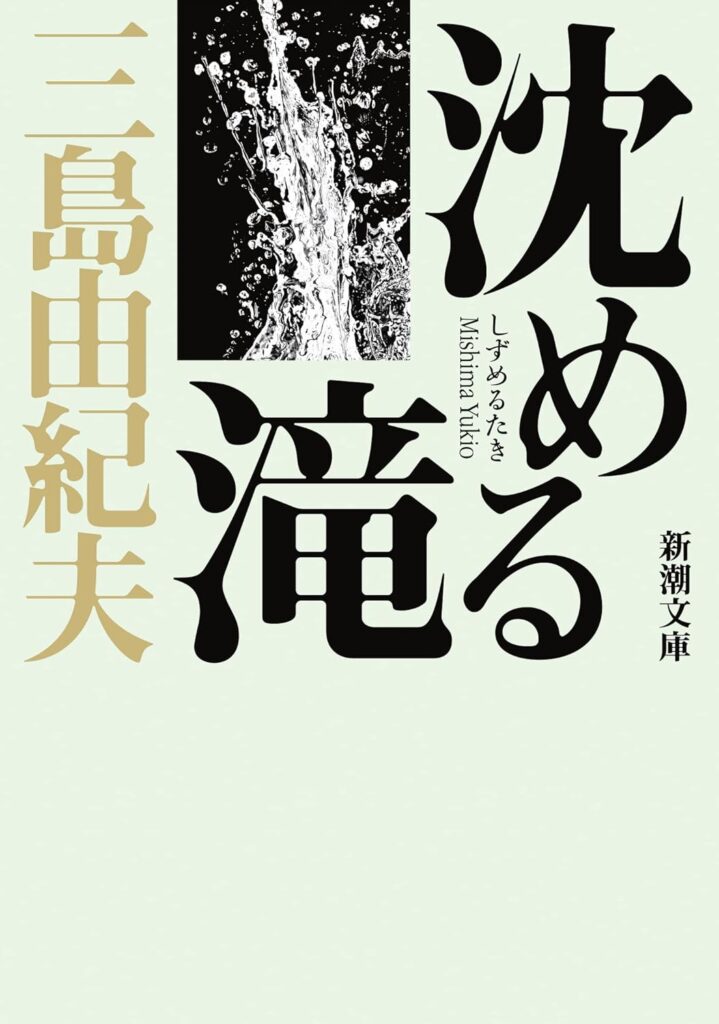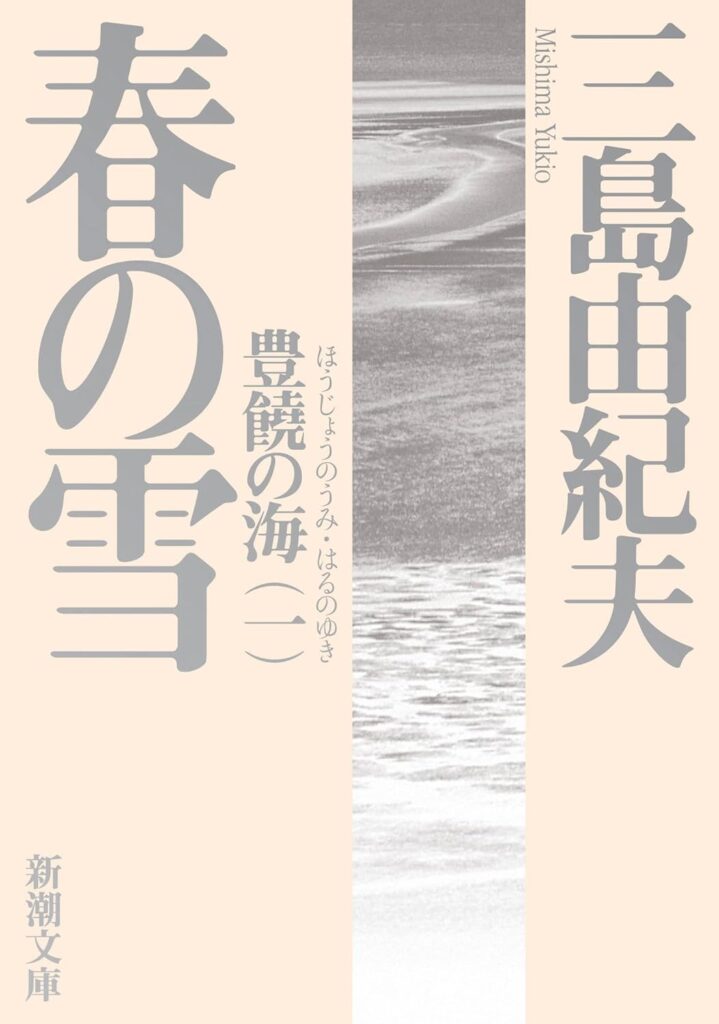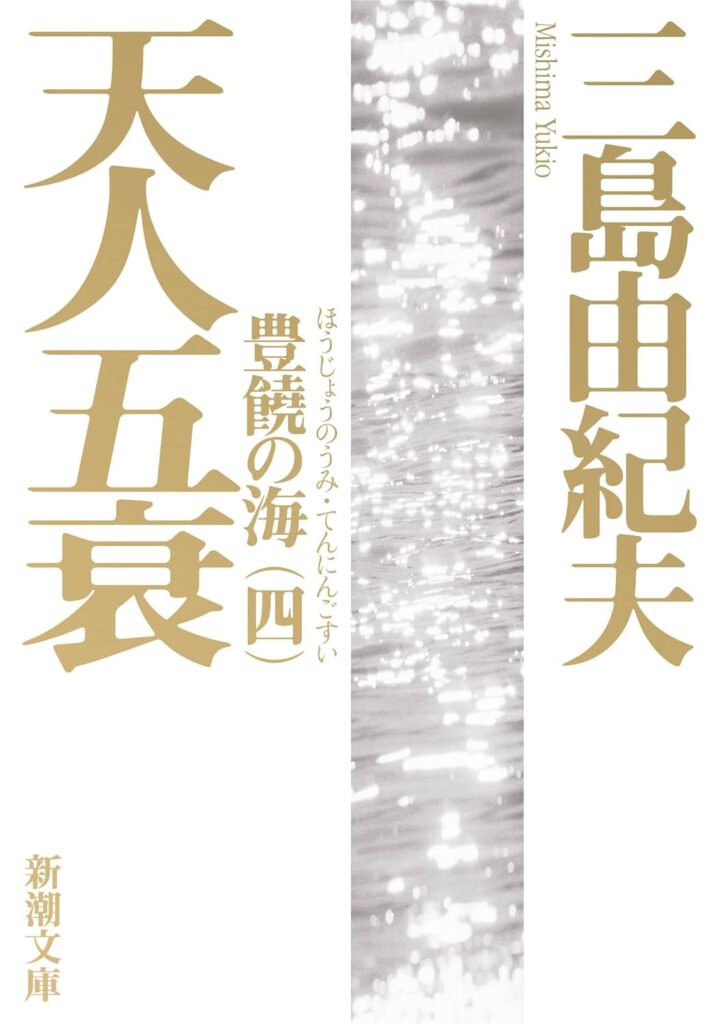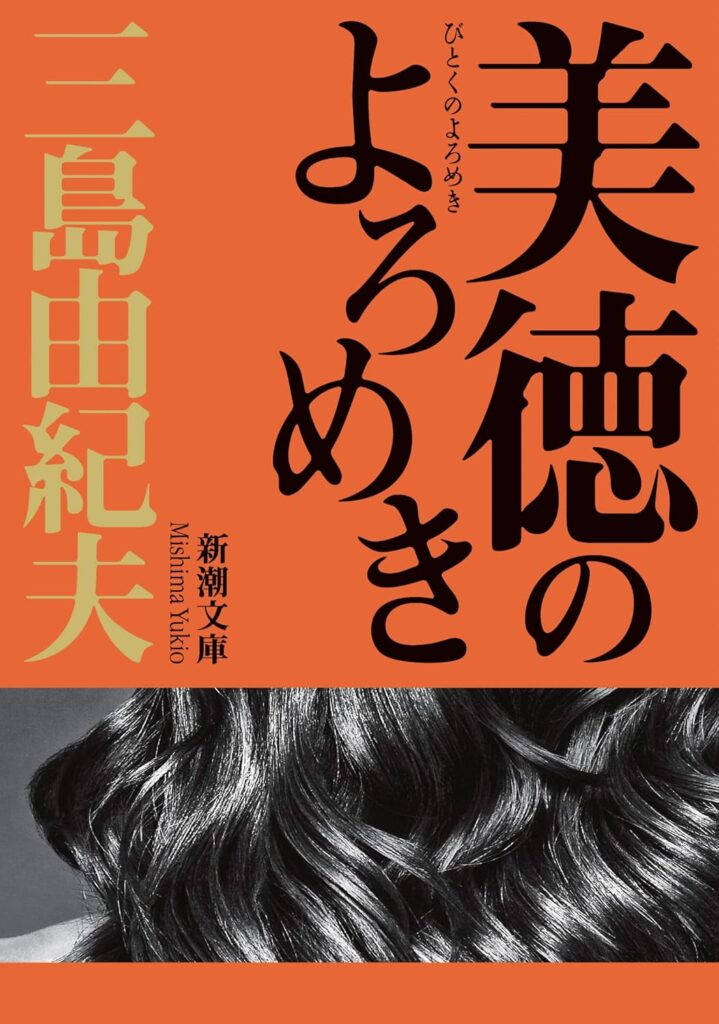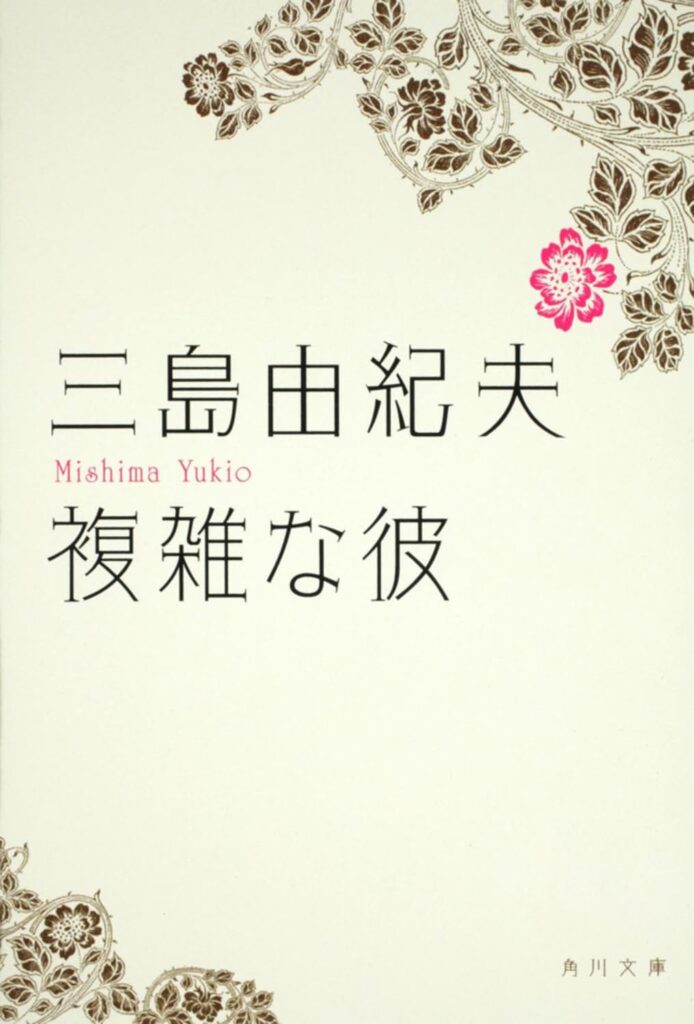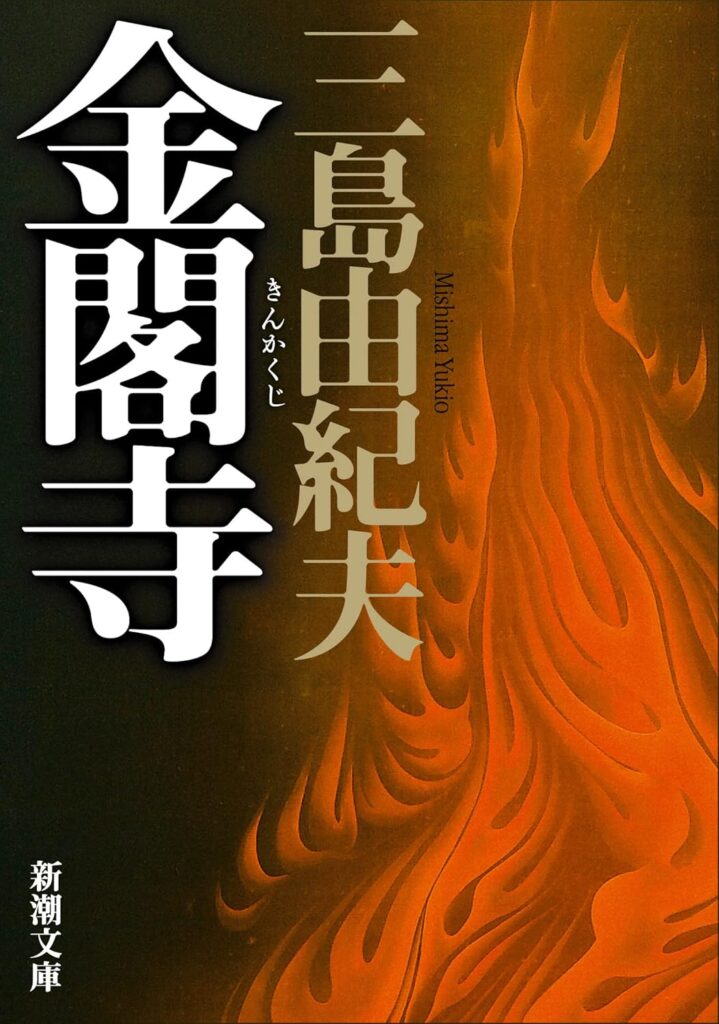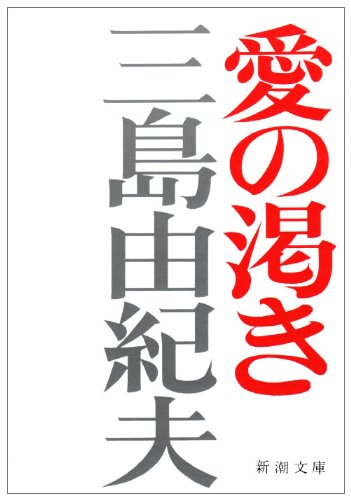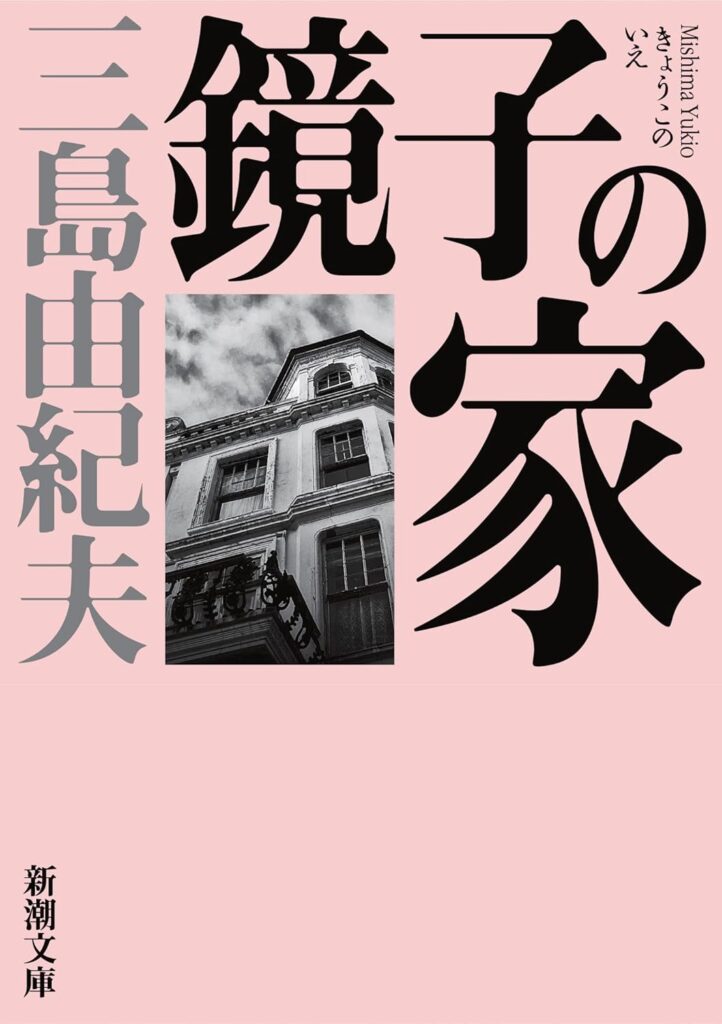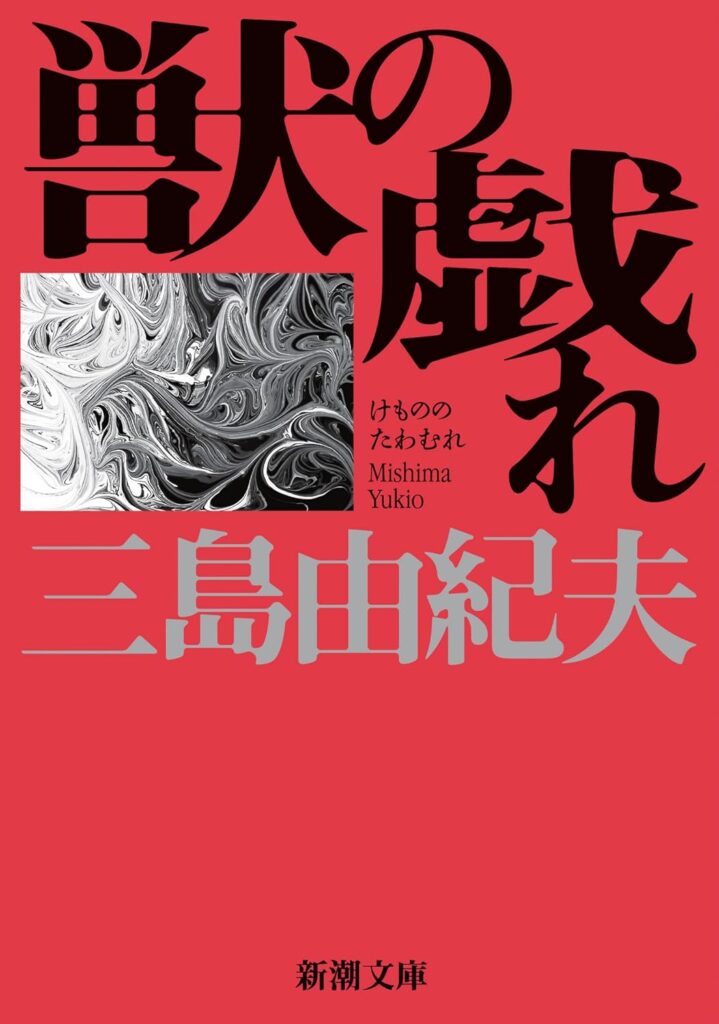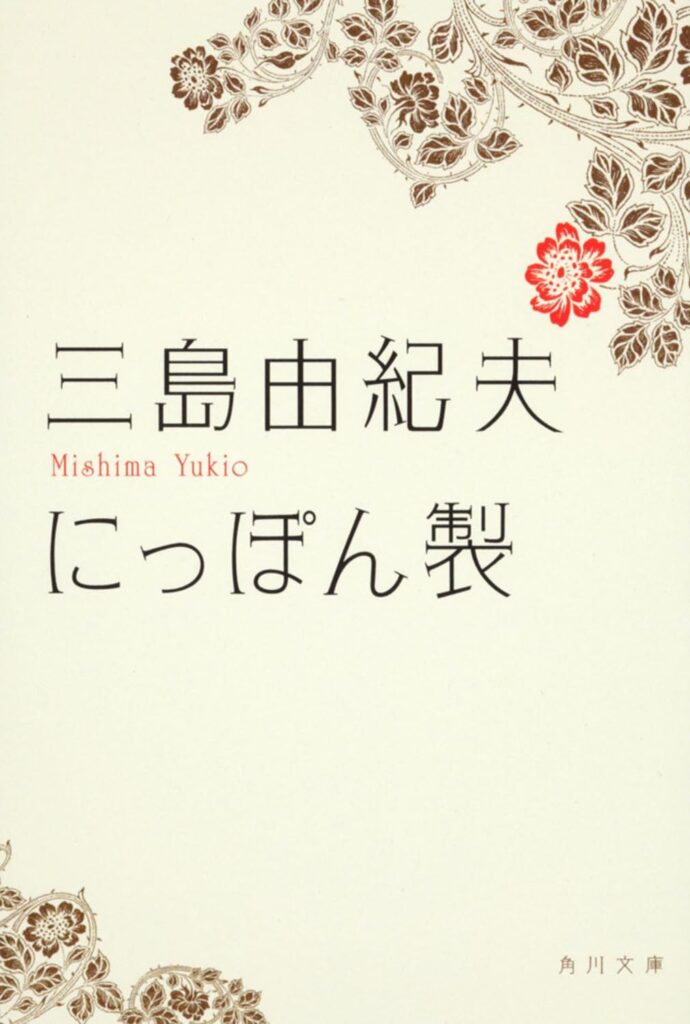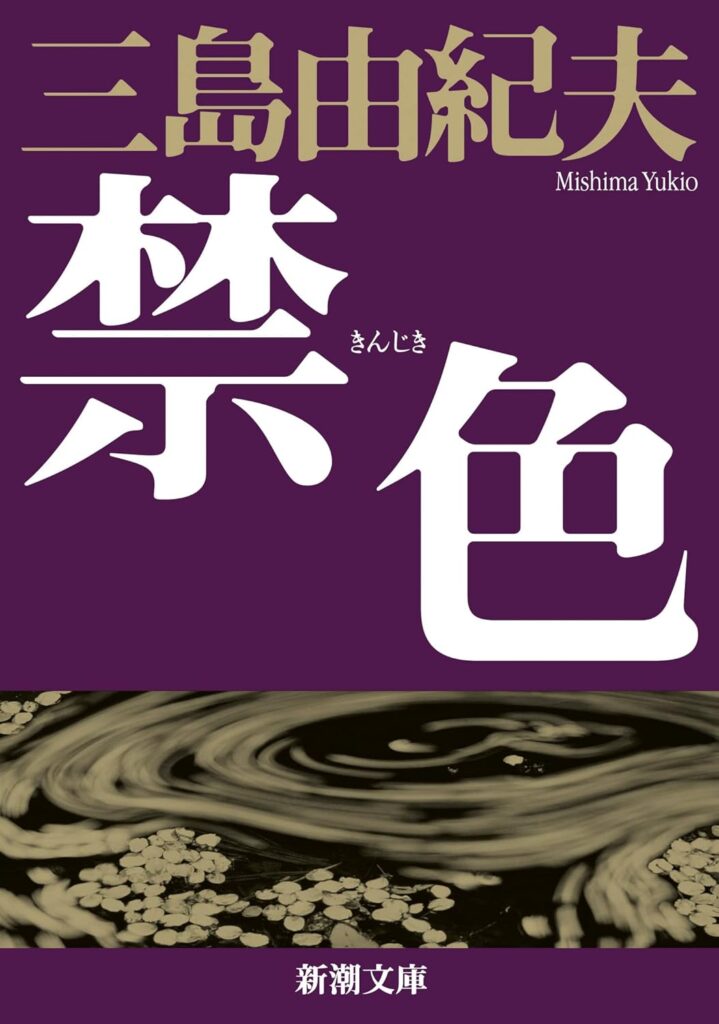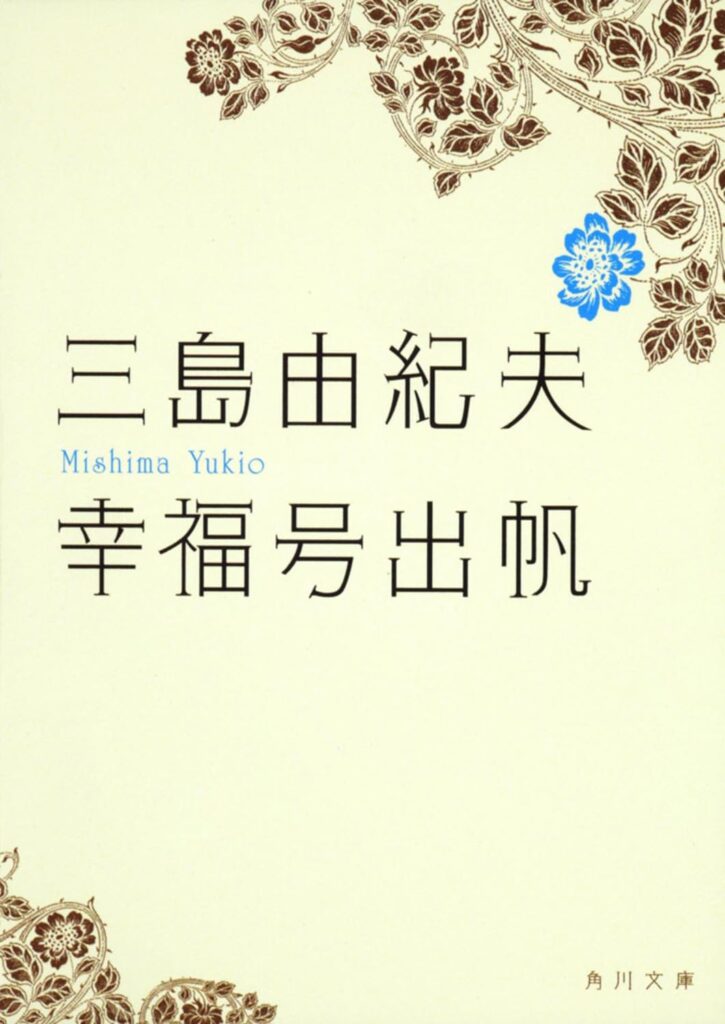小説「午後の曳航」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。三島由紀夫氏が描いた、少年たちの純粋さと残酷さが交錯するこの物語は、読む者の心に深く鋭い問いを投げかけてきます。一度触れたら忘れられない、強烈な印象を残す作品と言えるでしょう。
小説「午後の曳航」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。三島由紀夫氏が描いた、少年たちの純粋さと残酷さが交錯するこの物語は、読む者の心に深く鋭い問いを投げかけてきます。一度触れたら忘れられない、強烈な印象を残す作品と言えるでしょう。
この記事では、まず「午後の曳航」がどのような物語であるか、その詳細な筋道をお伝えします。物語の結末まで触れていきますので、まだ知りたくない方はご注意ください。登場人物たちの心の動きや、彼らを取り巻く状況がどのように変化していくのか、じっくりと追っていきましょう。
そして、物語の核心に迫る詳細な解釈と、私が抱いた赤裸々な思いを綴ります。少年たちの行動は、一体何を意味していたのか。そして、彼らが守ろうとしたものは何だったのか。様々な角度から光を当て、この作品の持つ多層的な魅力を解き明かしていきたいと考えています。
この記事が、「午後の曳航」という作品世界への理解を深める一助となり、また、これから作品を手に取る方にとっては、より豊かな読書体験へと繋がる導入となれば幸いです。それでは、三島文学の深淵なる海へ、一緒に漕ぎ出しましょう。
小説「午後の曳航」のあらすじ
物語の中心にいるのは、13歳の少年、黒田登です。彼は早くに父親を亡くし、横浜の邸宅で美しい母、房子と二人で暮らしています。多感な年頃の登は、亡き父の書斎にあった鍵穴から、隣の母の部屋を覗き見るという秘密の習慣を持っていました。それは彼にとって、大人の世界の不可解さと、母の女性としての一面を垣間見る行為だったのです。
そんなある日、房子は取引先の船会社に勤める二等航海士、塚崎竜二と恋に落ちます。登は最初、船乗りである竜二のたくましい肉体や、世界を股にかけるその生き様に、純粋な憧れと英雄的な理想像を抱きます。竜二もまた、登に父親のように接し、船に招き入れるなどして、二人の間には良好な関係が築かれていくように見えました。
しかし、登には学校の同級生たちと結成した秘密のグループがありました。そのグループは「首領」と呼ばれる卓越した知性を持つ少年を中心とし、大人たちの価値観や社会の欺瞞を冷ややかに見つめていました。登は、竜二への憧れを仲間たちに語りますが、首領はそれを鼻で笑い、竜二を房子の財産目当てだと断じます。彼らは、大人たちの世界を拒絶し、独自の論理と純粋さを追求していたのです。
物語が大きく動くのは、竜二が房子にプロポーズし、二人が結婚を決意してからです。登にとって英雄であったはずの竜二が、船を降り、陸に上がり、平凡な「父親」になろうとすること。それは登にとって、理想の裏切りであり、許しがたい「俗物化」に他なりませんでした。さらに、登の覗き見の事実が竜二に知られてしまいますが、竜二は登を叱責するでもなく、ただその穴を塞ごうとするだけでした。この一件で、登の竜二に対する幻滅は決定的となります。
登は首領に緊急会議を招集し、竜二の「罪科」を仲間たちに告発します。首領は竜二の「処刑」を提案し、少年たちはそれを実行に移す計画を練り始めます。彼らは、14歳未満の行為は罰せられないという法律を盾に、大人たちの世界への挑戦として、この恐ろしい計画を推し進めるのです。
そして運命の日。登は「友達がパパの航海の話を聞きたがっている」と竜二を誘い出します。何も知らない竜二は、少年たちの前で、誇らしげに自らの航海の体験談を語り始めます。少年たちは、睡眠薬入りの紅茶を竜二に飲ませ、彼が意識を失っていく中、その計画を実行に移そうとするのでした。物語は、衝撃的な結末へと向かっていきます。
小説「午後の曳航」の長文感想(ネタバレあり)
三島由紀夫氏の「午後の曳航」を読み終えたとき、私はしばし言葉を失いました。美しい文章で綴られる物語の中に、あまりにも鋭利な刃物のような純粋さと、それゆえの残酷さが潜んでいたからです。この作品は、単なる少年犯罪の物語として片付けることはできません。そこには、聖なるものへの憧れと、それが裏切られたときの絶望、そして純粋さを守るためなら破壊すら厭わないという、歪みながらも切実な魂の叫びが込められているように感じました。
物語の主人公である黒田登は、非常に繊細で、早熟な少年として描かれています。彼が抱える孤独感は、母・房子との関係性からも読み取れます。若く美しい母は、登にとって庇護者であると同時に、手の届かない異性としての側面も持っていたのではないでしょうか。父の不在と、母の新しい恋人の出現は、登の心に複雑な影を落とします。特に、鍵穴からの覗き見という行為は、彼の屈折した承認欲求や、大人たちの世界に対する不信感、そして純粋なものへの渇望が入り混じった象徴的な行動と言えるでしょう。
そこに現れたのが、航海士の塚崎竜二です。当初、登は竜二の中に「海」そのものを見出し、彼を英雄として崇拝します。鍛え上げられた肉体、世界を巡る冒険譚、そして何よりも「陸」の生活に染まらない自由な魂。それらは、登が追い求める「聖なるもの」の具現化でした。竜二が語る海の壮大さや厳しさは、登にとって、俗世から切り離された絶対的な価値観そのものだったのです。
しかし、この理想化された英雄像は、竜二が房子との結婚を決意し、「陸に上がる」ことを選んだ瞬間に脆くも崩れ去ります。登にとって、それは英雄の死であり、裏切りでした。海という無限の可能性を捨て、家庭という平凡な枠組みに収まろうとする竜二は、もはや彼の崇拝の対象ではなく、唾棄すべき「俗物」と成り果ててしまうのです。この急激な態度の変化は、思春期特有の潔癖さと、理想と現実のギャップに耐えられない未熟さから来ているのかもしれません。
登が所属する少年たちのグループもまた、この物語の重要な要素です。「首領」と呼ばれる少年は、大人顔負けの冷徹な知性とカリスマ性を持ち、他の少年たちを支配しています。彼らは、大人たちの欺瞞に満ちた社会を軽蔑し、独自の価値基準に基づいて行動します。彼らにとって、子猫を殺すことは、感情に流されず目的を遂行するための訓練であり、世界の不条理に対する一つの意思表示でもありました。この閉鎖的で排他的な小宇宙の中で、彼らの純粋さは歪んだ形で先鋭化し、常軌を逸した論理を生み出していきます。
竜二が登の覗き見に気づいた際の対応も、決定的な転換点でした。登が期待したのは、おそらく激しい怒りや、あるいは父親としての威厳ある叱責だったのかもしれません。しかし、竜二が見せたのは、事態を穏便に収めようとする、ある意味で「大人な」対応でした。それは登の目には、竜二がもはや魂の気高さを持たず、世俗的な分別に屈した姿と映り、最後の希望さえも打ち砕かれる結果となったのです。
そして、少年たちは竜二の「処刑」を計画します。彼らがノートに記した「塚崎竜二の罪科」とは、客観的に見れば些細なこと、あるいは登の主観的な解釈に過ぎないものがほとんどでしょう。しかし、少年たちの純粋な世界観においては、それは断罪すべき裏切り行為に他なりませんでした。彼らにとって、竜二を殺すことは、汚された理想を浄化し、自分たちの聖域を守るための儀式のようなものだったのかもしれません。
刑法第41条、つまり14歳未満の者の行為は罰しないという条文が、彼らの計画を後押しする皮肉な要素として機能します。法という大人社会のルールを逆手に取り、彼らは自らの「正義」を実行しようとするのです。これは、大人社会への痛烈な批判であると同時に、純粋さという名の狂気が、いかに容易に一線を越えてしまうかを示唆しています。
物語のクライマックス、何も知らずに自らの栄光の記憶である航海の体験を語る竜二の姿は、あまりにも悲痛です。彼が語る海の世界は、かつて登が憧れたきらめきに満ちていますが、その言葉はもはや少年たちの心には届きません。彼らにとって、それは過去の残滓であり、これから排除すべき対象でしかないのです。差し出された睡眠薬入りの紅茶を飲み干し、次第に意識が遠のいていく竜二の運命は、読者に強烈な無力感と戦慄を与えます。
この衝撃的な結末は、多くの問いを投げかけます。少年たちの行為は、果たして純粋さの表れだったのでしょうか、それとも単なる残虐性だったのでしょうか。三島由紀夫は、おそらくその両義性を意図的に描いたのでしょう。純粋さは、時として他者を傷つけ、破壊へと向かう危険性を孕んでいる。そして、その純粋さを守ろうとする行為が、いかにグロテスクな結果を招きうるかということを、この作品は冷徹な筆致で描き出しています。
「午後の曳航」は、美しいものと醜いもの、聖なるものと俗なるもの、生と死といった、三島文学に一貫して流れるテーマが色濃く反映された作品です。少年たちの潔癖すぎるまでの理想主義は、三島自身が抱いていた美意識と重なる部分があるのかもしれません。そして、その理想が現実によって汚されることへの耐え難い苦痛が、この物語の根底には流れているように感じられます。
登が見た「栄光」と「世界の終り」とは何だったのか。それは、竜二という英雄の失墜であり、自らの純粋な世界の崩壊だったのかもしれません。そして、彼らが実行しようとした行為は、その崩壊を食い止め、失われた栄光を取り戻そうとする、あまりにも歪んだ試みだったのではないでしょうか。
この作品を読むことは、決して心地よい体験ではありません。しかし、人間の心の奥底に潜む暗い輝きや、純粋さが持つ破壊的なエネルギーについて、深く考えさせられることは間違いありません。三島由紀夫が問いかけた「美とは何か、純粋さとは何か」という命題は、現代を生きる私たちにとっても、依然として重い意味を持ち続けているのです。
私は、この物語を読み終えて、少年たちの行動を単純に断罪することはできませんでした。もちろん、彼らの行為は許されるものではありません。しかし、彼らがそこに至るまでの心の軌跡を追うと、そこには現代社会にも通じる、純粋なものが生きづらい世界の歪みが映し出されているように思えてならないのです。それは、ある種の警鐘として、私たちの心に深く刻まれる物語と言えるでしょう。
まとめ
「午後の曳航」は、三島由紀夫氏が描いた、少年たちの純粋さが孕む危うさと、理想の喪失がもたらす悲劇の物語です。主人公である13歳の少年・登が、憧れの対象であった航海士・竜二の「俗物化」に幻滅し、仲間たちと共に恐ろしい計画を実行に移すまでを描いています。そこには、大人社会への不信感や、純粋な世界を守ろうとする少年たちの歪んだ正義感が色濃く映し出されています。
この作品の魅力は、何と言っても三島由紀夫氏の緻密で美しい文体と、登場人物たちの鋭敏な心理描写にあります。特に、思春期の少年が抱える潔癖すぎるほどの理想と、それが裏切られた時の激しい憎悪のコントラストは圧巻です。物語の結末は衝撃的であり、読者に強烈な印象を残すでしょう。
「午後の曳航」は、単に結末を知るだけでなく、そこに込められたテーマ性や、少年たちの心の機微を読み解くことで、より深く味わうことができる作品です。純粋さとは何か、正義とは何か、そして美とは何か。これらの問いについて、改めて考えさせられるきっかけを与えてくれます。
もしあなたが、人間の心の深淵に触れるような、強烈な読書体験を求めているのであれば、この「午後の曳航」を手に取ってみることをお勧めします。きっと、忘れられない一冊となるはずです。読後、あなた自身の心にどのような感情が芽生えるのか、ぜひ確かめてみてください。