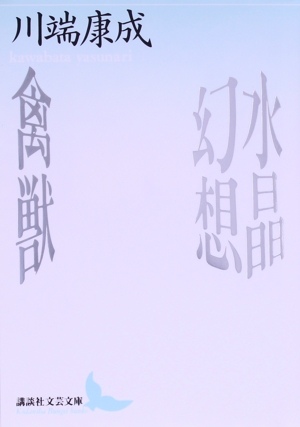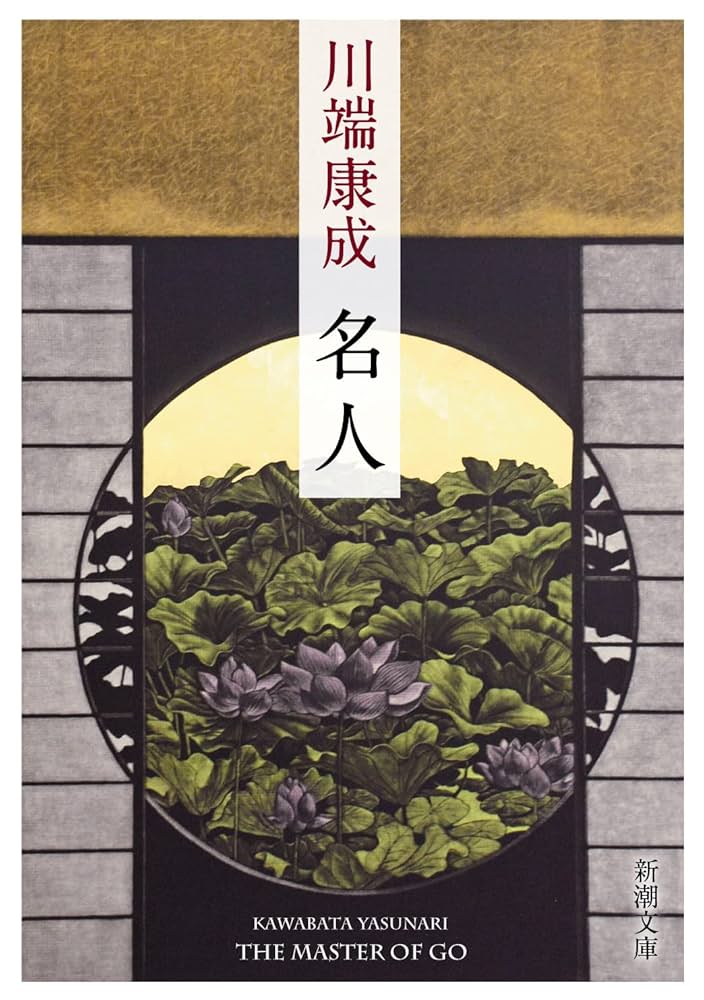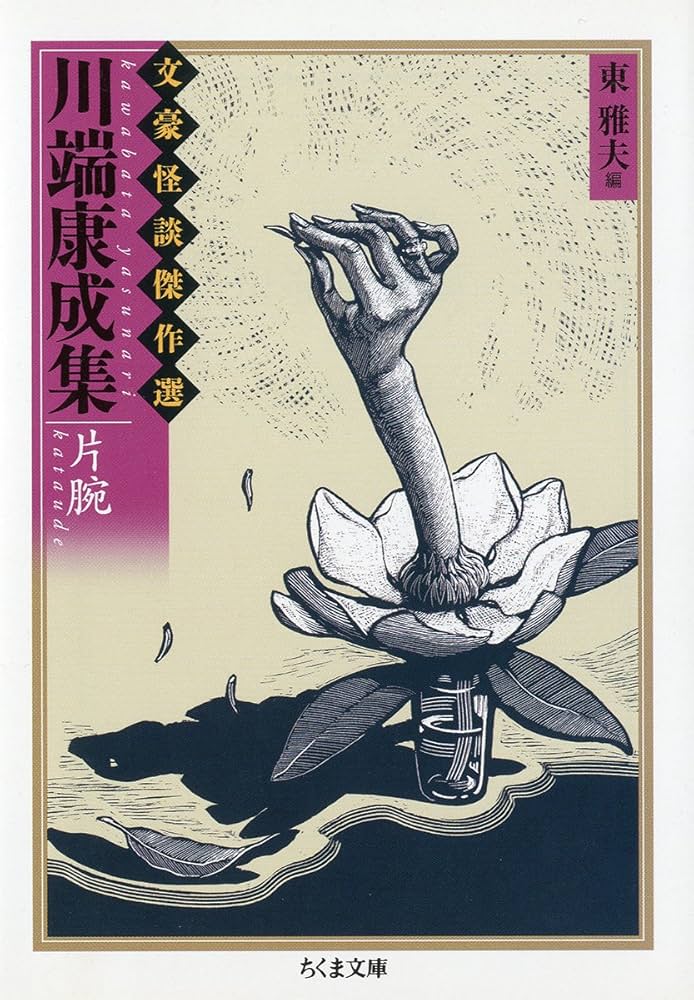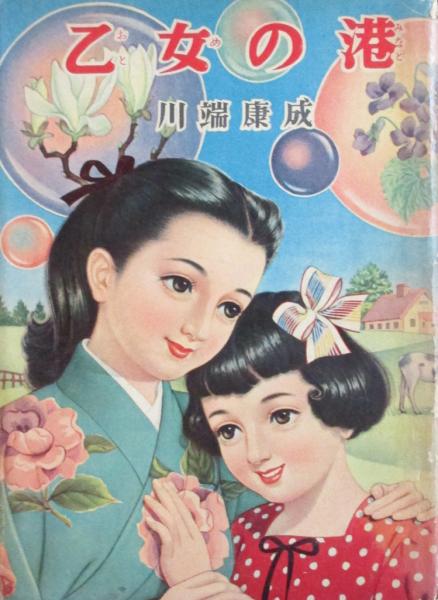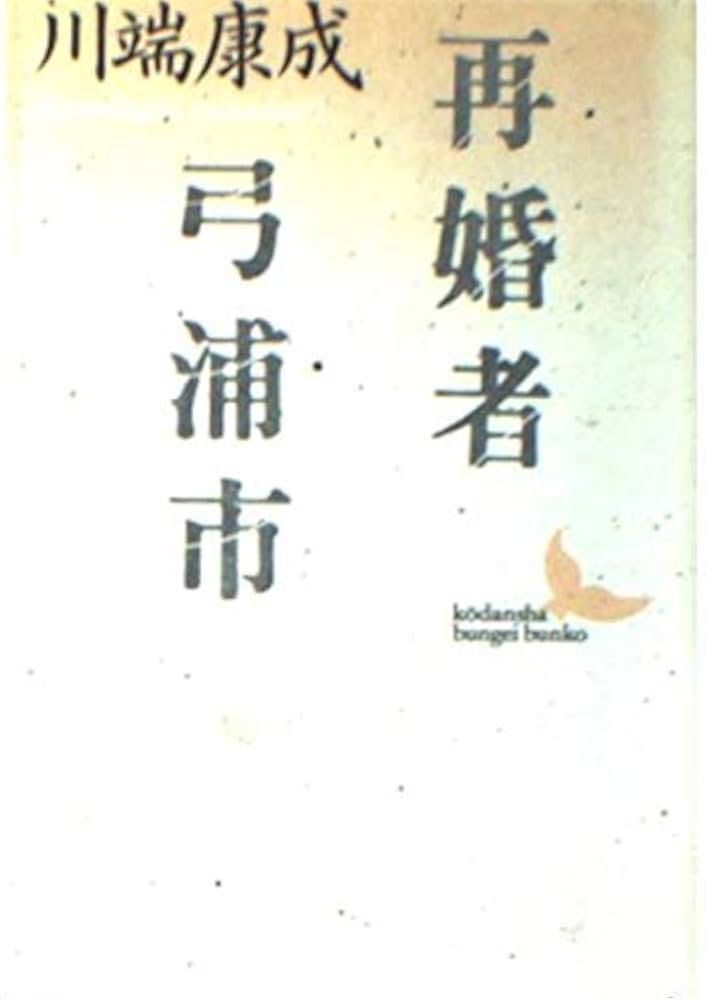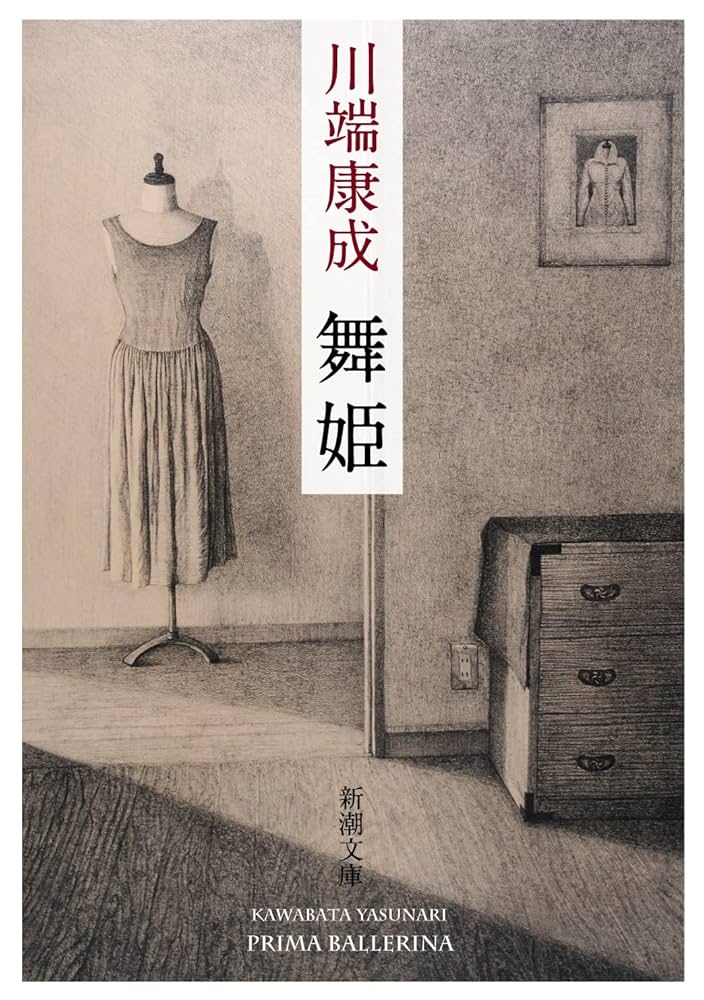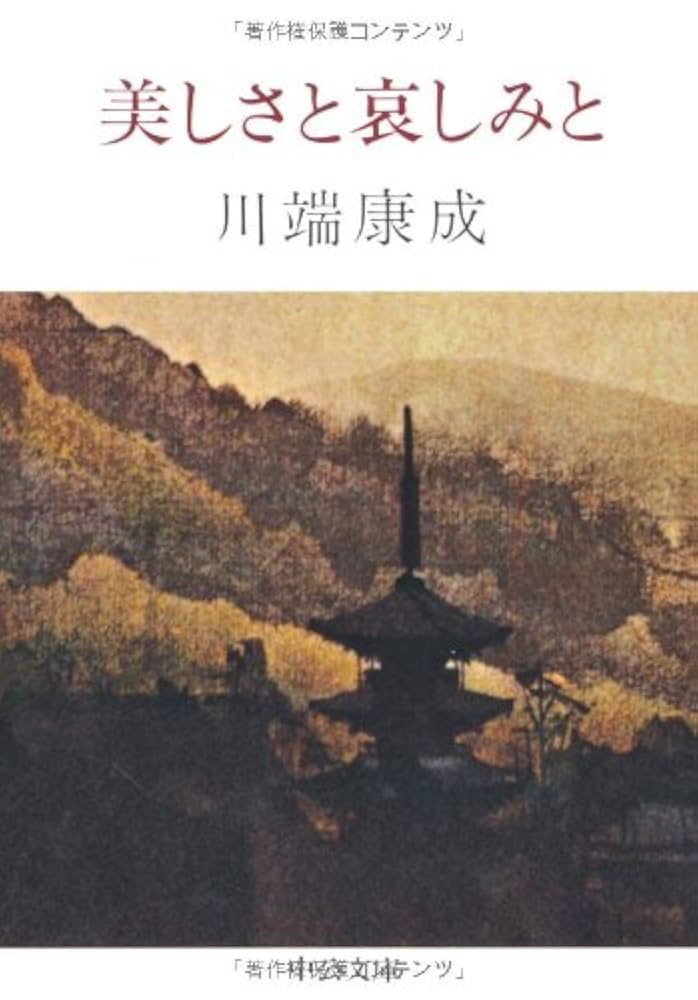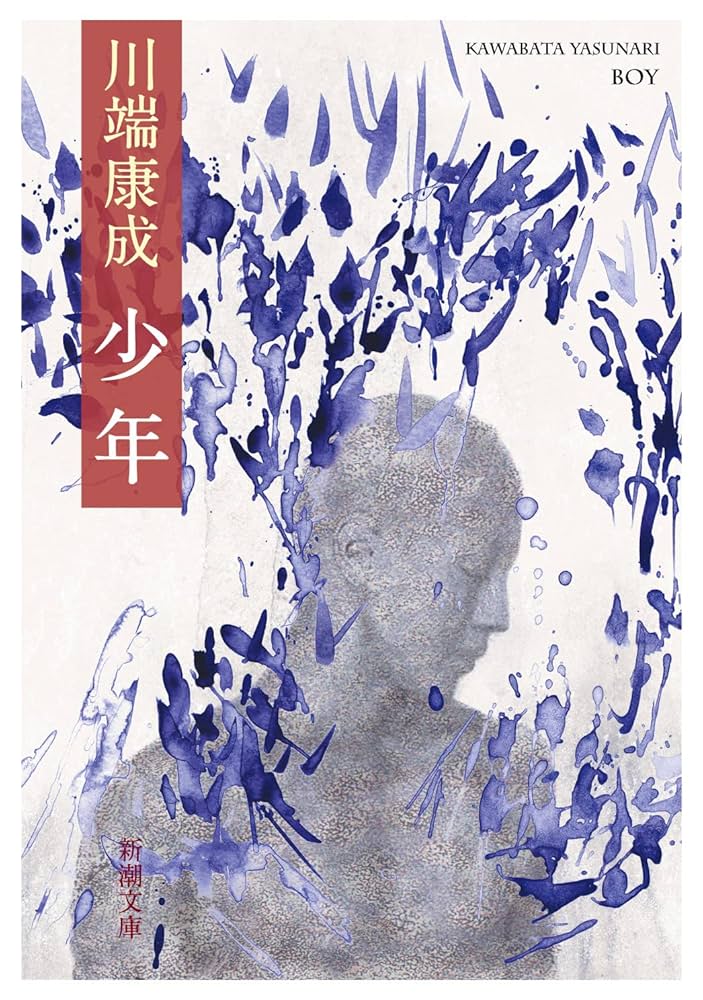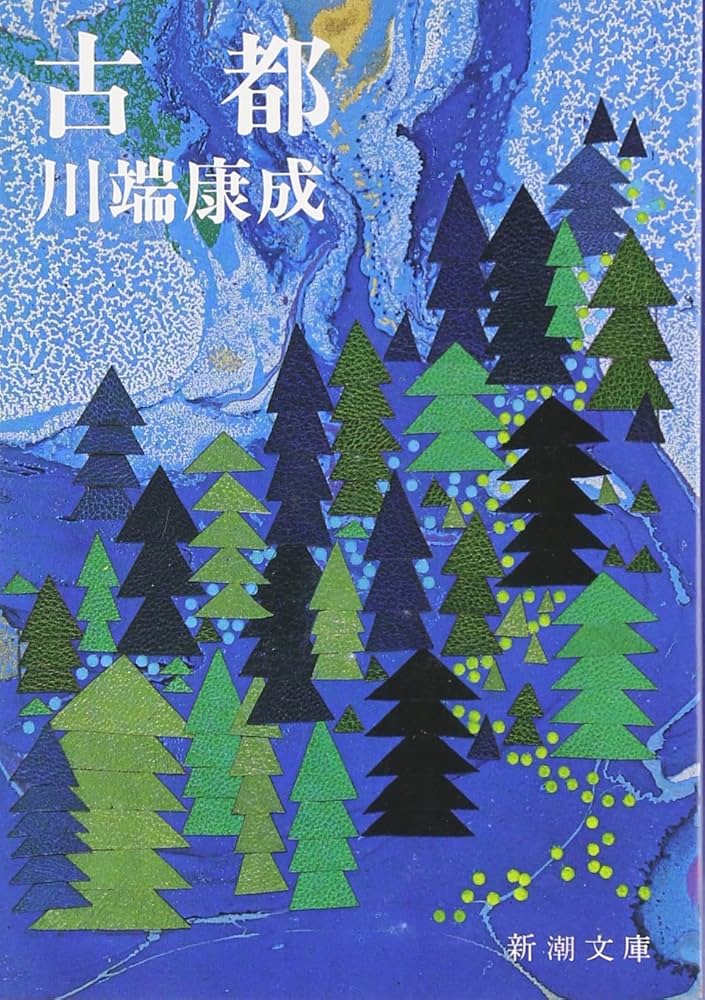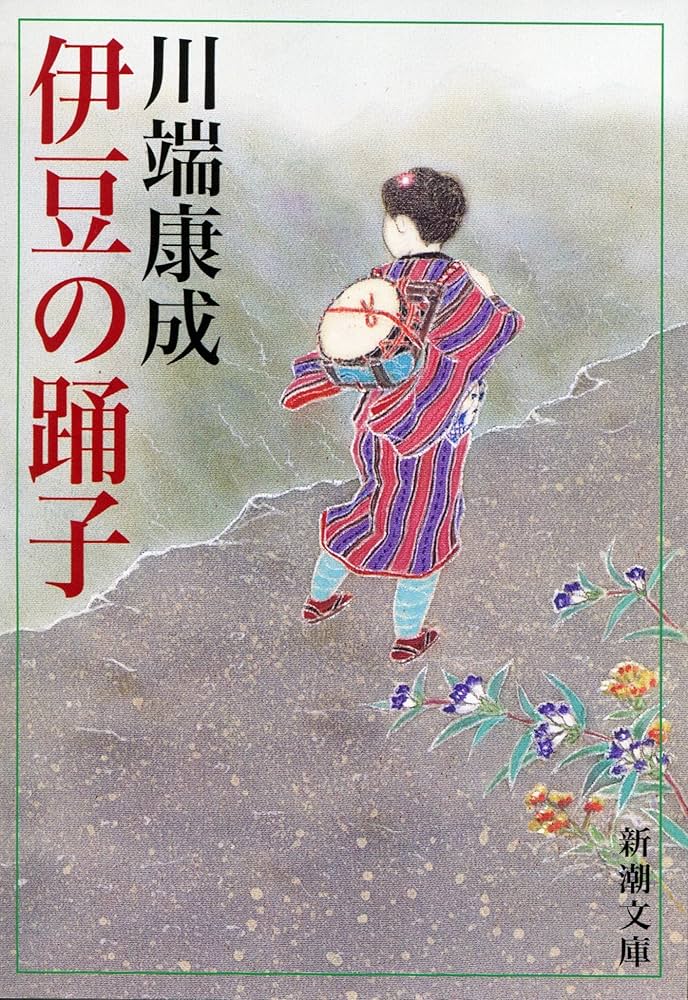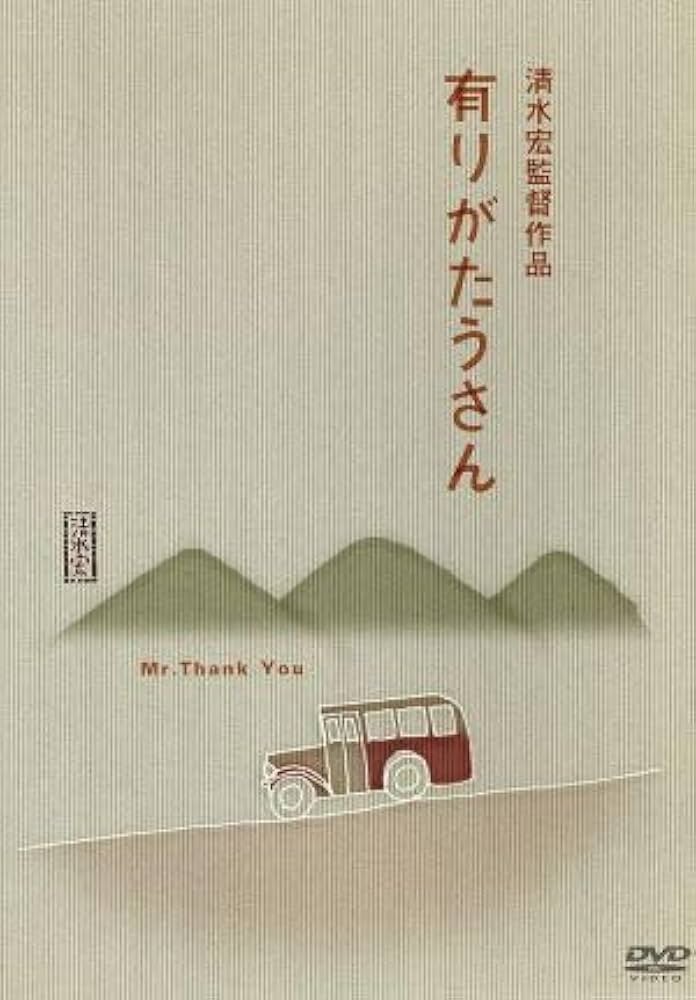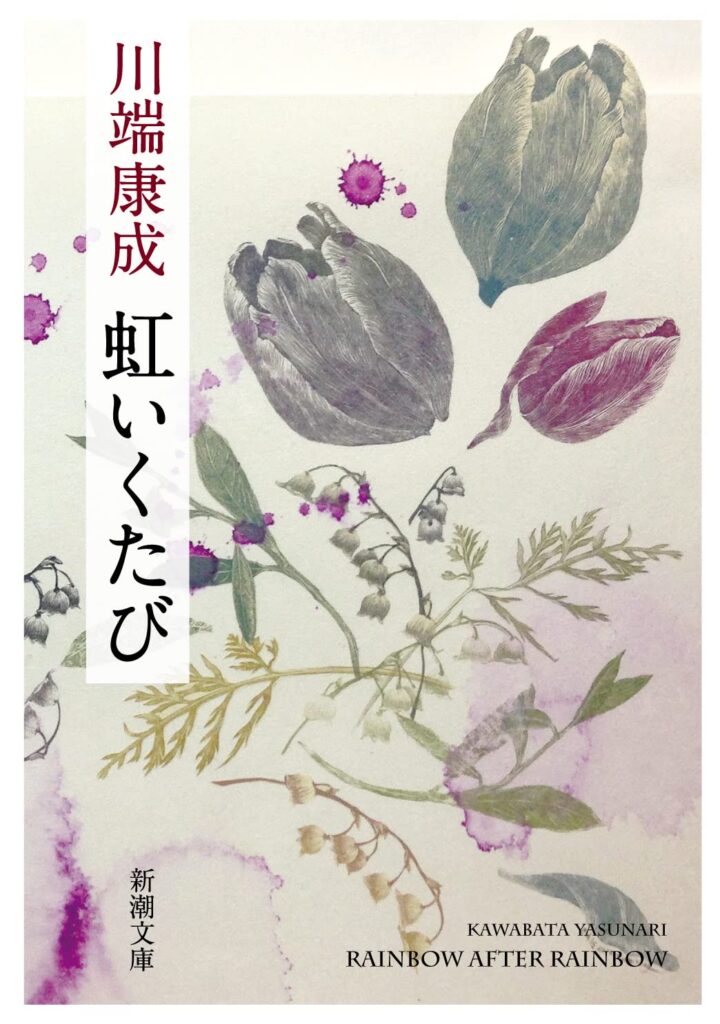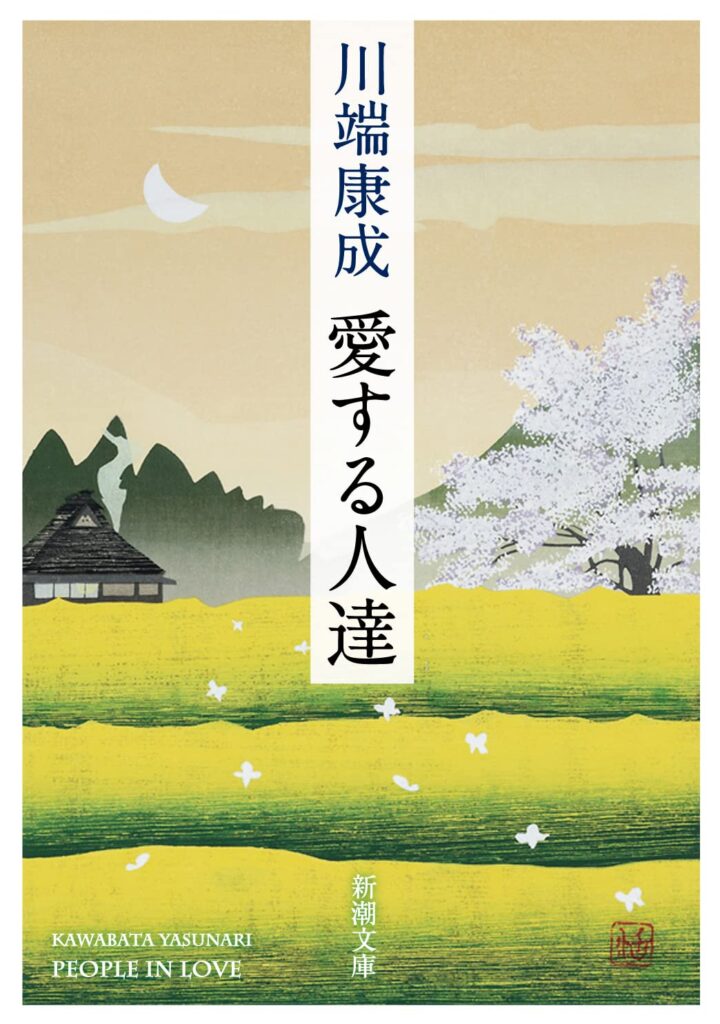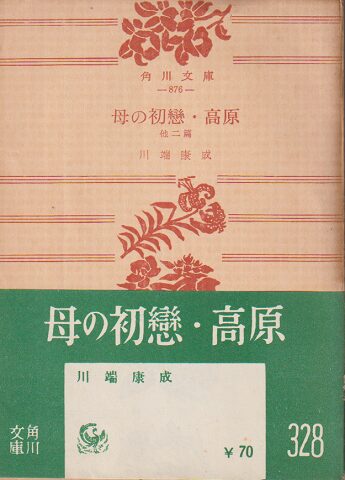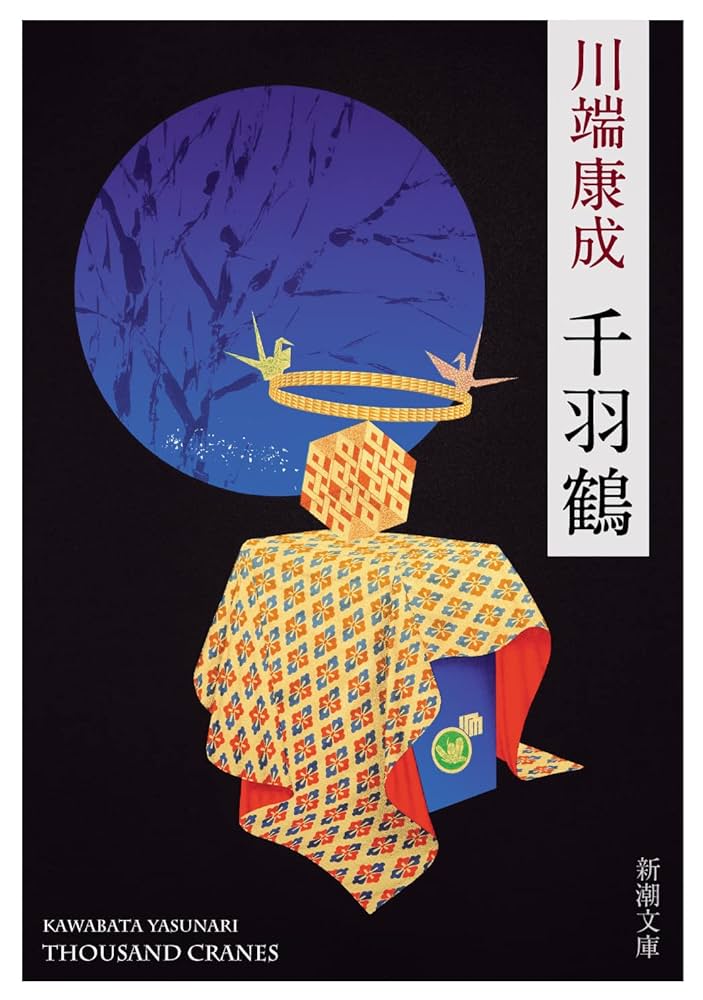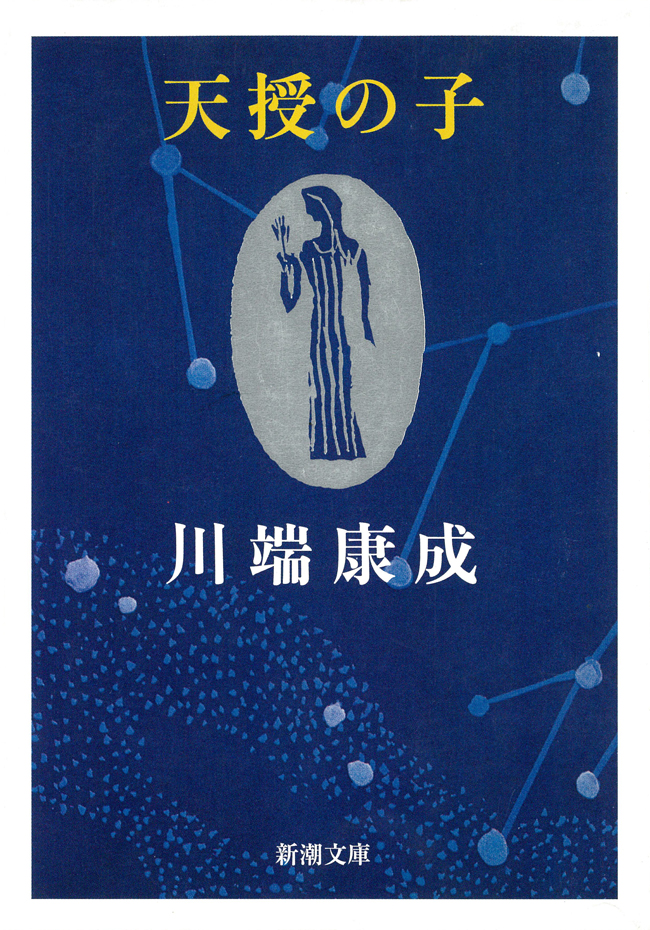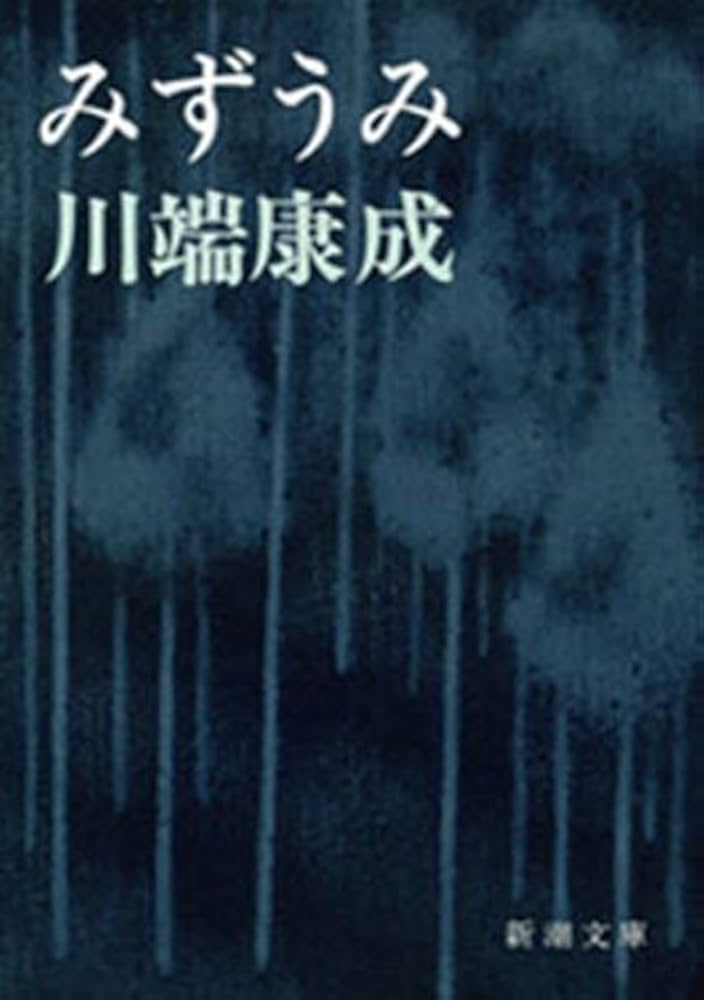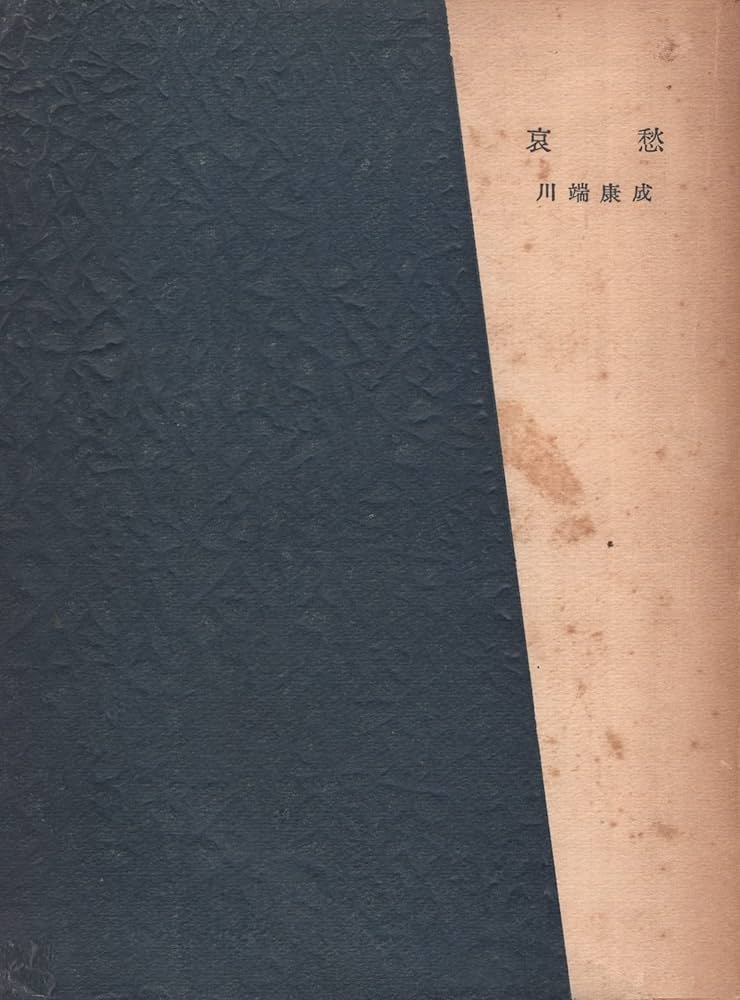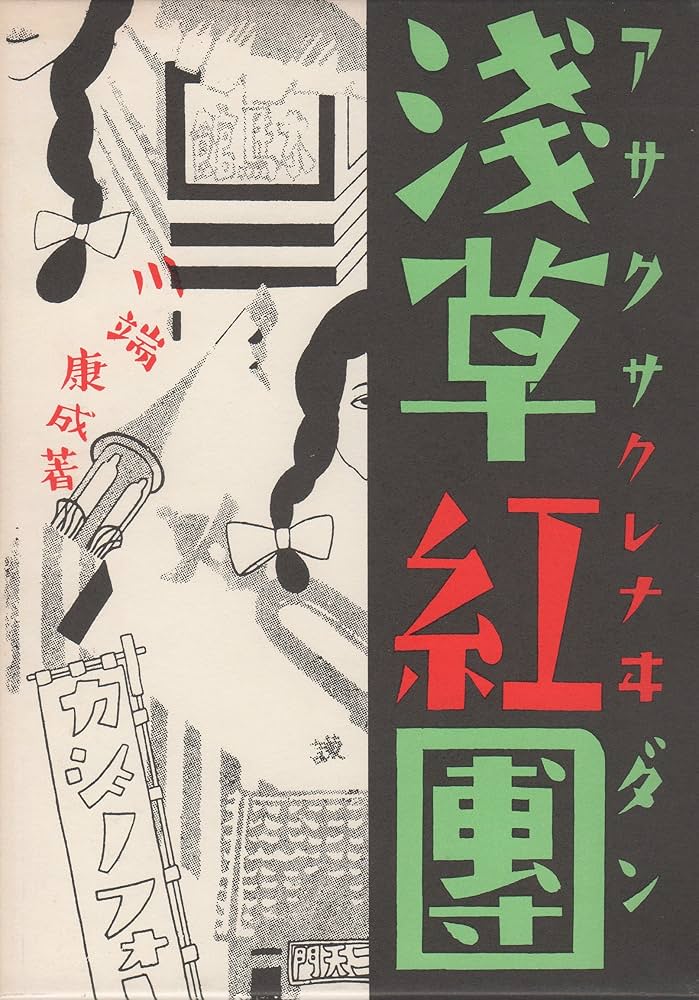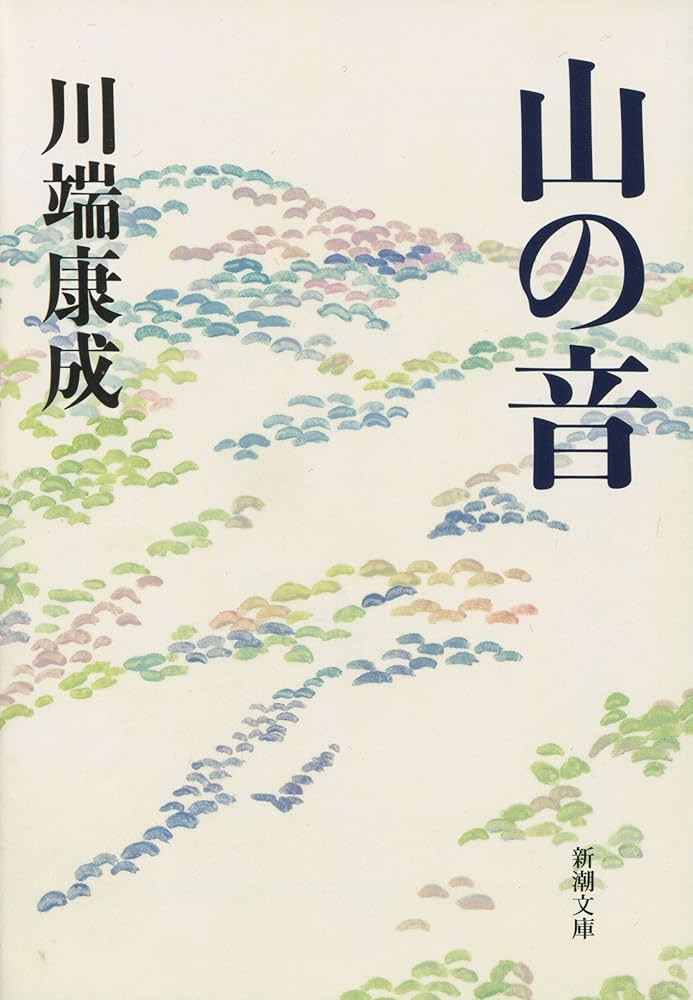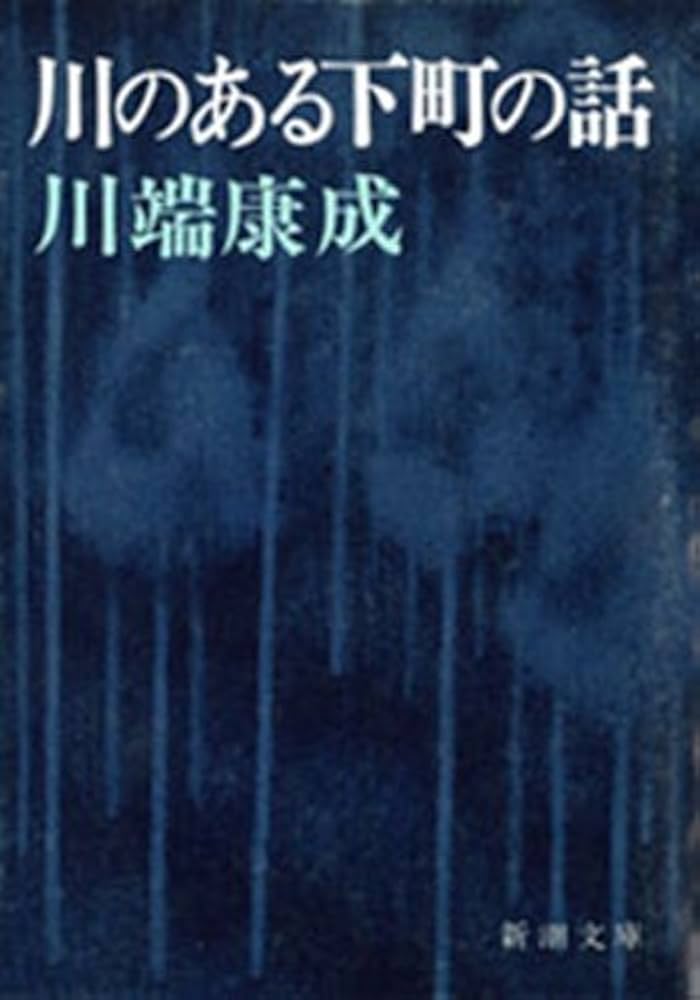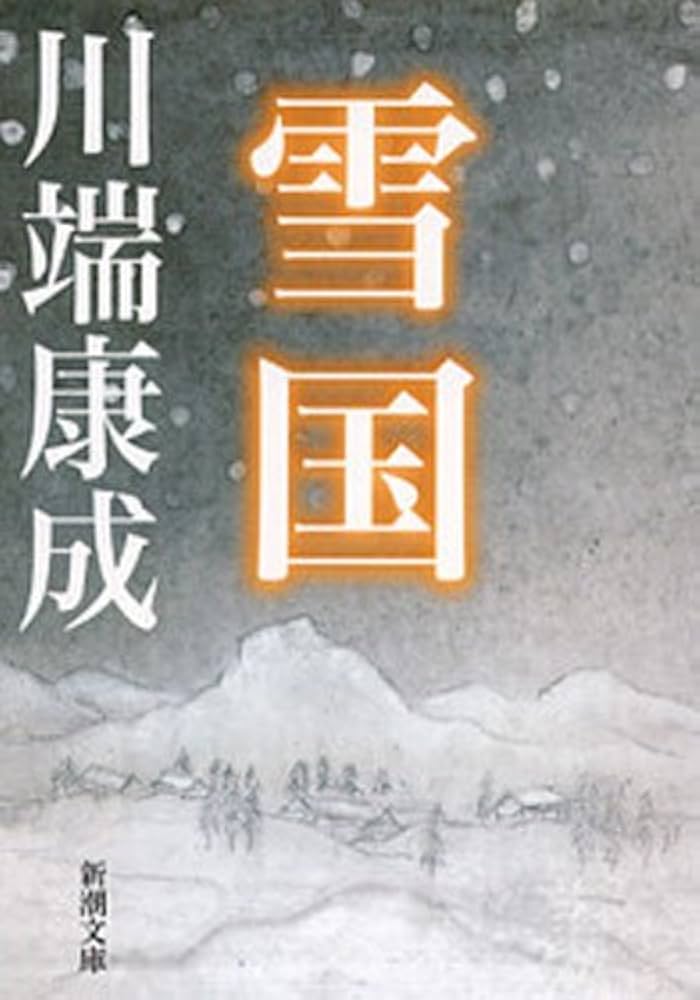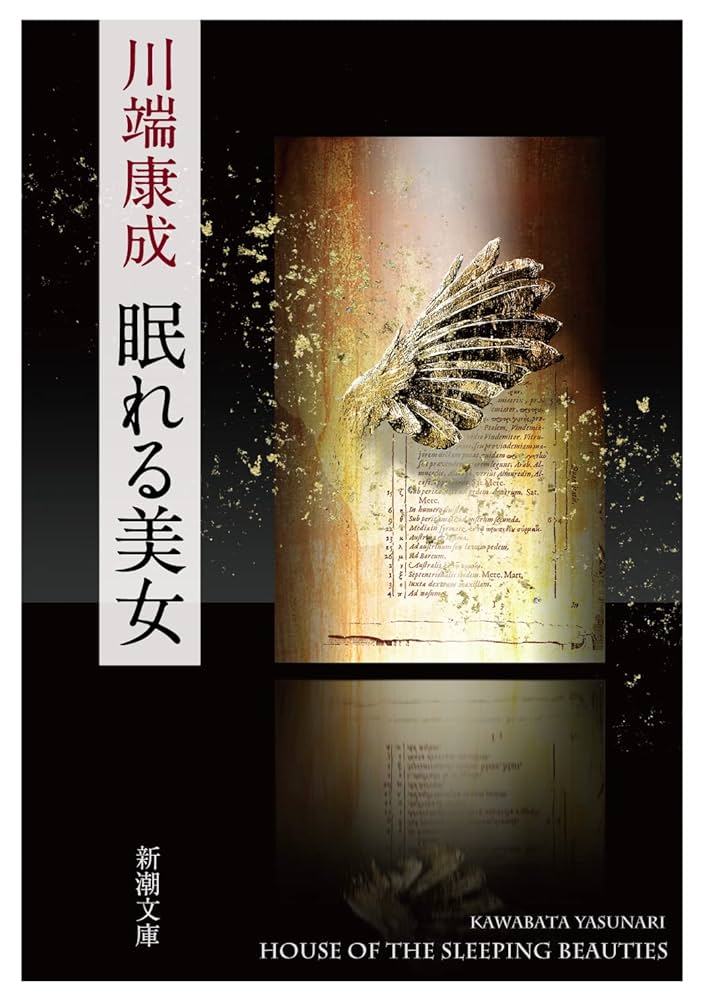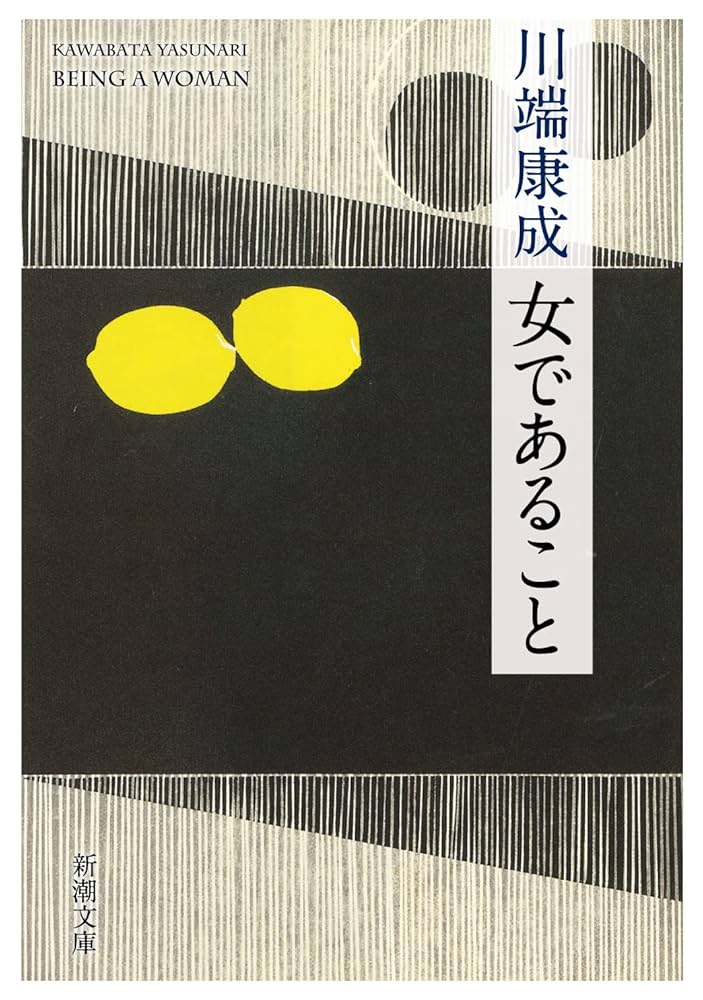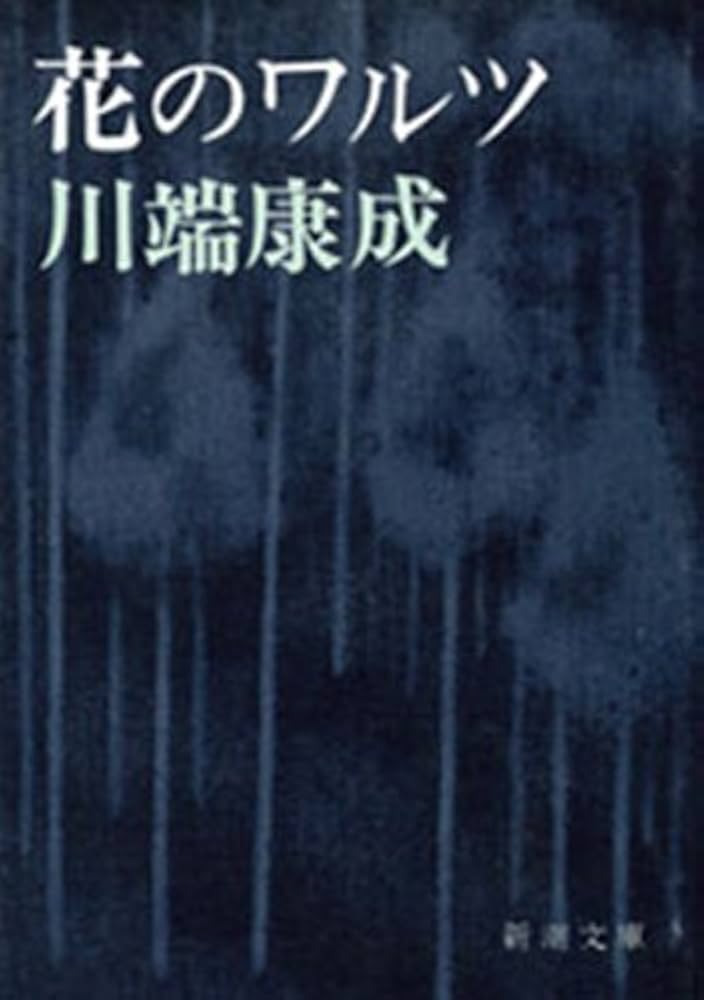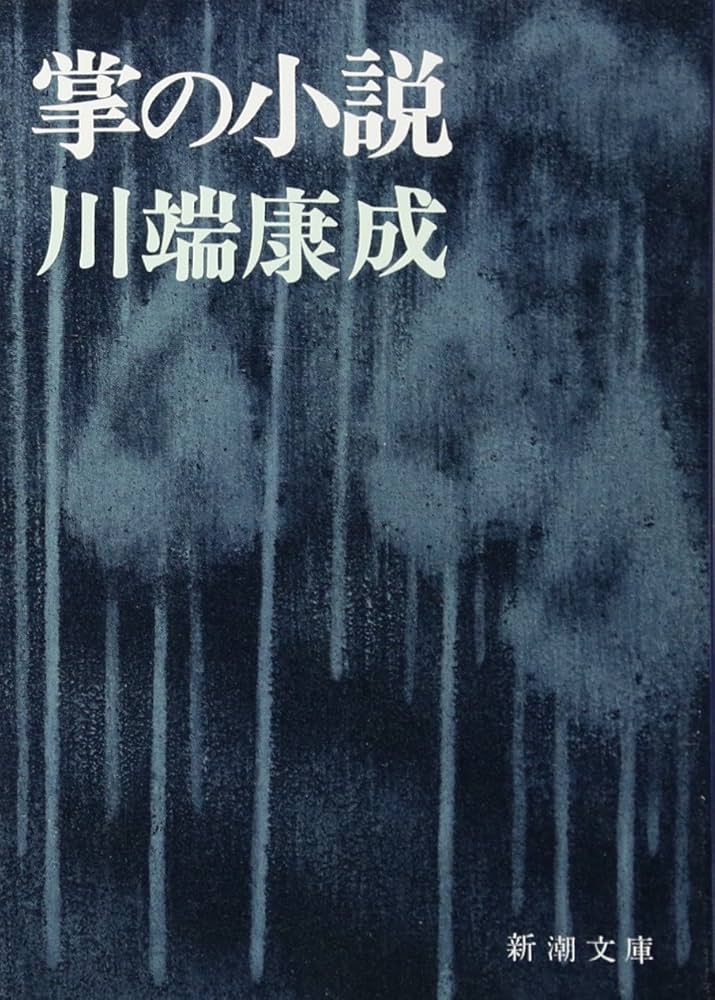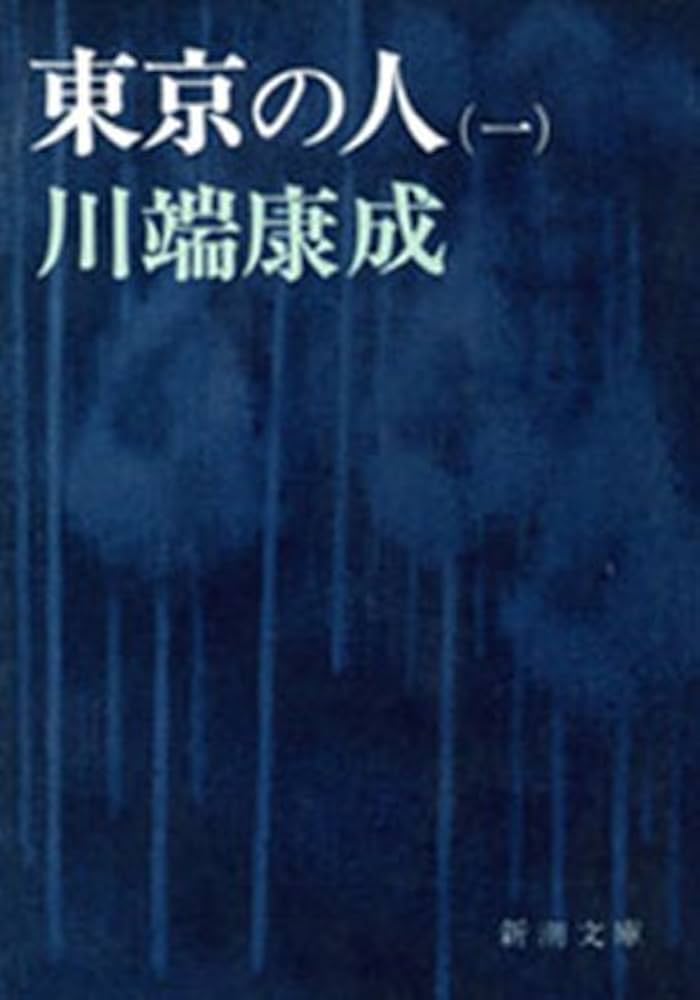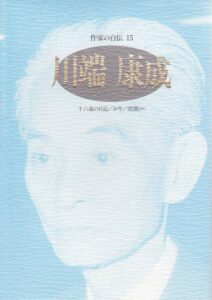 小説「十六歳の日記」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「十六歳の日記」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この作品は、川端康成がノーベル文学賞を受賞した大作家となる、はるか昔の記憶から生まれました。驚くべきことに、この日記の原稿は作者自身がその存在をすっかり忘れていて、何十年も経ってから偶然発見されたものなのです。まるでタイムカプセルのように、過去から未来の自分へ届けられたのですね。
作者が忘れてしまうほど強烈だった体験、それは最後の肉親である祖父の死を、たった一人で看取った日々の記録です。十六歳の少年が背負うにはあまりにも重いその記憶を、心が無意識に封じ込めてしまったのかもしれません。しかし、この忘却こそが、個人的な痛みを普遍的な文学へと高めるきっかけとなりました。
この記事では、そんな川端文学の「原点」ともいえる『十六歳の日記』の世界を深く掘り下げていきます。少年の目に映った世界の息苦しさと、その中にきらめく美しさとは何だったのか。ネタバレを含みますので、物語の核心に触れたい方は、ぜひこのまま読み進めてみてください。
「十六歳の日記」のあらすじ
物語の舞台は、大正時代の日本のとある家。主人公である十六歳の「私」は、中学校に通いながら、寝たきりの祖父と二人きりで暮らしています。学校から帰って玄関の戸を開けても、「ただいま」の声に返事はありません。家の中はしんと静まりかえり、少年の孤独が際立ちます。
祖父は白内障でほとんど目が見えず、耳も遠くなっています。自分で寝返りを打つことすらできず、一日中布団の上で過ごしていました。「私」の日常は、そんな祖父の介護に追われます。食事の世話、下の世話、そして終わりの見えない看病。それは少年が愛情を注ぐべき行為であると同時に、強烈な嫌悪感を抱かせるものでもありました。
ある日、少年は祖父の排尿を手伝います。苦痛にうめく祖父の声に涙ぐみながらも、少年は汚れた尿瓶の後始末に、耐えがたい現実の醜さを感じています。愛情と嫌悪、優しさと苛立ち。相反する感情が少年の心の中で渦を巻く、息の詰まるような毎日が淡々と、しかし鮮烈に描かれていきます。
やがて、祖父の容態は日に日に悪化していきます。これまで頑なに医者を拒んでいた祖父が、初めて往診に来た医者に涙を流して感謝する場面も。終わりが近いことを予感しながら、少年は祖父との最後の日々を過ごします。物語は、その緊迫した時間の中で、ある決定的な日を迎えることになります。
「十六歳の日記」の長文感想(ネタバレあり)
『十六歳の日記』は、川端康成という作家の魂の設計図のような作品だと、私は感じています。後年の華麗な作品群の源流が、この短い日記の中にすべて詰まっているように思えるのです。ここからは、その核心に触れるネタバレを含んだ感想をお話しさせてください。
この日記が特別なのは、何よりもその「発見の経緯」にあります。川端自身が完全に忘れていたという事実は、単なる面白いエピソードではありません。もし彼がこの日記をずっと手元に置いていたら、それは生々しい痛みの記録であり続けたでしょう。しかし、忘却という長い時間が、作者と作品の間に必要な距離を生み、個人的な体験を客観的な文学として見つめ直すことを可能にしたのです。
この再会によって、川端はかつての自分の中に、生涯をかけて描くことになるテーマの原型を見つけ出します。それは、人の顔色をうかがうことで形成された「孤児根性」や、見えない祖父を見つめることで生まれた「見る愛」といった、彼自身の心の深い部分に根差したものでした。忘れていたからこそ、これらは普遍的な輝きを放つ原石として再発見されたのですね。
物語が描き出すのは、息が詰まるような閉ざされた世界です。学校から帰った少年を待つのは、返事のない静寂と、病に伏せる祖父の存在だけ。この二人きりの空間で、少年は祖父の介護という、愛情と嫌悪が混じり合った複雑な行為に日々向き合います。
祖父の身体は、老いと病によって刻一刻と朽ちていきます。食事をしたことすら忘れてしまう姿、しわだらけの皮膚、そして絶え間なく続くうめき声。これらは少年の心をじわじわと蝕んでいきます。特に排泄の介助は、少年が直面する現実の醜さを凝縮した場面として描かれています。
祖父の苦しむ声に涙しながらも、汚物にまみれた世話には強烈な嫌悪感を抱く。この相反する感情こそが、この日記全体を支配する張り詰めた空気の正体です。読んでいるこちらも、その苦しいほどのアンビバレントな気持ちに胸が締め付けられるようです。この生々しい感情の描写に、物語の核心的なネタバレが含まれているといえるでしょう。
しかし、この極限状況の中から、川端文学の真骨頂ともいえる美学が生まれます。それは、批評家が「しびんの底に清水の音を感じる才能」と評した、あの有名な感覚です。醜い現実のまっただ中で、そこから逃れるように感覚を研ぎ澄ませ、美を見つけ出そうとする力。これは川端康成という作家だけが持つ、特別な感受性の最初の輝きでした。
これは、ただ「醜いものの中に美しさを見つける」という単純な話ではありません。耐え難い光景や臭気から意識をそらし、聴覚へと逃避し、尿の音を「清水の音」という詩的なイメージへと転換させる。これは、つらい現実を生き抜くための、少年の創造的な自己防衛だったのです。この感覚の転換によって、彼は一瞬だけ、現実の恐怖から解放されます。美を求める心が、生きるための力と深く結びついていることを、この一節は鮮やかに示しています。
この作品の関係性の中心にあるのは、祖父の「盲目」と、少年の「見る」という行為が生み出す、特別な力関係です。祖父は目が見えないため、少年の視線に応えることができません。この一方通行の視線が、二人のコミュニケーションのあり方を決定づけています。
言葉でのやり取りが難しくなるにつれて、少年が祖父を理解する手段は、ひたすら「観察」することだけになります。彼は祖父の顔をじっと見つめ、そこに浮かぶ生と死の気配を読み取ろうとします。この「見る」という行為は、単なる監視ではなく、消えゆく祖父とのつながりを保とうとする、必死の愛情表現でした。そして、この「見る愛」の究極の形が、まさしくこの日記そのものなのです。見ることで理解し、書き留めることで永遠にしようとしたのですね。
この「見る」行為は、川端自身の「孤児根性」とも深くつながっています。親戚の家で人の顔色をうかがって育った川端は、人をじっと見る癖を、卑屈な性質だと自己嫌悪していました。しかし後年、その癖の根源が、実は盲目の祖父を理解しようとした愛情にあったと気づきます。この解釈の転換は、彼にとって自分自身を肯定する、大きな救いとなったことでしょう。
一方で、この関係には逆の力も働いています。それは祖父の「見ない愛」です。目が見えないからこそ、祖父は少年が介護の際に見せるかもしれない嫌悪の表情や、思春期のもどかしさを見ることがありません。彼はただ、少年の存在そのものを無条件に受け入れてくれます。この視線の不在が、他者の評価から解放された絶対的な安全地帯を少年に与えていたのです。
少年は祖父に自分の「眼」を貸し、祖父は「眼」がないことで、少年の魂に裁かれることのない自由な場所を提供する。この視覚と安全の交換こそが、この日記の感情の核であり、後の川端文学が描き続ける愛と孤独、そして救済のモデルが生まれた瞬間でした。このあたりの心理描写の深さも、この物語の重要なネタバレと言えるかもしれません。
物語は、祖父の死が間近に迫る緊迫した時間へと進んでいきます。ある日、少年は家の外の世界で行われる、昭憲皇太后のご大葬に参列したいと願います。しかし、その道中で下駄の鼻緒が切れるという不吉な出来事が起こり、彼はすぐに家へと引き返します。彼の心が、祖父の運命と強く結びついていることを示す象徴的な場面です。
そして、この日記で最も重要なのは、書かれなかったこと、つまり祖父の死の瞬間の描写が完全に抜け落ちているという事実です。物語は、その日の出来事から、死後の場面へと一気に飛んでしまいます。この「語りの空白」は、単なる省略ではありません。それは、少年のアイデンティティの根幹であった「見る愛」が、その限界にぶつかり崩壊したことの証なのです。
彼のすべては「見ること」で成り立っていましたが、死という絶対的なものに直面した時、その視線は耐えきれず逸らされてしまいます。後の作品で川端が書いているように、少年は死の最終局面を「見る」ことができなかったのです。その結果、記録に決定的な空白が生まれました。この空白こそが、どんな言葉よりも雄弁に、絶対的な喪失の衝撃を物語っています。
祖父の死の瞬間という「語りの空白」がもたらした衝撃は、やがて身体的な症状として現れます。葬儀の準備中、喪主である少年は、生まれて初めて鼻血を出すのです。彼は「自分の弱い姿を見せたくなかつた」と、その場を慌てて駆け出します。この出来事について川端自身が後年、「この鼻血が祖父の死から受けた私の心の痛みを私に教へた」と語っています。
これは、心と体のつながりから見ても深く理解できます。極度のストレスや悲しみは、実際に体に変化をもたらし、鼻血を引き起こすことがあります。少年の鼻血は、意識から締め出された悲しみや衝撃が、行き場を失い、制御不能な身体という別のルートを通って現れたものでした。血は生命や血縁の象徴であり、その流出は、死によるつながりの断絶を体現しています。
彼は祖父の死の光景を見ることは避けられましたが、自分の手に流れる血の感触は避けられませんでした。意識が拒んだ「痛み」を、身体が強制的に突きつけたのです。この瞬間、祖父の死は、観察の対象ではなく、自分自身の内部で起こる紛れもない現実となったのでした。この身体的なネタバレは、物語の悲しみをより一層深いものにしています。
『十六歳の日記』は、川端文学全体の「源流」と呼ぶにふさわしい作品です。ここで描かれた、孤独な自己との闘いや救済への渇望、醜さの中の美、生と死、愛と嫌悪、そして視線をめぐる問題はすべて、後の彼の作品で繰り返し、より深く描かれていくことになります。特に、遺作となった『たんぽぽ』で描かれる、人の体だけが見えなくなる奇病は、この日記の「見る愛」と「見ない愛」の関係が、数十年を経て発展した究極の形と言えるかもしれません。十六歳の少年を苦しめた問いが、世界的作家となった最晩年まで彼を捉えていた証なのです。
まとめ
この記事では、川端康成の「十六歳の日記」について、あらすじからネタバレを含む深い感想までをお話ししてきました。この作品は、作者自身が忘れていたという特異な成り立ちを持つ、彼の文学のまさに原点となる物語です。
十六歳の少年がたった一人で祖父の死を看取るという、息の詰まるような日常。そこには、介護という行為を通して描かれる、愛情と嫌悪の入り混じった生々しい感情がありました。この強烈な体験が、後の川端文学を形作る重要な要素となっていったのです。
醜悪な現実の中で「しびんの底に清水の音」を感じる独特の美意識や、盲目の祖父と「見る」少年との間に生まれる「見る愛」と「見ない愛」の関係性。そして、決定的なネタバレとなる祖父の死の瞬間の「空白」。これら全てが、川端康成という作家の魂の核をなしています。
もしあなたが川端文学の奥深さに触れたいと考えるなら、この『十六歳の日記』は避けて通れない一冊です。短く、そして強烈なこの物語の中に、彼の文学のすべてが凝縮されているのを、きっと感じていただけるはずです。