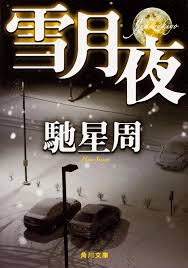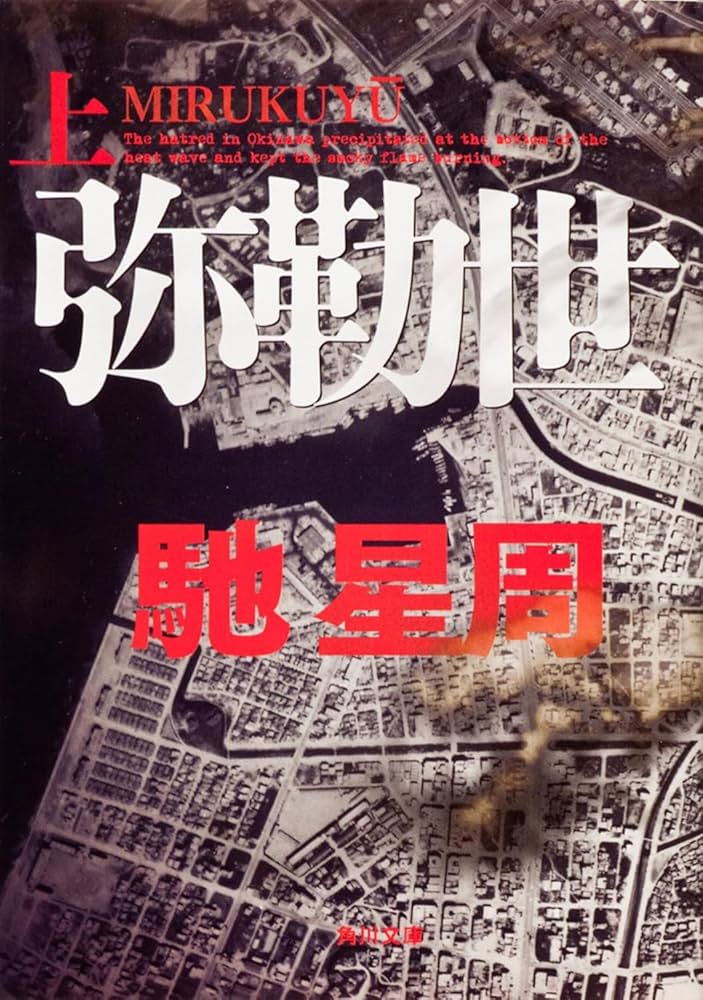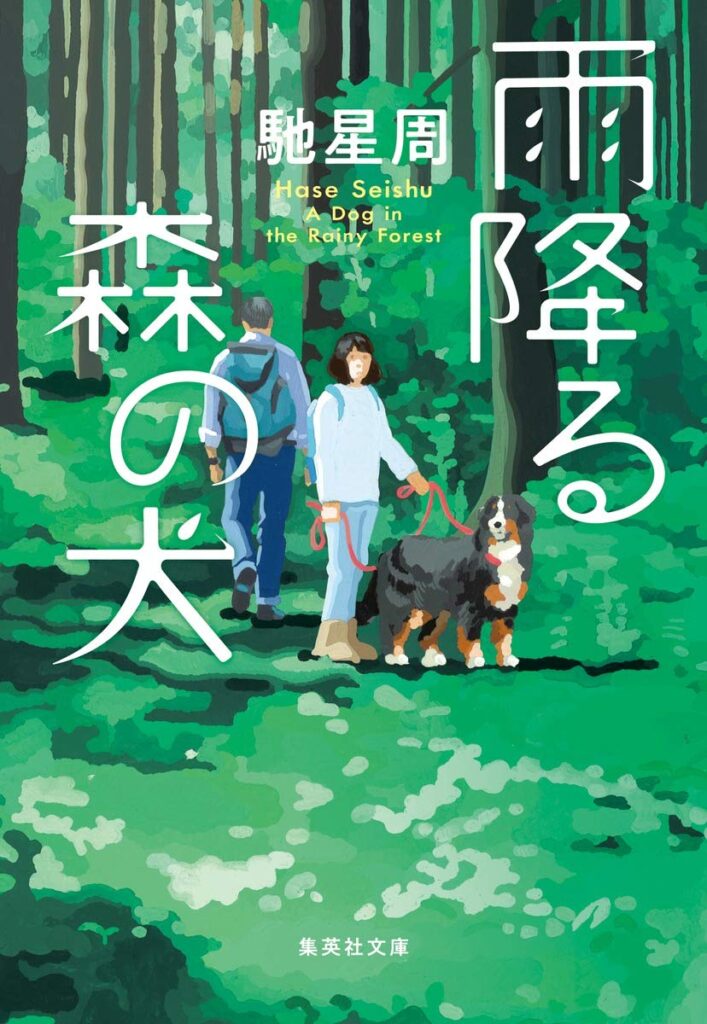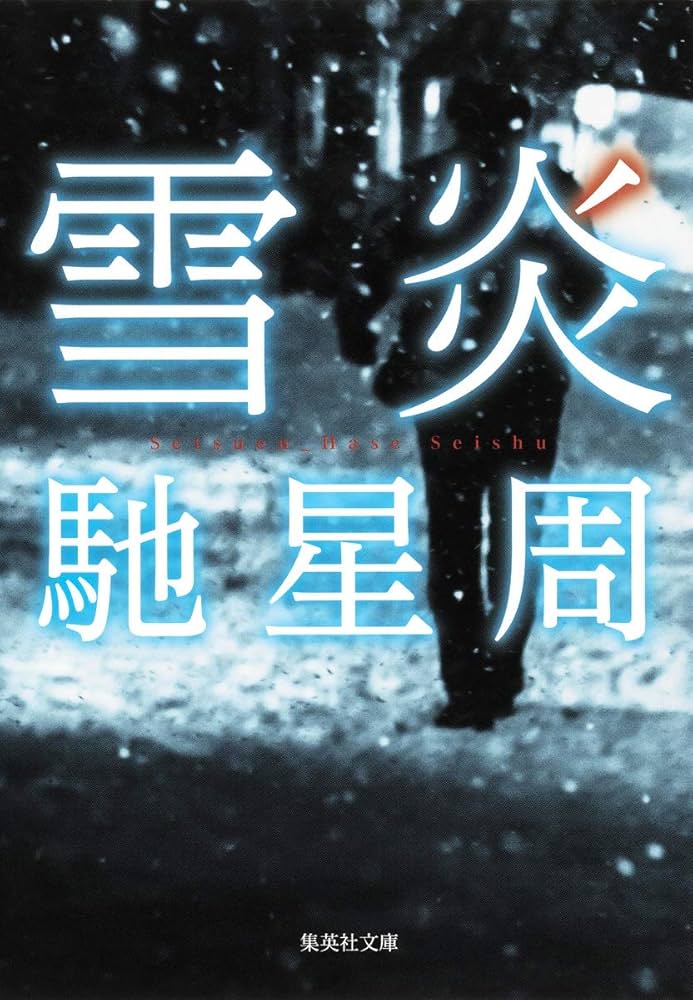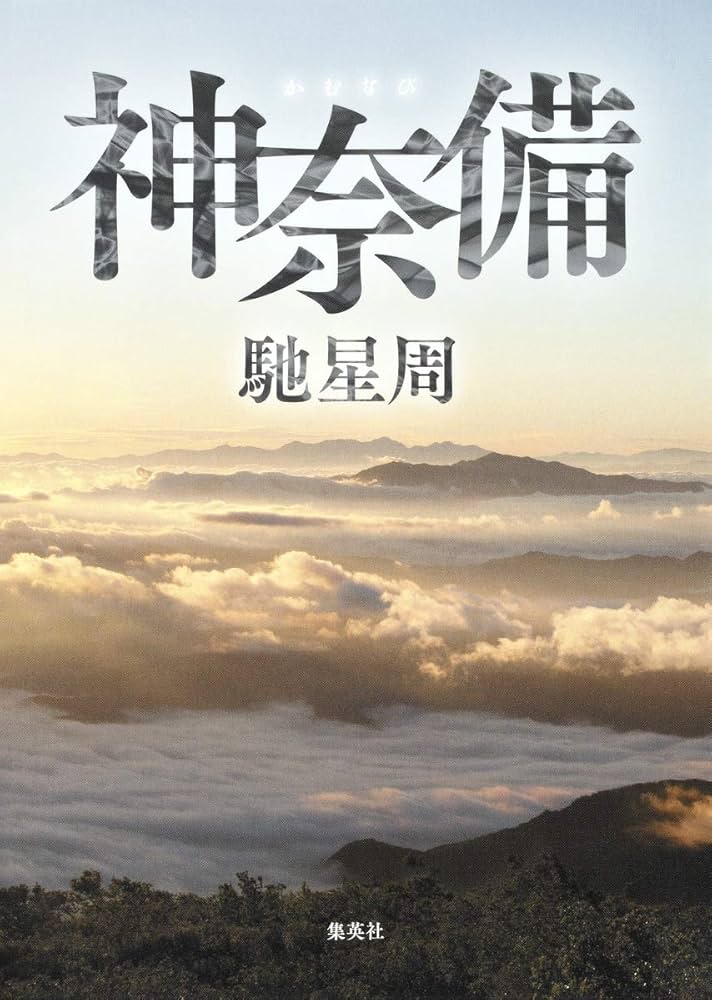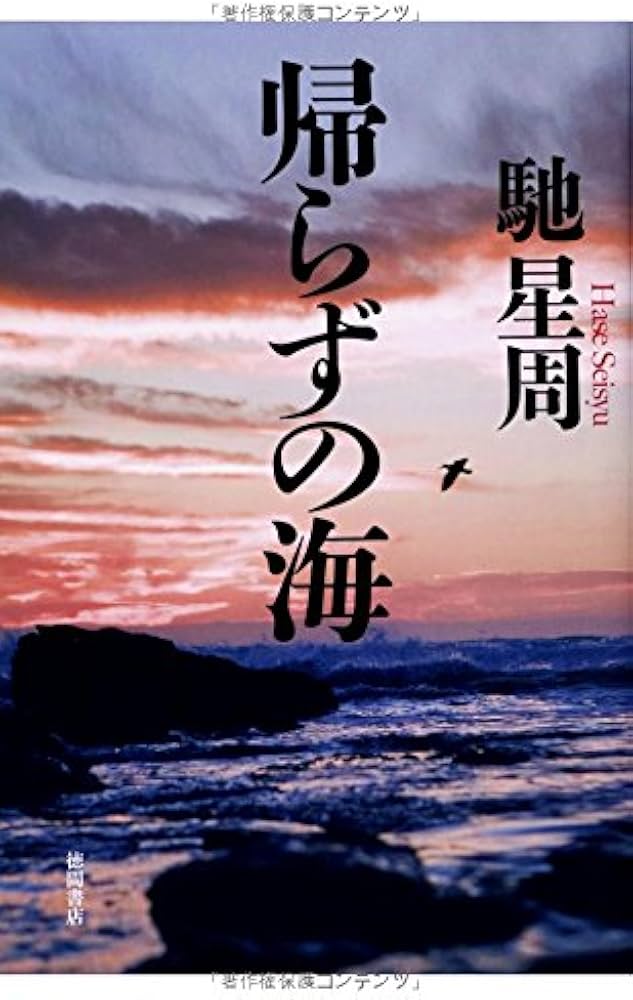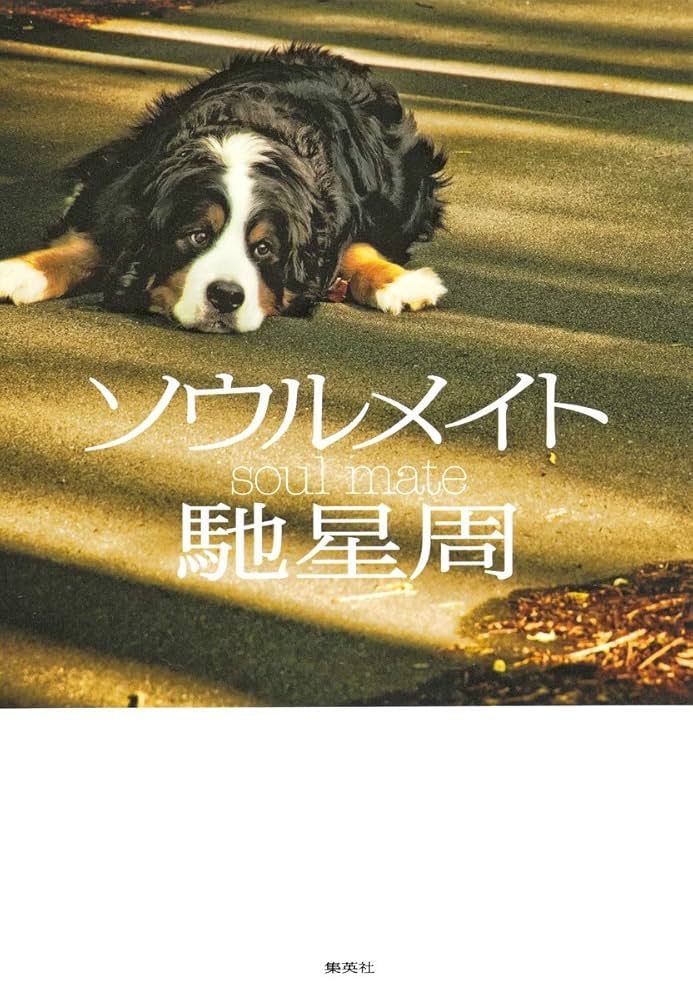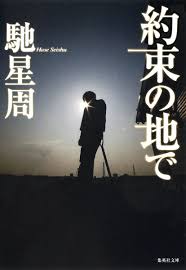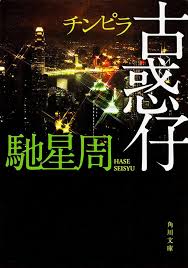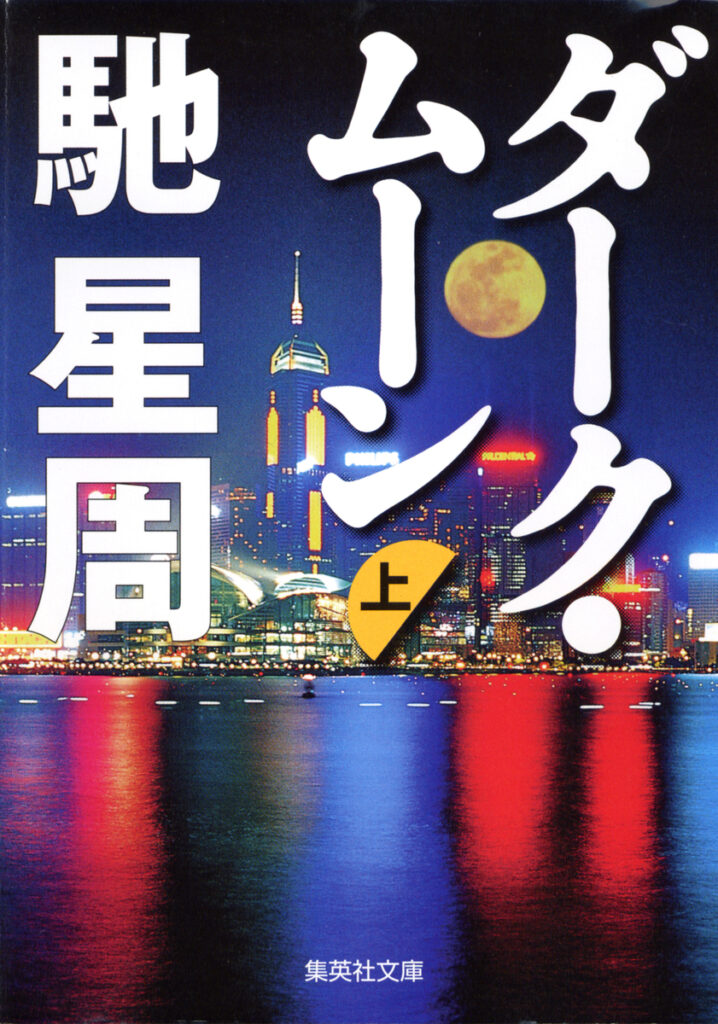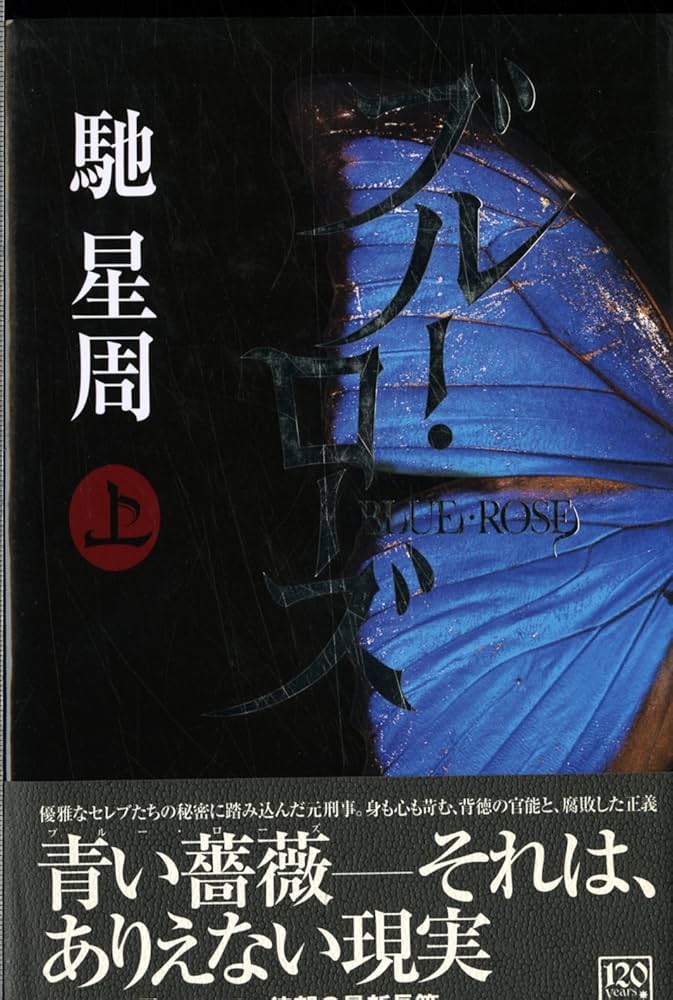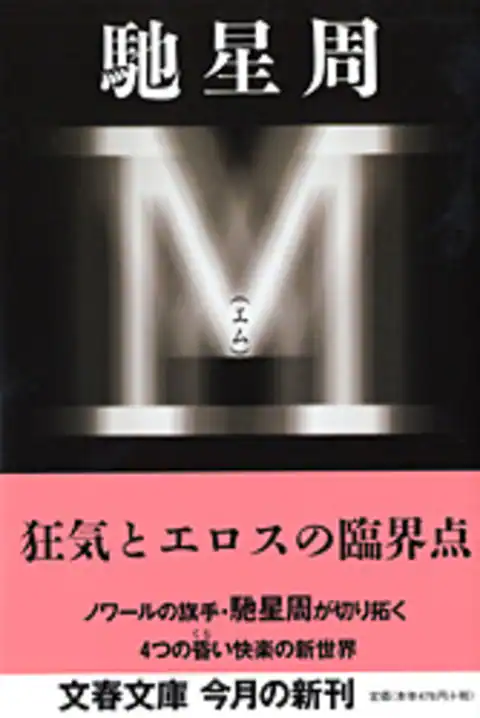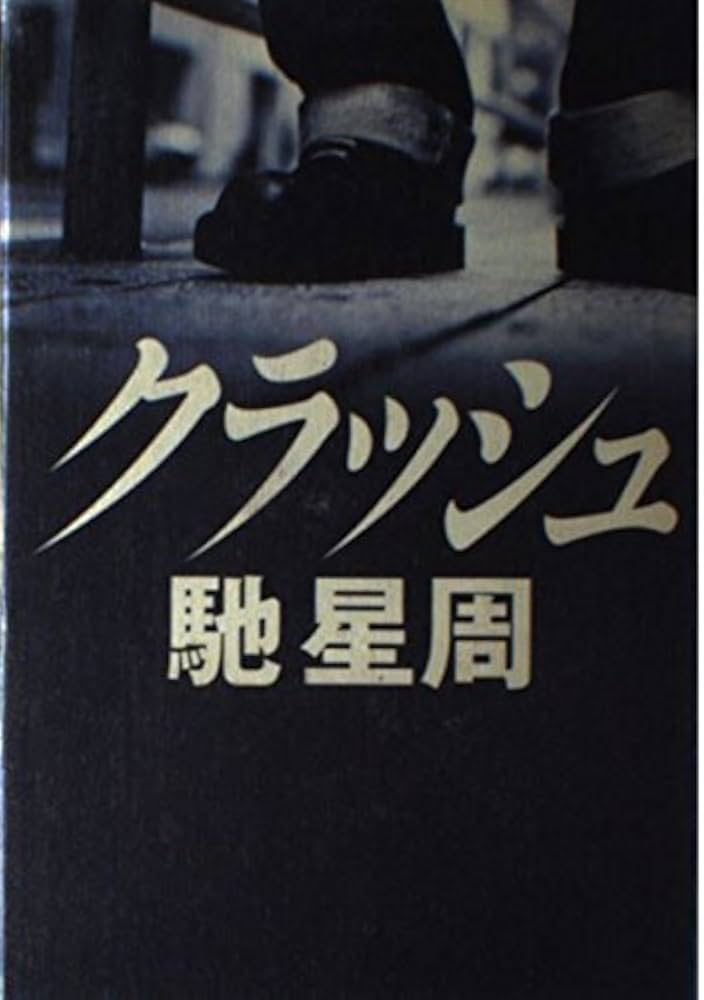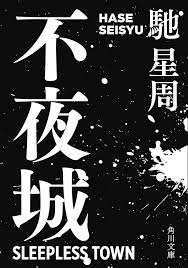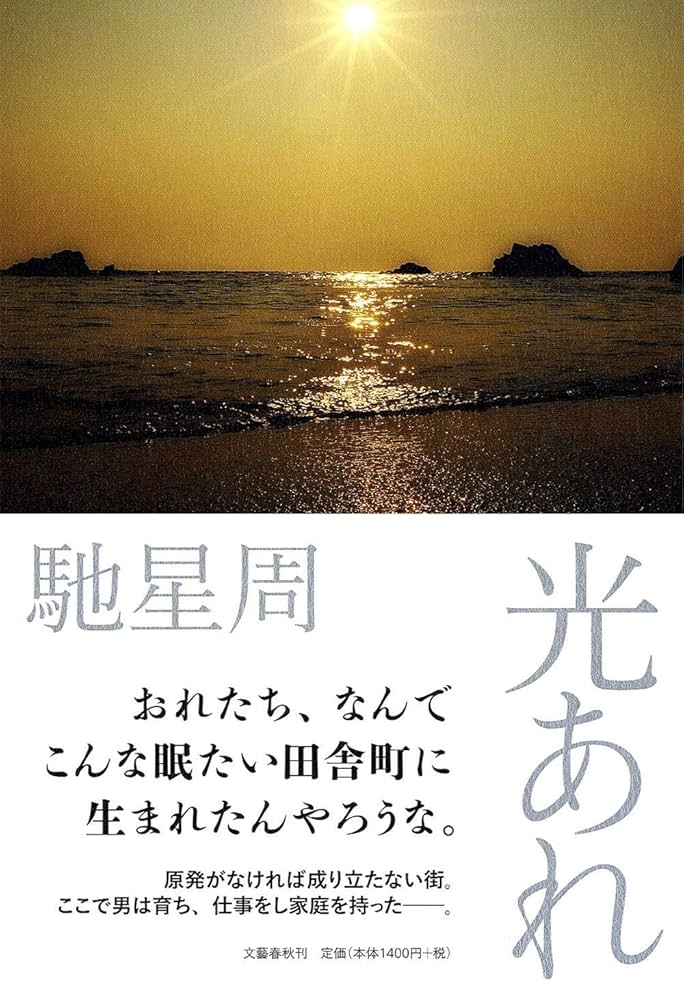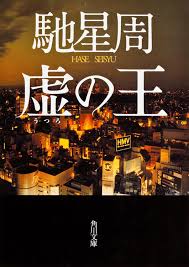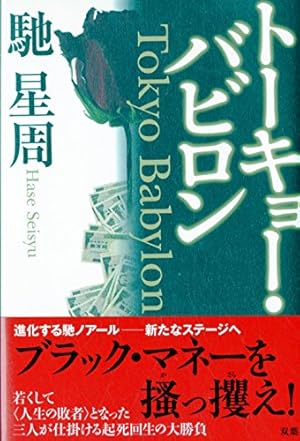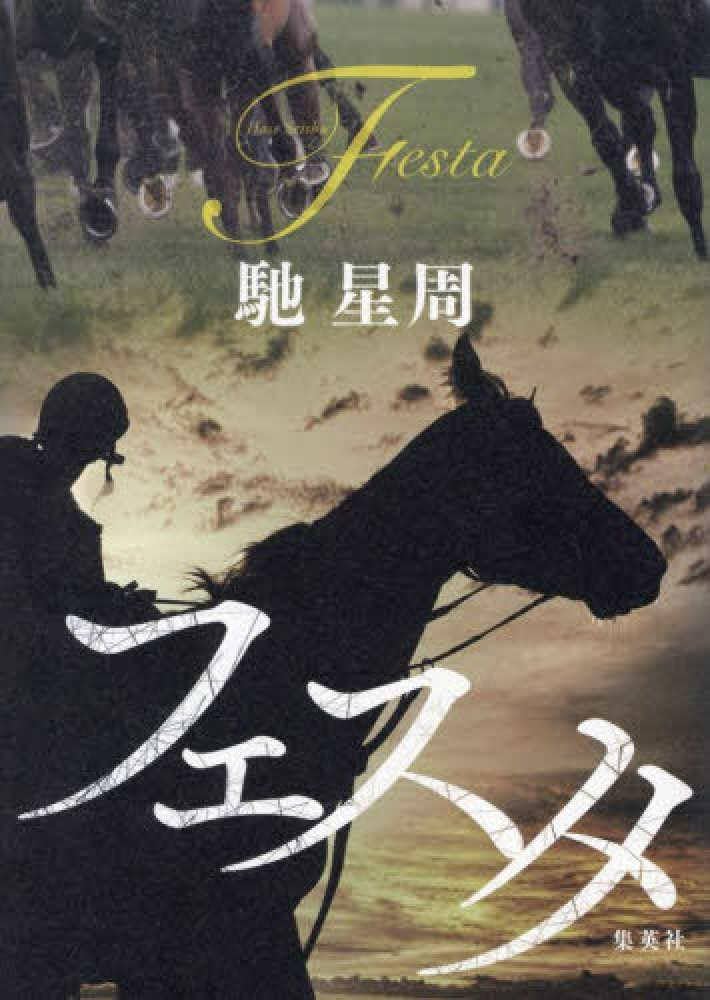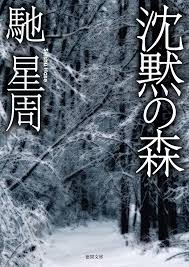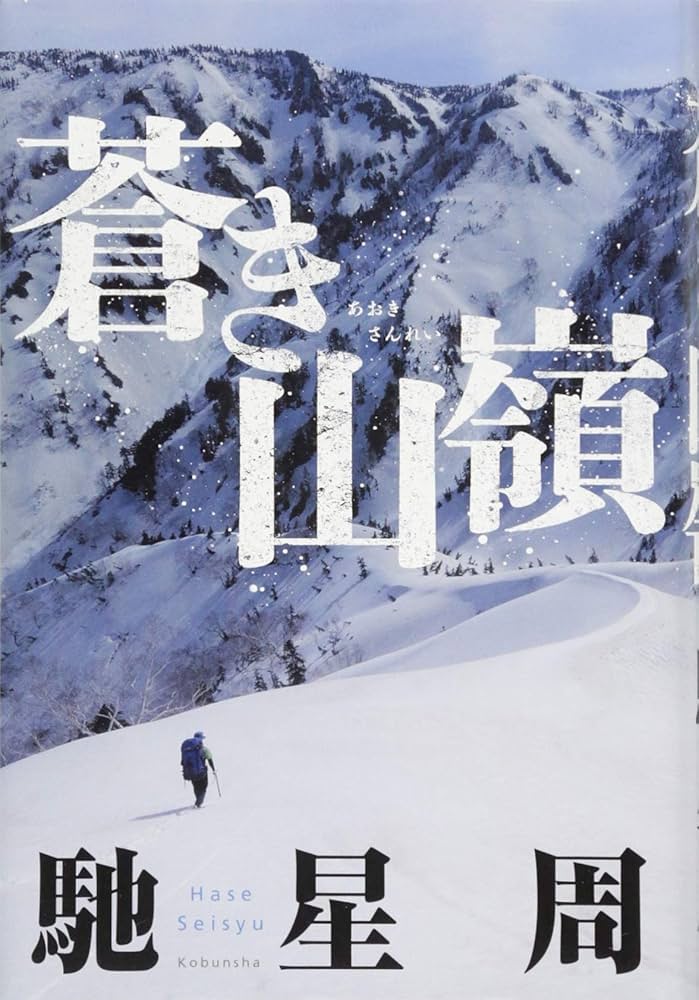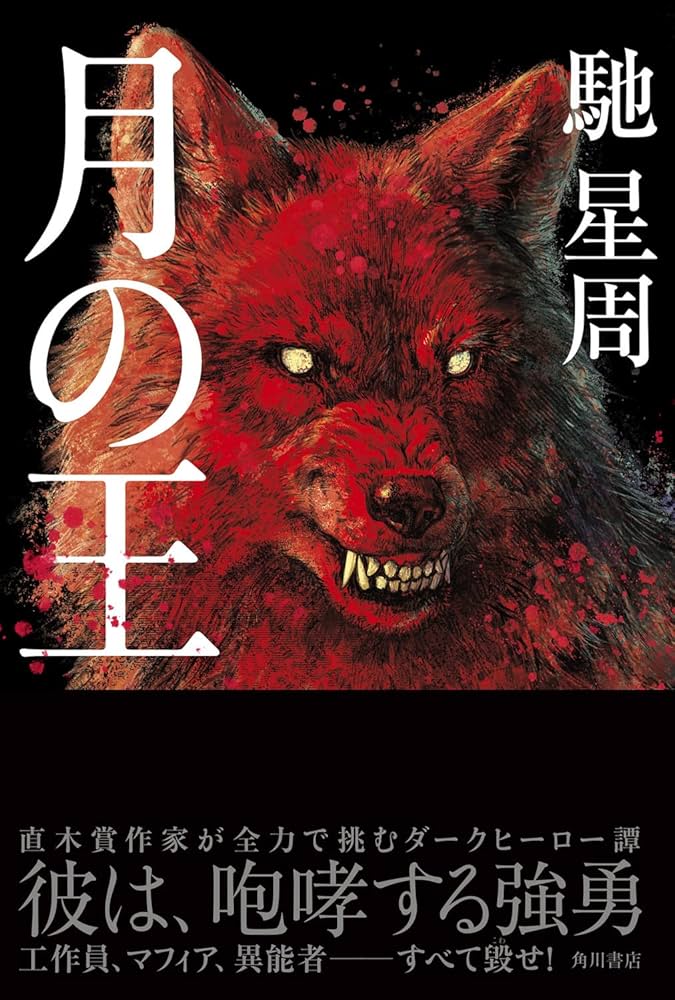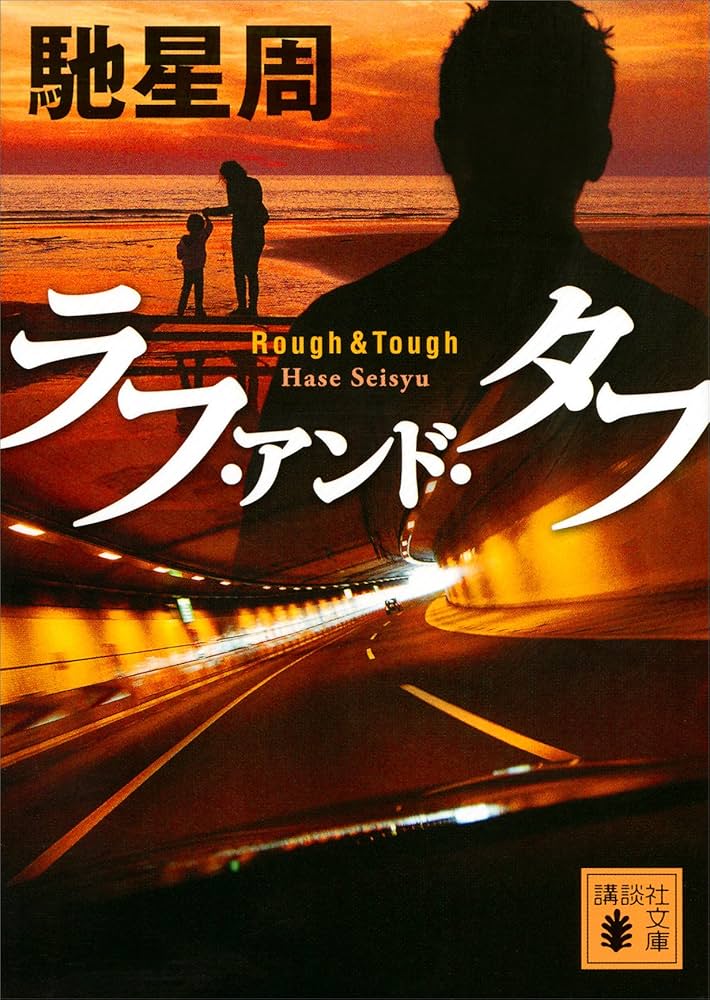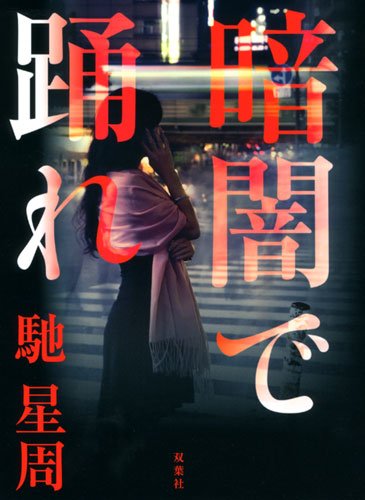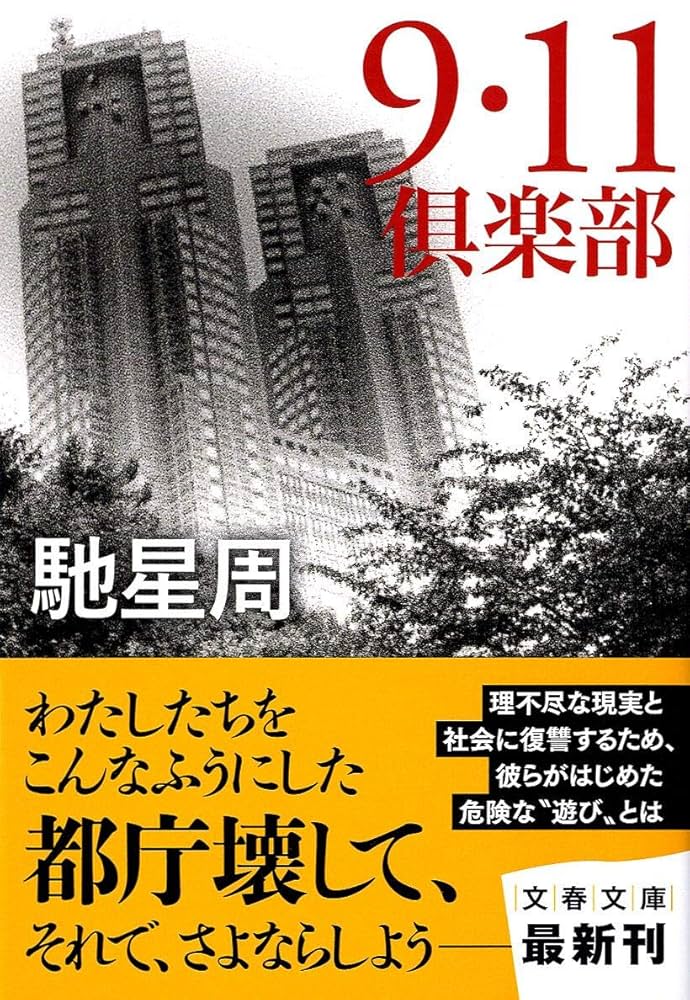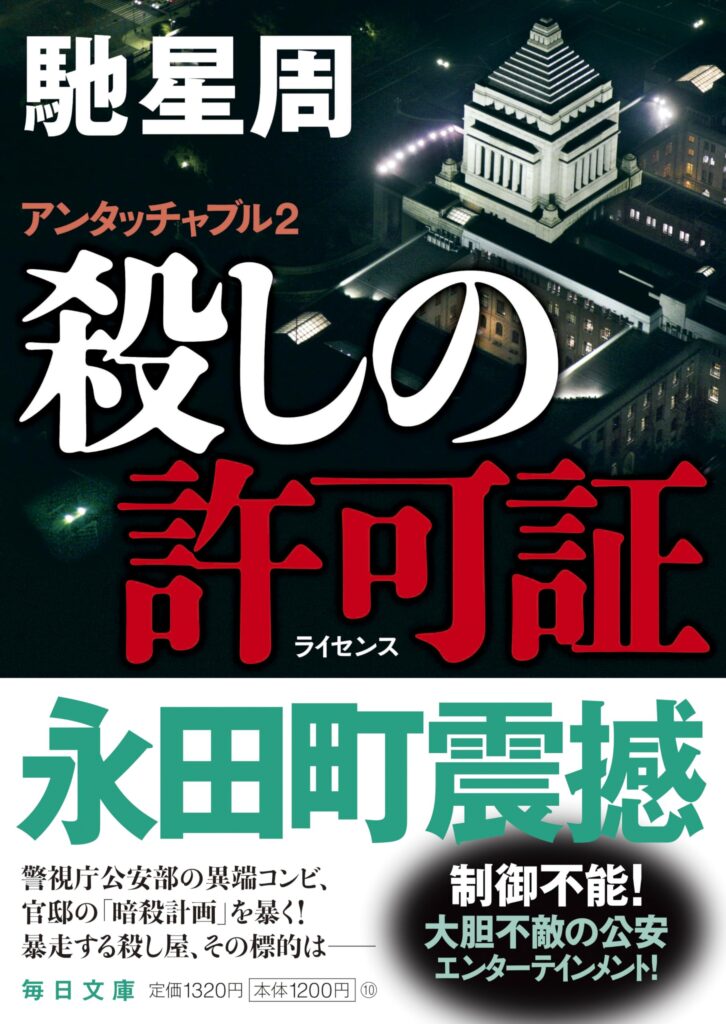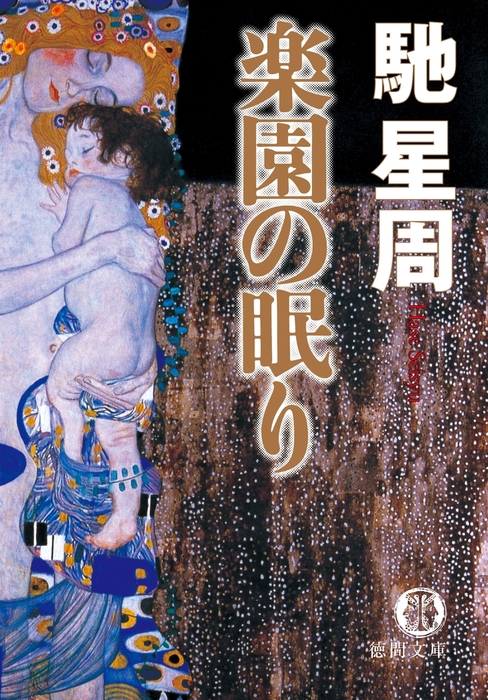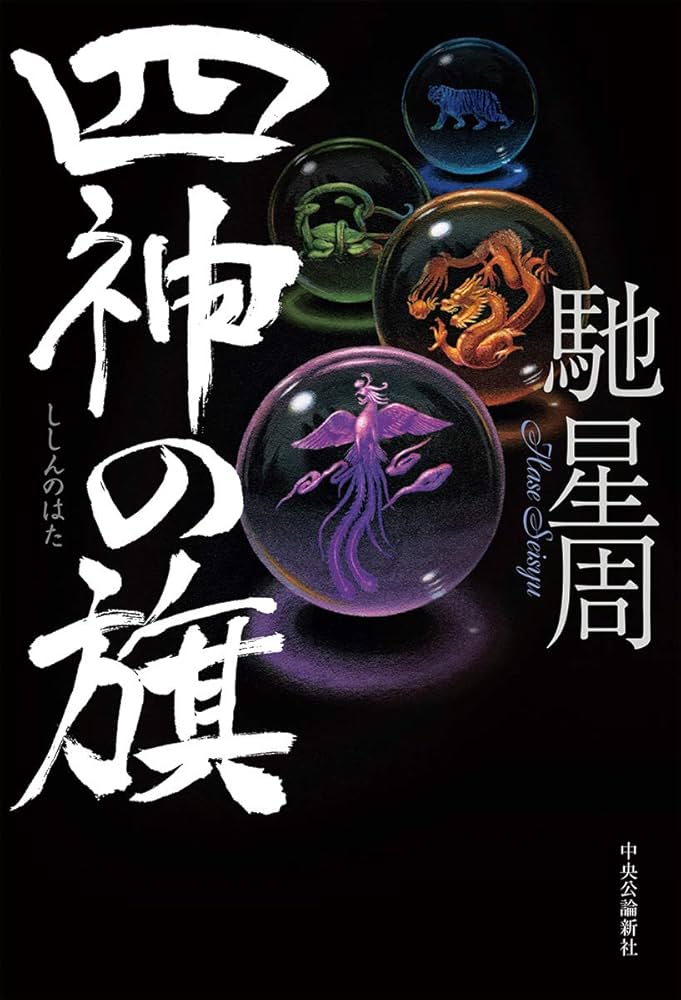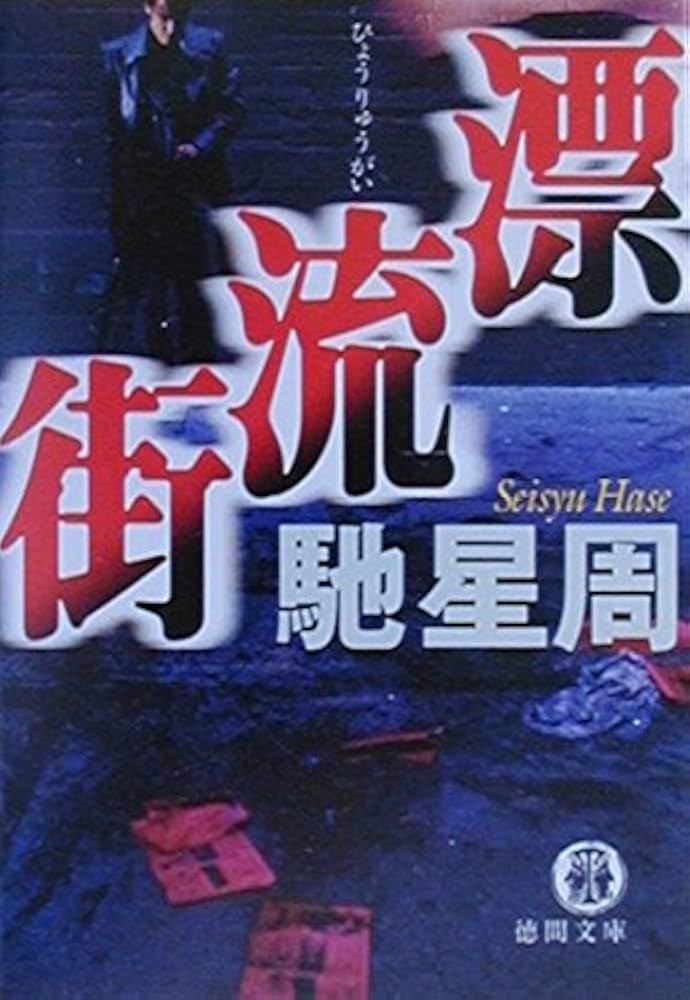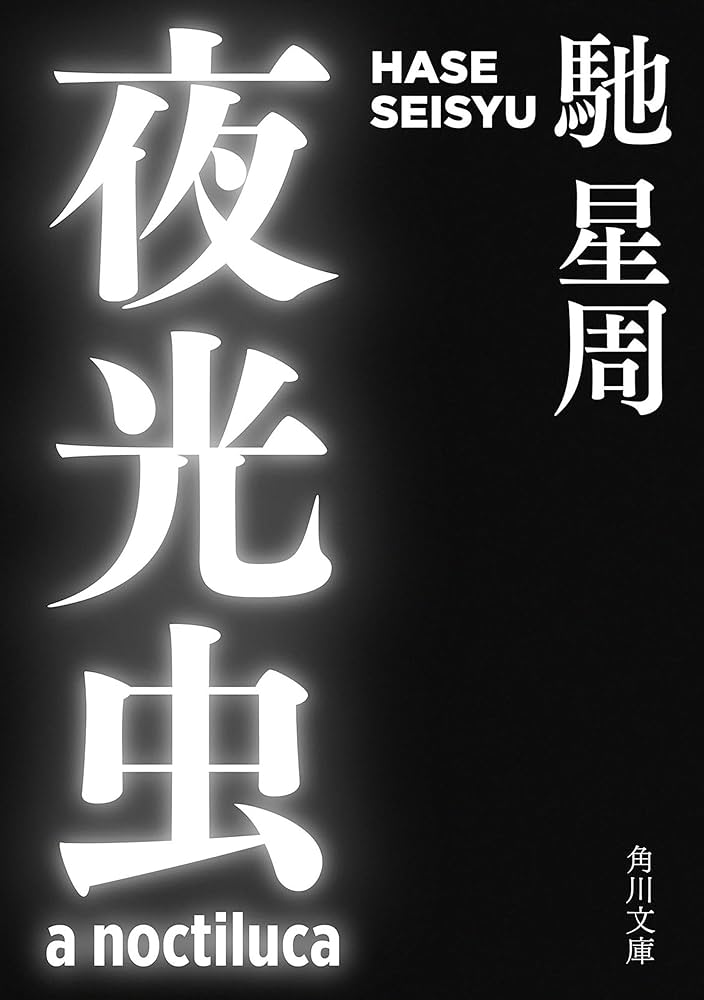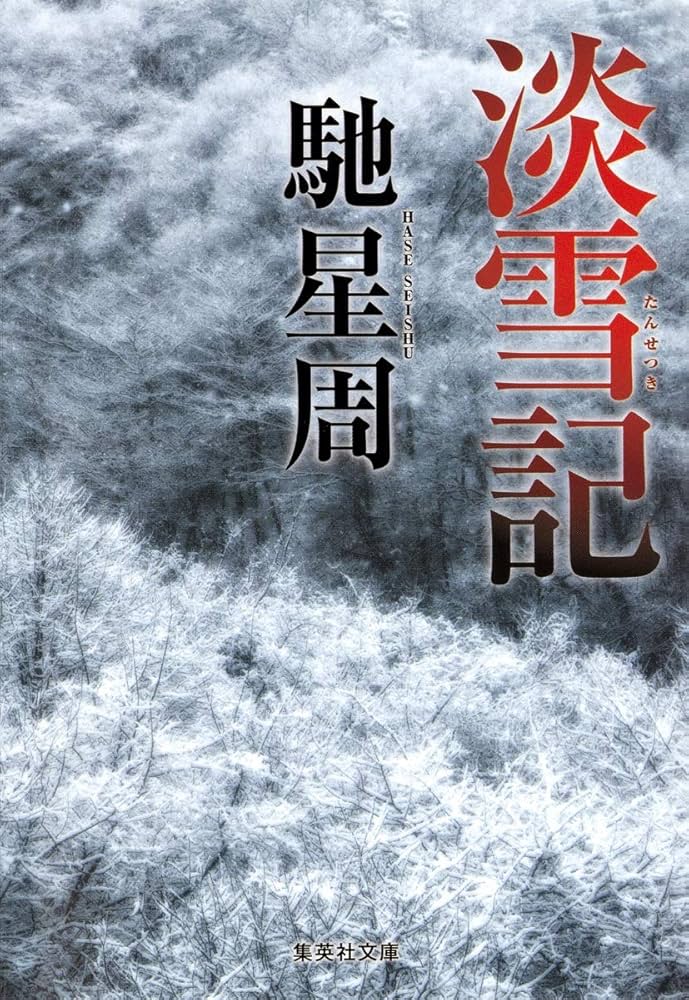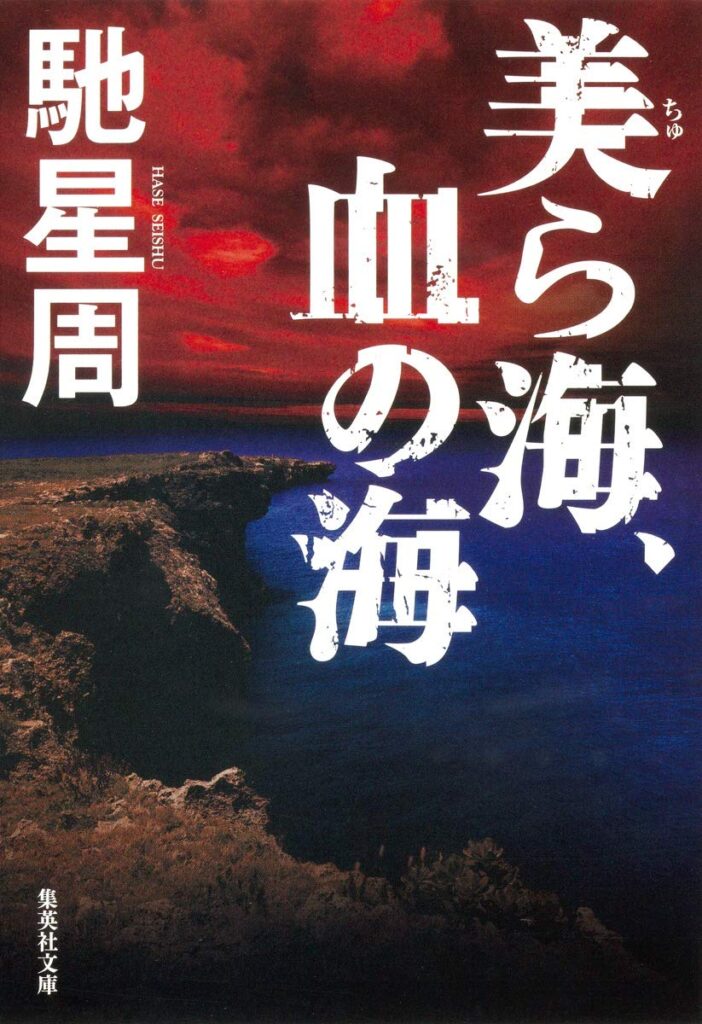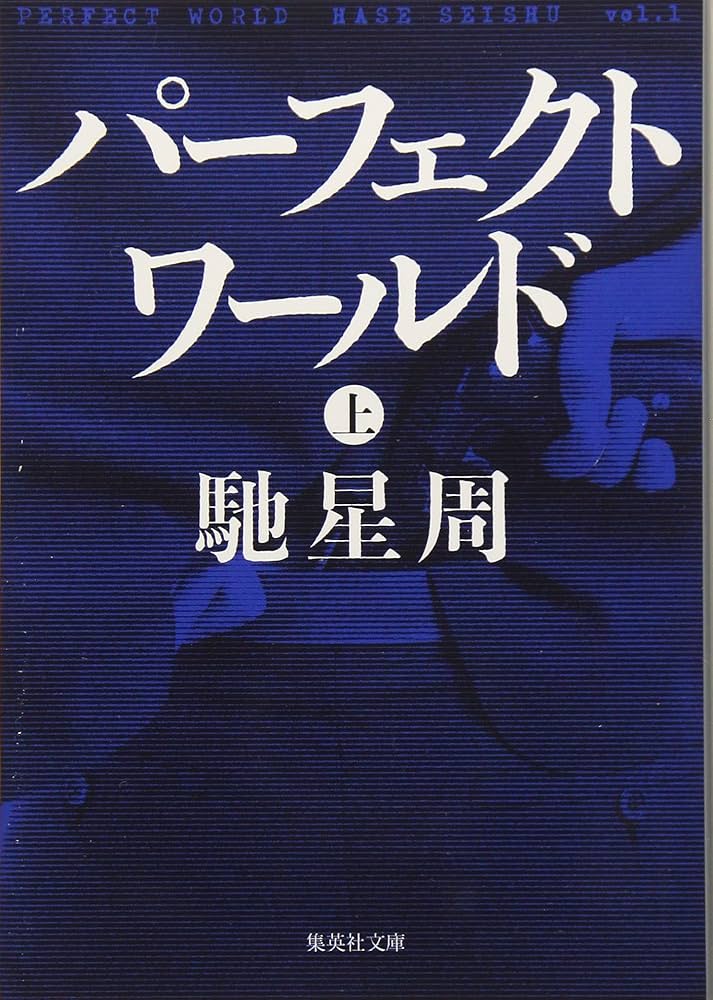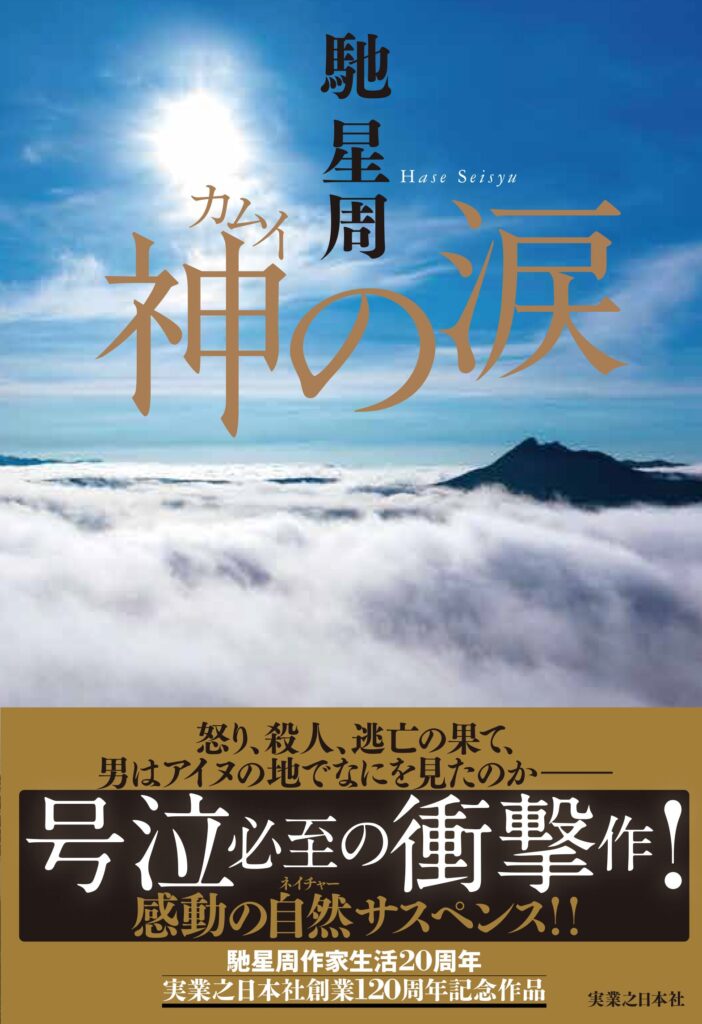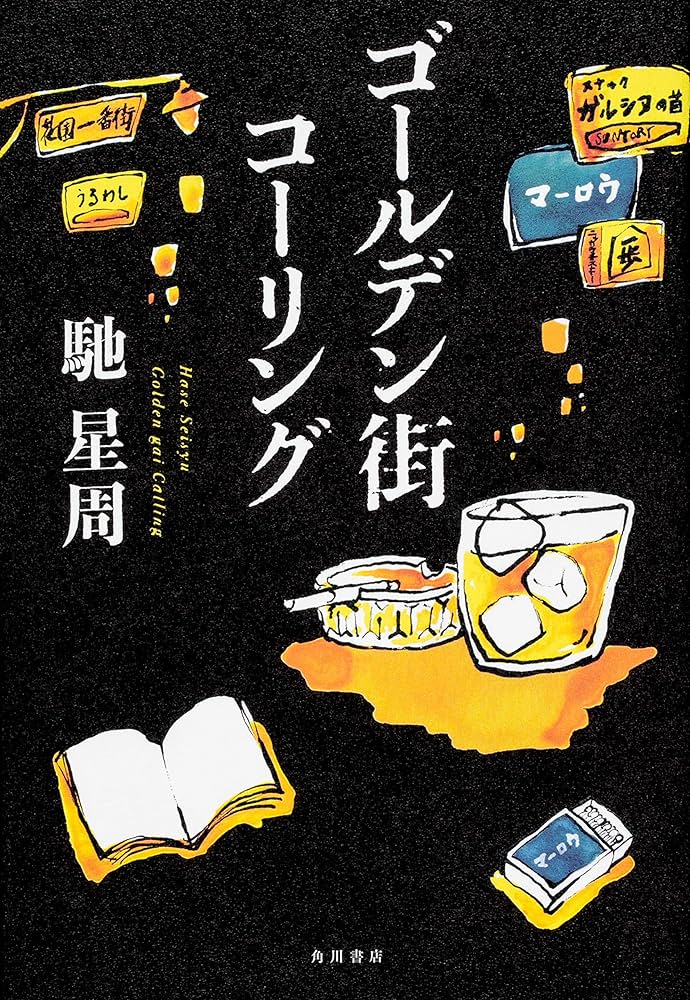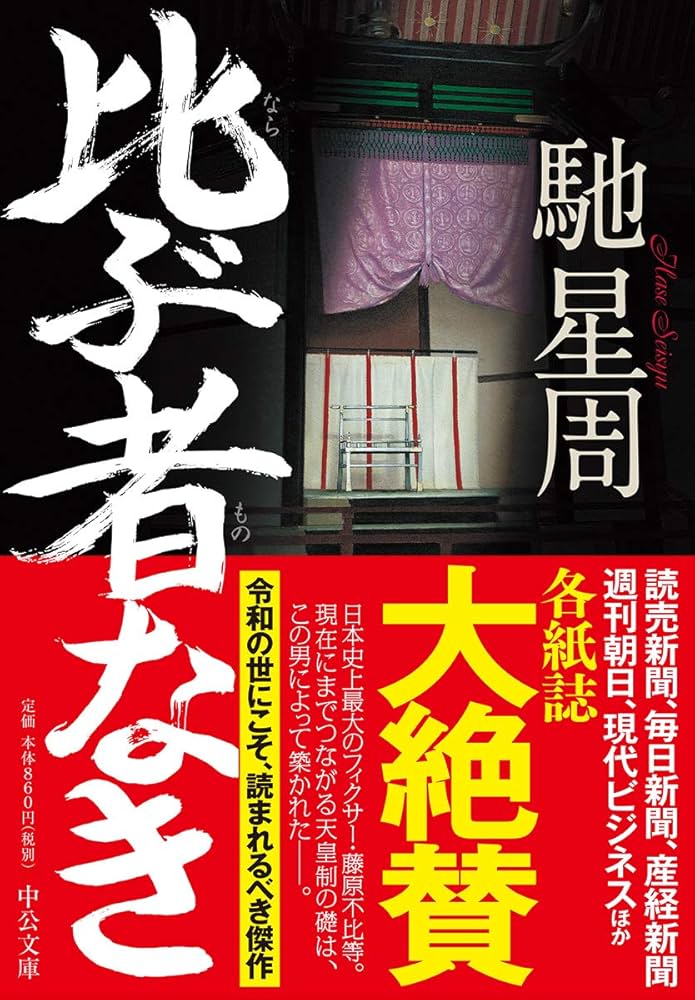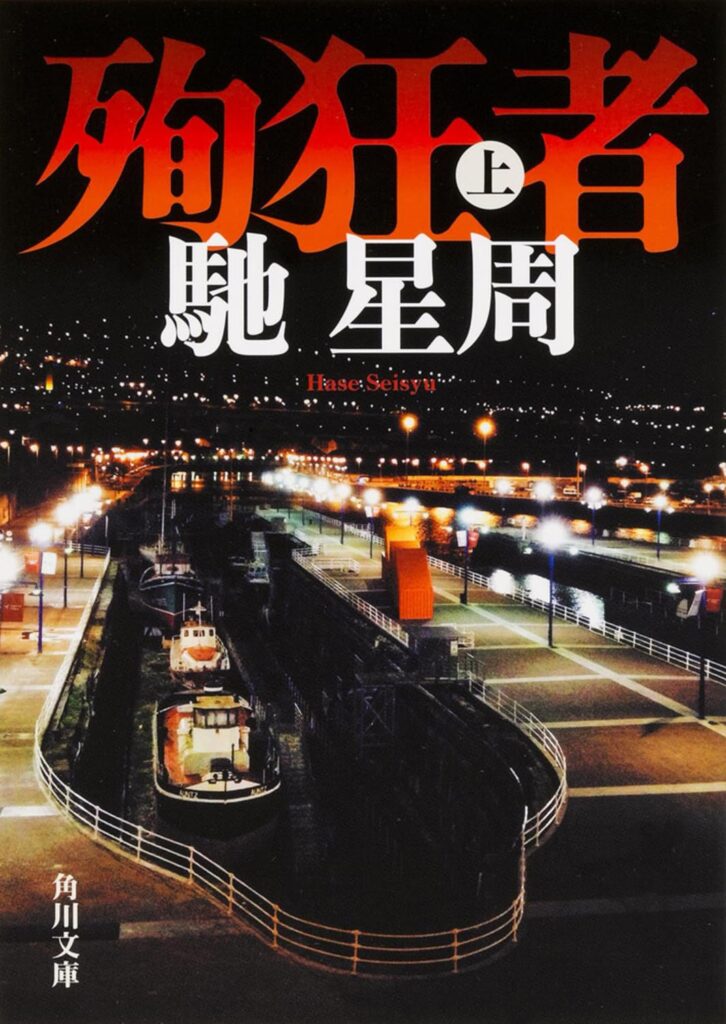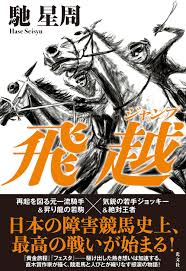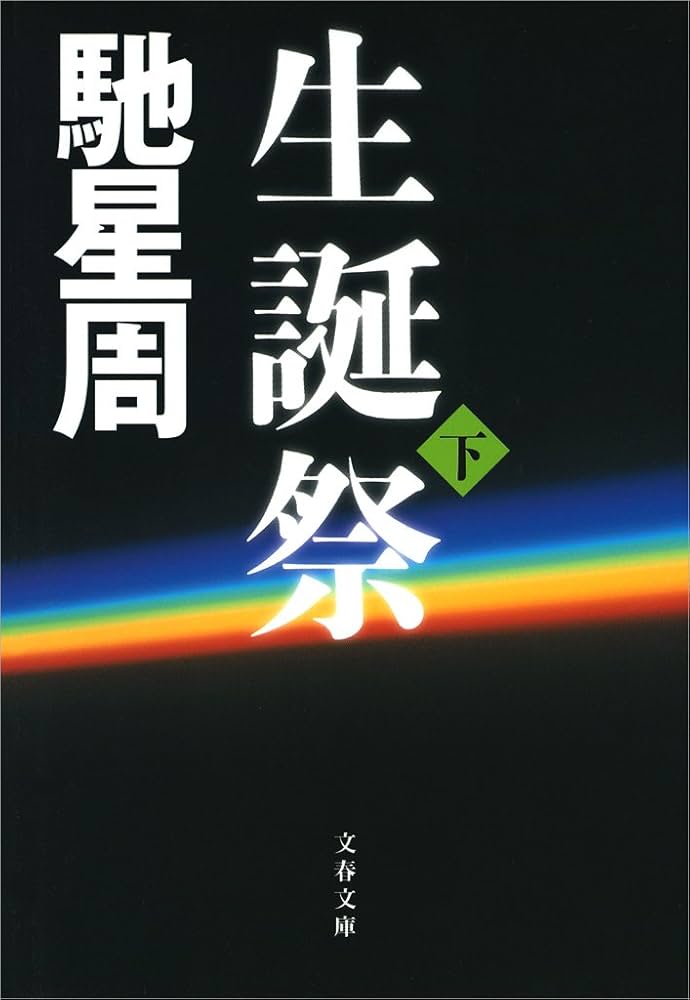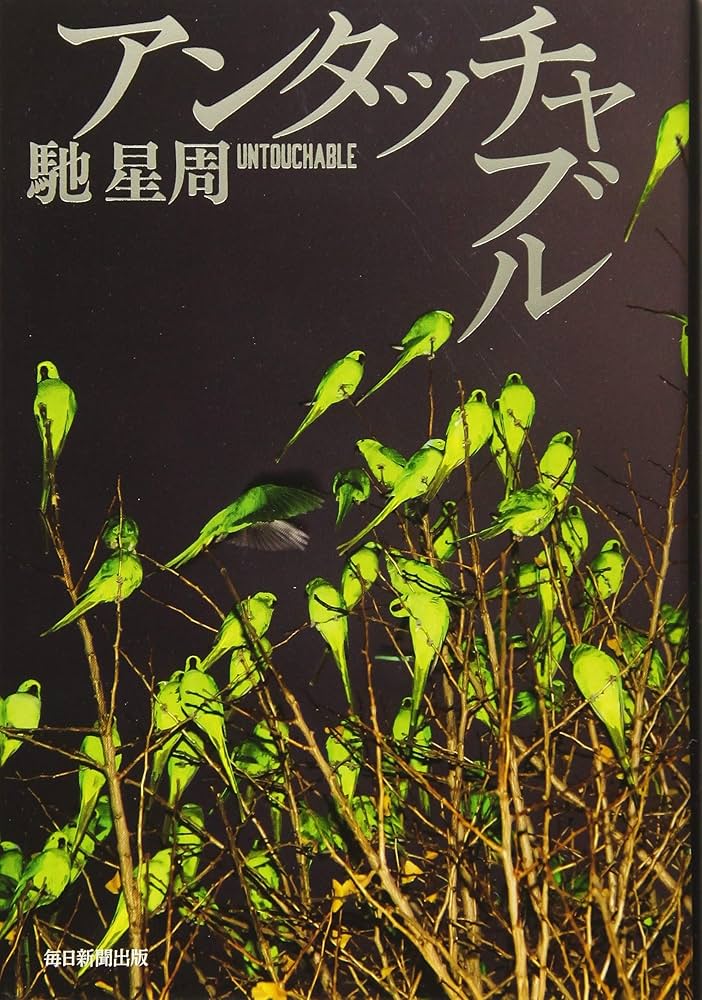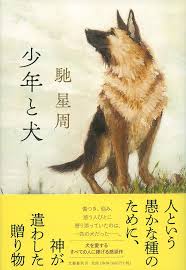小説「北辰の門」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「北辰の門」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
奈良時代、天平の世。都は天然痘の猛威に襲われ、政治を担っていた藤原不比等の子、藤原四兄弟が次々と世を去り、権力に空白が生まれていました。この混乱の中、静かに、しかし燃えるような野心を胸に秘めて立ち上がったのが、藤原仲麻呂です。祖父・不比等譲りの才気を持ちながら、彼は人間を駒としか見ない冷徹な合理主義者でした。
その対極にいるのが、皇位を継ぐ運命にありながら、一人の女性としてのささやかな幸福を願う阿倍内親王、のちの孝謙天皇です。かつて仲麻呂に抱いた淡い想いは、彼の非情さを知るにつれて、深い憎しみへと変わっていきます。権力の頂点を求める男と、権力からの解放を願う女。二人の宿命的な対立が、物語の幕開けを告げるのです。
本作は、単なる歴史上の権力闘争を描いたものではありません。それは、二人の男女が抱く、決して相容れない根源的な欲望のぶつかり合いを描いた物語です。彼らの対決は、政治の枠を超え、人間とは何か、生きるとは何かを問いかける、壮絶な魂のドラマなのです。
「北辰の門」のあらすじ
若く権力基盤を持たない藤原仲麻呂は、叔母である光明皇太后の絶大な信頼を足がかりに、権力の中枢へと食い込んでいきます。彼は皇太后の威光を巧みに利用し、自らの私的機関「紫微中台」を設立。国家の意思決定を意のままに操る、前代未聞の統治システムを築き上げました。
この紫微中台を武器に、仲麻呂は邪魔者を次々と排除していきます。最大の政敵であった橘諸兄を失脚させ、あろうことか実の兄である藤原豊成さえも罠にはめて追放。藤原氏のトップに君臨し、朝廷に敵なしの状況を作り出します。その冷酷で計算され尽くした手腕は、見る者を震え上がらせるほどでした。
そして彼は、自らの意のままになる駒として、かつて想いを寄せられた阿倍内親王を孝謙天皇として即位させます。この時点では、天皇でさえも彼の壮大な野望を実現するための道具の一つに過ぎませんでした。彼の権力は盤石になったかに見えました。
しかし、彼の権力は、光明皇太后という一個人の存在にあまりにも大きく依存していました。それはまるで、砂の上に築かれた楼閣のような、危うさをはらんでいたのです。やがて訪れる皇太后の死が、彼の運命を大きく揺るがすことになろうとは、この時の仲麻呂はまだ知る由もありませんでした。
「北辰の門」の長文感想(ネタバレあり)
馳星周さんが描く歴史小説は、ただの歴史の再現ではありません。そこに描かれるのは、権力、愛、憎しみといった、人間の生々しい欲望が渦巻く、まさしく「ノワール」の世界です。本作『北辰の門』は、その真骨頂とも言える作品ではないでしょうか。奈良時代という雅なイメージとは裏腹の、血と野望に塗れた人間ドラマがここにあります。
物語の中心にいるのは、藤原仲麻呂。彼は、祖父・藤原不比等という偉大な存在の血を継ぎ、並外れた政治的手腕を持つ男として描かれます。しかし、彼の本質は、人間を感情のない駒とみなし、自らの目的のためには非情な手段も厭わない、徹底した合理主義者です。
この仲麻呂という人物の造形が、まず見事です。彼は自らを理性の化身と信じ、他人の「情」を弱さとして唾棄します。しかし、読み進めるうちに、彼自身が誰よりも強烈な「情」――すなわち、権力への飽くなき渇望――に取り憑かれていることが明らかになってきます。この自己矛盾に気づかないまま破滅へと突き進む姿は、優れた物語の主人公が持つ悲劇性を完璧に体現しています。
その仲麻呂と対をなすのが、阿倍内親王、のちの孝謙・称徳天皇です。彼女は、生まれながらにして天皇となることを運命づけられていますが、その心の中では、ごく普通の女性として生きたいという切実な願いが渦巻いています。結婚し、子を産むという「人並みの幸せ」を、彼女は何よりも望んでいました。
当初、彼女は仲麻呂の野望のための傀儡として描かれます。かつて彼に抱いた恋心も、彼の冷酷さによって無残に踏みにじられます。しかし、物語は彼女がただ利用されるだけの弱い存在ではないことを示していきます。抑圧され、虐げられてきた経験は、彼女の中で仲麻呂への激しい憎悪となり、やがて自らの意志で立つための強大なエネルギーへと変わっていくのです。
仲麻呂が権力の階段を駆け上る原動力となったのは、叔母・光明皇太后の寵愛でした。彼は、皇太后を後ろ盾に「紫微中台」という、事実上の私的権力機関を作り上げます。これにより、本来の国家機関を形骸化させ、権力を自分一人のもとに集中させるという離れ業をやってのけます。
彼の策略は冴えわたり、政敵は次々と葬り去られます。その手腕は鮮やかでさえありますが、同時に彼の権力がいかに危うい基盤の上に成り立っているかも示唆されます。彼の権力は、法律や制度といった恒久的なものではなく、光明皇太后という一個人の存在に完全に依存していました。その支柱が失われた時、彼の帝国がもろくも崩れ去ることは、運命づけられていたのかもしれません。
本作のタイトル『北辰の門』が示すもの、それは仲麻呂の野望の最終地点です。彼が目指したのは、単なる臣下の最高位ではありませんでした。彼が夢見たのは、日本の歴史上、誰も成しえなかった「皇帝」としてこの国に君臨することでした。神話に連なる日本の「天皇」とは違う、実力で国を支配する絶対的な権力者。それは、国のあり方そのものを根底から覆す、あまりにも危険な夢でした。
しかし、彼の壮大な野望には、致命的な欠落がありました。彼は「皇帝になる」という目的そのものに取り憑かれ、皇帝になった先、この国をどうしたいのかという具体的なビジョンを持っていませんでした。彼の野心は、国や民のためではなく、彼個人の渇望を満たすためだけの、空虚なものだったのです。
ここに、彼の最大の皮肉があります。理性を信奉し、人の情を蔑んできた彼が、誰よりも非合理的で、純粋な欲望という「情」に突き動かされていたのです。彼は、自分自身の最も大きな弱点に、最後まで気づくことがありませんでした。
物語の潮目が大きく変わるのは、やはり、彼の絶対的な庇護者であった光明皇太后の死です。この出来事は、彼の権力基盤を根底から揺るがします。砂上の楼閣は、その土台を失い、一気に崩壊を始めるのです。
そして、重石から解放された孝謙上皇(譲位後の孝謙天皇)が、一人の人間として、そして為政者として劇的に覚醒します。もはや彼女は、仲麻呂の駒ではありません。長年溜め込んできた鬱屈と憎しみを力に変え、彼女は自らの足で立ち上がります。これは、権力に虐げられた一人の女性が、自己を確立していく再生の物語でもあります。
その覚醒を決定的なものにしたのが、僧・道鏡の存在です。歴史上では「怪僧」として語られがちな道鏡ですが、本作では全く新しい光が当てられています。彼は、孝謙上皇がそれまで決して得ることのできなかった、人間的な安らぎと親密さを与える存在として描かれます。二人の関係は、権力欲によるものではなく、孤独な魂が惹かれ合った、ある種の純愛として描かれているのが印象的です。この愛こそが、彼女に自信と、仲麻呂と対峙する力を与えたのです。
仲麻呂の転落は、結局のところ、彼の人間理解の浅さに起因します。彼は、人の心や絆が持つ力を、最後まで理解できませんでした。自らの権力でさえ、光明皇太后との個人的な絆の上に成り立っていたというのに、その本質を見ようとしなかったのです。結果として、孝謙上皇と道鏡の間に生まれた、より強固な人間的な結びつきの前に、彼はなすすべもなく敗れ去ります。自分しか愛せない男が、人を愛することで強くなった女に敗れる。この構図は、極めて現代的な心理劇のようです。
追い詰められた仲麻呂に対抗するため、孝謙上皇は切り札を切ります。かつて仲麻呂によって左遷されていた老練な学者、吉備真備を都に呼び戻すのです。女帝を支える道鏡、そして戦術を司る吉備真備。ここに、仲麻呂を倒すための強力な布陣が完成します。完全に孤立した仲麻呂に残された道は、もはや一つしかありませんでした。
最後の賭けとして、彼は「恵美押勝」の名のもとに軍事反乱を起こします。これが世にいう「恵美押勝の乱」であり、物語のクライマックスです。しかし、あれほど壮大だった彼の野望とは裏腹に、乱の結末は驚くほどあっけないものでした。吉備真備の周到な戦略の前に、彼の軍はなすすべもなく敗走し、仲麻呂自身も惨めな最期を遂げます。
このあっけない幕切れは、馳星周という作家の非情なリアリズムの表れでしょう。傲慢な野心家の末路は、英雄的な悲劇などではなく、ただ無様で突然の破滅でしかない。緻密な計画を巡らせた男が、自らの欠陥によって一瞬で全てを失う。これこそが、ノワールという物語の真髄です。欠陥のある基盤の上に築かれた権力など、所詮は幻に過ぎないという冷徹な真実を、読者に突きつけるのです。
物語は、藤原仲麻呂の「北辰の夢」が、儚くも潰え去ったところで終わります。しかし、彼の死で歴史が終わるわけではありません。彼の後も、藤原一族の権力への野心は絶えることなく、やがて平安の世へと続いていく。仲麻呂の壮絶な人生もまた、歴史という大きな流れの中の一つの出来事に過ぎないのだという、壮大な余韻を残して物語は閉じられます。本作は、歴史という大きな器の中で繰り広げられる、人間のどうしようもない業と情念を描ききった、傑作だと感じました。
まとめ
『北辰の門』は、藤原仲麻呂という一人の男が、理性を信じ、人の情を侮った末に破滅していく悲劇の物語でした。彼の野望は日本の国体すら揺るがす壮大なものでしたが、その基盤はあまりにも脆く、人間的な絆の力の前にもろくも崩れ去りました。
その一方で、この物語は、仲麻呂に虐げられてきた孝謙天皇が、一人の女性として自立し、信頼できる伴侶を得て最強の権力者を打ち破るという、勝利の記録でもあります。男性的な権力原理に対する、女性的な実存を賭けた闘いの物語として読むこともできるでしょう。
馳星周さんは、歴史上の出来事を、現代にも通じる生々しい人間ドラマへと昇華させる、類まれな才能を持っています。本作で描かれるのは、遠い昔の出来事でありながら、その根底に流れる権力への渇望や愛憎は、私たちの心にも深く突き刺さります。
歴史の知識がなくとも、あるいは歴史が好きだからこそ、より深く味わえる重厚な一作です。人間の業の深さと、それでも生きていく強さを感じさせてくれる、読み応えのある物語でした。