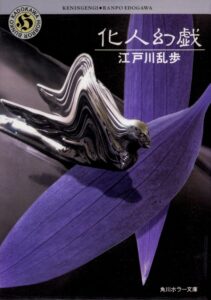 小説「化人幻戯」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。江戸川乱歩が生み出した、あの名探偵・明智小五郎が登場する戦後の長編作品ですね。数々の難事件を解決してきた明智ですが、この物語でも奇怪な事件に挑むことになります。
小説「化人幻戯」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。江戸川乱歩が生み出した、あの名探偵・明智小五郎が登場する戦後の長編作品ですね。数々の難事件を解決してきた明智ですが、この物語でも奇怪な事件に挑むことになります。
本作は、乱歩が還暦を迎えられてから書かれたもので、それまでの通俗的なスリラー作品とは一線を画し、本格的な謎解きを目指した意欲作と言われています。とはいえ、そこは乱歩。レンズや覗き見といったお馴染みのモチーフや、独特の倒錯した世界観もしっかりと織り込まれているのが魅力だと思います。
物語は、ある実業家の秘書となった青年が、不可解な出来事に巻き込まれていくところから始まります。怪しい脅迫状、断崖からの転落死、そして密室殺人…。次々と起こる事件の裏には、一体何が隠されているのでしょうか。明智小五郎は、この複雑に絡み合った謎を解き明かすことができるのか。
この記事では、物語の詳しい流れを追いながら、事件の核心部分にも触れていきます。そして、私個人の深い思い入れや考察を、たっぷりと語らせていただこうと考えています。読み応えのある内容になっていると思いますので、ぜひ最後までお付き合いくださいませ。
小説「化人幻戯」のあらすじ
物語は、主人公の庄司武彦が、父親の勧めによって実業家である大河原義明の秘書として雇われるところから幕を開けます。大河原氏は、犯罪や探偵小説、レンズいじりや奇術などを趣味とする、少々風変わりな人物でした。しかし、実業家としての手腕は確かで、若く美しい妻の由美子と共に暮らしていました。
秘書としての仕事にも慣れてきたある日、庄司は、大河原家に出入りしている青年、姫田吾郎から奇妙な相談を受けます。それは、差出人が分からない、怪しい白い羽根が何度も送り付けられてくるというものでした。秘密結社などに興味を持っていた姫田は、これを一種の脅迫ではないかと疑い、庄司の知り合いである探偵・明智小五郎に相談を持ちかけてほしいと頼むのでした。
それから間もない頃のことです。庄司は、大河原夫妻と共に熱海にある別荘へ出かけます。そこで、いつものように双眼鏡で景色を眺めていた大河原夫妻は、驚くべき光景を目撃してしまいます。断崖絶壁から、一人の男性が転落していく瞬間を捉えたのです。そして、その転落した男性こそ、あの姫田吾郎であったことが判明します。
事故か、それとも殺人か。警察の捜査が始まりますが、事件は混迷を極めます。そんな中、庄司を通じて事件を知った名探偵・明智小五郎が、捜査に協力することになります。明智は、鋭い観察眼と推理力で、事件の真相に迫ろうとします。
しかし、事件はそれだけでは終わりませんでした。姫田と仕事上のライバル関係にあったとされる村越という男が、なんと自宅の密室で銃で撃たれて死亡しているのが発見されます。さらに、村越の友人であった画家も、隅田川で水死体となって発見されるのです。連続する不可解な死。事件はますます複雑な様相を呈していきます。
果たして、これらの事件は繋がっているのでしょうか。姫田に送られてきた白い羽根の意味とは?そして、妖しい魅力を放つ大河原夫人・由美子の影が、事件の背後にちらつきます。彼女は事件にどう関わっているのか。名探偵・明智小五郎は、入り組んだ人間関係と巧妙に仕組まれた罠の中から、真実を突き止めることができるのでしょうか。物語は、驚くべき結末へと突き進んでいきます。
小説「化人幻戯」の長文感想(ネタバレあり)
さて、この「化人幻戯」という作品、江戸川乱歩が戦後、満を持して発表した大人向けの長編ミステリですね。明智小五郎も登場し、齢五十を重ねている設定ですが、まだまだ矍鑠としていて頼もしい存在です。小林少年に至っては、相変わらず少年のままなのがご愛嬌といったところでしょうか。
正直に申しますと、世間一般での評価は、もしかしたらそれほど高くない部類に入るのかもしれません。本格ミステリとしての体裁は整っていますし、密室殺人やアリバイトリック、暗号解読といった要素もふんだんに盛り込まれてはいるのです。ただ、個々のトリックを見ていくと、どこかで目にしたことがあるような、いわゆる古典的な手法が使われている部分もあり、斬新な驚きという点では少し物足りなさを感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、私はこの作品、決して悪くない、むしろ個人的にはかなり好きな部類に入る一作なのです。なぜなら、ここには乱歩が自身の作家人生で繰り返し描いてきたモチーフ、例えばレンズを通して世界を覗き見る行為、倒錯した性愛、探偵小説への偏愛、そして犯罪そのものへの強い興味といったものが、これでもかと散りばめられているからです。それらを全てひっくるめて、乱歩なりの「本格」という形に昇華させようとしたのではないか、そんな気概が伝わってくるように思うのです。
その乱歩らしいこだわりが、最も色濃く表れているのが、やはり犯人の人物像ではないでしょうか。本作の犯人は、いわゆる怪人二十面相のような、荒唐無稽な怪人ではありません。かといって、読者の意表を突くような、全く予想外の人物というわけでもないかもしれません。しかし、その内面に秘められた動機や思考回路は、後年のサイコスリラー作品に登場するような、理解を超えた恐ろしさを感じさせるものがあります。これこそ、乱歩の嗜好性が強く反映された部分であり、読んでいてゾクッとするような感覚を覚えるのです。
【ここからネタバレです】
本作の真犯人は、大河原夫人・由美子です。彼女の犯行動機は、金銭欲でもなければ、怨恨でもありません。それは「愛情」なのです。それも、常人には到底理解しがたい、歪んだ形の「愛情」です。彼女は、手記の中で自ら告白します。「殺すということは愛するということだ」と。
幼い頃、彼女は大切に飼っていたウグイスを、可愛くて可愛くてたまらないという理由で、自分の手で握り殺してしまいます。「その美しいウグイスを世界で一番愛していた」から、というのです。さらに衝撃的なのは、十二歳の時に、よく家に遊びに来ていた同年代の男の子を、同じ理由で殺害したという告白です。「その子が誰よりも好きで、可愛くてたまらなかったから」庭の池へ突き落とした、と。そして、その行為に対して後悔の念は一切なく、むしろ「愛情の極致まで行ってしまったという、充ち足りた感じ」「眠くなるような満足感」を得たというのです。
この犯人の心理描写は、本当に凄まじいものがあります。「今でも殺すことが、どうして悪事なのか、本当にわかっていないのですよ。みんながそう言うからそうだろうと思っているだけです。わたしはみんなとは違っているのです。心から理解することができないのです」という彼女の言葉は、善悪の基準というものが、いかに社会によって作られた曖昧なものであるかを突きつけてくるようです。チャップリンが映画「殺人狂時代」で指摘したように、社会のルールや道徳観念は、時に矛盾をはらんでいます。私たちは、社会秩序を維持し、それが自分たちの幸福に繋がると信じているから、それらの規範に従うわけですが、その枠組みから外れてしまった人間は、社会から逸脱した存在と見なされてしまう。由美子は、まさにそのような存在として描かれています。
彼女は、自分の異常性を自覚しながらも、それを隠し、周囲には魅力的な女性として振る舞います。庄司を手玉に取り、関係を持つ場面などは、彼女の妖艶さと計算高さがよく表れていますね。しかし、その心の奥底では、深い孤独感を抱えていたのではないでしょうか。だからこそ、名探偵・明智小五郎に対して、「ほんとうは、わたし、あなたに見破ってほしかったのです。どんなにあなたに会いたかったでしょう。そして、あたしの真実を見破ってほしかったでしょう」という言葉を漏らすのです。自分を本当に理解してくれる存在を、彼女は渇望していたのかもしれません。それは、社会に馴染めない者の切実な叫びのようにも聞こえます。
ミステリとしてのトリックに話を戻しますと、姫田殺害のアリバイ工作は、双眼鏡で遠くから犯行を目撃させるという、視覚を利用した古典的なものです。また、村越殺害の密室トリックは、テープレコーダーを使った音声によるアリバイ工作が用いられています。これらは、現代の目から見れば、あるいは見破りやすいトリックと感じるかもしれません。
また、本作は雑誌への連載小説だったためか、物語の展開にやや冗長さを感じる部分があるのも否めないかもしれません。特に中盤あたりは、少しだけ間延びしているように感じる方もいるかもしれませんね。乱歩自身、プロットをかっちり固めずに書き進めることもあったと聞きますから、その影響もあるのかもしれません。
しかし、そういった点を差し引いても、この「化人幻戯」には、それを補って余りある魅力があると私は思います。何よりも、由美子という稀代の悪女、その倒錯した心理描写が素晴らしいのです。トリックの巧妙さよりも、この異常な犯人像を描き切ったことこそが、本作の最大の価値ではないでしょうか。ある意味では、乱歩の代表作の一つである「陰獣」と対をなすような作品と言えるかもしれません。どちらも、人間の心の奥底に潜む暗い欲望や異常な愛情を描き出しています。
終盤、由美子の手記や、明智との対決における彼女の告白は、まさに圧巻です。やや説明的に感じられる部分もあるかもしれませんが、こここそが乱歩の世界観、その真髄を最も深く味わえる部分であり、本作一番の読みどころと言って間違いないでしょう。事件の真相が明らかになり、全てを語り終えた彼女が、警察が来るまでの間、「誰かを待っているのは所在ないものですわね。トランプがあるといいのに。こういうときの時間つぶしは、トランプ遊びに限るのよ」と、無邪気な口調でつぶやくラストシーンは、本当に印象的です。それは虚勢でも演技でもなく、彼女の本心から出た言葉のように思え、その底知れない異常性に、改めて慄然とさせられます。
ですから、もし「化人幻戯」を、単なるトリック重視の本格ミステリとして読んでしまうと、少し肩透かしを食らうかもしれません。しかし、江戸川乱歩という作家の持つ独特の美学、人間の心の闇や倒錯した愛情といったテーマに興味がある方にとっては、これほど読み応えのある作品も少ないのではないでしょうか。通俗的なスリラー作品群と比べても、決して劣るものではない、むしろ上位に位置づけられるべき深みを持った作品だと、私は考えています。繰り返しになりますが、個人的には大好きな一作です。
まとめ
江戸川乱歩の「化人幻戯」は、戦後に書かれた長編作品であり、名探偵・明智小五郎が活躍する物語です。熱海の断崖での転落死に始まり、密室殺人、謎の脅迫状と、次々に起こる奇怪な事件に明智が挑んでいきます。
本作は、本格ミステリとしての構成要素、例えばアリバイトリックや暗号解読なども含んでいますが、その真骨頂は、むしろ犯人の特異な心理描写にあると言えるでしょう。特に、「殺すことは愛すること」という常軌を逸した動機を持つ犯人像は、読者に強烈な印象を与えずにはおきません。
物語を通して、善悪の基準や社会規範といったものに対する問いかけも感じられます。なぜ人を殺してはいけないのか、その根源的な問いに、犯人の歪んだ論理が迫ってくるかのようです。トリックの斬新さという点では意見が分かれるかもしれませんが、人間の心の奥底に潜む不可解さや、倒錯した美を描き出す乱歩ならではの世界観は、存分に堪能できるはずです。
世間の評価がどうあれ、江戸川乱歩の持つ独特の雰囲気や、人間の心理の深淵を覗き見るような物語が好きな方にとっては、非常に興味深く、読み応えのある一作であることは間違いありません。ぜひ一度、手に取ってその世界に浸ってみてはいかがでしょうか。






































































