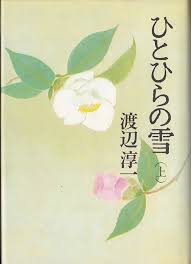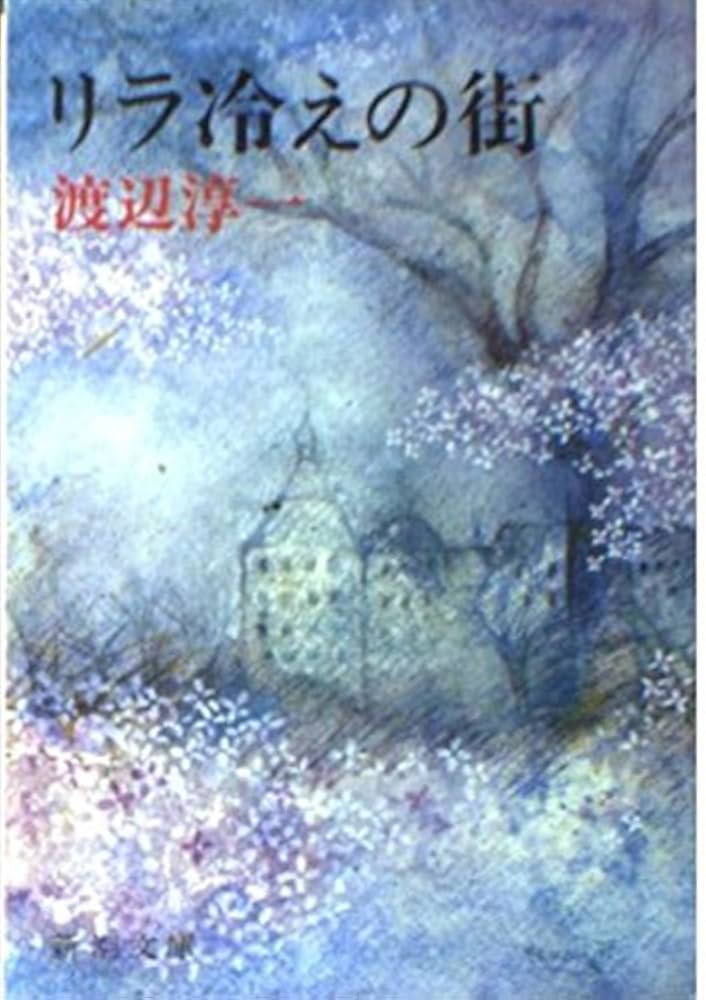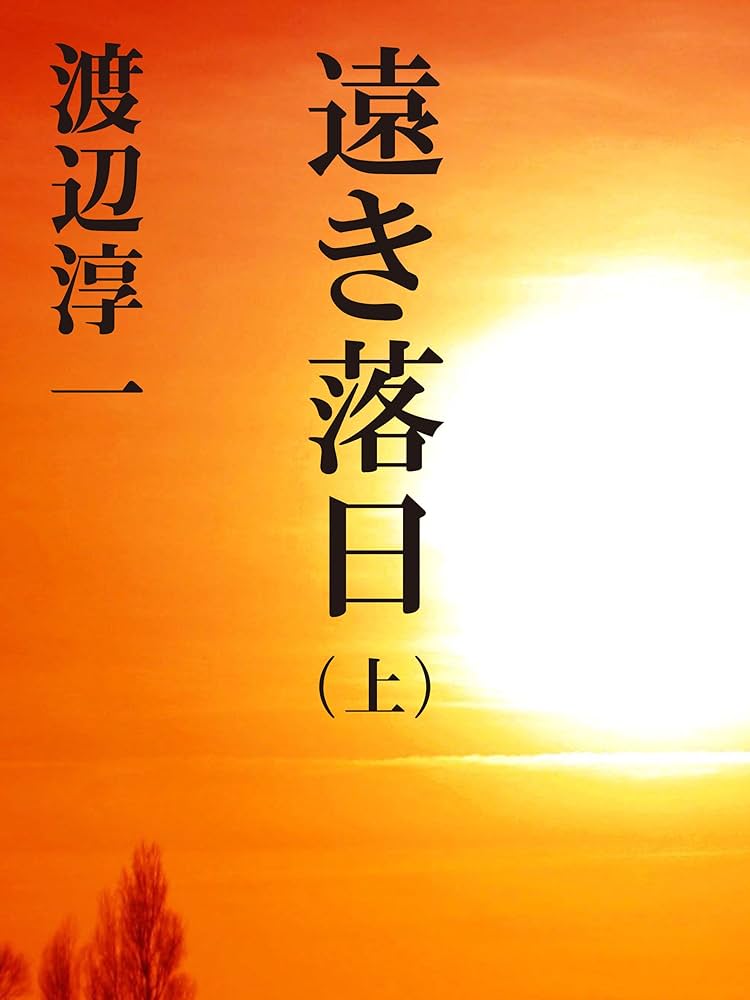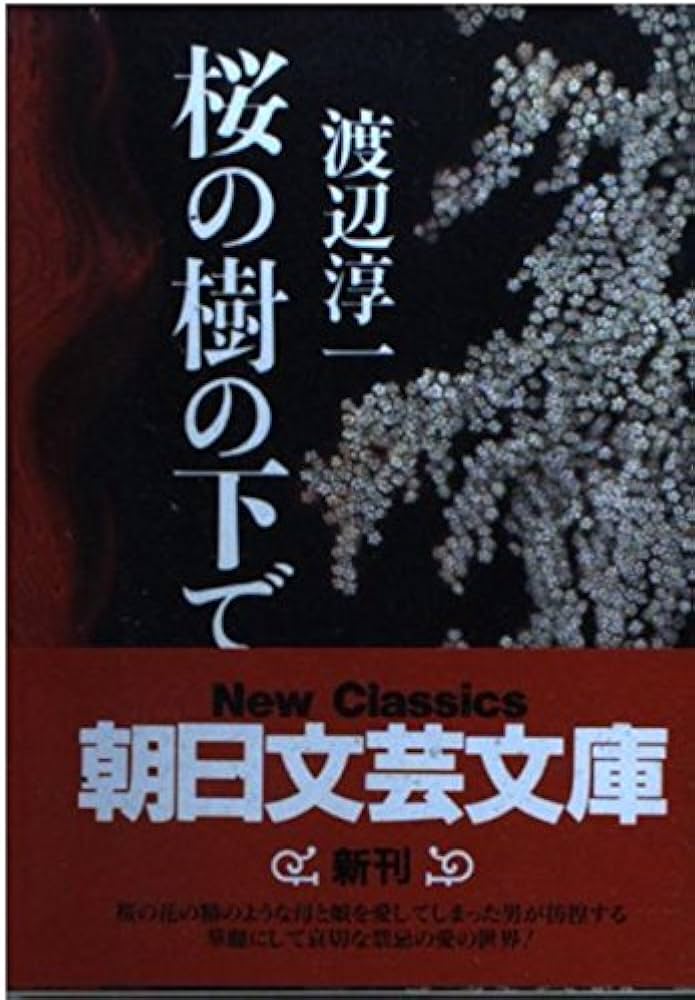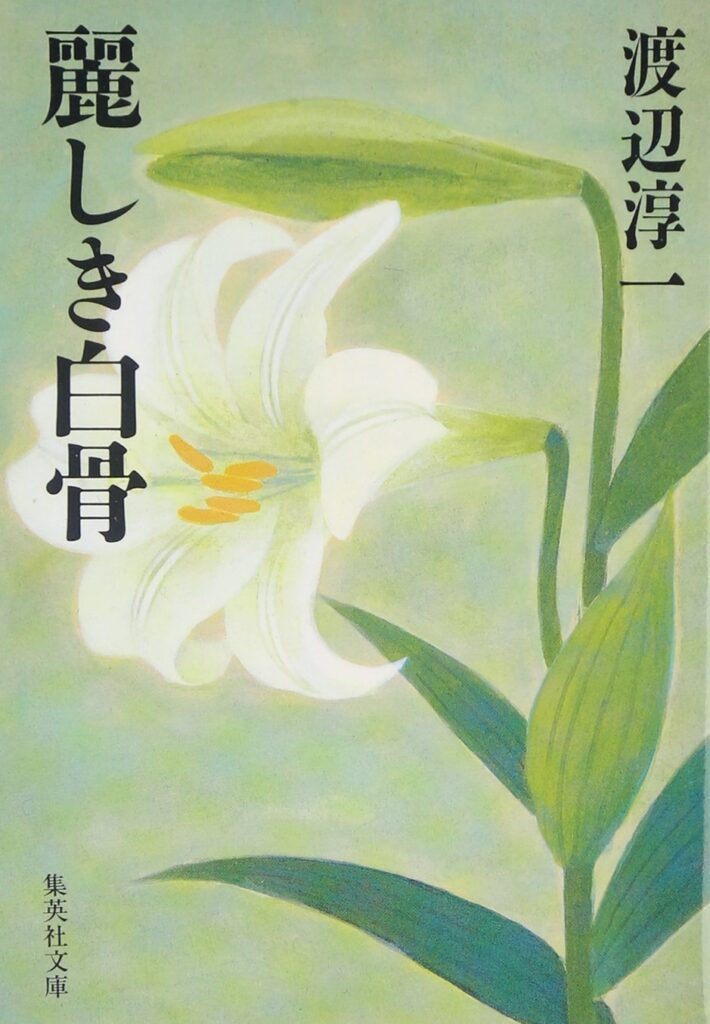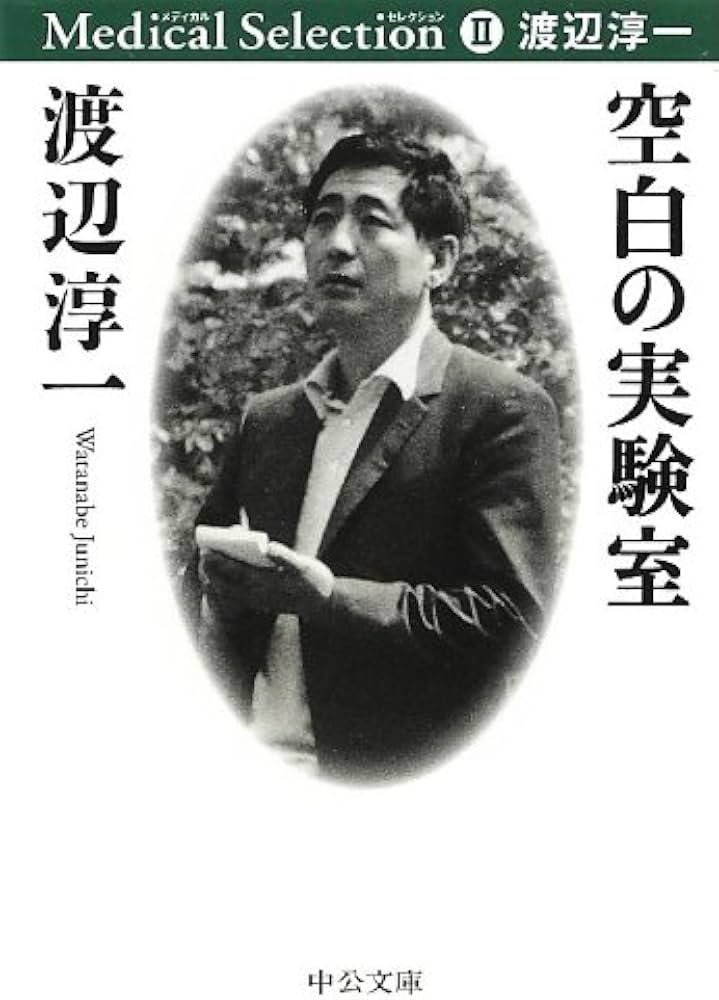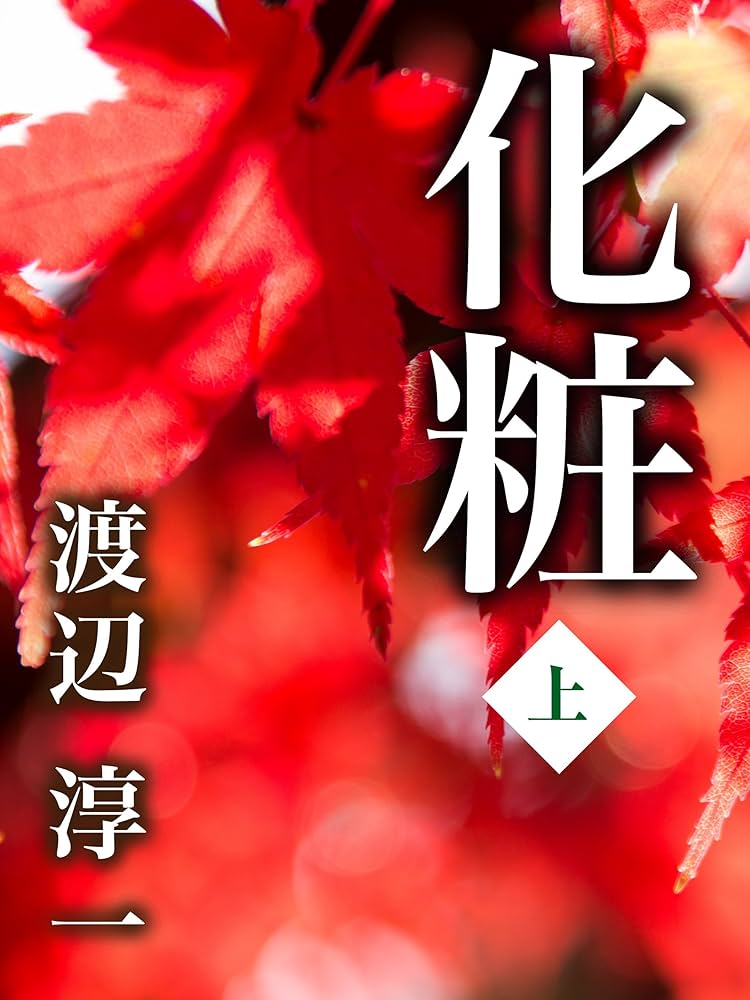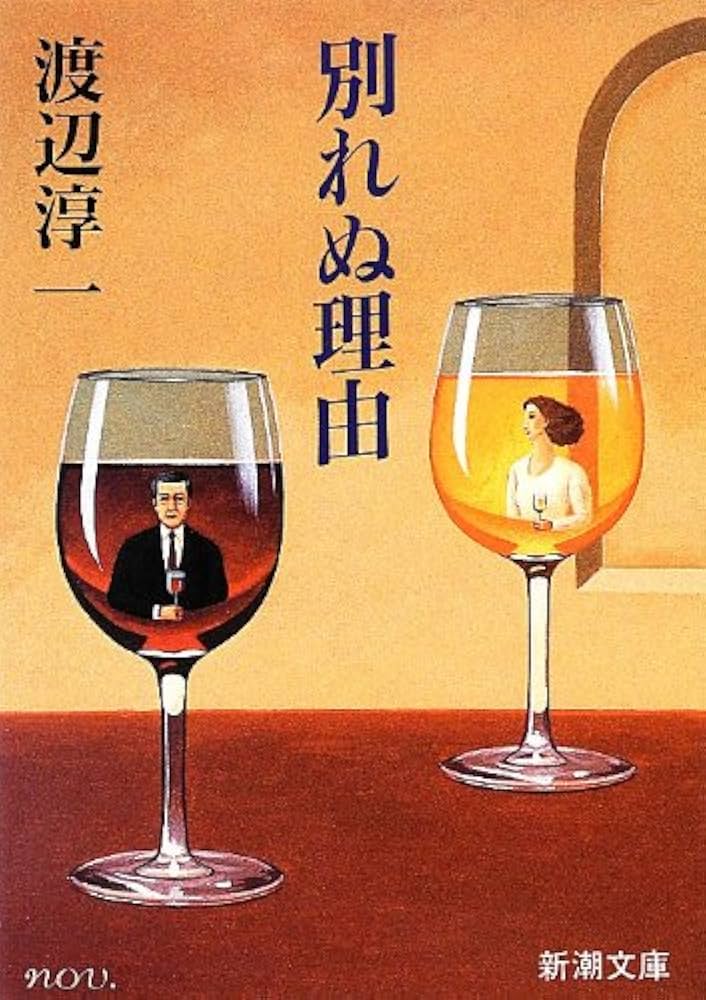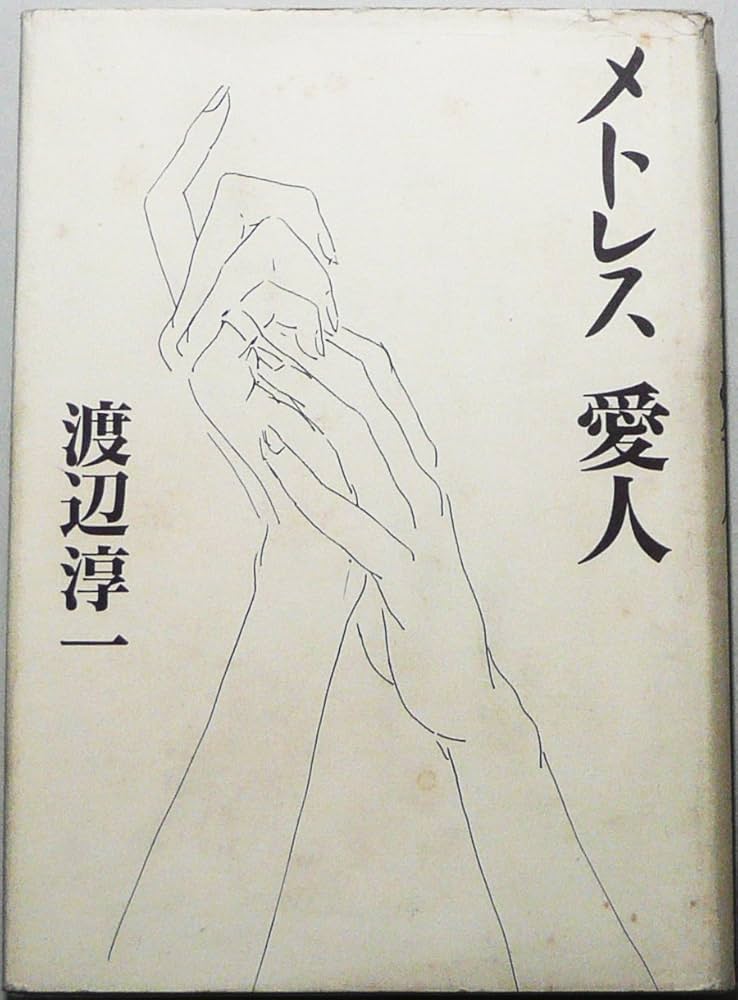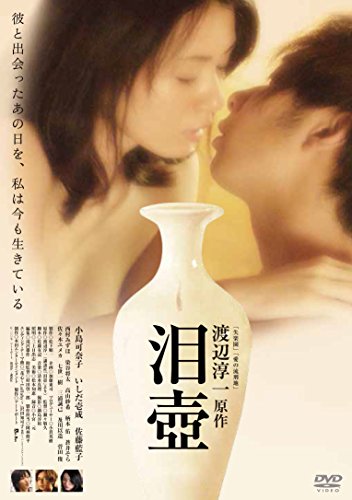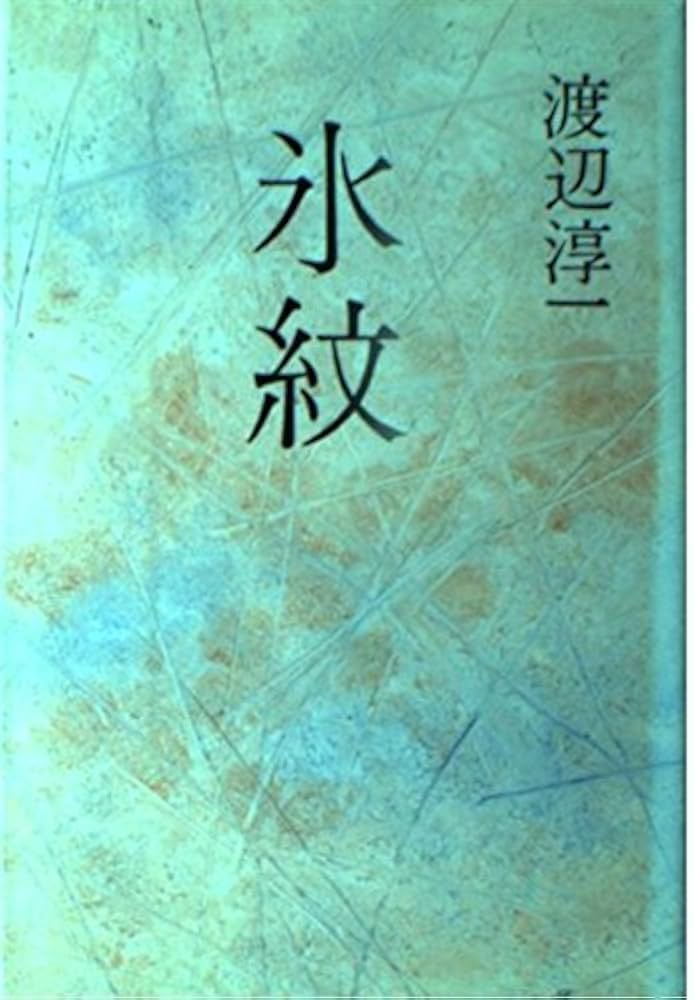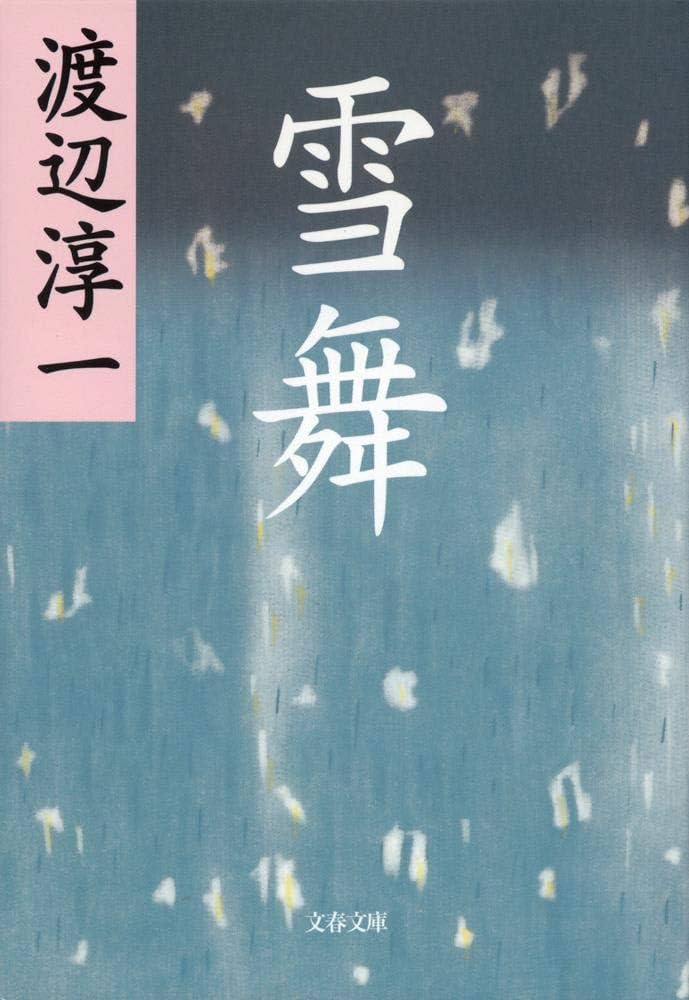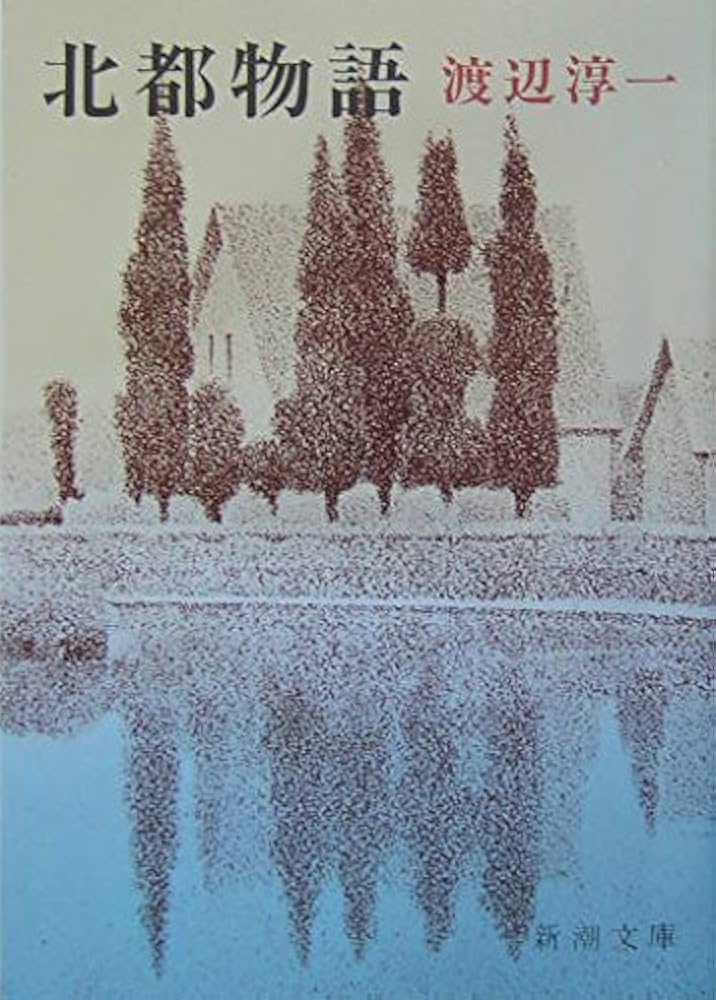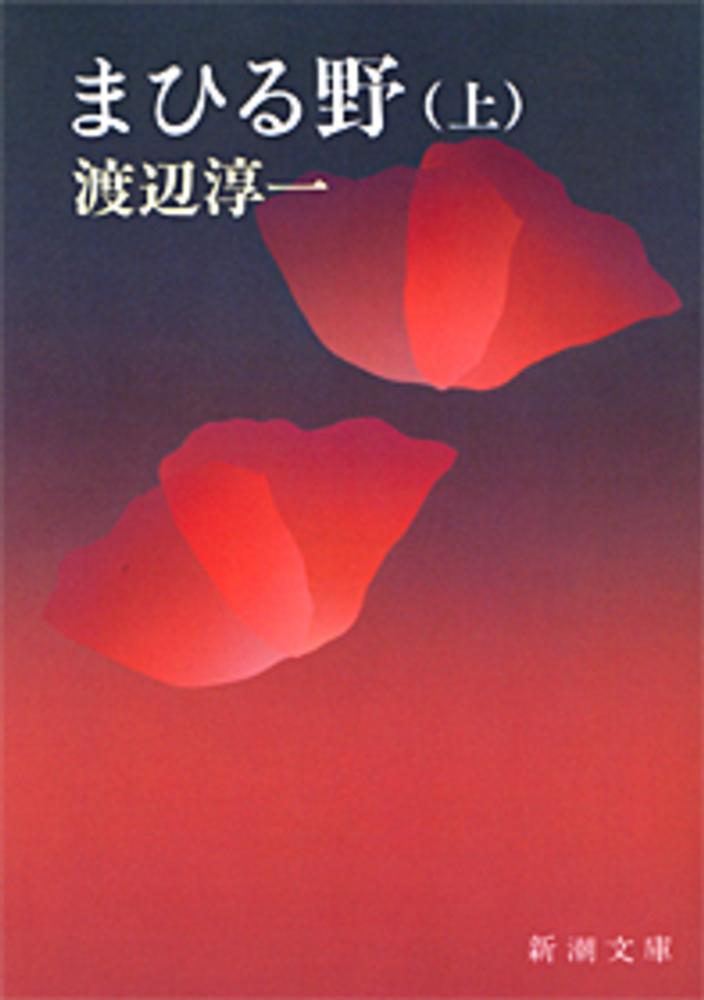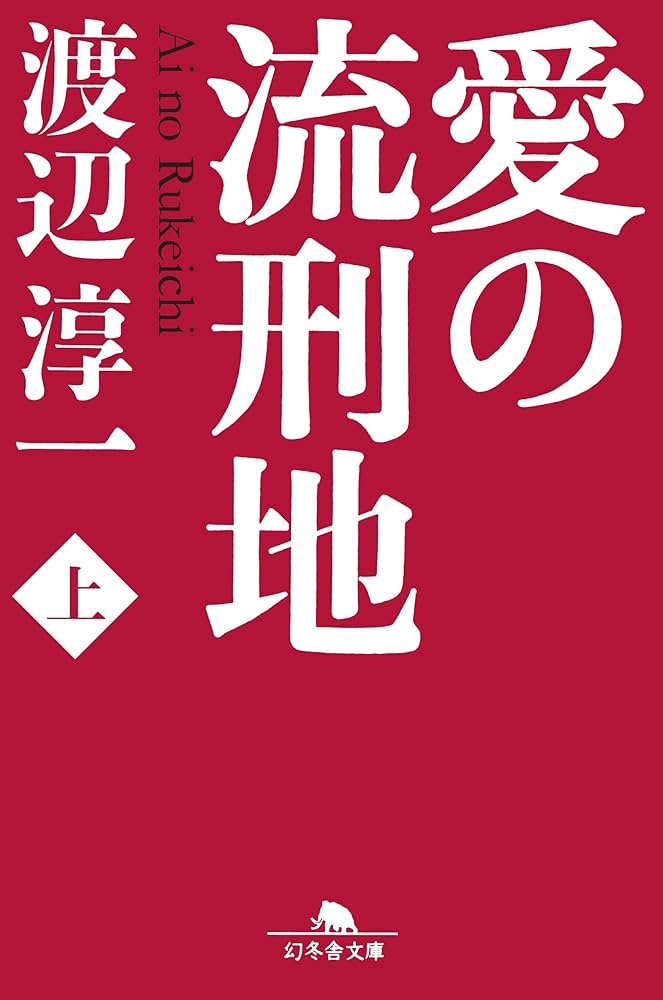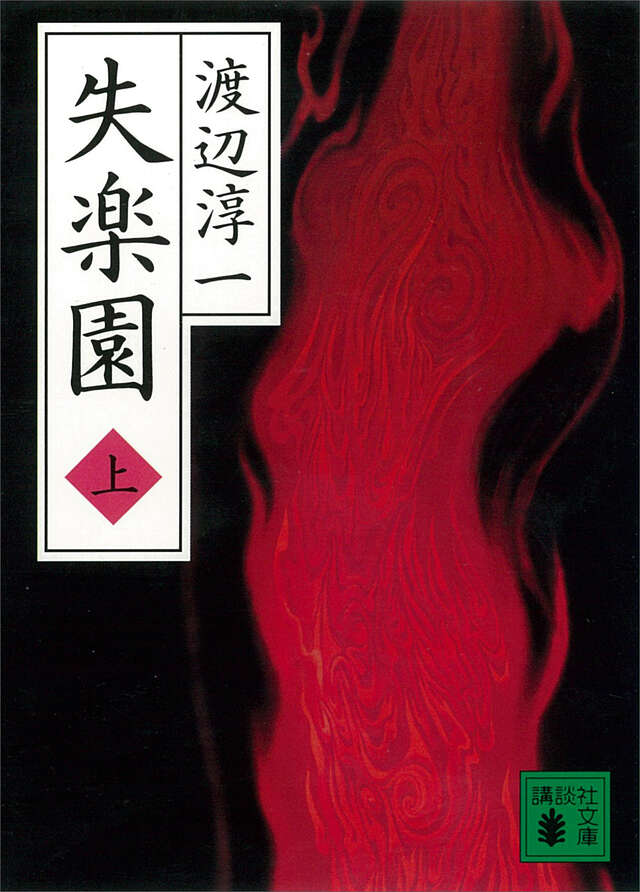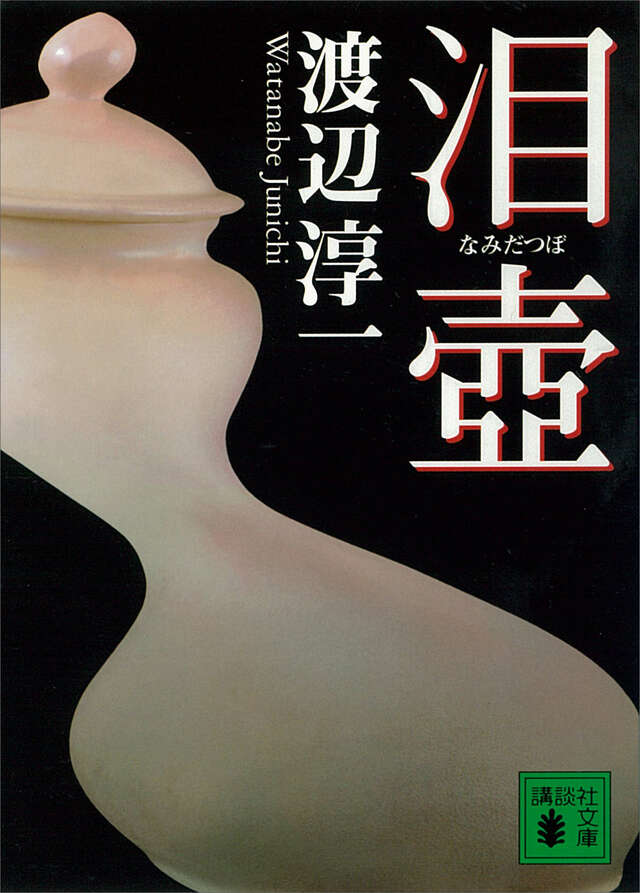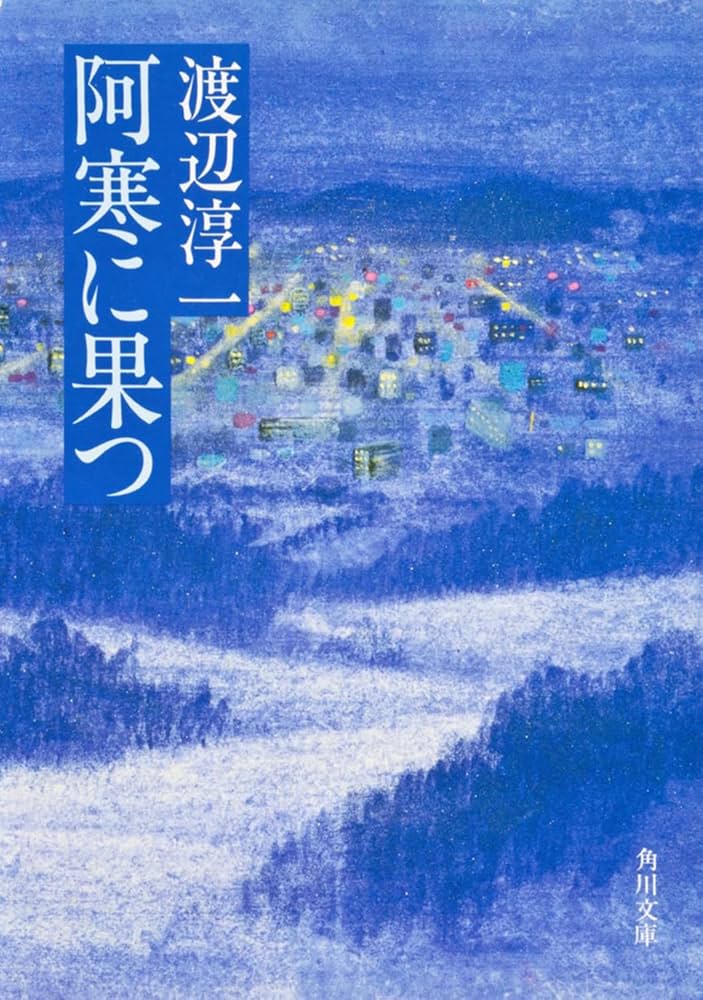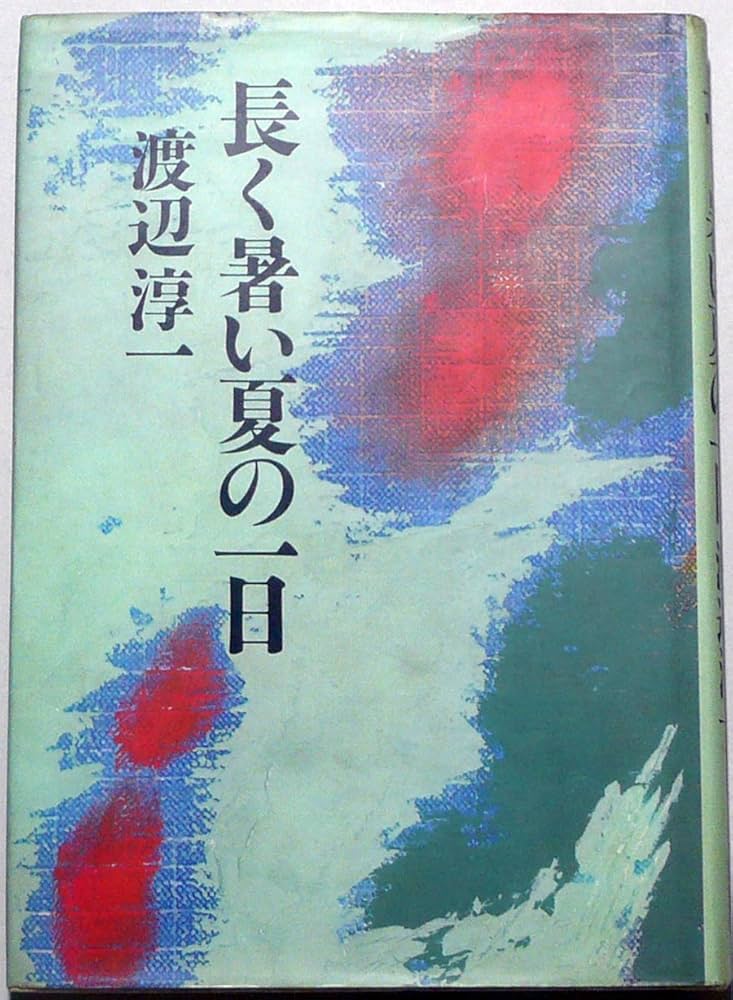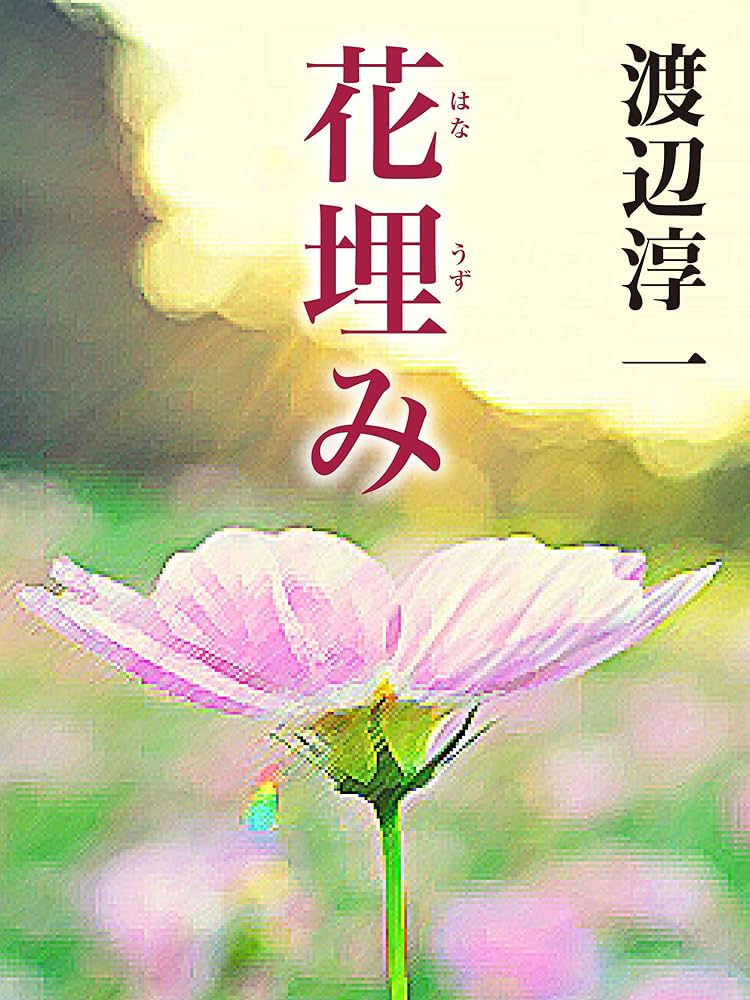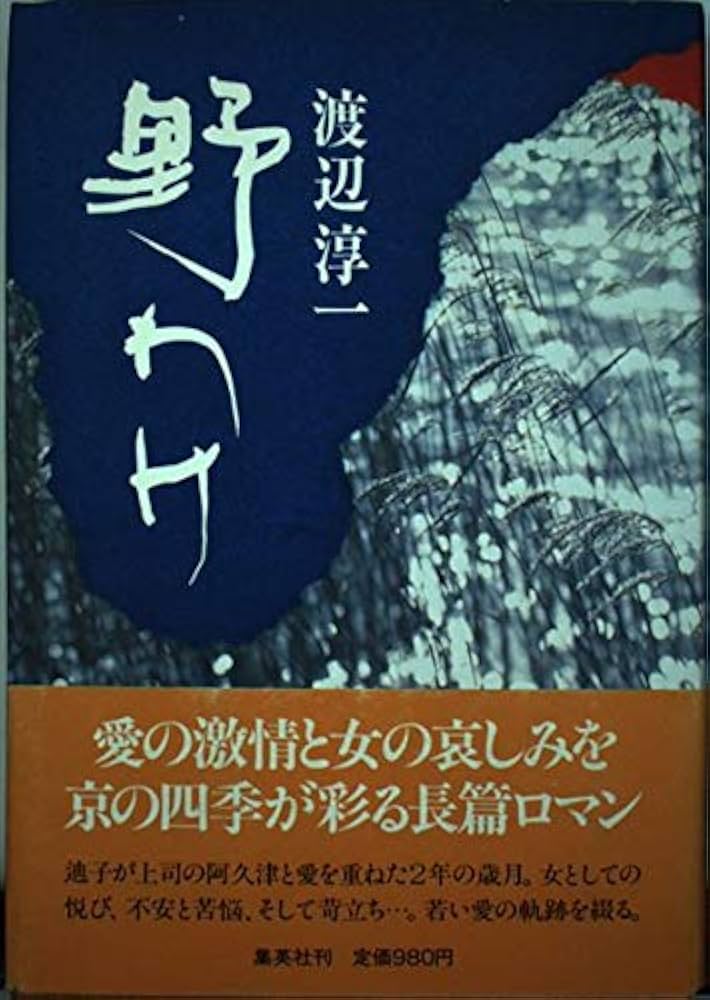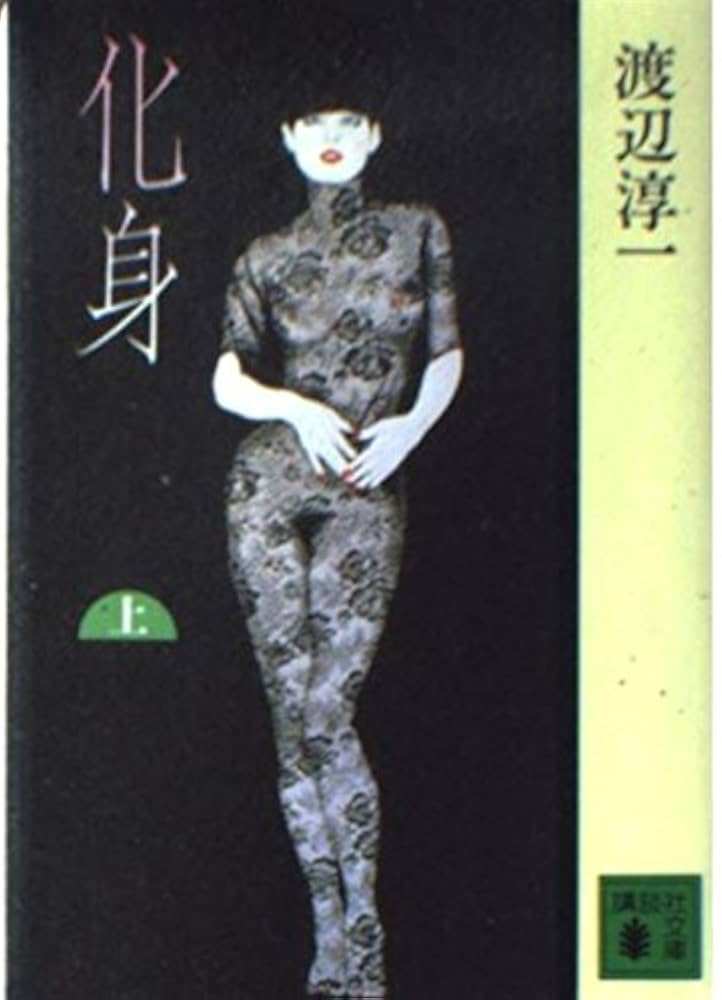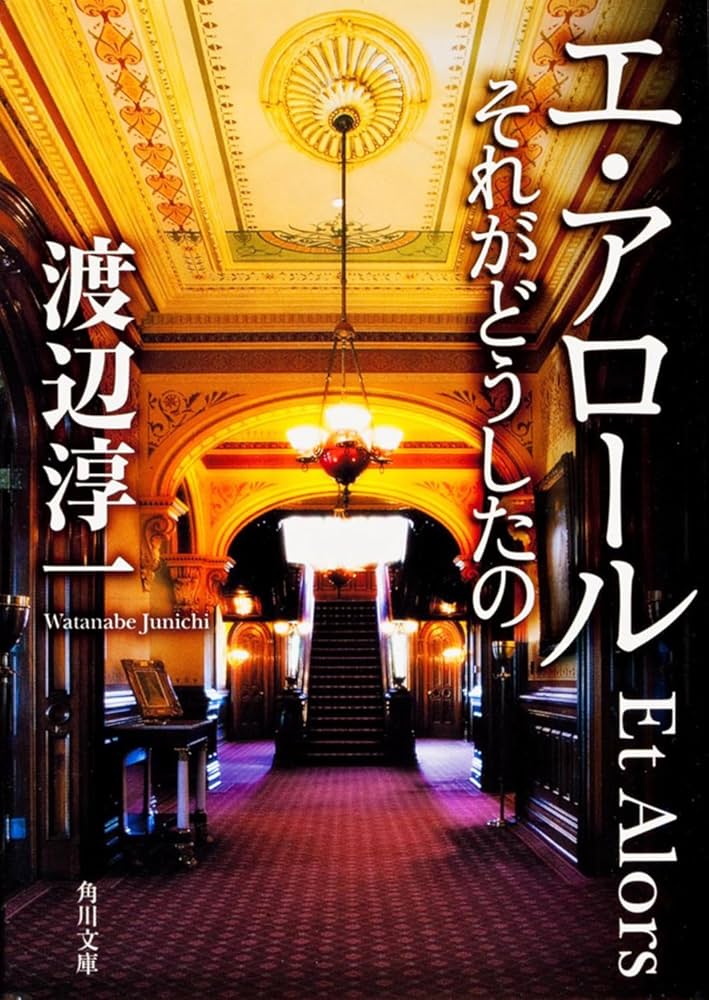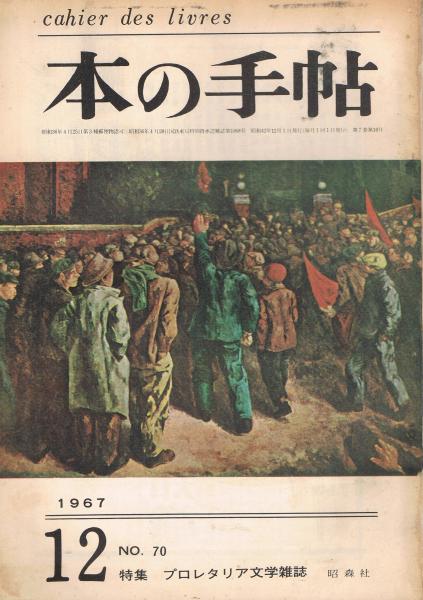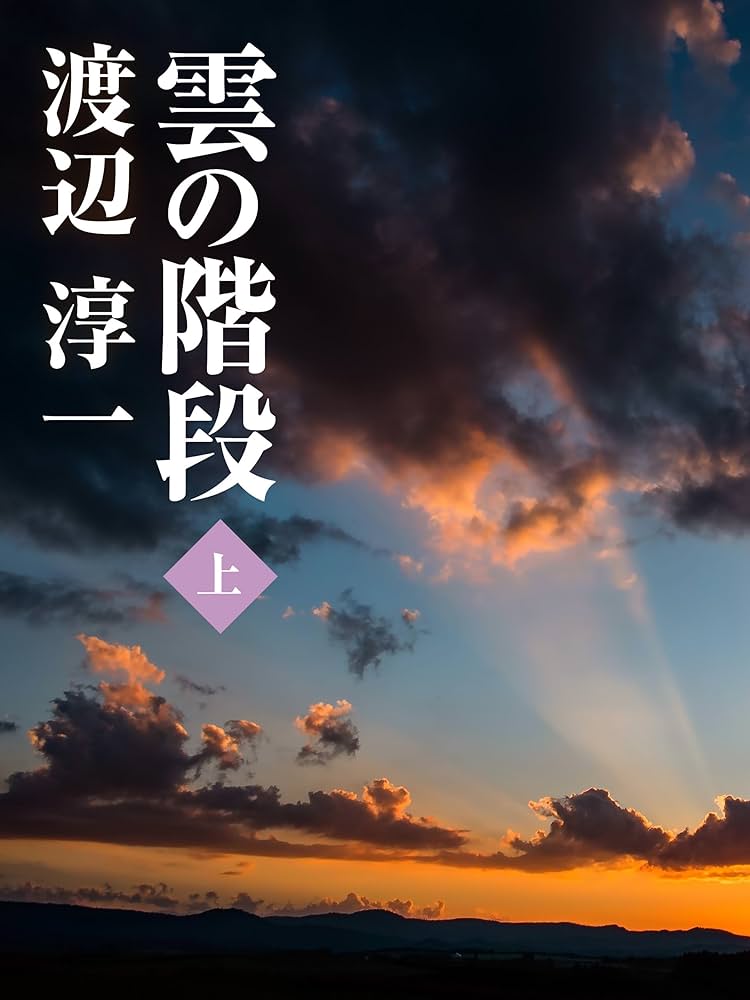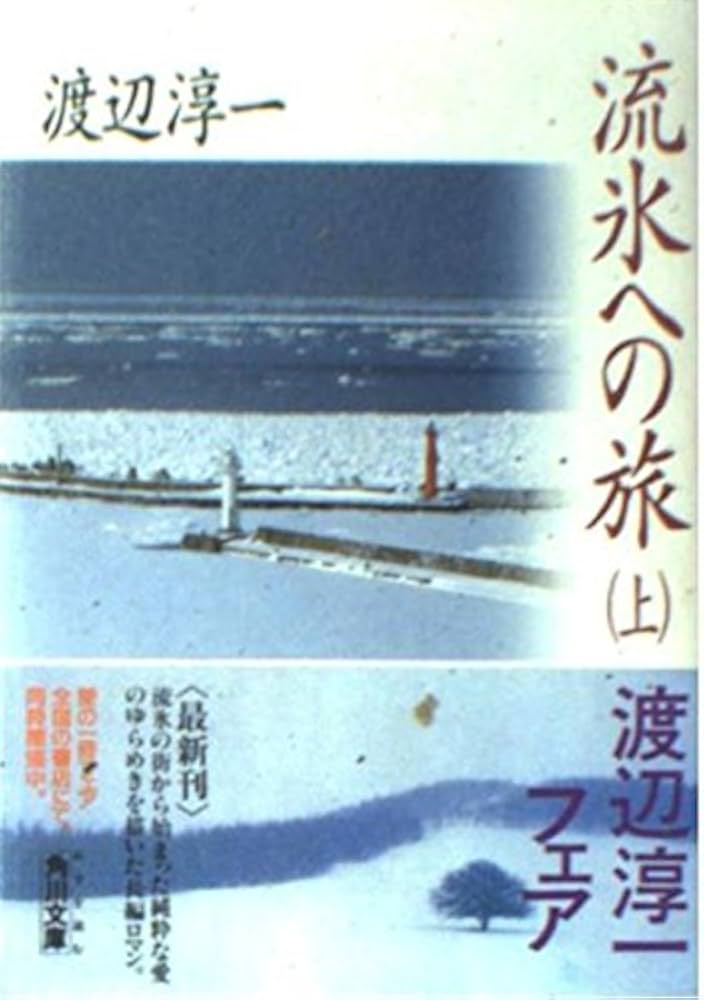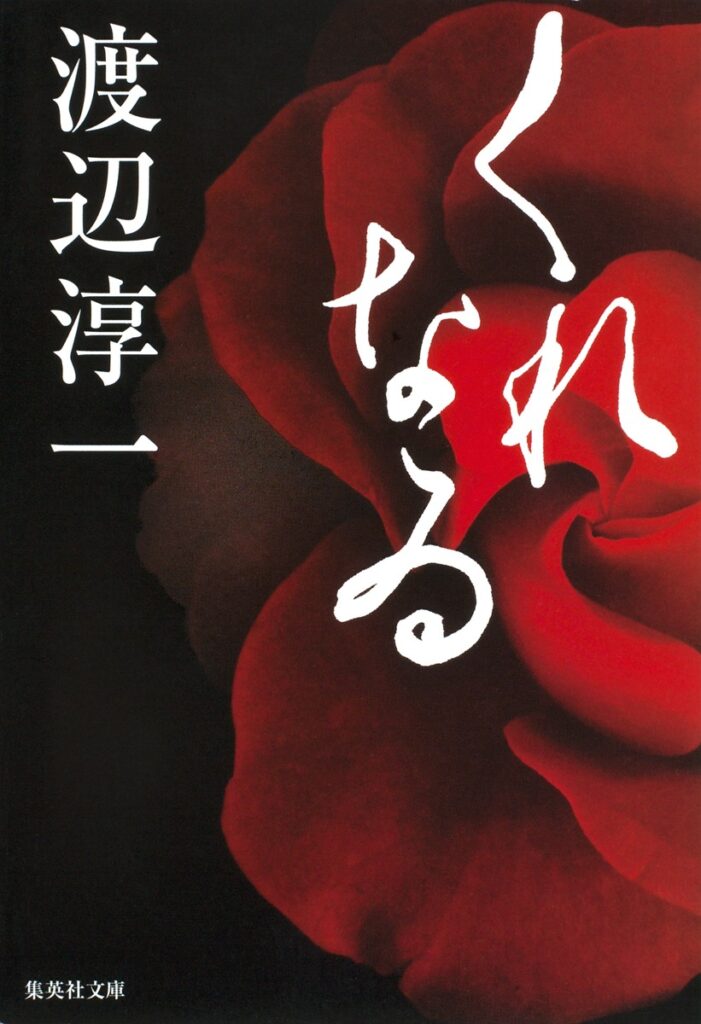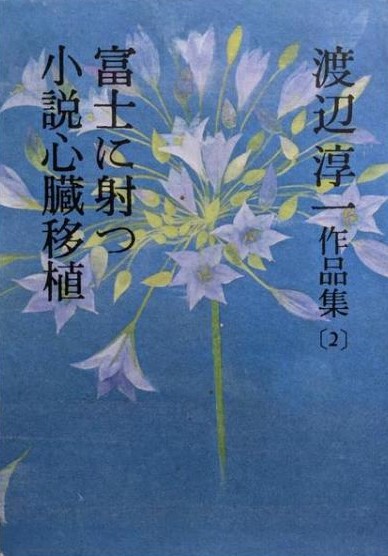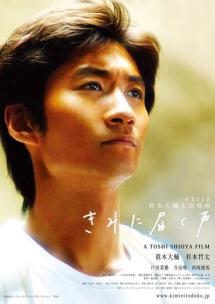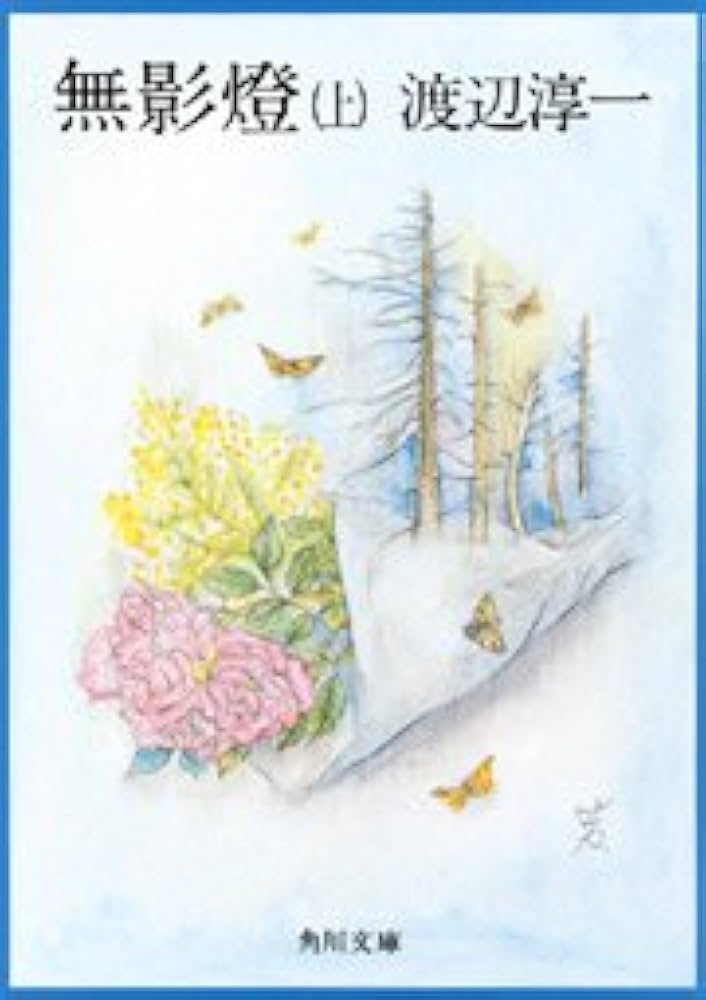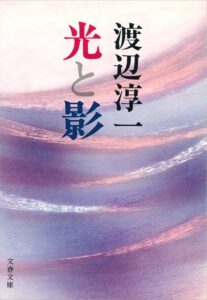 小説「光と影」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「光と影」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
本作は、渡辺淳一氏が作家としてその名を不動のものとした、記念碑的な作品だと私は考えています。1970年に直木賞を受賞したこの短編小説は、後の恋愛小説の名手としてのイメージとは少し異なり、ご自身の医師としての経験を色濃く反映した、人間の心理を深く、そして冷徹にえぐるような物語です。
物語の根幹にある問いは、非常に単純でありながら、私たちの誰もが人生で一度は考えたことのある根源的なものです。それは、ほんの些細な、そして全くの偶然が、二人の人間の人生を、なぜ「光」と「影」という決して交わらない道へと分けてしまうのか、という問いかけです。この問いを、渡辺氏は容赦のない筆致で描き切ります。
この作品を読むことは、人間の尊厳や努力といったものが、時として巨大な「偶然」という力の前ではいかに無力であるかという、厳しい現実に直面することでもあります。しかし、だからこそ本作は、単なる物語を超えて、私たちの心に深く突き刺さるのです。これから、その衝撃的な物語の世界へご案内いたします。
「光と影」のあらすじ
物語の舞台は明治初期、近代日本の黎明期に起きた内戦、西南戦争です。主人公は、将来を嘱望される二人の若き陸軍大尉、小武敬介(おぶ けいすけ)と寺内寿三郎(てらうち ひささぶろう)です。小武は秀才として知られ、常に寺内の一歩先を行く存在でした。彼自身もそのことに強い自負心を抱いており、二人の間には目に見えない序列が存在していました。
激しい戦闘のさなか、二人は運命を同じくします。ほぼ同時に、同じ右腕に敵の銃弾を受け、上腕骨を粉砕するという重傷を負うのです。同じ戦場で、同期の二人が、同じ箇所に、同じような傷を負う。この冷たい偶然の一致が、物語のすべての始まりとなります。
負傷した二人は、治療のために大阪の陸軍臨時病院へ後送されます。当時の医療水準では、彼らのような傷は腕を切断しなければ、感染症によりほぼ確実に死に至るものでした。小武も寺内も、軍人としてのキャリアが絶たれることを覚悟の上で、命を救うための腕の切断を受け入れようとしていました。
執刀医である佐藤軍医は、まず小武の手術に取り掛かります。手術は手際よく進み、予定通り小武の右腕は切断されました。しかし、次に寺内の手術を始めようとしたその時、佐藤軍医の心に、ほんの気まぐれとも言える医学的な探求心が芽生えます。この一瞬の思いつきが、二人の運命を永遠に分かち、壮絶な物語の幕を開けることになるのです。
「光と影」の長文感想(ネタバレあり)
渡辺淳一氏の『光と影』は、読後に深い余韻と、ある種の戦慄を残す物語です。それは、人間の嫉妬という感情がいかに根深く、そして恐ろしいものであるかを、冷徹なメスで解剖するかのように描き出しているからに他なりません。
物語の中心にいるのは、小武敬介と寺内寿三郎という二人の陸軍大尉です。小武は、誰もがその才能を認めるエリートです。彼の自己認識は、常に他者、特に同期である寺内との比較の上に成り立っていました。自分は寺内よりも優れている、その事実が彼のプライドを支える根幹だったのです。
一方の寺内は、凡庸とまではいかなくとも、小武のようなきらびやかな才気を持つ人物ではありません。しかし、彼は小武にとって、自身の優越性を確認するための、なくてはならない存在でした。この関係性が、後に訪れる悲劇の重要な伏線となっています。
西南戦争という歴史の渦の中で、二人は同じ銃弾によって右腕を砕かれます。この「偶然の一致」こそが、物語の残酷な出発点です。彼らが運び込まれた大阪陸軍臨時病院で、二人の運命は、一人の外科医の、ほんの些細な気まぐれによって決定づけられます。
執刀医の佐藤は、まず小武の腕を、当時の標準的な治療法に従って切断します。それは命を救うための、ごく当たり前の処置でした。しかし、続けて寺内の治療に取り掛かった時、彼はふと「切断せずに腕を残したらどうなるか、実験してみたい」という思いつきに駆られます。
この決断には、患者の将来性や価値を秤にかけるような意図は一切ありません。ただ、繰り返される切断手術へのわずかな倦怠感と、純粋な医学的探求心。それだけでした。このあまりにも個人的で、偶然の産物である判断が、一人の人生を「光」へ、もう一人を「影」へと突き落とすのです。
興味深いのは、手術直後の状況が、後の人生とは全く逆転している点です。腕を失った小武は順調に回復し、早期に退院の見込みが立ちます。一方、腕を「残された」寺内は、腕が化膿し、高熱と激痛にうなされる地獄の日々を送ります。彼はあまりの苦しさに、自ら腕を切断してくれと懇願するほどでした。
この皮肉な逆転は、人生の幸不幸が、目先の安楽さでは測れないことを示唆しています。寺内が後に掴む「光」は、この耐え難い苦しみの中から生まれてくるのです。そして小武の「影」は、比較的穏やかだったはずの回復期から、静かにその濃度を増していくことになります。
退院後、小武は軍人としての道を絶たれ、「廃兵」として偕行社(かいこうしゃ)という陸軍将校の支援団体で事務員として働くことになります。当初、病院で苦しむ寺内に同情すら覚えていた彼の心は、ある知らせをきっかけに、ゆっくりと、しかし確実に蝕まれていきます。
それは、寺内が奇跡的に回復し、不自由ながらも両腕が揃っているという理由だけで、現役に復帰したという知らせでした。小武の中で、憐れみは不信へ、そしてどす黒い嫉妬へと変質します。「天命の不合理」に対するやり場のない憤りが、彼の精神をねじ曲げ始める瞬間です。
ここから、物語は二人の人生を対照的に追いかけます。寺内は、その後の軍歴で驚くべき幸運に恵まれます。フランスへの留学、陸軍士官学校長、そしてついには陸軍大臣へと、栄光の階段を駆け上がっていくのです。物語は、この寺内が、史実で総理大臣にまで上り詰めた寺内正毅その人であることを示唆し、物語に圧倒的なリアリティを与えます。
寺内の栄達の知らせが届くたびに、それは小武の心を切り刻む鋭い刃となります。彼は偕行社の片隅で、自分から奪われたはずの輝かしい人生を歩む寺内の姿を、延々と心の中で追い続けるのです。彼の人生は、もはや寺内との比較なしには成り立たなくなっていました。寺内の「光」が強まれば強まるほど、小武の「影」は深く、濃くなっていく。二人の人生は、互いに無関係ではいられない、寄生的な関係で結ばれてしまったのです。
そして数十年後、運命は最も残酷な形で二人を再会させます。陸軍大臣となった寺内は、慣例により偕行社の社長を兼務することになり、長年勤めてきた小武は、その直属の部下、事務長として彼に仕えることになったのです。かつて見下していた男の前に、今は惨めな部下としてひざまずかなければならない。この屈辱が、小武がかろうじて保っていた理性の最後の糸を焼き切ります。
陸軍大臣室での対面の場面は、この物語のクライマックスの一つです。数十年にわたって蓄積された小武の怨嗟と嫉妬が、ついに堰を切ってあふれ出します。彼は寺内の前で自制心を失い、支離滅裂な言葉を吐き、自らを決定的に貶めてしまうのです。それは、自己破壊以外の何物でもありませんでした。しかし、その激情でさえ、「光」である寺内には何の傷も与えられません。ただ、自身の「影」としての立場を、公衆の面前で確定させるだけの結果に終わりました。
物語は、さらに時を経た大正時代、小武が偕行社を退職した後のエピソードで、最後のとどめを刺します。長年の疑問、「なぜ自分だけが腕を切断されたのか」その答えを求め、小武は引退した老医師、佐藤のもとを訪ねます。彼はそこに、何らかの理由、自分の苦しみに意味を与えてくれる答えを期待していました。
しかし、佐藤から返ってきた答えは、あまりにも陳腐で、そしてそれゆえに破壊的でした。佐藤は、二人の治療法を分けたことに大した理由はなかった、とこともなげに語ります。「ただ、カルテの順番がそうだっただけだ」と。最初に小武の手術を終え、次にたまたま寺内の番が来たから、気まぐれに違う方法を試した。ただそれだけだった、というのです。
この啓示は、小武の精神を完全に粉砕します。彼の全人生を支配してきた苦悩、嫉妬、失われたキャリア、そのすべてが、壮大な悲劇でもなければ、悪意ある陰謀でもなく、単なる事務的な順番という、全く意味のない偶然の産物だった。その事実が、彼の苦しみの重さを無意味なものへと変えてしまったのです。小武は発狂し、一人の壊れた人間として生涯を終えます。
『光と影』が私たちに突きつけるのは、人間を本当に破壊するのは、苦しみそのものではなく、「自分の苦しみが無意味である」という発見だ、という冷厳な事実です。もし運命が悪意や過ちによるものなら、まだ憎む対象を見つけることで救われたかもしれません。しかし、あまりに些細な偶然が原因だったと知ることは、人間の精神が耐えうる不条理の限界を超えていたのです。これこそが、医師であった渡辺淳一氏による、人間の魂に対する、最も冷徹な診断書なのかもしれません。
まとめ
渡辺淳一氏の『光と影』は、単なる小説という枠を超え、人生の不条理と偶然の恐ろしさを見事に描き出した傑作です。たった一つの偶然が、二人の人間の運命を「光」と「影」に無慈悲に引き裂いていく様は、読む者の心を強く揺さぶります。
物語を通じて描かれるのは、エリートであった小武の心に巣食う、寺内への嫉妬の深化です。その執拗なまでの心理描写は、人間のプライドがいかに脆く、そして一度崩れるとどこまでも人を蝕んでいくかを克明に描き出しています。これは、誰の心にも潜む可能性のある、普遍的な感情の闇なのかもしれません。
そして、この物語が最も恐ろしいのは、その運命の分岐点に、何の悪意も、意図も、深い理由すら存在しなかったという結末です。すべては執刀医のほんの気まぐれ、カルテの順番という些細な偶然の産物でした。この「意味の不在」こそが、主人公の精神を最終的に崩壊させるのです。
読後、私たちは、自らの人生における幸運や不運について、改めて考えさせられることになるでしょう。それは決して明るい気持ちにさせるものではないかもしれません。しかし、人間の心の深淵と、人生に横たわる厳粛な真実から目をそらさずに描いた本作は、間違いなく文学の力を感じさせてくれる一冊です。