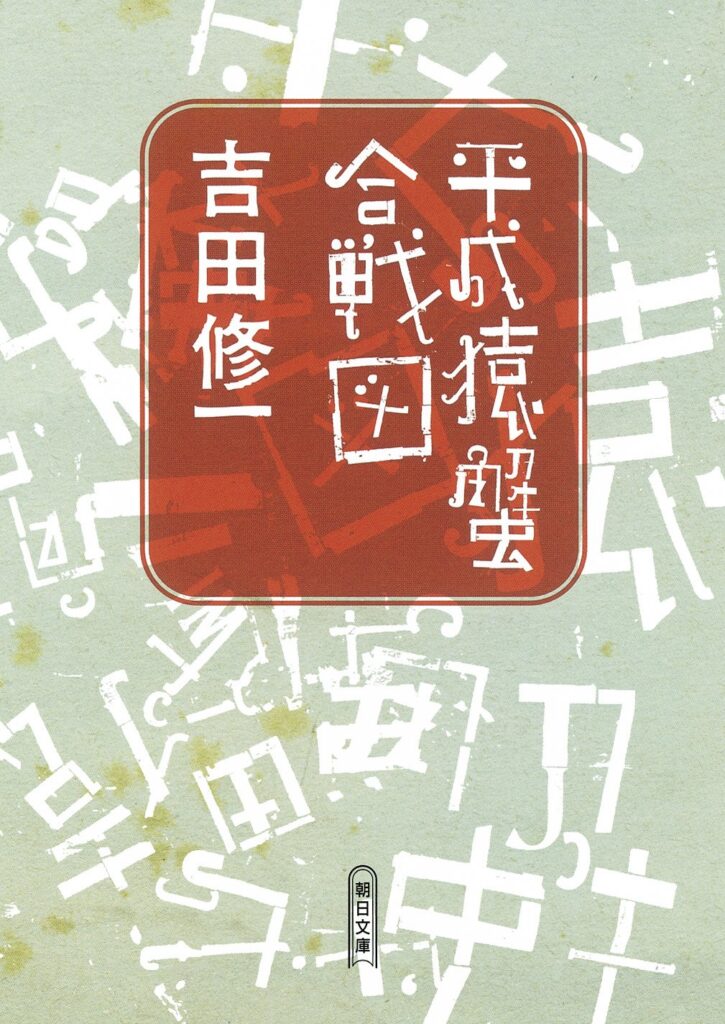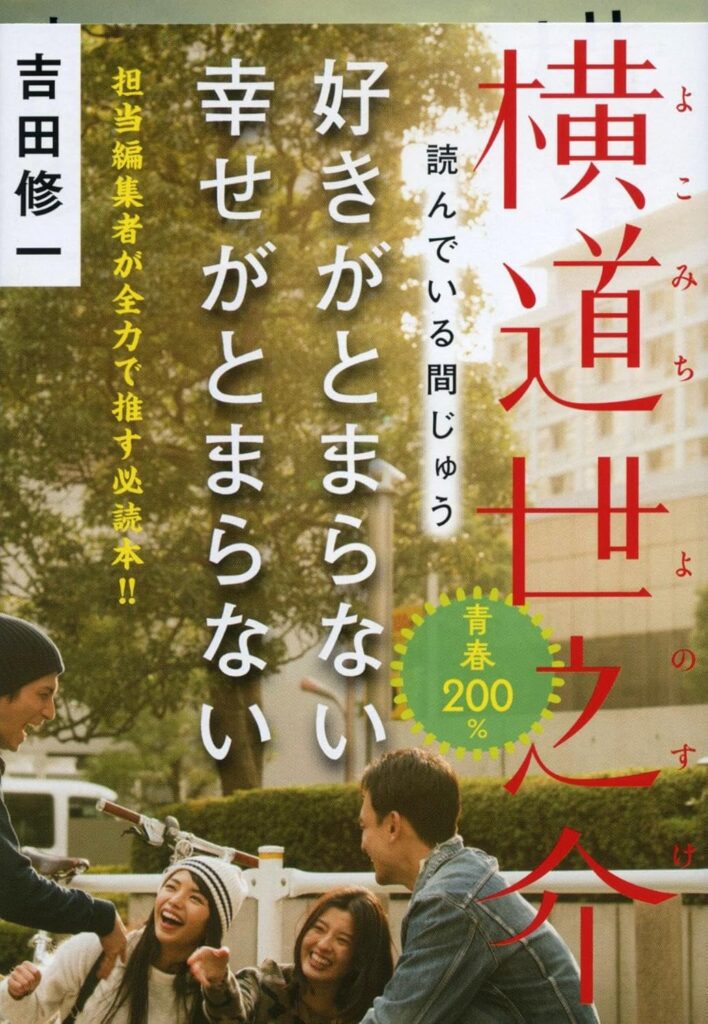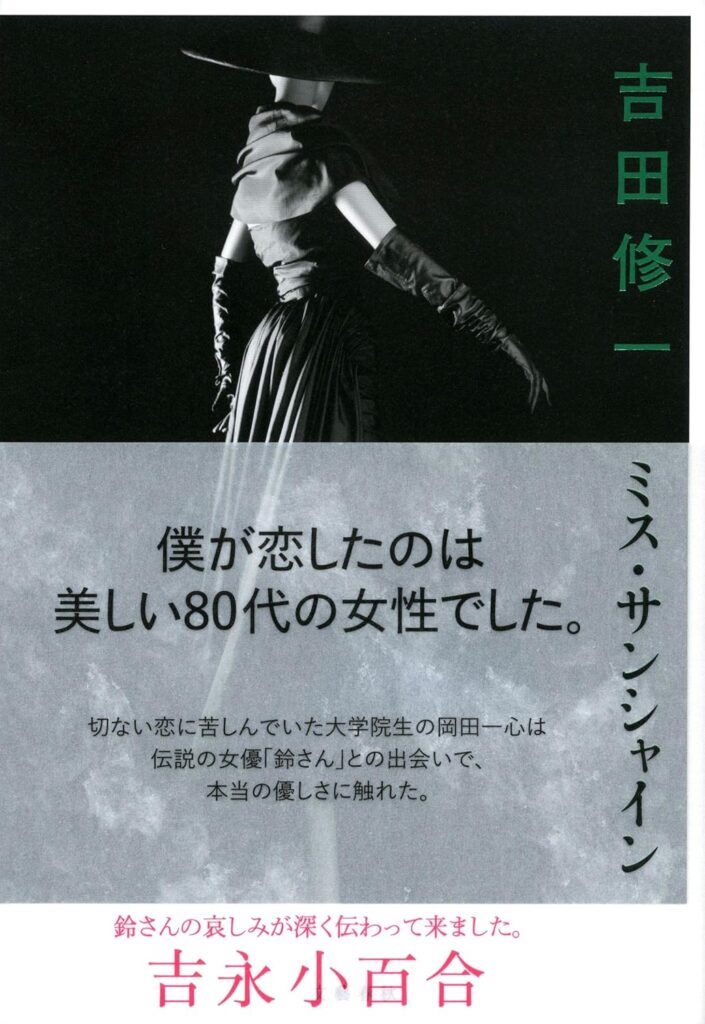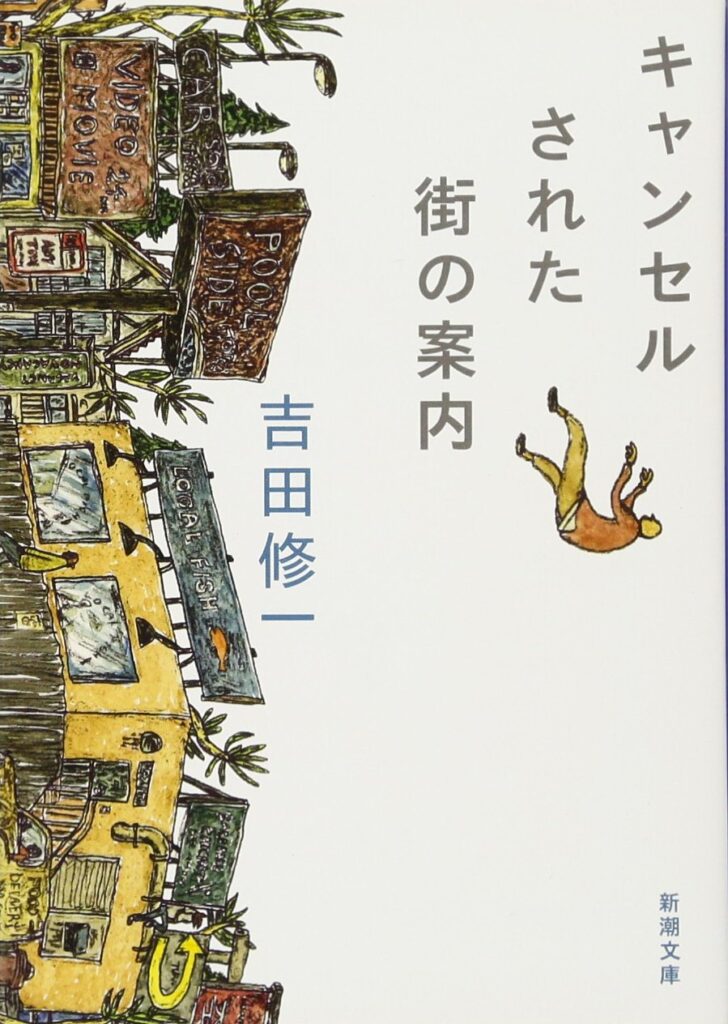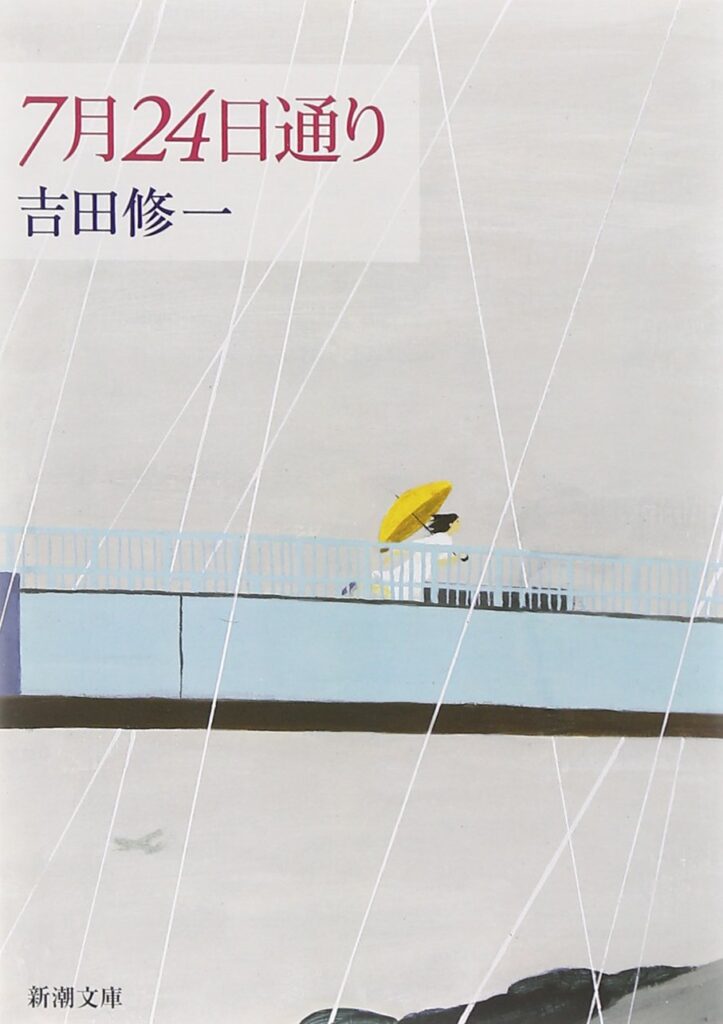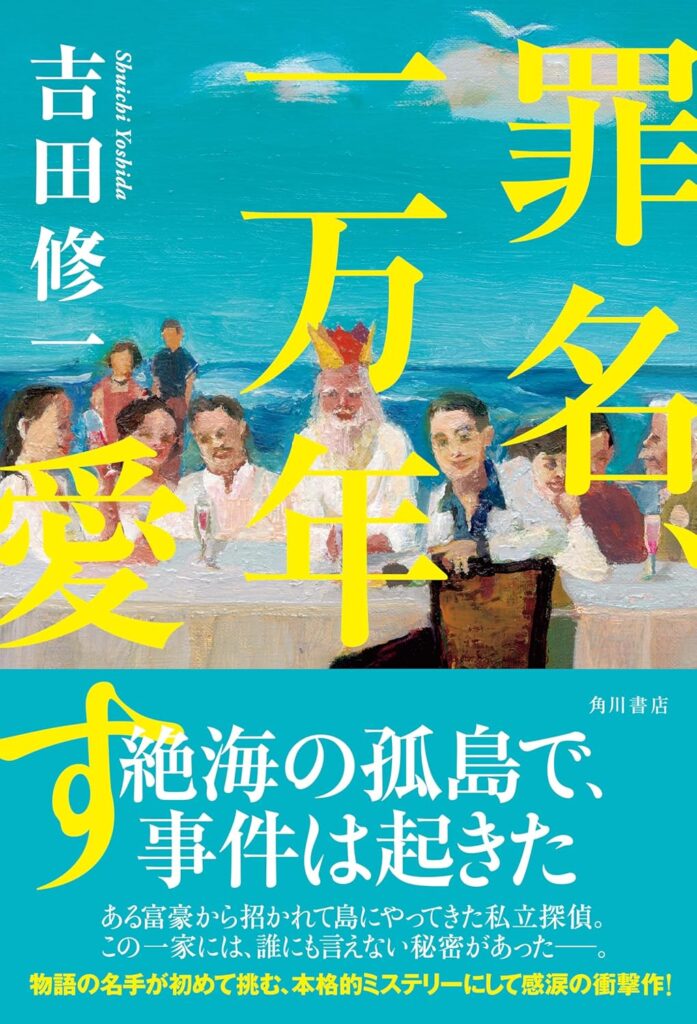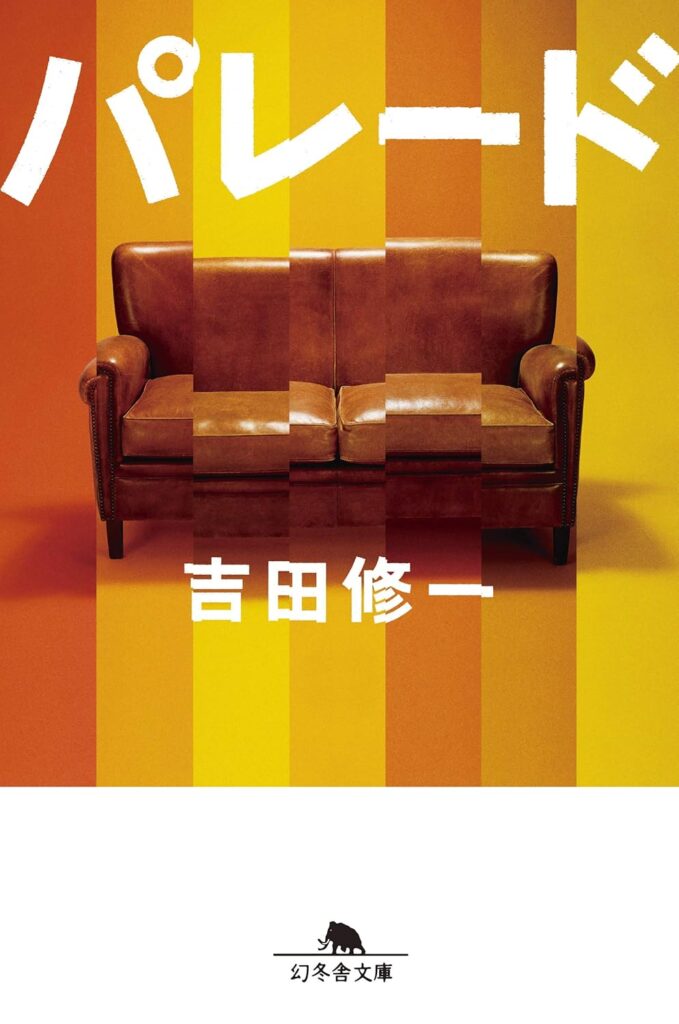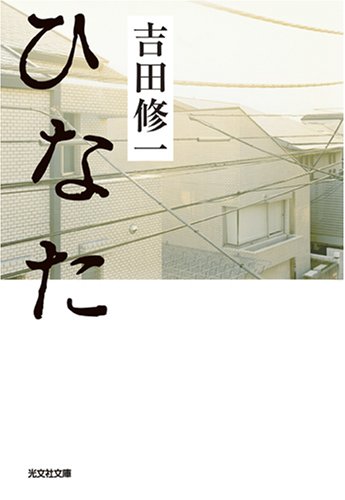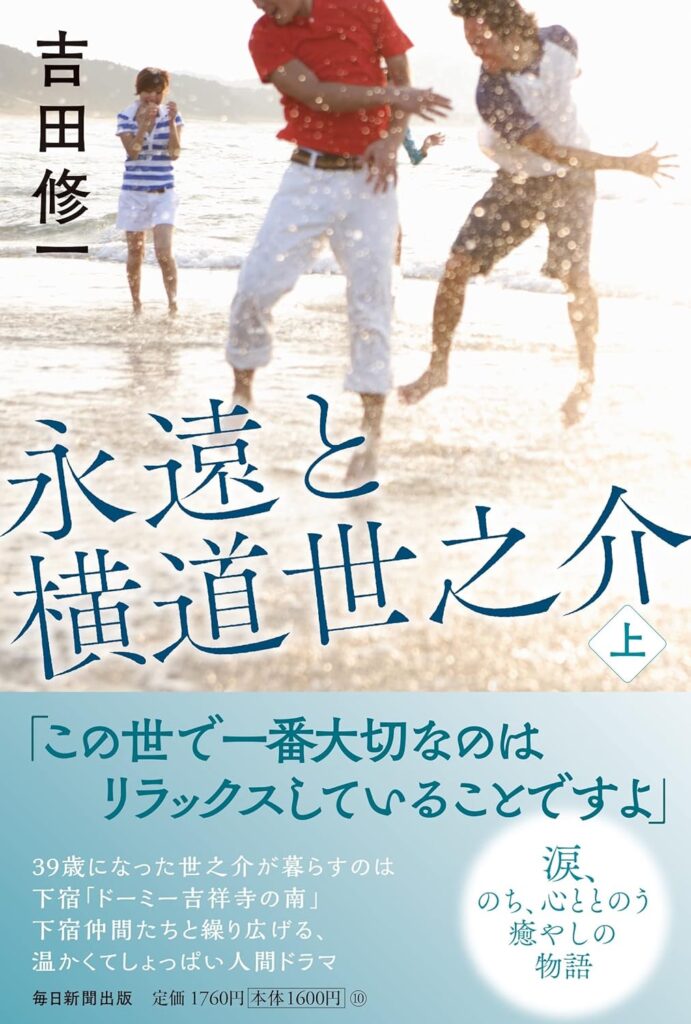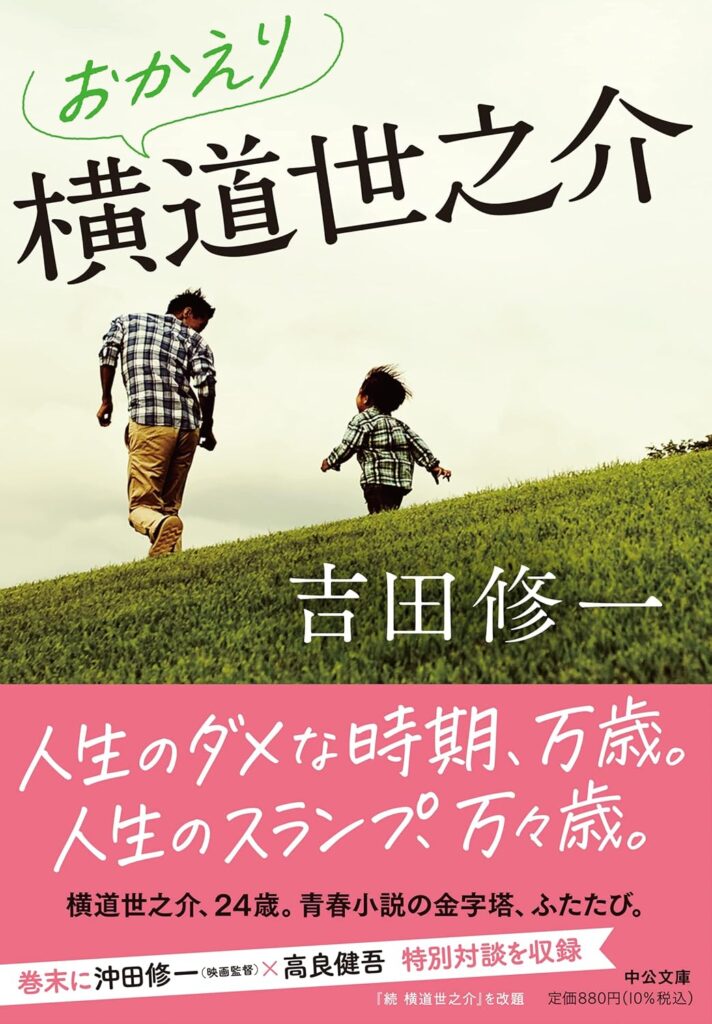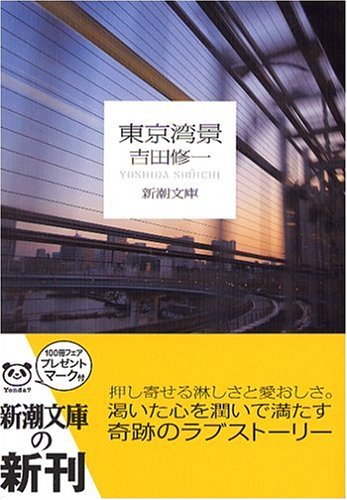小説「元職員」の物語の結末に触れつつ、その概要を紹介します。詳細な考察や読後感も心を込めて綴っていますので、どうぞ最後までお付き合いください。
小説「元職員」の物語の結末に触れつつ、その概要を紹介します。詳細な考察や読後感も心を込めて綴っていますので、どうぞ最後までお付き合いください。
この物語は、どこにでもいそうな一人の男が、日常の些細なきっかけから取り返しのつかない深みにはまっていく様子を描いています。読み進めるうちに、まるで自分自身の心の奥底を覗き込んでいるかのような、居心地の悪さを感じるかもしれません。しかし、それこそが吉田修一作品の持つ、抗いがたい魅力なのではないでしょうか。
舞台はタイのバンコク。蒸し暑い空気と喧騒、そして主人公が抱える秘密。それらが絡み合い、読者を息苦しいほどの緊張感で包み込みます。この作品を読むことで、私たちは人間の弱さや脆さ、そしてどうしようもない現実について、深く考えさせられることになるでしょう。
本記事では、この「元職員」という作品が読者にどのような問いを投げかけてくるのか、そしてその物語の核心に何があるのかを、私なりの視点で解き明かしていきたいと思います。読み終えた後、きっとあなたも誰かとこの物語について語り合いたくなるはずです。
小説「元職員」のあらすじ
栃木県の公社に勤める片桐は、どこか満たされない日々を送る平凡な男です。彼は妻との関係も冷え切っており、日常に息苦しさを感じています。そんな彼が、本来は妻と二人で訪れるはずだったタイのバンコクへ、一人旅に出るところから物語は始まります。
バンコクの熱気あふれる街で、片桐は武志という日本人青年と出会います。武志は現地で暮らしており、どこか飄々とした掴みどころのない若者です。彼の紹介で、片桐はミントと名乗る美しい女性と知り合います。彼女は娼婦であり、片桐は彼女と時間を過ごすようになります。
ミントとの関係を通じて、片桐はバンコクの夜の顔、そしてそこに生きる人々の現実を目の当たりにします。言葉も通じない異国の地で、彼は刹那的な安らぎと興奮を覚えますが、それは同時に彼の抱える「秘密」の重さを際立たせるものでもありました。
実は片桐は、勤務先の公社で巨額の金を横領していました。最初はほんの出来心、軽い気持ちで手を染めた不正でしたが、徐々にその額は膨れ上がり、もはや後戻りできない状況に陥っていたのです。上司の無関心や職場の緩慢な空気も、彼の犯行を助長する要因となっていました。
バンコクでの日々は、彼にとって現実逃避であると同時に、自らの罪と向き合う時間でもありました。しかし、彼は心のどこかで自分の行為を正当化しようとし、周囲の人々や環境のせいにしようとします。ミントや武志との交流、そしてタイで目の当たりにする日本人の姿は、そんな彼の内面を容赦なく映し出していきます。
やがて日本へ帰国する日が近づくにつれ、片桐の心は不安と焦燥感で満たされていきます。横領の事実がいつ発覚するのかという恐怖。しかし、彼は驚くべきことに、開き直りにも似た感情を抱き始めます。「どうにでもなれ」という投げやりな気持ちと、「自分は悪くない」という歪んだ自己肯定感が、彼の心を支配していくのです。物語の結末、彼がどのような選択をするのか、そしてその先に何が待っているのか、ぜひ本編で確かめてみてください。
小説「元職員」の長文感想(ネタバレあり)
吉田修一氏の「元職員」を読み終えたとき、胸に残ったのは、なんとも言えない重苦しさと、登場人物たちへの複雑な感情でした。この物語は、決して読後感が爽快なタイプのものではありません。むしろ、人間の心の闇や弱さ、そして日常に潜む陥穽をまざまざと見せつけられるような、ある種の不快感すら伴う作品と言えるかもしれません。しかし、それこそが本作の持つ力であり、読者に深い問いを投げかける所以なのでしょう。
物語の主人公である片桐は、どこにでもいそうな、しかし決して共感できるとは言えない人物です。彼は公社の職員として淡々と日々を過ごしていますが、その内面には鬱屈とした不満や、根拠のないプライドを抱えています。妻との関係は冷え切り、職場では天下りの上司のもと、半ば諦めにも似た感情で仕事に取り組んでいます。彼の心の中には、常に「自分はこんなものではない」という思いがあるものの、それを打破するための具体的な行動を起こすわけでもありません。
そんな彼が手を染めるのが、公金の横領です。最初はほんの些細な出来心から始まった不正は、雪だるま式に膨れ上がり、彼の日常を蝕んでいきます。しかし、片桐はその事実から目を逸らし、責任を他者に転嫁しようとします。上司の怠慢、妻の無理解、職場の閉塞感。彼はあらゆるものを言い訳にして、自らの罪の意識を薄めようと試みます。この自己正当化の心理描写は、読んでいて非常に息苦しさを覚える部分です。
物語の舞台となるタイのバンコクは、この作品において非常に重要な役割を果たしています。蒸し暑い気候、猥雑な街並み、そしてそこで出会う人々。それらは、片桐の心の空虚さや孤独感を際立たせる装置として機能しています。特に、娼婦のミントとの関係は象徴的です。言葉もろくに通じない彼女に対し、片桐は支配的な態度を取ろうとしたり、一方で束の間の安らぎを求めたりします。しかし、そこには真の心の交流はなく、彼の自己中心的な欲望が透けて見えるばかりです。
バンコクで出会うもう一人の日本人、武志もまた興味深い存在です。彼はタイで気ままに暮らしているように見えますが、その言動からは、片桐のような日本の中流階級の人間に対するある種の軽蔑が感じられます。武志の存在は、片桐が抱える欺瞞や自己満足を浮き彫りにする鏡のような役割を担っているのかもしれません。
この物語を読んでいて強く感じるのは、登場人物たちの「どうしようもなさ」です。片桐はもちろんのこと、彼の妻や職場の同僚、そしてバンコクで出会う人々もまた、それぞれの問題を抱え、どこか満たされない日々を送っています。彼らは互いに影響を与え合いながらも、本質的な部分では決して交わることなく、それぞれの孤独の中を生きているように見えます。
特に印象的だったのは、片桐が横領した金で手に入れたはずの「自由」や「快楽」が、いかに虚しいものであるかという点です。彼は大金を手にしたにもかかわらず、心からの満足感や幸福感を得ることができません。むしろ、金の重圧は彼をさらに追い詰め、孤独を深めていくだけです。これは、物質的な豊かさだけでは決して満たされない人間の心のありようを、鋭く抉り出していると言えるでしょう。
物語の終盤、片桐は日本への帰路につきます。彼の心の中には、逮捕されるかもしれないという恐怖と同時に、奇妙な開き直りの感情が芽生えています。「どうにでもなれ」という投げやりな態度は、彼が自らの罪と向き合うことを放棄したかのようにも見えます。この結末は、読者に対して明確な救いやカタルシスを与えるものではありません。むしろ、宙ぶらりんな不安感と、やるせない思いを残します。
しかし、この「救いのなさ」こそが、本作のリアリティなのかもしれません。現実の世界でも、問題が綺麗に解決したり、悪人が必ず罰せられたりするとは限りません。むしろ、曖昧な状況の中で、人々はそれぞれの折り合いをつけながら生きていくことの方が多いのではないでしょうか。「元職員」は、そんな現実の厳しさや不条理さを、容赦なく突きつけてくる作品なのです。
読者によっては、片桐の行動や心理に強い嫌悪感を抱くかもしれません。「なぜこんな愚かな行動を」「もっとまともな選択ができたはずだ」と。しかし、少し立ち止まって考えてみると、私たち自身の中にも、片桐と似たような弱さや自己欺瞞が潜んでいるのではないでしょうか。大きな不正ではないにしても、日常の中で小さな嘘をついたり、責任を回避しようとしたりすることは誰にでもあるはずです。
この物語は、そうした人間の普遍的な弱さを、極限的な状況に置かれた一人の男を通して描いていると言えます。そして、読者に対して「あなたは、本当に片桐を笑うことができるのか?」と問いかけてくるのです。その問いは、深く心に突き刺さります。
また、本作は実在の事件に着想を得ていると言われています。そのことを知ると、物語の持つリアリティがさらに増して感じられます。公金横領という犯罪は、決して遠い世界の出来事ではなく、私たちのすぐ隣で起こりうる問題なのかもしれない。そう考えると、片桐の転落していく様は、他人事とは思えなくなってきます。
吉田修一氏の筆致は、常に冷静で客観的です。彼は登場人物の感情を過度に煽るようなことはせず、淡々とその行動や心理を描写していきます。その乾いた文体が、かえって物語の持つ不気味さや緊張感を高めているように感じられます。読者は、まるでドキュメンタリーを見ているかのような感覚で、片桐の日常が崩壊していく様を目撃することになるのです。
「元職員」は、読む人を選ぶ作品かもしれません。エンターテイメントとしての楽しさや、感動を求める読者には、少し物足りないと感じるかもしれません。しかし、人間の心の深淵を覗き込みたい、あるいは社会の構造的な問題について考えたいという読者にとっては、非常に示唆に富んだ作品となるでしょう。
読み終えた後、私たちは「もし自分が片桐の立場だったらどうしただろうか」と考えずにはいられません。そして、日常の中に潜む小さな誘惑や、自己欺瞞の危険性について、改めて襟を正すことになるのではないでしょうか。それは、この物語が持つ、ある種の警鐘なのかもしれません。
まとめ
吉田修一氏の「元職員」は、公金横領という罪を犯した男の転落と、その心理を冷徹な筆致で描いた作品です。主人公の片桐は、決して同情できる人物ではありませんが、その弱さや自己欺瞞は、私たち自身の内面にも通じるものがあるかもしれません。
物語の舞台となるタイのバンコクの描写は秀逸で、主人公の心の空虚さや孤独感を効果的に際立たせています。登場人物たちは皆、どこか満たされない思いを抱えながら生きており、その姿は現代社会の縮図のようにも見えます。
この作品は、読者に爽快感やカタルシスを与えるものではありません。むしろ、重苦しさや不快感を伴う読後感をもたらすかもしれません。しかし、それこそが本作の持つ力であり、人間の本質や社会のあり方について深く考えさせられるきっかけを与えてくれます。
「元職員」は、単なる犯罪小説という枠には収まらない、人間の弱さと向き合うための物語と言えるでしょう。もしあなたが、日常に潜む危うさや、人間の心の複雑さに興味があるのなら、ぜひ手に取ってみることをお勧めします。きっと、忘れられない読書体験となるはずです。

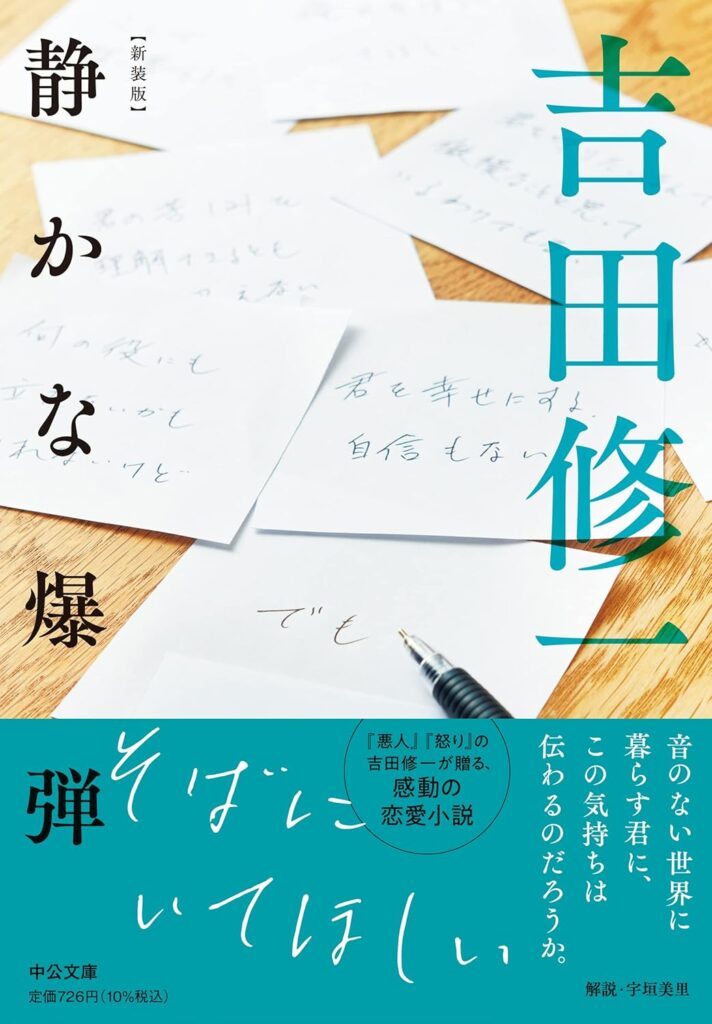
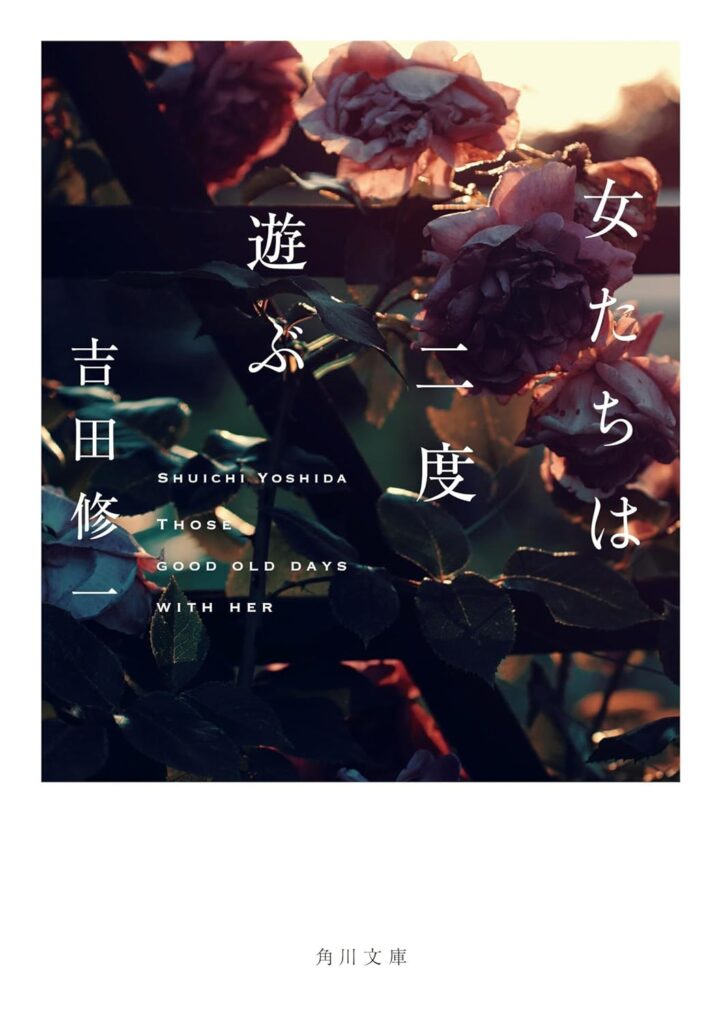
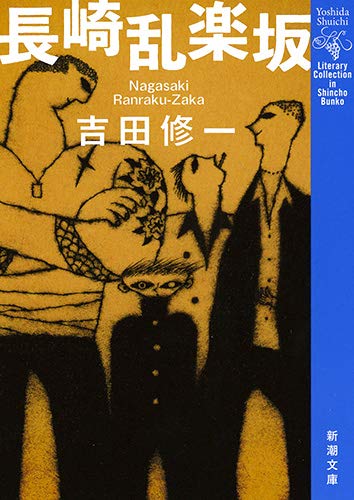
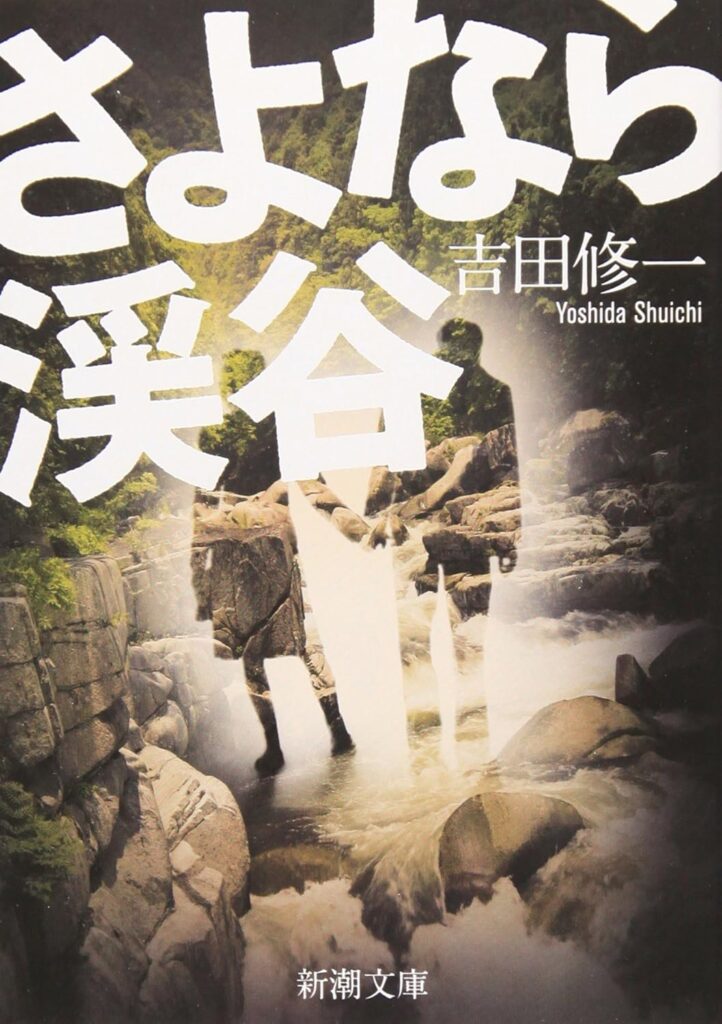
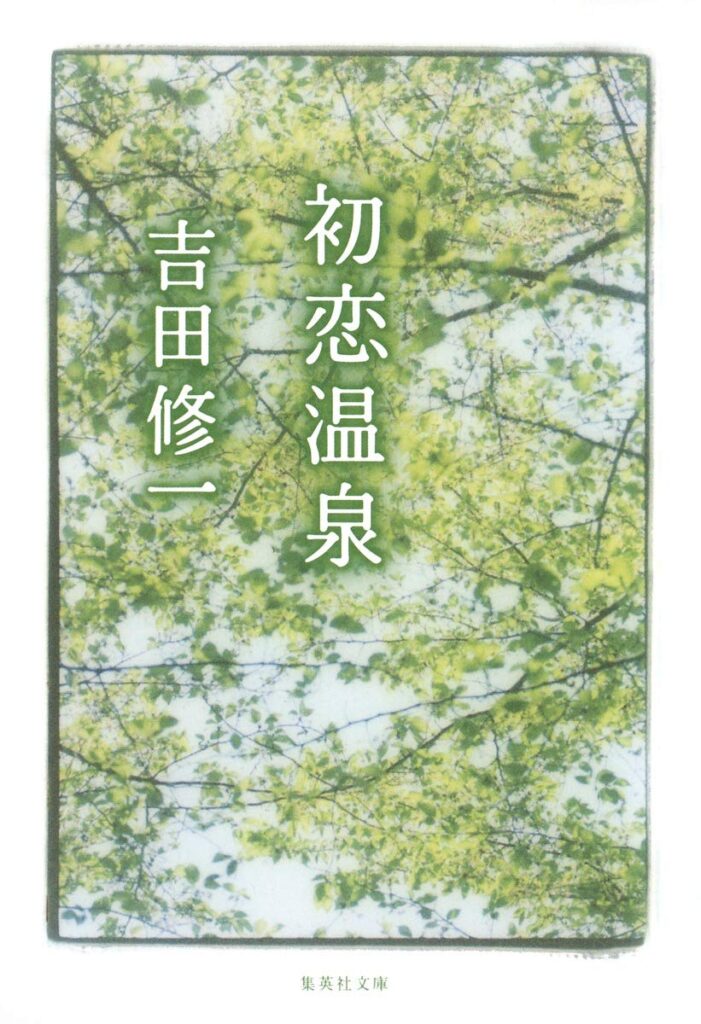
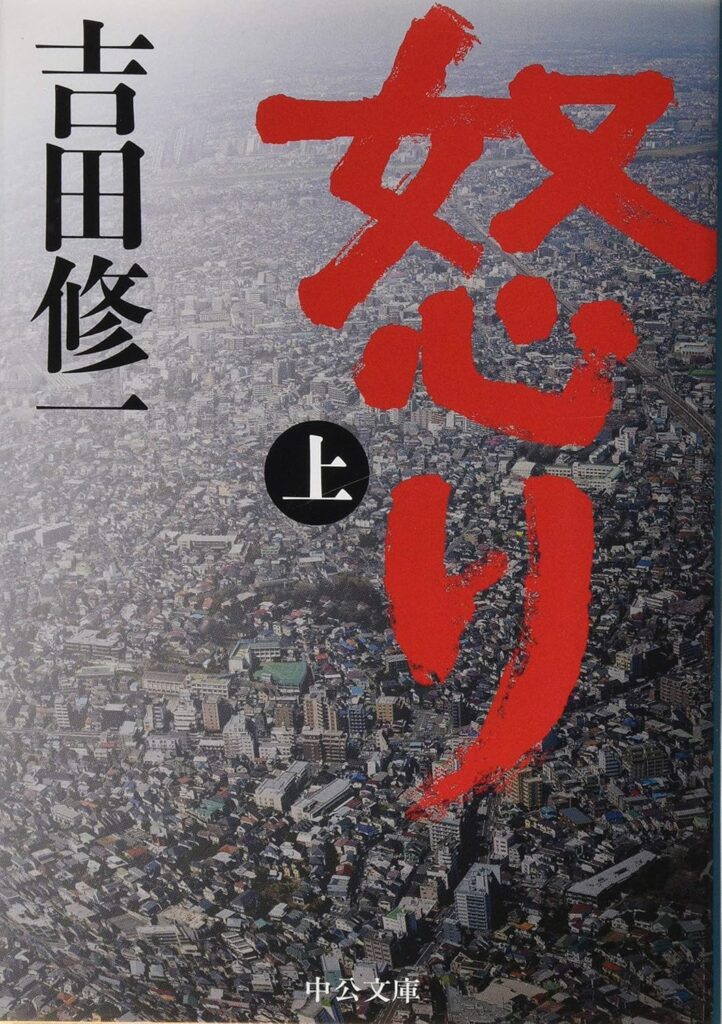
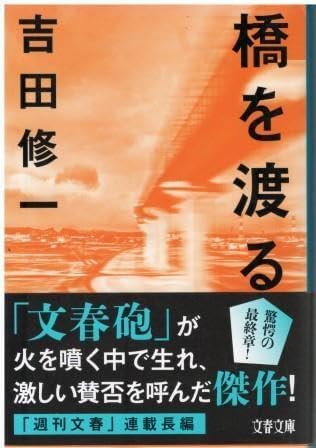
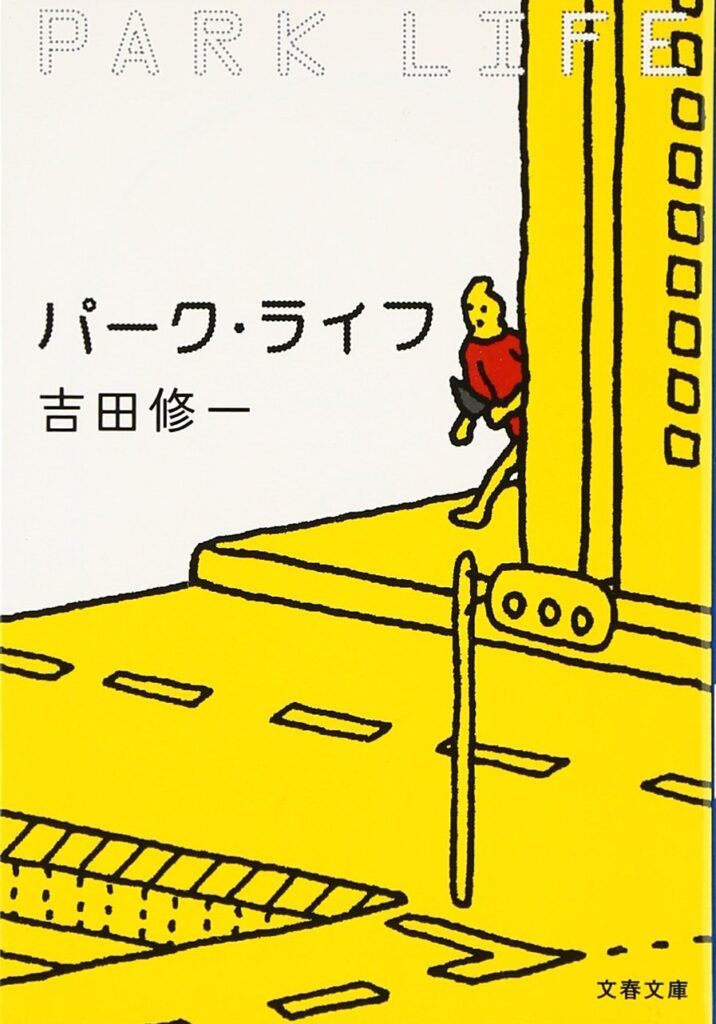
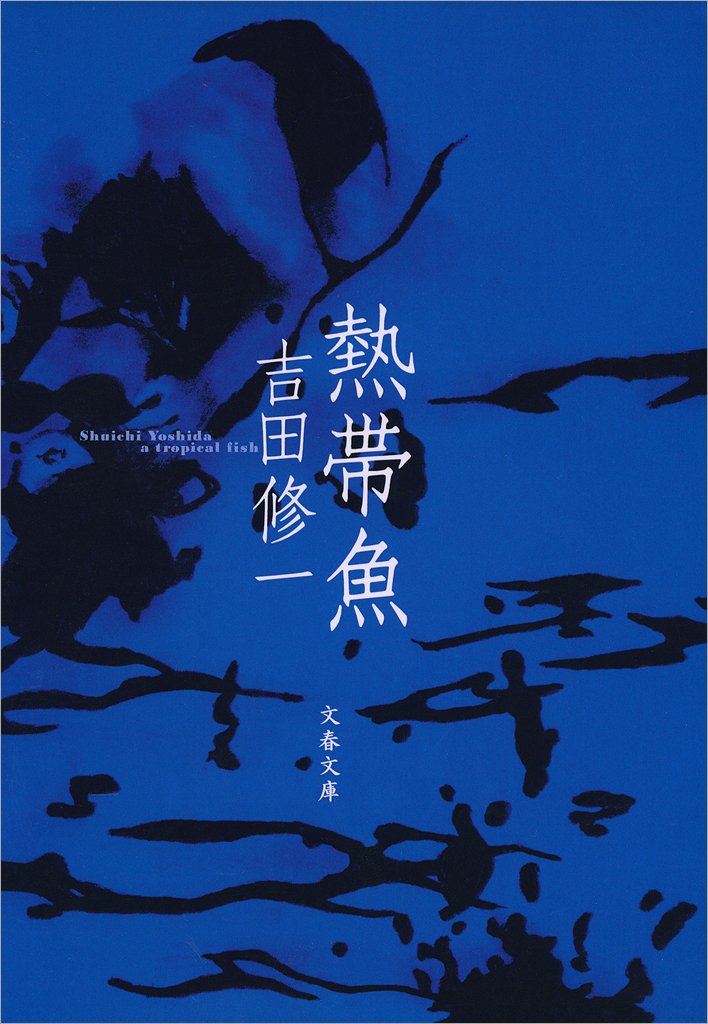
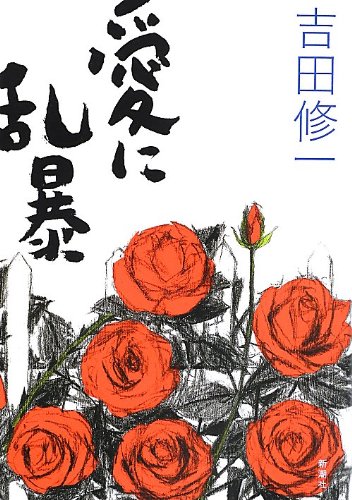
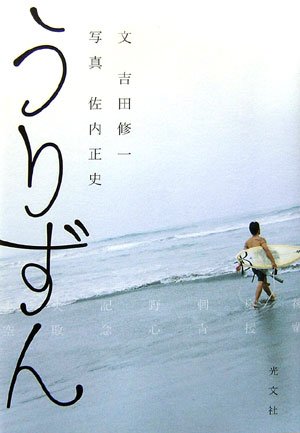
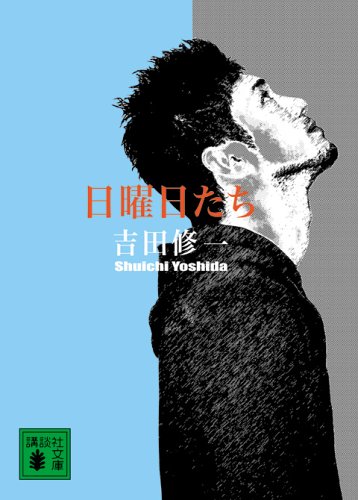
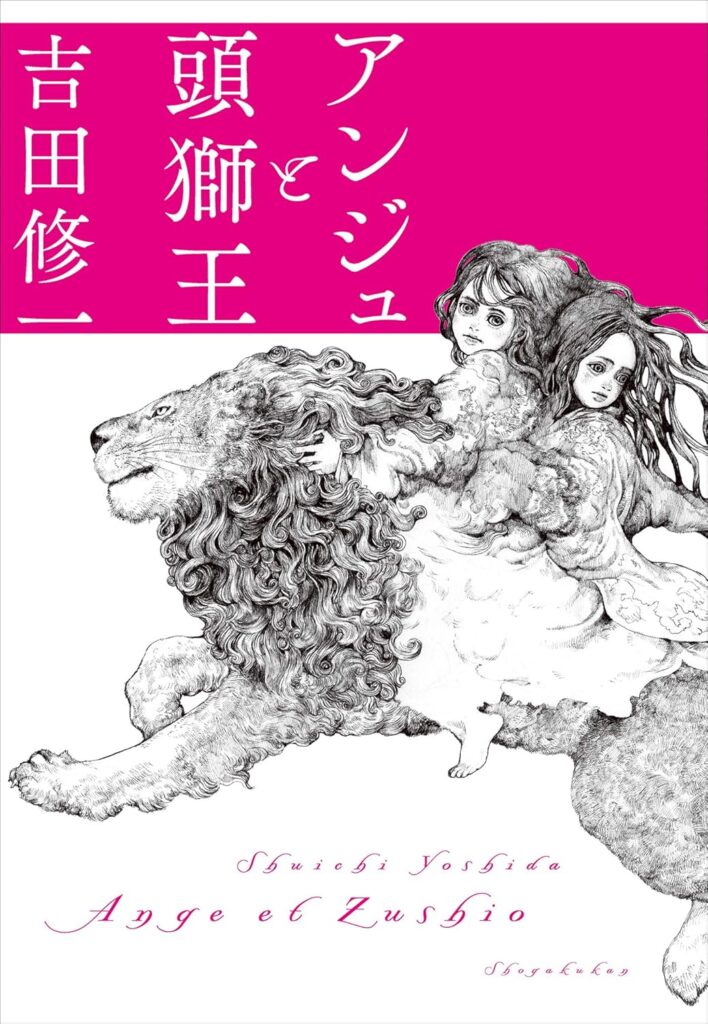
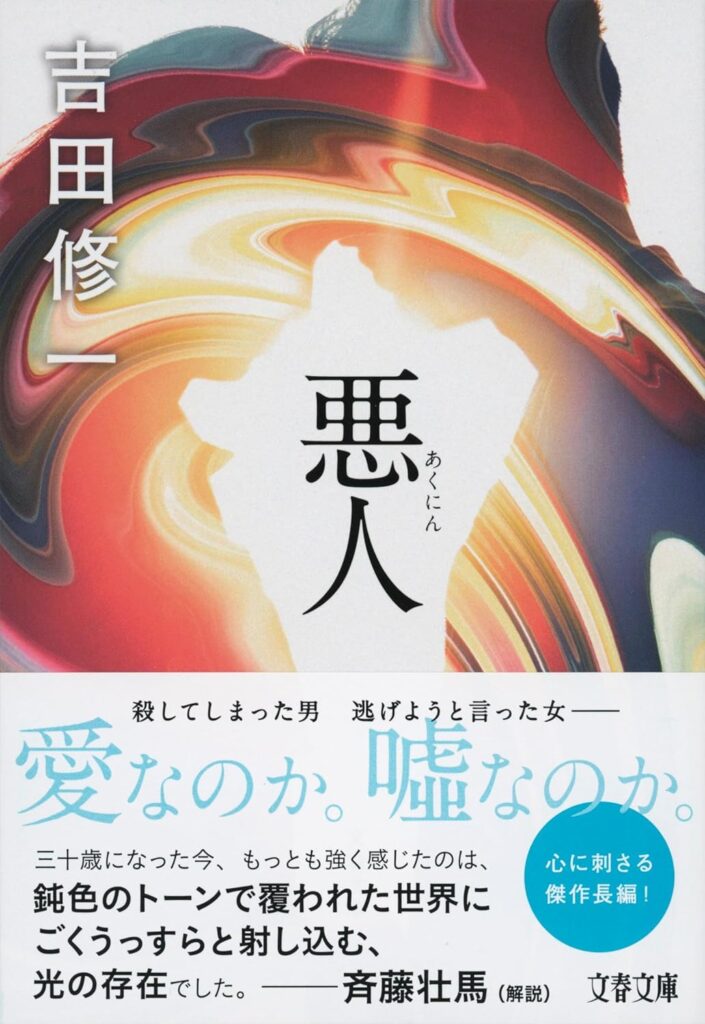
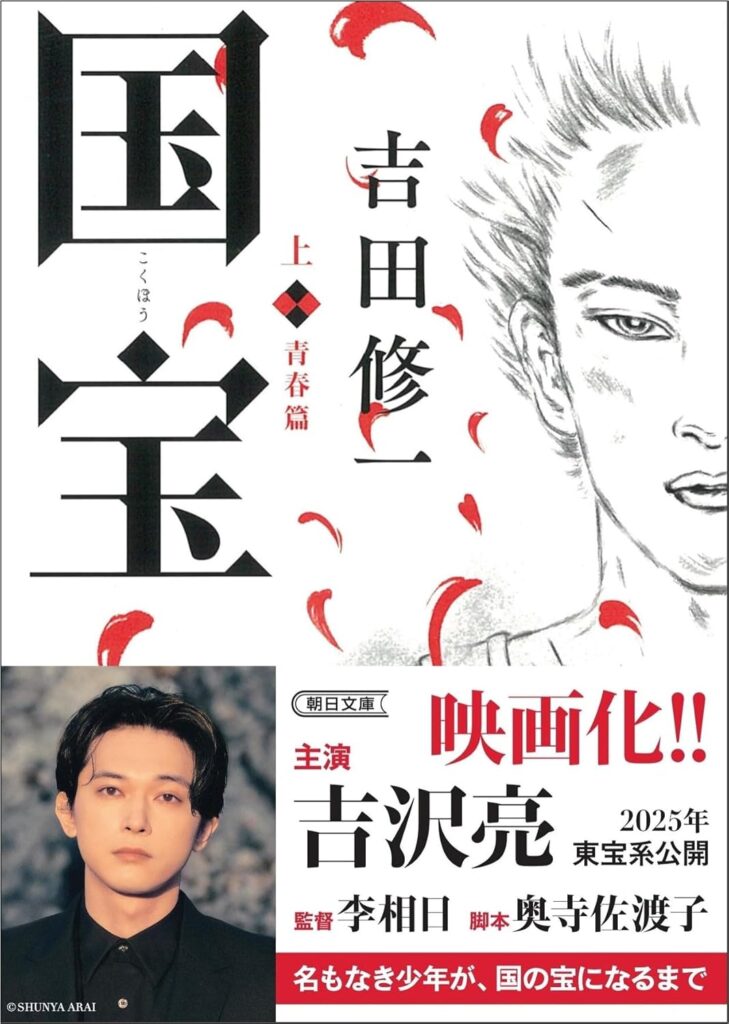
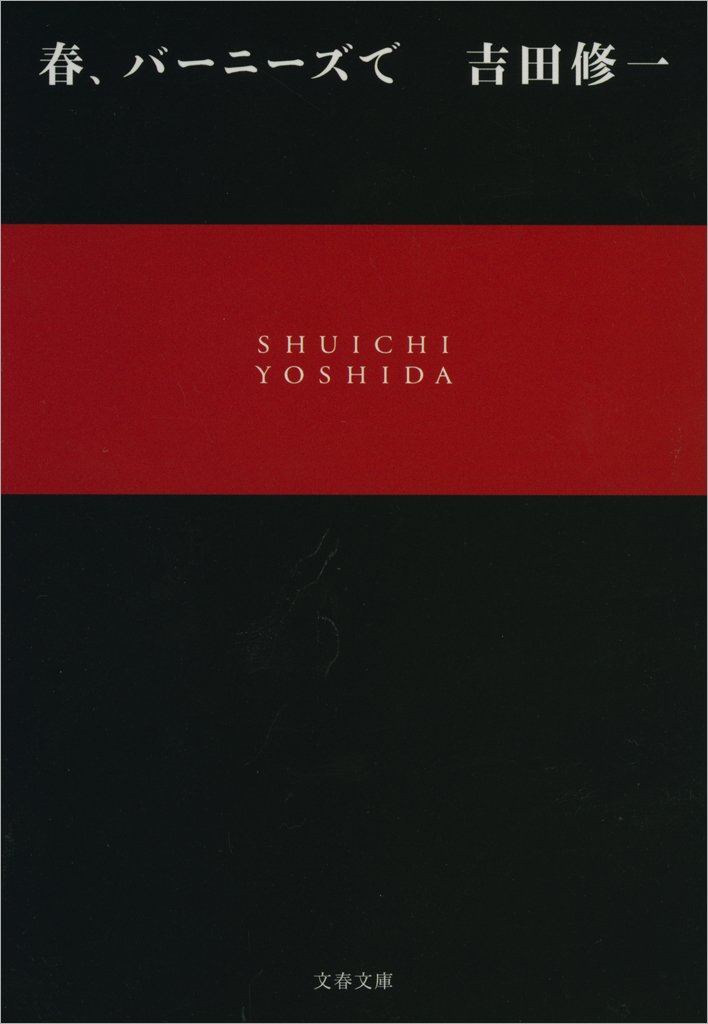
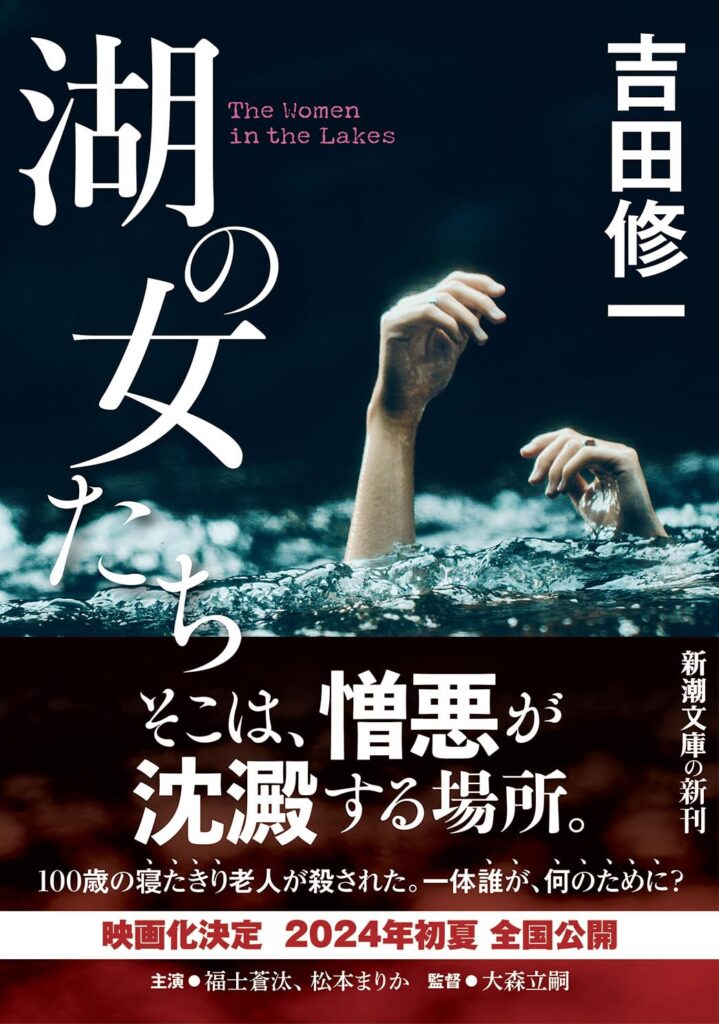
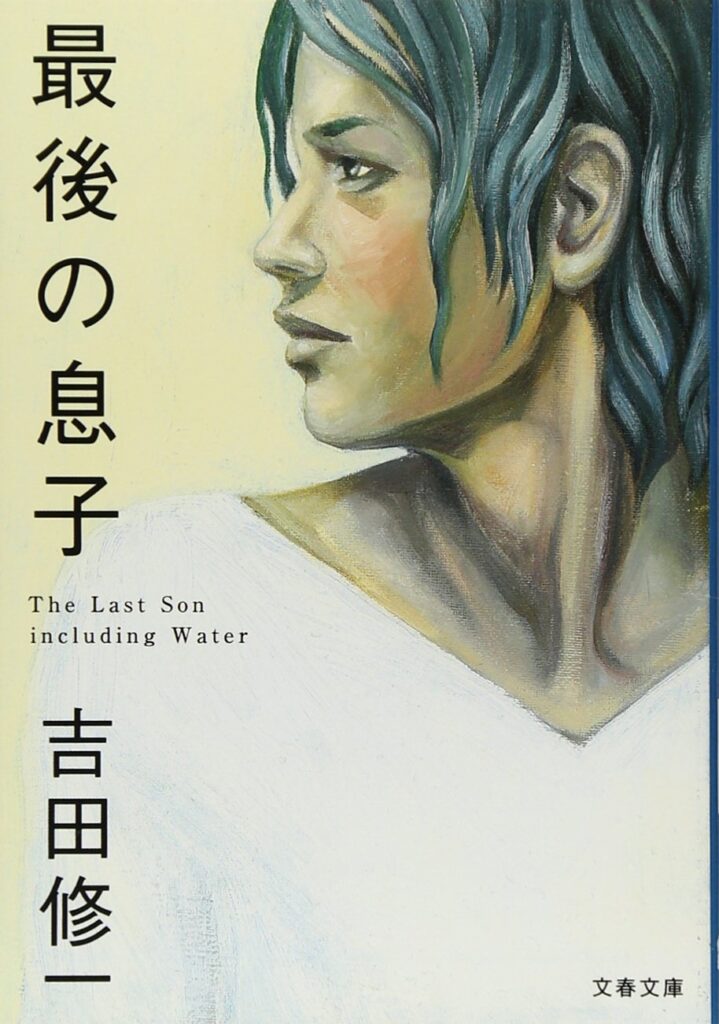
-728x1024.jpg)