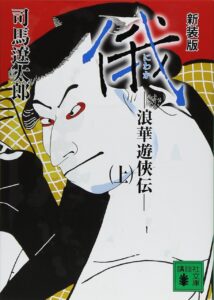 小説『俄 浪華遊侠伝』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。司馬遼太郎さんが描く、幕末の大坂を生きた一人の侠客の物語です。主人公は明石屋万吉という実在の人物で、その破天荒で波乱に満ちた生涯が描かれています。
小説『俄 浪華遊侠伝』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。司馬遼太郎さんが描く、幕末の大坂を生きた一人の侠客の物語です。主人公は明石屋万吉という実在の人物で、その破天荒で波乱に満ちた生涯が描かれています。
本作は、大坂という「町人の共和国」を舞台に、武士ではなく庶民の視点から幕末という激動の時代を見つめている点が特徴的です。万吉の生き様を通して、当時の大坂の空気や人々の暮らしぶり、そして時代の大きなうねりに翻弄されながらもたくましく生きる庶民の姿が生き生きと描かれています。
物語は万吉の少年時代から始まり、彼がどのようにして侠客としての道を歩むことになったのか、そして幕末の動乱期にどのように関わっていくのかが語られます。彼の行動は時に型破りで、危なっかしい場面も多いのですが、そこには彼なりの筋や「男伊達」があり、不思議と人を惹きつける魅力があります。
この記事では、そんな『俄 浪華遊侠伝』の物語の結末に触れつつ、その詳細な内容と、私が感じたこと、考えたことを詳しくお話ししていきたいと思います。司馬作品がお好きな方はもちろん、幕末の歴史や、力強く生きた人物の物語に興味がある方にも、ぜひ読んでいただきたい内容です。
小説「俄 浪華遊侠伝」のあらすじ
物語は天保年間、船場の商家で丁稚奉公をする11歳の万吉が、父の出奔を知るところから始まります。父は元隠密でしたが貧困に耐えかねて家族を捨て、残された母と妹は食べるものにも困る始末。万吉は家族を養う決意を固め、悪事を働いても家族に迷惑がかからぬよう、自ら無宿人となります。彼は露天神社で子供博奕の銭を奪い取り、初めての「稼ぎ」を得ますが、その代償にひどく殴られます。その痛みに耐えかねて泣いていたところを芸者の小左門に拾われ、彼の人生は一つの転機を迎えます。
その後、万吉は賭場荒らしを続け、稼いだ銭を母の元へ投げ込みますが、その行為が露見し、庄屋預かりの身となります。しかし、不思議なことに、その孝行ぶりが認められ、奉行所から表彰されるという経験もします。この経験は、彼の後の生き方に影響を与えたのかもしれません。
成長した万吉は15歳で極道屋として一本立ちし、その命知らずの気風で名を馳せます。ある時、米問屋から米相場を潰す依頼を受け、見事に成功させますが、奉行所に捕らえられ厳しい拷問を受けます。しかし、彼は決して口を割らず、その根性が認められ放免されると、米価高騰に苦しむ庶民から喝采を浴びるのでした。この出来事は、彼に「ひとかどの人間になった」という自覚を与えます。
25歳になった万吉は、町奉行・久須美祐雋から密命を受け、幕府隠密の救出に協力します。さらに翌年には、別の隠密探索にも協力し、密輸に関わった商人や与力の逮捕に貢献するなど、裏社会での信頼と実績を積み重ねていきます。彼の才覚と度胸は、次第に大きなうねりの中へと彼を導いていくことになります。
幕末の騒乱が激化する中、大坂の治安維持のため、小野藩は万吉に白羽の矢を立てます。万吉は士分に取り立てられ、配下の遊び人たちと共に警備隊を結成。しかし、活動資金は自腹であり、藩邸内で賭場を開くことで捻出するという、まさに破天荒な運営を行います。隊士たちは必ずしも勇敢ではありませんでしたが、万吉は惰弱な武士の姿も目の当たりにし、時代の終わりを予感します。
蛤御門の変で敗走した長州藩士が大坂へ逃れてくると、万吉は幕府の命令に背き、彼らを匿います。この行動が幕府に知られ、彼は裏切りによって新選組に引き渡されそうになりますが、辛くも脱出。その後も「往来安全」を信条とし、立場に関係なく困っている者を助け続けます。鳥羽・伏見の戦いでは幕府軍として従軍しますが敗走。維新後、他の親方衆が処刑される中、かつて助けた長州藩士・遠藤謹介によって命を救われます。万吉の人生は、まさに予測不能な「俄」のように展開していきます。
維新後も万吉の生き方は変わりません。相場で財を成しますが、それを溜め込むことなく、消防組の設立や授産施設の運営といった慈善事業に注ぎ込みます。その結果、莫大な借金を抱え、明治期の選挙干渉事件に利用されて破産しますが、本人は満足していました。「男伊達」を貫き、波乱万丈の人生を送った万吉は、大正時代に90歳近い高齢で、「ほなら、往てくるでえ」と、まるで汽車に乗るかのように陽気にこの世を去っていきました。
小説「俄 浪華遊侠伝」の長文感想(ネタバレあり)
司馬遼太郎さんの『俄 浪華遊侠伝』、読了いたしました。幕末から明治、大正を生きた大坂の侠客、明石屋万吉の生涯を描いたこの物語、非常に読み応えがありました。ただ、正直に申し上げますと、私の評価としては星2つ、点数でいえば69点といったところでしょうか。決してつまらなかったわけではありません。むしろ、万吉の破天荒な生き様や、当時の大坂の活気ある描写には引き込まれました。しかし、他の司馬作品で感じるような、心を鷲掴みにされるような熱さや、深い感動には、あと一歩届かなかった、というのが率直な気持ちです。
物語の始まり、11歳の万吉が父の出奔によって困窮する母と妹を救うため、無宿人となり賭場荒らしをする場面は、彼の後の人生を決定づける強烈な出来事です。わずか11歳で「俺が銭を稼ぐ」と覚悟を決め、実際に子供博奕から銭を奪い取る。その行動力と、家族を巻き込まないために自ら「悪」を引き受ける姿勢には、彼の持つ独立心と、ある種の潔さが表れています。しかし、同時に、その方法があまりにも短絡的で、危うさを感じずにはいられません。この「行き当たりばったり」とも言える性質が、彼の生涯を通じて貫かれる特徴であり、魅力でもあり、同時に危うさでもあるように感じました。
彼を拾い、姉のように面倒を見る芸者・小左門の存在は、荒んだ万吉の心にわずかな光を与えたのかもしれません。彼女との関係は、単なる男女の仲を超えた、不思議な絆で結ばれているように描かれています。彼女が後に町奉行を紹介するなど、万吉の人生の節目で重要な役割を果たす存在となる点も興味深いところです。しかし、二人の関係性の描写が、やや表層的に留まっているような印象も受けました。もう少し深く掘り下げてほしかった、とも思います。
青年期の万吉が、米相場への殴り込みで名を上げ、拷問に耐え抜く場面は、彼の「男伊達」が形成される重要なエピソードです。「いつでも死ねるのが商売」という彼の信条は、この経験によってさらに強固なものになったのでしょう。庶民からの喝采を浴び、「おれもいっぱしの人間になった」と感じる万吉の姿には、承認欲求のようなものも垣間見えます。彼が求めるのは金銭や権力ではなく、あくまで「男として認められること」なのだと感じさせられます。この純粋さとも言える動機が、彼を様々な騒動へと駆り立てていく原動力なのかもしれません。
幕末の動乱期、小野藩に請われて警備隊長となる展開は、物語の中でも特に異色で面白い部分です。士分に取り立てられながらも、活動資金のために公認の賭場を開くという発想は、まさに万吉ならでは。武士になりたいわけではなく、あくまで「侠客」としての自分の流儀を貫こうとする姿勢がうかがえます。しかし、いざとなると役に立たない子分たちや、惰弱な武士たちの姿を目の当たりにし、時代の変化を肌で感じていく様子は、単なる痛快な物語にとどまらない深みを与えています。
蛤御門の変の後、長州藩士を匿う場面は、万吉の人間性を示す重要なポイントです。幕府の命令に背き、危険を冒してまで「気の毒なやつ」を助ける。彼の行動原理は、政治的な立場やイデオロギーではなく、目の前の人間に対する情や、彼自身の「往来安全」というシンプルな正義感に基づいていることがわかります。「天下国家は語らず、他人からすれば『しょむないもん』のために全力を尽くす」という描写は、まさに彼の本質を表していると言えるでしょう。この行動が、後に彼の命を救うことになる展開は、因果応報を感じさせます。
鳥羽・伏見の戦いでの敗走、そして維新後の混乱期を生き抜く姿は、彼の生命力の強さを物語っています。他の親方衆が次々と処刑される中、彼だけが生き延びる。それは運の良さだけではなく、彼がこれまで培ってきた人との繋がり、特に遠藤謹介との縁によるものです。彼の「男伊達」が、結果的に彼自身を救ったとも言えます。しかし、一方で、時代の大きな流れには逆らえず、旧体制側についたことによる危うさも常に付きまといます。このあたりの描写は、歴史の非情さを感じさせます。
維新後、万吉は一時、相場で大きな財を成します。しかし、彼はその金を決して自分のために使おうとはしません。消防組の設立や、授産施設の運営といった慈善事業に惜しみなく注ぎ込みます。これは、彼なりの社会への貢献であり、「心映えを汚さない」ための行動だったのかもしれません。「俺でこそワルでも食えるが尋常な奴はこうはいかん」という彼の言葉には、自身の生き方への自負と、同時にある種の諦観のようなものも感じられます。しかし、その結果として莫大な借金を抱え、最後は選挙干渉に利用されて破産してしまう結末は、どこか物悲しさを感じさせます。彼が貫いた「男伊達」は、時代の変化の中で必ずしも報われるものではなかったのかもしれません。
登場人物たちも個性的です。万吉を支え続ける女房の小春。「亀山のちょん兵衛はん」と評する彼女の言葉は、万吉の落ち着きのない、しかしどこか憎めない性格を的確に表しています。子分の軽口屋との掛け合いは、物語に軽妙な味わいを加えています。難波の福とのライバル関係や、久須美駿河守、遠藤謹介、桂小五郎、大石鍬次郎といった歴史上の人物との関わりも、物語に厚みを与えています。特に、磯野小右衛門や渡辺昇といった人物との出会いが、万吉の後半生に大きな影響を与える様子は、人の縁の不思議さを感じさせます。
司馬さんが、ご自身の祖父が万吉の建てた家で餅屋を営んでいたという個人的な繋がりから、この作品に親しみを込めて書いた、という背景を知ると、また違った味わいが出てきます。大坂という土地への愛着、そして庶民の視点から歴史を描こうとする姿勢は、他の司馬作品にも通じるものがあります。タイトルの「俄」が示すように、万吉の人生は即興的で、滑稽で、しかしどこか切実な一場の芝居のようでした。「わが一生は一場の俄のようなものだった」という万吉自身の述懐は、彼の生き様を象徴しています。
では、なぜ私の評価が少し厳しめなのか。それは、万吉という主人公の人物像に、感情移入しきれなかった部分があるからです。彼の行動原理である「男伊達」は、魅力的ではありますが、時としてあまりにも刹那的で、深みに欠けるように感じられる瞬間がありました。彼の行動の結果が、必ずしも良い方向に向かうとは限らず、周囲を巻き込んでしまう危うさも常に感じられます。もちろん、それが人間臭さであり、リアリティなのかもしれませんが、他の司馬作品の主人公たち、例えば坂本龍馬や秋山兄弟のような、より大きな志やビジョンを持った人物と比較すると、やや物足りなさを感じてしまうのです。
引用されている言葉、「男子功名」を好む一方で、「他人の不幸に泣く」ことを否定し、「長い言葉をしゃべれない」万吉。彼の内面は、もっと複雑だったのかもしれませんが、その描写が少し足りないように感じました。「見通し」についての磯野小右衛門の言葉、「情緒(こころ)を殺して非人間にしてはじめてできる」という指摘は、感情や情に流されやすい万吉とは対照的で、印象に残りました。万吉は、良くも悪くも「人間的」すぎたのかもしれません。
また、物語の展開が、ややエピソードの羅列のように感じられる部分もありました。一つ一つの出来事は面白いのですが、それらが大きな流れとして、万吉の成長や内面の変化にどう繋がっていくのかが、少し見えにくいと感じる箇所もありました。もちろん、彼の人生そのものが「俄」のようなものだった、と言われればそれまでなのですが、読者としては、もう少し整理された構成や、テーマ性の明確化を期待してしまう部分もありました。
とはいえ、この作品が持つ魅力も確かです。幕末から明治にかけての大坂の雰囲気をこれほど生き生きと描いた作品は少ないでしょう。侠客という、歴史の表舞台にはあまり登場しない人物を通して、時代の変化を庶民の目線で追体験できるのは、貴重な読書体験でした。万吉の、損得を考えず、ただ己の信じる「男伊達」のために行動する姿は、現代社会に生きる私たちにとっても、何か考えさせられるものがあります。彼の生き方は、決して模範的なものではありませんが、その潔さや生命力には、惹きつけられるものがありました。
最後の場面、90歳近くになり、「ほなら、往てくるでえ」と陽気に世を去る万吉の姿は、彼の人生を象徴しているようで印象的です。波乱万丈、毀誉褒貶の激しい人生でしたが、彼自身は満足して「最後の俄」を演じきったのかもしれません。そう思うと、読後感は決して悪いものではありませんでした。
まとめ
司馬遼太郎さんの『俄 浪華遊侠伝』は、幕末から明治、大正という激動の時代を、大坂の侠客・明石屋万吉というユニークな主人公を通して描いた作品です。彼の人生は、まさにタイトルの「俄」が示すように、予測不可能で、即興的、そして波乱に満ちたものでした。
物語は、万吉の少年時代の困窮から始まり、彼が侠客として名を成し、幕末の動乱に巻き込まれ、そして維新後の新しい時代を生きていく姿を追っていきます。彼の行動原理は一貫して「男伊達」。損得を考えず、時に危うい行動を取りながらも、彼なりの筋を通そうとする生き様が描かれています。大坂という町人文化が花開いた土地を舞台に、庶民の視点から歴史が語られる点も、本作の大きな魅力と言えるでしょう。
正直なところ、主人公の行動原理に共感しきれない部分や、物語の展開にやや物足りなさを感じる点もありました。しかし、当時の大坂の活気ある描写や、万吉の破天荒ながらも憎めないキャラクター、そして彼の人生を取り巻く個性的な人々との関わりは、読んでいて非常に興味深いものでした。特に、時代の大きな変化に翻弄されながらも、自分自身の流儀を貫き通そうとした万吉の姿は、強く印象に残ります。
他の司馬作品ほどの熱狂的な感動は得られなかったものの、一人の人間の破天荒な生き様と、幕末から明治にかけての大坂の世相を知る上で、非常に面白い作品であったことは間違いありません。万吉の人生という「一場の俄」を、ぜひ覗いてみてはいかがでしょうか。






































