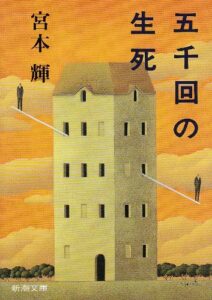 小説「五千回の生死」のあらすじを内容に触れつつ紹介します。長文の受け止め方も書いていますのでどうぞ。
小説「五千回の生死」のあらすじを内容に触れつつ紹介します。長文の受け止め方も書いていますのでどうぞ。
宮本輝さんの作品には、人生の深淵を覗き込むような、それでいてどこか温かい眼差しを感じます。「五千回の生死」は、1981年から1987年にかけて書かれた九つの短編が収められた一冊です。作者自身があとがきで語っているように、長編小説に取り組む合間に生まれた、いわば精神の「一輪差し」のような作品群が集められています。
それぞれの物語は、派手な事件が起こるわけではありません。日常の中でふと出会う出来事や、心に引っかかる人々との交流が、淡々とした、しかし確かな筆致で描かれています。表題作をはじめ、どの作品にも共通して流れているのは、生と死という重いテーマです。しかし、それが暗く重苦しいだけでないのが、宮本輝さんの作品のすごいところだと感じます。
この記事では、そんな短編集「五千回の生死」の中から、特に印象に残った作品の物語の筋とその結末、そして私が感じたこと、考えたことを詳しくお伝えしたいと思います。これから読もうと思っている方、あるいはすでに読まれた方にも、何か新しい発見があれば嬉しいです。
小説「五千回の生死」のあらすじ
物語の中心となるのは、表題作「五千回の生死」です。主人公は、亡くなった父親が残した莫大な借金の返済に追われる苦学生の“俺”。学費もままならず、生活は困窮を極めています。彼は、父の形見である年代物のライターを、裕福な友人である北村に高く買い取ってもらおうと考え、彼の家を訪ねます。しかし、期待は裏切られ、北村は家族旅行で不在。おまけに、なけなしの金も使い果たし、帰りの電車賃さえなくなってしまいます。
途方に暮れた“俺”は、真夜中の国道を、自宅まで何時間もかけて歩いて帰ることを余儀なくされます。疲労と絶望感に打ちひしがれながら歩いていると、後ろから自転車に乗った奇妙な男に声をかけられます。「乗っていけへんか?」男は馴れ馴れしく誘いますが、“俺”は見ず知らずの、しかもどこか異様な雰囲気を持つ男を警戒し、一度は断ります。
しかし、男は諦めません。しつこく後をついてきては、「乗っていき」と繰り返します。その屈託のない笑顔に、疲れ切っていた“俺”は抗う気力も失い、ついには男の自転車の荷台に乗せられてしまいます。走り出した自転車の上で、男は唐突にこう語り始めます。「俺、一日に五千回ぐらい、死にとうなったり、生きとうなったりするんや」。
男は続けます。「兄貴も病院の医者も、それがお前の病気やて言いよるんやけど、俺はなんぼ考えても、病気とは思われへん。みんなそうと違うんか? お前はどうや?」。最初は男を狂人ではないかと疑っていた“俺”ですが、男の「お前かて、死にたなったり、生きたなったりするやろ? そんな事思うの人間だけやろ? 俺が正常な人間やという証拠やないか」という言葉に、どこか心を揺さぶられます。
疲れ果て、半ば投げやりになった“俺”は、「もし死にたなったら教えてくれよ。そしたら俺は荷台から飛び降りるからな」と男に告げます。すると男は、「死にとうなった!」「生きとうなった!」と叫びながら、自転車を走らせます。そのたびに“俺”は荷台から飛び降りたり、再び乗ったりを繰り返す羽目に。そんな奇妙な道行のうちに、“俺”は次第に男に対して不思議な親近感を覚えていきます。男はさらに叫びます。「死んでも死んでも生まれてくるんや。それさえ知っとったらこの世の中、なんにも怖いもんなんかあるかいな」。
この短編集には、他にも印象的な作品が収められています。「トマトの話」もまた、父親の借金に苦しむ大学生が主人公です。道路工事現場のアルバイト中に、飯場で死期の迫った痩せた男と出会います。男に頼まれてトマトを買いに行き、そして男がトマトを胸に抱き涙する姿を目撃します。男は手紙の投函を託した直後に血を吐いて亡くなります。男の素性も、トマトに込められた思いも、手紙の宛先も謎のままですが、主人公の心に深く刻まれる出来事となります。これらの物語は、登場人物たちが死と隣り合わせの状況や、他者の死に触れることで、自身の生を見つめ直すきっかけを得る姿を描いています。
小説「五千回の生死」の長文感想(ネタバレあり)
宮本輝さんの短編集「五千回の生死」を読み終えて、私の心には深く、そして静かな波紋が広がっています。一冊に収められた九つの物語は、それぞれが独立した世界を持ちながら、どこか通底する響き合いを感じさせます。それはおそらく、どの物語にも人間の「生」と「死」という、避けては通れない根源的なテーマが色濃く影を落としているからでしょう。
まず、表題作である「五千回の生死」について語らないわけにはいきません。このタイトル自体が、読者の心を強く掴みますよね。日常の中で、私たちはどれほど「生きたい」「死にたい」という両極端な感情の間を揺れ動いているでしょうか。もちろん、作中の男のように「一日に五千回」というのは極端な表現かもしれませんが、程度の差こそあれ、誰もが経験する心の振幅ではないかと思うのです。
主人公の“俺”は、まさに絶望の淵にいました。父親が遺した借金という重荷、友人への最後の頼みの綱も断たれ、真夜中の国道を当てもなく歩くしかない状況。彼の心は、おそらく「死にたい」という思いに大きく傾いていたはずです。そんな彼の前に現れたのが、あの奇妙な男でした。最初は警戒し、狂人ではないかと疑っていた“俺”が、男の言葉と行動に触れるうちに、徐々に心を開いていく過程が非常に巧みに描かれています。
男の語る「一日に五千回ぐらい、死にとうなったり、生きとうなったりするんや」という言葉。これは単なる狂人の戯言なのでしょうか。それとも、人間の、いや生きとし生けるものの本質を突いた言葉なのでしょうか。男は「病気とは思われへん」「みんなそうと違うんか?」と問いかけます。この問いは、“俺”だけでなく、私たち読者にも向けられているように感じます。私たちは、常に揺れ動き、矛盾を抱えながら生きている存在なのではないでしょうか。
自転車の荷台での奇妙なやり取りは、この物語の白眉だと思います。「死にとうなった!」「生きとうなった!」という男の叫びに合わせて、飛び降りたり乗ったりを繰り返す“俺”。傍から見れば滑稽かもしれませんが、この反復運動の中に、生と死の絶え間ない循環、寄せては返す波のような生命の営みが象徴されているように思えてなりません。疲れ果てていたはずの“俺”が、この行為を通して、不思議な活力を取り戻していくように見えるのです。
そして、男が叫ぶ「死んでも死んでも生まれてくるんや。それさえ知っとったらこの世の中、なんにも怖いもんなんかあるかいな」という言葉。これは、絶望的な状況にある“俺”にとって、一条の光となったのではないでしょうか。死は終わりではない、生へと続く循環の一部なのだと。そう捉えることができれば、目の前の困難も乗り越えられるかもしれない。そんな力強いメッセージが込められているように感じました。この男は、世間の常識から見れば「愚者」かもしれませんが、“俺”にとっては、真理を突く「聖者」のような存在だったのかもしれません。
この物語が、大阪弁で語られていることも非常に重要です。標準語では表現しきれないであろう、登場人物たちの生々しい感情や息遣いが、大阪弁を通してダイレクトに伝わってきます。特に、男の言葉には、荒削りながらも妙な説得力があり、読者の心に深く突き刺さります。言葉の持つ力が、物語の世界をよりリアルに、より深くしていると感じました。
物語の結末、“俺”が男に父の形見のライターを渡す場面は、非常に印象的です。それは単なる物々交換ではなく、“俺”が過去のしがらみから解放され、新たな一歩を踏み出すための、ある種の儀式のように見えました。男という触媒を通して、絶望から希望へと心を転換させることができた“俺”。読み終えた後、私の心にも、まるで小さな火が灯ったような、ほのかな温かさが残りました。寒々しい夜道が、いつしか再生への道筋に変わっていたのです。
次に、「トマトの話」について触れたいと思います。こちらも「五千回の生死」と同じく、父親の借金に苦しむ大学生が主人公です。彼がアルバイト先の飯場で出会う、死を目前にした痩せた男。この男の存在が、物語に静謐ながらも強烈な印象を与えます。氏素性もわからず、ただ静かに死を待つ男。彼がなぜ、主人公にトマトを頼んだのか。そして、そのトマトを胸に抱き、涙を流したのか。
結局、その理由は最後まで明かされません。男が託した手紙も、宛先が不明瞭で投函できたのかどうかも定かではありません。しかし、この「わからなさ」こそが、この物語の深みなのかもしれません。トマトに込められた男の過去、故郷への思い、あるいは誰かへの愛情。それは読者の想像に委ねられています。ただ一つ確かなのは、死にゆく男の最期のささやかな願いと、それを見届けた主人公の心に刻まれた記憶です。
この物語を読むと、人の死というのは、たとえ見ず知らずの他人のものであっても、決して無関係ではないのだと感じさせられます。主人公は、男の死を通して、自身の生や、これから歩むであろう人生について、深く考えさせられたのではないでしょうか。トマトという鮮やかな色彩を持つ果実が、迫りくる死の翳りの中で、逆に生の儚さや愛おしさを際立たせているように感じました。非常に切なく、胸に迫る物語です。
さらに、参考にした文章でも言及されていた「眉墨」も忘れられません。思いもよらない母の病に直面し、内心の動揺を隠しながら気丈に振る舞う主人公。その姿は痛々しくもありますが、同時に人間の持つ強さをも感じさせます。そして、タイトルにもなっている「眉墨」。それは、女性の化粧道具の中でも決して目立つものではありませんが、顔の印象を決め、その人の意志や品格を表す重要なアイテムです。
病に侵されながらも、最後まで女性としての、人間としての矜持を保とうとする母親の姿が、「眉墨」という小道具を通して見事に描き出されています。そこには、作者の女性に対する深い洞察と敬意が感じられます。派手な出来事は何一つ起こりませんが、静かな筆致の中に、人間の尊厳や、親子の間の言葉にならない情愛が凝縮されており、深い感動を覚えました。この作品を読んで、宮本輝さんという作家の力量を改めて感じ入りました。
この短編集全体を通して流れる「生と死」のテーマは、決して暗く陰鬱なだけではありません。むしろ、死を意識するからこそ、生の輝きや尊さが際立ってくる。登場人物たちは、多くの場合、貧困や病、孤独といった厳しい現実に直面しています。しかし、そんな彼らが、他者とのささやかな交流や、ふとした出来事を通して、生きる力や希望の欠片を見出していく姿が描かれています。
宮本輝さんの文章は、時に淡々と、抑制的に感じられることもありますが、その行間には豊かな情景や、登場人物たちの微細な心の揺れが満ちています。参考にした文章の中には「作者本人の顔が透けて見えてくるように感じた」という感想もありましたが、私自身は、むしろ作者が良い意味で物語と距離を保ち、登場人物たちを客観的に、しかし温かい眼差しで見つめているように感じました。だからこそ、描かれる世界に普遍性が生まれ、読者は自身の経験や感情を重ね合わせることができるのではないでしょうか。
この「五千回の生死」という短編集は、人生に迷ったり、落ち込んだりしている時に読むと、特に心に響くかもしれません。絶望の中に希望を見出すこと。死と隣り合わせだからこそ感じられる生の輝き。そして、どんな状況にあっても人は生きていけるのだということ。そんな、静かだけれども力強いメッセージを受け取ったように思います。読後、しばらくの間、物語の余韻に浸り、登場人物たちのその後の人生に思いを馳せずにはいられませんでした。派手さはありませんが、心の奥深くに染み入る、味わい深い作品集であると、私は強く感じています。
まとめ
宮本輝さんの短編集「五千回の生死」は、日常に潜む生と死のドラマを、静かな筆致で描き出した珠玉の作品集です。表題作「五千回の生死」では、借金に苦しむ主人公が、夜道で出会った奇妙な男との交流を通して、絶望から再生へのきっかけを掴む姿が印象的に描かれています。
男の語る「一日に五千回、死にとうなったり、生きとうなったりする」という言葉や、「死んでも死んでも生まれてくる」という叫びは、読者の心にも深く響き、生きることの意味を問いかけてきます。大阪弁で語られる会話が、物語にリアリティと温かみを与えています。
他にも、死にゆく男とトマトを巡る切ない交流を描いた「トマトの話」や、母の病を通して人間の尊厳を描いた「眉墨」など、心に残る物語が収録されています。どの作品も、人生の困難や哀しみを描きながらも、決して希望を失わせない、宮本輝さんならではの温かい眼差しが感じられます。
派手な展開はありませんが、読後には静かな感動と、生きる勇気を与えてくれるような深い余韻が残ります。人生について考えさせられる、味わい深い短編集として、多くの方におすすめしたい一冊です。

















































