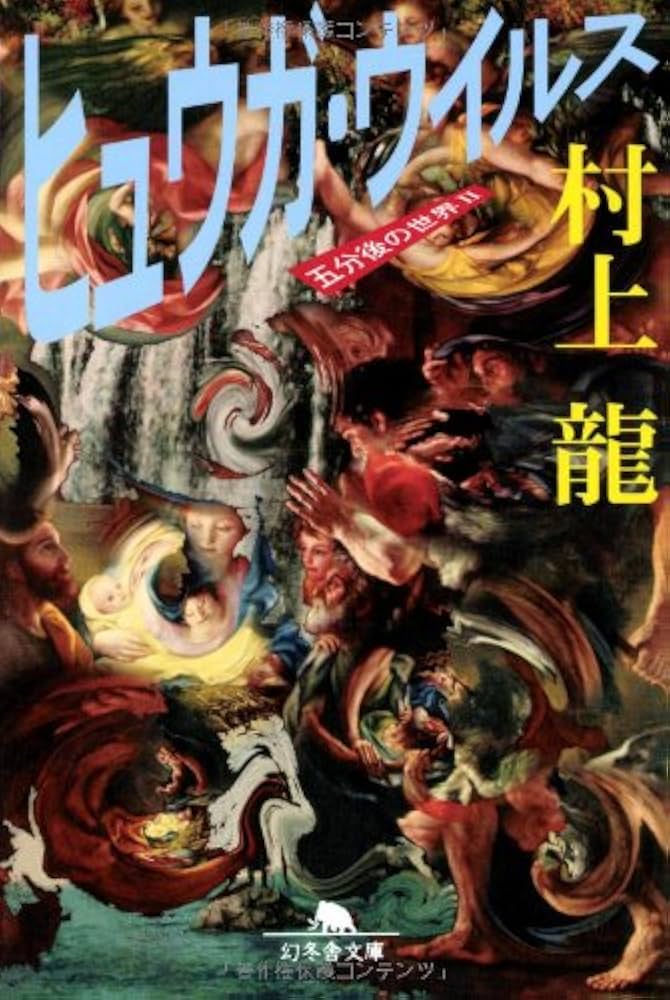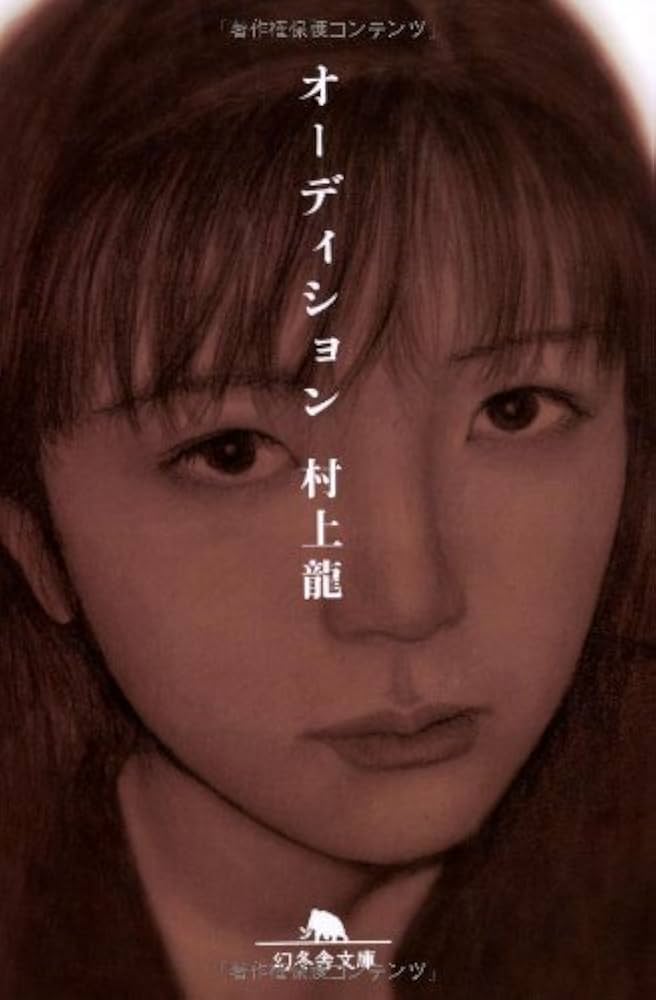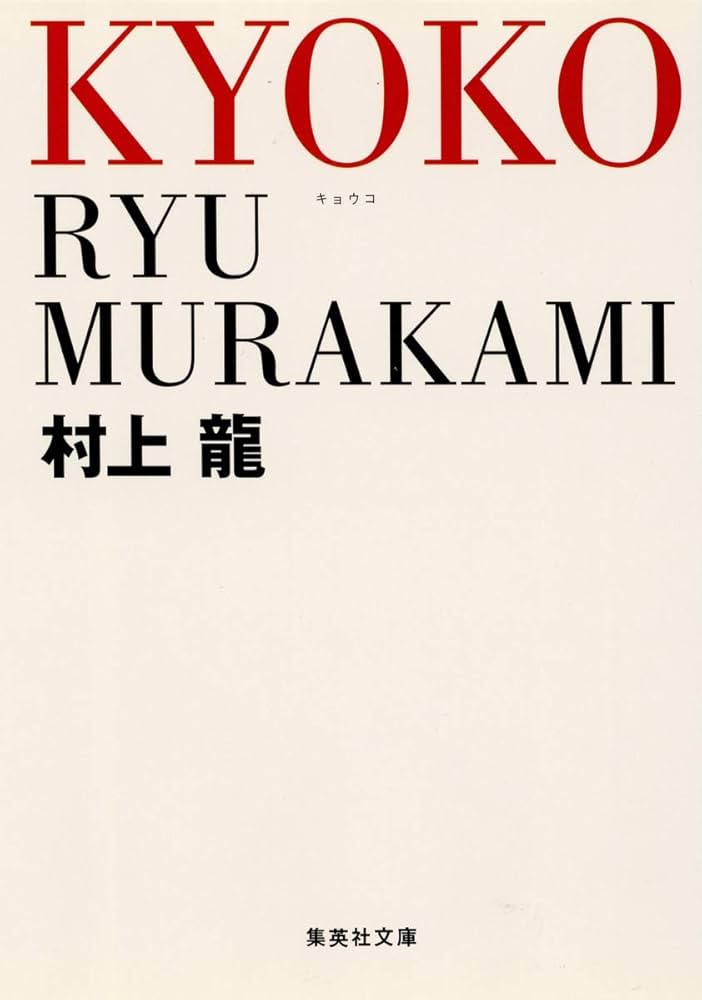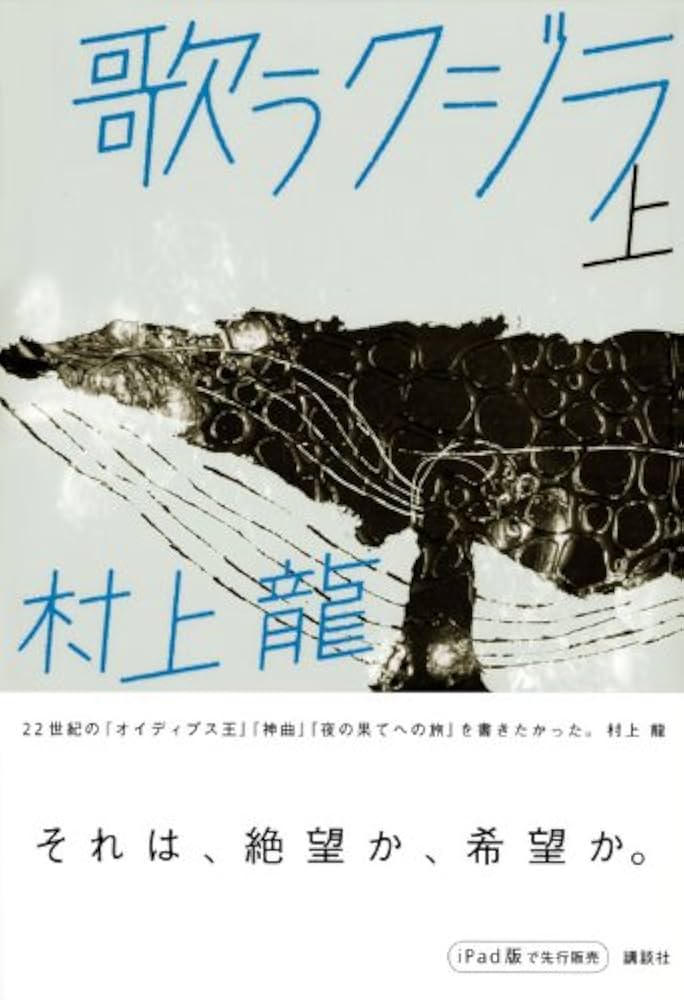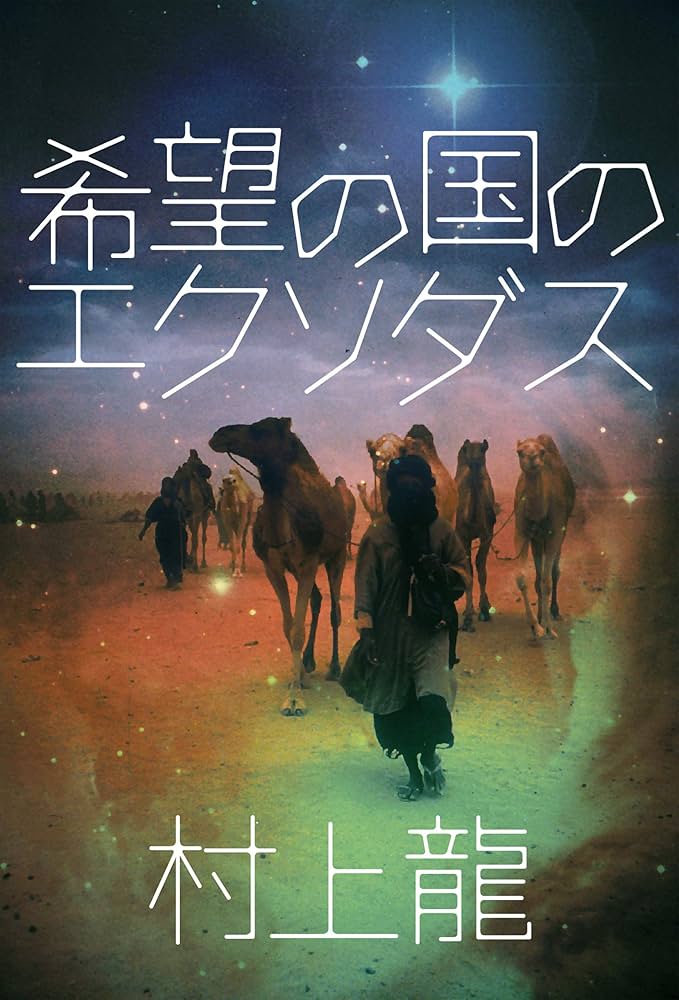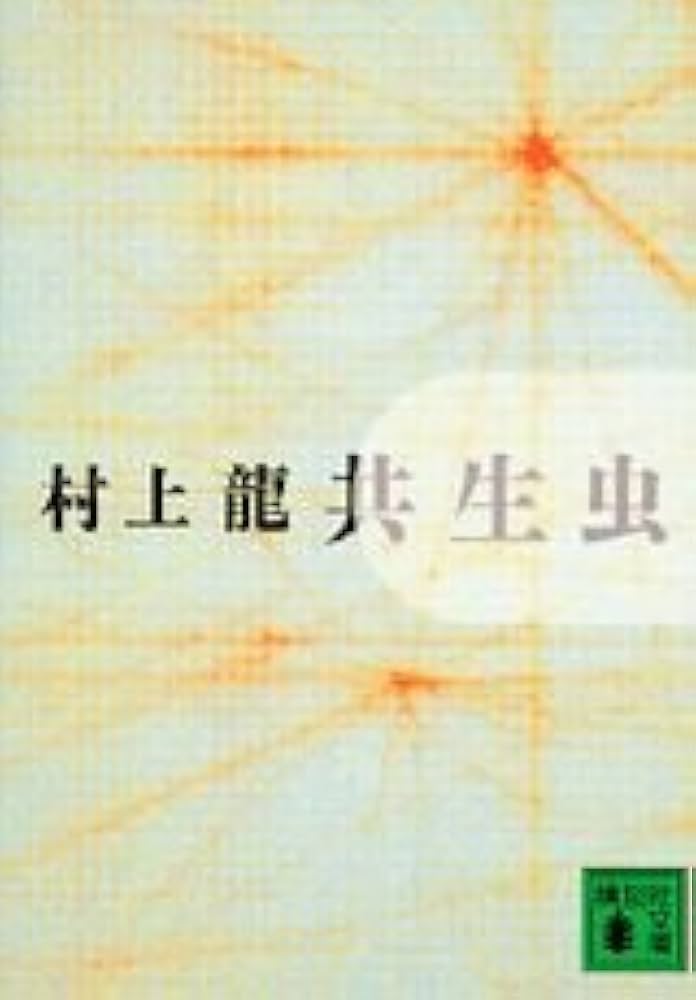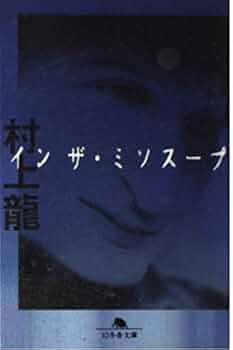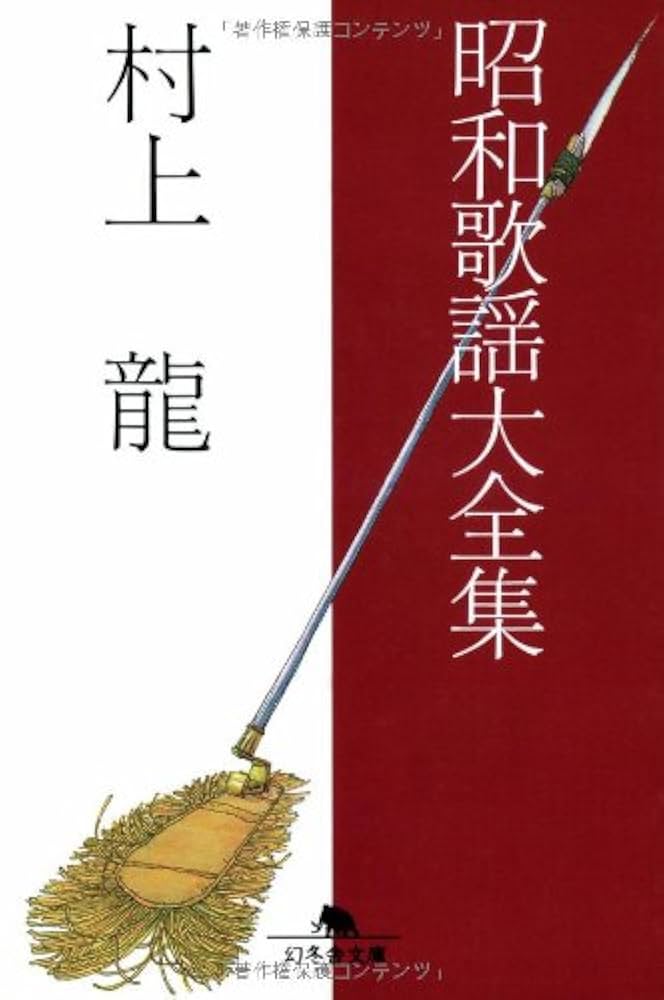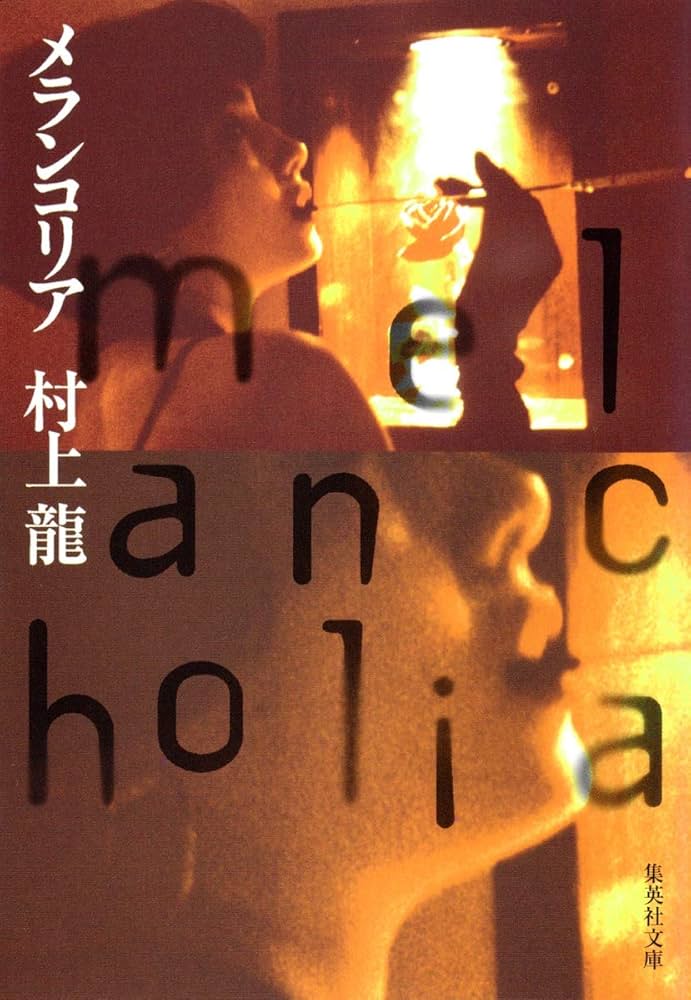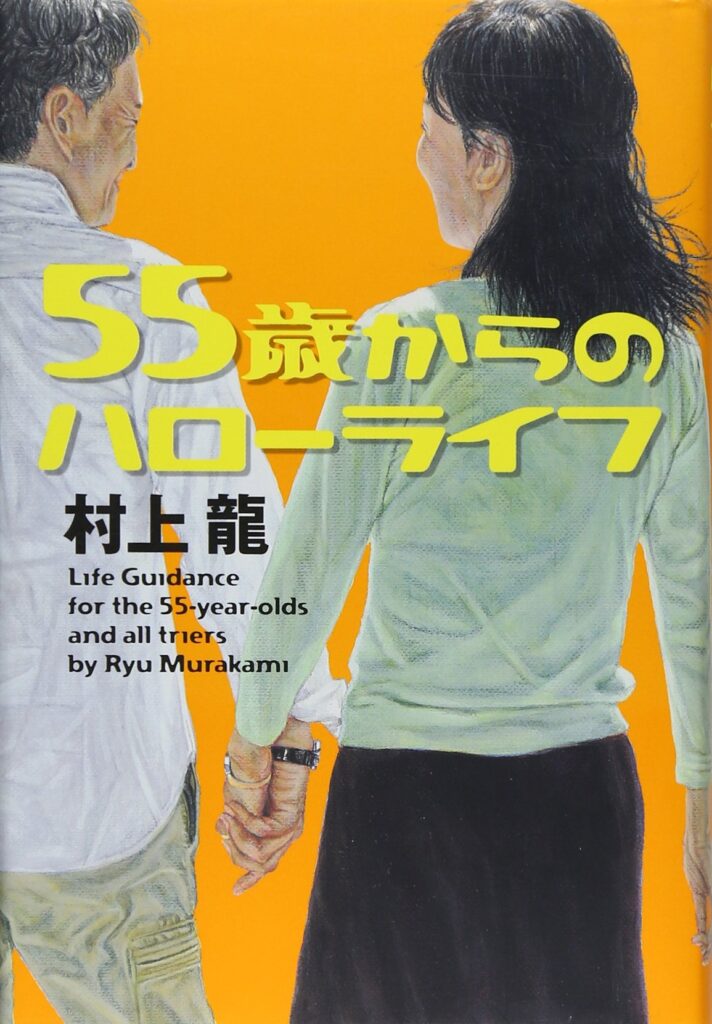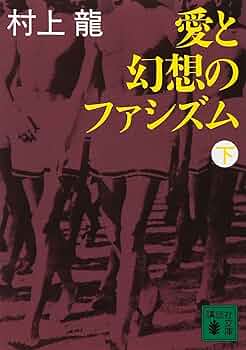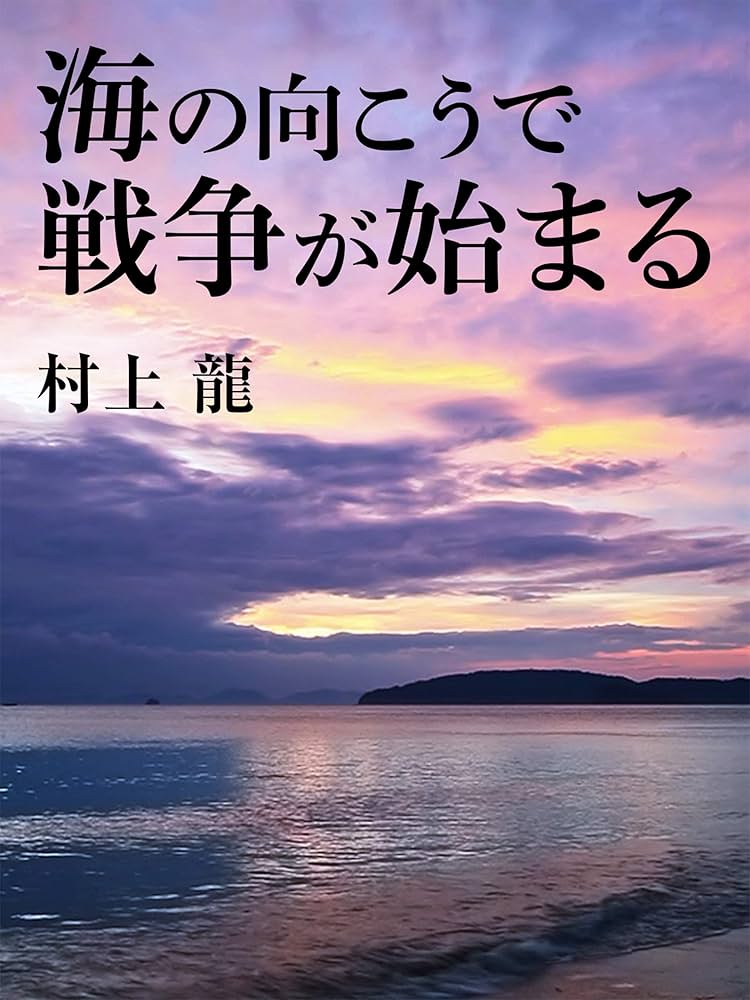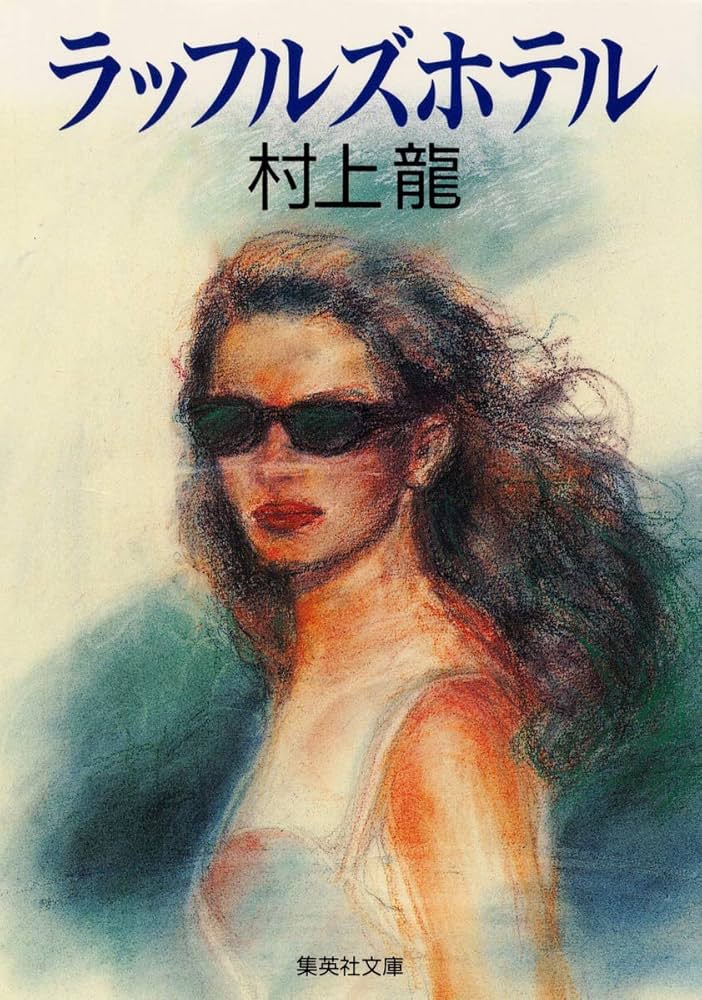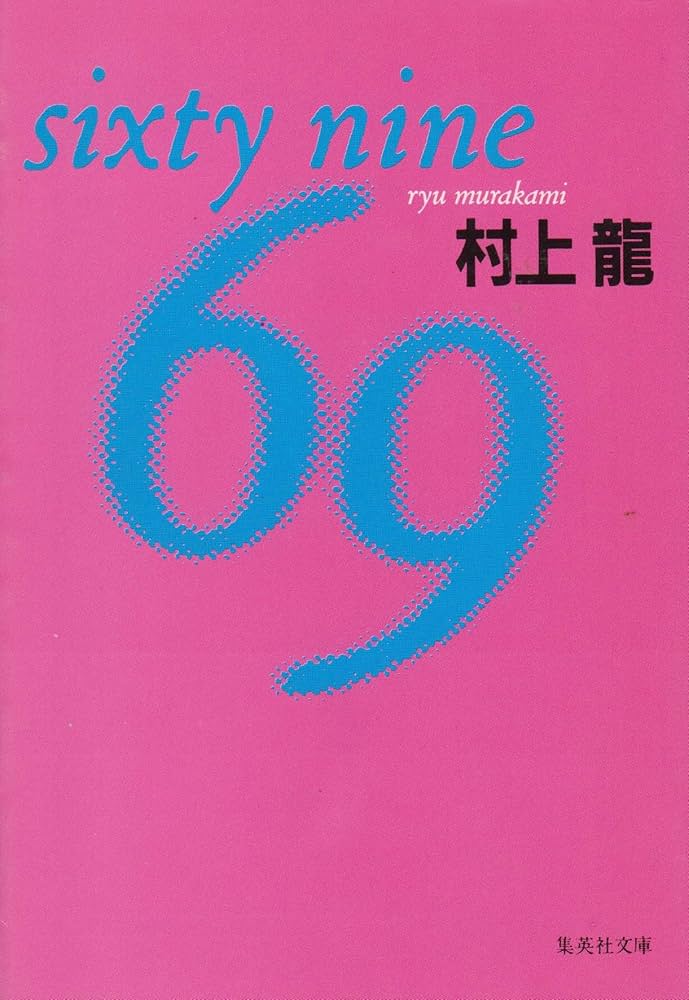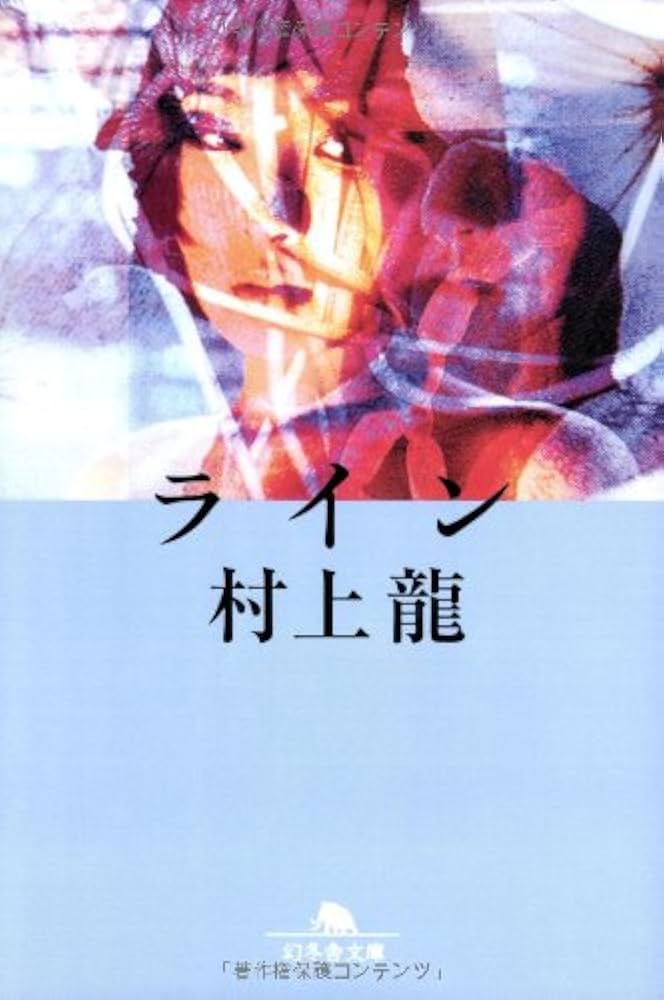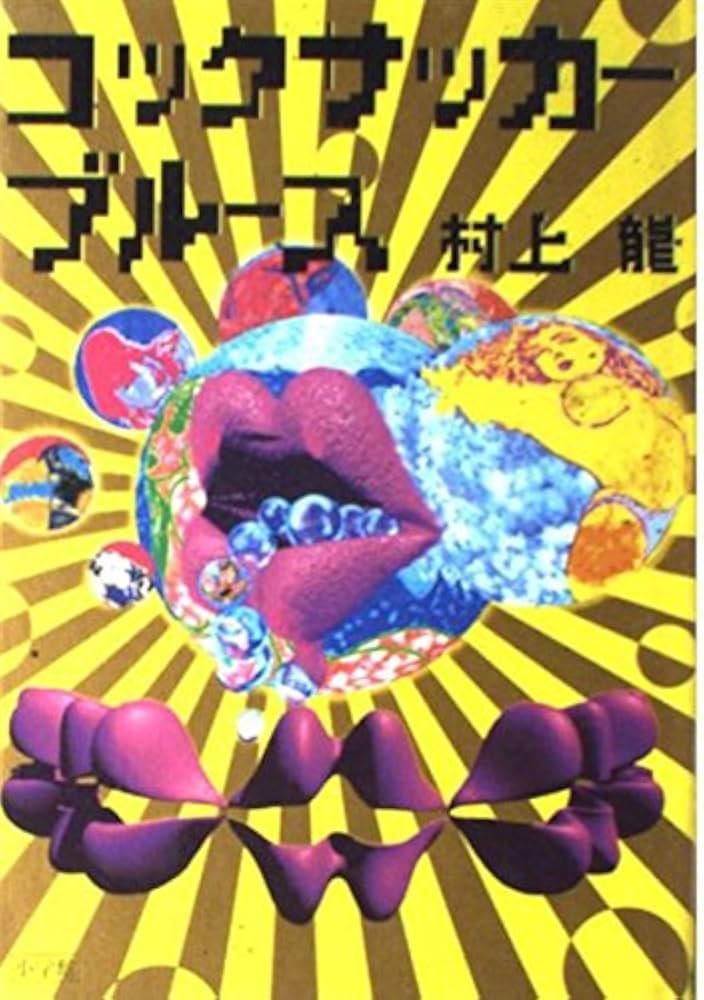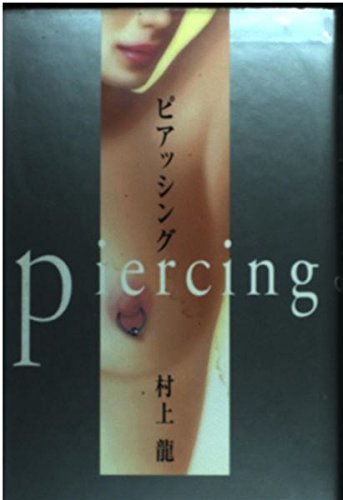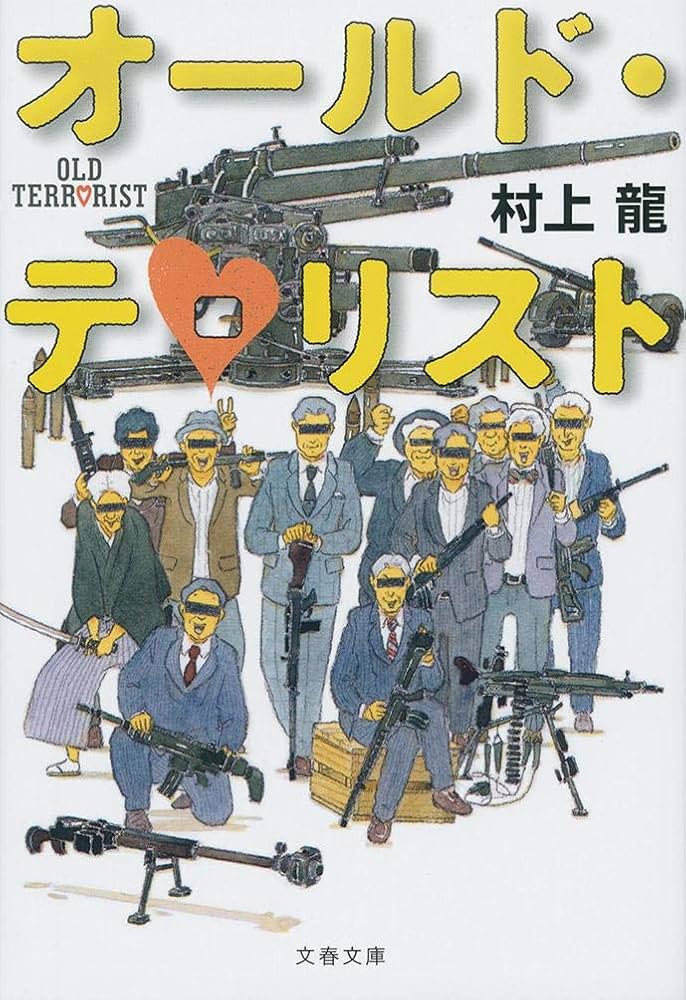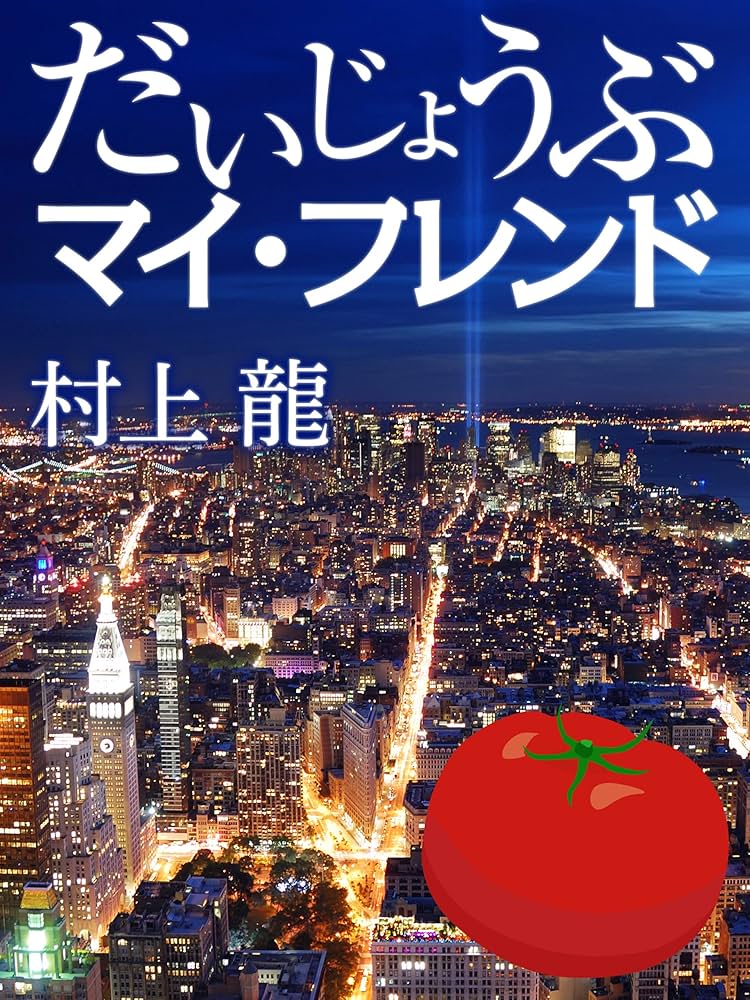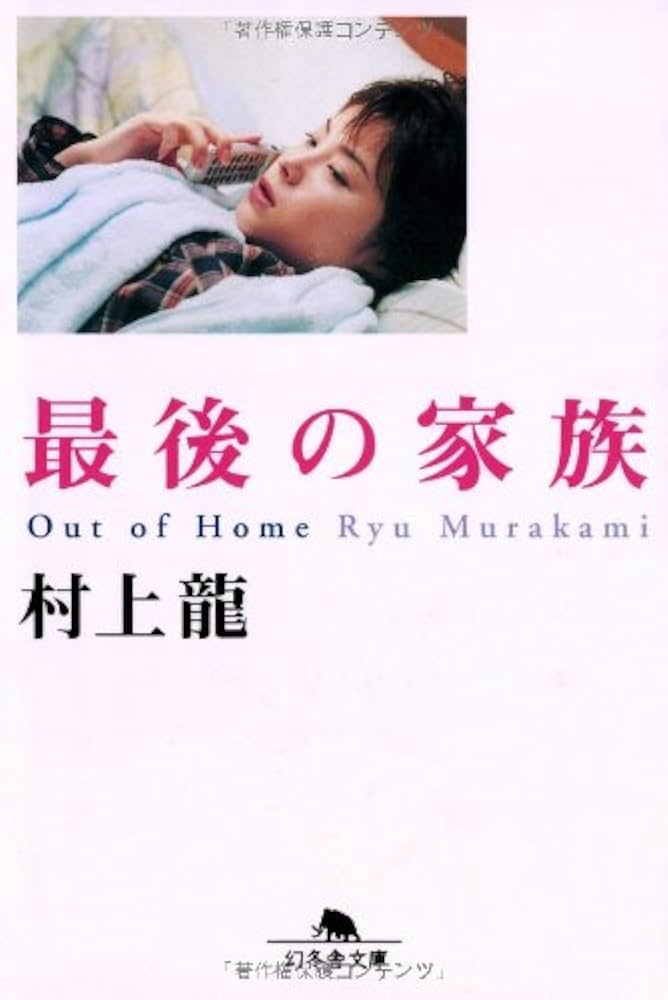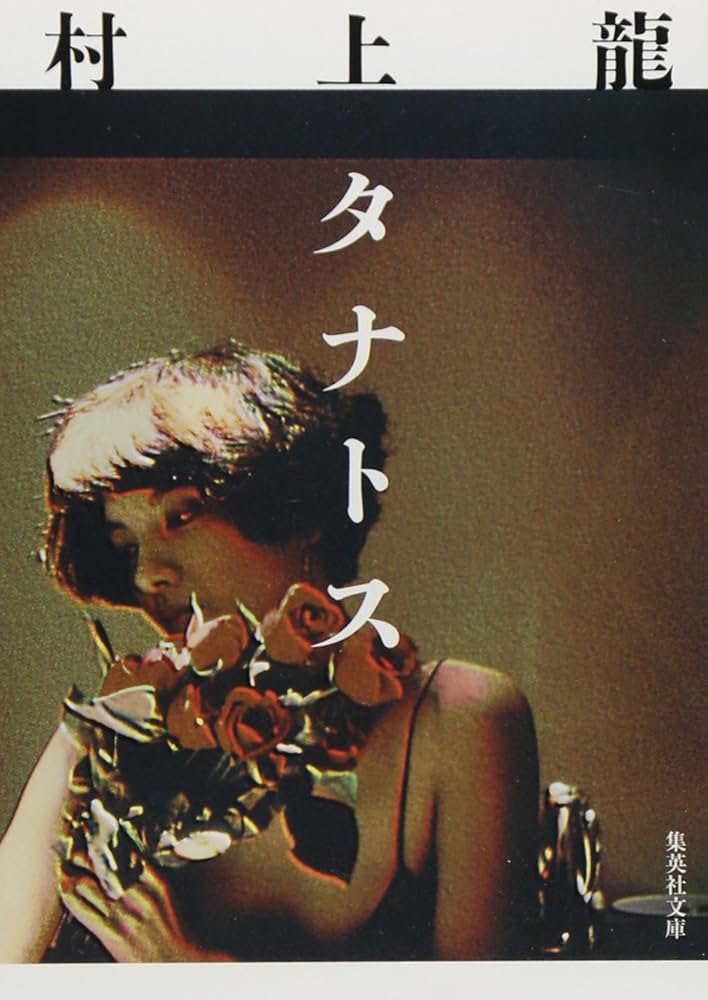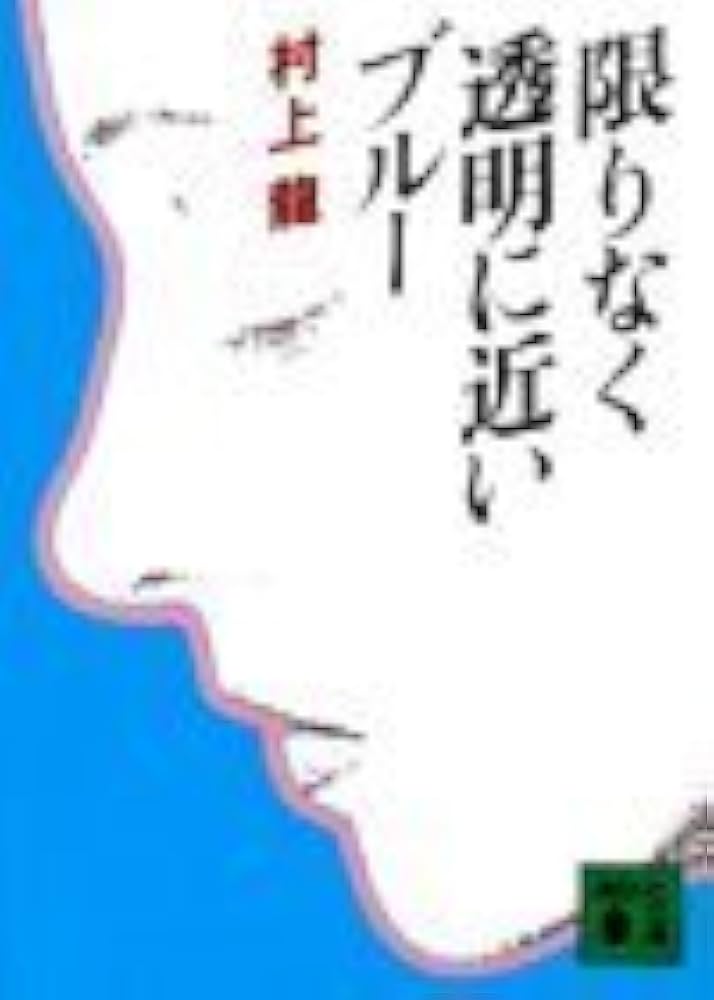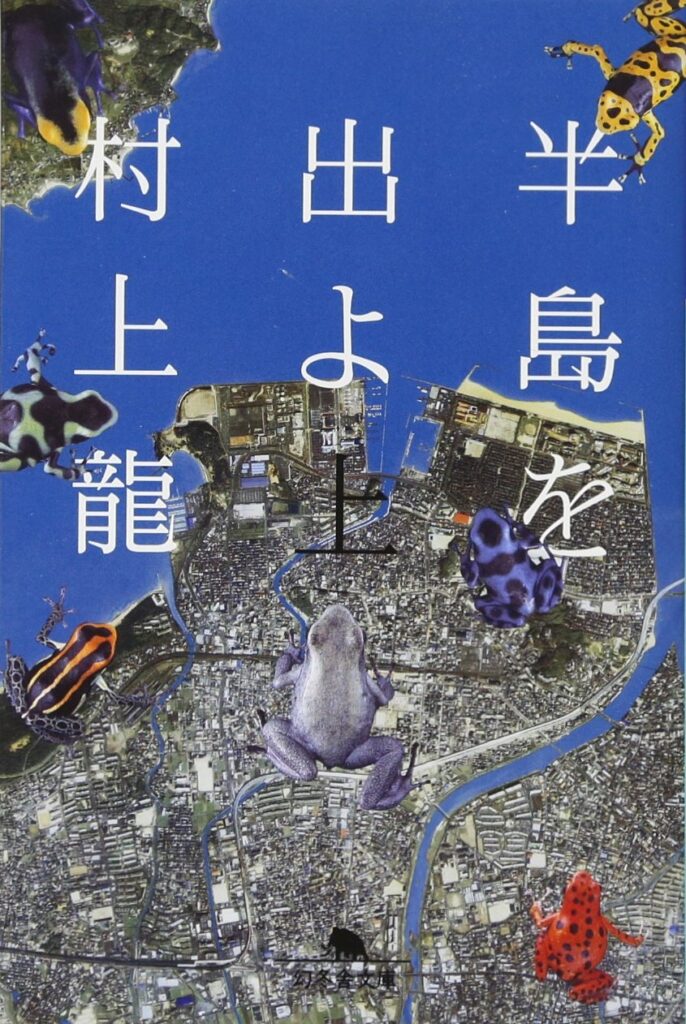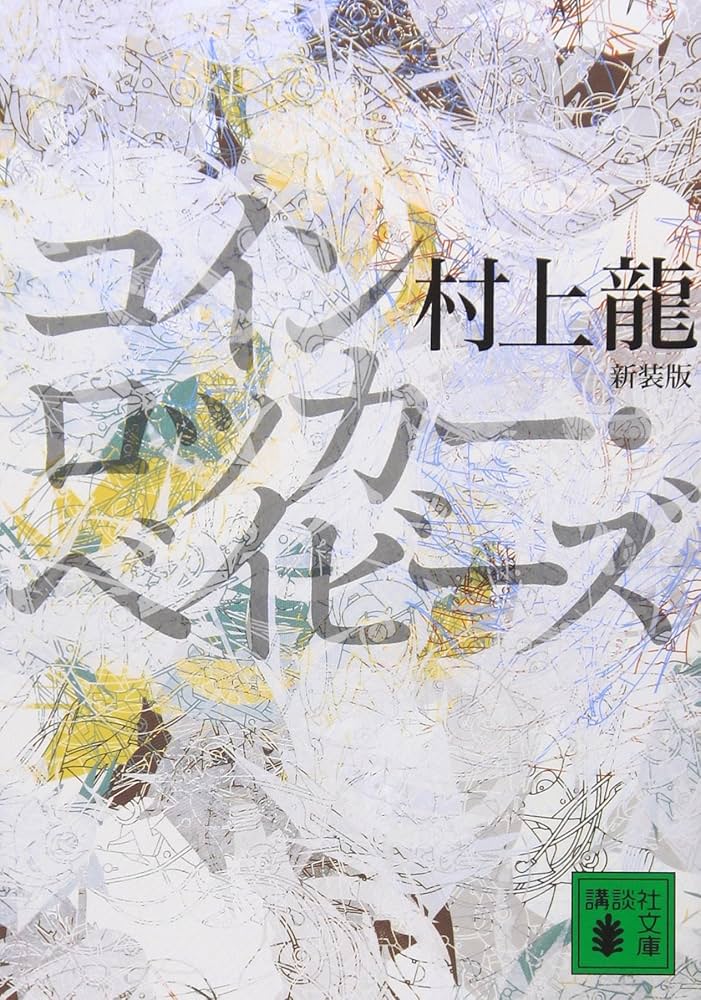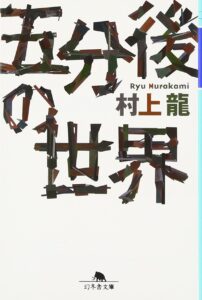 小説『五分後の世界』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説『五分後の世界』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
村上龍氏が描く『五分後の世界』は、もし太平洋戦争の終結が異なっていたらという架空の歴史に基づいた作品です。この物語では、広島と長崎への原爆投下後も日本が降伏せず、本土決戦が続くことで日本の人口が激減し、国土が連合国によって分断されてしまいます。そんな絶望的な状況下で、旧日本軍の一部が秘密裏に長野の地下に潜伏し、独自の地下国家「アンダーグラウンド」を築き上げます。彼らは地上を支配する占領軍に対しゲリラ戦を続け、やがて「戦争ビジネス」として世界中の紛争に介入するようになるのです。
主人公は、元の世界ではAV製作会社の社長を務めていた小田桐昭。ひょんなことから、この「五分後の世界」に迷い込んでしまいます。スパイ容疑で拘束され、強制労働に駆り出される中で、彼は「アンダーグラウンド」の国民兵士たちと遭遇します。彼らの圧倒的な戦闘力と、祖国の誇りをかけた生き様に小田桐は心を揺さぶられ、やがて自らも地下日本の一員として戦うことを決意するのです。
この作品は単なる架空戦記に留まりません。平和に慣れきった現代日本への強烈なメッセージが込められています。自らの誇りを忘れ、惰性で生きる現代人にとって、極限の状況下で命を燃やす地下日本の兵士たちの姿は、深い問いかけを投げかけます。読者は小田桐の視点を通して、何が本当に大切なものなのか、人間としての尊厳とは何かを深く考えさせられるでしょう。
『五分後の世界』は、読む者に強烈なインパクトを与える一冊です。過激な描写の中に、人間の本質と、国や民族のアイデンティティが息づいています。これは、私たちの生きる「今」を相対化し、未来への覚悟を促す、まさに必読の書と言えるでしょう。
『五分後の世界』のあらすじ
村上龍氏の『五分後の世界』は、我々の知る歴史とは異なる道を辿った日本を描き出します。物語の冒頭、1945年8月以降も日本が徹底抗戦を続けた結果、日本列島は米・英・ソ・中の四か国によって分割統治されてしまいました。主要都市は核の炎に焼かれ、飢餓と疫病によって日本の人口は激減し、国家は崩壊寸前の状態に陥ります。
そんな絶望的な状況下で、一部の旧日本軍将校団は長野県の地下に巨大な地下都市を築き上げました。これが、後に「アンダーグラウンド(地下日本国)」と呼ばれるもう一つの日本の誕生です。彼らは地上を支配する連合国軍に対し、巧妙な地下トンネル網を駆使したゲリラ戦を継続します。地下国家の人口はわずか26万人ですが、彼らは高度な技術力と教育水準を維持し、結束を固めて独自の文化と軍事力を発展させていきました。
一方、地上では占領四か国間の利害対立が激化し、東北戦争や西九州戦争といった局地戦が頻発します。そうした混乱の中、地下日本はアメリカ軍からの協力を要請され、中国軍ゲリラとの戦闘に介入。この勝利をきっかけに、地下日本は「亡国の残党」から一転、国際的な「戦争請負人」へと変貌を遂げていきます。
主人公の小田桐昭は、元の世界でAV製作会社の社長を務めるアウトローな男性です。彼は休養のため訪れた箱根で奇妙な現象に遭遇し、気づけば「五分後の世界」に迷い込んでいました。見知らぬ土地で治安部隊に拘束され、スパイ容疑で投獄されてしまう小田桐。強制労働に駆り出された地下トンネルの崩落現場で、彼はラテン系の血を引く混血の女性と出会います。そして、その現場が突然、激しい銃撃戦の舞台となるのです。
『五分後の世界』の長文感想(ネタバレあり)
村上龍氏の『五分後の世界』を読み終えて、まず感じたのはその圧倒的な世界観の構築力でした。単なる架空戦記という枠を超え、ディストピアと化したもう一つの日本を、細部にわたる歴史的設定とリアリティあふれる描写で描き切っています。平和な日本から突然放り込まれた主人公・小田桐昭の視点を通して、読者はこの過酷な世界へ没入していくことになります。
物語の導入部で描かれる、太平洋戦争終結後の日本の惨状は息をのむほどです。史実とは異なる道を辿ったことで、幾つもの都市が原爆で消滅し、人口は激減、国土は四か国に分割されるという描写は、想像を絶する絶望感を伴います。ここでの村上氏の筆致は冷徹でありながらも、日本民族が滅亡の淵に立たされた切迫感を読者に否応なく突きつけます。私たちが享受する平和が、いかに奇跡的なものであるかを痛感させられる幕開けでした。
そして、その絶望の中から生まれたのが地下国家「アンダーグラウンド」です。旧日本軍将校団が長野の地下に築き上げたこの秘密国家は、まさに民族の最後の砦。知的な財産を地下に移転させ、わずか26万人という少数精鋭で生き残ろうとする彼らの姿は、強烈な誇りと執念を感じさせます。特に「差別をしない」というUGの理念は、極限状態における人間の本質的な強さ、つまり「能力と勇気さえあれば出自を問わない」という潔さを際立たせています。地上で分断された世界とは対照的に、地下で団結を固める日本人たちの姿は、希望の光のようにも映りました。
地下日本が「戦争ビジネス」国家へと変貌していく過程も非常に興味深い点です。米軍への協力で世界にその戦闘力を知らしめ、キューバ革命やベトナム戦争、アフガニスタン紛争といった実際の紛争に影から介入していく姿は、フィクションであると知りながらも、その圧倒的なリアリティに引き込まれました。UG兵士たちの「世界最強のゲリラ兵」としての描写は、徹底した規律、無駄のない動き、そして命令への絶対的な忠実さという点で、既存の「日本人らしさ」とはかけ離れた、ある種の理想化された戦闘民族像を提示しています。これは、現代の日本人が失ってしまったかもしれない「誇り」や「覚悟」を問いかける、村上氏からの痛烈なメッセージのように感じられました。
主人公・小田桐昭がこの世界に迷い込むくだりも秀逸です。AV製作会社の社長という裏社会に生きる男が、ある日突然、見知らぬ戦場に放り込まれるという展開は、読者の予想を裏切りながらも、彼の内面に秘められた「生きる力」を浮き彫りにします。スパイ容疑で拘束され、強制労働をさせられる中で、彼の口から出る「古い映画のセリフのような」日本語は、平和な世界と戦火の世界との断絶を象徴する象徴的な描写でした。言葉の持つ意味、そしてそれが文化や環境によっていかに変質するかを考えさせられましたね。
小田桐が巻き込まれるトンネル崩落現場での戦闘は、本作の転換点の一つです。国連軍と日本人ゲリラ部隊による激しい銃撃戦の中に放り込まれた小田桐が、本能的に銃を手に取り、生き残るために戦う姿は、彼の潜在的な暴力性と生命力を示しています。この場面での描写は非常に生々しく、銃弾が飛び交い、血肉が飛び散る戦場のリアリティがひしひしと伝わってきました。そして、この修羅場を乗り越えたことで、彼は地下日本側に連行され、ついにヤマグチ司令官との対面を果たすことになります。
ヤマグチ司令官との出会いは、小田桐にとって大きな意味を持ちます。この地下国家のカリスマ的指導者は、異世界から来た小田桐の話に冷静に耳を傾けながらも、彼の内に秘められた戦士としての資質を見抜きます。小田桐が語る平和な日本の姿は、命を賭して祖国を守り続けるUGの人々にとっては驚きであり、同時に「もしも降伏していたら辿ったかもしれない末路」という皮肉な現実を突きつけます。この対話を通して、読者もまた、現代日本の「平和ボケ」について深く考えさせられるのです。
UG側に受け入れられた小田桐が、アヤコ少尉やライフル分隊の面々と出会う場面は、物語に人間的な温かみをもたらします。マツザワ・アヤコ少尉の毅然とした態度の中に見え隠れする女性らしさ、ミズノ少尉の人懐っこい笑顔、タケヒラ軍曹の頼もしさ。そして、若き兵士たちのそれぞれの個性が、過酷な世界の中で芽生える連帯感を印象付けます。彼らは決して饒舌ではありませんが、その行動や表情から、互いへの信頼と誇りが伝わってきました。小田桐がこの新しい「居場所」に少しずつ馴染んでいく様子は、読者にとっても安堵感をもたらす部分でした。
オールド・トウキョウ潜入作戦は、本作のクライマックスを飾る重要な展開です。UGの英雄的音楽家ワカマツの護衛という任務は、単なる軍事作戦ではなく、地下日本の「文化」と「誇り」を示すプロパガンダ的な意味合いを持っていました。占領下の東京で、秘密裏にコンサートを開催しようとするワカマツの姿は、芸術が持つ抵抗の力を示唆しています。暗い地下水路を進む道中のネズミ退治や、準国民本部での銃口を向けられるハプニングなど、細かな描写が緊迫感を高めていました。特にミヤシタの素早い対処は、UG兵士の錬度の高さを印象づける場面でしたね。
そして、コンサート終盤に勃発する市街戦は、本作で最も衝撃的かつ悲劇的な場面です。ヤマナカ、タケヒラ軍曹、クリハラ、コバヤシ、ナガタ…次々と仲間たちが命を落としていく描写は、読む者の胸を締め付けます。特にタケヒラ軍曹が重迫撃砲の砲撃を受け絶命するシーンは、あまりにも唐突で、戦場の理不尽さを突きつけられました。彼らは誰一人として、怯むことなく、自らの誇りのために命を賭して戦い抜きました。彼らの死は、小田桐の心に深く刻み込まれ、彼を大きく変容させることになります。
辛くも生還した小田桐の心理的な変化は、この作品の核心部分と言えるでしょう。元の世界では虚無感を抱えて生きていた彼が、死と隣り合わせの戦場で「本気で生きた」という実感を抱く。そして、散っていった戦友たちの誇り高い死に心を揺さぶられ、自らも彼らと同じように「本気で生きる」ことを選択するのです。アヤコ少尉の言葉や、ヤマグチ司令官の眼差しは、彼がようやくこの世界で「居場所」を見つけ、誰かに必要とされているという喜びを教えてくれました。
物語は、小田桐が元の世界に戻る術を探すことなく、自らこの戦乱のディストピアで生き続けることを決意する場面で幕を閉じます。この結末は、一見すると悲劇的にも思えますが、小田桐にとっては魂の救済であったと感じました。安全と安逸の中で失われた人間としての誇りを取り戻し、自らの意志で戦い続ける道を選んだ彼の姿は、現代の私たちに強烈な問いを投げかけます。村上龍氏がこの作品を通して伝えたかったのは、もしかしたら「強者であれ」というメッセージなのではないでしょうか。多数に流されることなく、自分の信念のために生きる。その覚悟こそが、混沌とした世界を生き抜くために必要なのかもしれない、そう思わせる傑作でした。
まとめ
村上龍氏の『五分後の世界』は、太平洋戦争が異なる形で終結した架空の日本を舞台に、地下に秘密国家を築いた日本人たちの壮絶な戦いを描いた作品です。主人公・小田桐昭が、平和な世界からこの戦乱のディストピアへ迷い込み、やがて地下日本の誇り高き兵士たちと共に戦う道を選ぶ物語は、読者に強烈なインパクトを与えます。
本作は、単なる架空戦記に留まらず、現代日本への深い問いかけが随所に散りばめられています。平和に慣れ親しんだ私たち日本人にとって、誇りや覚悟を胸に命を燃やす地下日本の兵士たちの姿は、自分たちの生き方を顧みるきっかけとなるでしょう。
極限状態における人間の尊厳、そして「生きる」ことの意味を深く掘り下げたこの作品は、私たちの心に深く響くこと間違いありません。刺激的な描写の連続でありながらも、そこには村上氏からの熱いメッセージが込められています。
読む者の価値観を揺さぶる、まさに「文学」と呼ぶにふさわしい一冊です。この作品を読み終えた後、あなたはきっと、自分自身の「五分後の世界」を考えることになるでしょう。