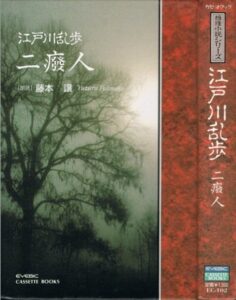 小説「二癈人」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。江戸川乱歩が生み出したこの短編は、静かな温泉宿を舞台に、二人の男の過去が交錯する物語です。一見、穏やかな昔語りから始まるのですが、読み進めるうちに不穏な空気が立ち込め、読者を深い闇へと引きずり込んでいきます。
小説「二癈人」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。江戸川乱歩が生み出したこの短編は、静かな温泉宿を舞台に、二人の男の過去が交錯する物語です。一見、穏やかな昔語りから始まるのですが、読み進めるうちに不穏な空気が立ち込め、読者を深い闇へと引きずり込んでいきます。
「癈人」とは、心や体に傷を負い、通常の社会生活を送ることが困難になった人を指す言葉です。この物語には、まさに二人の「癈人」が登場します。一人は自らが犯したとされる罪によって、もう一人は戦争によって、その人生を大きく狂わされてしまいました。彼らの出会いは偶然か、それとも必然だったのでしょうか。
物語の魅力は、単なる謎解きに留まりません。人間の心の奥底に潜む弱さ、欺瞞、そして諦念といった複雑な感情が、静かな筆致で丹念に描かれています。特に、衝撃的な真実が明らかになった後の主人公の反応は、読む者の心を強く揺さぶります。この記事では、その結末に至るまでの経緯と、私が抱いた様々な思いを詳しく述べていきたいと思います。
江戸川乱歩の作品に初めて触れる方にも、既にその世界観に魅了されている方にも、この「二癈人」という作品が持つ独特の味わい深さを感じていただければ幸いです。それでは、物語の核心に触れながら、その魅力と謎に迫っていきましょう。
小説「二癈人」のあらすじ
のどかな冬の温泉場。湯治に訪れていた井原氏は、同じく療養中の斎藤氏と出会い、意気投合します。斎藤氏は戦争で顔や体に深い傷を負っており、その痛々しい体験談を井原氏に語って聞かせます。その話を聞きながら、井原氏は自らの過去を省み、「戦争で人生を台無しにした斎藤氏には名誉があるが、自分には何もない」と、暗い気持ちに沈むのでした。
ふと、井原氏は斎藤氏の顔に見覚えがあるような気がします。確信はないものの、遠い昔、子供の頃の遊び友達だったのではないかという親近感を覚え、これまで誰にも話さなかった自身の過去を打ち明ける決心をします。井原氏は裕福な商家の生まれでしたが、大学時代に奇妙な病に悩まされることになります。それは夢遊病でした。
最初は寝ている間に友人の部屋を訪れて議論をふっかける程度でしたが、症状は次第に悪化していきます。ある朝、枕元に見知らぬ懐中時計が置かれているのを発見し、自分が寝ている間に盗みを働いてしまったことを悟ります。医者にも相談しますが、症状は改善せず、井原氏は「いつか眠っている間に取り返しのつかない犯罪を犯してしまうのではないか」という恐怖に苛まれるようになります。
そして、その恐れていた事態が現実に起こってしまいます。ある朝、下宿の管理人の老人が殺害され、金品が盗まれるという事件が発生します。井原氏が恐る恐る自室の押し入れを確認すると、そこには盗まれた老人の財産が入った風呂敷包みがありました。自分が夢遊状態のうちに、老人を殺害し、金品を盗んでしまったのだと確信する井原氏。
井原氏は自首しますが、夢遊病による犯行であること、動機の乏しさ、そして父が雇った弁護士や、最初に夢遊病を指摘した友人・木村の熱心な弁護活動のおかげで、最終的に無罪判決を得ます。しかし、「人を殺めた」という事実は井原氏の心を深く蝕み、故郷に戻ってからも心身を病み、社会から隔絶された生活を送る「癈人」となってしまったのです。
井原氏の告白を聞き終えた斎藤氏は、同情を示しつつも、事件の詳細や夢遊病の症状について鋭い質問を重ねます。そして、井原氏の夢遊病の根拠が、友人・木村の証言に大きく依存している点を指摘。斎藤氏は、木村こそが真犯人であり、井原氏を夢遊病者に仕立て上げ、罪を着せたのではないか、という驚くべき推理を展開します。井原氏は愕然とし、言葉を失います。やがて斎藤氏は静かに挨拶をして去っていきますが、井原氏は、その斎藤氏こそが木村本人であった可能性に気づき、自らの愚かさを嘆くと同時に、木村の周到な計画とその知性を、奇妙にも賛美せずにはいられないのでした。
小説「二癈人」の長文感想(ネタバレあり)
江戸川乱歩の「二癈人」を読み終えた時、私の心には深い静寂と、形容しがたい虚無感のようなものが広がりました。派手なトリックやアクションがあるわけではありません。静かな温泉宿で交わされる二人の男の会話が中心となる物語ですが、その静けさの中に、人間の心の闇と、抗いがたい運命の皮肉が凝縮されているように感じました。この感想では、物語の核心に触れながら、私が感じたことを詳しく述べていきたいと思います。もちろん、結末までの内容を含みますので、未読の方はご注意ください。
まず、この物語の巧みさは、井原氏の告白から始まるところにあると感じます。読者は井原氏の視点を通して、彼が経験したという夢遊病の恐怖と、それによって引き起こされたとされる悲劇を知ります。最初は、井原氏の語る言葉をそのまま受け入れ、彼の苦悩に同情を寄せます。夢遊病という、本人には自覚も制御もできない症状によって人生を狂わされてしまった男の悲劇として、物語は静かに進行していくかに見えます。
しかし、井原氏の話が進むにつれて、どこか釈然としない、奇妙な引っかかりを感じ始めるのではないでしょうか。特に、夢遊病の発作の証拠とされる品々が、あまりにも都合よく発見される点です。懐中時計が枕元に、そして決定的な証拠となる盗品が入った風呂敷包みが押し入れに。これらの発見は、井原氏にとっては悪夢の裏付けとなるわけですが、客観的に見ると、あまりにも出来すぎているように感じられます。
また、井原氏自身の認識の甘さ、あるいは受動的な性格も気になります。彼は友人である木村の言葉を比較的容易に受け入れ、自らが夢遊病であると信じ込みます。もちろん、夢遊病という症状自体が本人に自覚しにくいものであることは考慮すべきですが、それでも、自らの人生を左右するような重大な出来事に対して、もう少し懐疑的になってもよさそうなものです。しかし、井原氏は恐怖に囚われるばかりで、事態を客観的に分析しようとはしません。この受動性が、後の悲劇を招き寄せる一因となっているように思えます。
そこに登場するのが、戦争で傷を負ったもう一人の「癈人」、斎藤氏です。彼の登場は、物語の雰囲気を一変させます。当初は、井原氏と同じく人生に傷を負った者同士の共感や慰め合いが描かれるのかと思いきや、斎藤氏は井原氏の告白に対して、冷静かつ鋭い質問を投げかけ始めます。この対比が鮮やかです。過去の罪に囚われ続ける井原氏と、過去の出来事を客観的に分析しようとする斎藤氏。
斎藤氏の指摘は、読者が漠然と感じていたであろう違和感を、明確な形にしていきます。夢遊病の証拠とされるものは、すべて第三者が用意できるのではないか? 井原氏の夢遊病の目撃者は、突き詰めれば木村一人なのではないか? これらの疑問は、井原氏が信じてきた過去の出来事を根底から揺るがします。そして、斎藤氏はついに、木村こそが真犯人であり、井原氏を巧みに利用したのではないか、という核心的な推理を口にするのです。
この推理が提示される場面は、本作のクライマックスと言えるでしょう。井原氏が長年抱き続けてきた悪夢が、実は他者によって巧妙に仕組まれたものであった可能性。それは、彼にとって救いであると同時に、新たな絶望の始まりでもあります。自分が犯したと思っていた罪から解放されるかもしれない一方で、最も信頼していた友人に裏切られ、人生を操られていたという事実に直面させられるのですから。
そして、読者は薄々気づき始めるはずです。この鋭い推理を展開する斎藤氏こそが、かつての友人・木村本人なのではないかと。井原氏が斎藤氏に感じていた既視感、そして斎藤氏が井原氏の過去の事件について異常なほど詳しいこと。これらはすべて、斎藤=木村であることを示唆する伏線だったのです。なぜ木村は、今になって井原氏の前に現れ、このような残酷な真実を匂わせるような言動をとるのでしょうか。
その理由は、おそらく彼自身もまた「癈人」となったからではないでしょうか。斎藤氏(木村)は、かつて井原氏を利用して自らの目的(おそらくは老人への復讐など)を果たしました。その計画は成功し、彼は一時的に望むものを手に入れたのかもしれません。しかし、その後の戦争で彼は顔や体に醜い傷を負い、社会の表舞台から退かざるを得なくなりました。彼もまた、井原氏とは違う形で人生を損なわれた「癈人」となったのです。
同類となった者への奇妙な仲間意識か、あるいは長年抱えてきた罪悪感からの告白衝動か。もしかしたら、時効が成立していることを見越した上での、自己満足的な暴露なのかもしれません。彼の真意は定かではありませんが、井原氏の前で過去の事件を蒸し返し、真実の可能性を示唆する行為は、極めて残酷であると同時に、彼自身の苦悩の表れでもあるように感じられます。彼は井原氏に真実を告げることで、自らの罪を少しでも軽くしたかったのかもしれません。
この物語の最も衝撃的で、そして深い余韻を残すのは、真実(あるいはその可能性)を知った後の井原氏の反応です。彼は木村(斎藤氏)への怒りに燃え上がるかと思いきや、そうはなりません。激しい怒りの感情は一瞬湧き上がるものの、すぐにそれは消え失せ、自らの愚かさを嘆き、そして最終的には「木村の機知を賛美せずにはいられない」という心境に至るのです。
この結末には、様々な解釈が可能でしょう。長年の苦しみから解放されたことによる一種の虚脱感なのか。あるいは、自分を陥れた犯人の計画の巧妙さに、倒錯的な美しさすら感じてしまったのか。もしかしたら、あまりにも長期間「罪人」としての自己認識に囚われていたため、真実を受け入れる精神的な強さが、もはや残っていなかったのかもしれません。いずれにせよ、この諦念とも畏怖ともつかない感情こそが、井原氏を真の「癈人」たらしめているのではないでしょうか。彼は、自らの人生を狂わせた元凶を前にして、抵抗するのではなく、その存在をある種の超越的なものとして受け入れてしまうのです。
肉体的な傷によって「癈人」となった斎藤(木村)と、精神的な牢獄に囚われ続け、最終的に真実の前で完全に受動的な存在となることで「癈人」となった井原氏。この二人の対比は、本作の核となるテーマを浮き彫りにしています。どちらがより不幸か、という単純な比較はできませんが、井原氏の精神的な破綻は、読む者に重苦しい感覚を残します。
乱歩の作品には、しばしば人間の倒錯した心理や、社会の常識から逸脱した人物が登場しますが、「二癈人」はその中でも特に静謐な筆致で、人間の精神的な弱さや脆さを描き出しているように思います。例えば、「人間椅子」のような奇抜な設定や、「芋虫」のようなグロテスクな描写はありません。しかし、静かな会話の中に潜む悪意と、それに翻弄される人間の姿は、他の派手な作品以上に、人間の心の深淵を覗き込ませる力を持っていると感じます。
参考情報にあった谷崎潤一郎の『痴人の愛』との比較も興味深い点です。ナオミに翻弄され、自らを「痴人」と認める譲治の姿は、確かに木村の知性を賛美するに至った井原氏の姿と重なる部分があります。自己を破滅させる存在を受け入れ、ある種の諦念の中に安住しようとする心理。乱歩が描く「癈人」の姿には、そうしたマゾヒスティックな要素も含まれているのかもしれません。
最終的に、斎藤(木村)は「おそるおそる」挨拶をして去っていきます。この描写には、彼の罪悪感や、井原氏の反応に対する不安が滲み出ています。彼は井原氏を打ちのめしましたが、決して完全な勝利者ではありません。彼もまた、過去の罪と現在の境遇に苦しみ続ける「癈人」なのです。この救いのない結末、はっきりとした解決が示されないもどかしさこそが、「二癈人」という作品の持つ独特の魅力であり、読後に深い問いを投げかけてくる所以なのではないでしょうか。読み返すたびに、新たな発見や解釈が生まれる、そんな奥深い作品だと感じています。
まとめ
江戸川乱歩の「二癈人」は、静かな温泉宿を舞台に、過去の罪と戦争によって人生を狂わされた二人の男の邂逅を描いた短編小説です。主人公の井原氏は、大学時代の夢遊病が原因で殺人を犯してしまったと信じ込み、長年苦しんできました。しかし、温泉宿で出会った斎藤氏との会話を通じて、その悪夢が実はかつての友人・木村によって仕組まれたものであった可能性に気づかされます。
物語の核心は、衝撃的な真実が明らかになる過程と、その真実を知った井原氏の反応にあります。彼は犯人への怒りではなく、自らの愚かさを嘆き、最終的には犯人の計画の巧妙さを「賛美」するという、常人には理解しがたい心境に至ります。この諦念とも言える境地こそが、彼を真の「癈人」たらしめるのです。
一方、戦争で傷を負い、井原氏に真実を匂わせる斎藤氏(=木村)もまた、肉体的な意味での「癈人」です。彼の告白とも挑発ともとれる言動の裏には、罪悪感や同類意識といった複雑な感情が隠されているのかもしれません。二人の「癈人」の対比を通して、人間の精神的な弱さ、欺瞞、そして抗いがたい運命の皮肉が深く描かれています。
派手さはないものの、静かな筆致の中に人間の心の闇が凝縮されており、読後に重い余韻と深い問いを残す作品です。後味の悪さの中に、乱歩ならではの倒錯的な美学や、人間の深淵を覗き込むような魅力が感じられます。ミステリとしての面白さだけでなく、人間の心理を探求する文学作品としても、非常に読み応えのある一作と言えるでしょう。






































































