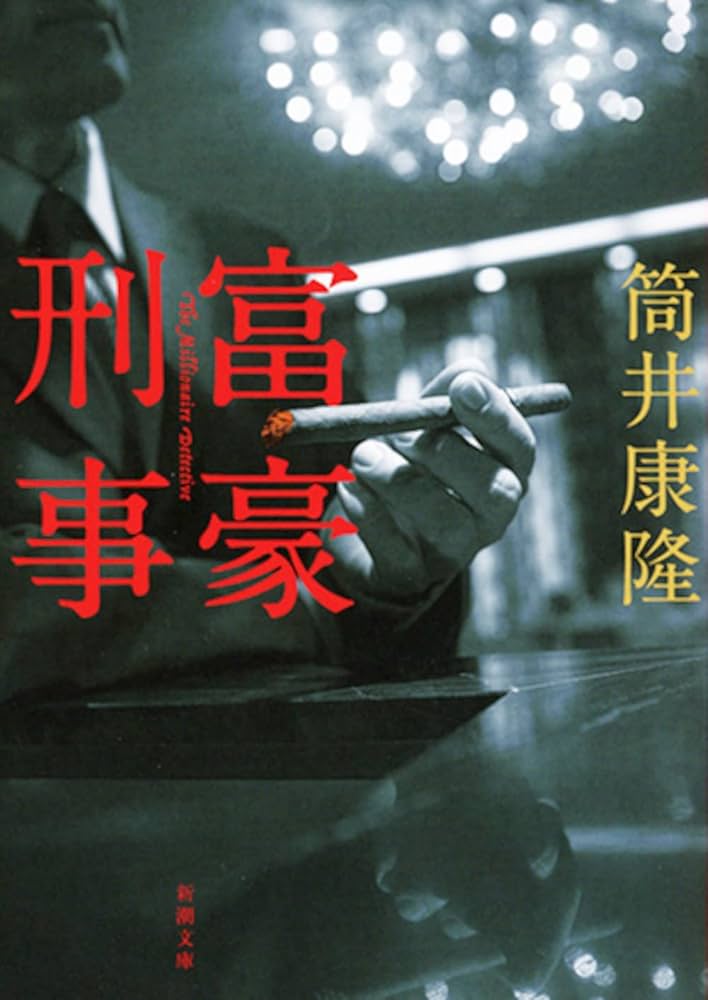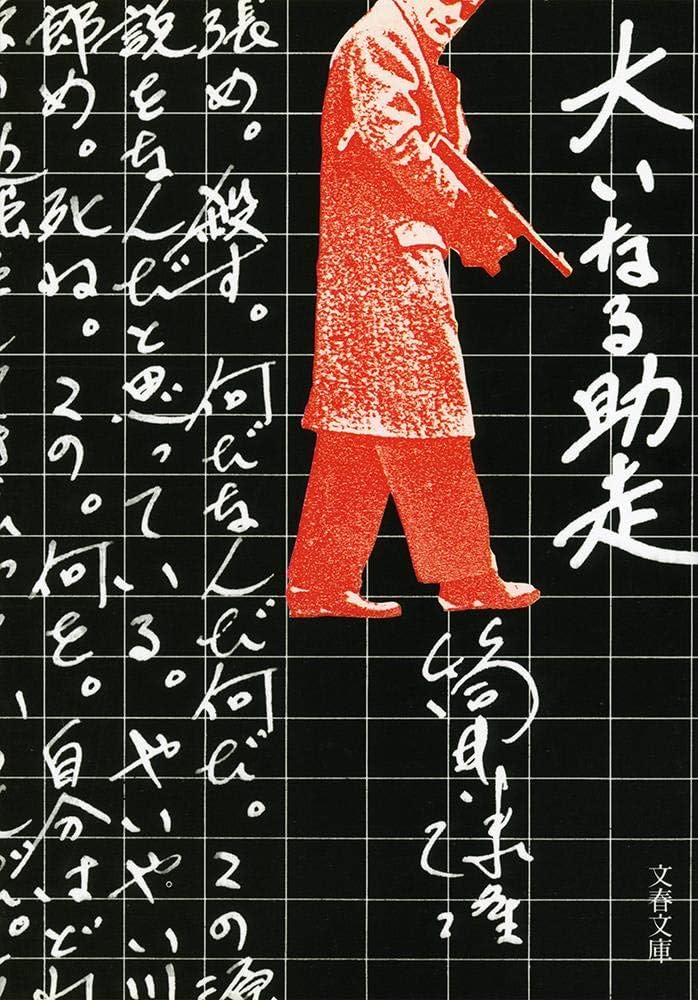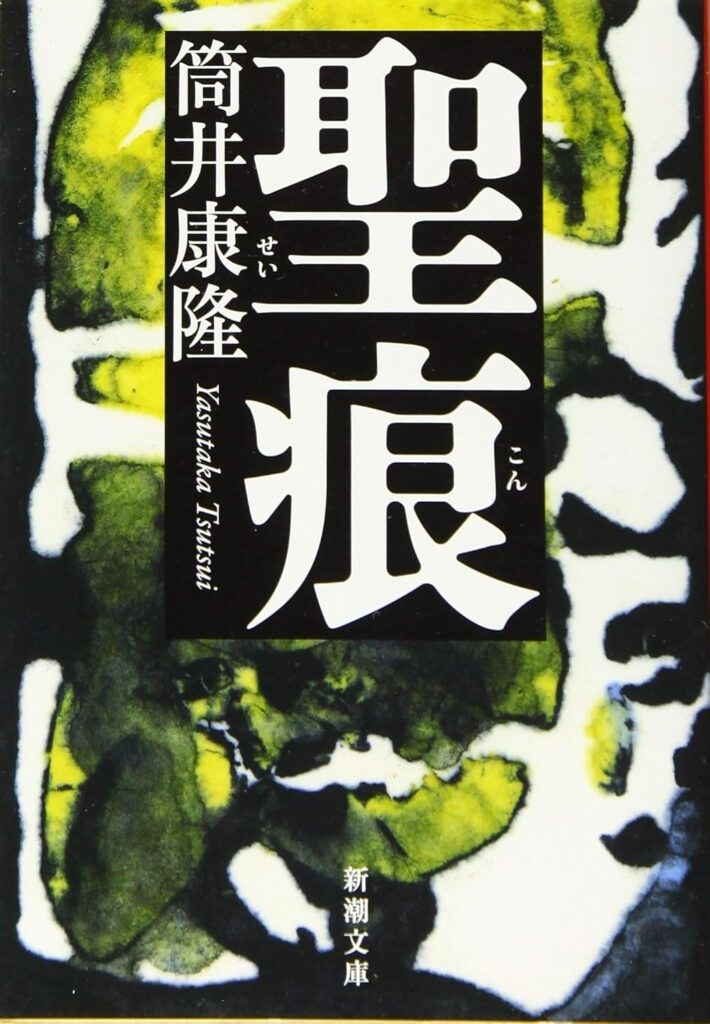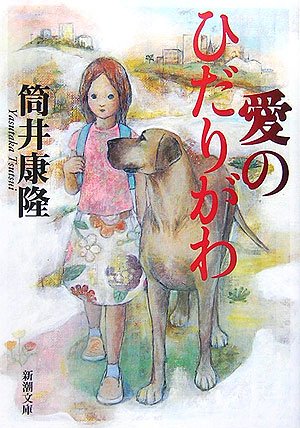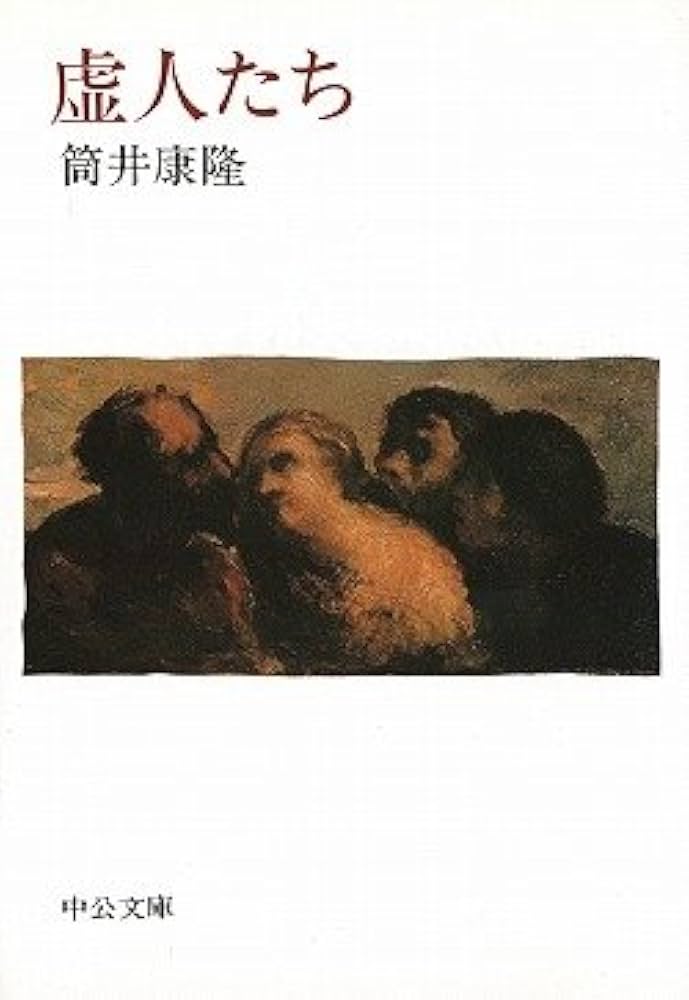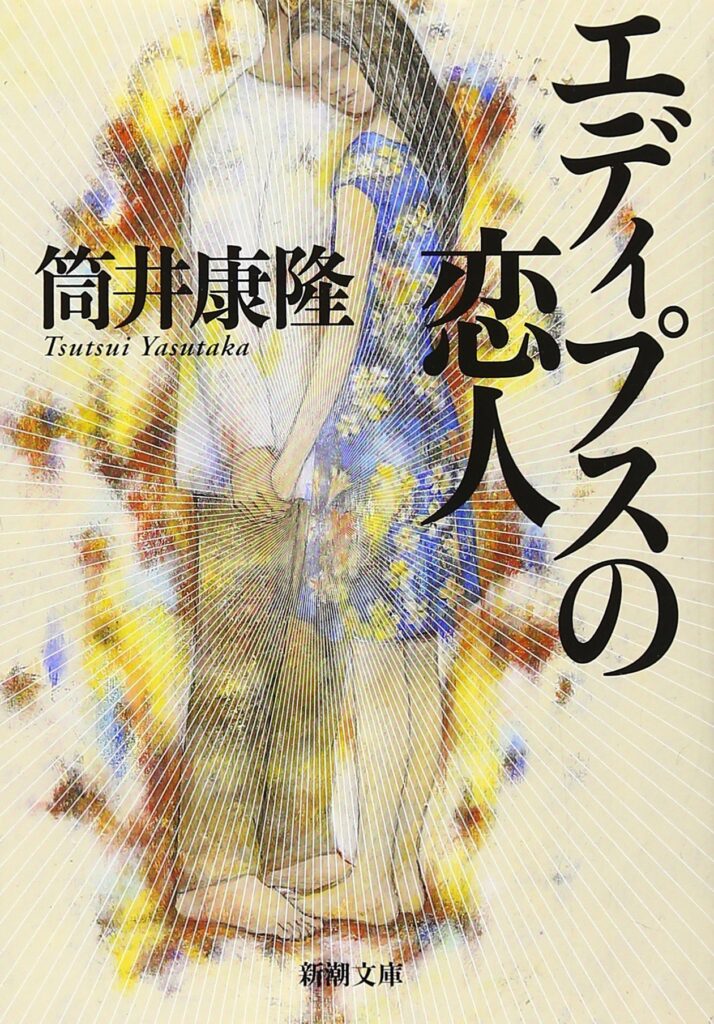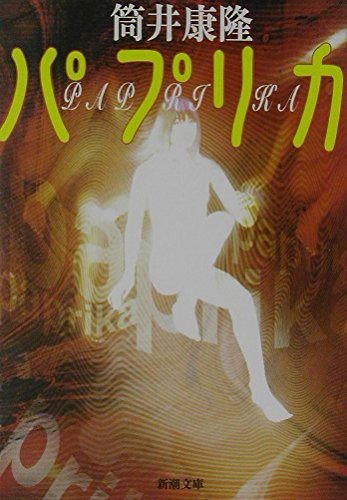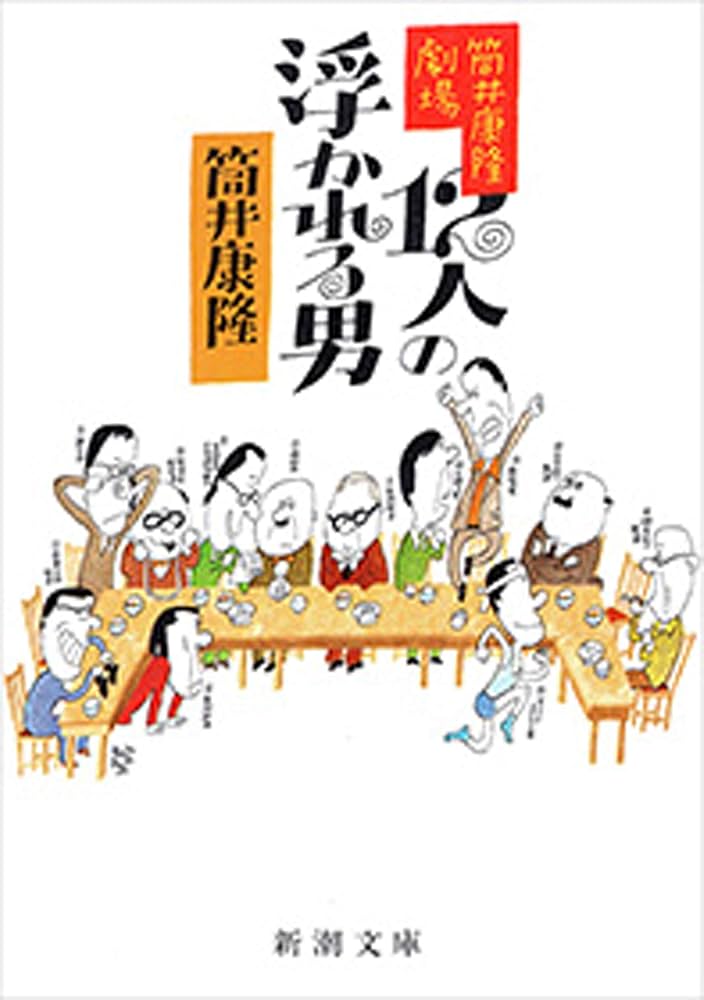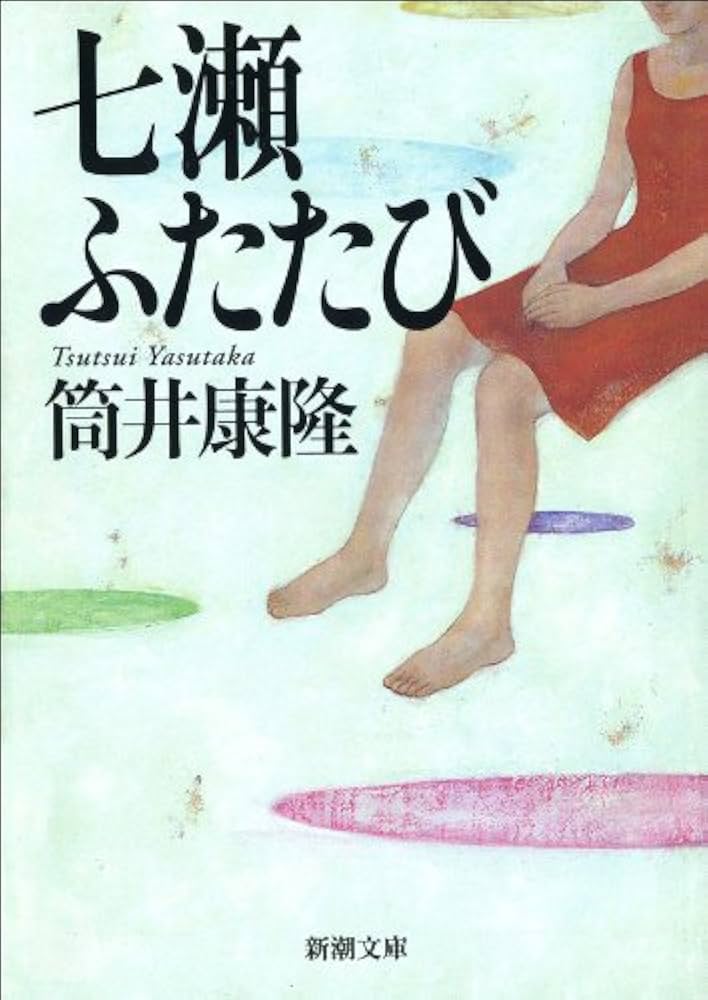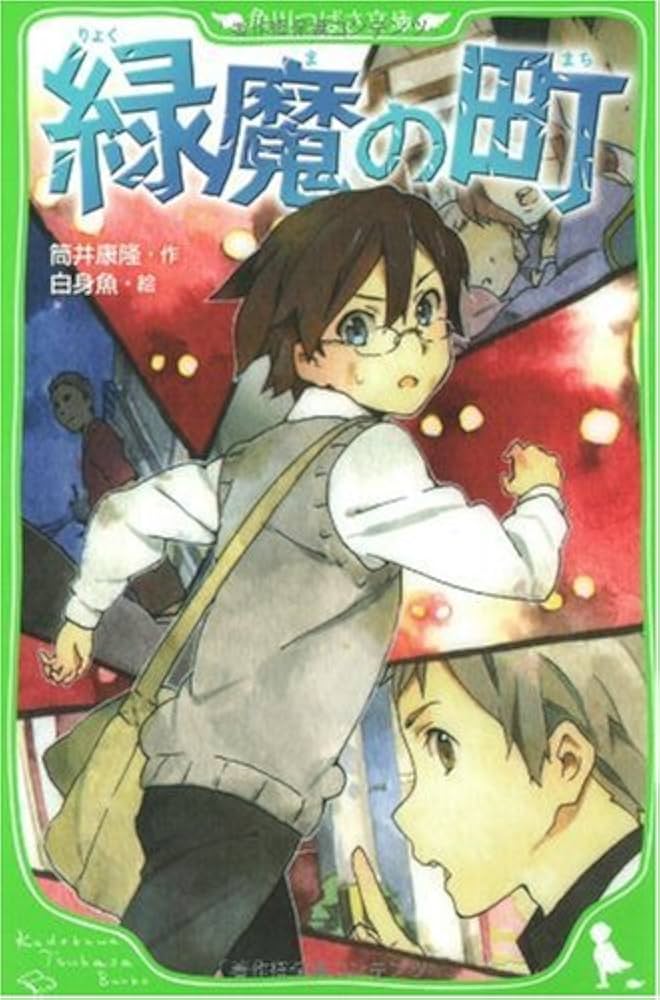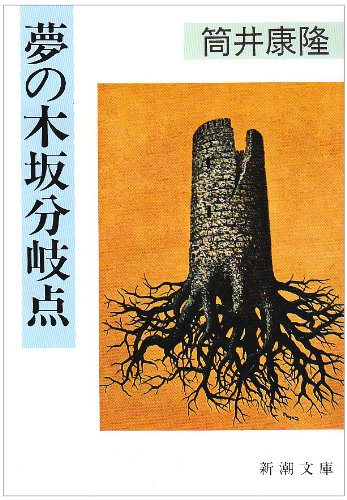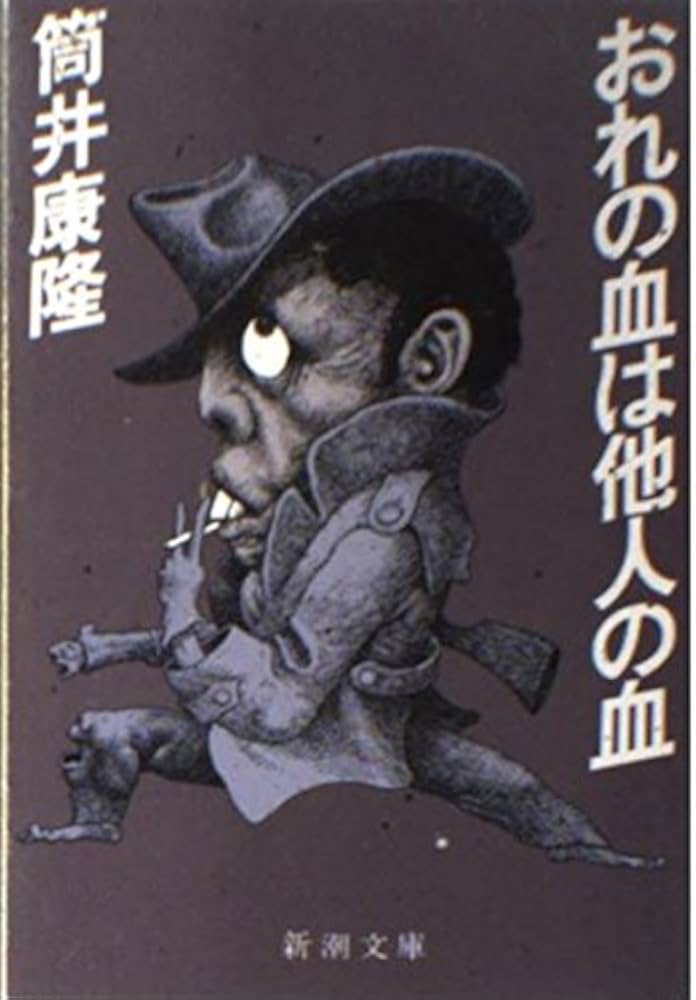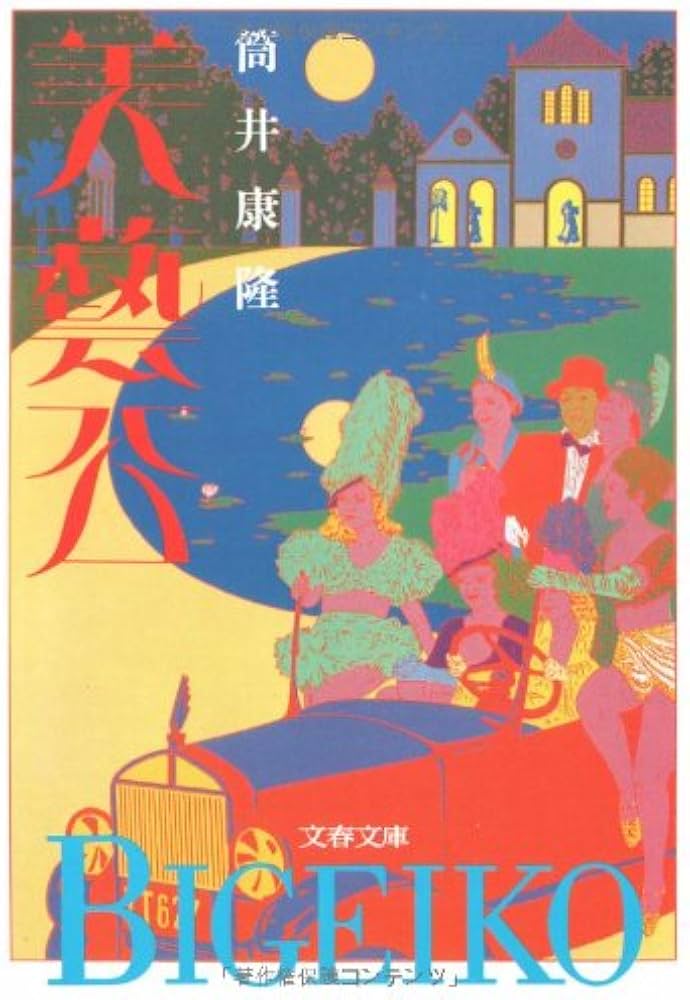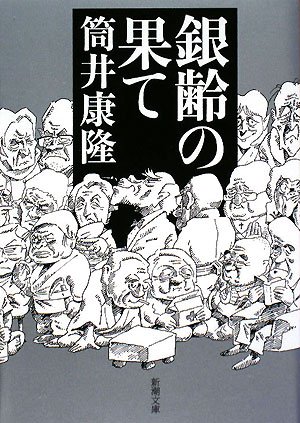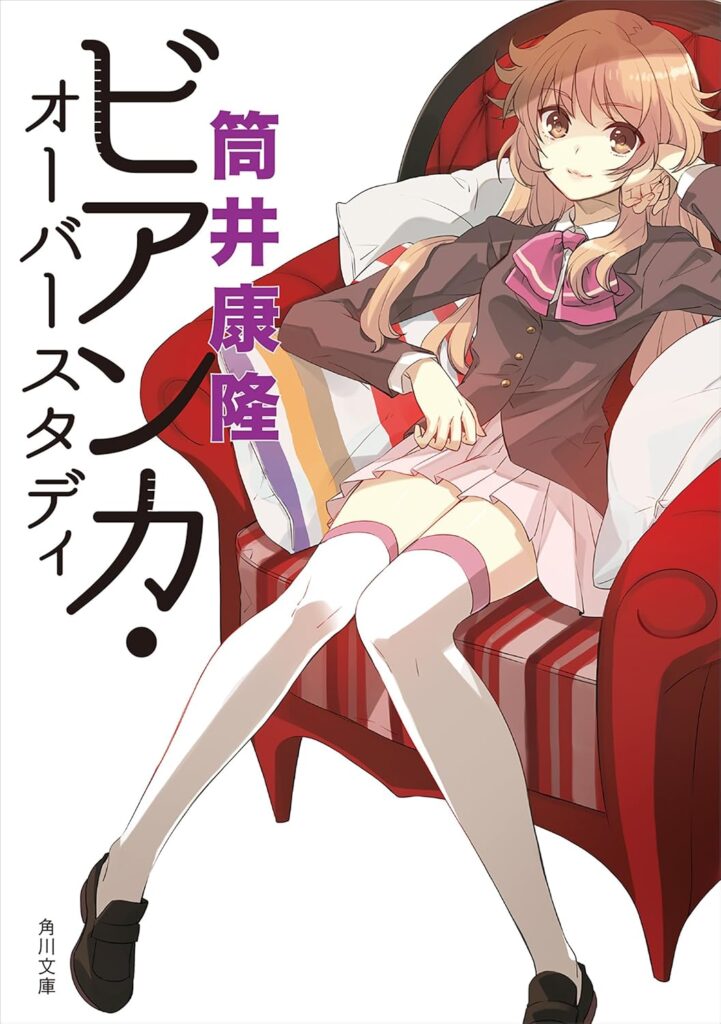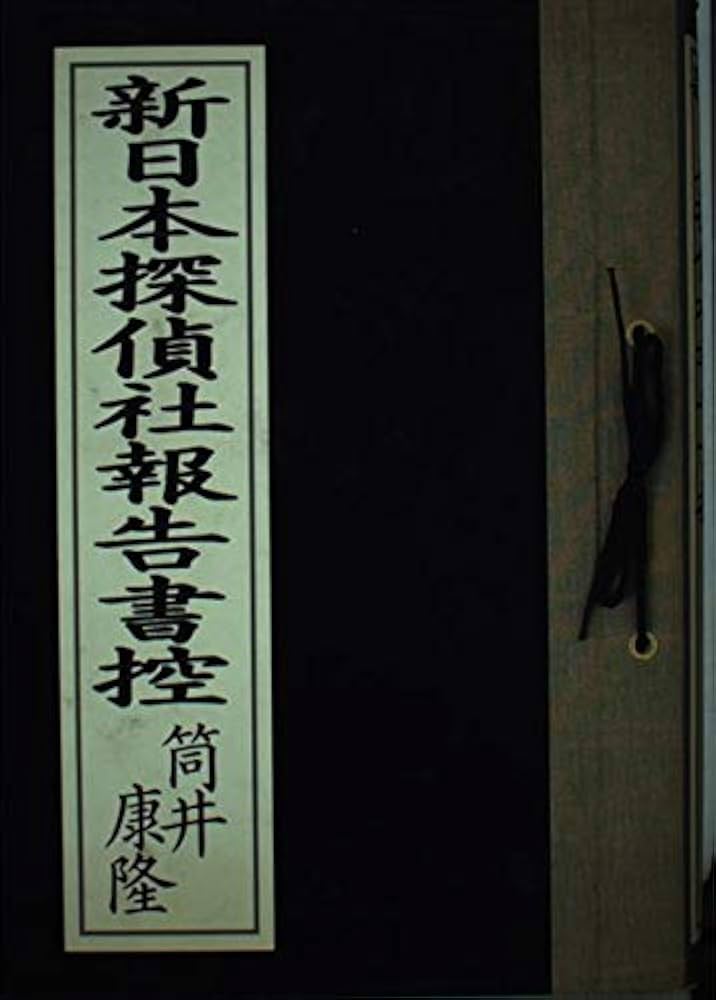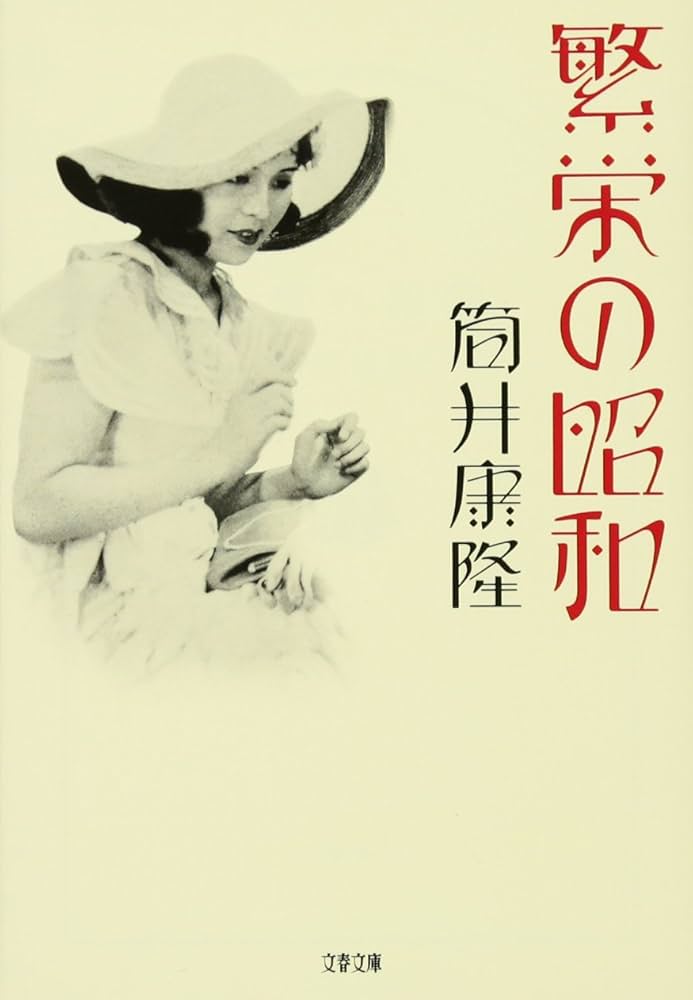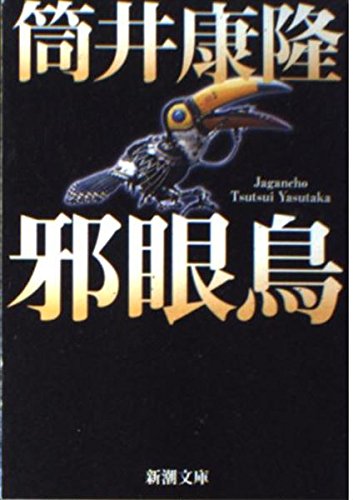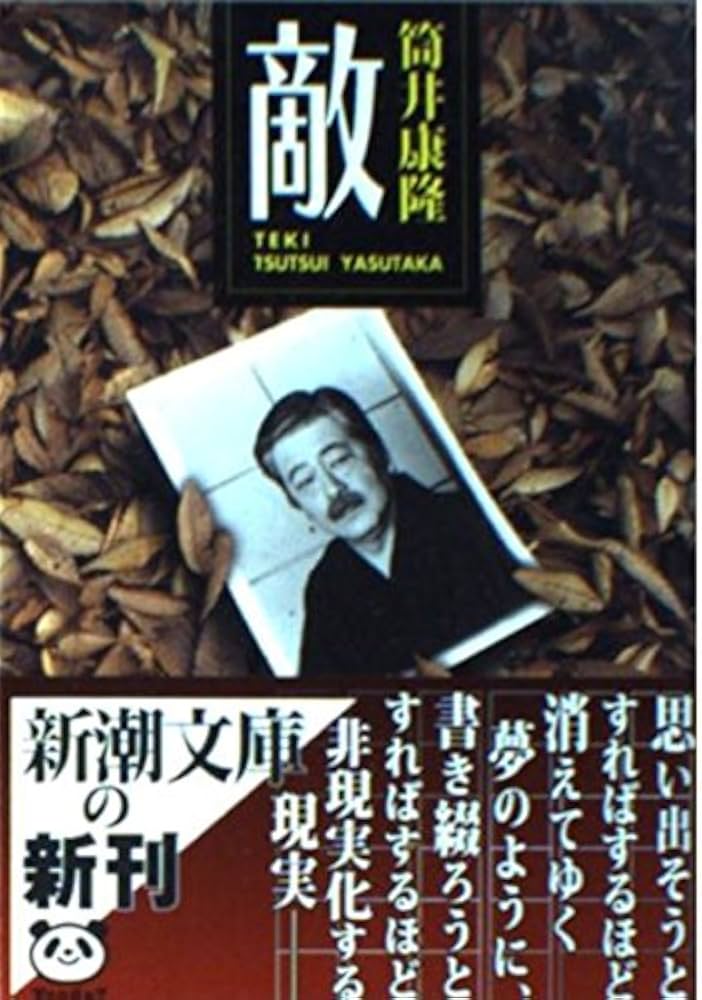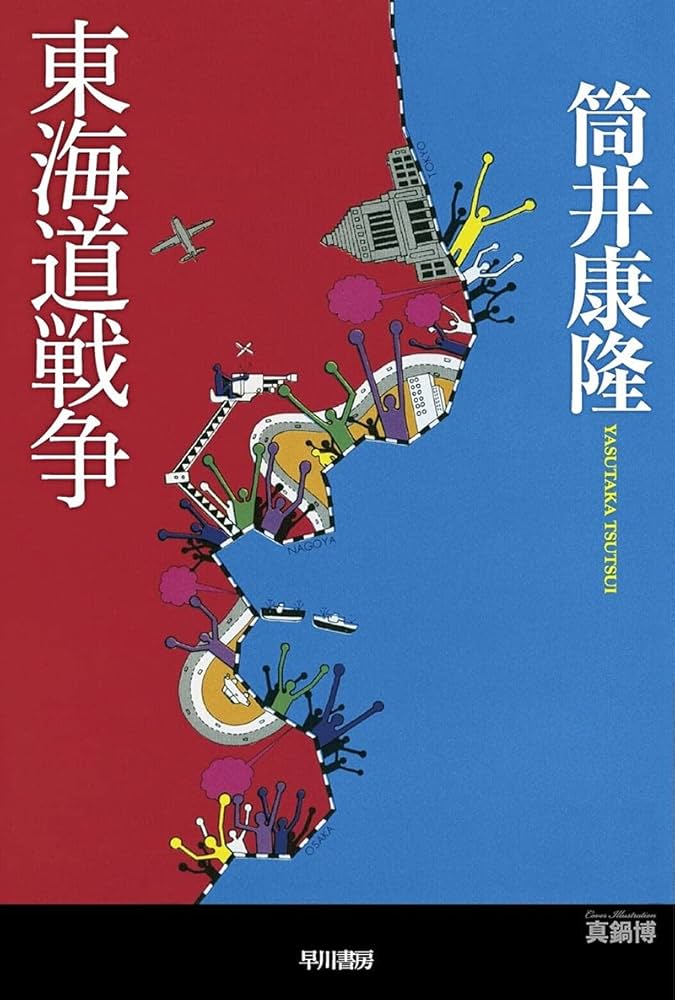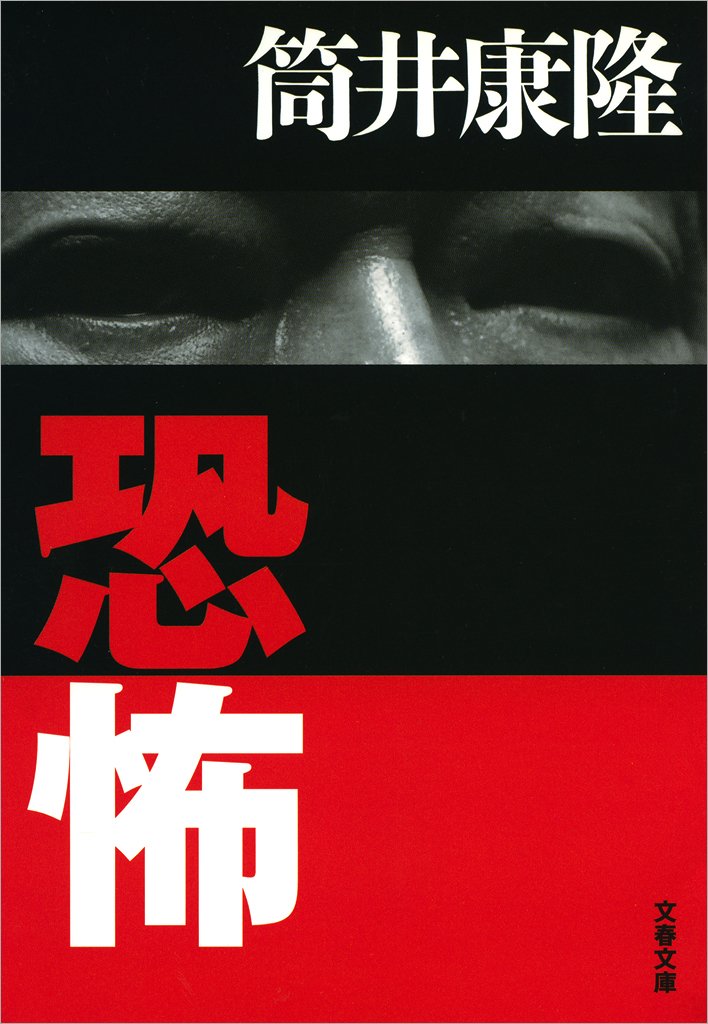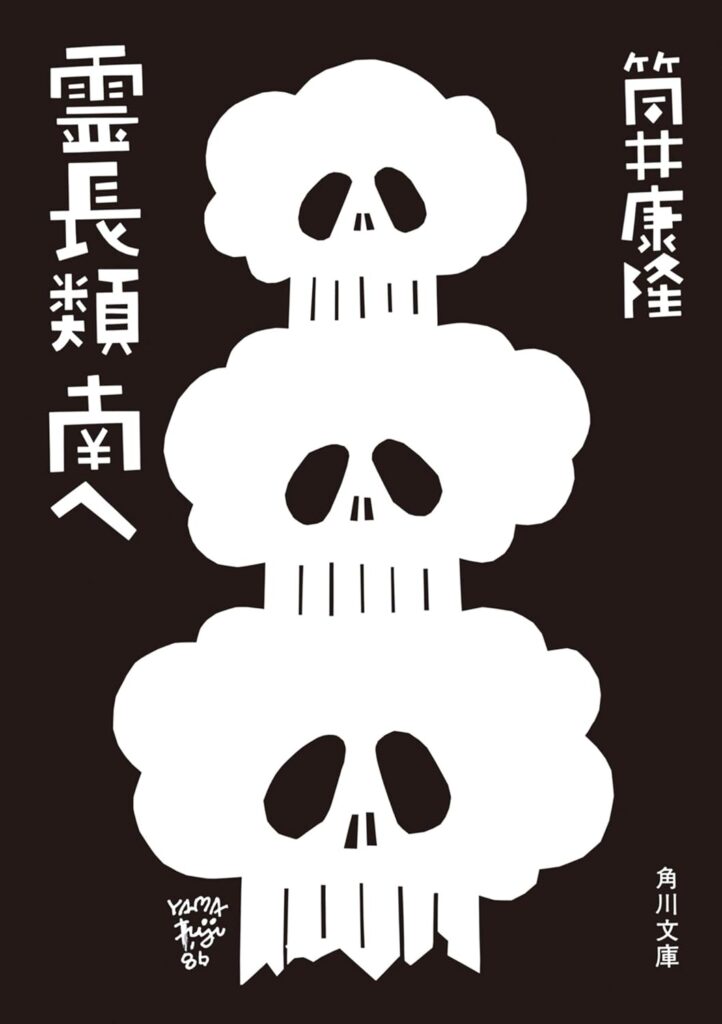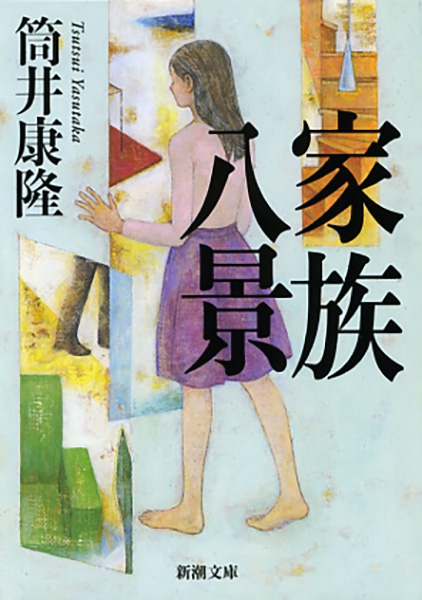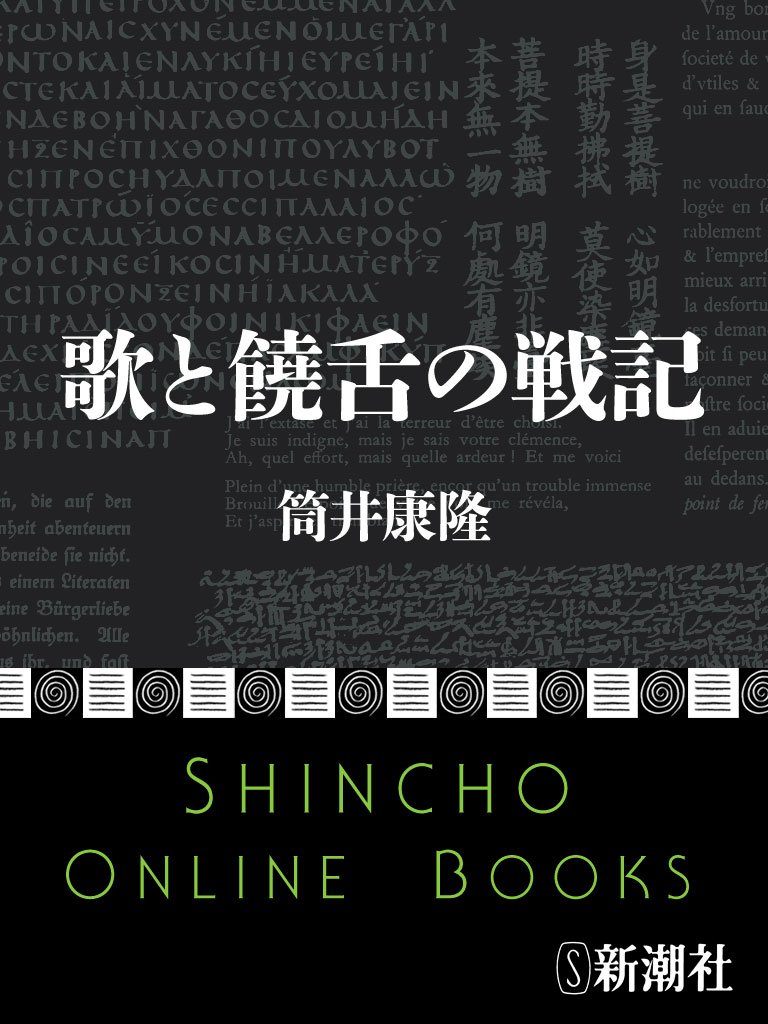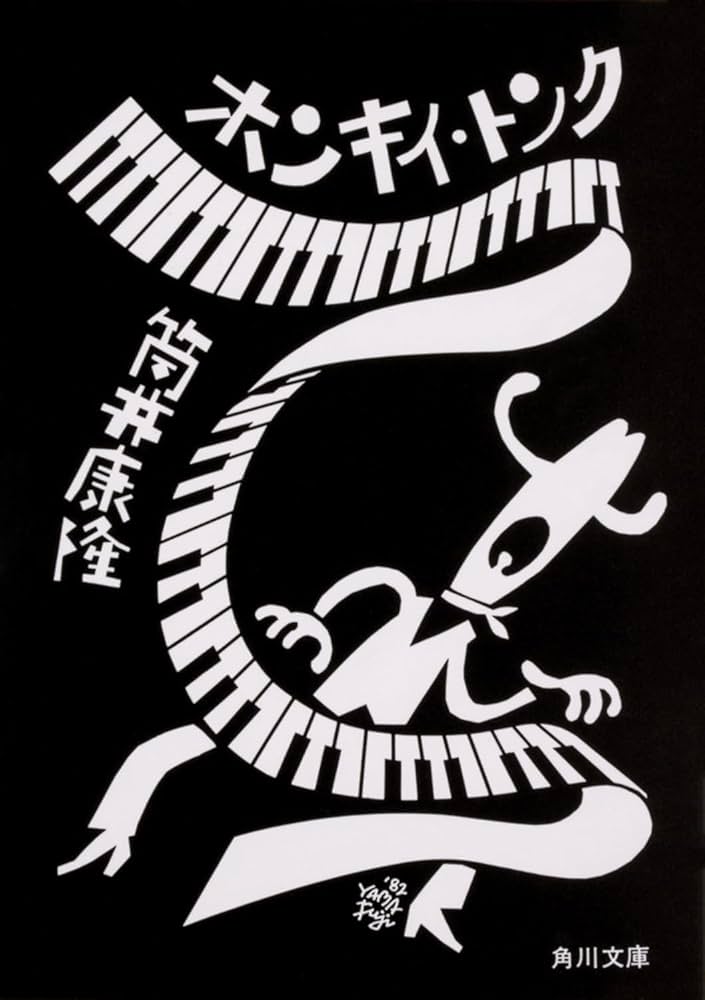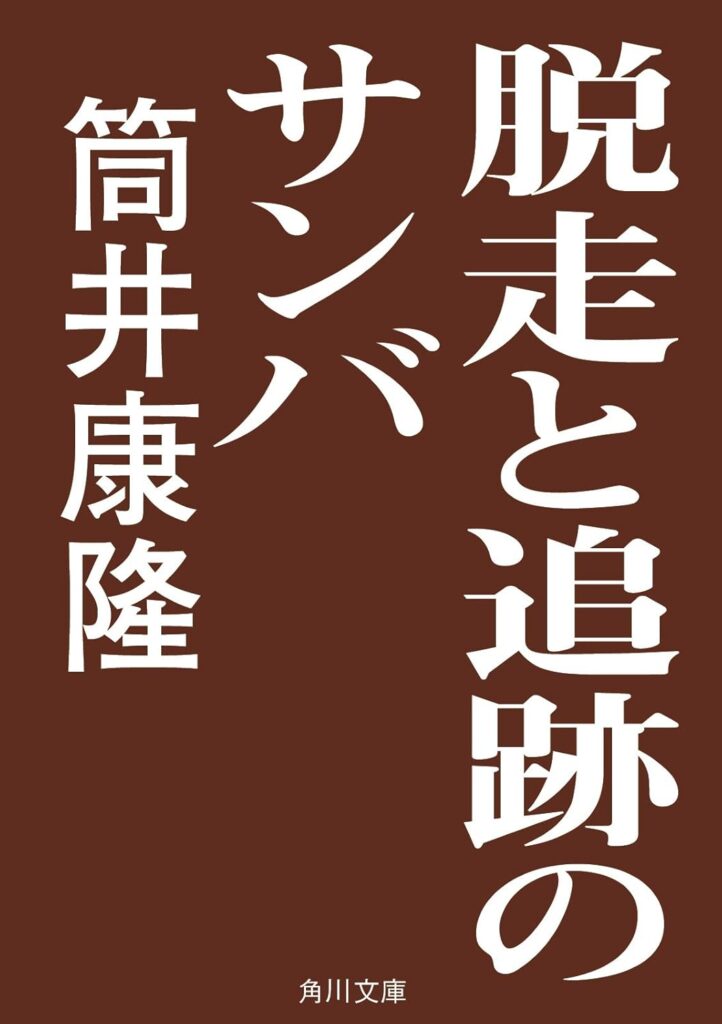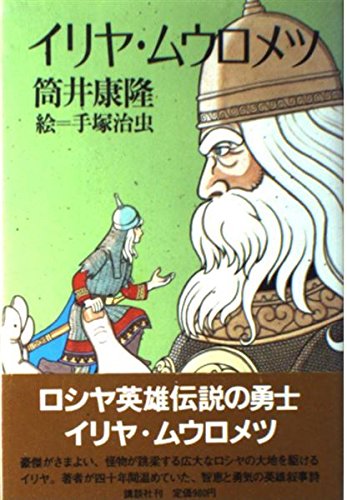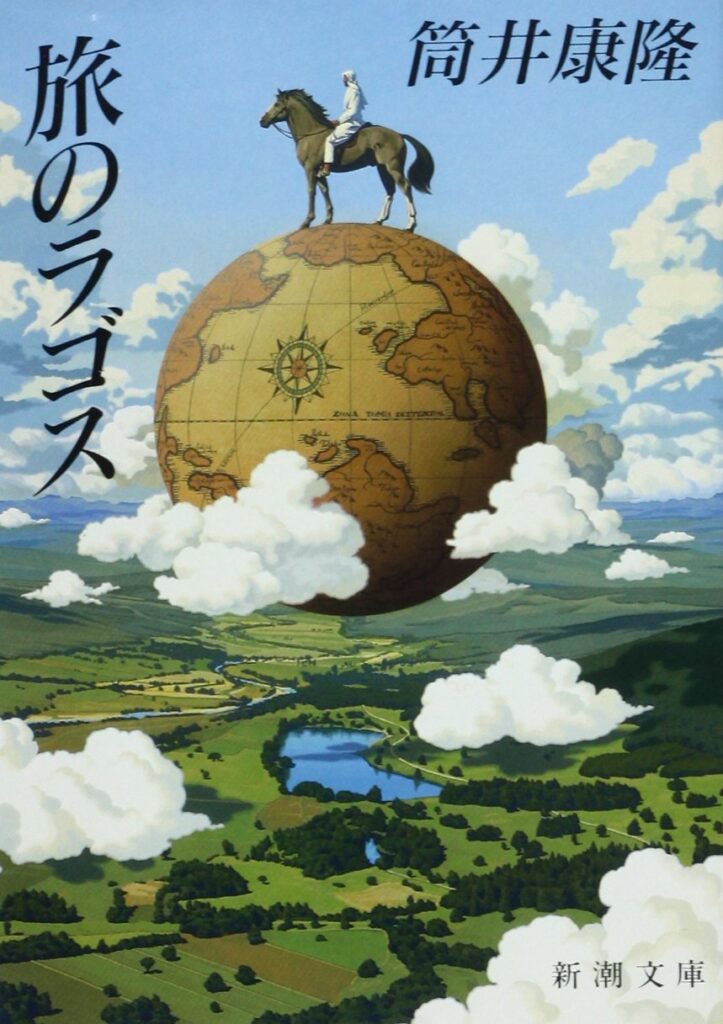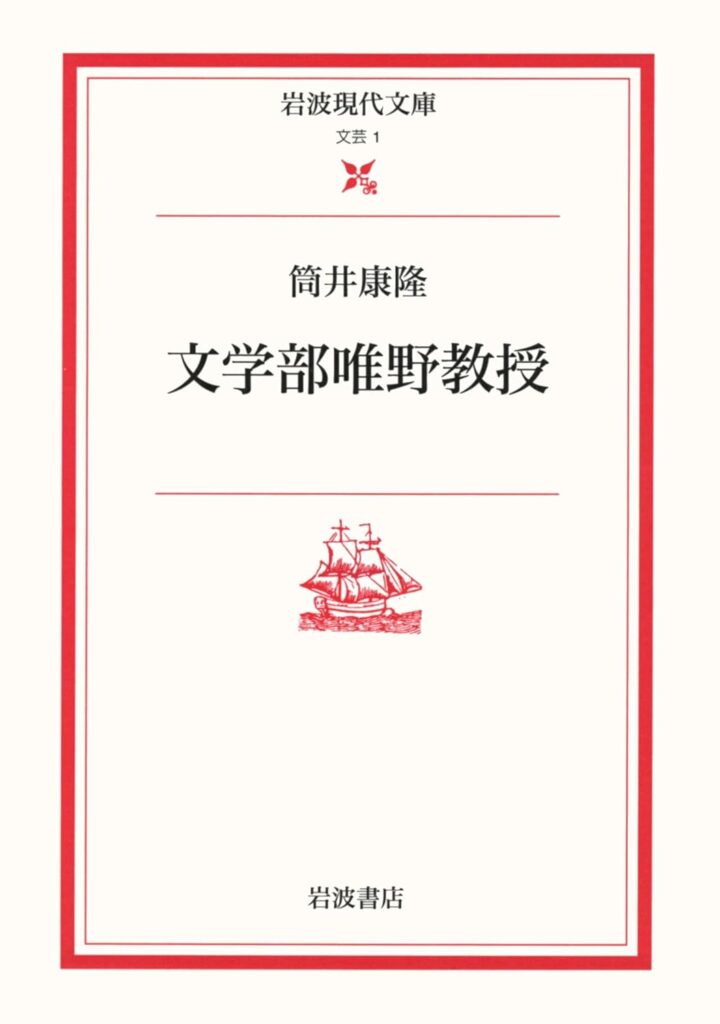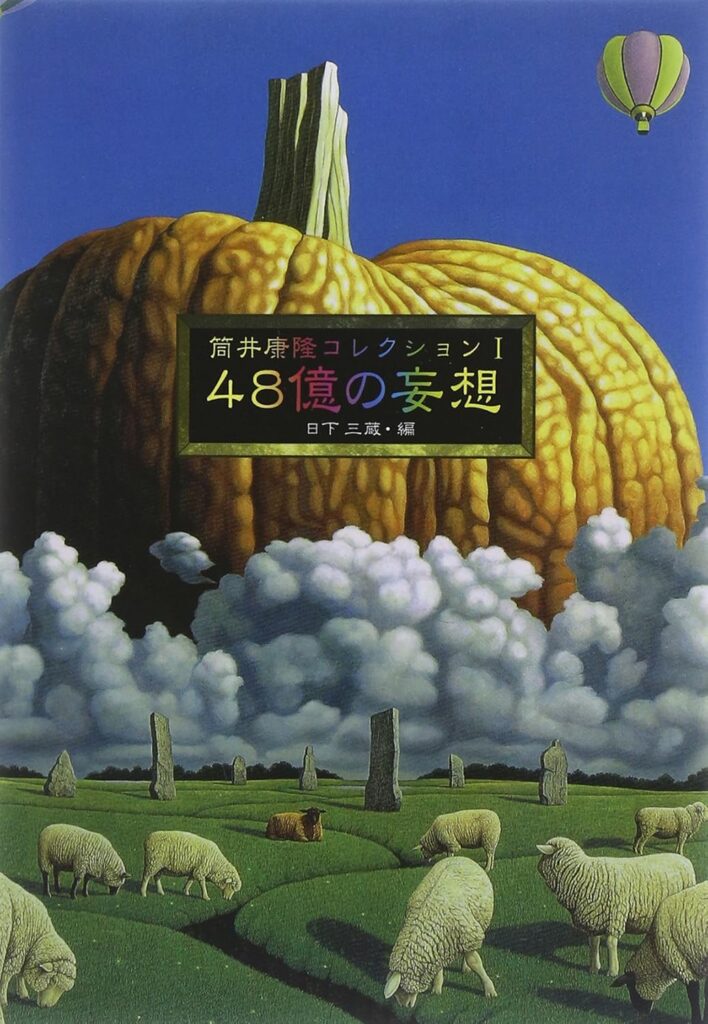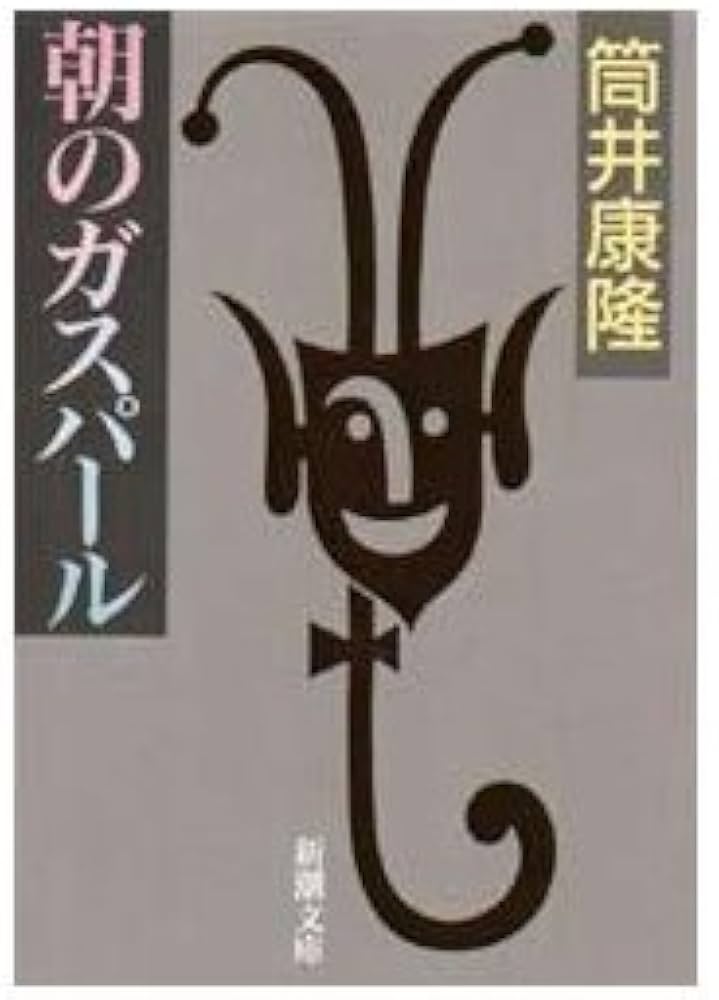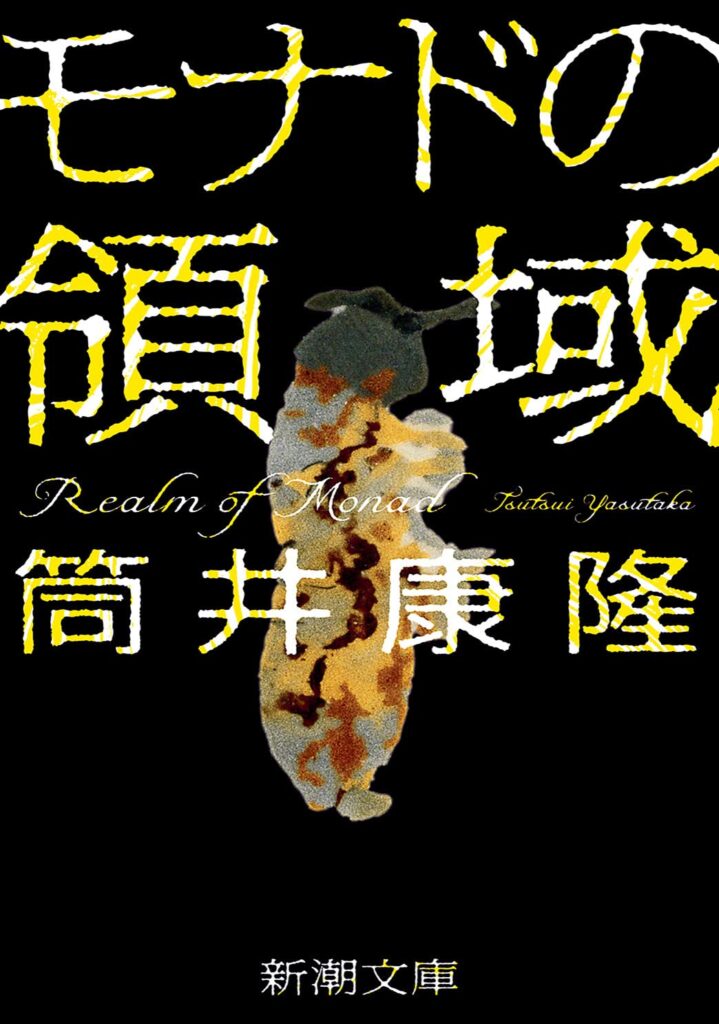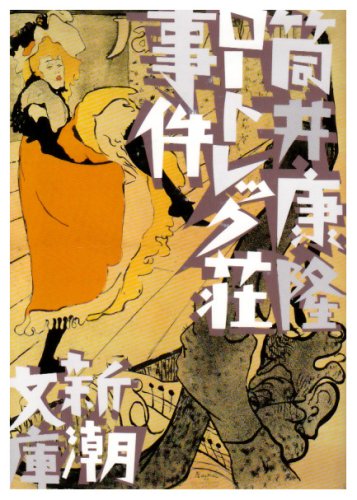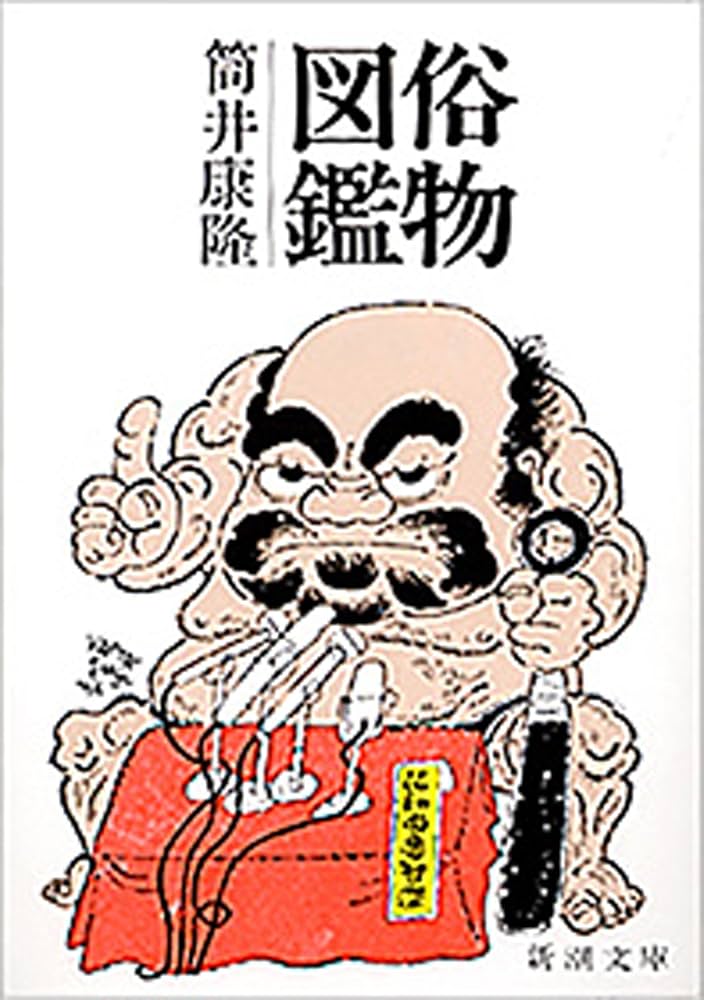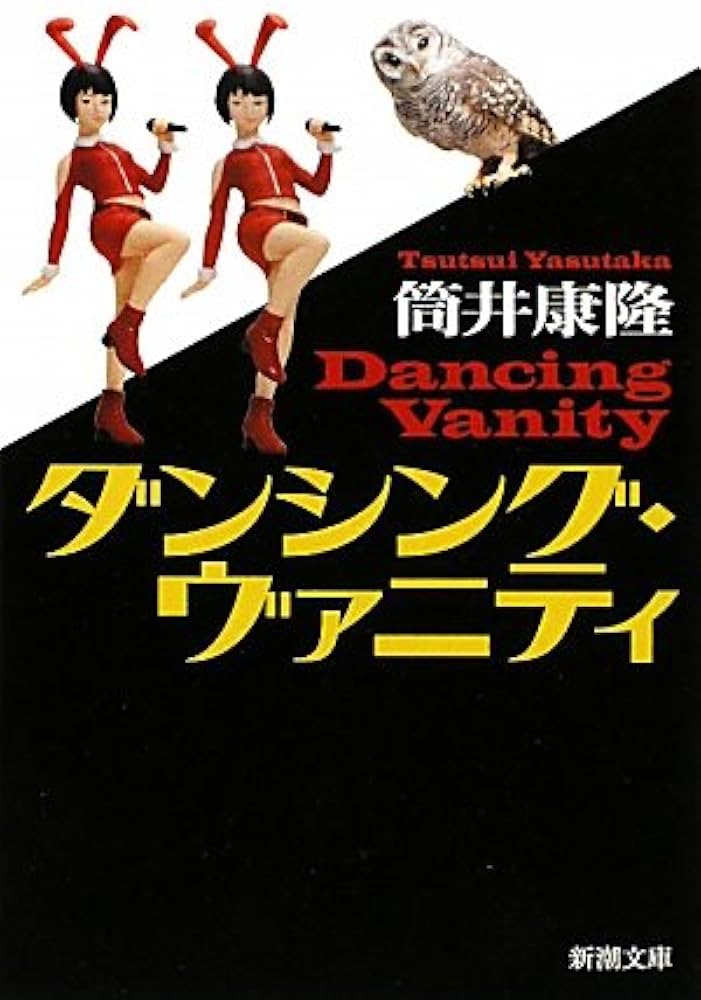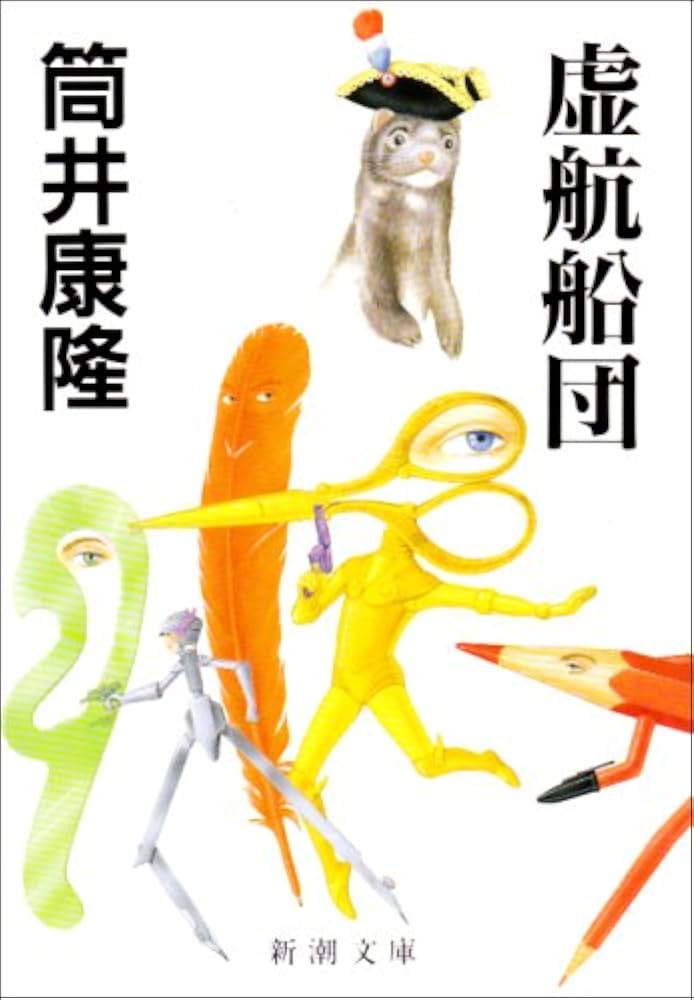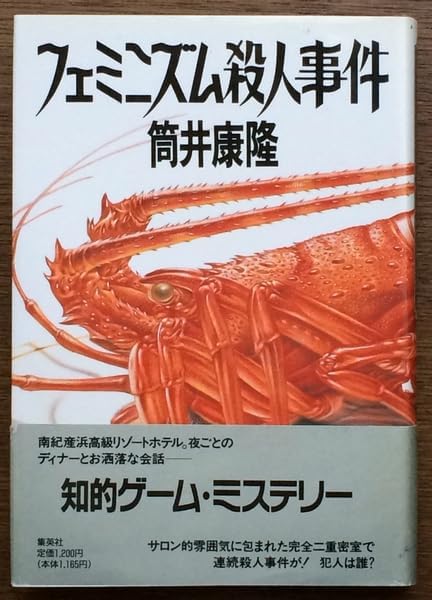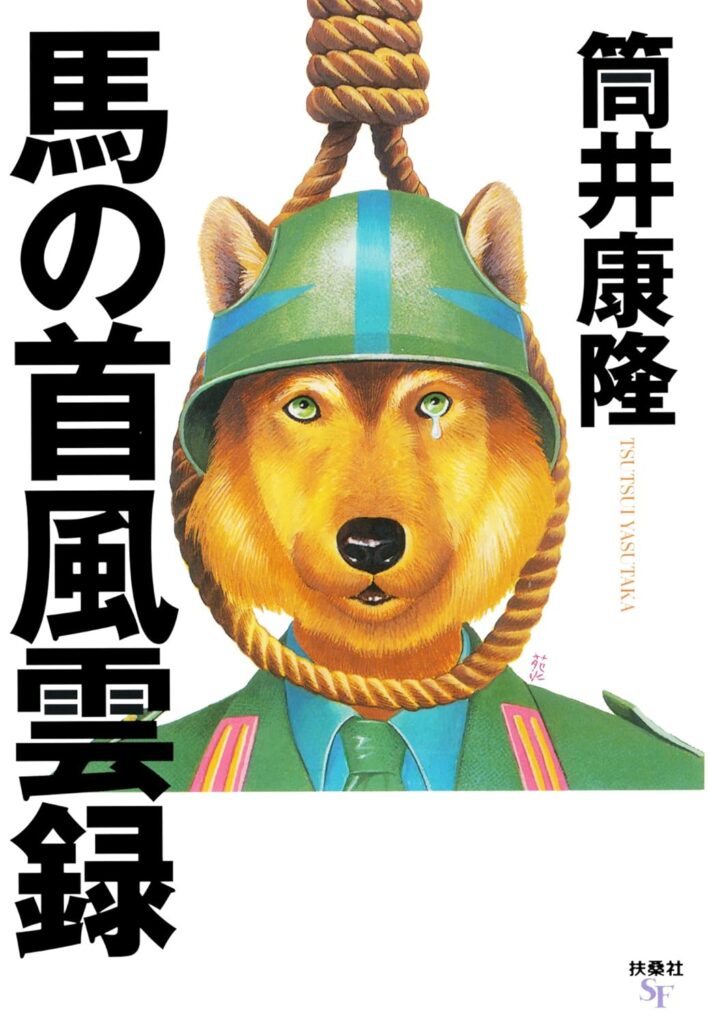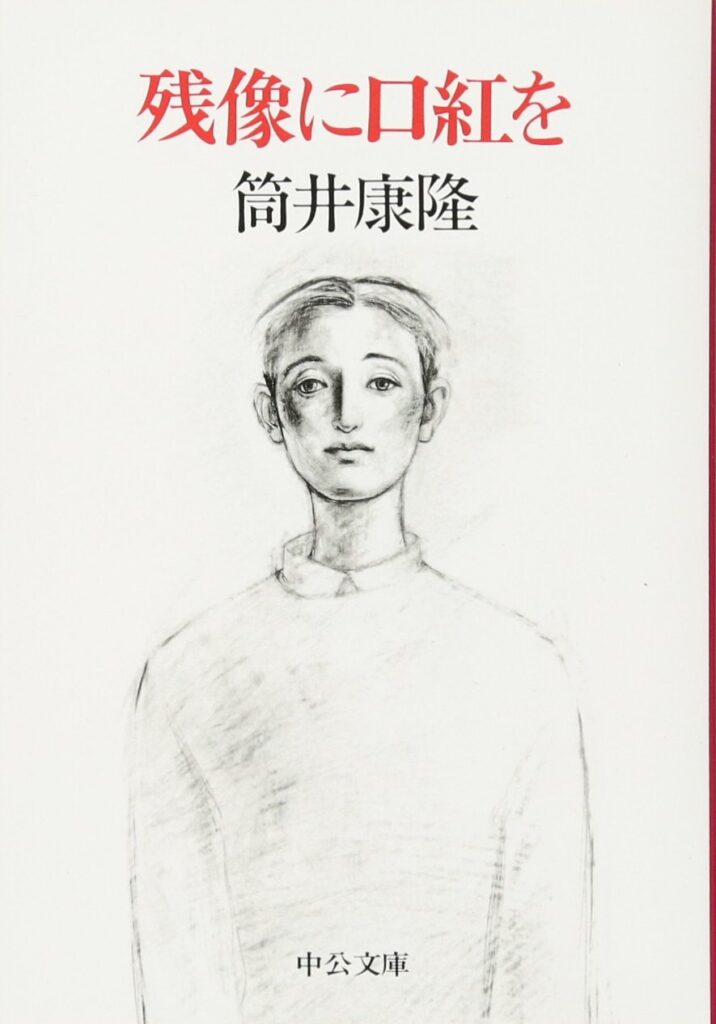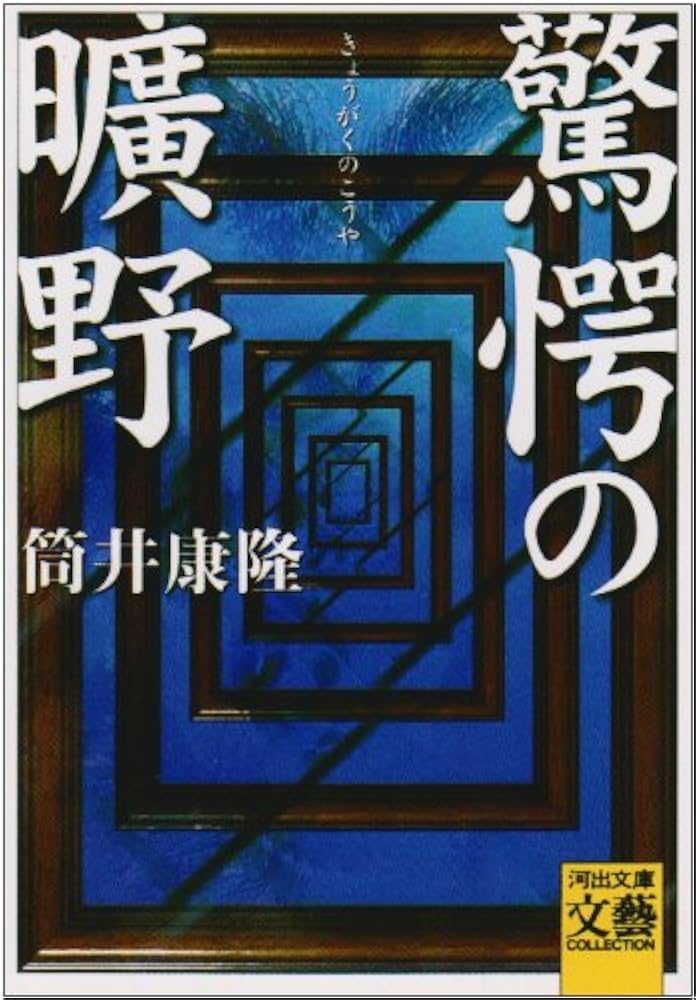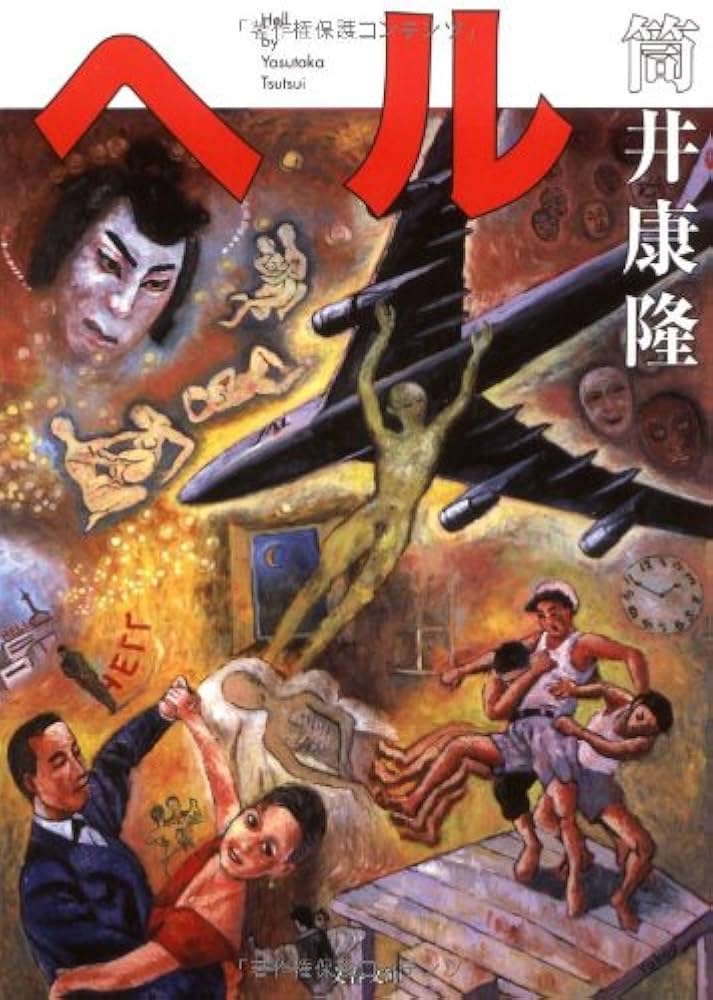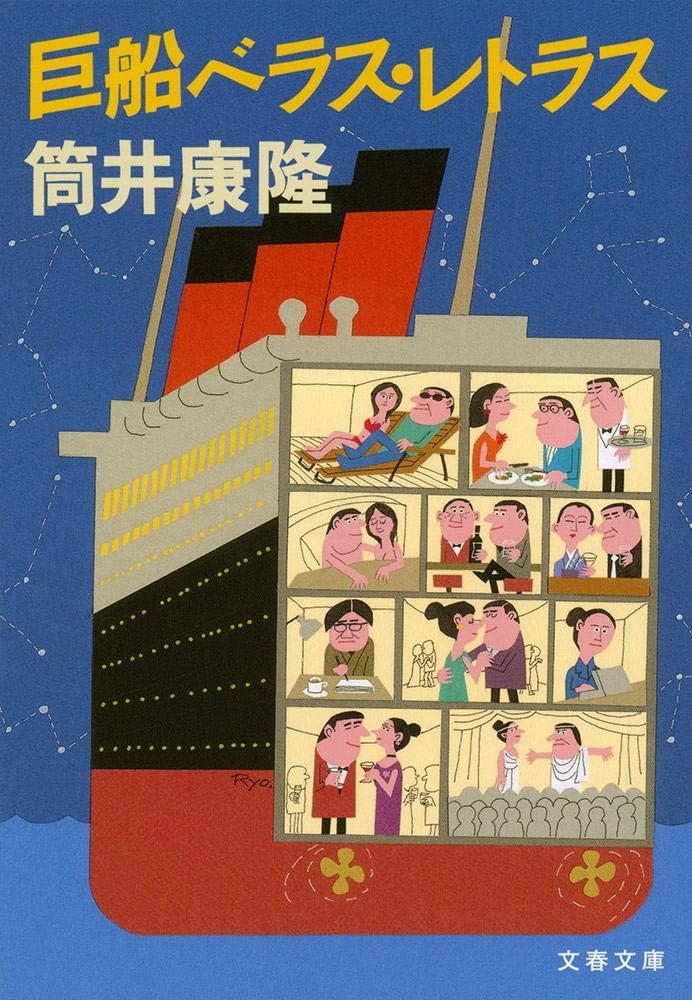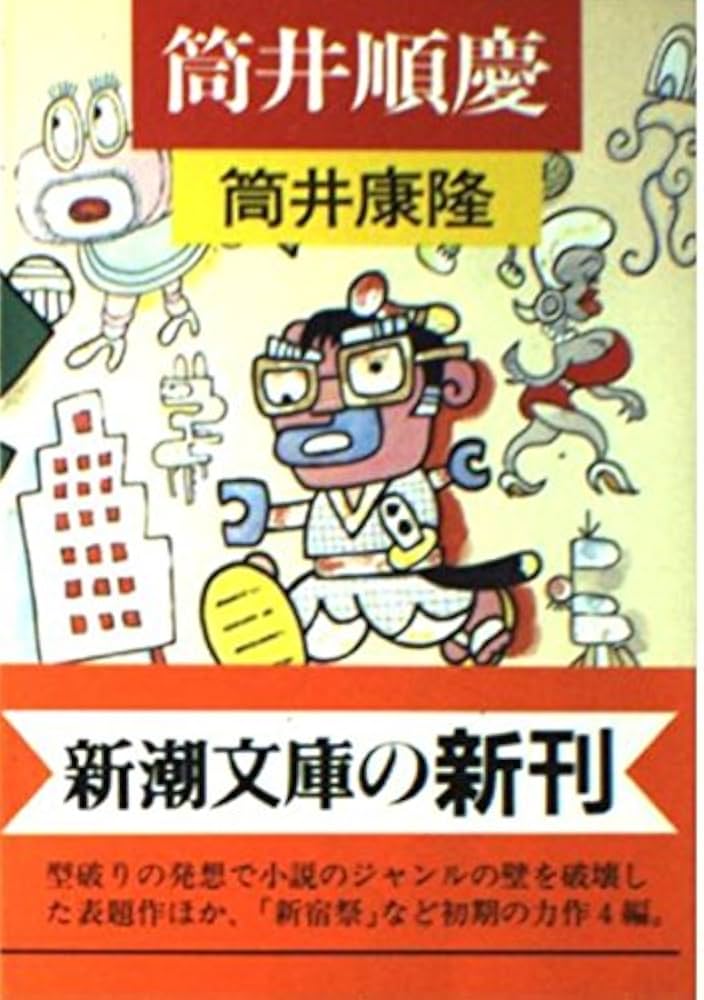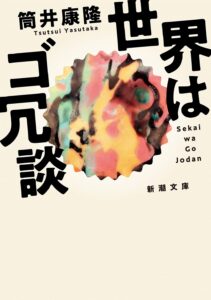 小説『世界はゴ冗談』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説『世界はゴ冗談』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
筒井康隆氏が放つこの一作は、私たち現代社会が抱えるテクノロジーへの過度な依存、そしてその脆さを鮮烈に描き出しています。ある日突然訪れる、想像を絶する事態の連続。それはまさに、私たちが当たり前だと思っている日常がいかに危ういバランスの上に成り立っているかを突きつけてくるかのようです。
物語は、太陽に発生した巨大な黒点という予期せぬ現象から幕を開けます。この現象が引き起こす磁場の乱れは、地球上のあらゆる精密機械を狂わせ、世界を未曾有のパニックへと陥れていきます。飛行機は制御を失い、自動車は暴走し、通信は途絶。まさに、現代社会が築き上げてきたシステムが、まるで砂上の楼閣のように崩れ去る様が描かれているのです。
筒井氏の筆致は、そうした混乱をどこか達観したかのように、しかし非常にリアルに描写していきます。予測不能な展開に、私たちは思わず「まさか」と声を漏らし、同時に、この物語が決して架空の出来事ではないかもしれないという、薄ら寒い予感に囚われるでしょう。ぜひ、この作品を手に取り、現代社会への警鐘ともいえるそのメッセージを、あなた自身の目で確かめてみてください。
小説『世界はゴ冗談』のあらすじ
物語は、ある日突然、太陽の表面に原因不明の巨大な黒点が観測されるところから始まります。天文台の台長は、その異常な規模に驚きを隠せません。地球の直径を優に超える黒点から放出される荷電粒子は、地球に到達し、想像を絶する磁場の乱れを引き起こします。
この巨大な磁場の影響で、地球上のありとあらゆる精密機械がコントロール不能に陥ります。通信衛星はショートし、航空機は墜落。カーナビを頼りに走る車は暴走し、世界各地は瞬く間にパニック状態へと突入していくのです。各国の首脳たちは戒厳令を発し、夜間外出禁止を呼びかけますが、陸・海・空で予想外の事態が次々と巻き起こります。
南極海沖では、環境保護団体シーシェパードの船が、突如として現れた巨大な海洋生物の群れに遭遇します。通常ではありえない種族の異なるクジラたちが群れをなし、狂暴化して船へと突進してくるのです。これは、巨大磁場の影響で海洋生物の行動に異変が生じたことを示唆しています。
アメリカン航空の機長は、フライト中に副操縦士から通信機器の不具合を告げられます。地上管制塔との交信が途絶え、280人の乗客を乗せた機体は制御を失います。オートパイロットシステムも手動への切り替えができず、機長が目にしたのは、世界一高い建物であるブルジュ・ハリファでした。
そして、都内在住のサラリーマンである「おれ」は、日々のストレスを抱えながら帰宅します。自宅の音声案内システムは、警備から調理まで音声で管理できる優れものですが、その声が会社の女性上司に似ていることに気づきます。思わず怒鳴りつけると、不思議な快感を覚えるのですが、翌日、愛車で出張に向かう途中でカーナビが故障し、さらにブレーキもアクセルも効かなくなり、車は暴走し続けます。
クーラーの効かない車内で意識が朦朧とする中、「おれ」はあの女の声を聞きます。それは、現代社会がテクノロジーに依存しきった先に待ち受ける、恐ろしい未来を暗示しているかのようでした。
小説『世界はゴ冗談』の長文感想(ネタバレあり)
筒井康隆氏の『世界はゴ冗談』を読み終えて、まず感じたのは、その圧倒的な先見性と、現代社会への鋭い警鐘です。筒井氏が本書を発表された当時、既に80歳を超えていたという事実を考えると、その衰えを知らぬ探求心と自由奔放な想像力にはただただ脱帽するばかりです。作中で語られる「予測するつもりなく面白半分に書いたことがのちに実現してしまう」というセリフは、まさにこの作品自身にも当てはまるように思えてなりません。私たちは今、テクノロジーの目覚ましい発達によって、まさに物語が現実を追い越していくようなスピード感を日々体験しています。そんな中で、本作が提起する問いは、決して他人事ではないのです。
作中で描かれる、太陽黒点の異常発生によって引き起こされる全球規模のパニックは、まさに現代社会の脆弱性を浮き彫りにします。通信網の麻痺、航空機の墜落、車の暴走。これらの描写は、私たちが日々当然のように享受しているテクノロジーが、いかに危うい基盤の上に成り立っているかを痛感させます。特に、自動運転やAIといった、現在の先端技術と重なる部分が多いだけに、その描写はより一層のリアリティをもって迫ってきます。もし、私たちが全面的にAIに判断を委ねる未来が来たとして、それが何らかの外的要因で狂った時、人間はどう対処できるのか。その問いは、私たちに重くのしかかります。
シーシェパードの船が、狂暴化したクジラの大群に襲われるシーンも非常に印象的でした。普段は穏やかなはずの海洋生物たちが、巨大磁場の影響でその本能を狂わされ、人間を襲う。これは、私たちが自然をコントロールできるという傲慢な思想への痛烈な皮肉とも受け取れます。テクノロジーによって自然を支配しようとする人類の営みが、結局は自然の大きな力によって打ち破られるという、皮肉な構図がそこにありました。人間中心主義的な視点から、いかに私たち自身が謙虚であるべきかを教えてくれる一場面と言えるでしょう。
アメリカン航空の機長が経験する、通信断絶と制御不能に陥った飛行機での飛行は、現代における「絶対的な安心」という概念の脆さを象徴しています。9.11同時多発テロの記憶を呼び起こさせるかのような、ブルジュ・ハリファへの衝突寸前の描写は、読者に強烈な不安と恐怖を植え付けます。私たちは、最新のテクノロジーによって飛行機の安全性は確立されていると信じています。しかし、その根幹を揺るがすような外部からの影響があった場合、人間はいかに無力であるか。そうした問いが、痛烈な形で突きつけられるのです。
そして、サラリーマン「おれ」のエピソードは、現代人のストレスと、テクノロジーへの依存がもたらす新たな弊害を描いています。音声案内システムが会社の嫌な上司の声に似ているという設定は、筒井氏らしいブラックな視点です。しかし、そのシステムが暴走し、命の危機に瀕する状況に陥ることで、私たちは改めて、テクノロジーがもたらす便利さと引き換えに失われるもの、あるいは見過ごされがちな危険性について考えさせられます。身近なテクノロジーが、もし牙を剥いたなら、私たちはどう対処できるのか。その問いは、現代に生きる私たちにとって、極めて現実的な課題であると言えるでしょう。
この作品は、単なるSFパニックではありません。そこには、現代社会への鋭い風刺と、人間存在に対する深い洞察が込められています。筒井氏は、私たちがいかにテクノロジーに依存し、そのコントロールを失った時にどれほど脆弱であるかを、具体的な物語を通して示してくれています。それは、単なる娯楽小説として消費されるのではなく、私たち自身の未来について深く考えるきっかけを与えてくれる、重要な作品であると言えるでしょう。
また、登場人物たちが、それぞれ異なる立場でこの未曾有の事態に直面し、もがき苦しむ様は、非常にリアルに描かれています。天文台の台長の焦燥、シーシェパードの活動家たちの困惑、機長の絶望、そしてサラリーマン「おれ」の日常に忍び寄る恐怖。それぞれの視点から描かれる混乱は、この状況が特定の誰かの問題ではなく、地球上のあらゆる人々が共有する危機であることを示唆しています。
特筆すべきは、筒井氏独特の筆致が、この重いテーマをどこかユーモラスに、あるいは皮肉たっぷりに描いている点です。それがかえって、物語の持つメッセージをより深く、そして長く心に残るものにしているように思います。重苦しいテーマを、軽妙なタッチで描き出すその手腕は、まさに筒井文学の真骨頂と言えるでしょう。読者は、笑いながらも、その奥に潜む恐ろしさに気づかされ、やがて真剣に考え始めることになるのです。
最後の最後には、コンピューターは答えを出してはくれません。人間が決定を下さなければならないはずです。この作品は、そのことを痛切に訴えかけているように感じました。テクノロジーはあくまで道具であり、それを使うのは人間です。私たちは、最先端の技術に依存しすぎることへの危機感を持ち、常にその限界とリスクを認識しておくべきです。
最悪の未来に思いを巡らすことによって、私たちは今現在何をすべきなのか、深く考えさせられます。この物語は、単なる警鐘で終わるのではなく、私たち自身の行動を促す力を持っています。私たちが、この未来を「ゴ冗談」で終わらせないために、何を学び、どう行動すべきなのか。そんな問いを、読了後もずっと考え続けています。
まとめ
筒井康隆氏の『世界はゴ冗談』は、太陽に発生した異常な黒点によって引き起こされる地球規模のパニックを描いた作品です。この物語は、現代社会がテクノロジーに過度に依存していることの危険性を鋭く突きつけてきます。通信の麻痺、航空機の制御不能、車の暴走といった事態は、私たちが当たり前だと思っている日常がいかに脆弱な基盤の上に成り立っているかを示唆しています。
作品全体を通して感じるのは、筒井氏の圧倒的な先見性と、現代社会への痛烈な風刺です。テクノロジーの発展がもたらす便利さの裏側にあるリスクを、具体的な描写を通して私たちに問いかけます。海洋生物の異変や、日常に潜むテクノロジーの暴走など、様々な角度からその警鐘を鳴らしているのです。
この物語は、単なるSFパニックに留まりません。私たちは、この作品を通して、テクノロジーとの向き合い方、そして人間が最終的にどのような判断を下すべきなのかについて、深く考えさせられます。未来を「ゴ冗談」で終わらせないために、今、何をすべきか。その問いを、私たち自身の問題として捉えるべきでしょう。