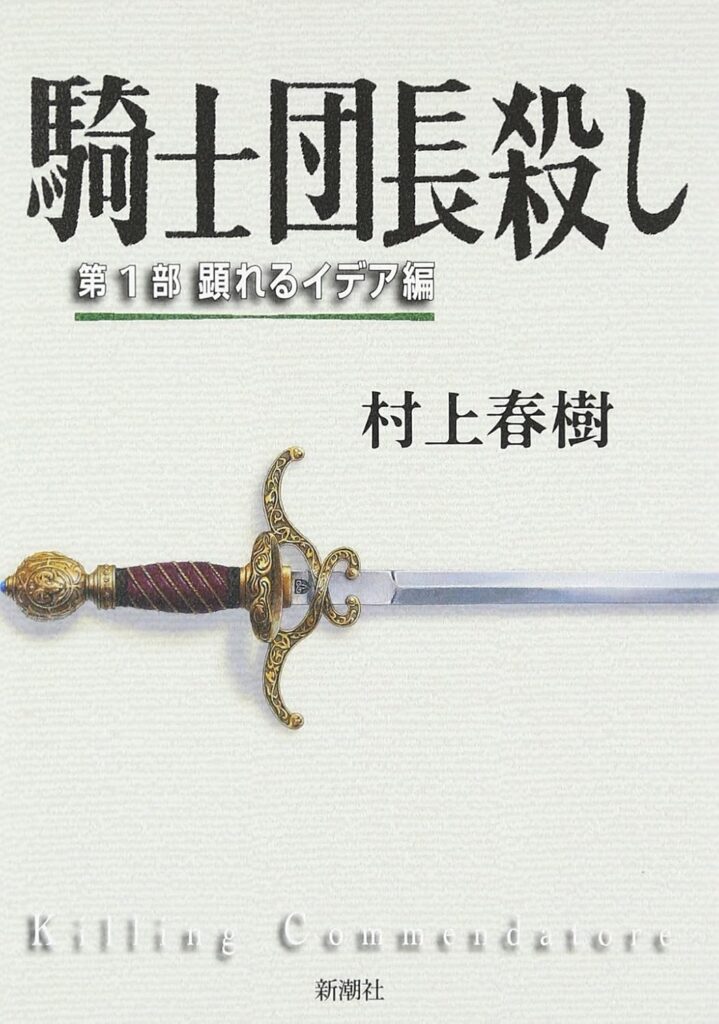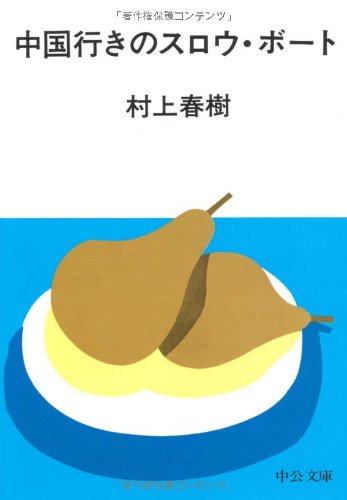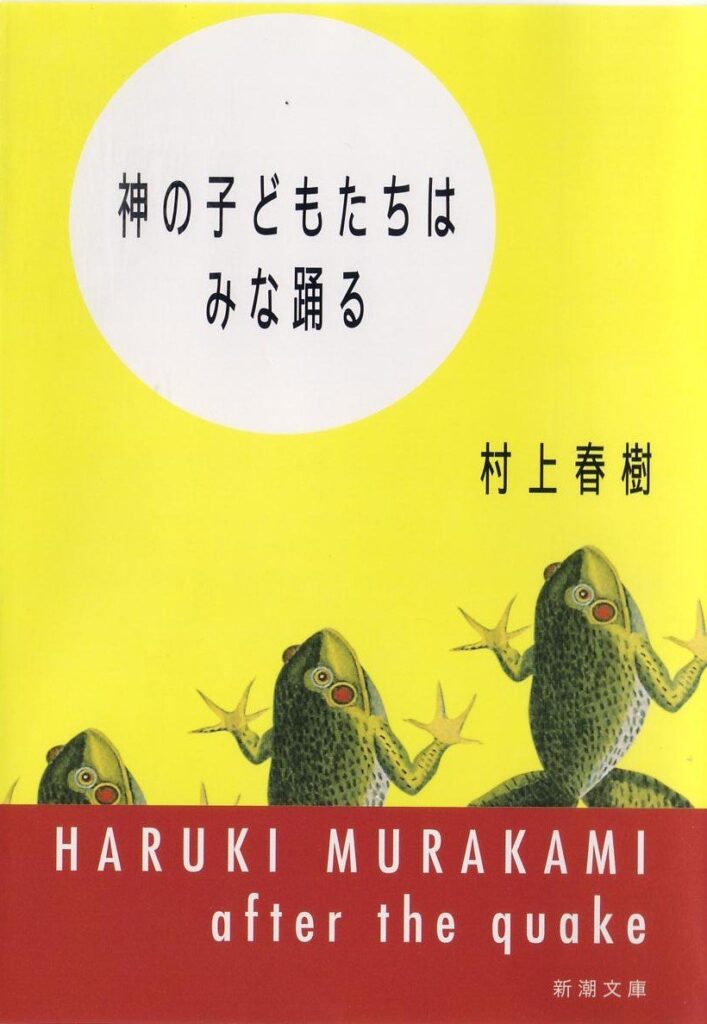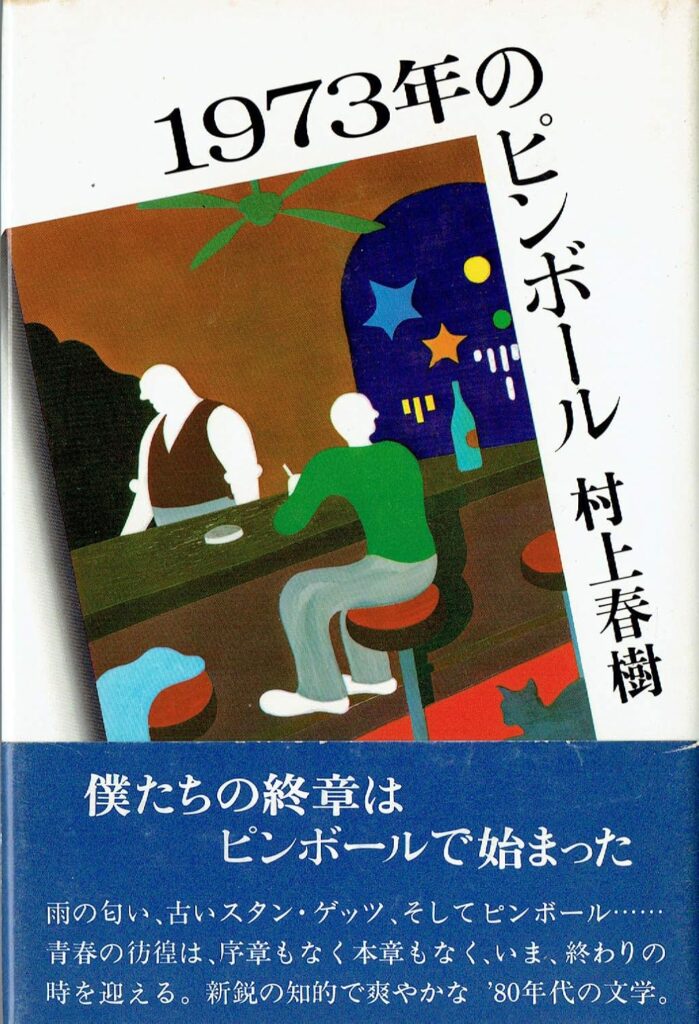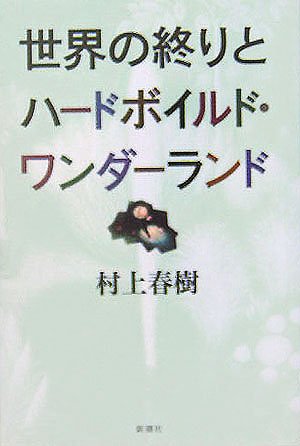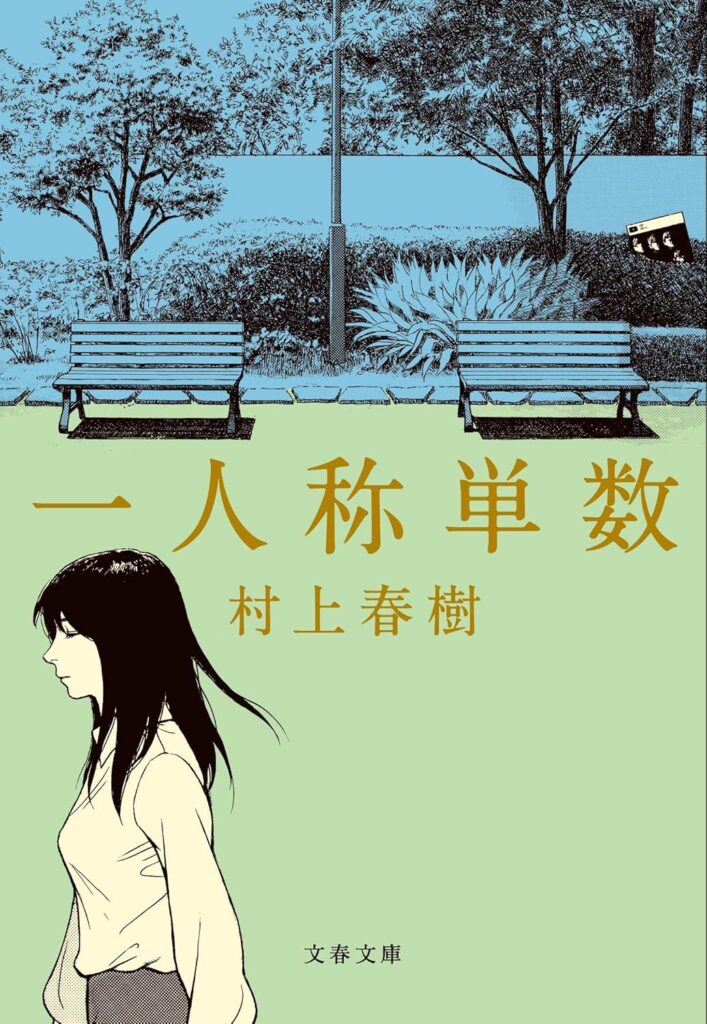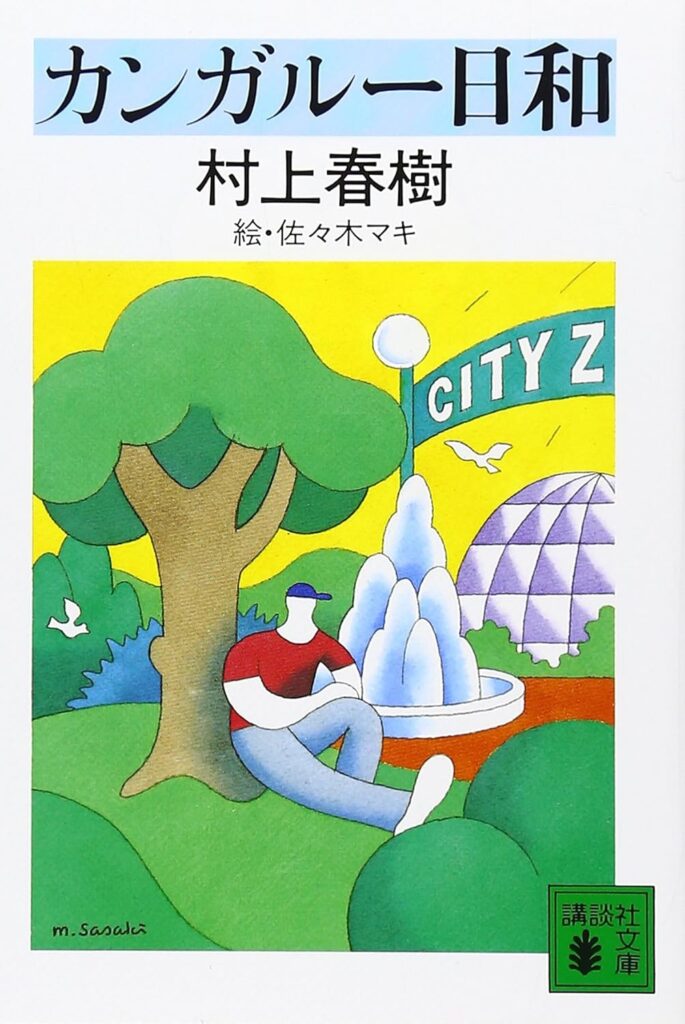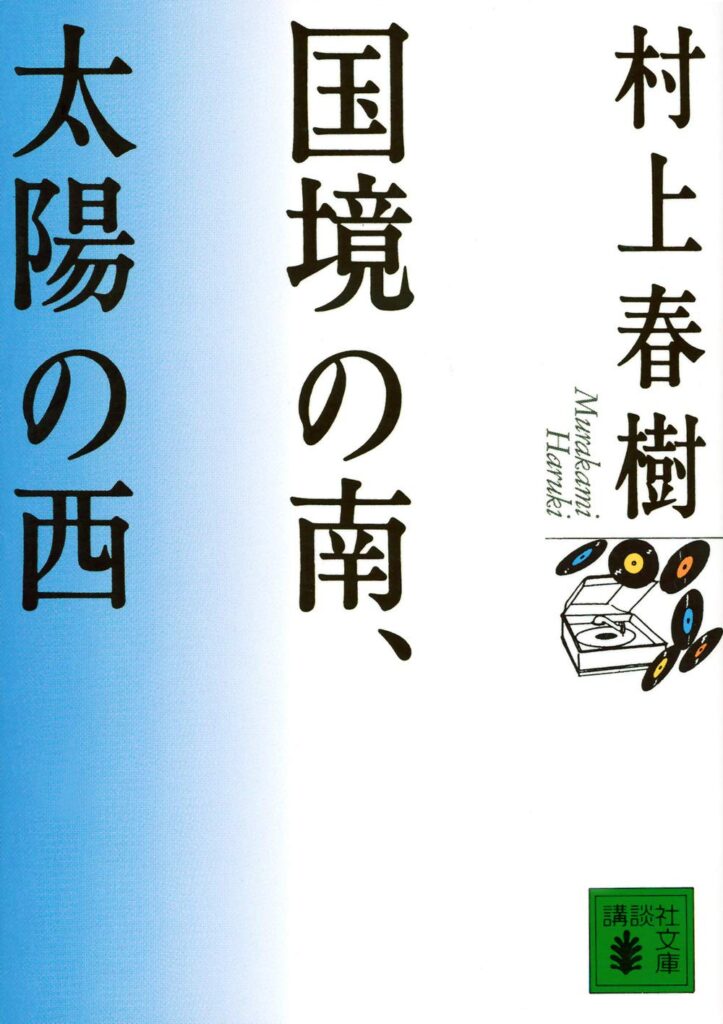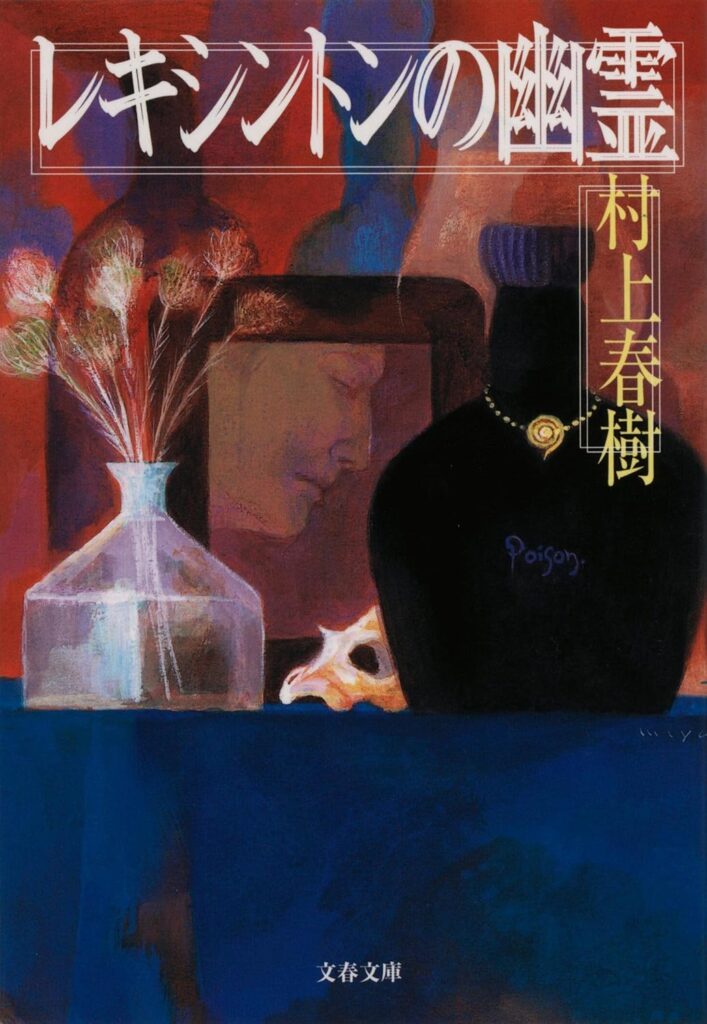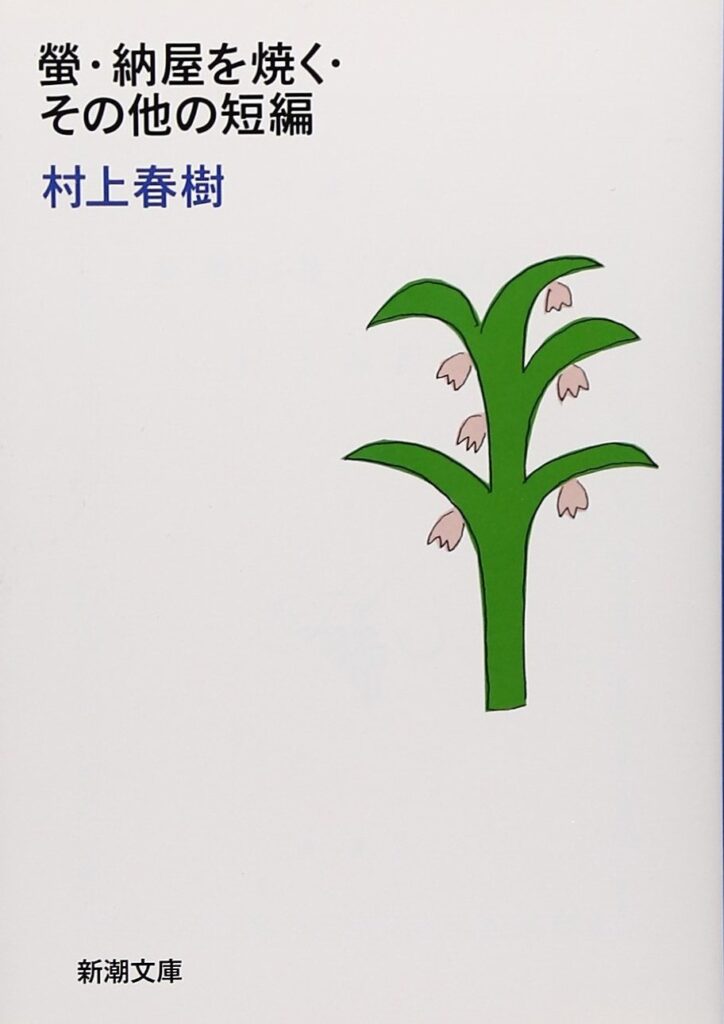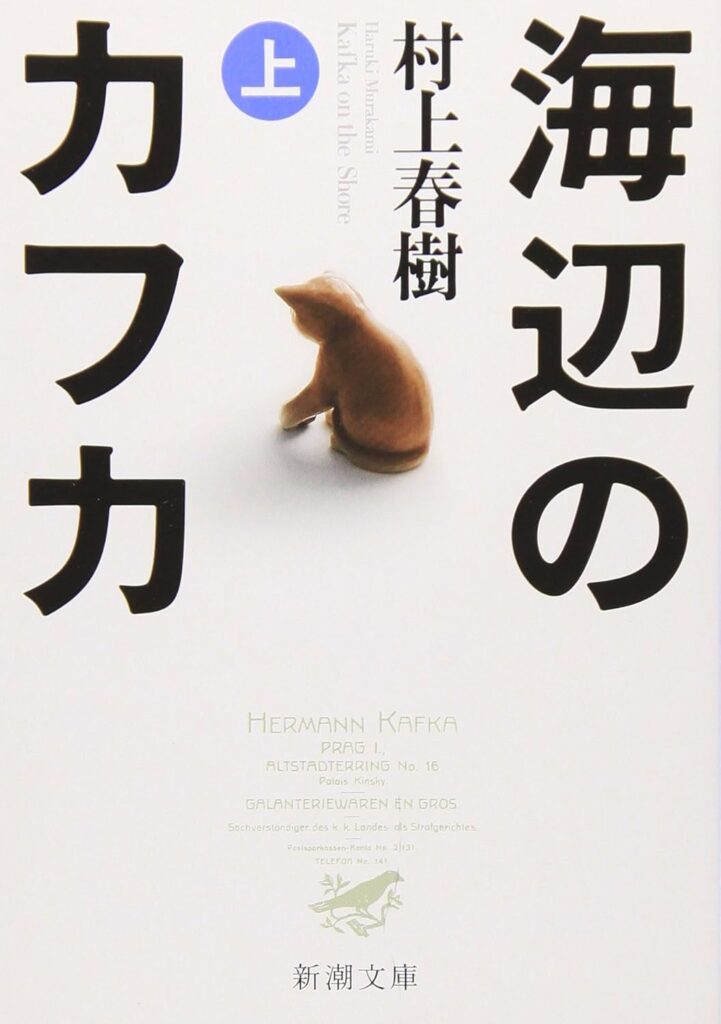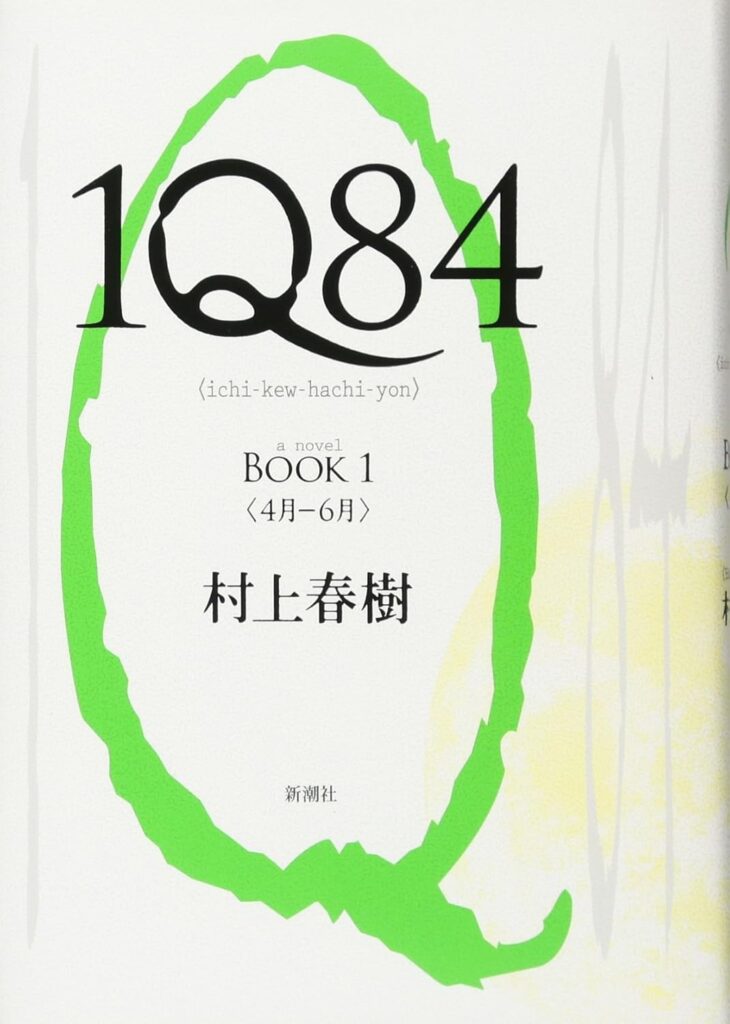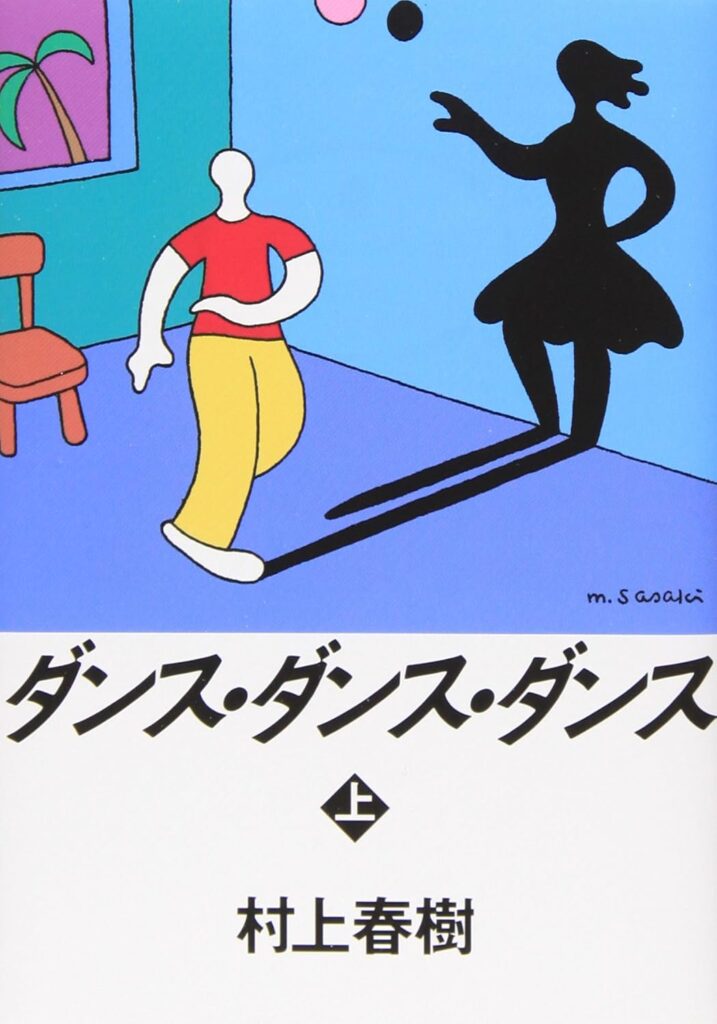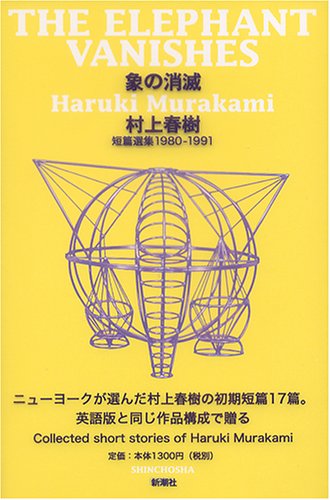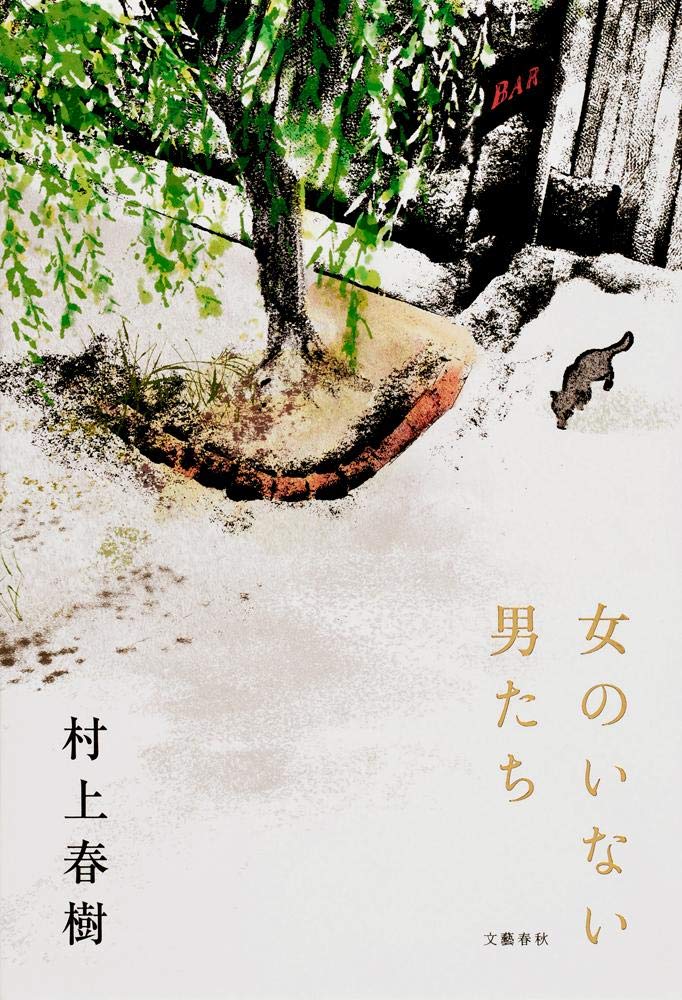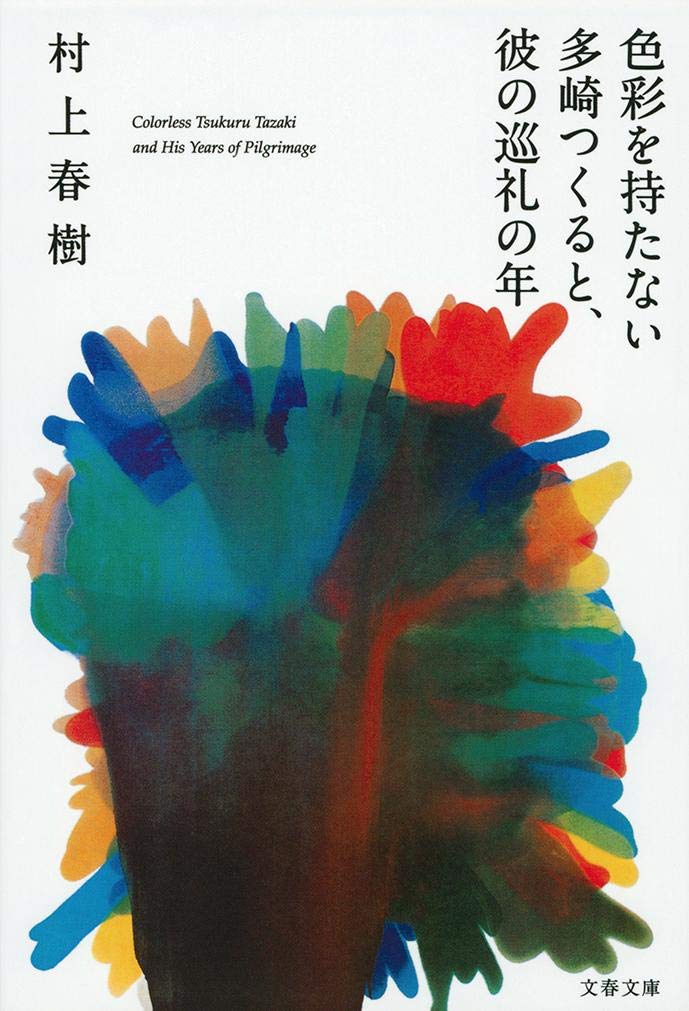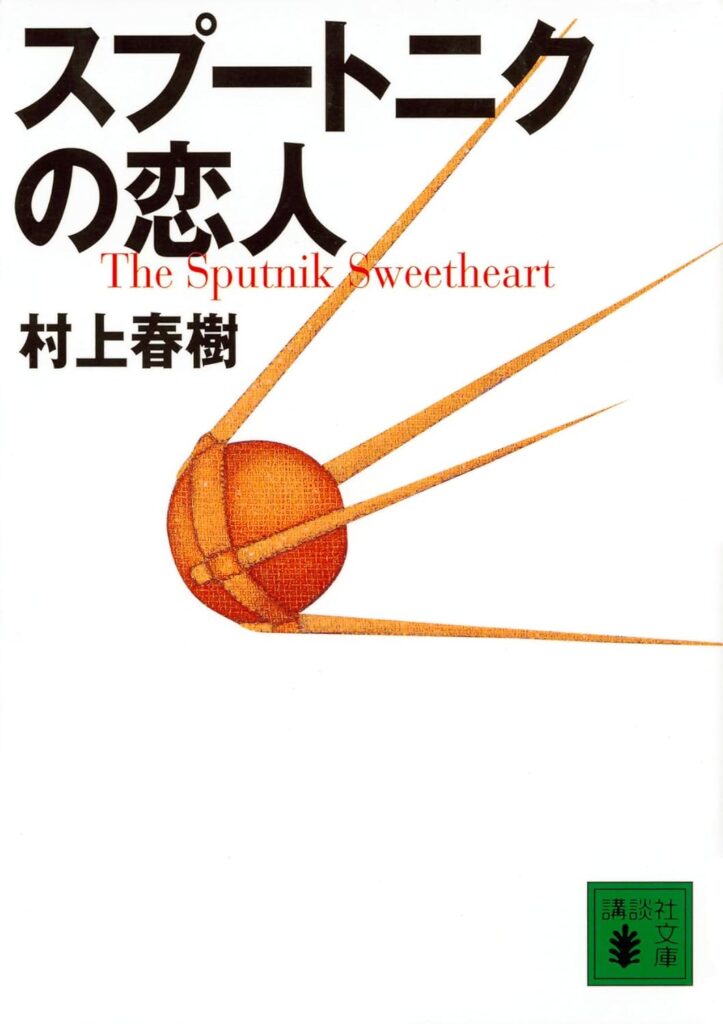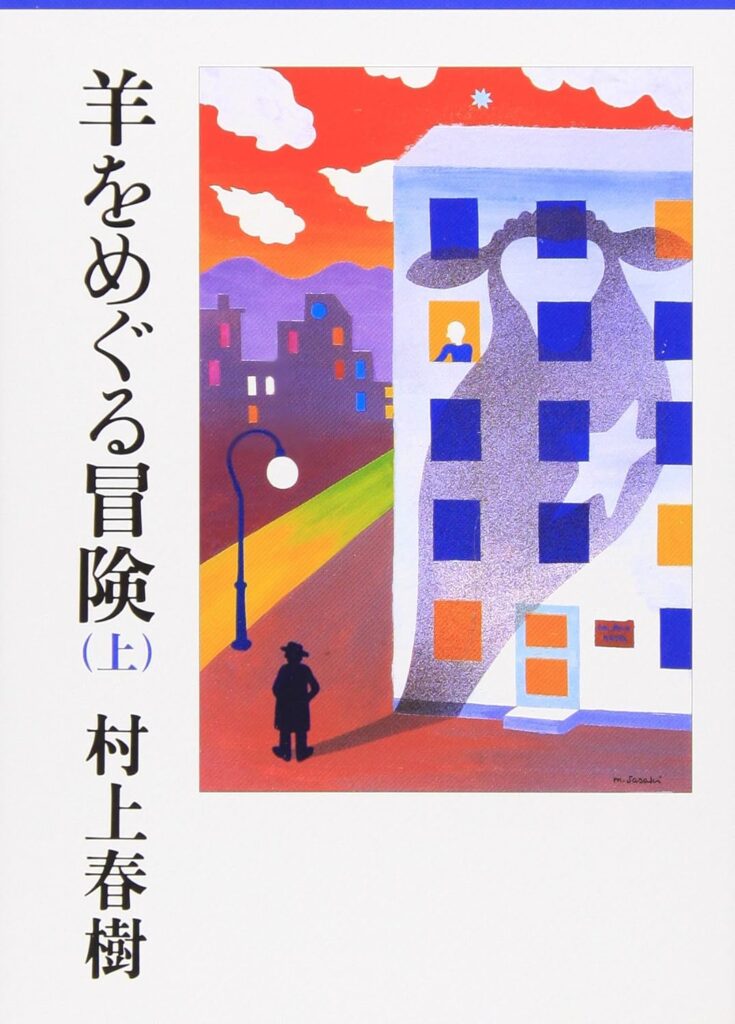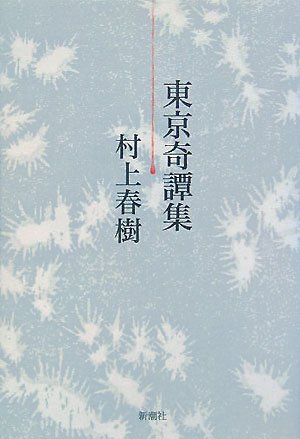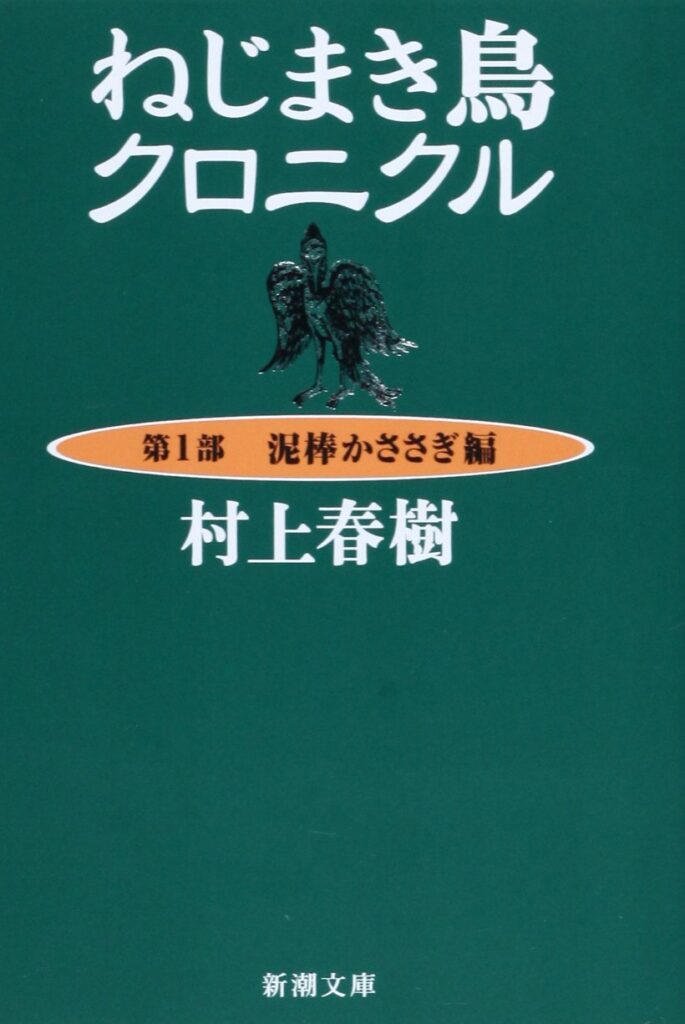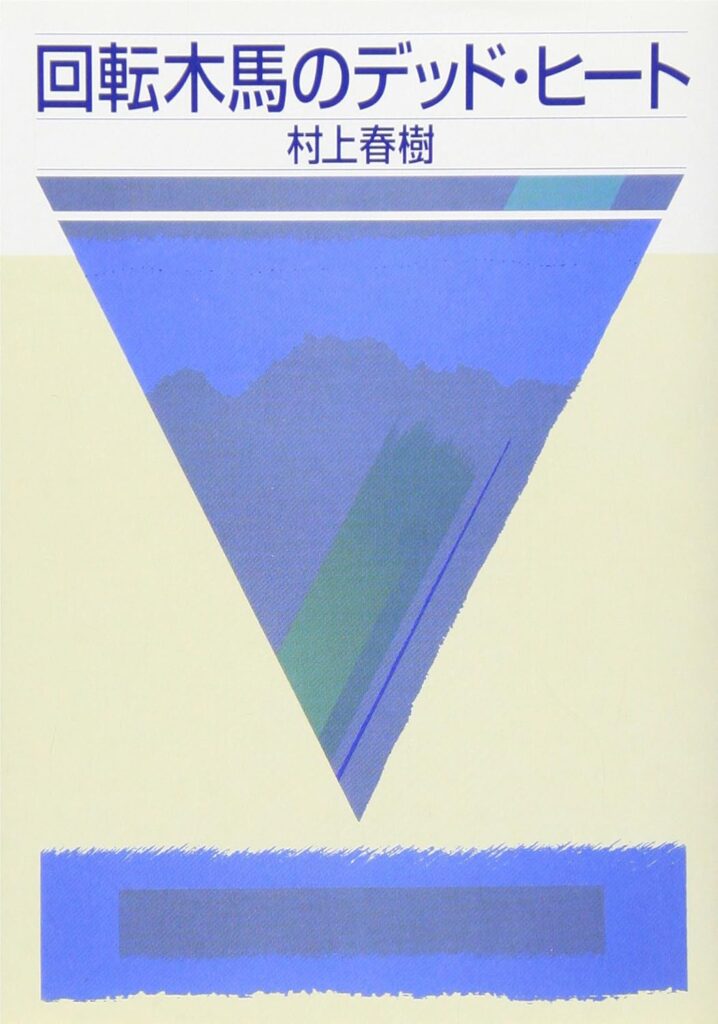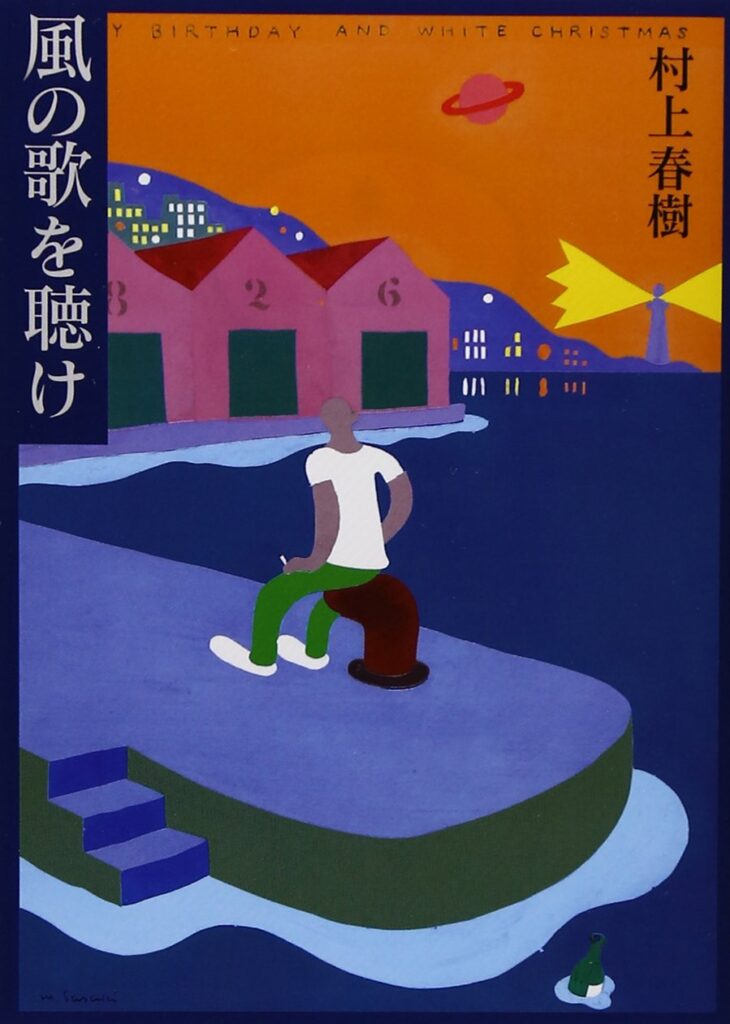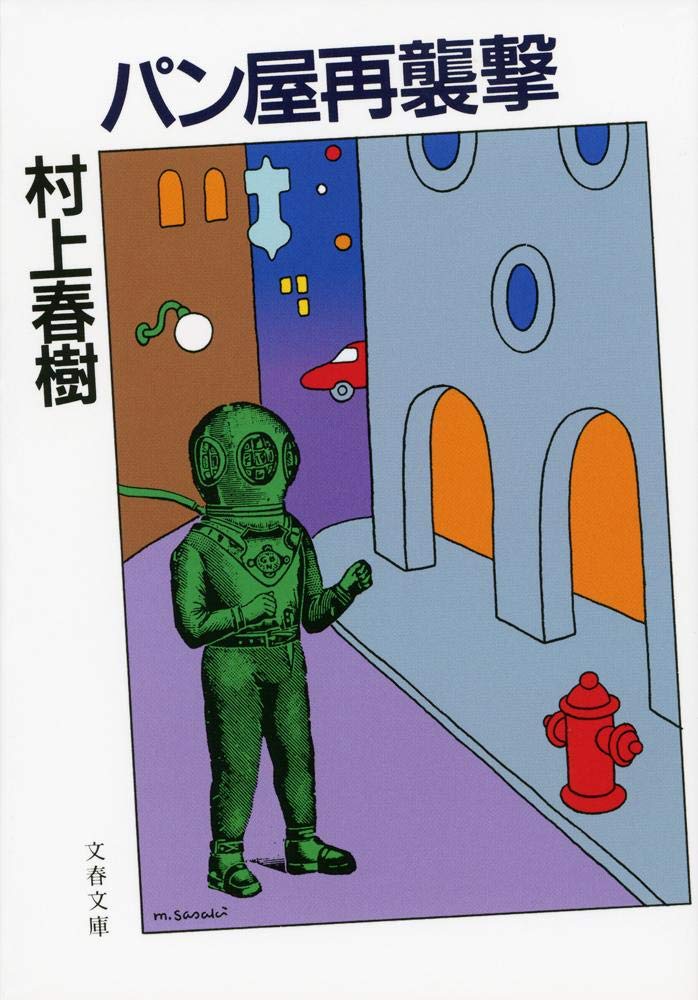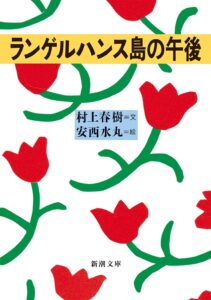 エッセイ「ランゲルハンス島の午後」のあらすじを結末込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。村上春樹さんの作品の中でも、特に短いこのエッセイ(あるいは掌編小説と呼んでもいいかもしれません)は、読んだ人の心に不思議な余韻を残しますよね。私にとっても、忘れられない一編となっています。
エッセイ「ランゲルハンス島の午後」のあらすじを結末込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。村上春樹さんの作品の中でも、特に短いこのエッセイ(あるいは掌編小説と呼んでもいいかもしれません)は、読んだ人の心に不思議な余韻を残しますよね。私にとっても、忘れられない一編となっています。
この作品は、エッセイ集の表題にもなっているので、ご存知の方も多いかもしれません。安西水丸さんの挿絵と共に、日常のささやかな出来事や著者の考えが綴られたエッセイ集ですが、その最後に収められているのが、この「ランゲルハンス島の午後」です。短い文章の中に、少年時代のある午後の風景と心情が、鮮やかに切り取られています。
この記事では、まず物語の簡単な流れ、どのようなお話なのかをご紹介します。そして、少し踏み込んで、物語の終わり方にも触れながら、私がこの作品を読んで何を感じたのか、どうしてこんなにも心惹かれるのか、その理由をじっくりと語っていきたいと思います。個人的な思い出も交えながら、この作品の魅力をお伝えできれば嬉しいです。
エッセイ「ランゲルハンス島の午後」のあらすじ
物語は、ある春の日の午後、主人公である「僕」(おそらく中学生くらいでしょうか)が学校をサボるところから始まります。理由は特に語られませんが、なんとなく学校に行きたくない、そんな気分だったのかもしれません。彼は自転車に乗り、目的もなくぶらぶらと走り、やがて古い石の橋の上にたどり着きます。
その橋は、綺麗で大きな川に架かっていて、そこからは遠くに海がきらめいているのが見えます。天気は良く、空はどこまでも青く澄み渡り、空気は暖かく、心地よい風が吹いています。彼は自転車を停め、橋の真ん中あたりで、まるで打ち捨てられた古いマットレスにでもなるかのように、ごろんと仰向けに寝転がります。
寝転がった彼の目に映るのは、吸い込まれそうなほど青い空と、白い雲の流れ。彼はポケットから取り出したチョコレートをかじりながら、ただぼんやりと空を眺めます。周囲には誰もいません。聞こえるのは、川の流れる音と、遠くの喧騒だけ。完全な静寂と孤独の中で、彼は自分だけの時間を満喫します。
そして彼は、空想を始めます。自分の膵臓の中にあるという「ランゲルハンス島」のことを。学校の生物の時間に習った、血糖値を調節する細胞が集まっている場所。彼は、その名前の響きから、南の海に浮かぶ美しい島を想像します。自分が今いるこの場所、この瞬間が、まるでその架空の島での午後のように感じられるのです。そんな空想に浸っているうちに、穏やかな時間が過ぎていきます。これが「ランゲルハンス島の午後」の物語の概要です。
エッセイ「ランゲルハンス島の午後」の長文感想(結末に触れています)
村上春樹さんの「ランゲルハンス島の午後」は、本当に短い、見開き2ページほどの文章です。しかし、その短い文章の中に、忘れがたい風景と、ある種の普遍的な感情が凝縮されているように感じます。初めて読んだのは、もうずいぶん前のことですが、今でも時折ふと思い出しては、あの春の午後の、少しけだるくて、でもどこか満たされた空気感を追体験するのです。
この作品の魅力は、まずその描写の鮮やかさにあると思います。古い石の橋、きらめく川面、遠くに見える海、そして何よりも、吸い込まれそうな青い空。村上さんの文章は、まるでカメラのレンズのように、その場の光景をくっきりと切り取って、読者の目の前に提示してくれます。主人公の少年が橋の上にごろりと寝転がる様子、ポケットのチョコレートをかじる仕草、それら一つ一つのディテールが、物語の世界にリアリティを与え、読者をその場にいるかのような気分にさせてくれます。
私が特に心を掴まれたのは、少年が学校をサボって、目的もなく橋の上で時間を過ごす、というそのシチュエーションです。誰にでも、特に若い頃には、理由もなく何かから逃げ出したくなるような、あるいはただ一人になってぼんやりと過ごしたい、そんな瞬間があるのではないでしょうか。私自身にも、似たような経験があります。参考資料にあった河合さんの文章にも、学校をサボって公園で過ごした日の記憶が語られていましたが、まさにそんな感じです。授業を抜け出して、人気のない場所で、ただ空を眺めていた時間。そこには、少しの後ろめたさと、それ以上に大きな解放感がありました。この作品を読むと、そうした自分自身の遠い日の記憶が、ふっと蘇ってくるのです。この短い物語は、まるで古い写真のように、色褪せることなく当時の空気感を閉じ込めています。
そして、この作品の核心とも言えるのが、「ランゲルハンス島」というモチーフでしょう。膵臓にある細胞群の名前。普通なら、そんなものに詩情を感じることはないかもしれません。しかし、主人公の少年は、その名前の響きから、遠い南の島の午後を連想します。学校で習った無機質な知識が、彼の自由な空想の中で、まったく別の、輝きを帯びたイメージへと変換される。この飛躍が、とても村上春樹さんらしいと感じます。
日常の中の退屈さや息苦しさから逃れて、自分だけの世界に浸る。それは、現実逃避と言えるかもしれません。でも、少年が橋の上で見つけた「ランゲルハンス島の午後」は、単なる逃避場所ではなく、彼にとってのささやかな聖域、あるいは「小確幸」(小さいけれども、確かな幸福)と呼べるような時間だったのではないでしょうか。誰にも邪魔されず、ただ自分と向き合い、空想の翼を広げる時間。それは、思春期の不安定な心にとって、なくてはならないものだったのかもしれません。
この物語の結末、というほど明確なものはありませんが、少年はしばらくそうして過ごした後、やがて起き上がり、また自転車に乗ってどこかへ去っていくのでしょう。特別な何かが起こるわけではありません。ただ、春の日の午後の、ほんの一瞬の出来事が描かれるだけです。しかし、その「何も起こらない」こと、その静謐さの中にこそ、この作品の深い味わいがあるように思います。それは、過ぎ去ってしまった青春の一コマであり、二度とは戻らない時間の輝きを象徴しているかのようです。
参考資料の中に、友人Nさんのエピソードがありました。彼女はこの「ランゲルハンス島の午後」が一番好きで、何度も読み返していたといいます。厳しい家庭環境で育ち、学校をサボることもできなかった彼女にとって、この物語の少年は憧れの対象であり、「ランゲルハンス島」は手の届かない理想郷のような場所だったのかもしれません。彼女が後に、大学の講義を休み、ただひたすら街を歩き続けたという行動も、どこか自分だけの「島」を探し求めていたようにも思えます。そして、彼女のあまりにも寂しい最期を知ると、この作品が持つ穏やかな光景の裏に、ある種の切なさや、人生のやるせなさのような影を感じずにはいられません。
Nさんにとって、この物語は慰めであったと同時に、手の届かない憧れであり続けたのかもしれません。そして、その憧れが満たされないまま人生を終えてしまったのかもしれない、と考えると、胸が締め付けられるような思いがします。もちろん、これは私の勝手な想像に過ぎませんが、この短い物語が、読む人それぞれの人生や記憶と深く結びつき、多様な解釈や感情を呼び起こす力を持っていることの証左ではないでしょうか。
村上春樹さんの作品には、しばしば日常の中に潜む異世界への入り口や、現実と非現実の境界が曖昧になるような描写が見られます。『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』のような長編はもちろん、この「ランゲルハンス島の午後」のような短いエッセイにおいても、その感覚は健在です。橋の上で空を見上げる少年は、物理的には現実の日本のどこかにいますが、彼の意識は、膵臓の中の細胞群から連想された架空の「島」へと飛んでいます。この、現実の風景と内なる空想がシームレスに繋がる感覚が、村上作品の大きな魅力の一つだと感じます。
また、このエッセイ集全体に言えることですが、安西水丸さんの描く、シンプルでどこか力の抜けたイラストレーションが、村上さんの文章世界と見事に調和しています。あの独特のタッチの絵があることで、「ランゲルハンス島の午後」の、あの少しぼんやりとした、夢うつつのような雰囲気が、より一層際立つように思います。文字だけを追うのとはまた違った、豊かな読書体験を与えてくれます。
この作品を読むたびに、私は自分自身の「ランゲルハンス島」について考えます。それは、物理的な場所である必要はありません。忙しい日常の中で、ふと心が安らぐ瞬間、自分だけの世界に浸れる時間。それは、好きな音楽を聴いている時かもしれないし、静かなカフェで本を読んでいる時かもしれません。あるいは、ただ窓の外を眺めて、雲の流れを目で追っているだけの時間かもしれません。どんな形であれ、そうした自分だけの「島」を持つことは、現代を生きる私たちにとって、とても大切なことなのではないでしょうか。
「ランゲルハンス島の午後」は、派手な出来事も、劇的な結末もありません。しかし、そこには、誰もが心のどこかに持っているであろう、過ぎ去った時間へのノスタルジーや、日常からのささやかな逃避願望、そして自分だけの聖域を求める気持ちが、静かに描かれています。だからこそ、この短い物語は、多くの読者の心に深く、そして長く響き続けるのだと思います。それは、単なる感傷ではなく、生きる上で必要な、心の栄養のようなものなのかもしれません。
何年経っても、何度読み返しても、この作品は色褪せることがありません。読むたびに、あの春の日の、暖かく、少しけだるい午後の空気が、ページの中から立ち上ってくるようです。そして、自分自身の心の奥底にある、忘れかけていた風景や感情を、そっと思い出させてくれるのです。それは、懐かしく、少し切なく、そしてとても愛おしい体験です。
まとめ
この記事では、村上春樹さんの短いエッセイ(あるいは掌編小説)、「ランゲルハンス島の午後」について、物語の概要と、その結末にも触れながら、私の個人的な感想を詳しくお話しさせていただきました。学校をサボった少年が、春の日の橋の上で見つけた、ささやかで個人的な「島」での時間。
この作品の魅力は、鮮やかな風景描写と、思春期特有の感情、そして日常からの解放感が、短い文章の中に凝縮されている点にあると思います。膵臓の細胞群「ランゲルハンス島」から南の島を連想するという、ユニークな発想も印象的です。読む人それぞれの記憶や体験と結びつき、深い共感やノスタルジーを呼び起こす力を持っています。
派手さはありませんが、読後には静かで、どこか切ない余韻が残ります。まだ読んだことがない方はもちろん、以前読んだことがある方も、ぜひ再読してみてはいかがでしょうか。きっと、あなた自身の心の中にある「ランゲルハンス島の午後」を、改めて見つけることができるかもしれません。この記事が、そのきっかけとなれば幸いです。