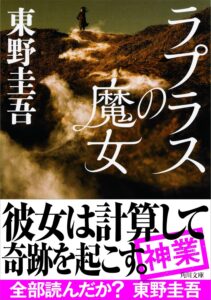 小説『ラプラスの魔女』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が描く、予測不可能な現象と人間の業が交錯する物語。果たして、その深淵には何が隠されているのでしょうか。凡百のミステリとは一線を画す、異色のエンターテインメントと言えるかもしれませんね。
小説『ラプラスの魔女』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が描く、予測不可能な現象と人間の業が交錯する物語。果たして、その深淵には何が隠されているのでしょうか。凡百のミステリとは一線を画す、異色のエンターテインメントと言えるかもしれませんね。
物語は、奇妙な硫化水素中毒死事件から幕を開けます。地球化学の専門家である大学教授・青江修介は、警察の依頼で調査に乗り出しますが、そこで謎めいた少女・羽原円華と出会います。彼女は、まるで未来を見通すかのような不思議な言動を繰り返し、青江を当惑させるのです。一見、単なる事故に見えた事件は、やがて複雑な人間関係と思惑、そして驚くべき「力」の存在へと繋がっていきます。
本稿では、この『ラプラスの魔女』という作品の核心に迫ります。物語の顛末、つまり結末までの流れを明らかにし、その上で、この私が感じた率直な思いを、少々長めになるかもしれませんが、述べさせていただきましょう。ネタバレを避けたい方は、ここで引き返すのが賢明かもしれませんよ。読み進めるも引き返すも、あなたの自由ですが。
小説「ラプラスの魔女」のあらすじ
物語は、地方の温泉地で発生した硫化水素による死亡事故から始まります。被害者は映像プロデューサーの水城義郎。警察は事故と事件の両面で捜査を進め、地球化学の専門家である泰鵬大学教授・青江修介に協力を依頼します。現場を訪れた青江は、そこで不思議な雰囲気を持つ若い女性、羽原円華の姿を目撃します。彼女は何かを探している様子でしたが、多くを語ろうとはしませんでした。
それから二か月後、今度は別の県の温泉地で、再び硫化水素による死亡事故が発生します。被害者は元俳優の那須野五郎。奇妙な偶然の一致に、青江は再び現地へ赴きます。すると、そこにはまたしても羽原円華の姿が。青江は、彼女が持つ、自然現象を正確に予測するかのような不可思議な能力を目の当たりにし、疑念を深めていきます。円華は一体何者で、何を追っているのでしょうか。
並行して、警視庁の刑事・中岡祐二も、最初の被害者・水城義郎の周辺を洗っていました。水城の母親から、生前に「妻に殺されるかもしれない」という相談を受けていたためです。捜査を進める中で、二つの硫化水素事故の被害者が、過去に著名な映画監督・甘粕才生と繋がりがあったことが判明します。そして、その甘粕才生もまた、数年前に自宅で発生した硫化水素事故で妻と娘を亡くし、息子・謙人は植物状態になるという悲劇に見舞われていたのです。
甘粕謙人は、円華の父である脳神経外科の権威・羽原全太朗の手術によって奇跡的に回復していました。しかし、その回復の裏には、ある秘密が隠されていました。謙人と、そして円華もまた、「ラプラスの魔女」と呼ばれるほどの驚異的な計算能力と未来予測能力を、脳の手術によって手にしていたのです。一連の硫化水素事故は、単なる偶然ではなく、この特殊な能力を持つ者によって引き起こされた、計画的な殺人だったのではないか。青江と中岡は、それぞれの立場から事件の真相へと迫っていくことになります。
小説「ラプラスの魔女」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは核心に触れつつ、この『ラプラスの魔女』という作品について、私の所見を述べさせていただきましょう。ネタバレを大いに含みますので、その点、ご留意いただきたい。
まず、この物語の根幹を成す「ラプラスの魔女」という設定。未来の物理現象を正確に予測できる能力、ですか。羽原円華と甘粕謙人が、脳外科手術によって後天的にこの能力を得た、というわけですね。なるほど、荒唐無稽と言ってしまえばそれまでですが、物語のエンジンとしては面白い試みと言えるでしょう。ピエール=シモン・ラプラスが提唱した思考実験上の存在「ラプラスの悪魔」をモチーフに、現代的なSF要素をミステリに組み込む。東野氏らしい、エンターテインメントへの貪欲さが垣間見える設定です。
しかしながら、この能力の描き方には、少々首を傾げざるを得ませんね。作中では、ナビエ=ストークス方程式といった専門用語を散りばめ、あたかも科学的根拠があるかのように見せかけていますが、その実態はかなり曖昧模糊としている。気象現象や物体の落下運動程度ならまだしも、人間の行動、特に殺意のような複雑な感情まで計算に入れて計画を実行するというのは、いささか万能に過ぎるのではないでしょうか。サイコロの目を当てるデモンストレーションがありましたが、あれと計画殺人を同列に語るのは、少々無理があるように感じます。都合の良い場面で能力が発動し、そうでない場面ではなりを潜める。これは物語の推進力であると同時に、ご都合主義との批判も免れないでしょう。
特に、円華が祖母の帽子を取り戻すシーン。風向きを読み、帽子が手元に戻ってくるように予測した、と。しかし、それほどの能力があるのなら、そもそも帽子が風に飛ばされること自体を予測し、未然に防げたのではないですかね? この種の細かな矛盾点が、物語への没入を時折妨げるのです。まあ、エンターテインメントですから、目くじらを立てるのも野暮というものでしょうか。
事件の真相、すなわち一連の硫化水素事故の犯人が甘粕謙人であり、その動機が父・甘粕才生への復讐であったという点。これは、ある意味で予想の範疇というか、物語の定石通りといったところでしょうか。才生が自身の歪んだ理想のために家族を殺害しようとしたという背景も、陳腐と言えば陳腐です。「完璧でない家族は不要」ですか。凡庸な悪党の典型のような思考回路ですね。彼を「天才」「鬼才」と持ち上げる描写が作中に見られますが、その行動原理からは、およそ天才性など微塵も感じられません。むしろ、自己愛と身勝手さだけが肥大化した、哀れな俗物という印象です。
クライマックス、廃墟での才生と謙人の対峙シーン。そして、ダウンバーストによる崩壊。これもまた、既視感のある展開と言わざるを得ません。まるで出来の悪い操り人形を見ているかのようでしたね、あの結末は。 才生が自らの罪を告白し、謙人がそれを録音している、というのも、少々安直な解決ではないでしょうか。才生が最終的に自死を選ぶのも、まあ、物語の収束としては妥当なのでしょうが、そこに深い感慨はありませんでした。
キャラクターに目を向けると、主人公格の一人である青江修介教授。彼は、いわば読者目線を代弁するワトソン役といったところでしょうか。事件の謎に迫り、円華の能力に驚き、翻弄される。彼の存在によって、読者はこの非現実的な設定に何とか食らいついていくことができる。しかし、彼自身の個性や魅力という点では、やや希薄な印象を受けますね。あくまで物語を回すための装置、という域を出ていないように感じられます。
刑事の中岡祐二は、対照的に人間味があり、好感が持てます。地道な捜査で真相に近づこうとする彼のパートは、ある種のリアリティを物語に与えています。しかし、最終的には警察上層部からの圧力で捜査から外されてしまう。これもまた、物語の都合と言ってしまえばそれまでですが、少々残念な扱いではありますね。彼にもっと活躍の場を与えても良かったのではないでしょうか。
そして、本作のタイトルロールである羽原円華。彼女の存在は、この物語の核でありながら、どこか捉えどころがない。母親を亡くした悲劇、そして「ラプラスの魔女」になることを望んだ動機。そこには共感できる部分もあるのですが、彼女の行動原理は、時に冷徹で、人間離れしているように見えます。それは能力の代償なのか、あるいは彼女自身の資質なのか。その曖昧さが、彼女を神秘的に見せると同時に、感情移入を難しくしている側面もあるでしょう。ボディガードの武尾徹との関係性も、もう少し掘り下げても良かったかもしれませんね。
物語のテーマ性について。「未来予測」という能力を通して、人間の存在意義や運命といった壮大な問いを投げかけているようにも見えます。謙人が才生に言い放つ「人間は原子だ。一つ一つは凡庸で、無自覚に生きているだけだとしても、集合体となった時、劇的な物理法則を実現していく。この世に存在意義の無い個体など無い」というセリフ。これは、作者からのメッセージと受け取ることもできるでしょう。どんな人間にも価値がある、と。しかし、そのメッセージを伝えるための物語装置として、「後天的に得た超能力による復讐劇」という設定が、果たして最適だったのかどうか。そこには疑問符が付きます。
東野圭吾氏の筆致は、相変わらず読みやすい。ページをめくる手が止まらない、という読者も多いことでしょう。冒頭で謎を提示し、読者の興味を引きつけ、徐々に真相へと導いていく。その構成力は確かです。しかし、本作に関しては、SF的な設定とミステリとしての論理性、そして人間ドラマの融合が、必ずしもうまくいっているとは言い難い。それぞれの要素が、どこかちぐはぐな印象を与え、物語全体の完成度を損ねているように感じられるのです。
読後感としては、決して悪くはありません。エンターテインメントとして、一定の水準は満たしていると言えるでしょう。しかし、心に深く刻まれるような感動や、知的興奮を得られたかと問われれば、残念ながら「否」と言わざるを得ませんね。東野作品には傑作も多いだけに、本作に対しては、少々辛口な評価にならざるを得ない、というのが正直なところです。まあ、これも一つの挑戦だった、ということなのでしょうかね。
まとめ
小説『ラプラスの魔女』。それは、科学と神秘が交錯する、いささか風変わりな物語でしたね。硫化水素による連続不審死、その裏に隠された驚くべき能力と、歪んだ家族の愛憎劇。東野圭吾氏らしい、読者を引き込むストーリーテリングは健在と言えるでしょう。
しかし、その核心にある「未来予測」という超常的な設定は、諸刃の剣でもありました。物語に非日常的な面白さを加える一方で、リアリティラインを曖昧にし、ミステリとしての緻密さを損なっている側面も否めません。登場人物たちの行動原理や、事件の解決方法にも、ややご都合主義的な甘さが見受けられたのは、少々残念な点でした。
とはいえ、エンターテインメント作品として割り切れば、十分に楽しめる一冊であることも確かです。ページをめくる手が止まらない展開、個性的な(あるいは、そう見せかけようとしている)登場人物たち。深く考えずに物語の流れに身を任せるならば、それなりに満足感は得られるのではないでしょうか。ただ、傑作か凡作かと問われれば、残念ながら後者に近い、というのが私の偽らざる評価です。フッ…まあ、判断は読者それぞれに委ねるとしましょうか。
































































































