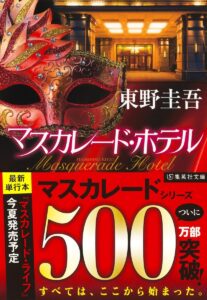 小説『マスカレード・ホテル』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が世に送り出した、ホテルを舞台にしたミステリー作品ですね。一流ホテル・コルテシア東京に、ある連続殺人事件の次の犯行が予告されたことから物語は動き出します。華やかな仮面舞踏会の裏側で、静かに、しかし確実に進行する悪意。それを阻止せんと潜入する若き刑事と、彼を迎え撃つ(?)ことになるプライド高きホテルマン。
小説『マスカレード・ホテル』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が世に送り出した、ホテルを舞台にしたミステリー作品ですね。一流ホテル・コルテシア東京に、ある連続殺人事件の次の犯行が予告されたことから物語は動き出します。華やかな仮面舞踏会の裏側で、静かに、しかし確実に進行する悪意。それを阻止せんと潜入する若き刑事と、彼を迎え撃つ(?)ことになるプライド高きホテルマン。
まあ、設定としては悪くない。刑事とホテルマン、水と油のような二人が、価値観の違いから反発し合いながらも、次第に奇妙な信頼関係を築いていく…というのは、使い古された感は否めませんが、読者の興味を引く定石ではあります。ホテルという閉鎖空間で繰り広げられる人間模様と、刻一刻と迫るタイムリミット。怪しげな宿泊客たちが次々と現れ、捜査は混迷を極めていきます。果たして仮面の下に隠された真実とは?
本稿では、この『マスカレード・ホテル』の物語の顛末、つまりは結末までを詳らかにし、併せて、私個人の少々辛口な評価を述べさせていただきましょう。世間の評判とは少し違う角度からの意見になるかもしれませんが、それもまた一興かと。しばしお付き合いいただければ幸いです。
小説「マスカレード・ホテル」のあらすじ
都内で三件の殺人事件が相次いで発生しました。それぞれの現場には不可解な数字の羅列が残されており、警察はこれを連続殺人事件と断定。捜査本部が設置され、暗号解読が急がれます。その結果、数字が示す座標から、第四の犯行現場が都内屈指の一流ホテル「コルテシア東京」であることが判明するのです。しかし、わかっているのは場所だけで、犯人が誰なのか、誰を狙っているのか、すべてが謎に包まれたまま。
事態を重く見た警視庁は、ホテル・コルテシア東京への潜入捜査を決定します。白羽の矢が立ったのは、若手ながら切れ者の刑事・新田浩介。彼はフロントクラークとしてホテルに潜り込み、内部から犯人の尻尾を掴むという任務を与えられます。そして、その新田の教育係兼監視役を命じられたのが、ホテル・コルテシア東京が誇る優秀なフロントクラーク、山岸尚美でした。「お客様第一」を徹底するホテルマンの鑑のような彼女と、「犯人逮捕」を至上命題とする刑事の新田。
当然ながら、二人の価値観は真っ向から対立します。客のプライバシーを尊重し、あくまでも「お客様」として接しようとする尚美。一方、すべての客を「容疑者」として疑いの目を向け、些細な言動も見逃すまいとする新田。彼らの間には、ことあるごとに火花が散ります。ホテルには、様々な事情を抱えた、いかにも怪しげな客たちが次々と訪れます。視覚障碍者を装う老婦人、執拗なクレームをつけてくる男、ストーカーに怯える花嫁…。
これらは果たして事件に関係があるのか、それとも単なる偶然なのか。新田と尚美は、互いに反発しながらも、それぞれの立場から情報を集め、推理を重ねていきます。ホテルという華やかな舞台の裏で交錯する、様々な人々の思惑と嘘。潜入捜査が進むにつれて、二人の間にも少しずつ変化が訪れます。異なる世界のプロフェッショナルとして互いを認め合い始めた彼らは、やがて事件の核心へと迫っていくことになるのです。
小説「マスカレード・ホテル」の長文感想(ネタバレあり)
さて、この『マスカレード・ホテル』、世間ではなかなかの高評価を得ているようですが、私にはどうにも腑に落ちない点が多く、正直なところ、手放しで称賛する気にはなれませんでしたね。満足度としては、星一つ、いや、おまけして二つといったところでしょうか。木村拓哉氏と長澤まさみ氏のキャスティングで映画化もされ、華々しい成功を収めたようですが、原作の物語構造そのものには、看過できない欠陥があるように思えてなりません。
まず、物語の根幹を成すミステリーの仕掛けについて。連続殺人事件に見せかけて、実はそれぞれの事件の犯人は異なり、黒幕であるX4(長倉麻貴)が自分の目的のために他の殺人を計画に組み込んだ…という構図自体は、まあ、悪くはないアイデアでしょう。ミスディレクションを狙ったものとしては、古典的とも言えます。しかし、その動機と実行計画の細部が、どうにも粗雑に感じられてしまうのです。
特に疑問なのが、X4こと長倉麻貴が、最終的なターゲットとして山岸尚美を狙う必然性です。確かに、一年前にホテル・コルテシア東京で尚美に冷たくあしらわれ、結果的に恋人であった松岡高志の子を流産してしまった、という恨みは理解できます。松岡への復讐は、まあ納得できる。しかし、その復讐計画に、なぜ尚美まで巻き込み、しかも一連の連続殺人事件のクライマックスとして殺害しようとするのか。その動機付けが、どうにも弱い。松岡殺害と尚美殺害、この二つの事件を結びつけられることを恐れた、という説明がありましたが、むしろ逆でしょう。松岡と長倉の関係性を考えれば、警察が二つの事件を結びつける可能性が高いのは明らか。連続殺人事件という煙幕を張る必要があったのは、むしろ松岡殺害の方ではなかったか? 実際、能勢刑事は松岡の周辺捜査から比較的容易に長倉麻貴へと辿り着いています。このあたりの計画の杜撰さは、X4を知能犯として描こうとしている本作の意図とは裏腹に、彼女を短絡的な人物に見せてしまっています。
さらに言えば、新田と能勢が交わす会話の中で、「事件の構造が警察に知られても、他に殺害計画を持っている場合はメリットがある」というくだり(415ページから416ページあたりでしたか)。これは正直、読んでいて首を傾げざるを得ませんでした。X4が二つの殺人を計画しており、一方を連続殺人事件に偽装することで、もう一方の殺人と自身との関連性を断ち切ろうとした…という理屈なのでしょうが、あまりにも回りくどく、現実味がない。まるで、後付けで理由をこじつけているかのような印象を受けました。この二人の会話がなければ、能勢刑事が都内で起きた別の未解決事件(松岡殺害事件)を洗う動機が生まれないため、物語の都合上、必要だったのでしょうが、もう少し説得力のある展開はなかったものでしょうか。
そして、極めつけは、長倉麻貴が老婆(片桐瑤子)に扮してホテルに潜入し、尚美に接近するというトリック。失礼ながら、これはいただけません。特殊メイクか何かを施したのかもしれませんが、三十代半ばの女性が、疑いの目を持って接客するプロのホテルマンや、ましてや潜入捜査中の刑事を欺き通せるものでしょうか。視覚障碍者を装い、白い手袋で火傷痕を隠す…という設定も、後付け感が否めません。ホテルという舞台は、様々な人間が「仮面」を被って集まる場所、というテーマ性を強調するための装置なのでしょうが、この変装トリックは、そのテーマ性を通り越して、リアリティの領域を逸脱してしまっているように感じます。まるで、出来の悪い手品を見せられているような気分でしたね。
ミステリーとしての驚きという点でも、物足りなさを感じました。確かに、犯人が老婆に変装していた、という点は意外ではありました。しかし、そこに至るまでの伏線や論理展開が弱い。怪しい宿泊客が次々と登場し、読者の注意をそちらに向けさせようという意図は見え見えで、かえって「この中に真犯人はいないのだろう」と勘繰らせてしまう。結局、最後に唐突に現れた(再登場した)人物が犯人でした、というのでは、フェアな推理ゲームとは言えません。
お仕事小説としての側面も、中途半端な印象です。ホテルマンとしての尚美のプロフェッショナリズムや、新田がホテル業務を通して成長していく姿は描かれてはいますが、深掘りされているとは言い難い。特に新田の成長は、やや表面的で、ご都合主義的に感じられる部分もありました。「お客様は神様です」的なホテル側の論理と、「疑わしきは罰せず」とはいかない警察側の論理の対立は、もっと深く掘り下げられたはずです。しかし、物語は安易な相互理解へと着地してしまい、テーマ性を深めるには至っていません。
キャラクター造形についても、やや不満が残ります。新田浩介は、エリート意識の強い若手刑事という設定ですが、その個性が十分に活かされているとは言えません。尚美も、完璧なホテルマンとして描かれていますが、人間的な深みや葛藤があまり感じられず、ややステレオタイプな印象を受けました。二人の関係性の変化も、もう少し丁寧に描いてほしかったところです。反発しあっていた二人が、いつの間にか互いを認め合い、最後には仄かな恋心のようなものまで匂わせる…というのは、いささか展開が急すぎやしませんかね。
もちろん、エンターテイメント作品として、多くの読者を引きつける魅力があることは否定しません。テンポの良い展開、個性的な(?)登場人物たち、華やかなホテルの舞台設定。これらが組み合わさることで、ページをめくる手が止まらなくなるような引力を持っていることは確かでしょう。しかし、それはあくまで表面的な面白さであり、物語の核となるミステリーの構成や、人物描写の深みといった点においては、物足りなさを禁じ得ないのです。
なぜこれほどまでに高い評価を得ているのか、私には正直、理解に苦しみます。映画化の成功によるイメージ先行もあるのかもしれません。あるいは、東野圭吾ブランドに対する信頼感でしょうか。しかし、作品単体として冷静に見た場合、手放しで傑作と呼ぶには、あまりにも多くの疑問符が付く作品だと、私は考えます。
まとめ
さて、長々と語ってきましたが、そろそろ筆を置くことにしましょう。本稿では、東野圭吾氏の小説『マスカレード・ホテル』について、物語の筋道から結末に至るまでを詳らかにし、併せて、私の極めて個人的な、そして少々手厳しい評価を述べさせていただきました。一流ホテルを舞台にした連続殺人予告と潜入捜査、対立する刑事とホテルマン…設定自体は悪くないのですがね。
しかし、その実態は、ミステリーとしての構成の甘さ、動機付けの弱さ、そしてリアリティに欠けるトリックが目につくものでした。特に、黒幕とされる人物の行動原理や計画の整合性には、首を傾げざるを得ません。お仕事小説としても、人間ドラマとしても、掘り下げが浅く、表層的な描写に終始している感が否めません。登場人物たちの魅力も、ステレオタイプな域を出ず、感情移入するには至りませんでした。
もちろん、これはあくまで私一人の見解に過ぎません。世には、この作品を絶賛する声も多いようです。エンターテイメントとしての読みやすさ、テンポの良さといった美点があることも認めましょう。ですが、それをもって傑作と称えることには、やはり抵抗があります。高評価に惑わされることなく、ご自身の目で確かめてみるのも一興かもしれません。ただし、過度な期待は禁物ですよ。
































































































