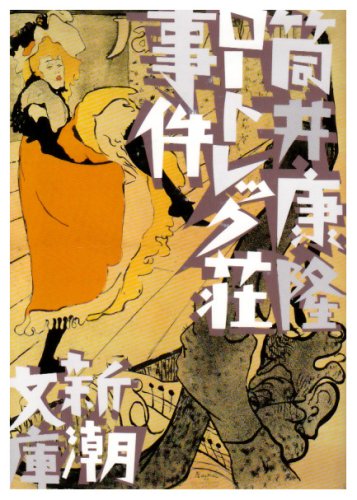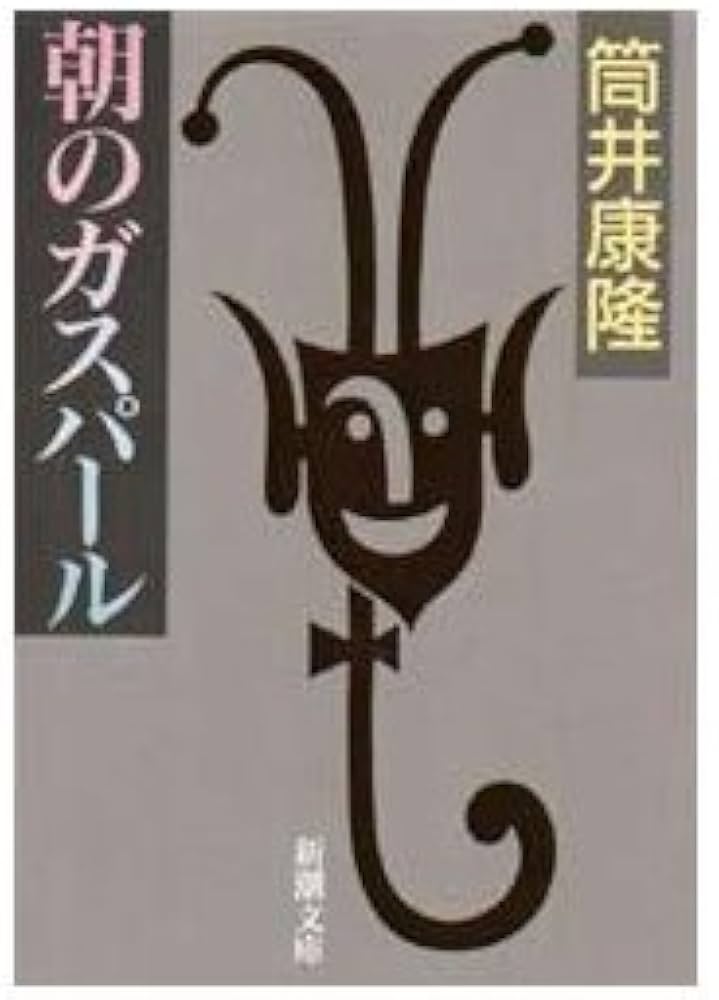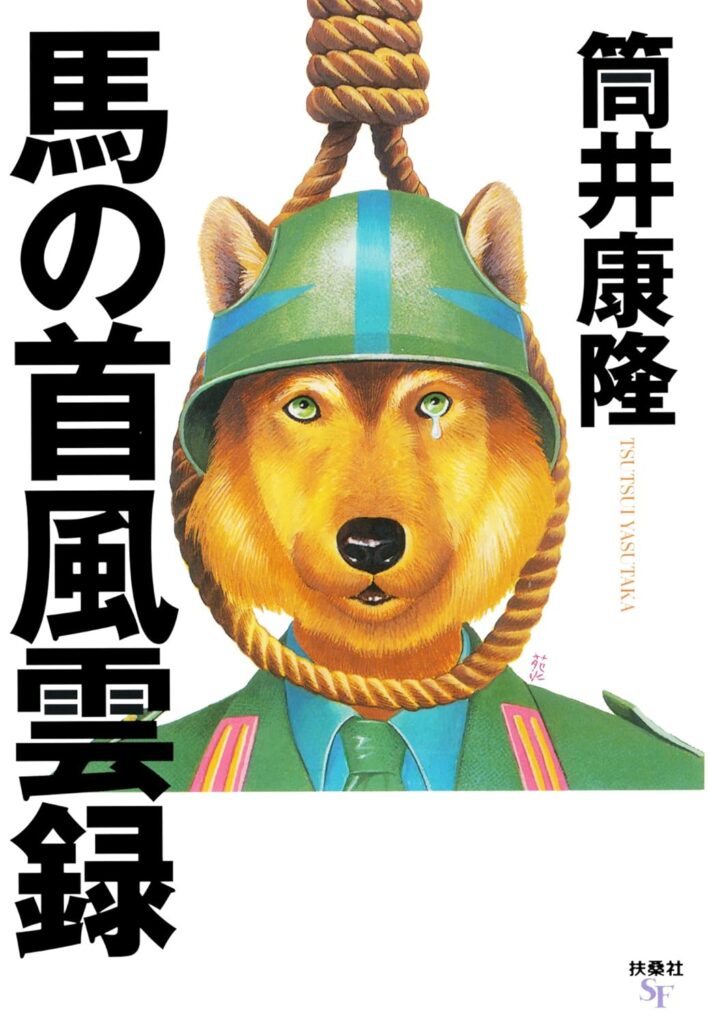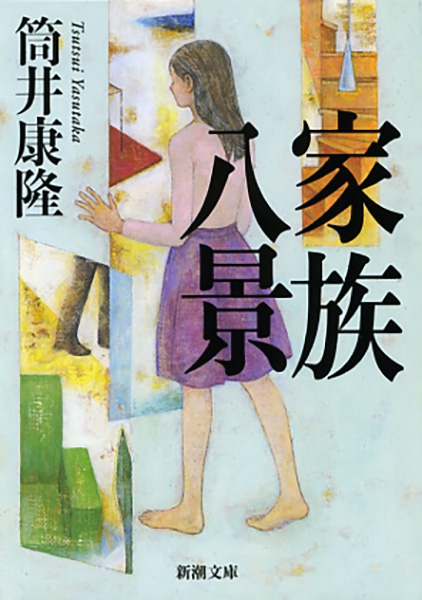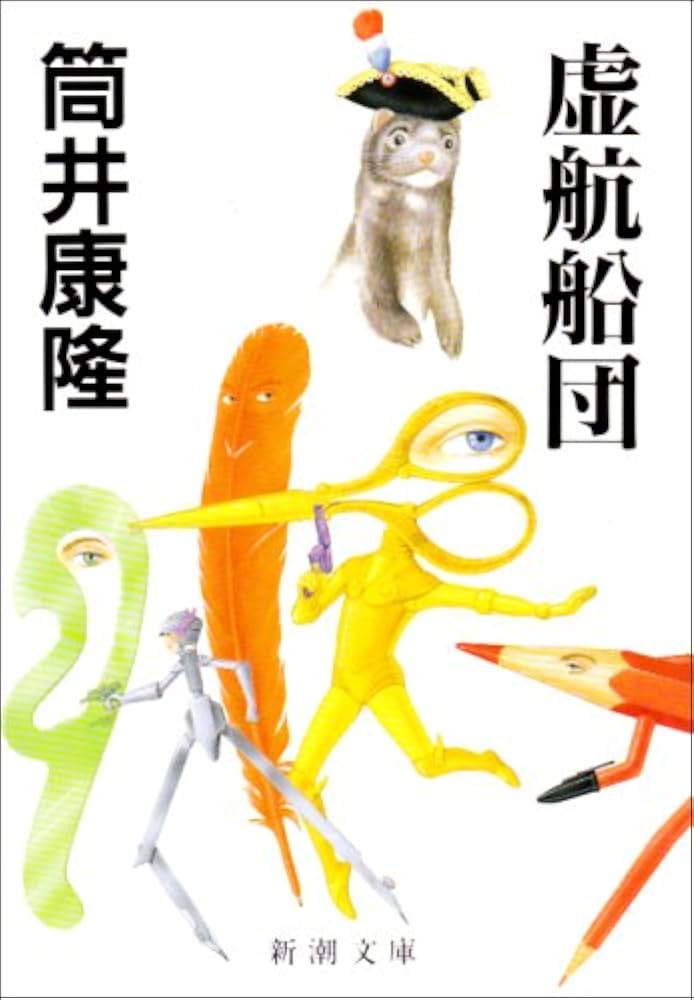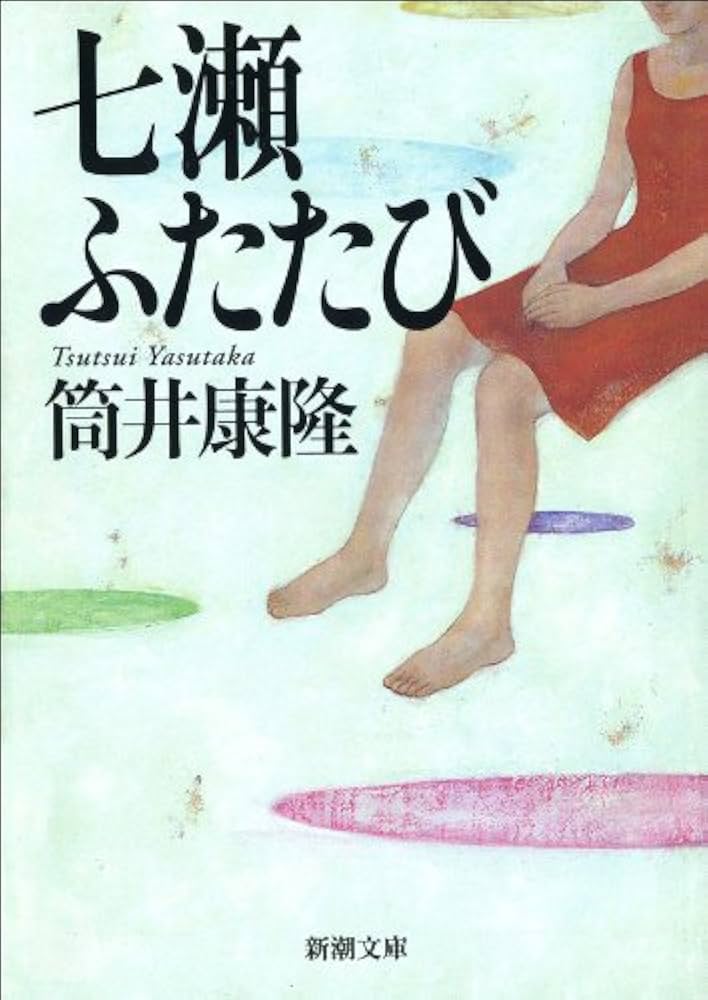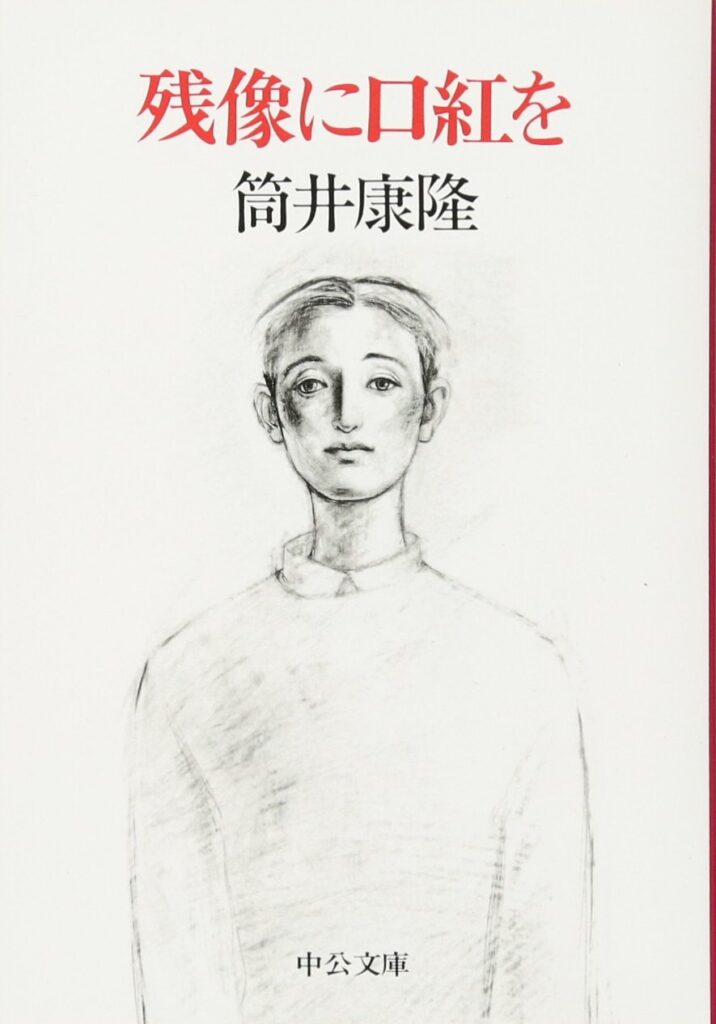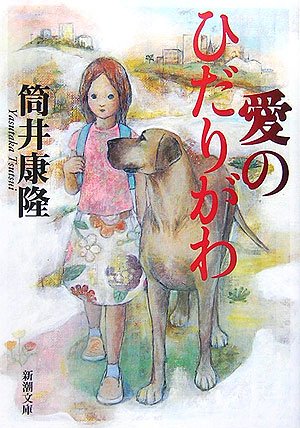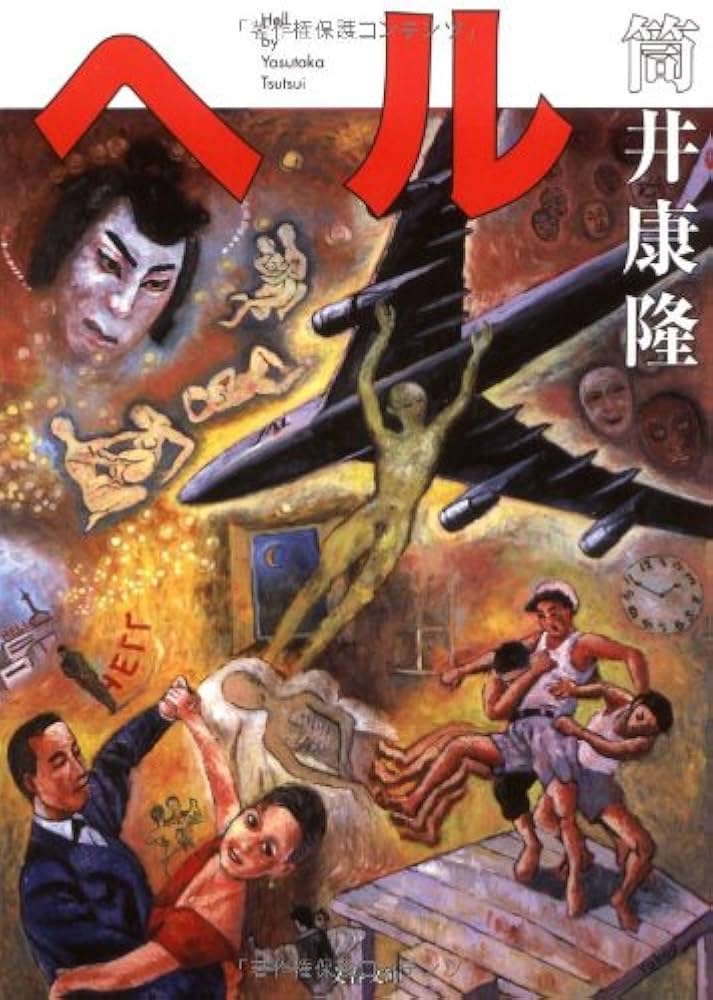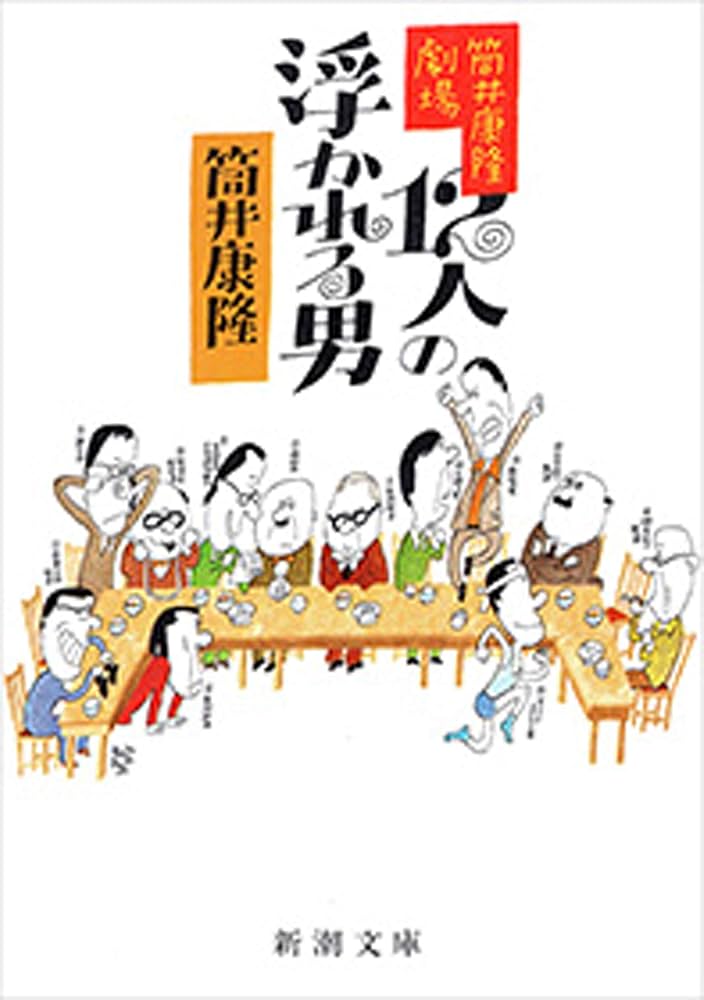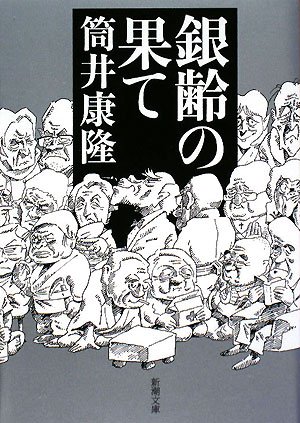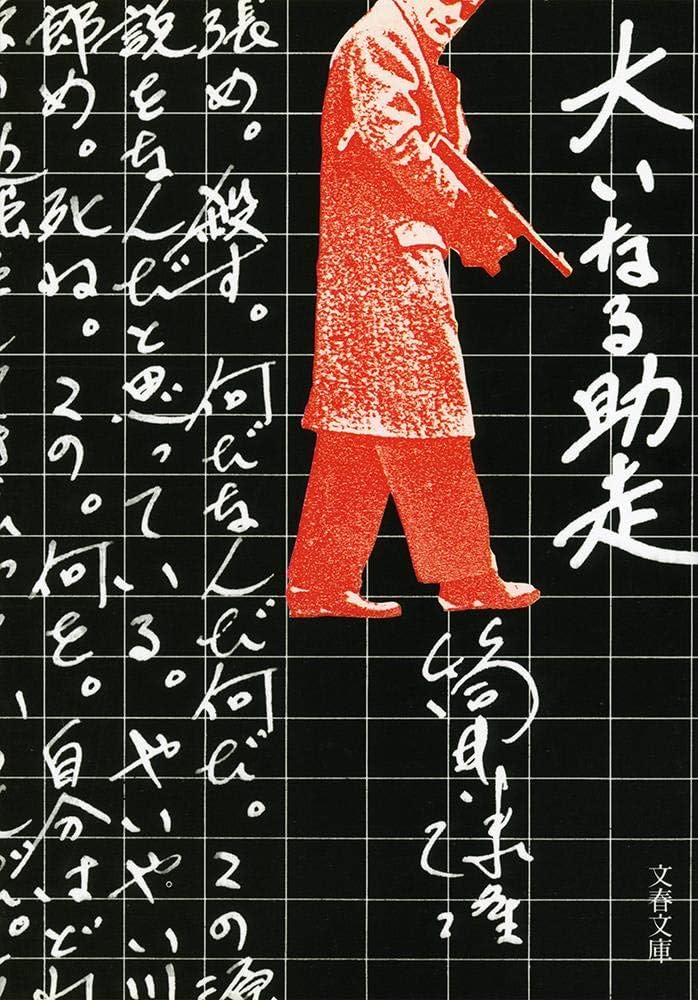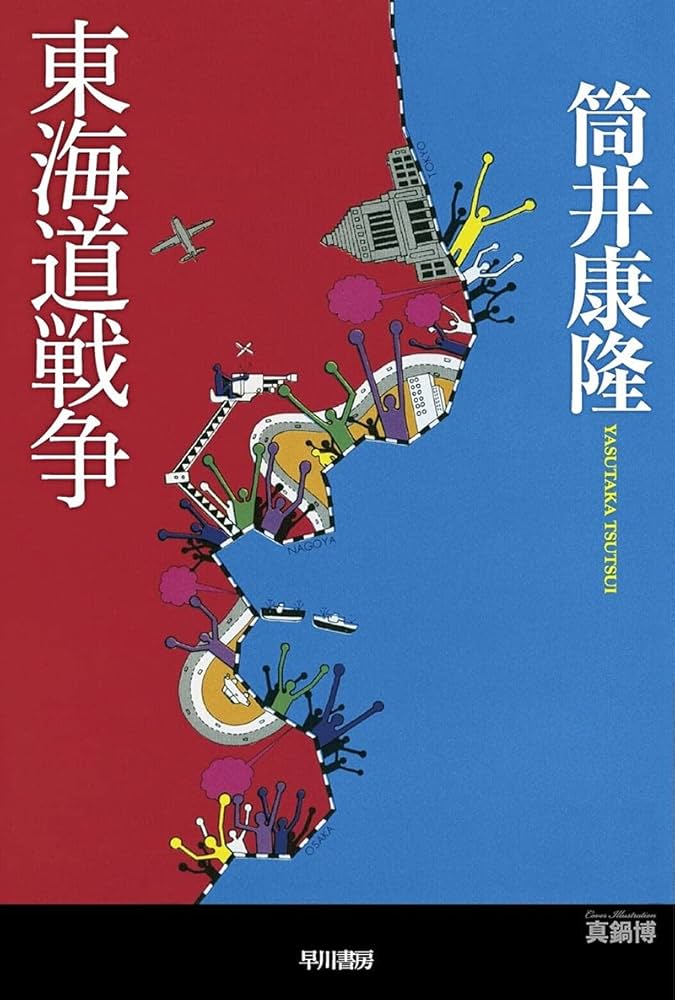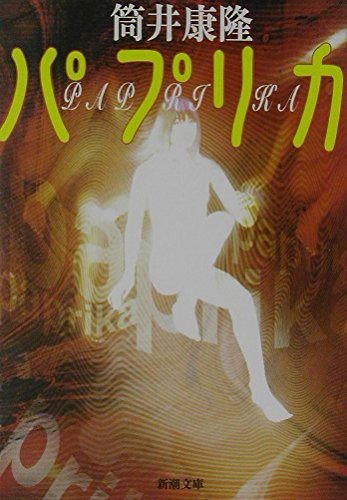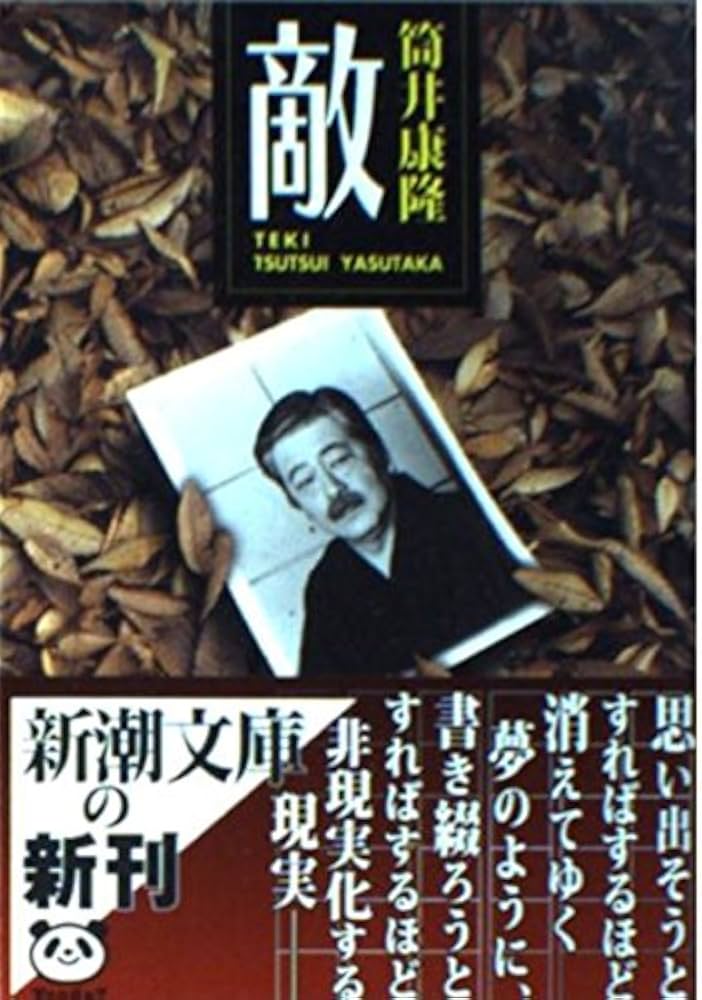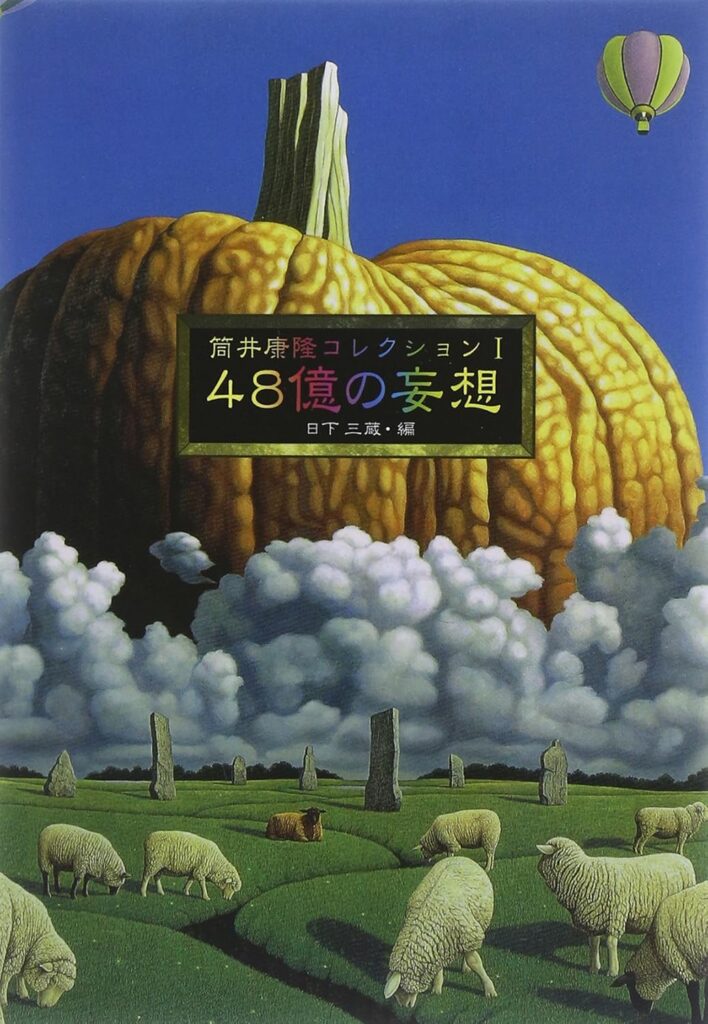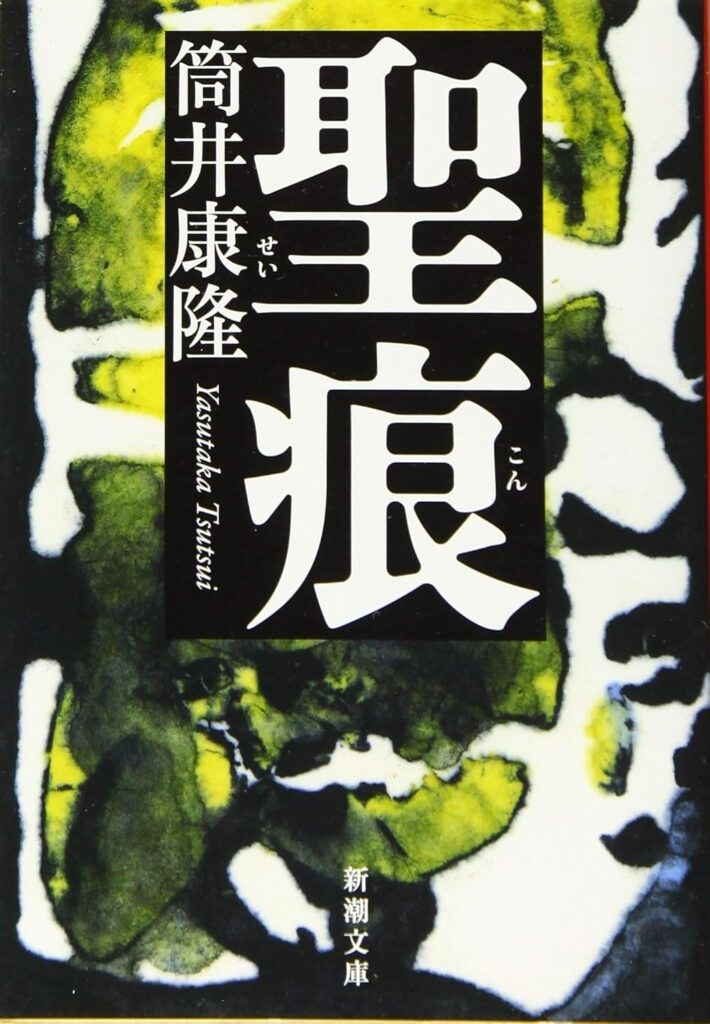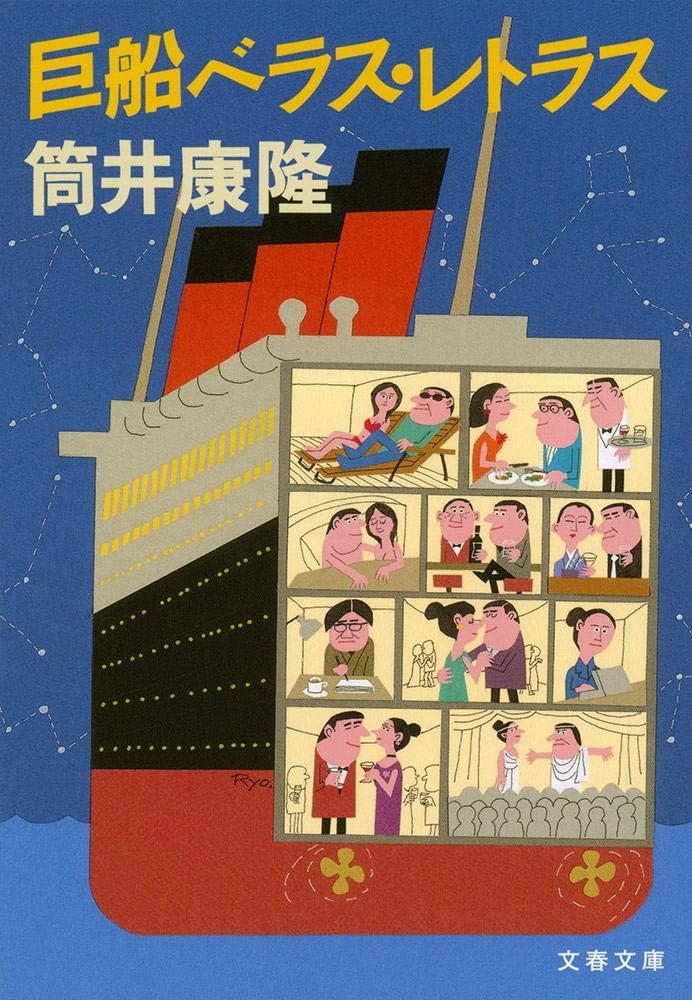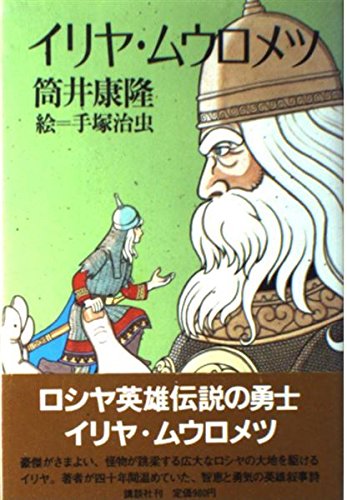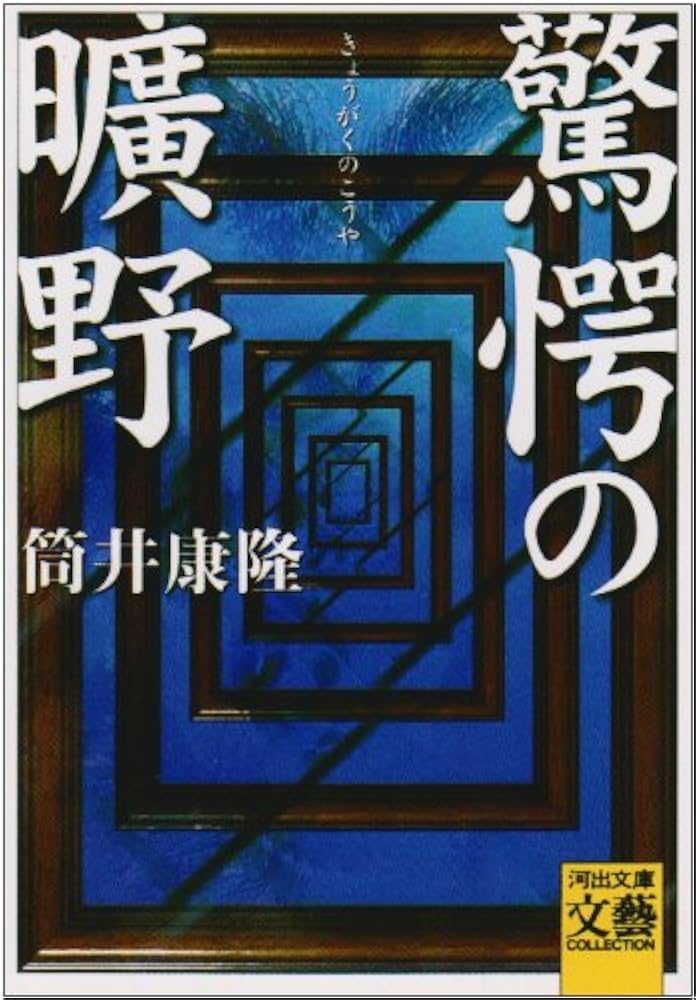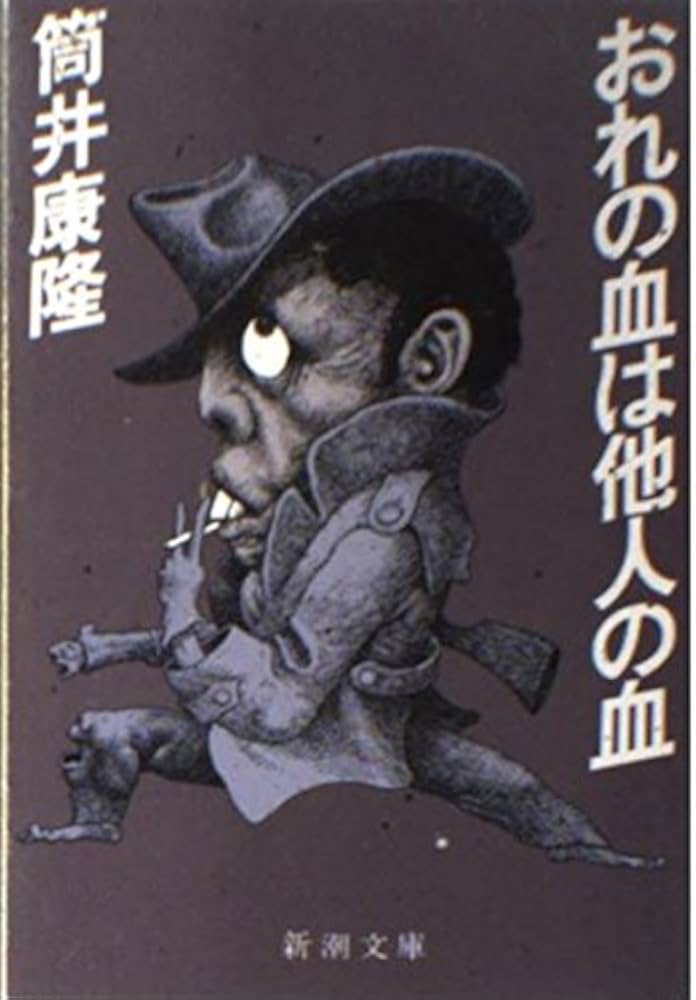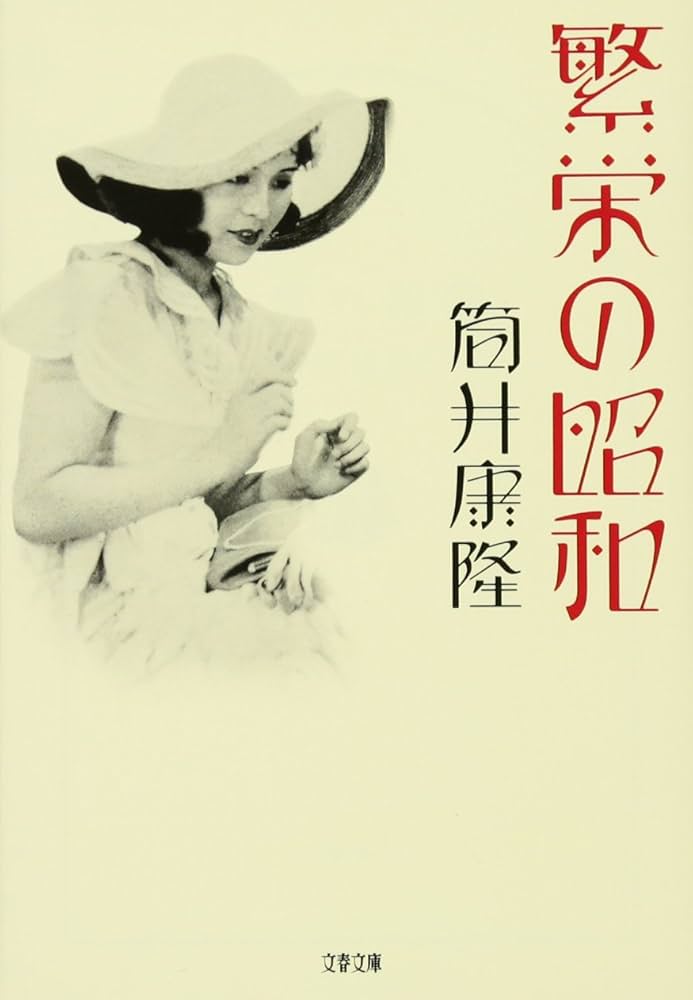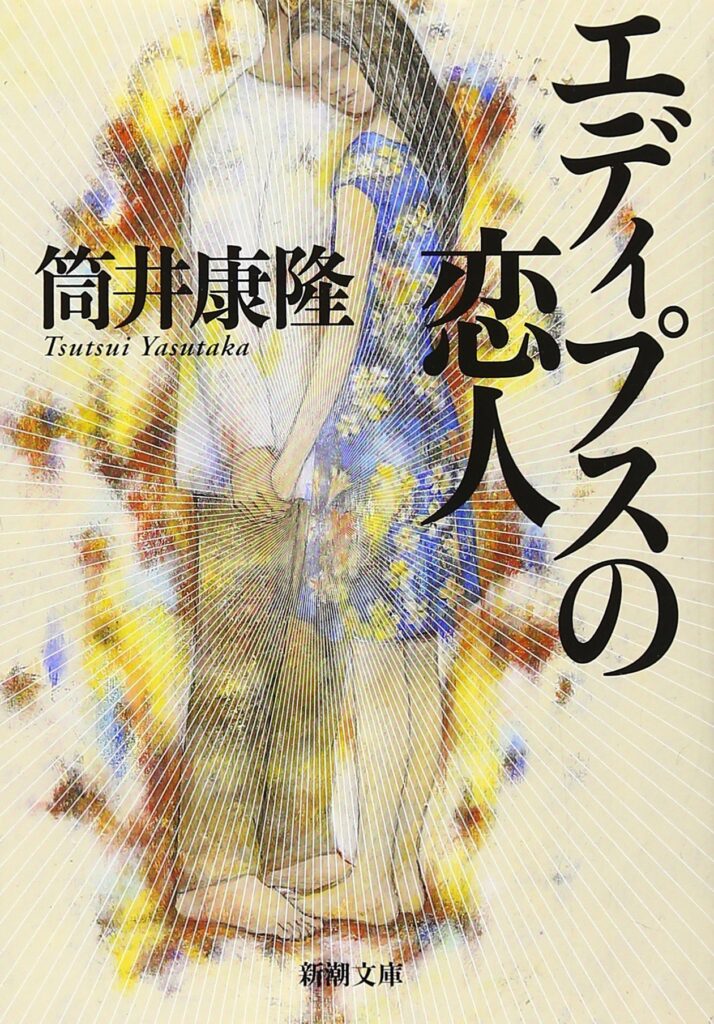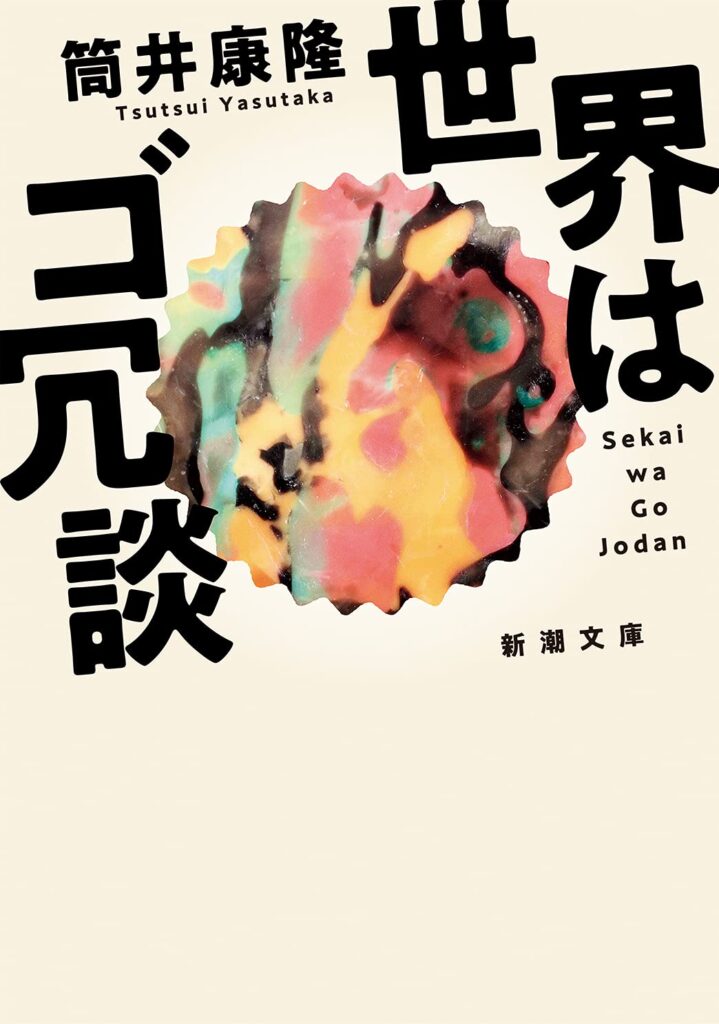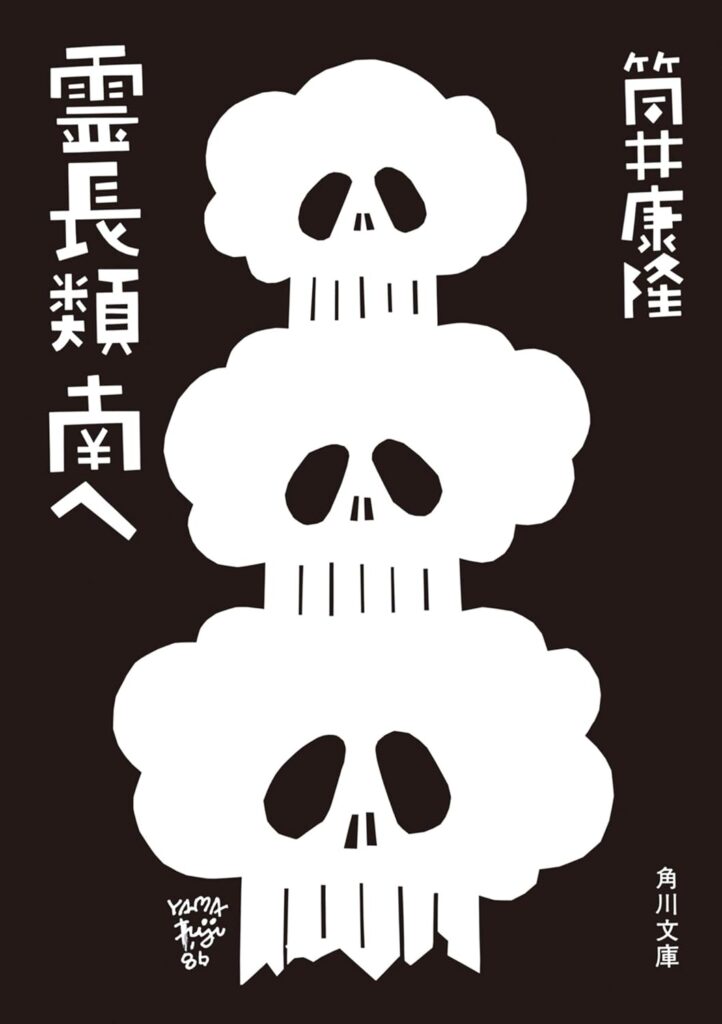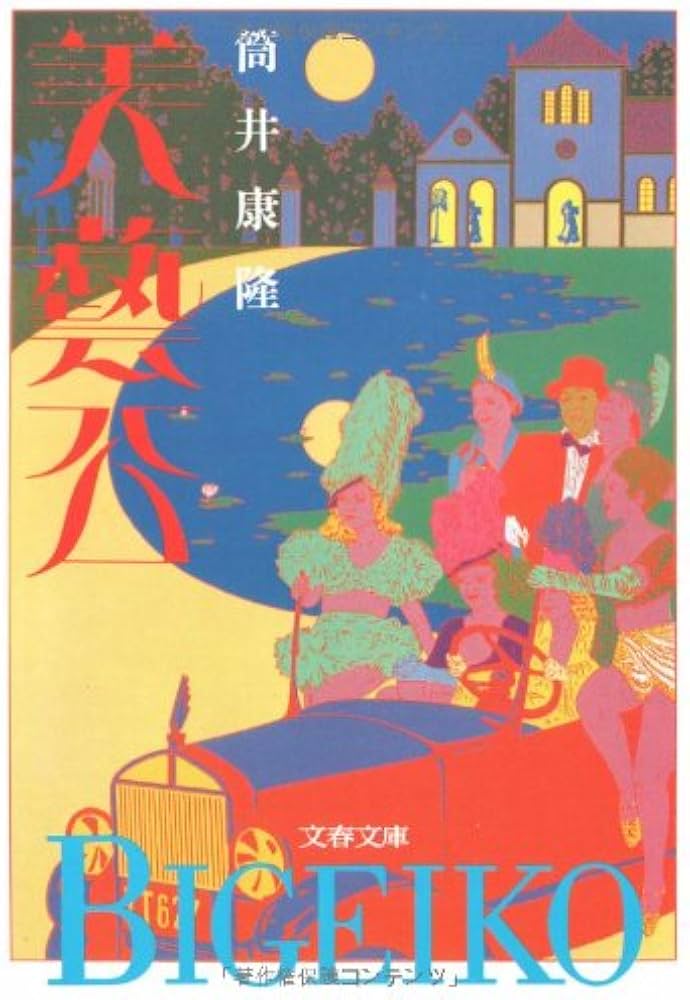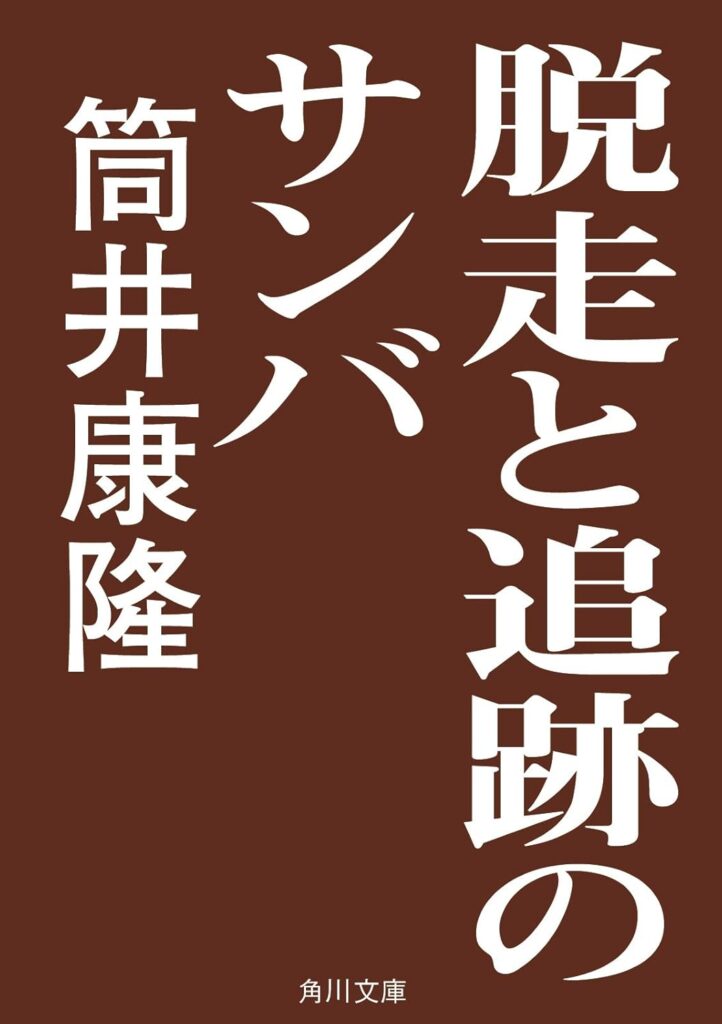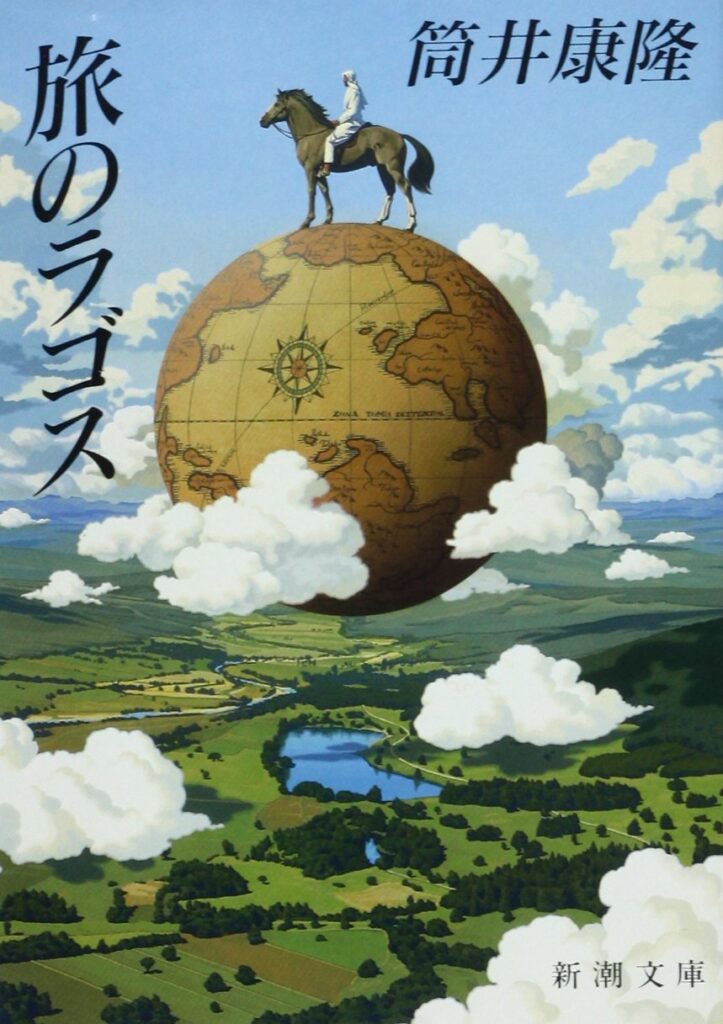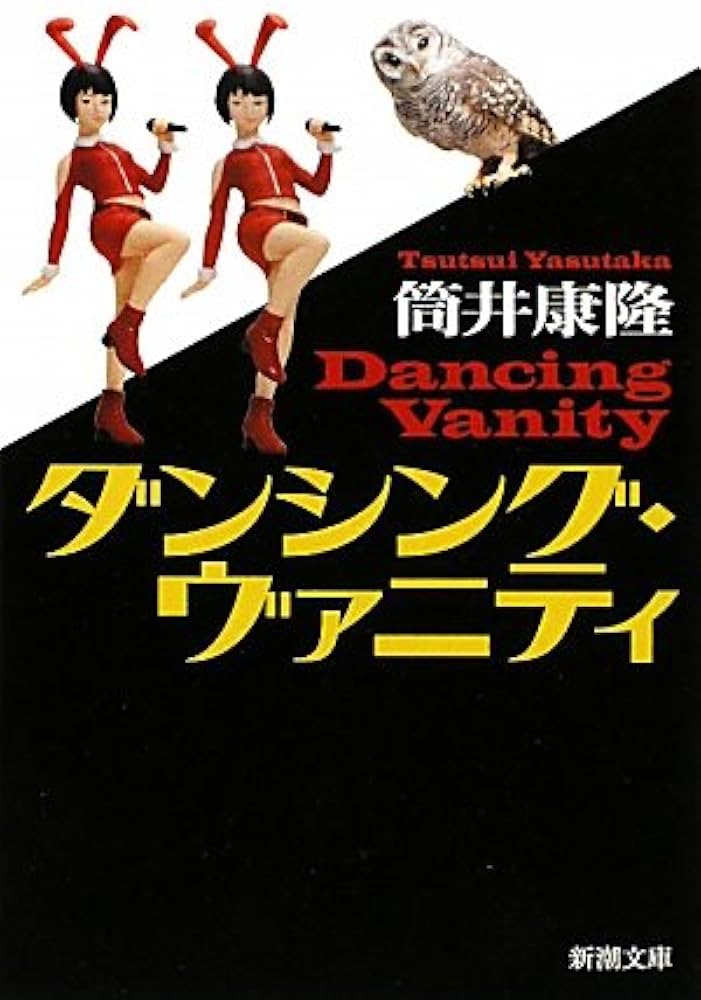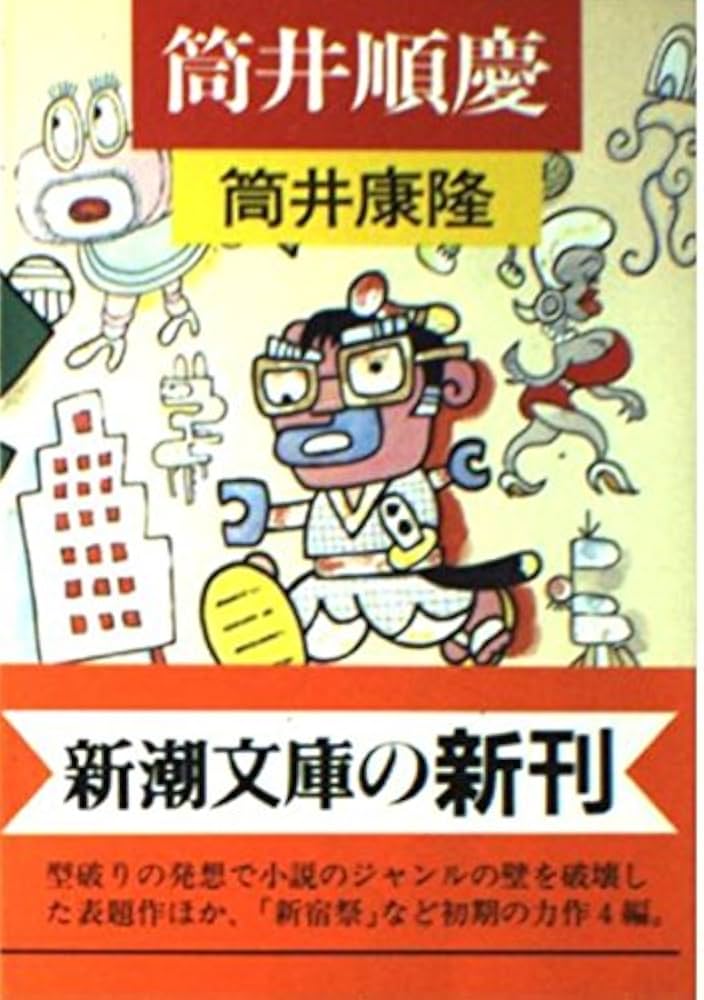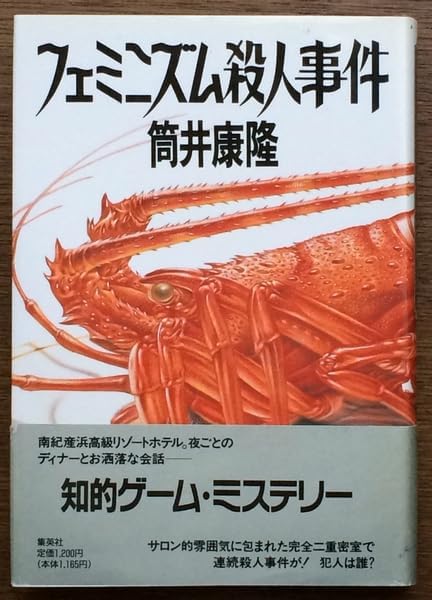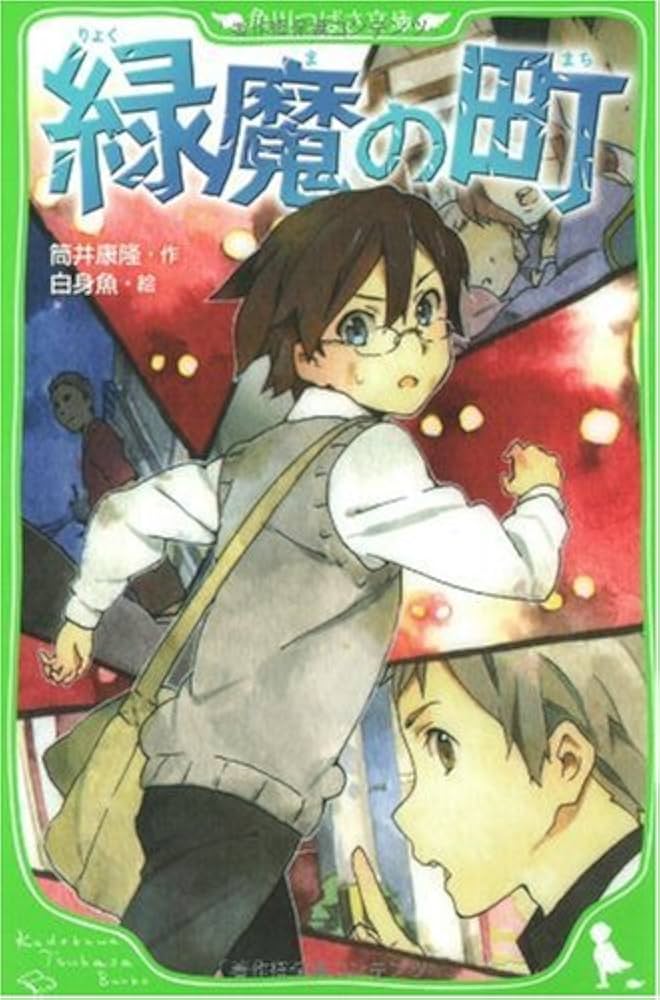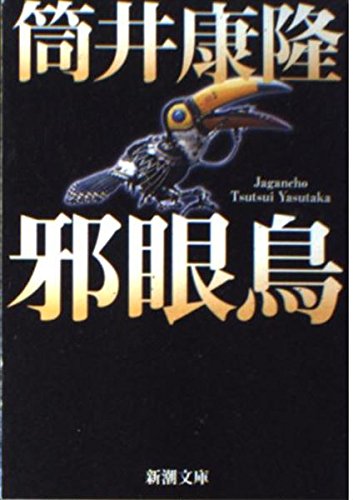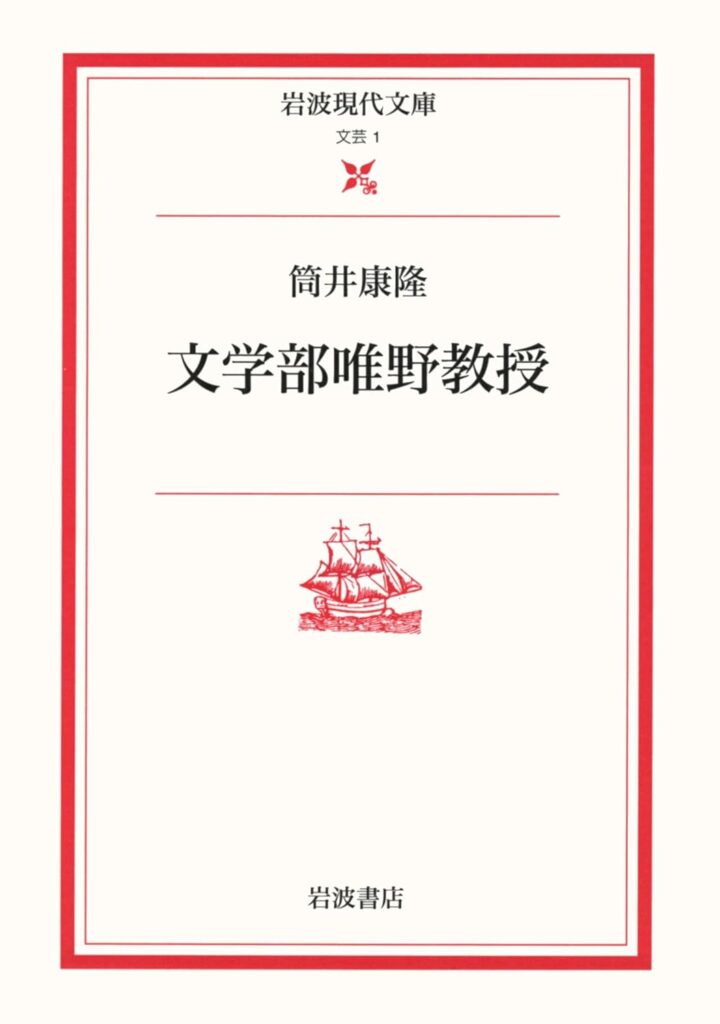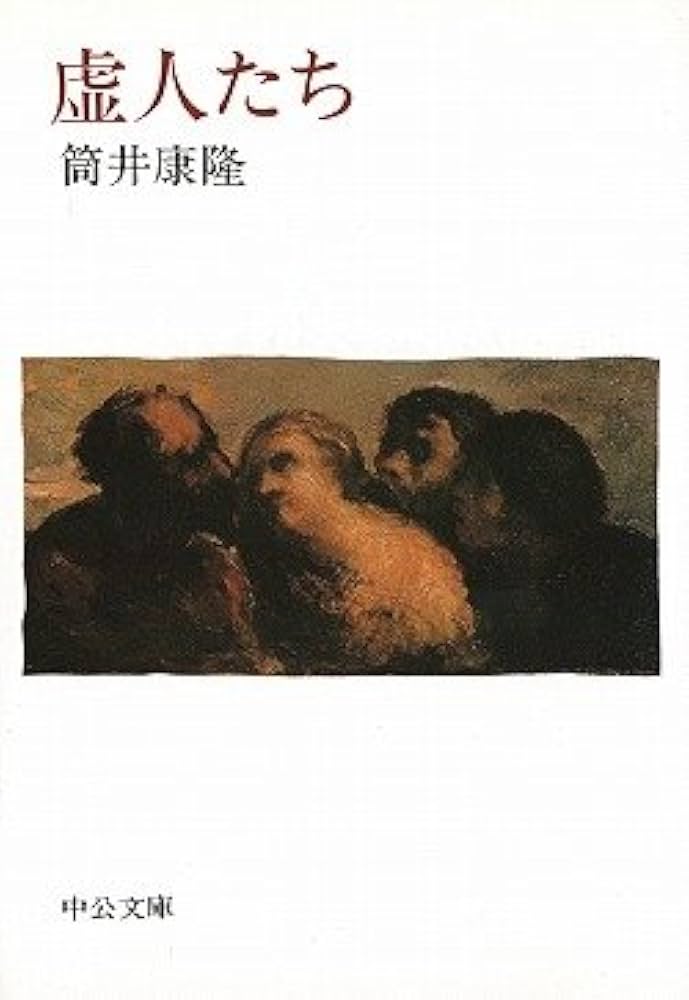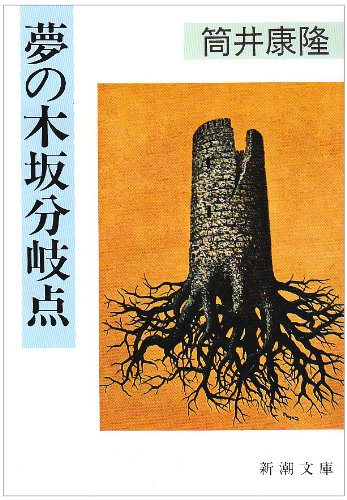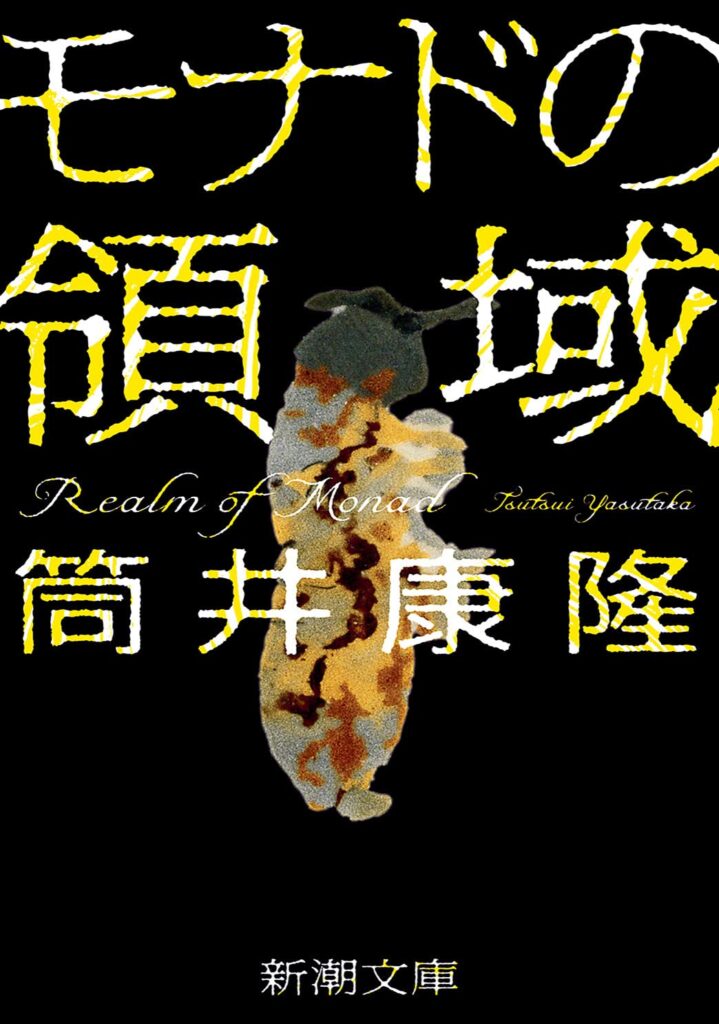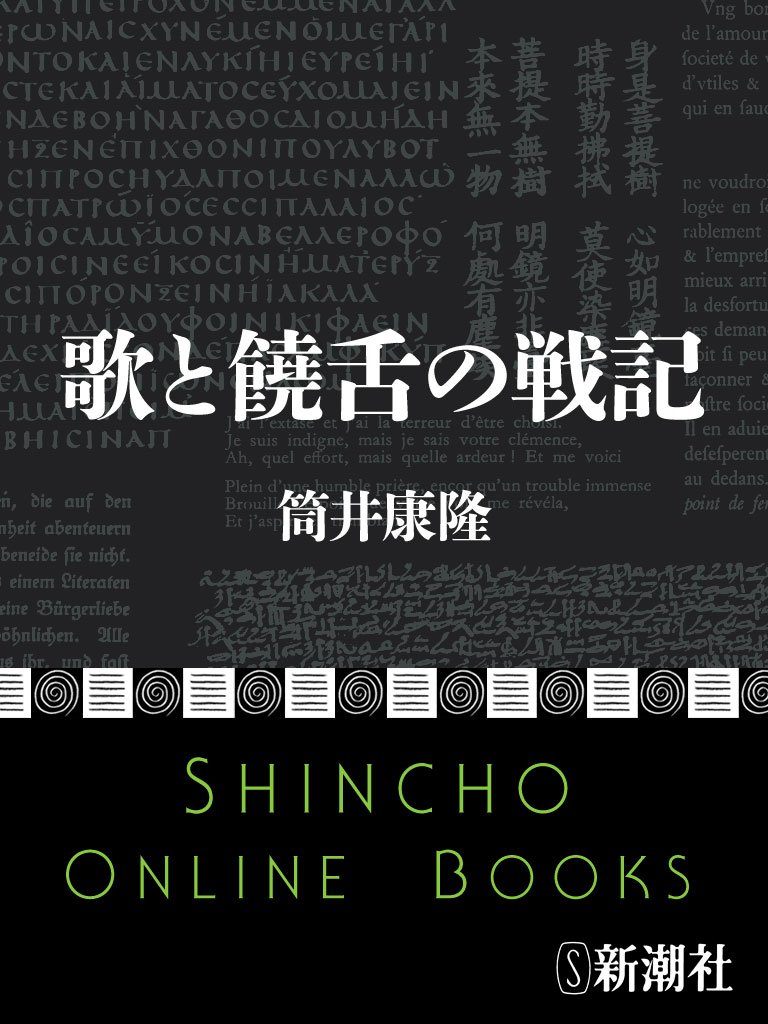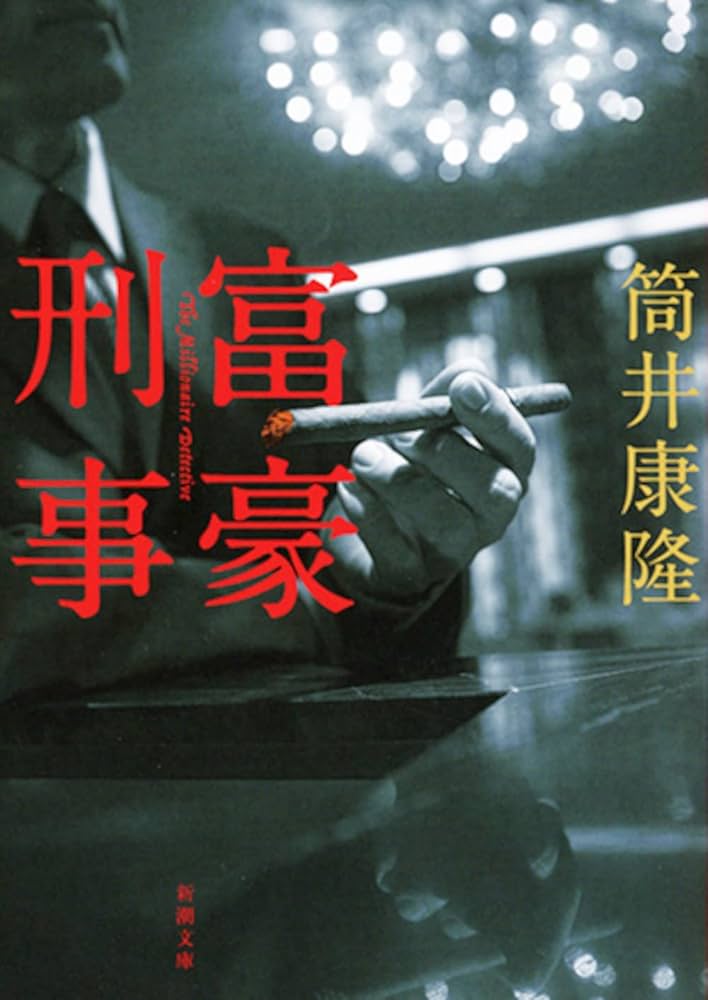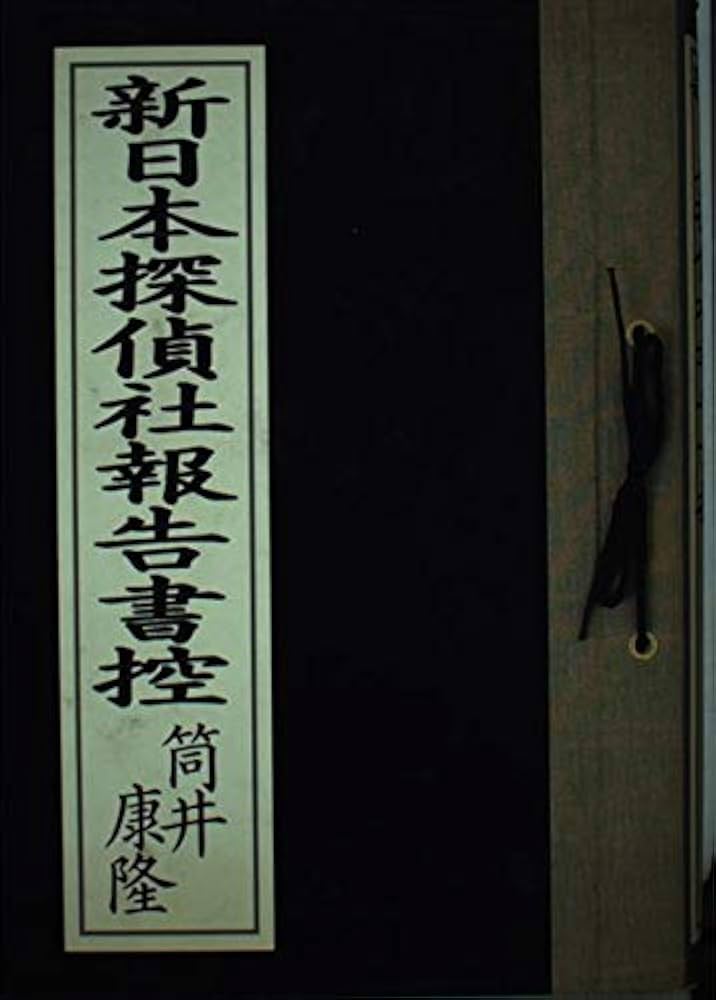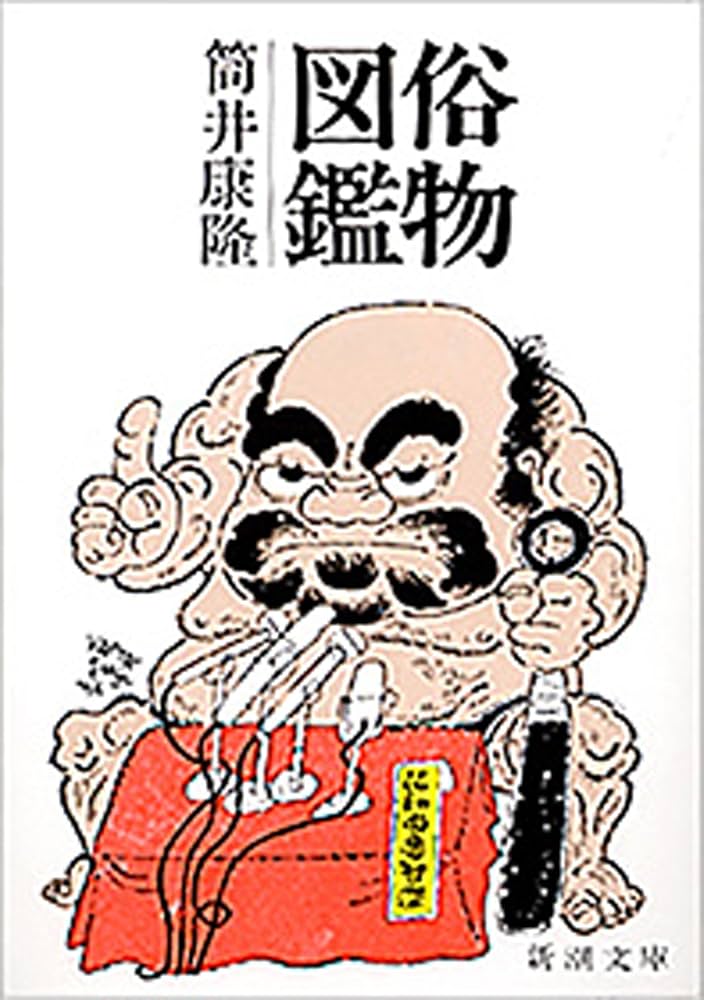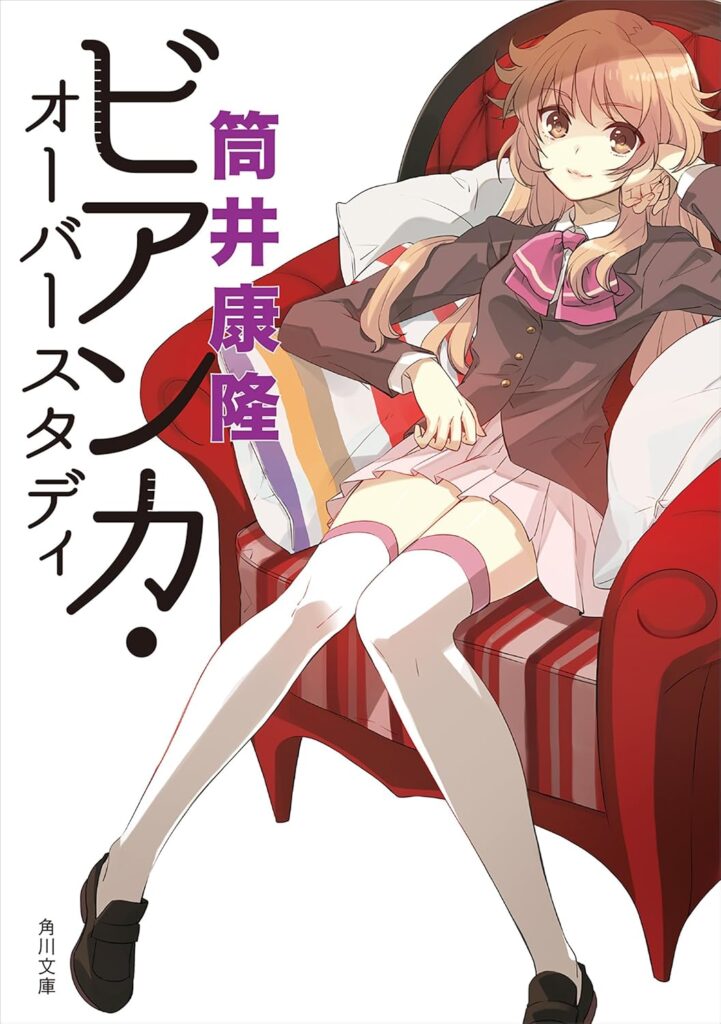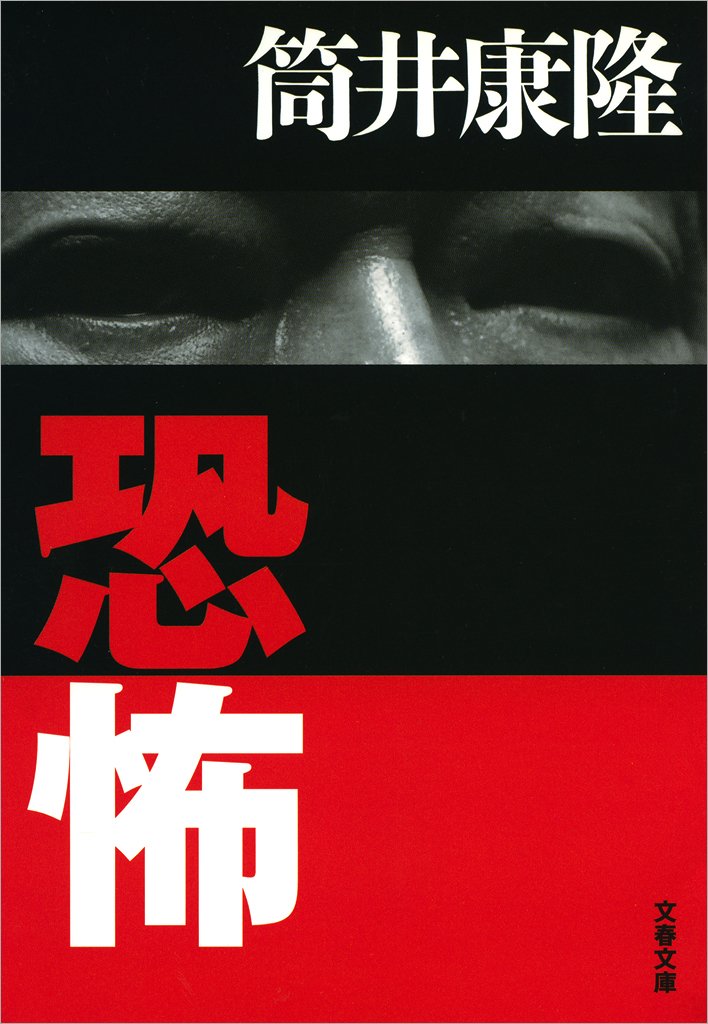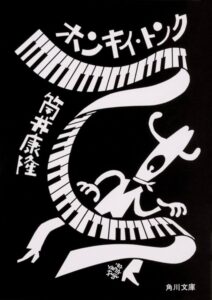 小説『ホンキイ・トンク』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。筒井康隆氏が1969年に発表したこの作品は、半世紀以上前のものですが、現代社会が直面するテクノロジーと人間の関係性、そしてその先にある人間の本質を鋭く描いていると言えるでしょう。一国の運命をコンピューターに委ねるという奇抜な設定は、発表当時としては斬新な発想だったに違いありません。
小説『ホンキイ・トンク』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。筒井康隆氏が1969年に発表したこの作品は、半世紀以上前のものですが、現代社会が直面するテクノロジーと人間の関係性、そしてその先にある人間の本質を鋭く描いていると言えるでしょう。一国の運命をコンピューターに委ねるという奇抜な設定は、発表当時としては斬新な発想だったに違いありません。
この物語が描くのは、コンピューターが絶対的な決定権を持つ世界における人間の滑稽さや、技術の進歩がもたらす予測不能な結果です。当時としてはSF的な未来像だったものが、AIの進化が目覚ましい現代においては、もはや絵空事ではないように感じられます。しかし、だからこそ、この作品が放つメッセージは、今なお私たちの心に深く響くのです。
筒井康隆氏ならではのブラックな視点と、どこか厭世的な雰囲気は、この作品でも健在です。社会の矛盾や人間の愚かさを容赦なく描き出しながらも、読者には不思議な読後感を与えます。果たして、狂ったコンピューターが導き出す結論は、本当に「狂っている」と断言できるのでしょうか。
『ホンキイ・トンク』は、単なるSF小説としてだけではなく、現代社会を生きる私たちに、改めて「人間とは何か」という問いを突きつける示唆に富んだ一冊と言えるでしょう。読み終えた後には、きっと、あなたの固定観念を揺さぶるような、忘れられない読書体験が残るはずです。
小説『ホンキイ・トンク』のあらすじ
『ホンキイ・トンク』は、駆け出しのコンピューター技師である築井が、上司からの無茶な辞令を受け、人口わずか3万人の新興国バカジアへと派遣されるところから物語が始まります。バカジアは、格安コンピューター「NG100型」を日本から買い付けた国で、その不安定な政情ゆえ、全ての意思決定を人間ではなく機械に任せるという前代未聞の試みに着手しようとしていました。
築井は、通訳もプログラマーもいない状況で、一人でバカジアに渡り、コンピューターを組み立てるという困難な任務を強いられます。日本を出てから3週間後、ようやくバカジアにたどり着いた築井の前に現れたのは、この国の若き元首であるプリンセス・ミオでした。彼女はコンピューターに強い好奇心を抱き、築井から熱心に情報を引き出そうとします。
翌日から、築井はミオと共にNG100型の組み立て作業に取りかかります。ミオはコンピューターの知識や操作方法を熱心に学び、築井は彼女に付きっきりで指導します。しかし、このコンピューター室には、ミオに秘かな想いを寄せる公爵のテレガーベラ・ポリが度々現れ、二人の間に割って入ろうとするため、作業はなかなか捗りません。
ミオの権限で公爵をコンピューター室への立ち入り禁止にし、何とか組み立てを終えたNG100型は、ついに記者団への披露目に漕ぎ着けます。しかし、ここで問題が発生します。NG100型が次々と打ち出す政策は、国内のカジノ禁止の翌日に賭博オリンピックの開催を決定したり、農地がないにも関わらず農地改革を宣言したり、爆弾の作り方も分からないのに核実験登録の申し込みをするなど、常識では考えられない奇想天外なものばかりでした。
どうやら、日本からの長時間の船旅のせいで、NG100型の中枢回路の調律に狂いが生じていたようです。バカジアは世界の笑い者になり、築井は自社製品の評判を落としたとして会社を馘になってしまいます。しかし、この狂ったコンピューターが打ち出す政策は、皮肉にもバカジアを世界一の人気国へと押し上げ、連日観光客が押し寄せるようになります。
実は、ミオは築井に内緒でコンピューターに細工をし、わざと調律を狂わせていたのでした。仕事も婚約者も失って日本に帰るわけにはいかない築井は、ミオに泣きつき、バカジアに永住することを決意します。しかし、築井とミオの密会疑惑が週刊誌に浮上し、外国人である築井へのバッシングが止まらない中、彼はバカジアを追われることになります。そして、ミオはテレガーベラとの婚約を発表するのです。
小説『ホンキイ・トンク』の長文感想(ネタバレあり)
『ホンキイ・トンク』を読んだとき、まず驚かされたのは、50年以上も前に書かれた作品でありながら、その内容が現代社会とあまりにもリンクしている点でした。人工知能の急速な発展や、あらゆる分野での自動化が進む現代において、私たちはまさに「コンピューターに委ねる」という選択を迫られているように感じます。この作品は、その選択がもたらす可能性と、同時に潜む危険性を、筒井康隆氏ならではの視点で描いてみせます。
主人公の築井は、ごく普通のコンピューター技師です。彼がバカジアという奇妙な国に派遣され、国家の命運を左右するコンピューターの設置に携わることになるのですが、その過程で彼は、自身の常識や価値観が次々と揺さぶられていく体験をします。特に印象的だったのは、NG100型が打ち出す政策が、当初は「狂っている」としか思えないものだったにも関わらず、結果的にバカジアを国際社会の注目を集める国へと変貌させていくという点です。
「狂ったコンピューター」が、なぜか「成功」をもたらすというこの皮肉な展開は、私たちに「正しさとは何か」という問いを投げかけてきます。人間が考える合理性や論理が、必ずしも最善の道ではないのかもしれない、という逆説的なメッセージが込められているように感じました。社会の規範や常識といったものが、いかに相対的なものであるかを、この作品は静かに、しかし鮮烈に示唆しています。
そして、この物語の核心にあるのが、プリンセス・ミオの存在です。彼女が意図的にコンピューターの調律を狂わせたという事実が明かされた時、私は大きな衝撃を受けました。彼女は、コンピューターの「狂気」をむしろ利用し、自国の現状を打破しようとしたのです。これは、人間がテクノロジーをどう使いこなすか、あるいはどう「弄ぶ」かという、より深いテーマを提示しているように思えます。
ミオの行動は、ある意味で非常に大胆であり、同時に計算高いとも言えます。彼女は、停滞したバカジアを変えるために、既成概念にとらわれない発想を必要としていたのでしょう。そして、その手段として「狂ったコンピューター」を選んだ。これは、私たちの社会が常に新しい発想や非常識を受け入れることの重要性を説いているようにも読めます。安定を求めるばかりでは、何も変わらない。時には「狂気」を受け入れることで、新たな道が開かれることもある、と。
また、公爵のテレガーベラ・ポリというキャラクターも、人間のエゴや嫉妬といった感情の普遍性を象徴しています。彼はミオに想いを寄せ、築井に嫉妬し、二人の関係を邪魔しようとします。コンピューターが国家の意思決定を担うというSF的な設定の中で、人間の感情が、いかに変わらず、そしていかに滑稽であるかを示しているように感じました。テクノロジーがどれだけ進化しても、人間の感情は変わらない。むしろ、テクノロジーが、そうした人間の根源的な感情をより鮮明に浮き彫りにする、という視点も読み取れます。
作品全体を覆うのは、筒井康隆氏ならではのブラックユーモアです。バカジアという国の名前自体が、既にその国の非合理性や滑稽さを暗示していますし、コンピューターが打ち出す政策も、その狂気と同時に、どこか笑いを誘います。しかし、その笑いの裏には、人間の愚かさや、社会の矛盾に対する鋭い洞察が隠されています。読者は笑いながらも、ふと立ち止まって考えさせられる、そんな二重構造がこの作品の魅力です。
築井が、最終的にバカジアを追われ、世界を放浪する姿は、ある種の寓話的な結末と言えるでしょう。彼は、コンピューターの調律を狂わせることに一流であるとされますが、それは彼がミオによって利用され、そして捨てられた存在であることを示唆しています。テクノロジーに翻弄される人間の姿、あるいは、テクノロジーを操る人間によって弄ばれる人間の姿が、そこに描かれています。
この作品は、SFというジャンルの枠を超え、現代社会におけるテクノロジーと人間の関係性、そして真実や常識といったものの曖昧さを深く考えさせてくれます。人工知能がますます私たちの生活に浸透していく中で、『ホンキイ・トンク』が提示する問題意識は、今後さらにその重要性を増していくに違いありません。
コンピューターが全てを決定する世界。それは、果たしてディストピアなのでしょうか、それともユートピアなのでしょうか。この作品は、その答えを明確には示しません。むしろ、その問いを読者一人ひとりに委ねることで、私たち自身の思考を促します。私たちは、コンピューターにどこまでを委ね、どこからを自分たちの手で切り拓いていくべきなのでしょうか。
また、筒井康隆氏の文章表現も、この作品の大きな魅力です。独特のリズム感と、時に唐突に、時に綿密に描写される情景は、読者を物語の世界へと引き込みます。一見すると荒唐無稽な設定でありながら、その描写は非常にリアリティがあり、まるで本当にそのような国が存在し、そのような出来事が起こっているかのような錯覚に陥ります。
特に、NG100型が次々と打ち出す政策の内容や、それに対するバカジア国民や国際社会の反応の描写は、筒井康隆氏の社会に対する洞察の深さを感じさせます。人間が、いかに簡単に、そしていかに滑稽に、新しいものや「狂った」ものに踊らされるか。その普遍的な人間の性質が、この作品には描かれています。
そして、最後のシーンでミオがテレガーベラと婚約を発表する展開は、築井の立場からすれば残酷であり、ミオの冷徹さを示すものでもあります。しかし、これは、権力者のしたたかさ、そして、目的のためならば手段を選ばない人間の本質を露わにしているとも言えるでしょう。築井は、ミオの策略の駒に過ぎなかったという、ある種の虚無感が残ります。
『ホンキイ・トンク』は、単なるSFエンターテインメントとしてではなく、現代社会が抱える問題や、人間の本質を深く考察するための示唆に富んだ作品です。テクノロジーの進化が加速する現代において、この作品が描くテーマは、ますます私たちにとって身近なものとなるでしょう。だからこそ、今改めて、この『ホンキイ・トンク』を手に取る意義があると言えるのです。
まとめ
『ホンキイ・トンク』は、筒井康隆氏が半世紀以上前に描いたにもかかわらず、現代社会に非常に深く響くSF小説です。一国の意思決定をコンピューターに委ねるという奇抜な設定を通じて、テクノロジーと人間の危うい関係性、そして人間の愚かさや滑稽さを鮮やかに描き出しています。特に、プリンセス・ミオが意図的にコンピューターの調律を狂わせ、それが皮肉にもバカジアを成功へと導く展開は、常識や正しさといった概念の相対性を問いかけます。
この作品は、人工知能の進展が目覚ましい現代において、より一層その示唆に富んだ内容が際立ちます。私たちはどこまでをコンピューターに委ね、どこからを自らの意思で決定すべきなのか、という問いを私たちに突きつけます。築井がバカジアを追われ、ミオがテレガーベラと婚約するという結末は、テクノロジーに翻弄される人間の姿と、権力者のしたたかさを印象的に示しています。
全体を通して、筒井康隆氏ならではのブラックユーモアが散りばめられ、読者は笑いながらも、その裏に隠された鋭い社会批判や人間洞察に気づかされます。倫理や道徳といった固定観念が揺さぶられ、私たちは「真の幸福とは何か」という根源的な問いへと誘われます。
『ホンキイ・トンク』は、単なるSF作品として消費されるものではなく、人間の本質や社会のあり方について深く考えさせる、普遍的なテーマを内包した傑作と言えるでしょう。今こそ、この名作を読み返し、未来への洞察を深めてみてはいかがでしょうか。