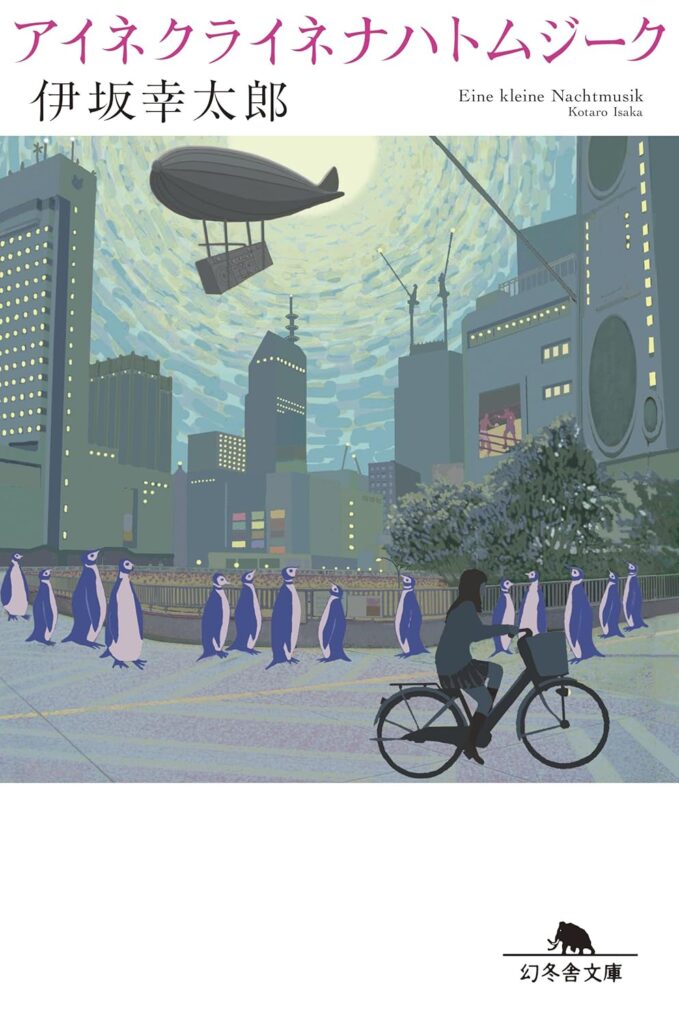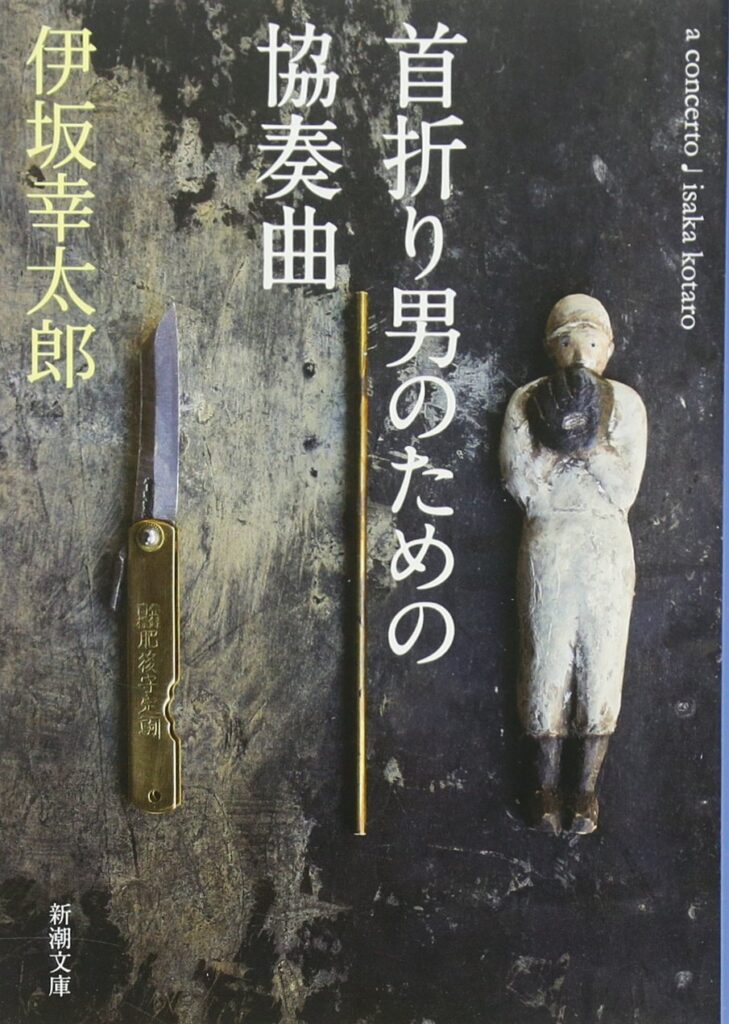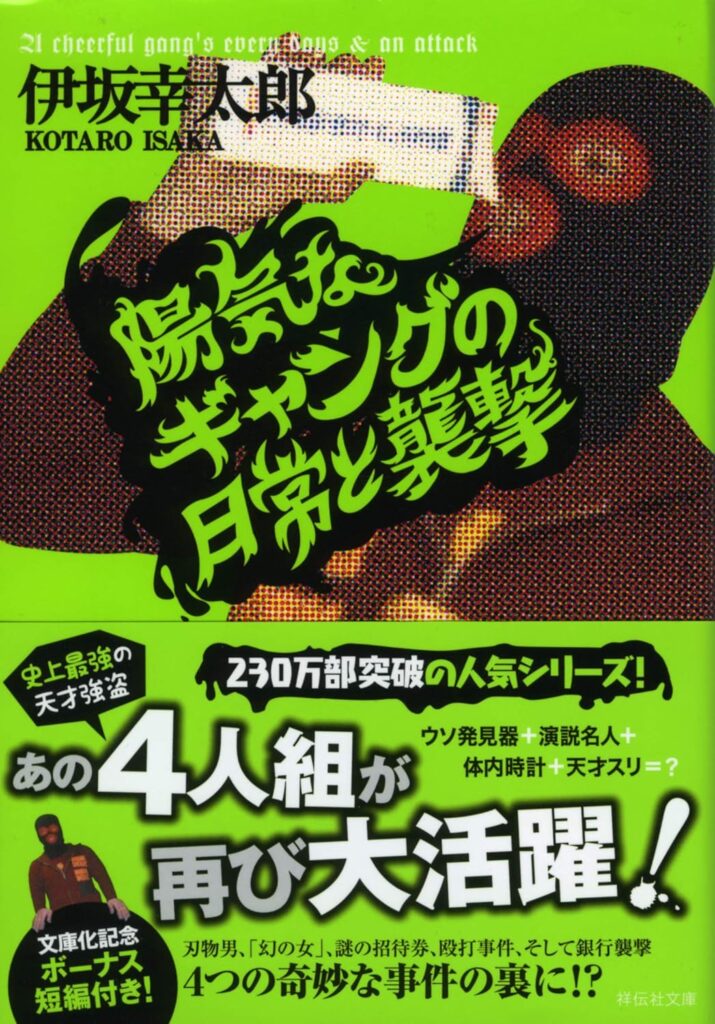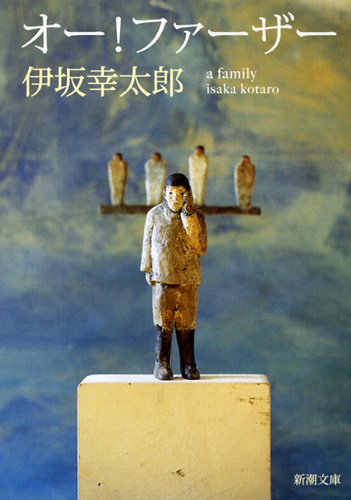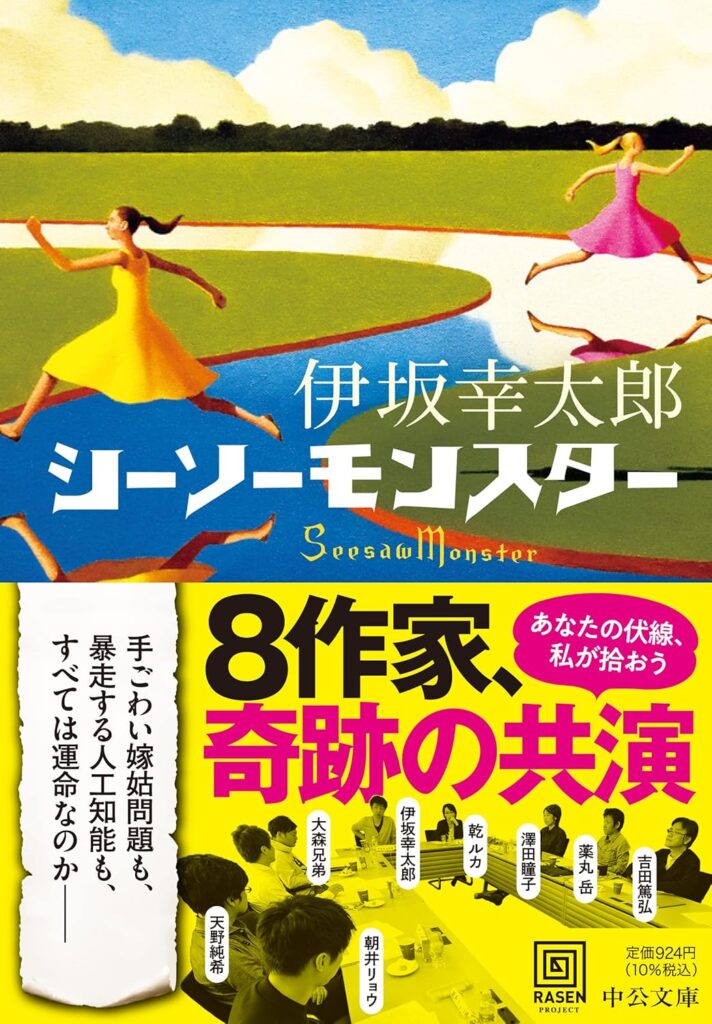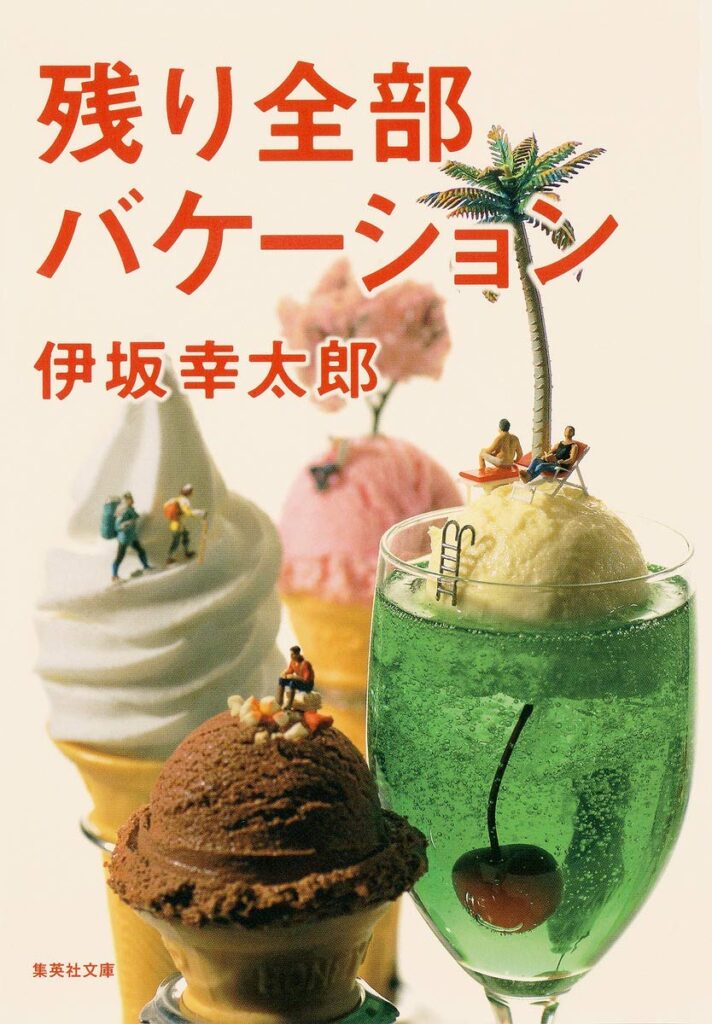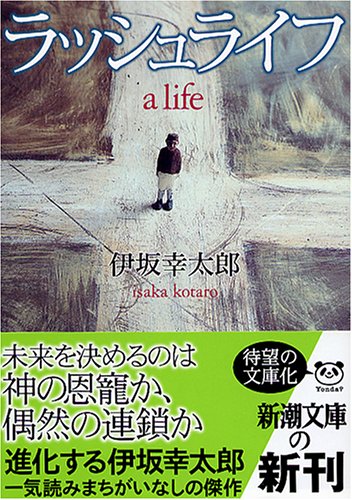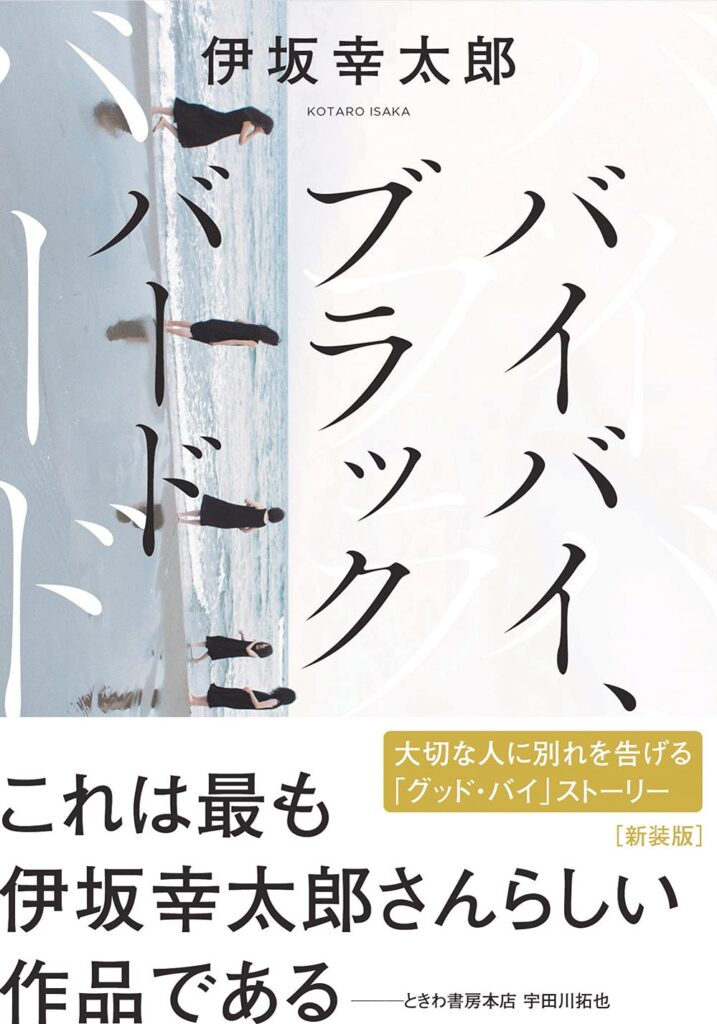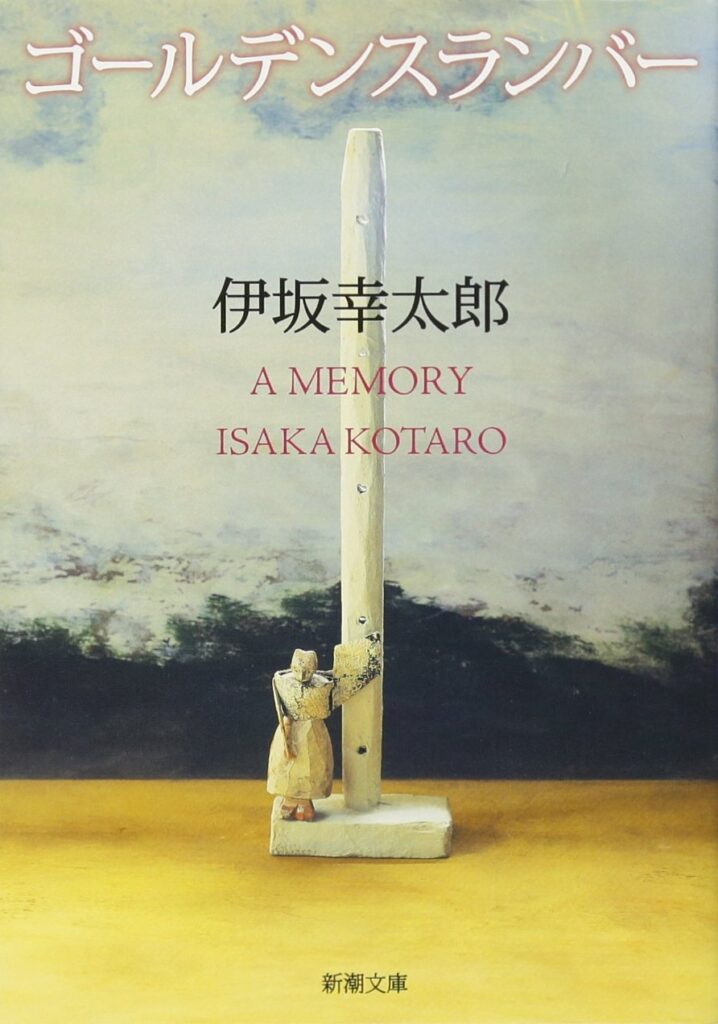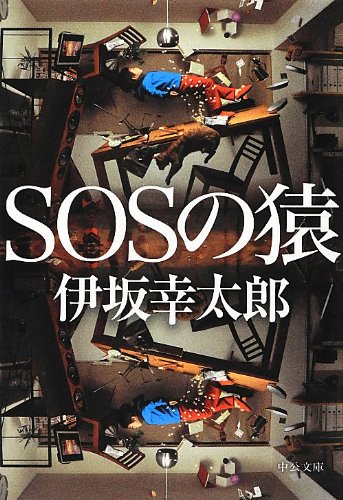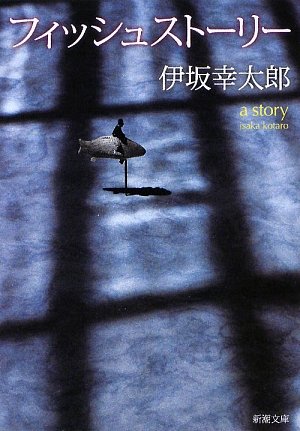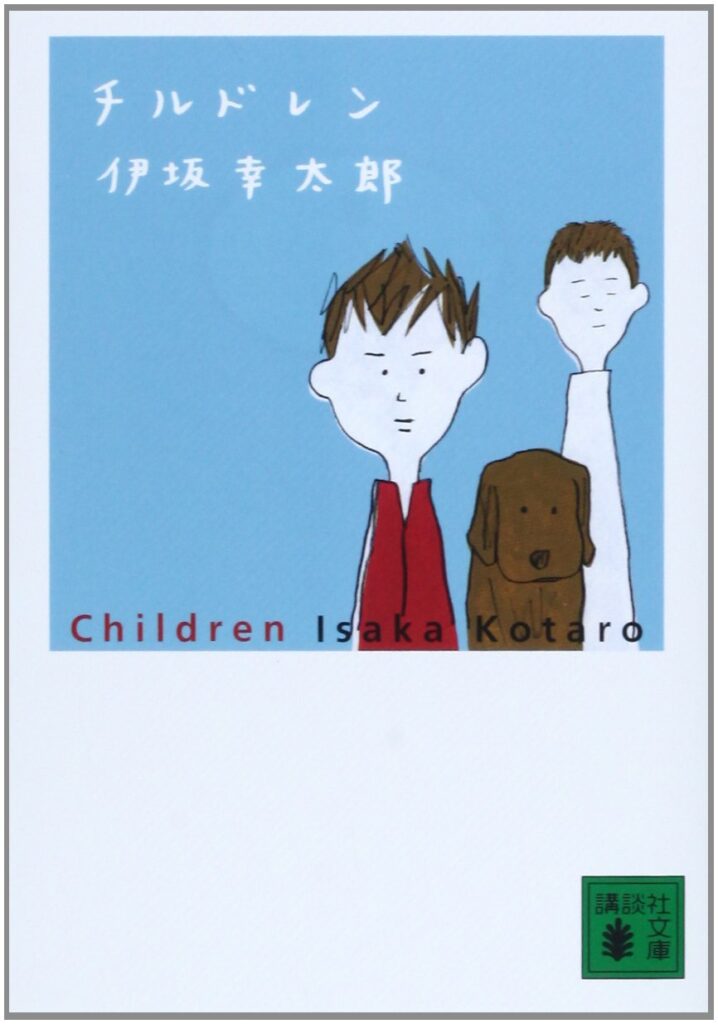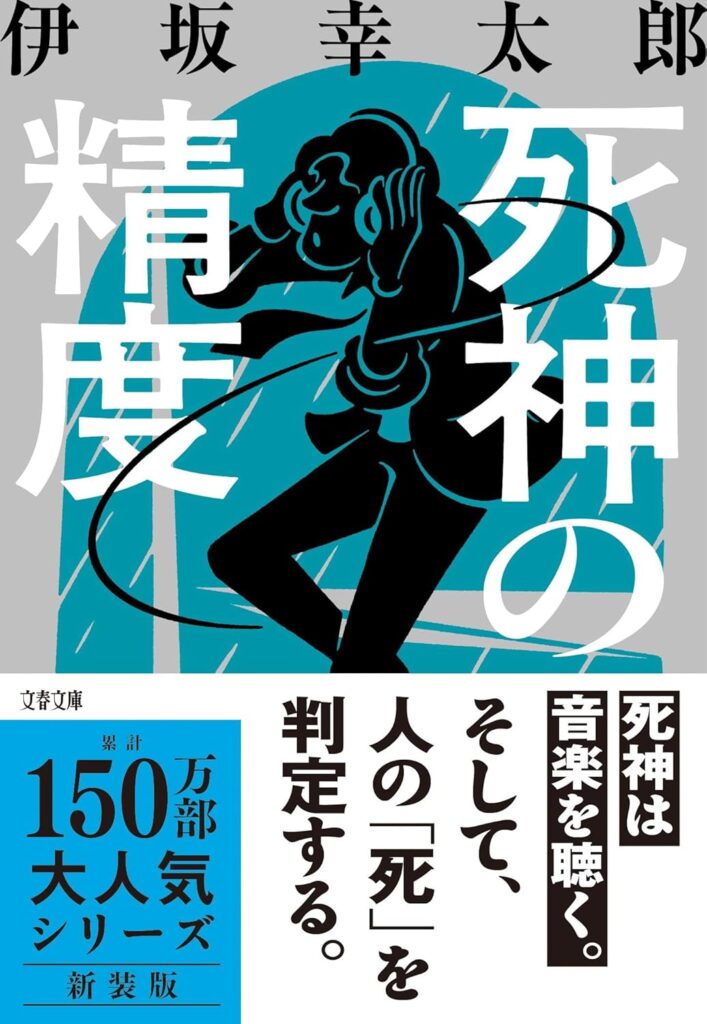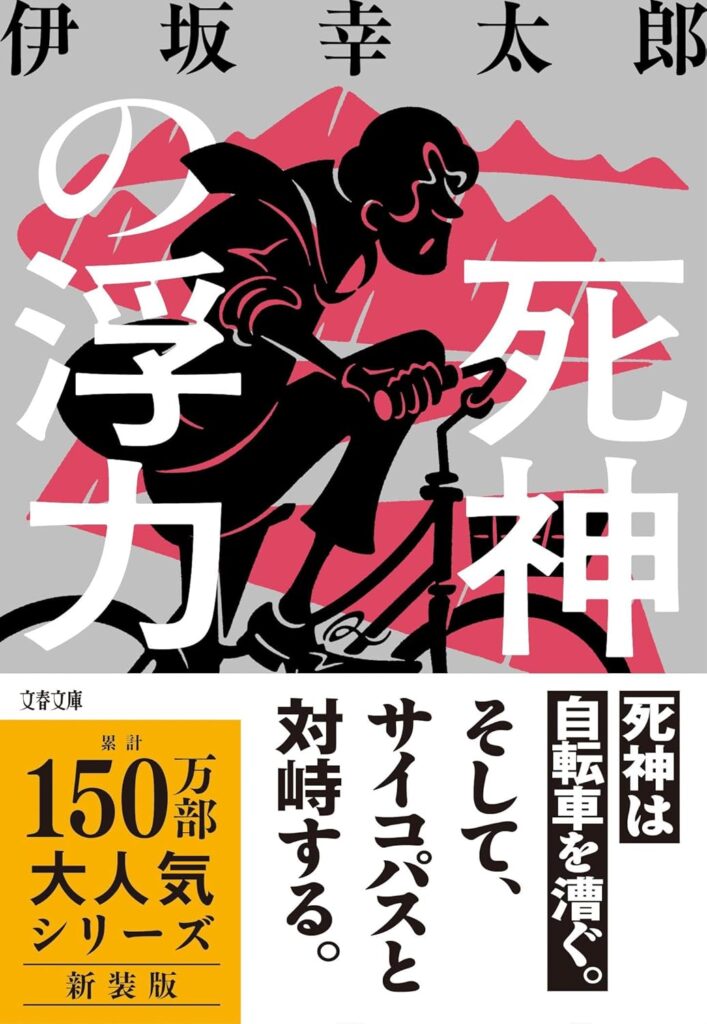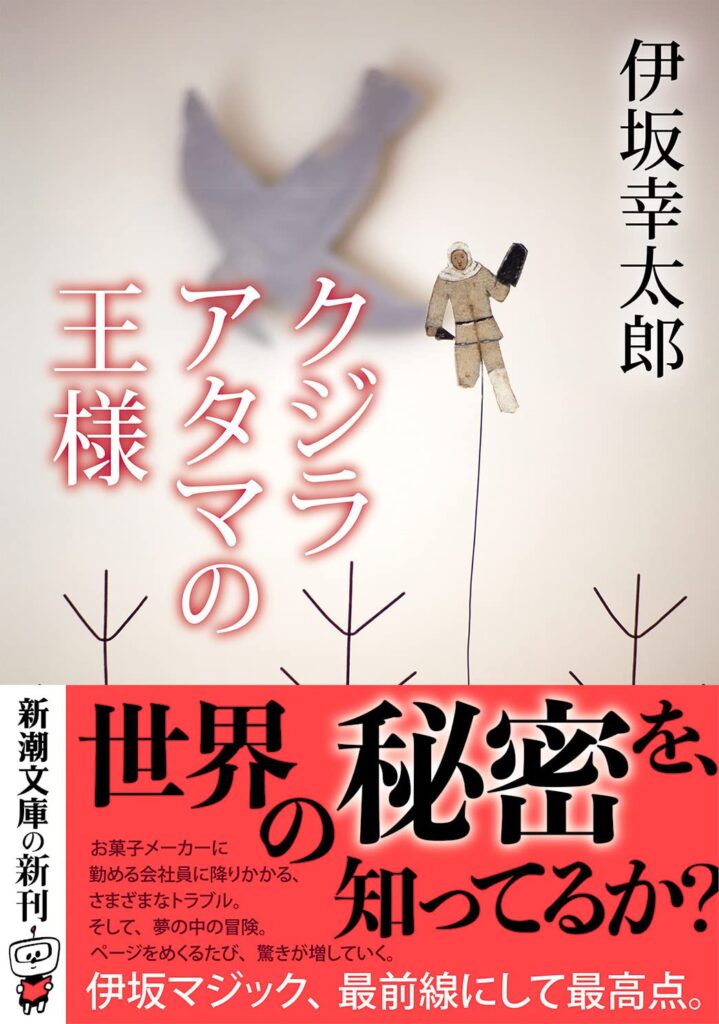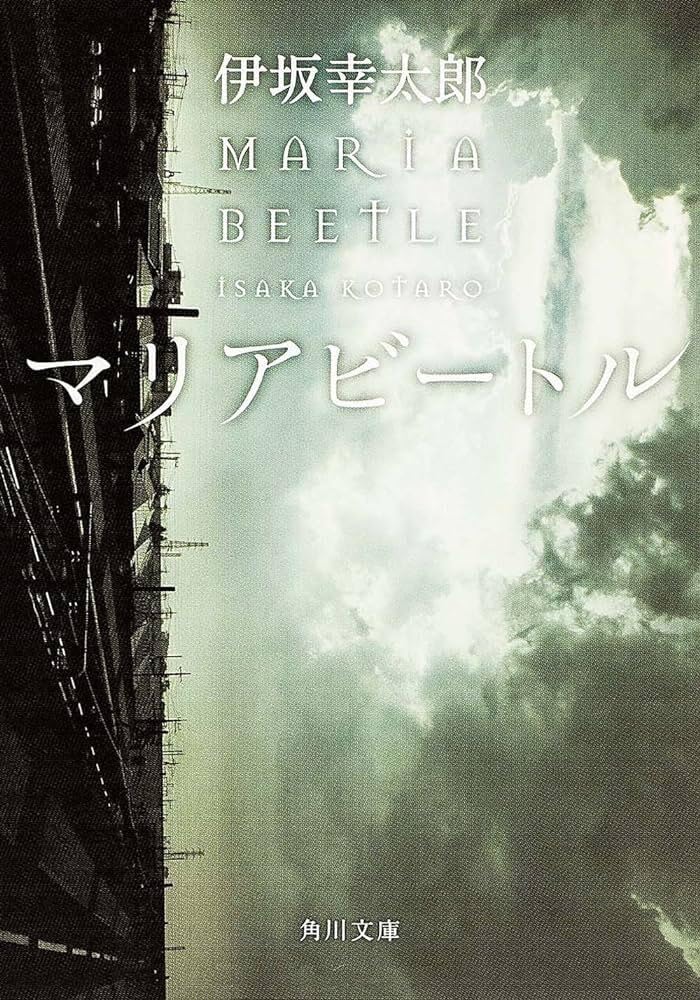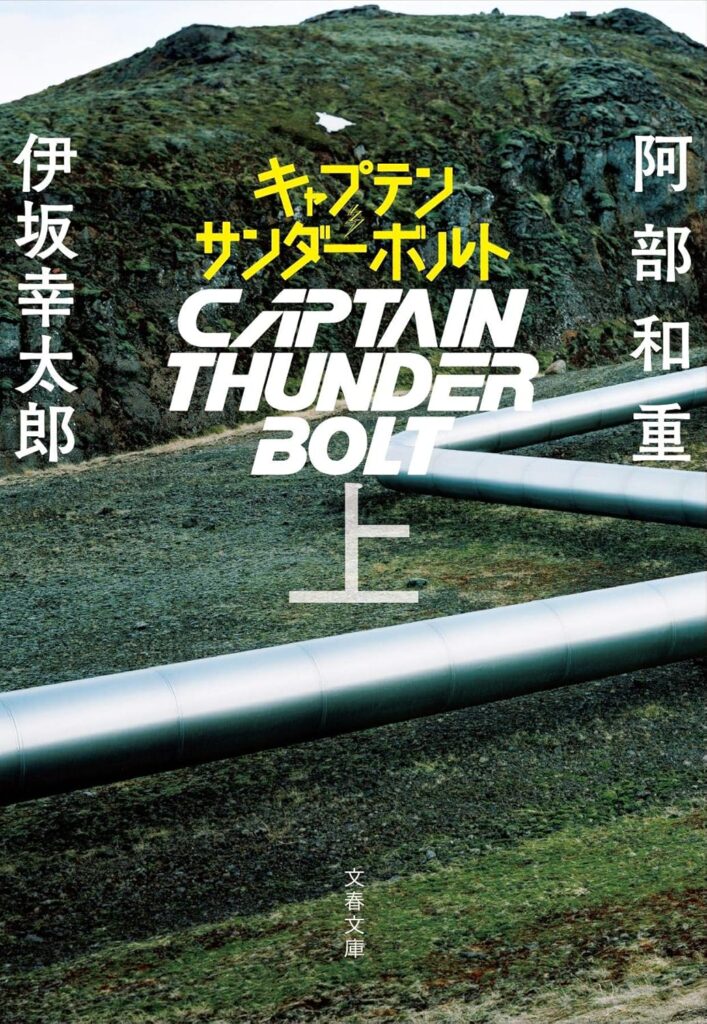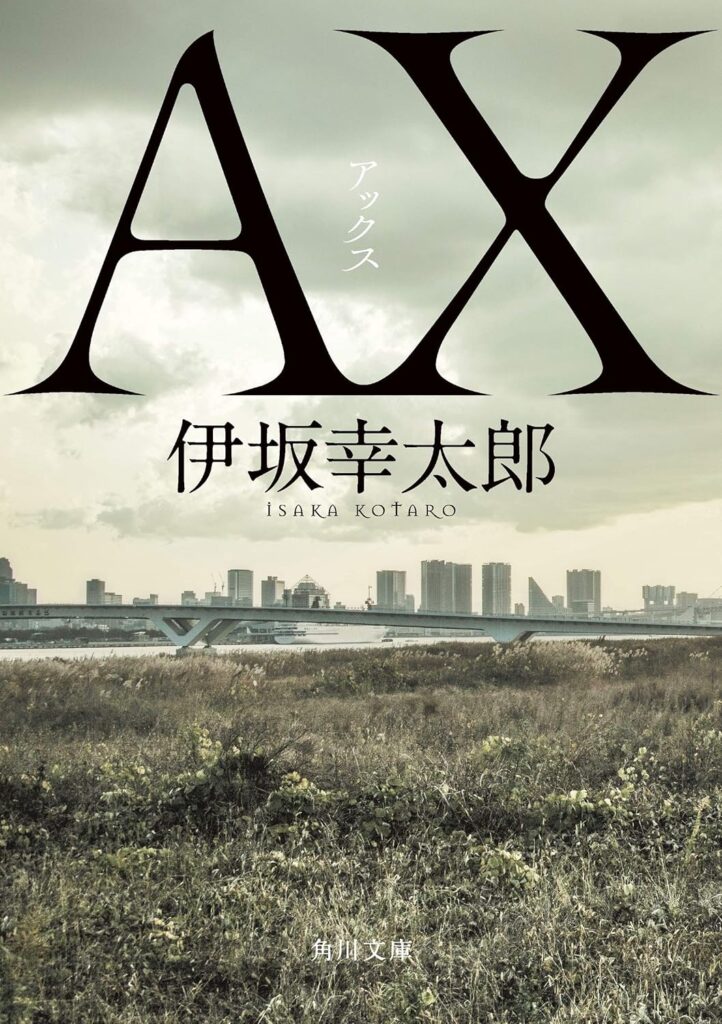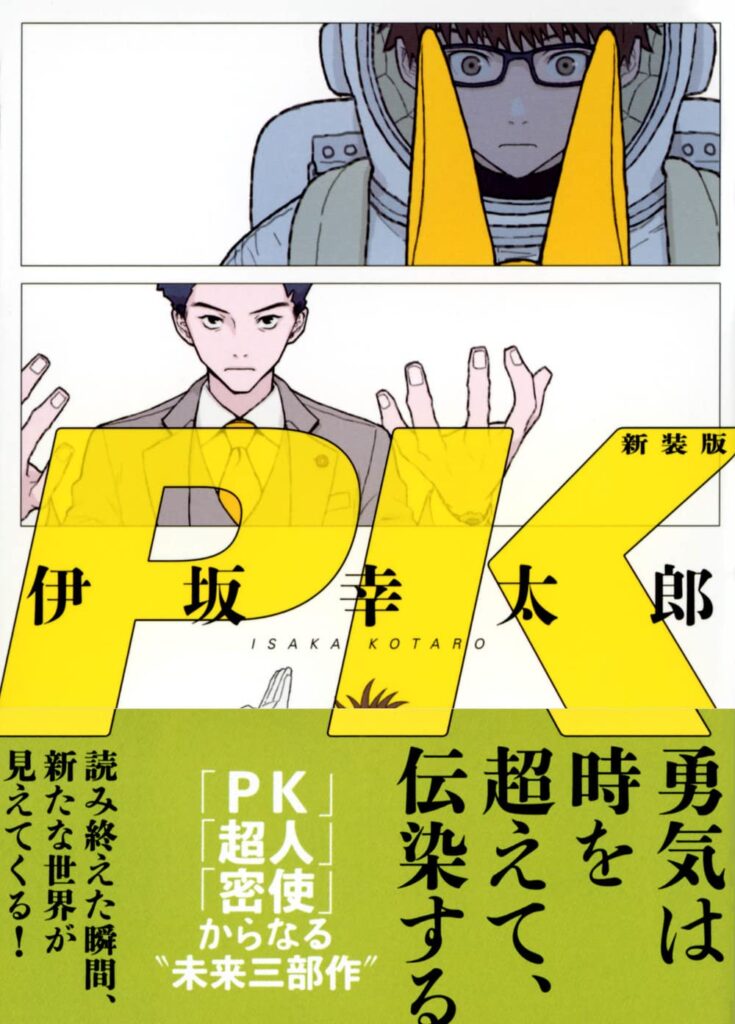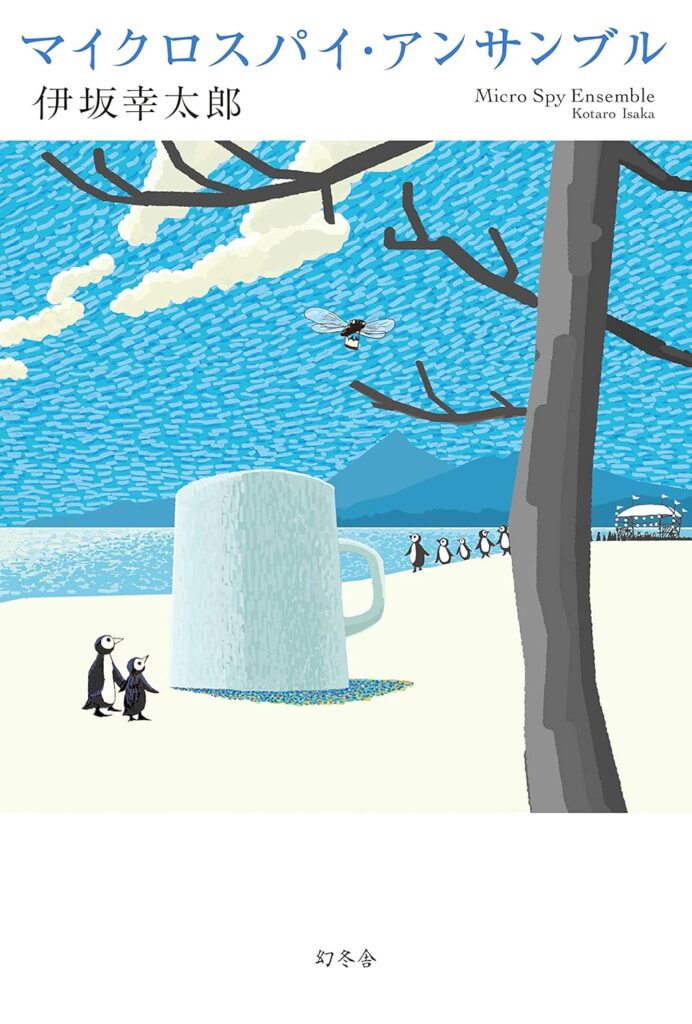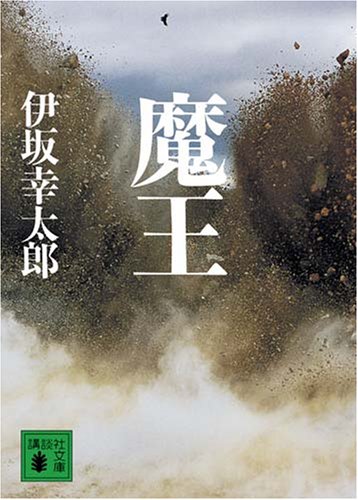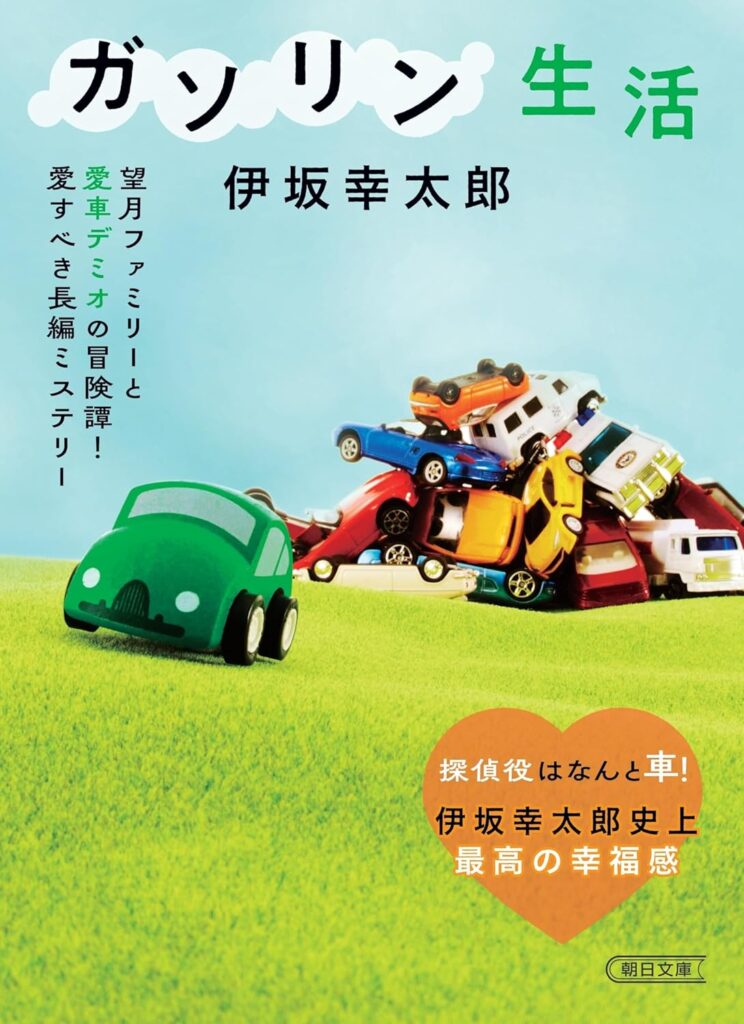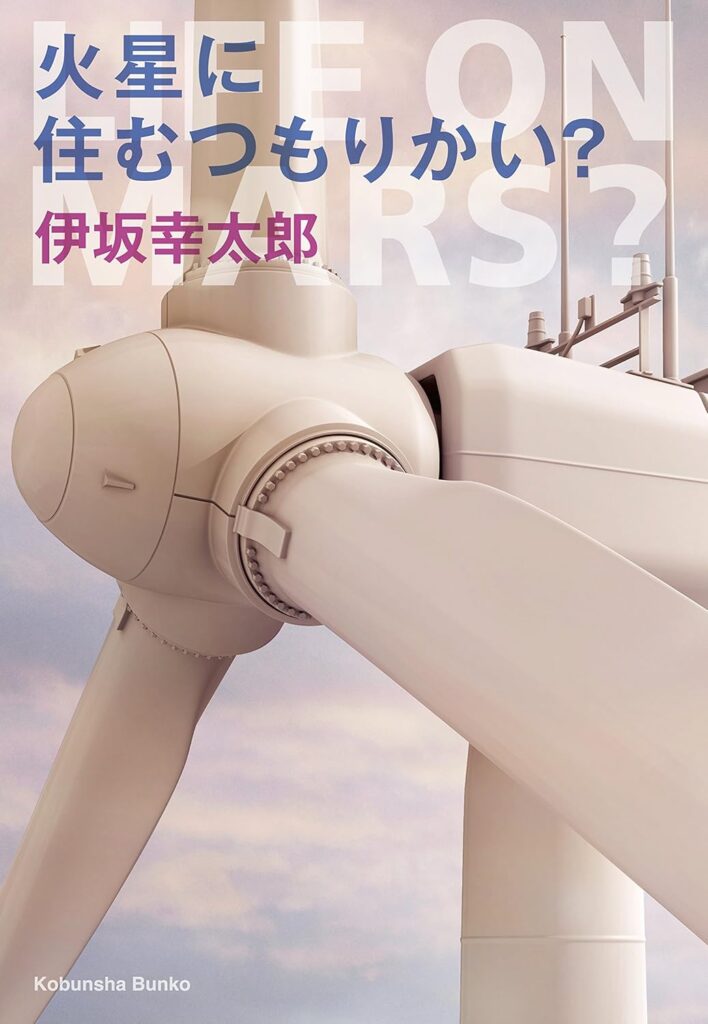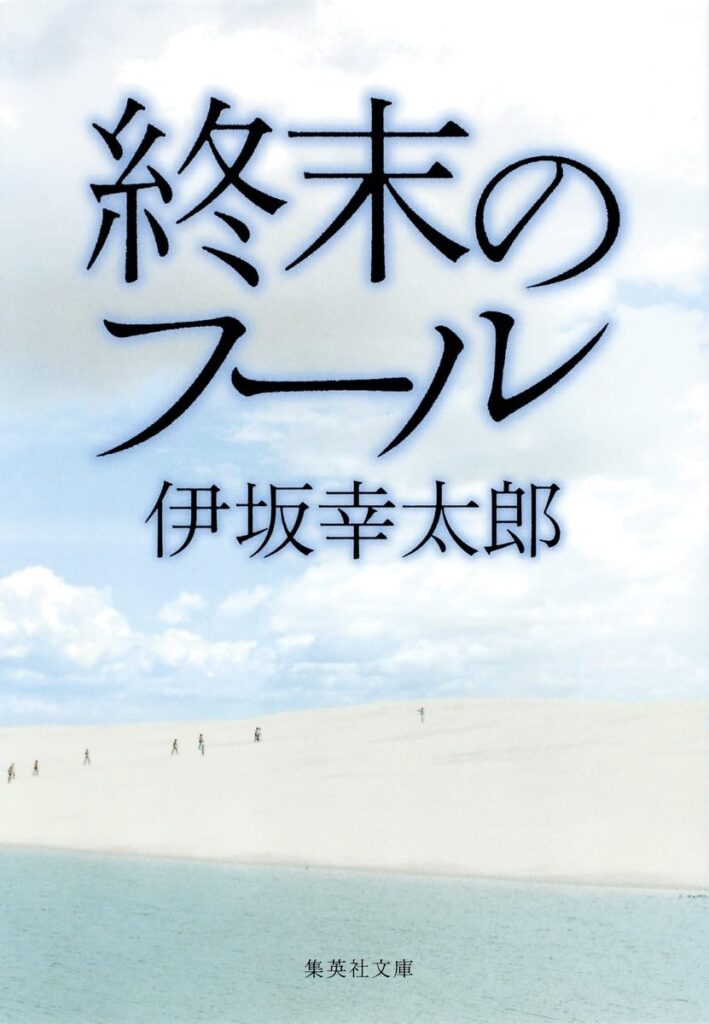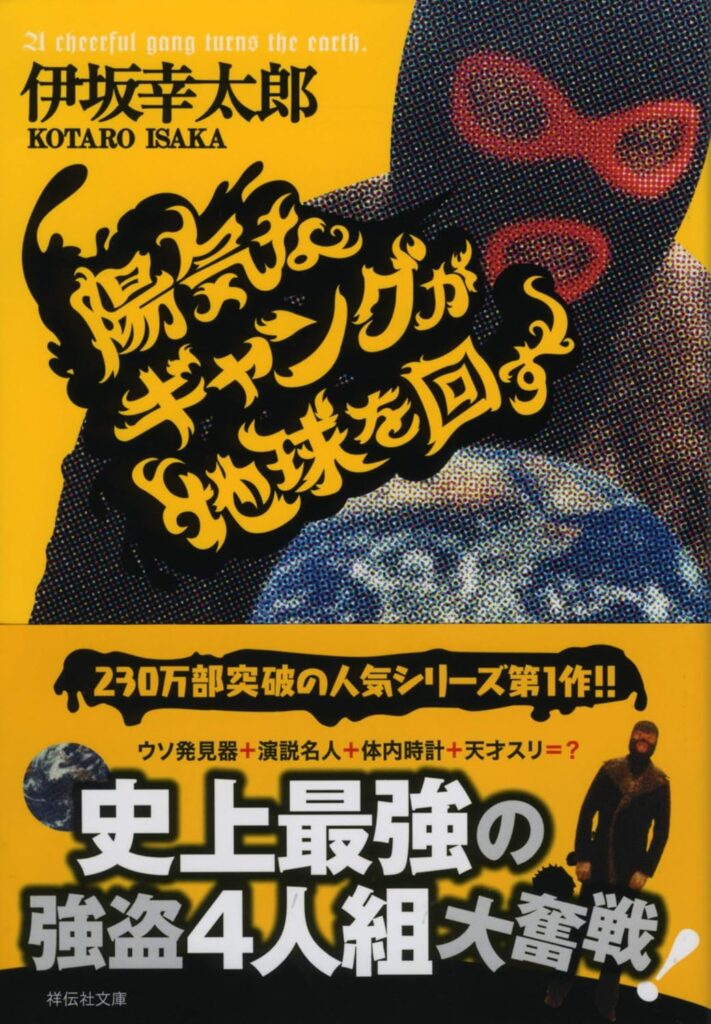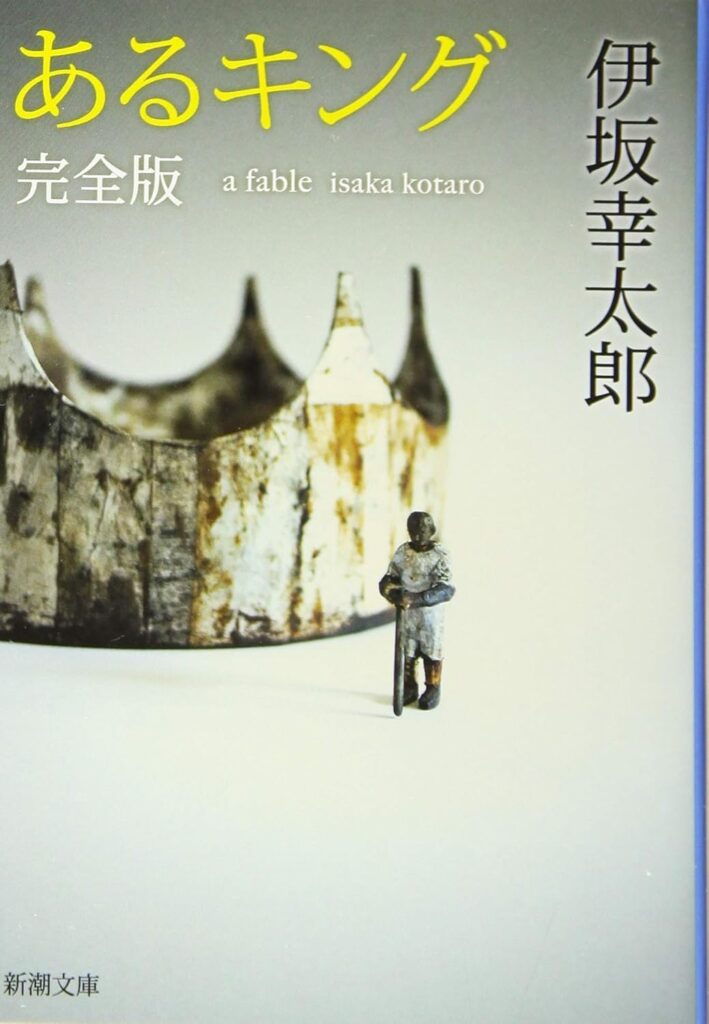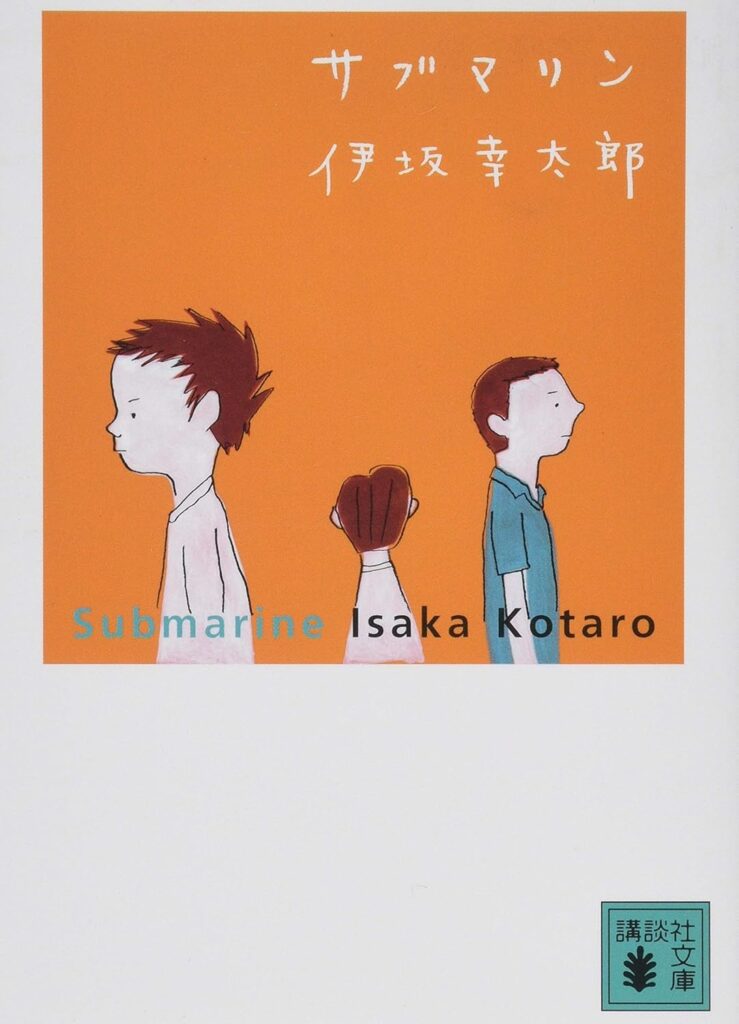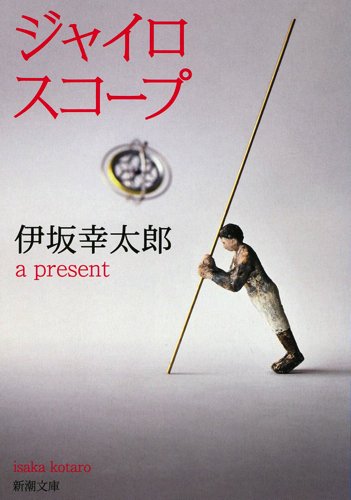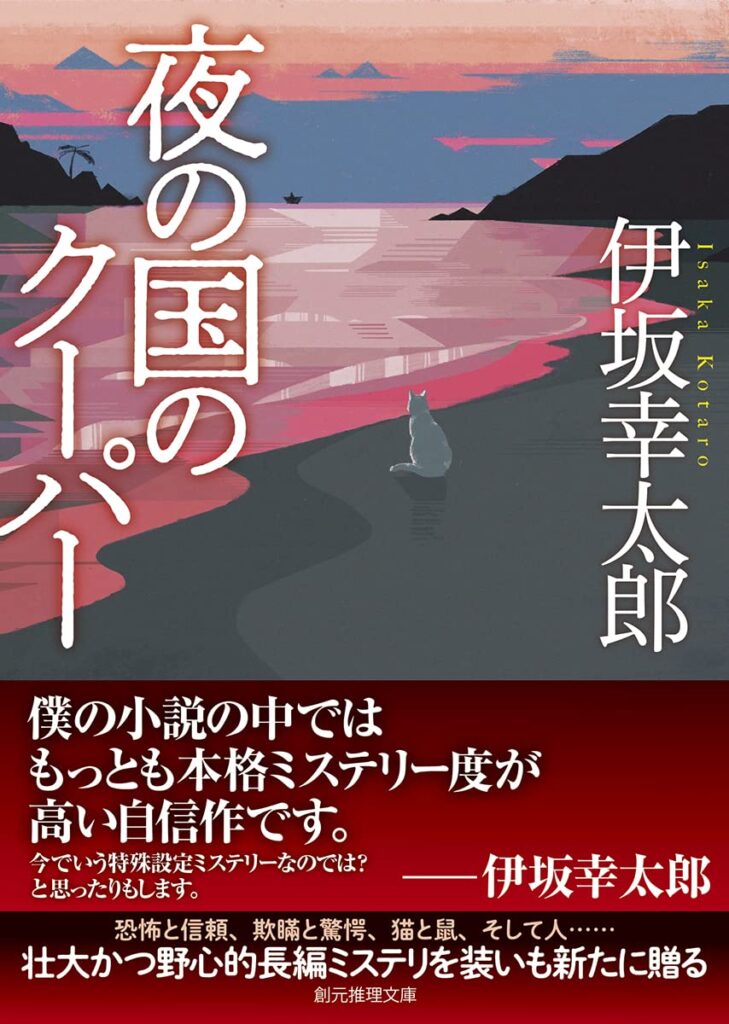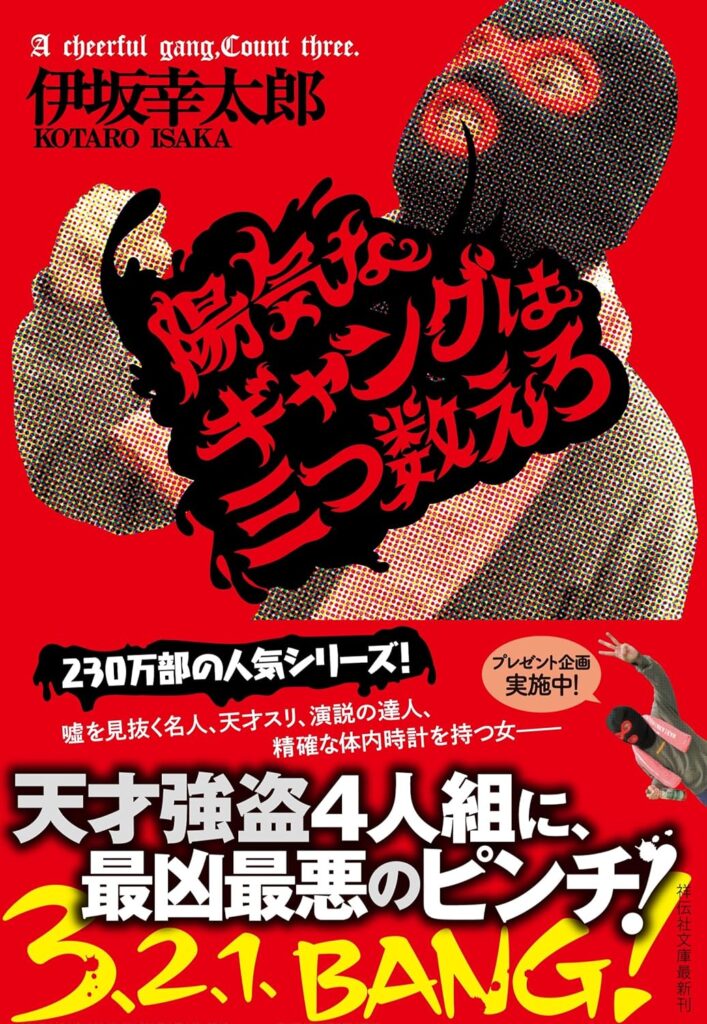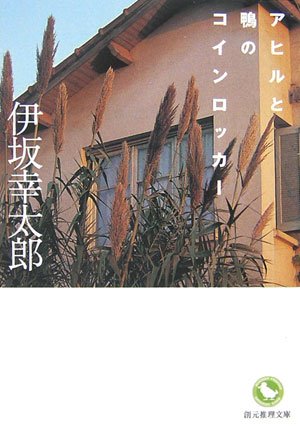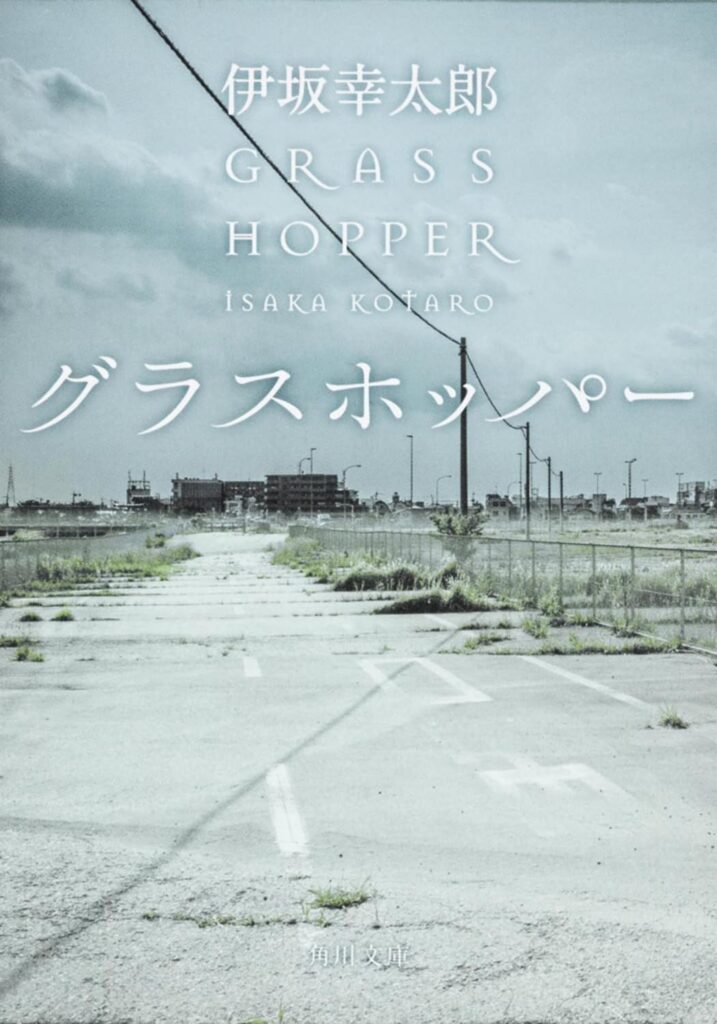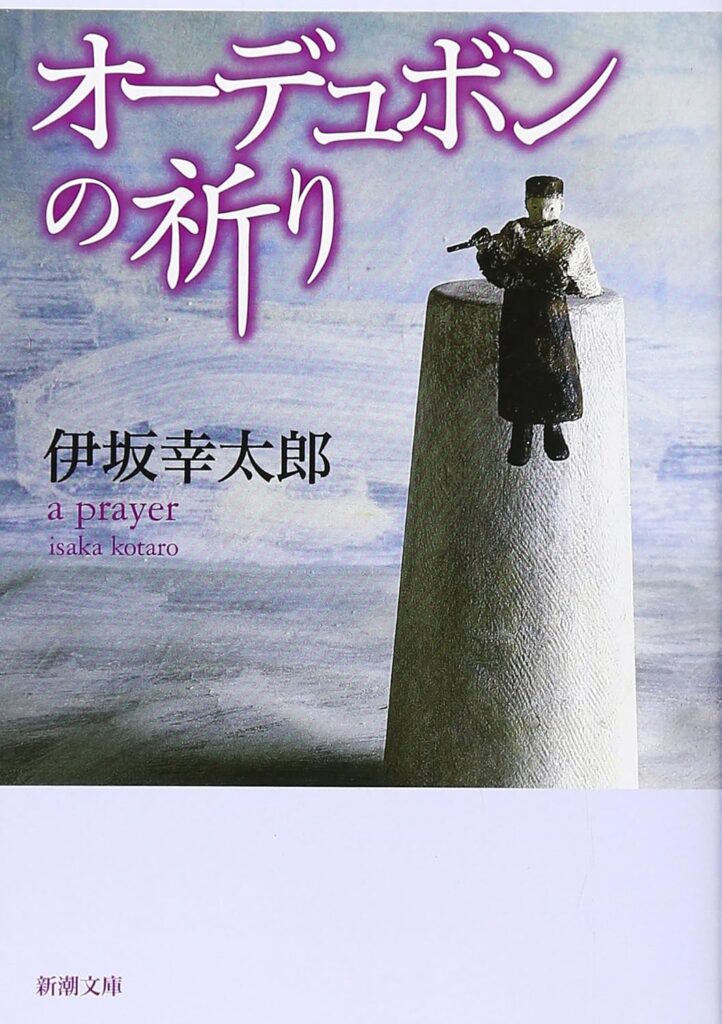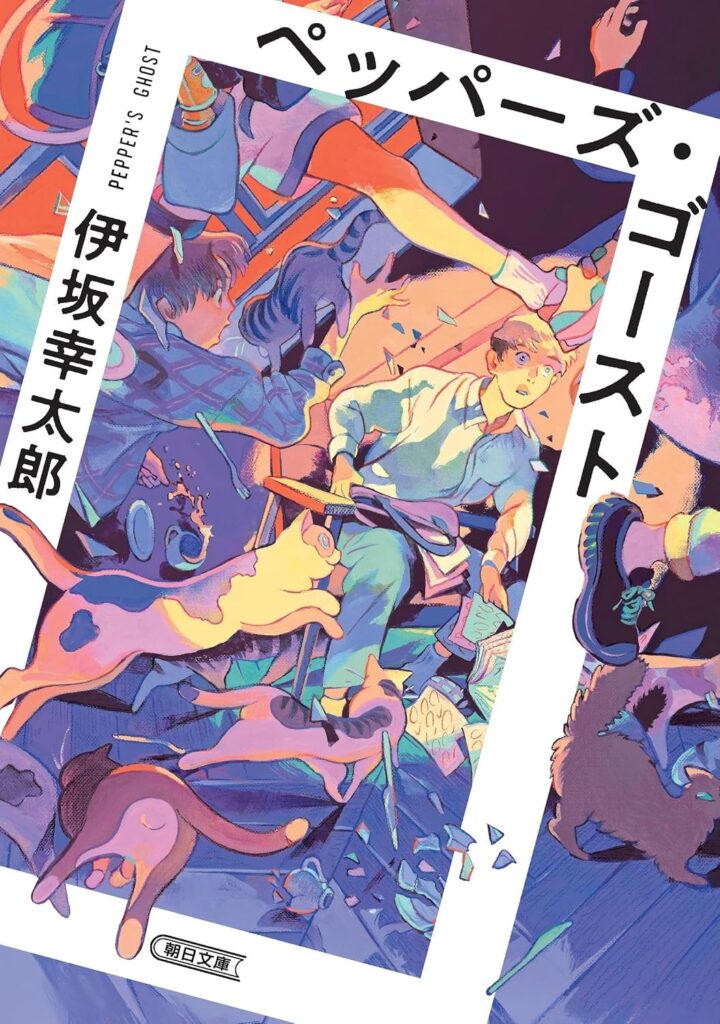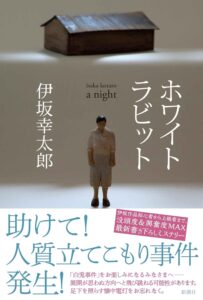 小説「ホワイトラビット」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。伊坂幸太郎さんの作品は、いつもながら独特の世界観と魅力的な登場人物たちが織りなす物語がたまりません。この「ホワイトラビット」も、その例に漏れず、一度読み始めたらページをめくる手が止まらなくなるような引力を持った一冊でした。
小説「ホワイトラビット」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。伊坂幸太郎さんの作品は、いつもながら独特の世界観と魅力的な登場人物たちが織りなす物語がたまりません。この「ホワイトラビット」も、その例に漏れず、一度読み始めたらページをめくる手が止まらなくなるような引力を持った一冊でした。
物語は、誘拐を生業とする組織の一員である主人公・兎田孝則が、自身の妻・綿子が何者かに誘拐されるという衝撃的な出来事から幕を開けます。愛する妻を取り戻すため、彼は組織の裏切り者とされる男を追うことになるのですが、事態は予想もしない方向へと転がっていきます。仙台を舞台に繰り広げられる、緊迫感あふれる展開は、読んでいるこちらの心臓まで掴んで揺さぶるかのようです。
この記事では、そんな「ホワイトラビット」の物語の核心部分に触れながら、その詳しい筋道をご紹介します。さらに、私自身がこの物語を読んで感じたこと、考えたことを、ネタバレを恐れずに、たっぷりと書き連ねてみました。物語の結末や仕掛けについて知りたい方、そして読後の興奮を誰かと分かち合いたいと感じている方にとって、この記事が一助となれば幸いです。
小説「ホワイトラビット」のあらすじ
兎田孝則(とだ たかのり)は、誘拐をビジネスとする犯罪組織に属し、いわゆる「仕入れ」、つまりターゲットを連れ去る役割を担っていました。組織に加わって二年、彼は綿子(わたこ)という女性と結婚したばかりでした。しかし、幸せな新婚生活は長くは続きません。ある日、その最愛の妻、綿子が何者かによって誘拐されてしまうのです。組織のボスである稲葉(いなば)は、綿子の解放と引き換えに、組織の金を横領して逃亡中のコンサルタント、折尾豊(おりお ゆたか)、通称オリオオリオを生きたまま捕らえてくるよう、兎田に非情な命令を下します。
妻を救いたい一心で、兎田は折尾がかつて過ごした宮城県仙台市へと向かいます。仙台駅で偶然にも折尾の姿を発見しますが、格闘の末、取り逃がしてしまいます。しかし、兎田は機転を利かせ、折尾が持っていたバッグにGPS発信機を仕込むことに成功していました。このGPSが示す情報を頼りに、兎田は折尾の潜伏先を突き止めます。それは、仙台市内の高台にある高級住宅街、ノースタウンの一軒家でした。
兎田がその家に忍び込むと、意外にも玄関の鍵は開いていました。家の中を捜索すると、二階の寝室、ベッドの下で折尾を発見します。しかし、折尾はすでに息絶えていました。家の中には、折尾と路上で口論となり、偶発的に彼を死なせてしまった無職の青年・佐藤勇介(さとう ゆうすけ)と、その母親、そして偶然その家に空き巣目的で侵入していた男・黒澤(くろさわ)がいました。「折尾を生きたまま連れてこい」という稲葉からの命令。このままでは綿子の命が危ない。絶体絶命の状況の中、黒澤が奇抜な計画を思いつきます。それが後に「白兎作戦」と呼ばれることになる作戦でした。
黒澤の計画は、この家で人質立て籠もり事件が発生したように偽装し、マスコミを呼び寄せ、大々的に報道させるというものでした。テレビ中継によって、兎田が警察に包囲され身動きが取れない状況を稲葉に知らせ、その間に稲葉の居場所を特定し、綿子を救出しようというのです。勇介は自らの家を現場として提供し、人質役まで買って出ます。計画は実行に移され、宮城県警のSIT(特殊事件捜査班)が出動。現場指揮官の夏之目(なつのめ)警視が、犯人役の兎田との交渉にあたります。テレビ中継が続く中、兎田たちは稲葉の居場所(仙台港の廃倉庫)を特定。そして計画通り、兎田は折尾の遺体を二階から投げ落とし、機動隊員の装備を奪って混乱に乗じて脱出。黒澤と共にタクシーで仙台港へ向かい、稲葉一味を制圧、無事に綿子を救出するのでした。
小説「ホワイトラビット」の長文感想(ネタバレあり)
伊坂幸太郎さんの「ホワイトラビット」、いやはや、これは本当に不思議な読書体験でした。読み終えた直後は、正直なところ、「一体、何だったんだ?」という気持ちと、「でも、なんだか面白かったぞ」という気持ちが入り混じって、頭の中がぐるぐるしていました。物語の筋道を追うだけなら、誘拐犯の男が誘拐された妻を取り戻すために奔走し、ひょんなことから出会った空き巣や一般人と協力して、奇策を用いて悪のボスを出し抜く、という、ある種エンターテイメント性の高い活劇として読むこともできるでしょう。しかし、この物語はそんな単純な枠には収まりきらない、もっと多層的で、どこか掴みどころのない魅力に満ちているように感じます。
まず、この作品の大きな特徴として挙げられるのが、その語りの形式ではないでしょうか。物語は、主人公である兎田孝則の視点だけでなく、空き巣の黒澤、SITの夏之目警視、事件に巻き込まれる佐藤勇介とその母親、さらには組織のボス稲葉や、物語の鍵を握る(ように思える)折尾豊など、複数の登場人物の視点がめまぐるしく入れ替わりながら進んでいきます。いわゆる群像劇の形式をとっているわけですが、それだけではありません。時折、「作者」とも思えるような、俯瞰的な視点からの語り、あるいは読者に直接語りかけるような文章が挿入されるのです。これが非常に独特で、物語の世界に没入しかけていると、ふと現実に引き戻されるような、あるいは物語自体が作り物であることを意識させられるような、不思議な感覚を覚えました。
作中でも触れられているように、これはヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』を意識した手法なのかもしれません。『レ・ミゼラブル』自体を読んだ経験がないので、そのオマージュがどの程度成功しているのか、あるいは元ネタを知っていればもっと深く楽しめるのか、という点については言及できません。しかし、この語りのスタイルが、「ホワイトラビット」という作品に、単なる娯楽小説とは一線を画す、ある種の文学的な深みや、実験的な面白さを与えていることは間違いないと感じます。物語の進行を時折中断して語られる蘊蓄(うんちく)や考察は、テンポを削ぐと感じる読者もいるかもしれませんが、私にとっては、物語世界の奥行きを広げ、登場人物たちの行動や心情に、より普遍的な意味合いを与えているように思えました。例えば、星の話や時間についての話は、後の展開の伏線にもなっているわけですが、それ以上に、人生の偶然性や、物事の見方について考えさせられるきっかけを与えてくれます。
そして、伊坂作品といえば、やはり魅力的なキャラクターたちの存在と、彼らが織りなす軽妙洒脱な会話劇を抜きには語れません。本作もその点は健在です。主人公の兎田孝則は、誘拐を生業とする組織の人間でありながら、どこか抜けていて、妻・綿子のこととなると途端に人間味あふれる表情を見せます。彼の相棒である猪田(いだ)とのやり取りも、緊迫した状況の中での数少ない癒やしとなっています。
しかし、本作で最も輝いているのは、やはり黒澤でしょう。『フィッシュストーリー』収録の「ポテチ」にも登場した空き巣ですが、本作では準主役級の活躍を見せます。飄々(ひょうひょう)としていて掴みどころがなく、それでいて頭が切れ、いざという時には驚くような行動力を見せる。彼が思いつく「白兎作戦」は、荒唐無稽でありながらも、物語を大きく動かす起爆剤となります。兎田や佐藤親子との、どこか噛み合っているようで噛み合っていない、それでいて絶妙なテンポで進む会話は、読んでいて思わず口元が緩んでしまう面白さがあります。「ポテチ」に登場した今村や、名前だけだった中村も登場し、彼らのチームワーク(?)や、とぼけたやり取りも健在で、ファンにとっては嬉しいサービスと言えるでしょう。
一方で、警察側の人物として登場する夏之目警視も、非常に印象深いキャラクターです。彼は、七年前に交通事故で妻と娘を亡くしたという重い過去を背負っています。その事故の原因となった占い師への復讐心を内に秘めながら、SITの指揮官として冷静沈着に職務を遂行しようとします。しかし、立て籠もり事件の犯人(と彼が思っている)兎田との交渉や、予期せぬ事態の連続に、彼の内面も揺れ動きます。彼の抱える葛藤や、過去と向き合おうとする姿は、物語にシリアスな軸を与え、単なるドタバタ劇に終わらせない深みをもたらしています。彼の視点を通して語られる、亡き娘・愛華(あいか)との思い出や、「はい、生まれました。はい、いろいろありました。はい、死にました。」という娘の言葉は、シンプルながらも強く心に響き、人生の儚さや、それでも生きていくことの意味を問いかけてくるようです。
さて、物語の核心部分、つまり「ネタバレ」について触れないわけにはいきません。この物語には、いくつかの大きな仕掛けが施されています。まず、物語の序盤で兎田が追いかける折尾豊が、実は早々に死亡しているという事実。そして、その死が、兎田が所属する組織とは全く無関係な、佐藤勇介という青年の偶発的な行動によるものだったということ。これにより、兎田が必死に追いかけていた「目的」が、実は最初から失われていたことが明らかになります。
さらに驚かされるのが、時間軸のトリックです。物語は、兎田が折尾を追って仙台に来た時点と、黒澤たちが空き巣に入り、折尾の死体を発見する時点、そしてSITが立て籠もり事件として出動する時点が、実は微妙にズレています。読者は、それらがほぼ同時に進行しているかのように読み進めてしまいますが、作中で語られるベテルギウスの光の話(遠い星の光は、私たちが見ている時点ではすでに過去のものである)などがヒントとなり、途中でその時間差に気づかされる構成になっています。この時間軸のズレが、物語にサスペンスと意外性をもたらしています。なぜ稲葉からの連絡が途絶えるのか、なぜ警察の到着が遅いのか、といった疑問が、このトリックによって解消されるのです。
そして、おそらく最大の驚きは、物語の終盤、というよりもエピローグで明かされる事実でしょう。立て籠もり事件の混乱に乗じて姿を消した黒澤が、実は折尾豊になりすましていたのではないか、という可能性が示唆されます。いや、可能性というよりも、ほぼそうなのだろうと思わせる描写があります。折尾豊、オリオオリオという名前。黒澤は、折尾が持っていた資料などを利用し、彼の知識やコンサルタントとしての能力を手に入れ、「オリオオリオ」として生き延びていくのかもしれません。そして、ラストシーン。泉中央駅のキオスクで新聞を買おうとした黒澤(と思われる人物)は、店員として働く綿子の姿を目にするのです。この再会が何を意味するのか、明確な答えは示されません。しかし、偶然が偶然を呼び、人と人とが繋がり、物語が続いていくことを予感させる、非常に伊坂さんらしい、余韻の残る終わり方だと感じました。まるで、夜空に打ち上げられた花火が消えた後も、しばらくその残像が目に焼き付いているかのような感覚です。
物語の整合性という点で見れば、確かに突っ込みどころがないわけではありません。「白兎作戦」の内容そのものも、かなり無理があると言えばありますし、機動隊員の装備を奪ってやすやすと脱出できるものなのか、といった疑問も残ります。しかし、この作品は、そうした細かなリアリティや整合性を追求するタイプの物語ではないのでしょう。むしろ、そうした「ご都合主義」とも取れる展開を、半ば意図的に、あるいは開き直って描いているようにすら感じられます。語り手が「まあ、小説ですから」とでも言いたげな雰囲気が漂っているのです。
それよりも重要なのは、登場人物たちがそれぞれの状況の中で、必死に、あるいは飄々と、困難に立ち向かい、選択をしていく姿そのものなのだと思います。兎田は妻のために、勇介は犯してしまった罪と向き合うために、夏之目は過去を乗り越えるために、そして黒澤は、おそらく彼自身の流儀で生きていくために。彼らの行動は、必ずしも社会的な正義に合致するものばかりではありません。兎田は誘拐犯、黒澤は空き巣、夏之目に至っては過去に殺人を犯しています。しかし、物語は彼らを単純な悪人として断罪するのではなく、それぞれの人間性や、状況が生み出す皮肉、そして再生の可能性を描き出そうとしているように見えます。
特に、佐藤勇介と母親の描き方は印象的でした。偶発的とはいえ人を死なせてしまった勇介と、それを隠蔽しようとする母親。しかし、立て籠もり事件という非日常的な状況を経て、彼らは自分たちの罪と向き合い、人生をやり直す覚悟を決めるように見えます。綿子救出に貢献したことも考慮されるでしょうが、彼らが未来に向かって歩き出すであろうことが示唆されるラストは、救いを感じさせます。
また、伏線の張り方と回収の見事さも、さすが伊坂作品といったところです。序盤で語られる、アルテミスがオリオンを誤って射殺してしまったギリシャ神話のエピソードが、ラスト近くの兎田と綿子の会話で、形を変えて繰り返される場面。中村がなぜか機動隊員の装備一式をコレクションしていたことが、脱出計画の鍵となる展開。あるいは、夏之目が占い師に抱く個人的な恨みが、事件解決後の彼の行動に繋がっていく伏線。これらが、パズルのピースがはまるように、物語の終盤で綺麗に繋がっていく様は、読んでいて快感すら覚えます。
この「ホワイトラビット」という物語は、ミステリーやサスペンスとしての面白さ、キャラクター小説としての魅力、そして人生や社会に対するちょっと斜めからの視点、それらが絶妙なバランスで配合された、伊坂幸太郎さんならではの一杯、と言えるのではないでしょうか。読んでいる間は、その奇妙な味わいに戸惑うこともあるかもしれませんが、読み終えた後には、不思議な満足感と、心に残るいくつかの問い、そして登場人物たちへの愛着が湧いてくる、そんな作品でした。整合性やリアリティを過度に求めず、物語の「おかしみ」や「飛躍」を楽しむことができる読者にとっては、忘れられない一冊になる可能性を秘めていると思います。個人的には、黒澤というキャラクターの魅力が再認識できたこと、そして夏之目警視の抱える悲しみと決意に、強く心を揺さぶられた一作となりました。
まとめ
伊坂幸太郎さんの小説「ホワイトラビット」は、誘拐組織の一員である兎田孝則が、誘拐された妻・綿子を取り戻すために奔走する物語です。組織の裏切り者・折尾豊の捜索を命じられた兎田ですが、仙台で彼を発見したときには既に死亡していました。折尾を誤って死なせてしまった青年・勇介や、偶然居合わせた空き巣・黒澤と共に、兎田は絶体絶命の状況を打開するため、「白兎作戦」と名付けられた奇策、すなわち人質立て籠もり事件の偽装を実行します。
物語は、兎田、黒澤、そして事件の捜査にあたるSITの夏之目警視など、複数の視点から描かれる群像劇の形式をとっています。さらに、時折挿入される俯瞰的な語りが、作品に独特の雰囲気を与えています。軽妙な会話、巧妙に張り巡らされた伏線と意外な展開、そして時間軸のトリックなど、伊坂作品らしい魅力が満載です。登場人物たちは、それぞれの事情や過去を抱えながら、予期せぬ出来事に巻き込まれ、選択を迫られます。
単なるエンターテイメントに留まらず、罪と罰、偶然と必然、そして再生といったテーマにも触れられており、読後には深い余韻が残ります。特に、黒澤の飄々としたキャラクターや、夏之目警視の抱える葛藤は印象的です。物語の整合性よりも、キャラクターの魅力や物語の勢い、そして独特の読書体験を楽しみたい方におすすめの一冊と言えるでしょう。