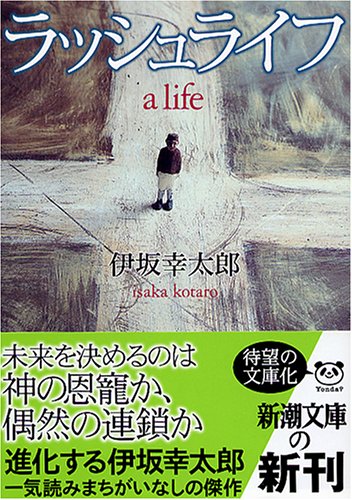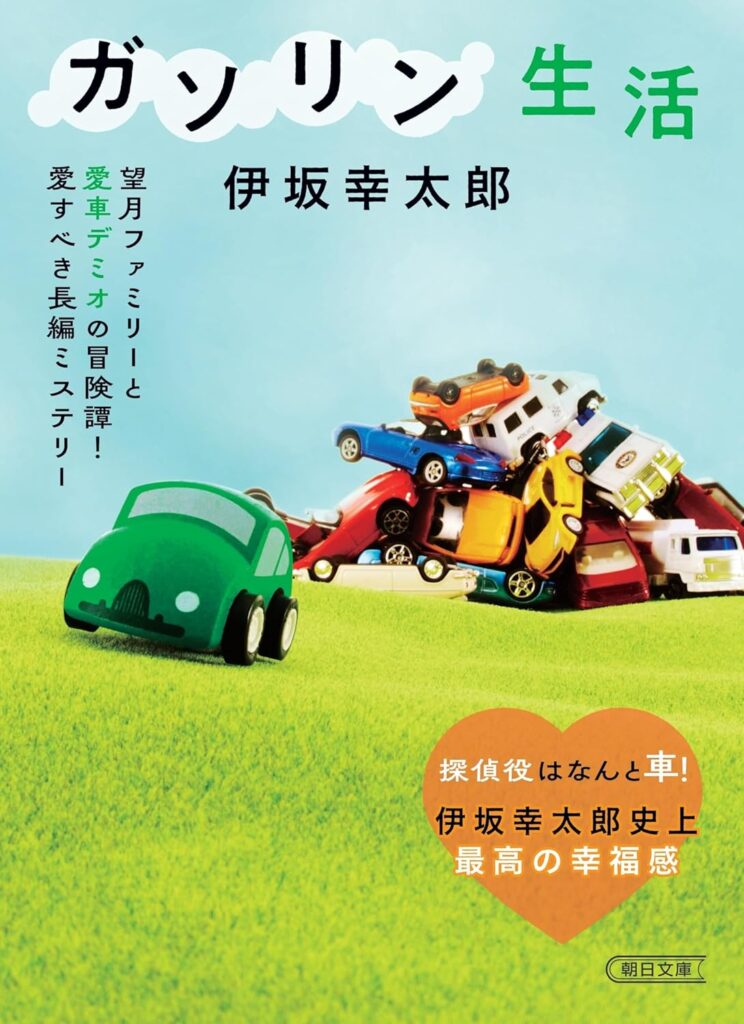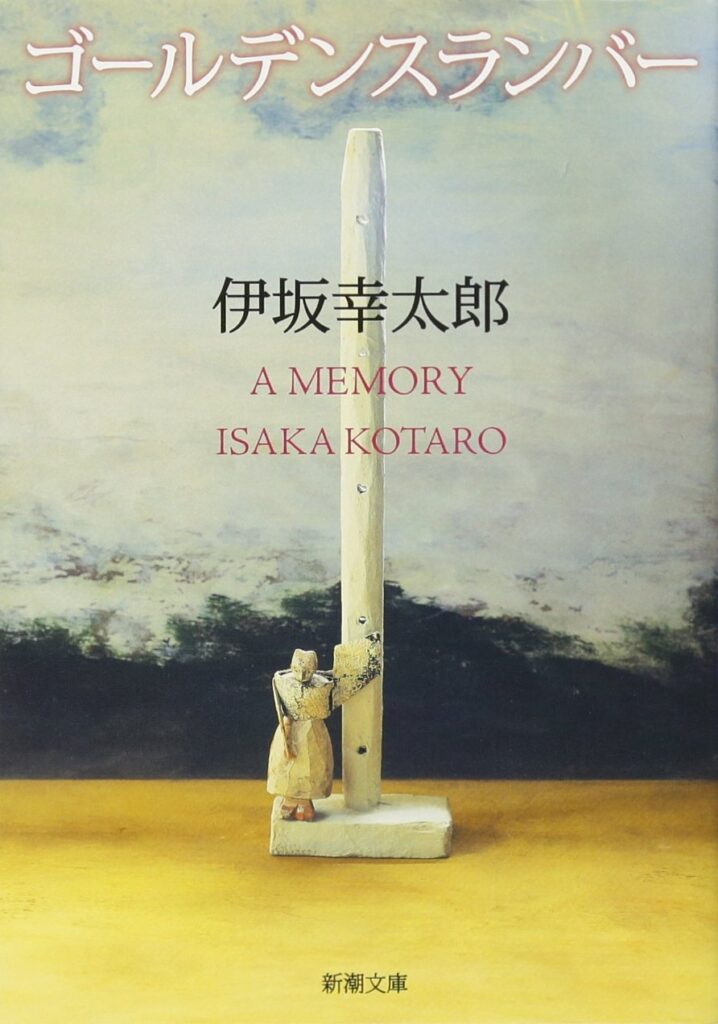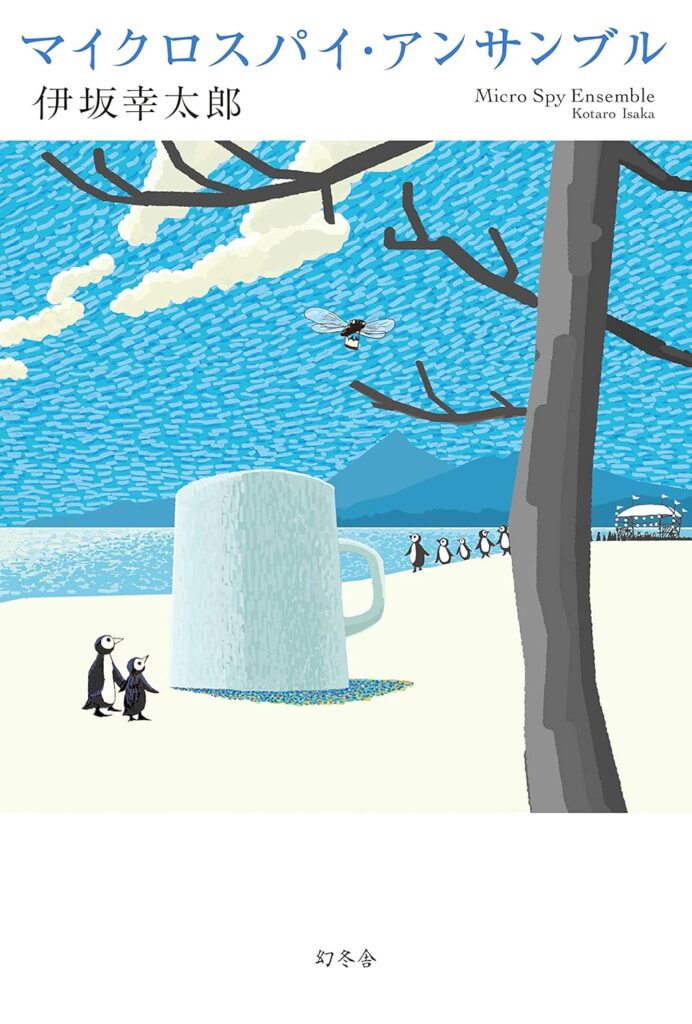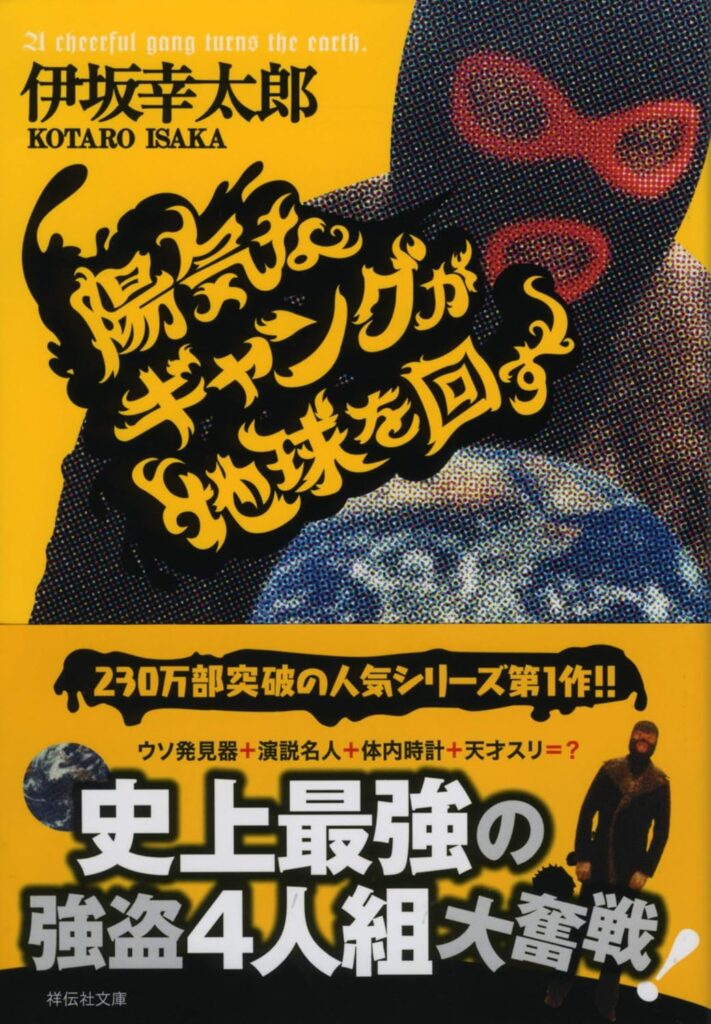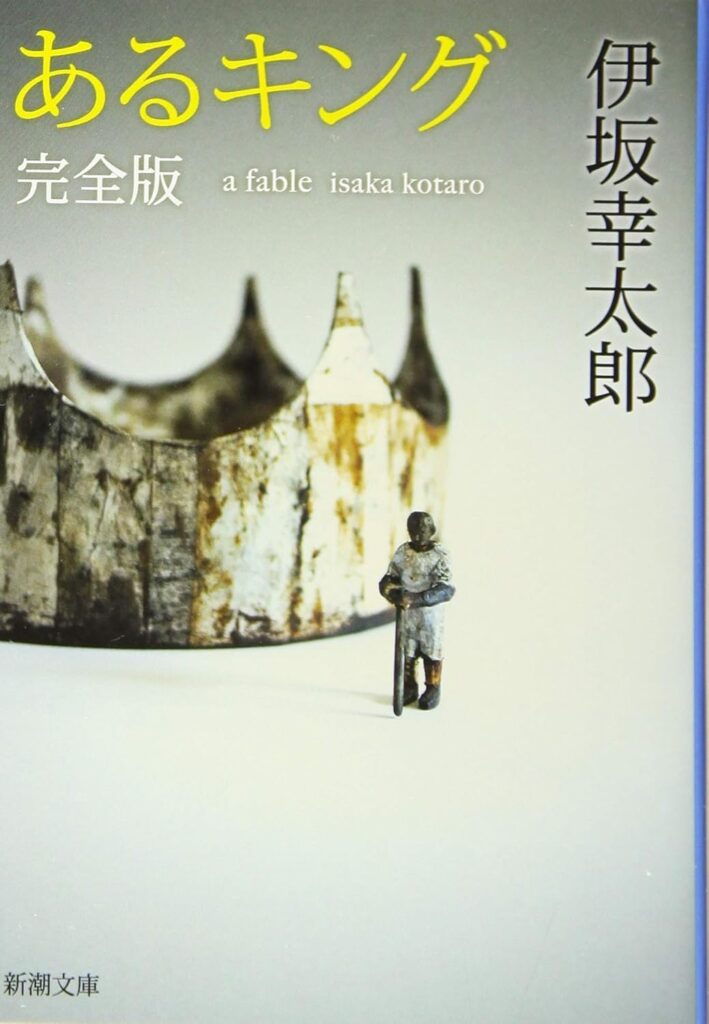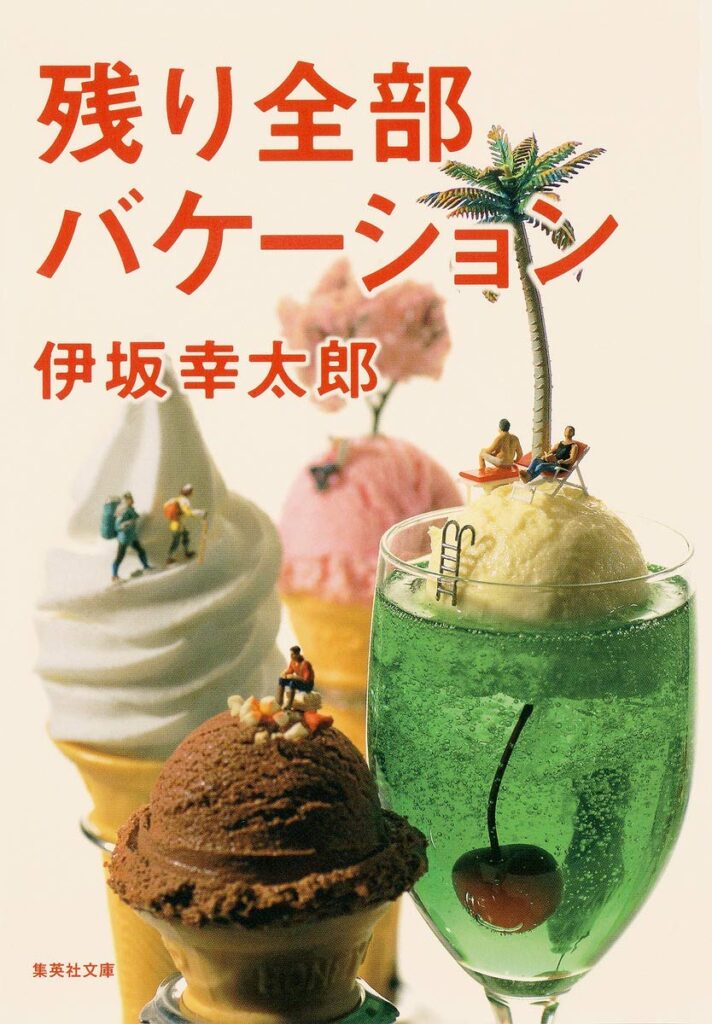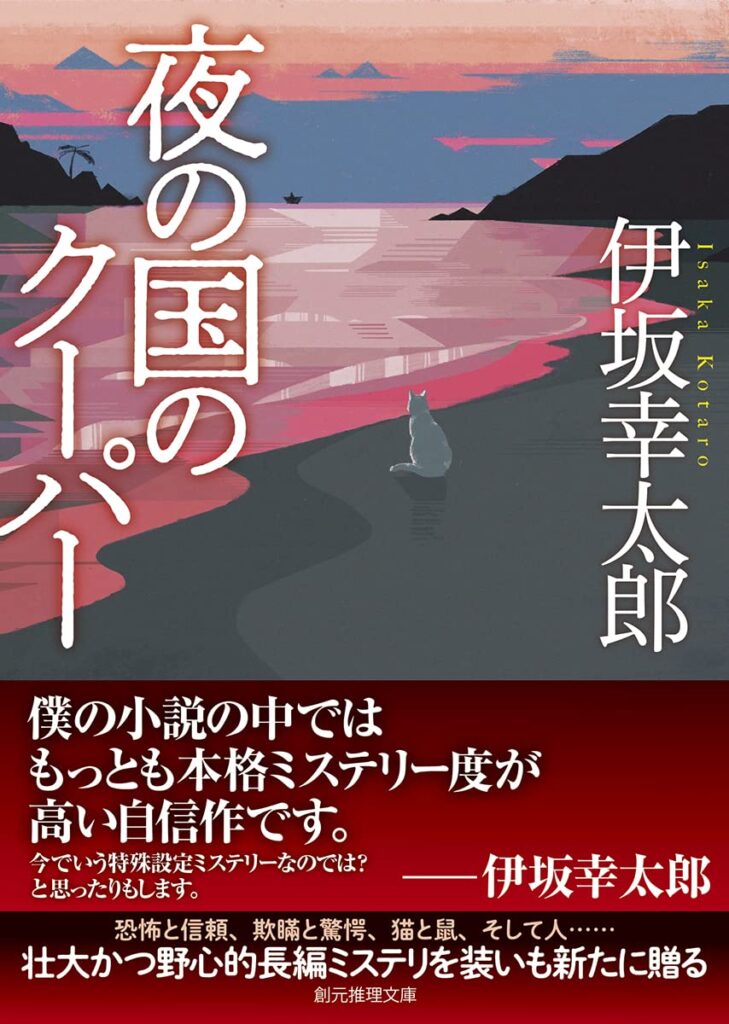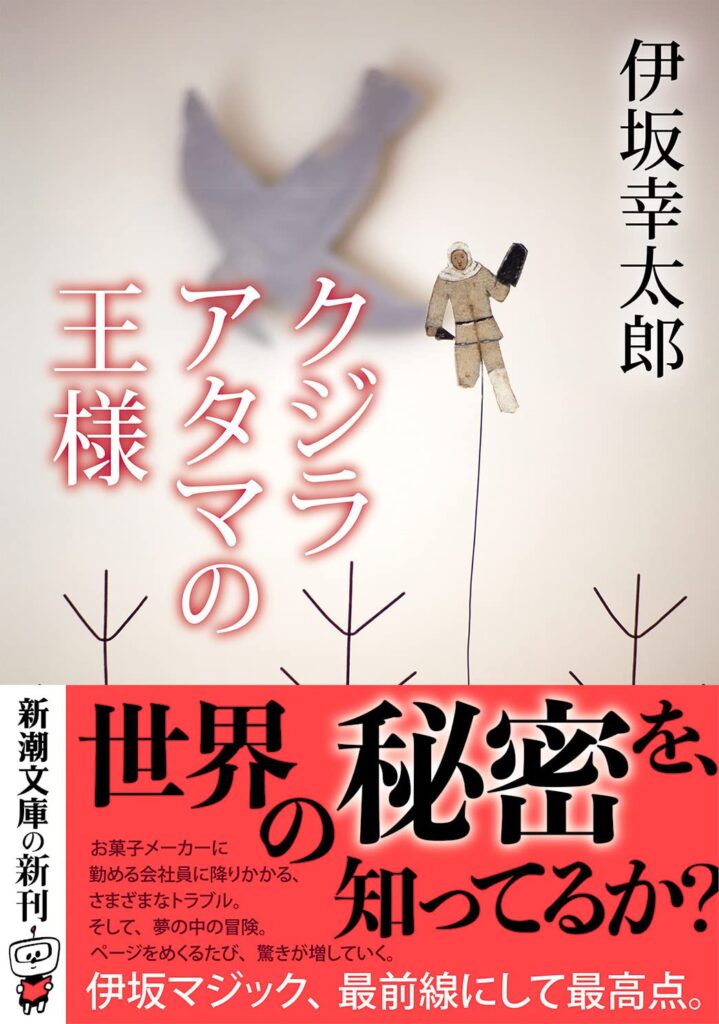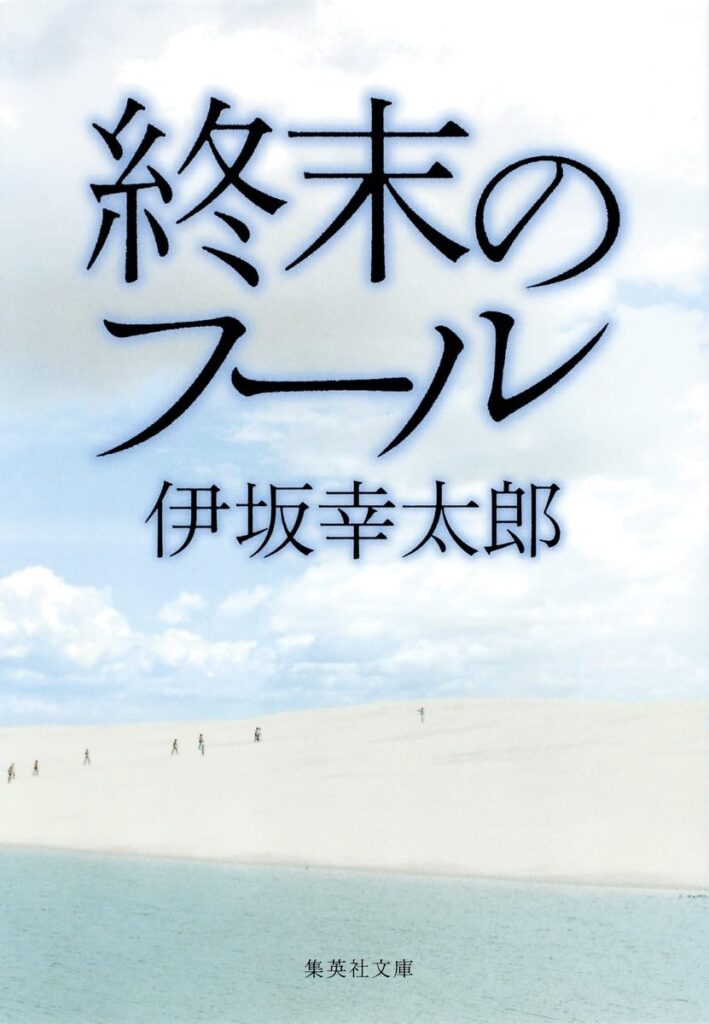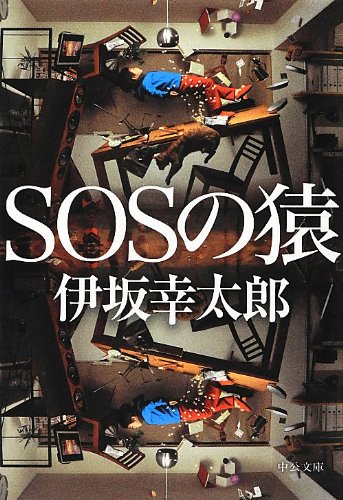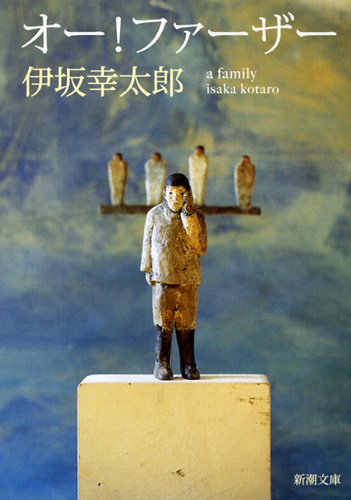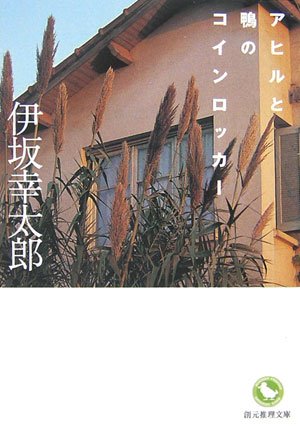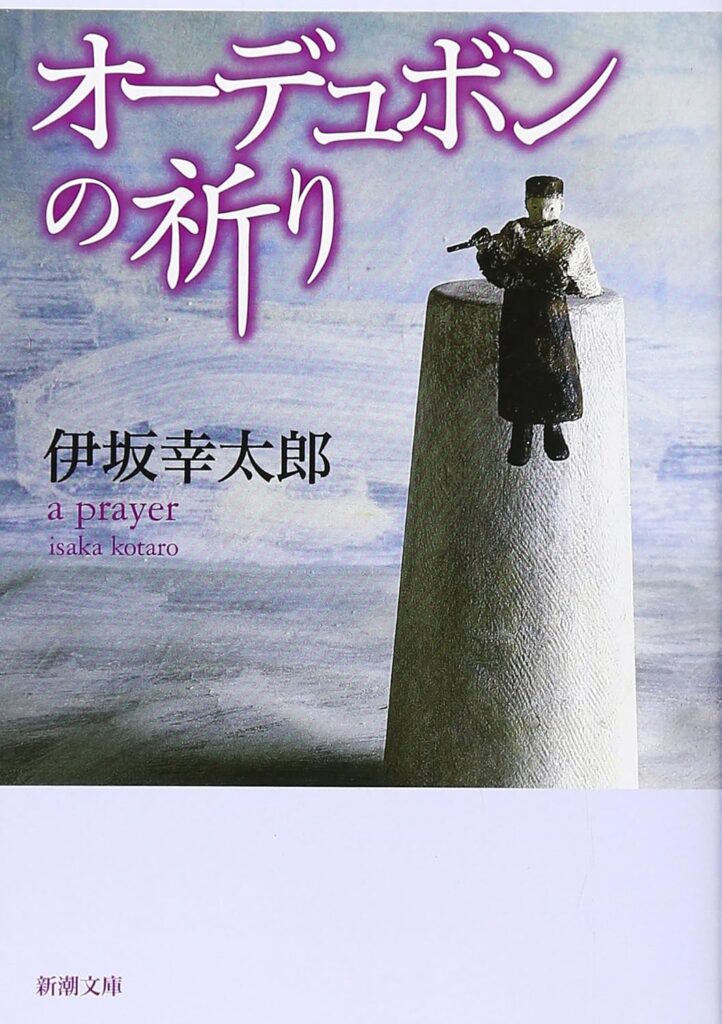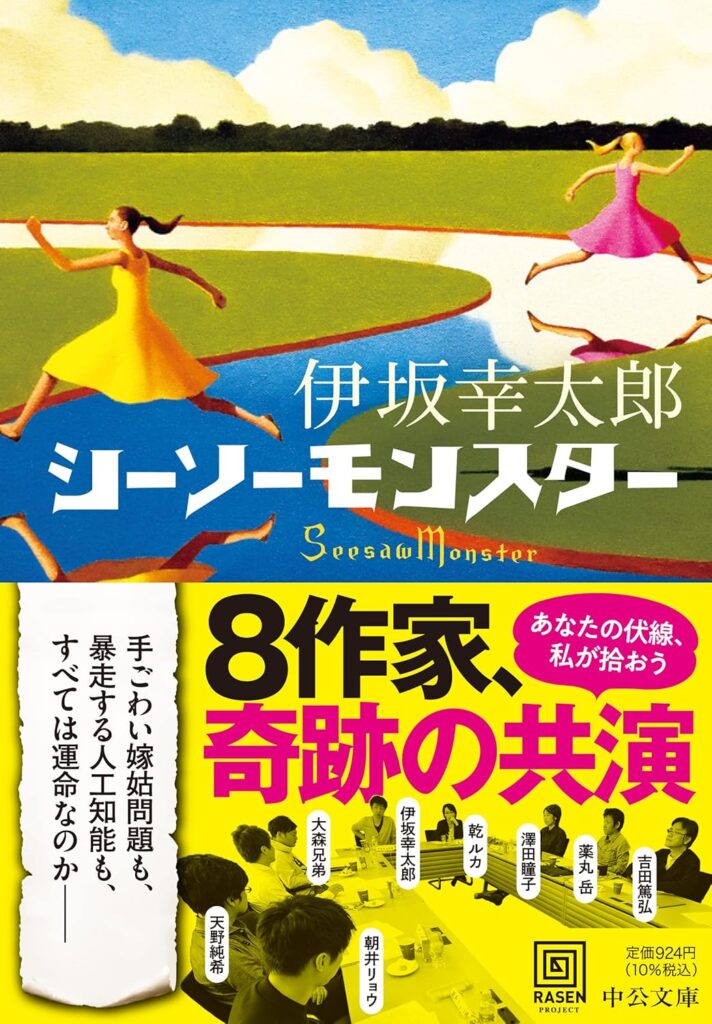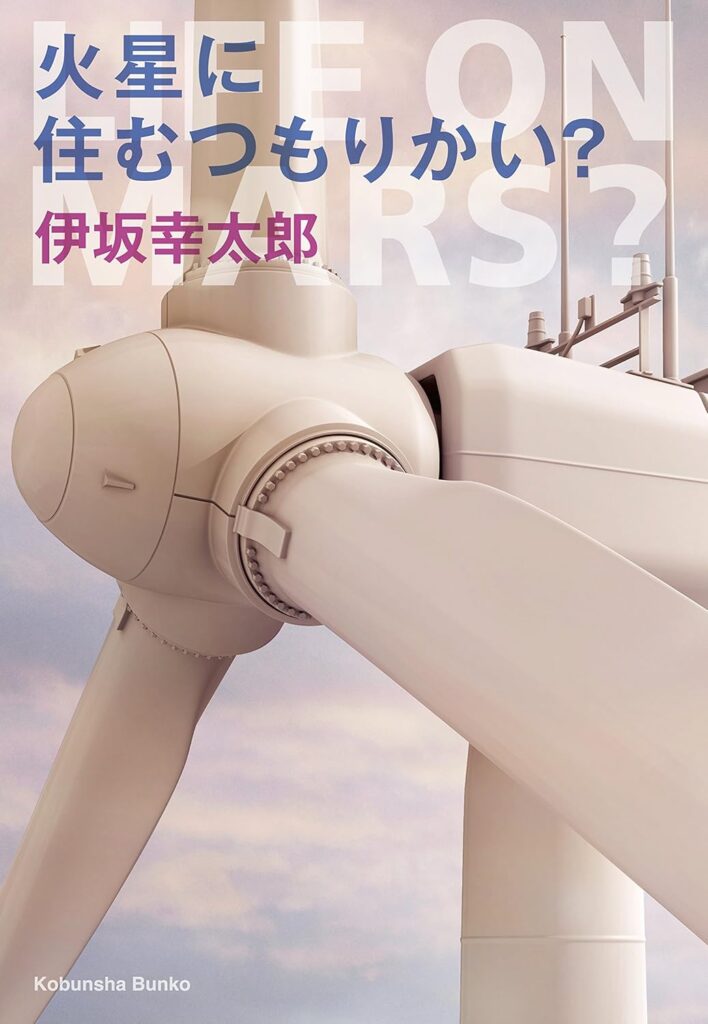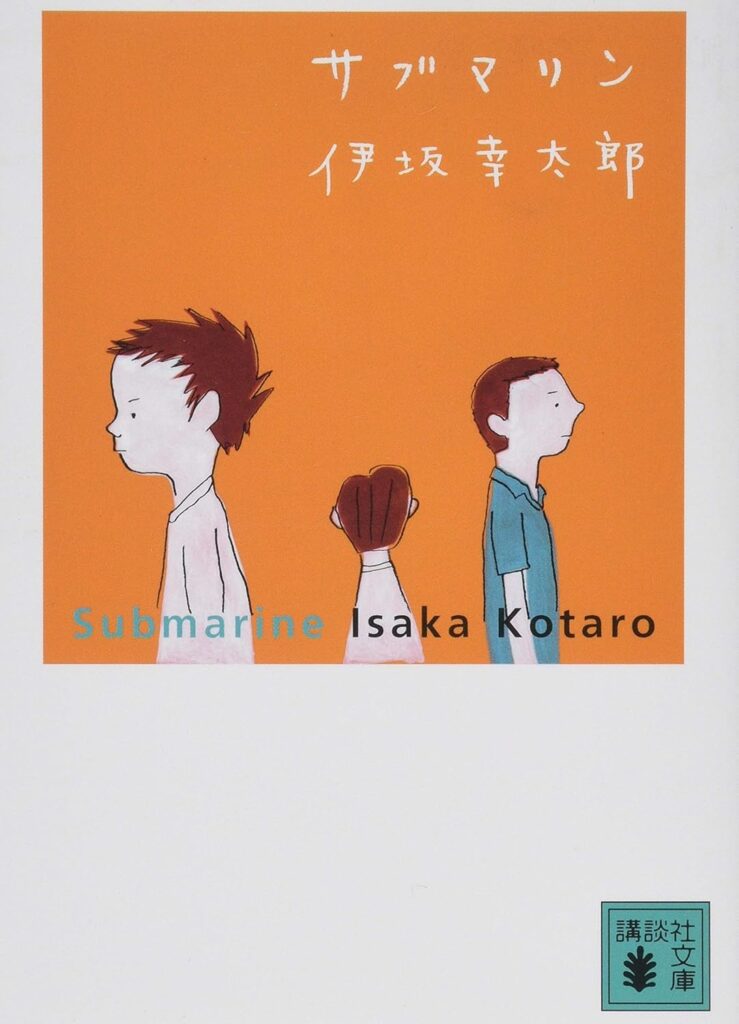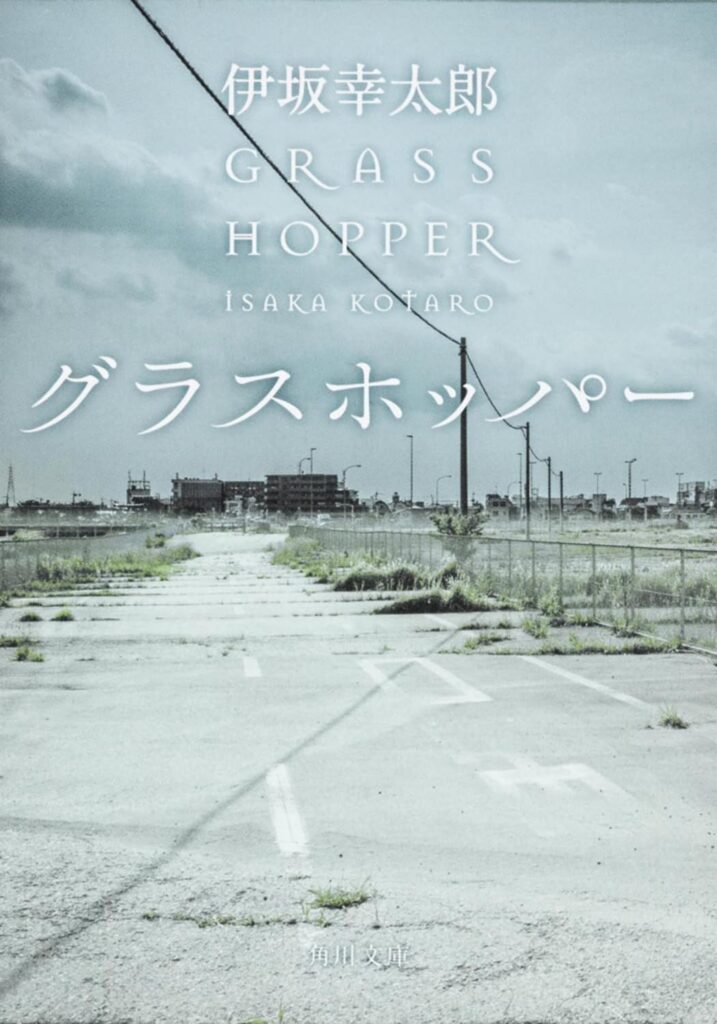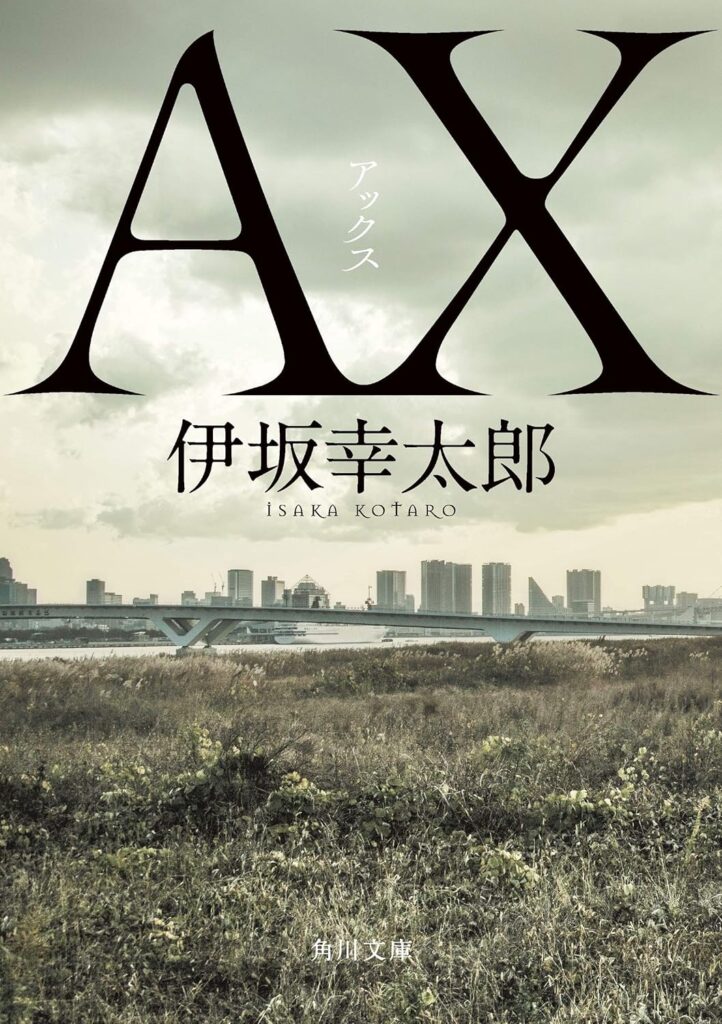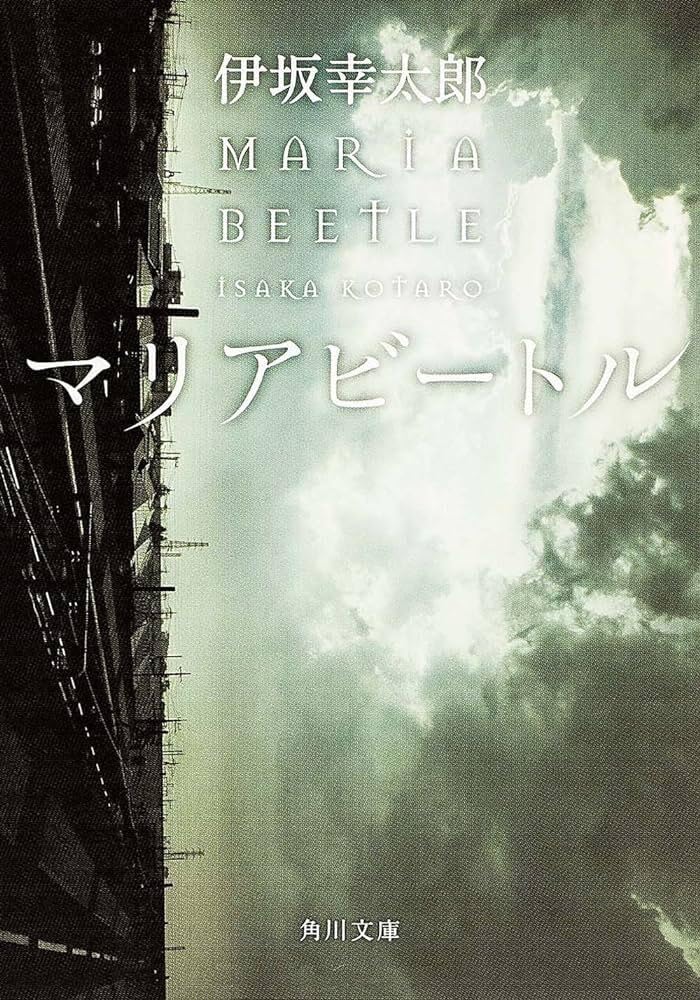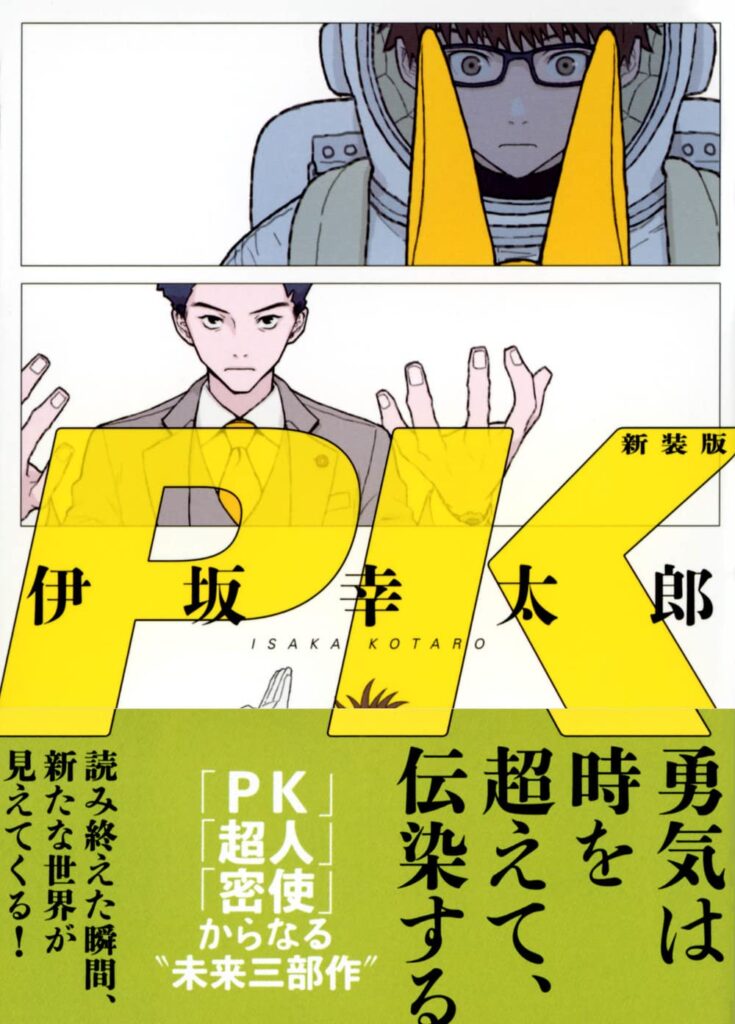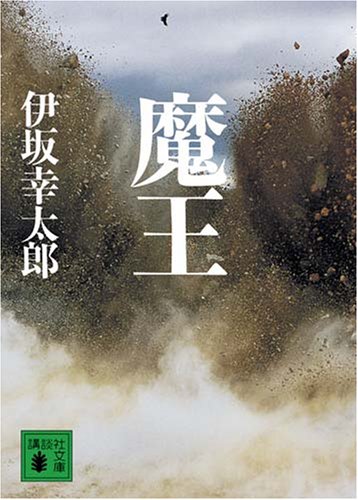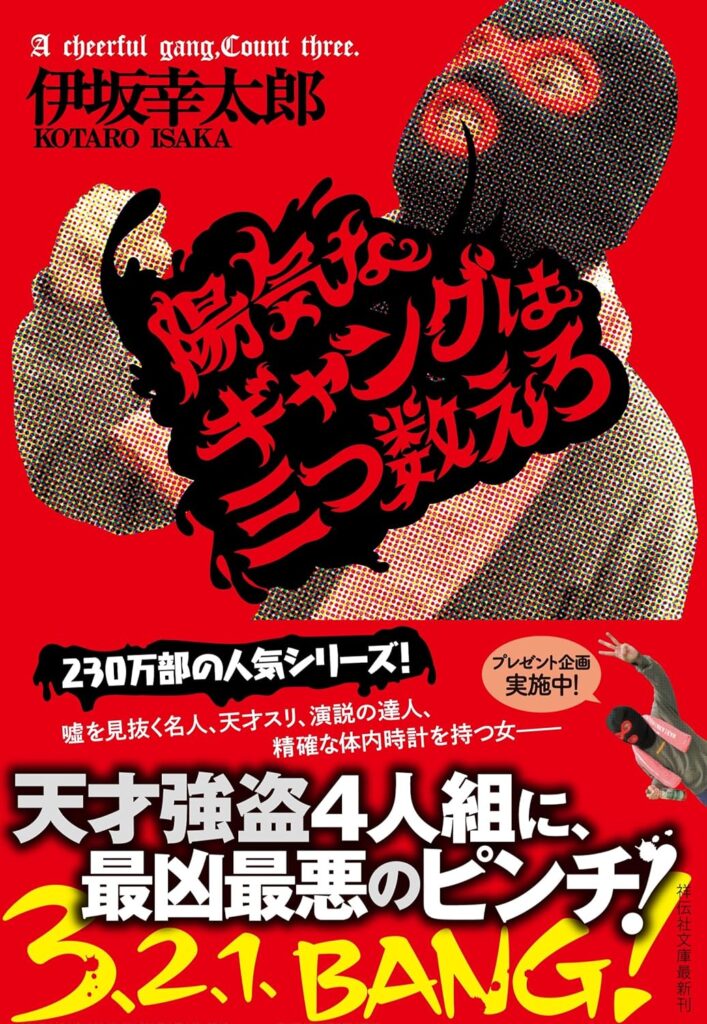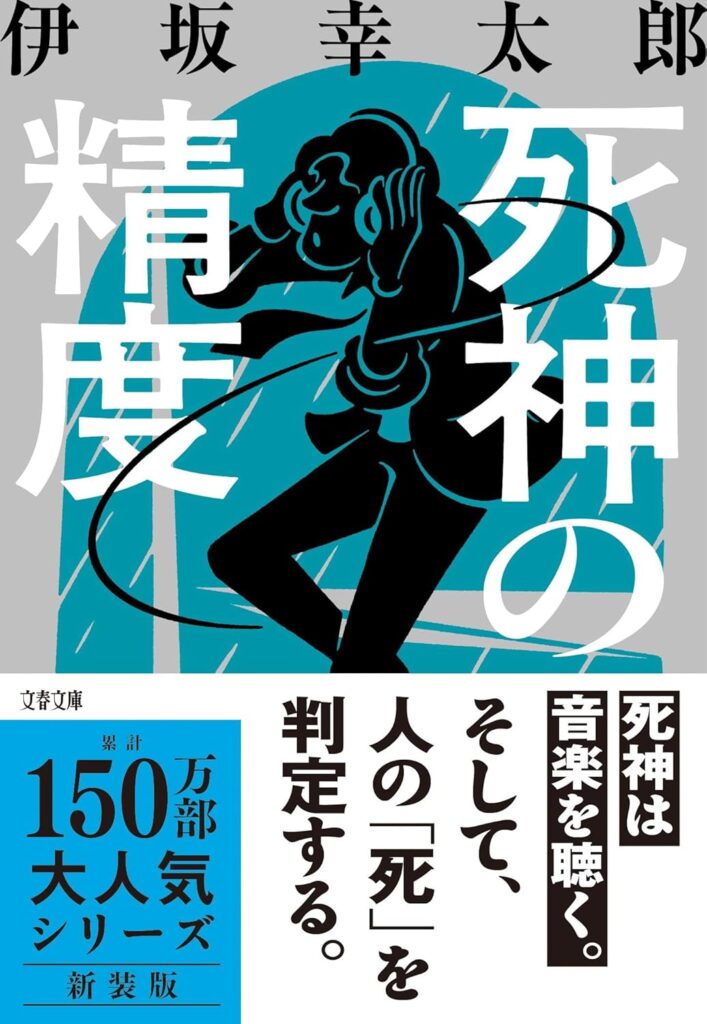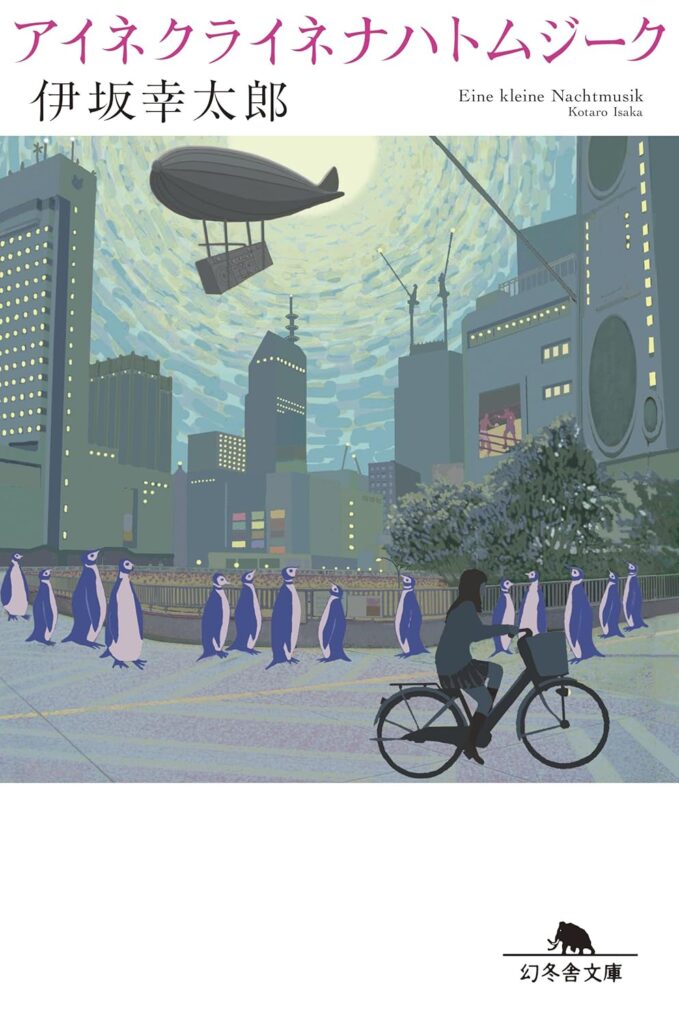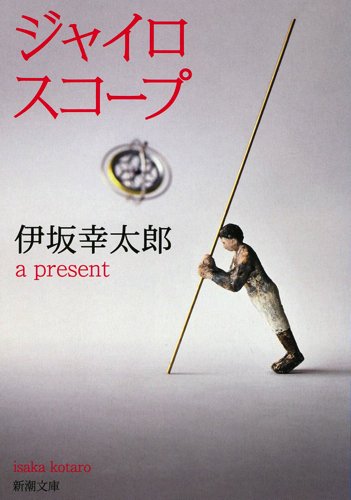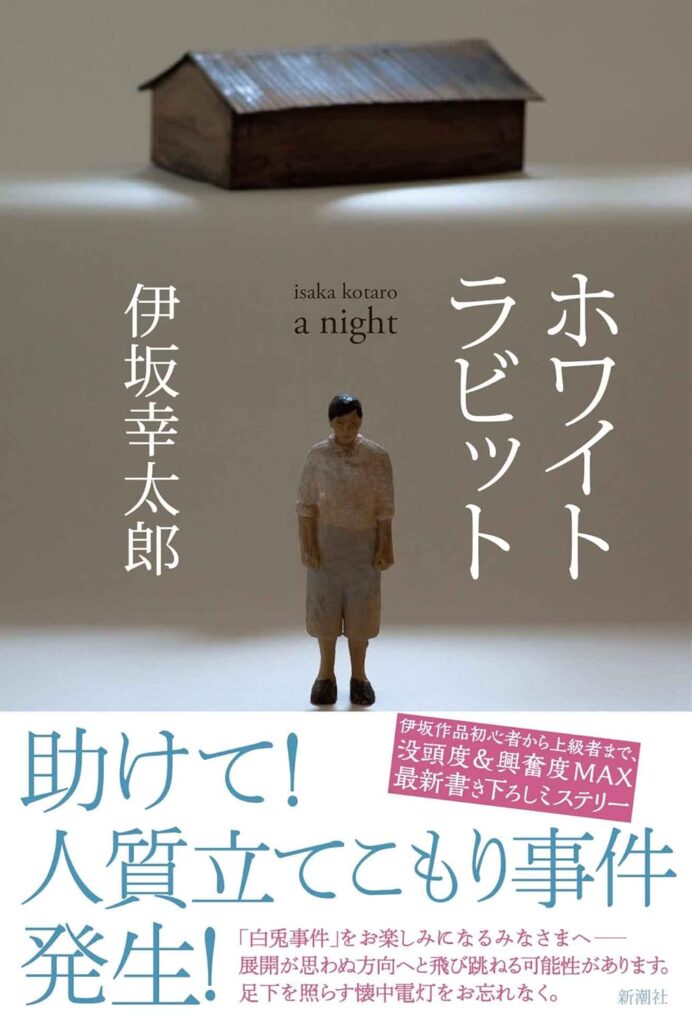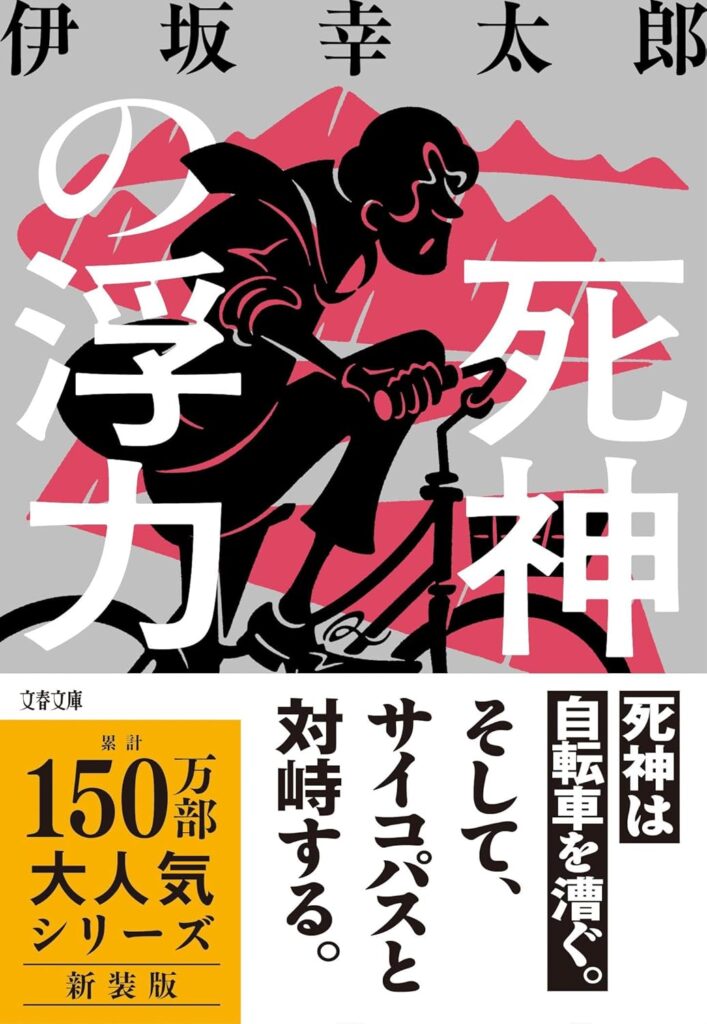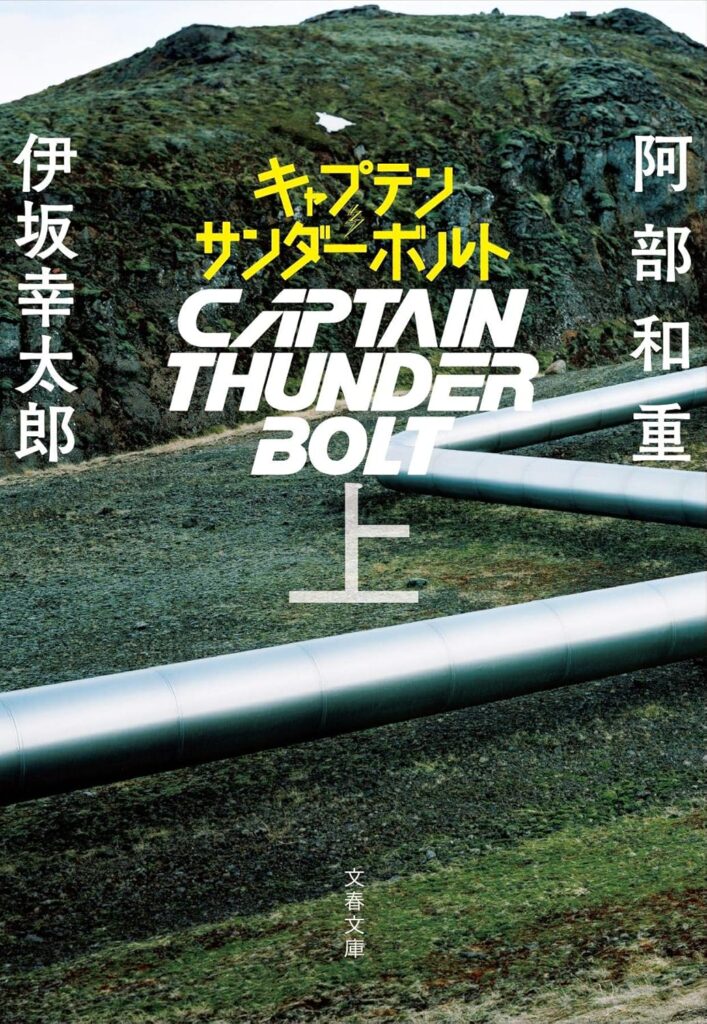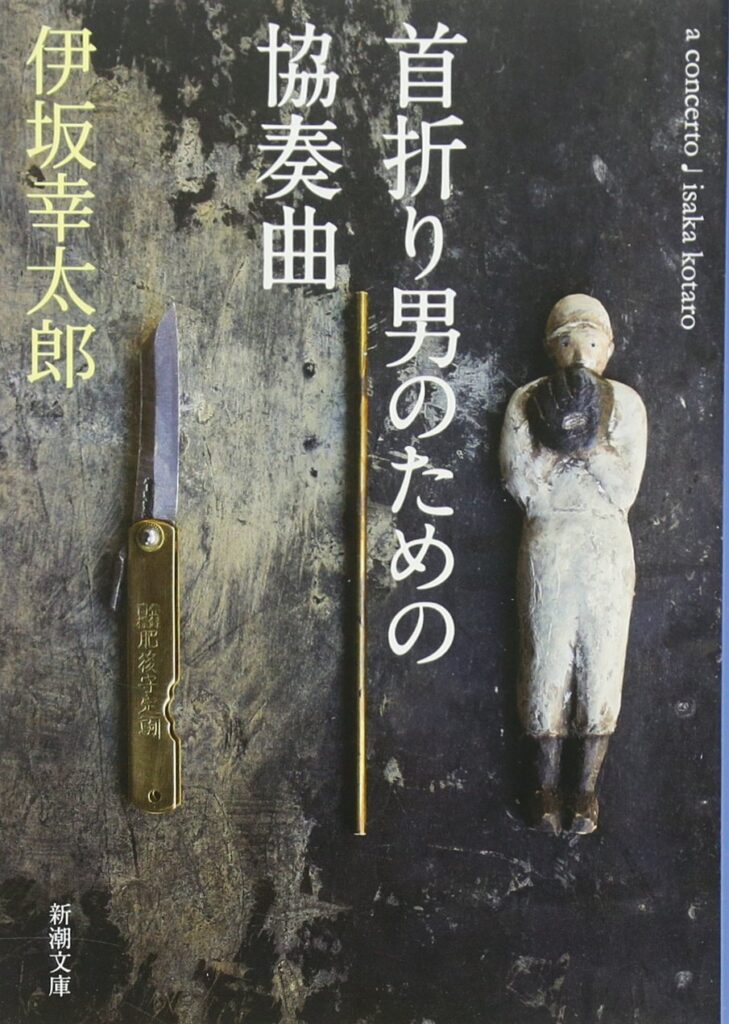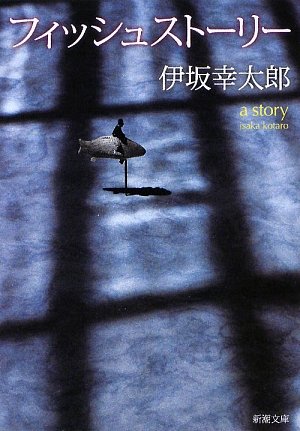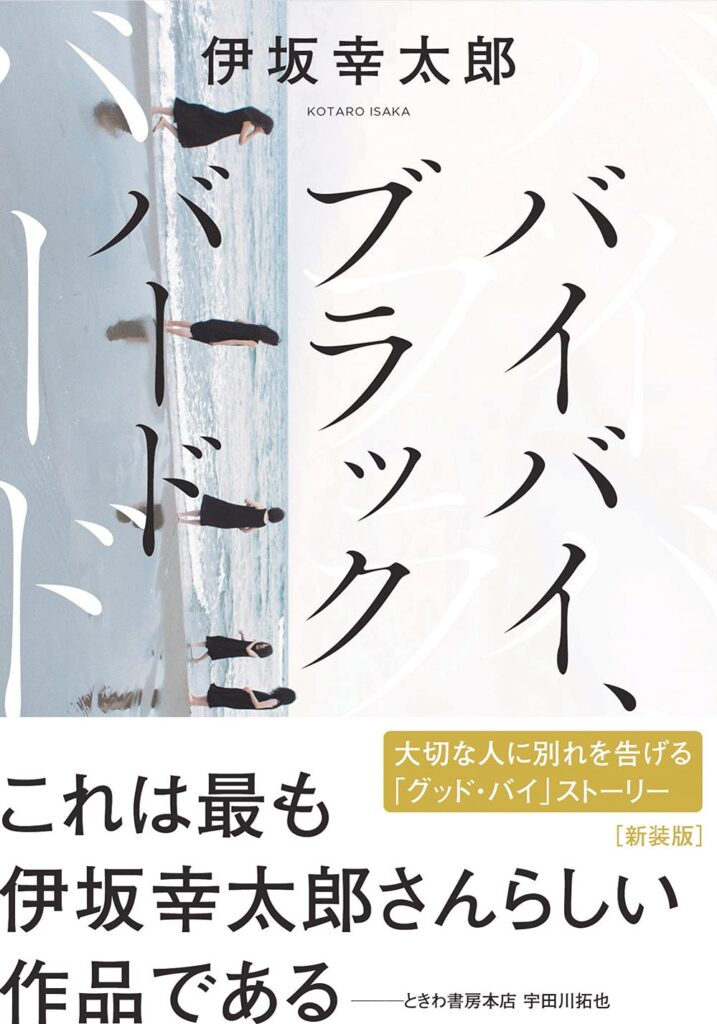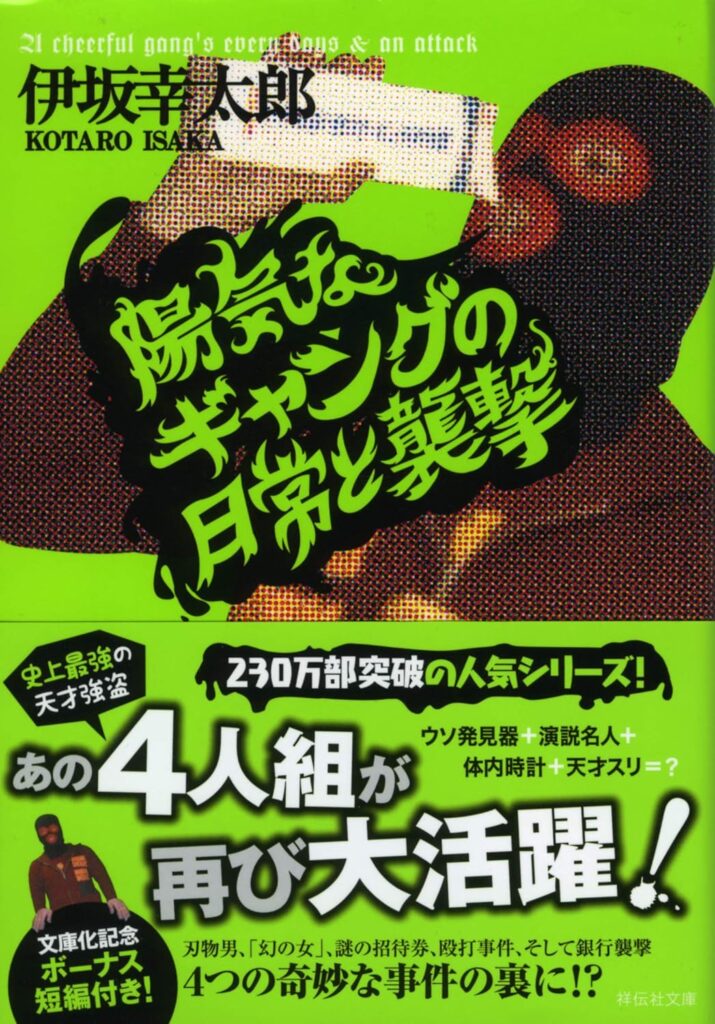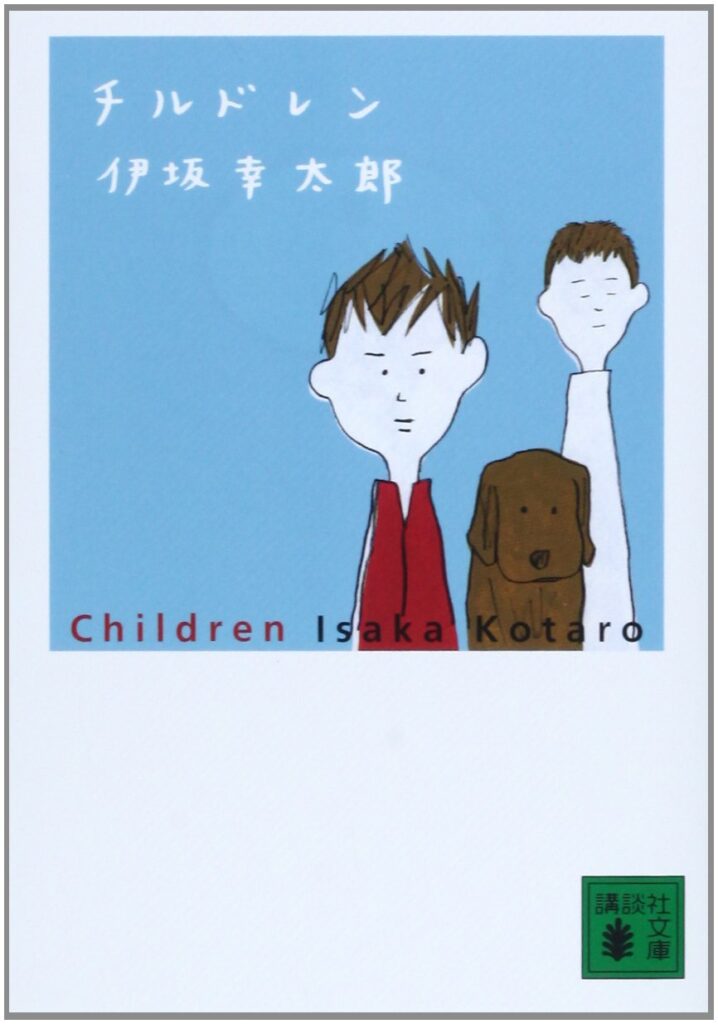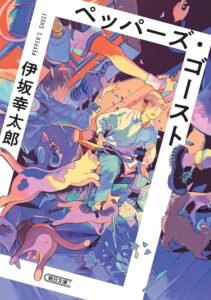 小説「ペッパーズ・ゴースト」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。伊坂幸太郎さんの手によるこの物語は、読む人の心を掴んで離さない、不思議な魅力に満ちています。日常と非日常が交錯し、予想もつかない展開が待っていますよ。
小説「ペッパーズ・ゴースト」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。伊坂幸太郎さんの手によるこの物語は、読む人の心を掴んで離さない、不思議な魅力に満ちています。日常と非日常が交錯し、予想もつかない展開が待っていますよ。
この物語の中心には、少し変わった能力を持つ国語教師、檀(だん)先生がいます。彼はなんと、他人の未来の一部を「先行上映」として見ることができるのです。その力が、彼をある出来事へと巻き込んでいきます。そして、もう一つの軸となるのが、彼の教え子、布藤鞠子(ふどうまりこ)が書く小説の中の物語。猫を愛する謎の二人組「ネコジゴハンター」の活躍を描いたその作中作が、現実と奇妙にリンクしていくのです。
この記事では、まず「ペッパーズ・ゴースト」の物語の筋道を、結末に触れながら詳しくお伝えします。その後、私自身がこの作品を読んで感じたこと、考えたことを、ネタバレを気にせずにたっぷりと語っていきたいと思います。作品の構造的な面白さや、散りばめられた哲学的なテーマについても触れていきますので、すでに読んだ方も、これから読もうか迷っている方も、ぜひお付き合いいただければ嬉しいです。
小説「ペッパーズ・ゴースト」のあらすじ
物語は、中学校の国語教師である檀先生の視点から始まります。彼は、生徒の布藤鞠子が書いた小説原稿を読むことを日課としていました。その小説は、動物虐待を行う者たちに制裁を加える「ネコジゴハンター」、ロシアンブルとアメショーという二人組(?)の活躍を描いたものでした。飄々としたアメショーと、極度に心配性なロシアンブルの掛け合いが印象的な物語です。
一方で、檀先生には秘密がありました。それは、飛沫を介して他人の「翌日」の一部が見えてしまう〈先行上映〉という特殊な力。ある日、彼は教え子が交通事故に遭う未来を見てしまい、注意を促すことで事故を防ぎます。しかし、そのことで生徒の父親であり、内閣府でテロ対策を担当する里見という人物に能力を知られ、疑われることになります。檀先生は能力について説明しますが、その後、里見は行方をくらましてしまうのです。
檀先生は〈先行上映〉で里見が監禁されている未来を見ます。彼を疑うのは、過去のテロ事件の被害者遺族で作る「サークル」と呼ばれる団体でした。檀先生は彼らに接触を試みますが、逆に自身も監禁されてしまいます。絶体絶命の状況に陥った檀先生を救ったのは、なんと鞠子の小説に登場するはずのネコジゴハンター、ロシアンブルとアメショーでした。作中作の登場人物が、現実世界に現れたのです。
「サークル」の目的は、ある種のテロ行為によって、世間にメッセージを伝えることでした。彼らは過去の悲劇を繰り返し経験するような絶望感、ニーチェの言う「永遠回帰」のような苦悩の中にいました。彼らは、自分たちが犠牲になることで、未来の同様の悲劇を防ごうとしていたのです。檀先生は、現実離れした助っ人であるロシアンブル、アメショーと共に、彼らの計画を阻止しようと奔走します。しかし、事態は単純ではなく、彼らの行動は予期せぬ結末へと向かっていきます。
小説「ペッパーズ・ゴースト」の長文感想(ネタバレあり)
伊坂幸太郎さんの「ペッパーズ・ゴースト」、読み終えた後の余韻がすごい作品でした。まず、構成の妙に唸らされましたね。私たち読者がいる現実世界、檀先生たちが生きる「ペッパーズ・ゴースト」の物語世界、そしてその中で布藤鞠子が書いている「ネコジゴハンター」の作中作世界。この三つの層が、見事な手つきで重ねられ、そして交差していくんです。
鞠子の書く小説パートは、当初、本筋とは別の、ちょっとした息抜きのような感じで挿入されているのかな、と思っていました。ロシアンブルの極端な心配性と、アメショーの楽観的でどこか達観したような物言いの対比が面白くて。「僕らは小説の登場人物だから、都合よく物事が進むのさ」なんてメタ的な発言も飛び出して、クスリとさせられます。この軽妙なやり取りが、檀先生が直面するシリアスな現実(〈先行上映〉の能力、里見の失踪、サークルとの対峙)と対照的に描かれているんですね。
ところが、物語が進むにつれて、この二つの世界がただ並行して存在するだけではないことが明らかになります。檀先生が監禁され、万事休すかと思われたその時、現実に現れるロシアンブルとアメショー! まさに「ペッパーズ・ゴースト」というタイトルが示す現象そのものです。ペッパーズ・ゴーストとは、舞台などで使われる視覚トリックの一種で、別の場所にいる(あるいは存在しない)ものを、あたかもその場にいるかのように見せる技術のこと。作中でも解説されていますが、鞠子の小説の中にしか存在しないはずのネコジゴハンターが、檀先生の目の前に現れる。この瞬間、「えっ!?」と思わず声が出そうになりました。これは、物語の構造そのものがタイトルの意味を体現しているという、非常に凝った仕掛けですよね。
しかも、このリンクは一方通行ではありません。物語の終盤、今度は檀先生自身が、私たち読者に向かって語りかけてくるような場面があります。「小説の中の登場人物だと思っていたロシアンブルたちが、読み手である壇先生の前に現れたように、もしかしたら、小説の登場人物である壇先生やロシアンブルたちが、今これを読んでいるあなたの前に現れることだって、あるかもしれない」…そんな可能性を示唆して、物語は幕を閉じます。この終わり方、ぞくぞくしましたね。現実と虚構の境界線が曖昧になるような感覚。読後、ふと背後を気にしてしまうような、不思議な感覚に襲われました。伊坂さんの作品には、時折こうしたメタフィクション的な仕掛けが見られますが、本作はその中でも特に鮮やかで、印象に残るものでした。
そして、この物語のもう一つの重要な柱が、ニーチェの哲学、特に「永遠回帰(永劫回帰)」の思想です。作中、この思想が繰り返し登場し、物語のテーマと深く結びついています。永遠回帰とは、ざっくり言えば、宇宙も人生も、全く同じことの無限の繰り返しである、という考え方。良いことも悪いことも、喜びも悲しみも、全てが寸分違わず永遠に繰り返される。そう考えると、一度きりの人生だからこそ意味がある、という価値観は揺らぎ、虚無感(ニヒリズム)に繋がる、とも解釈されます。
物語に登場する「サークル」のメンバー、つまりテロ事件の被害者遺族たちは、まさにこの永遠回帰の呪縛に囚われているかのように描かれます。愛する者を奪われた悲劇、癒えない心の傷、社会への不信感…そうした苦しみが、まるで終わりのないループのように感じられ、彼らを絶望させている。特に、リーダー格の庭野さんたちが抱える無力感は読んでいて胸が痛みました。彼らは、自分たちが経験したような悲劇が二度と繰り返されないように、新たなテロという手段で世の中に警鐘を鳴らそうとします。それは、ある意味で、永遠回帰のループを断ち切ろうとする、悲痛な試みとも言えるのかもしれません。
しかし、ニーチェの思想には、永遠回帰を肯定的に捉える側面もあります。作中で引用される「人生で魂が震えるほどの幸福があったなら、それだけで、そのために永遠の人生が必要だったんだと感じることができる」という言葉。これは、もし人生に最高の瞬間、肯定すべき一点があれば、その瞬間のために、他の全ての苦しみも含めて、この人生の永遠の繰り返しを肯定できる、という考え方を示唆しています。サークルのメンバーたちが計画した行動は、彼らにとっての「魂が震えるほどの幸福」をもたらすものだったのでしょうか。たとえ自らの命を犠牲にしてでも、未来の悲劇を防ぐことができたなら、それで全てが報われる…そう考えたのかもしれません。
ただ、物語は単純な自己犠牲の美談では終わりません。檀先生の推測によれば、庭野さんたちは爆破事件で死んだのではなく、どこか別の場所で生きている可能性がある。これもまた、「ペッパーズ・ゴースト」的な仕掛けと言えるでしょう。目の前から消えたけれど、別の隠れた場所に存在している(かもしれない)庭野さんたち。それに対して、別の隠れた場所(小説の中)に存在していたけれど、目の前に現れたロシアンブルとアメショー。この対比が見事です。彼らが本当に生きているのか、どこへ行ったのかは明確には描かれませんが、そこに希望の余地を残しているようにも感じられました。
登場人物たちも魅力的でしたね。主人公の檀先生は、〈先行上映〉なんていう特殊能力を持ちながらも、基本的にはごく普通の、少し気弱で優しい中学校教師です。過去に救えなかった生徒への後悔を抱え、だからこそ、目の前の危機から目を背けられない。彼の悩みや葛藤には、とても共感できました。スーパーヒーローではないけれど、自分にできることをしようと奮闘する姿は応援したくなります。もし実写化するなら、堺雅人さんが演じたらぴったりかも、なんて想像しながら読んでいました。
そして、何と言ってもネコジゴハンターの二人組、ロシアンブルとアメショー。このコンビは最高でした。ロシアンブルの心配性は、読んでいて「わかる!」となるところがたくさんありました。「とんかつの中までちゃんと火が通っているか不安になる」とか、日常の些細なことへの過剰な心配。でも、その心配性があるからこそ、彼は慎重に行動できるのかもしれません。一方のアメショーは、常に飄々としていて、物事の本質を見抜いているような鋭さも感じさせます。二人の軽妙な会話は、物語の重いテーマを和らげ、読む楽しさを与えてくれました。
鞠子の存在も重要です。彼女が書く小説が、物語を動かす鍵となるわけですが、彼女自身もまた、檀先生にとって守るべき存在であり、未来への希望を象徴しているように感じました。彼女がどんな大人になるのか、檀先生との関係はどうなっていくのか、もっと見ていたかった気もします。
物語全体を通して、伊坂さんは様々な問いを投げかけてきます。テロや暴力に対する考え方、メディアの責任、抑止力の意味、復讐心の是非、人生における後悔との向き合い方…。明確な答えを提示するのではなく、読者に考えさせる余地を残しているところが、伊坂作品らしいと感じます。特に、被害者遺族の心情描写は考えさせられるものが多かったです。法的には裁かれないけれど、遺族にとっては許しがたい存在(例えば、テロを煽ったキャスターなど)に対する怒りや無力感。それは単純に「悪」と断じられるものなのか? 彼らの行動は決して肯定されるべきではないけれど、その動機には理解できる部分もある…という複雑な感情を抱かせる筆致は見事でした。
ニーチェの哲学は難解な部分もありますが、この物語を通して触れることで、少し身近に感じられた気がします。永遠に繰り返されるかもしれない人生の中で、私たちは何を見出し、どう生きていくのか。絶望の中に、肯定できる瞬間を見出すことは可能なのか。そんな普遍的なテーマが、エンターテイメント性の高い物語の中に巧みに織り込まれていました。
少し気になった点を挙げるとすれば、サークルのメンバーたちが最終的にとった行動(病院での爆破計画)の動機付けが、やや唐突に感じられた部分もあったかもしれません。彼らの絶望感は伝わるものの、「だから集団自決(に見せかけたテロ)を」という飛躍には、もう少し丁寧な描写があっても良かったかな、と感じる読者もいるかもしれません。また、サークル内で意見が分かれ、一部メンバーが離脱していくあたりの展開も、もう少し掘り下げてほしかった気もします。
とはいえ、これらの点は些細なことで、全体としては非常に満足度の高い読書体験でした。伏線の張り方と回収、魅力的なキャラクター、テンポの良い展開、そして心に残るテーマ。伊坂幸太郎さんの持ち味が存分に発揮された、読み応えのある長編だと思います。現実と虚構が入り混じる不思議な世界観に、どっぷりと浸ることができました。読み終えた後も、ロシアンブルとアメショーがどこかで元気にやっているといいな、なんて考えてしまいます。そして、もしかしたら、すぐ隣に…? なんて。
まとめ
伊坂幸太郎さんの「ペッパーズ・ゴースト」は、現実と作中作が交錯する独特な構造と、ニーチェの哲学が織り込まれた深いテーマ性を持つ、非常に読み応えのある作品でした。特殊能力を持つ教師・檀先生と、彼を助ける(?)小説の中の登場人物・ネコジゴハンターの活躍から目が離せません。
物語は、サスペンスフルな展開の中に、登場人物たちの葛藤や哲学的な問いかけを巧みに織り交ぜています。特に、永遠回帰という思想が、テロ被害者遺族たちの絶望や行動原理と結びつけられている点は、深く考えさせられました。重いテーマを扱いながらも、ロシアンブルとアメショーの軽妙なキャラクターが物語に独特の味わいを加えており、最後まで飽きさせません。
読み終わった後には、現実と虚構の境界が少し揺らぐような、不思議な感覚とともに、人生や幸福について改めて考えるきっかけを与えてくれるでしょう。伏線の巧みさ、構成の妙、そして心に残るラストシーン。伊坂幸太郎ファンはもちろん、読み応えのあるエンターテイメント小説を求めている方におすすめしたい一冊です。ぜひ手に取って、この奇妙で魅力的な世界を体験してみてください。