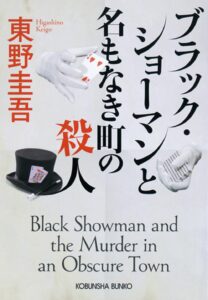
小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が送り出した、この現代を映すミステリについて、私なりの見解を述べさせていただきましょう。コロナ禍という、誰もが経験したであろう閉塞感を背景に据えながら、実に彼らしいエンターテインメントが展開されます。
物語の舞台は、どこにでもあるような地方の観光地。大きな計画が頓挫し、静まり返った町で起こる殺人事件。そこに颯爽と(?)登場するのが、元マジシャンという異色の経歴を持つ探偵役、神尾武史です。彼の型破りな手法が、澱んだ空気をかき回していく。この記事では、物語の筋道を追いながら、その核心部分にも触れていきます。
読み進めるうちに、あなたもこの”黒い魔術師”の仕掛けに魅了されるか、あるいはその胡散臭さに眉をひそめることになるか。いずれにせよ、退屈はしないはずです。私の綴る言葉が、あなたの読書体験の一助となれば、まあ、それも一興というものでしょう。しばしお付き合いください。
小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」のあらすじ
物語は、神尾真世が故郷の町へと帰るところから始まります。建築会社に勤め、結婚も間近に控えた彼女のもとに届いたのは、父・英一が何者かに殺害されたという報せでした。英一は元中学教師であり、真世の同級生たちの多くにとっても恩師。地元では人望厚い人物として知られていました。しかし、その彼がなぜ、誰の手によって命を奪われなければならなかったのか。
警察の捜査が進む中、真世の前に現れたのは、長年音信不通だった叔父の神尾武史。アメリカでマジシャンとして活動していたという彼は、どこか掴みどころのない雰囲気を纏っています。そして驚くべきことに、武史は警察とは別に、独自の手法で兄の死の真相を突き止めると宣言するのです。彼の言う「独自の手法」とは、まさに元マジシャンならではの観察眼、人心掌握術、そして少々…いや、かなりグレーな情報収集術でした。
舞台となる町は、世界中を覆ったコロナウイルスの影響で、計画されていた町おこしプロジェクトが頓挫し、閉塞感に包まれています。被害者である英一が殺される直前まで関わっていたのも、真世の同級生たちが中心となって進めていた、この町おこし計画でした。計画の中心には、人気漫画『幻脳ラビリンス』の作者となった同級生・釘宮克樹や、地元の有力者である柏木広大、広告代理店に勤める九重梨々香、IT企業の社長となった杉下快斗など、かつての仲間たちの顔ぶれが並びます。
武史は、そのマジックのような手捌きで、関係者たちの嘘や隠し事を次々と暴き出していきます。英一が誰に恨まれていたのか? 町おこし計画の裏には何があるのか? そして、犯人は本当に真世の同級生たちの中にいるのか? 武史のトリッキーな捜査によって、事件は思いもよらない様相を呈し始め、人間関係の複雑な糸が少しずつ解き明かされていくのです。真世は、叔父の危険なやり方に戸惑いながらも、父の死の真相を知るために彼と行動を共にせざるを得なくなります。
小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」の長文感想(ネタバレあり)
さて、東野圭吾氏による「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」について、核心に触れつつ、私の見解を詳しく述べさせていただきましょうか。この作品、多くの読者を惹きつけたようですが、手放しで称賛するには少々引っかかる点も、まあ、無きにしも非ず、といったところです。
まず何と言っても注目すべきは、探偵役を務める神尾武史というキャラクターでしょう。元マジシャンであり、現在はバーの経営者。飄々としていながらも、鋭い観察眼と、目的のためなら手段を選ばない大胆さ、悪く言えば厚かましさ、あるいは手癖の悪さをも持ち合わせています。彼の存在が、この物語の推進力であり、最大の魅力となっていることは論を俟たないでしょう。マジシャンとしてのスキル、例えば人の心理を読む術や、手先の器用さ(盗聴器を仕掛けたり、パスワードを盗み見たり、などという些か褒められたものではない行為も含めて)を駆使して情報を集め、真相へと迫っていく様は、従来の探偵像とは一線を画しており、新鮮に映ります。古典的な名探偵が持つような万能感、あるいは一種の超人性すら感じさせる造形は、近年の東野作品の探偵役――例えば加賀恭一郎や湯川学のように、人間的な葛藤や成長を描かれることが多い――とは異なるアプローチであり、意欲的と評価できるかもしれません。しかし、その一方で、彼のやり方はあまりにも強引で、倫理的に危うい。証拠集めのためなら平気で法に触れるような行為も厭わない姿勢は、読んでいて少なからず抵抗感を覚える向きもあるのではないでしょうか。まるで舞台袖から観客の反応を窺う演出家のように、武史は事件の真相を少しずつ明らかにしていきますが、その手法の是非は、読者の価値観によって評価が分かれるところでしょう。彼を「とんでもないヒーロー」と呼ぶか、「ただの厄介者」と見るか。私は、どちらかと言えば後者に近い感情を抱かなくもありませんでしたね。
対照的に、物語の視点人物となる姪の神尾真世は、どこまでも「普通」の女性として描かれています。父の死という悲劇に見舞われ、胡散臭い叔父に振り回されながらも、事件の真相を知ろうとする。彼女の存在は、読者が感情移入するための重要な装置として機能しています。しかし、彼女自身の主体性や、事件解決への積極的な貢献という点では、やや物足りなさを感じたのも事実です。武史の「助手」あるいは「ワトソン役」という立場以上に、彼女自身の葛藤や成長がもっと深く描かれていれば、物語により厚みが増したのではないか、とも思えます。まあ、武史の強烈な個性の前では、霞んでしまうのも致し方ないのかもしれませんが。彼女と婚約者・健太の関係性についても、作中で一応の決着(?)を見ますが、やや中途半端な印象は否めません。健太の過去に関する疑惑のメール。あれが結局、第三者による悪意ある工作だったのか、それとも健太の過去の一端を示すものだったのか。武史は健太を「真面目で正直な男だが、過ぎたるは及ばざるがごとし」と評しましたが、その真意は読者の解釈に委ねられています。個人的には、武史の洞察力を信じるならば、メールは悪質な嫌がらせであり、健太自身はシロだったと考えるのが自然かもしれません。しかし、明確な答えが示されないため、後味の悪さが残ることは否定できませんね。
そして、この作品のもう一つの大きな特徴は、コロナ禍という時代設定を真正面から取り込んでいる点でしょう。マスク、オンライン会議、移動制限、経済的な打撃といった、我々が経験したばかりの日常が、物語の背景としてリアルに描かれています。観光地が寂れ、町おこし計画が頓挫するという状況設定は、事件が起こる閉塞的な空間を作り出す上で効果的に機能しています。この試み自体は評価に値するでしょう。しかし、その設定がミステリーの根幹、つまりトリックやアリバイ工作、犯人特定のロジックに、どれほど深く、独創的に組み込まれていたかというと、少々疑問符がつきます。例えば、オンライン葬儀の映像が証拠の一つとして使われる場面はありますが、それが決定的な決め手となるわけでもなく、コロナ禍ならではの状況をもっと巧みに利用したトリックや展開を期待していた読者にとっては、物足りなさが残ったかもしれません。コロナ禍という設定は、物語のリアリティや雰囲気を高める以上の役割を、果たしきれていなかったのではないか。そんな印象を受けました。この時代設定は、数十年後に読まれたとき、果たしてどのように受け止められるのか。その普遍性には、やや懸念があると言わざるを得ませんね。
ミステリーとしての構成に目を向ければ、そこは流石に東野圭吾、と言ったところでしょうか。被害者である元教師・英一と、彼を慕っていた(あるいは、そう見せかけていた)元教え子たち。町おこし計画を巡る利害関係。それらが複雑に絡み合い、誰が犯人でもおかしくない状況が作り出されています。容疑者となる同級生たちのキャラクターも、それぞれに個性が与えられています。漫画家として成功したものの過去に影を持つ釘宮(のび太)、彼を利用しようとする抜け目のない九重(しずかちゃん?)、地元の実力者である柏木(ジャイアン)、銀行員の牧原(スネ夫)、エリート然とした杉下(出木杉)といった、どこかで見たような類型的な人物設定は、分かりやすさには繋がっていますが、深みという点では物足りないかもしれません。そして、犯人。成功のために恩師の忠告を疎ましく思い、衝動的に殺害に至ってしまったという動機は、人間の弱さ、愚かさを描いており、一定の説得力はあります。しかし、その犯行に至るまでの心理描写や、犯行後の隠蔽工作などが、やや類型的であり、驚きという点では控えめだったように感じます。武史が手品のように真相を暴く、という触れ込みでしたが、実際には地道な情報収集と推理の積み重ねであり、トリック自体に派手なマジック的要素があったわけではありません。これは期待の仕方によっては、肩透かしと感じるかもしれませんね。
結局のところ、「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」は、魅力的ながらも賛否両論ありそうな探偵役と、現代的な設定を盛り込みつつ、安定した筆致で描かれたエンターテインメント・ミステリー、とでも言っておきましょうか。読みやすい文章、テンポの良い展開は健在であり、多くの読者を楽しませる力を持っていることは確かです。しかし、武史のキャラクター造形や手法、コロナ禍設定の活かし方、ミステリーとしての驚きといった点においては、更なる深みや独創性を期待したい、というのが正直なところです。続編も刊行されているようですが、この”黒い魔術師”が今後どのように進化していくのか、あるいはしないのか。まあ、見守っていくとしましょうか。
まとめ
さて、東野圭吾氏の「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」について、色々と語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。この作品は、コロナ禍という現代的な背景の中で展開される、一風変わった探偵役が活躍するミステリーです。
元マジシャンという経歴を持つ神尾武史の、型破りで少々(いや、かなり)強引な捜査手法は、物語に独特の推進力と、ある種の胡散臭さをもたらしています。彼のキャラクターを魅力と感じるか、それとも鼻につくと感じるかは、読者次第でしょう。安定したストーリーテリングと読みやすさは、さすが東野作品といったところですが、ミステリーとしての驚きや、設定の深掘りという点では、更なる高みを期待したくなる部分も、なきにしもあらず、です。
とはいえ、エンターテインメント作品として十分に楽しめる水準にあることは間違いありません。特に、一筋縄ではいかない探偵役が好きな方や、現代社会を反映したミステリーを読んでみたいという方には、手に取ってみる価値があるかもしれません。まあ、読後感がすっきり爽快、とは言い切れないかもしれませんがね。それもまた、この作品の味ということなのでしょう。
































































































