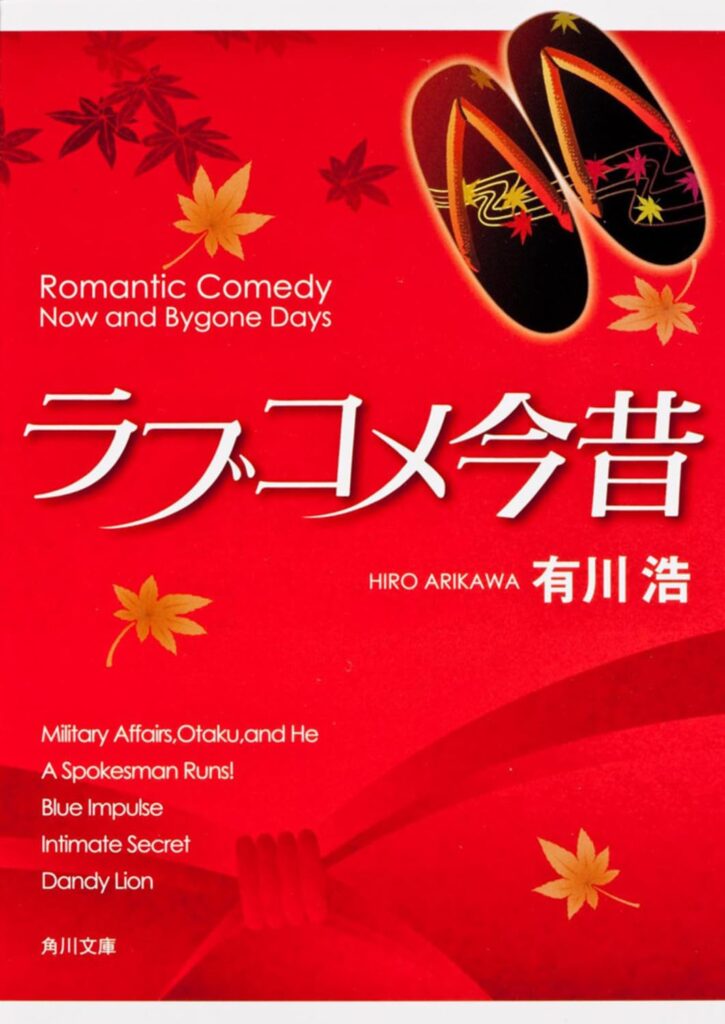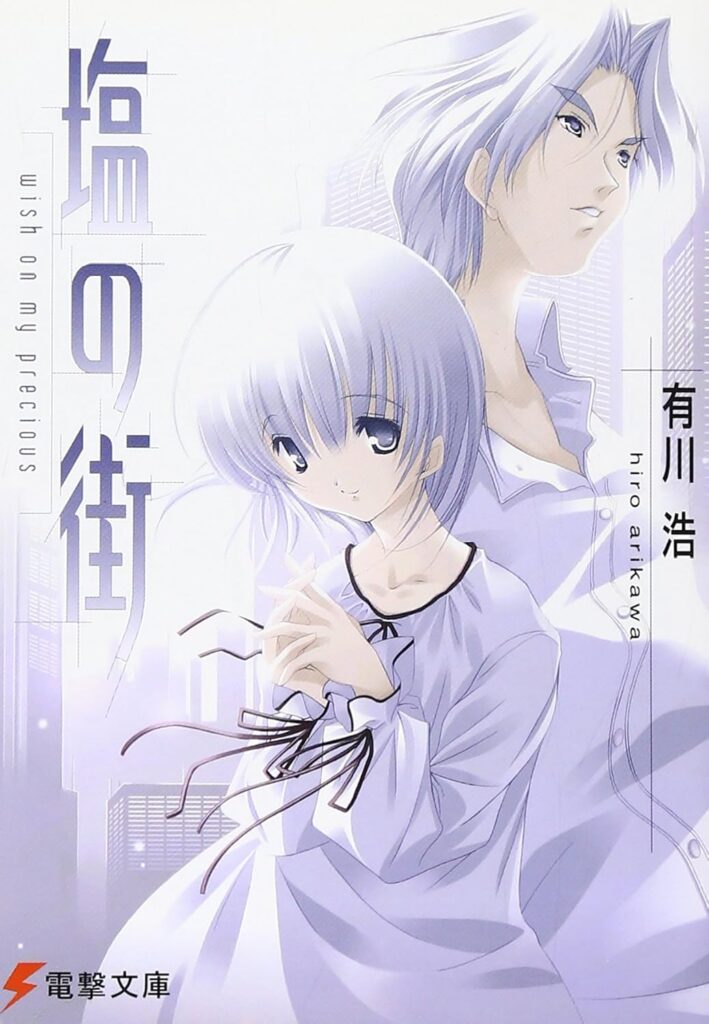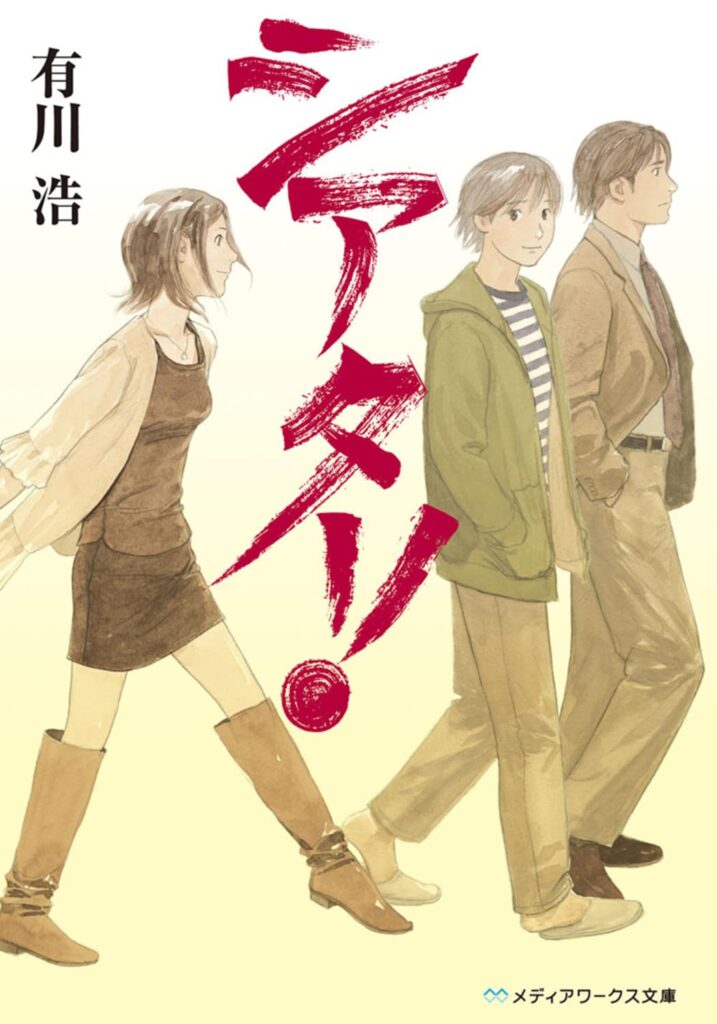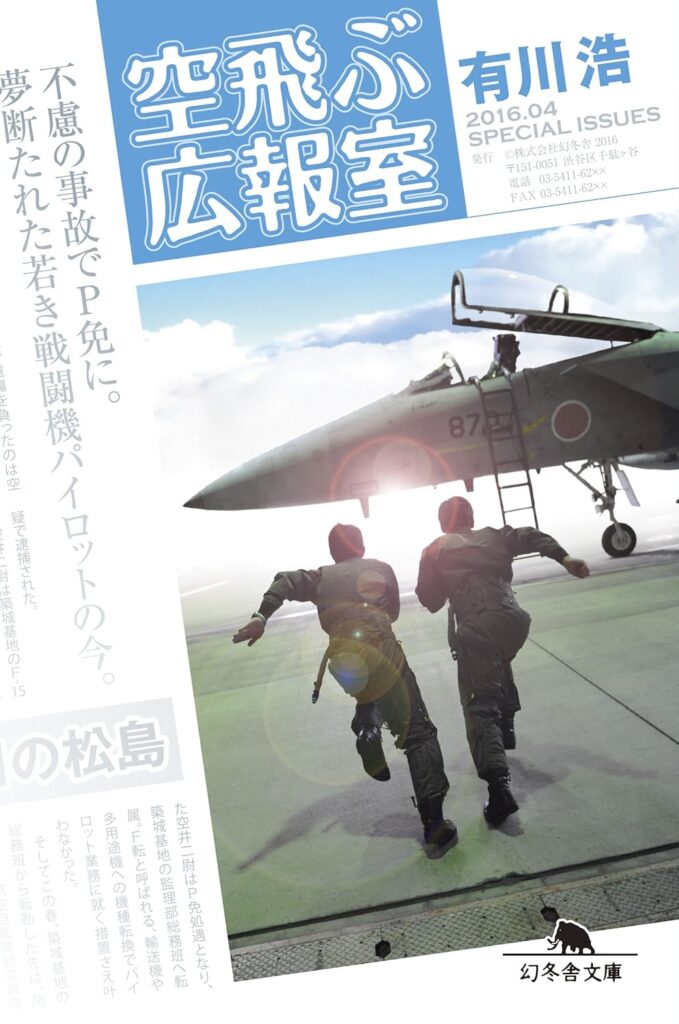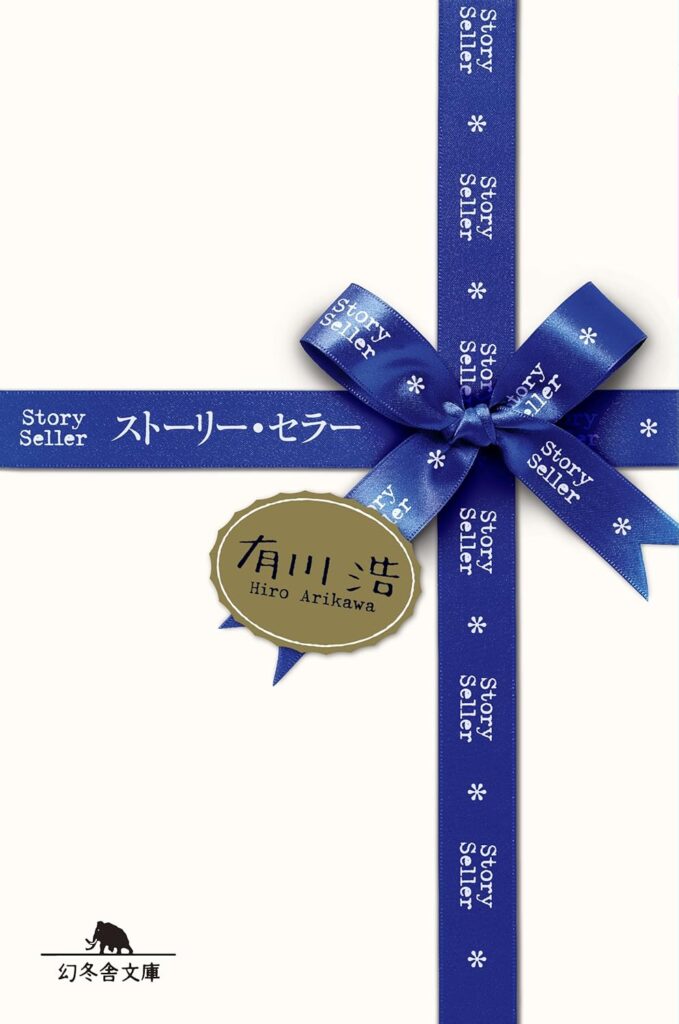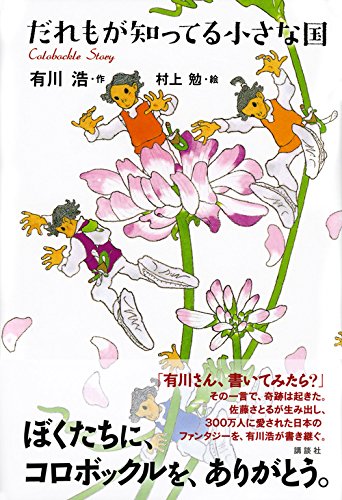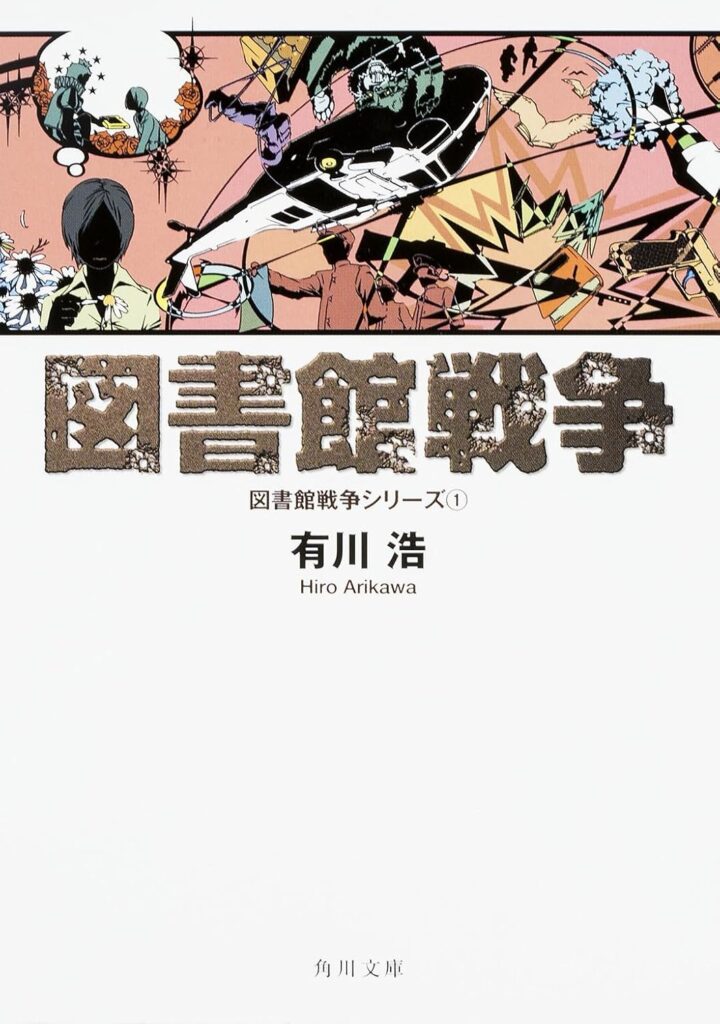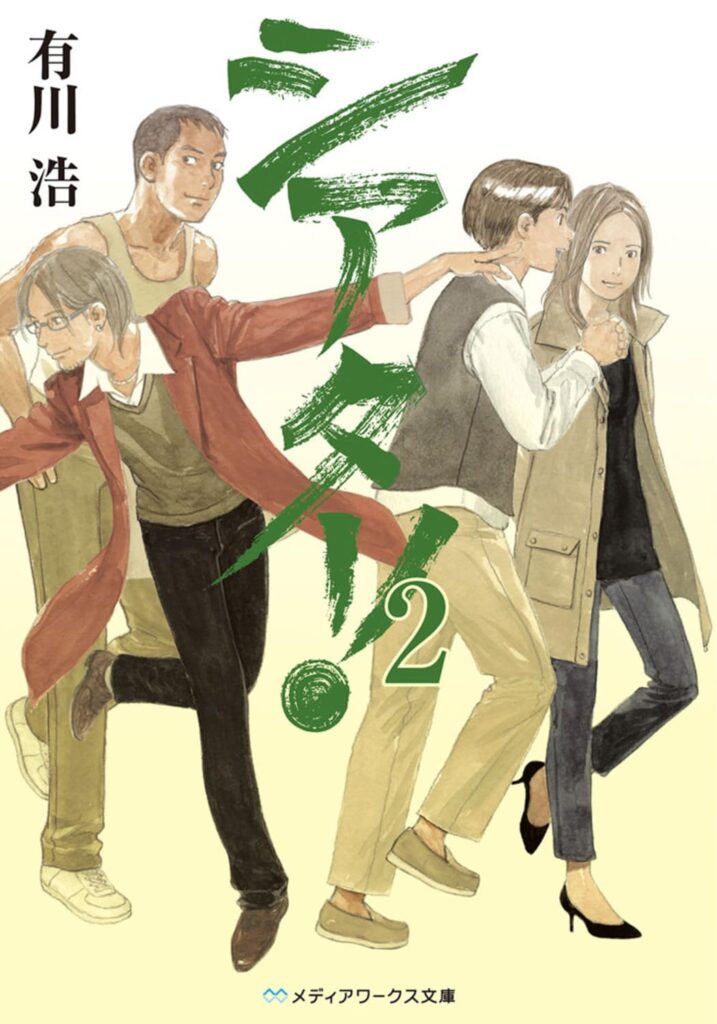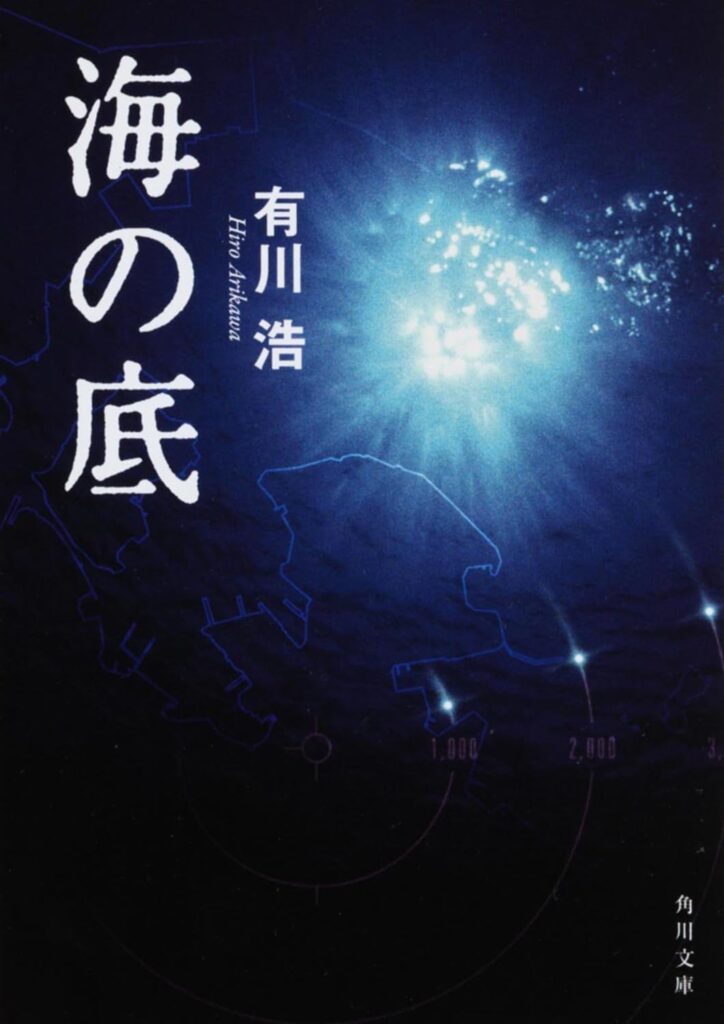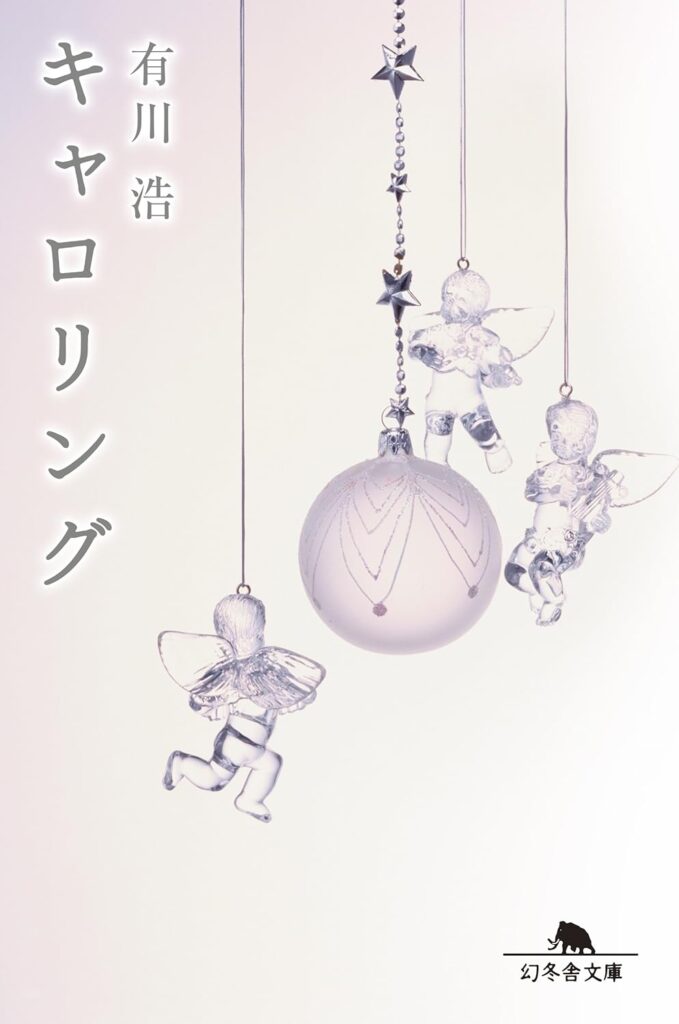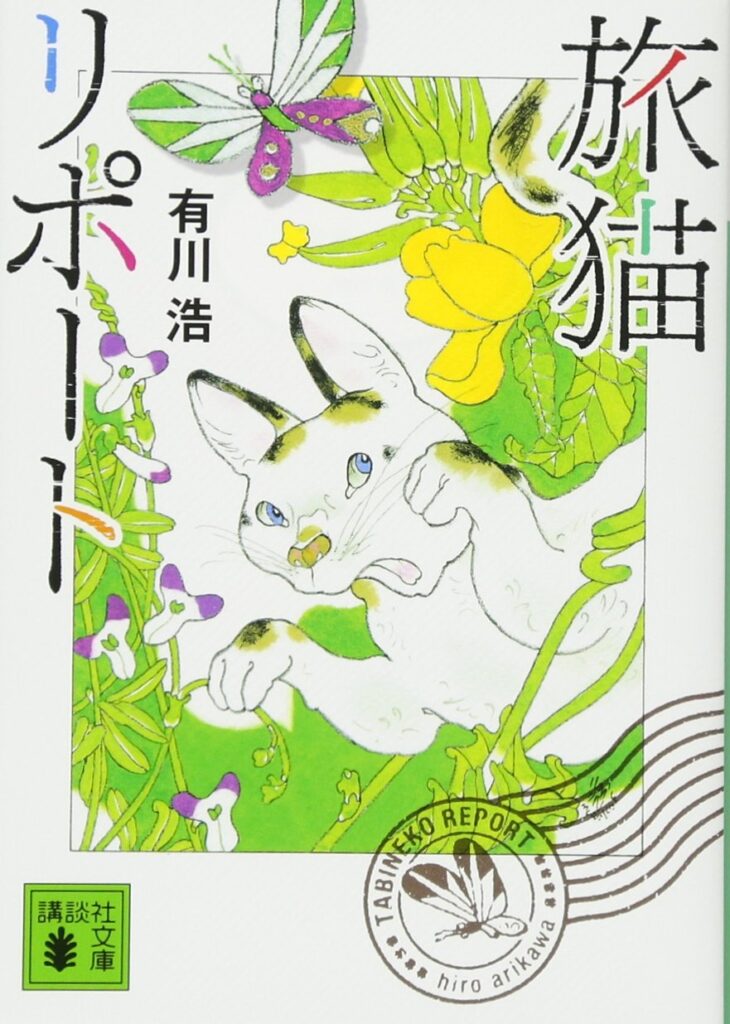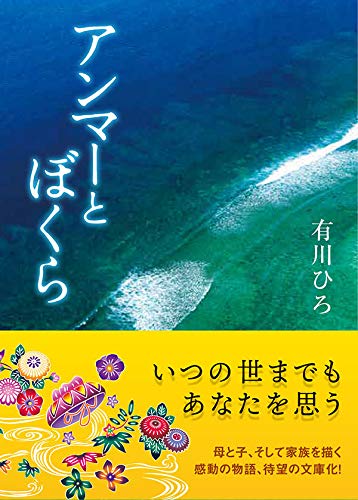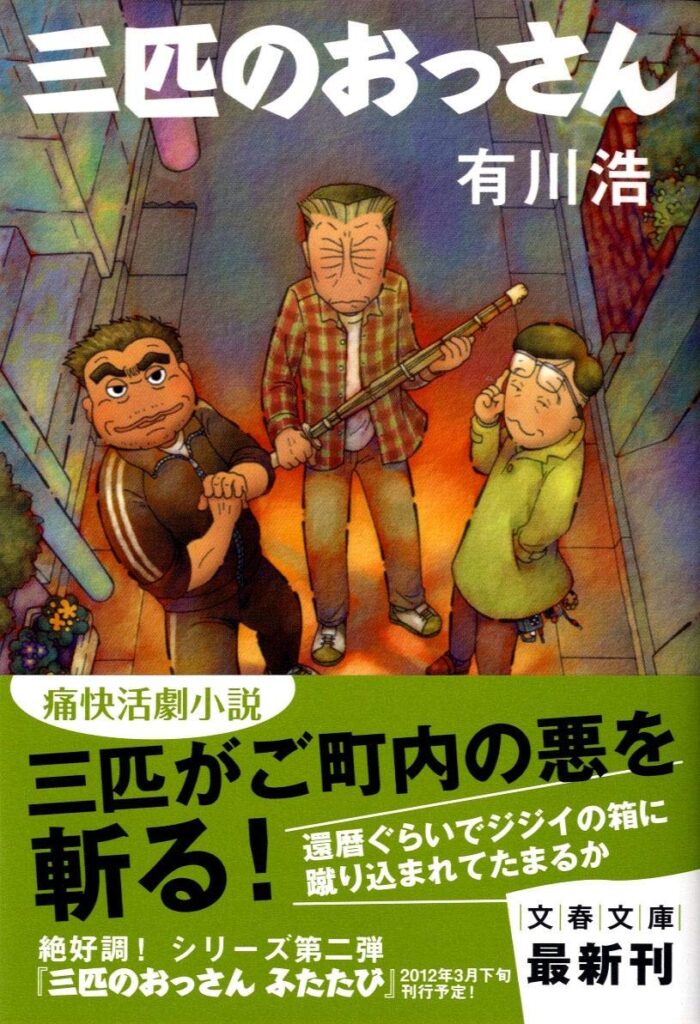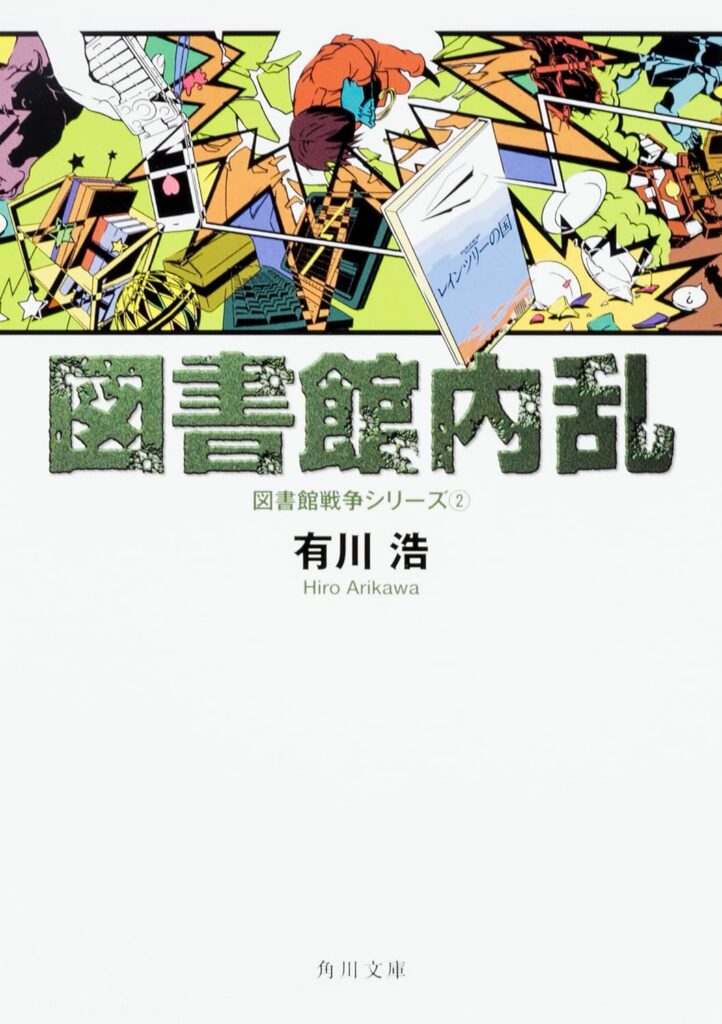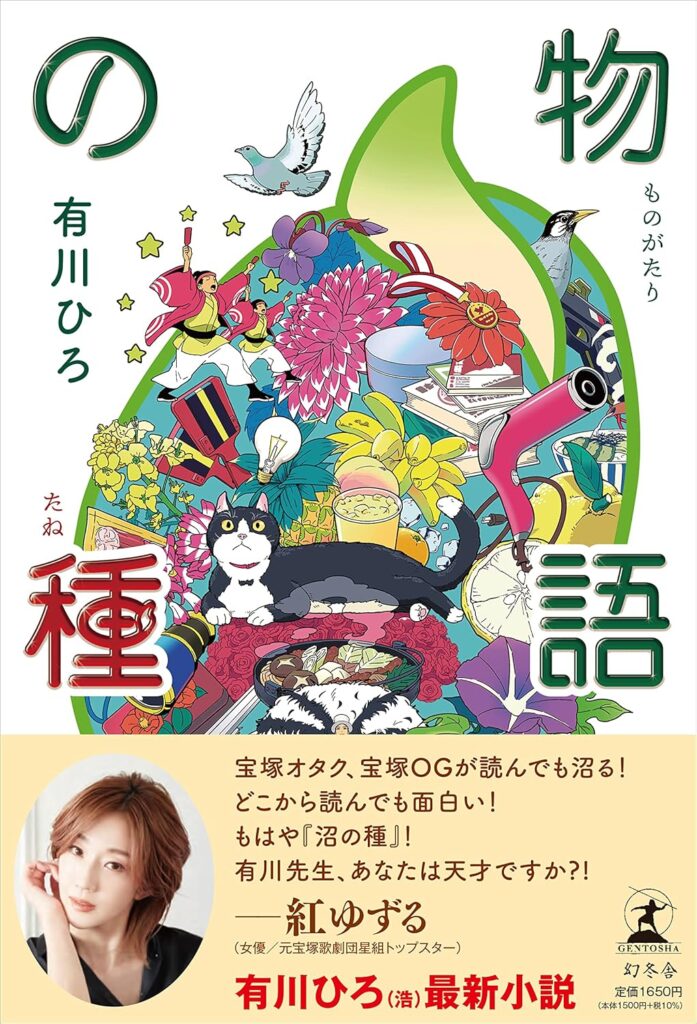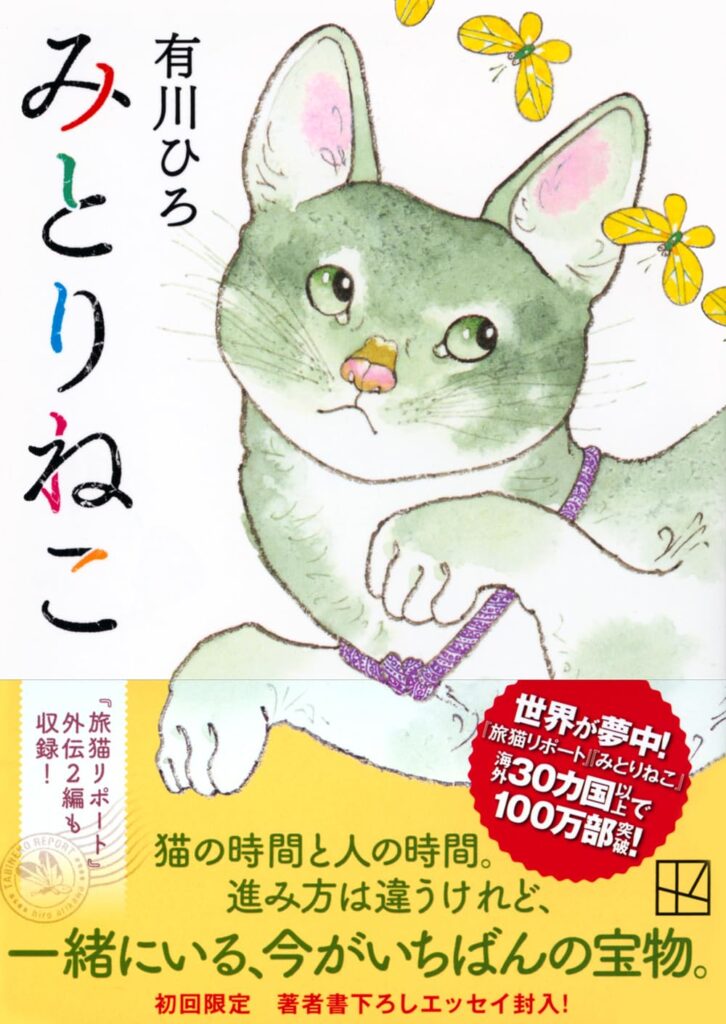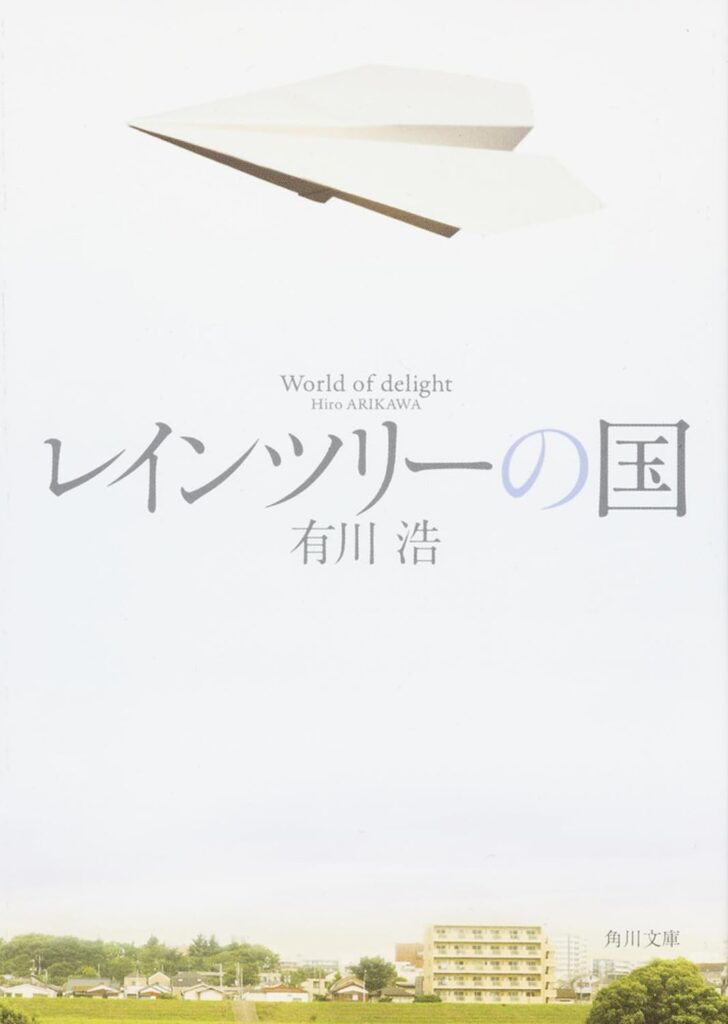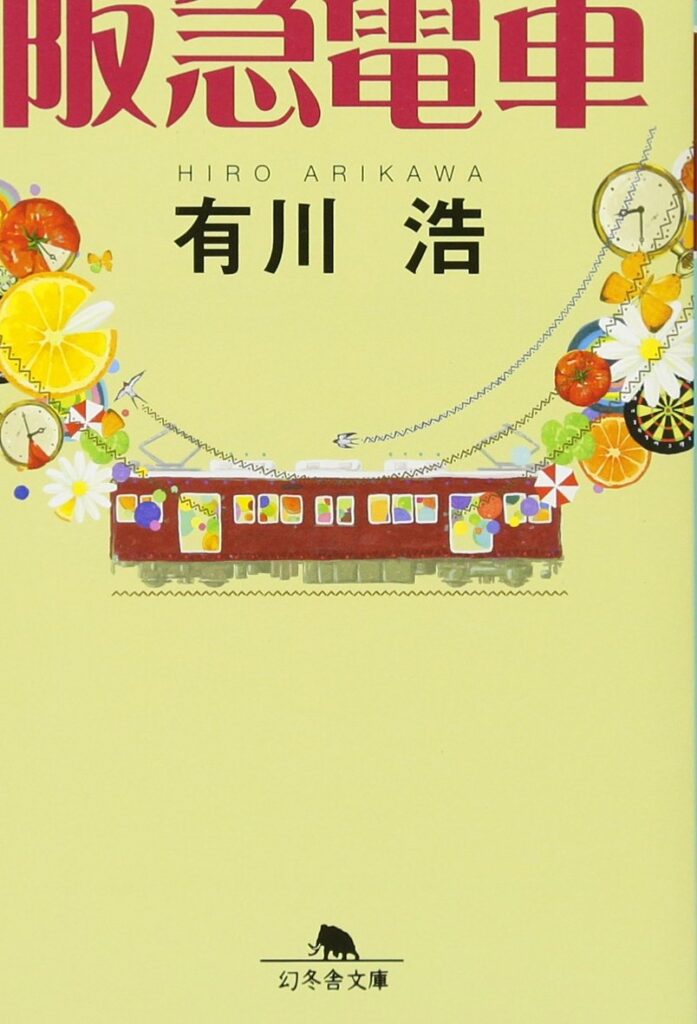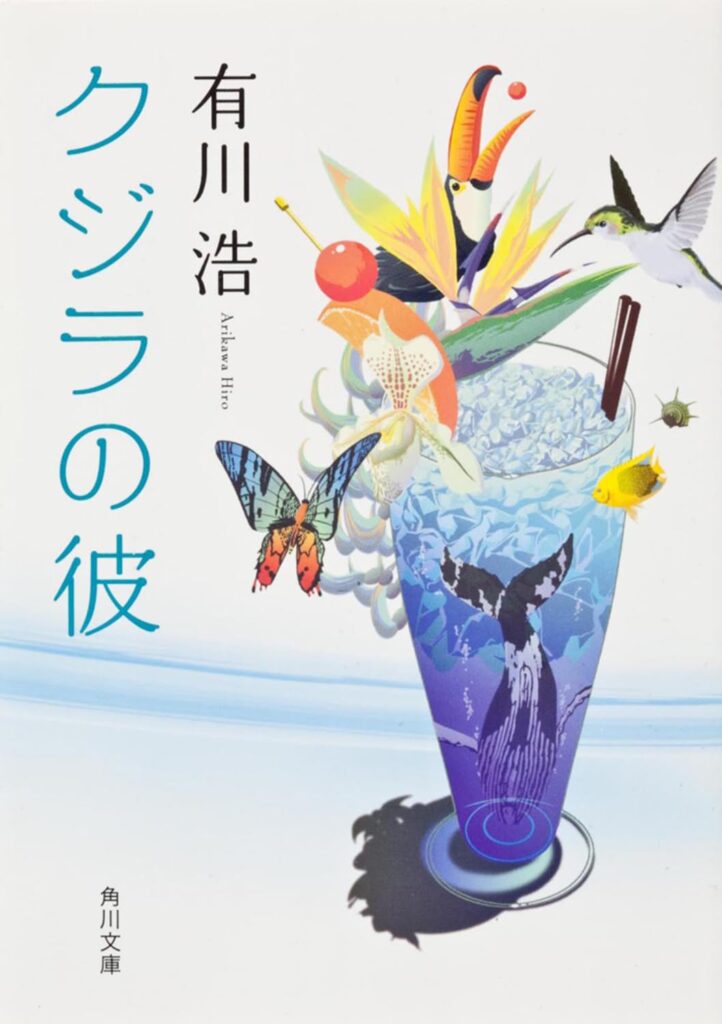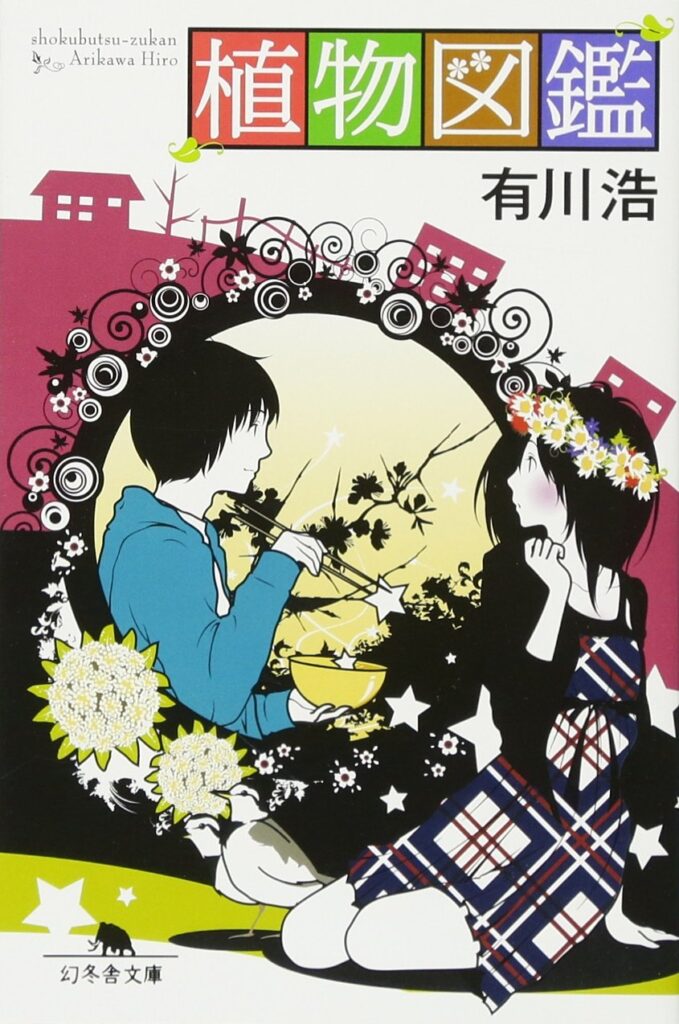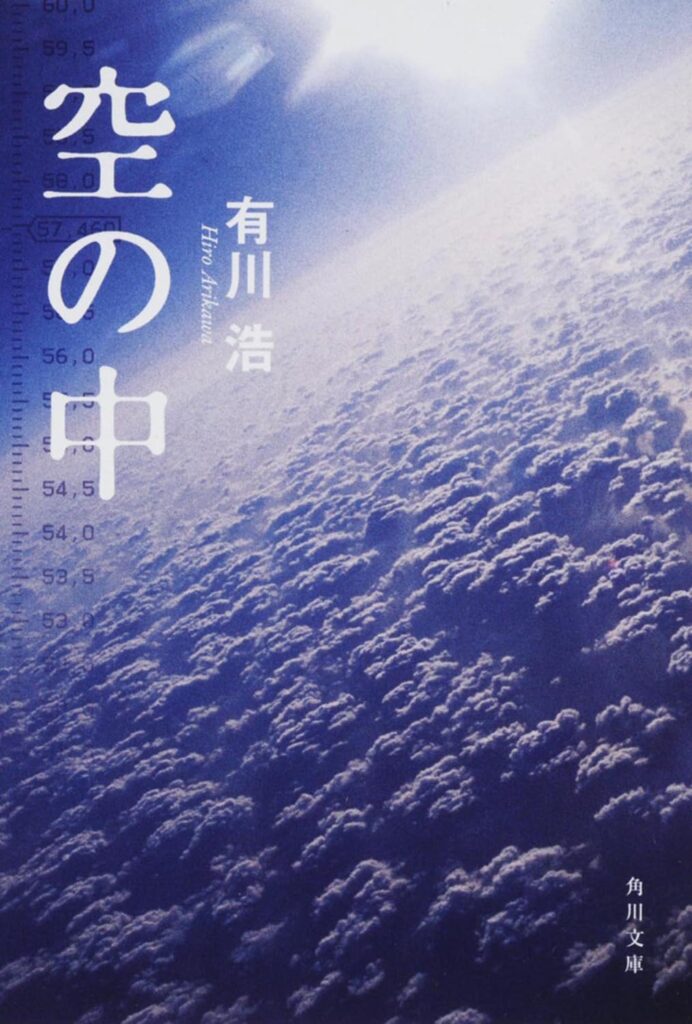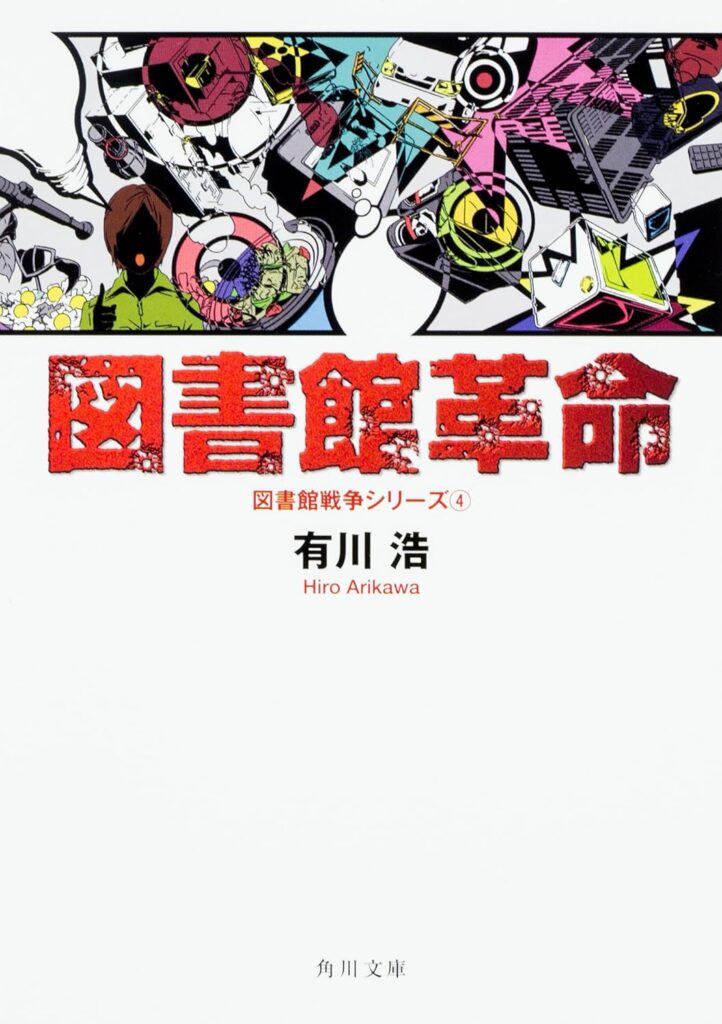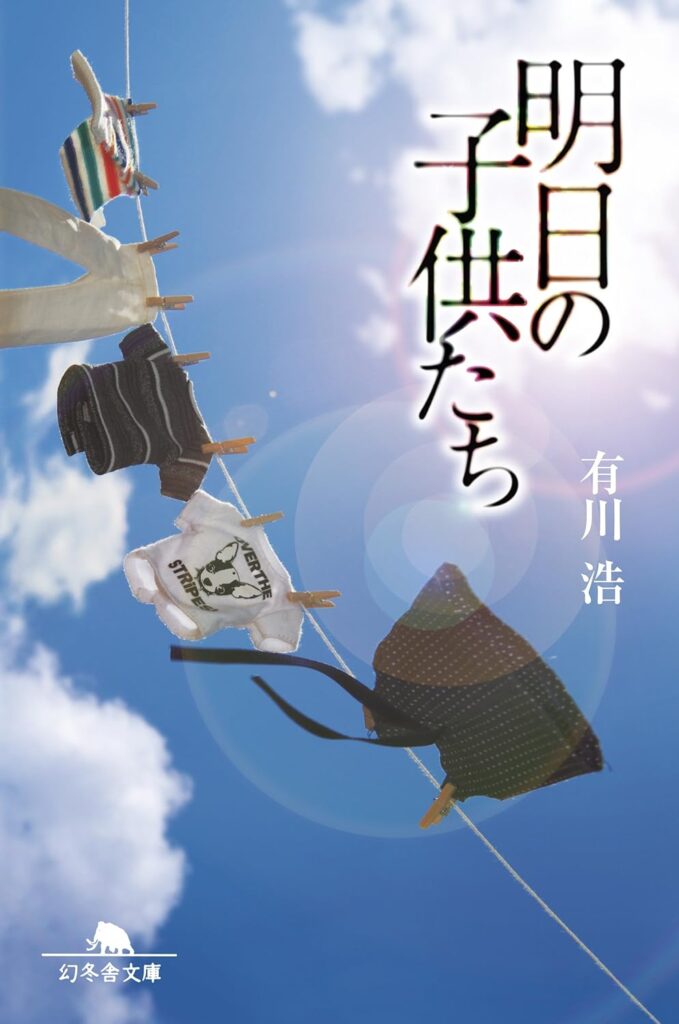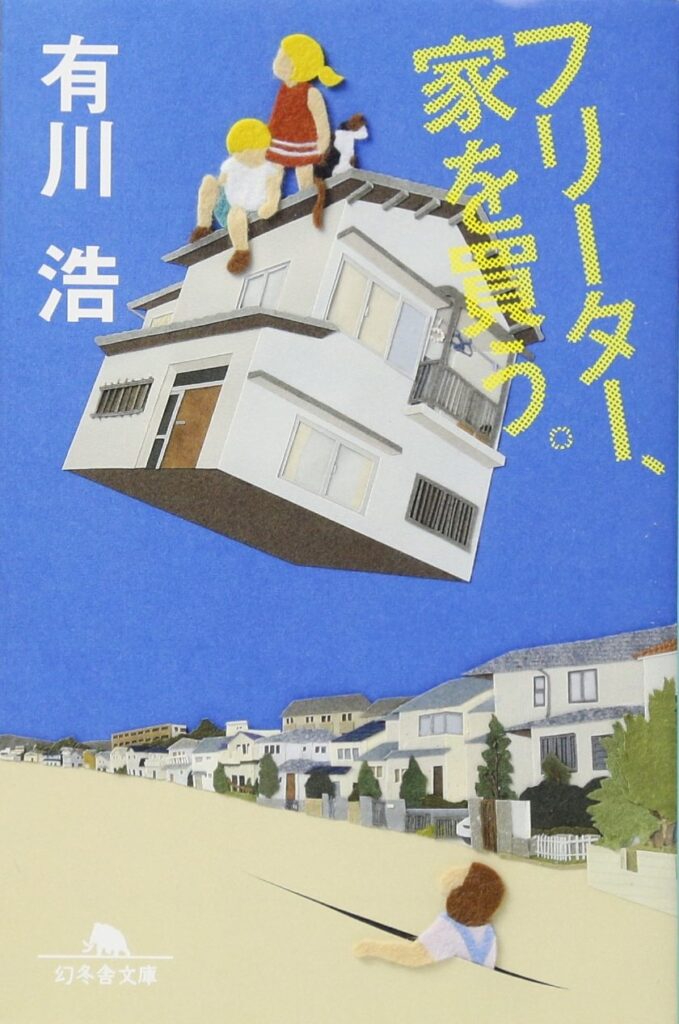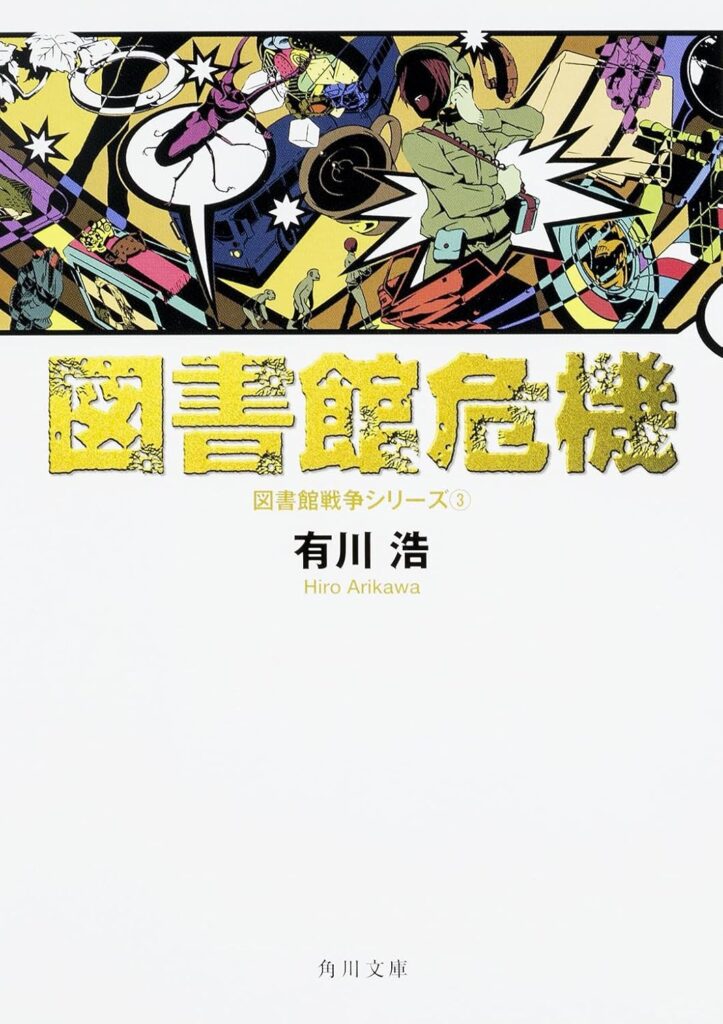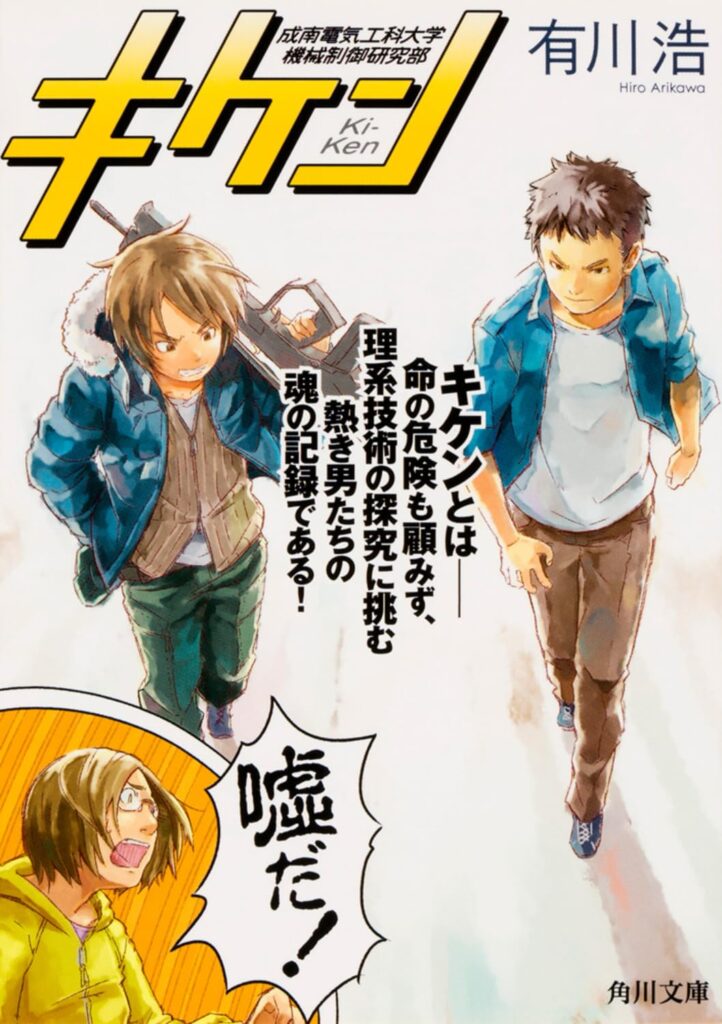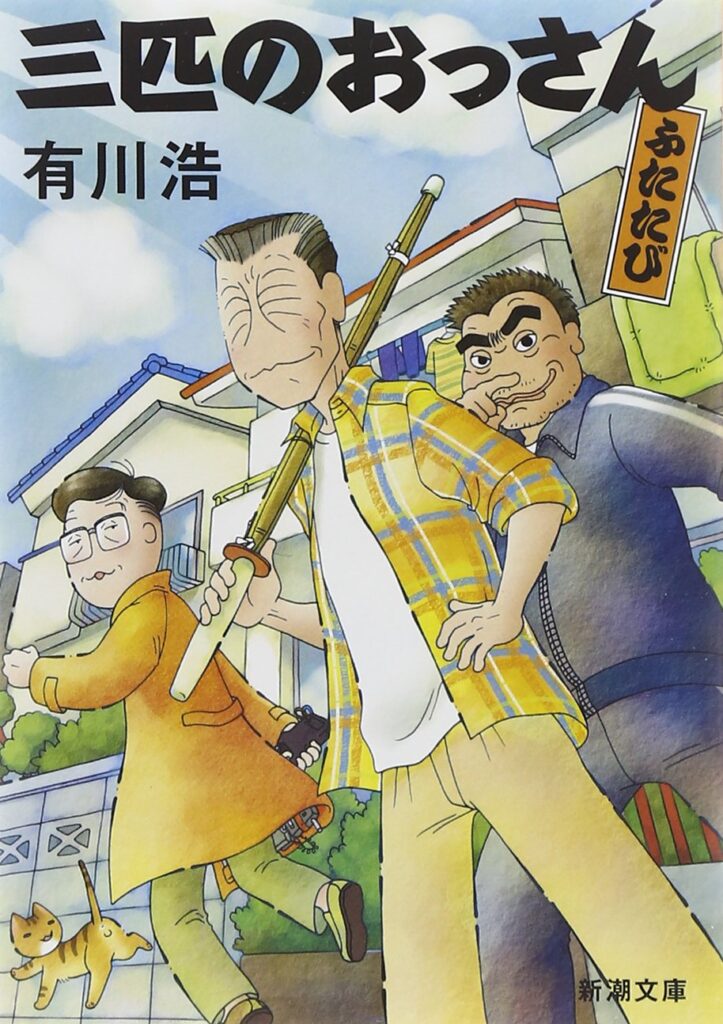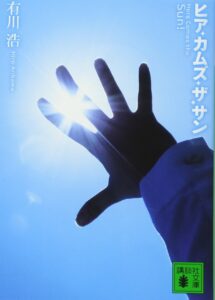 小説「ヒア・カムズ・ザ・サン」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。有川浩さんが描く、少し不思議で、とても温かい物語の世界へ、一緒に足を踏み入れてみませんか。この物語は、人と人との繋がりや、言葉にならない想いが丁寧に描かれていて、読み終えた後にはきっと、心がじんわりと温かくなるはずです。
小説「ヒア・カムズ・ザ・サン」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。有川浩さんが描く、少し不思議で、とても温かい物語の世界へ、一緒に足を踏み入れてみませんか。この物語は、人と人との繋がりや、言葉にならない想いが丁寧に描かれていて、読み終えた後にはきっと、心がじんわりと温かくなるはずです。
物語の中心には、物に触れることでそこに残された記憶や感情を読み取ることができる、特別な力を持った編集者の青年がいます。彼の力が、ある父と娘の複雑な過去と現在を結びつけていくことになります。一見するとファンタジーのようですが、描かれているのは非常に人間的な葛藤や愛情、そして長い年月が生んだ誤解と、それを解きほぐそうとする人々の姿です。
この記事では、物語の詳しい流れ、登場人物たちの心の動き、そして物語の核心に迫る部分まで、深く掘り下げていきます。読み進めていただくことで、この作品が持つ独特の魅力や、登場人物たちが抱える想いの深さを感じ取っていただけると思います。もし未読で、結末を知りたくないという方は、ご注意くださいね。それでは、物語の世界を紐解いていきましょう。
小説「ヒア・カムズ・ザ・サン」のあらすじ
物語の主人公は、文芸誌「ポラリス」の編集者である古川真也。彼には、物に触れることで、そこに込められた強い想いや記憶の断片を感じ取るという、秘密の力があります。この力を活かし、時に悩みながらも、作家たちの心に寄り添い、信頼関係を築いてきました。彼の日常は、同僚であり同期の大場カオルとの、互いを認め合う関係性によって支えられています。カオルは真也とは対照的に、地道な努力で仕事に向き合う実直な編集者です。
ある日、編集部に大きな仕事が舞い込みます。アメリカで「HAL」というペンネームで活躍する謎多き脚本家の新作映画「ダブル・マインド」の特集を組むことになったのです。編集長の安藤みずほは、HALの正体が白石晴男という日本人であり、20年ぶりに帰国する彼の娘が、他ならぬカオルであることを突き止めます。安藤は感動的な父娘の再会と独占取材を目論みますが、カオルは複雑な心境を隠せません。20年前に両親が離婚して以来、父に捨てられたという思いを抱き続けていたからです。
成田空港でHALこと白石晴男を出迎える真也とカオル。白石はカオルへ一通の手紙を差し出しますが、カオルは受け取ることができません。その手紙を拾い上げようとした瞬間、真也の力が発動し、手紙に込められた驚くべき秘密──白石晴男を名乗る男の正体と、本当の白石晴男に起きた悲劇、そしてカオルへの深い愛情を知ってしまうのです。
真也が触れた手紙から読み取ったのは、目の前の男が本物の白石晴男ではなく、彼の大学時代からの親友、榊宗一であるという事実でした。本物の白石晴男は、脚本家として成功し、いつか妻と娘をアメリカに呼び寄せたいと願っていましたが、数年前に交通事故で亡くなっていたのです。榊は親友の遺志とペンネーム「HAL」を受け継ぎ、脚本家として活動を続けていました。そして、ずっと見守ってきたカオルに、父親として会いたいと願いながらも、真実を告げられずにいたのでした。真也はこの秘密を知り、榊とカオル、そして事情を知るカオルの母・輝子との関係を取り持つために動き出します。
小説「ヒア・カムズ・ザ・サン」の長文感想(ネタバレあり)
有川浩さんの「ヒア・カムズ・ザ・サン」、この物語に触れると、まるで陽だまりの中にいるような、温かくも少し切ない気持ちに包まれます。特殊な能力を持つ主人公、複雑な家庭環境、隠された真実と、要素だけを並べるとドラマチックで奇抜な印象を受けるかもしれませんが、実際に描かれているのは、とても繊細で、普遍的な人の心の機微です。
まず、主人公の古川真也。彼の持つ「サイコメトリー」に似た能力は、物語の重要な鍵となります。物に触れるだけで、持ち主の強い想いや記憶の断片を感じ取ってしまう。これは、編集者という、作家の「想い」を形にする仕事において、非常に強力な武器になり得ます。原稿に込められた熱意、言葉の裏にある迷い、それらをダイレクトに感じ取れるのですから。でも、真也自身はこの力を「ズル」だと感じ、罪悪感を抱いている。特に、実直な努力家である同僚・カオルの姿を見るたびに、その思いは強くなるようです。この葛藤が、真也というキャラクターに深みを与えています。彼は決して万能の超能力者ではなく、力に戸惑い、悩みながらも、誠実に人と向き合おうとする一人の青年なのです。彼の能力は、単なる便利な設定ではなく、人と人とのコミュニケーションの本質、言葉だけでは伝わらない想いの存在を、私たちに改めて気づかせてくれる仕掛けになっていると感じました。
そして、物語のもう一つの軸となるのが、大場カオルと、彼女の父を巡る物語です。20年間会っていなかった父、しかもその父はアメリカで成功した有名脚本家「HAL」。カオルにとっては、幼い頃に自分と母を捨てた存在であり、わだかまりがあるのは当然です。編集部の企画とはいえ、再会には複雑な感情が渦巻きます。空港での対面のシーンは、読んでいるこちらも緊張しました。差し出された手紙を受け取れないカオルの気持ち、痛いほど伝わってきます。
ここで、真也の能力が決定的な役割を果たします。カオルが落とした手紙に触れたことで、彼は衝撃的な真実を知る。目の前にいる「白石晴男」は偽物で、本物の父は既に亡くなっていること。そして、偽物の父、榊宗一が、どれほど深くカオルを想い、見守ってきたかということ。この真実が、物語を一気に核心へと導きます。
榊宗一という人物の造形が、また素晴らしい。彼は、亡くなった親友・白石晴男の才能を信じ、彼を支え、そして彼の死後、その夢と名前を引き継ぎました。それだけではありません。彼は、親友の娘であるカオルの成長を、父親代わりのようにずっと見守ってきたのです。お食い初め、七五三、小学校の入学式…。本来なら実の父親がいるべき場所にいたのは、榊でした。カオルへの愛情は本物であり、それは親友への友情と、彼自身の優しさから生まれたものなのでしょう。だからこそ、彼は「白石晴男」としてカオルに会うことに苦悩し、真実を隠したまま父を演じることに耐えられなかった。手紙に込めた想いを、真也が読み取ったのは、ある意味で必然だったのかもしれません。
真実を知った真也の行動も、彼の誠実さを表しています。彼は一方的に真実を暴露するのではなく、榊の想いを尊重し、カオルと、事情を知る母・輝子を交えて、まずは榊宗一として向き合う機会を作ることを提案します。彼の能力は、人の秘密を暴くためではなく、拗れてしまった関係を解きほぐし、人が本来持つべき温かい繋がりを取り戻すために使われる。ここに、作者である有川浩さんの優しい眼差しを感じます。
物語のクライマックスは、榊がカオルに真実を告げる場面…ではなく、むしろその後の、彼らがどう関係性を再構築していくか、という部分にあるように思います。カオルにとって、実の父が亡くなっていたという事実は衝撃的だったでしょう。そして、ずっと「父の友人」だと思っていた男性が、実は誰よりも深く自分を愛し、見守ってくれていたという事実。それは、まるで足元が崩れるような驚きだったはずです。しかし、彼女はそれを受け入れ、榊との間に新しい関係を築こうとします。それは、単純な「父と娘」という形ではないかもしれません。でも、血の繋がりを超えた、深い愛情と信頼に裏打ちされた、かけがえのない絆であることは間違いありません。
榊がアメリカへ帰る日、真也のデスクに置かれた小さなプレゼント。名前はなくても、真也には誰からのものか、そしてそこに込められた感謝の気持ちが伝わってくる。このラストシーンは、言葉にしなくても通じ合う想いの確かさと、未来への希望を感じさせてくれて、とても心に残りました。榊はきっと、またカオルに会いに日本へ来るのでしょう。その時、二人の関係は、さらに温かく、確かなものになっているはずです。
この物語は、劇団キャラメルボックスの舞台作品と連動した企画から生まれたという背景も興味深い点です。同じあらすじの骨子から、小説と演劇、それぞれがどのように物語を肉付けしていったのか、想像するのも楽しいですね。小説版である本作は、登場人物の内面描写、特に真也の能力を通した心情の読み取りや、カオル、榊の葛藤が丁寧に描かれているのが特徴だと感じました。
「ヒア・カムズ・ザ・サン」というタイトルは、ビートルズの名曲を思い起こさせます。「太陽がやってくる」という言葉通り、物語は困難や悲しみを乗り越えた先にある、温かな希望の光を感じさせてくれます。嘘や隠し事から始まった関係が、真実を知ることで、より深く、本物の絆へと昇華していく。その過程が、とても感動的でした。特殊な設定でありながら、描かれているのは人と人との普遍的な繋がりと愛情。有川浩さんならではの、優しさと強さが詰まった、読後感の良い作品だと思います。登場人物たちの不器用ながらも懸命な姿に、きっと多くの人が共感し、心を動かされるのではないでしょうか。
まとめ
有川浩さんの小説「ヒア・カムズ・ザ・サン」は、物に触れることで記憶を読み取る力を持つ編集者・古川真也と、彼の同僚である大場カオル、そしてカオルの父を巡る、少し不思議で心温まる物語です。物語の核心には、カオルの父に関する大きな秘密があり、真也の力がその秘密を解き明かすきっかけとなります。
この物語の魅力は、特殊な設定を活かしながらも、登場人物たちの繊細な心の動きや、家族や友人との絆、真実と向き合うことの難しさや大切さを丁寧に描いている点にあります。偽りの関係から始まったとしても、そこには本物の愛情が存在し、真実を知ることで、より深く、かけがえのない繋がりが生まれることを教えてくれます。
読後は、まるで優しい日差しを浴びたような、温かい気持ちになれるはずです。切なさの中にも希望があり、登場人物たちの未来に思いを馳せたくなる、そんな読後感を与えてくれる一冊です。人と人との繋がりの温かさを再確認したい方に、ぜひ手に取っていただきたい作品です。