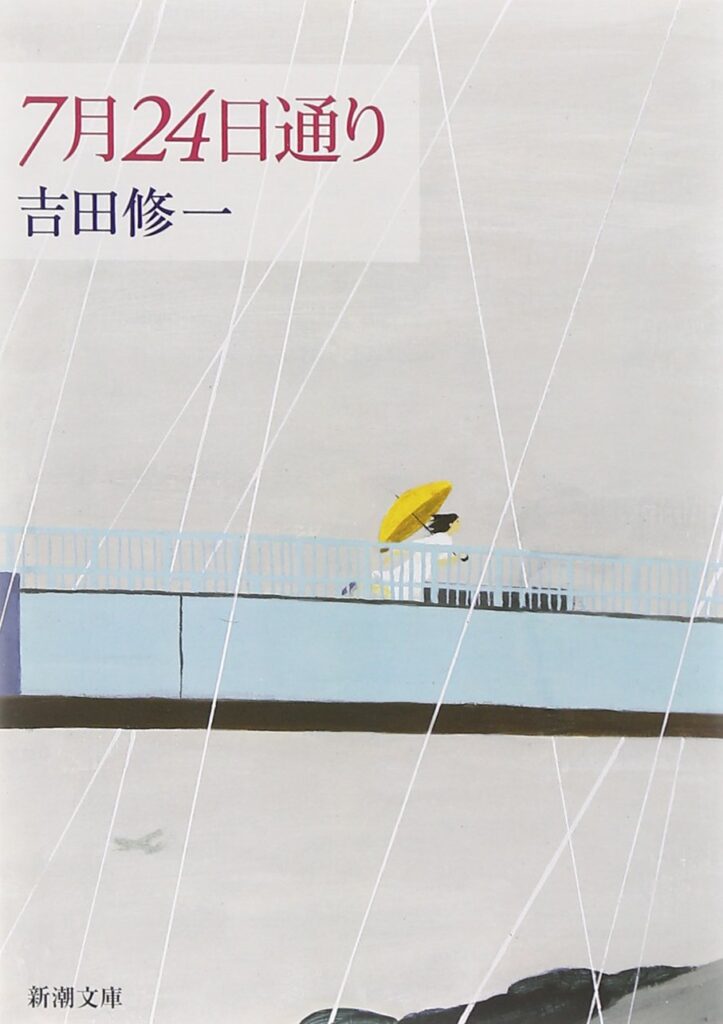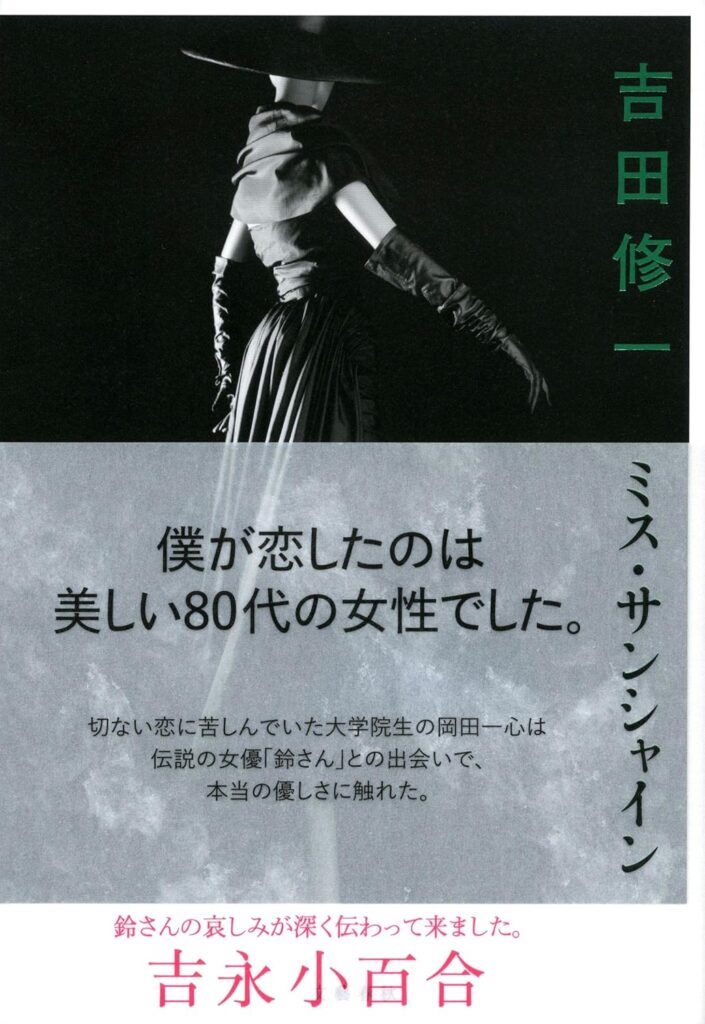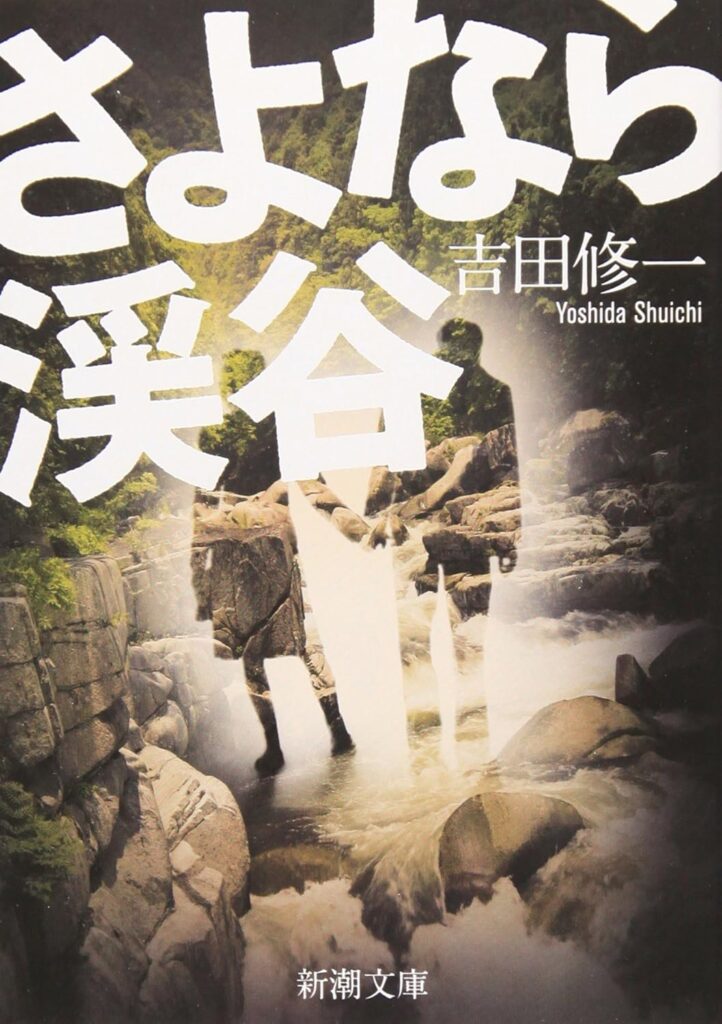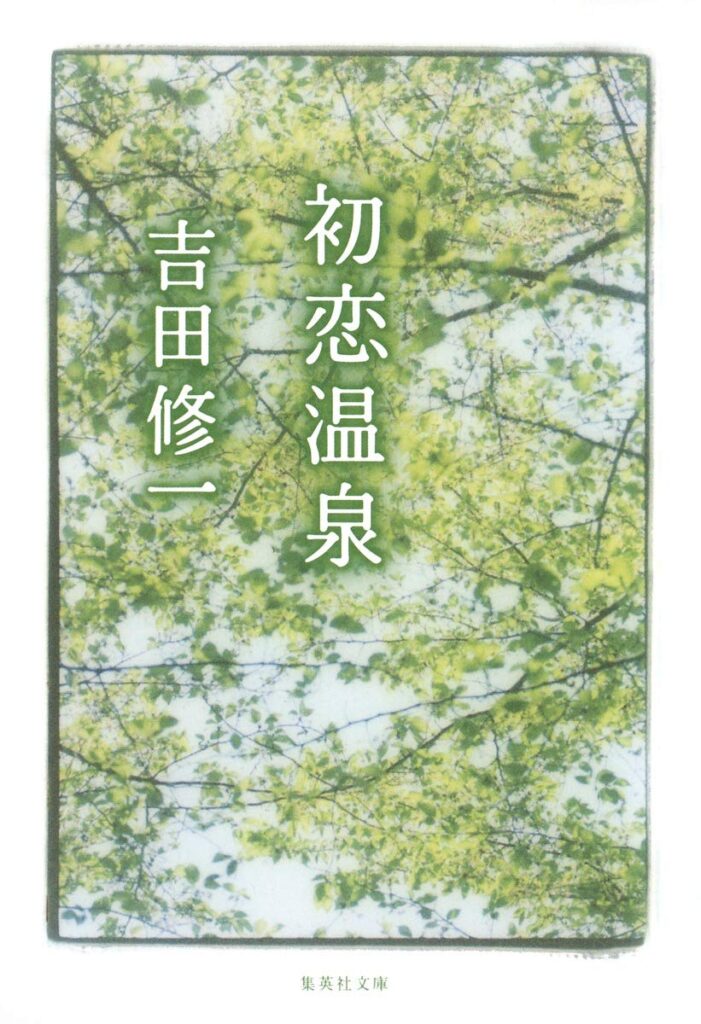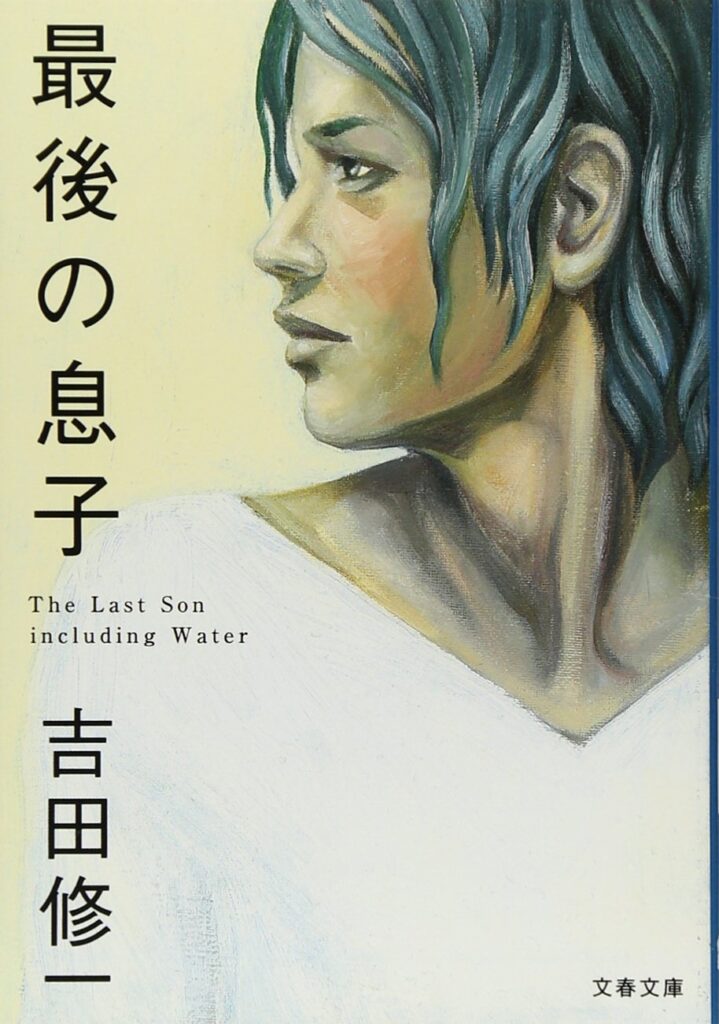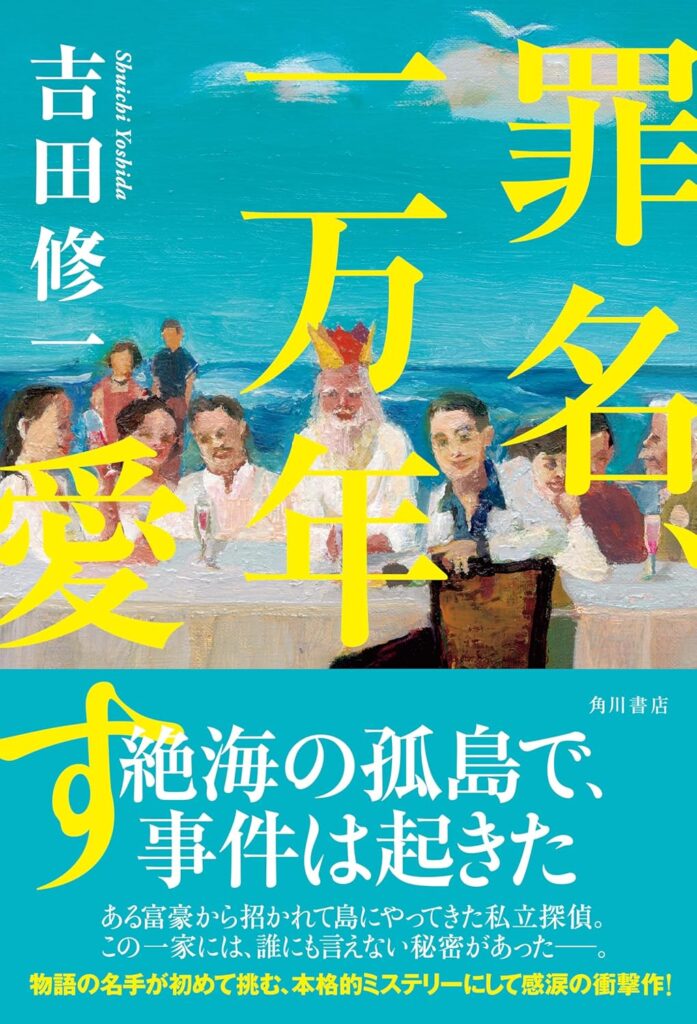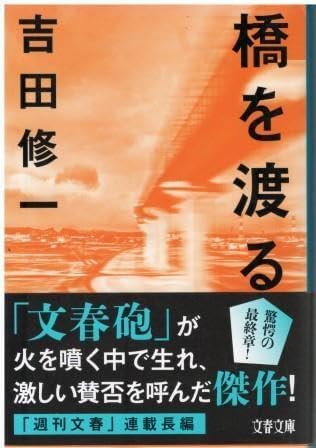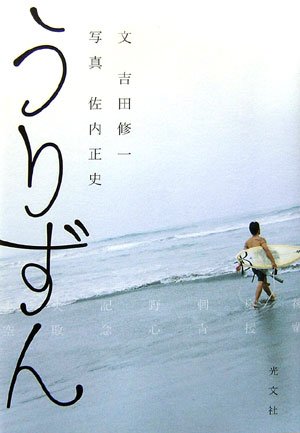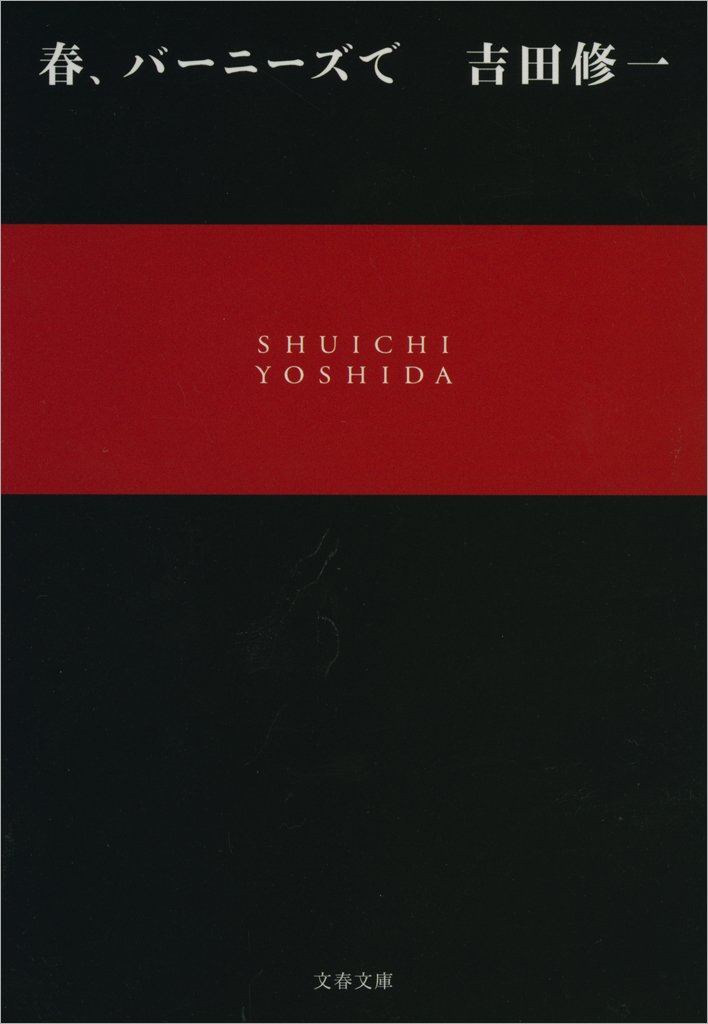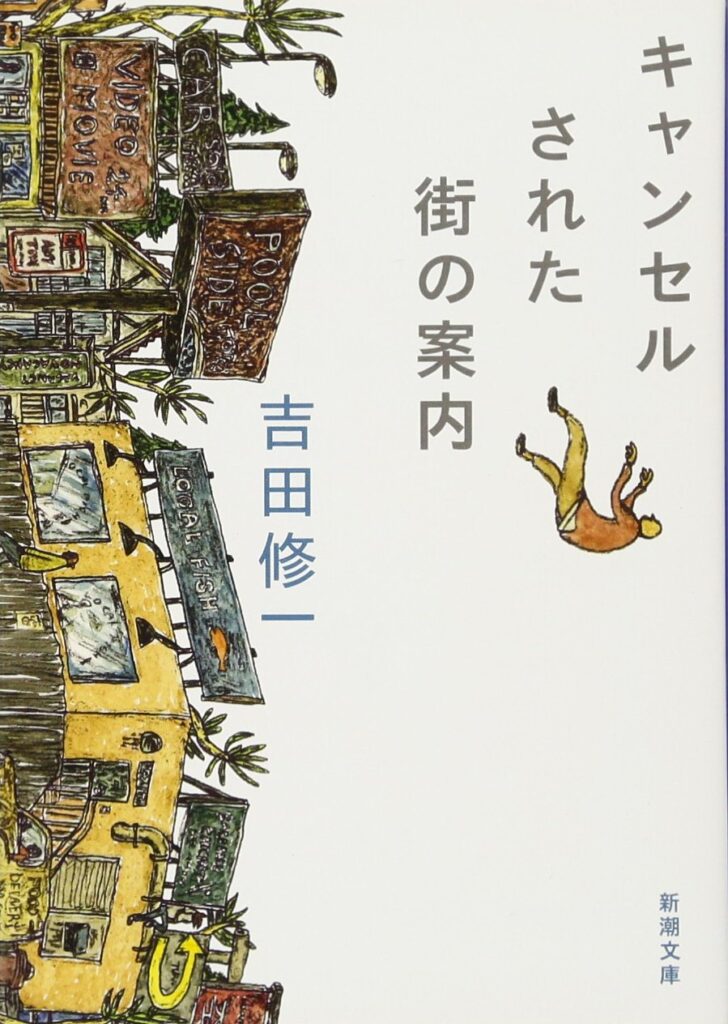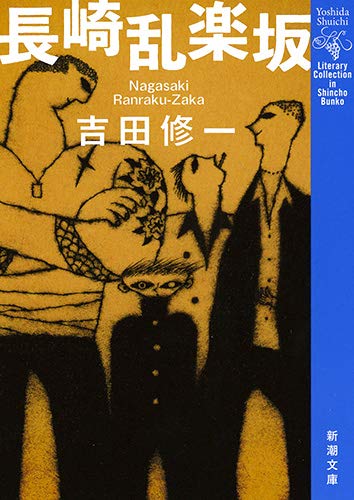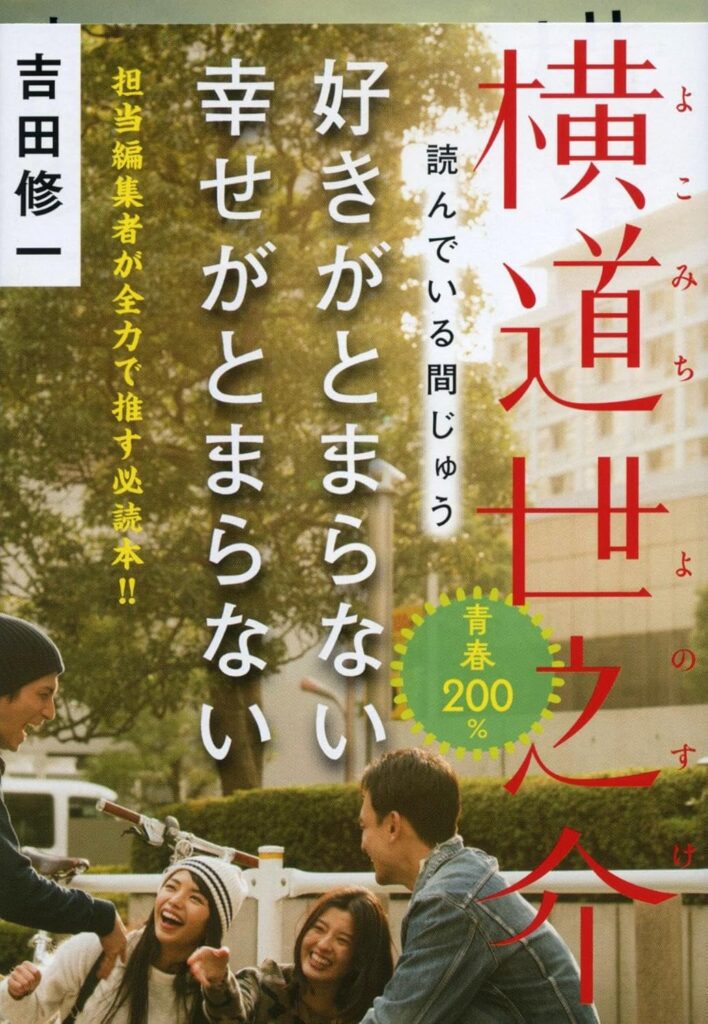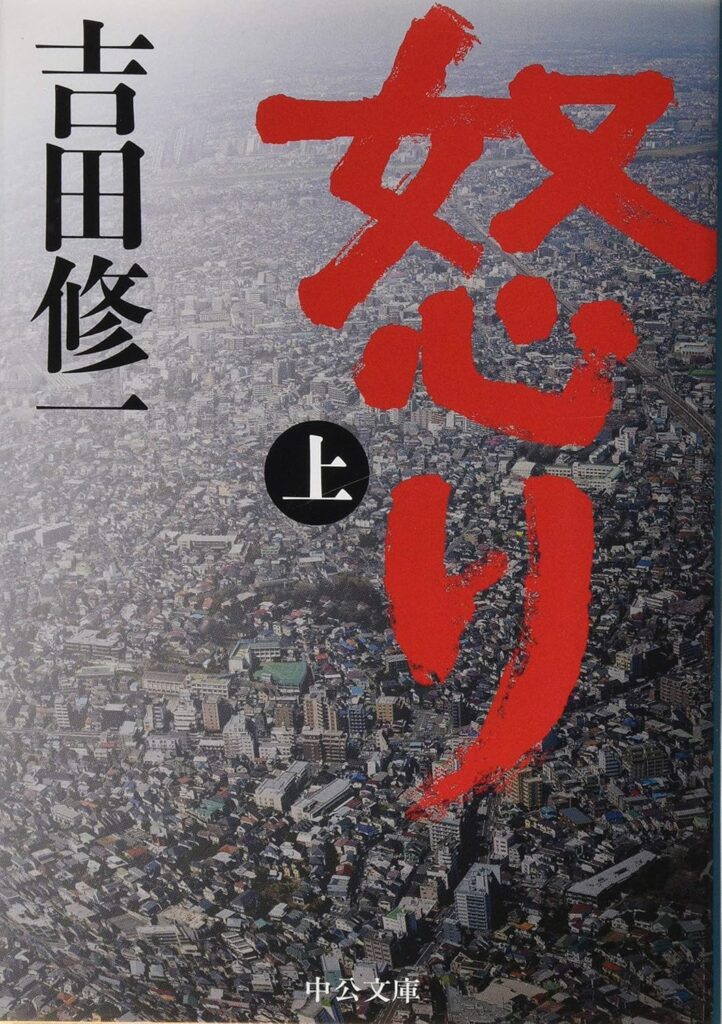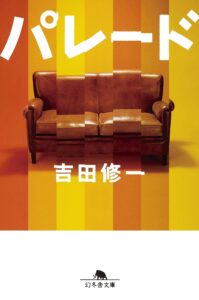 小説「パレード」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。吉田修一さんの手になるこの物語は、一見するとどこにでもありそうな若者たちの共同生活を描いているように見えます。しかし、その日常の薄皮一枚下には、現代社会の歪みや人間関係の希薄さ、そして目を背けたくなるような真実が潜んでいるのです。
小説「パレード」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。吉田修一さんの手になるこの物語は、一見するとどこにでもありそうな若者たちの共同生活を描いているように見えます。しかし、その日常の薄皮一枚下には、現代社会の歪みや人間関係の希薄さ、そして目を背けたくなるような真実が潜んでいるのです。
物語が進むにつれて、登場人物たちが抱える秘密や心の闇が少しずつ明らかになっていきます。彼らの行動や選択は、時に私たち読者の心をも揺さぶり、自分自身の内面と向き合うことを迫られるかもしれません。それは決して心地よい体験ばかりではないかもしれませんが、だからこそ「パレード」は多くの人々を引きつけてやまないのでしょう。
この記事では、そんな「パレード」の物語の核心に触れながら、その魅力と奥深さをじっくりと紐解いていきたいと思います。彼らの送る日々の詳細と、その裏側に隠された衝撃的な出来事、そしてそれらが織りなす人間ドラマについて、私の抱いた思いを交えつつお伝えしていきます。まだこの作品を読んでいない方、あるいは読んだけれどもっと深く理解したいと思っている方の、一つの道しるべとなれば幸いです。
読み進めるうちには、もしかしたらあなたが普段目を向けていない社会の側面や、人間心理の複雑さについて、改めて考えるきっかけを得るかもしれません。それでは、若者たちの共同生活が織りなす、きらびやかで、それでいてどこか物悲しい「パレード」の世界へご案内しましょう。
小説「パレード」のあらすじ
都心にほど近い、ありふれた2LDKのマンション。そこでは、年齢も職業もバラバラな男女4人が、奇妙なルームシェア生活を送っていました。伊原直輝は映画配給会社に勤める会社員。杉本良介は直輝の大学の後輩で、自由気ままな大学生活を謳歌しています。大垣内琴美は、恋人を追いかけて地方から上京してきたものの、今は無職で時間を持て余し気味。そして相馬未来は、雑貨店で働きながらイラストレーターになる夢を追いかけています。
彼らはそれぞれに干渉しすぎることなく、つかず離れずの共同生活を送っていました。表面上は穏やかな日々。しかし、近所では若い女性を狙った連続暴行事件が発生し、不穏な空気が漂い始めていました。住人たちはその事件について噂話を交わすものの、どこか他人事のように捉えている節がありました。良介は、隣室の住人の怪しげな様子や、近隣で起こる事件に漠然とした不安を感じてはいましたが、深く追求しようとはしません。
そんなある日、未来が酔って新宿二丁目から小窪サトルというミステリアスな少年を連れ帰ってきます。サトルは多くを語りませんが、夜の仕事をしていることを匂わせ、あっという間に彼らの日常に溶け込んでいきました。こうして、5人での新たな共同生活がスタートします。サトルの出現は、それまで保たれていた微妙なバランスを少しずつ崩していくことになるのです。
良介は、隣の部屋で何か違法なことが行われているのではないかと疑い、潜入を試みます。しかし、そこは売春宿ではなく、よく当たると評判の占い師の館でした。拍子抜けする良介でしたが、この出来事もまた、彼らの日常に潜む奇妙さの一片を垣間見せるものでした。
5人での生活が続く中、直輝の行動に少しずつ異変が現れ始めます。夜中にジョギングに出かけると言っては、長時間戻ってこない。そして、彼が不在の夜に限って、近隣の暴行事件が発生していることに、良介や琴美、未来、そしてサトルも薄々気づき始めます。しかし、誰もそのことに触れようとはしません。彼らは、直輝が犯人かもしれないという疑念を抱きながらも、見て見ぬふりを続けるのです。
物語の終盤、直輝が犯行に及ぶ瞬間が描かれます。そして、その現場をサトルが目撃。しかし、サトルは直輝を警察に通報するでもなく、マンションへ連れ帰ります。リビングでは、何も知らないかのように、あるいは全てを知った上で、良介、琴美、未来が談笑しているのでした。彼らの日常という名の「パレード」は、衝撃的な真実を内包したまま、これからも続いていくかのように幕を閉じます。
小説「パレード」の長文感想(ネタバレあり)
小説「パレード」を読み終えたとき、まず感じたのは、胸の内に広がる言いようのない空虚感と、現代社会が抱える病巣をまざまざと見せつけられたような衝撃でした。この物語は、単なる若者たちのルームシェア生活を描いたものではなく、その奥底に潜む人間の孤独や無関心、そして都市という空間が持つ匿名性の恐ろしさを、静かに、しかし鋭く抉り出してきます。ここからは、物語の核心に触れながら、私が抱いた思いを詳しく述べていきたいと思います。
まず、登場人物たちの人物像が非常に巧みに描かれていると感じました。主人公格の一人である杉本良介は、どこにでもいそうな普通の大学生です。彼は周囲で起こる出来事に対して、ある程度の関心は示すものの、決して深入りしようとはしません。その態度は、現代の若者たちが持つある種のドライさや、面倒事への回避傾向を象徴しているかのようです。彼が抱く漠然とした不安や、事件の真相に薄々気づきながらも行動を起こさない姿は、読者にとって共感と苛立ちを同時にもたらすのではないでしょうか。
大垣内琴美は、恋愛に依存し、現実から逃避しているかのような女性です。彼女の行動原理は常に「彼氏」であり、その存在に自分の価値を見出そうとしているように見えます。彼女の脆さや空虚感は、都会で生きる孤独な魂の叫びのようにも聞こえてきます。彼女がサトルと一時的に心を通わせる場面がありますが、それもまた、彼女の寂しさを埋めるための一時的な繋がりに過ぎなかったのかもしれません。
相馬未来は、自立した強い女性のように見えますが、その内面にはやはり埋めがたい孤独や不安を抱えています。イラストレーターになるという夢を追いながらも、どこか満たされない日々。彼女がサトルを部屋に連れ込んだのは、酔った勢いだけではなく、日常に変化を求める無意識の渇望があったからではないでしょうか。彼女もまた、直輝の異変に気づきながら、共同生活の「調和」を乱すことを恐れて口を閉ざしてしまいます。
そして、物語の中で最も異質な存在感を放つのが小窪サトルです。彼は年齢不詳で、多くを語らず、どこか達観したような目で周囲を観察しています。彼の存在は、他の4人の住人たちの隠された本音や、彼らの関係性の歪さを浮き彫りにする触媒のような役割を果たしているように思えます。彼が直輝の犯行を目撃しながらも、それを告発せず、ただ静かに受け入れる態度は、この物語の持つ不気味さを一層際立たせています。サトルは、この「パレード」のような日常の虚飾を見抜き、その一部として存在することを選んだのでしょうか。
物語の核心を担う伊原直輝。彼は一見すると、ごく普通の会社員です。しかし、その内面には深い闇を抱え、夜な夜な通り魔殺人を繰り返します。彼の犯行動機は明確には語られませんが、日常のストレスや疎外感、あるいは存在証明への歪んだ欲求などが複雑に絡み合っているのかもしれません。彼が犯行後も何食わぬ顔で日常に戻り、ルームメイトたちと接する姿は、人間の心の不可解さと恐ろしさを感じさせます。
この物語の最も衝撃的な点は、直輝の犯行に気づきながらも、他の4人の同居人が「見て見ぬふり」を続けることです。彼らは、自分たちの平穏な日常が壊れることを恐れ、真実から目を背けます。そこには、個人の問題への不介入、責任回避、そして何よりも「無関心」という現代社会に蔓延する病理が見て取れます。彼らの態度は、私たち読者自身の心にも問いを投げかけてきます。「自分ならどうするだろうか?」と。
「パレード」というタイトルも非常に示唆的です。作中には具体的なパレードの描写はありません。しかし、彼らのルームシェア生活そのものが、虚飾に満ちた「パレード」のようにも見えます。表面上は楽しく、和気あいあいと振る舞いながらも、それぞれが仮面をつけ、本音を隠し、お互いの深い部分には踏み込まない。それはまるで、華やかでありながら実態のない行列のようです。また、通り魔事件の犯人である直輝が、夜の街を徘徊する姿も、ある種の倒錯した「パレード」と解釈できるかもしれません。
吉田修一さんの筆致は、淡々としていながらも、登場人物たちの心理描写が非常に巧みです。直接的な感情表現を抑えることで、かえって読者の想像力を刺激し、物語の奥深さを増しています。行間から滲み出てくる登場人物たちの孤独や不安、そして社会の歪みが、静かに、しかし確実に読者の心に染み込んできます。
この物語は、私たちに多くの問いを投げかけます。現代社会における人間関係の希薄さとは何か。都市で生きるということの孤独とは。私たちは、すぐ隣で起こっているかもしれない「悪」に対して、どこまで無関心でいられるのか。そして、見て見ぬふりをすることの罪とは何か。
結末は、ある意味で非常に救いのないものです。直輝の犯罪は露見せず、4人の同居人たちは彼との共同生活を続けることを選択します。それは、彼らが「日常」という名の欺瞞を受け入れ、その一部として生き続けることを意味しているかのようです。この結末は、読者に重たい余韻を残し、物語が終わった後も長く考えさせられることになるでしょう。
しかし、この物語は単に絶望を描いているだけではないのかもしれません。彼らの姿を通して、私たちは現代社会が抱える問題を直視し、それについて考えるきっかけを与えられます。それは、私たちがより良い社会や人間関係を築いていく上で、避けては通れない問いなのかもしれません。
「パレード」は、人間の心の闇や社会の病理を描きながらも、どこか美しさを感じさせる不思議な魅力を持った作品です。それは、吉田修一さんならではの繊細な感性と、鋭い観察眼によって生み出されたものでしょう。この物語を読む体験は、決して楽しいものではないかもしれませんが、人間の本質や社会のあり方について深く考えさせられる、貴重な時間となるはずです。
彼らの「パレード」は、私たちの日常と地続きなのかもしれない。そう考えると、背筋が凍るような思いがします。しかし、その現実から目を背けずに、私たち一人ひとりが何ができるのかを考えることこそが、この物語が私たちに突きつけている課題なのかもしれません。
この作品が投げかける問いに、明確な答えを出すことは難しいでしょう。しかし、その問いと向き合い続けること自体に、意味があるのだと私は思います。そして、それこそが文学の持つ力の一つなのではないでしょうか。
まとめ
吉田修一さんの小説「パレード」は、現代社会に生きる私たちの心に深く、そして静かに爪痕を残す作品と言えるでしょう。若者たちのルームシェアという一見ありふれた設定の中に、人間の孤独、無関心、そして都市生活の匿名性といったテーマが巧みに織り込まれています。物語を読み進めるうちに、登場人物たちの心の闇や、彼らの選択が浮き彫りになり、読んでいるこちらまで息苦しさを覚えるほどです。
この物語の大きな特徴は、登場人物たちが抱える問題の根深さと、それに対する彼らの「見て見ぬふり」という態度です。近所で起こる連続暴行事件の犯人が同居人かもしれないと薄々感づきながらも、誰もその事実を突き止めようとせず、自分たちの日常を守ろうとする姿は、現代社会における人間関係の希薄さや事なかれ主義を象徴しているかのようです。
「パレード」というタイトルが示すように、彼らの生活はどこか虚飾に満ちた、表面的なものに感じられます。華やかで楽しげに見える日常の裏側には、深刻な問題が隠蔽され、誰もがそれに気づかないふりをしている。この構造は、私たち自身の日常や社会全体にも通じる部分があるのではないでしょうか。読み終えた後には、ずしりとした重い問いが心に残ります。
この小説は、単に物語を楽しむだけでなく、私たち自身が生きる社会や、他者との関わり方について深く考えさせられるきっかけを与えてくれます。心地よい読書体験とは言えないかもしれませんが、だからこそ記憶に残り、折に触れて思い返してしまうような力を持った作品です。

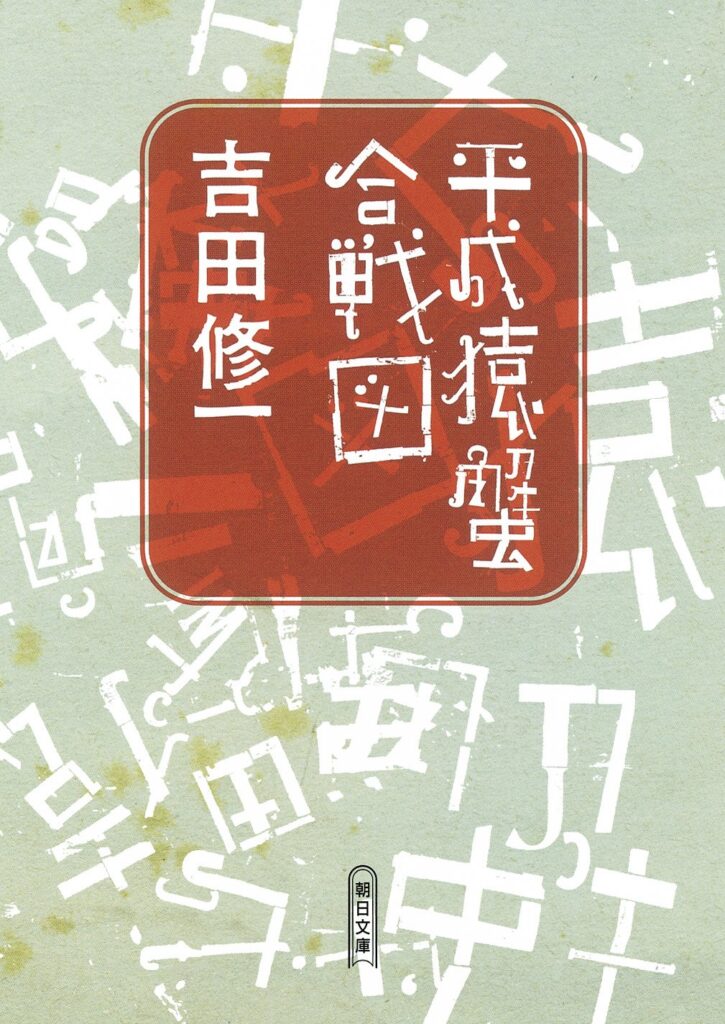
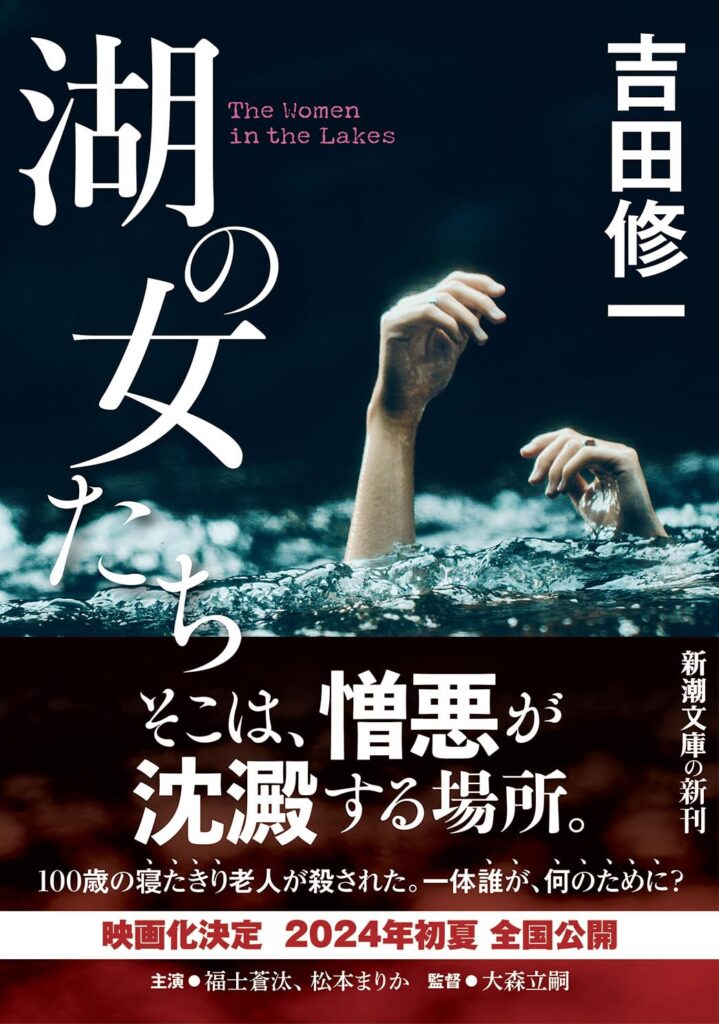
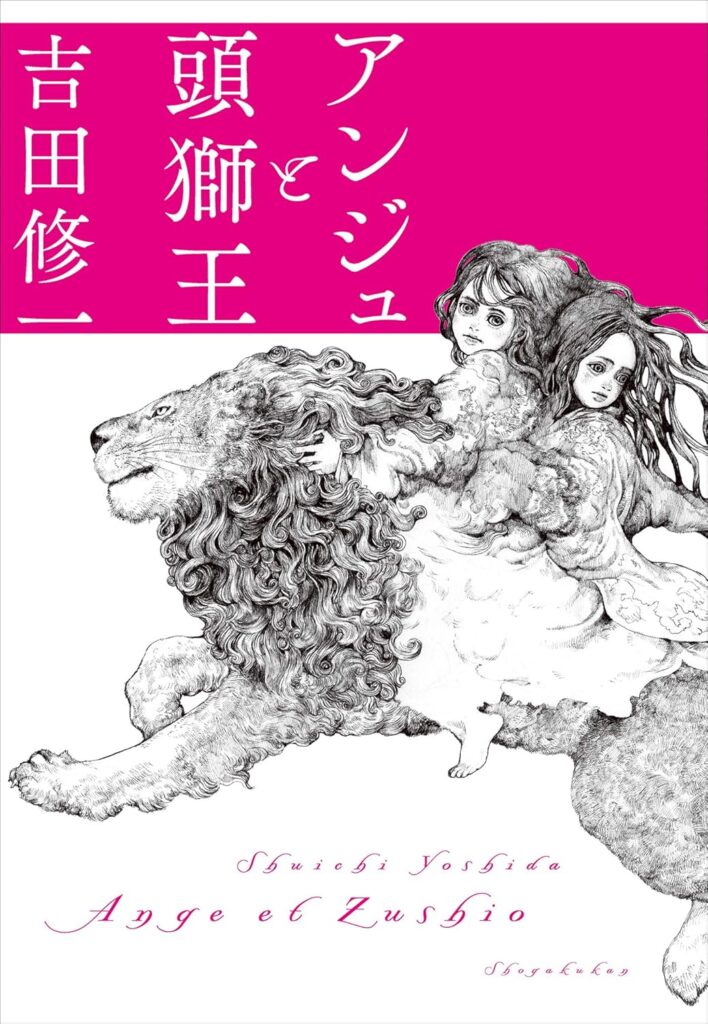
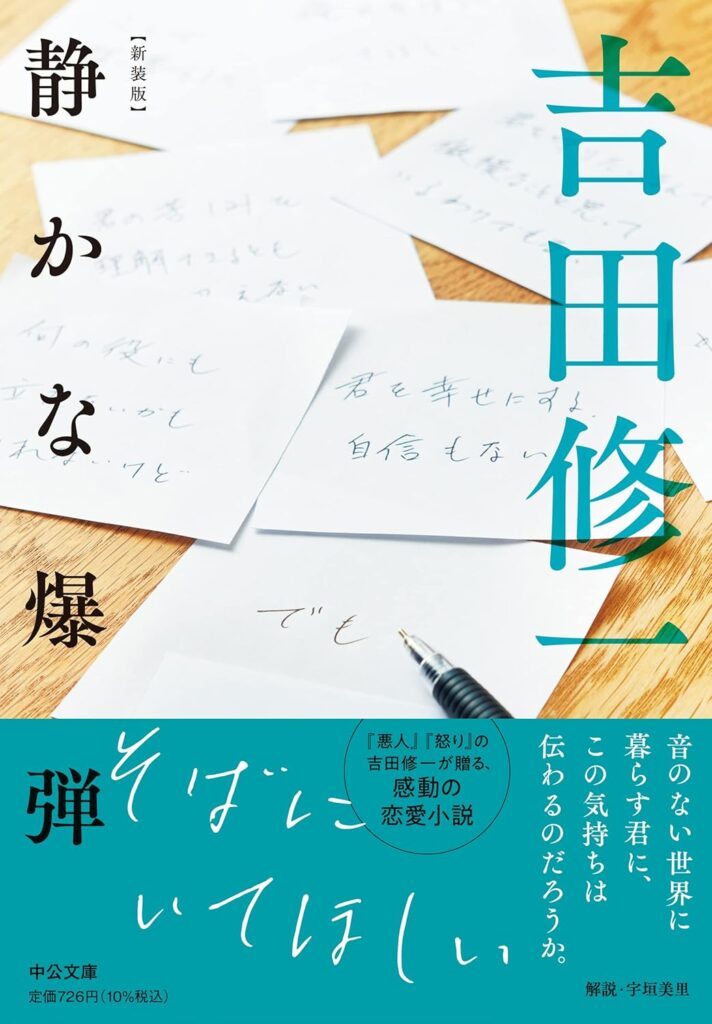
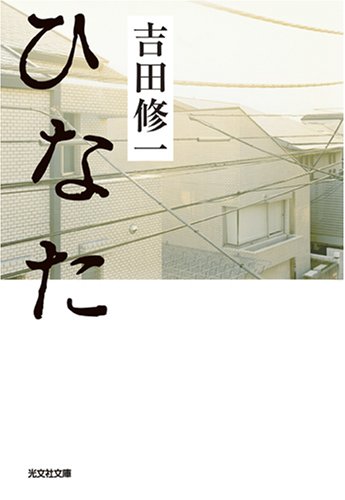
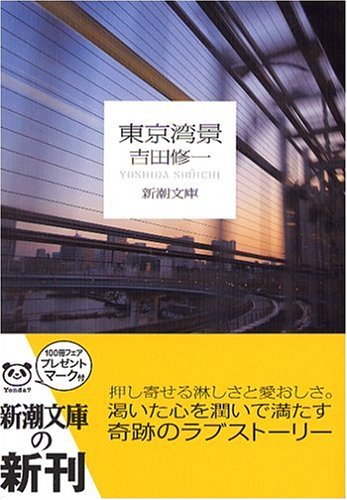
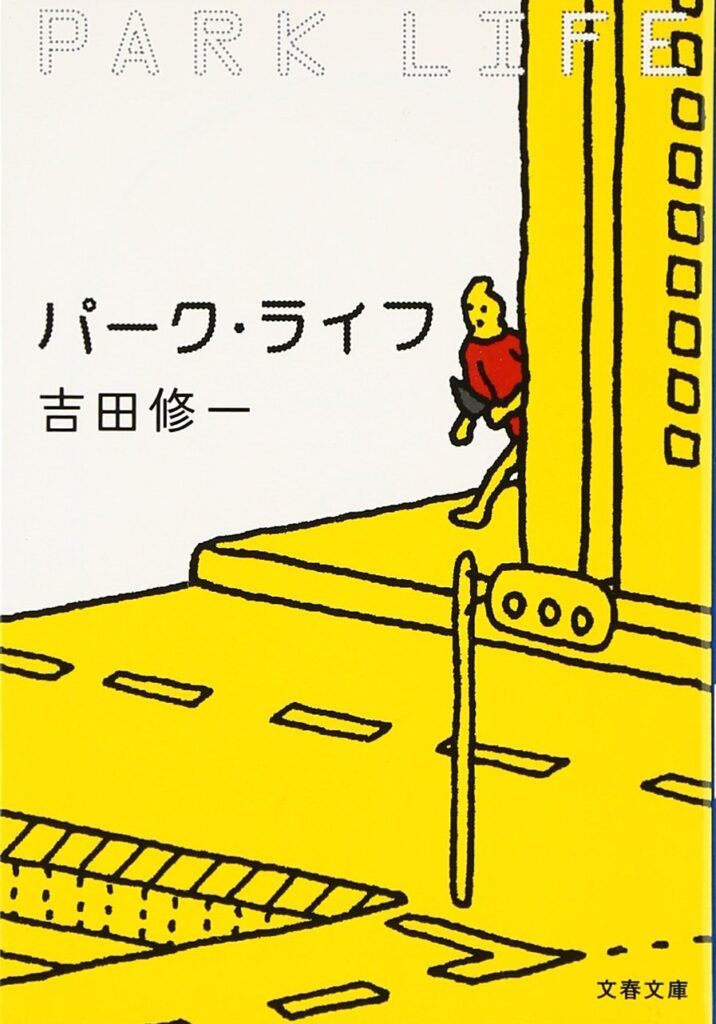
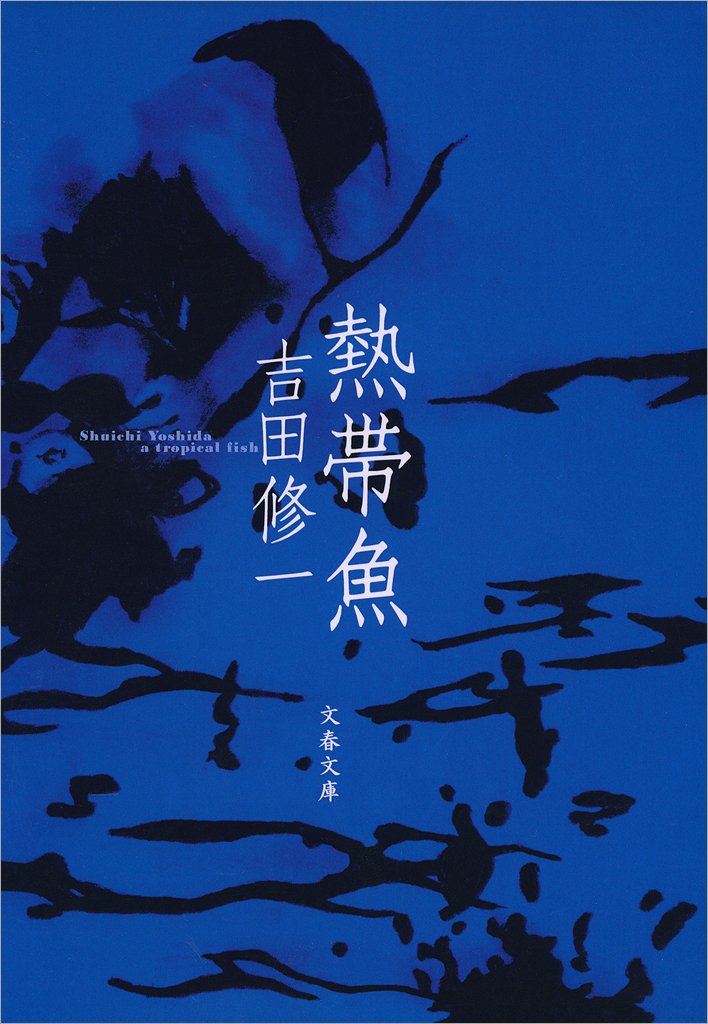
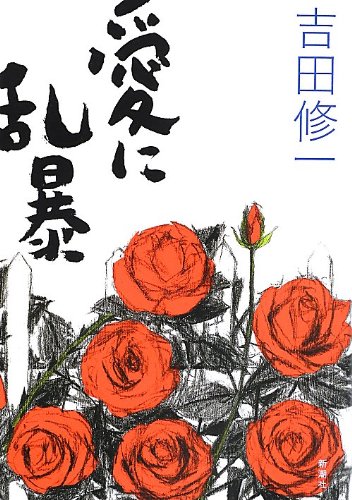
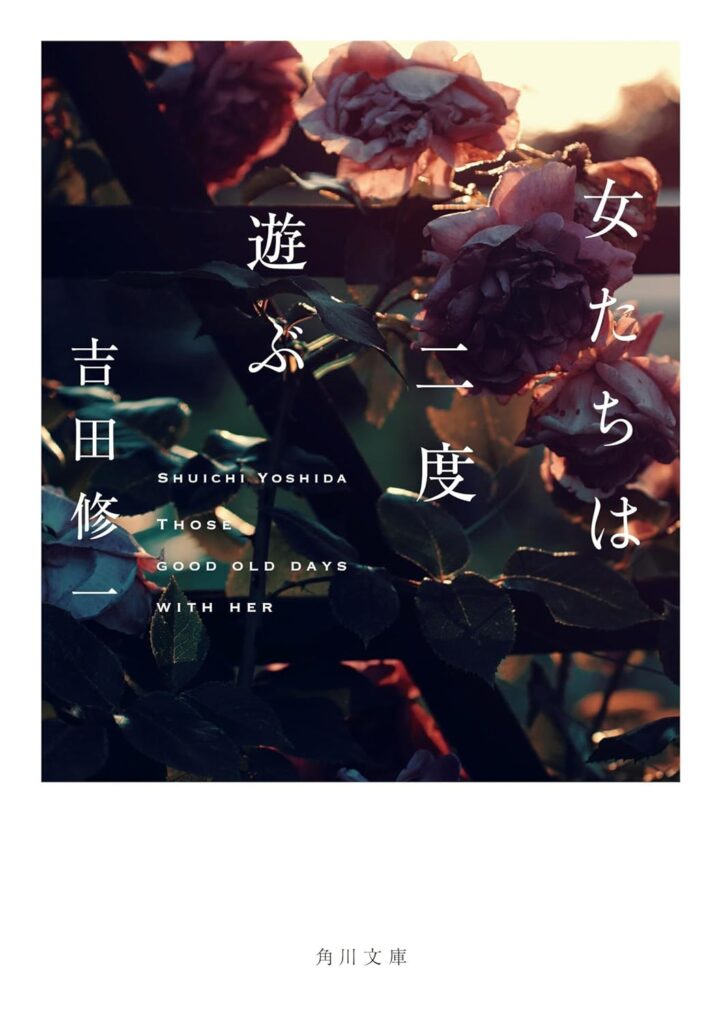
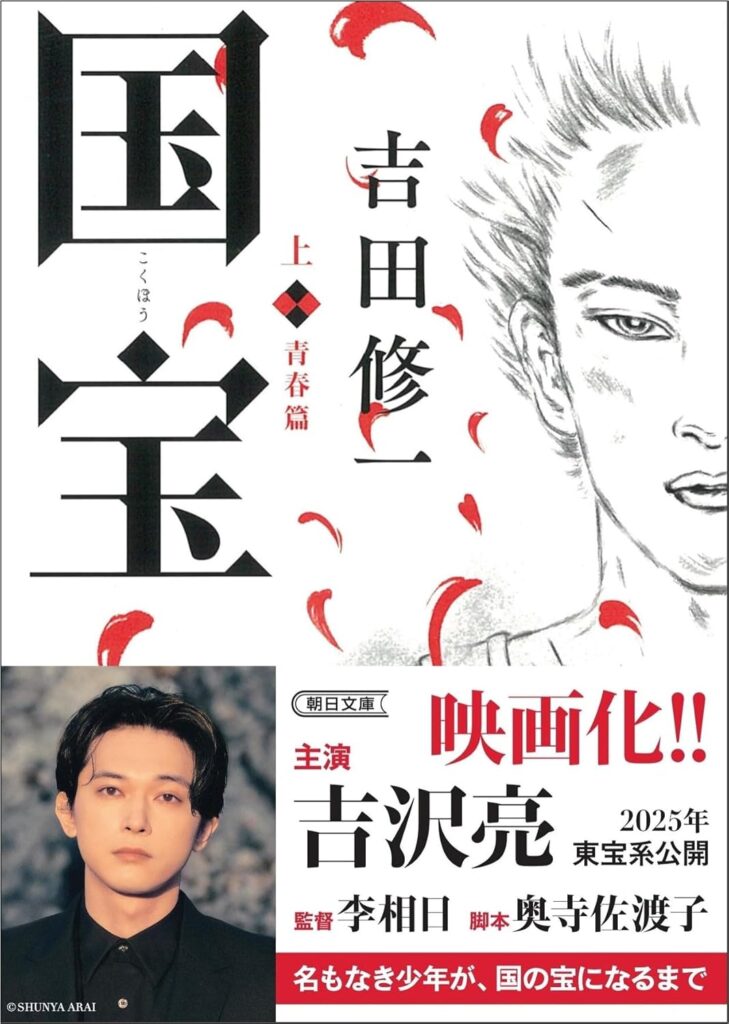
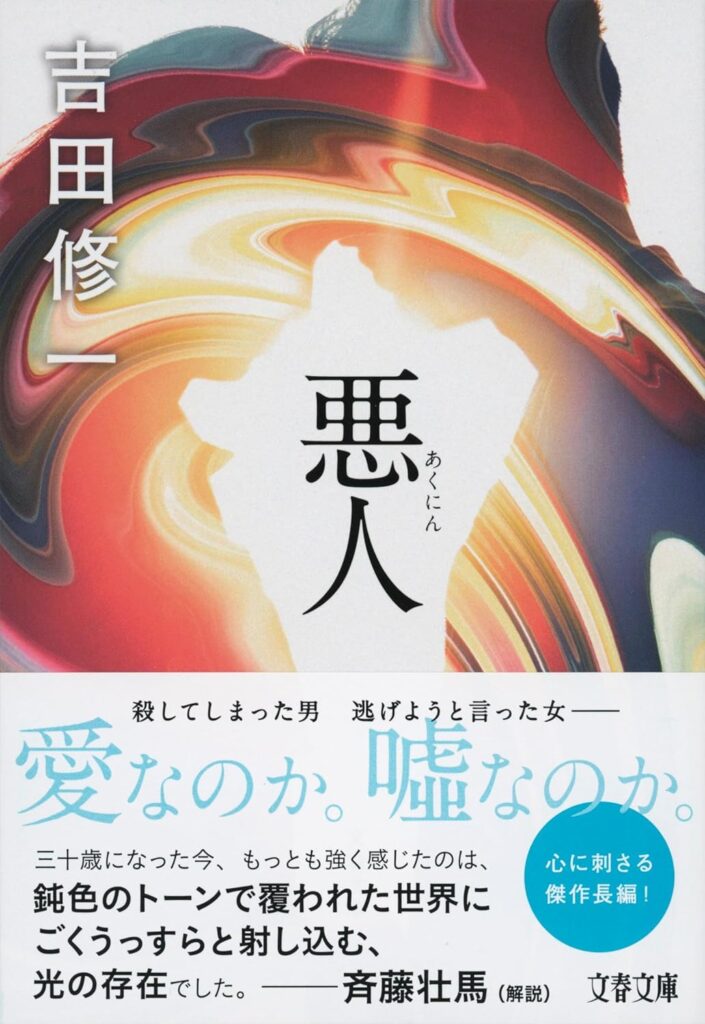
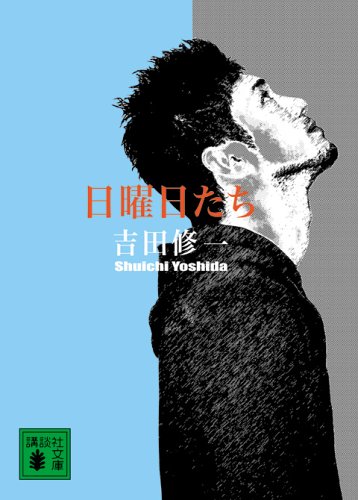
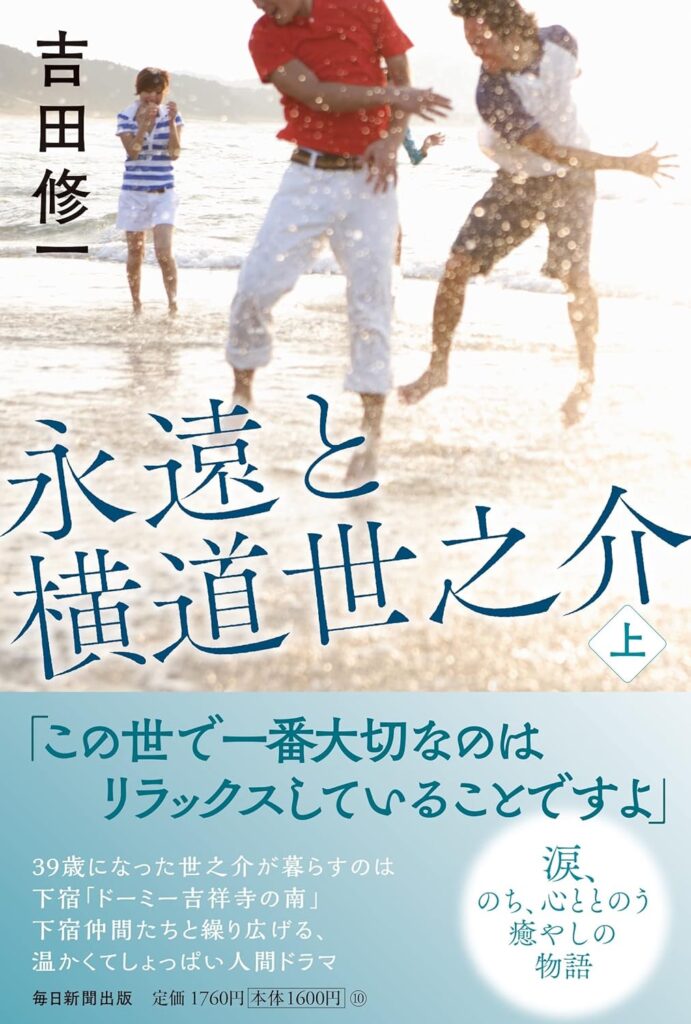
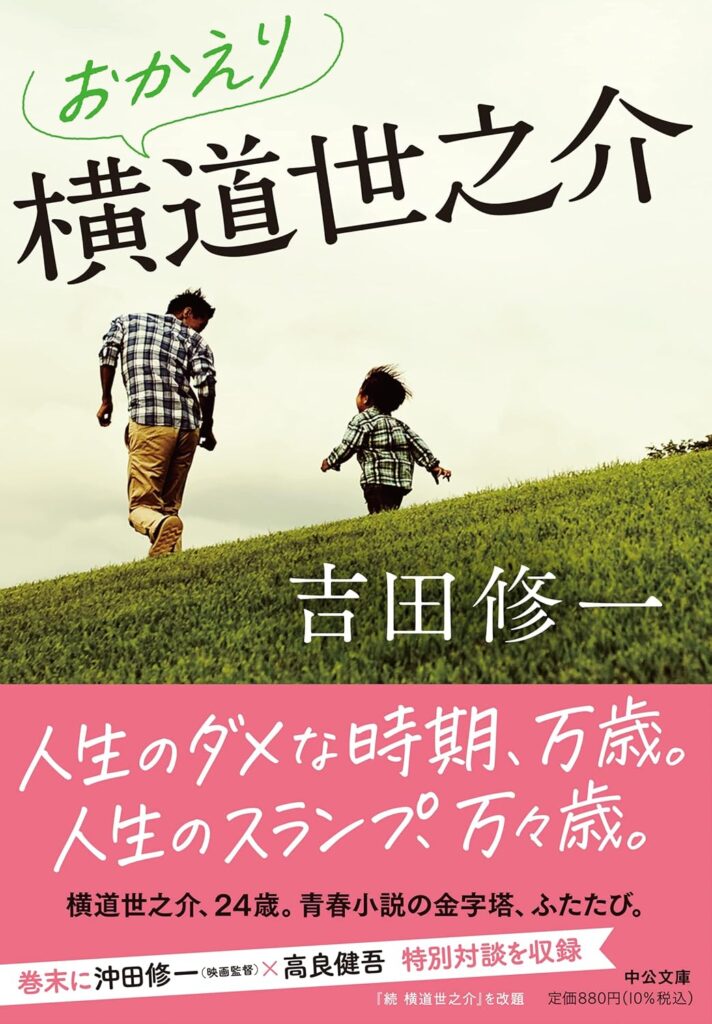
-728x1024.jpg)