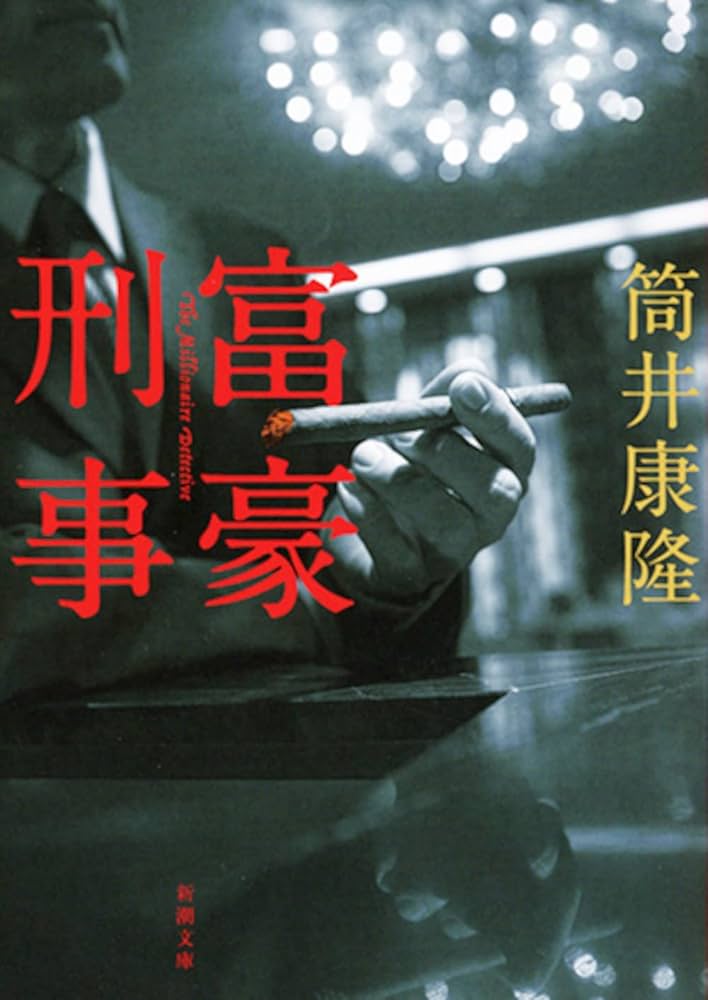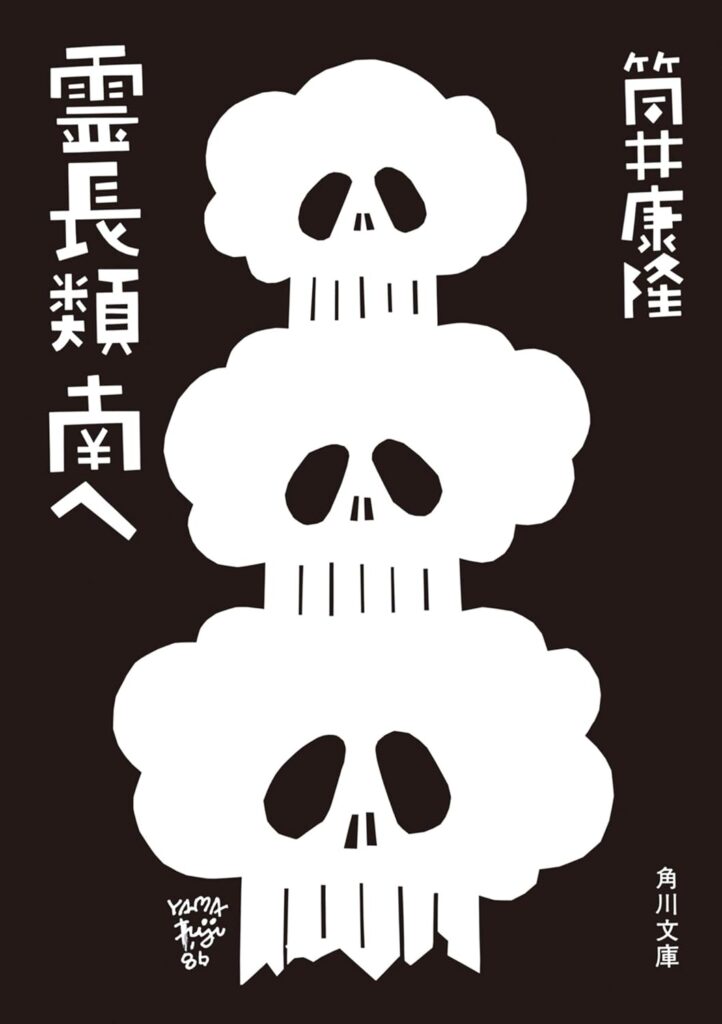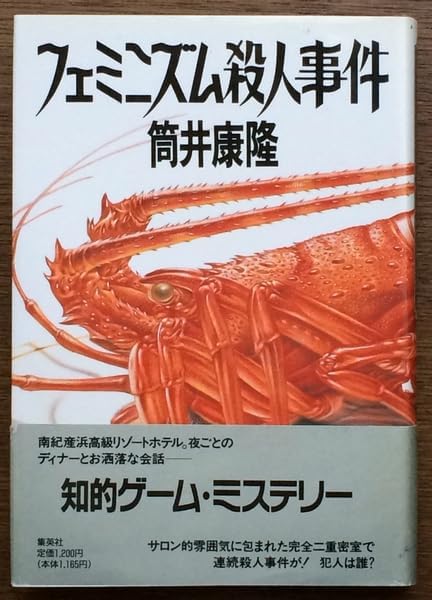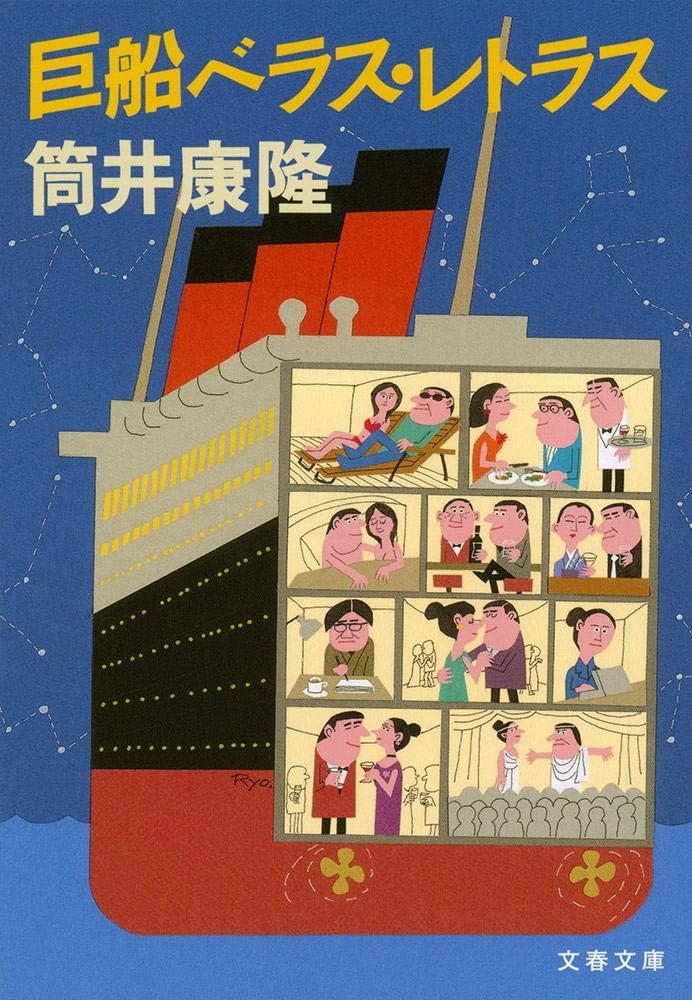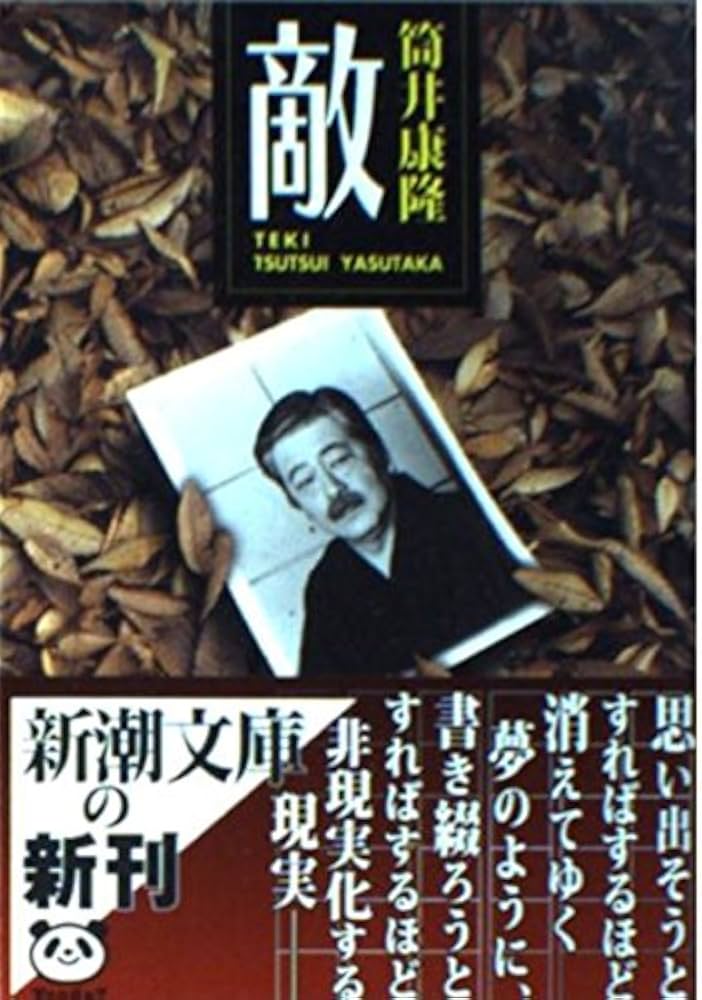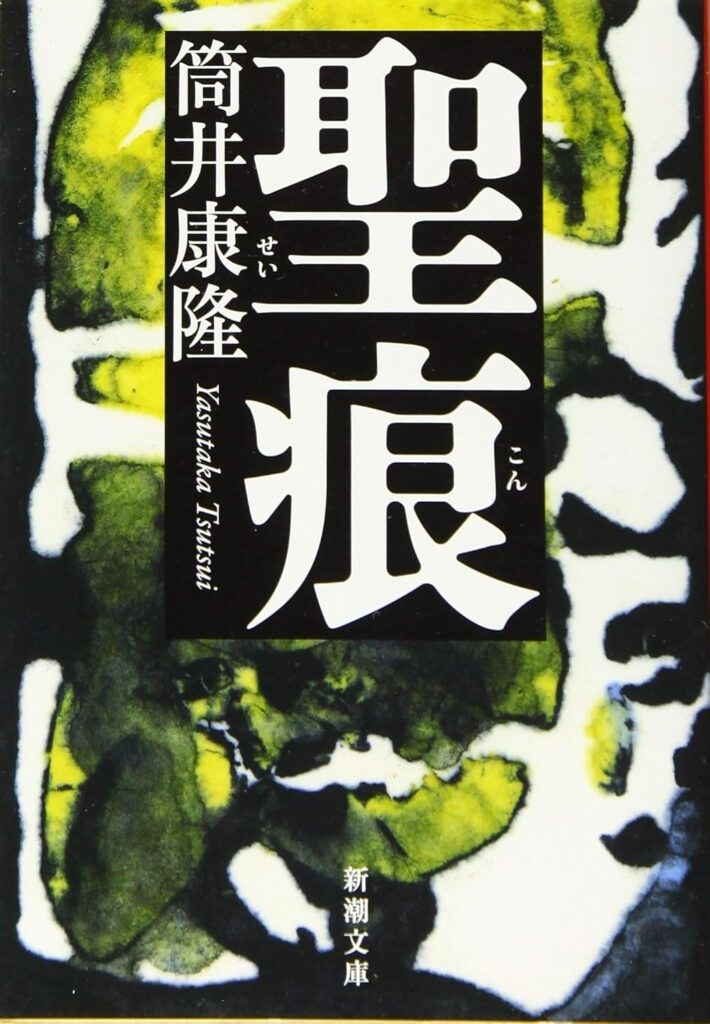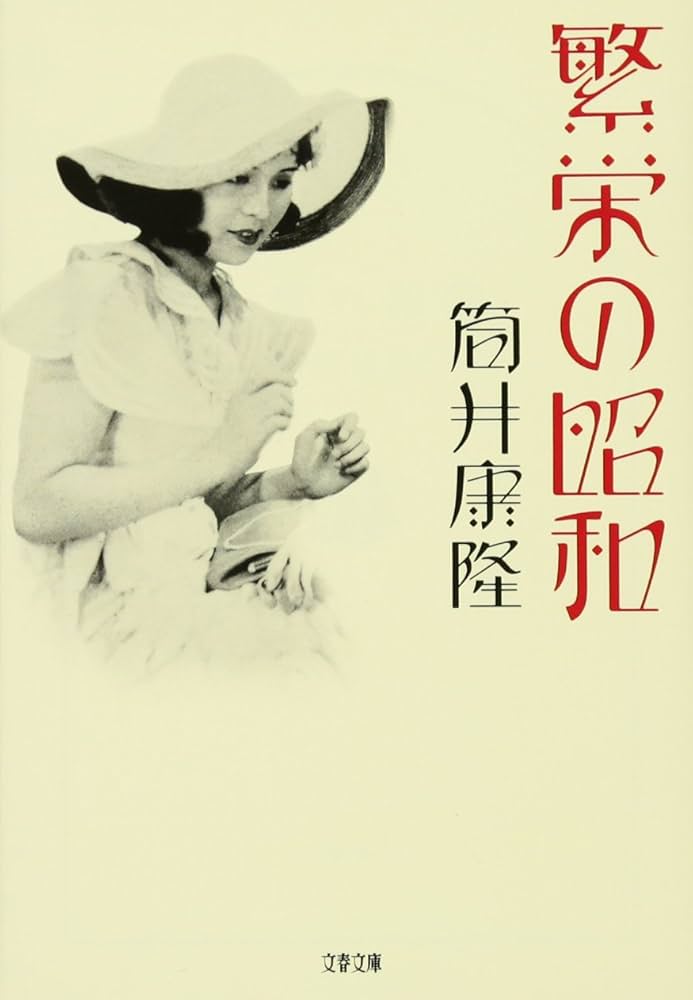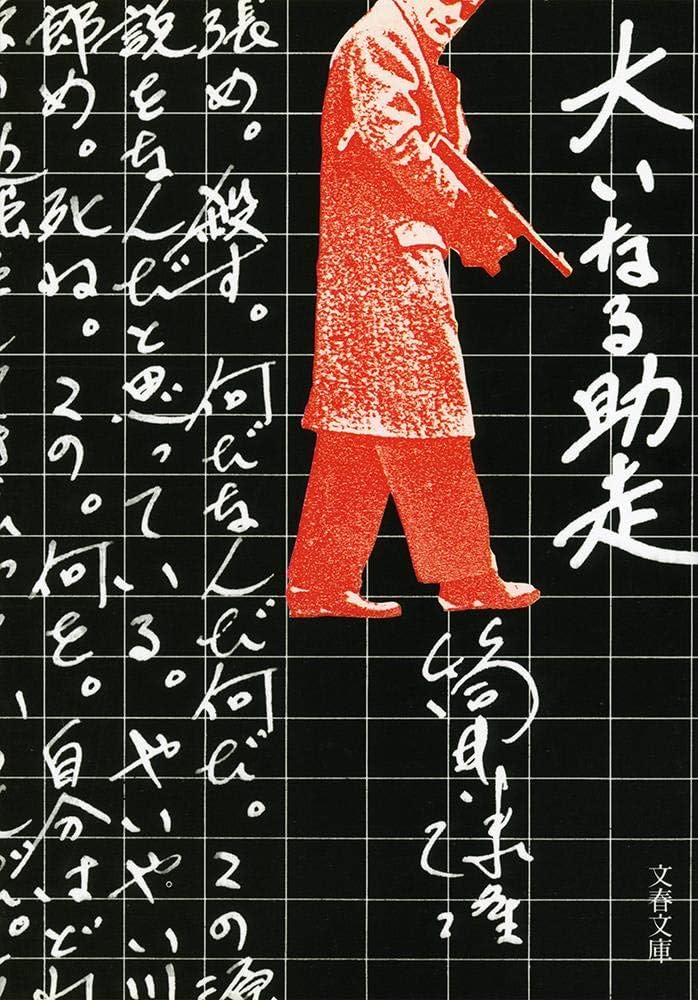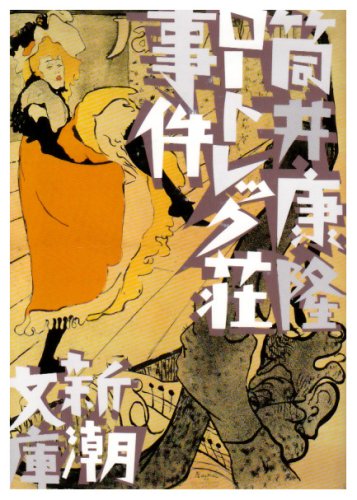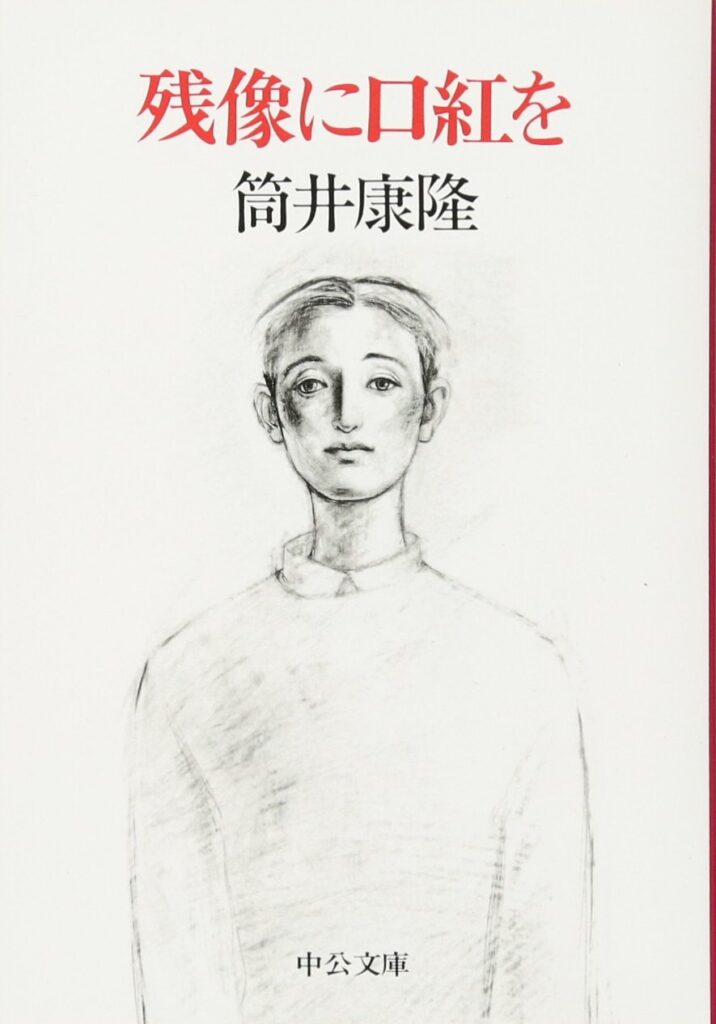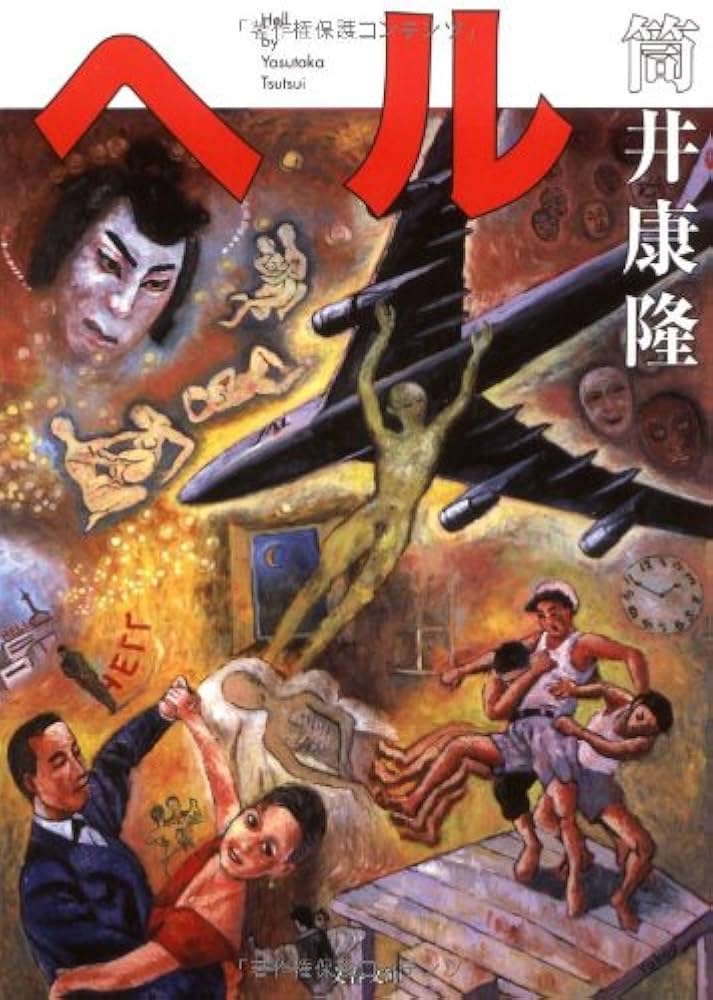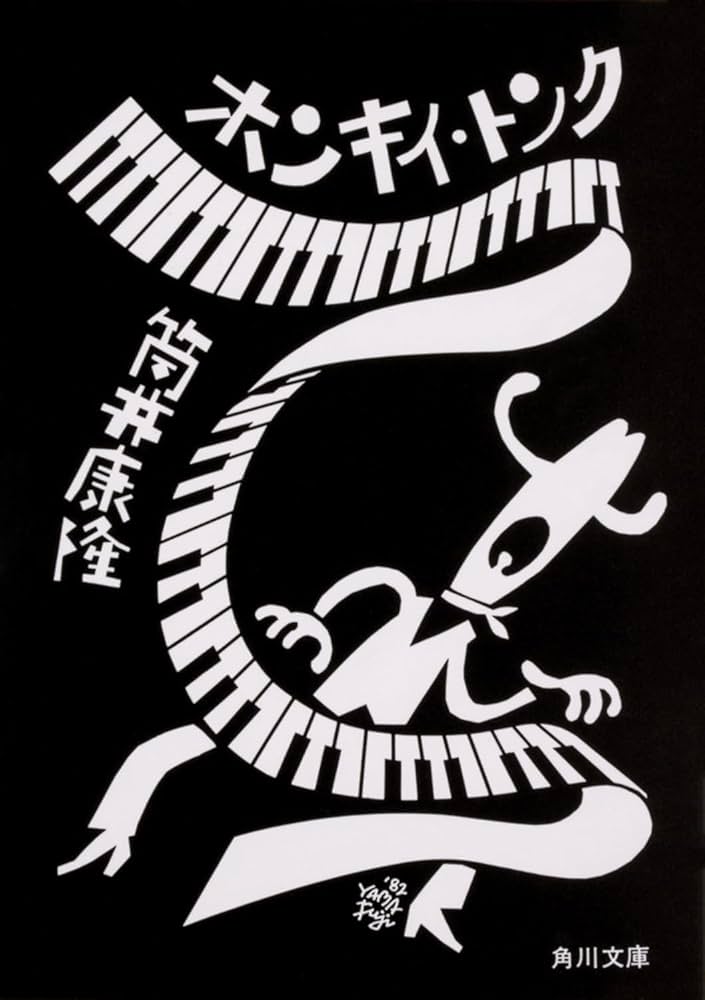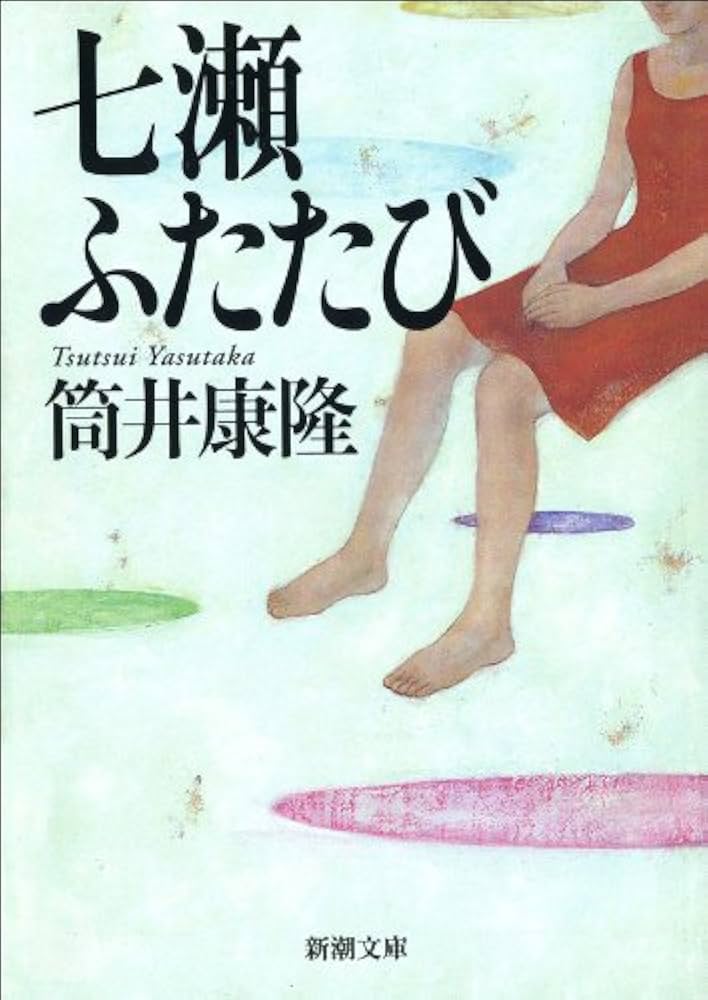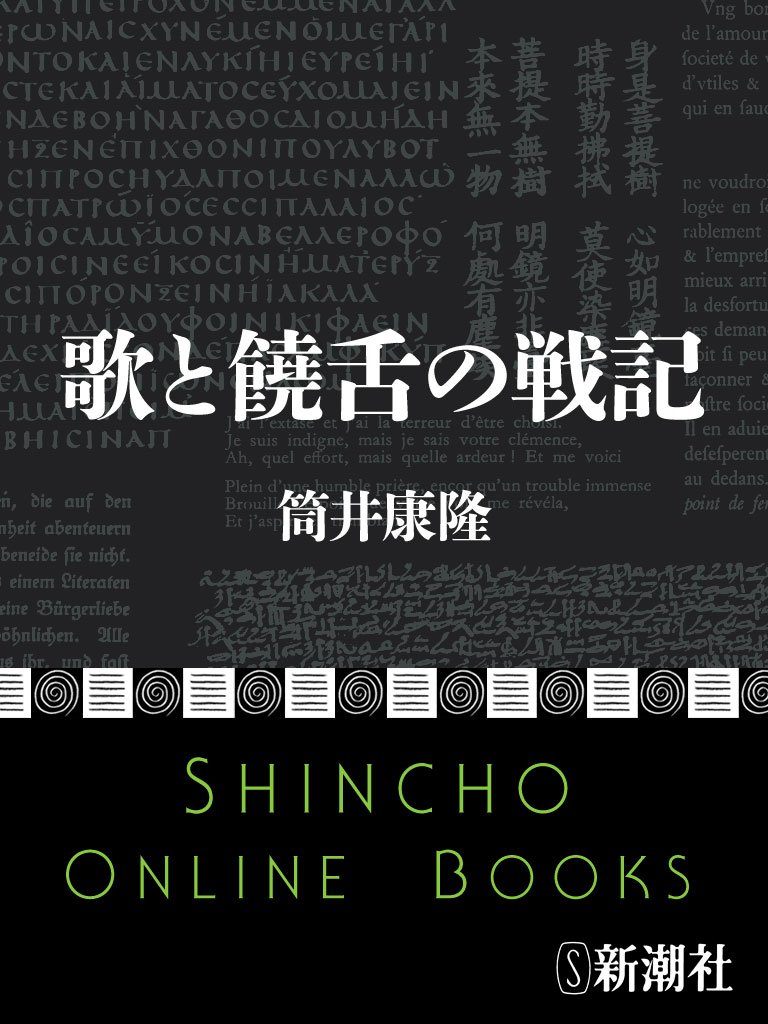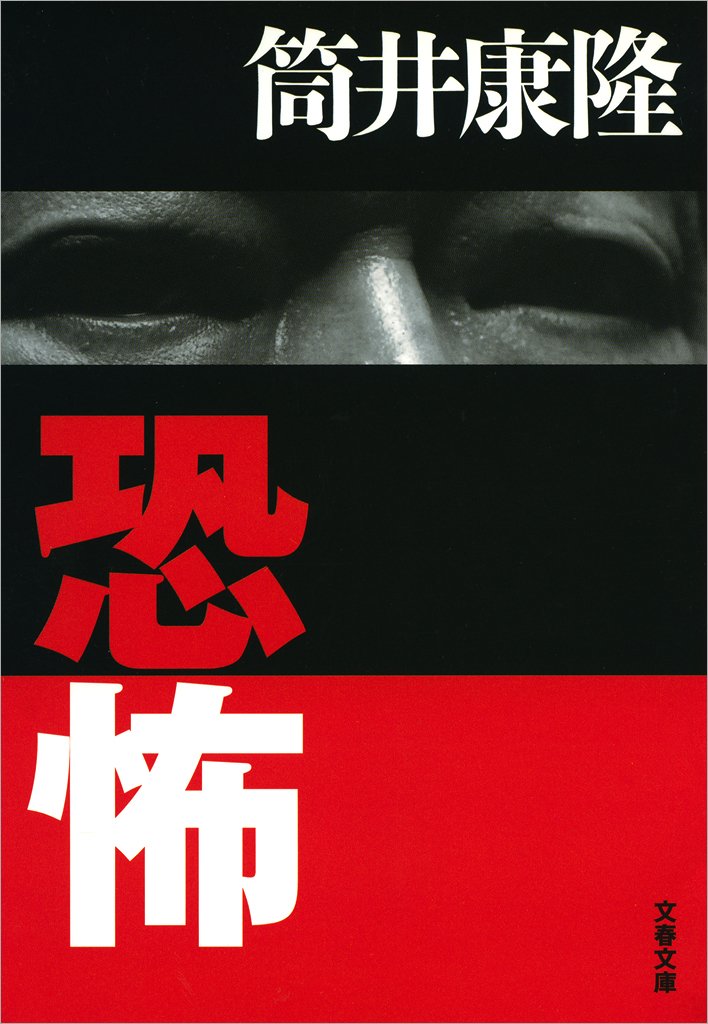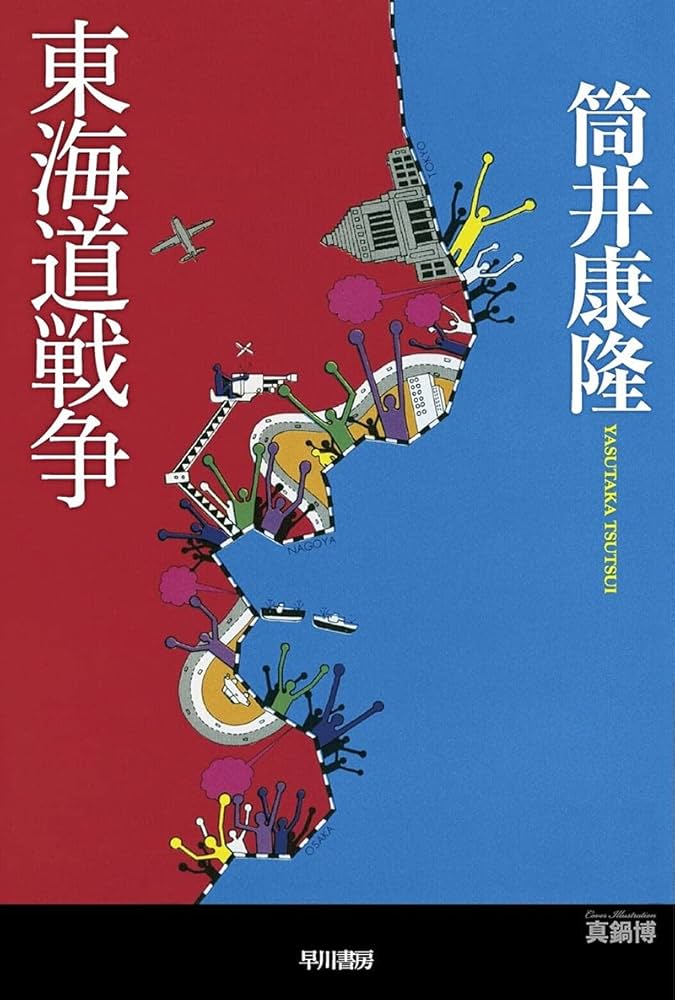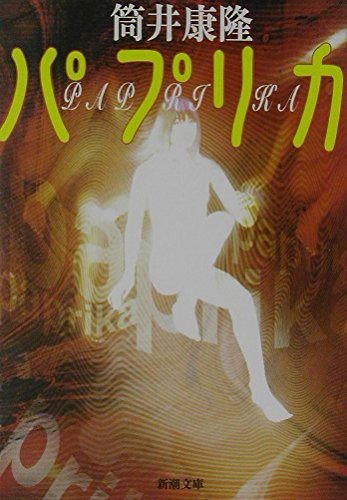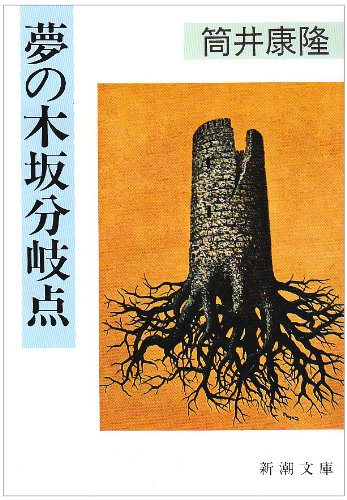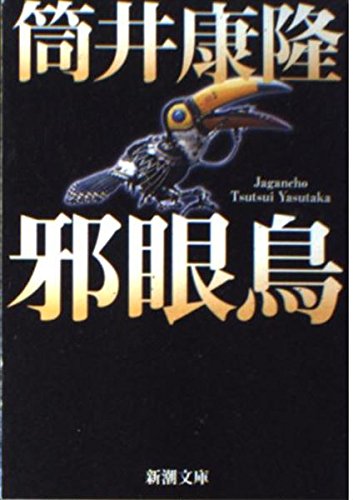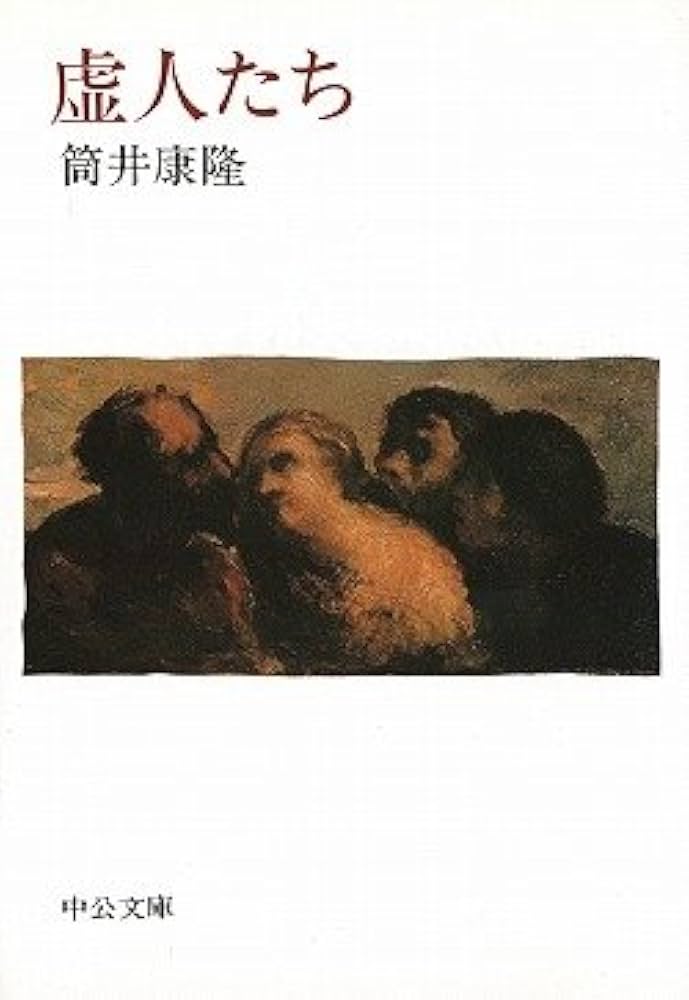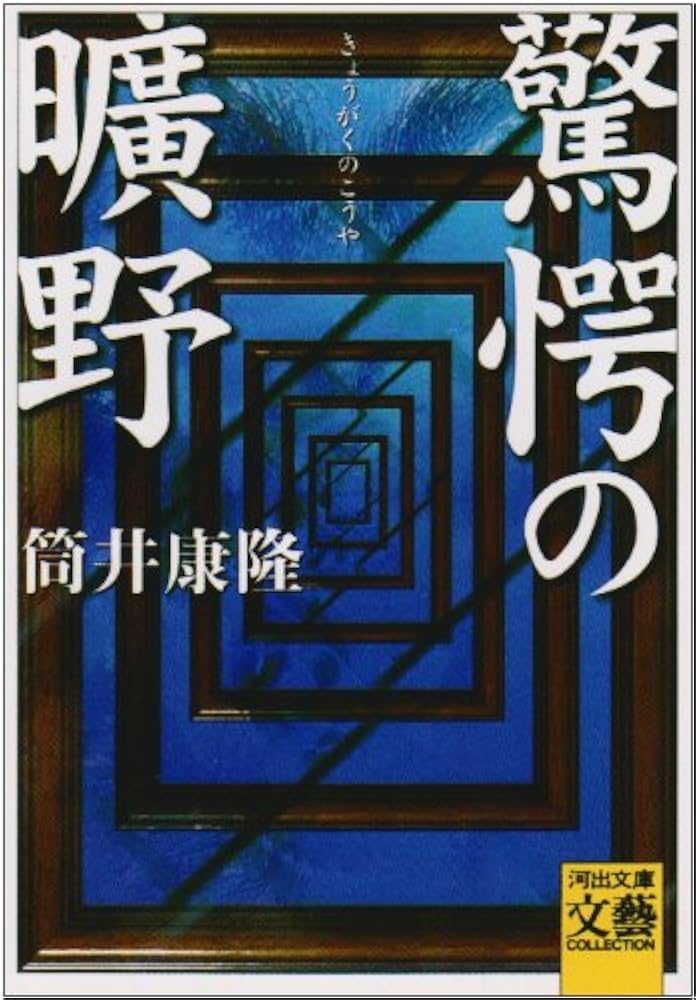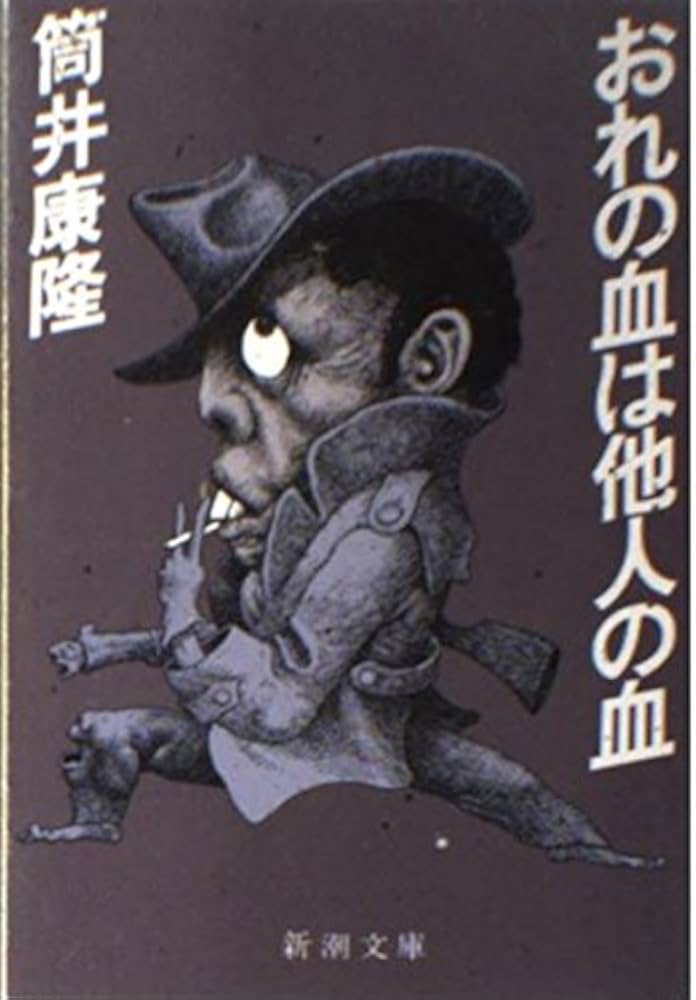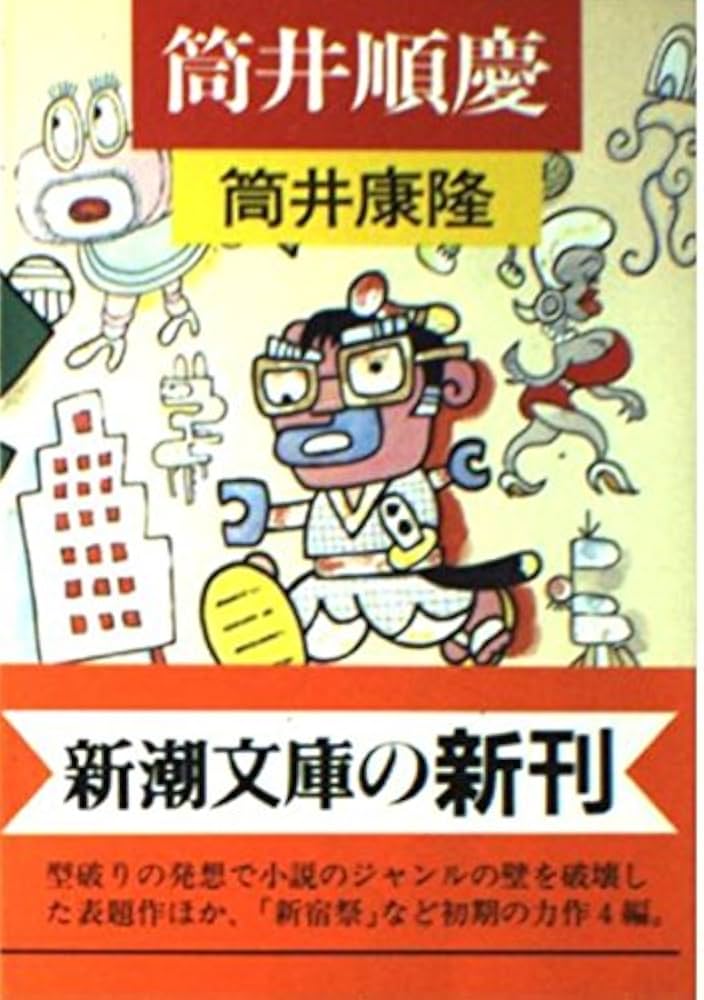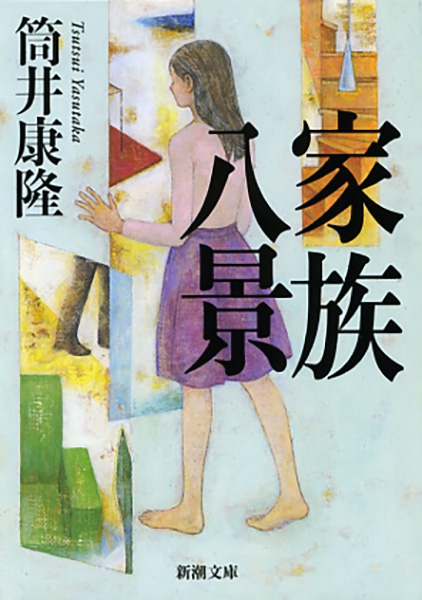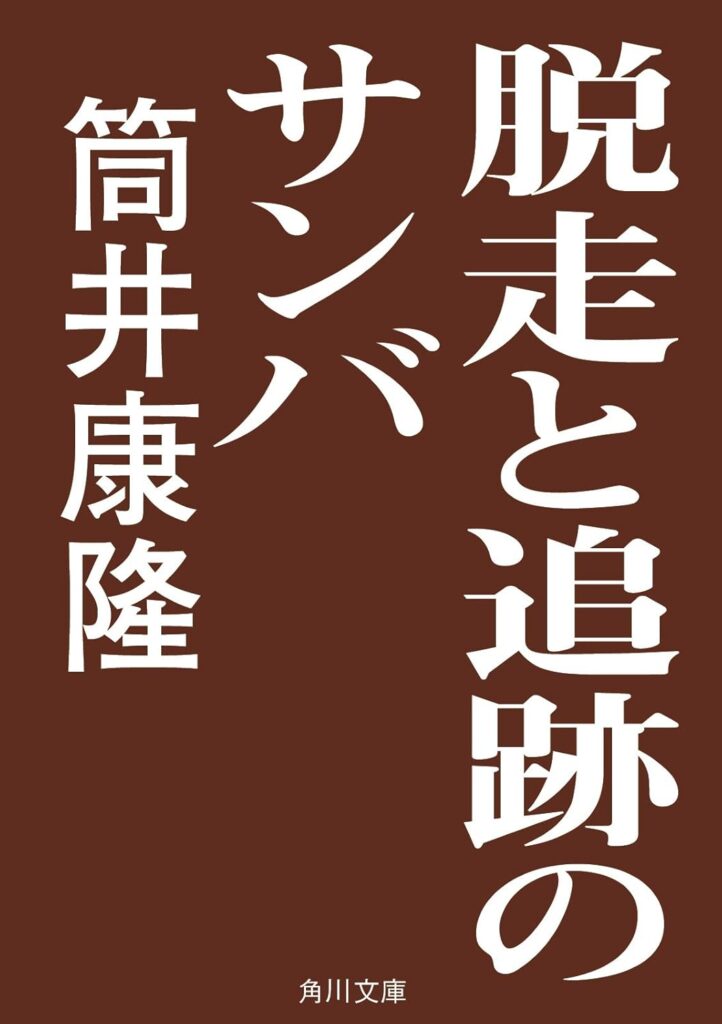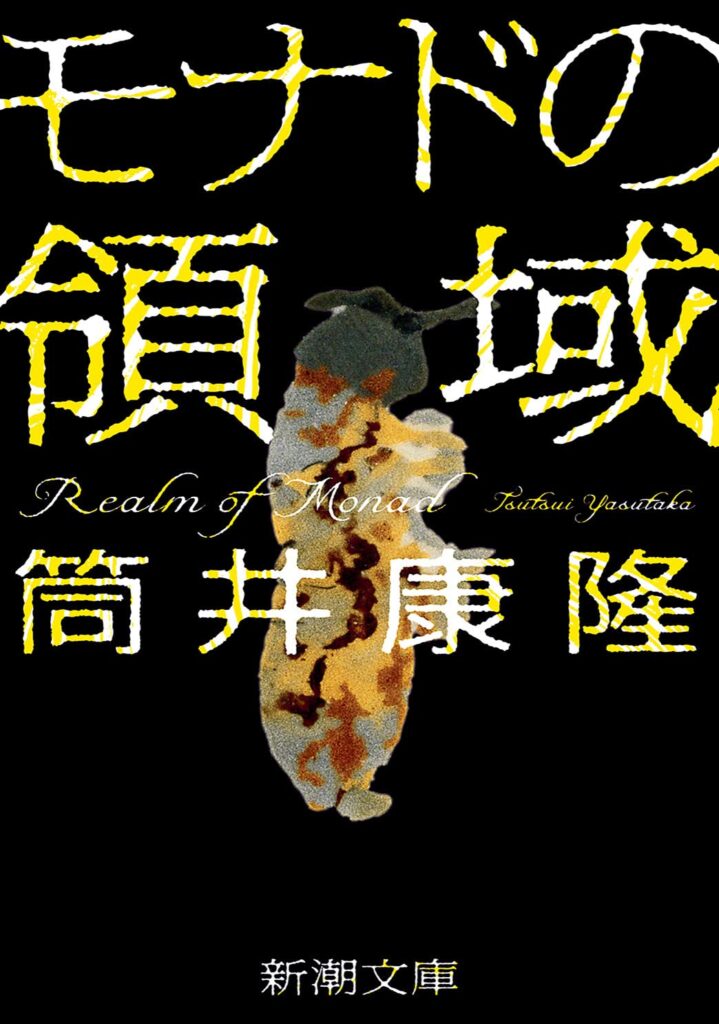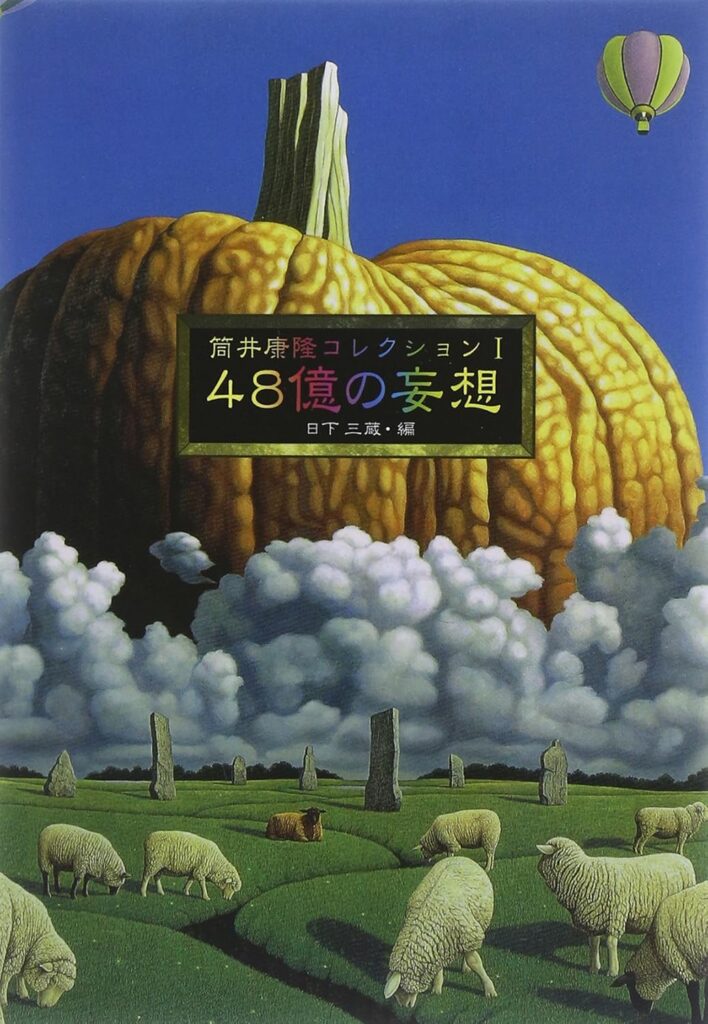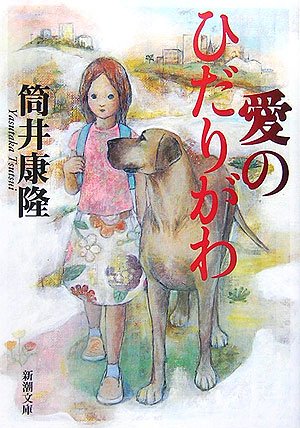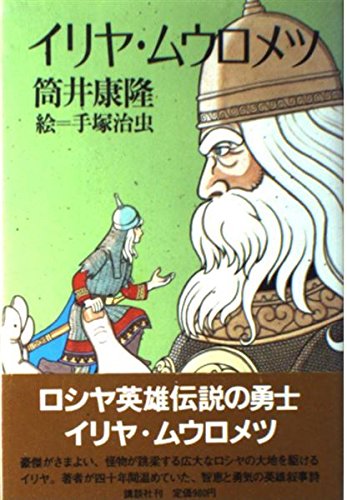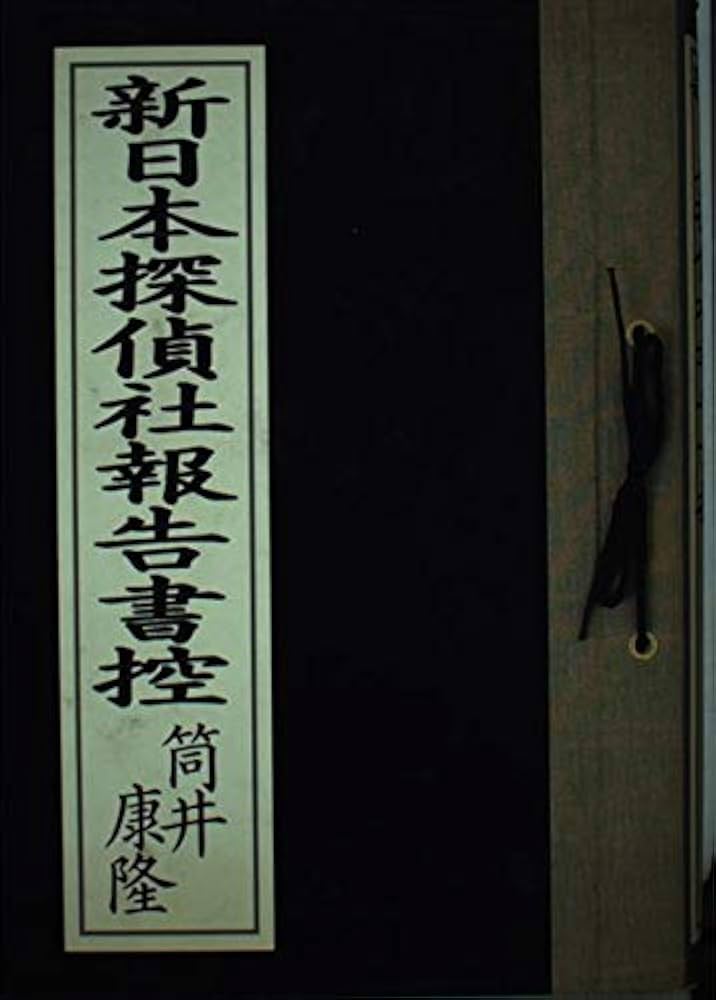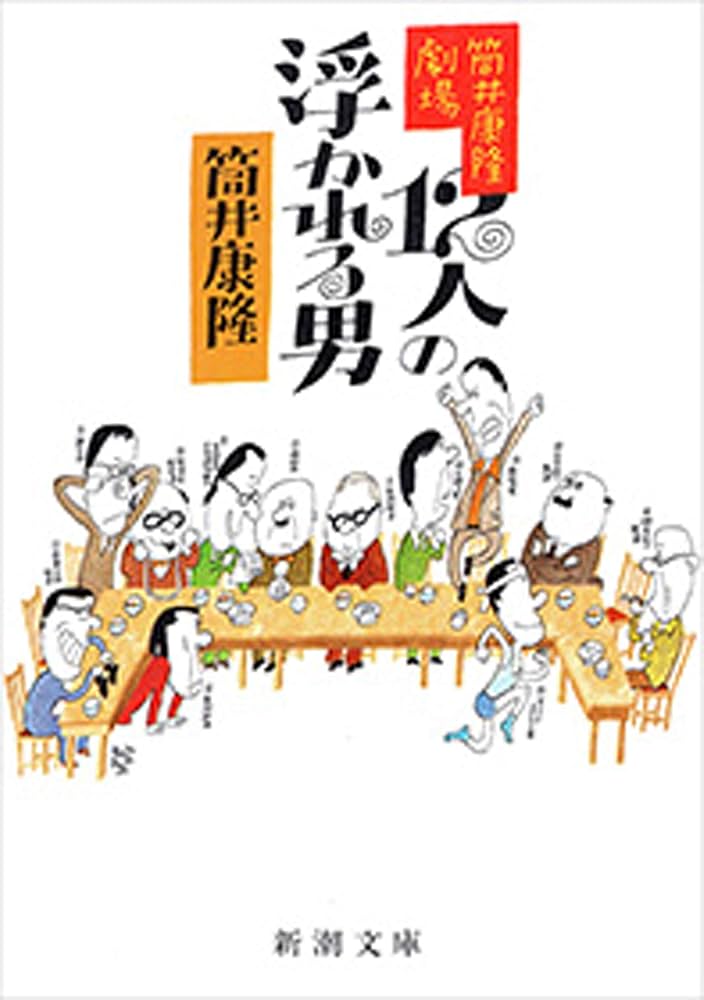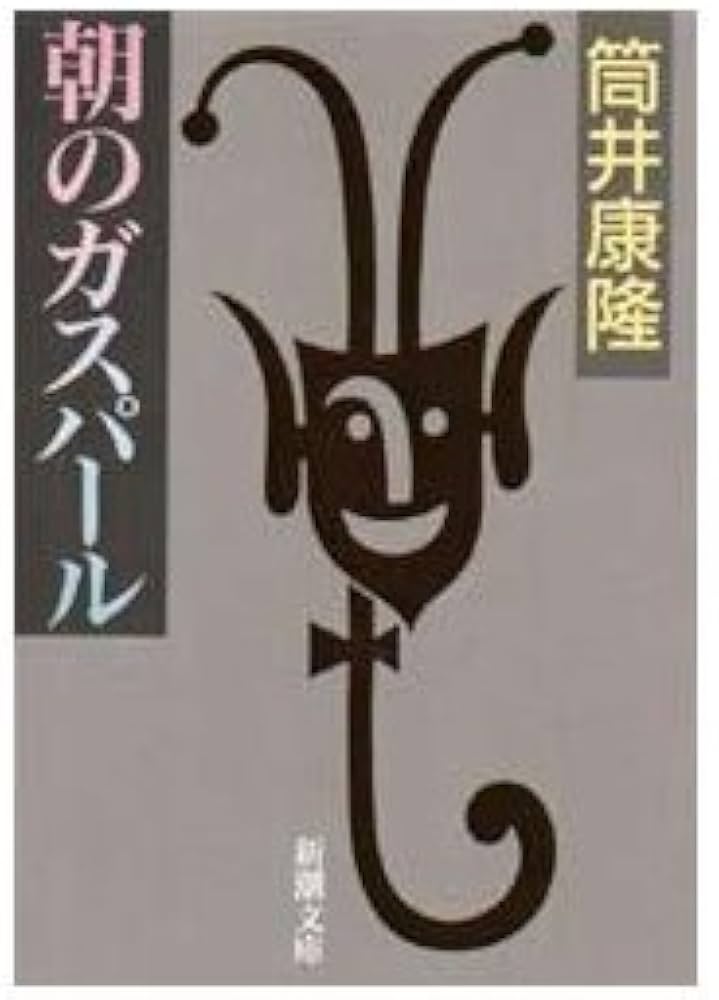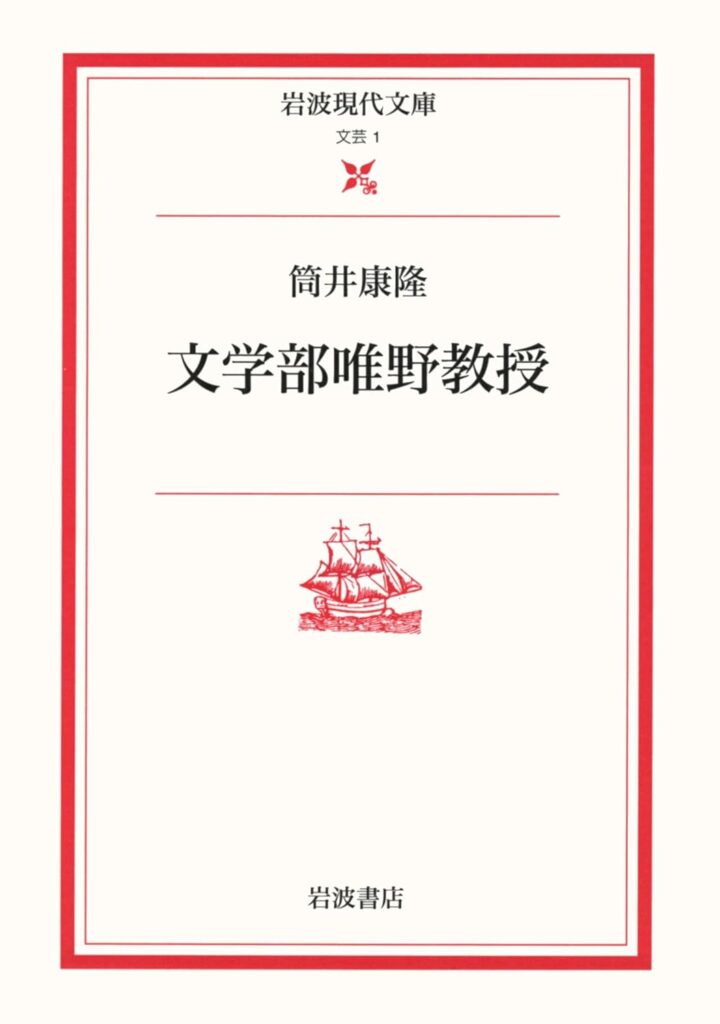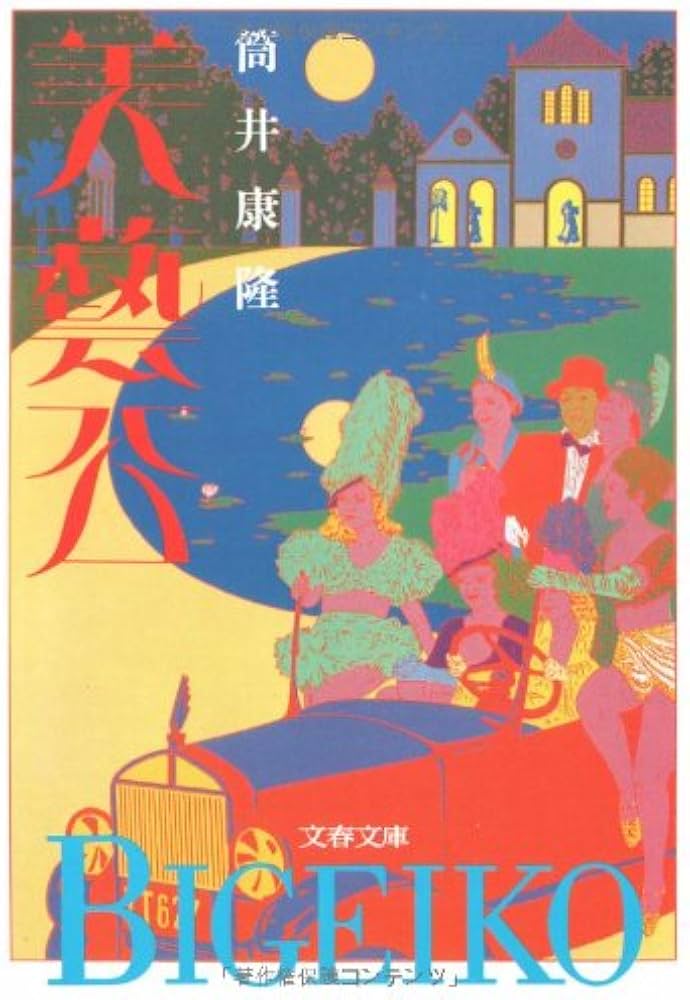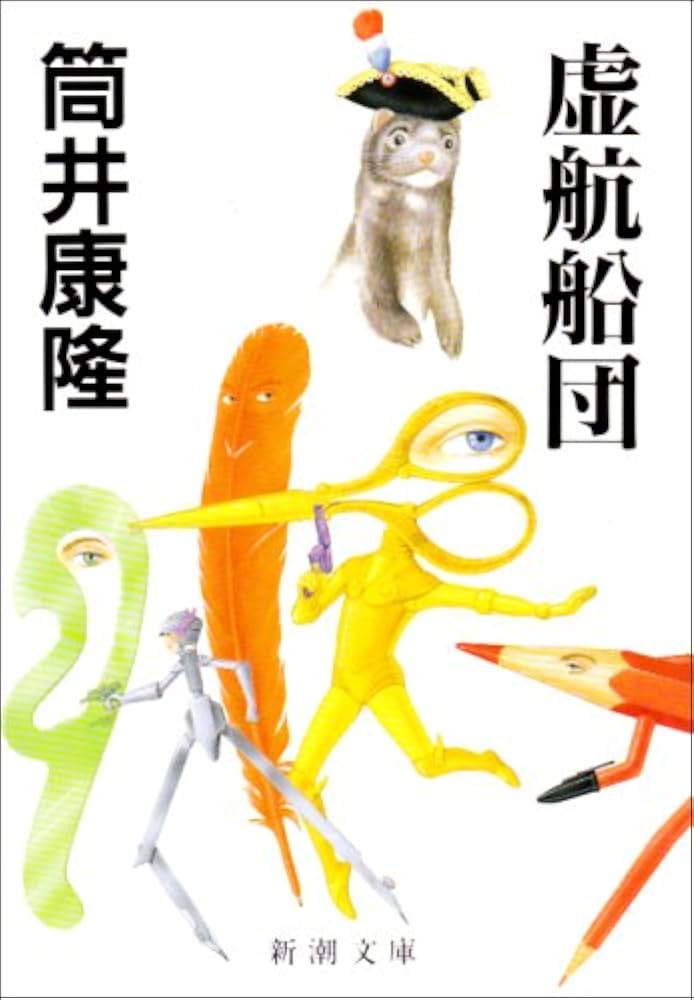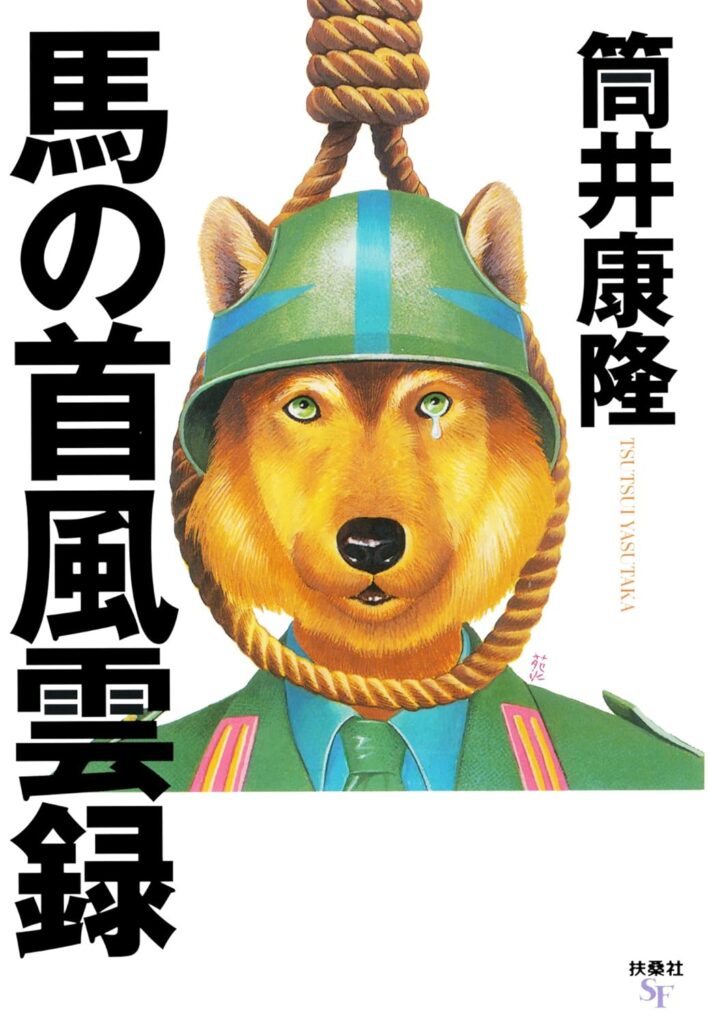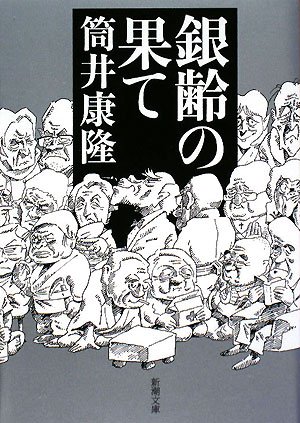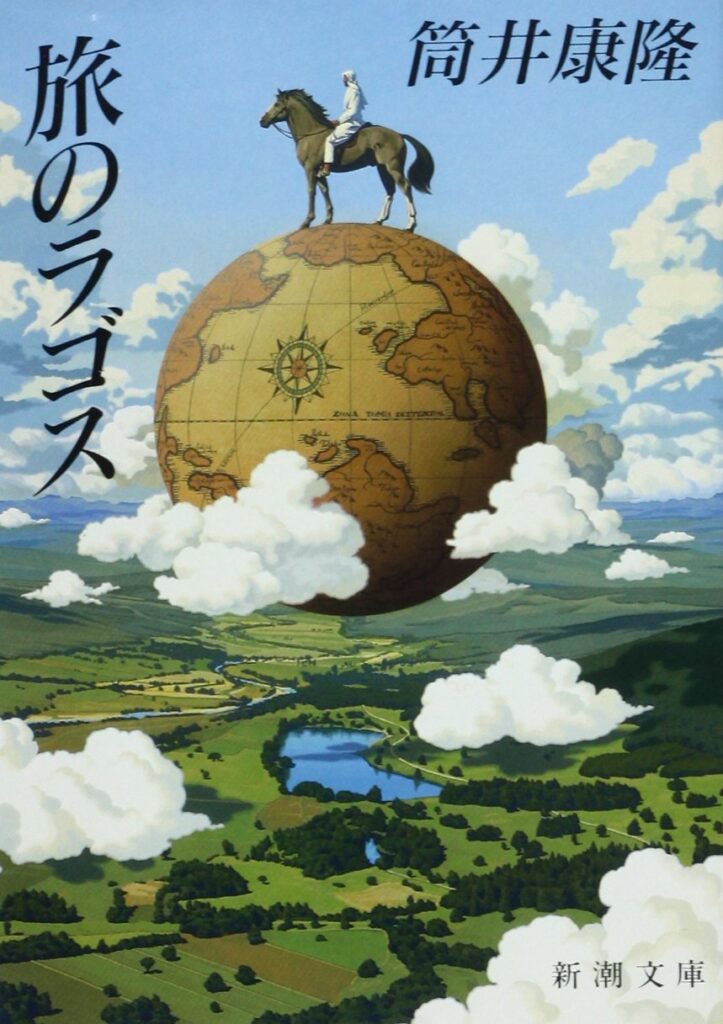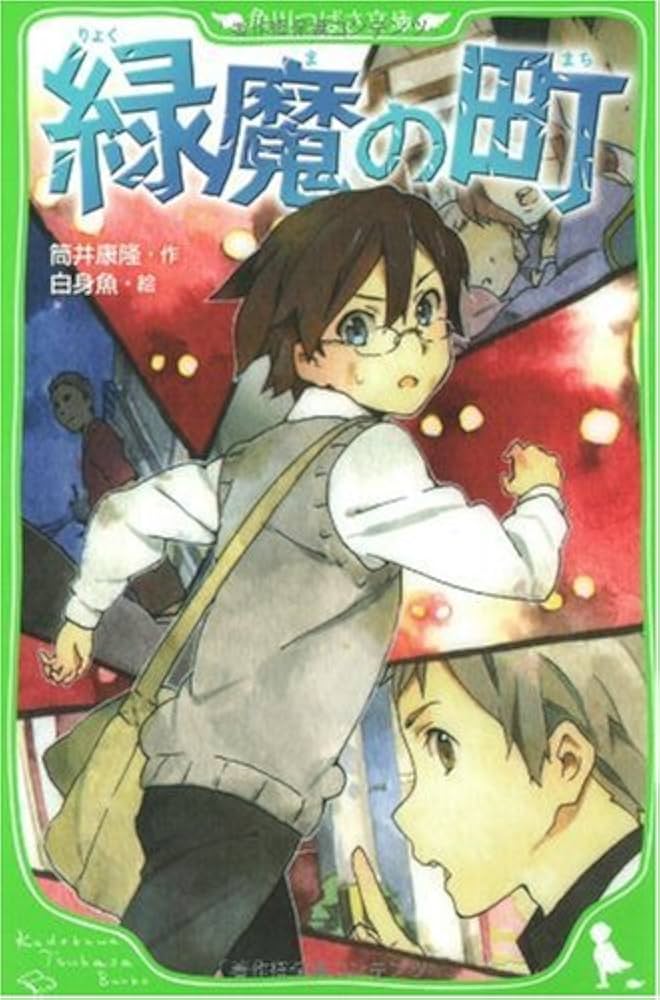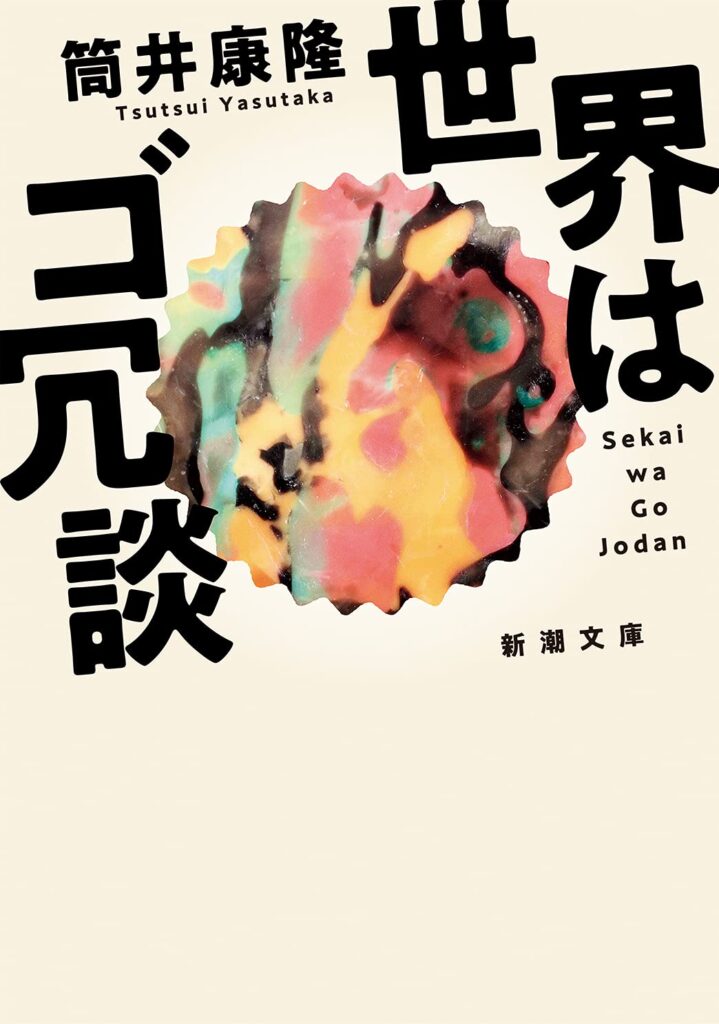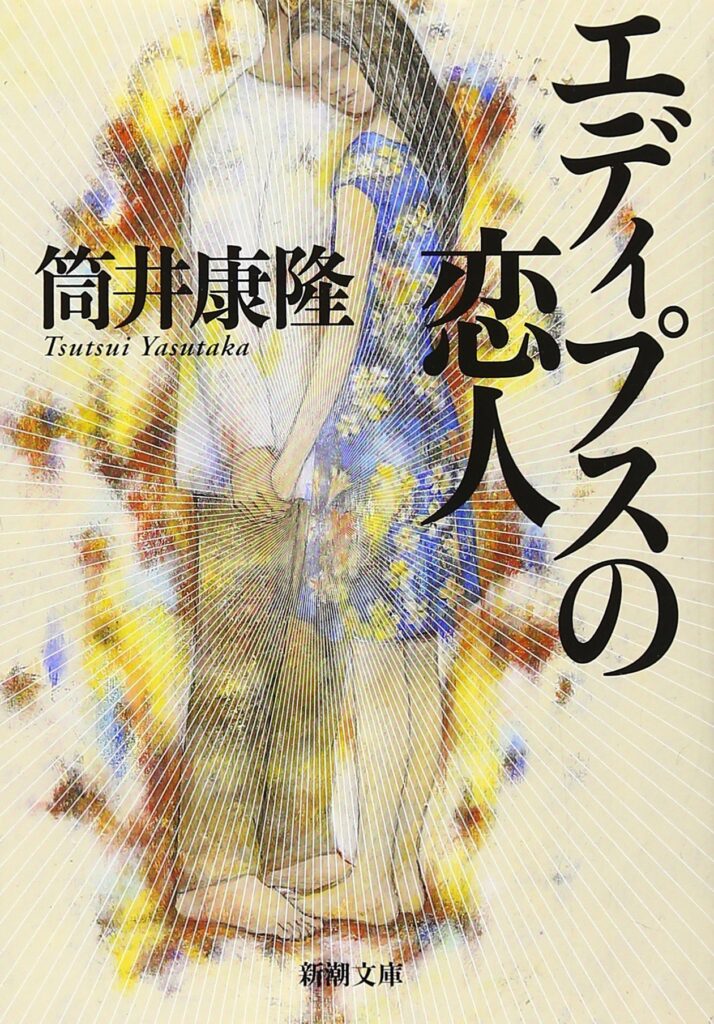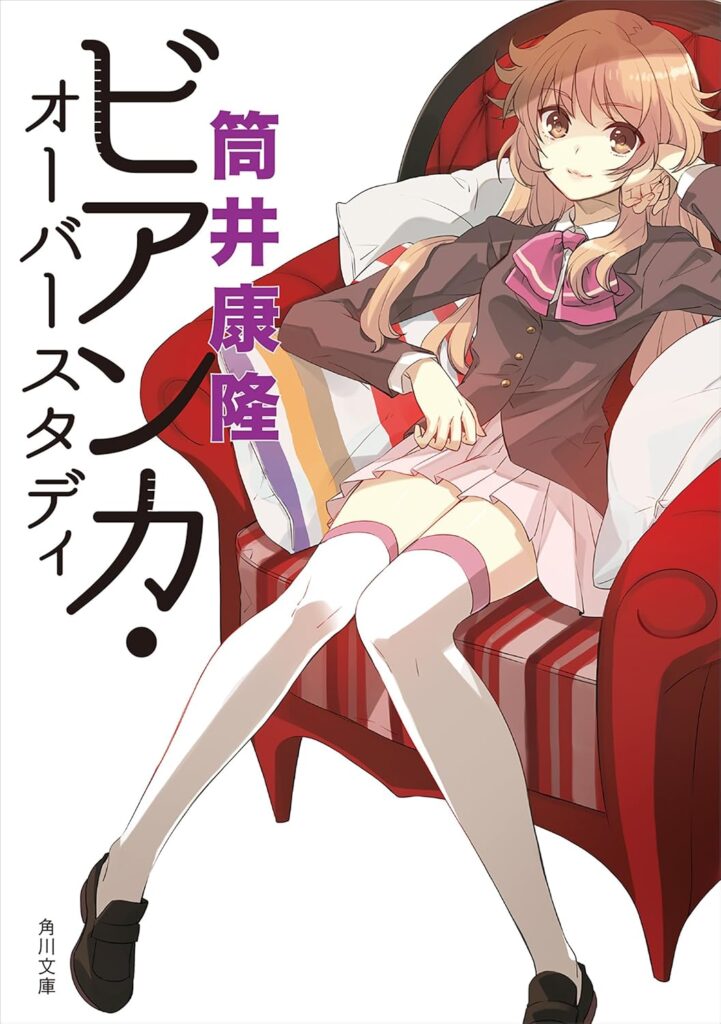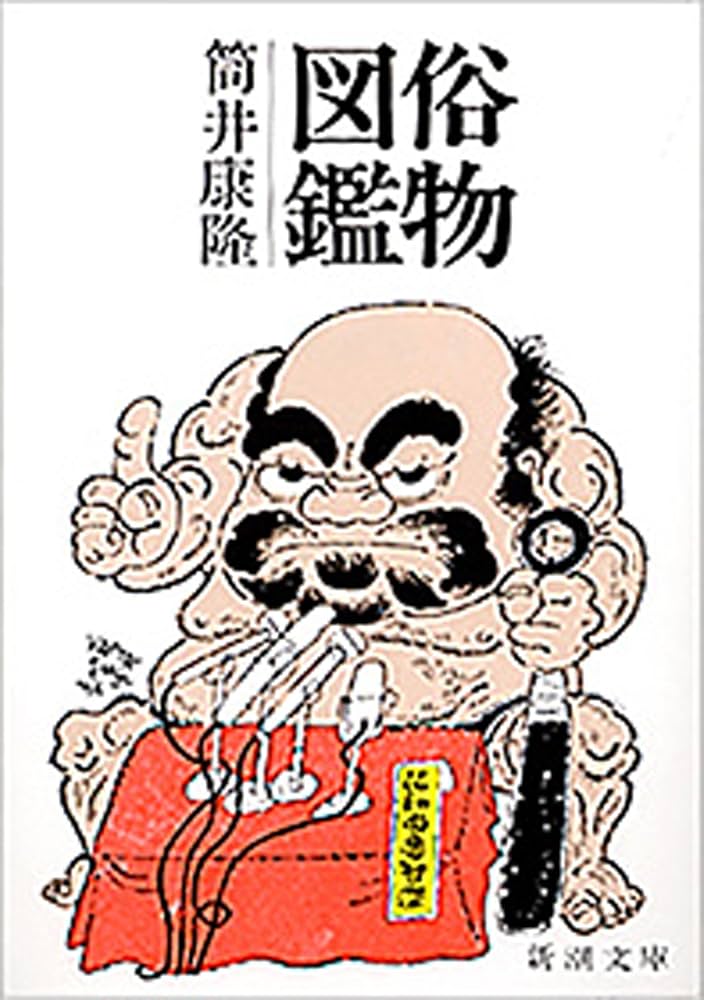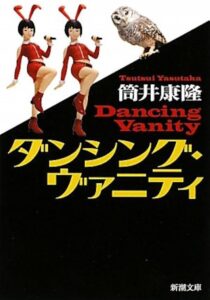 小説「ダンシング・ヴァニティ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「ダンシング・ヴァニティ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
筒井康隆氏が放ったこの物語は、一度足を踏み入れたら抜け出せない迷宮のような、不思議な魅力に満ちています。ページをめくるたびに繰り返される光景、しかしそこには常に微妙な変化が加えられており、読んでいるこちらの現実感覚までが揺さぶられるような、独特の読書体験が待っています。
この記事では、まず物語の骨子となる部分を、結末には触れずにご紹介します。これから『ダンシング・ヴァニティ』を読もうと考えている方は、まずはこちらで物語の雰囲気をつかんでいただければと思います。どのような奇妙な世界が広がっているのか、その入り口までご案内いたします。
そして、その先には核心に迫る詳細な物語の解読と、私の心を揺さぶった点についての個人的な思いを綴ったパートを用意しました。既にこの作品を読まれた方、あるいは結末を知った上で深く味わいたいという方に向けて、物語の細部に宿る意味や、反復の果てに見える情景について、共に考えていければ幸いです。
小説「ダンシング・ヴァニティ」のあらすじ
美術評論家である「おれ」の日常は、ある一点から奇妙に逸脱し、そして回帰する繰り返しに囚われています。書斎で仕事をしていると、決まって家族の誰かが呼びに来るのです。家の前で、またしても何やら騒動が起きている、と。おれはうんざりしながらも、その対応に追われることになります。
この家の前の騒ぎは、何度も何度も繰り返されます。しかし、その内容は少しずつ異なり、関わる人々の言動も微妙に変化していくのです。それはまるで、同じようでいて全く同じではないデジャヴュの連続。おれは混乱しながらも、妻や娘たち、そして老いた母がいる家族を守ろうと四苦八苦します。
さらに、おれの現実感覚を狂わせるように、不可解な出来事が次々と起こります。とうの昔に死んだはずの父親や息子が、まるで生きているかのように目の前に現れ、会話を交わすのです。庭には見たこともない奇妙な動物たちがうろつき始め、日常の風景はシュールな悪夢の色を帯びていきます。
不思議なことに、そんな混沌とした反復の日々の中にあっても、おれの人生そのものは着実に進行していきます。美術評論家として名声を高め、少しずつ老いていくのです。この終わらない繰り返しは一体何なのか。そして、このループする生に行き着く先はあるのでしょうか。物語は、その答えをすぐには見せてくれません。
小説「ダンシング・ヴァニティ」の長文感想(ネタバレあり)
『ダンシング・ヴァニティ』を読み終えた今、私の心には言いようのない感慨が渦巻いています。これは単なる物語ではありません。人生そのものを、その構造から再定義しようとする、文学的な試みなのではないでしょうか。その驚くべき手法と、胸に迫る情感について、詳しくお話しさせてください。
この作品の根幹を成しているのは、何と言っても執拗なまでの「反復」と、その中に仕込まれた「変奏」です。まるでコピー&ペーストをしたかのような文章が何度も現れる。読んでいると、「あれ、この場面さっきも読んだぞ」と既視感に襲われ、思わずページを戻してしまう。この体験こそが、作者が仕掛けた最初の罠であり、招待状なのです。
しかし、注意深く読み比べると、そこには必ず微妙な、しかし決定的な差異が存在します。登場人物のセリフが少しだけ変わっていたり、状況がわずかにエスカレートしていたり。この「ズレ」が、物語を単なる停滞から救い出し、奇妙な推進力を与えています。読者は混乱しながらも、その違いを探すことに夢中になり、いつしかこの異常な文体の中毒になっていることに気づかされます。
物語は、美術評論家である「おれ」の一人称で進みます。この設定が実に秀逸です。美術評論家とは、作品を客観的に分析し、その価値を言語化する存在。しかし本作の「おれ」は、自らが巻き込まれている「人生」という名の奇妙な芸術形式を、当事者として眩暈を感じながら体験し続けます。批評する者が、批評されるべき現実の渦中にいる。この構造が、「ヴァニティ(虚栄)」という題名に深い奥行きを与えています。
「ヴァニティ」とは、虚栄心だけでなく、空虚や無意味さをも指し示す言葉です。おれが必死に守ろうとする日常、築き上げていく名声、それら全てが、巨大な反復の前では空しい営みに見えてくる。その一方で、意味を見出そうとあがくこと自体が、人間の根源的な「虚栄」なのかもしれない。そんな哲学的な問いが、物語の底流には絶えず流れているのです。
物語の起点として何度も繰り返されるのが、「家の前で起こる騒動」です。些細な喧嘩から始まるこのトラブルは、反復されるたびに少しずつその様相を変え、おれの対応も変化していきます。この場面は、物語の「錨」のような役割を果たしています。どれだけシュールな展開に逸脱しても、物語は必ずこの日常の騒がしさに引き戻されるのです。
この騒動は、私たちの人生における「どうにもならない他者」や「理不尽な厄介事」の象徴とも受け取れます。どれだけ解決しようと努めても、形を変えて何度も押し寄せてくる問題。その中で家族を守ろうとするおれの姿は、滑稽でありながらも、切実なものとして胸に響きます。
反復されるのは、外的なトラブルだけではありません。妻や娘、母といった家族との会話もまた、同じようなやり取りが繰り返されます。心配、いらだち、愛情。それらが入り混じった日常の断片が、変奏を伴いながら何度も描かれることで、家族という関係性の複雑さと、それでも失われない絆の確かさが浮かび上がってきます。
混沌とした状況の中、おれが「家族を守らねば」と奮闘する姿は、この物語の感動的な側面の一つです。全てが無意味な繰り返しに思える世界にあって、その行動だけが確かな手触りを持っているように感じられます。しかし、その奮闘さえもがループの一部であるという事実に、私たちは一種のやり切れなさを感じずにはいられません。
この物語の超現実性を決定づけているのが、死んだはずの肉親の登場です。亡き父、そして幼くして失った息子。彼らが何でもないことのように現れ、おれと会話を交わす場面は、読者の心を強く揺さぶります。それは単なる幽霊や幻覚として片付けられるものではなく、生と死の境界線そのものが溶け出してしまったかのような、不思議な実在感を持っています。
この死者たちの来訪は、おれの記憶や悔恨が具現化したものなのでしょうか。それとも、この世界では、生者と死者が同じ時間を共有しているのでしょうか。答えは示されません。しかし、この交流を通して、失われた時間や、取り戻せない過去というものが、現在と地続きの場所にあるかのように描かれるのです。
さらに、物語の奇妙さを加速させるのが、「謎の動物」たちの存在です。おれの家の周りをうろつくこれらの動物たちは、一体どこから来たのか、何者なのか、一切説明がありません。彼らは、この世界の非合理性や、人間の理解を超えた論理が侵入してきたことの証人です。
死んだ家族の登場が、個人的な過去との接続であるとすれば、この動物たちは、より普遍的で根源的な「異物」の象徴と言えるかもしれません。日常が、その足元から静かに、しかし決定的に崩壊していく。その静かな恐怖を、彼らの不可解な存在感が際立たせています。
これほどまでに反復と混沌に満ちた世界でありながら、物語は驚くべきことに「進行」します。おれは美術評論家として成功を収め、確実に年を重ねていくのです。これは、本作のループが完全な円環ではなく、少しずつ上昇していく「螺旋」の構造を持っていることを示唆しています。
同じような毎日を繰り返しているようでいて、人は確かに老い、経験を積み重ね、変化していく。この当たり前の、しかし時に残酷な真実が、反復という特異な形式によって、より鮮烈に描き出されます。ループの中で達成される「成功」は、果たして本物の喜びなのか、それとも、いずれは消えゆく虚しい飾りに過ぎないのか。その両義性が、物語に深い味わいを与えています。
作中で示唆される「うつし世は夢。夜の夢こそまこと」という言葉は、この物語を解くための重要な鍵となります。もはや、どこからが現実で、どこからが夢なのか、その境界は判然としません。いや、もしかすると、おれの体験するこの反復世界全体が、一つの長大な夢なのかもしれません。
夢の中では、論理や因果律は意味をなさず、連想やイメージが世界を支配します。本作の構造は、まさにその「夢の論理」で成り立っているように思えます。そう考えるとき、現実そのものの不確かさ、私たちの足場がいかに脆いものであるかという感覚が、肌で感じられるようです。そして、その不確かな現実の上で営まれる人生の、なんと儚く、そして虚しいことか。
物語は、永遠に続くかと思われた反復の果てに、静かな終わりへと向かっていきます。おれは人生の最終盤を迎え、病床に伏すのです。ループし続けた人生が、死という絶対的な一点へと収束していく。このゆるやかな下降の描写は、これまでの喧騒が嘘のような静寂に満ちています。
死を目前にしたおれの脳裏に去来するのは、これまで何度も繰り返されてきた人生の断片です。家の前の騒動、家族との会話、死者たちとの再会。それらの場面が、走馬灯のように、しかしこれまでとは違う意味合いを帯びて蘇ります。全ては、この瞬間に至るための前奏だったのかもしれません。
そして、物語は息をのむほどに美しいラストシーンで幕を閉じます。それは「詩のようだ」としか言いようのない、記憶と言葉が織りなすモザイク模様です。反復され、変奏され、積み重ねられてきた全ての要素が、最後の瞬間に一つのハーモニーを奏でる。それは、明確な答えや解決ではありません。ただ、そこには静かな受容と、しんみりとした感動がありました。
この結末がなぜこれほどまでに心を打つのか。それは、私たち読者もまた、おれと共に何度も同じ場面を体験し、その細かな差異に心を配り、その世界に深く没入してきたからです。積み重ねられた時間の厚みが、最後の言葉の一つひとつに、忘れがたい重みと輝きを与えているのです。この読後感は、まさに『ダンシング・ヴァニティ』でしか味わえない、唯一無二のものでした。
まとめ
この記事では、筒井康隆氏の傑作『ダンシング・ヴァニティ』について、物語の筋道からネタバレを含む深い読み解きまでをご紹介してきました。この作品の魅力は、何と言ってもその特異な「反復と変奏」のスタイルにあります。読者を混乱させながらも、やがて引き込んで離さない力を持っています。
物語は、美術評論家である主人公の奇妙な日常を追います。繰り返される騒動、現れる死者たち、そしてループしながらも進行していく人生。そのシュールで混沌とした世界は、私たち自身の人生が持つ不条理さや、夢と現実の曖昧な境界線を映し出しているかのようです。
反復の果てにたどり着く、静かで詩的な結末は、この物語が決して単なる実験的な作品ではないことを証明しています。それは、人生の虚しさと、それでもなお存在する愛おしさを見事に描ききった、感動的な文学体験と言えるでしょう。
まだこの奇妙で美しい「ダンス」を体験していない方には、ぜひ挑戦していただきたい一冊です。そして、既に読み終えた方も、この記事をきっかけに再読し、新たな発見をしていただけたなら、これほど嬉しいことはありません。