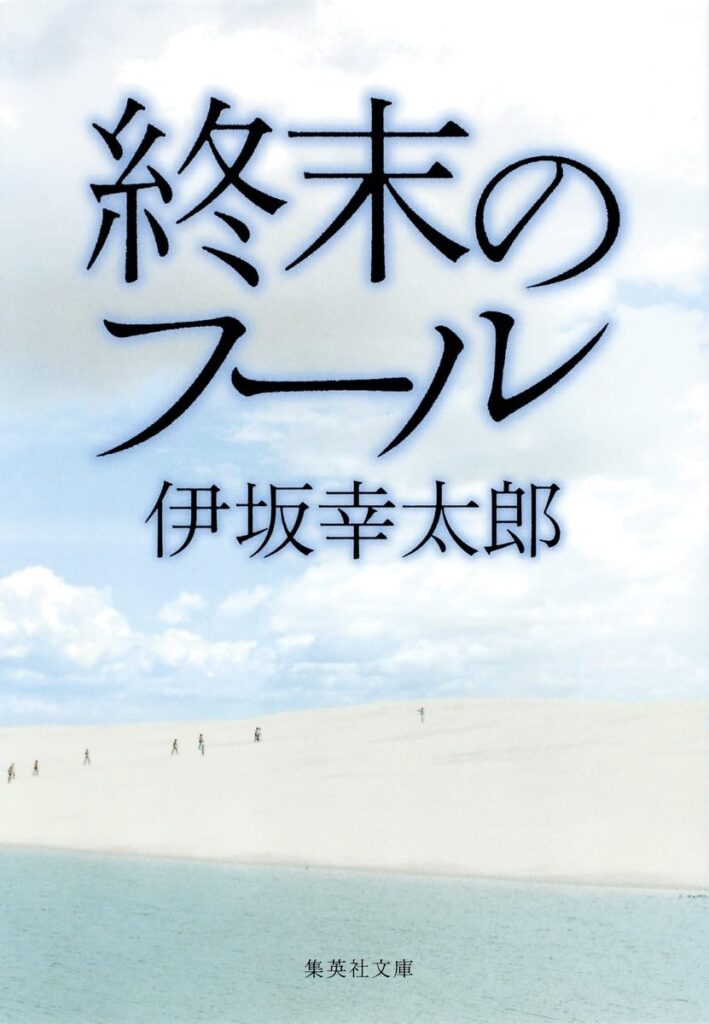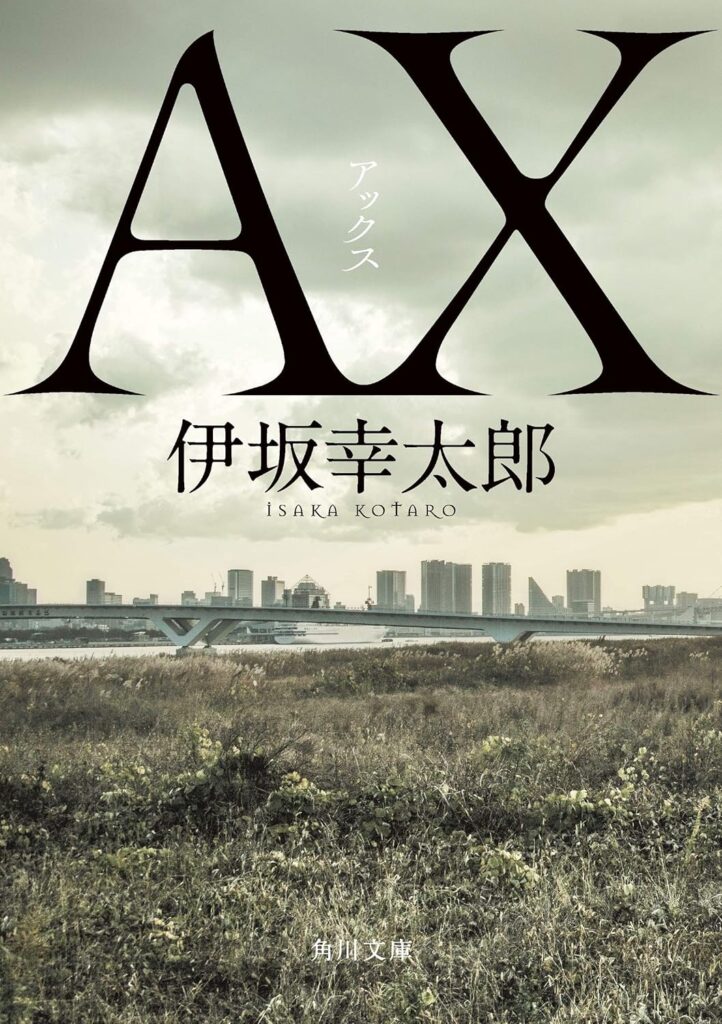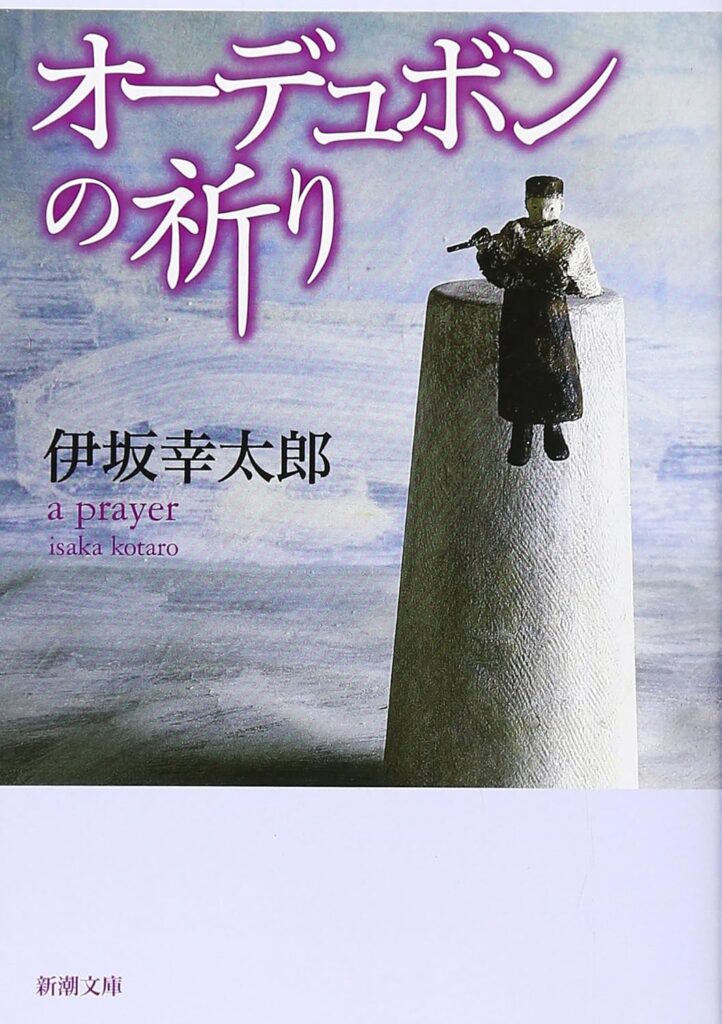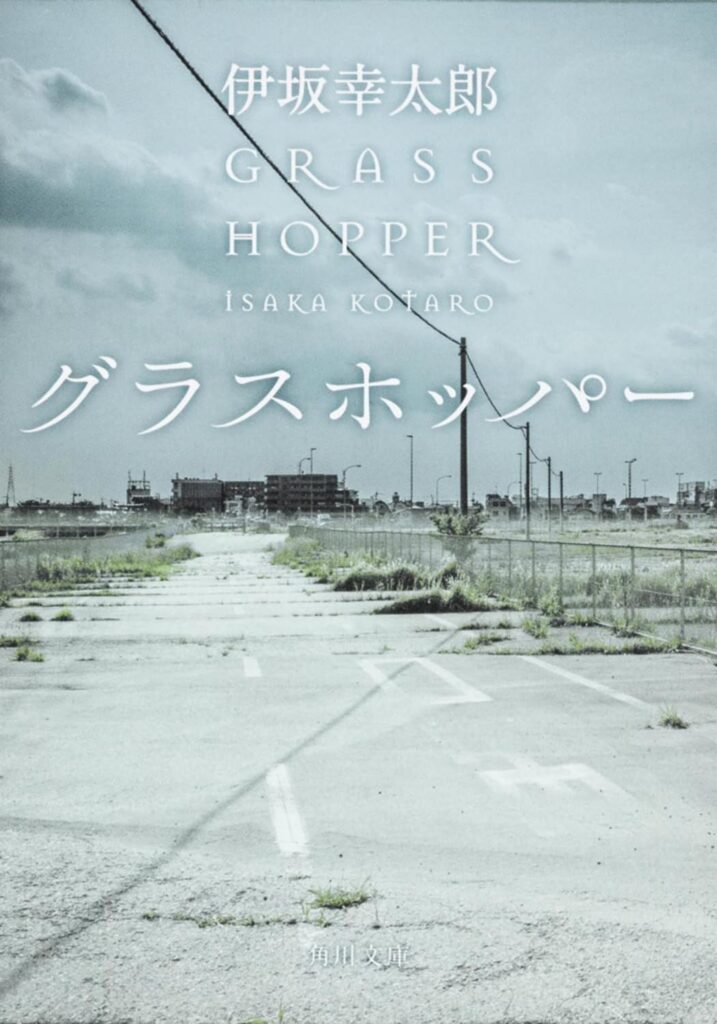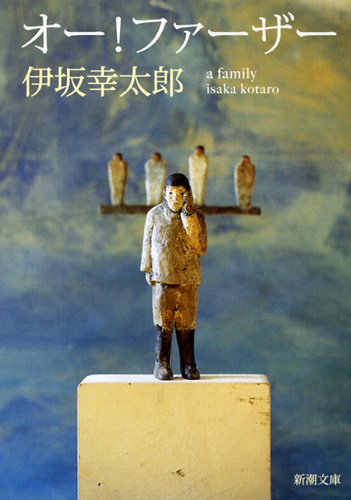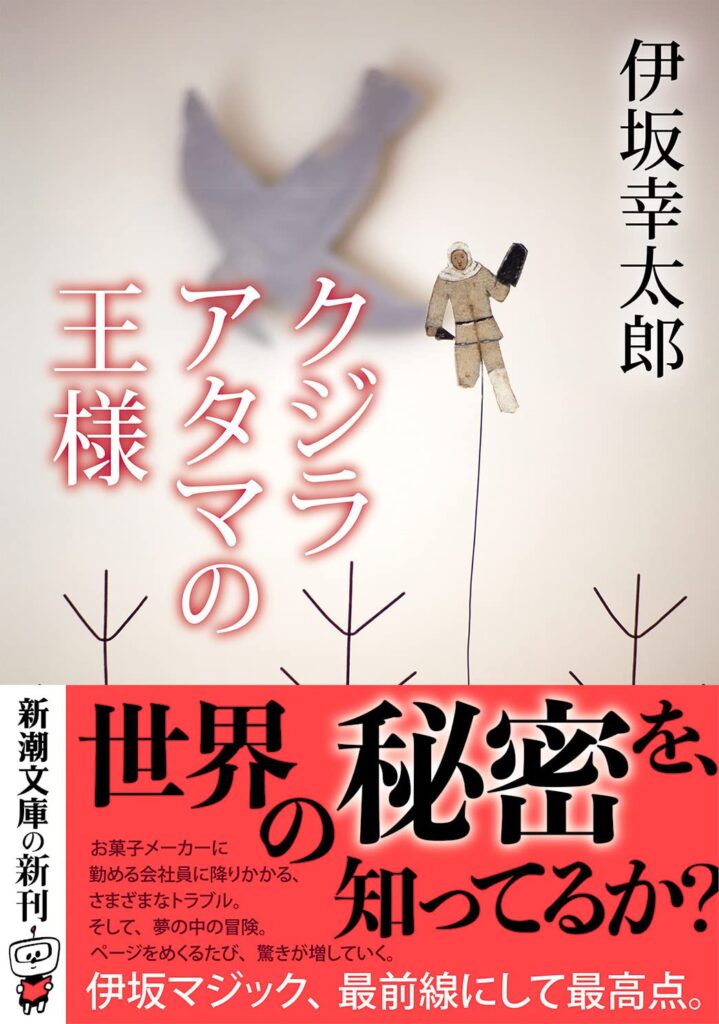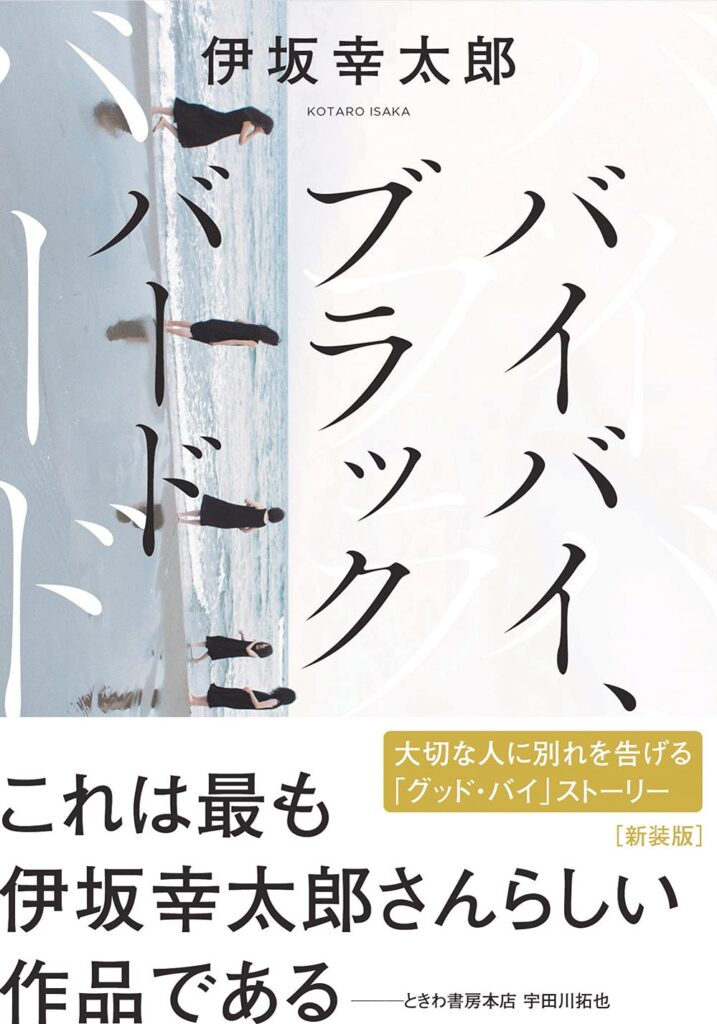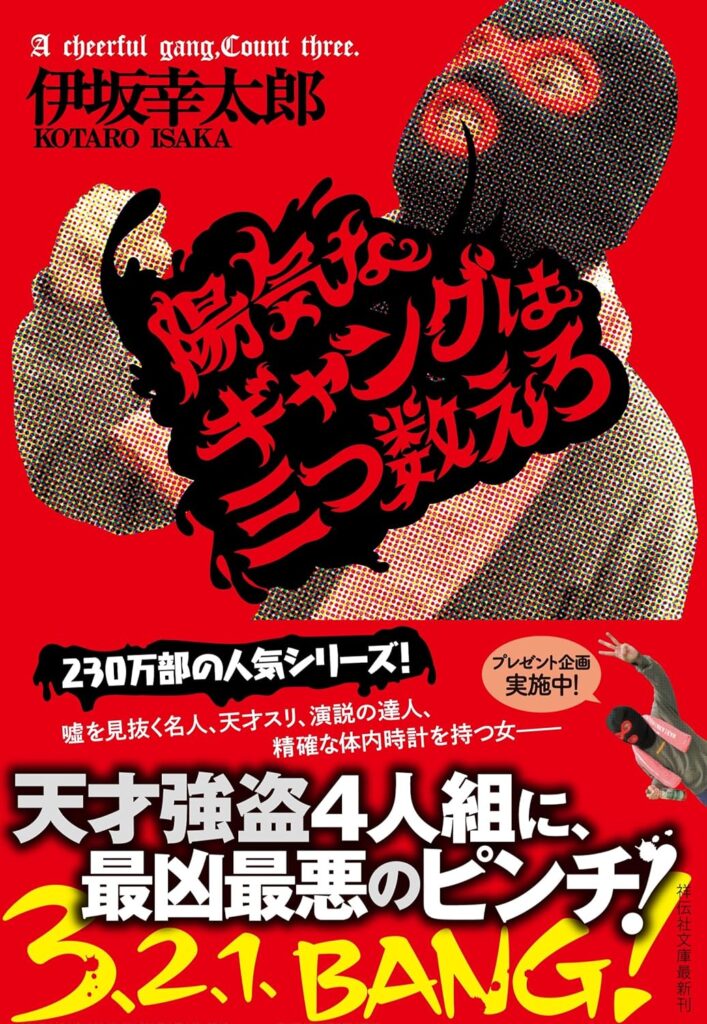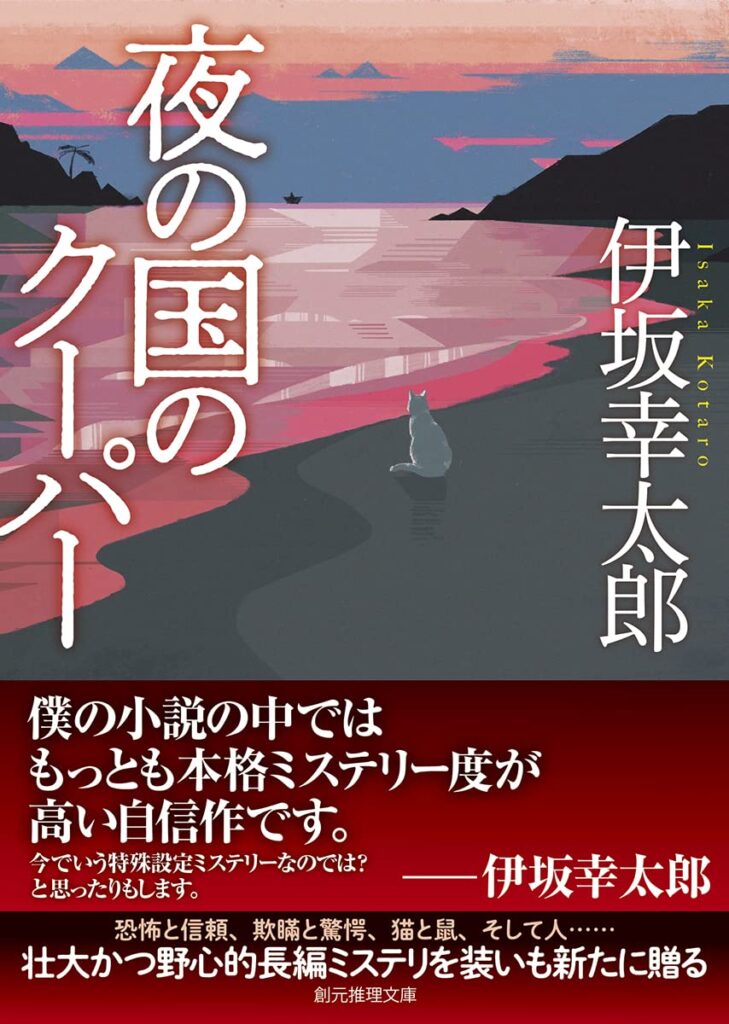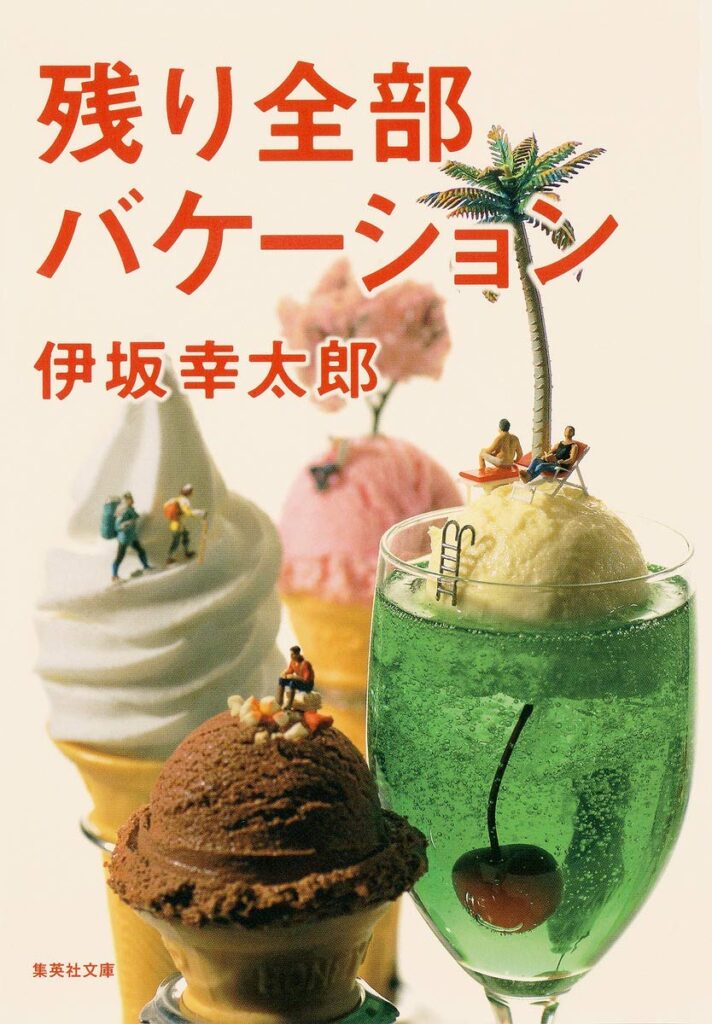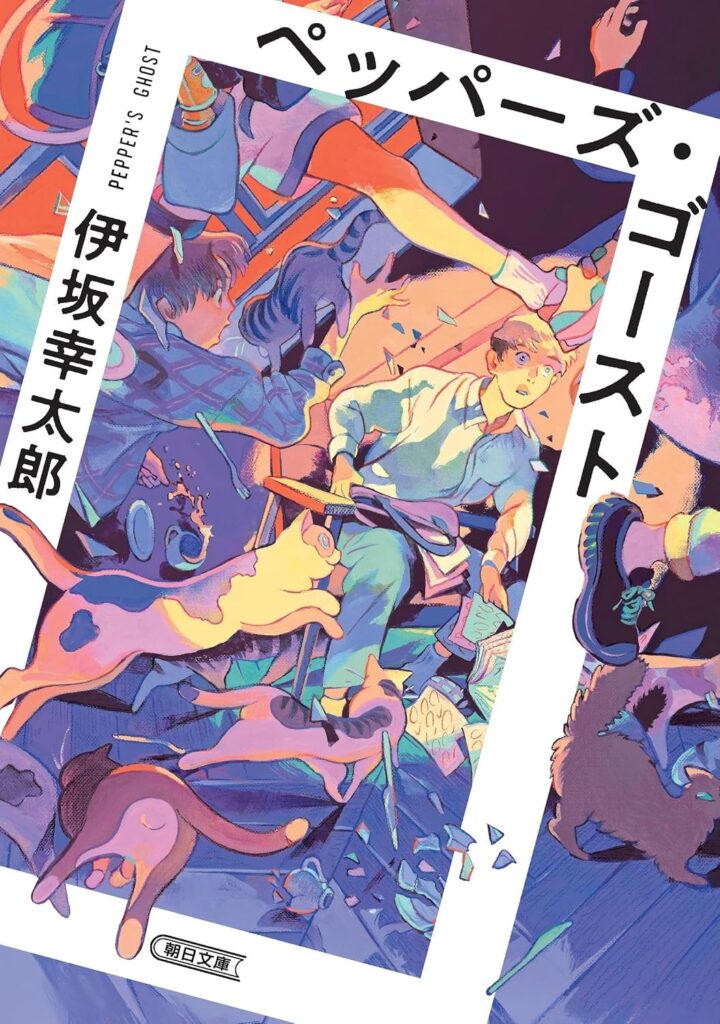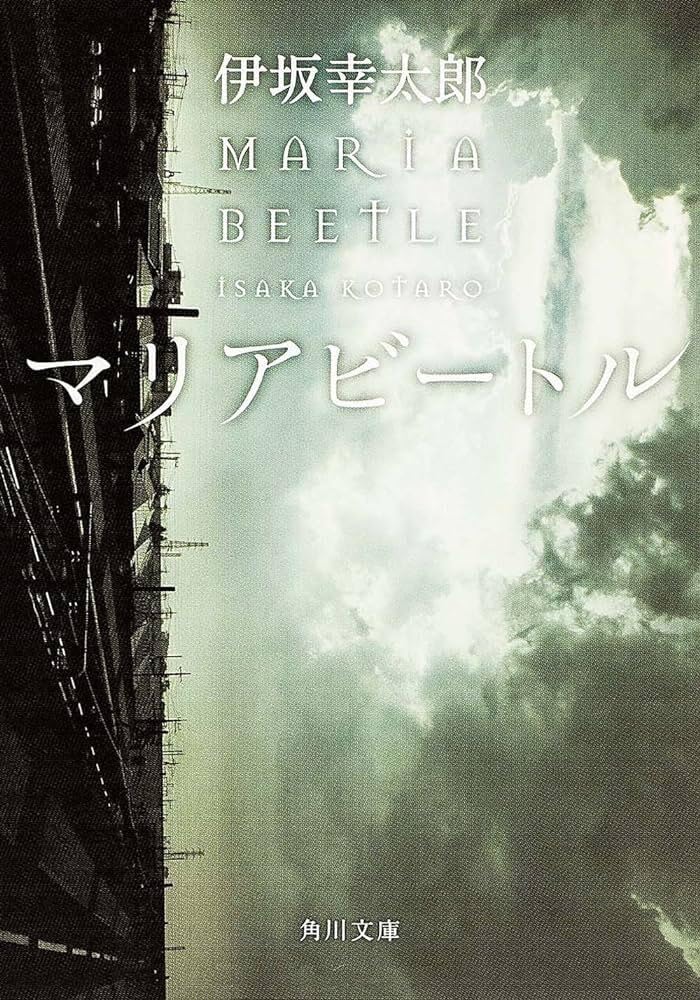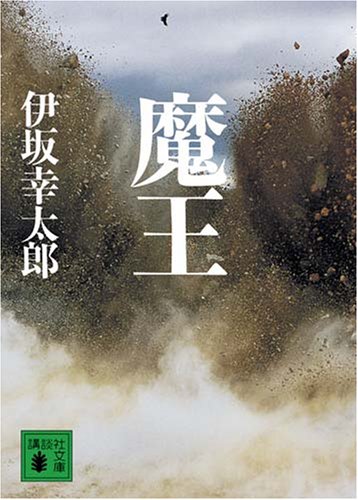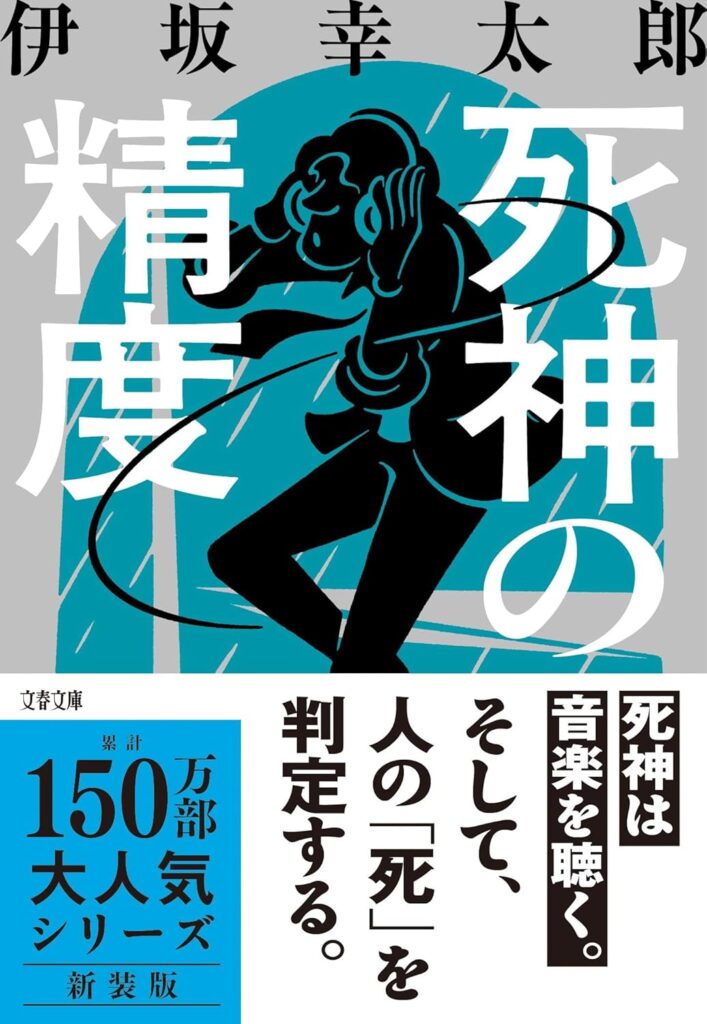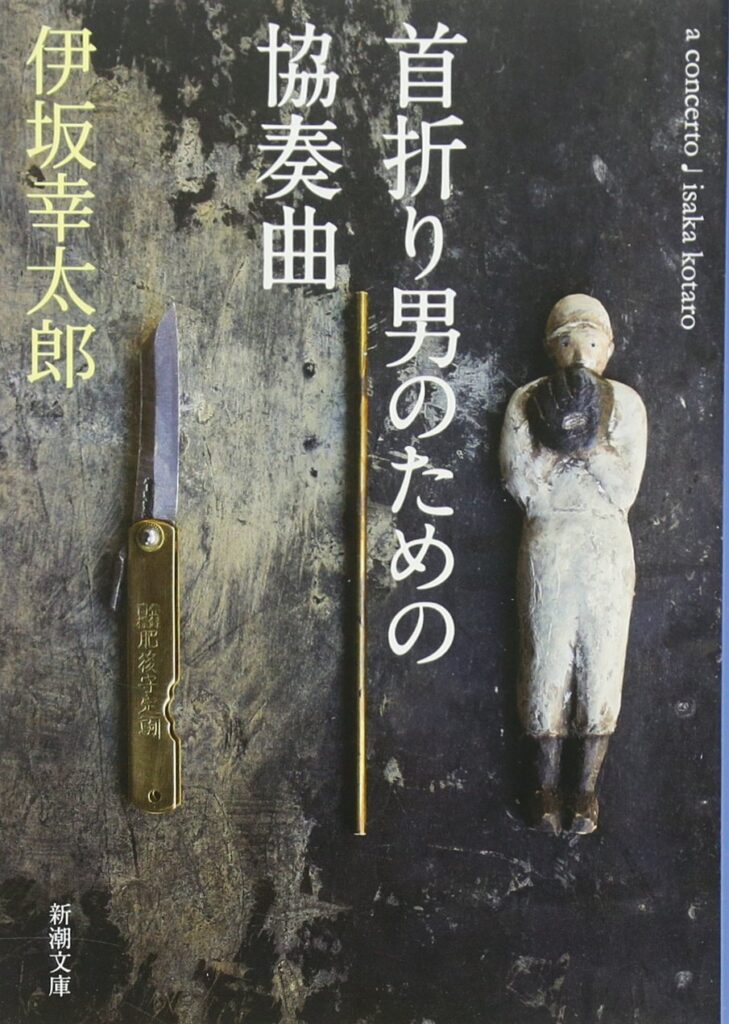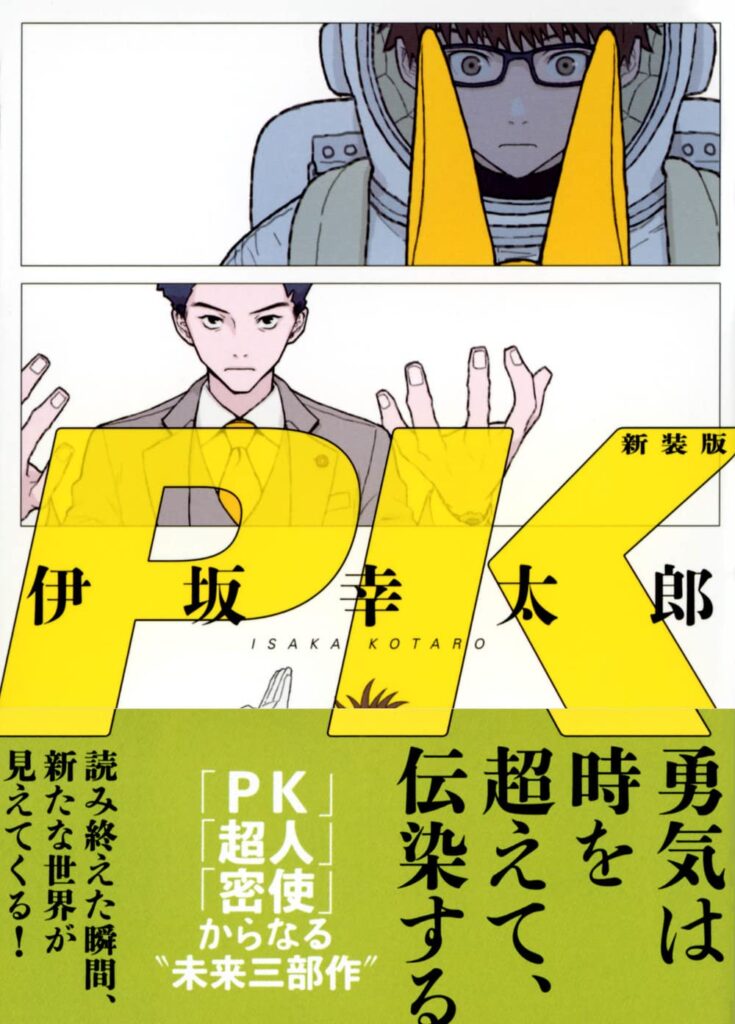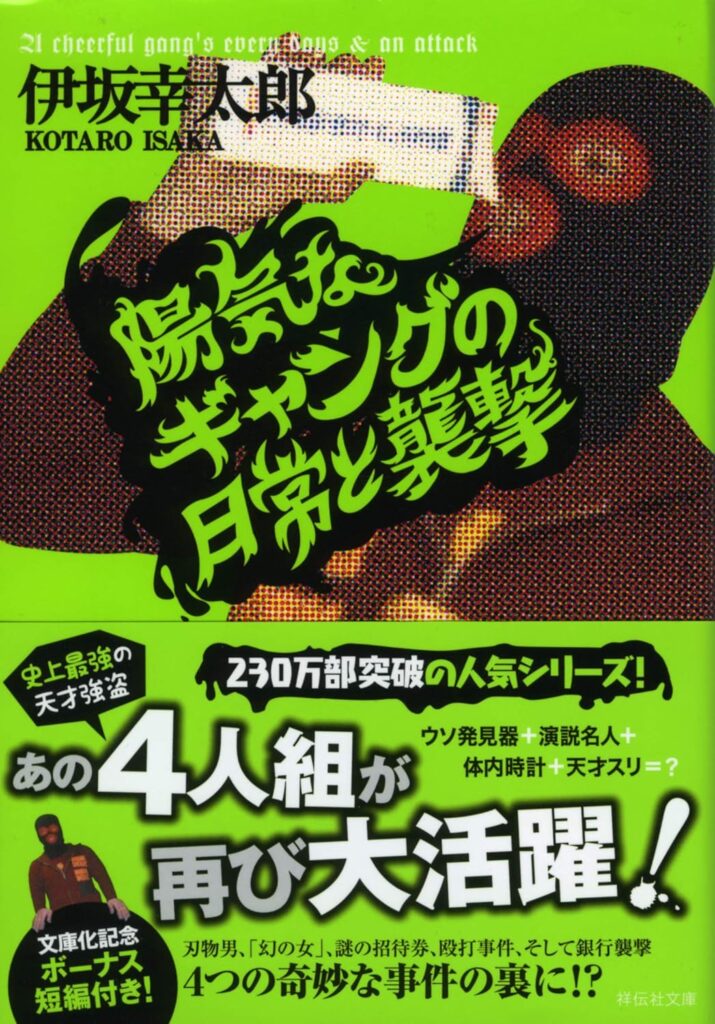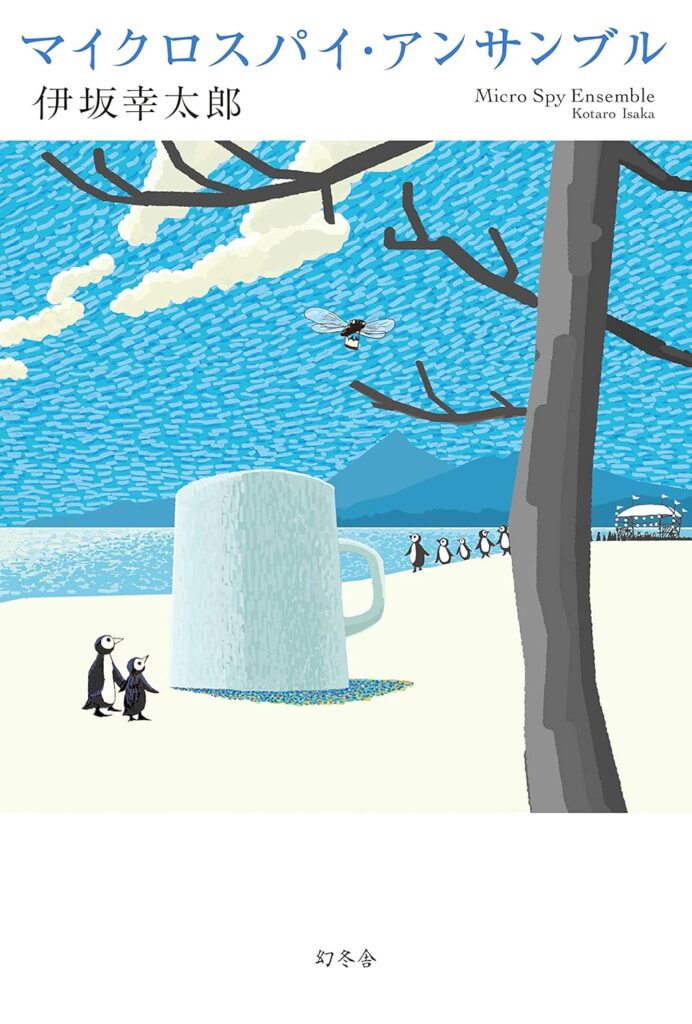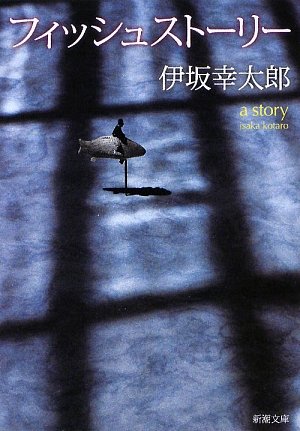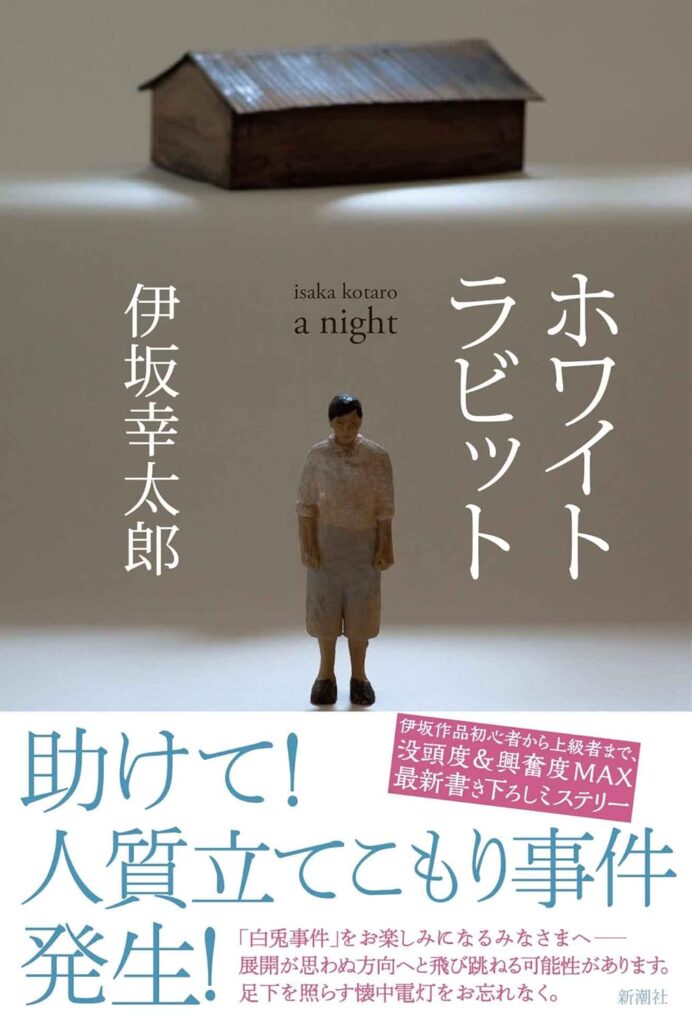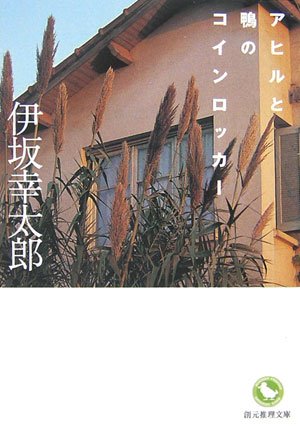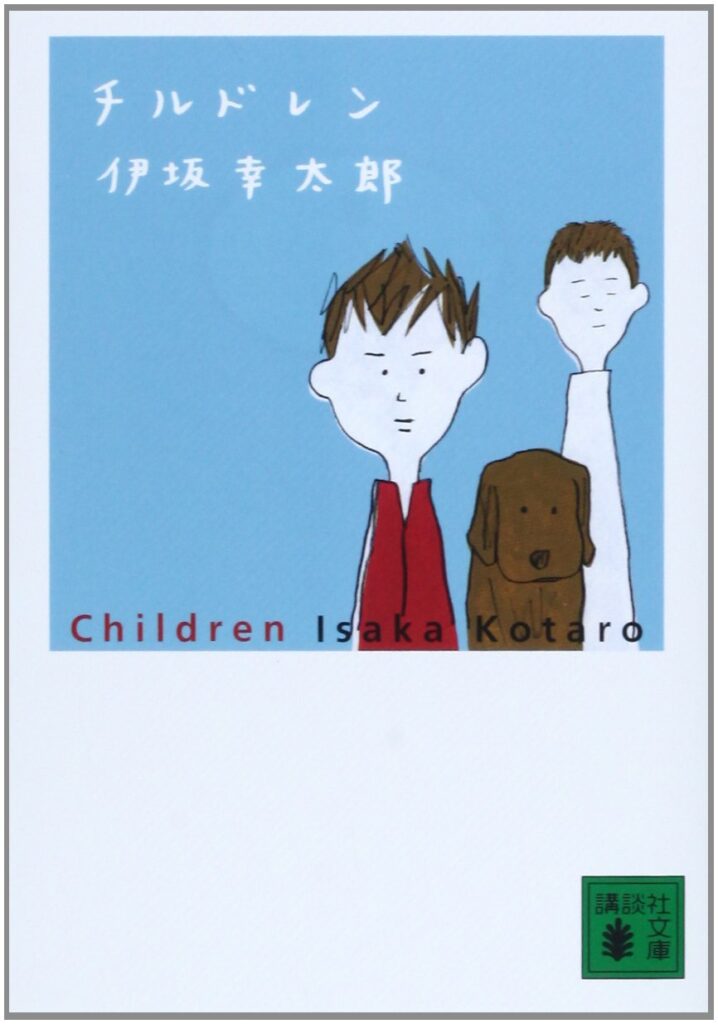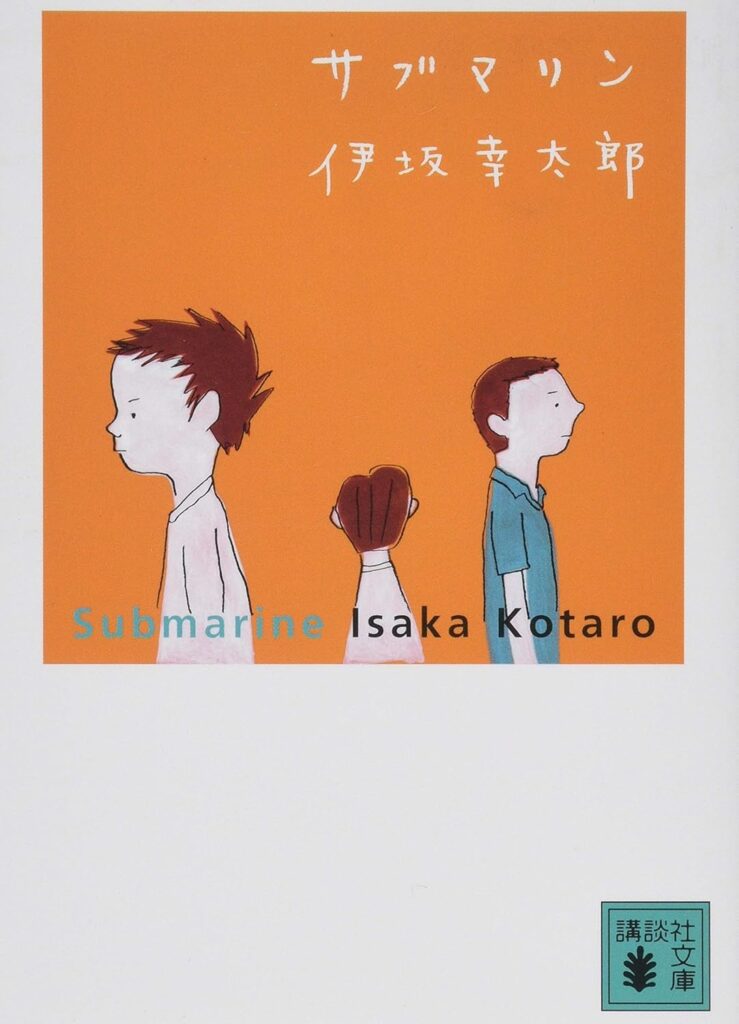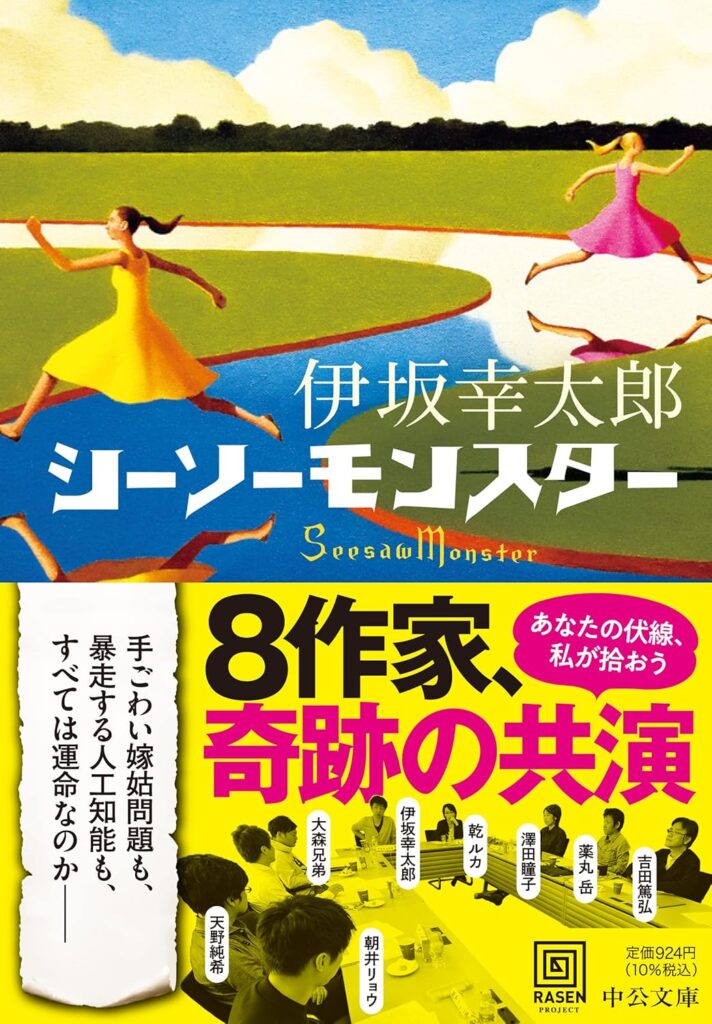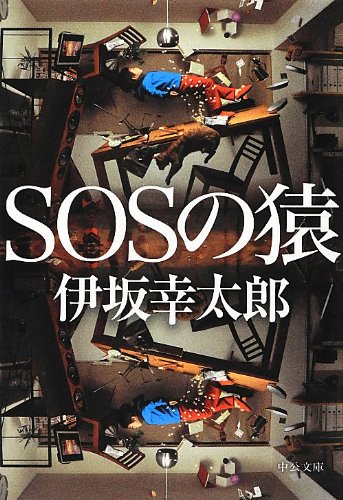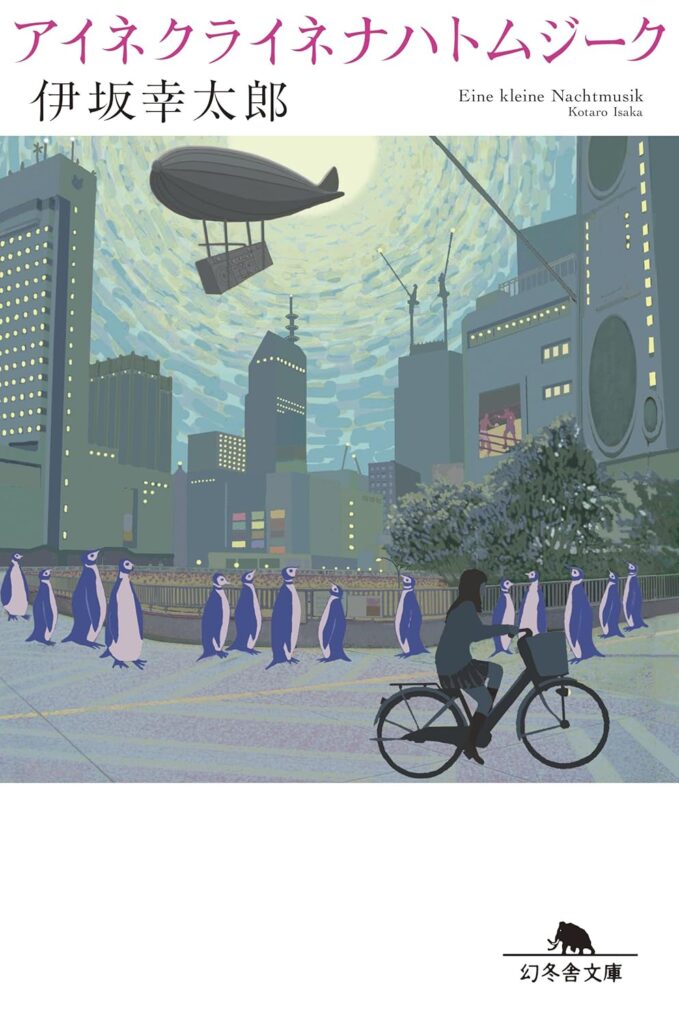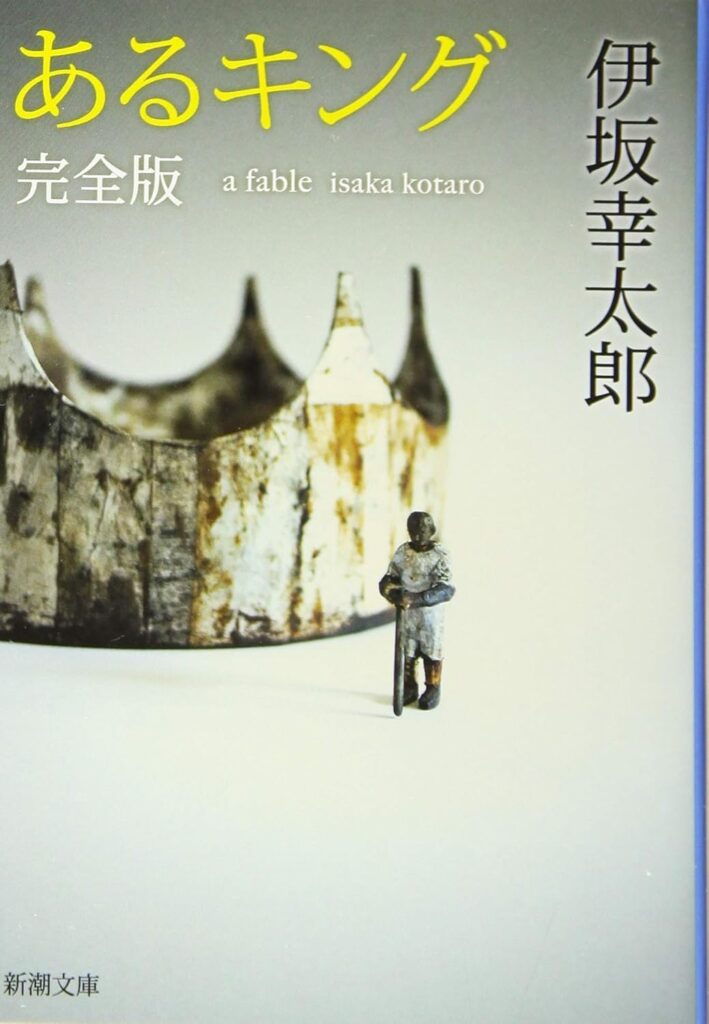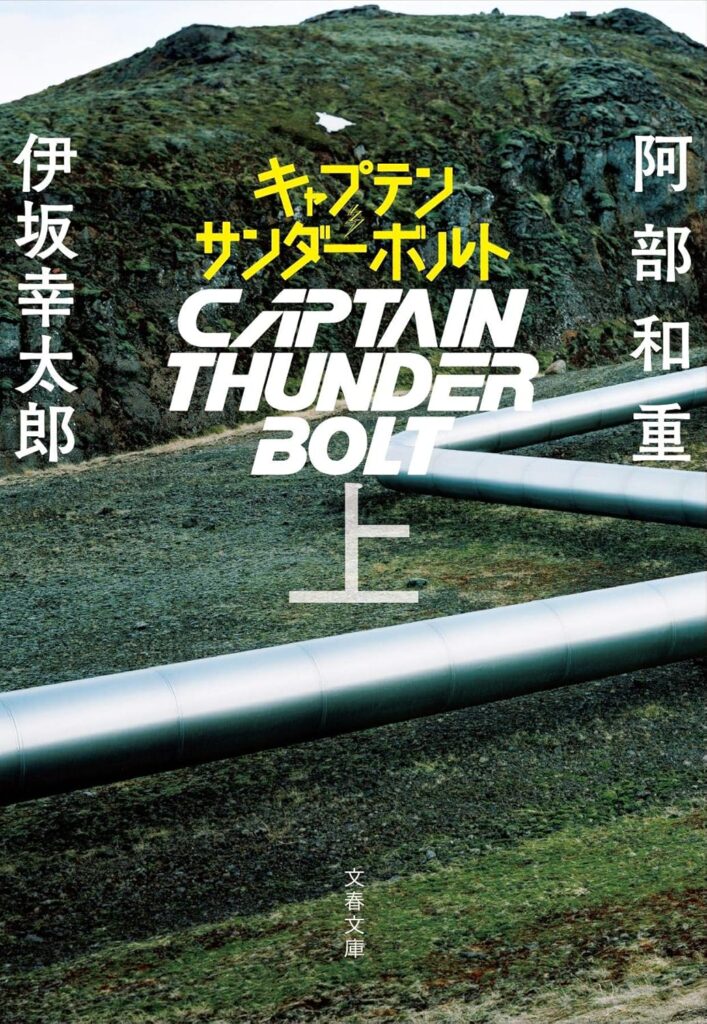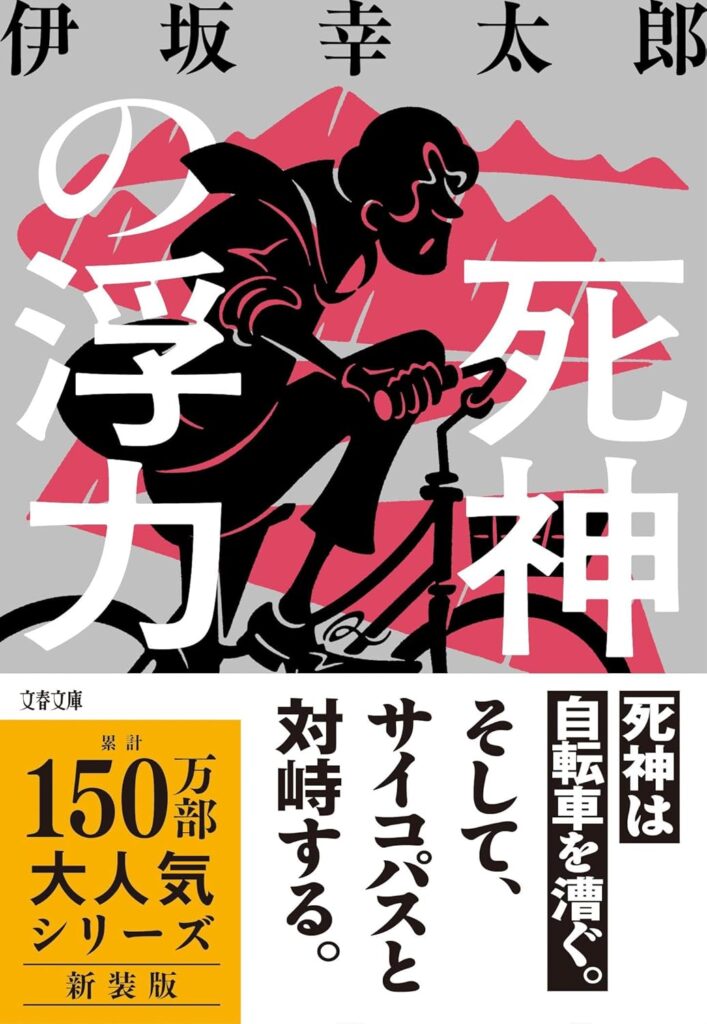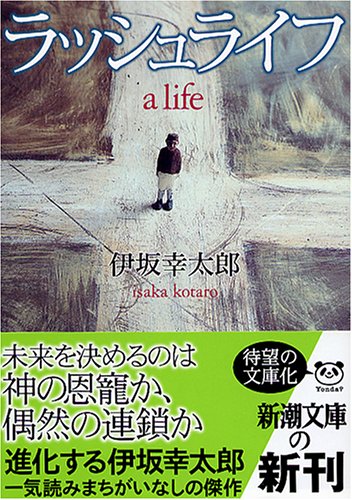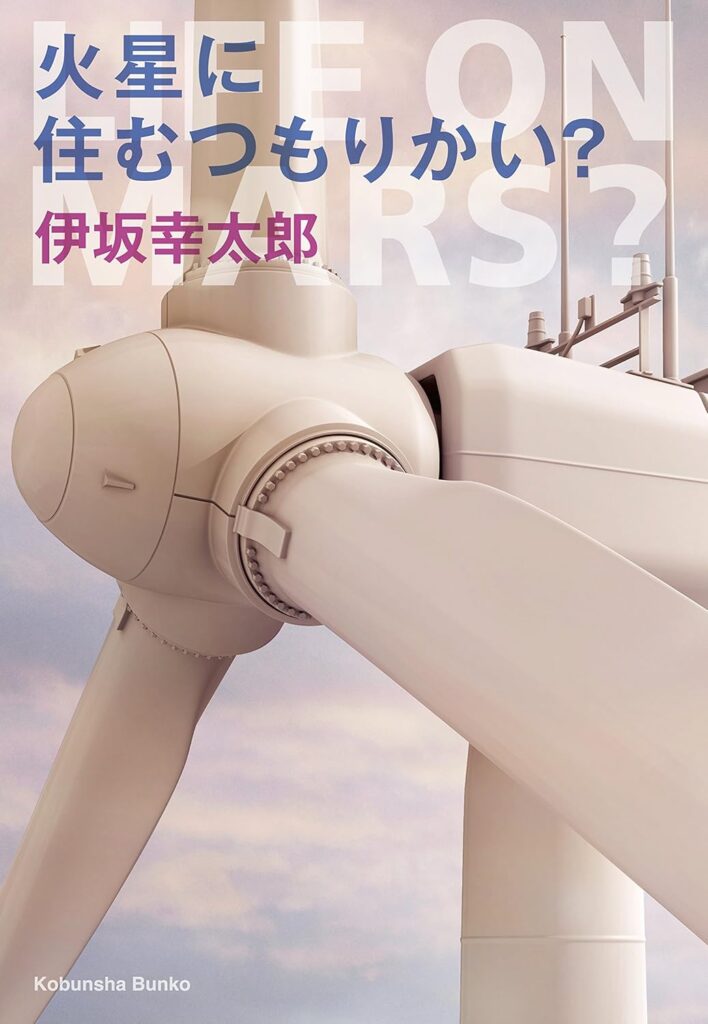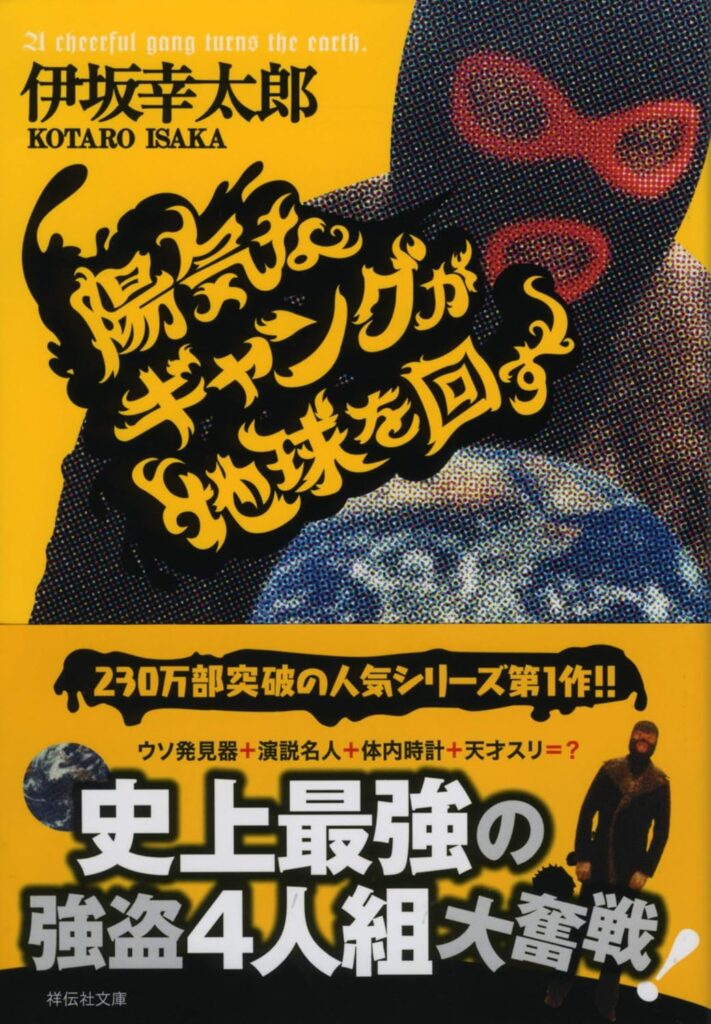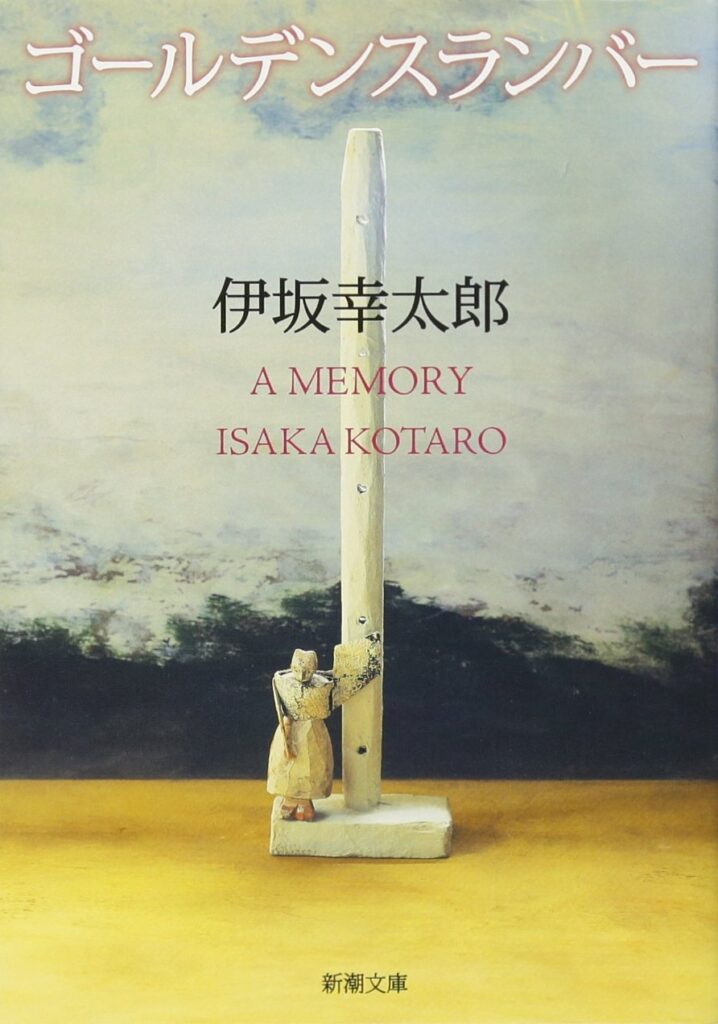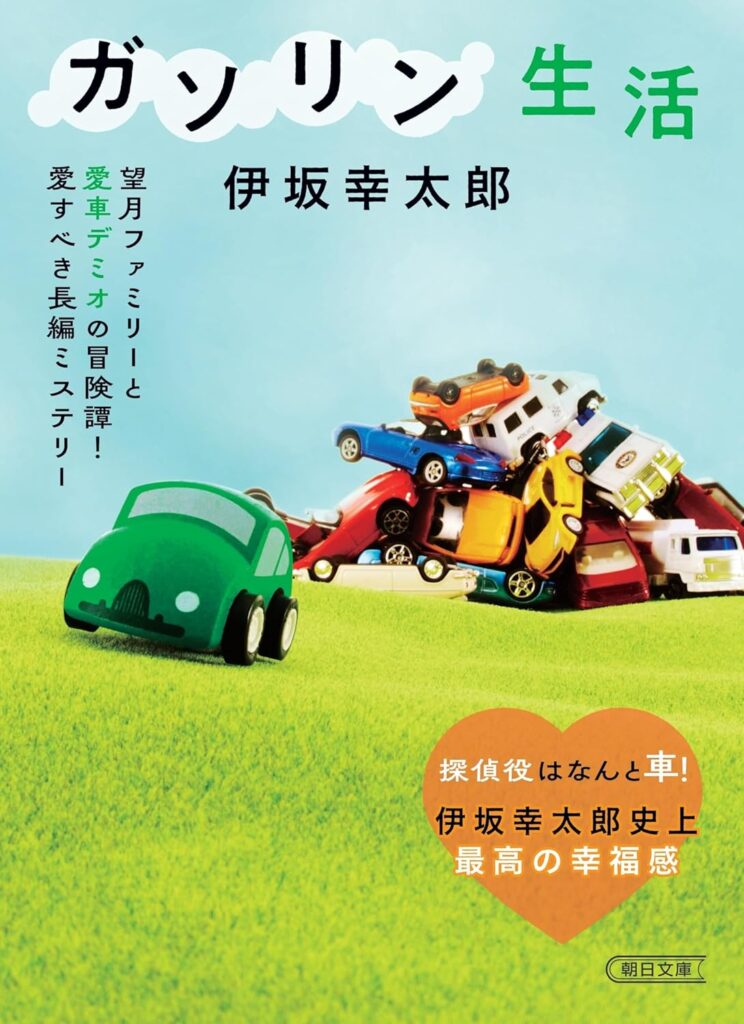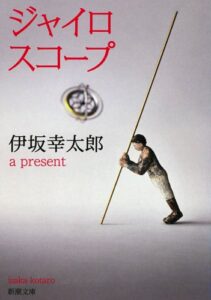 小説「ジャイロスコープ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。伊坂幸太郎さんの手によるこの短編集は、デビュー15周年を記念して書かれた作品群で構成されています。七つの異なる物語が収録されており、それぞれが独立した輝きを放ちながらも、どこか伊坂さんらしい繋がりを感じさせる、そんな一冊になっています。
小説「ジャイロスコープ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。伊坂幸太郎さんの手によるこの短編集は、デビュー15周年を記念して書かれた作品群で構成されています。七つの異なる物語が収録されており、それぞれが独立した輝きを放ちながらも、どこか伊坂さんらしい繋がりを感じさせる、そんな一冊になっています。
本書のタイトル『ジャイロスコープ』は、回転するコマを三つの輪で支え、どの方向にも自由に向きを変えられる装置のことだそうです。まさにその名の通り、収録されている物語たちは、それぞれが驚きと意外性に満ちた、個性豊かな顔ぶれ。それでいて、軸はぶれずに伊坂幸太郎さんの世界観をしっかりと保っている、そんな印象を受けますね。
この記事では、そんな「ジャイロスコープ」に収録された各短編の物語の概要、少し踏み込んだ結末の部分、そして私個人のたっぷりとした評価を書き連ねていきます。伊坂作品がお好きな方はもちろん、これから読んでみようかなと考えている方にも、本書の魅力が伝われば嬉しいです。
小説「ジャイロスコープ」のあらすじ
「ジャイロスコープ」には、色とりどりの七つの物語が収められています。まず「浜田青年ホントスカ」では、家出をして蝦蟇倉市(がまくらし)に流れ着いた青年・浜田が、スーパーの駐車場で「助言あり〼」という奇妙な看板を掲げる相談屋・稲垣と出会うところから始まります。稲垣の助手として働くことになった浜田ですが、一週間後、稲垣自身が相談者として現れ、事態は予想外の方向へ。実は浜田の家出と稲垣の相談屋稼業には、ある計画が隠されていたのです。浜田自身の秘密も明らかになり、二人の関係は奇妙な結末を迎えます。
次に「if」は、通勤バスでバスジャックに遭遇した山本という男性の物語。犯人に言われるがままバスを降りた山本は、事件前に見かけた困っている老婆を助けなかったこと、そして何もできなかった自分を後悔し続けます。しかし、もしあの時、違う選択をしていたら…? という可能性を描きます。時を経て再び似た状況に遭遇した山本は、過去の経験を胸に、今度こそ違う行動を起こそうとします。選択によって変わるかもしれない未来、そして過去の後悔と向き合う姿が印象的です。
「ギア」は、これまでの伊坂作品とは少し毛色の違う、荒廃した世界が舞台。ワーゲンバスのような車に乗る人々が道を進む中、運転手が語る「セミンゴ」という奇妙な生物の話。一匹見たら必ず十匹は近くにいるというその生物は、当初は作り話だと思われていましたが、突如起こった地震の後、彼らの目の前に信じられない光景が広がります。「二月下旬から三月上旬」は、幼馴染の慈郎とジョン、二人の男性の四半世紀にわたる友情と、時間の流れを描いた物語。時折見せる慈郎の不思議な言動が、どこか幻想的な雰囲気を醸し出しています。
そして「一人では無理がある」は、クリスマスプレゼントを配る「リアルサンタ」の仕事に焦点を当てた物語。配達員の松田は、うっかりミスで少年に頼まれたものとは違うプレゼント(プラスドライバー)を届けてしまいます。しかし、その間違いが思わぬ形で、ストーカー被害に遭っていた女性・梨央を救うことに繋がります。偶然と善意が織りなす心温まる展開が見どころです。「彗星さんたち」は、新幹線の清掃員たちが主人公のお仕事小説風の一編。主任が入院し、残されたメンバーで奮闘する中、清掃する車両で奇妙な現象に遭遇します。それはまるで、一人の女性の人生を追体験しているかのようで…。清掃員たちのチームワークと、ささやかな奇跡が描かれます。最後の書き下ろし「後ろの声がうるさい」では、新幹線を舞台に、これまでの短編に登場した人物たちが偶然乗り合わせます。彼らの会話を通して、それぞれの物語のその後や裏側が垣間見える、ファンには嬉しい一編となっています。
小説「ジャイロスコープ」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは小説「ジャイロスコープ」を読んだ私の個人的な評価を、ネタバレも気にせず、たっぷりとお話しさせていただきましょう。伊坂幸太郎さんの作品は、いつも軽やかな筆致の中に、人生の真理や人間の複雑な感情が織り込まれているように感じますが、この短編集「ジャイロスコープ」も、まさにその魅力が詰まった一冊でした。七つの物語はそれぞれ独立していますが、読み終えた時には、まるで精巧なからくり箱を開けるような楽しみと共に、不思議な満足感に包まれましたね。
まず「浜田青年ホントスカ」。家出青年と胡散臭い相談屋という組み合わせからして、もう伊坂さんらしいですよね。浜田が稲垣の仕事ぶりを観察する一週間、ちょっとした相談事に対する稲垣の斜め上なアドバイスに、浜田と一緒に「ホントスカ?」と心の中で突っ込みを入れてしまいます。でも、ただの変な相談屋かと思いきや、ラストで明かされる真相には驚かされました。浜田が実は金持ちの息子で誘拐計画があったこと、そして稲垣はその計画に加担しつつ浜田を監視していたこと。さらに、浜田自身も本物の浜田ではなく、彼を殺して成り代わった人物であり、稲垣殺害も依頼されていたなんて! どんでん返しの連続に、ページをめくる手が止まりませんでした。結局、殺す気になれず稲垣と街を出るという結末も、単純な悪人では終わらない、どこか憎めないキャラクターたちの人間味を感じさせます。何が正しくて何が間違っているのか、簡単には割り切れない現実の複雑さを見せつけられた気がします。
「if」は、個人的にとても考えさせられた一編です。「あの時こうしていれば…」という後悔は、誰しもが経験することだと思います。バスジャックという極限状況で、何もできなかった自分を責め続ける山本。彼の後悔の念が生々しく伝わってきて、胸が締め付けられました。そして描かれる「もう一つの選択肢」。老婆に声をかけ、結果的にバスジャック犯を取り押さえる未来。これがパラレルワールドなのか、それとも20年後の再挑戦なのか、はっきりとは書かれていませんが、どちらにせよ「選択」が未来を変える可能性を示唆している点が興味深いです。特に、20年後に同じメンバーが再び集い、今度こそ勇気を出す、という解釈だと、過去の失敗を乗り越えて成長する人間の姿が描かれていて、希望を感じますね。人生は選択の連続であり、その一つ一つが未来に繋がっているのだと、改めて考えさせられました。
「ギア」は、他の作品とは一線を画す、ポストアポカリプス的な世界観が新鮮でした。荒廃した道を走るバス、そして「セミンゴ」という謎の生物。メタリックな銀色で体長三メートル、メトロン星人似…想像するだけで不気味です。「一匹見たら十匹いる」という法則が、ゴキブリではなくこのセミンゴに当てはまる、という会話から、じわじわと不穏な空気が漂ってきます。そして、地震と共に現れるセミンゴの大群! この展開は、ホラーやSF的な要素もあって、伊坂さんの引き出しの多さを感じさせます。絶望的な状況の中でも、バスの乗客たちの間のどこか間の抜けた会話が、伊坂作品らしいおかしみを添えています。限られた情報の中で、読者の想像力を掻き立てる筆致は見事でした。
「二月下旬から三月上旬」は、慈郎とジョンの長年にわたる友情物語。小学生時代の出会いから、四半世紀という長い時間軸を描くことで、人生の移ろいと変わらない友情の温かさが伝わってきます。母親との関係に悩んでいた慈郎にとって、ジョンはまさに救いだったのでしょう。時折、慈郎が誰もいない空間に向かって話しかける描写があり、これが彼の精神的な不安定さなのか、それとも何か超常的な存在を示唆しているのか、少し不思議な余韻を残します。個人的には、長い付き合いの中で、相手がそばにいなくても心の中で対話するような感覚、そういったものを表現しているのかな、とも思いました。派手な事件が起こるわけではありませんが、二人の関係性を通して、人生の機微をしみじみと感じられる作品でした。
「一人では無理がある」は、サンタクロースを題材にした、心温まる一編です。プレゼント配達団体に所属する松田の、ちょっとドジだけど真面目な仕事ぶりが微笑ましい。彼が間違えて届けてしまったプラスドライバーが、梨央がストーカーを撃退するのに役立つという展開は、まさに「風が吹けば桶屋が儲かる」的な、伊坂さん得意の連鎖反応ですね。ストーカーの恐怖という緊迫した状況と、サンタやプレゼントというファンタジックな要素が絶妙に組み合わさっています。特に、プレゼントを受け取った少年が、梨央に鉄板(これも別の偶然で手に入れたもの)を渡し、それが結果的に梨央を助けることになる流れは、人の善意や偶然が巡り巡って誰かを救うという、優しいメッセージを感じました。「サンタクロースは本当にいるんだ」と信じる少年の純粋さが、物語全体を温かく照らしているようです。
「彗星さんたち」は、新幹線清掃員という、普段あまり光の当たらない職業の人々にスポットを当てた、お仕事小説的な趣のある作品です。主任の鶴田さんが倒れ、残されたメンバーが一丸となって仕事に取り組む姿には、プロフェッショナルとしての誇りと仲間意識が感じられて好感が持てました。そして、清掃中に遭遇する不思議な出来事。年齢の違う姉妹が、後ろの車両に行くほど成長しているように見える…まるで一人の女性の人生を見ているようだ、という仮説。このミステリアスな現象の真相は、鶴田さんが息子夫婦に送った手紙の内容とリンクしていることが示唆されます。直接的な説明はないものの、病床の鶴田さんの想いが、清掃員たちにささやかな奇跡を見せたのかもしれない、と考えると、じんわりと胸が熱くなります。日常の中の非日常、そして人と人との見えない繋がりを描いた、美しい物語だと感じました。
そして、書き下ろしの「後ろの声がうるさい」。これはもう、短編集全体を締めくくる最高のデザートのような作品ですね! これまでの短編に登場したキャラクターたちが、偶然同じ新幹線に乗り合わせるという、ファンにはたまらない展開です。浜田と稲垣、山本、梨央親子、慈郎とジョン(の気配?)、デザイナーの青年(第4章・第5章の人物)、そして清掃員たち…。彼らの会話や様子から、それぞれの物語の「その後」が少しだけ見えたり、別の物語との繋がりが示唆されたりします。例えば、「浜田青年ホントスカ」の稲垣が、新幹線で隣の席の乗客に「相談屋」としてアドバイスをする場面などは、思わずにやりとしてしまいました。各物語が独立しているようでいて、同じ世界のどこかで繋がっている、という伊坂作品ならではの感覚を、この最終話で改めて強く感じさせてくれます。読後感が非常に良く、この一編があることで、「ジャイロスコープ」という短編集がより一層味わい深いものになっていると思いました。
全体を通して、「ジャイロスコープ」は、まさに伊坂幸太郎さんの魅力が凝縮された短編集だと言えます。軽快で洒脱な会話、日常に潜むちょっとした不思議や悪意、予想を裏切る展開、そして根底に流れる人間への温かい眼差し。それぞれの物語は異なるテーマや雰囲気を持っていますが、「選択」「偶然」「人の繋がり」「過去との向き合い方」といった、伊坂作品に共通する要素が随所に散りばめられています。特に、ささやかな偶然や小さな選択が、思いもよらない結果に繋がっていく様子は、読んでいて本当に面白い。人生って、こういう小さな出来事の積み重ねでできているのかもしれないな、なんて思ったりもします。
伊坂さんの長編作品のような、壮大な伏線回収や社会的なテーマを期待すると少し物足りないかもしれませんが、一つ一つの物語の完成度は高く、気軽に読めて、かつ心に残る読書体験ができるはずです。伊坂作品の入門編としても、あるいは長年のファンが著者の新たな一面を発見するためにも、おすすめできる一冊だと感じました。バラエティ豊かな七つの物語を、ぜひ味わってみてください。
まとめ
伊坂幸太郎さんの短編集「ジャイロスコープ」は、七つの異なる物語が収録されており、それぞれが個性的でありながら、伊坂さんらしい世界観で繋がっているような魅力的な作品集でしたね。家出青年と相談屋の奇妙な関係を描く話、バスジャックでの選択と後悔を巡る話、荒廃した世界と謎の生物の話、サンタクロースのプレゼントが繋ぐ偶然の話など、本当に多彩な物語が楽しめます。
各物語は、会話のテンポの良さ、予想外の展開、そして日常に潜む不思議や皮肉といった、伊坂作品ならではの要素が満載です。特に、登場人物たちの何気ない選択や、偶然の出来事が連鎖して予想もしない結末へと繋がっていく様は、読んでいて飽きることがありません。まるで、人生そのものが持つ予測不可能性や、人と人との不思議な縁(えにし)を描いているかのようです。
デビュー15周年記念作品ということもあり、これまでの伊坂作品のファンはもちろん、初めて伊坂さんの作品に触れる方にも、その魅力を存分に感じ取ってもらえる一冊だと思います。読み終えた後には、きっと心の中に温かいものや、少し考えさせられる何かが残るはずですよ。ぜひ手に取って、この七つの伊坂ワールドを体験してみてください。