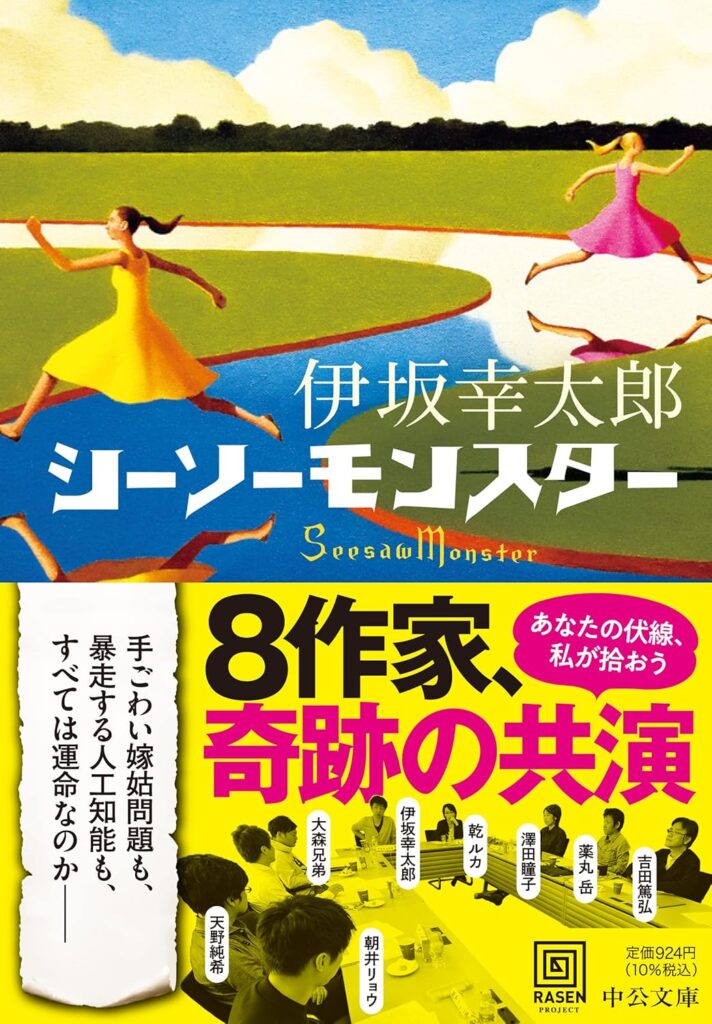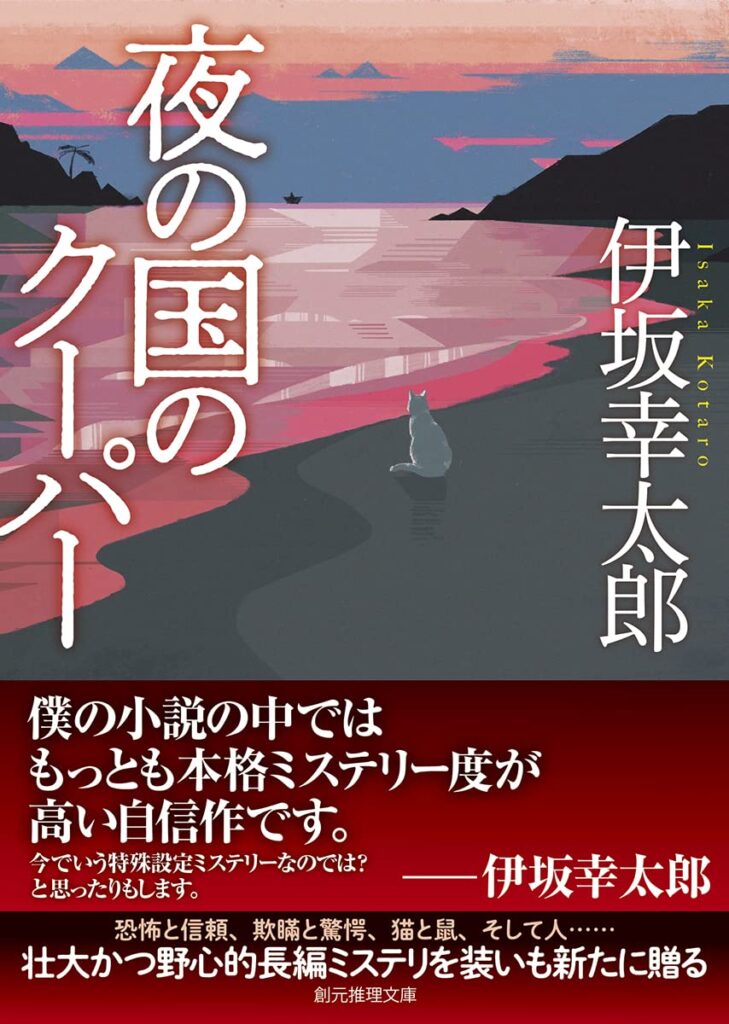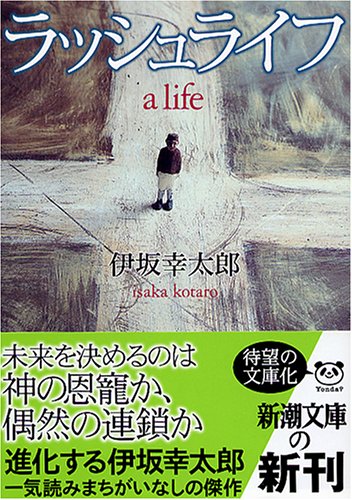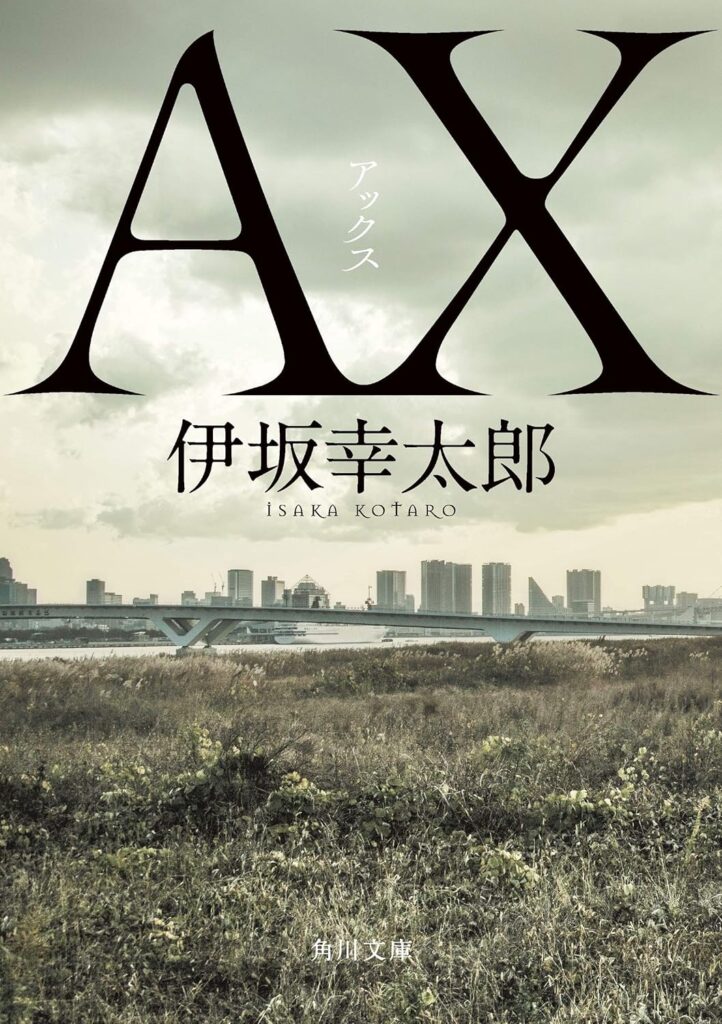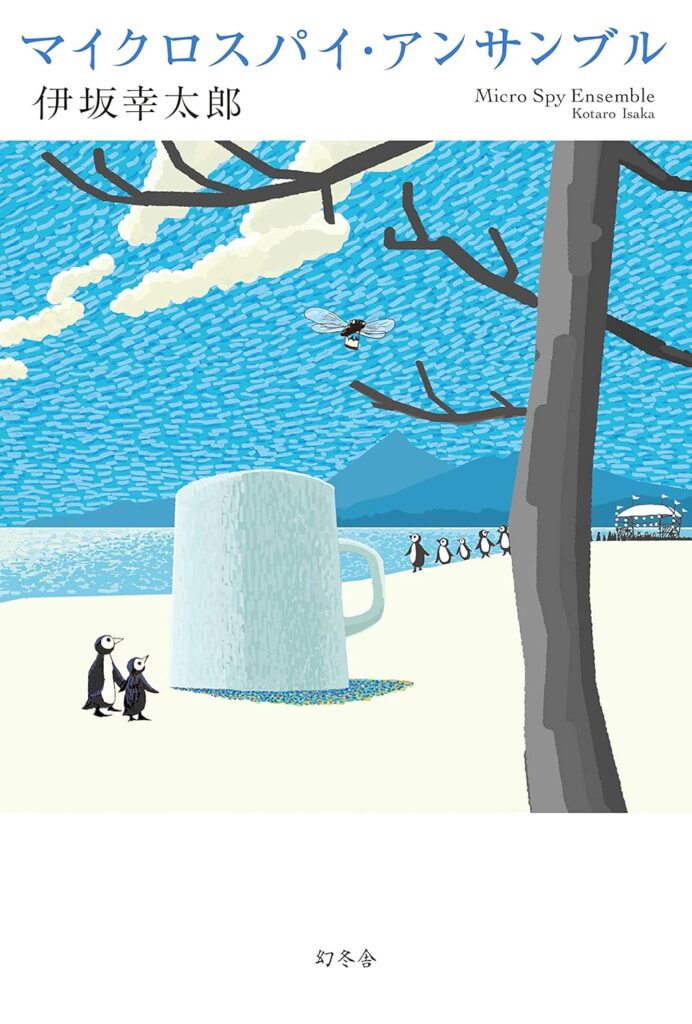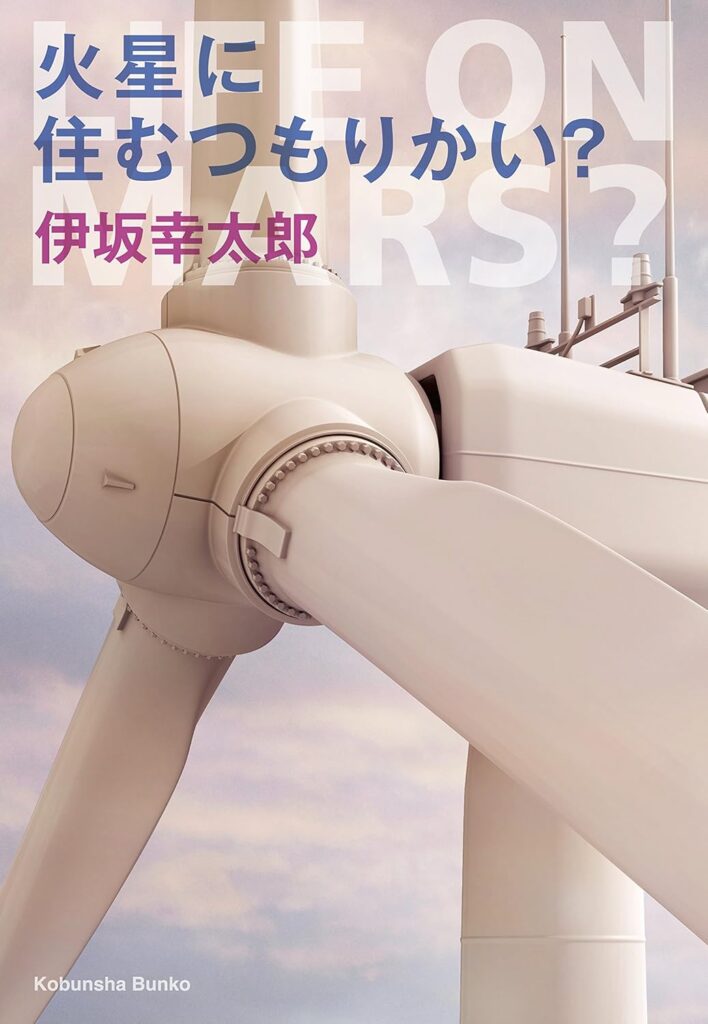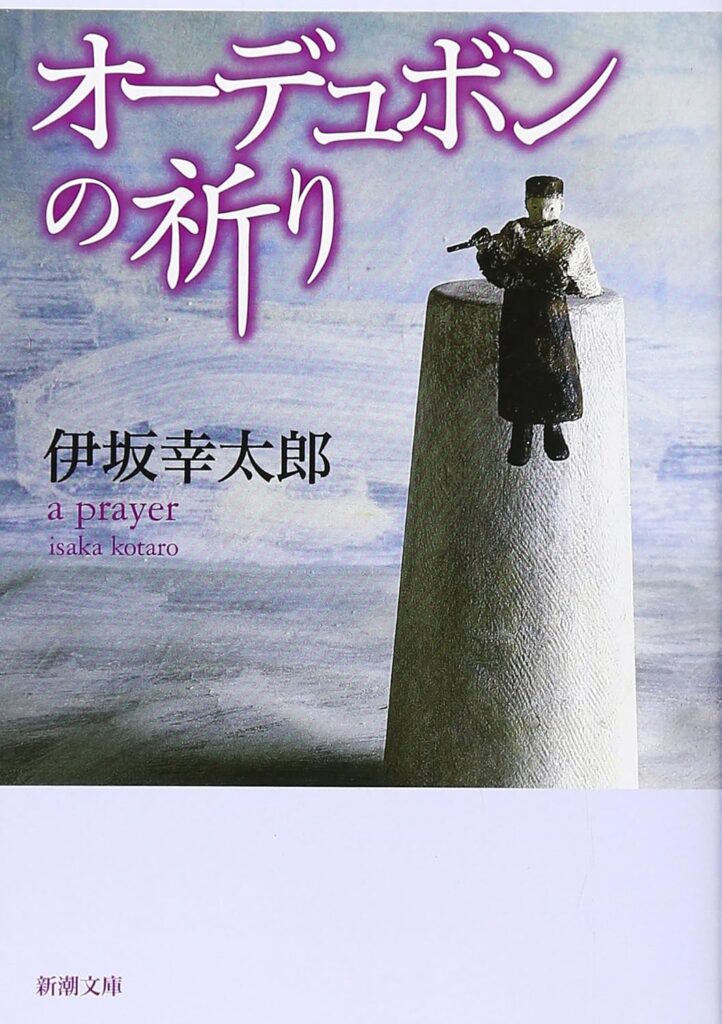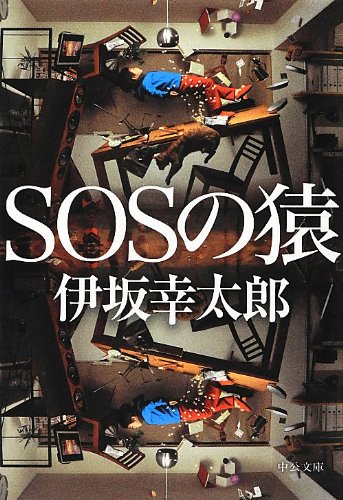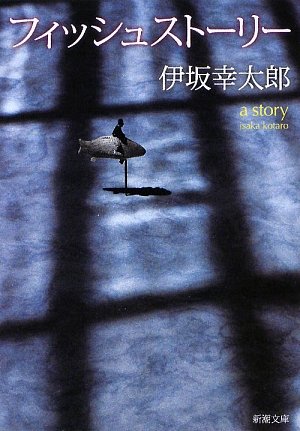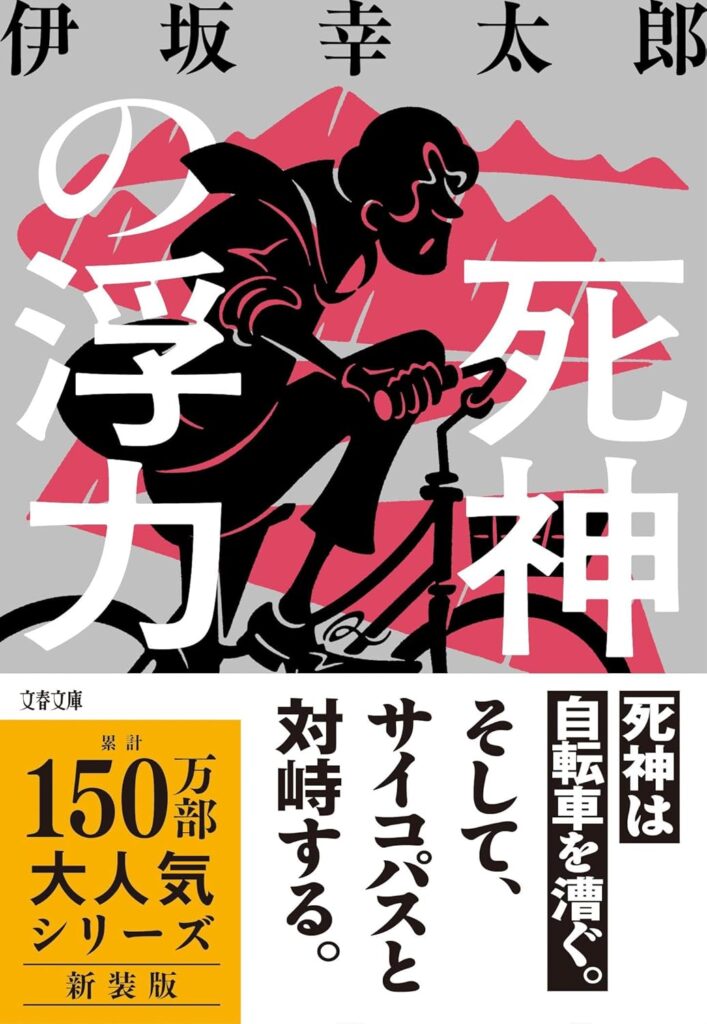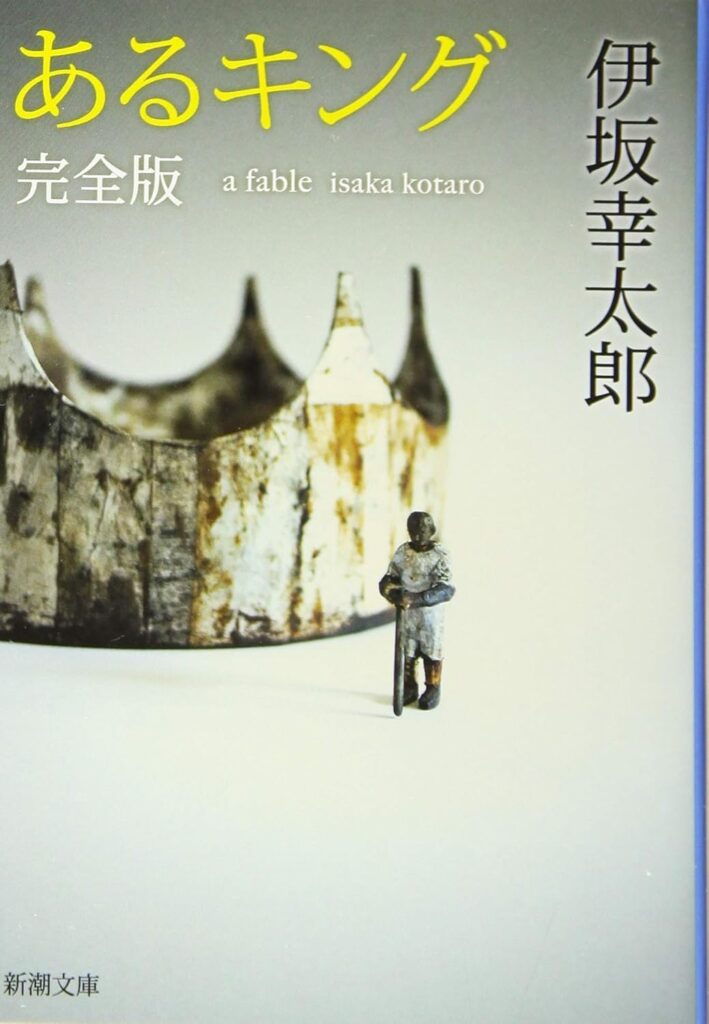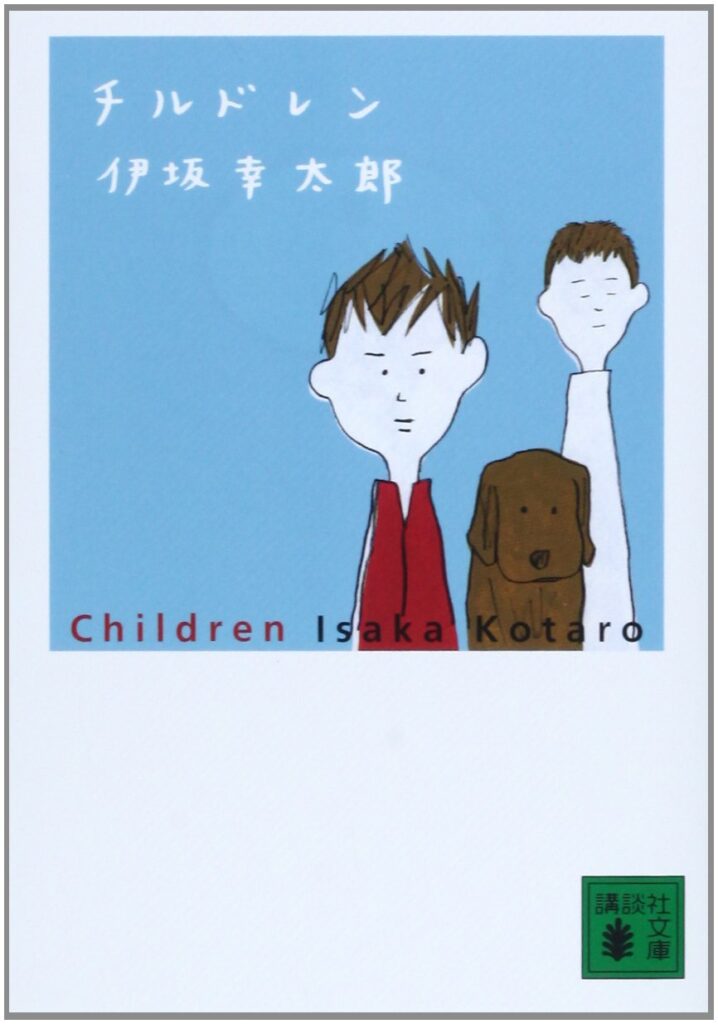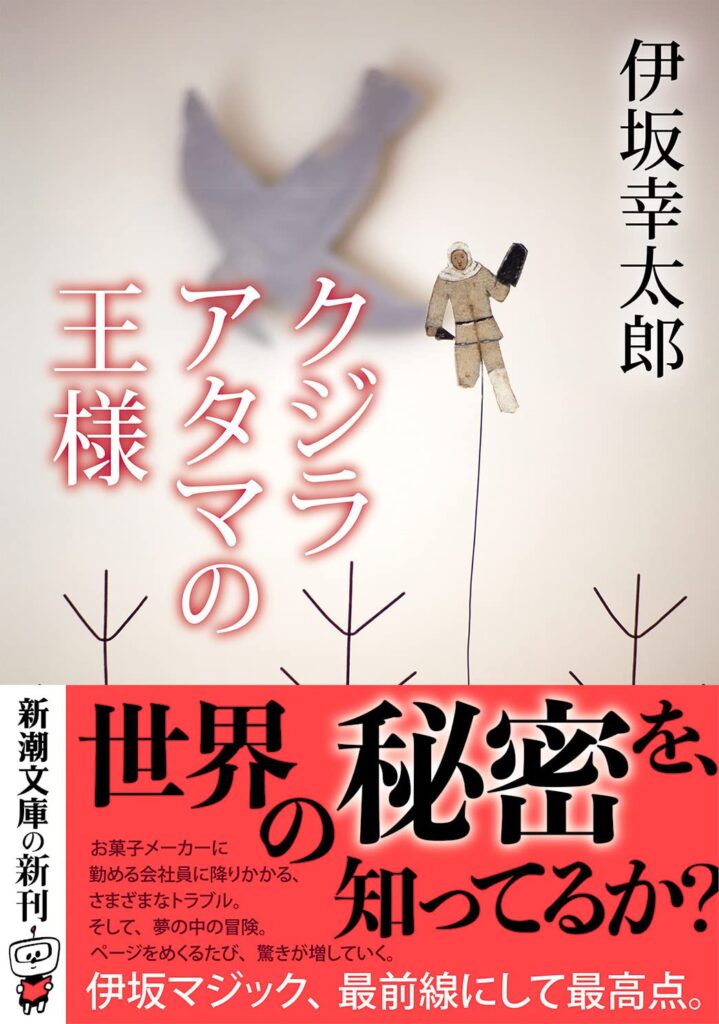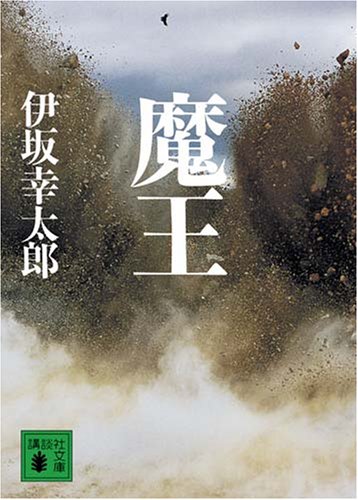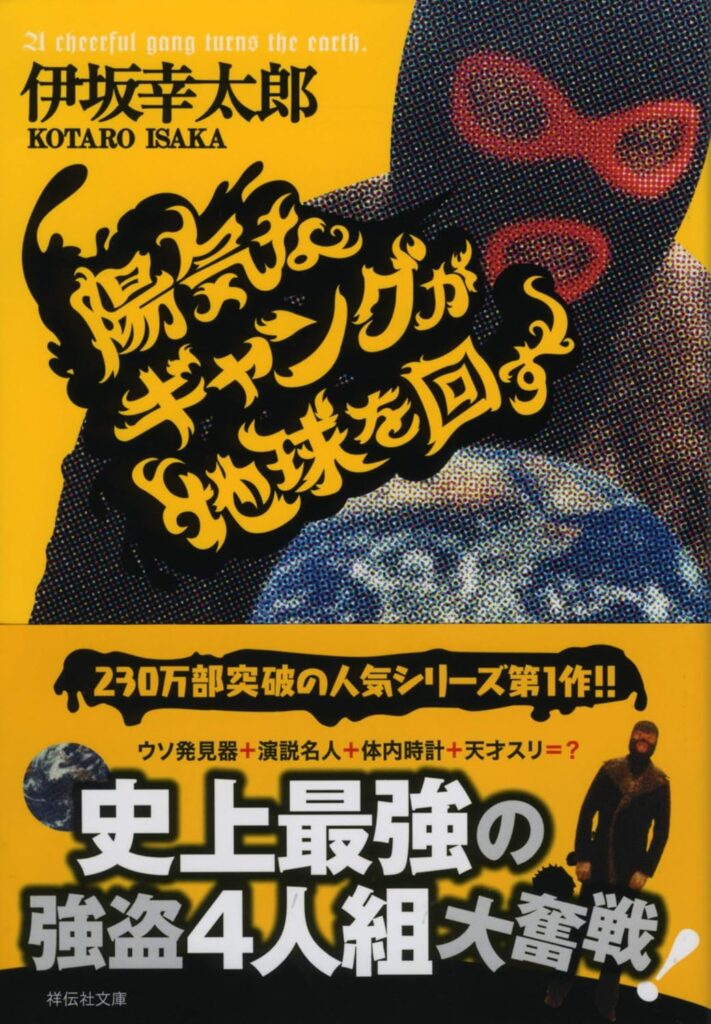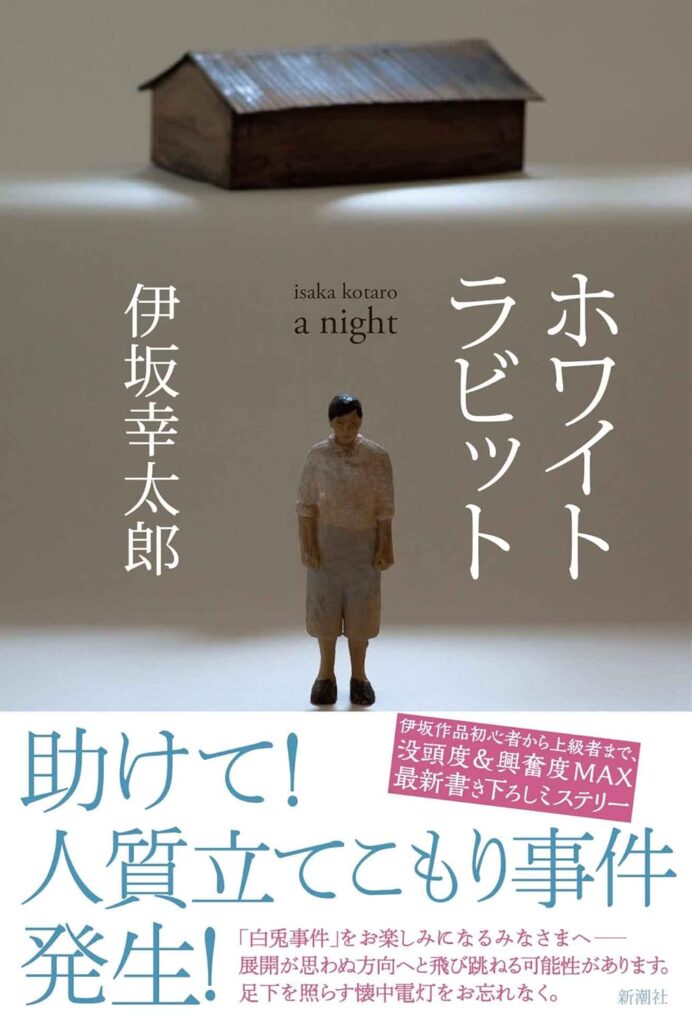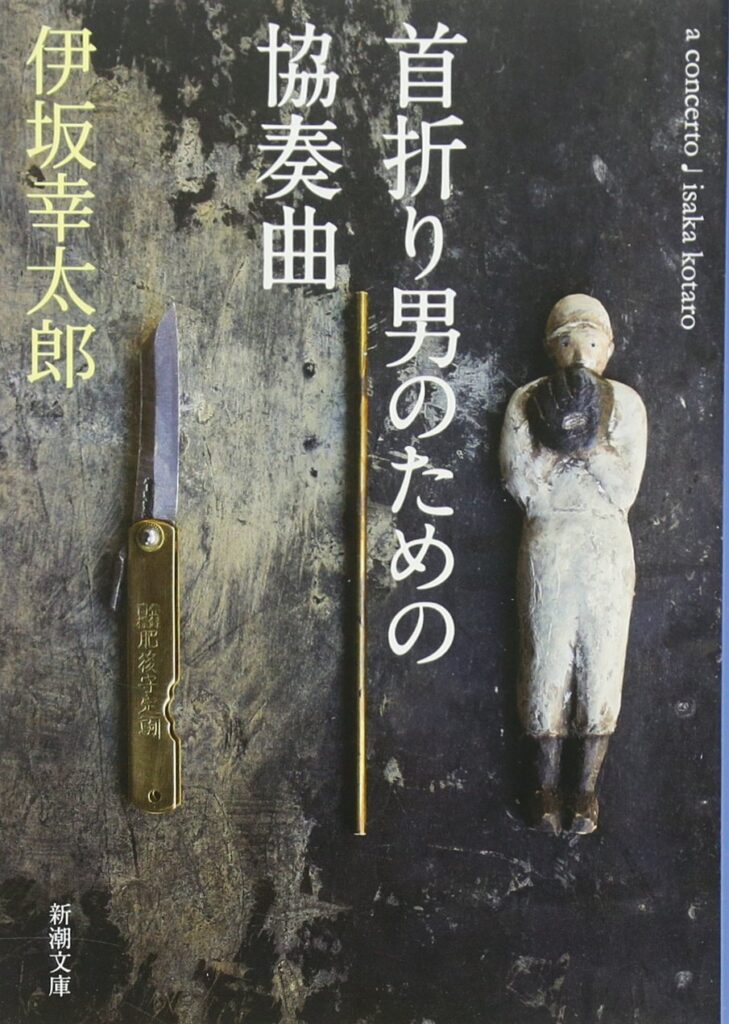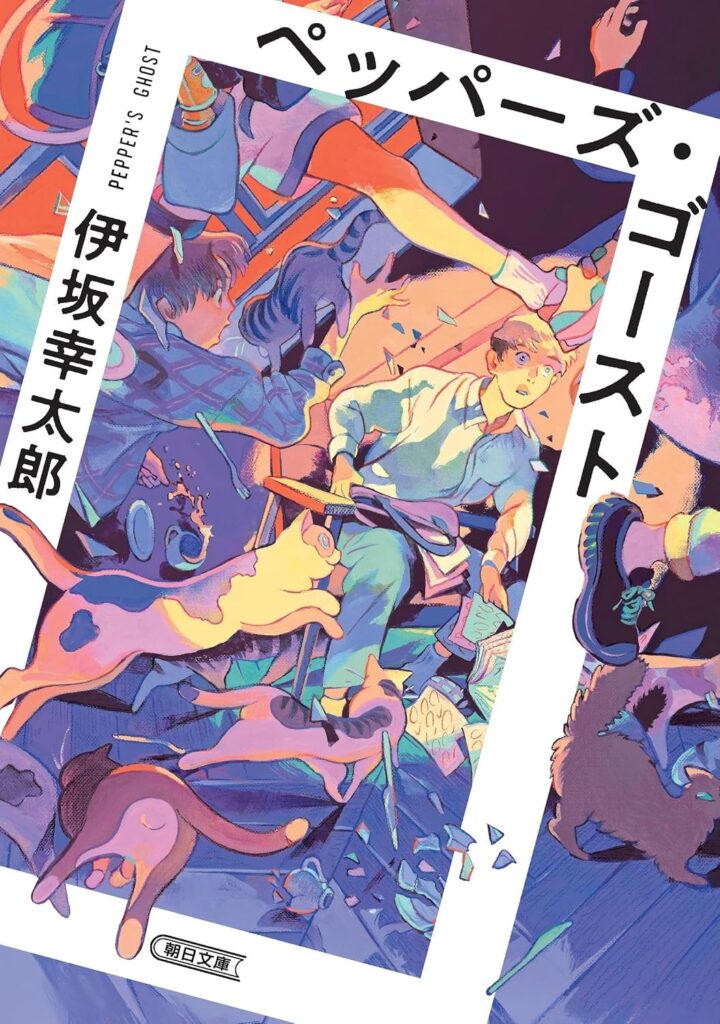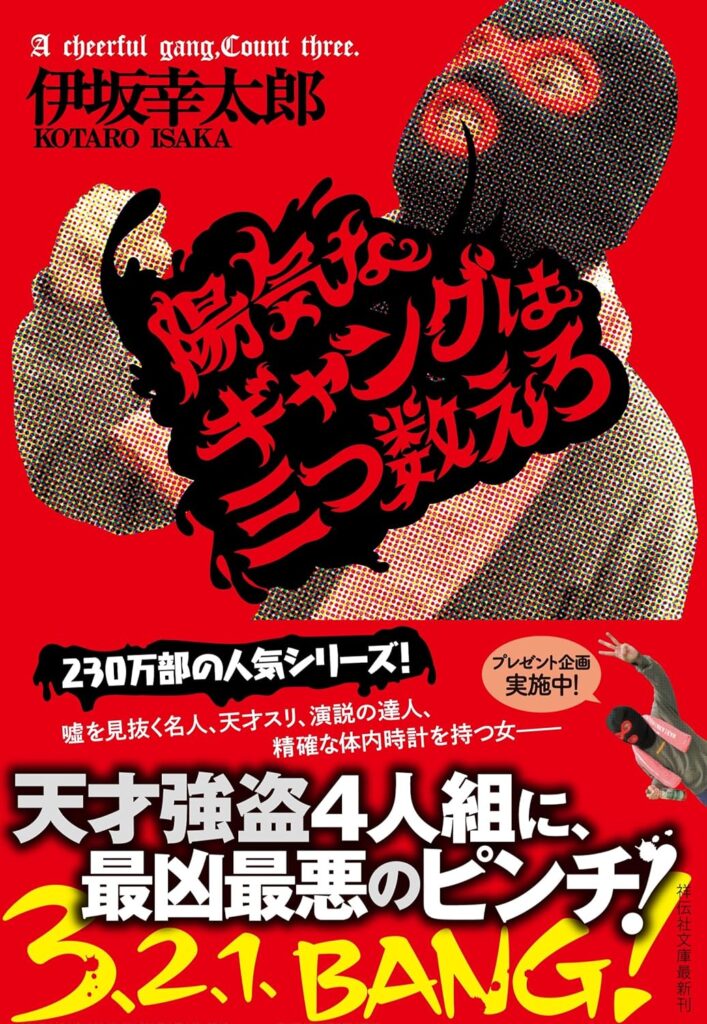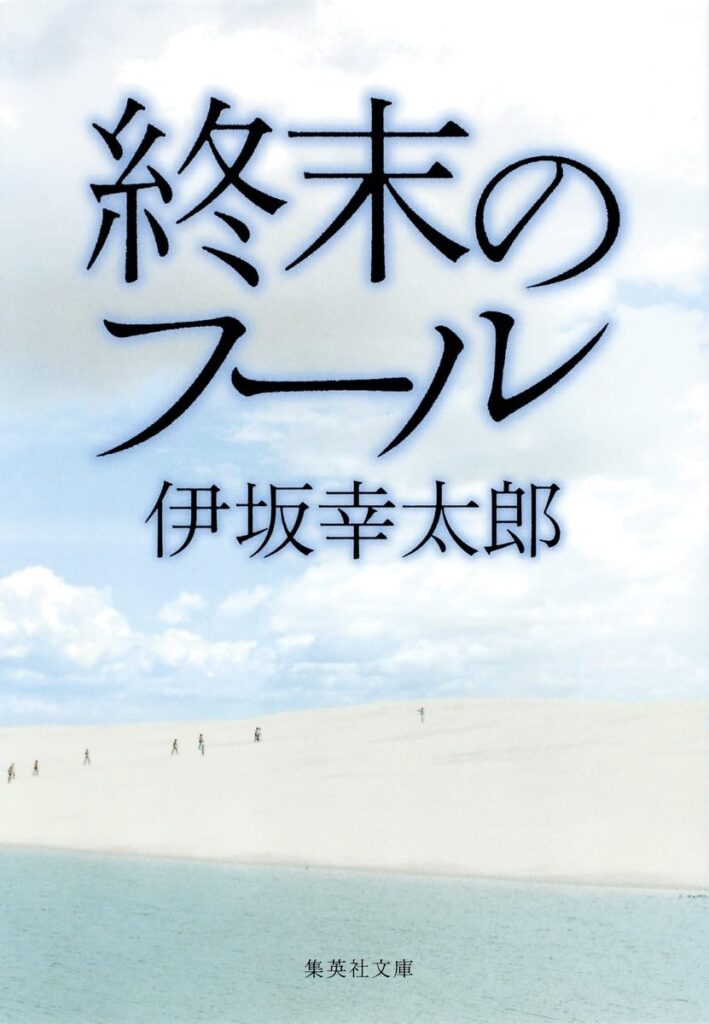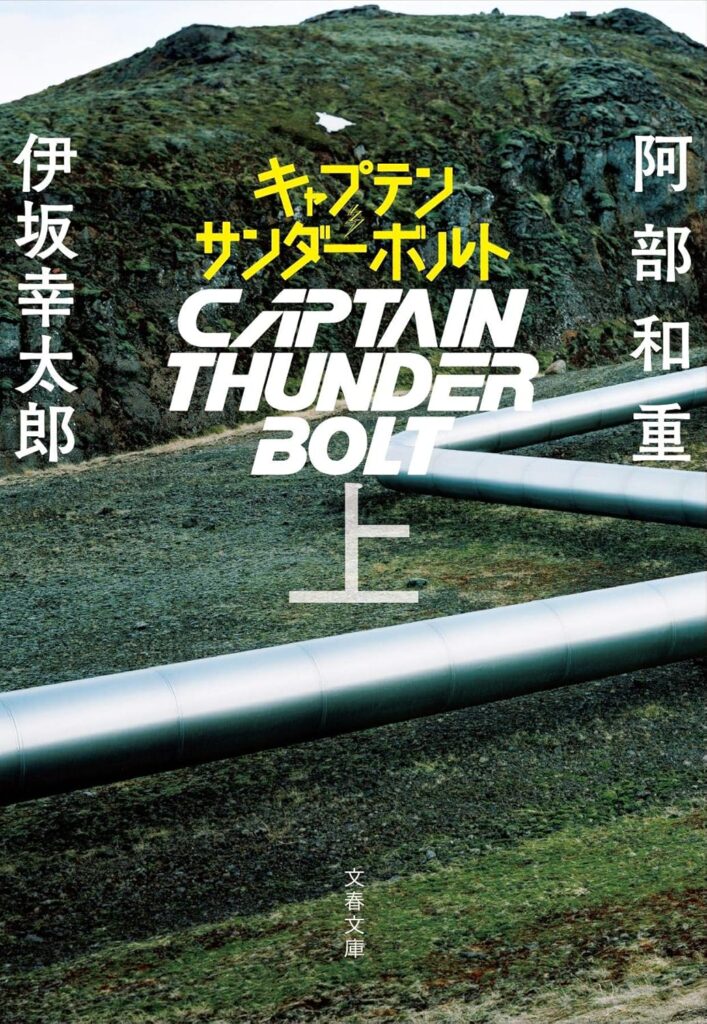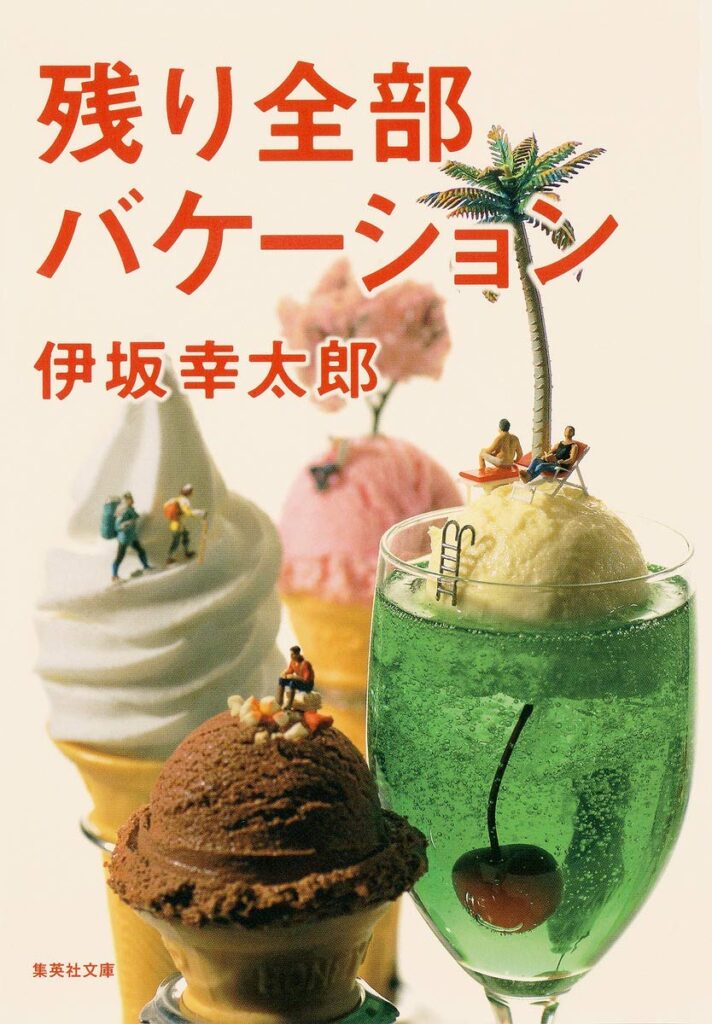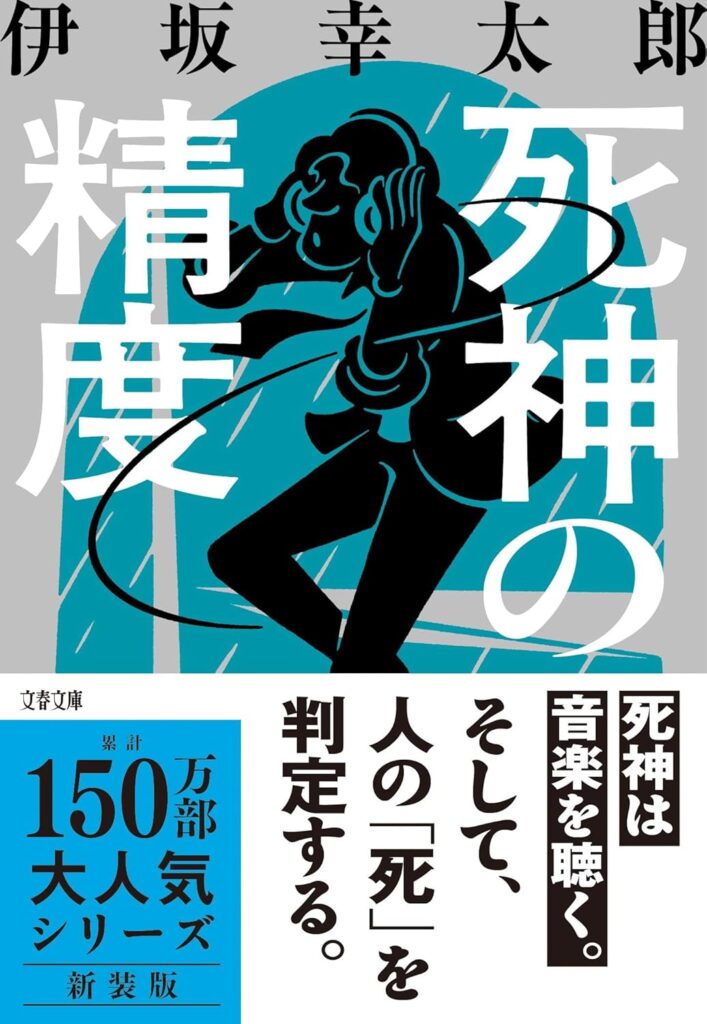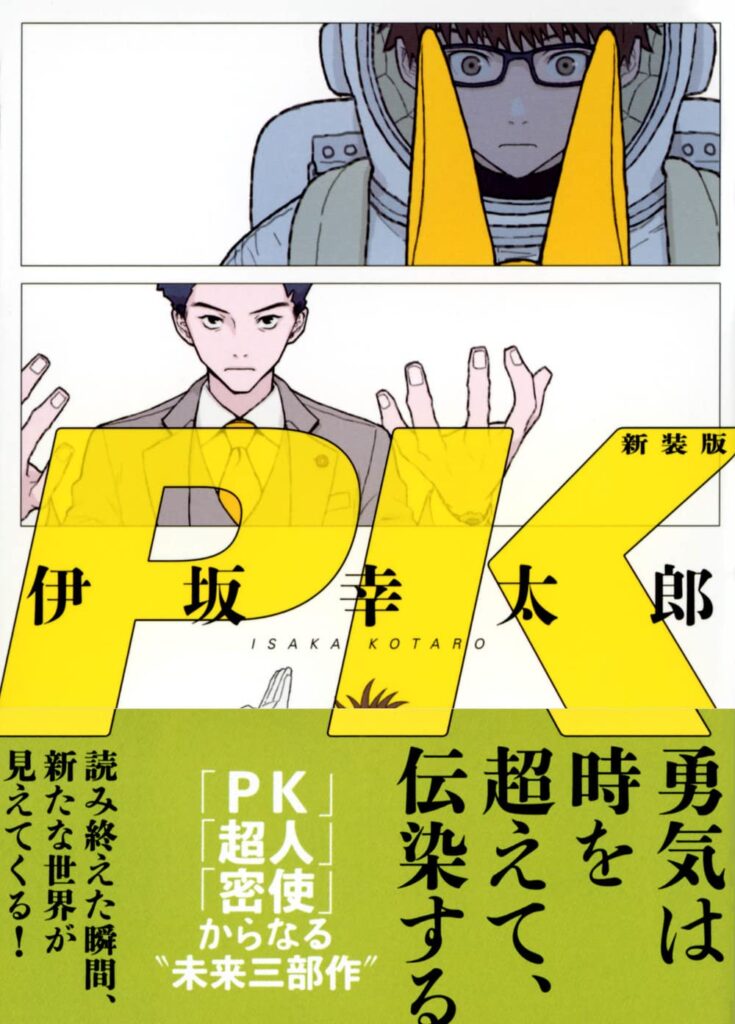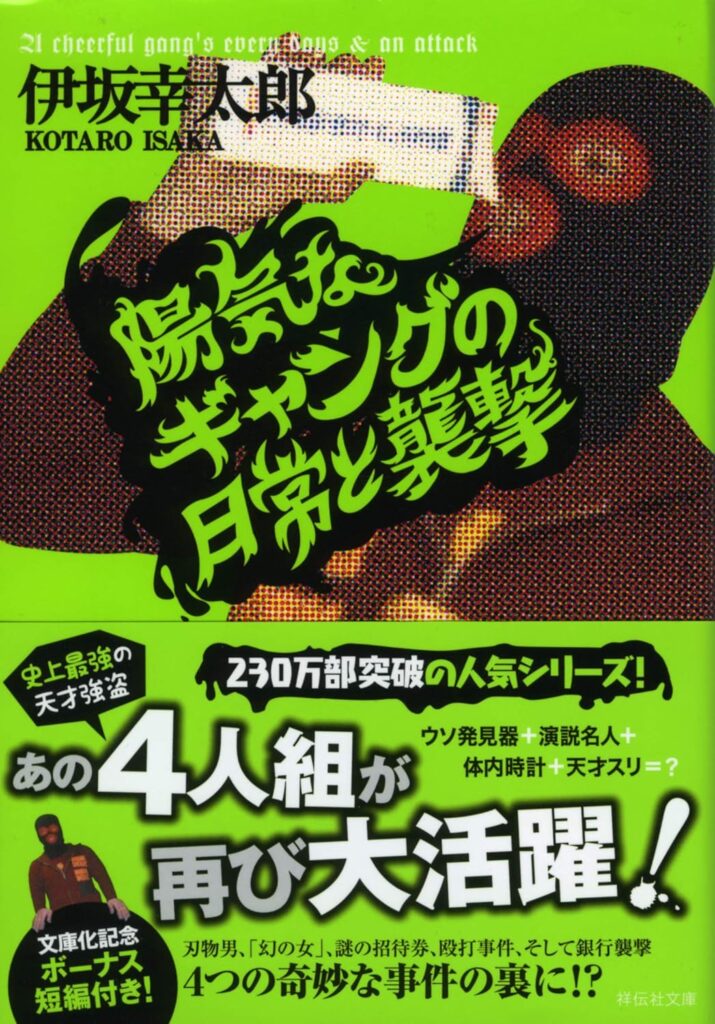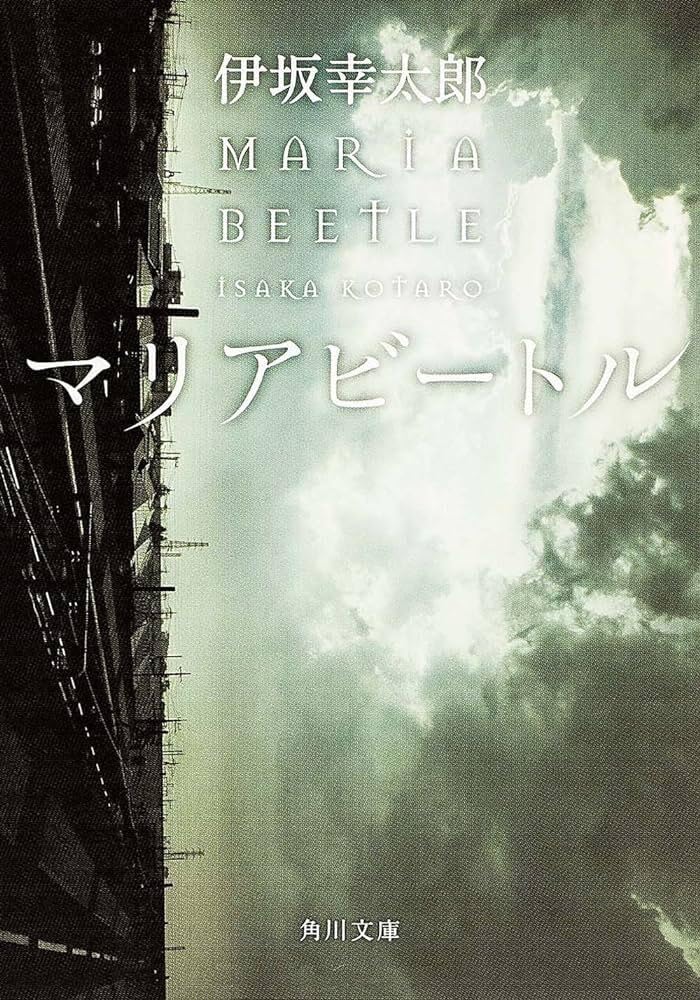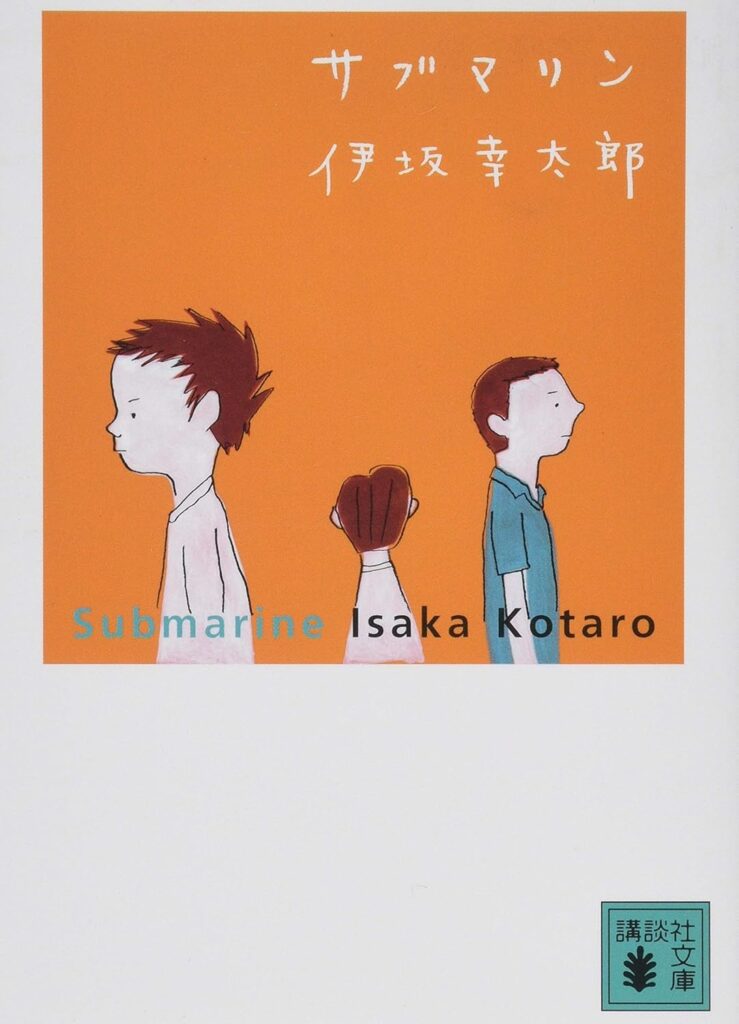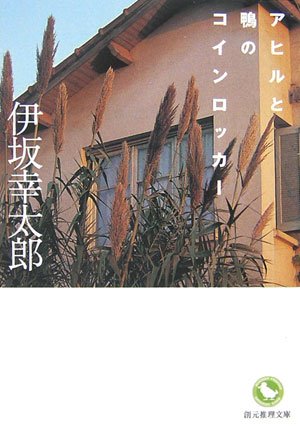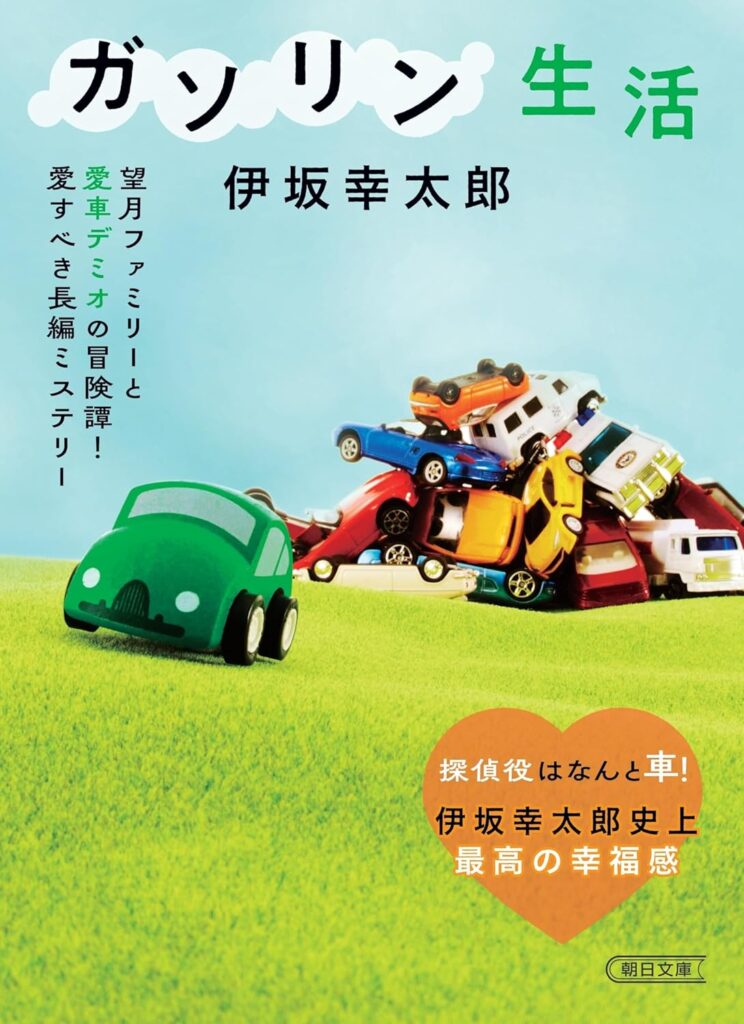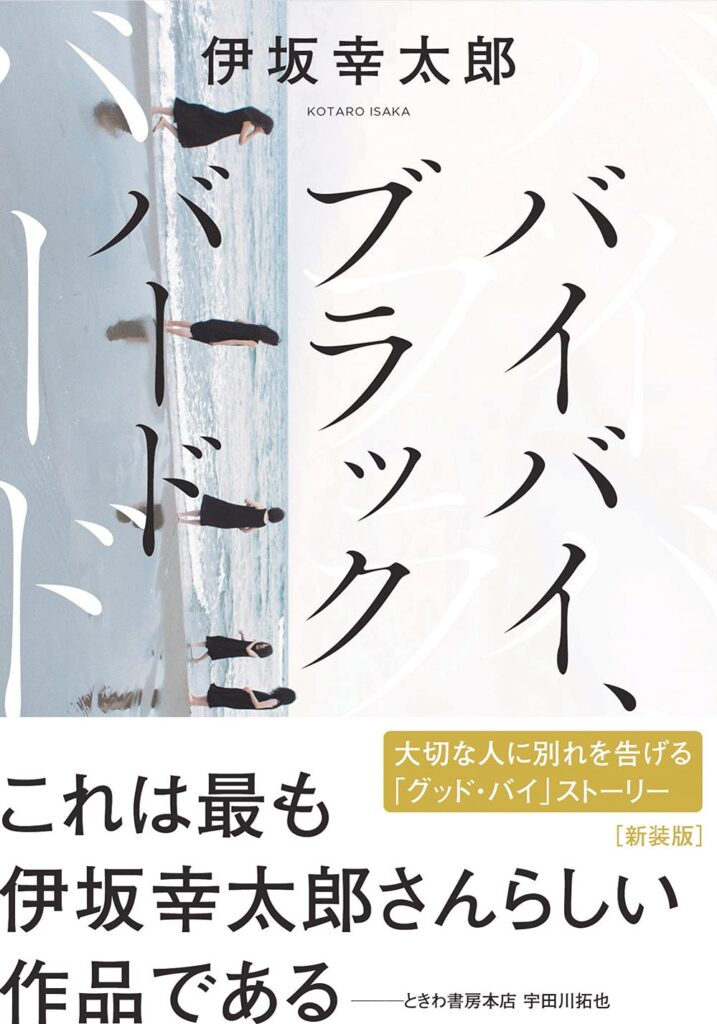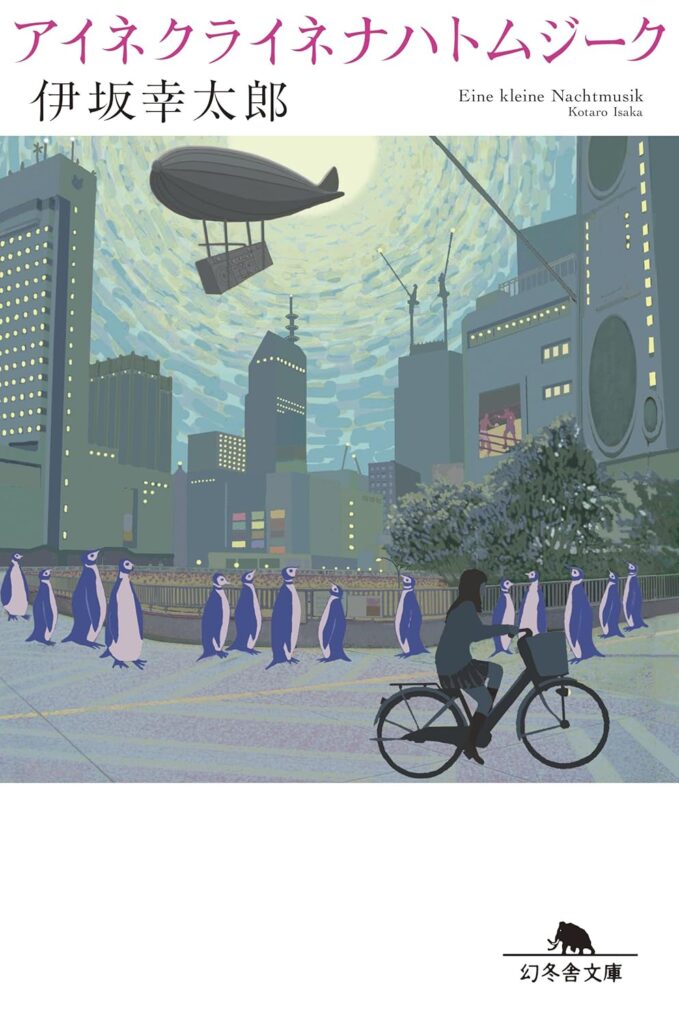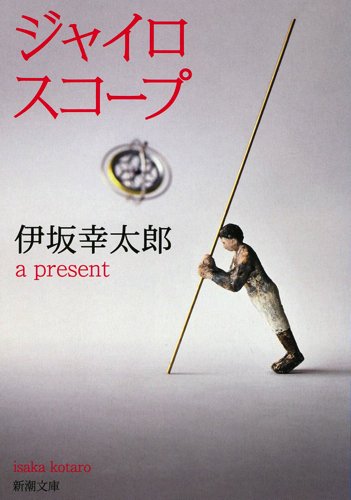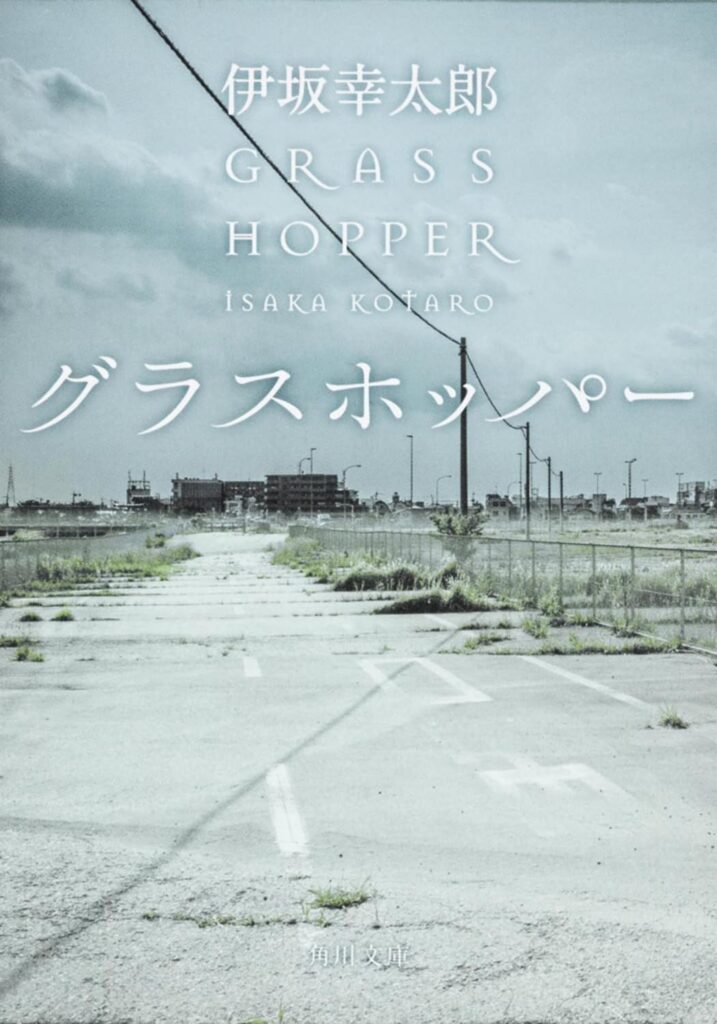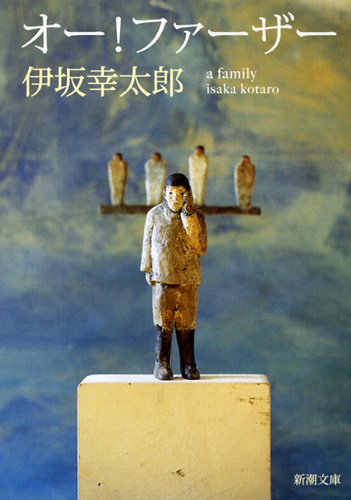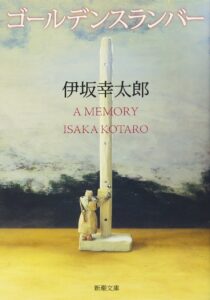 小説「ゴールデンスランバー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、ある日突然、巨大な陰謀の渦中に放り込まれた青年の、必死の逃走劇を描いた作品です。読み始めると、ページをめくる手が止まらなくなること請け合いですよ。
小説「ゴールデンスランバー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、ある日突然、巨大な陰謀の渦中に放り込まれた青年の、必死の逃走劇を描いた作品です。読み始めると、ページをめくる手が止まらなくなること請け合いですよ。
物語の主人公、青柳雅春は、ごく普通の、どこにでもいるような青年です。しかし、新首相の凱旋パレードが行われるその日、彼の日常は音を立てて崩れ去ります。旧友との再会が、まさか壮大な逃亡劇の幕開けになるとは、彼自身、夢にも思っていなかったでしょう。無実の罪を着せられ、たった一人で巨大な権力に立ち向かうことになる彼の運命から、目が離せません。
この記事では、物語の始まりから結末までの流れ、そして私がこの作品を読んで何を感じ、考えたのかを、詳しくお伝えしたいと思います。物語の核心に触れる部分も多く含みますので、まだ作品を読んでいないけれど結末を知りたくない、という方はご注意くださいね。それでは、一緒に「ゴールデンスランバー」の世界へ足を踏み入れてみましょう。
小説「ゴールデンスランバー」のあらすじ
物語は、仙台で行われた新首相・金田貞義の凱旋パレードの日から始まります。宅配ドライバーの青柳雅春は、大学時代の友人である森田慎吾と数年ぶりに再会します。昔話に花を咲かせる二人ですが、森田の様子はどこかおかしいのです。彼は青柳に「お前は首相暗殺犯、オズワルドにされるぞ」と衝撃的な言葉を告げ、逃げるように促します。その直後、パレード中の首相がラジコンヘリの爆発によって暗殺され、森田の乗っていた車も爆発。青柳は、何が何だかわからないまま、警察に追われる身となります。
メディアは一斉に青柳を犯人だと断定し、彼の過去の出来事(アイドルを助けた美談さえも)を悪意的に報道し始めます。青柳は、自分が巨大な組織によって計画的に犯人に仕立て上げられようとしていることを悟ります。頼れる人もなく、街中に設置された監視カメラ「セキュリティポッド」が彼の一挙手一投足を監視する中、絶望的な逃走が始まります。彼はまず、大学時代の後輩である小野一夫に助けを求めますが、無情にも通報されてしまいます。
しかし、すべてが敵ではありませんでした。元恋人の樋口晴子は、テレビで報道される青柳像と、自分が知る彼の些細な癖との違いから、彼の無実を確信します。また、職場の元同僚・岩崎は危険を顧みず、荷物に偽装して青柳を一時的に匿ってくれます。さらに、ひょんなことから出会った連続通り魔「キルオ」こと三浦と名乗る男にも助けられます。彼は青柳に、整形手術で青柳に似せられた偽物が存在することなど、陰謀の一端を教えますが、警察の罠にかかり命を落としてしまいます。
絶体絶命の中、青柳は父親がテレビインタビューで「息子を信じている」と毅然と語る姿に勇気づけられます。そして、病院で出会った裏稼業の男・保土ヶ谷の助言を得て、大胆な反撃を計画します。それは、マスコミを利用し、生中継で自らの無実を訴えるというものでした。しかし、計画は警察の妨害によって失敗に終わります。万策尽きたかに思われた青柳ですが、多くの人々の見えない手助けによって追跡をかわし、最終的にはキルオを整形した医師の手によって顔を変え、別人として生きる道を選ぶのでした。
小説「ゴールデンスランバー」の長文感想(ネタバレあり)
伊坂幸太郎さんの「ゴールデンスランバー」、読み終えた後、しばらく呆然としてしまいました。面白かった、という一言ではとても足りない、様々な感情が渦巻くような、非常に密度の濃い読書体験でしたね。首相暗殺の濡れ衣を着せられた青年・青柳雅春の、たった二日間の逃亡劇。しかし、その二日間には、彼の人生の過去と未来、そして彼を取り巻く人々の想いが凝縮されていました。
まず、この物語の構成が素晴らしいと感じます。現在進行形の緊迫した逃亡劇と、過去の大学時代の友人たちとの何気ない、けれど温かい日々の回想シーンが巧みに織り交ぜられています。この対比があるからこそ、青柳が失った日常の尊さ、そして彼がなぜこれほどまでに多くの人に(知らず知らずのうちに)助けられるのか、その理由が深く伝わってくるのです。何気ない会話、ちょっとした出来事、それらが後になって重要な意味を持ってくる。伊坂作品ならではの伏線の張り方と回収の見事さには、今回も唸らされました。
主人公の青柳雅春。彼は特別なヒーローではありません。むしろ、どこにでもいるような、ちょっとお人好しで、流されやすいところもある普通の青年です。宅配ドライバーとして働き、昔の恋人に未練があったり、ご飯粒を残す癖があったり。そんな彼が、突然「首相暗殺犯」という国家レベルの陰謀に巻き込まれるのですから、その理不尽さ、恐ろしさは計り知れません。街中の監視カメラ、メディアによる一方的な情報操作、警察という巨大な権力。まさに、個人では到底太刀打ちできないような巨大な壁に囲まれてしまいます。
それでも彼は逃げ続ける。なぜか。それは、彼が本来持っている人の良さ、そして彼を信じてくれる人々の存在があったからでしょう。特に印象的なのは、やはり彼を助けようとする人々の姿です。
大学時代の友人・森田慎吾。彼は陰謀に加担させられながらも、最後の最後で友情を選び、青柳を逃がします。「お前はオズワルドにされるぞ」「生きろ、人間関係が残ってりゃ、なんとかなる」という彼の言葉は、物語全体を貫く重要なメッセージとなっています。彼の犠牲があったからこそ、青柳の逃亡は始まった。その重みを、青柳はずっと背負い続けることになります。
元恋人の樋口晴子。彼女が青柳の無実を信じる根拠が、「ご飯粒を残す癖」という非常に個人的で些細なものである点が、とてもリアルで心に響きました。大きな証拠や理論ではなく、その人となりを知っているからこその確信。そして、青柳が昔隠した車の鍵の場所に思い至り、バッテリーを交換しておくという行動力。言葉を交わさずとも伝わる二人の間の信頼関係には、胸が熱くなりました。ラストシーン、整形した青柳に気づきながらも、娘に「たいへんよくできました」の判子を押させる場面は、静かな感動を呼びます。それは、彼の逃亡と選択を肯定する、最高のメッセージだったのではないでしょうか。
そして、異色の存在感を放つのが、連続通り魔の「キルオ」こと三浦です。彼は法や社会の規範からは外れた存在でありながら、独自の論理と行動力で青柳を何度も窮地から救います。なぜ彼が青柳を助けるのか、その動機は最後まで明確には語られませんが、彼の中にある種の「正義」や「反骨精神」のようなものが感じられました。彼が警察の罠にかかり、青柳に「気をつけろよ、青柳!」と叫んで絶命する場面は、衝撃的であり、非常に切なかったです。彼のような存在さえも、この巨大な陰謀の前では無力なのかもしれない、と思わされました。
一方で、人間関係の暗い側面も描かれます。大学の後輩・小野一夫の裏切りは、青柳にとって大きなショックだったでしょう。信頼していた相手からの裏切りは、物理的な危機と同じくらい、精神的に追い詰められるものです。この出来事を通して、人は状況次第で簡単に変わってしまう脆さを持っていること、そして、それでも人を信じようとする青柳の姿が描かれます。
物語のテーマは多岐にわたります。まず、「無実の罪」と「巨大な陰謀」。なぜ青柳が選ばれたのか、その明確な理由は最後まで明かされません。それが逆に、誰にでも起こりうる理不尽さ、現代社会に潜む見えない恐怖を際立たせています。理由なき悪意、組織的な情報操作によって、一個人の人生がいとも簡単に破壊されてしまう。これはフィクションでありながら、決して他人事ではない、と感じさせられます。
「監視社会」への警鐘も鳴らされています。街中に張り巡らされたセキュリティポッドは、安全のためという名目のもと、人々のプライバシーを常に監視しています。それが、一度敵とみなされた人間にとっては、逃げ場のない檻となる。テクノロジーの進化がもたらす光と影を考えさせられました。
「メディアの在り方」も重要なテーマです。青柳は、メディアによってあっという間に極悪非道な犯人に仕立て上げられます。真実かどうかは二の次で、センセーショナルな情報が垂れ流され、大衆のイメージが形成されていく。情報を受け取る側としても、何が真実なのかを見極めることの難しさと重要性を痛感しました。
しかし、この物語は絶望だけを描いているわけではありません。絶望的な状況の中にも、確かな「友情」「信頼」「家族愛」そして「人間の善意」が光として描かれています。青柳の父親が、世間の非難に晒されながらもテレビカメラの前で「息子を信じます」と毅然と言い放つ姿。岩崎のように、損得勘定抜きで手を差し伸べてくれる元同僚。顔も知らない花火職人が、昔の約束を覚えていて打ち上げてくれる花火。そうした人々の小さな善意が連鎖し、青柳の逃亡を支えるのです。それはまるで、暗い夜空に打ち上げられた大輪の花火のように、一瞬ではあるけれど、確かな希望の光を投げかけるのです。
ビートルズの楽曲「Golden Slumbers」が、物語全体に印象的に使われているのも見逃せません。”Once there was a way to get back homeward”(かつて故郷へ帰る道があった)という歌詞が、青柳の失われた日常への郷愁と、それでも前へ進もうとする決意を象徴しているように感じました。音楽が、物語に深みと情緒を与えています。
結末について。青柳は結局、無実を証明することはできませんでした。そして、整形手術を受け、別人として生きていくことを選びます。事件の真相、つまり誰が何の目的でこの陰謀を企てたのかは、最後まで明かされません。この「解決しない」結末に、もどかしさを感じる読者もいるかもしれません。しかし、私はこの終わり方が「ゴールデンスランバー」らしいと感じました。
巨大な悪に打ち勝つのではなく、その手から逃れ、しぶとく生き延びること。そして、自分を助けてくれた人々の想いを胸に、新しい人生を歩み始めること。それは、完全な勝利ではないかもしれないけれど、人間としての尊厳を守り抜いた、一つの力強い「答え」なのではないでしょうか。彼は「たいへんよくできました」の判子を手に、過去を背負いながらも、未来へと歩き出すのです。
この作品は、息もつかせぬスリルとサスペンスに満ちている一方で、人間関係の温かさや切なさ、そして社会に対する鋭い問いかけが込められた、非常に多層的な物語です。読み返すたびに、新たな発見や感動がある。そんな深みを持った傑作だと、私は思います。青柳雅春という一人の青年の逃亡劇を通して、私たちは、生きること、信じること、そして困難な状況でも失われない人間の絆について、改めて考えさせられるのです。
まとめ
伊坂幸太郎さんの「ゴールデンスランバー」は、首相暗殺の濡れ衣を着せられた青年・青柳雅春の、息もつかせぬ二日間の逃亡劇を描いた物語です。この記事では、その波乱万丈な物語の筋書きを、結末の核心に触れながらご紹介しました。平凡な日常から一転、巨大な陰謀と国家権力に追われる身となった青柳の運命を追体験していただけたでしょうか。
また、この作品を読んで私が感じたこと、考えたことを詳しく述べさせていただきました。絶望的な状況下でも失われない友情や信頼、家族の絆。そして、監視社会やメディア報道の危うさといった、現代社会に通じるテーマ。スリリングな展開の中に、人間の持つ温かさや弱さ、そして強さが巧みに描き出されています。読み終えた後には、きっと様々な想いが胸に残ることでしょう。
青柳は、多くの人々の助けを得て生き延び、別人として新たな人生を歩み始めます。事件の真相は闇に葬られたままですが、彼の選択と、彼を支えた人々の想いは、静かな感動を与えてくれます。「ゴールデンスランバー」は、単なるエンターテイメントに留まらず、私たち自身の生き方や社会との関わり方についても深く考えさせてくれる、読み応えのある一冊です。未読の方はもちろん、再読を考えている方にも、この記事が何かの参考になれば幸いです。