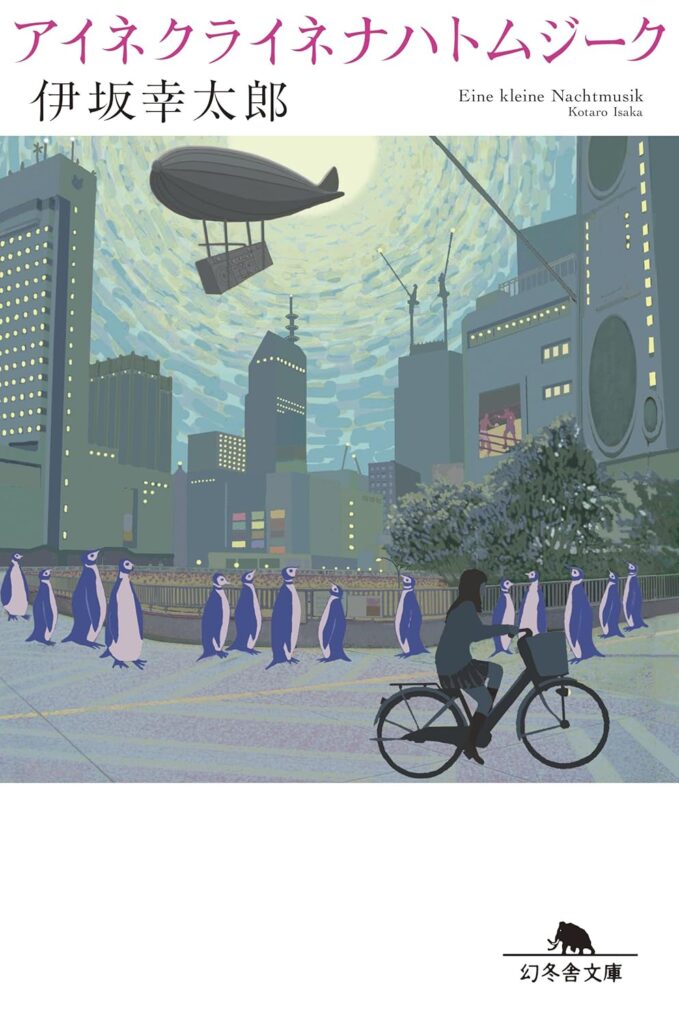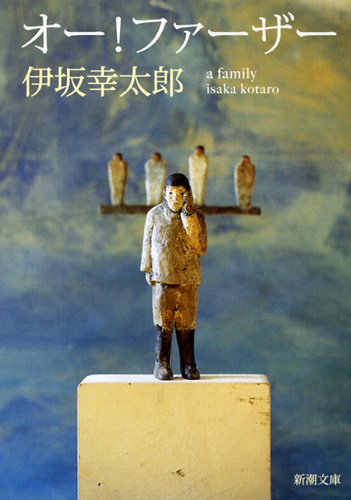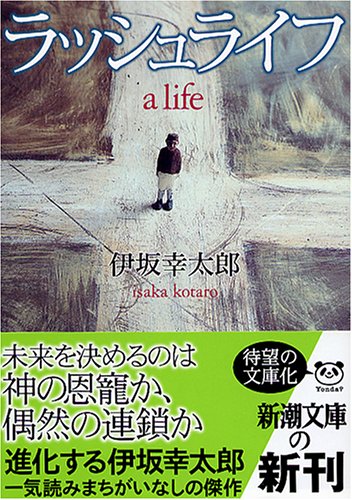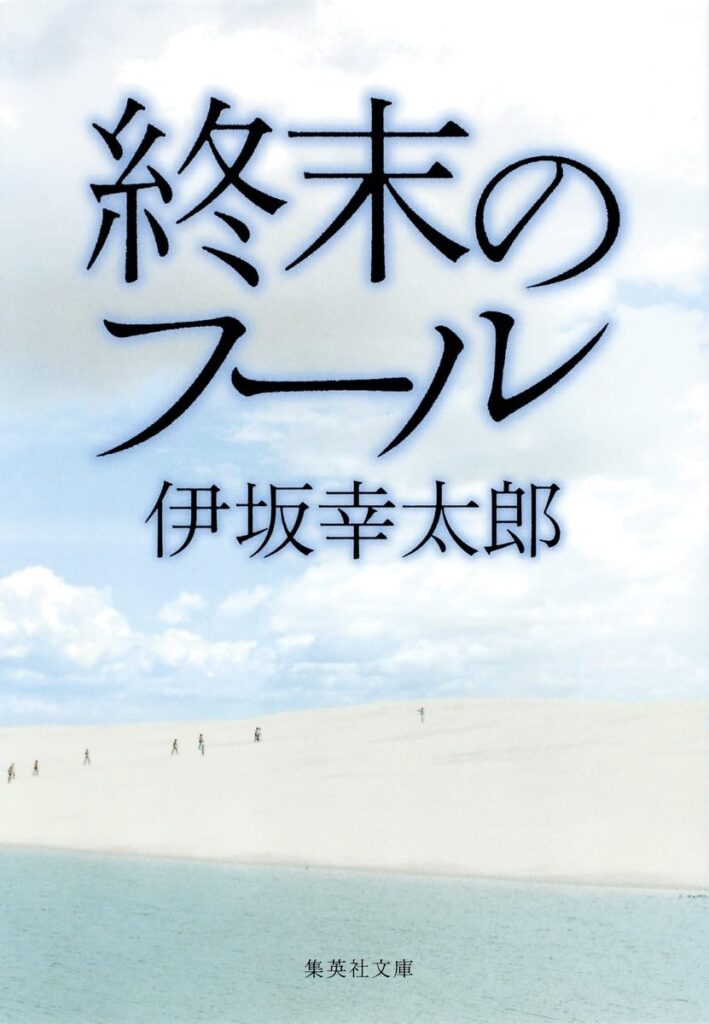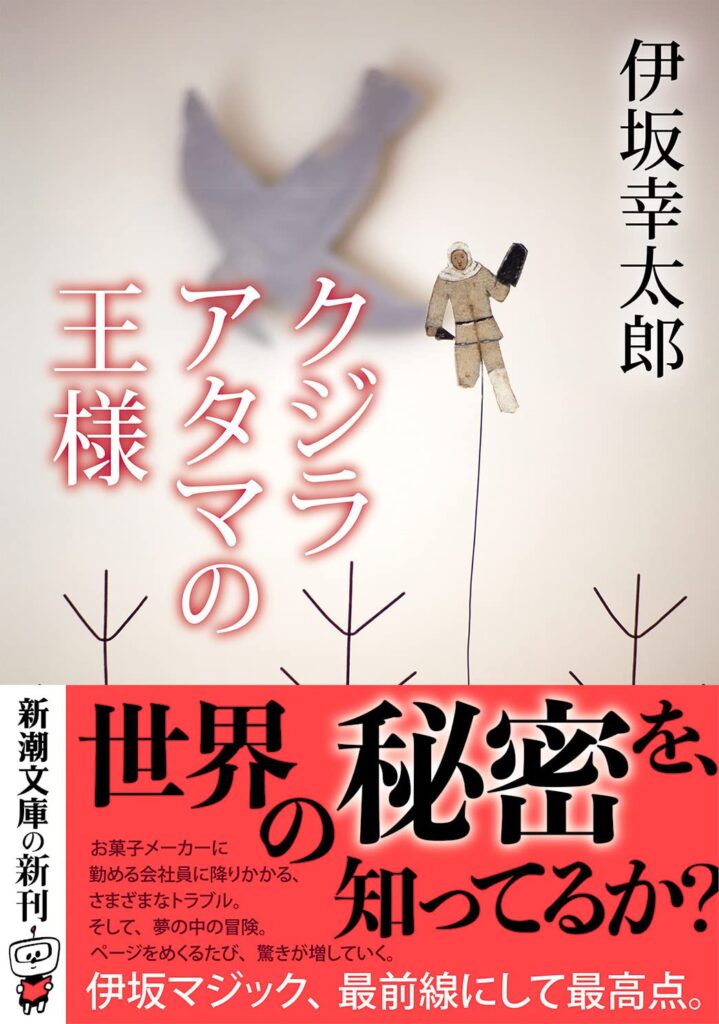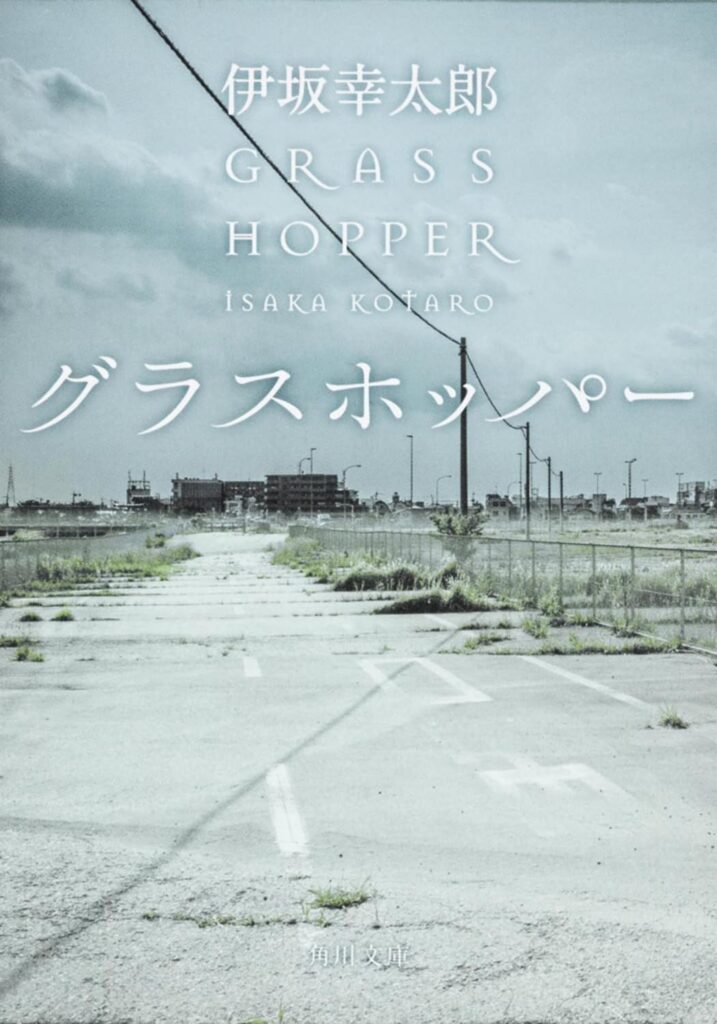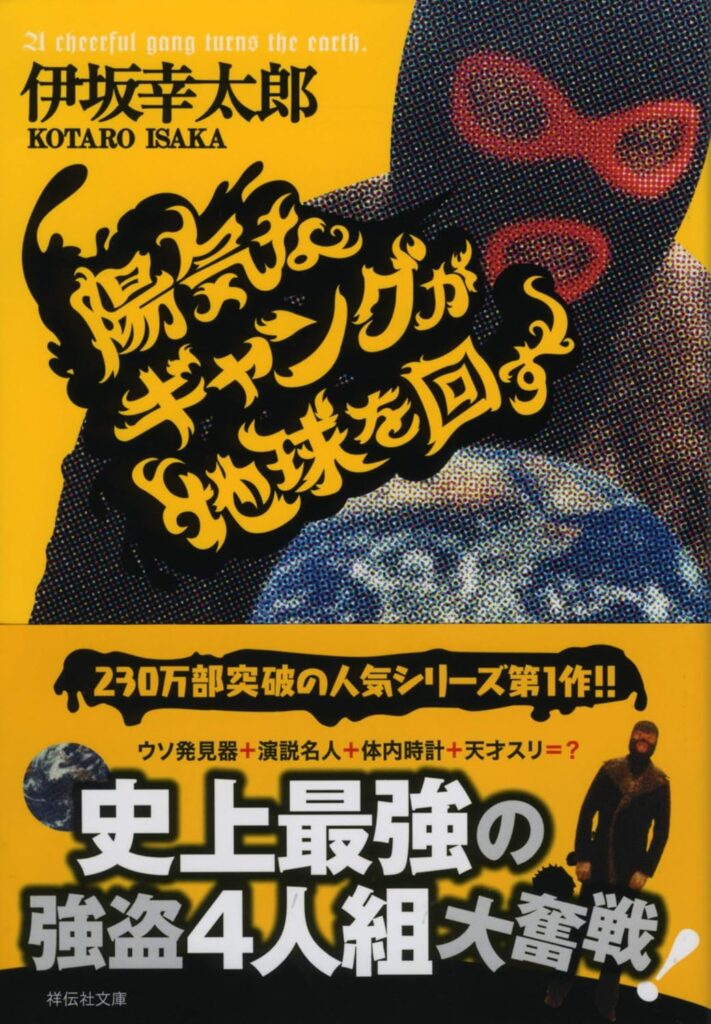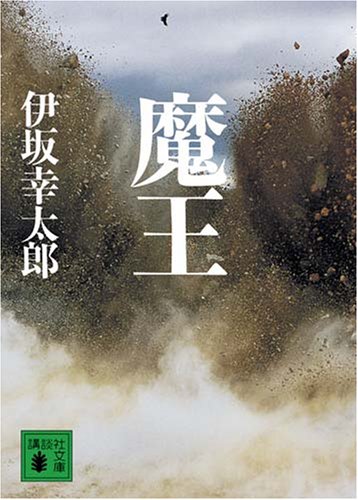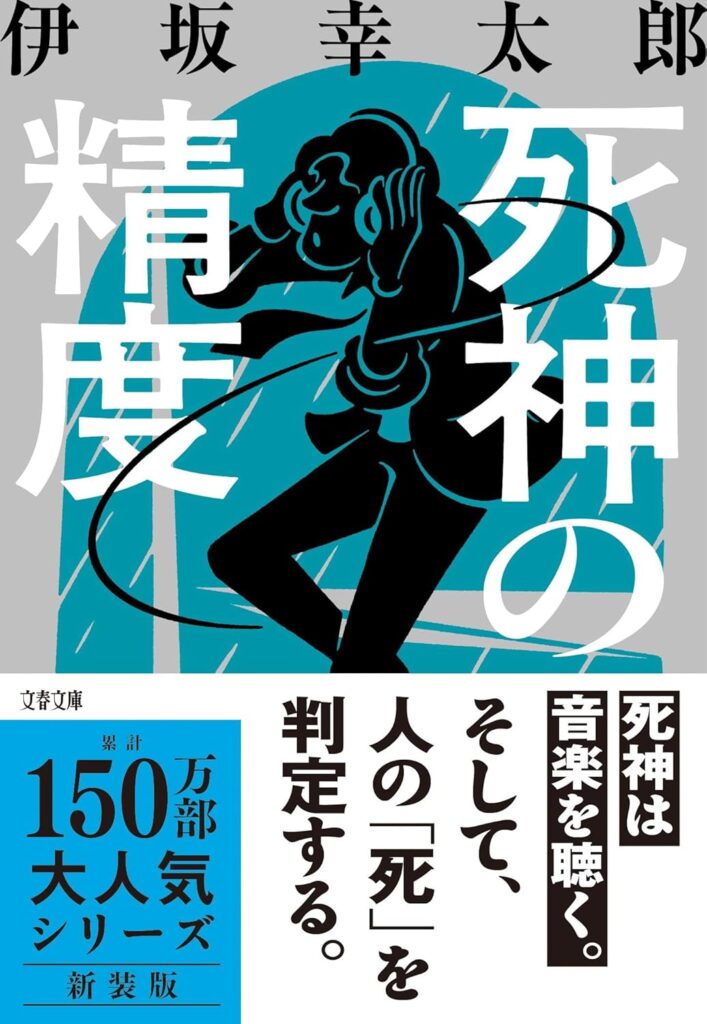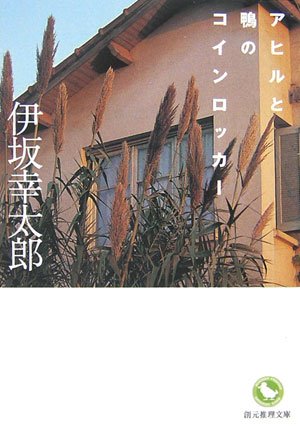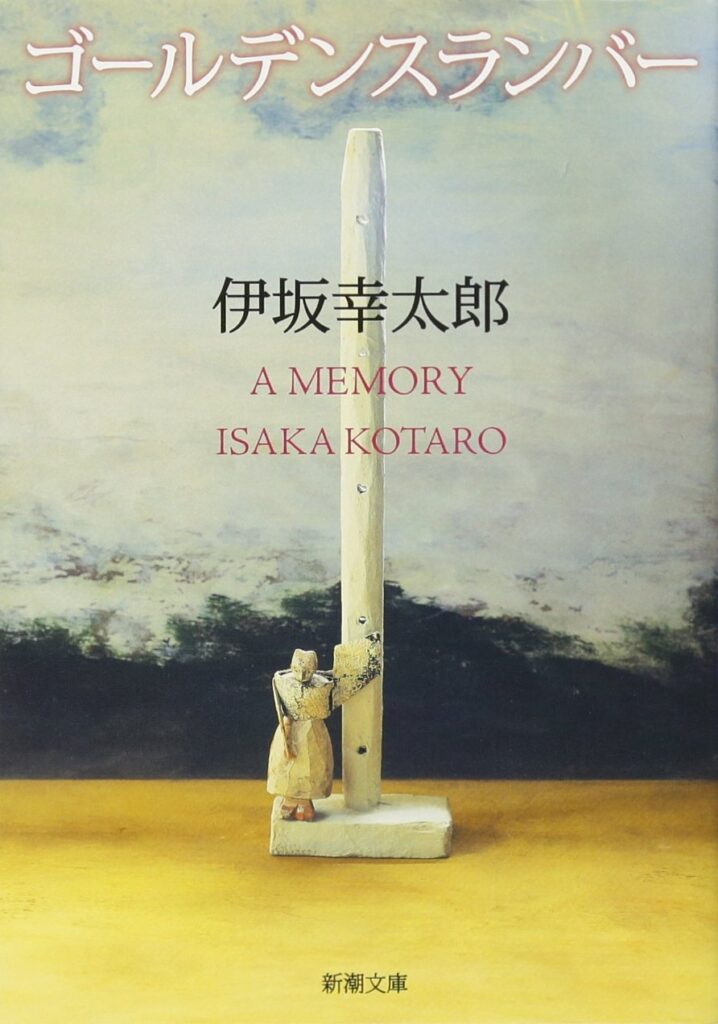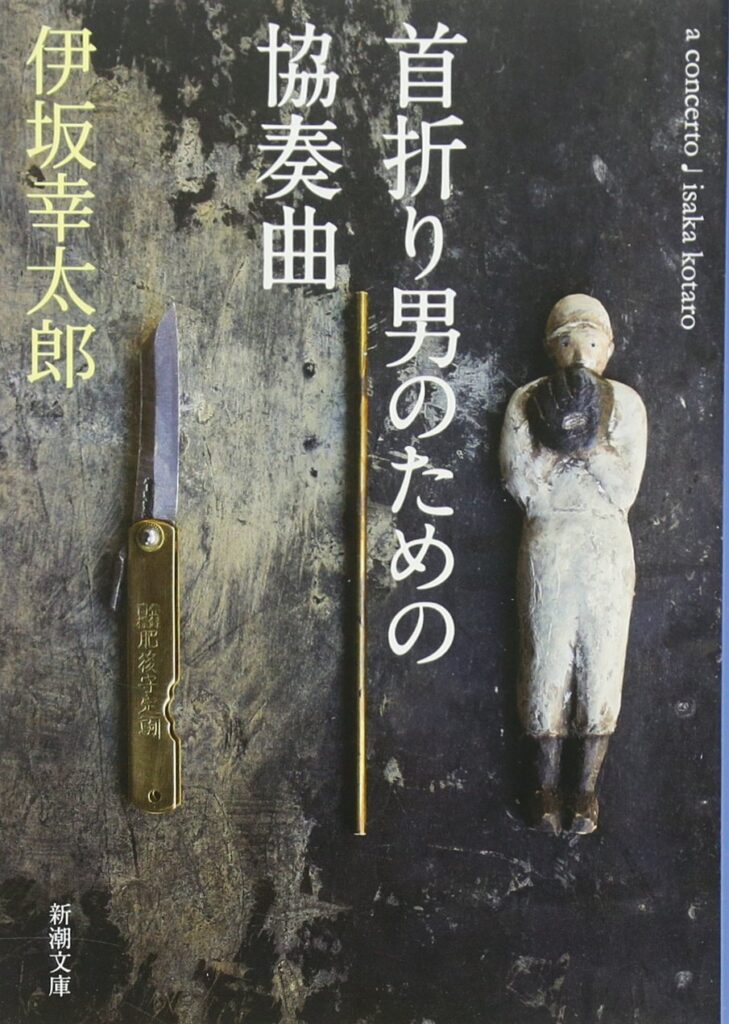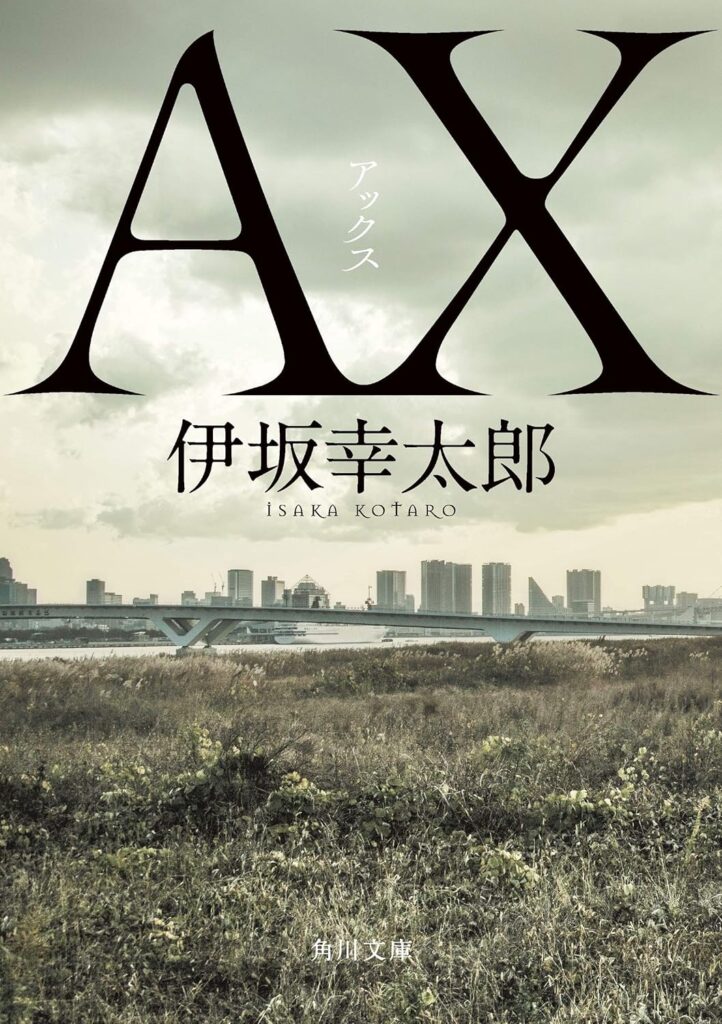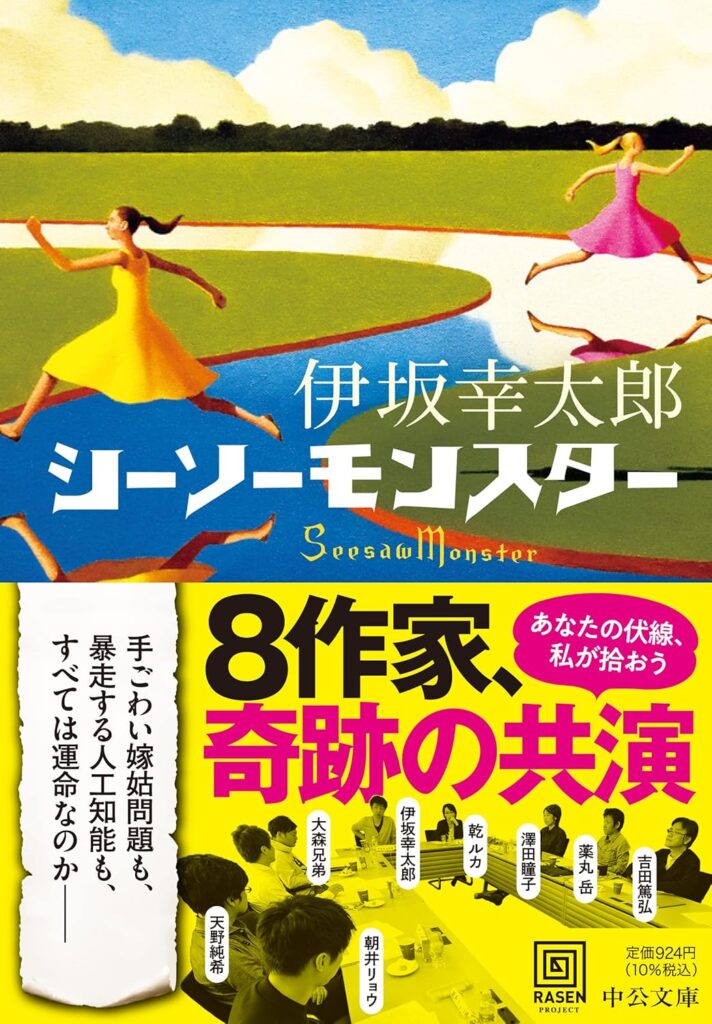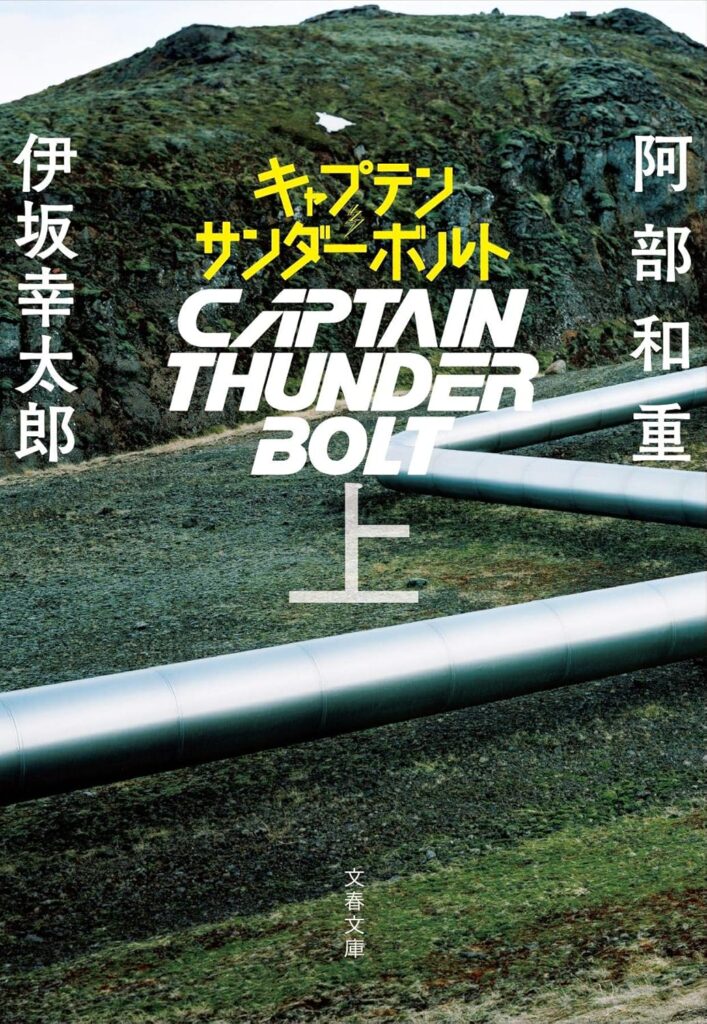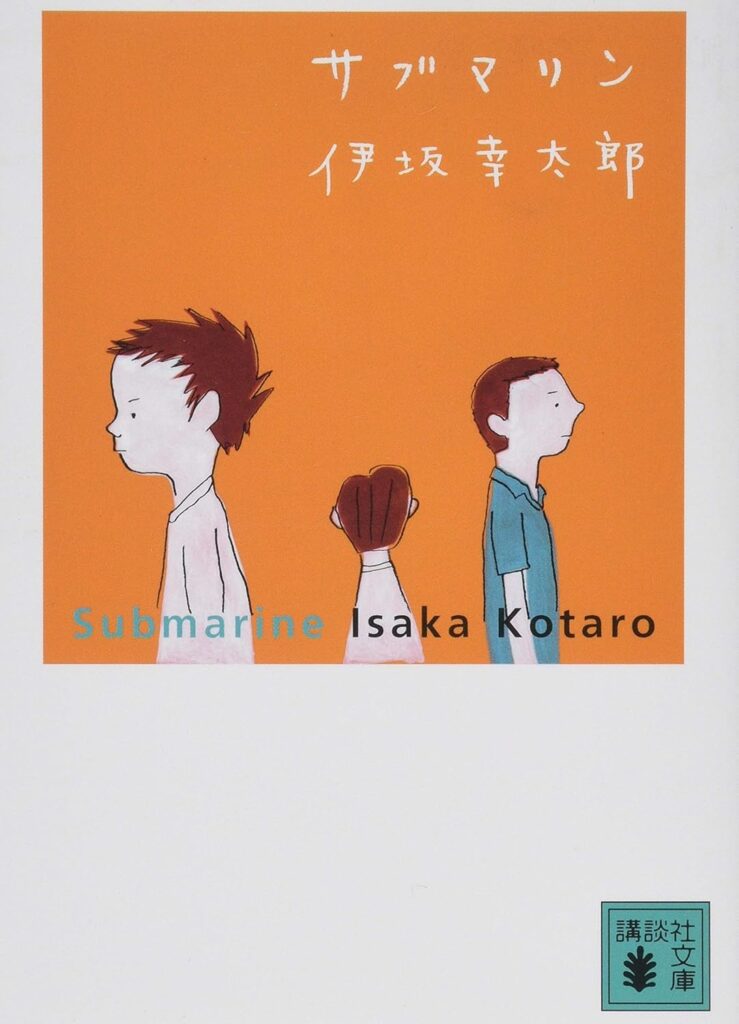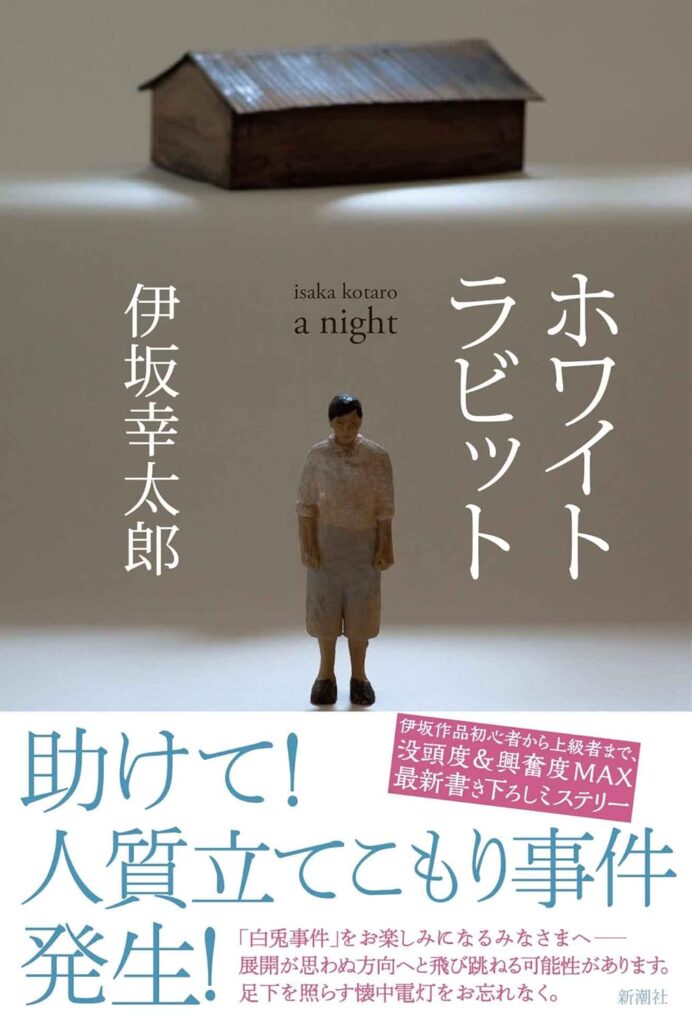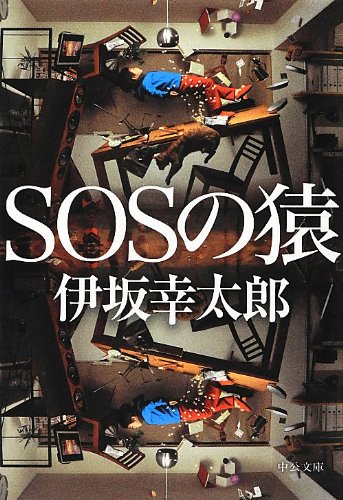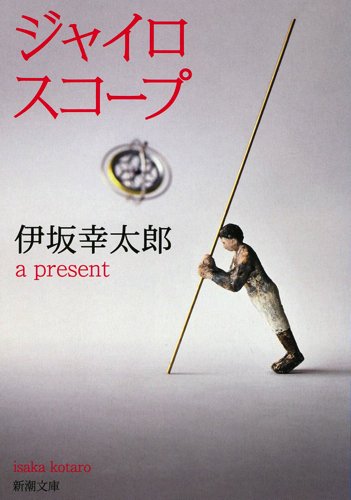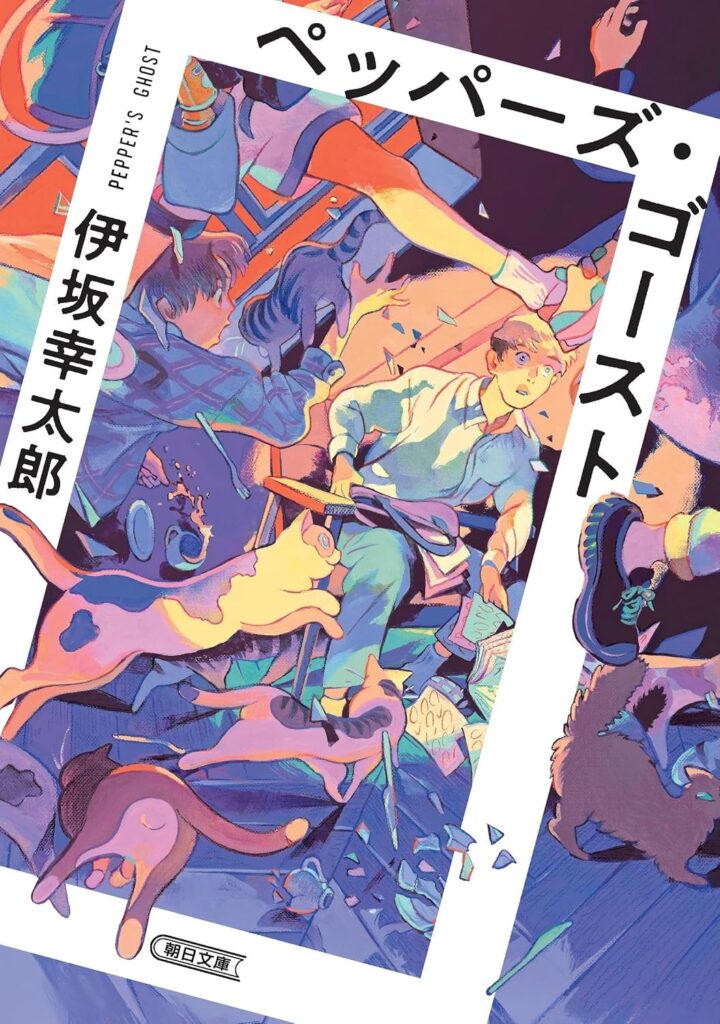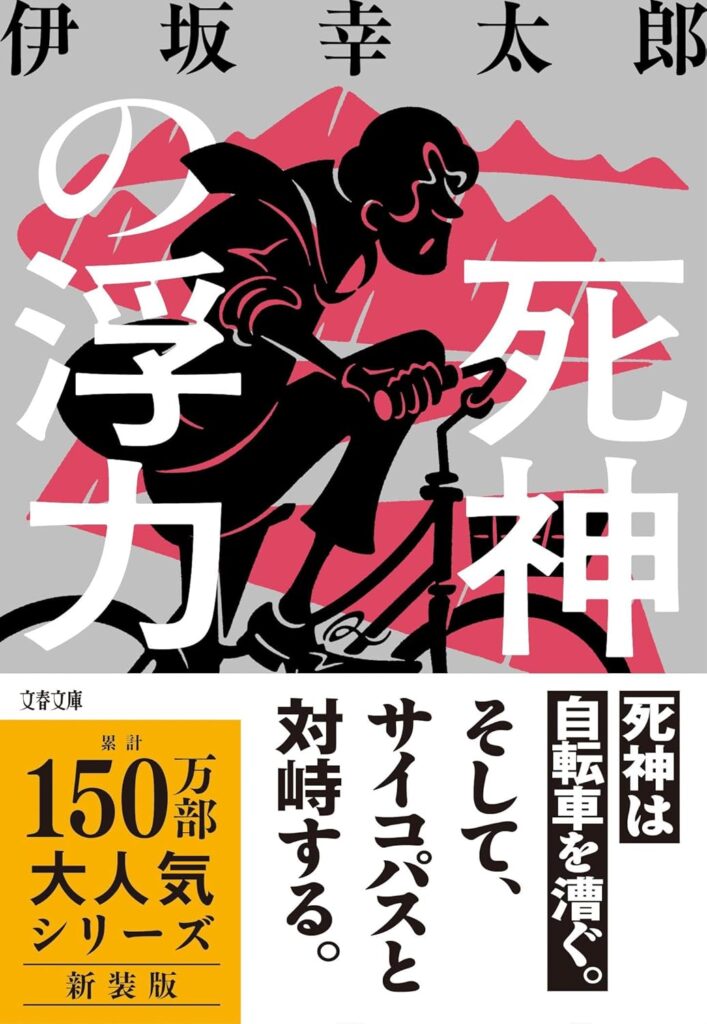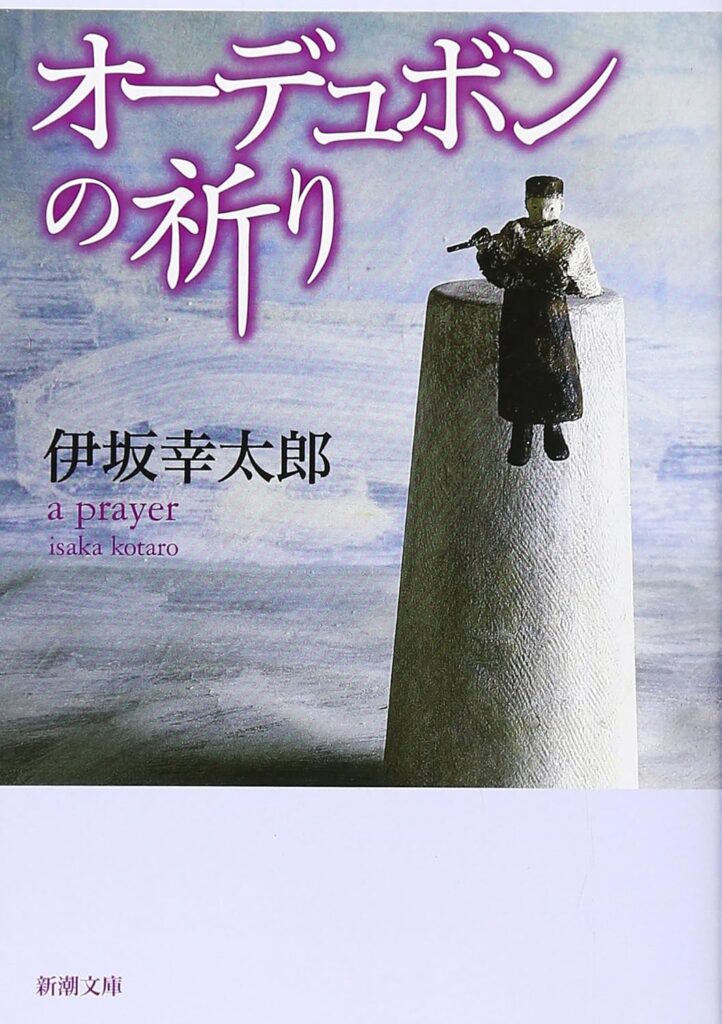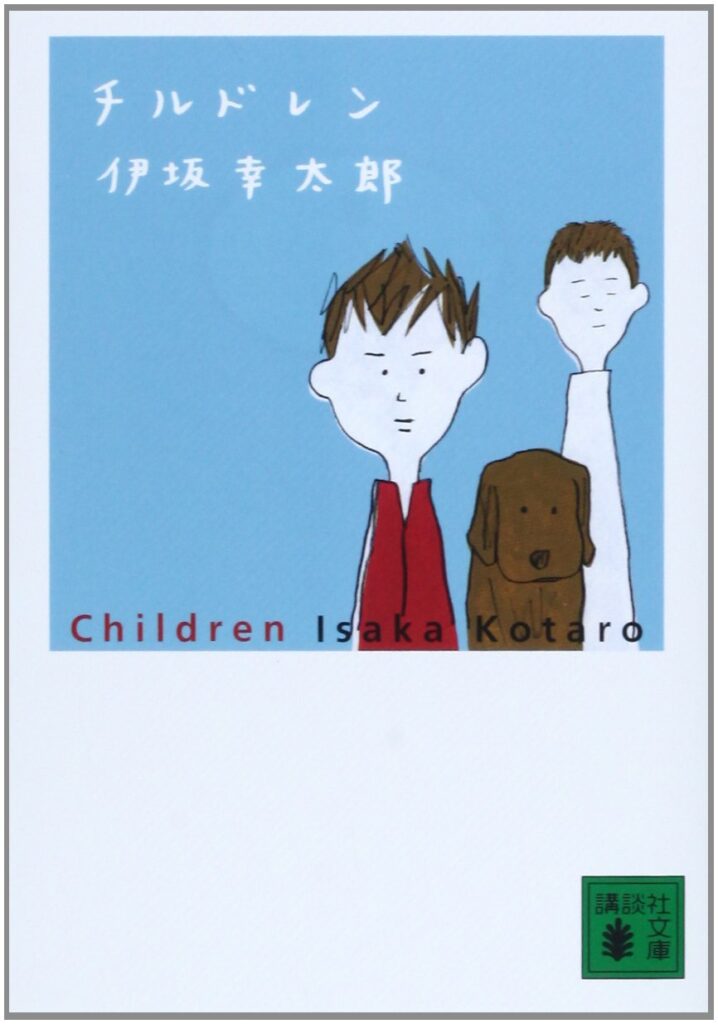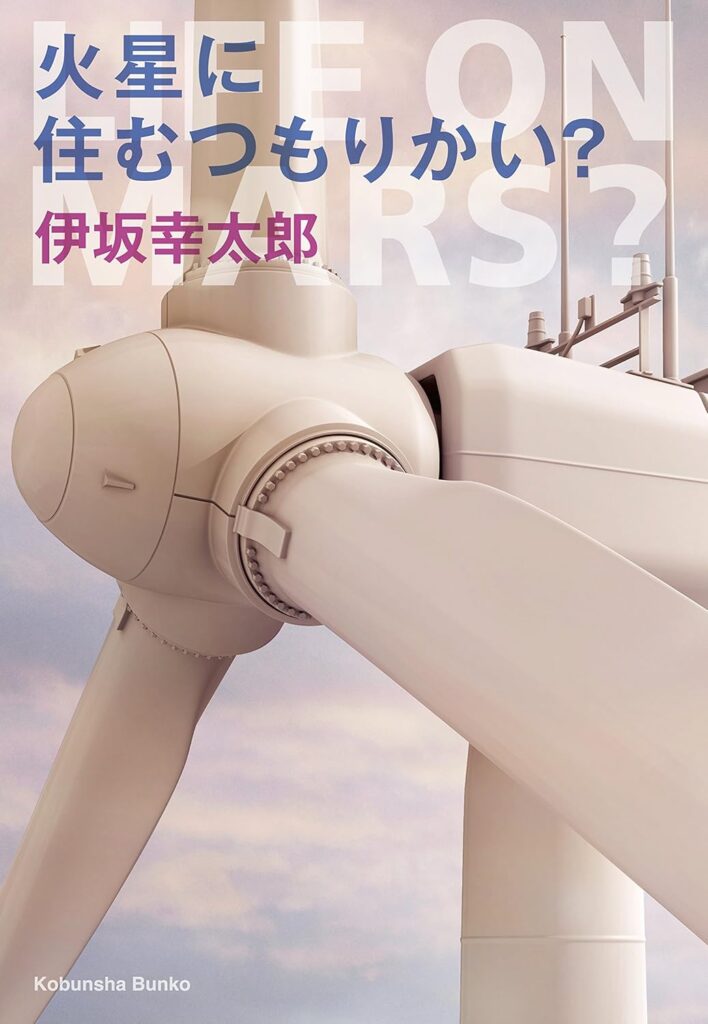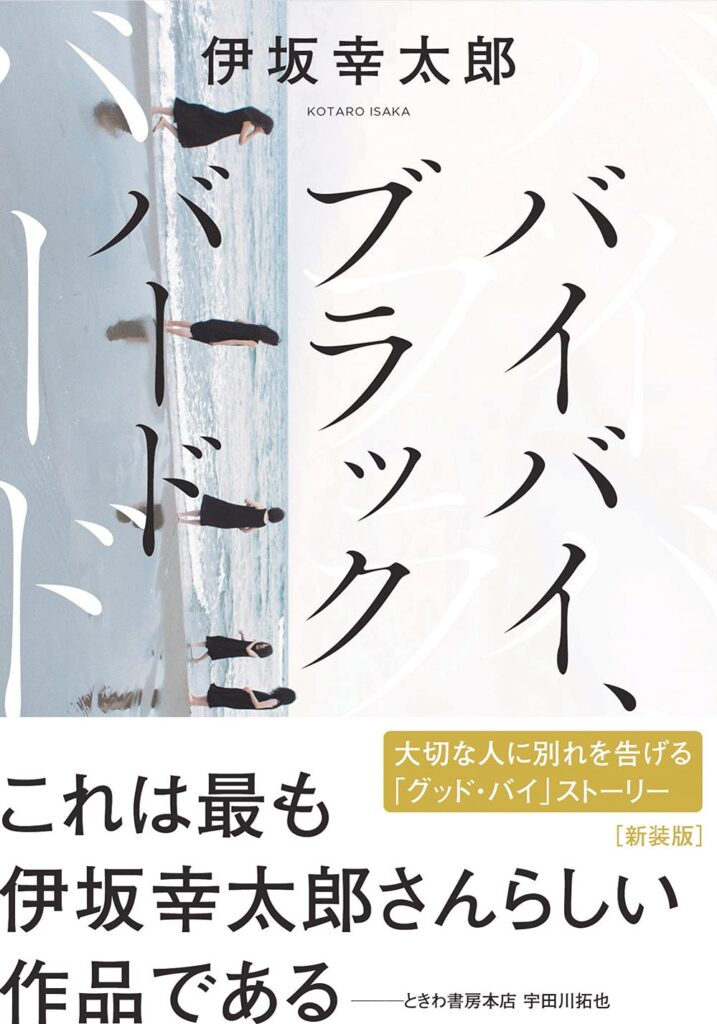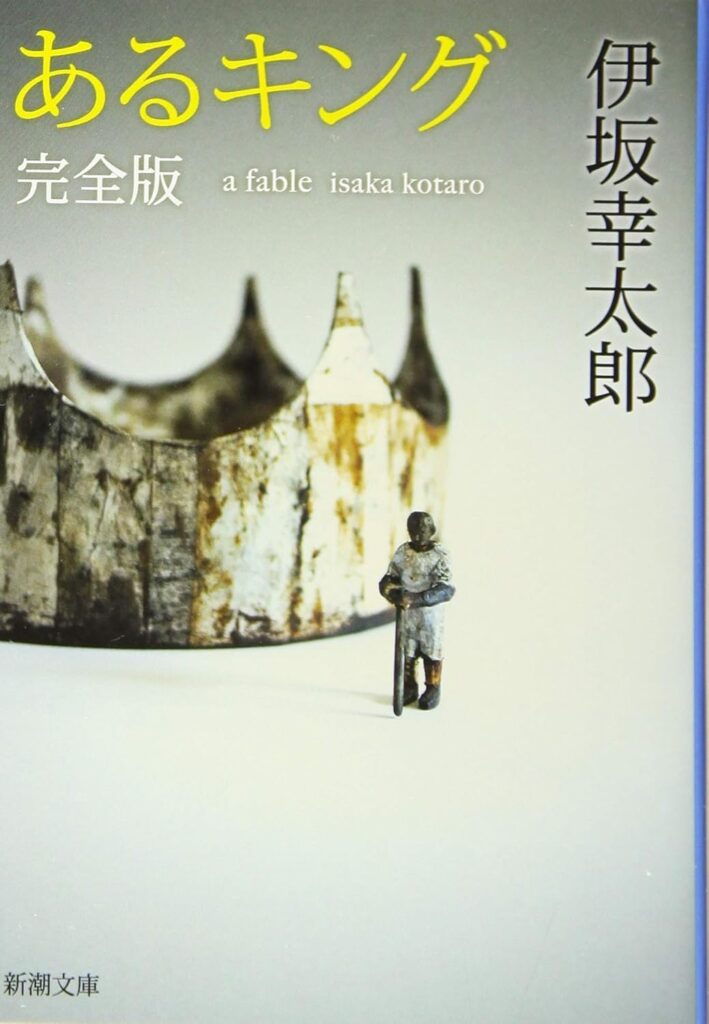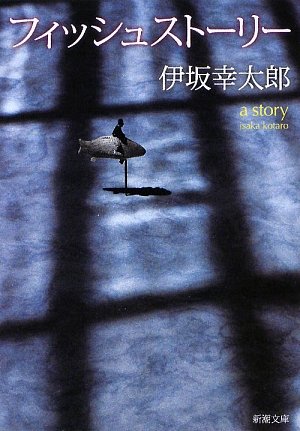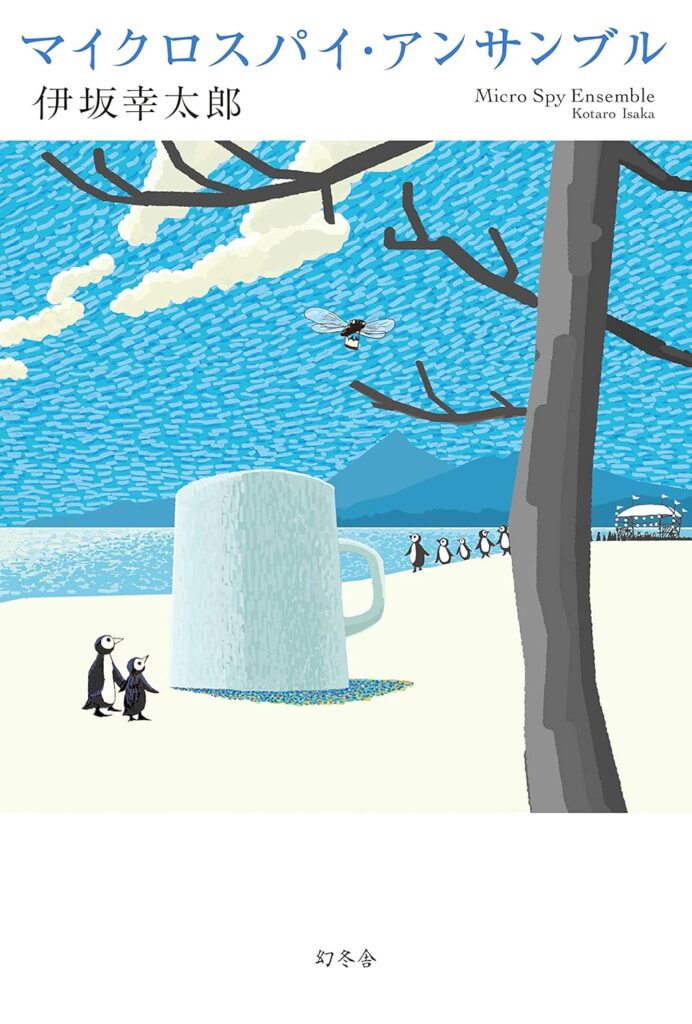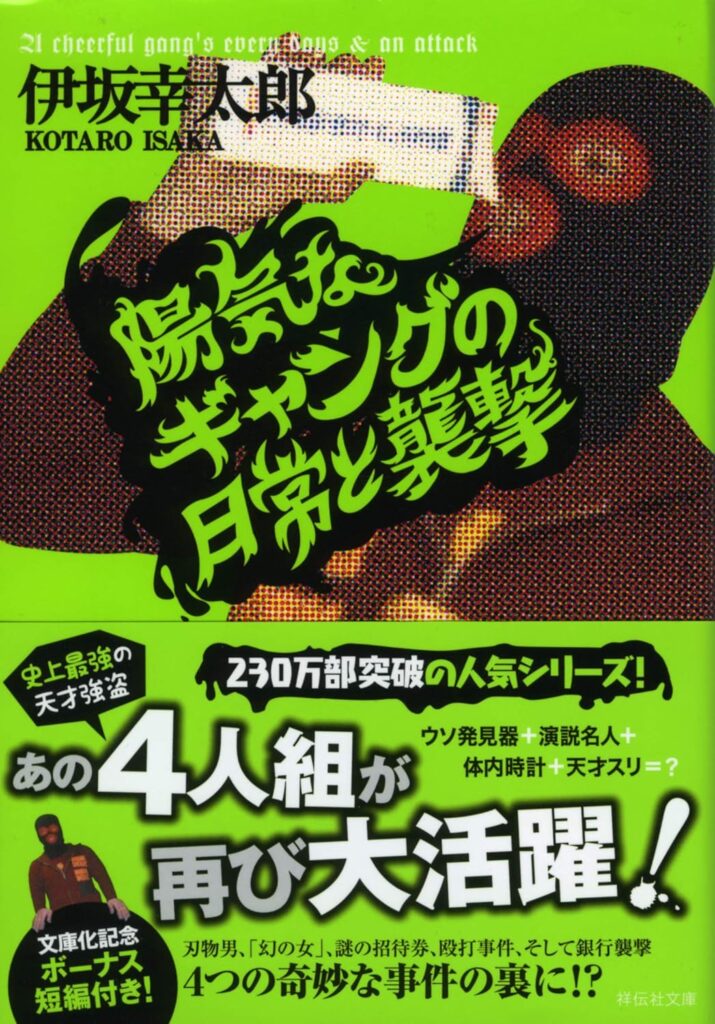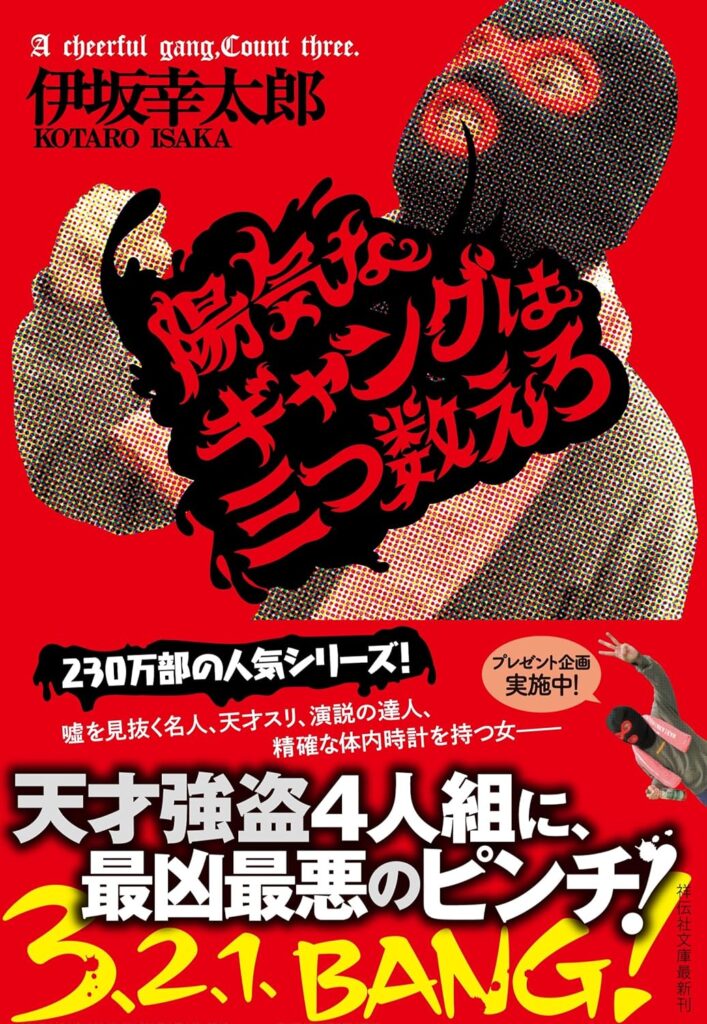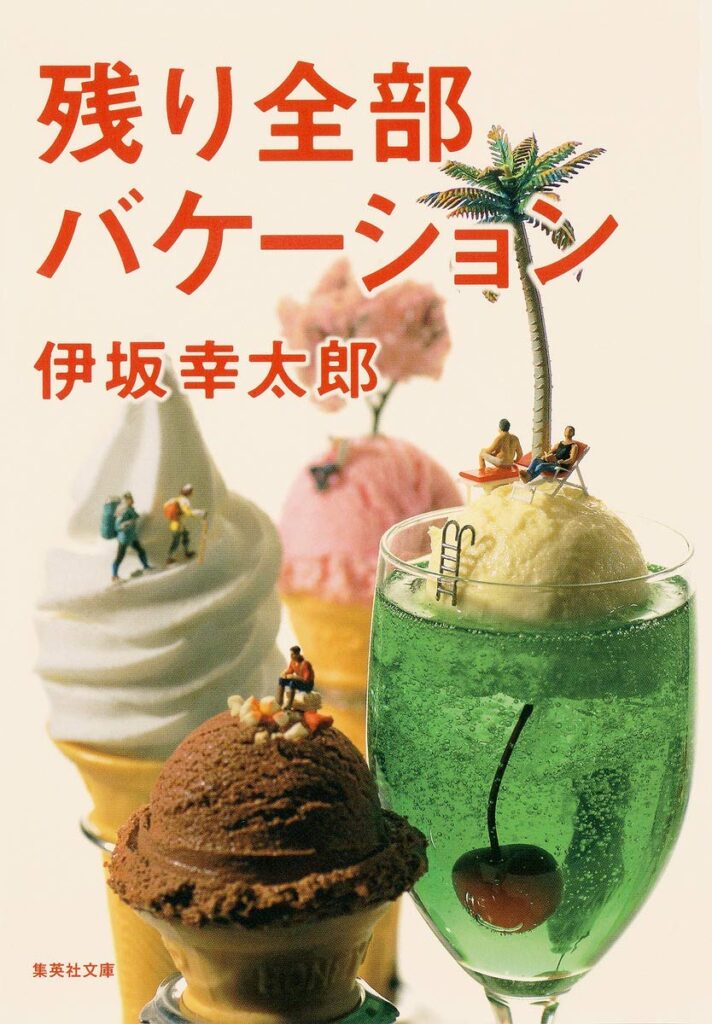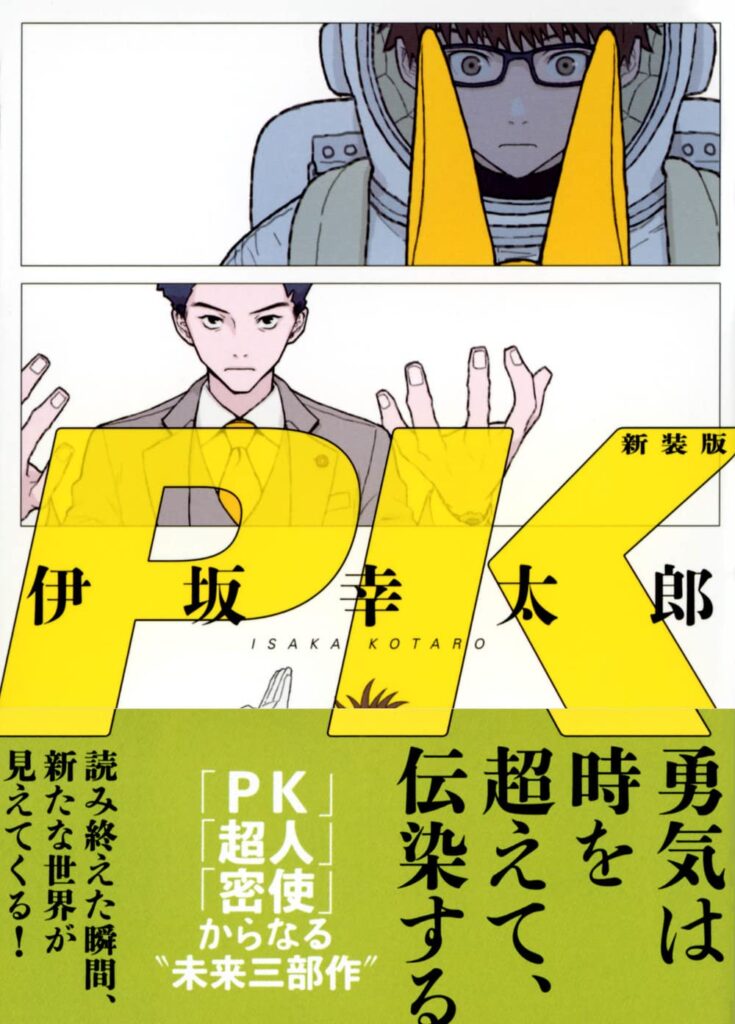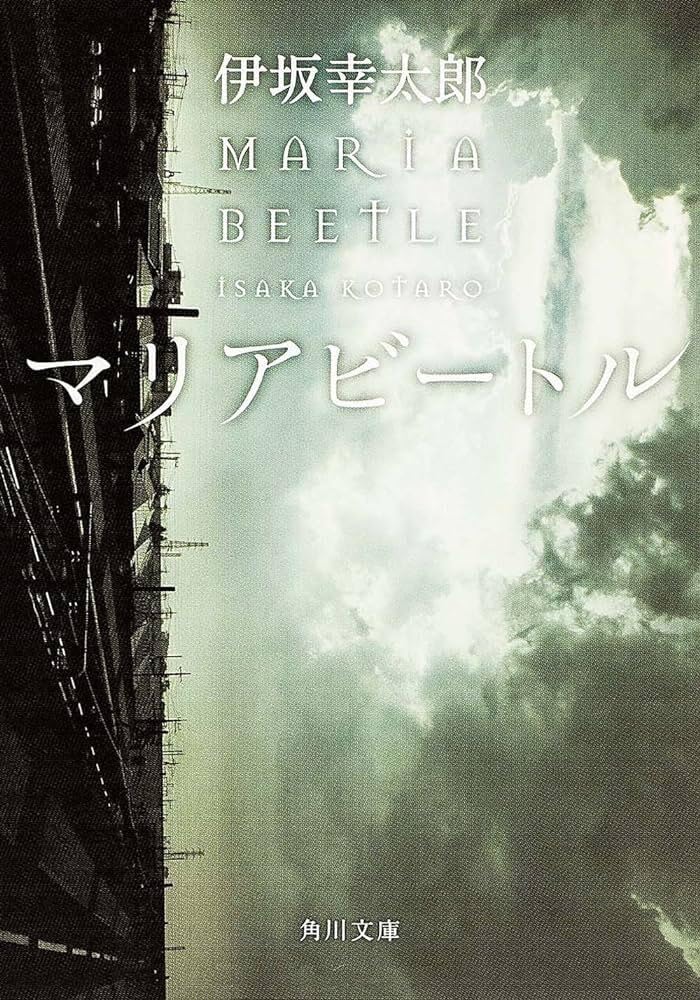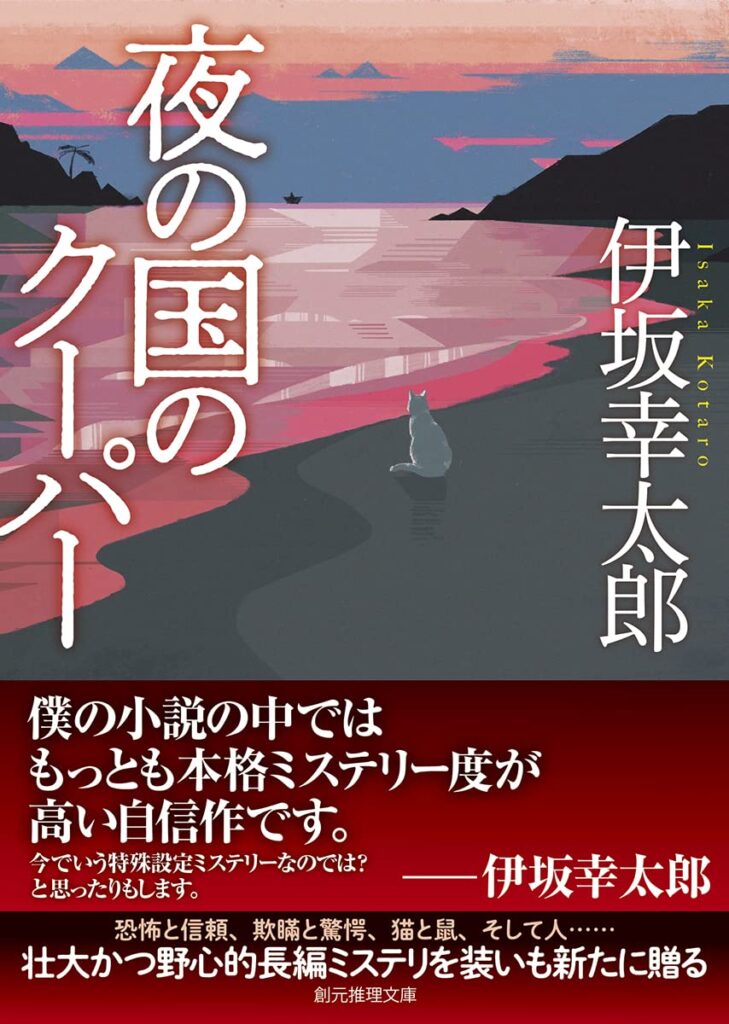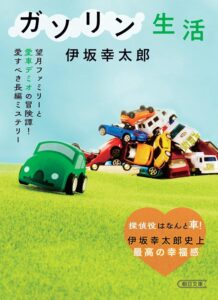 小説「ガソリン生活」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「ガソリン生活」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、なんと車が主人公なんです。ちょっと変わっていますよね。望月(もちづき)家で大切にされている緑色のデミオ、通称「緑デミ」が、私たちに彼らの日常や、巻き込まれるちょっとした事件について語ってくれます。車同士って、実は排気ガスが届く範囲でおしゃべりできるんですよ。緑デミも、お隣さんの白いカローラGT、通称「ザッパ」や、配達中のトラックなんかと情報交換しています。
物語は、この緑デミの視点を通して進んでいきます。望月家の家族のこと、新米ドライバーの長男・良夫(よしお)くんのこと、そして、ある日偶然出会った女優・荒木翠(あらき みどり)さんのこと。彼女との出会いが、やがて大きな出来事へと繋がっていくんです。この記事では、そんな「ガソリン生活」の物語の詳しい流れ、結末の秘密、そして私が感じたことをたっぷりとお伝えします。
車から見た世界って、どんなふうに見えるんでしょうか。人間の知らないところで、車たちは何を思い、何を話しているのか。そんな、普段は想像もしないような視点から描かれる、温かくて、少しだけスリリングな物語の魅力を、これからじっくりとご紹介していきたいと思います。ネタバレも含まれますので、まだ読んでいない方はご注意くださいね。
小説「ガソリン生活」のあらすじ
望月家の愛車である緑色のデミオ、私たちは親しみを込めて「緑デミ」と呼びましょう。彼は、自分の持ち主である望月家のことや、日々の出来事を私たちに教えてくれます。緑デミの日課は、隣に住む校長先生・細見(ほそみ)さんの愛車、白いカローラGT「ザッパ」とのおしゃべり。車同士は、排気ガスが届く範囲なら会話ができる特別な能力を持っているのです。彼らは、人間の知らないところで、交通情報や近所の噂話、時には車ならではの悩み(事故や車検への恐怖!)などを共有しています。人間が感情的に鳴らすクラクションは、彼らにとってはとても不快なものだとか。
そんな緑デミの平穏な日常に、変化が訪れます。望月家の長男で大学生の良夫が、運転免許を取得したのです。初心者マークの良夫が運転する緑デミは、最初は少し不安そうでしたが、次第に彼の運転にも慣れていきます。ある日曜日、良夫と小学生の弟・亨(すすむ)がドライブからの帰り道、思いがけない人物を乗せることになります。それは、人気女優の荒木翠でした。突然の出来事に驚きながらも、彼女の気さくで明るい人柄に、兄弟も緑デミも好感を持ちます。緑デミにとっては、忘れられない特別な乗客となりました。
ところが翌日、衝撃的なニュースが飛び込んできます。荒木翠が、トンネルでの交通事故で亡くなったというのです。報道によれば、彼女とその友人は、執拗なパパラッチから逃れるためにスピードを出しすぎ、トンネル内で事故を起こして車ごと炎上してしまったとのこと。昨日まで元気だった人を乗せたばかりの緑デミは、大きなショックを受けます。そして、事故の際にパパラッチが救助もせずに写真を撮り続けていたという話を聞いた良夫と亨は、強い憤りを感じ、そのパパラッチ、玉田憲吾(たまだ けんご)に一矢報いようと考えます。
時を同じくして、望月家の高校生の次女・まどかとその恋人・江口(えぐち)くんが、不穏な出来事に巻き込まれていました。江口くんの昔の知り合いであるトガシという男が率いるグループから、無理やり危険な手伝いを強要されそうになっていたのです。事態を知った良夫と亨は、二人を助けるために指定された廃パチンコ店へと向かいますが、そこで暴力的な状況に陥り絶体絶命のピンチに。その時、隣人の細見先生と、なんとあのパパラッチの玉田がザッパに乗って現れ、元不良たちを相手にすることに慣れている細見先生の見事な機転で、望月家は危機を脱するのです。しかし、荒木翠の事故の真相については、車たちの間でも様々な噂が飛び交い、謎は深まるばかりでした。
小説「ガソリン生活」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは伊坂幸太郎さんの「ガソリン生活」を読んだ、私の個人的な思いや考えを、ネタバレを気にせずにお話ししたいと思います。この物語、本当に面白かったですね!まず何と言っても、車が語り手っていう発想がすごいな、と思いました。
普段私たちが当たり前に乗っている車が、実は意志を持っていて、仲間たちと会話しているなんて。考えただけでワクワクしませんか?主人公の緑デミは、望月家の家族を静かに見守りながら、私たち読者にその日常や事件を伝えてくれます。彼の目線、というか、まあ車なので「ライト線」とでも言いましょうか、そこから見える世界は、人間が普段気にしないようなこと、例えば駐車場の定位置からの眺めとか、ガソリンスタンドでの出来事とか、そういう細かな描写が新鮮でした。
緑デミの相棒である、お隣のザッパとの掛け合いも良い味を出していますよね。ベテラン(?)のザッパが、まだ若い緑デミにあれこれ教えたり、一緒に噂話をしたり。まるで人間同士の井戸端会議みたいで、微笑ましくなります。車たちの会話を通じて、彼らが何を大切に思い、何を恐れているのか(やっぱり事故と廃車は怖いみたいです)が伝わってきて、単なる「モノ」ではない、個性を持った存在として彼らを感じることができました。
そして、緑デミのオーナーである望月家の人々。これがまた、魅力的な家族なんですよね。長男の良夫くんは、ちょっとおっとりしているけれど、名前の通り「良い夫」ならぬ「良い人」。彼の運転する緑デミは、最初はヒヤヒヤさせられるんですが、その一生懸命さが伝わってきて応援したくなります。弟の亨くんは小学生なのに、ものすごく頭が切れる。大人顔負けの洞察力で、物語の謎を解き明かす重要な役割を担います。彼の冷静なツッコミは、物語の良いアクセントになっています。
高校生のまどかちゃんとその彼氏の江口くんが巻き込まれる事件は、物語にサスペンスの色を加えます。普段はのんびりした雰囲気の物語に、ピリッとした緊張感が走る。でも、そこでも望月家の家族の絆が試され、描かれるのが良いんです。お母さんも含めて、みんなで困難に立ち向かおうとする姿には、温かい気持ちになります。
物語の大きな転換点となるのが、女優・荒木翠の登場と、その後の悲劇的な事故です。緑デミが偶然彼女を乗せた、ほんの短い時間。その時の彼女の飾らない優しさが印象的だからこそ、事故のニュースは衝撃的でした。そして、事故の原因とされるパパラッチの存在。特に玉田憲吾という人物は、最初は本当に嫌なやつ、という印象です。人の不幸をネタにする、許せない存在として描かれます。良夫くんたちが彼に立ち向かおうとする気持ちは、読んでいるこちらもよく分かります。
でも、物語が進むにつれて、この玉田という人物の印象が少しずつ変わっていくんですよね。まどかちゃんたちのピンチに、意外にも助けに来てくれたり。そして、クライマックスで明かされるトンネル事故の真相。これには本当に驚かされました。
実は、玉田は荒木翠を追い詰めたのではなく、むしろ彼女を救おうとしていた。事故で亡くなったのは、まどかちゃんたちを脅していたトガシとその仲間であり、玉田はその事故を利用して、パパラッチに追われる人生に疲れていた荒木翠が「死んだことにして」新しい人生を歩めるように画策した…というのです。
このどんでん返し! まるで、パズルのピースが一つずつはまっていくように、亨の推理が真相へと導いていくのです。それまでの伏線、例えば玉田が事故現場から一度タクシーで離れたという車の噂話などが、ここで一気に繋がります。悪役だと思っていた人物が、実は…という展開は、伊坂作品の得意とするところかもしれませんが、今回も実に見事でした。玉田なりの歪んだ正義感というか、彼なりのやり方で人を救おうとした行動には、単純に善悪では割り切れない複雑さを感じます。
そして、この真相を知っているのは、人間界ではごく一部の人と、そして車たちだけ、というのがまた面白い。車たちのネットワークを通じて、「荒木翠は生きているらしい」という噂が広まっていく。でも、人間社会では彼女は「事故死した悲劇の女優」のまま。この情報の非対称性が、車が語り手であることの意味を、より深くしているように感じました。
車たちの視点だからこそ描けること、人間には見えない真実がある。それは、物理的な視点だけでなく、物事の本質を見る視点でもあるのかもしれません。人間は時に感情や偏見に左右されてしまうけれど、車たちは(少なくとも緑デミたちは)もっとフラットに物事を見ているような気がします。クラクションを嫌う彼らのように、表面的な騒がしさではなく、もっと静かな真実を捉えようとしているのかもしれません。
物語全体を通して流れているのは、やはり望月家の温かい雰囲気と、伊坂さんらしい軽妙な筆致です。シリアスな事件が起こっても、どこかクスッと笑えるような会話があったり、緑デミのちょっととぼけたような語りがあったりして、重くなりすぎない。それでいて、家族愛や、正義とは何か、真実はどこにあるのか、といったテーマについて、ふと考えさせられる。このバランス感覚が絶妙だなと思います。
読み終わった後、なんだか自分の家の車も、もしかしたら何か話しているんじゃないかな、なんて想像してしまいました。緑デミやザッパのように、私たちの知らないところで、いろんなドラマが繰り広げられているのかもしれませんね。
「ガソリン生活」は、奇抜な設定でありながら、描かれているのは普遍的な家族の物語であり、ちょっとしたミステリーであり、そして心温まる人間(と車)ドラマでした。日常にちょっとした不思議と、心地よい読後感を求めている方には、ぜひおすすめしたい一冊です。特に、伊坂幸太郎さんの作品が好きな方なら、きっと楽しめると思います。
まとめ
伊坂幸太郎さんの小説「ガソリン生活」は、緑色のデミオ、通称「緑デミ」が語り手を務める、一風変わった物語です。車たちが意志を持ち、お互いに会話を交わすという設定が、物語に独特の彩りを与えています。緑デミの視点を通して、オーナーである望月家の日常や、彼らが巻き込まれる出来事が描かれます。
物語は、望月家の長男・良夫が運転免許を取ったり、人気女優の荒木翠を偶然乗せたりといった日常的なエピソードから始まりますが、荒木翠の突然の事故死をきっかけに、ミステリーの様相を呈していきます。パパラッチの玉田の存在や、次女まどかが巻き込まれる事件など、ハラハラする展開も待ち受けています。しかし、小学生の次男・亨の鋭い推理によって、事故の意外な真相が明らかになるのです。
この作品の魅力は、車というユニークな視点、個性的な望月家の面々、そして伊坂さんらしい軽快な語り口と、読者をあっと言わせるストーリー展開にあります。温かい家族の絆と、少しだけ不思議でスリリングな日常が描かれた「ガソリン生活」は、読後に爽やかな感動を与えてくれる素敵な物語だと感じました。