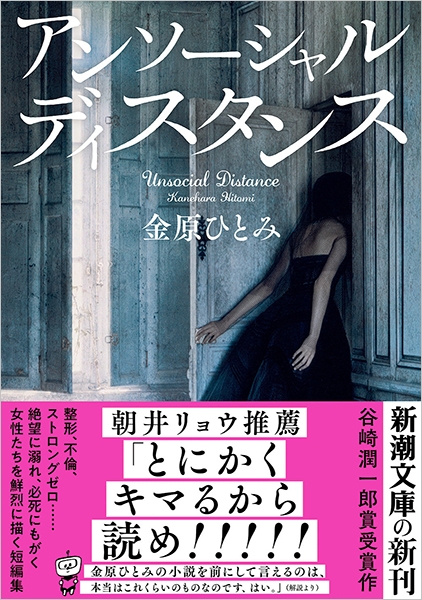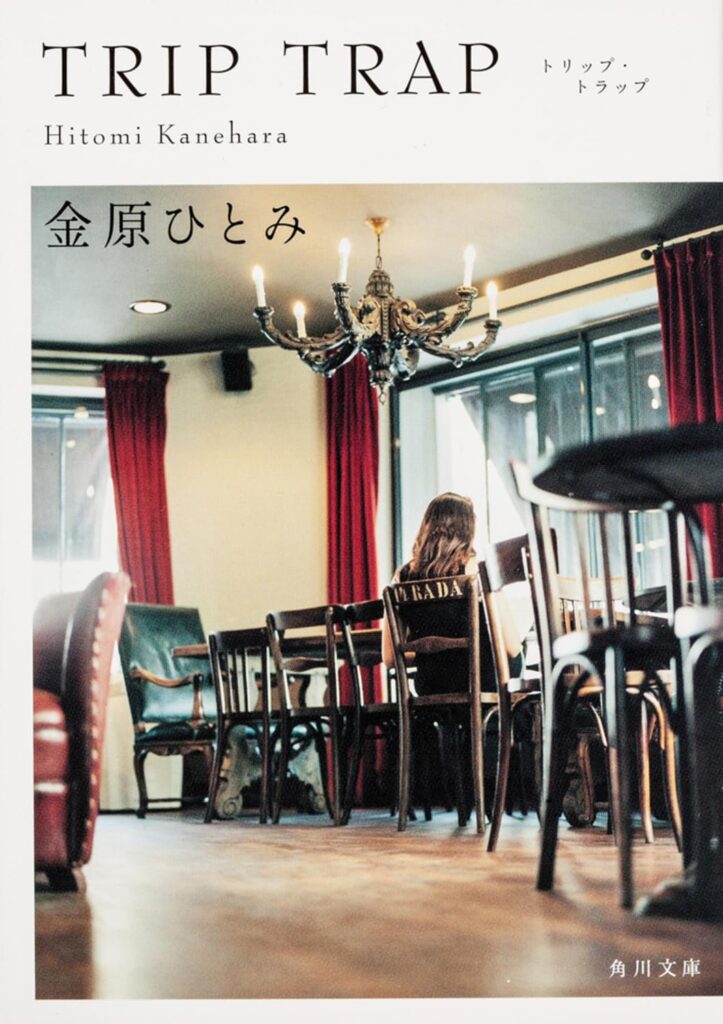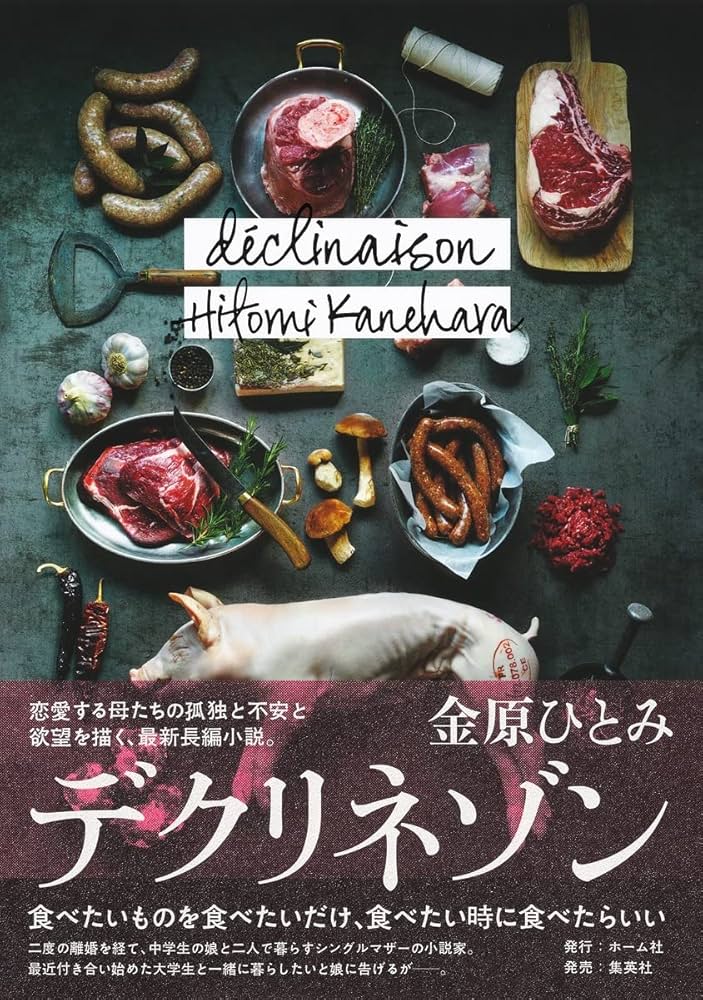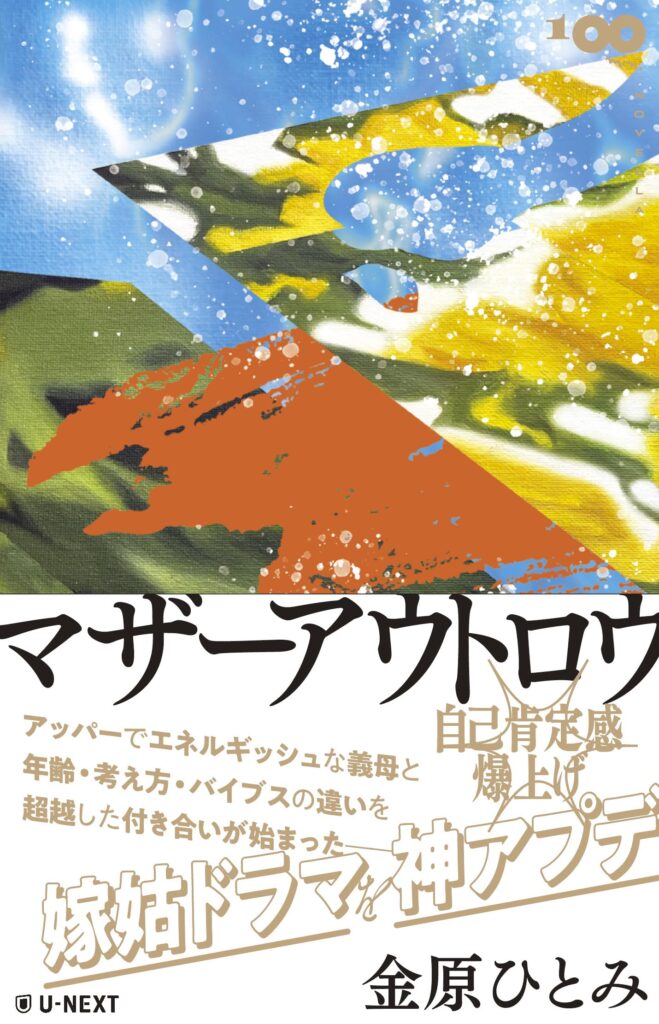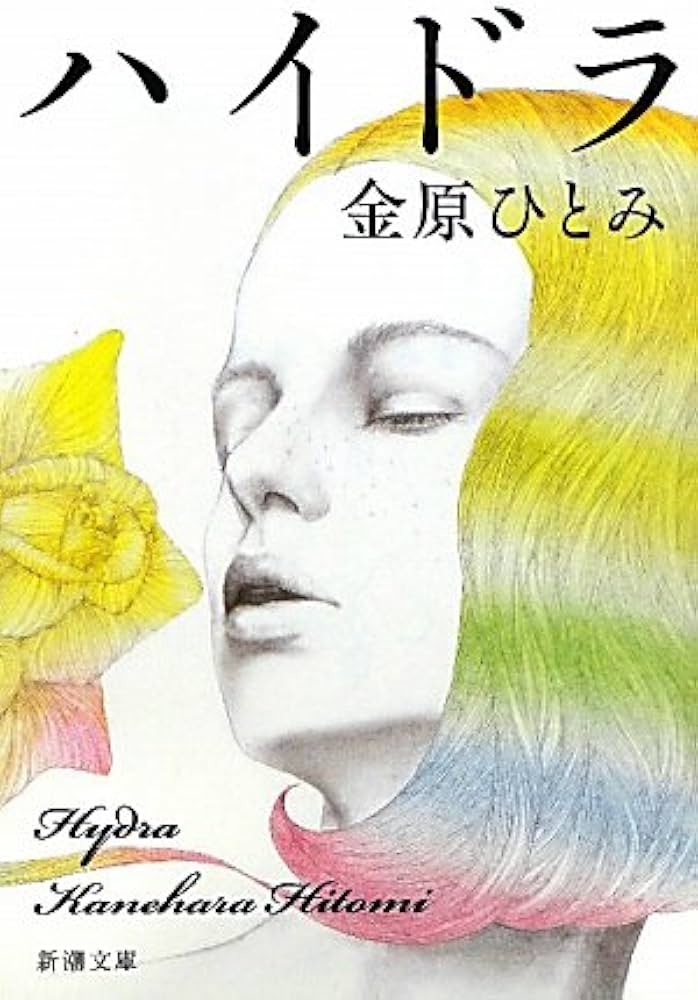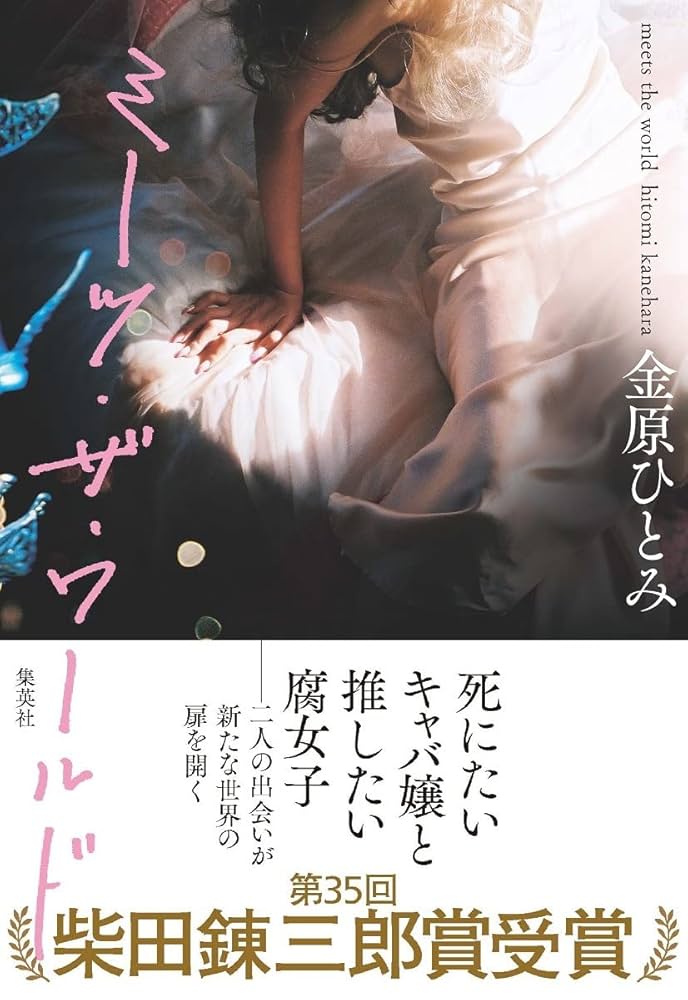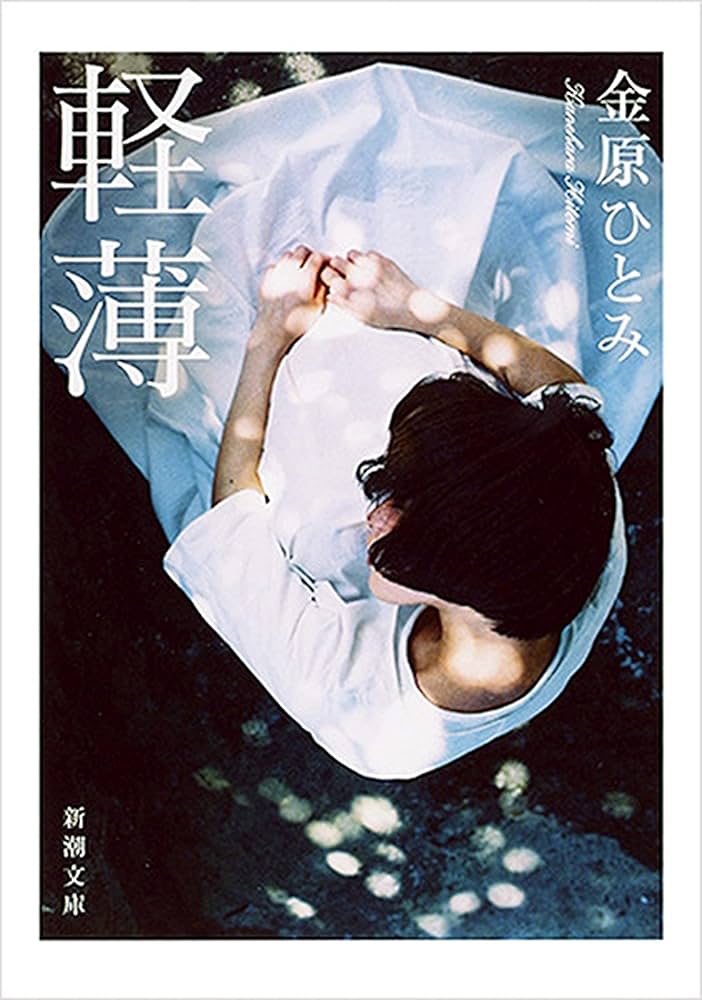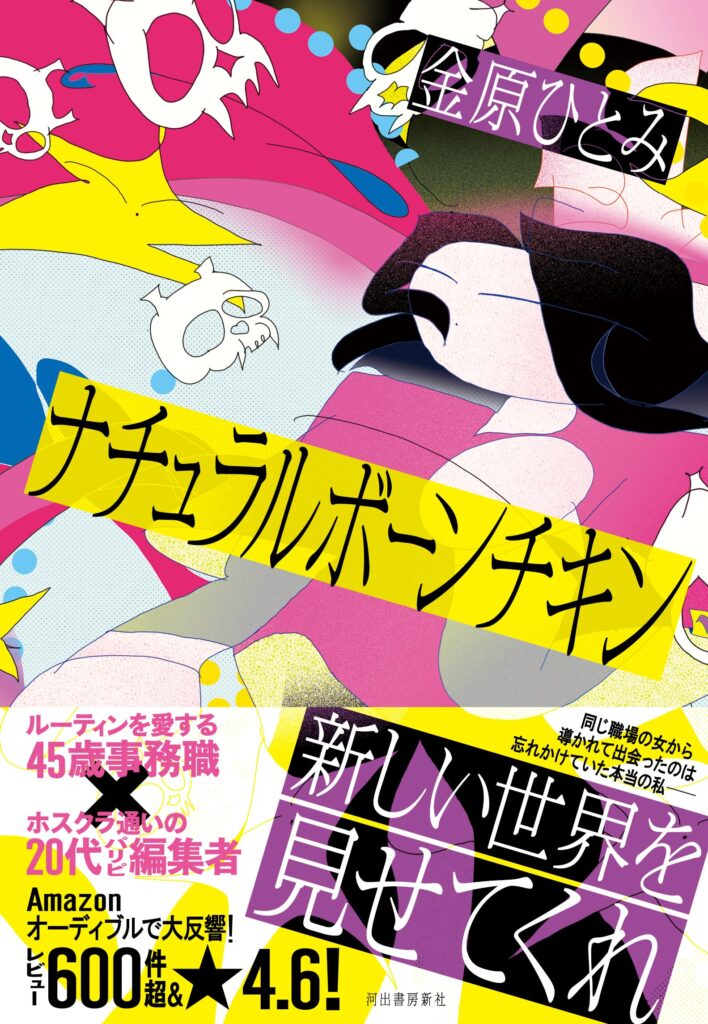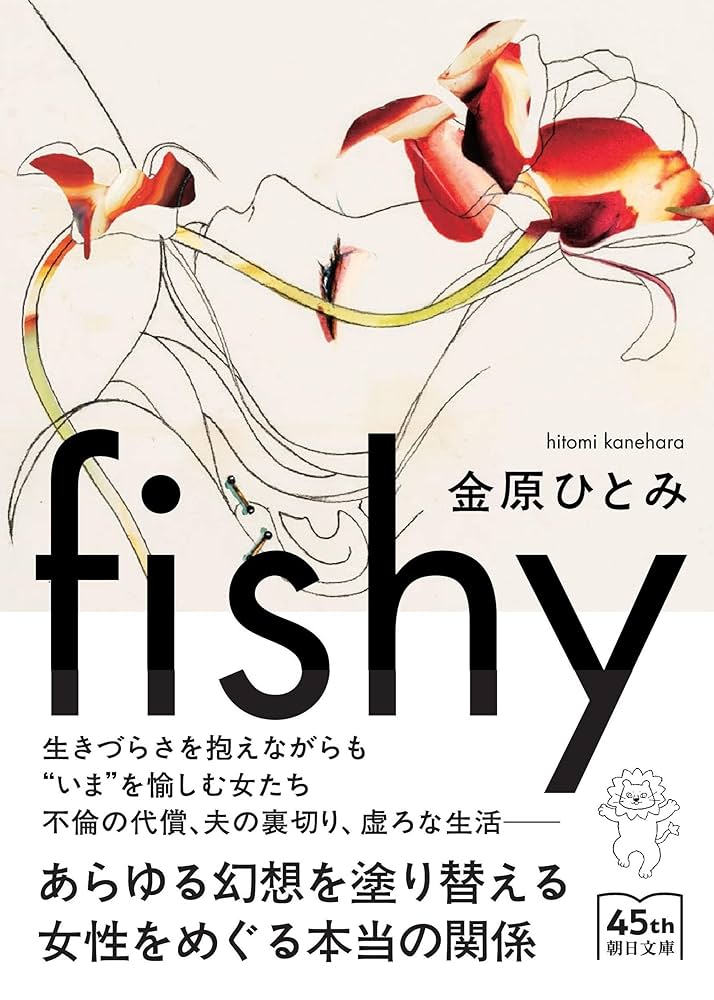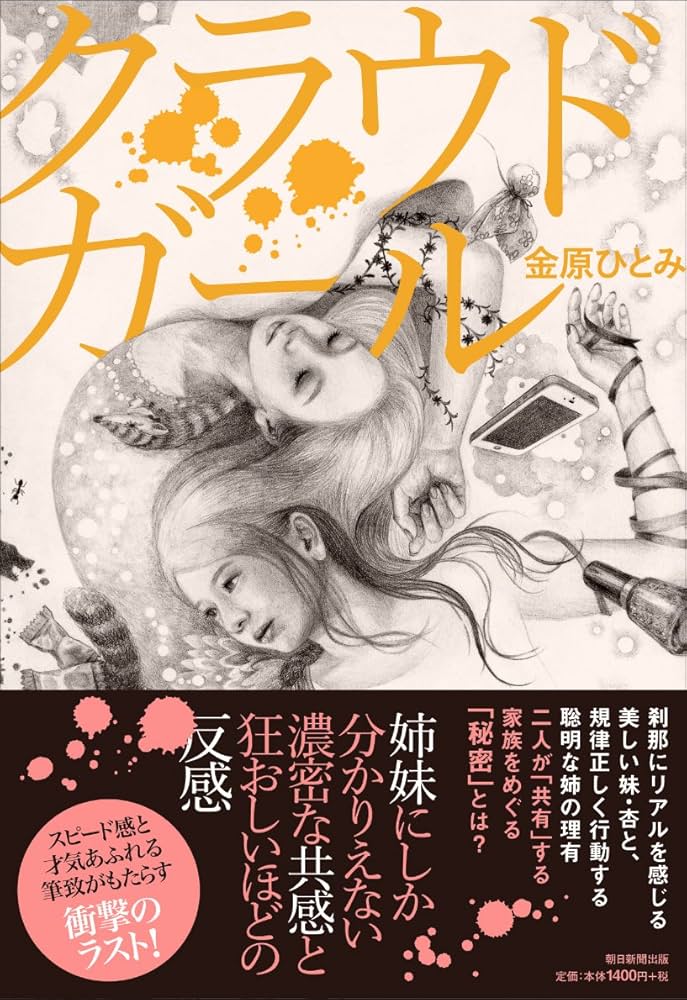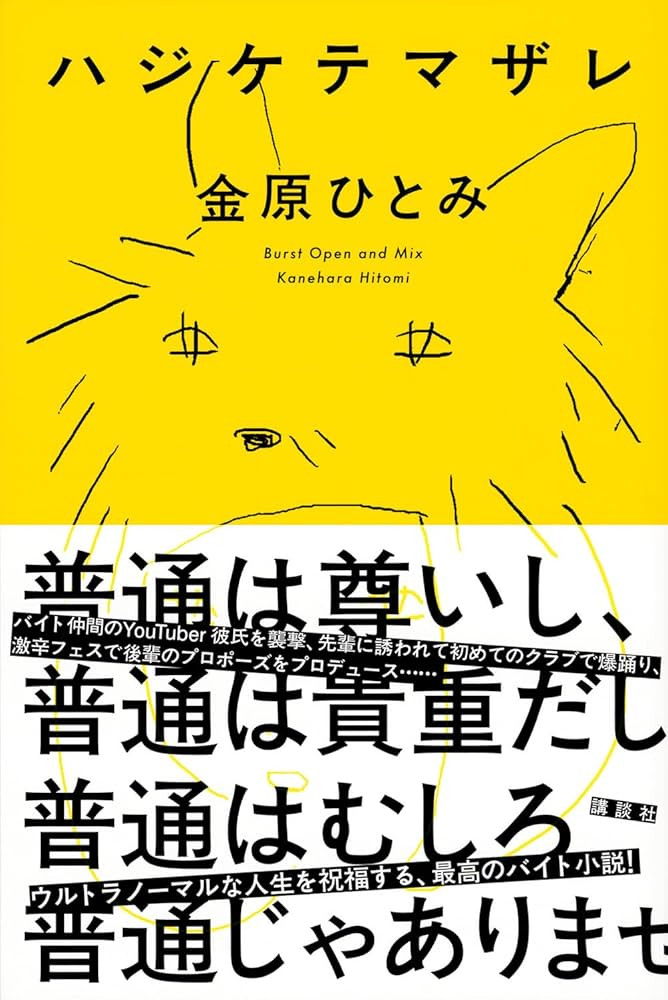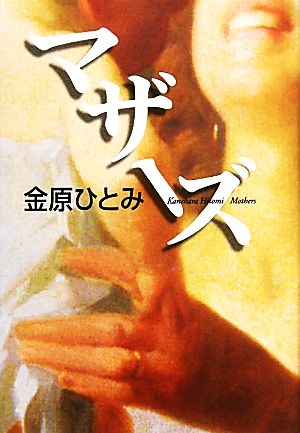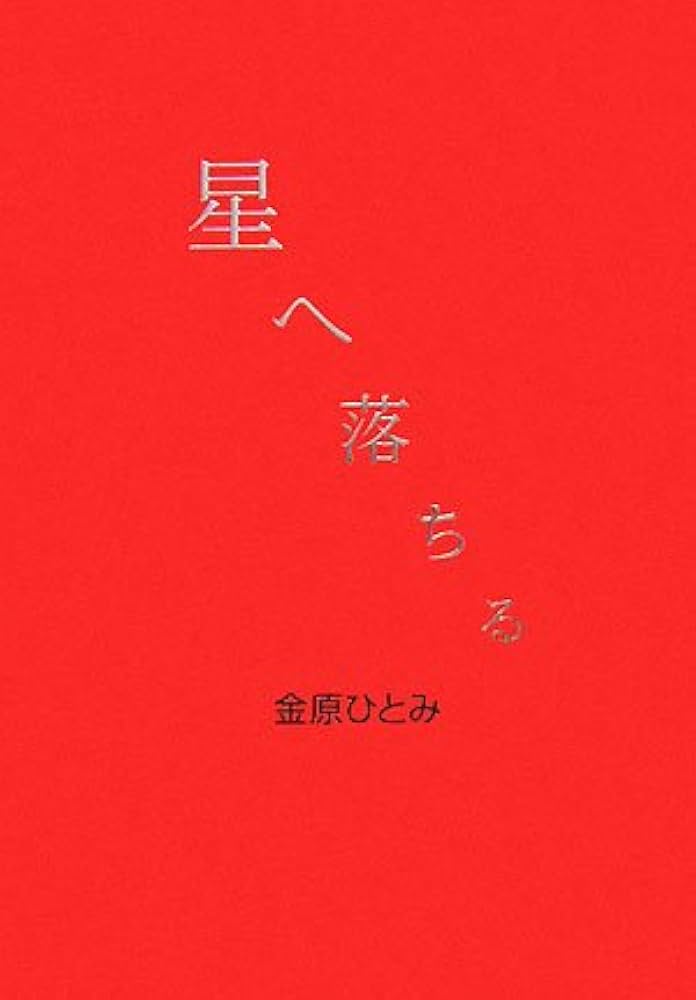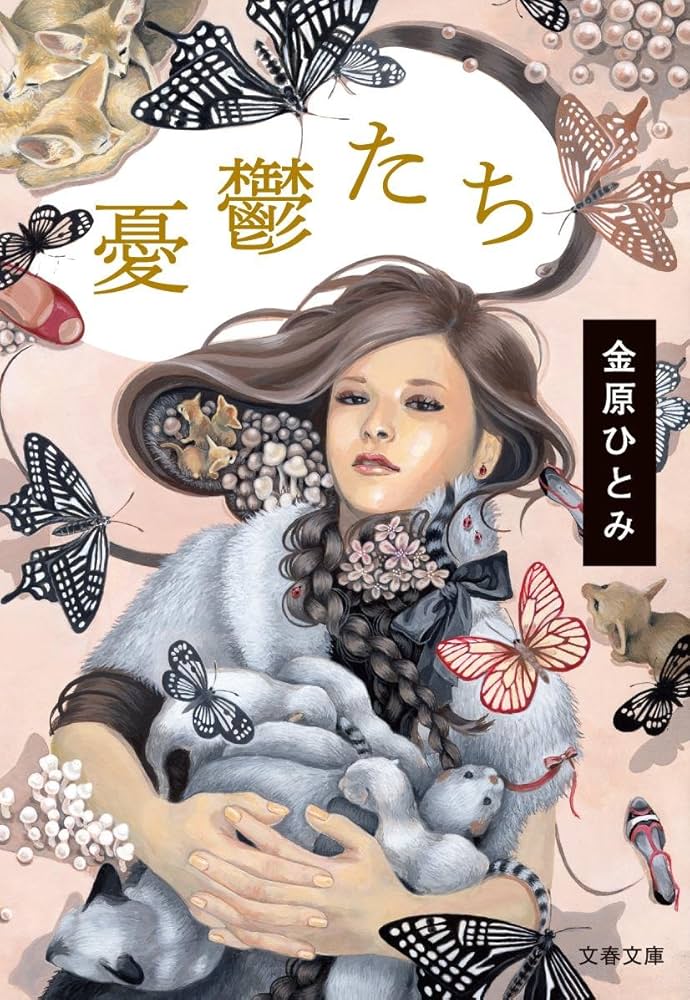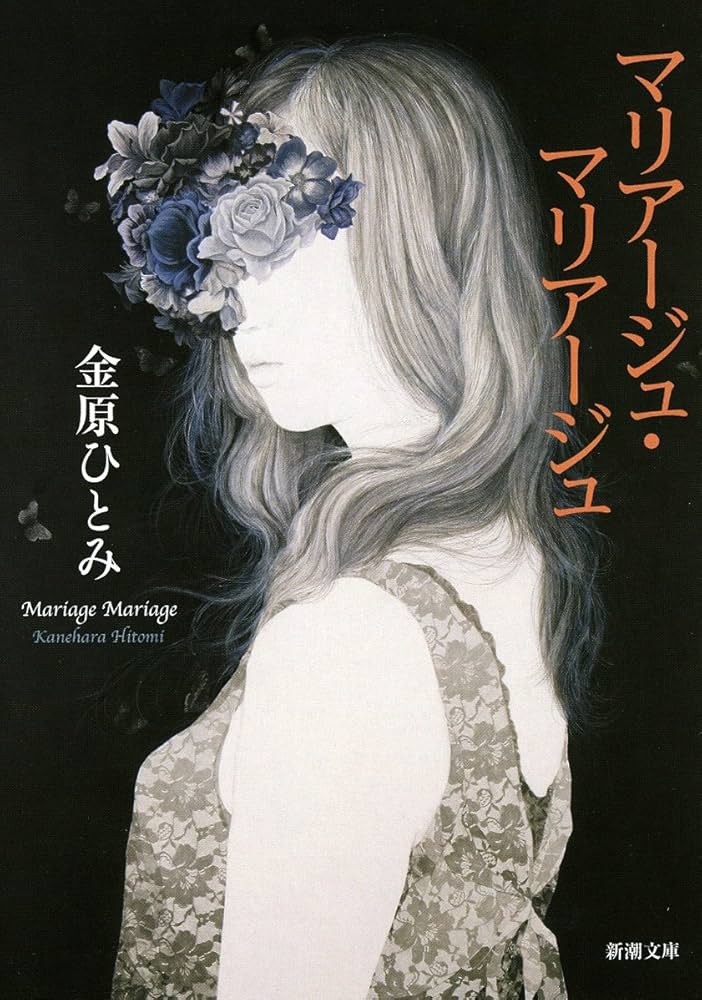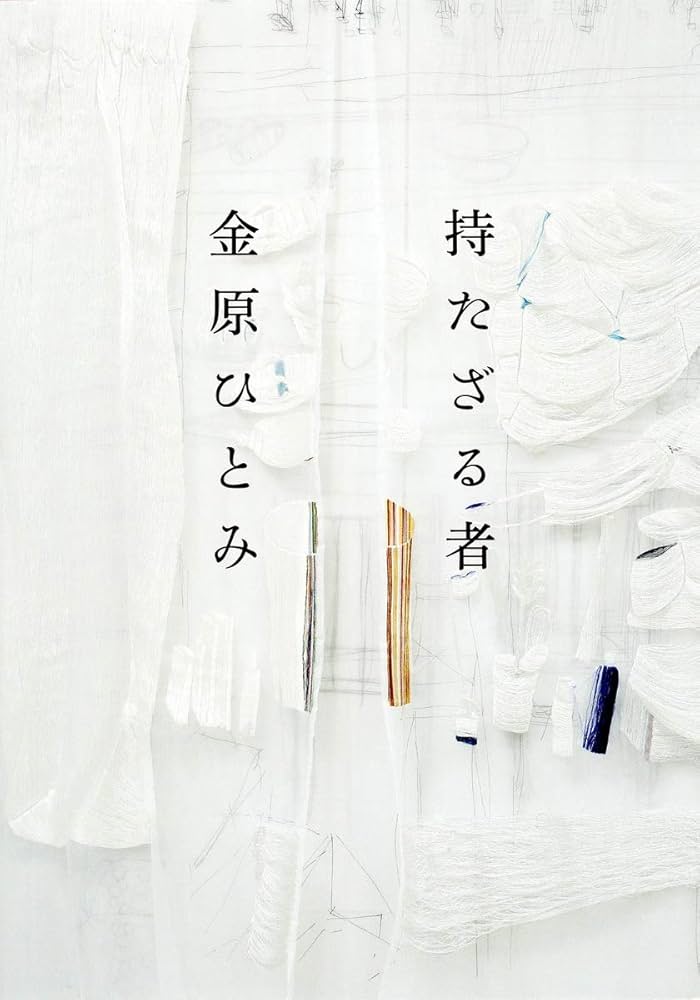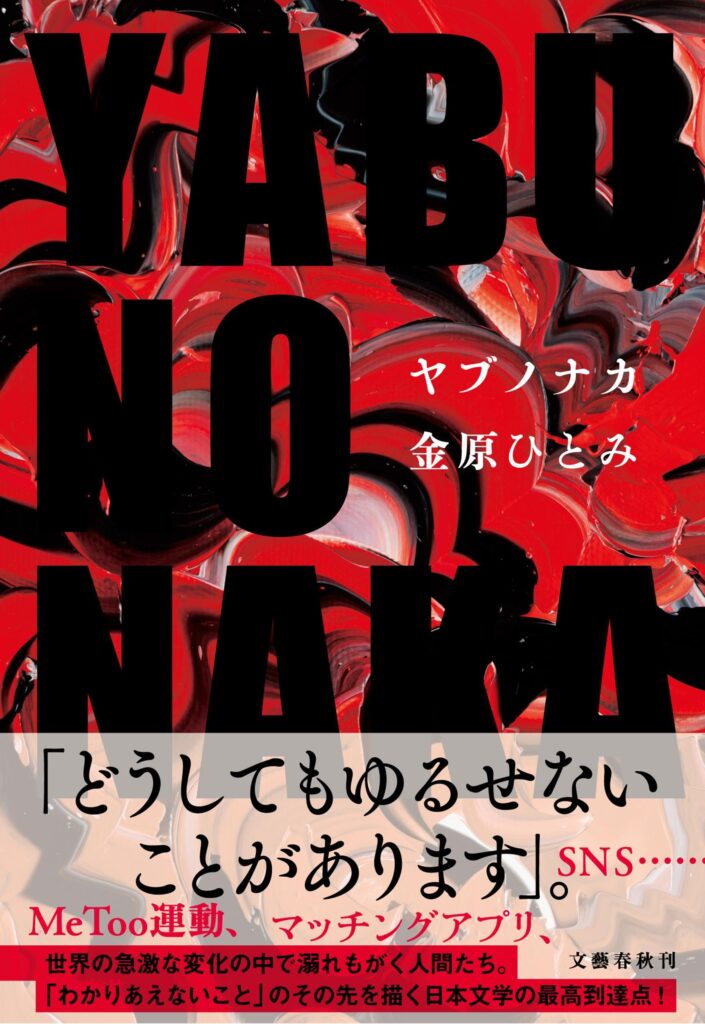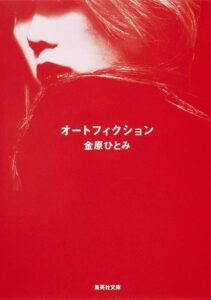 小説「オートフィクション」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「オートフィクション」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
はじめに押さえたいのは、物語が現在から過去へとさかのぼる構成だという点です。二十二歳の冬から十八歳の夏、十六歳の夏、十五歳の冬へと移り、主人公の心の源流を探る道のりになっています。
タイトルどおり、自伝的創作という揺らぎの場に読者を招き入れる一作です。虚実の境目を曖昧にしながら、語りの信頼性そのものを問い直します。
この記事では、冒頭の章に触れる軽いネタバレを交えつつ流れをなぞり、その後に核心へ踏み込みます。読みどころとテーマを丁寧に手繰り寄せ、作品が残す痛みと救いの両方を言葉にしていきます。
「オートフィクション」のあらすじ
二十二歳の冬。新婚まもない作家・高原リンは、帰国便の機内で不安に呑み込まれていきます。夫と客室乗務員が不倫しているのではないかという妄想が膨らみ、嫉妬と恐怖が思考を支配します。現実感が少しずつ崩れ、リンは自分の心がつくり出す像と向き合わざるを得ません。
場面は十八歳の夏へ。リンは衝動と孤独に突き動かされるまま関係を重ね、危うい夜へ足を踏み入れます。快楽と暴力の境がにじむ経験にさらされ、同意の不確かさや自己嫌悪が彼女の内側に沈殿していきます。
十六歳の夏。居場所のなさを埋めようとするリンは、自由を名乗る風に身を投げつつ、誰にも繋がれない心細さに震えます。関係は軽く、言葉は荒く、未来はまだ輪郭を持ちません。
十五歳の冬。家族との距離、身体に刻まれた出来事、後年の嫉妬や恐怖の“核”にふれる兆しが描かれます。ここで提示される経験と選択が、のちの章で示されるリンの感情の振れ幅の起点となっていきます。ただし結末までは伏せられ、読者は原因と結果のあいだに残された余白を抱えたまま次章へ導かれます。
「オートフィクション」の長文感想(ネタバレあり)
まず惹かれるのは、逆行する時間の設計です。現在の壊れかけた感情から過去へ降りていくため、読者は“答え”を見たあとに“なぜそうなったか”を遅れて受け取ります。この順序が、リンの思考の癖――最悪を先取りする想像――と響き合います。
オートフィクションという枠組みは、作家の私生活を覗く刺激ではなく、語り手の自己神話化と自己分解を同時に進める装置として機能しています。読者は「これは事実か?」と問い続けるより、「そう語ることで何が守られ、何が削ぎ落とされるのか」を考えるよう促されます。
機内での嫉妬は典型的なネタバレ要素ですが、ただの事件ではありません。現実と妄想の境目を自分で塗り替えてしまうリンの危うさが最初に露出する導火線であり、関係へ過剰な“検閲”をかけてしまう彼女の生存戦略の表れです。
「オートフィクション」は、嫉妬を悪癖として切り捨てません。疑いに駆られた内面を、恐怖の感受性として描き直します。裏切りを想像してしまうことは、被害を回避したいという願望と地続きであり、その敏感さが彼女を守りも破りもするのです。
語りは年齢に応じて手触りが変化します。二十二歳の章の文体は神経質で、自分の言葉に追い詰められていく。十六歳や十五歳では荒く速い息遣いが前に出る。年齢が下がるほど、語りの統御が利かなくなるように見えるのが秀逸です。
“スミス・スミス”のような妄想上の気配を家に住まわせてしまうくだりは、怖さと可笑しみが同居します。不安は名前を持つと輪郭を得て、現実を侵食する。この命名の効用が、後年の関係にも反復されます。
十八歳の夜――同意の曖昧さが露出する場面は読み手の身体を強張らせます。ここで作品は、性的経験を“成熟の証”として消費するロジックを拒み、むしろ経験が心に残す裂け目を丁寧に示します。
十六歳の章は、誰にも繋がらない自由を目指すほど孤独が濃くなる逆説を描きます。帰りを待つ人から離れるほど、帰る場所の必要性が強まる。リンの「依存しない」という宣言は、依存への恐れの裏返しとして響きます。
十五歳の冬では、家族という最小単位のひび割れが示されます。家庭へ向けられた不信と、身体に生じた出来事――妊娠とその中断――が、のちの年齢での自己否定、過剰な嫉妬、関係からの逃走を準備していたと読めます。ここに物語の“核”が沈んでいます。
「オートフィクション」は、出来事を一義的な原因に還元しません。むしろ、複数の小さな傷が互いを増幅し、やがて人格の“基礎設定”を変えてしまう過程を可視化します。読者は“説明”より“作用”を体感します。
語りの信頼性は揺れ続けますが、その揺れ自体が真実味を帯びます。人は自分の過去を、現在の感情の色で塗り直して語る――この当たり前を、作品は手触りのまま提出します。だからこそネタバレを知って読んでも、体験としての強度は落ちません。
「オートフィクション」という呼称を作中で言語化する場面は、読者に読書契約を提示します。事実性の追跡に躍起になるかわりに、語りが自己を守る膜にも、自己を切開する刃にもなる二重性を見抜けるかが問われます。
現在章のラストでリンが“書くこと”へ身を向ける決断は、物語の倫理的な支点です。誰かを糾弾するでも、誰かに赦しを乞うでもない。言葉へ戻ることが、彼女にとって唯一の自己保存であり、他者と距離を保つ作法でもあるのです。
「オートフィクション」は、男性像を単純に悪として配置しません。優しさも残酷さも、関係の場に同居する。だから読者は誰かを断罪して安堵する道を奪われ、代わりに“関係の作法”を自分の生活に引き寄せて考えることになります。
作品全体を貫くのは“孤独の物質感”です。寒さや匂い、皮膚のざらつきが、感情の記憶装置として働き、言葉と身体が乖離したり再接続されたりする。ここに金原作品ならではの即物性が息づいています。
文体の変奏は読みの快楽そのものです。二十二歳の章の過敏な独白、十八歳の奔流、十六歳の乱反射、十五歳のこわばり――この推移が、単なる回想ではなく“今この瞬間”の生々しさとして立ち上がります。
「オートフィクション」を読み解く鍵は、“自分を疑いながら自分を語る”という矛盾を抱きしめられるかどうかです。リンは虚栄でも卑下でもなく、自分の語りの危うさごと提示します。その正直さが、読後に奇妙な爽やかさを残します。
「オートフィクション」は恋愛小説でも告発の書でもなく、“自分の語りを自分で引き受ける練習”の記録です。ネタバレを知っていてもなお、語り直しの身ぶり自体が読むたびに新しくなる。そこにこの作品の耐久力があります。
まとめ:「オートフィクション」のあらすじ・ネタバレ・長文感想
二十二歳から十五歳へ逆向きにたどる構成が、原因と結果を反転させ、読者の理解を揺さぶります。これにより、あらすじをなぞるだけでは掬えない感情の沈殿が見えてきます。
「オートフィクション」は、事実か創作かという二択を超えて、語ることの倫理と危うさを体感させます。虚実の間に読者を立たせる設計が魅力です。
機内での嫉妬、十八歳の夜、十五歳の冬――各章の体験は、後年のリンの反応の“書き換え”として繋がります。ネタバレを踏まえて読む二度目の読書も大いに報われます。
結局のところ、「オートフィクション」は“書くことへ戻る”物語です。言葉へ回帰する終盤の身ぶりに、この長篇の静かな救いが宿っています。