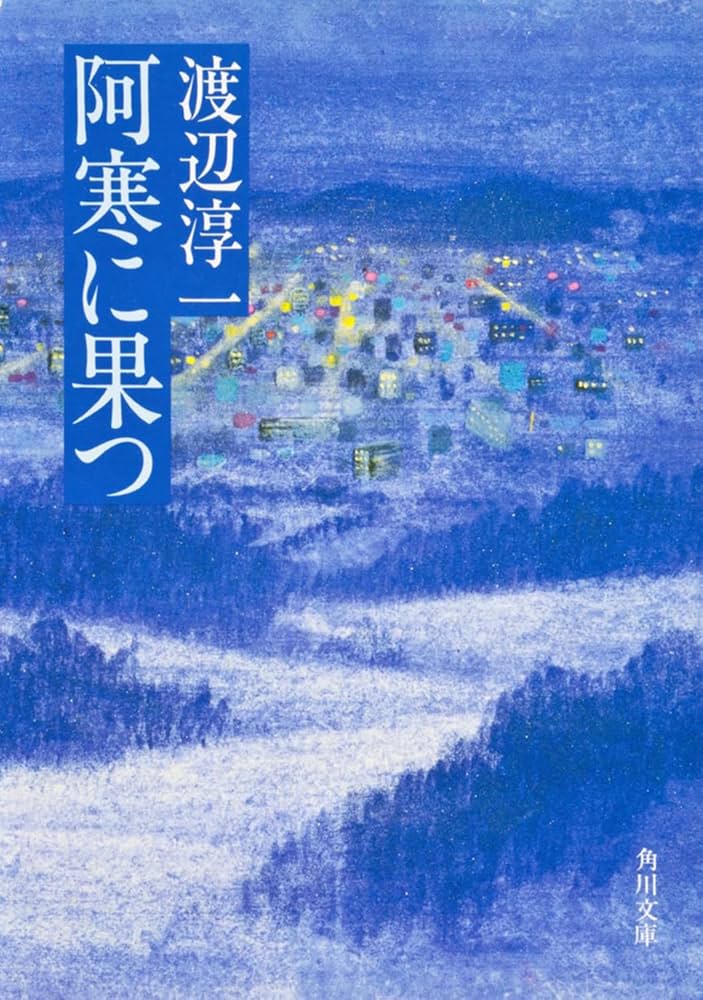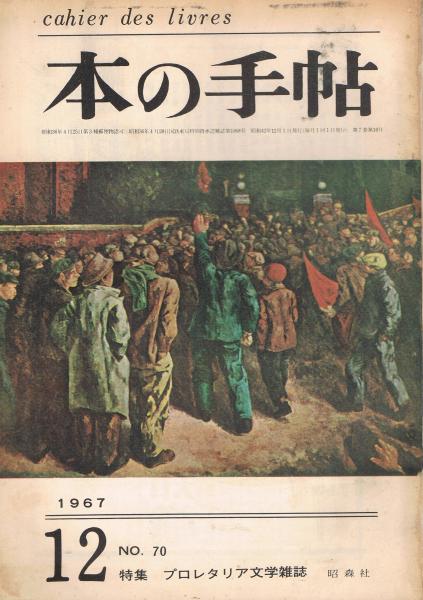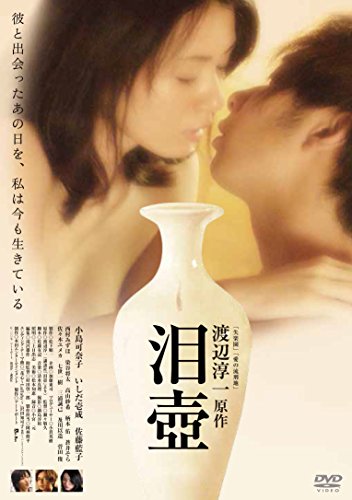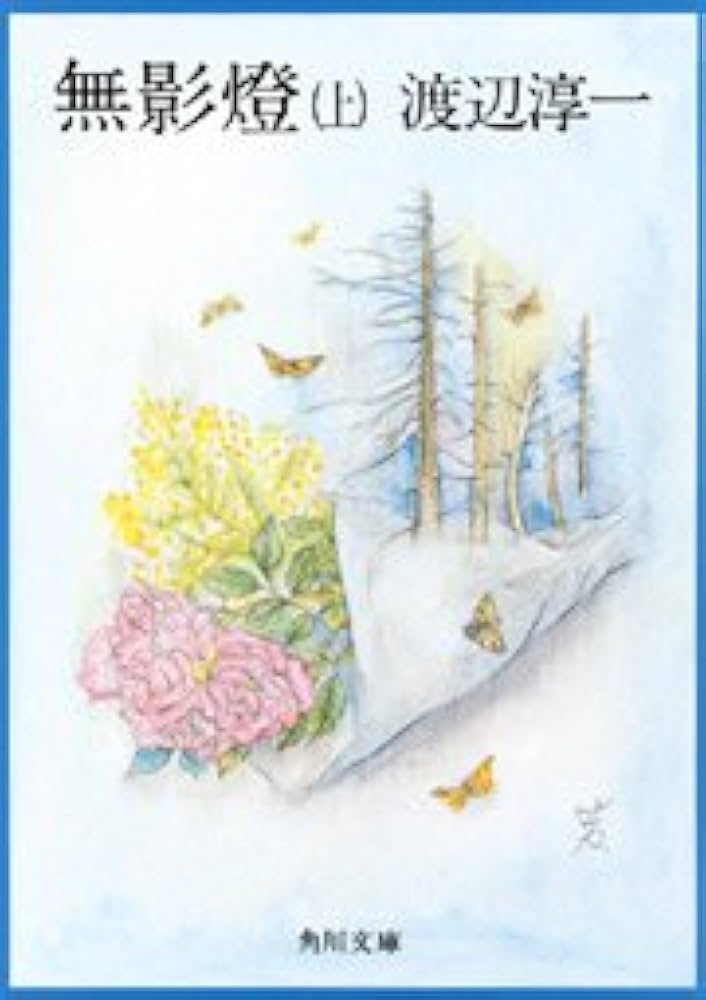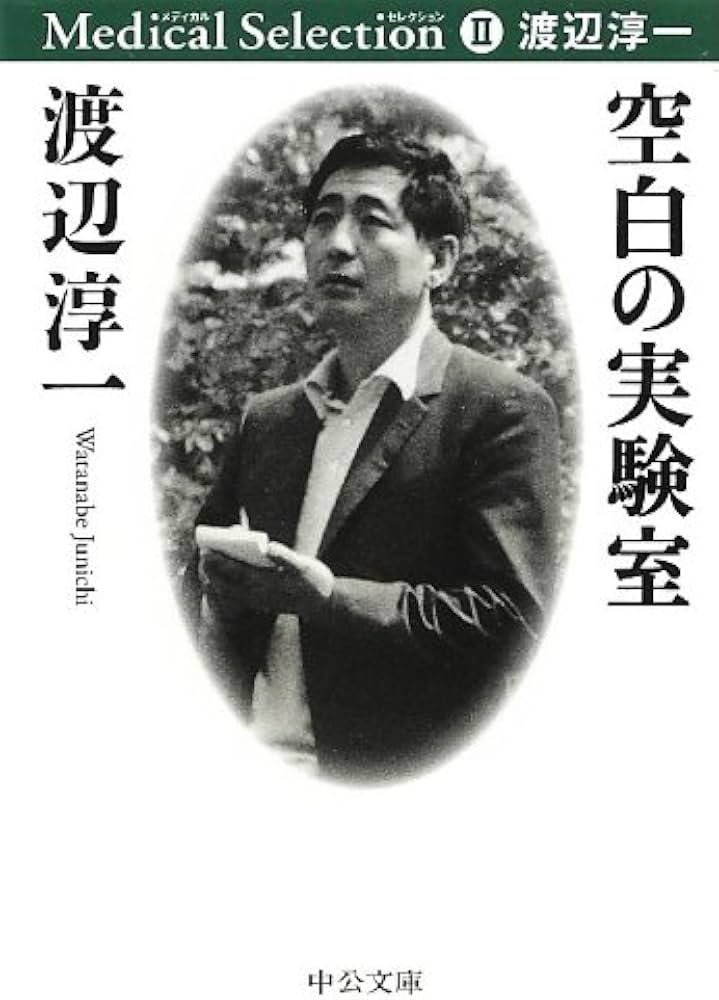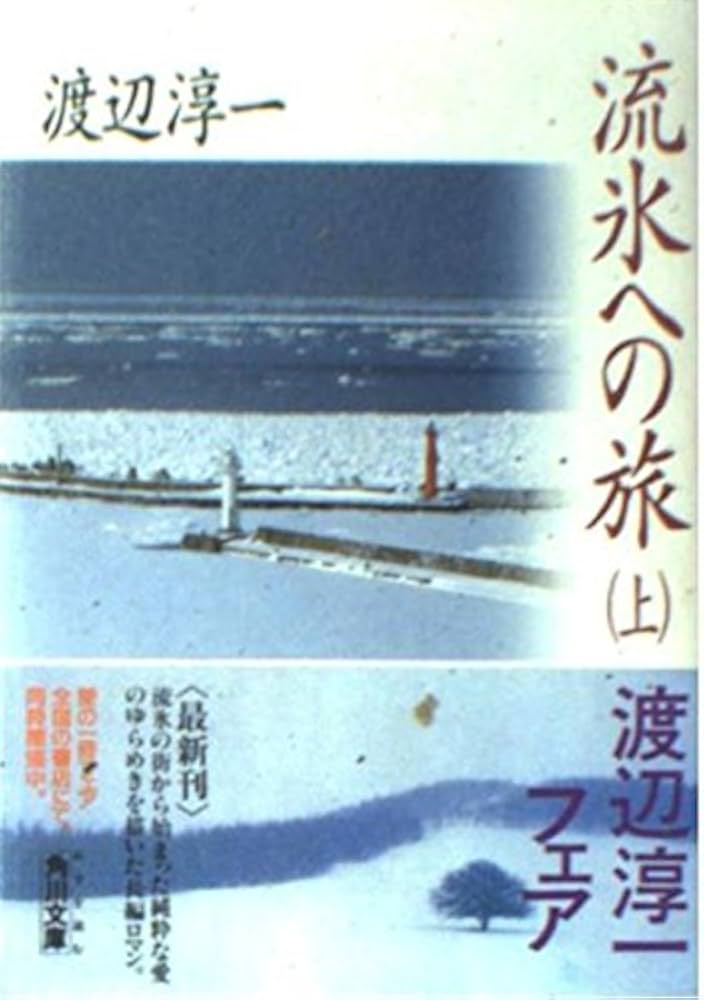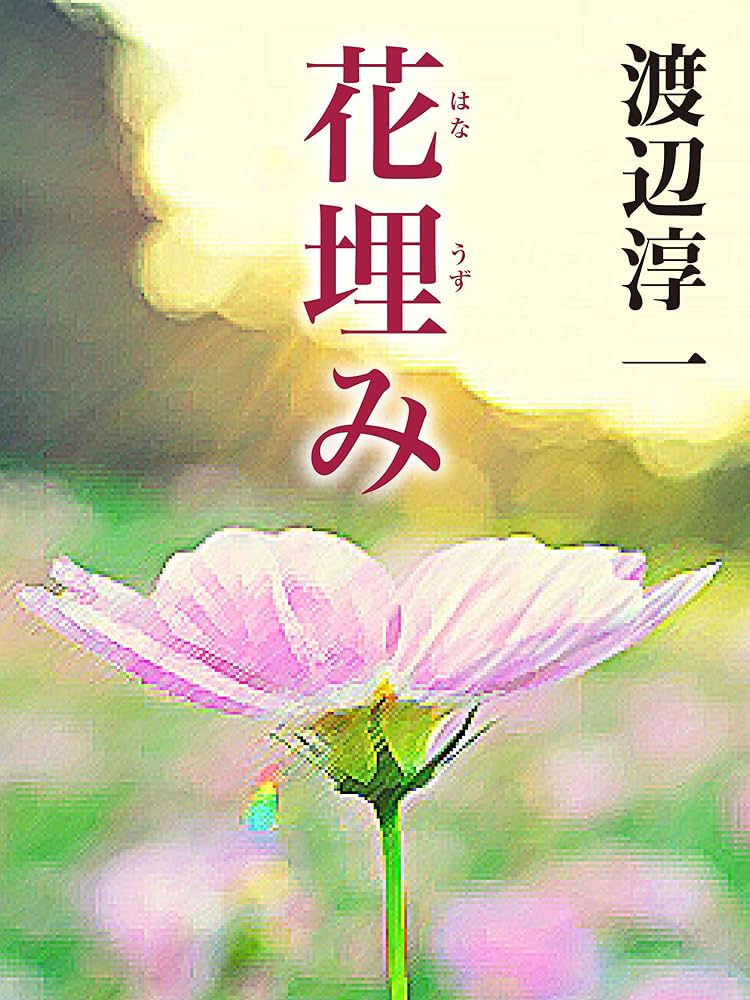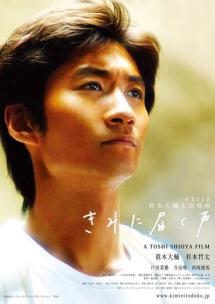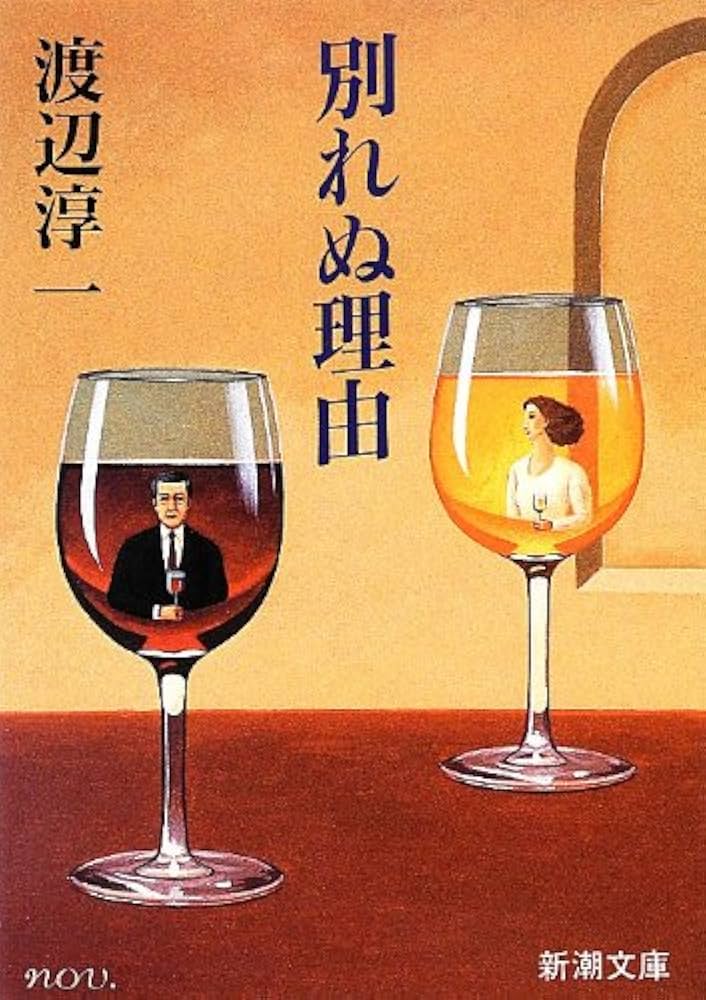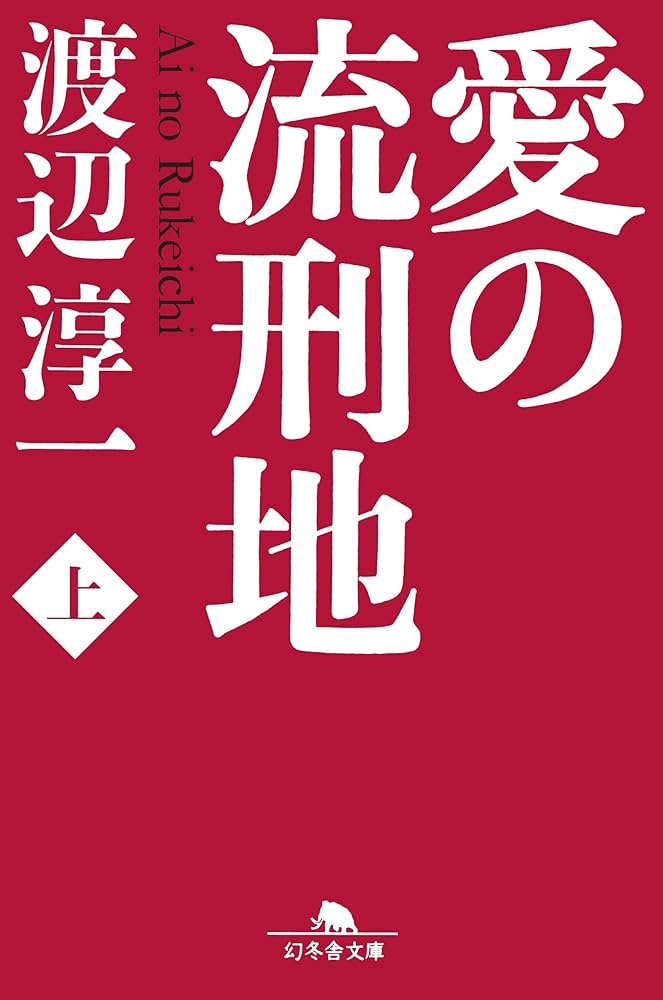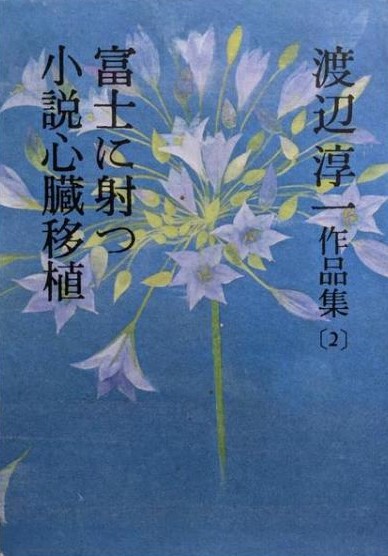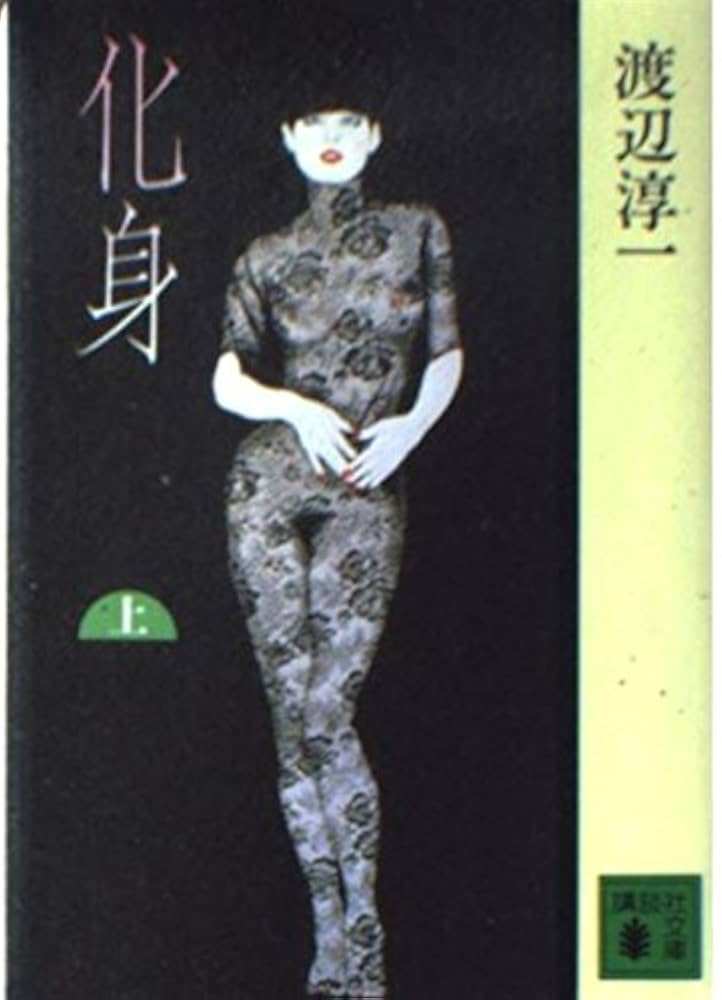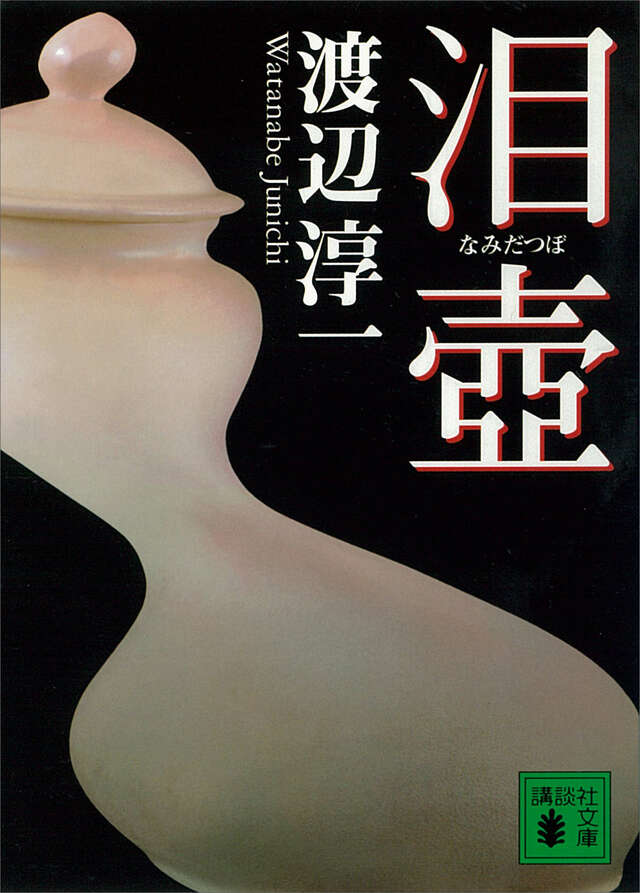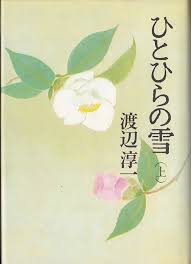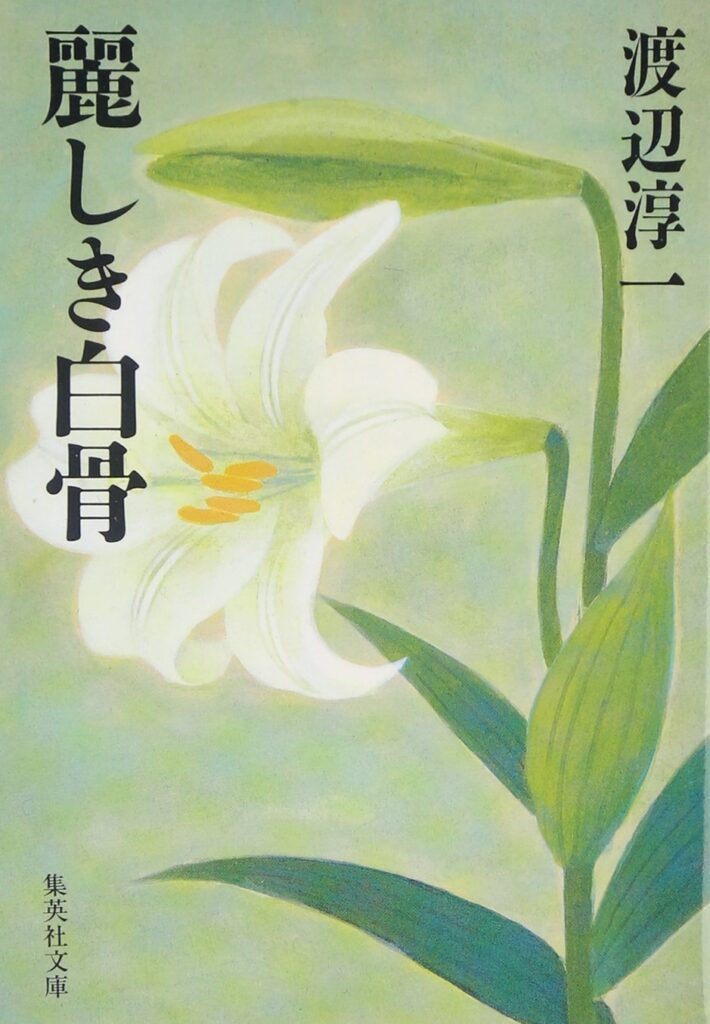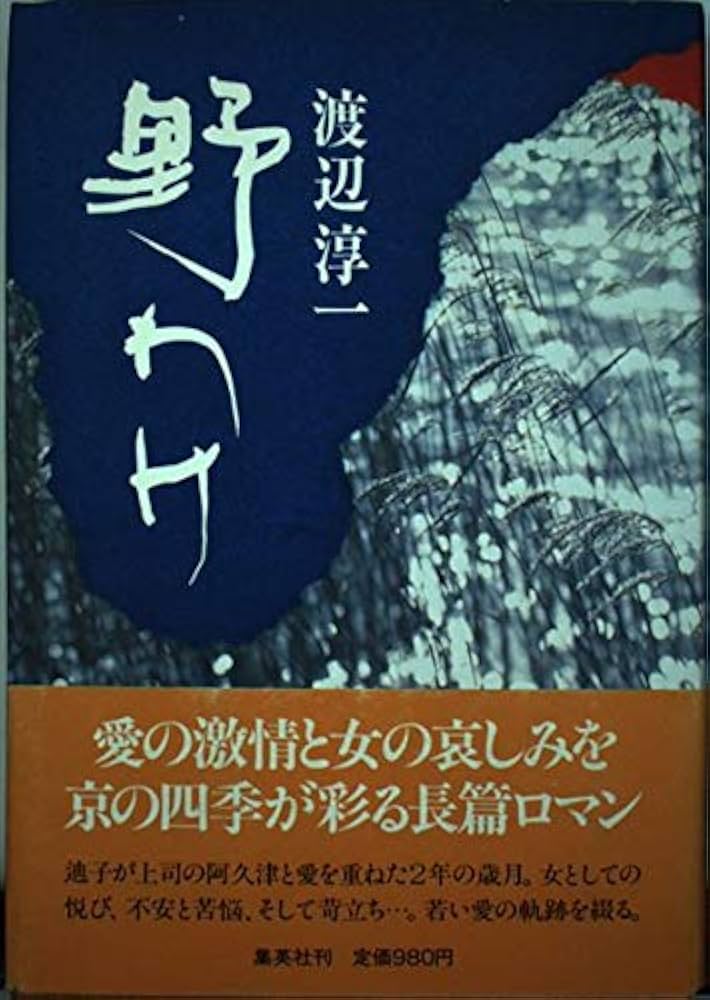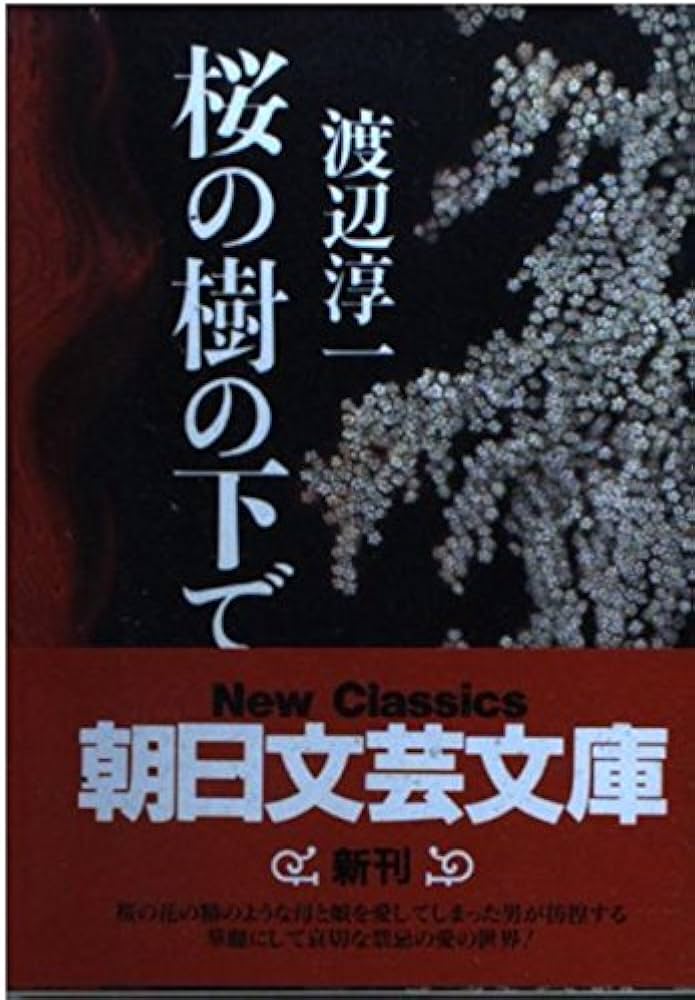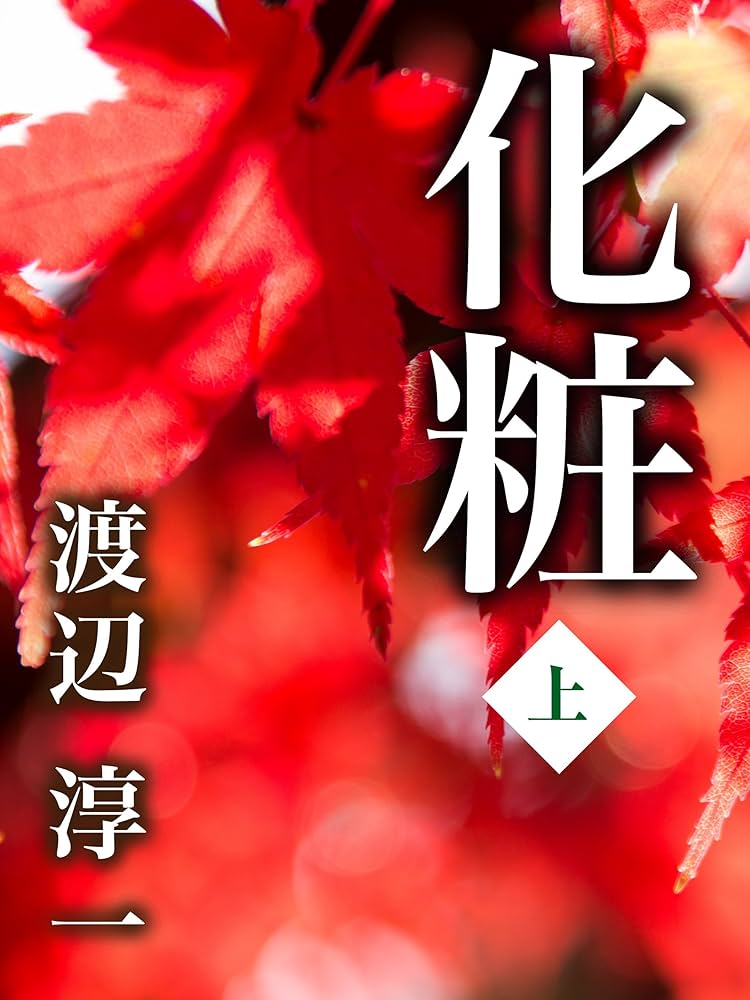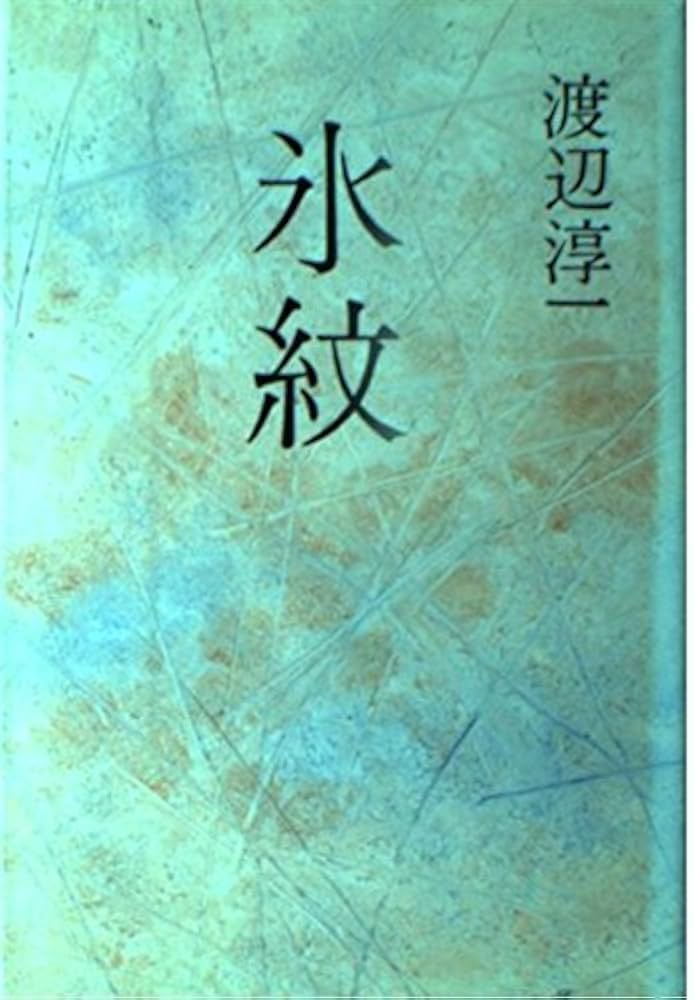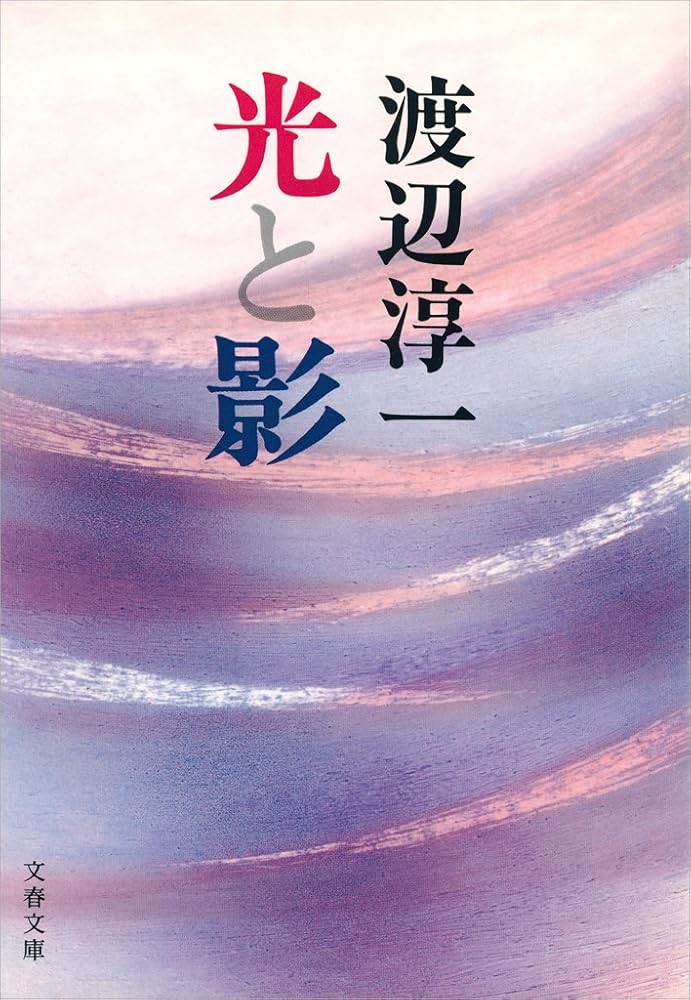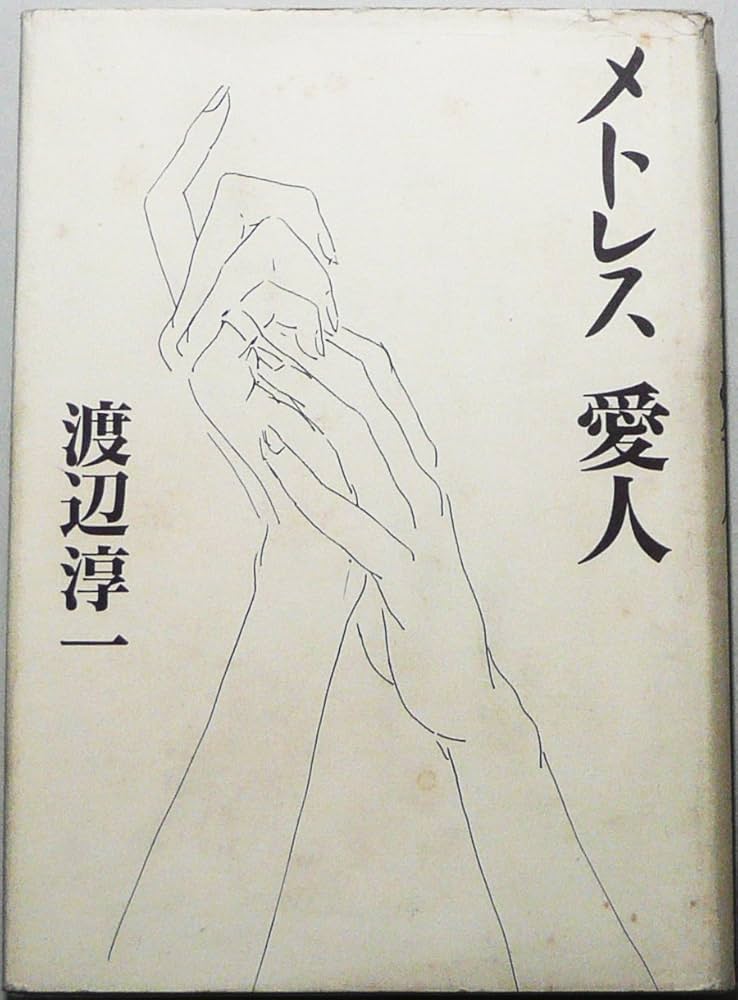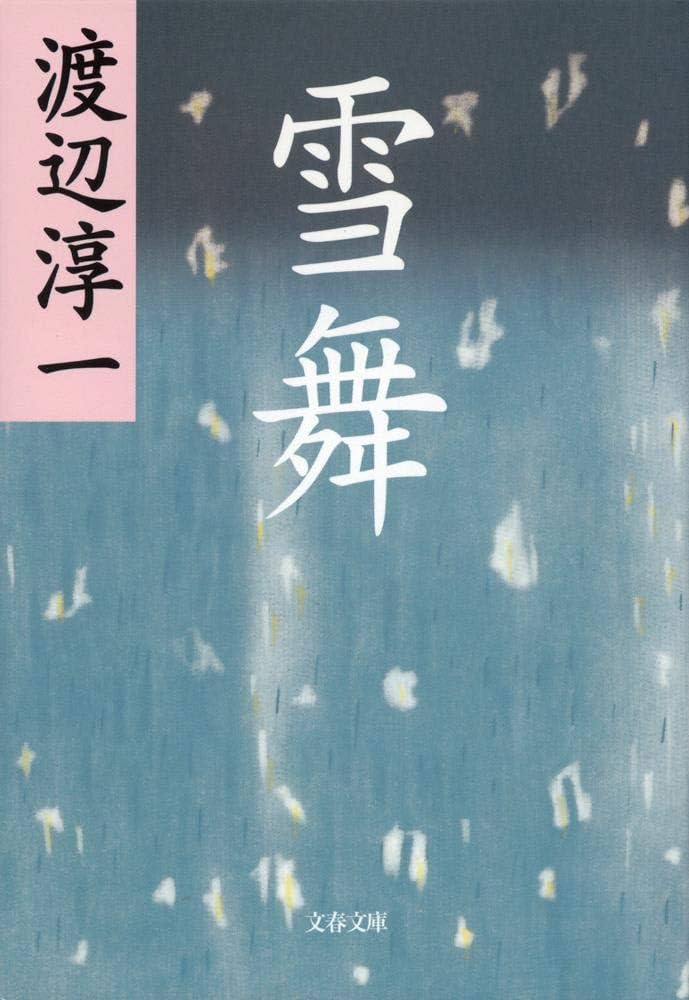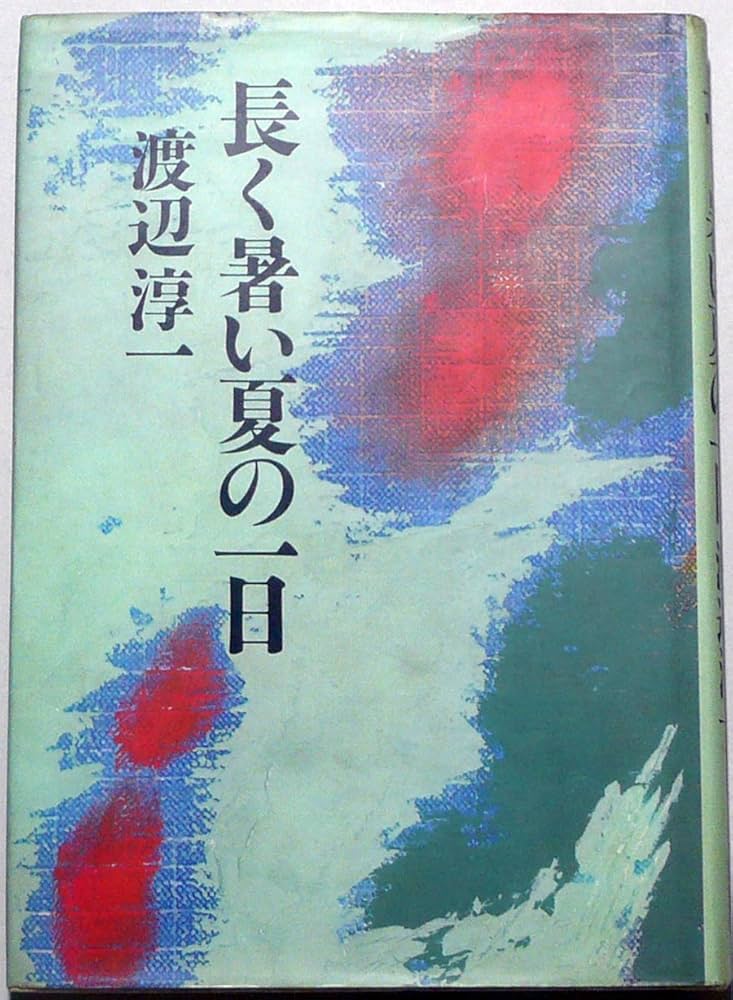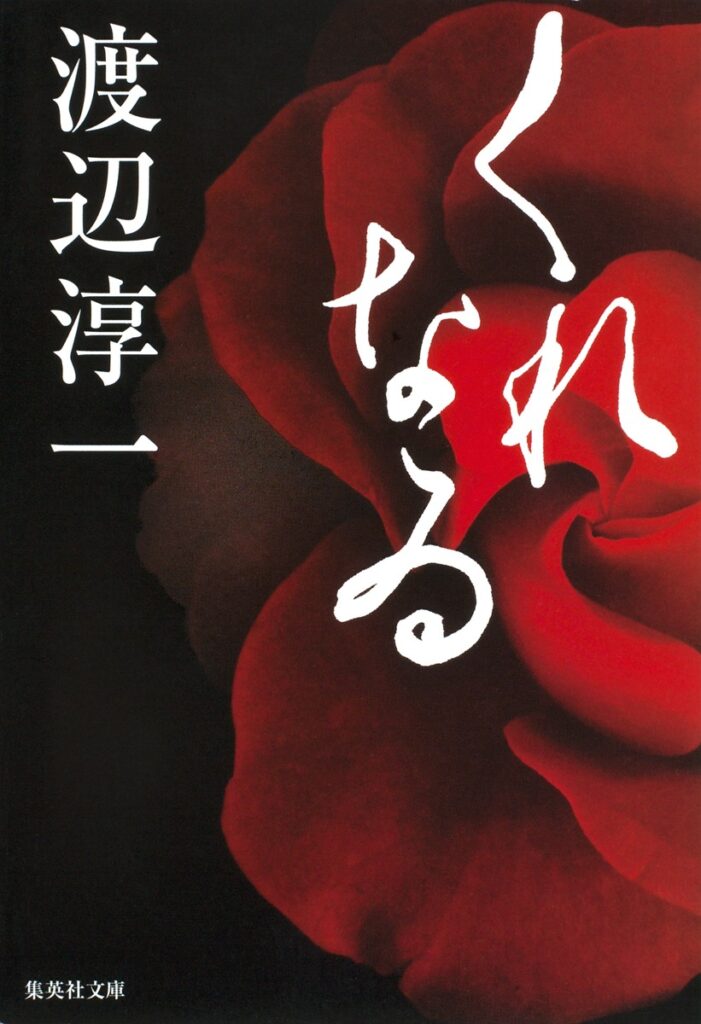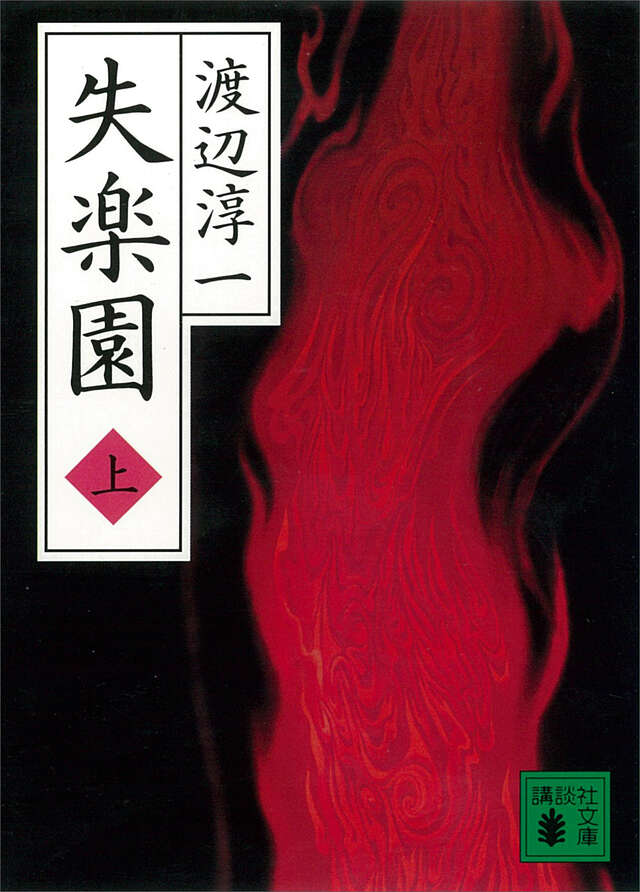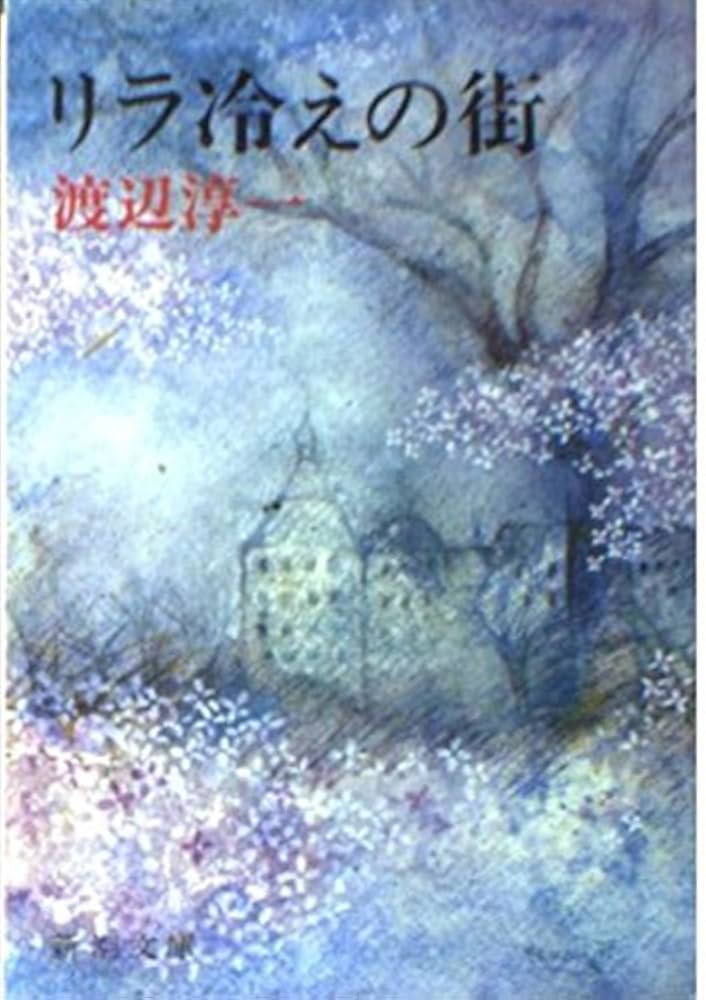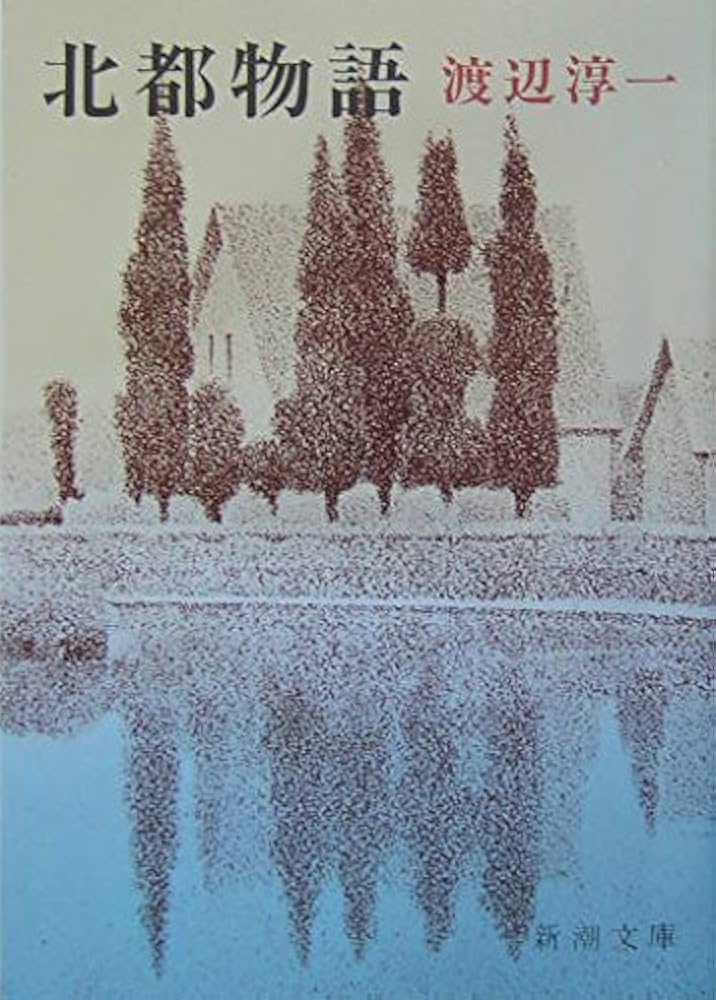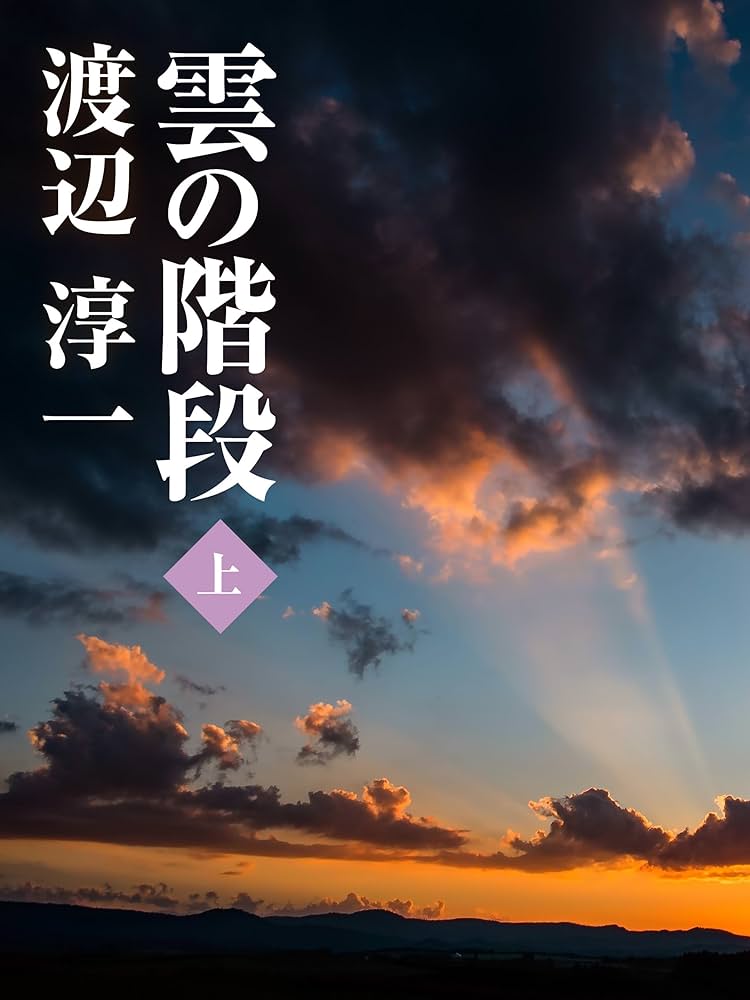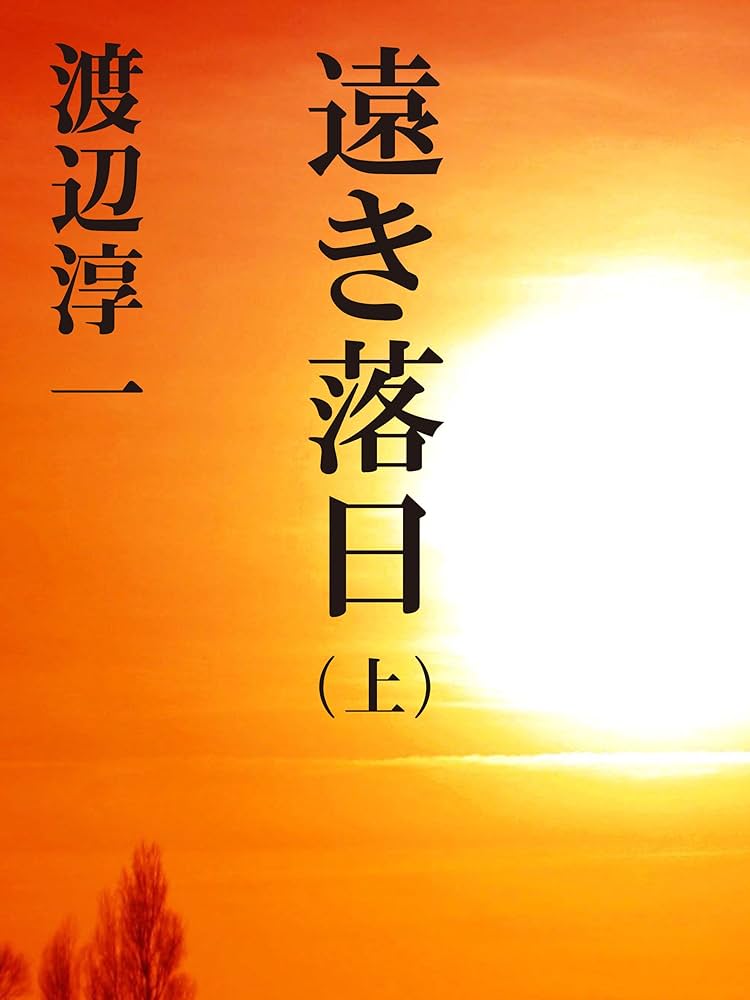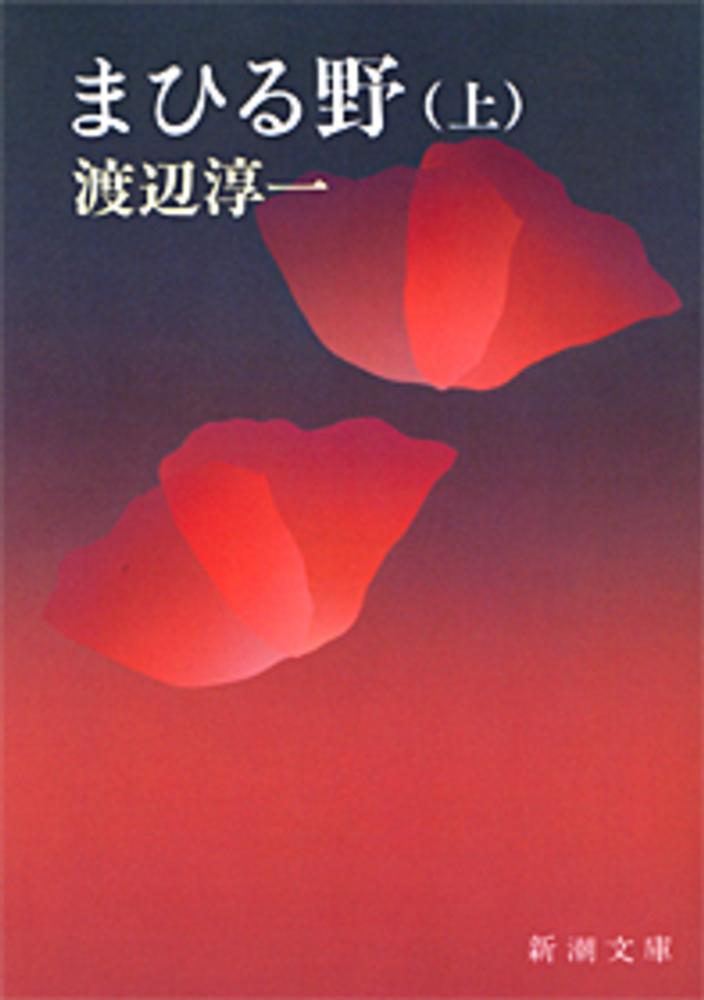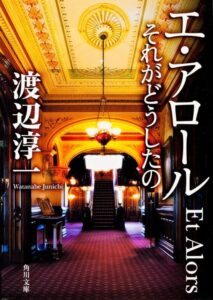 小説「エ・アロール それがどうしたの」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「エ・アロール それがどうしたの」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
渡辺淳一氏が描くこの物語は、単に老後の生活を描いたものではありません。銀座の一等地にそびえる高級高齢者住宅「ヴィラ・エ・アロール」を舞台に、人間の根源的な欲望や情熱、そして「老い」というものにどう向き合っていくのかを、真正面から問いかけてくる作品です。
物語のタイトルにもなっている「エ・アロール」とは、フランス語で「それがどうしたの?」という意味。この一つの言葉が、登場人物たちの行動原理となり、世間の常識や体面に縛られず、自らの心に正直に生きる姿を鮮烈に描き出しています。彼らの生き様は、時に滑稽で、時に切なく、そして圧倒的な生命力に満ちています。
この記事では、まず物語の骨子となる展開を紹介し、その後、物語の核心に触れる結末までを含めた詳細な考察を記していきます。この物語が投げかける「老い」と「生」の問いに、一緒に向き合っていただければ幸いです。
小説「エ・アロール それがどうしたの」のあらすじ
物語の主人公は、大学病院に勤務していた真面目な内科医、来栖貴文です。彼は、自由奔放な父親が創設した銀座の高級高齢者住宅「ヴィラ・エ・アロール」の経営を引き継ぐことになります。しかし、その施設の理念は「入居者の自由を最大限に尊重する」という、彼の常識とはかけ離れたものでした。
「ヴィラ・エ・アロール」に集うのは、社会的地位も経済力も手に入れた、個性豊かな高齢者たち。彼らは「年甲斐もなく」という言葉をものともせず、恋愛や自己表現に情熱を燃やします。若き理学療法士に熱烈なアプローチをかける未亡人、施設の花である元スチュワーデスを巡って火花を散らす二人の紳士など、次々と騒動が巻き起こります。
院長として、その都度対応に追われる来栖。彼は、入居者たちのあまりにストレートな欲望や行動に戸惑い、ときに呆れながらも、その根底にある生命の輝きに触れていきます。「エ・アロール(それがどうしたの?)」の精神を掲げるこの場所で、彼は管理者として、一人の人間として、否応なく彼らの人生の渦中へと巻き込まれていくのです。
常識や倫理観を揺さぶる出来事が続く中、施設は大きな事件に見舞われます。それは、この自由な楽園の存続そのものを揺るがすほどの、衝撃的な出来事でした。来栖は、そして入居者たちは、どのような選択をするのでしょうか。物語は、誰もが予想しなかった方向へと進んでいきます。
小説「エ・アロール それがどうしたの」の長文感想(ネタバレあり)
この物語は、読者に「老いるとは、どういうことか」という問いを、非常に鮮烈な形で突きつけてきます。私がこの作品を手に取ったとき、高齢者施設の物語と聞いて、どこか穏やかで、人生の終幕を静かに迎える人々の姿を想像していました。しかし、ページをめくり始めてすぐに、その予想は心地よく裏切られることになります。
渡辺淳一氏が描いたのは、枯れていく姿ではなく、最後の瞬間まで燃え盛ろうとする命の炎でした。「エ・アロール それがどうしたの」というタイトルが、まさにその精神を象徴しています。世間体?年齢?常識?「それがどうしたの?」と一蹴し、自らの欲望に忠実に生きる。その姿は、痛快でありながら、人間の本質的な部分をえぐり出す鋭さを持っています。
物語の案内役となるのは、院長の来栖貴文です。彼は私たち読者と同じように、常識的な視点を持つ人物として描かれています。だからこそ、私たちは彼の戸惑いや葛藤に共感しながら、施設で繰り広げられる常識外れの出来事を体験することになります。彼の存在は、この物語の過激さを中和し、読者を物語の世界へといざなう巧みな仕掛けだと感じました。
来栖が管理する「ヴィラ・エ・アロール」は、銀座という日本の中心地にあります。郊外の静かな場所ではなく、欲望と文化が渦巻く街の中心に老人たちの城を築いたという設定が、まず素晴らしい。それは、老いを社会からの引退や隔離ではなく、人生の連続したステージとして捉えるという、作者の強い意志の表れに他なりません。
入居者たちのエピソードは、どれも強烈な印象を残します。特に、元スチュワーデスの江波玲香さんを巡る、立木重雄と野村義夫の三角関係は、物語の大きな軸となります。妻を亡くし生きる気力を失っていた野村が、玲香への恋心をきっかけに再び生気を取り戻していく姿は、愛が人に与える力の大きさを感じさせます。
一方で、プレイボーイとして鳴らした立木は、まさに「エ・アロール」精神の化身のような存在です。彼の行動は常に周囲を驚かせ、来栖を悩ませます。しかし、その行動の根底には、人生を最後までしゃぶり尽くそうという、すさまじいほどのエネルギーが感じられます。彼が病に倒れ、延命治療を拒否して自らの死に方を選ぶ場面は、彼の生き様の集大成であり、深い感銘を受けました。
これらの恋愛沙汰や騒動は、一つひとつが「人間は年齢では定義できない」という事実を物語っています。私たちはつい、高齢者を穏やかで無性的な存在として見てしまいがちです。しかし、この小説は、嫉妬も、独占欲も、性的な欲求も、若い頃と何ら変わらず、いや、むしろ人生の残り時間が少ない分、より純粋で切実な形で存在し続けるのだと教えてくれます。
そして、物語は衝撃的な事件によって大きな転換点を迎えます。入居者である堀内氏が、自室に呼んだ女性との行為の最中に急死してしまうのです。この出来事は、施設の理念である「自由」がもたらす最悪のリスクが現実になった瞬間でした。自由には責任が伴う、というありふれた言葉が、ずしりと重くのしかかってきます。
この事件をきっかけに、入居者たちは恐怖と嫌悪から次々と退去し、施設は経営危機に陥ります。理想を掲げるだけでは済まない現実。自由という理念が、共同体を崩壊させかねない危険性をはらんでいることを、物語は冷徹に描き出します。ここで試されるのは、来栖が、そして残った入居者たちが、それでも「エ・アロール」の精神を貫けるのか、ということでした。
物語を通じて、来栖は常に観察者、調停者としての立場にいました。彼は入居者たちの巻き起こす情熱の奔流を、一歩引いた場所から眺め、対処する存在だったのです。彼自身は、編集者の麻子という恋人がいながらも、「結婚はしない」というある種醒めた関係を築いており、施設の老人たちのような情熱とは無縁の場所にいるように見えました。
しかし、この物語の本当のすごさは、その結末にあります。入居者たちの恋の成就を見届け、その情熱に触れることで少しずつ変わり始めていた来栖。彼が最後に直面するのは、自分自身の失恋という、あまりにも皮肉な現実でした。あれほど他人の恋愛のために奔走した彼が、自らの愛を失うのです。
この結末は、一部で放送されたテレビドラマ版とは大きく異なるといいます。ドラマでは、来栖が麻子に「それがどうしたの?」と問いかけ、二人の関係が前向きに進むところで終わる、希望に満ちたものだったようです。しかし、原作であるこの小説は、そんな安易な救いを主人公に与えません。
他人の人生に深く関わり、「エ・アロール」の何たるかを学んだはずの来栖が、いざ自分の身に喪失が降りかかった時、どう振る舞うのか。作者は、そこを描きたかったのではないでしょうか。幸福を保証してくれる魔法の言葉などない。人生は、自分の力でその痛みや悲しみを引き受け、「それがどうしたの?」と呟きながら、また一歩を踏み出すしかないのだと。
来栖は、この痛みを伴う結末によって、初めて「エ・アロール」の真の住人になったのだと私は解釈しています。他人の情熱を管理し、理解したつもりになっていた彼が、自らが傷つき、失う当事者となる。その時、この言葉は単なる威勢のいいスローガンではなく、人生のままならなさを受け入れるための、切実な呟きに変わるのです。
この小説が読後、深い余韻を残すのは、このほろ苦い現実感ゆえでしょう。ただ自由を賛美し、情熱的に生きることを勧めるだけの物語ではない。その先にある痛みや孤独、そして喪失までをも描き切っているからこそ、登場人物たちの生き様が、より一層輝いて見えるのです。
私たちは、来栖の最後の姿に、自分自身の人生を重ね合わせずにはいられません。どれだけ正しく、真面目に生きていても、理不尽な悲しみは訪れる。その時に、私たちは胸を張って「それがどうしたの?」と言えるだろうか。この問いこそが、渡辺淳一氏がこの傑作を通して、私たち一人ひとりに投げかけたものではないでしょうか。
この物語は、人生の最終章を目前にした人だけでなく、これから人生の様々な局面を迎えるであろう、すべての世代の心に響くものだと思います。情熱的に生きることの素晴らしさと、それに伴う痛みを、これほど鮮やかに描き出した作品はそう多くはありません。読後、きっとあなたの世界を見る目が、少しだけ変わっているはずです。
まとめ
渡辺淳一氏の小説「エ・アロール それがどうしたの」は、高齢者たちの恋愛模様を描きながら、人間の生の根源を問う、非常に力のこもった作品でした。銀座の高級高齢者住宅を舞台に、登場人物たちが常識や世間体に縛られず、自らの情熱に身を任せて生きる姿が描かれます。
物語の核心にあるのは「それがどうしたの?」という言葉に集約される哲学です。この言葉を胸に、彼らは恋に悩み、嫉妬に燃え、人生の最後まで自己の欲望に忠実であろうとします。その姿は、私たちが抱きがちな「老後」のイメージを根底から覆すものでした。
しかし、この物語は単に自由を礼賛するだけではありません。自由がもたらす混乱やリスク、そして避けられない喪失の痛みまでをも描き切っています。主人公である院長の来栖が、他者の情熱を見守った末に自らの愛を失うという結末は、この物語のテーマを象徴する、ほろ苦くも深い余韻を残します。
情熱的に生きることは、必ずしも幸福な結末を約束するものではない。それでも、痛みや悲しみを含めて、人生を丸ごと引き受けることの尊さを、この物語は教えてくれます。読み終えた後、人生の悲喜こもごもを、より深く愛おしく感じられるようになる、そんな一冊でした。