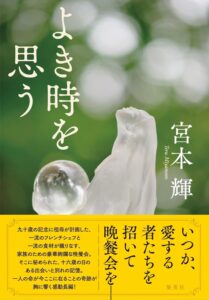 小説「よき時を思う」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「よき時を思う」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
宮本輝さんの作品は、いつも私たちの心の奥深くに響く何かを届けてくれますね。今回の「よき時を思う」も、まさにそんな一冊でした。物語の中心となるのは、九十歳を迎える祖母・徳子さんが開く、壮大な晩餐会です。
この物語は、語り手である孫娘・綾乃の視点を通して、徳子さんの波乱に満ちた人生と、彼女を取り巻く家族の姿が丁寧に描かれています。読んでいるうちに、まるで自分も金井家の一員になったかのような温かい気持ちに包まれました。そして、徳子さんが晩餐会に込めた想いが、静かに、しかし力強く伝わってきます。
この記事では、物語の詳しい流れと、物語の核心に触れる部分も含めて、私が感じたこと、考えたことをたっぷりとお伝えしたいと思います。読後感がとても良く、心がじんわりと温かくなるような物語ですので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。
小説「よき時を思う」のあらすじ
物語の語り手は、三十歳を目前にした金井綾乃。彼女は東京・東小金井にある、叔母夫婦が海外赴任中に空けている「四合院造り」という中国の伝統様式で建てられた家に住みながら、海運会社で経理として働いています。この家自体が、物語に独特の雰囲気を与えています。古風でありながら、どこか懐かしく、静謐な空気が流れているようです。
綾乃の実家は滋賀県近江八幡市。兄、妹、弟がいる四人きょうだいの長女です。物語の主役とも言える祖母の徳子さんは、大津の名家の出身。十六歳で結婚したものの、夫はわずか二週間で出征し、戦死。その後、婚家を出て小学校教師となり、綾乃の祖父と再婚。長年教職を務め、多くの教え子たちを送り出してきました。夫亡き後も、綾乃の両親と共に元気に暮らしています。
そんな徳子さんが、九十歳の誕生日を記念して、自らの費用で盛大な晩餐会を開くことを計画します。場所は一流レストラン。招待客は息子夫婦(綾乃の両親)、そして四人の孫たちとその配偶者(長兄のみ既婚)。ドレスコードは男性がタキシード、女性はイブニングドレスという、まさに特別な夜会です。
物語は、晩餐会の準備を進める徳子さんと、それを手伝う綾乃たち家族の様子を中心に描かれます。準備の過程で、綾乃は徳子さんの過去、特に最初の夫との短い結婚生活や、教師時代の情熱、そして晩餐会開催に込めた深い想いを知ることになります。徳子さんが大切にしてきた品々が孫たちへ贈られる場面や、かつての教え子たちとの再会を通して、徳子さんの人となりが浮き彫りになっていきます。
並行して、綾乃の弟・春明のエピソードも語られます。彼はレトルト食品の製造販売会社に就職したばかりでしたが、ある事情から急遽社長に就任。若き経営者として奮闘する姿も描かれ、物語に別の彩りを加えています。春明が開発に関わるカレーの話は、晩餐会の豪華な料理とはまた違った「食」の魅力として描かれています。
そして迎える晩餐会の夜。ドン・ペリニョンのロゼに始まり、ポメリー、モンラッシェといった高級シャンパンやワイン、カニのテリーヌ、カスピ海産キャビア、コンソメ・ド・ジビエ、フランス産天然鴨、子羊の鞍下肉…と、最高級の料理が次々と登場します。その描写は読む者の想像力をかき立て、まるでその場にいるかのような至福の感覚を味わせてくれます。この晩餐会は、単なる食事会ではなく、徳子さんの九十年の人生、そして関わってきた人々への感謝と讃嘆の儀式なのです。
小説「よき時を思う」の長文感想(ネタバレあり)
宮本輝さんの描く世界に、またしても深く引き込まれてしまいました。「よき時を思う」は、派手な事件が起こるわけではありません。しかし、登場人物たちの丁寧な日常、心の機微、そして人生に対する静かな肯定が、読者の心をじんわりと満たしてくれる、そんな物語でした。特に、祖母・徳子さんの生き様には、胸を打たれずにはいられません。
物語の核となるのは、徳子さんが九十歳の誕生日に開く晩餐会です。この晩餐会は、単なる長寿のお祝いではありません。徳子さん自身の人生、そして彼女の人生に関わったすべての人々の生を讃え、感謝するための、いわば聖なる儀式のようなものです。「きょう生きていることへの敬意。自分の生命への敬意と讃嘆、家族や友人たちへの生への敬意と讃嘆をあらわすためのもの」という徳子さんの言葉には、重みと輝きがあります。
十六歳で結婚した相手は、わずか二週間で戦地へ赴き、帰らぬ人となりました。若くして戦争未亡人となった徳子さん。それでも彼女は、数年間婚家に留まり、その後、自らの意志で教師の道を選び、多くの子供たちを育て、やがて綾乃の祖父と再婚します。その人生は、決して平坦ではなかったはずです。しかし、徳子さんは常に前を向き、凜とした姿勢を崩さず、自分の人生を丁寧に紡いできました。その強さと潔さ、そして深い愛情が、晩餐会の準備を通して孫の綾乃にも伝わっていきます。
晩餐会の準備は、それ自体が物語の重要な要素となっています。特注の招待状、一流レストランの選定、ドレスコードの設定、当日の料理とワインのメニュー決定…すべてに徳子さんの美学とこだわりが貫かれています。それは決して見栄や贅沢のためだけではなく、招待する家族への深い愛情と、この特別な「時」を最高のものにしたいという強い意志の表れなのでしょう。読んでいるこちらも、準備段階から心が躍るような気持ちになりました。
そして、晩餐会の描写。これはもう、圧巻でした。ドン・ペリニョンのロゼ、ポメリー・キュヴェ・ルイーズ、モンラッシェ・グラン・クリュ、シャトー・マルゴー、そしてペトリュス…!ワイン好きならずとも、その名を聞いただけでため息が出そうな銘酒が並びます。料理も、カニのテリーヌ、カスピ海産キャビア、コンソメ・ド・ジビエ、青首鴨のブレゼ、子羊の鞍下肉…と、言葉を尽くして描写される一皿一皿が、まるで目の前にあるかのように立ち上ってきます。五感を刺激され、幸福なため息が漏れるような感覚でした。
しかし、この物語の魅力は、豪華な晩餐会の描写だけではありません。語り手である綾乃の心の動きが、とても丁寧に描かれている点も素晴らしいと感じました。三十歳を目前にし、仕事や自身の将来について漠然とした思いを抱える綾乃。彼女が、祖母・徳子さんの生き様に触れ、家族との時間を過ごす中で、少しずつ自分自身を見つめ直し、成長していく姿が共感を呼びます。特に、徳子さんから譲り受けた品々や、祖母の過去の話を聞く場面は、世代を超えた心の繋がりを感じさせ、温かい気持ちになりました。
綾乃が暮らす東小金井の四合院造りの家も、物語に深みを与えています。中国の伝統的な建築様式で建てられたその家は、静かで、どこか神秘的な雰囲気さえ漂わせています。中庭を囲むように建てられた家々は、まるで家族の絆を象徴しているかのよう。綾乃がその家で過ごす時間、庭の草木の手入れをする様子などは、日々の暮らしを大切にすることの意味を静かに問いかけているように感じられました。
弟・春明の物語も、見逃せない要素です。若くして会社の経営を任され、戸惑いながらも奮闘する姿は、読んでいて応援したくなりました。彼が開発に関わるレトルトカレーの話は、徳子さんの豪華な晩餐会とは対照的に、日常の中にある「食」の喜びや大切さを教えてくれます。異なる世代、異なる立場で奮闘する家族の姿が、物語に奥行きを与えていますね。
徳子さんが大切にしている法華経の「妙音菩薩品第二十四」のエピソードも印象的でした。「これは真実で、お伽話ではないと信じて読め」という徳子さんの言葉は、単なる宗教的な教えを超えて、人生における希望や、目に見えない大切なものを信じることの重要性を伝えているように思えました。徳子さんの精神的な支柱となっているものが垣間見える場面です。
宮本輝さんの作品には、時として人間の暗い部分や悪意が描かれることもありますが、この「よき時を思う」には、いわゆる「悪人」は登場しません。登場人物たちは皆、それぞれの人生を懸命に生きており、互いを思いやっています。だからこそ、読後感がとても清々しく、温かい気持ちになれるのかもしれません。もちろん、人生には困難や悲しみもありますが、それらを乗り越えてきた徳子さんの姿は、私たちに静かな勇気を与えてくれます。
晩餐会というクライマックスの後、物語は再び綾乃が暮らす四合院造りの家に戻ります。そして、家の持ち主である三沢兵馬という人物の、これまであまり語られなかった過去や心情が少しだけ明かされ、物語は静かに幕を閉じます。この結びは、少し意外な感じもしましたが、金井家の物語だけでなく、人生は様々な場所で、様々な形で続いているのだという余韻を残してくれます。まるで、澄んだ空気の中に優しい光が差し込むような、穏やかな終わり方でした。
この物語全体を貫いているのは、「丁寧に生きること」への賛歌ではないでしょうか。日々の小さな出来事を大切にし、人との繋がりを慈しみ、そして自らの人生を肯定する。徳子さんの生き様は、まさにその実践でした。そして、その精神は、晩餐会という特別な「時」を通して、綾乃たち孫世代にも確かに受け継がれていくのだろうと感じました。
読み終えて、自分の人生についても少し考えてしまいました。自分は日々を丁寧に生きているだろうか。大切な人たちとの時間を慈しんでいるだろうか。そして、いつか人生の終わりを迎える時に、徳子さんのように「よき時を思う」ことができるだろうか、と。「小病小悩」という言葉も心に残りました。人生を振り返れば、多くの出来事は小さな病や悩みなのかもしれない、という達観した視点。そう思えれば、少し心が軽くなるような気がします。
宮本輝さんの紡ぐ物語は、いつも人生の豊かさや複雑さ、そしてその中に確かな希望があることを教えてくれます。「よき時を思う」は、その中でも特に、温かく、優しく、そして読む者の心を深く満たしてくれる傑作だと感じました。贅沢でありながら、どこか手の届くような温かみのある輝き。そんな特別な読書体験でした。
まとめ
宮本輝さんの小説「よき時を思う」は、九十歳の祖母・徳子さんが開く豪華な晩餐会を中心に、家族の絆や人生の素晴らしさを描いた物語です。語り手の孫娘・綾乃の視点を通して、徳子さんの波乱に満ちた人生と、晩餐会に込められた深い想いが丁寧に綴られています。
物語の魅力は、圧巻の晩餐会の描写だけではありません。綾乃が祖母との交流を通して成長していく姿、弟・春明の奮闘、そして物語の舞台となる四合院造りの家の静謐な雰囲気など、細部にわたって丁寧に描かれています。「丁寧に生きること」の大切さ、人生への肯定といったテーマが、温かい筆致で描かれており、読後には心がじんわりと温かくなるのを感じるでしょう。
特に、徳子さんの凜とした生き様、そして「きょう生きていることへの敬意」を表すために開かれた晩餐会の意義には、深く感銘を受けます。悪人が登場しない、穏やかで優しい物語でありながら、人生の深みや豊かさを感じさせてくれる作品です。
宮本輝さんのファンはもちろん、心温まる物語を読みたい方、日々の暮らしを見つめ直したいと感じている方におすすめの一冊です。読めばきっと、あなた自身の「よき時」について思いを馳せることになるでしょう。

















































